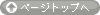「ねじまげ物語の冒険」へようこそ
この小説は、ねじまげ三部作の第二弾です。
伝説の書を胸に、本の世界の登場人物たちと奮闘する少年の姿を描いたファンタジック冒険小説!
侍の少年との友情を軸に、洋一がロビン・フッドの世界を冒険します。
ねじまげ物語の冒険
◆ 第一部 果てしない物語の果てしない始まり
○ その少年についてもし――
あのときああしていたら、あのときああだったらという思いは誰にでもあろうと思うが、牧村洋一がどこともしれない場所で、ちびのジョンや赤服ウィル、時代錯誤のお侍、信用のおけないほらふき男爵といった面々にとりかこまれながら、木につるしたハンモックにくるまり、うつらうつらと考えていたのは、次のようなことだった。
あの日、父さんと母さんが死んでいなかったら。
男爵の誘いを断っていたら。
どうなっていたろうか?
このようなタラレバというものは、人の耳にはいると女々しく聞こえるものだし、聞こえれば、いってもしょうのないことをぐずぐず言うなと叱りとばしたくもなる。だけど、彼のために弁護をするならば、両親の死というものこそ、彼にはどうしようもないもので、あのとき男爵の誘いをことわるのはいっとう無理なことだった。
彼はまだ小学五年生の子供だし、背もふつうだし成績も悪いし、とり柄もなければ小づかいもすくなかった。そんなわけで、このさきの人生を養護院で暮らすなんて、絶対に嫌だったのである。
洋一は家に帰りたかった。生まれそだった図書館に帰りたかった(正確には、今もその図書館にいるのだが。いるはずだ。きっと)。養子なんて絶対にいやだし、両親には帰ってきてほしかったのである。
あのとき彼の願いはそれだけで、しようもないことは言わなかったし、高望みもしなかった。無理なお願い、だけをした……。
洋一少年のそだった環境は、ちょっとばかり変わっていた。
住んでいるところは古い洋館だし、その広い洋館は、図書館に改造されていた。両親は古今東西のあらゆる本をかき集めていたが、その屋敷は山のうえに建っていたから、利用者はあまりにもすくなかった。
さきほどのお話のとおり、それは意外でひっそりとした場所であったから、不思議なことや奇怪なことが、近寄りやすかったのかもしれない。いまから考えると、洋一の両親というのも、ちょっと奇怪な人たちだった。
洋一の両親は、牧村恭一、薫と言った。洋一にとって、両親というのはかならず家にいて、そして、なんの仕事もしていない人たちだった。二人は本にかかりきりで、まさに本にとりつかれたような人たちだった。収入はいっさいない。豪奢な屋敷に住んでいるわりに、暮らしむきは質素なものだ。
それでも洋一は両親が好きだった。長いのぼり道にこそ辟易していたが、あの古びた屋敷のことも好きだった。利用者がすくないといっても、おしかける友人は多かったのであって、ただ彼らのたいはんが本嫌いであっただけのことだ。
とはいえ、洋館だって刺激物としては負けてはいない。その屋敷はゲームの一場面を連想するのに十分だし、なんといっても、こども心を刺激するのに、あんな立派な建物はなかった。こどもをいっとう育てるものが、いっとう不可思議なものであるならば、あの洋館こそが、打ってつけだったのだ……。
このように書くと誤解をうけるかもしれないが、洋一はその屋敷に帰ってはいた。帰るときはこそこそしなかったし、堂々と門から入った。彼は、いままさにその日――屋敷に帰った、あの日のことを考えていたのである。
あの日というのがいつなのか、洋一にはもうわからなかった。彼の時間はめちゃくちゃだった(いやいや、一番にめちゃくちゃになったのは彼の人生そのものだが!)。一時間が数ヶ月になったようにも思うし、あるいは止まったようにも思えてくる。
洋一は毛布を引き寄せ、しかめっ面をしながら、大人めかしい考えに、小さな胸を痛めていた。いやいや人生というのはなにが起こるかわからない、なんでこんな目にあうんだと、ふんたらかんたら考え、人前では見せなくなった涙を、こっそりぽろりとこぼすのだった。
だが、このようにとうとつな話。諸兄とて突然されても、話の道筋などはわかりはしまい。だから、この少年のこれまでに目をむけたい。あの日から、これまでの話。
いや、まわりくどい物言いをしてもうしわけない。率直に言おう。
彼はいま、本の世界のなかにいる……
◆ 第一章 恐怖の院長とほらふきな男爵について
□ その一 養護院みろくの里の実体について
○ 1
果てしない夜の森のなか、洋一少年が思いをはせていたあの日というのは、冬も間中の寒い夜のことだった。
その日、古い石油ストーブの前で、彼は毛布にくるまっていた。外をわたる風に、洋館の窓はゆれていた。そうしてただ一人、お気にいりの本を膝におき、クリームパンと、瓶詰めの牛乳に手をのばしていたその間に、彼の両親はこの世の人ではなくなった。手の届かぬところに、行ってしまったのである。
警官が訪ねてきたのは、洋一がそろそろ時間の遅いのを心配しはじめたころだった。
洋一は玄関に応対に出て、そこで三人の警官から事情を聞いた。聞いているうちに、彼の手からは、牛乳とパンと毛布が落ちた。ほとんど飲み終えていた牛乳が床にこぼれ、その白い液体が、彼の真っ白になった脳裏に、いやに強く焼き付けられた。
いやな予感がした。
彼は毛布をもったまま、警官に誘われた。パトカーに乗るのは初めてだったし、隣にすわる警官たちは、いたわりの目を向けていた。
パトカーは、サイレン音を鳴らしもしなかった……
○ 2
洋一は病院までつれていかれたが、両親には会わせてもらえなかった(二人の体が、すっかり燃えたことを知ったのは、ずっと後のことである)。
洋一のまわりで、時間が呆然とながれていった。死というものは、大人でも理解しがたいものであったし、両親の死を受け入れるには、彼はまだ幼すぎた。相談をしようにも、となりにいる警官は、洋一にはちょっとばかりおっかなかった。ともだちに電話をしたかったが、夜も遅いし、どこからどこにかければいいのかわからなかった。電話番号のひかえすらない。
洋一は、父さんと母さんはまだ手術室にいて、まだ治療を受けているにすぎないんだと、そんな考えにしがみついた。呆然とはさきほど述べたが、彼の脳みそは大部分が考えることを放棄したかのようだった。
やがてそんな時間も過ぎ、病院の安置室の長椅子にすわりこむ洋一の前に、役所の人間が現れた。彼らはもうあの屋敷には住めないこと、法律により、養護院で暮らさねばならないことを告げた。洋一には親戚がいなかった。彼の唯一の身内は安置室にいるから、独りぼっちになったわけだ。肉体的にも、精神的にも……。
役所から来た女は、足立という名前で、きれいだが冷たい感じのする背の高い女性だった。冷えきっていたのは洋一の身と心の方だったから、そんなふうに感じたのかもしれない。
ともかく、洋一は病院をでると、その人の車に乗せられ、いったんは、自宅の図書館までつれもどされた。服や身のまわりの品を持っていくためである。
足立は屋敷までの道々、養護院はどんなところか、そこではどんなふうに暮らさねばならないかを話してくれた。また、屋敷にはときおりもどっていいこと、そのおりは養護院の院長を通し、自分に連絡をつけることを約束させた。鍵はわたしが持っておくから、心配しなくていいのよ……。
車のヘッドライトは、夜の無機質な街を照らしていた。車はゆったりだとも、速かったともいえる。時間の感覚が、なかったのだ。
洋一は足立の方は見ずに、窓の外ばかり向いていた。外に知り合いがいないか、ともだちが呼び止めてくれはしないかと、そんな姿ばかりを探していた。
彼は、ともだちの寺勘たちのことを思った。
ときおり、足立の車は、柳やんやかっつんの家の前を通ったが、どの家並みも明かりは消えていて、彼の期待した友人の姿は、どこにもなかった。
屋敷につくと、洋一は、わざとゆっくり自室に向かった。後ろから、足立が屋敷を見回し、感嘆の声を上げるのが聞こえた。家具や、造りの広壮なことに驚いたのである。屋敷だけを見ていると、洋一の家は、とほうもないお金持ちだと人は思うのだが、じっさいには、つつましやかな生活だった。
洋一は旅行用のバッグを探し出し、こどもの頭でいるだろうと思われるものを、バッグの中にほうりこんでいった。その間も、外で物音がするたびに窓に駆け寄り、両親か、あるいはクラスメートの姿をさがした。そのたびに、がっかりしては引き返すのだ。
阿部先生は、なんでこんなときにかぎってきてくれないんだろう。今が一番肝腎なときじゃないか、文化祭や体育祭より大事なときだと、彼は思った。
洋一は、パンツをたくさんと、ズボンを少々、セーターを一枚用意した。たまにもどってこられると足立はいっていたから、ゲームやおもちゃは持っていくのを控えることにした。養護院がどんなところかわからないし、山さんみたいな、いやなやつがいたら、ゲームをとられないともかぎらない。
それから、養護院はどこにあるんだろう、これまでの学校に通えるんだろうかと不安に思って、最悪の結果を予想した。だから、足立に訊くのは控えることにした。たびたびもどってきたかったから、わざと置いていったものもあった。帰るときの、口実になるように。
つまるところはこういうことだ。
洋一は、ちょっと待ってよ、と言いたかった。車に乗っている間も、カバンに服をつめている間も、ずっとそう言いたかった。足立が、もう屋敷にはなかなか戻れないだろうとか、はやく新しい親御さんが見つかるといいのだけれど、といっているときは、とくに強くそう言いたかった。彼にはろくすっぽわけがわからなかった。人が死ぬだとか、両親にはもう会えないだとか、こんなときの世の中の仕組みだとか……
そんなことを理解するには、彼の心は柔軟でありすぎたのかもしれない。だけど、洋一だって、もうどうにもならないということは、わかっていた。
荷造りはすんだ。足立の車はゆるやかに発車して、屋敷につづく坂道をゆっくりと下った。洋一はシートにへばりつくようにして、その道と屋敷を視界におさめつづけた。自宅のある丘を離れ、あの林が見えなくなると、洋一はゆっくりと前をむいて座り直した。
○ 3
養護院みろくの里は、三十人ばかりのこどもたちを収容している。院長の自宅は、その邸内にあって、問題が起これば、いつでも駆けつけるというわけである。
さて、洋一をこの養護院に送ってきたものの、足立はこの院に洋一を預けるのは気が進まなかった。この辺りには、他に市立の養護院がなかった。みろくの里は評判がよかったけれど、それは、この院がどんなこどもでも預かるからだった。みろくの里がいいと思っているのは足立の上司だったが、その人たちは、みろくの里には来たこともなかった。事務処理もこどもたちの世話も、足立が一人でやっていた。だから、現場を知っているのは、足立だけなのだ。
足立はインターホンを押した。扉はすぐに開いた。鼻にドアがぶつかりかけた。扉の裏で待ちかまえていた男が、急にドアを開けたのだ。
洋一は、クラスでもとくに後列から三番目に背が低かったが、院長は背が高かった。洋一が見上げると、八の字の髭がにょきりにょきりと立体型にくっきり見えた。
院長は、女性にも洋一にも注意を払わなかった。酔っているようだった。
足立がどぎまぎした様子で言った。「団野院長、夜分遅くにもうしわけありません」
「ああ、まったくだな」
院長は言った。
「こちらは牧村洋一君ともうします。あの……院長、聞いてらっしゃいます?」
「それがどうかしたのかね……この子は孤児なんだろう」
と、院長は急に高くなった声でそう訊ねた。
「そのとおりですが、院長」
足立が院長の肘をとり、洋一から離れるような仕草をみせた。彼らは玄関の奥に寄った。院長は足立の話を少しだけ聞くと、洋一に向かって身をかがめた。
洋一は院長の肌から、日本酒の臭いをかいだ。彼の父親はワインやウィスキーを好んだ(日本酒はわたしを訳をわからなくさせる。ワインなら本が楽しめる、というのが理由だった)。なんだか嗅ぎなれない、いやな臭いだと洋一は思った。
「牧村」
と団野は言った。洋一君とも洋一、とも言わなかった。名字で呼ばれたので、洋一が感じていた団野院長の冷たい感触は、いっそう強くなった。
「親が死んだのか? 君には親戚がいないのか? 独りぼっちなんだな?」
院長は最後の、独りぼっちなんだな、を噛み締めるようにゆっくり言った。洋一は答えることだけができずに、ひゅっと息をのみこんだ。
洋一は、足立にこう言いたくなった。ぼくを連れて帰ってください、ここに残したりしないでください、この人と、二人きりにしないで下さい!
そんなことを言ったら、院長はどう思うだろうか? 最後に感じたこの思いで、洋一は胸に渦巻くその言葉を、口にすることだけは踏みとどまった。洋一は虐待を受けたことはないが、虐待のなんたるかは知っている。
洋一は、こわばった顔のまま、小さく幾度かうなずいた。院長の髭だけが、うれしそうに笑った。
洋一は、よりいっそうの不安を覚えたのだった。
○ 4
足立は去っていった。彼女は去り際に、気をつけてね、と洋一に言いたかったが、そんな失礼なこと、院長の前でいえるだろうか?
団野院長が玄関を閉めた。団野院長は、目の前に立った。洋一は、扉と院長にはさまれた格好になる。洋一には院長のズボンとチャックしか見えない。背の高い人だな、と思った。ぼくが小さすぎるのかな?
次の瞬間には、洋一は顔を平手打ちにされ、タイルの上にしりもちをついていた。なにが起きたのかわからずにいるうちに、鼻血が垂れ落ち彼の服に赤い染みを、一つ、二つともうけていった。
「夜分遅くに申し訳ありません」と院長は上目遣いで足立の口まねをした。「まったくだな。礼儀がなっとらん。失礼じゃないか。そうは思わないか? わたしは寝ていたかもしれない。酒を飲んでいたかもしれない。女と淫行をしていたかもしれないではないか。そうは思わないか?」
と訊きながらも、院長の目は、洋一を通り越していた。地球の中身でも覗いているかのような、心ここにあらずな目……
洋一は震えて黙りこんだ。両親が死んだのだって、彼にとっては口も利けないほどショックなことだ。骨が砕けるほど強烈な平手打ちを食ったのだって初めてだ。彼は父さんにはぶたれたことはなかったし、母さんにぶたれたのだって、もういつのことだったか思い出せもしないほど。それに、院長は手首付け根の硬い骨で、洋一のあごを正確に打った。彼のダメージは、脳みそにまでおよんで、いまだにぼうっとしている。その意味では、あの瞬間だけは、院長の足下は確かなものだったといえる。
院長の目の焦点が、ようやく洋一を探り当てた。洋一は院長の目玉に、怒りの熱気が揺らめくのを見た。
「お前はあいさつをしらんのか……」
「はい……?」
「はい? イエスなのか? そうなのか……」院長は洋一の襟首をひっつかむと、むりやり立たせ、「悪い子だ。すごく悪いじゃないか。うちじゃな、悪い子には折檻することになってる。折檻しないと、こどもはいいこととわるいことを覚えないんだよ! なぜなら、こどもには理屈をいっても無駄だからだ」
院長は酔っているとは思えない力で、洋一の体をドアに放り投げた。硬い樫のドアに背骨が跳ね返され、内臓が、胸から飛び出るほどの衝撃を受けた。
洋一が咳きこみうずくまっていると、院長は間も与えずに髪をつかみあげ、
「悪い子だ悪い子だ、覚えろ、覚えろ、しつけを覚えろ! 俺にあったらあいさつをすると!」
大声で叫びながら、洋一の頭を扉に打ち当てはじめた。洋一は脳みそを揺さぶられ考えることもできない。ようやっと考えられたのは、今日繰り返しつぶやいてきた言葉で、これは夢だ、の一言だった。
「みんな、なんでも俺に押しつけやがって、市の補助金なんてくそくらえだ」
院長は、最後に洋一の体を、ボールみたいに床にたたきつけた。
「くそくらえだ」
そういうと彼は立ち去ったのだが、恐怖と痛みに震える洋一の目には、院長の足下しか見えなかった。
○ 5
骨が折れたんじゃないかと思った。肩甲骨や肋がひどく痛かった。こんなふうに痛めつけられたのは初めてだ。ともだちと喧嘩をしたことはあるが、それは痛めつけられたなんて言わない。院長は大人の圧倒的な力で、彼をおもちゃみたいに扱った。ゴミやボールをほうるみたいに、彼の体をほうり投げた。
だけど、彼が本当に冷凍庫に放りこまれたネズミみたいに震えだしたのは、鞭を持ってもどってくる院長の姿を目にしたときだ。こんな恐怖は、これまでなかった。
「おしおきだ」院長は言った。「おしおきだ。いうことをきかないやつはおしおきだ。しつけのなってない子はお仕置きだ! 俺様が悪いお前をとことんこらしめてやるぞ。腕を出せ!」
院長の持っている鞭は、乗馬につかう、短いが威力の鋭そうなやつだった。彼はそれをびゅんとふるわせた。鞭が棚にぶつかり木枠が裂けた。
洋一は、扉まで後ずさると、腕を体の後ろにかくし、
「ぼくはなにもしてません!」
と泣きながら叫んだ。
「いやしている」
院長は、壁にかかった額縁の絵を鞭で打った。分厚い紙が、斜め一文字にきれいに裂けた。
洋一は、ぼくのほっぺもあんなふうにさけるんだ、と震えた。生まれてはじめて、どんなことでもするから、許してほしいとさえ思った。
院長は鞭の端を両手で持ち、仁王立ちした。
「お前は甘ったれてる。その証拠にあいさつもろくにできない。俺の睡眠のじゃまをした。酒を飲むのをじゃまをした。うちの院では、そういう小僧はきつくしつけるんだ。俺はそのためにお前を預かっている。両親にかわってお前をしゃんとしてやるぞ、とことんだ!」
「あやまります!」
洋一は言った。院長ははっとしたようにしゃべるのをやめ、天井を見ていた目を水平の位置までおろした。それでも洋一のことは見ようとしなかった。
「悪いことしたんならあやまるよ。だってぼく、こんなところに連れて来られるなんて知らなかった。ぼく……」
「知らないことが罪なんだあ!」
とたんに院長が駆け寄ってきて、その右のつま先で、洋一のみぞおちを蹴り上げた。
洋一は痛みで息がつまる、横隔膜が引きつって、息も吸えない。
「知ったふうな口をきくな! 知ったふうな口をきくな! こどもは大人のいうことを聞けばいいんだ!」院長は叫びながら、なんどもなんども足を踏みおろす、洋一の体めがけて。「そうしないと、まちがうだろう! 誰かが、お前たちを、しつけなければ、世の中は、どうなる? むちゃくちゃに、なってしまう。そうならないために、しつける、役目が、大人には、あるんだ!」
院長は酒に酔った荒い息を吐き、洋一を見下ろした。「腕を出せ」
洋一は震えながら丸まっている。彼は泣きながら言った。
「おしおきならもう受けた。もういいでしょう!」
「なんだその口の利き方は?」
洋一が見上げると、院長はあまりのことに呆然としているようだった。そんなふうに反論されるのは、さも心外だと言いたげに見下ろす。
焦点が二転三転して、洋一の目線と合った。
「誰にそんな口の利き方を習ったんだ?」
「誰でもいいよ! ぼくの父さんはぼくを叩いたりしなかった……」
「いまは、俺がお前の父さんじゃないか」
「お前なんか、ぼくの父さんじゃない……」
洋一は泣きながら、そっと膝元に顔をうずめていった。そうしたら、体が小さく丸まって、消えてしまえるみたいに。
院長はうなり声を上げながら、踵を洋一の後頭部に振り下ろした。院長は飛び上がると、お尻から彼の背中に落ちた。あまりの衝撃に洋一の体が伸びると、こんどは右足の上で地団駄をふみはじめた。
「こい」と院長は洋一の腕をひっつかみ、彼の体を引きずりだす。「二度とそんな口の利けない子にしてやるぞ! 俺にそんな口をきいたやつがどんな目にあうか、お前の体に焼き印をおしてやる!」
洋一は引きずられながら意識がもうろうとして、逃げなきゃ逃げなきゃと思うのに、頭が扉や壁にぶつかってもどうにもできず、その身に起きたあまりに理不尽な出来事のために、軽い緊張病を起こしていた。彼は痴呆のように口を半開きにし、よだれを垂らしていたのだが、院長が煙草を束にして丸め、それに火をつけだすと、急にしゃんとなった。
「どうするの?」
「吸うと思うのか?」
「ぼ、ぼくにそいつを押しつけたら、きっと黙ってないぞ」
「誰がだ?」
院長は洋一を見下ろした。真剣な目で。
「誰が黙っていないんだ。お前の親は丸焦げになって、ずっと黙ったままだ」
それがさもおもしろいジョークだとでもいうかのように一笑いした。洋一が泣き始めると、拳で彼の頭をこづきはじめた。
「泣くな、こいつ。男だろう、男だろう、男だろう。鍛え直してやるぞ、お前を俺がきたえなけりゃあ、そうとも、とことん、とことんやらなけりゃあ」
煙草に火がまわった。十本ばかりが重なり合い、その先端の火口は赤い火の玉に変わった。
「誰も助けなんてこないんだぞお。それなのに、俺に逆らうってことがどういうことなのか、こいつで体に刻みこめ!」
洋一は逃げようとしたが、院長は彼の頭を床に押しつけている。洋一は痛みとあきらめの気持ちも手伝って、抵抗らしい抵抗もできなかった。
院長は彼の背中に、服もめくらず火のついた煙草を押しつける。洋一の耳に服がとけるジュウッとした音が届き、彼は皮膚が焼ける痛みに声をかぎりに絶叫した。
洋一は信じられなかった、こんな痛みも自分がこんな声をだしたことも。彼がちょっとでも怪我をしたら心配してくれる母さんがもういなくって、見知らぬ男に煙草の火を押しつけられていることも。
「どうだ! 誓え! ここに神に誓って誓約しろおっ! 二度と俺には逆らわないと! この院で起きたことは絶対に口外してはいけないんだぞお! みながそうしてきたようにお前も誓えええ!」
誓う! 誓います!
洋一は自分の喉がそういうのを聞いた。服や皮膚だけでなく、頭の中にも火がついたかのようだった。
「いい子だ」
院長の体が離れた、洋一はぐったりと床にしなだれた。
しかし、院長は手にした煙草の幾本かに火が消え残っていることに気がついたようで、その火を消すのに、灰皿ではなく洋一の体をつかうことを思いついたようだ。
院長は、消え残しの一本を、洋一の右手に押しつけた。新しい痛みに苦悶する洋一の耳で、もう一本。こめかみでもう一本。そして、親指の爪に一本ずつ。
「お前は、しばらく外に出ることを禁ずる。この家の部屋に閉じこもってろ。いいか、体の傷を誰かに見られたら、俺が困るんだ……」
ぼくの体を傷つけたのは院長じゃないか……と洋一は心で、悲鳴混じりの非難を上げた。
○ 6
洋一は自分が気を失っていたのか、そうでないのか、後になっても思いだすことができなかった。だけど、院長が彼の手を引きずり、廊下を引きずっていた光景を覚えているということは、完全に気絶していたわけではなかったらしい。ともかく、院長は自宅の物置に連れて行くと、その部屋に彼を押しこめた。それから、忙しくて放尿のことを今の今まで忘れていたみたいに、壁に向かってしょんべんをした。
足下に飛沫が飛んできた。
その後、院長は洋一の元にもどってきて、テーブルに紙とペンを用意した。書け。と彼は言った。
「お前がここで暮らすための誓約書だ。いっておくが、これはれっきとした法律にのっとった書類なんだ。汚すなよ」
と院長は言った。
「お前は、ここで起きたことを誰かにしゃべってはいけないし、俺に逆らってもいけない。養護院の仲間とはうまくやれ。掃除や雑用もすべてお前に課せられた義務だ。うちではな、こどもには労働の義務があると見なしている。お前は働いて金を稼がねばならん。お前が食う飯のための金を、お前の親父や母親が稼いだみたいに、こんどはお前が稼ぐんだ。ここに名前を書け」
院長は洋一に紙に書かれた内容をひととおり読ませたあと、誓約書の下にある署名欄に名前を書かせた。
そのあと、院長が懐からカッターナイフをとりだしたので、洋一は、あ、と声を上げた。
「心配するな。判を押すだけだ」
といいながら、院長は彼の親指を切り裂いた。
カッとした痛みがあった。かと思うと、洋一の親指に、見る見るうちに血があふれ出してきた。
院長は指にたっぷりと血がついたことを確かめると、名前の横に拇印を押した。
「これでいい。これでお前は正式にうちの院生となった。お前は以降十年間をここで暮らすんだ。これからは俺と養護院の生徒がお前の家族だ」
院長は誓約書を掲げた。
「逃げ出してはいけないと書いてある」
「誓約書に違反したら、どうなるの?」
洋一は怖ろしかったが、どうしても訊きたくてその質問を口にした。それに、これ以上は痛めつけようがないんじゃないかという、期待があった。
院長はさも心外なことを聞いたと言いたげに、
「それは法律違反じゃないか……そんなことをしたらどうなると思う?」
洋一はうなだれて答えなかった。
「お前は裁判にかけられて、刑務所に入ることになる」
院長は保証すると言いたげにうなずいた。それから、洋一の頬をはりとばした。
「そこはここなんかより、何十倍も怖ろしいところだ。そこに入らないためなら、なんでもするという気分にお前はなる。養護院を変わりたいなんて、そんなことは思ってもだめだ。そんなことはできない。世話になった俺にたいして失礼じゃないか。しゃんとした俺様がお前をしゃんとさせてやっているというのに。第一どこも似たようなものだし、どこよりもうちがましだからな」
院長は立ち上がると、扉に向かっていった。
「お前はここにいるんだ。わたしの許可がないかぎり、一歩も外に出てはいかん。出るかでないかは傷の治り具合をみて俺が決める。もし、規則をやぶったときは……わかっているな?」
院長は部屋を出ていった。出ていくときは洋一を見もせずにこう言い残していった。
「養護院、みろくの里に、ようこそ」
□ その二 ほらふき男爵、かく現りき
○ 1
暗闇だった。その闇の中で洋一が覚えているのは、体の痛みと心の痛み、院長の放ったアンモニアの臭気。日本酒のまじった、あの臭いときたら……。
時折身じろぎしたが、その身じろぎすら体に走る激痛のために、苦痛ですらあった。彼は暗闇のなかで涙した。院長の痛烈なことばの数々は、受け入れるべからず両親の死を、むりやり洋一の喉に押しこんできた。もう二人には会えないんだ、と思うと、彼はつらかった。自分もこの世から、消えてしまいたかった。
これからは自分が家族だ、と院長は言った。洋一は、
「あんな家族なら、欲しくないよ……」
と、闇の中で答えた。
洋一は闇の中で横たわったまま、夜が明けるのを待った。夜が明けたとて、ここを出られる訳もないのだが、院長に逆らって、ふたたび虐待が行われれば、拘束はさらに長引くものと思われる。
「父さんも、母さんも、ぼくをちゃんと育ててくれたんだ……お前なんか」
熱いものが喉にかかって、先をつづけられなかった。びっくりするほど熱い涙がこみ上げて、しゃくり上げて泣いたのだった。
あんなふうにいわれっぱなしで、自分や父さんにたいしてもうしわけがなかった。なんとすれば、両親はもう反論なんてできないのだから、かれこそがあの院長に、きっといってやらなければならなかったのだ。
それから洋一は院長にいわれたことを一生懸命考えてみた。大人からこんなふうに扱われたからには、自分が悪いことをしたからじゃないかと、疑ったのだ。だけど、院長の発した言葉の数々は、彼にとってたいはんが意味不明なものだったし、自分のどこが悪かったのかはわからなかった。
洋一は涙をこぼしたが、院長に聞こえないよう、必死に嗚咽をかみころした。それから、誓約書の規則をやぶったら、刑務所にいれられるなんてほんとかな? と考えた。いくら彼が小学生とはいっても、多少の知識はある。
院長の言葉は信じがたかったが、それでも彼はこどもだ。
刑務所がここよりもおっかないところなのは、ほんとかもしれない。あそこは、罪を犯した大人の人がはいるところだ。
事態がこれ以上悪くなるなんて、それこそお笑いぐさだが、いまの洋一にはすべてが悲観的に見えた。生活と人生がすべてひっくりかえった小学生が、奈落の底まで落ちこんだとして、それを攻められる人なんて、きっと三千世界にいやしないのである。
○ 2
さて、牧村洋一は、体をのたくる激痛に歯を鳴らしながら、なんとか手をつき身を起こした。闇に目がなれて、涙をぬぐい落としてみると、そこがデスクや本棚のおかれた狭い物置であることがわかった。
洋一は立ち上がって、扉に鍵がかかっているか確かめようかと思ったが、足を振り上げ、暴れ狂う院長の姿がなんども脳裏をよぎって、立つことすらかなわなかった。そんなふうにおびえるのは腹立たしくもあったが、院長の殴打は彼のガッツを根こそぎ持ち去ってしまったものらしい。
洋一は腫れ上がった瞼の下で、部屋の端にカーテンが掛かっているのを見た。一瞬彼は、映画の主人公よろしく、そこから逃げだす自分の姿を想像したが、体が怪我で思うように動かないいま、逃げだしたところで捕まるのは時間の問題だった。車でここに来たから、自分のいた洋館がどのあたりにあり、どのぐらいの距離があるのか皆目わからなかった。ここを出たところで、家に帰り着くのはむりだと彼は考えた。なによりも、自分が逃げだすことを、院長は望んでいるような気がして(望んでいるのは、その結果行われる虐待をだ)、洋一は行動を起こす気になれなかった。
窓があると思われるカーテンの向こうから、ホトホトと中をおとなう物音がしたのは、洋一がしばらくここに身をひそめていようと、考えることすら放棄しようとした、まさにそのときだったのである。
○ 3
洋一はびっくりして目をしばたかせた。誰? と彼は声をかけたのだが、喉からは空気の漏れるかすれた音しかでなかった。院長の言葉と打撃は、彼をすっかり萎縮させていた。あの院長が、窓にまわって見張っているんだろうか? と彼は考えた。
洋一は、もうなにもかもが嫌になり、また涙をこぼしながら横たわろうとした。そのとき、
「洋一、洋一……」
窓の外にいる誰かが、彼の名を呼んだ。院長の声ではなかったが、洋一はかえりみなかった。
「ぼくはもういない。牧村洋一は死んじゃったんだ……」
洋一は空耳だろうと、背を向けつづけた。ひどい激痛で、考えることすら億劫だった。すると、
「洋一、おらんのか? おのれ、返事がない。奥村、玄関にまわって様子を見てきてくれ」
玄関っ?
洋一は体を痛めたことも忘れて、身をひるがえした。
たいへんだ、そんなことになったら、院長がまた目を覚ましちゃう。
洋一は立ち上がってとめようとしたが、院長に痛めつけられた足のために、その場に膝をついてしまった。
「待って……」と彼は院長に聞こえないよう細心の注意をはらって、外の男に声をかけた。「ぼくならここにいる。よけいなこと、しないでよ」
「おお、洋一、そこにいたか」
洋一は外の男の無遠慮な大声に腹が立った。
「ちくしょう、ぼくはこんなに苦労してるのに、なんでそんな大声をだすんだよ」
というと、身も世もなく泣けてきた。
「うむ、この窓には鍵がかかっておるな」
「格子もじゃまですな」
別の男が言った。
「洋一よ、わしらに手を貸して欲しい。まずは窓を開けて、顔を見せてくれ。洋一」
洋一は耳をうたがった。ぼくの方こそ、人の手を借りなきゃ立てないぐらいなのに、手を貸してくれだって?
いったいどうなっているんだろうという疑惑が心をかすったが、洋一は心にわいたかすかな希望にすがりついた。スーパーヒーローを信じるには彼は年をとりすぎていたけれど、それでも外の男たちが自分のことを知っていて(でなければ、なんで名前を呼んだりするだろう!)、院長とは無関係の人間であることだけはわかった(そうでなければ、なんで窓から呼びかけたりするだろう!)。
「役所の人なの?」
洋一は言った。足立という人の様子から見て、あの人たちは、あたごの実態を少しは理解しているようだった(それなのに自分をひきわたすとはひどい話だが)。ひょっとしたら、外にいるのは父さんの友人かもしれない。
ともあれ、いまの洋一は、なんにでもすがりつきたい気持ちだった。彼は痛む足を引きずり、ソファーやデスクに手をついて、窓ににじり寄りはじめた。
「待って、すぐに開けるから、待ってよ。玄関にはまわっちゃだめなんだ」
「おお、洋一、なつかしきわが友よ。顔を見るのも久方ぶりなら、声を聞くのも久方ぶり……」
外の男は、舞い踊るような声音で言った。洋一は、どうにも変な人だな、と泣き笑いの顔に滴をつけながら、窓へと向かっている。
「待ってよ。院長に痛めつけられたんだ」
洋一はやっとの思いで窓にたどりついた。薄い緑のカーテンを月明かりが照らし、外ではまだこの夜にみた満月が照っているようだった。自宅であんパンを食べ、本を読んでいた時分のことを思いだすと、すべてが夢であるような気になった。
ああ、この痛みだけでも、夢と消えてくれたらいいのに。
洋一はカーテンに手をかけた。咳きこむと、白い息の中に血の飛沫がまじり、彼はぞっとした。口の中もずいぶん切ったようだった。
「なにがあったのだ洋一、しっかりせい」と表の御仁は慌てた様子だ。「我らには危険が迫っておる。気を抜いてはいかんぞ」
抜いたりするもんか。
洋一はカーテンを引き開けた。そして、口をあんぐりと開けた。
格子の向こうにはどでかい鷲鼻をした白髪の男が立っていた。
十八世紀の貴族が被っていたような、豪奢な絹の帽子を頭に乗せている。その帽子からは、大きな鳥のはねが、ひらひらと揺れていた。洋一が、絵本でみた貴族の挿絵を想像したのは、男の目が青かったからだ。本物の白人で、しかも、その髪は、ルイ十六世のように幾重にもカールをまいていた。窓の向こうに立っているから全身は見えないが、大昔の赤い軍服めいたものを着こめかしている。背も高いようだった。
洋一は顔をゆがめてカーテンを閉めようとした。頭がおかしくなったと思ったからである。
「どうした?」
とその赤づくめの服を着こんだ白人の老爺は言った。洋一は老人をよくよく見直した。彼の服はナポレオンが着ていた服みたいに紐やボタンがあちこちについて、装飾がほどこされている。おまけに腰にはサーベルをさしている。
「本物なの?」
「なにをいってる。こどものころ会ったろう?」
「記憶にないよ。あんた、誰?」
「わしはミュンヒハウゼン男爵。お前の父の親友にして、よき仲間、お前の名付け親でもある」
洋一は顔を上げた。両親から、自分の名前をつけたのは、外国人だと聞いていたからだ。だが、洋一の頭ではミュンヒハウゼンの名が、いくつもの連想をともなって、ぐるぐると回っていた。
ミュンヒ、ハウゼン。
「でも、ぼくその名前きいたことあるよ。家にある本に出てたもん」
「いかにも。わしこそがほらふき男爵」
「なにをいってんだ。父さんのともだちだって? じゃあなんでこんなときに仮装してるんだよっ」
洋一は窓を開けた。十二月の冷たい空気がしのびこんできた。男爵の背後には、着物をめかしこんだ小柄な男が立っている。頭の上に乗っかっているのはちょんまげみたいだ。月代こそ剃っていないが、腰には刀を差している。
最初の男はミュンヒハウゼンの仮装で、こっちは侍の仮装をしてる……洋一の心に、むらむらと怒りがわいた。しかも、男のわきには、洋一とおなじぐらいの年恰好の少年が、男と似たような格好をして立っていた。その少年も、おもちゃみたいな刀をさしている。
「誰だよ!」
声がすっとんきょうに高くなった。
ミュンヒハウゼンがふりむいた。
「彼は奥村左右衛門之丞真行。お前の両親の友人だ。あれは奥村太助と申すもの。奥村の子息である」
と言った。
洋一は怒りに身を震わせた。
「ぼくの父さんも母さんも死んじゃって、あさってには葬式があるんだぞ。ともだちならなんでそんなふざけた格好をしてるんだよ」
「お前こそずいぶんではないか」ミュンヒハウゼンは落ち着きはらって、鷲鼻の下のちょび髭をなでた。「ひさしぶりにあったというのに、ふざけたとはなんだ。お前を見つけだすのには苦労したのだぞ。しかし、お前の身に起きたことを思えば……」
ここでミュンヒハウゼンは口をぽかんと開けた。
「その傷はどうした?」
自分では気づかなかったが、洋一の姿はまったくひどかった。まぶたも唇も腫れ上がっているし、やけどをしたところは広範囲に炎症をおこしている。殴られすぎたのか、ろれつもおかしくなっていた。
「ここの院長にやられたんだ」
思いだすだけでも悔しく、くちびるをかみしめる。ミュンヒハウゼンと奥村が顔を見合わせた。
「何者だ?」
と、男爵は怒りを押し隠した声で(隠しきれていなかったけれど)言った。
「ここの院長だよ。団野院長。知ってて来たんじゃないの?」
男爵は渋い顔をした。
「われわれは今日になってようやくこちらに到着したのだ。だが、一歩間に合わず恭一たちは救えなかった」
洋一の頭で、またも疑問が渦を巻いた。その疑問は、心を締めつける荒縄のようだった。
救えなかった――救えなかったと男爵は言った。両親は交通事故で死んだと聞いている。事故は突発的に起こるものだ。なのに、救えなかったとはどういうことだろう?
奥村が、「男爵、そやつもウインディゴの手のものかもしれませぬ。急ぎましょう」
「ウインディゴってなにっ?」
洋一はとうとう悲鳴を上げた。ミュンヒハウゼンと奥村はまた顔を見合わせた。「知らんのか?」と男爵は逆に面食らったようだ。
「知るわけないよ。ぼくはあんたたちのことだって知らないんだぞ」
奥村が、
「ともあれ、ここから救い出しましょう」
と言った。洋一は初めて奥村と目があった。気づかわしげな視線だった。それは、両親が彼にいつもかけてくれた視線だった。不覚にも、洋一は鼻っ柱が熱くなった。
「だめだよ、ぼく契約書にサインしちゃった。ここを出たら、ぼくは刑務所にいれられるんだ」
「なんの話だ?」とミュンヒハウゼン。
「契約書なんだ。院長にいわれたんだ。ぼくはこの養護院を出てはいけないし、ここのことを誰かに話してもいけない。ぼくはもう二度とここから出られない……」
洋一が涙ながらに訴えると、男爵は怒りに身を震わせた。
「わしはお前の洋館に立ち寄り、お前はお前を保護する施設に入れられたと聞いた。わしは、お前がこの国とこの国の役人に保護されていると信じた。だが、来てみればどうだ。わが親愛なる友人の息子にして名付けの子は、痛めつけられ、目も覆わんばかりのありさま」
「でも、ぼく……」
「しっかりしろ洋一、人を保護する法はあっても、人を縛る法などないぞ。さしづめそやつはウィンディゴに支配されておるのだろう。だが、わしらが来たからには安心しろ。お前の身は必ずや守ってやる」
その申し出に、洋一の顔はかがやき、胸は熱い思いでみたされた(ウィンディゴのことはさっぱりわからなかったけど)。洋一は目の前をじゃまするデスクを乗り越え、格子に近づこうとした。だが、そのとき、彼の背後で扉が開き、廊下の明かりが暗い物置に差しこんだ。
○ 4
団野は部屋に入ってくるなり、開口一番、
「なにをしている」
と言った。団野は男爵たちに度肝をぬかれたようだ。彼らから目を離すことができなかったが、それでも洋一のもとに駆け寄り、彼をデスクから引きはがすことはできた。洋一が、体にはしった激痛に悲鳴を上げ、表の三人が怒りを発した。
「なんだお前らは」と団野は言った。「ここは俺の敷地内だぞ。なんだ……おかしな格好をしやがって! とっとと出ていけ!」
「貴様などにいわれなくとも出ていくわい」と、男爵は、口辺に唾をとばしてわめいた。「ただし、その子も一緒だぞ。我が輩こそは、その子の真の保護者だからな」
「なにをいってやがる、この餓鬼にもう身寄りはいないんだ」
そういって、洋一の頭を押さえつけた。団野のローブからただよう酒の香りが、強く彼の鼻腔をみたした。このさき洋一は、酒の臭いを嗅ぐたびに、真っ赤な唇を、叫びの唾でぬらす団野のことを思いだす。
開け放たれた窓からは、真冬の冷気が、かんかんと部屋に注ぎこむのに、団野の体からは、狂気の熱気が漂いだすかのようだ。現に、団野は、零下に近い室温のなかで汗をかき、真夜中だというのに、きれいになでつけた前髪を、額に幾筋もたらしている……。
洋一は、団野が手荒くあつかう体の痛みよりも、心の痛みのほうが強かった。男爵はああいってくれるけれど、ぼくの身内はもういないんだ――
「だから痛めつけてもいいというのか?」
奥村はまるで居合い斬りをしかけるかのように、低く腰を落としている。彼が低音の押し殺した声でいうと、団野ははっと洋一を見下ろした。
「この子はうちの院生だ。院生は規則にしたがう必要がある。院生はしつける必要だってある」院長は燃えたぎる眼光で、奥村たちをみわたした。「ここでは団体生活をおこなっているんだ! 規則をさだめてしたがわせなければ、院内の生活はどうなる! 院内の規律は! それにこどもを鍛えるのは俺の役目だぞ! この俺の使命! だから――」
「だまれ、この若造!」と男爵は手にしたサーベルで地面をつき、雄々しく腕を振り上げた。あふれんばかりの情熱という点では、かれも団野に負けてはいない。「その子は我が同胞にして我が家族! 手をあげるものは何人たりともゆるさんぞ!」
「俺があずかったんだ!」と院長は唾を飛ばしてわめいた。「俺がこの子の親代わりだ! おいっ!」
団野は洋一の右手をつかみ上げる。洋一は骨が砕けるんじゃないかと思ったが、団野から目線をはずせなかった。ちょっとでも視線を外したら、また痛めつけられると信じていたからだ。
「オマエはここの生徒だ」団野は洋一のほおを拳で殴りつけた。男爵たちが、抗議の悲鳴を上げた。「ここの院生こそがオマエの家族だ!」もう一度。「俺がオマエの親で!」もう一度。「オマエは息子なんだ! わかったかわかったかわかったか」
団野はそう連呼しながら、洋一の頭をこずきつづけた。男爵たちがなにかを叫んでいるが、洋一の心には、もう団野に殺される恐れしかない。
舌が口の中でふくれあがり、気管をふさいで、息もできなくなった。もう息をしたくなかった。恐怖心が彼の体を殺しかかっていた。
だが、こめかみから流れだした血が、床に落ちた瞬間、ショック死しかかっていた身のこわばりがとけた。血は、事故を連想させた。両親の姿が、彼の目蓋に浮かんだ。両親はいなくなったけれど、彼の体は、二人の記憶を誰よりも色濃く残している。その点で、洋一の両親は、この世とつながっている。洋一は、自分が死んだら、二人は本当にこの世から消えていなくなってしまうんじゃないかと、そう信じたのだ。
血の水滴がまた三つ――洋一はふりむき、団野の姿を視界にとらえた。
洋一は、ふりあがる団野の拳のタイミングを見計らうと、かの拳が舞い降りかけた瞬間、身をひるがえし、戸口にむかって駆けだした。団野は目標をうしなって、身をふらつかせている。男爵は、走れ、玄関まで走れ、と、狂ったように叫んでいる。
洋一は走った。ふらつく足で、痛む肋を腫れ上がった指で押さえ、自由への扉めがけて駆けぬけた。後ろからは団野が狂気の熱を帯びた罵声を上げ、スリッパをばたつかせる音も高らかに追ってくる。追いついてくる。玄関が見えた。廊下を曲がって、一歩二歩、廊下をなかばまで来たときには、彼はゴールを目前にひかえたマラソンランナーのように疲労困憊だ。洋一はドアノブに向かって、めいっぱいに手を伸ばした。
団野は彼の襟首をひっつかみ、その自由への逃避行を阻止したのだった。
洋一は虎柄にもにた敷物のうえで、体をふりまわされた。
「貴様あ、契約書にサインしたろう! 忘れたのかあ!」
団野はもう一度洋一をぶとうとした。洋一は両腕で頭を抱えながらわめいた。
「お前なんかぼくの両親じゃない! あんな契約書くそくらえだ! ぼくは、ぼくはあんなもの……」
団野は洋一にのしかかり、顔を床にたたきつけ、押さえつけた。洋一は苦しい息の下で、まだなにかをしゃべろうとした。かれ自身のためだけではなく、両親のために。ここでひきさがったら、一生団野のことをおびえて暮らさなきゃいけなくなるとわかっていた。だが、洋一は団野の膝で首をおさえつけられて、ほとんど窒息しかかっている。男爵が玄関扉を引き開けて、昔日の勇者のごとくおどりこんでこなければ、彼はきっと涙の下で意識をなくしていたにちがいない。
洋一が顔を上げると、無敵の男がそこにいた。海賊が被るような金縁の黒帽子に、大きな鳥の尾羽をなびかせ、息も切らせて駆けこんでくる。ああ、そう、彼は年老いたフック船長のようでもある。だけど、彼はほらふき男爵その人だ。サーベルを手に傲然と立ち、ブーツの音も高らかに玄関口から上がりこんでくる。
「貴様、洋一から離れろ!」
ミュンヒハウゼンは、扉を叩きあけた瞬間から絶叫をした。三百五十年の長きにわたって、人々に愛されつづけた男爵の義侠心に火がついた。彼はサーベルを引き抜いて突進したから、さしもの団野院長も、洋一の上から身をひきかけた。
「不法侵入だぞ」と彼は言った。「こんなことをしでかしてただですむと思うな! 警察は貴様らをとっつかまえるぞ、そんな刃物でこのわしを脅したんだからな!」
「なにをこのちょび髭の下郎!」
と男爵は火のでるような絶叫を上げ、手にしたサーベルを床に突きたて、
「奥村、ここはわしに任せろお!」
と背後の二人に呼ばわった。
「決闘じゃ」
男爵は右の手袋を脱ぐと、団野にむかって放り投げた。
「その子と我が命をかけて決闘をもうしこむぞ! さあかかってこい!」
○ 5
団野はミュンヒハウゼンがそう宣言したあとも、まだ年若の奥村の方が脅威のようで、表の二人に油断なく視線をはしらせた。男爵は両腕を上げて、ボクシングのポーズをとっている。団野を挑発するかのように、軽く拳をくりだした。
洋一の体から、そっと圧力が遠のいた。
団野は立ち上がり、うめき声をあげながら、ミュンヒハウゼンとにらみ合った。
最初のうち、男爵は優勢だった。格闘技をかじっていたようで、軽快なジャブをくりだし、右左のフックを浴びせかけたが、団野も狂える闘争本能で盛んに応戦をした。
男爵は、おそらくは七十になんなんとする老人である。男爵のはなった十発のパンチのうち、八割は相手方をとらえはしたが、団野のはなった二発の渾身のフックと右ストレートが男爵の顔面をとらえると、このはてなき闘争は完全な逆転劇を展開しはじめた。男爵は巧みなボクシング技術で、団野のくりだす闇雲な攻撃をかわしはしたが、あふれ出る鼻血で息を切らし、目にみえてスピードは鈍り、足下も不確かなものとなった。
団野の拳が、男爵のこめかみをとらえると、奥村が刀に手をかけとびだしかけた。男爵は大手をふってこれを制し、
「来るな、奥村、これはわしとこいつの問題」
と苦しい息の下で言った。
洋一は、なんど男爵にサーベルをとってと言いかけたかわからない。だが、彼の目にやどる不屈の闘志が消えさるまでは、その言葉を口にすることはできなかった。なによりも、洋一は見たかった。かのミュンヒハウゼン男爵が、数々の困難劣等をのりこえて、恐怖の院長を討ち果たすところを。
一方、男爵はその洋一の視線に気がついていた。明るい屋内灯の下で見ればどうだろう、我が名付け子の、惨憺たるようすは。かならず牧村親子を守るといいのこしてきた国の者たちに、もう顔向けもできない。
だが、男爵の体は、その不屈の闘志にもかかわらず、自らの期待を裏切ろうとしていた。数刻もえない闘争で、体力は尽き果て、膝はその身を支えることすらおぼつかない。
男爵は団野の狂い獅子のような猛攻をひたすら受けつづけるばかりで、反撃の余力ものこしていない。男爵の必死のブロックは、団野の若い力任せの攻撃を防ぎきれなくなった。男爵の腕は骨も砕けんばかりにはじかれ、団野の拳はついにその身に届きはじめた。アゴをはじかれボディブローをくらい、ミュンヒハウゼンはその身を屈しかけている。
男爵はボクシング技術を捨てて、団野の腰にくみついた。彼は足腰を奮いたて、団野の体を押しこみ、壁際に体勢をもちこんだ。勢いあまって、ミュンヒハウゼンは頭蓋を壁につきあてたが、もうかまっていられない。団野は拳を振り上げ、ミュンヒハウゼンの痩せこけた老体をうちすえるが、男爵も腰にかぶりついてはなれない。彼は洋一の敵をとろうと必死だった。あまつさえは、この団野が洋一の両親を殺した憎い敵のような気になってきた。
ミュンヒハウゼンは、足をつっぱって団野の胴体を圧迫した。団野が苦しんで攻撃の手をゆるめる。男爵は一瞬のすきをついて身を起こすと、団野の顎をめがけて、猛烈に身を突き上げた。
骨の砕ける、いやな音があたりに響いた。男爵の頭突きは、団野のとがったあごを見事にとらえた。団野の体から急速に力が抜け、壁に向かって崩れかかった。
男爵は身を離すことすら億劫になり、しばらくその体勢のまま団野に身をあずけていた。
そのうち、団野は壁にもたれかかった姿勢のまま、ずるずると身をすべらせ、そのまま床まで崩れ落ちていった。
○ 6
洋一の見ている目の前で、男爵と院長はともに床まで頽れていった。洋一の目には二人が相打ったように見えた。だが、血を噴き、正体なく首をくゆらせる団野を見て、男爵の勝利を確信した。
「おみごと!」
奥村が大声をあげてミュンヒハウゼンに駆けよった。
男爵は重たそうに痩せた身をひきおこし、どっかりとあぐらをかいた。
洋一は痛む膝をかばいながら立ち上がろうとした。奥村の息子が駆けつけ、脇に手をさしいれる。洋一は、痛む肋に顔をしかめながら、太助をみる。
男爵は団野のことをいまいましそうに睨みつけながら、
「ここが物語の世界なら、首を刎ね落としてやるのに」
洋一は、興奮にまぎれて、その言葉を聞きのがした。まだ、このときは。
ミュンヒハウゼンは、奥村に支えられて立ち上がった。洋一がちかづいた。
男爵はこの数分の闘争で、めっきりと年老いたかのようだった。
「遅くなってすまなかったな」
洋一に負けないくらいに顔を腫らした男爵が、彼の頭に手をおいて、
「恭一のことはすまなかった。あいつは立派なやつじゃった。しかし、お前も恭一に負けないぐらいに立派な男になったらしい。お前とわしはともにあやつに負けなかった。そうおもわんか?」
男爵に言われて、洋一の目に涙がたまった。あやつとは院長のことなのだとは、容易にわかった。だけど、院長に痛めつけられても洋一の心が折れなかったのは、ひとえに男爵のはげましのあったおかげである。団野は彼の体を痛めつけた。けれども、それ以上に両親が死んだんだと思い知らされたとき、彼の心はへし折れる寸前までいった。団野の拳と言葉は愚風のようで、彼の身骨を砕こうとした。だが、その折れかけた細い身茎を支えてくれたのは、名付け親を名乗るやせっぽちの老人なのである。
洋一は、この日一度たりとも口にできなかった疑問を、男爵になら話すことができた。ミュンヒハウゼンはたしかにほらふき男爵なのかもしれないが、いつわりは一言たりとももうさなかった。それは、男爵の心と言葉が、見事に一致しているからだった。だからうつむいてこう訊いた。
「父さんも母さんも、まちがいなく死んだんだ。そうでしょ?」
頭におかれた男爵の手が、そのときだけは揺らいだようだった。
「牧村は世界中に仲間がおる、とびきり優秀なやつじゃった。わしはあいつが大好きじゃ。だが殺された。殺されたのだ」
「誰に?」
洋一は、涙にくもる目で男爵をみあげた。彼はこのときだけは、まだ見ぬその相手をはっきりと憎んだ。
「洋一、お前にこのようなことをつたえるのはつらい……。ほらも吹けぬほらふき男爵、あいすまぬ」と男爵はポロポロと涙をこぼしながら頭をさげた。背後で奥村親子も泣きにくれている。「この奥村左右衛門之状真行は、恭一とともに旅した無二の仲間である。そして、恭一と薫の二人は、ウィンディゴの手によって命を落としたのだ。車の事故とは、見せかけだ」
男爵は大きく鼻をすすった。
「ウィンディゴって? 外人?」
男爵は迷うように、洋一の顔の上で視線をさまよわせた。
「話してよ」洋一は、男爵の豪奢な服の袖をとった。その服が、本物の絹の手ざわりであることを知った。「話してよ。ぼくには知る権利がある。そうでしょ?」
男爵はだまって視線をそらす。
「ぼくは知りたいんだ。父さんも母さんもいつもぼくになにか隠してた。ぼくにはわからないことがいっぱいあるんだ。二人とも図書館をやってたって、ろくに働いてないのに、なんでうちには生活するだけの金があるのか、うちは市立の図書館でもなんでもないのに、それこそ私設の図書館なのに、世界中から本を集めたりしてる。父さんのところには世界中から手紙が届いてた。世界中に仲間がいるってのはうそじゃないんだ、きっと。だって、いろんな国の人が、電話をかけてきてたもん」
「まずは、おちつけ」
「いやだ」と洋一は男爵の手をふりはらった。「ぼくが立派に育ったって、本気で思ってるなら話してよ。父さんも母さんも、ぼくがこどもだと思ったから話さなかったんだ。二人ともだまったまま死んじゃった。い、命を落とすぐらい、危険なことなのに……」
そんなのひどいと思った。
「だから、話してよ男爵。ぼくは、ほんとのことが知りたいんだ」
男爵は払われた肩に、もう一度両手をおいた。彼は片膝をつき、洋一と顔の高さをおなじくし、
「お前はほんとに見上げたやつだ。だが、この話は……いままで聞かされたことがなかったのだから、信用できるかできないか」
彼は吐息のかわりに顔を垂れ、その面を上げ、
「お前にわしの知るすべてを話す。だが、恭一たちが死んだいま、わしらはお前の助けを借りねばならない。話を聞いたあと、お前にはこれからの生き方を決めてほしいのだ。お前は一人前の男だし、生き方を決める権利とてもっている。お前はもう、そういうことを決めていかねばならんのだ」
男爵は、両親が死んだのだからだ、という言葉をのみこんだ。そのことを、洋一は直観で知りえた。洋一は、その重荷をかんじて体が震えたし、また涙がこぼれそうになった。だけど、どうあっても、そうしたことから逃げるわけにはいかないのだから、なんとか涙をのみこんだ。「わかったよ、男爵」
「わしはお前に強制はせん。あるいはわしらと来るより、ここにいた方が安全なこともあるだろう。そのことも、わかるか?」
洋一はうなずいた。男爵は満足そうに頭をなでた。「それでいい。それでこそ、恭一の息子だ」
男爵は、倒れている団野をかえりみて、きらりとその目を光らせた。
「さて、契約書とか言ったな」
◆ 第二章 狂った物語と世界の真実
□ その一 三人の新しい仲間と、牧村一家の役目のこと
○ 1
「おい、起きろ」
奥村が刀のこじりで、団野の肩をついた。
「狸寝入りなどしおって。貴様、洋一に書かせた契約書をどこに隠した」
洋一は、まだ団野に息があったことに驚いた。
奥村につめよられると、団野は抵抗する気力もうせたようだ。奥村は細身ながら、その身ごなしは、いかにも武術で練りあげたらしい、無駄のなさと切れがあった。
「暖炉の上の金庫にある……」
と団野は言った。口元から、大量の血液がこぼれ落ちた。酔っていることも手伝って、血が止まらないものらしい。胸元を血で染めながら、奥村にひったてられた。
洋一は、あたりに立ちこめる血の臭気に、団野にたいする恨みの気持ちも忘れた。彼の人生はいたって平穏で、身のまわりでおきた暴力と破壊の結果に、ついていけなかったのだ。
三人は団野の惨憺たる様子にも顔色ひとつかえていない。みんなこういう光景になれているんだろうか? と洋一は思った。気後れから、リビングに向かう一行とも、距離を置いた。
団野は院生に内職をさせ、こつこつと金を稼いできた。リビングの調度は、デスク、絨毯にいたるまでかなり豪奢なものだった。カーテンひとつにいたるまで、ずいぶん金をかけているようだ。
大柄な暖炉をつくり、その上には壁をくりぬいた金庫があった。団野がダイヤルをまわし金庫を開けると、札束やダイヤがみえた。かなりの量だ。そのうえに、院生に書かせた契約書の束が、クリップでとめられ乗っかっていた。団野は契約書を男爵にてわたすと、暖炉の前にすわりこんだ。
ミュンヒハウゼンはしばらくその契約書をパラパラとめくっていたが、やがてびりびりにやぶくと、暖炉にほうりこみ火をつけた。暖炉のなかで、契約書はこれまでの院生の苦しみをあらわすように、身をくねらせ真っ黒になる。紙は灰になり、団野のかわした契約も反故となった。
団野はその間、ぐったりとうなだれたまま、男爵の方を見ようともしなかった。ひとつには、あごが砕けて、しゃべることもおっくうであったのだ。
ミュンヒハウゼンは、真っ黒な墨とかしていく契約書をみつめながら、団野にむきなおり、
「これが本物であろうとなかろうと、紙切れで人を縛ることなどできはせんぞ」
とおごそかに言った。この後、男爵はさまざまな事柄を告げては洋一を悩ませることになるが、このときの振る舞いだけはまっとうだったといえる。
団野は、一瞬、ミュンヒハウゼンをにらみあげたが、すぐにそっぽを向いた。
「貴様、他の院生にもおなじことをしておるのだろう。一人前の男のくせに、弱い者いじめなどをしおって、恥を知れ」と言った。
それから洋一にむかって、
「たとえ契約が本物だろうと、無法な法にしたがうことなどはないのだ。社会の法がいかに必要だろうとも、人は魂に法をもっておる。魂の法とは名誉なのだとわしは思う。人の名誉尊厳をおかす権利など、神にとてありはしない」
男爵はふさがっていない方の目で、団野をにらみつけた。
「貴様が正しいと思うのなら、わしはこの子の洋館におるから、いつでもかかってこい。わしのこの身と名誉にかけて相手になるぞ」
○ 2
団野の家を出たとき、洋一はまさに十何年の刑に服した囚人の気分だった。外はまだ夜で、事故の起こった夜のままで、だけど彼には十年ばかりの月日がたったかのように感じられたのだ。この夜は実にさまざまなことが起こり、そのたいていのことが彼にとっては初めての経験ばかりだった。だけど、彼の中でまったく色あせることなく燦然と輝きつづけていたのは、両親を亡くした悲しみという感情だった。
洋一は団野の庭に立ちつくし、しばらくあたりを見回した。男爵たちは無言で洋一の言葉を待っている。ミュンヒハウゼンは来たけれど、彼の両親は来ていない。吐く息がいやに白く、洋一はそのことにすら悲しみを感じた。
空を見上げた。悲しみは去らなかった。新しくできた三人の仲間の方を向き、無言で話のつづきをうながした。
男爵はゆったりと足を踏みかえながらきりだした。
その大筋はこうだ。洋一の両親、牧村恭一と牧村薫の二人は、ただの私設図書館の職員なのではなく、本の世界をまもるための番人だった。彼らは世界中から初版本を集め図書館に保管していた(どうりで古めかしいへんてこな本ばかりあるわけだ! 大昔の作家の生原稿まであったのだから!)。
そして、男爵はこういうのである。いま、世界の人たちは本を読まなくなり、物語は力をなくし、その世界は崩壊しかかっている。ある本では話の筋が完全に狂い、善人が悪人となっている。登場人物たちの多くは目的意識をなくし、役割を忘れさっている……。
ちょっと待ってよ、と洋一は言った。「本の力とか、本の世界とか、どういうこと?」
「だから本の世界があるのだ。お前の両親は……」
「じゃあ、男爵は!」と洋一は大声をだした。「本物のほらふき男爵だって、そう言ったじゃないか!」
「そのとおり」
「じゃあ、もしもだよ」と洋一は急きこんだ。「もしもその話がほんととして、だったら男爵は本の世界の住人ってことになる」
「そのとおりだ」と男爵は重々しくうなずいた。「わしはもともとがほらを吹くという人物だ。余人とはちがい、創造の力をもっておるのだ。つまりは、物事を生みだす力だ。だから、物語の世界と中間世界を行き来することができたのだ」
洋一は言葉をなくした。ようやっと、「中間世界?」と問いかえした。
「本と現実世界の中間にある世界のことだ。中間世界は現実の人々の思考の力、意識の力でできておる……とわしは思っておる」
「勝手に思えばいいじゃないか」と洋一は言った。その唇は震え、瞳からは涙があふれだしていた。「勝手にすればいい。本の世界とか、中間世界とかわけのわからないことをいうな!」と彼は言った。「ぼくは両親のことが知りたいんだ。父さんと母さんがなんで死んだのか知りたいんだ。理由なんかなくたって知りたいんだ! それなのに、わけのわからないことをいうな!」
と彼は言った。彼の言い分は理不尽なものだった。運や不運というものは元来わけのわからないものだし、洋一の両親が事故で死んだのだとするのなら、そこには男爵の知る理由などあるはずはないのだから。
「洋一」
と男爵はなだめるように手を伸ばしてくる。彼は後ろに躙り下がってその手をかわす。
「よいか、中間世界では狂った物語の影響が如実にあらわれておる。彼らは中間世界の住人なのだぞ」
と改めて奥村たちを紹介する。
本の世界というだけでも信用できないというのに、この中間世界というのも洋一の理解を苦しめた。それらの世界は、これまでとこれからの人々の記憶や感情の力で形作られていて、その意識の質により、いくつもの世界にわかれている。中間世界は中つ国とも呼ばれていて、たとえば、奥村親子たちがやってきた世界は、夢と冒険の中つ国と呼ばれているし、ウィンディゴが支配しているのは悪の中つ国である。三人は次元をわたる機関車にのって(江戸時代に奥村の先祖がつかったものらしい。ひどく骨董めいた話だった。)現実の世界にやってきた。しかし、時すでに遅く、牧村夫婦は命を落としたあとであり、たった一人の子息は役人によりつれさられたあとだった。
洋一はますます頭が混乱した。目の前にいるこの男爵が、体温を感じ、血をながしているこの男爵が本の登場人物にすぎないなんてそんなことがあるはずがなかった。洋一はこれまでなんどとなく本を読んできたが、物語の筋が狂っていたことなんていちどもない。
「さきほどからもうしているウィンディゴとは」男爵はさらにいう。「おそらくはわしと同種の……創造の力をやどした人物のはずだ。あやつは悪の登場人物をしたがえて日々力を増しておる。自分たちの都合のいいようにストーリーをねじまげておる。悪の中間世界を支配し、別の世界に影響をおよぼしておる」
奥村が言った。「我々はウィンディゴの勢力と戦ったが、力およばなかった」
「そこで我々は本の世界をたてなおし、すこしでもウィンディゴの勢力をそごうと考えたのだ」
ほらふき男爵は本の世界をとびだし、本の世界の救済にのりだしたが、そんななか、長年本の世界をまもりつづけた洋一の両親は、ウィンディゴの手により殺される。洋一の両親は世界中の初版本だけではない、伝説の書物をもっていて、本当はその本をまもることこそが役目だったのだ。伝説の書は、書かれたことを現実にしてしまう力を持っている。そしてそれをつかえるのは、ゆいいつ創造の力をもつ現実世界の人間だけなのだ……。
洋一はなんとか反論しようとした。本の世界などないし、次元をわたる機関車もない(そもそも別の世界というもの自体がないのだ)。文字はちゃんと紙に印刷されているのだから、それが初版本とはいえ、話が変わってしまうなんてこと自体がありえない。が、男爵も奥村たちもそれが当然の事実であるかのように話し、洋一との会話は、ある、ない、の堂々巡りにおわってしまう。
洋一はこの三人は頭がおかしいんじゃないかと疑った。男爵も奥村も根っからの善人なのだとは思う。まっすぐないい人たちなのだと……。だけど、あの格好としゃべっていることを考えると、団野に負けないぐらいの気ちがいとしか思えない。
自分をだましているのならまだいい、始末に負えないのは、この三人が自分の主張を芯から信じていることだ!
たとえ善人でも、気の触れた人はいるにちがいない……。
洋一は男爵の話をよくよく考えようとした。矛盾をというよりは、ちょっとでも信用できそうな部分を探そうと努力した。だけど、そもそもが荒唐無稽な話すぎて、受け入れようにもとっかかりすら見あたらない。洋一は男爵のことを信じたい気持ちと、そんなばかげた話はありえないと叫びだしたい気持ちとで、はちきれんばかりだった。洋一のまわりにはゲームも映画もふくめて(ちくしょう漫画もだっ)作り物の話ならごまんとある。そして彼はそれが作り物だと知っている……。物語の種は出尽くしたといっていいほどだし、いろんなことに説明がついてる。つまり不可思議なことを受けいれる下地は、彼の心から消えかかっていた。その意味で、人が本を受けいれがたくなっているとはいえる。だからといって、出来物の本が狂ってしまうだとか、この現実以外にも、いくつも世界があるだとか、それも本の世界だとかいう話はまったく受け入れがたかった。彼はこの三人は頭がおかしいんじゃないかと思いかけた。死んだ両親の知り合いのことをそんなふうに思うなんて、彼の良識(それが小学五年生の良識とはいえ)が許さなかったが、そもそも自分の親の知り合いだという話自体が怪しいものだった。
「だが、今後をどうするのだ」
と男爵は言った。洋一の怒りに初めて揺らぎがさした。
「わしとしては、残ったおぬしの力を借りたい。もはやここに残るわけにもいくまい。役人の世話になるというのなら、それでもいいが……」
「家に帰る。あそこはぼくの家だ!」
「それでもよい。家に帰れば、なにが起こっているかはハッキリするからな。だが、お主あまり気を抜きすぎて怪我をするなよ」
よけいなお世話だ、と洋一は思った。
○ 3
洋一はふるさとの洋館に向けて、暗い夜道を歩いていく。住宅街を抜けるせまい路地だった。さほど高くもないブロック塀が無表情につづいている。街灯の明かりが四つの影を、たがいちがいに伸ばしている。洋一は街路にみおぼえがあった。自転車でなんども通ったことがある。近くには押尾琢己というともだちの家があるはずだ(タク、タク、とともだちは呼んでいる)。とすると、あの養護院はおなじ町内にあったわけだ。
さて――
洋一こそ救うことができたが、恭一と薫の二人が死んだいま、一行の足取りは重いものであり、陽気な気配はどこにもない。奥村が洋一の手をひき、くたびれきった男爵を太助が支えている。だが、一行のなかで、もっともくたびれきり重い足を引きずるように一歩一歩足を進めていたのはきっと洋一だったろう。
彼は今日起こった出来事と、さきほど男爵から聞かされた言葉とをいくどとなく反芻した。痛めた足をひきずりながら歩き、いまごろ寺勘たちはのんびり眠ってるんだろうなあと恨みがましい気持ちで考えた。寺勘こと寺内勘太郎は、クラスでも一番の親友だった。養護院を逃げだしたことで、もとの学校にはもう戻れないだろうし、とすると寺勘たちにも二度と会えないわけだ。そもそも彼の人生がこれからどうなるのかすらわからない。それなのに、男爵ときたら……(洋一はこの老人のことを男爵と呼ぶことすらいやだったが、ほかに呼びようがないのだから仕方がない)。
洋一は両親の死とあんな養護院に預けられたショックでほとほと弱り果てているのに、あんなばかげたつくり話をきかされて、腹が立つやらすっかりうちひしがられるやらで頭のなかがくらくらした。男爵のことを一端は信用したのだが、その気持ちが消えかけたほどだ。
洋一はいつの間にか奥村の手を握りしめている。奥村が不審そうにかえりみた。
不審といえばこの奥村自体が不審だった。彼は本物の侍で、号を休賀斎ともいうらしい。彼は幕末に中間世界にわたった日本人の子孫だそうだ(少なくとも彼らの頭のなかでは、と洋一は皮肉めいた気持ちで考えた)。曾々祖父は幕府の御家人だったそうで、上野の戦争で負けたあと、仲間とともに中間世界にわたる町人たちのなかにまぎれこんだのだという。
「傷は痛むか」奥村が言った。彼はゆったりとくつろいだ様子の中にも目つきだけは鋭く、いかにも剣の達人といった風情があったが、つないだ手はいかにも柔らかく暖かだった。低く落ち着きのある声色で、そのいたわりのにじむ声を聞いていると、こんな人たちのいうことは信じるもんかと気をはる洋一も、ほろりと涙をこぼしそうになる。
奥村は、身長は百六十センチのなかばほどで、彼の父親の肩ほどしかない。背格好まで、昔の日本人そのままだった。
奥村は思いをめぐらすように、天に首を仰向ける。彼はこちらの世界にはじめてきた。中つ国とはずいぶんちがうようだった。
奥村は言葉を選び選びして話しはじめた。「君の父上とは、こどものころあったぎりだったよ。わたしは久々の再会を楽しみにしていた」と湿りを帯びた声で言った。彼は今三十七才で、恭一と出会ったころにはすでに元服をおえていたそうだ。そのころは中つ国とこの世界の通路はあちこちにあった。恭一は父親に連れられてなんどか中つ国を訪れていた。だが、その通路がウィンディゴの手により封じられたあとは、恭一の消息は男爵のもたらす風聞によるばかりだった。奥村は年の似た息子たちを引き合わせようと考えていたが、自分が恭一に会うことは二度とふたたびなかったわけである。
奥村は気を取り直すように肩をゆすり、こうきりだした。
「こどものころの恭一は気が強くてな。わたしはすでに剣術がそうとうつかえたんだが、恭一のやつは関係なく突っかかってきてな。向こうみずで、考えるより先に行動しては、あとで困ってな」
奥村は思いだすようにかすかに笑ったが、その笑いもじきに涙にまぎれてしまう。
「だが、勇敢で正義感の強いやつだった。わたしはあいつが大好きだった。会えなくなったそのあとも。わたしとあいつは血を分けた義兄弟だ」
洋一は驚いて言った。
「親指の傷のこと」
恭一の指には一文字の傷があり、こどものころともだちと兄弟の誓いをかわしたときに作ったのだといっていた。親類はいないが、血を分けた義兄弟がいるんだと。だから、家族の誓いのために親指に傷をつけた団野のやり方は、洋一にとっては他人以上に信憑性のあることだった。
奥村は軽く驚いたように洋一をみおろした。「そうだ。あいつの指にも残っていたか」
「強い思いのこもった傷はな、なかなか消えんのだ」
と男爵がぶっきらぼうに言った。
奥村はまた前を向いて歩きはじめた。
「よくあちこちを冒険したなあ」
洋一にはその冒険の内容まではわからなかったが、こどものころの父親の姿がほんの少し覗けた気がしてうれしかった。恭一は本好きで穏やかな人だったが、こどものころはそんな一面も持っていたのである。
「紹介が遅れたが」奥村はやさしげに微笑した。「あれはわたしの子息。奥村太助だ」
左隣を歩く少年がぺこりと頭を下げた。一つ年上ということだった。洋一より二ヶ月遅い八月生まれだ。父親とおなじ直新陰流を習い、こんどの旅にくっついてきた。
「わしらは恭一の力を借りるつもりじゃった」男爵が肩を落として言った。「洋一よ。ウィンディゴはまったくやりたい放題じゃぞ。中間世界との通路はあらかた閉じられてしまうし、使えるものもわしらにとっては危険すぎる。骨董の機関車をつかってやっとこの世界に来れたのだ。新陰流の使い手もほとんどやられてしまったぞ」
「わたしの仲間だ」と奥村が言った。
「わしらは狂った本の世界をすこしでも元にもどし、ウィンディゴの勢力を少しでもそいでおきたかった。だが、やつらはわしらの行動を読んでおるようだ」
「母さんは? 母さんも中つ国に行ったことがあるっていうの?」
「なにをいっとる。お前の母親はもともと中つ国の人間ではないか」
洋一はあきれて口を開けた。だけど言葉が出てこなかった。彼は奥村に手を引かれて後ろ向きに歩いている。その視線の先で男爵はひどく落ちこみ、見た目以上に年老いてみえた。
「母さんは、母さんはまともだった」
「あたりまえだ」
洋一はふと思いついたことを急いで言った。「戸籍は? 生まれたら役所に登録するもん」
「そんなものはなんとでもなる」
そんなばかな、と洋一は思った。奥村が常識人(のように見える)だから、ついほだされそうになったが、やっぱり男爵のいっていることは異常だった。おかしいよ、そんなの、と洋一は小声でいいかえした。
「なら、母親の祖父母はどこにおる。お前は会ったことがあるのか?」
母方どころか両親のどちらの祖父母とも会ったことがない。そもそも血縁がまったくないから、養護院に預けられたのだ。洋一は黙ったが、男爵のいっていることにはまったく納得できなかった。そもそも、祖父母がいないことと中つ国や本の世界のことは関係がないのである。
洋一は男爵にたいして恩義があった。これから養護院に閉じこめられて生きていかなければならないと信じていたから(それも十年だ!)男爵が院長を倒したときの感動といったらなかった。だけど、自分の両親が本の登場人物に殺されたと聞かされては黙ってはいられない。
男爵は本の世界云々の話以外は、いっていることはまっとうだった。彼の口振りは端々から誠心を感じさせるものだった。洋一はその矛盾に苦しんだ。そもそもミュンヒハウゼンとは、ほらふきを生業としているのである。これらの話自体がほらであってもおかしくはない。洋一は本物のほらふきは自分のうそを信じることができるという話を聞いたことがある。嘘発見器にも引っかからない人間がいるのだ。男爵もそのたぐいの人なのかもしれない。
このままついて行っていいのか迷った。だけど、相談すべき人が今はいないのだ……。
洋一はこれからの身の振り方を決めるにあたって本当に迷った。せめて担任の阿部先生にだけでも相談したいと思った。男爵がまともならすぐについていってかまわない。団野の元を離れ、もといた洋館に戻れるのなら、なんだってしただろう(後に残る院生のことを思うと、気の毒でならなかったが)。
結局、洋一が男爵に手を貸すことにしたのは、彼の話を信じたからではなく、生まれ育った家に帰りたいという一心だった。断ったところで、洋一には養護院での暮らししか残されていないのだ……。
洋一の両親がどうやって殺されたのか、それは男爵にもわからないということだった。
月は沈み、星は消えた。夜は朝に変わろうとしている。洋一は、白い息を薄靄に吐き出しながら、ここまで誰にも行き当たらなかったのは、幸いだったなと考えた。それから、両親が事故にあったのはどこなんだろうと考え、また涙をにじませるのだった。
○ 4
それから歩くこと一時ばかり、洋一はついに図書館のたつ小高い丘の森を目にした。その山は針葉樹の深い緑を基本としている。一行は洋館へとつづく、さほど道幅のない曲がりくねった坂道を見上げて立った。空気は冷え冷えとして靄も出ている。日が昇りきるまでは、まだまだ時間があった。車が通るには狭すぎる道が、丘の上の屋敷まで曲がりくねって続いている。少し高いビルに登れば、町のどこからでもその屋敷は見えたから、利用者が少ないわりに名前だけは知られていた。
その森が両親のものなのかはわからなかったが、ほとんど手入れはされていなかった。道は一応舗装され、コンクリートの路肩もちゃんとある。対向車両が来ると、徐行して通るのがやっとだった。交通の不便はあるが、静けさだけは一等地であったから、その昔は利用者も多かったらしい。
洋一はこの坂を、そのさほど長くもない人生でなんど上り下りしたかわからない。坂の袂で丘を見上げながら、まるで十年ぶりに生まれ故郷にもどってきたかのような、そんな心持ちだった。道の脇に生える下草にさえ、懐かしさを覚えた。
洋一は友人たちとピストルごっこをし、山を駆け回り、カブトムシを捕ったりしたことを思いだした、繁殖のために、古畳を拾ってきたこともあった。あれはどこに隠したんだっけ……。
秘密基地を造り、キャンプをし、焼き芋を焼いて、鳥の巣を作った。この山はこれまでのかれであり、これからのかれでもあるはずだった。両親の、死さえなければ……。
男爵は疲れた体に鞭打った。「さて、もうひとふんばりだ」
○ 5
男爵は洋館へとつづく道々、なんとか洋一を訓戒しようとした。洋一はそれが宗教家の述べる信条よろしく、仲間内でしか通用しないばかげた戯言としかとることができなかった。
洋一は黙って話を聞いている太助を不思議に思った。二人はほとんど話をしていない。
「君はどう思ってるんだよ? 本の世界に入れるとか、そんなこと本気で信じてるのか?」
洋一の声はいささか挑戦的になったが、これはいたしかたない。
太助は洋一の言葉にかすかに眉根を曇らせた。「わからない。ぼくも本の世界には入ったことがないんだ」
洋一は男爵に、ほらあ、という顔をしてみせた。
「無理もない。信じがたいという諸君の気持ちは、わがはいがいっとうよくわかる。なにせ、そんな反応にはなれっこだからな」
さもあろう、と洋一は思った。
「だが、お主たちの気持ちとこれから降りかかるであろう苦難は無関係なのだ。城にさえつけば、なにが真実かはじきに明確になるだろう。そのときにこの話を信じず気を抜いて敵の計略にかかったとして、そんなときに相手は容赦などしてくれん。一流の剣客たちですら命を落とすような危険な輩が相手なのだ。腹だけは屹度かかえて、覚悟してくれ」
太助が、本の世界のことはともかく、ウィンディゴはほんとにいるし、中間世界はほんとにあるんだ、と言ったから、洋一はますますふさぎこんだ。どうやら味方はいないものらしい。
洋館までの道には外灯すらない。森閑としていた。夜は明け始めていたが、鳥の声すらしなかった。洋一には通い慣れたその道が、妙に禍々しく見えたのだった。
○ 6
その洋館は巨大な建築で、小規模ながら三階建ての、立派な城の様相を呈していた。二階と三階には立派なバルコニーがある。西洋の城と聴くと、誰もが連想するような鋭角な尖塔が三本ばかり。正面には三メートルばかりの巨大な門をようし、中に入るとすぐは、舞踏会が開けるほどのりっぱなホールがあって、奥にはスロープの階段が二階までつづいている。
個人が持つにしてはいささか大仰すぎるほどで(恭一の愛車はボロのサニーだったし、牧村家はじっさい慎ましやかな生活をしていた。)、事務処理に来ていた役場の職員は(男爵たちは彼らに洋一の居所を聞いたらしかった。訊きだすには骨がいったことと思われる。)ここを結婚式場にでも変えてはどうかと冗談口を叩いたほどだ。日本で造られたというよりは、ヨーロッパの古城を移植したといった方が想像しやすいかもしれない。
その城がいつできたのか知っている人は一人もいなかったし、ゆいいつ知っていたと思われる洋一の両親は死んでしまったのだから、なんとでもいえるわけだ。男爵ならばいろいろと知っていることも多かろうが、洋一はもうこの老人のいうことに聞く耳を持つ気がしなかった。後々には事情が変わるわけだが……。
屋敷の内訳はこのような形である。部屋は大小三十を数え、トイレは一階と二階にふたつあり、ほとんどの部屋が本で埋まっている(トイレもふくめて)。洋一の部屋と両親の部屋は二階にある。ともだちが来たときにつかう部屋は、一階の玄関の右側。開けると庭に出られる大きな観音扉がついているから冬場は寒い。もちろん個人の部屋にも本がたくさんある。
通路にも各個室にも羅紗地の高価な絨毯をひいていて、これだけでも図書館の値打ちは高かった。高級な暖炉があちらこちらにあったし(それこそ院長宅の暖炉など比較にならない)、天井を支える柱は本物の大理石。図書館という体裁があるとはいえ、親子三人が暮らすにはあまりにも広すぎる。このため洋一は、三階にはかくれんぼにつかう以外は、ほとんど行った試しがない。
おかしなことは、その図書館の書物が、あらゆる国の言語で集められていることだ。洋一の両親はフランス語の部屋、英語の部屋と整理してはいたが(もちろん日本語の部屋がもっとも蔵書豊かだが)これでは利用者がふえないのも当然といえた。こうした事情も、洋一が男爵の言葉をまるきり否定できない要因のひとつだった。日本にある日本の図書館で、外国の客などめったに来ないのに(なにせ日本人すら来てくれないのだから)外国語の書物を集める理由がないのである。洋一は以前から不思議だった。図書館には作家の生原稿を集めた部屋もあって、結構値打ちものと思われるこれらの品々をどうやって集めてくるのか実に不思議だった。それに、男爵が話していた伝説の書――洋一はそれとおぼしき本の在処を知っている……。
一行は朝靄を抜けて鉄格子の門をくぐった。空はまだ明け切ってはいない。地面の土は朝霜で氷り、踏むとパリパリと音を立てる。その薄い日射しともいえない日射しの中で、苔むした白亜の洋館を見上げたとき、洋一は百年ぶりに凱旋した兵隊のように、妙に感傷的な気分になった。この図書館だけが変わっていないことに(敷地に生えている草の数すら変わっていないことに)妙に不思議と感動したのだった――出発したのは、この晩のことだったのだから変わっていなくても当然だったが、彼の体内時計はずいぶんと早回しを行ったようで、この一晩が十カ年にすら感じられたのだった。そして洋館は自分の凱旋を喜んでいるようにさえ見えた。
洋一は、今にもこの窓の明かりがついて、心配した両親が飛び出してくれたらいいのに、と思った。そして、長い坂道にこそ辟易しながらも、自分がこの図書館をどれほど深く愛していたかに気がついた。へんてこな部屋、へんてこな書物、へんてこな両親を愛していた。どれもが彼の自慢の種だった。
洋一は二人に会うのは無理なんだという気持ちと、もしかしたらという期待を、胸でせめぎ合わせながら、玄関の階段に近づいた。脇に回ると、左から三つ目、下から三番目のブロックに手をかけた。そのブロックを揺り動かすこと数度、ブロックが石垣から外れた。洋一はそのあとにできた空洞に手を差しこみ、冷たく冷えた鍵をとりだした。ふりむくと、三人に震える声で言った。
「あった……」
もしこれまでの人生のなにもかもが変わったのなら、この鍵もなくなっていて、もう洋館には二度と踏みこめないだろうと覚悟していた。だから、その合い鍵の存在は、洋一の肺に朝のすがすがしい空気を送りこむように、胸にあったかすかな希望をふくらませた。
洋一が、泥で汚れ朝露に濡れる合い鍵を、大事な戦利品のように掲げてふりむいたとき、洋館ではすべての部屋で明かりがつき、何万人という数の人間の声があふれ出してきた。
洋一は図書館をかえりみた。玄関の階段をふらつく足で下りながら。明かりのついた窓を見た。見慣れた厚手の本が、ボールのように横切るのを見た。ガラス越しに、空を飛び交う本の姿を、確かに見た。
「誰かいる……」と洋一が震える声でつぶやいたときには、ミュンヒハウゼンと奥村は鋭く剣を抜いて、洋一と太助の背後にきていた。男爵が厳かな声で、こうつぶやくのが聞こえた。
「すでにはじまっておる。見捨てられた書物が、怒り狂っておるぞ……」
□ その二 見捨てられた書物と、最初の対峙について
○ 1
洋一は震える指で、時代めかした大きな鍵を扉の穴に差しこんだ。くるりと回すとかちゃりと大きな音がした。中から聞こえた人のさんざめく声がぴたりとやんだ。洋一はこう思った。こいつらぼくらが来てるのに気づいてる。
洋一がふりむくと、男爵は大きくうなずいた。ミュンヒハウゼンは帽子を手で押さえ、足を開いて身構えた。奥村と太助は中からなにかが出てくるのに備えるように扉の脇に回りこんだ。
洋一はその巨大な扉をゆっくりと開いていった。中から明かりの筋が伸び、バルコニーのつくる影をすーっと左右に払っていく。洋一はホールを目にした。昨晩出かけたときと、なんら変わりがないようだった。洋一はそっと身を忍ばせて、ホールの絨毯にその足を置いた。その瞬間人声が復活して、洋一は尻餅をついた。目を回しながら感じたのは、今屋敷には何万人という人間がいるということだった。ただいるだけではなくて、ありとあらゆる騒ぎをしている。悲鳴がするし、話し声に怒鳴り声、男女の聞くに堪えない嬌声に、断末魔の声までする。まるで屋敷の中で、騒ぎ合って、愛し合って、殺し合って、大喜びして……人間がいとなむありとあらゆる行為を一時に営んでいるみたいだ。
「しっかりしろ、洋一」
男爵が洋一の脇に手を差しこみ、彼を外に引きずりだした。洋一は男爵の腕に手をかけ、息も絶え絶えに言った。
「な、なにがおこってるの?」
「あれは本から漏れる声だ。登場人物の声が漏れ出ておるのだ」
と男爵。奥村が刀を鞘に収めながら洋一の傍らに片膝をついた。
洋一は太助と顔を見合わせる。二人は本の世界になどはとんとお目にかかったことがなかった。声(というか騒動)を聞いたあとも、男爵の話はピンとこなかったが、それでも度肝を抜かれたのだ。
太助は男爵を助けるという父親についてここまで来た。奥村左右衛門之丞真行がミュンヒハウゼンを補佐しているように、父を助けるのはほんのこどものころからの彼の役目だった(もっとも奥村休賀斎は他人の助けなど必要としない人物ではあったが。武家の惣領ともなれば、こんな役目も致し方がない)。本の世界を救うだとか、伝説の書だとかいう話は、いっさい男爵のほらであって、真剣に考えてみたことはなかった。だけど、機関車にのって別の次元に来られたのはうそ偽りのない話だし、本の世界を守る一家というのもほんとにいた。太助は、物語の世界というのはほんとにあるのかもしれない、自分はその世界を冒険することになるかもしれない、と思って、にわかに緊張したのだった。
一行は中を確かめながら、ホールへと踏みこんでいった。屋内には人影らしきものはなにもなかった。だけど、あちこちの部屋からは人の気配がして、声も漏れでていた。本のある部屋はどこだ、と男爵が訊くと、洋一は、たいていの部屋には本がある、と答えた。
ともあれほらふき男爵は左手のもっとも手近な扉に身を寄せていった。中からは、人の声が寸断なく漏れ出てくる。悲鳴、話し声、怒鳴り声、声という声と物音が。洋一は男爵の腰にピタリと寄り添って、耳をそばだてていたが、やがて
「ここはぼくの家だぞ」
と怒りに震える声で言った。彼は物語の世界なんてまだ信じることができなかった、両親と自分の留守中に泥棒が入ったにちがいないと信じた。
男爵が彼の肩を叩いて合図した。「中に踏みこもう。頼むぞ奥村」
○ 2
男爵が金のドアノブに手をかけ、チョコレート色の扉を開いた瞬間、中からは轟然たる風が一同に向かって吹き付けた。口の中で風が渦を巻き、息も吸えない。洋一は自分の見たものが信じられなかった。部屋の中では本という本が、鳥のように羽ばたきぶつかりあっていたからだ。
男爵は果敢にも部屋に飛びこみ、唸りを上げて立ちつくす。洋一たちも中に入ったが、本という本がこうも暴れていては手の施しようがない。本は仲の悪いのもいるらしく、互いをちぎり合ったりしている。おまけに男爵の手元では、本の見開きから、馬が出てこようとしていた。
洋一は、その馬が充血したギョロ目をいかつかせ、ぶふうと鼻から吐いた息で、髪をなびかせるのを感じた。馬は空間に身を乗りだした瞬間に実物大の大きさになるようで、ページの縁に前足が出ると、その蹄は実物大に大きくなった。身をくねらせながら現実世界に出てこようとしたのだが、あと少しのところでミュンヒハウゼンに本を閉じられてしまった。
馬はいななきを残して洋一の前から消えた。男爵の手の中で本が暴れ出し、彼はこいつめこいつめとその本を縦に横にと振り立てた。別の本が抗議をするかのように男爵の頭を表紙の角で攻撃する。ミュンヒハウゼンは後頭部に一撃を食らって足をよろめかせたが、それでも気丈に本をつかんでいる。
そのとき、部屋中の本が互いに争うのをやめ、洋一たちに目をつけた。本は空中で制止した。その刹那、洋一は部屋にある何百という本の背表紙から悪意が放たれるのを感じた。
奥村が暴れる本を叩き伏せようとする男爵の肘をとり、洋一と太助を追い立てた。空中に浮かんだ本が、四人の後を追うようにゆっくりと向きを変えている。本の群れがこちらに向かって突撃を開始しようとした瞬間、洋一の鼻先で扉が閉まった。本のいくつかが扉にぶつかり音を立てた。
洋一は高鳴る心臓に手をやることもできずに、呆然と見開いた目をこすった。おかげでまつげが目に入ったが、その痛みも気にならない。なにが起こったのかわからなかった。洋一は男爵たちをかえりみて、「ありえないよ」と叫んだ。ちょうど男爵が、部屋から持ちだした本を踏みつけにするところだった。
「貴様」と男爵は地面に落ちた本に向かっていった。「わしはお前たちを助けに来たのだぞ。狂った世界を元に戻しに参ったのだ。わかったか」
絨毯の上で本が抗議するように飛び跳ねた。男爵は屋敷中に聞こえるように、首を仰向けて口説した。
「よいか貴様ら! 我が名はミュンヒハウゼン、高名なるほらふき男爵である! 本の世界を救うため、物語を飛び出し、仲間と共に馳せ参じた。残念にも牧村夫妻は命を落としたが、子息と我が輩、そして中つ国の仲間がいるかぎり、物語は終わりはしない。諸君らに良心があり……」騒いでいた屋敷がしんとなった。とここから男爵は涙に視界を曇らせ、わきおこる熱情に声をつまらせだす。「自らの物語を思う心があるならば、いっときでいい、我が輩らに力をかしてくれ。我が輩は……」
そのとき、静まりかえったかと思った屋敷内から一斉に抗議の声があがり、あちらこちらで扉が開きはじめた。洋一たちはほうほうの体でその場を逃げだした。
洋一は先頭になって男爵たちを本のない場所へと導いた。彼のよく知る図書館は一夜にしてお化け屋敷になったかのようだ。あちらこちらで廊下をうろつく人影が見えた。洋一はなんども方向を転換せねばならなかった。この屋敷の中で本のない部屋なんて、それこそ見つけだすのに苦労したが、記憶の地図を返す返すようやく一つ見つかった。
彼らは洋一を先頭に廊下を走って、ついに本のない物置小屋へと逃げこんだ。そこは掃除用具を入れこんだ部屋で、中は埃っぽく、四人が入ると(うち二人がこどもとはいえ)ずいぶん手狭だ。今日はなんと物置に用のある日だろうと思うと、情けなかった。
一同は真っ暗な部屋で座りこんで荒い息をついた。とくに体を痛めている男爵と洋一には全力疾走が身に堪えた。
洋一は壁をさぐって物置の明かりをつけた。
「持ってきたの?」
男爵はへたりこんだままだったが、その膝元ではまだ赤い本を手にしていた。見慣れたはずの本の背表紙がなんとも薄気味悪く不吉なものに見えた。
「捨ててくればよかったのに」
「あ、あいつら」と男爵はその本を持ち上げ、荒い息の下で言った。「わ、わしらにたてつきおってどうなるか見ておれ」
だが、洋一はさきほどの抗議の中にも、賛同の声があがったのを確かに聞いた気がした。その証拠に男爵が手にもつ本は先ほどはあれほど暴れていたのに今はすっかり大人しくなっている。果たして、奥村が、
「ですが、その本は聞く耳をもっているようですな」と言った。
「さもあらん。見て見ろ、本の題名を」男爵は洋一に向かって本を突き上げた。本の表紙には、『ロビン・フッドの冒険』とある。「多くの人に読みつがれた歴史ある本だ。そのような本は強い力をもっておる」
彼は気迫のこもった目で洋一をにらんだ。屋敷ではまだ騒ぎがつづいている。でも、山の中だから、誰も気づく人はいないんだろうな、と彼は思う。つまり、誰か洋一がいなくなったことに気づいて洋館を訪ねてくるまで、この自体を知る人はいないわけだ。団野は洋一がいなくなったことを隠すに決まってる。
男爵は洋一に向かって言った。「どうじゃ。これで信じたか?」
「あれを信じろっていうの?」
洋一には男爵の申し出の方が信じられない。
「きっとぼくらは院長に殴られすぎて頭がおかしくなったんだよ」
「それとも今見たものは夢かうつつのたぐいだと?」
「でなきゃなんなんだ」洋一は頭をかきむしった。「どうすればいいんだよ。せっかくうちに帰ってきたのに、ぼくはゆっくり休みたいだけなんだ。体だってぼろぼろなんだ」
男爵は座りこんだまま洋一の胸を突いた。「その痛みこそが現実なのだ。今の情況とて現実なのだ。目をさませ」
洋一は半分べそをかいて問い返した。「ぼくにどうして欲しいのさ?」
「伝説の書を手に入れたい。本の場所へ案内しろ」
○ 3
「ともかく」
男爵は言った。
「本の多くはウィンディゴの影響を受け、やつに味方しておる。悪の中つ国の力が物語の世界に影響しておるのだ」
「物語はハッピーエンドに決まってるんだ。正義は必ず勝つんだぞ」
「それは昔の話だ」ミュンヒハウゼンは洋一を睨んだ。「わしが今知る物語には」と彼は前置いた。「悪が正義をうち倒し、誠が嘘に破れ、陽が陰にとってかわる、そんなものばかりだ」
「それがウィンディゴのせいなの?」
洋一は尋ねた。男爵は無言でうなずいた。洋一は無意識のうちにほうきをつかんで考えこんだ。ある疑惑がさっと心に浮かんだ。物語の世界が本当だとして、ウィンディゴが本当にいるとしたら――? ぼくの父さんと母さんがそいつに殺されたのもほんとかもしれない。
まだ見ぬウィンディゴにたいして、猛烈でどす黒い怒りが胸の中で渦を巻いた。
「伝説の書はなにも書かれてない本だ。そうでしょ?」
男爵は目を見開いた。「伝説の書を開いたことがあるのか?」
洋一がうなずいて口を開こうとすると、男爵が慌ててその口をふさいだ。「待て待て待て。伝説の書のありかはいうな。誰が聞き耳を立てておるかわからんぞ」と彼は言った。その証拠に屋敷はまた静まりかえっている。まるでウィンディゴ配下の書物が、全精力を傾けて洋一たちの居場所を探っているかのようだった。
洋一は声を落として言った。「でも、ぼくは伝説の書に落書きしたのに、なにも起こらなかった」
男爵は顔を真っ赤にした。大事な伝説の書に落書きをしたときいて腹を立てたようだった。
「それはお前がものを書いたときになにも念じておらんかったからだ。その本はな、人の意志、信じる力に反応するのだ。ただの落書きなんぞが現実化してたまるか。あれを使いこなすにはとんでもない修練がいると思え」
洋一はむっとした。
「ともかく伝説の書の在処をお前は知っておるわけだ」
男爵が身をかがめる。洋一はミュンヒハウゼンの耳にささやいた。「両親の部屋の机においてある」
男爵はあまりのことに唖然とした。「鍵をかけた金庫か書箱にいれておらんのか? むき出しにおいてあるのか?」
「そうじゃなかったらぼくがさわれるわけがないよ」
奥村は声を出さないよう注意して笑った。「いかにも恭一らしい」
「赤い表紙のでっかい本でさ、カバーもなんもないやつで」
「それだ!」
「か、どうかはわからないけど、すごく大事な本だっていってた」
「中にはなんと?」
「なんにも。真っ白なページだった。分厚い本なのに、ずっと白紙なんだ。それにぼく……」と洋一は告白を恥じるようにうつむいた。「あの本を持ったとき、熱いと思ったんだ」
あの本は生きてるみたいだった、と洋一は言った。
男爵たちは顔を見合わせた。もはや、まちがいない、と男爵は言った。
「なんということだ。ことは一刻を争うぞ。ウィンディゴのやつに先を越されるわけにはいかん。やつがそれを手にしたらきっと使いこなして、世の中をめちゃめちゃにしてしまう」
「そいつはこっちの世界に来てるの?」
洋一は訊いた。身の程も考えずに。彼はこれほど怒りが強ければその力だけでウィンディゴがやっつけられる気がした。男爵のいうとおり、いかに世の中が変わろうとも、彼の中ではまだまだ正義が悪に勝つ古い世界が信じられていたからである。
それに対する男爵の答えは頼りなかった。
「わからん。やつの動きがわしに読めるわけがない」
ともあれ、彼らはせっかく逃げこんだ安全な物置を出て、両親の寝室に向かうことになった。問題は両親の部屋にも本があることだが、男爵がいうには、「恭一が部屋に置くぐらいだから、それらの本は力の強い、正しい本に決まっておる」
彼はそれらの本自体が強い力を持っているのでウィンディゴの影響を受けていないはずだと信じたがっているようだった。
「もっとも、お前は気をとち狂わせておったようだがな」と男爵は「ロビン・フッド」を見下ろして言った。
○ 4
洋一たちはこっそりと部屋を出たのだが、六歩と行かないうちにその行動を知られることになった。静まりかえっていた屋敷がまた騒がしくなり、騒音という名の強風はたちまち暴風の域に達した。書物があちこちの部屋から飛び出してくる。中には、五、六キロはあろうかという、巨大なハードカバーもあって、洋一はあやうく頭を砕かれかけた。彼らは全力で二階に駆け上がると、両親の部屋に逃げこんだ。
両親の部屋は広かった。壁は本棚に埋め尽くされている。ベッドは右の隅に、ストーブが中央にあり、恭一が生前くつろいで本を手にしていたソファがそのそばにある。そして、窓際に背を向ける格好で大きなデスクが置かれている。洋一のともだちが、校長机と呼んでいた立派なデスクだ。
この部屋だけは見受けられる異常はなにもなく、両親の生前の姿を保っているかのようだった。奥村が洋一の肩を叩いて指さす先で、彼の両親が残したらしいいくつもの文様が壁に描かれているのが見えた。暗い部屋の中にもかかわらずまっさきに目に飛びこんできたのは、紋様自体が光を放っていたからである。
「恭一の残した結界らしい」
「おかげで助かったぞ」
とミュンヒハウゼンは急にのびのびとした大股で恭一の大机に歩み寄った。よく見ると、寝室にはあちこちに不思議な文字が書かれていた。大きな物は、東西南北に四つある。洋一は書物の喧噪が部屋にはいった瞬間に遠のいたことに気がついた。洋一は男爵のあとについて大机まで歩いていき、両親の残した遺品の数々を眺めやった。恭一の残した万年筆、開いたままのノート。もう二人がつけることはないライトをつける。明かりが落ちる。洋一は涙のこもった目で男爵を見上げた。
「どうだ?」とミュンヒハウゼンが訊く。
「なくなってる。きっと父さんが隠したんだ」
「ウィンディゴが持っていったんじゃあ」太助が言った。
「いや、やつがこの部屋に入れたとはおもえん」
男爵が持ち主の断りもなく引き出しを開けはじめた。
洋一は壁に据え置かれた本棚によっていった。棚にはくたびれた古い書物や新書本までありとあらゆる時代の本が並べられている。この部屋の本は洋一ですら許可がない限り読むことはできなかった。両親は男爵のいう、強い力をもった本ばかりをこの部屋に集めたのだろう。
「あったぞ」
男爵が言った。洋一がふりむくと、ミュンヒハウゼンが一番下の引き出しから、広辞苑ほどの分厚さのある古びた本を取りだしたところだった。一同は男爵のもとに集まり彼の手元をのぞきこんだ。
「あったぞ、これこそ伝説の書だ」と男爵は本の表紙をぱたぱたとはたいた。それからまた引き出しの中をのぞきこみ、「鍵はかけられておらんが、封印がほどこしてあるぞ」と机の中にあった魔よけをみつけて感嘆を上げた。
「あいつは勘がよかった。身に危険がおよんでいることに気づいていたのでしょう」と奥村が静かな口振りで言った。ミュンヒハウゼンは洋一に伝説の書を手渡した。洋一はその本を手にした瞬間、以前とおなじ熱気を掌に感じた。その本にはタイトルも表紙絵もない。だが、真っ赤なその装張は洋一の手の中でうずくような息吹を発していた。この本には力がある。
洋一がペーパーバックを開くと、本はパリパリと真新しげな音をたてた。ページにはなにも書かれていないが、真っ白というよりは古茶けた色をしていた。ページを繰ったが、どのページにもなにかが書かれたような痕跡がない。昔書いた落書きが、どこにもなかった。
「ボールペンで書いたのに……」
彼がつぶやくと、しばらく経つとすべての文字は消えてしまうのだと男爵が答えた。本には文字を書きこむ必要すらないらしい。危険な書物なんじゃぞ、と男爵は言った。
洋一は男爵を見上げた。「これはおもちゃじゃないってすごく怒られたよ」
「さもあろう」危険もあるからな、と彼はうなずいた。
「これからどうするの?」
洋一がいうと、男爵はふたたびこの屋敷に来てはじめて手にした本、ロビンフッドを一同に向けて示し、「これもなにかの縁じゃ」と言った。「まずはこの本の世界にはいる」
その言葉を訊いた瞬間、洋一は脳天までしびれあがった。驚きと興奮のあまり、髪が逆立つかのようだった。ここにあるのが両親のお気に入りの本だというのなら、洋一にとってはロビン・フッドこそがお気に入りだった。カバーこそなくなっているが(ロビンと森の盗賊たちが、木陰から、道を行くノッティンガム侯爵とその一行の様子をのぞき見ている絵のついたやつ)、洋一はその本をなんど読み返したかわからない。盗賊たちが悪い代官をやっつける痛快さが好きだし、とくに主人公を支えるちびのジョンが大好きだった。洋一はともだちと森の盗賊ごっこをずいぶんした。母さんの家裁道具からゴムひもを盗んで手製の弓矢を作ったこともある(ときどき弓矢がピストルにかわったけど)。
男爵と奥村は『ロビン・フッド』を開いて、物語の冒頭辺りを確かめはじめた。
「すごいよ」と彼は太助に向かって言った。「ロビン・フッドに会えるんだ。読んだことある?」
太助がうなずく。洋一はつづけて言った。「ほんとにすごいよ。知ってる? ロビン・フッドにはモデルになった人物がいるかもしれないんだ。でもぼくたちは本物のロビン・フッドに会えるかもしれない」
「君は本の世界なんてないっていってたじゃないか」
「お前こそ、中間世界から来たとかいってたくせに信じないのか」
二人の言い争いは、大人たちの、「物語が変わっておる」
というつぶやきで消されてしまった。男爵が呆然たる顔でふりむいた。「この物語ではロビン・フッドは冒頭から死んだことになっておる」
「そんな」と洋一は、本を男爵の手からひったくった。彼は本の世界をまるきり信じていなかっただけに、ロビン・フッドに会えないという現実が耐え難かった。
「どうなるの? ロビンは生き返るの?」
「わからん」男爵は首を横に振った。「物語が変質をはじめてからは、わしは他人の本にはいったことがない」
「わたしもないな」
「本の世界にはいったことがあるの?」と太助が訊いた。
奥村は、恭一と二度ほど物語の世界に入りこんだことがある、と言った。男爵がこの二人にはわしが方法を教えたから、そういうこともあるだろうと付け足した。
「ともあれ、この世界に入りこんでみんことにはいかんともしがたいわい。まったく、主人公がことの一から死んでおるとは、サー・ロビン・ロクスリーもなんともふがいないではないか」
「ちくしょう、それもウィンディゴってやつがやったんだ」と洋一は決めつけた。
「もうしばらく先まで読んで物語がどう変わったのか、頭に入れた方がいいでしょう」奥村が言った。「これからも変わりつづける可能性があるとはいえ」
男爵がうなずこうとしたそのときである。
「ミュンヒハウゼン!」
誰のものともしれぬ野太い巨声が、屋敷中に響き渡ったのである。
○ 5
その声を聞いた瞬間にミュンヒハウゼンは、
「ウィンディゴ!」
と叫び、サーベルをひきぬいた。ゆっくりとその場で一回りをし、警戒するように周囲に気を配る。
声はさらに、
「久しいな、ミュンヒハウゼン!」
と言った。
奥村が声の方向に見当をつけ、バルコニーのガラス戸に走り寄ると、真冬用にあつらえた分厚いカーテンを引き開けた。洋一はウィンディゴに対する怒りを新たにしていたが、カーテンがあいた瞬間悲鳴を上げて太助とともにしりもちをついた。
窓の外には、巨大な顔がうかんでいた。でっかい団子鼻だ。仁王のような形相をして、一同を睨みつけている。しかも透明で背後の空をうつしている。奥村が長刀をすっぱ抜いて、二人の前に回りこんだ。
「あ、あれがウィンディゴ」洋一は唖然と言った。
「うろたえるな」とミュンヒハウゼンは言った。「やつはお前がもっとも怖れるものに姿を変えるぞ」
「さよう」ウィンディゴは怒鳴った。部屋の結界がすこしゆらいだ、辺りの喧噪がもどってくる。「察しのとおりだミュンヒハウゼン。わしはお主とおなじく、創造の力を擁する者! さあ、その本を渡してもらおうか。伝説の書はお主にはすぎ足るものだ」
「黙れ!」洋一は窓に駆け寄ろうとして、奥村と太助に抱き留められた。「お前が父さんと母さんを殺したんだな! よくも、よくもやったな。見てろ」
「黙れ、わっぱ!」ウィンディゴの怒声にうたれ、洋一はその場にくずおれた。男爵すらも片膝をついた。「身のほどを知るがいい! ぬしらの仲間はほとんどが死に、残ったのはそこにいる奥村休賀斎と小僧!」とウィンディゴはおどすかのごとく窓際まで攻め寄せてくる。「そして、なにも知らぬ非力な牧村の子息」
ウィンディゴは洋一をあざ笑いつ、窓から離れていく。洋一は悔し涙を流し、奥村の手の中で暴れた。あんまり暴れるものだから、奥村の刀で手の甲を切ってしまった。
「洋一、やつの口車に乗るな!」
と奥村は刀をおさめながら説き聞かせた。
男爵が小声で、「そのとおりじゃ、いまは物語の世界をただし、少しでもやつの力を弱めるしかないのだぞ」
その男爵の言葉をウィンディゴは聴いていたようだ。
「あわれなるかな、ミュンヒハウゼン」顔だけのウィンディゴが宙を回る。「本の世界を救おうなどとやめておけ。人々はもはやお主を必要とはしておらぬ。善がお主にどれだけ味方する! まだ、わしにさからうつもりか! もはやお主に力は残されておらぬ! その証拠にお主は年老い、創造の力も大半をなくしておるではないか!」
洋一は驚いてミュンヒハウゼンをかえりみた。男爵はがっくりと肩を落としてうなだれている。ウィンディゴの言葉は事実らしかった。だから、彼は牧村一家の助けと、伝説の書とを求めたのだ。男爵がいった、ほらもふけないほらふき男爵とはこういう意味だったのだ。
「世界の人々はお前の紡ぐ物語を忘れ去ろうとしている。もはやお前を信じておらんのだ」
ウィンディゴの巨顔が壮絶とも呼べる笑みを形作った。
「お前なんか!」怒鳴る洋一に、太助が組みついた。「ぼくの父さんと母さんを殺したって、まだ男爵がいる!」
「ミュンヒハウゼン!」ウィンディゴはさも驚いた風に、「やつは年老い力をなくしておる。世界の人々はお前を忘れ去ろうとしている」
ウィンディゴが窓に近づく。
「だまれ!」
洋一は涙をながし、ウィンディゴに向かおうとした。
奥村は開き戸まで駆け寄り、カーテンをしめた。そのカーテンの裏地では、洋一の母親がほどこしたらしい、呪文の文字が光を放っている。
両親は死んでもぼくを守ってるんだ、と思うと、洋一の胸は二人への愛情と悲しみ、ウィンディゴにたいする新たな怒りで熱くなった。
カーテンがしまると、音は遠ざかり、ウィンディゴの声は、はるかかれ方から響く遠雷のようになった。
奥村が肩に手を回すと、洋一はがっくりとうなだれた。ふりむくと、男爵もおなじように消沈していた。三人は男爵のところまで歩いていった。男爵はひどく青ざめた顔をしていた。近づいてきた三人に気づき、気丈にも立ち上がった。
「ぼくは男爵を信じるよ」と洋一は言った。「前はあんなこと言ったけど、全部取り消す。だって男爵は院長の家でぼくを助けてくれた」
「わしはもうだめだ……」
「男爵、あいつの言葉を聴いちゃだめだ。ぼくは男爵を信じる。男爵は本物のミュンヒハウゼン男爵だ」
「ああ、ああ」ミュンヒハウゼンはウィンディゴの言った言葉がひどくショックだったようだ。その顔は蒼白なまでに青ざめている。「だが、やつの言ったことも真実なのだ。わし自身の物語世界がすでに狂いを見せておる。わしの仲間たち、グスタバス、アドルファス、バートホールド、アルブレヒト……あやつらはいまいったいどこでどうしておるのか」とミュンヒハウゼンは帽子をむしりとる。
洋一は男爵の白髪頭を見下ろした。「ぼくには強くあれって言ったくせに……」怒りに震える胸。そこから息を吹きだした。「この大うそつき。弱虫のへっぴり腰野郎!」
「なにおう」これには負けず嫌いの男爵が目を剥いて立ち上がった。
「男爵のほらふき。でも、こいていいほらと悪いほらがあるぞ」
「なにを言うか、お前はなにもわかっておらんのだ!」
「わかってないのは男爵だ」洋一は静かに言った。「男爵はぼくに力を貸して欲しいって言った。なのに男爵は自分があきらめてる。うそはついてもいいけど、約束を破っちゃだめなんだぞ!」
「言われましたな」
奥村は伝説の書をとって戻ると、ミュンヒハウゼンの胸に押しつけた。
「男爵」と洋一はミュンヒハウゼンの手をとった。以前は彼の情熱を表すかのごとく熱い力に満ちていた手が、今は冷たく冷えている。そのことも、彼の心を傷つけた。洋一は目に涙を溜めた。声は震えた。「本の世界がほんとにあって、父さんたちが殺されたのもほんとなら、敵をとりたいよ男爵」
「それは我が悲願でもある」
とミュンヒハウゼンは言った。彼の頬に赤みが差した。彼は名付け子の前で弱気になった自分を恥じた。恭一たちは本の世界を守るため――それはいうまでもなくミュンヒハウゼンの世界を守るためでもある――戦って亡くなった。世界中の人間が彼を忘れ去ろうとも、少なくとも牧村夫妻は彼のことを信じて亡くなったのである。
男爵は立ち上がると、洋一の肩に手を置き、日が差してきた表に向き直った。
「この期におよんで弱気になるなどわしはどうかしておった。ウィンディゴ!」と外に向けて呼ばわる。「貴様など世間にろくに名も知られておらぬ。わしの物語はこれまで全世界で読み継がれてきた」
「映画にもなった」と洋一。
「そのとおり!」
男爵が声も高らかに叫んだ。奥村が快活に言った。
「では、まずはロビン・フッドを救いにまいりましょう」
○ 6
洋一たちは、物語の世界に入りこむしかなくなった。忘れられた書物が、部屋を攻撃しはじめたからだ。壁が太鼓のように音をたて、扉の蝶番はがたつき軋み音を上げている。天井からはちりつもった埃まで落ちてきた。洋一と太助は無意識のうちに手をとりあった。何者かが中に入ろうとしている。恭一がつくった結界がいかに強力とはいえ、あまり時間は残されていなかった。
隣で男爵が急いで懐に手をつきこむと、中から二枚の紙をとりだし、二人の少年に手渡した。
「これには、物語の世界にはいるための呪文が書かれてある、一字一句まちがえるなよ」
と彼は言った。それから『ロビンフッドの冒険』を手にすると、部屋の中央に行った。男爵はページをぱらぱらと繰ると、
「この辺りがいいだろう」
と言って、そのページを手で押し、しっかりと開いた。
「城の中の調理場のシーンだ。我々はそこにでるぞ」
洋一と太助はその紙片に目を通して、なんとかそのへんてこな呪文を暗記しようとした。そのとき男爵は懐から伝説の書をとりだし、じっと見つめた。ややあってその書物を洋一に向かってさしだし、
「お前がもっておれ」
と言った。洋一はその本が(すくなくとも男爵にとっては)重要な本だとわかっていたから驚いた。
「でも――」
「おぬしの両親が半生をつうじて守りぬいた本だ。お主が持っておれ」と男爵は言った。「万が一、ということがないかぎり、この本をつかってはならん。とはいえ、お主ではなにを書きこもうとも現実化はせんだろうがな」
洋一は伝説の書を恐る恐る受けとった。彼はその本の背表紙をなで、ためつすがめつ眺めつした。父さんと母さんに変わってぼくがこの本を守るんだ、と思うと、こころよい緊張感のようなものが胸を走る。彼はうなずいて、伝説の書を胸に抱いた。洋一は伝説の書をセーターの中につっこんだ。
こどもたちは男爵と奥村にせきたてられて本の前に立った。四人は本を囲んだ。
男爵が言った。
「手を取り合え」
洋一は太助の手をとった。そして、開いた左手でミュンヒハウゼンの手をとった。ミュンヒハウゼンは一心に『ロビン・フッド』を見つめている。
本当に本の世界に入れるんだろうか?
そう疑問を浮かべた瞬間に、洋一はその書物の放つ脈動をかんじ、本が生きていることを確信した。彼らを中心に左回りの風がおきた。ウィンディゴが騒いでいる。まるで地震が起きたかのように鳴動している。洋一はこう思った。あいつらこの部屋をサイコロみたいに揺すぶってるぞ。
男爵はそんな妨害をものともせず落ち着き払って言った。
「目を閉じろ」
取り囲まれているさなかに目を閉じるのは怖かったが、同時にものすごく興奮してもいた。洋一は自分の股間が硬くなっているのに気づく。わき上がるような力を感じた。その力は彼のまだ知らぬ性の衝動にも似て、まるで、原始の力が彼の中に眠る能力を目覚めさせていくかのようだった。目を閉じているのに周囲の景色が見えた。洋一は四人のつないだ手を通して、未知なるエネルギーが駆けめぐるのを感じた。歓喜ともとれるうめき声がする。ウィンディゴの怒りの叫びも。
「呪文を思い浮かべろ」
その瞬間、洋一のまぶたの裏には、ほんとにあの呪文が浮かんできた。日本語だけでなく、ありとあらゆる言語で浮かんできた。洋一はうろたえながらも、呪文が消えないようにしがみつく。体ではなく精神の力で。彼は呪文の音を覚えることは無意味なんだと直覚する。だから、その言葉の裏にある力をつかまえにかかった。
ウィンディゴは男爵のいうとおりとてつもない、怖ろしいやつだ。でも、自分に、自分たちにこんなことができるのなら、両親の仇を討つことだって不可能ではない気がする。
ウィンディゴがガラス戸にぶつかる音がし、男爵が叫んだ。
「声をそろえて唱えるんじゃ」
四つの声が唱和する。「ラガナリボーノ、オチミマーヤ、タエガンカウコ!」
その瞬間、洋一のお気に入りの本である『ロビン・フッドの冒険』は光り輝き、瞼を通して四人の脳髄を貫いた。その光とともに文章の洪水がおしよせてくる。脳を文の流れに揺さぶられ、洋一は悲鳴を上げた。彼らの意識は遠くなった。洋一が目を開こうかと迷った刹那、髪の毛をわしづかみにされるような感触が彼を襲った。腰が浮いたかと思うと、洋一の体は虚空にむかって放り投げられた。天井にぶつかると思ったのに、そんな感触はない。目を開くこともできずに彼は大空高くに舞い昇っていった。
数瞬の後、四人の姿はわずかな煙を残してその部屋からかき消えていた。
あとには、風にページをはためかせる
『ロビン・フッドの冒険』
だけが残された。