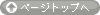「ねじまげ世界の冒険」へようこそ
このページは、ネットで小説を読まれる方用に用意しました。
長編、短編とそろえています。古い作品もあるので、できには目をつぶってやってください。
ねじまげ三部作も、よろしく!
ねじまげ世界の冒険
▼第九部 ねじまげ世界、最後の冒険 前段
○ 章前 二〇二〇年 ――ねじまげ世界 正午ごろ
□ 一
ペンライトの明かりは、あまりに心許なかった。高村利菜と石川紗英の目前には、深い闇がつづいている。トンネルかと見まごう巨大な下水管である。こんな場所を歩くのに、頼りになるのは、か細いライトが一本だけ。
自分と紗英が死んでしまって、それでこんなところを歩いているような、そんなばかげた空想がわく。
胸に手をあて、心臓の鼓動をたしかめる。まだ生きている。一方で、子どものころにも似たような体験をした気がした。こういうのを、なんというのだ? 既視感?
彼女は物思いにはまってこう思う。自分は死んではいけないのだ、絶対に生き抜かなきゃいけないのだと。それに、少年? 少年がここで死んだ。
「こんなときにおかしなことをいうようだけど……」紗英がとうとつに口を開く。利菜は少し驚いてふりむく。「神保町に、こんな下水管があったかな」
二人の女性は暗闇の中で目を見交わす。
「なにいってるの?」
「考えてもみてよ。あたしたち、子どものころからあの川で遊んでるのに、こんな下水管は、見たことがない」紗英は天井を見上げる。「それに、なんのための配管なの?」
言われてみれば、不思議な造りだった。利菜はライトを振って、天井や左右の壁を照らす。さきほどは鉄の鋼管だと思っていたが、今は石組みになっている。壁に手をふれるとじっとりと冷たい、そして、自分たちは下水の脇にもうけられた歩道の上にいて、配管はさきほどより大きくなって見えた。足下の水路には、脈々と水が流れている。
利菜はほとんど麻痺した頭の片隅で、まずいことになった、と考えた。子どものころこんなことはよくあった。ねじまげ世界に迷いこんだのは確実だ。
水路の水がふえ、石畳にまであふれてきた。靴のまわりをサラサラと流れ出すのを二人は呆然と眺める。
「利菜、さっきから、変な臭いが」
と紗英が言った。利菜も気がついた。ものの腐ったような臭い、腐り、膿をだし、「それでも生きてる……」と彼女はつぶやく。紗英が何? と聞き返したときには、その音が二人の耳に届いていた。水をはね除ける、パシャリパシャリという音。
ペンライトを手にしたまま氷ついた。水はもう膝下まで来ている。紗英が脇をむいたとき、そこにはこの一年ずっと近しい人として付き合いを続けてきた溺死女がいて、彼女を水底に引きずりこんだ。
「紗英!」
利菜は水を跳ね散らかし、紗英の後を追った。水路に飛び込むと片腕を水につっこんだ。ライトをかざして覗きこむが、二人の姿はどこにもない。
「ああ、何てこと。紗英、どこなの?」
「無駄だよ」
耳元で声がした。
利菜が首をふると、通路に金髪の青年がいた。青年は生きたまま腐ったかのようだった。大けがをおって、いかにも古びた包帯をこれ見よがしに巻いている。自分でもよくわからないような郷愁がわいて涙が出そうになる。「向こうに行ってよ」と彼女は言った。
「もう助からないよ、利菜」
「え?」あたしの名前を――「ノーマ?」
利菜が呼びかけると、青年はにこりと笑った。そのまま消えた。
「記憶が、記憶が戻りかけてる」
利菜は泣きべそをかいて、水底を探る。ライトをふると、水路の真ん中で、紗英が溺死女に抑えつけられている。水量はどんどん増していて、彼女の腰にまで達している。二人は水中でもみあっていて、溺死女の真っ白な着物が水中にゆったりと広がり、絞殺の真っ最中だというのに、優雅な姿だ。
利菜が水から足を引き抜くようにして近づくと、溺死女がこちらを向いた。
「離せ、こいつ!」
利菜はペンライトを構え直すと、ライトの縁で女のこめかみを力いっぱい殴る。水がとんで顔にかかる。
ふやけた皮膚がずるむける感触に怖気をふるいながら、「紗英を離せ。向こうにいけ!」と突き飛ばす。そして紗英の脇をとると、力任せひきあげる。紗英は両手をふって空気を求める。溺死女がグレコローマンスタイルで、腰を低く落としながら、二人の周囲を窺っている。もう一度頭をなぐると(肘までしびれが走る強さで。女の頭蓋骨は窪んだかもしれない)、ようやく側を離れていった。
「紗英、紗英、しっかりして」
と頬を叩く。呼吸が整うと、紗英はその場に吐いてしまった。わななく手をみつめ、「これ、血だよ」と言った。
利菜は紗英を見た。ライトで自分の手を映す。赤かった。下水の中で二人の鼻は馬鹿になっていたようだ。足下を流れるのは、確かに大量の血だった。
利菜は耳元できこえた奇妙な声にふりむいた。紗英が両手をかかえて奇声をあげている。利菜は彼女の腕をつかんで、
「紗英、しっかりしてよ」
「冗談じゃないよ!」
「なんだって?」と訊きかえす。
地上では、佳代子が母親の手にかかり死にかかっていた。達郎たちはまだ間に合ってない。溺死女の打撃は、メンバーの絆を断ち切るに十分だったようだ。紗英は大口を上げて利菜に怒鳴った。
「冗談じゃないって言ったのよ! なんなのよ、これは。なんでこんな目にあわなきゃならないのよ!」
「そんなこと」
「もういやだよ。こんなところになんか戻んなきゃよかった」
「なにっ?」
「あたしはフライトアテンダントなのよ! それが、なんでこんな穴蔵を這い回んなきゃいけないのよ!」
「何言ってるの……」
利菜は呆然とした。その胸を紗英が叩いた。
「あんたに何がわかんのよ! みんなわかってない! あたしがどんなに苦しんだか、どんな目にあってきたか! もう耐えらんないよ。この一年連絡もよこさないでさ」
「それはみんなのせいじゃないよ! わかってるはずよ」
「知ったふうなこと言わないで!」と紗英は両手をふった。
「このままイギリスに逃げ帰るっての!」
「そうよ! 全部やになったのよ!」
「馬鹿言わないでよ」と利菜は言った。「みんなはどうするのさ! イギリスに戻ったってなんにもなんないわよ! これはおさそいなんだ! わるいものなんだ! どこにいたって関係ない!」
「黙れ、ちくしょう!」
紗英が利菜をつきとばす。彼女は壁に頭をぶつけた。
「なにすんのよ!」
「全部あんたのせいじゃない! あんたがあたしを連れこんだのよ! 勝手に森で迷ってさ! へんな世界につれてったんじゃないか! もう付き合いきれない! 佳代子たちだって、もう生きてなんかいないわよ!」
「あの子が死んだりするもんか!」と紗英の腕をとる。「さあ、進むの。イギリスなんかに戻らせないわよ」
「うるさい、こいつ!」
紗英は拳をかためて、利菜を殴った。彼女がひるんだすきに、紗英は血をはねのけながら、来た道をひきかえしはじめた。
「もうあんたなんかと一緒にいるもんか!」
「待て!」
と利菜は腰にくみつく。
「離せ! 離せよ!」
「離すもんか。みんなを助けるんだ。ヒッピたちを」
「ヒッピたちがいたって、サウロンにはかないっこ……」
二人はそこではっとする。紗英の口にした名前が胸に響いた。利菜は呆然と彼女をみた。「あんた、記憶が」
「そんな」紗英の喉がひゅっと鳴いた。「なんで急に?」
そのときペンライトよりずっと強い灯りが、二人の足下を照らし出した。彼女たちはその光にひるんだ。
「誰」
と利菜は言いペンライトの先を上げる。下水の先にランタンをもった男が立っていた。利菜は妙な親近感をおぼえたのだった。その顔には見覚えがある。年老いてひどく疲れて見えるが。記憶の中で、彼は生々しくよみがえる。現在の疲れた顔と、若々しい顔とが重なり合う。利菜はこうつぶやいた。
「ビスコ」
□ 二
「ビスコなの?」
と利菜は訊いた。信じられない気持ちだった。あのとき死んだはずだ。二十五年も前に……
路地の向こうに立ち、死を覚悟したビスコが、今も脳裏に鮮やかだ。二十五年前の背中がよみがえる。ああ、思えば、あたしもあのときの彼より年を食ったんだなあ、と思う。彼はたった一人で、サウロンに立ち向かった。死に際こそ見ていないが、あり得ない、と彼女は思った。
「あんたのはずがないよ。あのとき死んだはずじゃない」
「誰なの?」
と紗英が訊いた。ビスコは、紗英に会う前に死んだのだ。
「ヒッピの仲間だったやつよ。でも死んだのよ。サウロンに立ち向かって死んだんだから」利菜は男に向き直る。「どうやってここまできたの?」背後に目をやった。「一人なの? あんたがビスコ本人だっていうんなら、証拠をみせなよ!」
ビスコが苦笑しながら、右腕をさしだす。
「さわるといいさ。あのときもそうしたろう」
と言った。それで思い出したのだが、子どものころ、彼女は相手の考えを読んだり、自分の記憶を見せたりすることが(わずかな期間ではあったが)できたのだ。
利菜は胸元に手を引き寄せる。「できないよ……」
「なぜだ?」とビスコはいぶかる。
利菜はくちびるをなめビスコをじっと見つめた。昔のような力が振るえるとは思えなかった。記憶の中の自分と、現在の彼女との合間には、二十五年の年月が寒々と横たわっている。それに、ビスコがもし、サウロンだったら? と疑う。本当のことをいうのはまずい気がする。
三人の間で沈黙が流れた。ビスコは腕をさしだしたままだ。彼女のなかで記憶がどんどん強くなる。ああ、彼はビスコ本人だ。年老いても、あれから二〇年以上がたっても、面影は消えようがない。
そのとき頭上から、ズシン、ズシンと地響きの音がして、パラパラと土埃がふってきた。下水の先で溺死女が叫んでいたが、ビスコはわずかにランタンを掲げてみせただけで、くだらん、と言った。
「あいつの言ってること、あたしわかるよ」と紗英がささやく。二人はときおり頭上を見上げる。「だって記憶が戻ってきた。サウロンのことも、みんな覚えてる」
「あたしもだよ」
「なんだと?」とビスコがききとがめる。「おまえたち記憶がないのか?」
「そうじゃない。これまでは記憶がなかったのよ」と利菜は言った。「あんたはどうなの?」
「覚えていたさ。だが、世を隠れていたせいで、おまえたちがその後どうなったかは知らないのだ」
利菜は寒そうに腕をさする。実際気温はひどく下がっていた。それに上から聞こえるこの響き音はなんなのだろう? 幻聴でないのなら、いったい何が起こっているのか?
「あたしはね、あんたたちのことを、ずっと忘れてたのよ」ゆっくりと話をきりだす。「サウロンがいなくなって、あのときあたしたちが望んだのは、ふつうの子どもに戻ることだった。あたしたちは自分で記憶を消したのよ。だから、もうあのときみたいな真似はできない」
「馬鹿な真似を」声が怒りをふくむ。「なぜ、そんな真似をした! おまえたちは、これまでの人生を無為に過ごしてきたというのか! なぜ力を鍛えなかった!」
「だって、そうしなきゃ、元の生活に戻るなんて無理だったじゃない!」声は、いいわけがましかった。「子どもだったのよ。まだほんの。あんな秘密を抱えてなんか、生きられない」
ビスコは黙った。彼自身気持ちの整理がつかないようだった。「グループの証はまだ持っているのか?」
と言って、顔を上げる。利菜が口元を押さえるのをみて、彼はほほえむ。
「持ってる。記憶はなくなっても、あれだけはなくさなかった」
サイポッツの国でヒッピたちから手渡された赤い布地のことだった。紗英が、本当なの? と訊いた。利菜はうなずく。
ビスコはうつむき、「世を捨てたのはおれも同じだからな。きさまらを責められん」
「何があったの」と利菜は訊いた。
ビスコはふいに二人とは反対側の壁を向いた。そこにまるで記憶をうつす映写機があるかのように。「おれはあのとき死のうと思った。だが、死ねなかった。瀕死の状態で救われたのだ――」
ビスコは語りだした。貴族街で別れて以降の話だった。誰もが知らず、彼自身もまたはじめて口にする話。
そのとき彼が浮かべたのは、まぎれもない沈痛の表情だった。
「死にかけで捨て置かれたおれを救ったのは、城仕えをしていたはしためだった。その女に命を救われた。女の看護をうけ、恥ずかしながらその女に惚れたのだ」下を向いて嘆息する。「おれは自分の人生をその女のために使おうと思った――おれは生きることにした。世を捨て、国を離れ過去を捨てたのだ。勝手かもしれないが、あのとき人生を捨てたのだから、新しい人生は、女のために使いたかった」ビスコは恥じらうような表情をみせた。「仲間は苦労したろう。我々の始めた戦争のせいで、サイポッツの国はいちじるしい混乱が起こった。身分制度はくつがえされた。おまえたちがサウロンを追い払ったあとも、新勢力と、旧勢力が争いあったのだ」
「ヒッピたちはどうなったのよ」
しばらく間があった。「ヒッピは死んだ。サウロンに会う前に、政敵との争いに巻きこまれて、暗殺されたのだ」
「うそよ……」心臓がきゅっと縮んだ。「あいつは死なない。死ぬはずがない。もういっぺん同じことが起こったら、一緒に戦うって誓ったんだから!」
洞穴に、反響する。そのとき一際大きな振動が起こって、下水を流れる血の川までが揺れた。天井の壁がはがれたのか、遠くでぼちゃりと水音が立った。まるで利菜の怒りに対する抗議のようだ。
「だが、死んだのだ。ヒッピはもういない。あいつは革新派のリーダーだった。命を狙われてもしかたがないだろう」ビスコの声に、なじるような語調がまじる。二人は睨み合うが、「だが、ペックたちは生き残った。赤いバンダナを奴らは忘れずに持っているぞ」
利菜の頬を涙がこぼれた。「あたしも持ってる……記憶がなくなっても、あれだけはなくさなかった」
「単刀直入に言うぞ。サウロンが戻ってきた。きさまらが送った世界でさらに力をつけ、その世界を支配したのだ。奴は我々の世界にまいもどってきた。おまえたちのしたことは時間稼ぎにすぎなかった」
「言わないで……」額を手で覆う。悲嘆が大きすぎて、事実を受け入れられない。
「どうするの?」紗英が訊いた。「どうするのよ。そんな奴らが戻ってきて、サウロンは殺しようがないのにどう戦うの? 今度別の世界におくったって、あいつはまた戻ってくる」
「紗英、もういいよ」利菜は紗英の手をとった。「今は言わないで」
水滴の音がぴちゃりぴちゃりと響いてきた。紗英が黙ったのは、利菜の手が震えていたからだ。その手は信じて欲しいと言っている。信じて、支えて欲しい。一人では、きっと立ち向かえない。それは紗英だっておんなじで、手を握りかえすと利菜も落ち着いたようだった。
「あんたは何をやってたの?」と訊いた。
「ノーマの死を耳にしたとき、おれは自分をなすべきことを知った。おれは先々代の神官たちのもとにいき、儀式の全容を習った。おれが最後の神官だ。だから、この世界にくることができた」と彼は言った。「おれは神官たちとともに暮らした。儀式を習い覚えたあとも、世を捨てて暮らした。おかげで政権闘争には巻きこまれずにすんだ。だが……」
「サウロンに会ったの?」と利菜。
「おれが生きたのは女のためだ。全てを捨てるなどむりだった。心が、死んでいなかった。あの女に惚れたのだ――だが、聞いてくれ。その女が死んだ。おれは、どうすればいい……」
足下で、水面がたゆたう。冷静な彼は涙しなかったが、二人の女性には泣き顔にみえた。
「あんた、仇を討つために……」と紗英が訊いた。
「姿は変わっていたが、あれはサウロンだった。奴は戻ってきた」
戻ってきた――その言葉に利菜と紗英はぞっとなった。戻ってきたのは何もサウロンだけじゃない。
「世界の変転は、規模をましている。あるいは滅亡こそが我々の意志なのかもしれないが……」
「そんなことない、あたしは旦那や順子や、みんなのことが大事だって思ってる」と紗英の肩をつかむ。「滅亡が意志だなんて信じない、あたしたちの存在に価値がないなんて思わない」一息に話す。「あんただってそうでしょ。あんたの奥さんは、あんたにとって価値があったんだから。だからここまできたんでしょ」
「利菜……」
と紗英は言う。そのとき、遠ざかったのだった。吐き気も弱気も。意気地があったし、勇気だって残っていた。子どものころは、なにかを信じて、もっと大きなことにだって立ち向かった。信じることは、大人にだってできるはずだ。子どものように純粋でなくても、打算が働こうとも。
利菜は水路の中央で傲然と立っている。なんだか、水位も下がった気がした。「あたしやみんなの思いがうそだって言うんなら、否定したらいい。あたしはやめない」と言う。「だって、あたしは信じてる。サウロンにだって、最後まで抵抗してやる」
「そうだね」と紗英は静かに言った。「あんたがすごすご引き下がるような奴だったら、ノコノコついてきたりしない」
「あんた、ついてきたんじゃない」と否定する。「一人でだって、ここに来たって思うよ」
二人はまた手をつなぐ。
「買いかぶり」
と紗英は薄く笑った。
「それで」ビスコは腕を組んだ。冷たい怒気が声にまざる。「記憶をなくしたというが、装置のことは覚えているのか?」
「それは……」
「おれはおまえたちなどどうでもいい! サウロンを、殺したいたのだ!」絶叫がこだまする。「おまえが家族を思うように、おれにとっても全てだった。大事だった」手をさしだす。「装置を。勝ち目をなくしたわけじゃない。戦うことが必要なら、もう一度やろう」
差しだす手は、さながら契約めいていた。利菜はためらった。足下には、あいかわらず冷たい血の川がある。けれど、手の先の紗英は暖かい。
行こう。
その言葉を、利菜は口に出して言わなかった。だけど、二人の仲間にはそれぞれ伝わった。
彼らは再び歩をそろえると、姿を消した。
水路のさらに深みへと。
この世の闇の深淵へと。
◆第二十一章 ねじまげ世界の子どもたち
○ 一九九五年 ――変わった討論会
□ 三
子どもたちは、体を駆けめぐる力に呻きをあげた。受け取った膨大な歴史に圧倒されていた。フロイトは何かの助けになればと記憶を手渡した(文字通り)のだろうが、今ではその記憶に負けて発狂しそうになっていた。利菜は二倍にふくらんだような頭を左右にふった。脳はパンパンに腫れて(筋トレをした後の二の腕みたいにパンプアップして)
、頭蓋骨を圧迫していた。利菜はその重みに負けてふらつく。達郎は支えようとしたが、二人してしゃがみこんだ。口端をよだれが落ちるが、下も口もしびれあがってどうにもできない。フロイトがこの一年耐えに耐えながらついに自殺を図った気持ちも今ならわかる気がした。彼らは全部を受けとったわけじゃない、記憶を六人でわけあった。それでも頭がくらくらする。困惑。自分が自分でないような感じ。他人になった感覚に苦しむ。
世界はねじ曲げられている……
この夏何度も頭に浮かび続けたあの言葉が、警告であったと知ったとき、彼女は純然たる恐怖を感じる。
新治は立っていられず、すわりこむ。紗英が壁にもたれる(そのとき、壁から伸びた手に首筋を撫でられ、彼女はとびのく)。達郎は、早くここから抜け出さないと考える。みんなも同じ考えだ。六人はまた一つにつながって、互いの考えが手に取るようにわかった。利菜は少し安心する。達郎たちが窮地に陥り、そして危険を承知で救いに来てくれたこともわかったからだ。ヒッピたちはいなくなったが、ここにだって仲間がいる。誓いこそたてていないが、彼女たちはグループそのものだった。
「だけど、そうはいかないよ」と佳代子が言う。みんなは彼女をみる。「だって、あたしたち、八月十七日にいるんだよ。おまもりさまに行く前じゃん。外に出て、自分と鉢合わせしたら……」
「あ、ああ……」
達郎が額をおさえる。上気したあげく、熱っぽかった。脳細胞を記憶が回る。ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。
寛太が後ろを向いて、おえ、と吐くまねをした。「だめだ、このままじゃ気が狂う」目が充血している、口元に垂れた唾を拭う。
利菜は身じろぎもできない。脳みそがにえたぎっている、耳からとろけでそうだ。細胞が疲労に耐えきれないのだ。酸欠になり、手足から力がぬける。こんなに苦しいのなら、死んでしまいたい……。
だけど、向こうの世界に残してきた仲間。彼らの存在が、心の防波堤となっていた。彼らは命がけで助けてくれた。ヒッピは言ったじゃないか、向こうの世界の仲間を助けてやってくれ。だけど、ほんとに助けがいるのはあいつらの方だ。
彼女はいますぐにでもゲートを開いてみんなを助けに行きたかった。でもそれは意味がないことを知っている。今の自分たちではなんの助けにもならない。それに向こうで利菜は何週間も過ごしたのに、両神山から戻ってまだ数日しか経っていないのだ。というよりも、彼らは佳代子の言葉通り、過去に来てしまっているみたいだ。
利菜はどうにか立ち上がる。過去に戻れるんなら、いくらでもチャンスはある。前に進むんだ。と彼女は考える。友だちのために。今この場にいる、死者たちのために。
「記憶を整理しないと」利菜は吐き気を飲みこんだ。「あたしたち、世界の秘密を握りかけてる。これは重要なんだよ、命を失うより大事なことなんだ。そうしないと、あたしたち消えちゃうかもしれない」
利菜の言葉には重みがある。彼女は一度、この世界から消えかけているからだ。そのときは、友だちがつなぎとめてくれたのだが、今度は全員がねじまげ世界にいる。戻れないかもしれない、という思いが全員の脳裏をよぎった。何とか助け合ってきた彼らも、今度ばかりは困難の途中で死ぬかもしれない。やるべきことを完遂できそうになかった。
目を閉じると、脳疲労がジワジワと目玉にまで染みこんできた。
それでもあたしたちは、やらなきゃいけない。
サウロンとマーサは世界のねじまげに立ち向かった。彼らの記憶を受け取った後だけに、いささか大げさな利菜の決意にも今は現実味があった。
利菜は無言で仲間たちに決起を促した。
もう疑えない。疑っちゃいけない。きっと全てが真実だ。だって、ねじまげなら目の前で起こってるじゃないか。
達郎がうなずいた。六人全員が同意を示した。そのうなずきは固い結束となって六人を結びつけた。そのとき坪井善三の家が怒りの唸りを上げた。
利菜は家を眺めわたす。階段では家主が珍客に挨拶をしようと、いまだに歩を進めている(家主こそ、珍しいヘアー《ヘッド》カットをほどこされていたが)。
家が液状化したように歪み始めた。その家は、おまもりさまでもあったし、わるいものそのものでもあった。空間が光を放ち、その光は物質となって、火の粉のように子どもたちに当たる。はじめは美しいと思った利菜たちだったが、光が悪意を持ち、肌を叩き出す。慌てて避けた。
「い、痛い」
床が大波のように揺れ、利菜は立っていられなくなり床に転がった。佳代子が隣に落ちる。彼らは大時化の海原にある、ひとかたまりの小舟のようだった。達郎が手を伸ばし、二人を捕まえた。
「みんな、固まれ、離ればなれになるな!」達郎は利菜に訊いた。「どうなってるんだ!」
「ゲートを開いたせいよ! ますますねじまげが強くなってる!」
彼女たちは二つの世界をつなぐことで、さらにねじまげを強くしてきた。それに精神だ。彼らの精神が不安定になっていることが、空間の歪みに影響を与えている。みんなは壁際に一塊になり手足を寄せ合う。
だけど、どうすればいい? 記憶が脳細胞を(ぐるんぐるん)かけずり回って、とても考えをまとめられない。
紗英が苦しい顔を上げた。「記憶を追い出す方法、一個だけあるかもしれない」
みんな期待をして耳を寄せた。家ではわるいものがそっと聞き耳をたてている(新治の顔の脇に耳が伸びてきた。彼はその耳を叩いた)。紗英はそのことを察して、そっとささやく。
「みんな覚えてる? おまもりさまで死体の記憶に追っかけ回されたとき……」
「あれか」
寛太が死体にふれたとき、一同は死者の記憶に引きずりこまれた。同じ殺され方で死体になりかけた。紗英はあんなふうに記憶を外に出せばいいんじゃないか、と言った。
「でも、できるかな?」新治が言った。「ぼくらは死んでない。なのに、頭の中から追い出すってことだよ」
「これは他人の記憶だもん。きっとできるよ」紗英が言った。
「でも、せっかくいろんなことがわかってきたのに?」佳代子が言った。「あたしたち知らなきゃいけないんだ。そういう役目なんだ。そうでしょ?」
利菜は必死に考える。「あんときは、あたしたち、記憶の中に入れた(というか無理矢理誘いこまれたのだが)。あれとおんなじことをやるしかないよ」
利菜は追い出した記憶に入り、世界がねじまがった元凶を知らなきゃいけないとも言った。それと装置の在処だ。あれを見つけないとサウロンは封じ込めない。
「それに、もう限界だ……」と寛太が言った。このままでは発狂するのは目に見えている。気が狂わないまでも脳溢血で事切れそうだ。
「い、急ごう」と達郎。「ともかくやるしかないよ。死にたくなかったら、やろう」
彼のまぶたは半分下がっている。両目が閉じたとき、達郎ちゃんは死ぬんだな、と利菜は考える。みんなの視線は利菜に注目した。この中でちゃんとした修行をうけたのは、利菜だけだ。
利菜は視線を泳がせる。マーサから習ったことはほんのわずかだし、期間も短い。だけど、友だちは彼女に信頼をよせている。この信頼こそが、力なのかもしれない。利菜がマーサに習ったことと言えば、魔法とは精神の力に他ならないことだけで、それで十分のような気がした。これまでも、なにかを信じて生きながらえてきた。それに、今はサウロンやマーサの記憶を受け取っている。彼らの知識や経験があるということだ。
装置がどのようなものだったかも、おぼろげながらわかった。想像を現実化、あるいは物質化するものすごい代物だ。
やっぱりあの装置はこの世界にあるんだ。と利菜は考える。想像が現実化しているのはこの世界でだけだ。二つの世界がつながると、ヒッピの世界でも現実化が起き始めた。
死者たちの雄叫びがわき起こり、超音波みたいな悪意の波動が、子どもたちの体を打った。この企てが成功しないように、じゃまだてしている。
「やっぱりあの装置は必要だよ! 紗英のいうとおりやってみよう!」
「どうすればいいんだ!」
「手をつないで!」
みんなはひっぱたかれたように目を覚ます。ねじまげに抵抗する手だてが、一つだけあったのだ。
六人は手をつなぎあった。疲労は極致に達していた。脳みそは記憶の詰めこみで(適量の五百倍はあるかもしれない)、臨界点を越えている。そんなときに力をつかうのは最悪なことだ。脳神経が断たれる音が、とぎすまされた耳に聞こえる。ぶつりぶつり。利菜の膝がおれかけるがどうにか立った。
六人の意識がつながりあうと、それは新たに生まれた精神のようだった。利菜は新たに生んだ意志でもって、その家を静めにかかる。水飴のようにゆがんだ壁面が元の材質に戻っていく。死者たちの叫びが遠ざかった(でも消えない。消えることはない。今この瞬間にも、死者の苦しみは生まれているから)。坪井善三は、階段の半ばまで達していたが、急に毒々しい力が抜けて、階段の中央で倒れてしまった。もう一度死んだかのようだ。子どもたちは、それを眺めやりながら考える、あんなふうにはなりたくないと。
利菜はみんなに呼びかけた。
「集中するんだよ。記憶を外に出すんだから。おまもりさまの記憶みたいに」
「ど、どうやってだよ」
「風船を想像するのよ」と彼女は言った。「だって、あの装置はこの世界にあるんだよ。きっと現実化できる。これまでだってそうだった」
利菜はゆっくりと呼吸を落ち着ける。そして、目を閉じた。疲れていたが(あの戦闘からこちら、休むことなくここまできていたのだから当然だ)、なんとかして風船をイメージしようとする。辺りは静寂に包まれる。家が静かになっているのか、自分が感じなくなっているのか、どちらともいえない。ただ、自分の頭から浮き上がる風船をくっきりと思い描いたとき、六人前頭葉からなにかが出てきた。それは空気を吸ったみたいに、記憶を吸ってふくらむ。驚きで、佳代子たちの精神がぐらついた。利菜は平常心をたもつよう呼びかける。精神を乱した瞬間に、想像が暴走し出すとわかっていたからだ。子どもたちの頭部を包むようにして、玉が浮かぶ。それは、七色に輝き、音をかなでた。まぶたの向こうで光が乱舞する。焼け付くようだった細胞が、少し楽になる。
その玉は暖かい。きっと生者の記憶だからだろう。利菜は、出て行け、と念じた。佳代子たちが後に続いた。
出ろ、出ろ、外に出ろ、玉になれ、風船になれ。
光は子どもたちの記憶を吸い続ける。髪を引きずりながら、ズルズルと浮かび、離れていく。
利菜がおそるおそる目をあけると、六つの珠は暗い部屋を七色に輝かせ、頭上に浮かんでいる。利菜はそれを中央に向けておしやった。一つに合わせようというのだ。
ずるりずるりと玉は離れていく。ふれてもいないのにずいぶんと重い。六つの玉が渦を巻いてまじりあう。キン、という高い金属音とともに、巨大な一つの球体となった。
「やった……」
利菜は手をつないだまま、呆然と光の玉を眺める。みんなの顔は七色に照らされ斑になっている。それはおまもりさまでみたどの記憶よりも大きかった。七色の太陽のようにコロナを放ち、ゆったりと回転している。
「どうするの?」紗英が震え声で訊いてきた。
「中に入って確かめないと」利菜が手を伸ばすと、紗英が止める。利菜は彼女をにらみ、「何があったか知るチャンスなんだよ。それに、装置の在処がわかる。マーサおばあさんの記憶もあるから」
坪井宅では、わるいものが再び騒ぎはじめている。犬の遠吠え、獣たちのわめき、それらが原始的な恐怖をかきたてようとする。それは世界のねじまげに逆らう子どもたちへの抗議に他ならない。
利菜はマーサのことを思いながら玉を見上げる。「あの人の記憶が必要なんだ。だって、あの人は全部忘れてる。秘密を握れるのは、あたしたちしかいない――」
そのときだった。
ガチャリガチャリグワラリ
扉がいくつも開く音がした。扉の向こうにあるのは黒い暗渠。そこからは目がのぞいている。釈尊会の信者たちだ。瞳には意志の輝きがなく、その奥にはどす黒い悪意だけが見とれた。殺される……と佳代子がつぶやく。なるほど、教祖の死体を見つけたら、彼らがすべきことは一つだった。
「お母さん」と利菜は言う。あの中に母親がいると思ったのだ。達郎が彼女を抱くようにして、
「やめろ利菜。行くんだ。おばさんはいたって、おばさんじゃない」
「でも……」
達郎は夢中で利菜の手を引っ張った。みんなはひとかたまりとなり、巨球にむかって手を伸ばす。大人たちが部屋を飛び出してきた。達郎は夢中で床を蹴る。無数とも思える手が子どもたちに伸びて、そのうちの一本はあやうく紗英の髪を捕まえかけた。
子どもたちは、その一歩寸前で、光玉へと姿を消したのだった。
○ ジノビリ歴三年 ――牢獄にて
□ 四
ヒッピは朦朧とした意識の中で、フロイトの言葉と格闘していた。トレイスはゲートに気づいてるんだ、みんなを逃がさないと!
まどろみから目を覚ます。自分はまだ目を開けていないか、失明するかしたのだと思った。鼻先も見えない暗闇だと、自分が寝てているのか立っているのかもわからなかった。闇の中に浮いているような感覚。だけど、すぐに意識がはっきりして、固い石組みの上に寝ているとわかった。痛覚が戻って、骨のあちこちが痛い。死体の群れにやられたのか、ひっかき傷からは血がうっすらとにじんでいる。
仲間とはぐれたのかと思うと恐ろしかった。けれど、その気を失うほどの恐怖も、誰かの息づかいを感じて和らぐ。
「ペック、パーシバル!」と彼はメンバーの名前を一人一人呼んでいく。「どこだ?」
ペックたちは彼と同じように冷えた体に辟易としながらも返事をしていった。肉厚な手が彼の指に触れる。ペックだろう。彼らは手探りで一塊になった。
渦をとおる前、マーサは牢獄のことを話していた。とすると、目的の場所にはこれたのかもしれない。問題は全員そろっているかどうかということだ。
子どもたちは暗闇の中に、まだ死体がいるのではないかと思った。けれど、あのゲートは閉じたのだから、わるいものがいたとしてもずいぶんとましになっているはずだ。
そのとき――
「トゥルーシャドウ、灯りはまだつかないかい」
とマーサの声がした。そして、カチッ、カチッという音。かすかな明かりが数度明滅。
「利菜は、元の世界に戻れたのかな?」
ペックの声がする。すぐ近くだった。ヒッピはわからないと答えた。空気のよどみ具合は、密室だと告げている。
トゥルーシャドウの手元で松明が灯る。一同は互いの顔にすらぎょっとなったが、すでにゲートは消滅しており、死体の群れは居なくなっていた。だが、空間は不安定なままのようだった。視界がおかしい。まるで液体の中にいるみたいだ。空間がところどころで波打っている。
フロイトの言葉通り、朽ち果てる寸前の牢獄があった。
「フロイトの言った通りだよ」とヒッピは言った。「この牢獄だって、三〇〇年前に誰かが作ったものなんだ。エビエラがダンカン人に作らせたんじゃないかな」ヒッピは部屋を見回す。「見てよ、ダンカン人のレリーフだ」
「奴らの都の地下なのかもしれん」とトゥルーシャドウは言った。「あの穴は最近掘られたものに見える」
ヒッピは頭を巡らせる。スミスという人物が世話を焼いていたのなら、それ以外の通路があったとは思えない。エビエラは牢獄を作ったあとは、全ての出口をふさいだはずだ。
「じゃあ、おれたち王都を脱出できたんだな」
とパーシバルが言った。興奮するのはまだ早い、とトゥルーシャドウは言った。トゥルーシャドウが見つけたのは、脱獄囚が掘ったような粗末な通路である。トゥルーシャドウがたいまつを近づけるが、そこには真っ黒な気体がドロドロと漂うばかりで奥をのぞくことができない。
ヒッピはその気体にさわろうとしたが、恐ろしくて手を引っ込めた。
「フロイトはこの牢獄が次元の狭間にあるって言ってた」
「つまり、おれたちは次元の狭間にいるということか?」
トゥルーシャドウは岩屋を見渡す。
「牢獄は回廊とつながることもあったと言ってたろ? なら、この牢獄も元の場所に戻るのかもしれない」
トゥルーシャドウは少し驚いた顔でこの少年の瞳をとくと覗きこんだ。
「エビエラが牢獄の出口を残したはずがないよ。ぼくなら全部ふさぐ。この穴は最近になってダンカン人が掘ったんだよ」
「ダンカン人はなんで穴を掘ったんだ?」とパーシバル。
「ダンカン人には、トレイスに関する伝承が、何か残っていたのかもしれん」とマーサは言った。
トゥルーシャドウがヒッピにささやいた。「出口はここだけだ。おそらくダンカン人の王宮の地下だろう。王宮の地下に悪魔が眠る――奴らの伝承の通りだ」
「それなら、牢獄が元の場所に戻っても、ぼくらは外に出られない」
ヒッピは必死に頭を働かせた。仲間達を救うために状況を把握しようとした。利菜がこの世界から消えたことはヒッピにとっても大きな痛手だった。仲の良い双子のように彼を支えた利菜の存在が心から全くなくなってしまった。つまりまあ単純に言えば、彼の精神力はたったの半分になったわけだ。彼に別の視点を与えてくれた数々の知覚が消えたのだから。ヒッピはそのことにとまどってもいた。便利な多重人格者だった彼も並の人間に格下げだ。
しっかりしろ、利菜がいなくたってこれまではしっかりやってこれたじゃないか、と彼は自分を励ます。けれどこれほどの窮地がこれまでなかったことも事実だ。
「ゲートをもう一度開こう。別の場所にうつるんだよ」とモタは主張した。
「それはだめだ。だいいちどこへ行くつもりだ。どこへ飛ばされるかわからないぞ」
「じゃあ、どうするんだよ」
パダルたちが不信の目を向けてくる。ヒッピは急に友だちに憎しみを覚えた。
「ここで利菜を待つんだ。あいつが戻ってこられるように」
「戻ってくるとは限らない。来なかったらどうするんだ」とパーシバル。
「戻ってくる。あいつは装置を必ず見つける」いやに確信に満ちた口調にパーシバルたちも黙った。「ぼくはあいつと精神がつながってた。あいつは最後まで戻ってくるつもりだった」
「だが、装置が見つかるとは限るまい」とトゥルーシャドウ。
「いや、フロイトは最後の最後で何かしたんだ」
ヒッピはちらりとマーサを見た。彼女は何も言わなかったし、うなずきもしなかったが、その目の輝きは何事か知っているようだった。
「利菜を待とう。ぼくらがいなきゃ、あいつだってこの世界には来られない」
「賭けだね」とマーサは嘆息する。
「みんな忘れてるよ」とパダルが悲鳴のように言う。「サウロンはこの牢獄のありかを知ってるんだぜ! そのうち、ぼくらを見つけにくるに決まってる」
そうなったらおしまいだ。とまではパダルも言わなかった。けれど、みんなが同じ言葉を思い浮かべた。相手は二十人からのナバホ族を一人で殺すような古代の怪物である。
「利菜が装置を見つけて戻ったとして……」とトゥルーシャドウはマーサの側に行き、子どもたちには聞こえぬ声で言った。「今度はそれを使いこなすものがいない。装置の正体は誰も知らない」
「利菜は気づいたのかも知れない。こちらとあちらの世界はずいぶんとちがうようだ」
「だが、あの子は子どもにすぎない。向こうの仲間とて同様でしょう」
「サウロンにとっては、大人も子どもも変わりがないよ」
トゥルーシャドウは吐息をついた。「信じて待つしかありませんな」
「奥が見えるぞ!」
トゥルーシャドウが顔を上げると、パーシバルが壁面の穴に顔をつきこんでいる。通路をふさいでいた次元の壁がなくなったのだ。パーシバルはヒッピが止めるのも聞かずに、穴蔵から身をのりだす。「トゥルーシャドウ、上から灯りだ! 誰かくる!」
「ダンカン人だ!」
トゥルーシャドウは剣をとりだす。壁面に駆け寄ると、パーシバルが体をどけた。トゥルーシャドウがたいまつを奥に突き出すと、通路は思ったよりも急斜面である。彼は体を戻すと、クロスボウに矢を装填しながら言った。
「通路がつながっている。牢獄が元の次元に戻っているんだ。おまえたち、下がっていろ!」
「どうするつもりだよ!」パーシバルがトゥルーシャドウのでっかい背中を叩いた。
「もう逃げ場はないんだ。戦うしかない」
こんなところでか――?
ヒッピたちは顔を見合わせる。彼らも銃は回廊に落としてしまって、二挺しか残ってない。ヒッピが弾数を確かめると、あと四発。
「ここはダンカン人の都なんだぞ」ペックがささやいた。「こんな弾数じゃとても戦えない。別の手を考えないと……」
せっかくここまで逃げてきたのに。パーシバルが奥歯を噛みしめる。それはこの場にいた一同の気持ちを代弁していた。
ヒッピはぐっと顔を上げた。気がつくと、天蓋の固い岩からも清水がじわじわとしみ出して、あちこちで落水がはじまっている。牢獄が元の場所に戻ったせいだ。
利菜……と彼は祈るような気持ちで一瞬目を閉じ、次元の向こうに消えた友だちを思った。彼は苦渋の決断を迫られている。選択肢はほとんどないというのに、心を決めることのなんと難しいことか。
待とう……と彼は言った。
「利菜も向こうの世界でグループとがんばっているんだ」とヒッピは岩屋を足早に歩き回り、仲間達を鼓舞して回った。「やるべきことをやるのはぼくらも同じだ。ここで利菜たちを待とう」
ペックはふう、と吐息をついた。それは恐怖によるものというよりは、むしろ安堵から出た吐息に近かった。
「わかったよ」
パダルとモタは抗議しようとしたが、ふりむいたペックの目がいやに落ち着いて、その顔は微笑をふくんでいたので何も言えなかった。
「ぼくはヒッピの言うとおりにする。だって、ぼくらは誓いをたてたから。あの子はぼくらのグループの一員じゃないか」
その言葉は染みるようにみんなの心に落ちていった。その染みたものはある種の重さとなってパーシバルの顎をうなずかせた。
「グループは助け合う」
パーシバルはある種の感動をもっていった。
「たとえ互いが死んでもだ」
ヒッピが手の甲を差し出すと、ペックたちはその掌の上に互いの手を重ねていった。トゥルーシャドウはそんな子どもたちを守るように立ち、ダンカン人の到来を待ちかまえた。
ダンカン人の足音が、ヒタヒタとせまってきた。
○ 記憶の中へ
□ 五
内臓が、引っ張られる。
胃袋が、六倍に伸びて、でんぐりかえった。骨も肉も何もかも。ゲートをかっとぶのは、細い水道管に無理矢理引きずりこまれるのに似ている。型にはめてやるよ! となめ太郎が言った。利菜は気の狂うようなその一瞬、母親のことを考え続けた。わるいものは父さんだけじゃなく、母親も人質に取っている。みんな悪人ばっかりだ。
体が伸ばされ叩かれる感覚に、めまいを起こす。それでも手の平からは友だちの存在を感じていた。自分たちは、ともに制約を交わしたグループなんだと感じたとき、その短くも長い旅は終わり、伸びきった彼女の魂は元の138センチの生身に収まった。
脚が地面をつかみ、ふらつく体を支えた。利菜は辺りを見回す、深い森の中にいる。彼女は記憶の残りカスを追い出すみたいに側頭部を叩く。疲れは残っているがずいぶんましになっていた。
「ここって記憶の中なの?」と佳代子が訊いた。新治たちは辺りの物に触れて確かめている。まるで現実と変わりがない。ただ、すごい既視感がある。
「これってただの記憶じゃないよ」利菜が言った。「気をつけないと、おまもりさまでも記憶の中で怪我をしたでしょ?」
利菜はこれが記憶だけど、現実と変わりがないことを言い聞かせた。利菜の二の腕には、兵隊に斬られた傷がまだあった。
佳代子が、「じゃあ、記憶の中で、死にでもしたら……」
「この場所、見覚えがあるぞ」
と達郎が言った。利菜は記憶をコントロールできるのか心配したが、一同は記憶のまっただなかにいたし、マーサの知識や体験を得たことで、どう扱えばいいかが、感覚的にわかってきた。
「たしか、こっちだよ」
利菜は先頭に立って歩き出した。イニシエの森とはまったくちがう森だった。ここにある木はもっと細いし、動植物も違っている。でも、ヒッピたちの世界であることは間違いない。利菜がみんなにそのことを説明していたとき、林がきれて、崖にできた洞窟が姿をあらわした。「サウロンが流れついたのは、ここだよ……」と彼女は言った。
洞窟は大人がすっぽり入れるほど広い。崖にぽっかりと口をあけ、子どもたちをのみこむみたいに見えた。奥はひどく暗いが、光が切れる寸前のところに、人の足が転がっていた。サウロンだ、と利菜が言った。
みんなはしばらく無言で見つめていた。足は微動だにしない。呼吸もしていないみたいだった。もっとよく見ようと、洞穴内に踏み入った。光の角度が変わり、闇にも目が慣れた。ミイラだ、と誰かが呟いた。
水分の大半をなくし、サウロンはみにくくしぼんでいる。黒く焼かれたような皮膚が骨にまとわりついている。こんな状態で生きているなんて信じられない。髪もほとんど抜け落ち、服も着ていない。これが皇帝と戦った代償なんだろうか?
「誰かに乗り移るのはこの後だろ?」と達郎が言った。あるいはここにあるのは単なる抜け殻なのかも知れない。「生きてるのか?」
「ほんとの英雄だったのね」佳代子が言った。
「今はちがうよ」利菜が興奮していった。ナバホ族を残虐に殺すトレイスの姿を急に思い出したからだ。「この人は、もう元のサウロンじゃない。いろんな人間といっしょくたになってる」
「いま、殺せばいいじゃないか」寛太が不用意に近づく。新治が止めた。「そうすればみんな終わりだ」
「無駄だよ。これは記憶だもん」と利菜は言う。「あたしたち、過去にきた訳じゃない。記憶の中でサウロンを殺してもなんにもならない」
「だけど、ぼくたちは死ねば終わりなんだ」と新治が言った。
「記憶をうつろう」と利菜は言った。自分にはそれが出来る気がした。「サウロンの記憶はもういいよ。肝心なのは、マーサおばあさんの記憶……」
彼女は危険を感じてふりむいた。サウロンの目が開いていた。こんなに干からびているのに、目玉だけはヌラヌラと赤く光っている。胸を悪寒が走ると、利菜は無意識に身を投げ出していた。背中の上を衝撃が通り過ぎる、服がはためき、皮膚が剥けるほどに波打った。利菜が地面にたたきつけられた瞬間、洞窟の壁が崩れて岩が落ちてくる。利菜は無数の土石に押しつぶされて、どっと息を吐いた。あばらが軋み、内臓が破裂しかかる。生き埋めになったと感じたときには、意識をなくしかけていた。
そのとき、足首をつかまれた。
サウロンだ、サウロンがあたしの足をつかんでる!
サウロンの意識が体に忍びこんでくる。全身の体液が凍るような冷え冷えとした感触に、視界がくらんだ。利菜は体をふさぐ岩の重みも忘れて絶叫したかったが、呼吸も出来ない。
□ 六
利菜……
佳代子が跪いた。岩に手をついた。利菜がこの真下にいるとは信じられなかった。達郎達は夢中で岩をどかそうとするが、同時に悲鳴を上げてもいた。身体がうまく動かない。痛覚をどでかい針で何度もぶっさされている気分だ。彼らは精神をつなぎ合わせていたから、骨がきしみ内臓を圧される感触がまざまざと伝わる。それに利菜の体に乗った岩はあまりに重い。
それに、サウロンだ! サウロンにつかまって苦しんでる!
佳代子はとっさに、岩から伸びた利菜の手をつかんだ。
「みんな手をつないで!」と彼女は言った。「記憶をうつらないと! どこでもいいから思い出して! 利菜が死んじゃう!」
達郎たちはあわてて利菜の手をつかんだ。別の記憶を、安全な場所を、必死にさぐった。
肉体のねじまげ現象がまたおこった。佳代子たちは利菜の上から、岩の重みがぬけるのを感じた。一同は一塊になって、真夜中の森に放りだされた。佳代子は地面をかくようにして利菜に近づき、
「利菜、大丈夫!」
と両手で頬を抱える。紗英が手足を確かめてまわる。さいわいどこも折れてない。でも、擦り傷だらけだ。ショック状態で、混濁している。
佳代子は男の子たちを向いて言った。
「もう無理だよ。利菜はけがしてるんだよ――」
□ 七
利菜はその言葉をどこか遠くで聞いていた。まるではるか上空から下されるお告げみたいだ。けれど、友だちがまた引き返そうとしているとわかったとき、急に頭がはっきりとなった。ぱっと目を開いて佳代子の腕をにぎる。痛む内臓をだまして言った。
「あたしなら、大丈夫だよ」と咳きこむ。本当はあちこち痛かったのだが。骨が折れていないとはいえ、筋を痛めたのかもしれない。でも引き返すなんてとんでもない。「ここは、どこなの?」
達郎がわからないと答える。利菜は自分が両神山を念じたことを思い出す。周囲の木立は杉のようだ。
「きっとマーサおばあさんの記憶だよ。ここは両神山だ」
利菜みんなに説明した。一同は獣道に座り込んでいる。森はむやみに湿気っていて、樹木は露に濡れている。深夜みたいだ。
「マーサおばあさんは、江戸時代の人なのよ。元はまさって名前。向こうでも最初はそう呼ばれてたけど、そのうちになまったんじゃないかな」
マーサは記憶をなくしたし。
「いまがいつ頃かわかるの?」佳代子が訊いた。
利菜は佳代子の手を借りて立ち上がる。夜だから、よくみえないが、周囲の木立には見覚えがあった。
寛太が、「ちょっとまてよ。ここはあの山なのか? 両神山なのか?」
「たぶん、大丈夫だよ」と佳代子。「今って、あの人が、向こうの世界にいく前でしょ? 装置が埋まる前だから、まだふつうの森なんだよ」
利菜は斜面を見おろした。獣道が這うように伸びている。この時代にも植林というのはあったようで、杉はどれもひどく細い。ここは両神山の中腹でこの道が麓の村まで続いているとわかった。なんだか頭の中にナビゲーターがいるみたいだ。
「この道をまささんが登ってくるのよ」利菜はまささん、と言った。今のマーサとこの時代のまさはちがいすぎて、別の人間のように感じた。
まさは、麓の村人である(今となってはその村ももうないが)。といっても、元から住んでいたのではなく、夫とともに遠くから越してきたのだ。二人は当時禁教だったキリスト教を信仰していた。弾圧を逃れてあの村にたどりついたのだが、その村にも捕り手はおしよせてきた。まさと三郎は、追っ手をおそれて山に逃げこみしばらく潜んでいた。侍は村人をつれて山狩りを行う。三郎は、銃にうたれ、まさだけを逃がす。そのまさが、丘をのぼってこようとしてる。
彼女らが知りたいのは、装置の在処だった。この記憶は目的と無関係だ。だけど、利菜は動きたくなかった。まさに何が起きるか知っているのに、見捨てるなんて出来なかった。
「利菜」と達郎は言った。「マーサおばあさんを助けるつもりなら、まちがってるぞ。全部終わったことなんだから、おまえもそういったじゃないか」
「わかってるよ、そんなこと」
佳代子が手をとった。「あんたは自分じゃわかんないかもしんないけど、ひどい怪我かもしんないのよ。岩に押しつぶされたんだから」
利菜はさきほどのことを思い出し、震えた。だけど、まさがあんまりにもかわいそうだ。あの人はひとりぼっちで別の世界で暮らさなきゃいけない。利菜はそれとまったく同じ目にあったのだ。だから、あの人を見捨てるなんて出来なかった。
両神山の山頂付近には、例のお堂がある。あそこまでついてくのか? と達郎が訊いた。
新治が言った。「侍も後から来てるんだろ。ぼくたちも襲われる」
足音がした。みんなは道を逸れて斜面に隠れた。利菜がふりむくと空には満月があった。それで山の中が明るいのだ。細い陰が斜面を走ってくる。
利菜はみんなを責めるみたいに、「三郎さんを置いて一人で逃げてるのよ。あたしはマーサばあさんに世話になったから。記憶の中だからってほうっておけない」
まさは足を引きずっているみたいだ。大勢に責め立てられて、ほとんど死ぬ思いで逃げてきたのだ。着物のすそをからげて、履き物も脱ぎ捨てて、懸命に駆けてくる。泣き顔をうつむけてほとんど前を見ていない。子どもたちは本気で彼女が憐れになった。
「よし、助けよう」と達郎は言った。
六人が獣道に出て行くと、まさは泣き顔をうつむけていたから、しばらく子どもたちに気づかなかった。やがて、道をふさぐ人影に足をとめた。利菜は慌てて声をかけた真雅、引き返そうとしたからだ。
「まって、マーサおばあさん――まささん! 助けたいのよ!」
まさがふりむいた。「あんたたち、なんであたしの名を……」
「三郎さんに頼まれたのよ。逃がしてやってくれって」利菜は山頂を指さして、「逃げる道なら、上にある」
「上に行ったってなにもないわよ」とまさは泣きながらいいかえす。「三郎はそこにはいないもん」
「だけど、逃げなきゃ……」
と寛太がつぶやく。まさは、背後からせまるたいまつの灯りに不安を覚えたものらしい。一歩一歩足を引きずりながら、こちらにのぼってくる。まさは美しい人だった。マーサは白髪だったが、彼女はまだ黒髪だ。涙に濡れて、頬は煤けている。山で生活したせいか垢じみていた。それでもきれいな人だった。三百年の苦労がマーサに変えてしまったのかと思うと、利菜はふいに泣けてしまった。達郎がまさの前で腰を落とした。
「なに?」
「足を怪我してるだろう。はやく」
と達郎が言う。本当なら、まさは山道をこのまま夢中で駆け上がったはずだ。だけど、利菜に呼び止められた今は、緊張の糸も切れて一歩も動けそうにない。まさは達郎の背に被さり吐息をついた。子どもたちはいたわるようにまさを支える。まさはこんなところにいる子どもたちを疑問に思うには心が壊れすぎてしまったんだろう。それでも彼女は子どもたちをいたわった。
「ありがとう。あんたたち、だけど、あたしは罪人なのよ。一緒にいると、ひどいめに……子どもだからわかんないだろうけど、三郎も、あたしも」
そこで、夫を思い出したのか、目に手をあてて泣きはじめた。利菜も下を向いて泣いた。マーサだって元々はこんなふうにやさしくて率直に感情をあらわす人だったのである。まさとマーサの間を埋めた出来事を知っているだけに、彼女はうんと悲しくなる。
「行くぞ」
達郎がぶっきらぼうに言い捨てた。子どもたちは山道をのぼりはじめた。
江戸時代の両神山は、おまもりさまとはずいぶんちがった。おまもりさまは平坦な樹海だったが、ここでは勾配が六人を苦しめた。子どもたちはときおり後ろを気にしたが、追っ手の松明は見えない。捕らえた三郎に手間取っているんだ、と思うと利菜は身内が冷える気がした。
一同は、ついに山上のお堂にたどりついた。利菜がおまもりさまで見つけたお堂と瓜二つだ。おまもりさまではひどくうら寂しく見えたが、それはここでもかわらない。空が開けて星空がどっと降ってきた。まさが達郎の背をおりて、ふらふらとお堂に近づいていく。
「ありがとう、あんたたち」お堂の前に立ち、ふりむく。「どうやって、お礼をいったらいいか」とまさは泣き出す。「もう、三郎はいないんだね。あの人は追って来られないんだね」
「そんなことないよ」と利菜は言った。事実を知っているのに、うそをつくのは辛かった。「三郎さん、後から追いかけてくる。そうでしょ?」
まさの瞳がまた揺れた。利菜の言葉を信じているとも、たんに悲しんでいるとも見て取れた。まさは利菜の髪をなでた。「そうかもしれないね。きっとそうだね」とうなずく。「あんたたちがあたしの子どもだったらよかったのに。あの人との間に生まれた子だったらよかったのに」まさはみんなを抱き寄せた。「さあ、もうお行き。後ろの山は深いから、向こうには間違ってもいっちゃいけないよ。西に向かって降りれば、粟倉村につくから」
まさは、自分がお堂に残って兵隊をひきつけるつもりだった。それなら、子どもたちが逃げられると信じているのだ。「あたしなら、大丈夫。三郎と、ここで会う約束をしたから、もう……」
まさは耐えきれなくなったのか、震える唇をかくしてそっとお堂に姿を消した。扉をしめた。
利菜はその場を動けなかった。新治が、あの人どうなるの、と訊いた。
このあと、利菜のときと似たことが起こる。銅鏡がにぶく光って、それに近づいたまさは、向こうの世界につれこまれる。
お堂に近づくと、まさは扉のすぐそばでうつぶせに倒れていた。気を失ったのか、疲れて眠ったのか、わからなかった。
もう行こう。達郎がつぶやいた。みんなはお堂を離れた。
利菜は、自分の存在がその場から消える瞬間、祈るように呟いた。大丈夫、そこならきっと安全だからね……。
□ 八
六人は、その後もまさの様子をたびたび覗いた。まさは神官たちに保護され、サイポッツの都につれていかれた。エビエラの弟子となったのは、その後のことである。大鏡のある場所には、機会をみつけては戻っているようだった。
エビエラはそんなまさを見て、あるとき、元の世界に連れて行った。たった一人で二つの鏡をつなぐことができるとは、本当に力のある魔女だったのだ。
元の世界への帰還は、まさにとって、残念ながら良い結果をもたらさなかった。まさが見たのは、夫の生きている姿ではなかった。三郎の死体だったからだ。山の中に、捨て置かれていた。
三郎はその当時の禁をおかしていた。まさにまんまと逃げられたことで、追っ手の怒りをかったようだ。死体は片づけることすら許されなかったのだろう。
まさは三郎の遺体を埋めて、墓をつくったあとも、しばらくその場にいた。
何時間も。
□ 九
まさの記憶をのぞくのは辛いことだった。まさは辛い修行に耐えて懸命に生きた。淋しさを紛らすみたいに蓮っ葉な口をきいて、師匠とよく喧嘩をした。だけど、胸にかかえた辛さも恨みも、隠せなかった。一人ぼっちの彼女は涙を人に見せなかったが、だけど、そうも言っていられなくなる。サイポッツの世界では、すでにあのサウロンが勢力を伸ばしつつあったからだ。サウロンは、計画の完遂だけを目的に生きていた。皇帝が死んだとは信じることができなかったし、あのような種を生み出すにいたった世界そのものを憎みきっていた。彼は幾人ものサイポッツと融合を繰りかえし、変質を遂げていく。オットーワイドはそのうちの一人で、ムーア教団の教祖だった。その変貌に気づいた政治家が、後をつけ回すようになる。その男がトレイスだった。トレイスになったサウロンは、政治の世界に踏み出していく。当時は、平民と貴族の区別がなく、完全な共和政治が行われていた。議員に姿をかえたサウロンは、有力者を殺し、ついに制度をくつがえす。自ら皇帝を名乗り、都を支配下においた。
トレイスの暴挙に、都にいたサイポッツの多くは難民となる。彼らはイニシエの森に安居を求めた。その中に、共和国の政治家であるハフスがいた。ハフスたちは森の魔女エビエラに助けを請う。そして、エビエラはイニシエの民に協力をもとめる。サイポッツの軍隊と、イニシエの民との戦争はこうして起こったのだ。けれど、進化種であるサウロンの前では、エビエラといえども敵とはなりえなかった。おまけにサウロンは、帝国の生み出した機械を持っていた。外見は小さな箱だが、人の思念を現実化する力をもっていた。サウロンはその小さな箱を、なぜか聖柩(せいひつ)と呼んでいた。隆盛を誇った帝国のそれが唯一の名残だというのなら、柩といえなくもない。
老いた現在とは比較にならなかった。エビエラに勝ち目はなく、ハフスたちは戦争による勝利を放棄した。奸計をもってサウロンを眠らせると、装置を奪い取り彼を次元回廊に封じこめることに成功する。エビエラは、サウロンが殺した相手に乗り移ることまでをも見抜いていたのだ。
エビエラは、サウロンなきあと、装置の扱いに苦慮したようだ。装置の力はすさまじく、とても扱いきれるものではなかったからだ。まして、他人の手に渡すには危険すぎるしろものだ。彼女は年老いている。エビエラは装置の行く末を案じた。サウロンはいつ出てこないともかぎらない。彼を殺す方法は、彼女でも最後まで思いつかなかった。
エビエラは、その装置を別の世界に隠すことを決意する。まさの世界に。
最後に、エビエラは、まさの記憶を消した。装置の在処が洩れることを心配したのだろうが、長い生涯をつらい記憶とともに生きねばならない弟子を、不憫に思ったのだろう。
まさはマーサと名乗るようになる。イニシエの民は、戦争の記憶とともに、エビエラの遺言を守り続けた。そして、数百年がたった。
□ 十
記憶を抜け出たとき、子どもたちは、静かな心持ちだった。泣くこともなく、騒ぐこともなかった。気持ちの整理がつかなかった。ひどく濃密で感傷的な映画を見た後のようだ。
エビエラは、まさがハフスと添いとげることを望んだようだが、結局は、まさの望み通りになった。彼女は記憶をなくした後も、あの森で三郎の帰りを待ち続けたわけだから。そのことが良かったのか悪かったのか、利菜には判別がつかない。
記憶の珠は消えていた。信者はいなくなったみたいだ。坪井の死体もなくなっている。彼らは車座になる、話し合いをはじめた。重要なことはいくつもあった。
利菜はエビエラたちが、サウロンの牢獄をつくるところも見てきた。工事に協力していたのは、ダンカン人だった。彼らの王宮の、はるか地下に牢獄を築いたのだ。その後、ダンカン人たちは偶然にもサウロンの牢獄につづく通路を発見した。どうりでダンカン人は、森の民なのにサウロンと関わりを持っていたはずだ。彼らの裏切りは、エビエラが三百年前にサウロンの牢獄を築いたときから必定であったのだ。
サウロンの牢獄自体は、エビエラが装置の力で次元の狭間に封じていた。通路をふさいでダンカン人側からも近づけないようになっていた。その仕掛けが崩れたのも、三百年の年月がもたらした誤算であったのだろう。
利菜は窓に目をやった。八月の大気が復活していた。日差しがじりじりと一枚ガラスを焼いていた。強烈な夏の生命力。なのにこの家は死体でいっぱいだ。
ややあって、佳代子が言う。「装置を手に入れなきゃ。あのときの神官もエビエラって人も死んだんだから」
「あんなことがあったなんて……」利菜は首をうつむける。複雑な感情が胸をふさいでいる。「あたし、マーサおばあさんを助けてあげたい。みんな協力して」
友だちはみんなうなずいた。けれど、最後の対決が近づいているのも事実だった。記憶の中でサウロンの力はいやというほど目にしているだけに、異世界に渡って古代の英雄と対決するという馬鹿げた話も奇妙なほど現実味があった。
利菜たちは話を進めた。あの装置はずっとおまもりさまにあった。だから、この世界でだけで想像の現実化が起こったのだ。世界の崩壊がこの世界にも及んで、装置はいよいよその猛威を振るい始めている。人々の集合無意識と結びつき始めていた。神官たちが大鏡とこの世界の鏡を繋げたままにしたのは、いつかきっと必要になるとわかっていたからだった。
「早く装置を手に入れないとまずいぞ」達郎が言った。「サウロンに先を越されたらおしまいだ」
紗英が、「それって、おまもりさまに戻るってことでしょ?」と言う。「あんなすごいもん、どうにもできないよ。頭の中身を現実化しちゃうんだよ。わるいものも全部。今だって、悪い考えを抑えらんないのに」
「でも、サウロンに取られるよりましだよ」佳代子が言った。利菜もうなずいた。「あの場所は、もうあたしたちしか知らない。誰にも頼めないんだし」
「もう一つ、わかんないことがあるんだけど……」新治がひかえめに訊いた。「エビエラって人は死んじゃったのに、マーサおばあさんは死ななかったろ?」
それについては、なんとなく見当がついた。まさは、元々あの世界の人間じゃない。この世界からもいなくなった。人類の集合無意識からも、サイポッツの集合無意識からもはみ出してしまった。記憶や意識が溜まり続けるものならば、まさには帰るところがなくなったのだ。たぶん、ハフスやスミスも、別の世界の人間なんだろう。サウロンも。サウロンと融合した、トレイスも。仮説にすぎないが、きっとそうだとみんなは思った。
「もう行こう」
と達郎。もう行くの? と紗英。心底怯えた表情だ。
「エビエラは一人でもこっちの世界に来ることが出来た。サウロンにだってできるかもしれない」
ねじまげはさらに強くなっているんだし。
達郎が立ち上がった。男の子たちは後に続こうとしたが、佳代子が呼び止める。
「ちょっと待ってよ。今は何日なの? あたしたち、八月十七日に来てたのよ。今まで記憶の中にいたからって、時間が経ったとはかぎんないじゃん」
達郎はハッとふりむく。「おれたちがおまもりさまに行く前に装置を取ったりしたら、利菜は向こうの世界に行かないことになる」
「そうだよ。ぼくたち、過去をいじることになる」新治が言った。
「おれ、漫画で読んだことがある」寛太が言った。「世界がいくつも増えるんだ。タイムパラドックスってやつだ」
「本当は何日だったの?」と利菜。
「たしか八月二十一日だ」達郎が答える。
「本当に? あれから二日しかたってないの?」利菜は目を丸くする。
「それでも、今日が十七日なら、おまもりさまに行く前だよ。三日もオーバーだ。装置をとったら、わるいものも収まって、みんなおまもりさまには行かないかもしれない」
「待つのか?」と寛太が訊いた。ここで八月二十日が来るのを待つのか、と訊いている。それなら、捜索隊が引き上げるまで待った方がよかった。
「この家で?」冗談じゃないよ、と紗英が言う。
達郎が、「今日が何日か確かめよう」
六人は階段をおり、居間にいった。達郎がテレビをつけてチャンネルを回すと、ちょうど笑っていいともをやっていた。
「木曜のレギュラーメンバーだ。まだ十七日なんだよ」
「もう一度、ゲートを開けないかな?」佳代子が言った。「そんで三日後のおまもりさまに行くの。どうかな?」
「無理だよ」と利菜は首をふる。「未来に出られるかわかんないし、それにどうやって出口とつなぐの? どの出口と?」
失敗したら、どこに出るかしれない。利菜たちはその結果を思って身震いをした。ひょっとしたら、サウロンの二の舞になるのかもしれないのだ。
「サウロンは絶対あきらめないよ」と利菜は言った。「あいつは、帝国がまだ滅んでないって思ってる。世界が間違った方に進んだって信じてるのよ」
サウロンの計画は、宇宙を地球でいうところのビックバン以前の原始の姿に戻すことだったのだ。究極のテロリストみたいなやつだ。
みんなは無言で互いをみつめあった。利菜は苛々と腕を組んだ。こうしている間にも、ヒッピたちはサウロンに見つかっているかもしれない。
「どうすればいい?」
と彼女は友だちに知恵を求めた。達郎はじっと考えこむ。リトルの監督みたいに作戦を練る。窓の外をみた、まだ日が陰るほどじゃない。だが、朝とはいえないようだ。正午を少しすぎだろうか?
「記憶にはいってた間、外の時間は進んだと思うか?」
達郎の言葉に、みんなは考えこむ。
「どうかなあ、進んだとは思うけど、どのぐらい向こうにいたかわかんないよ」
弟の言葉に、達郎はうなずいた。
「時間を飛ばさなかったらどうなるかな?」と彼。「つまり、記憶の中で、ちゃんと三日間すごすんだよ。そしたら、こっちでも三日経ってるかもしれない」
五人は顔を見合わせる。
「おれたち、記憶の中で、まささんと話し合ったよな。あれって夢みたいにあやふやなもんじゃなかった。怪我もしたし、おれたちにとっては現実だった。時間もちゃんと動いてた気がする」
「でも、記憶はもうなくなったじゃない」
「もう一度記憶を出すんだ。もう一度やってみよう。ぐずぐずしてたら、また坪井の奴らが……」
「待って」
利菜が大声を出した。達郎たちは驚いて彼女をみた。
「な、なんだよ。反対なのか?」
「そうじゃない。浮かんだのよ。すっごくいい考えが」達郎の腕をつかむ。「装置の場所はわかったけどさ、達郎ちゃん、あれを手に入れてどうするつもり?」
「どうって……」
「あたしたちだって、あの装置はとれないよ。だって、どうやって使えばいいかも知らない。エビエラって人以外は使えなかった。わるいものが出てきておしまいだよ。エビエラだって、あれが危険だったから、手元から遠く離れた世界に埋めたんでしょ?」
その通りだった。
「つまりさ、わるいものを……なめ太郎や溺死女を生んでるのは、あの装置なわけでしょ? そんなもんに手を出したら、ただですむわけないよ」
「じゃあ、どうするんだ?」
「装置の扱い方は、使える人に教えてもらうしかないよ」利菜は勢い込んで言った。
「なに?」と達郎が訊きかえす。「マーサばあさんか? あの人に教えてもらうのか?」
「ちがう。まささんは装置を使えなかったし、今はあの頃の記憶がないんだよ。エビエラだよ。記憶の中で、エビエラに修行をしてもらえばいいんだよ」
みんなは呆然となった。
「記憶の中でか? エビエラに教えてもらうのか?」寛太が独り言のようにつぶやく。
「そうだよ。あれはただの記憶じゃなかった。起こったことをただ繰り返してただけじゃなかったでしょ? あたしたち、サウロンに襲われた。まささんとは、会話だってできた。達郎ちゃんは、あの人を背負ったじゃない。あの人はちゃんとした人間だった」
利菜はまさやエビエラに人格があったと言いたいのだ。その意味でも、あの記憶は記録映像とはちがう。
「あたしたちのことなんて説明すんのよ」佳代子が訊いた。
「それに、サウロンをやっつけた後にいかないと」と紗英。「装置をつかって練習するってことでしょ」
「それなら、うまくいくかもしれないな」達郎がつぶやいた。「でも、サウロンは殺せないんだぞ。エビエラだって、閉じこめる以外に方法を考えつかなかった」
「でも、あたしたちはサウロンの過去を知ってる。今度はエビエラも思いつくかもしれない」
達郎が、「死んだ人間だぞ。記憶の中の人間だぞ」
「パラレルワールドってことじゃない」
と紗英が言った。みんなは彼女を睨んだ。これ以上、ややこしくなる言葉を増やして欲しくなかった。
利菜が言った。「もういっぺんやろう。手をつないごうよ」
六人は再び輪となった。彼らは意念を集中して、取り決めておいた記憶をひっぱりだす。くたびれ果てていたから、今度の珠は小さかった。記憶の大半を外に出してしまったことも響いていた。
利菜たちは、エビエラに会うために、記憶の世界に姿を消した。だけど彼らは気づかなかった。考えが及ばなかった。坪井の家にあれほどいた信者たちがいなくなっていたことに。
わるいものが、ずっと聞き耳を立てていたことに……。
○ 記憶の森にて
□ 十一
彼らはあの日のヒッピたちのように(あるいは三百年前のハフスたちのように)、おっかなびっくりエビエラの家へと近づいていった。時間は早朝で、季節は秋口。夏にいた利菜にとっては少し肌寒いが、サウロンを倒した直後に戻って来れたとわかった。マーサの家は昔どおり、ムスターサに壊される前の姿だった。三百年前のはずだが、扉も扉の脇の鐘も利菜の記憶と一致している。
少し離れた茂みからエビエラの家をのぞいた。なんだか近づきがたい。マーサの語ったエビエラの悪いうわさも、子どもたちの不安に拍車をかけていた(愛弟子にここまで悪く言われるとは、いったいどんな人物だろう?)。とくに、寛太と新治はエビエラに会うのをいやがった。寛太は悪ガキだったし、新治はきびしくされるのが苦手だったのだ。
「みんなしっかりしてよ」と利菜は言った。「装置をつかって練習するのが一番いいんだから。あれがどんなものか知っとかないと……」
物の落ちるどさりという音がして、利菜はふりむいた。まさだった。足下に、洗濯物の入った籠が転がっている(ふいにマーサに洗濯をやらされていたヒッピの姿が思い起こされて彼女は泣けてきた)。
「あんたたち」まさは純粋にとまどっている。「どうしてここに?」
利菜はみんなと顔を見合わせた。記憶の中の出来事なのに、まさは彼らを覚えている。利菜は物も言わずにまさの腰に抱きついた。佳代子と紗英も。まさがかわいそうだった。彼女はこれから何百年もひとりぼっちで暮らすことになるのだ。
「みんな……」まさが訊いた。「どうやってこっちに来たの? 大鏡をぬけてきたの?」
「ちがうんだ」
達郎たちは少し離れたところにいた。まさの瞳にはあのとき以上の深い悲しみがあって近寄りがたかったのだ。
「何が違うの? じゃあ、どうやって……」
まさは、この子どもたちについて何も知らないことに気づいたようだ。あのときは暗闇だったし、夢中だった。どの子も見覚えがない。それに見たこともない服装だ。
「あの世界の人間じゃないの? そうなのね?」
とまさは訊いた。利菜は答えに迷う。友だちと視線をかわし、やがてうなずいた。達郎が言った。「おれたち、エビエラって人に、修行をしてもらいたいんだ」
「師匠に弟子入りしたいってこと?」まさは驚いた。「それは無理よ。あの人は、弟子をとらないし、それに今は……」
利菜は先を読んでいった。「装置を埋めにいくんでしょ?」
まさが身震いをする。「何をいってるの? あんたたち……」まさは笑い飛ばそうとしたが、できなかった。子どもたちの目に、真剣な光があったからだ。「なんで知ってるの……」頑なになる。利菜の肩をつきはなす。「あんたたち何者なの?」
利菜はまさの腕をつかみかえした。「エビエラの修行が必要なのよ。装置をつかわなきゃいけないから」
ヒッピたちを助けたいんだ、と彼女は言いたかったが、それをいってもまさはとまどうばかりだろう。まさはきゅっと口元を引き結ぶ。女の子たちから体を離した。
「あれは使っちゃいけない。使えるもんでもない。そんなことは口にしてもいけない。あんたたちは命の恩人だけど、いうことをきくわけにはいかない」背を向ける。「帰ってちょうだい。あれは誰にも渡せない。見せるわけにもいかないんだから」
「でも、いずれは必要だと思ってるんでしょ」と佳代子も訊いた。「サウロンをやっつけるのに、また使わなきゃいけないから」
まさの口元は笑おうとした――けれど目に見えるほどに震えて、しかたなく息をのむ。「サウロンの名前なんて口にだしちゃだめよ……だいいちトレイスがサウロンだって、なんで知ってるの。あいつの残党狩りはまだ終わってない。あんたたち、その候補になりたいの? もう終わったのよ、あいつはいないの!」
利菜は左右に首を振る。ちがうよ、と彼女は言った。まさに否定されたことがむやみにショックだった。今回先頭を切って戦ったのは、目の前にいるまさのなれの果てなのである。
「何がちがうの?」とまさは訊いた。
「サウロンをあれでやっつけたなんて、自分でも思ってないんでしょ? だって、あいつは死んでないじゃない!」
「それは殺せないからよ!」とうつむく。「本当はあたしだって」
まさは泣き出しそうだ。利菜はこの戦争で、サイポッツやまさたちが、どんなひどいめにあったか知っている。それを思い出させるようなことを言うのは辛かった。でも、引き下がったら、未来のまさが救えないのだ。
利菜はあの危機的状況でも、マーサが無事だと思いたかった。マーサも、ヒッピたちも、みんな。
「もういい加減にしてちょうだい。あいつのせいで大勢死んだのよ。もう終わってほしい。続きがあるなんて考えたくもない」
まさは籠を拾うと、家に向かって歩き始めた。
利菜は友だちが止めるのもかまわず後を追った。彼女の腕をとった。「だけど、サウロンが出てきちゃったのよ! あたしたち、あいつを食い止めなきゃいけないの」
まさはふりむいた。怒っているというよりも、戸惑っているようだった。
「サウロンは三百年後に回廊から出てくる。あいつはサイポッツと蛮族を戦わせた。今よりずっと大勢死んで、あたしたちもう負けかけてる。このままだと装置もサウロンが取り戻しちゃう! そうさせちゃいけないの、わかってるでしょ?」
まさは顔を上げた。涙がいっぱいたまる目で利菜をみた。
「そんな話は信じられない。自分たちが、未来から来たなんてせりふは聞きたくない。あたしはあんたたちが好きだから言ってるの。戦争でみんな気が立ってるのがわからないの!」
利菜は言葉に詰まった。未来から来たわけじゃない。今いるのは過去ですらないからだ。「ふざけてなんかない。まささんに何があったかなら、あたしたちみんな知ってる」
「エビエラに会わせてよ。あの人なら、わかるはずだから」
お願いします、と、みんなは何度も言った。まさにすがりつくようなかっこうだ。拾った籠がまた落ちた。まさは髪をかきあげた。何度も。やがて、
「わかった――わかったよ。あんたたちには、恩があるしね。だけど、会わせるだけよ。あたしはあんたたちの味方はしない。師匠に何を言われても、責任もたないよ」
まさは、家に向かって歩きだした。利菜は慌てて洗濯物を拾い集めた。後に続いたのだった。
□ 十二
「師匠、会わせたい人がいるんですけど……」
「そのようだね」
とエビエラは言った。利菜はまさの後から中に入った。怒鳴られるかと思ったが、エビエラは涼しい顔をしている。もう相当の高齢のはずだが、現在のマーサよりも若く見える。同じ色のローブ、少し背が高かった。それに痩せぎすのマーサに比べると、小太りでその分しわも少なかった。目の大きな人で、その瞳で利菜を見下ろす。
「変わったのがきちまったね」と吐息をついた。
「言ってることも変わってるんですよ。サウロンや装置のことを知ってるし、あの回廊のことまで……」
エビエラが手をあげた。まさは黙った。利菜を指差し、「おまえ、こっちへきな」と言った。彼女は名指しをされて、びくびくと側に寄った。
「この子たち、向こうの世界であたしを助けてくれたんです」
まさが小声で口添えをした。
「例のガキどもかい。どれ」
エビエラの手が、利菜の頭にのった。エビエラの意識が脳をまさぐる。利菜は抵抗せずに受け入れるようつとめた。
エビエラは少し目を開けた。
「おまえ、修行を受けたことがあるのかい。いったい誰に……?」
エビエラは黙った。利菜は目を閉じているので、表情はわからなかったが、苦悶しているのは感じられる。どうなるんだろう? と彼女は思う。自分の記憶をみて、エビエラが受け入れられるかは確信がなかった。
「ふむ、こいつは……こいつは驚いた」とエビエラはつぶやく。やがて手を離すと、黙って椅子にもたれかかる。うなだれ、静かに涙をこぼした。
「師匠……」
まさが気遣うように近づいたが、エビエラはそれよりも早く顔を上げた。もう涙はなかった。
「いいだろう。ガッハッハッ、まさがしわくちゃのばばあになろうとはね」
まさは驚いて目をしばたかせる。エビエラが、
「記憶を見せてもらったが、この子たちの言ったことは本当らしい」
「そんな……」
「とくに、利菜と言ったね。おまえは面白いよ。どうやらあたしの孫弟子と言っていいようだね。よく来た」さらりと言った。「おかげで、サウロンのことがずいぶんとわかった。まさよ。この娘はどうやらおまえの弟子らしい」
エビエラは、利菜たちのことをまさに詳しく話した。自分たちが記憶にすぎないこともふくんでいた。まさは目を丸くして聞いた。信じていないようだった。
「サウロンが皇帝と戦った英雄だったとはね。しかも、三百年後には世界の崩壊はずっと進んできているわけだ」
話が終わると、エビエラは順繰りに六人の顔を見た。
「さて、これからおまえたちに修行をつけてやらねゃあいかん。そこで率直にいうが、三日では装置を扱えるようにはならん。当たり前だがね。そもそも三日ていどの修行でサウロンに対抗しようなんていうのがあまったれた話さ。おまえたちから仕入れた情報によるとだよ、サウロンってのはサイポッツではないんだろう。あたしらよりもずっと進化した、別個の種族と考えていいと思う。装置を使いこなせたとしても、あいつに勝てるとは限らんよ」
まさが子どもたちをちらちら見ながら、「師匠、本当にサウロンが出てくるんですか?」とささやいた。
エビエラがうなずいた。「そうだ。未来でおまえはしわだれのババアとなり、トレイスと戦う。そして、この子たちの肩に未来がかかっているようだ。今の状況では、あの装置をとりにいけるのはこの子たちしかいない。厳しいがやってもらうしかないだろう。この子たちの記憶はどう考えても本物だからね」と吐息をついた。「まず最初に誤解から解いておこう。おまえたちは装置のことを、なんでも希望をかなえてくれる魔法の箱のように思っているが、そうではない。確かに頭の中の想像を現実化するが、本来強い意志の力でしか扱えない物なんだ」
「でも、おれたちの世界では、わるいものが現実化してるんです」と達郎。
「なめ太郎に溺死女かい? 確かに悪い考えや想像が現実化しているのは、山に埋めた装置のせいだ。サウロンの行ったねじまげのせいでもある。人間の集合無意識と、装置が感応したとしか思えない」とエビエラが言う。「つまりおまえたちは、今までも装置を使ってきたと言えなくもないんだよ。その意味では、おまえたちも普通の子どもではない。問題は、サウロンが我々よりずっと進化した人間だということだよ。おまえたちが装置を使っても、あいつに勝てる見込みがないうえに、あいつのことは殺せないときている」
「装置を使うのは、そんなに難しいんですか?」と利菜は言った。
「そんなことはないさ。想像の現実化なら、もう体験ずみだろう。使いこなす必要があるのは、おまえたちの精神の方だ。もうひとつ問題があるよ。おまえたちは、ただ使うだけでなくサウロンと戦わねばならないってことさ。そこまで使いこなせるかね?」
みんなは顔を見合わせた。装置をもって念じれば、サウロンを簡単に倒せるような、単純な考えしか持っていなかった。
エビエラは話を続けた。「装置を手にしていたときのサウロンは、そりゃあものすごかった。もともとスケールのでかい人間なんだろうが、考えることもでかかった。おまけに不可思議な力をもともと持っている。皇帝ほどではないにしろだよ。装置をもつってことは、サウロンの力に発想で勝負するようなもんさ」
「装置を、マーサおばあさんに渡そうと思うんです」と利菜。
「どうだろうね。あいつは精神力があっても、頭が固い」
彼らは外に出た。エビエラはまさに命じて薬草をとりにいかせた。エビエラが装置を持ち出すと、利菜はその小ささにまずおどろいた。それに箱ではない。キューブだ、と寛太がつぶやく。エビエラが顔を上げた。
「小箱だって聞いてたから」
利菜が答えると、エビエラはうなずく。
「三百年の間で誤伝したんだろう。実際には金属の塊だ。中がどうなっているのかは皆目わからんがね」
黒かった。つやがない。素材もわからなかった。不可思議な金属音がする。伝承では小箱になっていたが、実際には、寛太の言葉どおり四面体のキューブだった。砕くことも溶かすこともできない、堅固な金属だ。表面には不思議な幾何学模様が彫り込まれている。
エビエラが利菜に装置をわたす。彼女は二本の指で、くるくると回した。軽かった。なんだか……魅惑的で、強力に人を惹きつけるものがある。利菜は自分の内面を引きずり出されるようで、少し怖かった。装置は熱を持っていた。まるで生き物のような、魂を感じる。指の先で、脈打っていた。それに利菜が手にした瞬間に、文様がかわった。
「おまえの想像に、装置が反応しているのさ。機械――といっていいのかわからんがね。おまえの生命に感応しているといってもいいね。人が手にしたときに、その装置はたしかに生きているんだろう。他の者も持ってみな」
みんなは順繰りにもった。持ち主ごとに模様が変わった。音も持つ者によってちがう。感情にも反応するみたいだ。
エビエラは、装置の重さを変える実験をやらせた。重いと念じると、重くなり、軽いと念じたときには宙に浮いた。新治が重いと念じたときには、本当に持っていられなくなり、装置は地面にめりこんでしまった。取り出すのにも苦労して、結局はエビエラがやったのだった。
「ごらんのとおりさ。想像にも、得意不得意があるだろう。あざやかに念じられることもあれば、そうでないことがある。当人ごとで特性というか、性格が違うためだろう」
エビエラが目を閉じて念じると、地面に雑草が生い茂り、たちまち大木にまで成長した。エビエラの庭は小さな森にかわった。子どもたちを畑につれていき、野菜や花を育てる訓練をやらせた。利菜は装置に念じて、植物を次々に成長させた。寛太は、自宅で農業をやっているだけあり、野菜を育てるのがうまかった。花をうまく成長させたのは紗英だった。だが、エビエラのように、何もないところから生み出すのは難しかった。
子どもたちが興奮すると、すぐさまエビエラの叱声がとんだ。彼女は、精神のバランスを失うことを極力きらった。
「使い道は食物を成長させるだけじゃないよ。ようは発想しだいだ。たとえば他人に幻覚をみせたり、意のままに操ったりすることも可能だ」
装置をもったエビエラが指を向けると、新治の腕が軽々とあがった。エビエラが指をまわすと、新治はくるくると回った。子どもたちはわっと騒いだ。手品のように感じたのだ。だが、新治がえんえん踊らされるに当たって、彼らの笑いはひっこんだ。新治の表情は苦悶そのものとなり、それでも踊りは止まらない。
「師匠、もうやめてください」
まさが言った。
エビエラはすわりこんだ新治に、「どんな感じがした?」と訊いた。
「ぼく、抵抗できなくて……」
「抵抗ならできたさ。強い意志の力さえあれば、とめることはできたはずだ。おまえたち、今までそうしてきたろう。わるいものやおさそいに抵抗してきたはずだ」
利菜はしばらく考えた。やがてうなずいた。
「困ったことにね、トレイスは――じっさいにはサウロンだが。装置がなくたって、このぐらいのことはできるんだよ」
新治が半べそをかきながらいった。「今のはとめられませんでした」
「ようは集中力の問題だろう。命の危険にさらされれば、誰だってくそ力は出るだろう? 友人も側にいたしね」エビエラは、かすかに笑ったようだ。「さて、今回はおまえたちの手元に装置がある。といっても、現実の世界で、うまく手に入れられればの話だが……おまえたちは、心をつないで精神を強めることもできるようだしね。あたしの時よりも条件はいいかもしれない」
「知っててやったわけじゃないですよ」
「それでいいよ。理屈の問題じゃないからね。この場合、大切なのはできるかできないかでしかない。これまではそれで生死をわけてきたんだろう?」
六人は神妙な顔でうなずいた。
「さて……」
エビエラは子どもたちから少し離れた地面に棒をたてる。それから装置をほうってよこした。利菜は胸元で受けた。
「そいつを使って、この棒に火をつけてみな」
「師匠、いきなりそんな……」
とまさが言った。利菜もとまどうが、自分の力を信頼してもいた。向こうの世界でいろいろあった後だからだ。果たして、エビエラも、
「その子はもうすでにおまえの修行を受けている。念じるんだよ。その念が装置を通るように、イメージを使ってでも何でもいい。視覚のみならず、五感をすべて使ってやれ。呼息を装置に向けてもいい。自分のやりやすい方法でかまわん。さあやれ!」
突然の大声に、利菜はあわてて装置を顔の高さにもちあげる。地面にささっているのはなんの変哲もない枝である。利菜は気を取り直すと、ゆったりとした呼吸を繰り返しながら、目をなかばとじ、うっすらとした視界の中で枝をみつめる。あの棒を燃やす、燃やすんだ……とひたすら念じた。利菜は額に汗をかきはじめた。鼻の奥で、鼻毛が焦げるような臭いがした。体温が危険なぐらいに上がると枝の先からチリチリと煙が立ち始めた。利菜はそのことを見るというよりも感じて、少し笑みをもらす。達郎たちが騒ぎ出すと、エビエラが何かをいって、腕を向けた。
枝は突如として帝国時代のサウロンに変わった。死に物狂いの形相でわめいている。佳代子たちの悲鳴が聞こえた。
利菜が目を開くのと、サウロンがおそろしい速さで大地を駆けてくるのは同時だった。利菜は悲鳴を上げて尻餅をつきながら、夢中で装置を振った。頭の中には炎のことしかない。炎と、恐怖の熱情。燃えろ! あいつを燃やせ!!
利菜は腕が抜けるような、装置ごとサウロンに向かって引っ張られるような感覚を覚えた。同時に周囲の空気が、サウロンに向かって吸い込まれた。一気に真空になったかと思うと、サウロンを中心に炎が爆発的に噴き上がる。サウロンを一瞬に飲みこんだ。
「やった、やったぞ」
達郎の快哉は、すぐに消えてしまった。利菜の腕に異変が起こっていたからだ。利菜は、かすかな痛みを感じて手をみおろす。装置を持った手が、なくなっていた。真っ黒だ。利菜はうそだと思って、目を近づける。黒い影の隙間から(黒いのは焦げた肉で、利菜が動くたびに、パリパリと裂け出す)、赤い肉が見えた。血が滴った。腕が消し炭に変わったと認識した瞬間に、腕を磨り潰されるほどの痛みが脳髄を貫く。
「うわ、うわあ!」
と利菜は言った。彼女は腕を抱えようとするが、さわることも出来ず、また曲がらない。装置が落ちると、一味はますますひどくなる。滴る血液に、溶けた皮膚がまざっている。消し炭になった部分がベロリとはがれた。出血がますますひどくなる。達郎たちが駆け寄ったが、利菜は地面をのたうち回っていて、とりつくしまもない。
エビエラが近づいてくる。装置を拾いあげると、左手を利菜の上にかざし、もごもごと呪文を唱えはじめた。利菜は激しい憎しみを覚えたが、右手がぽっと温かくなると、痛みが和らぎはじめた。彼女は泣くのをやめて手を見おろす。みるみるうちに傷がふさがっていく。出血が止まり、細胞がぷつぷつと音をたてて生まれてくる。痛みが完全に消えると、皮膚の再生がはじまった。すごい、と彼女は言った。
「見ての通りだよ」とエビエラが言った。「こいつがどんなに危険かわかったろう。自分自身の想像ですら、制御しきれるものではない。たとえばおまえたちが、おまえたちのいうところのわるいものを呼び出したとしよう」利菜を見下ろし、「やったことがあるようだが、それを制御できたかね? そいつを支配下におけたりできるもんだろうか?」
利菜は首をふった。まだショックが消えていなかった。利菜は腕を曲げたり伸ばしたりする。紗英と佳代子は、エビエラに非難の目を向けている。まさが利菜の手をさすりだすと、そのときには産毛すら元通りになっていた。
「念じるのはいいが、我を忘れてはいけないね。この装置は何をしでかすかわからない、暴れ馬のようなものなんだ。強く念じることはさっきのように炎そのものになりきることでもあるんだが、それをコントロールするには、自分を保つ必要があるんだよ。つまり、主観と客観を両立させること、それをともに高めることだ。そのためには、姿勢と呼吸を整えること、その上で、熱い心と冷静な心を両立させるんだ。こいつは念を現実にしちまうんだから。持っている間は下手なことは考えちゃいけない」
利菜は神妙にうなずいた。装置の恐ろしさが身に染みてわかった。
「どうもおまえたちは集中力にむらがある。まあ、まともな修行を積んだわけではないから、無理もないが」
「でも、師匠もいったじゃないですか。いざというときに出来るのが一番いいって」
まさがかばうように言う。
「普段できても、本番で使えなきゃどうにもならんさ。だからって、なりゆきに任せるわけにはいかんだろう。さあ、昼食をとったら、午後からは再び練習だ。個々の練習がすんだら、おまえたちの心を一つにして、念力をまとめる練習をはじめるよ」
エビエラの修行はえんえんつづいた。マーサのときとおなじだ。薬湯を飲み、疲労を回復させながらの厳しいものだった。利菜もヒッピたちを救おうと必死だ。
エビエラは念を強くするよりも、正確さにこだわった。精神の均衡を保つことを、口を酸っぱくして子どもたちに教えた。
「あせるな、怒るな、威張るな、くさるな、めげるな、負けるな、あきらめるな。わかったか」
子どもたちはまさの家事仕事もよく手伝った。まさはよく笑った。エビエラの修行は厳しさをまし、そして、三日がたった。
□ 十三
エビエラは修行の最後に子どもたちを大鏡まで連れて行った。彼女は巨大な台座をあがり、大鏡の前に立った。野ざらしになっているだけあって、その鏡面はくすみ、エビエラの姿もおぼろである。
「おまえたちは何度もゲートを開いたことがあるようだが、やみくもや偶然では困るよ。知ってのとおり、ゲートは力の集まる場所にしか出現しない。次元のひずみを利用するんだから。そうして空いた入り口を、どこにつなげるかだ」
利菜は手を上げて、「向こうの世界で待っている人がいないと、戻れないんでしょ」
「それは少しまちがってるね。待っている者が必要というよりも、出口そのものをみつけることが困難なんだ。世界は無数にあるんだからね」
「じゃあ、あたしたち、ヒッピたちのところには戻れないんじゃ」佳代子が訊いた。
「それは大丈夫だよ」
と利菜。ヒッピの存在こそ感じないが、ゲートを開けば話は別だ。ヒッピはきっとあの回廊にいるはずだから。あそこから逃げられたとも思えなかった。
エビエラはうなずいて、「あたしもそう思うよ。ともあれ、ゲートを開く、という感覚そのものを体で覚えるんだ。後のことはおまえたち次第という他ない」
達郎が頭を下げた。「エビエラさん、何から何までありがとう。おれたち……」
「あたしのことは師匠と呼びな」とエビエラが遮った。「稽古をつけたのは、何もおまえたちのためだけじゃない。結局、サウロンが再び世に姿を現したのは、あたしの不手際という他ないんだからね」と言った。「いいかい、装置は利菜かヒッピ、どちらかに持たせるんだ。できれば利菜がいい。装置の扱いを知ってる。マーサでもだめだ」
「なんで利菜なんです?」と達郎。
「わけは言えない、サウロンは心をさぐれるからね。おまえたちの誰かから作戦がもれる怖れがある」
いよいよお別れだった。これから現実の世界に戻らねばならない。
まさがみんなを呼び寄せる。彼女は腕を広げると、子どもたちみんなを抱いた。
「あんたたちが立派にやってることを、あたしは誇りに思ってるよ。あたしはあんたたちが大好きだから。一人も欠けないことを祈ってる。無理はしちゃいけないよ。怖かったら逃げたっていい。死んだらもう会えないんだから。今生が大事なんだから」
「さあ、湿っぽいのはここまでだよ」とエビエラが言った。「サウロンの野郎はどこにいるかしれたもんじゃない、世界の崩壊だって進んでるんだからね」とおどしてから、「自分は大したもんなんだって胸を張っていって来い。生き死にをかけてる奴に、文句をいっていい奴なんていやしないよ。威張ったっていい。心を張れなきゃ、サウロンには立ち向かえないんだからね」
師匠は、ふだんから威張ってるくせに、と、まさは子どもたちだけに聞こえる声でささやいた。
エビエラは子どもたちと手をつなぎ合う。大鏡を囲うようにして半円を描いて立った。
「おまえたちは、力の高め方を覚えている。今回は、ゲートのコントロールを覚えるんだ。次元のひずみというのは力の集積点だ。そこを見つけるんだよ。見つけ方は、人それぞれ。臭いで感じる者もいれば、目に見える者もいる。五感を高めて頼ること。教えた呼吸法や姿勢を守って、天地の力を集めるつもりで」
呼吸とともに、意識が深まていく。手足が温かくなる、前頭部が冷たくなった。体の芯をやわらかいものが立ち上っていく。雑念が消えて、まわりと溶け合うような心地がしはじめた……
「さあ、次元のひずみを生み出すよ。念を一点に集中しろ」
利菜は閉じた目の中に、ひずみを見た。子どもたちは脂汗をかきながら、その一点を押し広げようとする。
エビエラの声が聞こえる。
「いいよ。ひずみをとらえた。さあ、力を放て!」
一同は、体の中にたまった力を、ひずみに向かって押し出した。大鏡の周囲には、風が幾重にも吹き荒れた。鏡に黒点が浮き上がり、渦を巻きだす。さすがに装置を使っているだけあって、今度ばかりは簡単だった。
「これが入り口だ。問題は、出口だね。行くべき世界、場所を正確に思い描くんだ」
「どうやって?」寛太が訊いた。
「念じろ、と言う他ないね。その場所を五感で感じるんだ。ただし、行く先は、ここと同じような、パワースポットでないといけない。そうした場所にしか、次元の裂け目は生まれないからね。今回は、両神山の鏡を念じろ」
彼らは手をつなぎあい、銅の鏡をイメージする。利菜は興奮に胸を高鳴らす。ヒッピたちにこういってやりたい気分だ。あたしは装置を見つけた、今すぐそっちに戻るから、と。
達郎が、渦に手を伸ばした瞬間、利菜はふりむいた。エビエラとまさに顔を向けた。利菜には後悔していることがあった。マーサは三百年三郎を待った。それは自分があのとき、三郎が必ず来るからと、真実を知っていながら嘘をいったからではないかろうかと。自分がまさの落胆を大きくしてしまったから、マーサは記憶を失っても、独りぼっちで森にいたのではないだろうかと。
辺りは次元のひずみの影響を受けて、すっかり歪んでいる。そのせいか、まさの顔が、泣き顔に見える。利菜はためらいつつも大声で言った。
「まささん、あたし、嘘ついてごめんね!」
「いいのよ、あたしだって、三郎のことはわかってた!」まさは風の音に負けないよう、声を張り上げる。「でも、いまは師匠がいるし、仲間もいる。それに三郎のことを、愛してる。それだけで十分だよ!」
利菜はうなずいた。達郎がゲートに腕をいれる。体が伸びていく感覚、非物質化する感覚がまたおこった。利菜の体がこの世界から消える瞬間も、まさは何事か呟いていた。そのときには、利菜の体は薄まりすぎて、まさの言葉は聞き取れなかったのだが、彼女にはまさがこういっているような気がした。
いつかまた会える気がする
○ 一九九五年 ――両神山にて
□ 十四
記憶の世界からいきなりおまもりさまのお堂に戻る、というのはいささか虫が良すぎたかも知れない。利菜はゲートに飛び込んだ瞬間に、わるいものの存在を感じたからだ。この世界に戻ってからは、あいつらは四六時中彼女に張りついているし、彼女を殺す算段を四六時中練っている。おまけに今回は声が聞こえた。いつもはF1マシンに乗り込んだときのような、うなるような風きり音がするだけだ。けれどこの声は――聞き覚えがある。それはその夏、母親が何度も唱えていた言葉だったから。
南無南無南無南無、法蓮華経。
利菜は坪井の信者たちがあの家になぜいなかったかに気がついた。彼らは自分たちの目論見を聞いていて、先におまもりさまに出かけたにちがいない。あそこにいた連中はわるいものそのものだったから。利菜はゲートの中で、みんなに手を離さないよう呼びかけた、心に念じた。だけど、こいつはただの声じゃない。ここでは声が物質化して(マンガの擬音語みたいに巨大な3Dと化して)、列車みたいに突撃してきたからだ。利菜たちは悲鳴を上げて、互いの指をからませあう。物質としての体は薄まっていたから、精神の力で結びつき合った。
やがて体が縮んで、利菜は再び生身を取り戻す。細胞が結集して、筋肉や骨格を再生する。利菜はゲートから放り出されるようにして地面に転がる(ゲートからはまだ声が聞こえた。「南無南無南無南無……」それはゲートの閉じる、ピシャリ、という音とともに、この世界からも閉めだされた。利菜の耳はまだワンワンなっていたが、世界は静寂を取り戻したのだった)。肺が空気を吸いこんだ。細胞たちが突然の目覚めに歓喜を上げた。再び感覚を取り戻してみると、疲労や痛みはいっぺんに戻ってきた。利菜はその苦しみに、堅く目を閉じた。悪夢に悶絶するかのように左右に身をくねらせる。
「利菜、利菜」
佳代子が、彼女の頭を抱える、頬を叩いた。利菜はうめきをこらえて、まぶたを押し上げる。まぶしかった。自分で思う以上に疲れていたようだ。慣れが麻痺させていたけれど、やっぱりあの装置を使うのは利菜の五体には相当の負担らしい。
佳代子の心配げな視線と目があう。隣にいるのは紗英だった。「大変だぞ……」と三人の真上で達郎が言った。
顔を上げた三人は、視界をおまもりさまが埋めるのを感じた。一同は前回の恐怖を思って呻きを上げた。巨大な杉木立に、苔むした岩の群れ。散らばる死体。霧がそうした死者を埋めている。彼らの苦悶を封じ込めるかのように。さらなる闇におしやるかのように。
戻ってきた、と利菜は涙をこぼして言った。ああ、あたしたちはおまもりさまに戻ってきた……。
「お堂がないぞ」
寛太があちこちを歩き回っている。そして、彼の背後の霧の陰には、血まみれの男たちが見え隠れしている。死体が動いているのかと思ったが、そいつらは坪井の家にいた連中だった。
そこにいたのは信者でない連中もいた。神保町の普通のおじさんおばさんも混ざっていた。その中には知人もいて、女の子たちはまったく同時に(鏡が三つ並んだみたいだ)、口元に手をやった。エビエラとまさの修行は無駄でなかったらしい。利菜は信者たちが今何を考えこれまで何をしてきたかが一瞬にしてわかってしまった。彼らはおまもりさまの影響をまともにうけて憎みあい殺し合っていた。その証拠に今だに鍬や刀を持っている(きっと森の死体から奪ったのだ)、新参者の子どもたちを、仕留めるつもりだ。
達郎がそのことを感じ取って、「みんな集まれ!」と号令する。彼らは飴玉にアリが群れるようにして達郎の元に集まる。新治がひやああ、と情けない声を上げて泣き始める。達郎が、
「こいつらが邪魔したんだ。おれたち、お堂に出られなかった!」
大人たちは、恐ろしい雄叫びを上げながら、子どもたちを囲みはじめた。血で顔を塗り上げた姿は、もはや何人でもなくなり、未開人のようだった。言葉をなくし、記憶をなくし、本能のままに動いている。この夏に何度も見かけたわるいものそのものだ。利菜たちは、身を寄せ合えばこの世から消えてしまえるかのように、互いの体を抱き合う。
「ここって、おまもりさまのどのへんなの?」紗英が震え声で言う。「両神山でないんなら、装置をとりにいけない」
生き残った大人たちは三十人ばかりいる。じりじりと身を寄せてくる。でも、死人も混じっているみたいだ。利菜がよく見ると、その中にはちゃんとなめ太郎や溺死女がいた。でも、みんなで手をつなぎあって追い払ったところでどうにもならないだろう。大人たちは幻覚ではないからだ。わるいものは、ここにきてこの連中を確実に仕留める方策を見つけたらしい。利菜は寛太と紗英の肩を抱きながら、顔をあおのける。
「三郎!!」
声は、霧を飛ばして広がった。巨大な木立を揺るがすように、太古にして未来の空気に広がる。返事はない。それでも三郎と連呼する。
「利菜?」佳代子がけげんな顔をする。
「三郎が装置を守ってるのよ」
利菜は今こそ、エビエラとまさが、装置を三郎の墓に埋めたわけを理解した。彼らは、三郎の亡骸を聖櫃の守り人としたのだ。彼女は立ち上がると、森に向かって呼びかける。
「三郎さん、お願い! 装置を守ってるんなら、その場所まで通してよ! まささんを助けるのに、必要なのよ!」
佳代子が立ち上がった。寛太も。紗英も。新治も。達郎も。突然の風が、子どもたちを襲った。竜巻が落ち葉を舞い上げ、紗英と寛太が転んだ。利菜は佳代子と、新治は達郎と手をとりあい、風に抗して立ち向かう。彼らは感じていたのだ、殺意ではない、傍観者の視線を。
大人たちは風に負けて前に進めなくなった。
三郎がいる……、と利菜はつぶやく。三郎が見ている。姿は見せないが、近くにいる。
利菜は手を広げ、「疑うんなら、心を覗いたっていい!」と言った。「まささんが危ないのわかるでしょ! ずっとあなたのこと待ってるのよ!」
信者たちは、ますます怒りの声を強くする。一人が槍を投げてきた。それは利菜の胸元をめがけて一直線に飛んできたのだが、猛烈な風に方向をかえ、あらぬところに突き刺さる。男たちは、まるでシンクロのチームのようにいっせいに首をかしげた(こんな状況でなければ、じつに滑稽な仕草だ)。
「利菜……」
佳代子が、彼女の袖をひいた。利菜の視線は佳代子の視線の先を追う。
「三郎だ……」
霧の中に三郎が立っていた。それは不思議な光景だった。三郎は侍の手によってズタズタに斬り裂かれたはずなのに、今は神主のような服装をしている。おまもりさまには一番そぐわない格好だろう。そして、青白く透き通っていた。三郎の背後にいる信者は、まるで水面に映るかのように歪んで見える。
利菜たちは幽霊なんて信じていなかった。三郎の姿を見た後も、彼が霊体だとは思えなかった。ただ、来てくれたことにどっと安堵したのだった。
利菜がまさの分も含めて三郎のもとに駆け寄ると、佳代子たちが慌てて後を追う。大人たちも後を追ってくる。利菜は夢中で彼を捕まえようと、三郎の胸に飛び込んだ。
――ところが、彼女は三郎の体をすり抜けてしまい、頭から地面に突っ込みかけた。慌てて足をだし、たたらを踏みながらふりむいた。佳代子たちが三郎の背を抜けてこちらに来る。
利菜は景色のかわりように驚いた。おまもりさまが消えていたのだ。辺りにあるのは手入れもされず、貧相にやせ細った杉林だ。それに空が急に開けて、青空が覗いている。周囲も明るくなっていた。
利菜のかたわらには巨大な楠木がある。背後をみる。お堂があった。数日前に逃げこみ、見知らぬ世界に連れ込まれることとなった小さな社だ。だけど、その社は年月の重みをまともに受けてきたのか、すっかり朽ち果てている。
楠木の根元には、小さな墓が落ちていた。
三郎は、墓石の側にひっそりと佇んでいる。
「あなたが連れてきてくれたの?」
信者たちは一人もいない。ここに来られたのは六人だけで、おまもりさまに閉じこめられた彼らの末路を思うと、戦慄に震えたのだった。
彼女たちは無言で墓石を見下ろした。記憶の通りだとしたら(そして、サウロン自身がこの世界に手を出していないのだとしたら)、この下には三郎の遺体と装置があるはずだった。彼女たちはしばらく躊躇うように黙り合った。大人たちを出し抜いて装置を手に入れたのはうれしい。でもそのためには、墓を暴くことになる。
「だけど、掘らなきゃ」利菜がみんな勇気付けるようにいった。「三郎さん、この石どけていい? 装置をとらなきゃいけないから」
三郎はうなずく代わりに身を引いた。利菜は申し訳なくて涙が出た。佳代子が彼女の決意を励ますみたいに肩を抱く。子どもたちが墓石をどけると、その下からは、ムカデや虫が這い出してきた。女の子たちは悲鳴を上げた。寛太は思わず、「ご、ごめんよ」と三郎に言った。三郎はかたわらで寛太を見下ろしていたが、何も言わなかった。
しゃべれないんだろうか?
ただその目に、怒りはない。子どもたちが感じたのは深い信頼だった。この人は三百年間ずっと、この場所を離れなかったけど、なにが起きているかは知っているのかもしれない。
寛太が虫をおっぱらう。利菜は彼を押しのけるようにして地面に指をつきたてた。ぬめりとした泥の感触が爪の隙間に入りこむ。死体の腐った肉をつかんでいる気がして、吐き気をこらえる。
「ほ、掘ろう」と達郎がみんなを励ました。
子どもたちは夢中で掘った。地面は三百年の間にすっかり硬くなっていた。細かい石交じりの土が、子どもたちのやわらかな皮膚を傷つける。寛太の家で土いじりにはなれていたが、まさかこんな山奥で墓堀をするとは思わなかった。
五十センチと掘らないうちに、白い骨が見えた。達郎は慎重に土をどけていった。わけもなく、指が震えた。きっと死者に対する畏怖の念が、震えとなって出ているのだ(死者本人が傍らにいるのだからなおさらだ)。その骨はどうやらアバラの辺りらしいとわかった。利菜は記憶をたぐって、もう少し下だよ、と言った。まさは、死体の手を組ませ、その手に装置を持たせたからだ。さらに土を掘った。三郎の骨はあちこち砕けている。六人は彼がなぶり殺しにされたことを思い出す。みんなは、ごめんなさい、ごめんなさい、とあやまりながら、土を掘りすすんだ。涙がにじんだ。
やがて、指の骨が見えた。装置を取り出すには、三郎の腕をどける必要があった。利菜たちは、二手に分かれて手首の部分まで掘り進む。大人の大きな手だった。六人は厳粛な気持ちで三郎を見上げた。
うなずいたようにみえた。
寛太が慎重に指を持ち上げると、人差し指が手根骨から抜けてしまった。なにしてるのよ、と佳代子がなじった。寛太は、手首をつかむと、手のひら全体を思い切ってどかした。装置の上端部がみえた。
「ほんとにあった……」と利菜は言った。彼女は三郎を見上げる。「ほんとに持っていっていいの? ずっと守ってたのに……あたしたちうまく使えないかもしれない」
佳代子が手首をつかんだ。泥の感触に、ひやりとする。
「そんなこといってる場合じゃないよ。これがないとサウロンと戦えないし、ヒッピたちだって助けられない」
利菜はうなずいた。佳代子は心を鬼にしていっている。その気持ちをくんだのだ。
達郎が装置を持って、左右に揺らした。記憶の中でみたものとおんなじだ。指が触れると、金属音がして、文様がかわる。達郎が引き抜くと、ぎゅぽりという泥の縮まる音がして、かすかに水滴が滴った。
達郎は、装置が脈打つのを感じた。
「三郎さん、おれたち、これ借りるよ。でもちゃんと返すから。まささんが危ないの、ほんとなんだ」
「それに、世界中だよ」
紗英が言った。みんなは彼女をみた。紗英は世界中が危ないと言いたいのだ。みんなはその言葉を笑い飛ばしたかったが、できなかった。紗英に向かってうなずいたのだった。
「行こうよ。鏡を使えば、ヒッピたちのところに出られる」
佳代子が言った。利菜たちがお堂に向かい始めても、三郎は楠木の下に立っていた。利菜は離れるのをためらって友だちから遅れがちになった。
おまもりさまでは時間の流れが止まっていたが、この両神山ではちゃんと三百年がたっていて、お堂はすっかり朽ち果てていた。扉は崩れおち、屋根には鳥が巣をつくっている。その屋根も崩れ落ち、階段は苔むしていた。こうなると、銅の鏡が残っているのかも疑問だった。こんなところで、三郎は一人だったのだ。まさと同じように。
利菜はお堂に入る直前に、三郎に呼びかけた。
「まささん、三郎さんのこと愛してるって、それで十分だっていってた。あたしが助かったのも、三郎さんのおかげだよ」
三郎はうつむいている。
「あたしたち、必ず戻ってくる。まささんと約束したから」
三郎の顔が上がった。一人も欠けることなく、と彼は言ったようだった、そう感じたのだ。
楠木の下にたたずむ三郎が、かすかに笑ったようにみえた。利菜は少し安心をして、友だちのあとに続いた。
□ 十五
お堂の中は、天井の梁が落ち、床が腐って前に進むのも苦労した。さらに、鏡は、台座を転げ落ち、あおむけに転がっていた。寛太は苔まみれになった鏡を手に持った(鏡と呼ぶにはあまりに重い)。彼はシャツをつかって苔を拭った。苔は落ちたが、鏡面は水気に濡れていた。
利菜は装置を顔の高さまで持ち上げる。エビエラが持っていた物と同じだ。不安の音色を奏で、人を虜にしようとしている。
「おれたちだけで、装置を使うのか?」
寛太は不安そうだ。肝心の利菜がコントロールに失敗しているのだ。みんなは利菜の右手をみた。火傷のあとは欠片もないが、むき出しの筋肉から血が滴る様子は忘れようと思っても無理な話だ。利菜だってそうだ。みんなが痛みを共感したとはいえ、一等強く感じたのは本人である利菜なのである。恐怖がむずむずと胃袋を突き上げて、彼女は唾を飲み下す。その装置は恐怖の塊だったが、同時に魅惑的でもある。欲望をかなえるものだ。手に取り、思うままに使いたくなる。
「だめだよ、みんな」食いつきたげな顔つきに、ぴしゃりと言う。「あたしたち、ちゃんと師匠に教わった。これを使うには、自分を保たなきゃだめだって。もう、誰も助けてくれないんだよ。装置に飲みこまれたらおしまいになるんだから」
飲みこまれたがっているのは、奥深くにいる自分だ。そこにはきっと醜い物や悪い物が詰まってる。数々にわるいものの出会ってきた仲間たちは、そのことを否定できなかった。それに、自分自身の奥の奥には人類という規模の、でっかいわるいものが控えているのだ。
「そうだよ、しっかりしないと」佳代子は辛そうだ。「みんなを助けられるのは、あたしたちしかいないんだから」
「師匠に習ったことのおさらいをしよう」と利菜は言った。
「そんな場合じゃないだろう」
と達郎は言った。ヒッピたちは一刻も早い助けを必要としている。
「わかってるよ。でも、失敗できないのよ」
利菜は満身がひどく重たくなった。責任という名の深海にいるみたいだ。水圧が彼女をつかまえて重たくしている。利菜は息苦しさに咳き込む。唾を拭いながら、大人ならうまくやるんだろうな、と思う。あたしが母さんぐらいの大人だったら、もっとしっかりしてるし、心だってコントロールできるんだろうな、と。それから母親のことを思い出し、きつく目を閉じた。
母さんが、この森に来てたらどうしよう。
水圧はぐんぐんきつくなる。利菜は自分の思いに押しつぶされそうになる。佳代子がそんな肩に手を置いた。みんな心配そうに彼女をつないでいる。心をつないだ現在、個人の痛みは全員のものだった。達郎が言った。
「ヒッピたちを助けに行こう。あいつらは利菜を助けてくれたから、今度はおれたちが借りを返す番だ」
彼らは、鏡を床の材木にたてかけさせる。手をつないで深呼吸をおこなうと、子どもたちは、利菜の手のひらにのった装置に、それぞれの手を重ねていった。
「開け……」
と利菜はつぶやいた。みんなは装置に向かって念を集中させていく。鏡を中心にゲートが開くところを想像する。問題は出口だ――手の下で、装置がグラグラと揺らめくのを感じる。まるで、装置が地震そのものになったみたいだ。鏡が光を放ち、その奥から空間をのみこむように、ゲートがあらわれた。利菜はその先にヒッピを感じた。
生きてる……と彼女は言った。利菜の感激や目の終わりに浮いた涙を全員が感じている。その光景が見えたし、みんなの様子を体で感じた。マーサおばあさんも生きてる、と佳代子が言った。どうやら回廊にはいないみたいだが、ひどいピンチには変わりがない。そして、サウロンがすぐ近くにいることも。
「あたしたちには装置がある……」
利菜がいうと、五人がうなずく。
ゲートは六人の目の前でギザギザに口を開けている。利菜はゲートがその時々によって形を変えることに気がついた。それは渦ではなくてたんなる亀裂。それは彼らの恐怖と希望を写すみたいに七色が混じったり漆黒が混じったりした。概ねは真夏の雲のように真っ白だった。未来はどうなるかわからない、とそのゲートは告げているみたいだ。
あのとき生きて欲しいとヒッピは言った。今は彼女が同じ気持ちでいた。
「ヒッピ、待ってて……」と彼女は言った。みんなは覚悟を固めると、手を取り合い、開いたばかりのゲートに飛び込んだ。