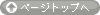�u�˂��܂����E�̖`���v�ւ悤����
���̃y�[�W�́A�l�b�g�ŏ�����ǂ܂����p�ɗp�ӂ��܂����B
���ҁA�Z�҂Ƃ��낦�Ă��܂��B�Â���i������̂ŁA�ł��ɂ͖ڂ��Ԃ��Ă���Ă��������B
�˂��܂��O������A��낵���I
�˂��܂����E�̖`��
����ܕ��@�ٕ�
���@�͑O�@����ܔN�@�����\����@�\�\�[��
���@�@�@�@��
�@���_�R����x�@�ɂ���ǂ��ꂽ�Ƃ��A����q�͊����̉Ƃɔ��܂�Ƃ����Ă����Ȃ������B�щp�̕�e�����Ă������A����q�͎щp�Ƃ��������������A�o���̐e�������͂Ȃ����Ƃ��Ă��A����悤�Ƃ��Ȃ������B
�@�[���̓c���́A�Ԃ����ߔ�����Ă����B��l�̔w��ɂ͊����̉ƁB�����ɂ̓p�g�J�[����܂��Ă���B�[�����Ƃ肩�����e�ƂȂ�A��t���x�̕����݂͂��Ȃ��B���̂������A�q�ǂ������ɂ́A�Ȃ�̗͂��Ȃ������̎Ԃɂ݂����B
�@�x�������͎Ԃ���~��Ă������A���̑����ɂƂ܂ǂ��Ă����B�V���͋~�������Ƃ߂�悤�ɉƂ�������݂邪�A�����Y�͂��ǂ��Ă��Ȃ��B�o���q�������Ԃ����������Ƃ����Ƃ��A�B�Y�͑̂��Ă݂�Ȃ�������B�N���̎q�ǂ������𗼘r�ł������A�e���������Ƃ��Ăł��ǂ��͂炨���Ƃ����B�q�ǂ������͔������Ŏ肪�����Ȃ������B���Y�o���q�ɂ��ΐ�Îq�ɂ��A�q�ǂ��������Ȃ�����ȂɂЂ��������Ă���̂��킯��������Ȃ������B�x�������Ă���Ȃ����B�q�ǂ��Ȃ�A����ȂƂ��́A���e�Ƃ�������̂��ӂ������炾�B
�@�ł��A�B�Y�����́A�������������ꂽ����Ȃ����̂킯���A�����Ɨ������Ă����B�o���o���ɂȂ�����݂�ȎE�����B���̕��e��A���������Ȃ����o���q�̂��Ƃ��A�m���Ă������炾�B���ǁA�Z�l�̐e�A���́A�x�@�̐��������Ă�Ė߂��Ă������B����q�͕�e�����������̂������ڂ����ڂ��Ă���B��邢���̂Ɏx�z����Ȃ������āA�߂�����A�E���ꂩ�˂Ȃ��ڂ��������B
�@�݂�Ȃ͂Ƃ��ɂ��邱�Ƃ������ꂽ���A����ł��ׂĂ��I������킯�ł͂Ȃ������B���Ԃ͎R�ɍs���O��肸���ƈ������Ă������A�ܐl�̒N�������̂��ƂɋC�����Ă����B
�@�����A���Ȃ��B
�@���̖�̈����͂����Ƃ��Ђǂ������B�B�Y�͖���ʖ���������Ă����B�щp�ɂ̂��������A����i�߂�ꂽ�B����q�ƐV���������Ă���Ȃ�������A�ق�ƂɎ���ł�����������Ȃ��B�悤�₭�����������܂����Ƃ��ɂ́A���������Ȃ��Ȃ��Ă����B�ނ̕z�c�͂��ʂ��̂��炾�B�l�l�͊�����T�����B�[���œD�܂݂�̑卪�ɂނ���Ԃ���Ă����B���ׂȂ���A���ׂȂ���A�Ƃ��킲�Ƃ̂悤�ɂԂ₢�Ă����B�卪������������������Ƃ��A�����͂Ԃ�Ԃ�Ɛk�����B
�@���o�A�����̃I���p���[�h�Ő������S�n�����Ȃ��B�q�ǂ��������܂����Ă��������A���E�́A�����ʂ��邱�ƂŊ��S�ɉ�ꂽ�悤�������B
�@����q�͗��ɂ�������߂̈ӎ��̂��܂�A�H�����̂ǂ�ʂ�Ȃ������B���̂Ȃ��ł́A���܂������˂悩�����̂ɁA���܂��玀�炢���̂ɁA�ƒN������ꂽ�����Ō�肩���A�C�����������������B����q�͗��͎���łȂ��A���������ɂ���A�Ƃ������������B�Ƃ��ɂ͌��ɏo���Ă������������B�щp���S�z���Č����䂷�����B
�@�l�l�͉���q���������Ȑ^�������Ȃ��悤�ɁA������������点��悤�ɂȂ����B���_���������A���̂��Ƃ��݂�Ȃ̊W�����������Ă����B�����܂Œz�����M���́A���������Ȃ����Ƃŕ��������Ă����B
�u���_�R�ɂ��ǂ邵���Ȃ���c�c�v
�@�Ɖ���q�������͂��߂��̂́A����ڂ̖邾�����B����܂łǂ�Ȃɂ܂��Ă��A�x�@�ɖ₢���킹�����Ă��A���������Ƃ����A���͓����Ă��Ȃ������B���R���낤�Ɖ���q�͎v���B���������邱�Ƃ�����Ƃ���Ȃ�A����͂��̎q�����Ƃ����B�ޏ������͗��̍s�����m���Ă����B�����āA�؈���Đl�̉ƂŌ�������Ȃ����B
�@����q�͂��̌��̂��Ƃ��v���Đg�k��������B�������́A����������c�c�B
�u����Ȃ̂ނ��Ⴞ�v
�@�B�Y�������ƁA����q�͂������������B
�u�����O�������H�v
�@�����H�@�ƒB�Y�͂����������B
�u�����O�������H�@�V���[�g�������H�@���̔��^��A�ǂ����������H�v
�@�l�l�͓������Ȃ������B�щp�ł������B
�u����������Ȃ��Ƃ��Y��Ă�B���̂��Ƃ��ǂ�ǂ�����Ă������Ȃ̂�B���A���̎q�̂��Ɗo���Ă悤�ƁA�����Ȃ��Ǝv��������������ǁA���ɂ��������̂Ɂv
�@�݂�Ȃ͂Ƃ���ꂽ�悤�Ɏ��ɂނ�������q�̂��Ƃ��v���o���B����q�̓`���V�̗��ɗ��̂��Ƃ��v���o���邩���菑�����B���̎����ɂ��肵�߁A
�u�ł��A�����o���Ă��Ȃ���B���ɏ������݂̂Ă��A�҂�Ƃ��Ȃ�����B���̎q�A����ς肱�̐��E�ɂ��Ȃ��v����q�͎����̋������������B�u�����ɂ����Ȃ���c�c�B������A���̎q�̂��Ƃ��Y��Ă��B���̎q�Ƃ��J���ꂿ������B���͂������Ȃ��v
�u�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ����H�@����Ȃ��Ƃ킩��킯�c�c�v
�u�킩�����B�킽���킩��B���͂����ɂ��Ȃ����āv
�@����q�͏���w�������B����q�͋������B
�u�킩�����B���͂��܂��肳�܂̌������ɂ���B���̎q��T�������āA����Ȃ��Ȃ��ƁB����Ȃ���������Ȃ��āA�݂�Ȃ̐S���Ȃ��Ȃ��ƁB��������K�v������́A�킩��H�@�����������ɂ���̂Ɂc�c������Ă�̂ɁA�J���ꂩ�����Ă�B�����݂��Ă������v
�u�x�@���������Ă邶��Ȃ����v�ƒB�Y�͌������B
�u�x�@���Ȃɂ�I�@�Ȃɂ��Ă����̂�I�@���̂��Ə����Ă���Ȃ��A�������̂��Ƃ��v
�u�߂�́H�v�щp�͐u�����B�u���̎R�ɖ߂�́H�@����T���ɁH�v
�@�B�Y�����Ȃ������B���S�����悤�ɁB
�u���̂�����̂ɁH�v�щp�������ƁA�݂�Ȃ͓����Ȃ������B���܂��ĐO�����݂��߂��������B�u���܍s������A����ǂ����߂��Ă���Ȃ���I�@����ǂ��납�A�������炪������̒��ԓ�������邩������Ȃ���I�v
�u���ǂ�����������̂�I�v
�@����q���щp���Ђ��ς������Ƃ����B�����ƒB�Y������q��}�����B
�u��������I�v�B�Y���������B�u�݂�ȁA����̍l�����������A�������Ă悭������v�������ށB�u���������͂��ǂ��Ă��Ȃ��B�������B��邢���̂����������Ȃ��B����ł��ꂽ���A���܂��肳�܂ɂ��ǂ�̂��ނ肾�B����q�̂������Ƃ����������A�щp�̂������Ƃ���������B�����́c�c�v�B�Y�͎R�̕��p���w�������B���܂��肳�܂̕��p���c�c�B�u�����͂��ꂽ�������̂�҂��Ă�̂�������Ȃ��B���̂܂܂Ȃɂ����Ȃ��ł�����A�݂�Ȃ����܂����B���ꂽ���͂Ȃɂ������Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B�ł��A���܂��肳�܂ɂ͍s���Ȃ��B��������Ȃ��ł��Ȃɂ��N���Ȃ��B�s������A��ɎE�����B��������H�v�B�Y�ɂ͒��ق��Ԃ��Ă����B�u�݂�Ȃ������E���B������������@���l���Ȃ��ƁB���������Ȃ�������A���ꂽ���������~���Ȃ��v
�@�щp�͌������B�u�ł��邱�ƂȂ�ĉ����Ȃ���v
�u�����Ǝq�ǂ��̂܂܂ł�������Ȃ�A�D���ɂ����v
�@�B�Y�͈Âɑ�l�ɂȂ�Ƃ���������Ȃ��A����A�q�ǂ��̂܂܂Ȃ��ƁA�V�w�����}���Ȃ��܂܁A���̉Ăɕ����߂���ƁA���������Ă���B���������Ȃ����悤�ɁB
�@�V���͗܂��ʂ������B�ق��݂̂�Ȃ��B�����͖X�q��ڐ[�ɂ��Ԃ�Ȃ������B
�@�B�Y�͎q�ǂ��ł��邱�Ƃ����ǂ����������B�ܐl�����������̂͊ȒP���B���܂ł������܂��Ă���Ȃ�Ė����������B�������Ȃ��ƁA�������͖̂��ӂɂ��A�E�l�S�����������Ă��邩������Ȃ��̂��B
���@�@�@�@��
�@���̖���ǂ�����Ă̂肫�����̂��A�B�Y�͌�ɂȂ��Ă��v���o�����Ƃ��ł��Ȃ������B�͐�]�I���B����ǁA�����������邱�Ƃ��ł���Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ƃ����A�ϐM�I�Ȋ�]�������������ɂ������B���̎v���ɂ�������A�ǂ��ɂ����̖���̂肫�����̂��B
�@���������̖ʁX�́A����̕��j��b���������B�C�ɂȂ�̂͑{���̂��Ƃ��B
�@����q���e���r���������A�j���[�X�ł͂���Ă��Ȃ������B���̓���ԁA�e���r�ŗ��̖��O�����L�����Ȃ������B�B�Y�������j���[�X�Ō����̂́A���_�R�ō����̎��̂����������Ƃ������̂���ŁA���̂��Ƃɂ͂܂������ӂ�Ȃ��B
�@�B�Y���݂�Ȃ��\���Čx�@�ɓd�b�������B�Ή��ɂł��w�x�́A�S���ɂ����ƌ������҂�����Ă���ԁA�҂������̉��y�ɂ́A�Ȃ�ǂ��������������B���͒B�Y�ɂ�����߂�Ƃ����A�o�����ׂ��͂��܂������Ȃ�ƁA�Ɛ����������B�B�Y�͂��炭���炦�Ă������A������b���u�����ƂȂ�ǂ��v�����B
�@���y���Ƃ��ꂽ�B�{���̌x���̐��������B����҂����ꂽ����A�������Ă��������́A����Ȏq�ǂ��̑{���͂��Ă��Ȃ��A�Ƃ������̂������B�V�c�Ƃ����S���x���́A�{���̓͏o���o�Ă��Ȃ��ƌ������B
�@�B�Y�́A���҂��Ɩ₢�������ꂻ���ɂȂ������_�œd�b���������B
�@��b���u���A��R�ƌ������B
�u�����ւc�c�v
�@�ނ݂͂�Ȃ������B�݂�Ȃ��B�Y���݂��������B
�@��₠���ĉ���q���������B�ْ������ʎ����������B
�u�Ȃɂ��������́H�v
�u����q�̂������Ƃ��肾������B�x�@�͗��Ȃ�Ēm��Ȃ����āB����ȑ{�����ĂȂ����Ă����Ă�B��������̑{���������ĂȂ��v
�u����Ȃ̂���������v�щp���������B�u���̂��Ƃ�����́H�@����Ȃɗ��̂��Ƃ������Ă��̂ɁH�@�����������āA�������Ȃ��Ȃ������āA�x�@�ɂ����ƌ�������ˁH�v
�@�Ƃ܂ǂ����������킷�B
�u�킽�����l���Ă�Ƃ���Ȃ�c�c�v�Ɖ���q�͑����̂B�ċz�͐A�����̂����炦�Ă���B�u���̂��Ƃ�Y��Ă�͎̂�������������Ȃ��B�݂�Ȃ͂����Y��Ă邩������Ȃ������B�ŏ����炢�Ȃ����ƂɂȂ��Ă邩������Ȃ��v
�u�܂Ă�B���Ƃ�����A����Ȃӂ��ɂ��Ȃ��Ȃ�����́c�c�v
�@�B�Y�͂̂ǂ����炷�B
�u�����Ƒ吨���邩������Ȃ��v
�@�V���͐k�����B�݂�Ȃ̋��ɋ������Ă����̂́A�[����]�������B���ꂽ���ɂ͂ƂĂ��������Ɗ����͎v�������A�B�Y�̐S���������������B�щp�͌����������Ă�ȂȂ��B
�u����T����́H�v
�@�ޏ��͂Ԃ�Ԃ�k���Ă���B
�u�ǂ�����āH�@�������������ɂ����đς����Ȃ��̂Ɂc�c�H�v
�@����q���щp��������������B�щp�̗܂͔M���A���|�����������f���͗₽�������B�ޏ��͂����Ƃ݂�Ȃ����グ���B�d�ꂵ����C���A�ޏ��̔x�������Ԃ��B����q�͌��ő������Ȃ���A�������肵�Ȃ���ƕ@��������B�������炾�߂��B���͂����Ɗ댯�Ȃ���B����ɂ܂��������B���Ԃ͂����Ղ肠�邵�A��Ȃ�肺��܂��c�c�B
�@�ޏ��͂��������ɂ����������āA���ӂƕs���ɂ݂�����ŗF���������グ��B�ޏ��͌������B
�u������������@�A��������邩������Ȃ��B�݂�ȁA�o���ā\�\
���@��Z��Z�N�@�\�\�_�ے�
���@�@�@�@�O
�@�\�\����B���̂���Ɋ�������C��A���̎���̕��͋C�̂��Ƃ��B
�@�������������u�ԁA���͐_�ے��ɂ��ǂ�̂m�ɂ����B��l�͐V��������A���S�̓d�Ԃɏ�芷���Ă���B�i�F�͂������Ɨ���Ă���B�ߌ��������ƁA���̌i�F�����Ȃꂽ���̂ɂ����B���͎O�\���̂�����A���w�ܔN���̎q�ǂ��̖ڂɂ��ǂ�B�]�݂��̉���ł́A���̂���̋L�����������B�����������͂��܂����A����A�Ƃ����ɂ��܂��Ă����̂�������Ȃ��A�Ɣޏ��͍l����B���̋L���Ƃނ������̂����낵���A��ɂ����r�[���𐨂��悭���������B�щp������Ȕޏ������ڂɂ݂Ă������A�₪�Ă͂��Ȃ��悤�Ƀr�[�������������B
�@��l�̕����́A�����O�̃V���c�ɃX�g���b�`�W�[���Y�A���ɂ͂�������ȃX�j�[�J�[�Ƃ������ł����������B�q�ǂ��̂���́A�����������͂��܂�ƁA���ł�����Ăǂ�Ȃɉ���Ă������i�D������̂��˂������B��l���Ė��ӎ��ɂ���ȕ���������Ԃ̂��A���ɂ͂��������A���낵�����������B
�@�g�ѓd�b�̃p�l���ӎ��ɂȂ��߂�B�A���e�i�������قǂ����{�������Ȃ��B�{�^���𑀍삵�āA����q�̔ԍ�����т����B�R�[���{�^���������Ď��ɂ����Â��邪�A�g�т̃X�s�[�J�[�͒��ق��Ă���B
�u���H�v�щp���������B
�u�g�т��Ȃ���Ȃ��B�R�[���Z���^�[���o�Ȃ��v
�u�����H�v�щp�͎����̌g�т��Ƃ肾���B�������ȃp�l�������݂��݂܂Ō��킽���B�u�A���e�i�������ĂȂ��v
�@�щp�͂��炭�g�т𑀍삵�����A���ʂ͂��Ȃ��������B�������B
�@��l�̋����Ɍ��t�������B���̐������A�J�肩�����A�v�������A���ɂ��Ă������t�A���E�͂˂��܂����Ă���B
�@���̂Ƃ��A�O���Ґ��̓d�Ԃ��A�_�ۉw�ɒ�Ԃ����B�k���̔����S�g���ƊJ�����B��l�͌g�т���ɁA��R�Ɣ��̌�����������Ȃ��߂��B���������͐_�ے��ł���Ȃ��ꏊ�ɂ�����Ȃ����A�Ɨ��͂������B���܂��肳�܂ł̑̌����t���b�V���o�b�N���A��l�͖��ӎ��Ɏ���Ƃ肠�����B�\���͊ՎU�Ƃ��Ă���B�����̒��֎q�ɂ͗����t��������A���\�N�����u���ꂽ�z�[���ɂ݂����B���͂ǂ�Ȏ�������Ăł��A����q�ƘA�����Ƃ�ׂ��������ƍl����B���̎q�������w�ő҂��Ă��Ă��ꂽ��A�ǂ�Ȃɂ������̂ɁB
�@��l�͍��Ȃ���������ƍ���������B�щp���ނ�I����ו������낷�B���̂��������A���̓z�[������ڂ𗣂��Ȃ��B�d�Ԃ��炨�肽���Ȃ��A���̂܂܋A���Ă��܂����������B�ł��A���e�Ɖ���q�����̂��Ƃ�����B�݂�Ȃ��ق����āA�s���Ă��܂��Ȃ��c�c�B
�@�d�Ԃ��~���ƁA�₦�������������B��l�̂ق��͖��l�ŁA�����J���܂��Ă���B��͈�ʂ̉_�ł���B��ɂЂ낪���������J�ɂ�����A�Ђ܂�肪��������Ă���B�߂��Ă�����l�Ɍh�ӂ��͂���Ă���݂����ŁA�Ȃ��������������B
�@�ڂɂ݂���i�F�A���ɂӂ�镗�̊��G�A��C�̍�����܂��̂̂܂܂��B�����������ܔN���̂܂܂̂悤�Ɋ�����B���̂���̒��A���̂���̋C�z���܂��߂��Ă����B��C�̂�����������́A�E�C�Ȃ낤���H
�@���������͖߂��Ă����B�ӂ����ю�����ꂽ�悤�Ȋ��o�B�������Ė����Ɨ��͎v���B��\�ܔN�O�̊X�ɂ����悤�ȋC�����āA�|���Ȃ�B
�@�w�͌܌��J�ɕ����߂��Ă���B
�u���̓d�ԁA�N������ĂȂ���v
�@�щp���Â��ɂ������B�����ӂ�ނ����B�d�Ԃɂ͓�l�̂ق��ɏ�q���Ȃ������悤���B
�@��l�͓d�Ԃ��~��Ă����̂Ƃ���ŗ����������B
�u�ԏ��͂ǂ������́H�v�щp���������B
�@�d�Ԃ̔����܂�Ȃ����A�ԏ��̎p���Ȃ��B���͂Ԃ₢���B���̗�ԁA������������������ĂȂ������B
�@���̂Ƃ��A���l�̂͂��̃z�[������A�����������B
�@�����щp�̕I���Ƃ����B���̘r���Ђ��đ������B�щp�����ǂ낢���B
�u�ǂ�����̂�v
�u�B���̂�v
�@�擪�̎ԗ��ɋ삯���ƁA�^�]�m�̎p���Ȃ��B�^�]�Ȃ͂�����ۂ��B�ޏ��͜��R�ƂȂ�B
�u����ȁc�c�v
�@�\���ɐl���͂����Ă����B��l�͂Ƃ����ɐg���ӂ���ƁA�z�[�����瑫���̂��A���H�ɂ��肽�B�܌��J���܂Ƃ��ɂق������B���Ǝщp�̓R���N���[�g�̃z�[���Ɋ炾�����̂������āA�j�����̗l�q��������B�����h�~�̉��F���^�C�����傫���݂���B��\�l���肪���낼��Ƃ���Ă���B�N����܂��܂��B��������B�ނ�͎�Ɏ�ɖ_��V���x���������Ă���B�N�����������悤�Ȗڔz�肾�B
�u������������T���Ă�́H�v
�u�ق��ɂ��Ȃ���v
�@�Ɨ��͂�������B����ǁA��������������̂͒N���m��Ȃ��͂����B�щp�������₢���B
�u�Ȃ�ŗ���̂��킩�����̂�v
�u�܂����A�ꂳ�c�c�H�v
�@�щp�͂͂��ƂȂ�B�u�悵�Ȃ�v���̘r�Ɏ���������B�u���̕ꂳ��A����������Ēm��Ȃ������B�A�����Ƃ�Ȃ����Ă����Ă������v
�u�ł��c�c�v
�u����Ȃ��Ƃ��A�����Ȃ��Ɓv
�@���Ȃ������B
�@��l�͐g�������߂�ƁA�d�Ԃ̘e�ɂ܂��B�y������邭�B�ԗ��̐�ڂɂ���ƁA�����Ő��H�����ǂ�͂��߂�B���������Ђ��������Ă���B�����̉Ƃ́A�������炸���Ɛ��Ȃ̂��B
�@�w�ł́A�j�������ԗ��ߓn���Ă���B�d�Ԃɏ�肱�������悤���B
�@�Ȃ�ǂ߂��ڂ݂��Ƃ��A�z�[���̂͂��ɂ����j�������������B�u�������I�v
�@��l�͒E�e�̂��Ƃ��삯�����B�j���������H�ɔ�т����B�������ǂ�������B���܂�吨�ő��邩��A�[�ɂ���l�Ԃ͓y�������ē]���������Ă���B
�@���ꂾ�������Œǂ��Ă���̂ɁA�����������[���̂������R������Ȃ�ė��ɂ͎v���Ȃ��B���܂�����A�E�����ƐM�����B
�@��l�́A�J�̒����Ȃ蒷�������𑖂����B�����ʂ��A���X�X�ɂ͂���B�ՎU�Ƃ����ʂ肪�ڂɂ������B�q�ǂ��̂���Ȃ�ǂ��ʂ��������B�X�����X�������Ƃ͂����A��������l���Ȃ��B���������Ƃ߂�̂͌����Ƃ͎v���Ȃ��������B
�@�������炰�āA���X�X���ʂ���B�r��ɏo���B�����ɂ͒ʂ�Ԃ��Ȃ��B�j�����͈����������悤�ŁA���������������Ă���B��l�͉~�����̂͂�������A�쌴�ɂ��肽�B�앝�͂�����̂́A���ʂ͂�������ւ��āA�ʍ����̒������Ƃڂ�����������낿���Ɨ���Ă��邾���ł���B��l�͂��̐��˂Ƃ��Đ���킽��B���ɑ���������B�����ǂ�����Ă��܂����B
�@�Ί݂̋����ɂ͓[�g���͂��鋐��ȍ|�ǂ����������Ă���B���͗���Ă��Ȃ��B
�@��l�͍|�ǂɂ��ǂ���ƁA�͌��Ɏ�����Čċz�𐮂ƂƂ̂������B
�u���A����������Ȃ����v�Ǝю}�͌������B�u�q�ǂ��̂���݂����ɂ́A����Ȃ�����c�c�v
�u�����N�����Ă݂Ƃ߂Ȃ�c�c�v
�@���̓o�b�O����y�����C�g���Ƃ肾���B�|�ǂ��Ƃ炷�B�����͐^���Â����A���ɂ͂��ꂻ�����B�����͊����̉Ƃɂނ��Ă����B
�@���͋���Ȋ������ɏP��ꂽ�B�ȑO�ɂ�����Ȃ��Ƃ��������Ƃ�����悤�ȁA����ȋC�������̂��B
�u����ɓ������H�v
�@�щp�����育�݂���B
�u��ɂ͂�����Ȃ���B���̐l���ł������ꂽ�炷���ɂ݂���v
�u�Ȃ�ł������������������̂�v
�u�����Ȃ��ł�v
�@���͖ڂɂ��̂��킹�Ďщp��ق点��B���܂��ɐM�����Ȃ����A���̊X�ł̓����`��U�����p�����Ă���̂��B�E�l���B���R���킩��Ȃ��Ƃ͂����A���������̂����錋�ʂ͖ڂɂ݂��Ă����B
�@�щp���Q������B�u�ق��ɕ��@�͂Ȃ������ˁv
�u�����������Ɓv
�@�|�ǂ́A�n�ʂ���ꃁ�[�g�������ɂ���B���͑����̂��āA���̉��ɃX�j�[�J�[���Ђ��������B�щp�������グ�A����������B�ォ��A�щp�������ς肠����B
�@���͑������҂���҂��Ⴂ�킹�Ȃ���A�����Ƃ炵���B�|�ǂ͓S�L���A��C�͂�ǂ�ł���B�ڂɂ݂���قǂ̎��C����l���B���ꂪ�ア�������w�h�������܂�A�X�j�[�J�[�����点��B
�@���͂��̉��������A�c������ɂȂ�ǂ������C�������B��������������Ƃ�����낤���H
�u�ǂ��ɒʂ��Ă�Ǝv���H�v�щp���������B
�u�܂������s���Ƃ�����A�͓���ɏo��͂���v
�u����Ȃɂ��܂������Ǝv���H�v
�u�^���悯��Ώ�ɂł�����v
�u�����̉^�̈����͎��؍ς݂�v
�@�щp���f���̂Ă�ƁA���͂ɂ��Ə��Ĕ�������������B�u�d�Ԃ͖��l�����A�ςȂ̂ɒǂ��������邵�ˁv
�u�^�̈����������͂��߂���A���̈�N�̂��Ə���������������B�����������_�Ȉ�ɂ������Ă����āA����Ȃ������H�v
�u��҂Ƃ̃��}���X�������ꂿ�Ⴝ�܂�Ȃ����v
�@��l�͕��������Ȃ����Ȃ���A�����ǂ����ǂ�͂��߂�B
�u���̏L���A�C���������Ȃ��v
�u����ł����ɑ���������ˁv
�@�щp�͌������B�u�j�ɂ͐U���邵�A�d���͋x�E�����A���o�݂͂邵�A���͍r��邵�A�Q�s�������B���̈�N�܂Ƃ��ɃZ�b�N�X�����ĂȂ��̂�v
�u�������A�U�߂����Ă悩�����킠�v
�u����ȏ㈫�����Ƃ�����Ȃ炢���Ă�B���������A�����N�����āA�����ǂ��������v
�u���͂��܂ɂȂ��Ă���v
���@���́@�T�C�|�b�c�̍�
���@�@�@�@�l
�@�����ɂȂ�A�ꓯ�͈�������ڂ����܂����B�q�b�s�͊z�ɂ������ʂ̊����ʂ������B���������Ă����悤�����A����ł�����Ȃɖ������̂͂Ђ����Ԃ肾�B
�@�O�͂������X�Ƃ����Ă���A�J�[�e�������߂�������́A����Ƃ�����C�����̂т��ށB�q�b�s�͂��̃J�[�e���̌������ɒN������悤�ȋC�����Đk�����B�y�b�N���A�u���͂܂��ڂ��o�߂Ȃ��ȁv�Ƃ����āA�ނz���炳�܂������B
�u�����A�������ǂ��A�x�x�͂ł��Ă��B�o�������Ȃ�͂₭���ȁB�ǂ������܂ł͓���Ƃ��������ˁv
�@�}�[�T�͘V�k�Ȃ̂ɒ����猳�C�ł���B�O�l���̃����b�N�ɕK�v�ȕ��������߂���ł���B�ꓯ�͂��ꂩ��̗��H���v���ƁA���肵���B
�@�Ƃ�����A�}���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�O�l�̓}�[�T�ɒ��d�ɗ�������A�q�b�s�Ƃ̕ʂ�������B�y�b�N�͐e�F�̐g���������A�l���Ă݂�ƁA��O�ł͗���ɂȂ�Ƃ͂����Ȃ��M���̓�l�Ɨ������鎩���̂ق����댯��������Ȃ������B�}�[�T�̓q�b�s�ɁA���̐��_�Ɋ�����Ȃ��悤�A�C�s���Ă��炤�Ƃ����Ă����B�}�[�T�͂���܂ŁA�l�ɂǂ�Ȃɐ����悤�Ƃ���q���Ƃ낤�Ƃ��Ȃ���������A���̓�l�͋{�얂�p�t�̂��A�͂��߂Ă̒�q�ƂȂ�̂������B
�@���܂ł̓��̂�̓}�[�T�̂������Ƃ���A����̎��Ԃ����������B�}�[�T�̒n�}�͓I�m�ŁA��s�͍ŒZ�̓��������ǂ邱�Ƃ��ł����B�����Ƃ��A���o�ɂ��т��Ȃ���̗��͗e�ՂȂ��̂ł͂Ȃ������B���ǂ̂Ƃ��뗘�̂����Ƃ���A��邢���̂��Ăт悹��̂͂�邢���̂ł����Ȃ��B�ꓯ�͂��������܂������i�r�X�R�ł����j�i�B����ɃT�C�|�b�c�̓C�j�V�G�̐X�̂����鐶�����ƓG���Ă�������A�ŏ�������Ղȓ��̂�Ȃ��̂͂������̂ł���B�X�̐�͂��ɍ���������A��������G�z�o�̍��̏�ǂ��݂��Ƃ��̎O�l�̊����͂͂��肵��Ȃ��B��x��x�Ȃ炸�A�������̌i�F�͌����Ȃ��Ǝv���Ă����B
�@���ǎO�l�̃T�C�|�b�c�́A�X�ٕ̈ςɂ͋C�Â��Ȃ������B�����ނ�͐X�̊e���ɉe���݂��B�����ł������ڂ���ƌ���悤�ɂ��ē_�݂��Ă����B�y�b�N�͂����̌��o���Ǝv���������Ƃ������A���߂Ă��邤���ɖ�����]���z���Ƃ���悤�Ȃ���Ȉł������B
�@�T�C�|�b�c�̓s�͏�ǂƖx�ň͂��Ă���A���ɂ͂���ɂ͐����ʂ邵���Ȃ��B��ԂŖ�͂��܂��Ă������A���f�ŊO�o�����O�l�́A�����Ȃ��A�閾�����܂��Ă����ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�m�[�}�����͗���Ƃ��ɂ������p���H���A�ӂ����ї��p���邵���Ȃ������B�ނ�͔�ꂽ�̂ɕڑł��āA�B���Ă��������D��x�ɂ����ׁA�Ί݂ւƂ킽��A��ǂɋ�������p���H�ւƂ��̂т������B
�@���̗p���H�́A�Ԃ�����ǂƊX���ނ���ł���B�����r�����������痬���Ă���̂ł���B�r���͍�����ʂ��܂łÂ��Ă���B
�@�G�z�o�́A���H�����B�������̓s�ł�����B���H�ƐΏ�̓����������A�����������݂��`�����Ă���B
�@�p�[�V�o���̏������n�}�́A�i�o�z���ɂƂ�ꂽ�܂܂����A�O�l�͂ւ������Ȓn�}���v���N�����Ȃ���A�ǂ��ɂ��o���ɂ��ǂ�����Ƃ��ł����B
���@�@�@�@��
�@�T�C�|�b�c�̓s�s�͐Ώ~���߂��A�����̃p�����v�킹��B�L��ȕ���ɔ��B���A�G�z�o�̑��ɂ��A���ӂɂ͂������̓s�s���_�݂��Ă���B�嗤�ł��ł�����ȍ��Ƃł���B�l���͓�\���l�B
�@�G�z�o���̓���́A�M���ꖜ�ɑ��A�������\�㖜�l�ł���B����������A�ƒf�I�Ȉ������͂��܂�ƁA�l�X�̓s�s�Ȃꂪ�͂��܂������A�e�푰�Ƃ̐퓬���n�܂�A���܂ł͓�̎�����ƂȂ��Ă����B�Ⴂ�j�����������Ƃ��ĂƂ������ŁA�����X�ɂ͏��q�ǂ���A�a�l���ӂ��Ă����B���ꂽ��̂Ȃ��ɂ͑f���̉��������̂�����B�����X���ƍ߂̉����ƂȂ��Ă��A�������̂Ȃ����Ƃ������B�T�C�|�b�c�ɗF�D�I�Ȏ푰���G�z�o�ɓ����Ă��Ă������A�ނ�ɑ��鍷�ʂ��͂��܂�A�����͋}���Ɉ������Ă����B
�@���ʂ̃p�[�V�o���͏�ǂ������̕��u�����ŁA�p�_���A���^�ƂƂ��ɁA�q�b�s�ƃy�b�N�̋A���҂���тĂ����B�������ɂ͕����̉X�ɂ�����A�����̔����ɂ͘m���R�ς݂ɂ���Ă���B�p�[�V�o�������͖ѕz���������݁A���\���K�ɉ߂����Ă����B���܂�̂͌��ԕ����Ђǂ����Ƃ��炢���B
�@�l�l�������o�Ă���A�����Z�����o���Ă���B�p�[�V�o���͏����ɂ����̑����J���āA�p���H�̏o������A�l�l�̎p���o�Ă���̂�҂��Ă���B�p�_���ƃ��^�͌�����ɂ����āA�J�[�h�Q�[���ɋ����Ă���B���̎O�l�̒��ł͂��т̃p�V�B����ԔE�ϗ͂��������B
�@�₪�Ď��Ԃ͂����A���^�ƃp�_���͖���ɂ����B�������������ł���B�������A�����������݂͂����B�p�[�V�o���͏����̑����J���āA��ǂɖڂ����炷�B�����ɂ͗p���H�ւ̓�������������B�i�q���͂߂������̊ȒP�Ȕr���a�������B�₪�Ă��̊i�q�����������ގw���������B�i�q���͂��ꓪ���o�Ă���ƁA�p�[�V�o���͂�����̓�l�ɍ��}���āA���������₭�o�čs�����B
���@�@�@�@�Z
�u�y�b�N�A�y�b�N�v
�@�y�b�N�̓r�X�R�Ɏ���������Ƃ����������~�߂��B�����Ɍ��������Ǝv�������A���̐��ɂ͕������ڂ�������B�ӂ�ނ��ƁA�p�[�V�o���A�p�_���A���^�������B�݂�Ȃ��c�c�Ǝv���ƁA�y�b�N�͂ӂ��ɗ܂��ނ̂��o���Ėڂ��u�����B�݂�Ȃɉ���̂����ꂵ�������������A�����ɂ��Ȃ������o�[�̂��Ƃ��v���Ĕނ͗܂����B���̓�N�ԁA���܂��܂Ȗ`�������ʂ��Ă����ނ�̃O���[�v���A��l�����A�����܂��q�b�s�������Ďl�l�ƂȂ����B
�@�p�[�V�o���͋A�肪�x���̂��Ȃ��낤�Ƃ������A���̗܂����Ă�߂��B�ނ͂Ȃɂ����킸�Ƀy�b�N��������߂��̂ł���B�p�_���ƃ��^�����̗ւɂ��������B�ނ炾���āA��l�̂��Ƃ��S�z���������A����ȏチ���o�[����������ǂ��Ȃ�̂��s���ł��������̂��B�Ƃ��ɁA�y�b�N�ƃq�b�s�́A�����ȈӖ��ŃO���[�v�̒��S�ɂȂ��Ă������炾�B
�@�p�[�V�o���͎������܂����ł������B�u�悭�߂��Ă����ȁB�悭�߂��Ă��ꂽ�ȁB����A�C�j�V�G�̐X�ɍs�������Ȃ�Ă��������ǂ��A�ł��A����ȐX�A�������Ƃ��Ȃ�����ȁB�悭���܂�Ȃ�������v
�@�����I����ƁA�p�[�V�o���͑嗱�̗܂����ڂ��͂��߂��B�O���[�v�̂Ȃ��ł���ԂɌ��܂��ς₢���A�������Ƃ����Ƃ��A�܂������ɋ����̂��ނ������B
�u�ڂ���A�i�o�z���ɂ��܂����B����ŋA�肪�x�ꂽ�v
�@������āA�O�l�͐������Ă��ɋ������B�����Ԃ�A�炪���߂Ă����B�ؑ��̋��|�͂��܂��܂Ȍ`�Ŏq�ǂ������ɂ��`����Ă������炾�B
�@�r�X�R���p���H���甇���������Ă����B�m�[�}�Ɏ��݂��Ă���B��l�̐N�͖����Ŏq�ǂ��������݂Ă���B
�u�����A������͂Ȃ�ȂH�v�ƃr�X�R�B
�u�F�����ł��B�p���H�̒n�}�͂��̎q���������ꂽ��ł��B�݂�Ȃڂ���̂��Ƃ�҂��ĂĂ��ꂽ�v
�@�y�b�N�������ƁA�p�[�V�o�������ӂ��ɏ����B
�u�q�b�s�͂ǂ�������H�v
�@�p�[�V�o�����u�����B�y�b�N�͕ԓ��ɂ��܂����B�r�X�R�����͂��݂܂킵�Ă���B��ǂ̏�ɂ�������͂��Ȃ��悤�������B
�u��Z�ɘb���Ă��v�ƃr�X�R���������B
�@�y�b�N�͂��̘Z���Ԃ̌o�܂������܂�Řb�����B�Ƃ�����m�[�}���͂�݂����B�q�b�s���}�[�T�̒�q�ɂȂ����Ƃ����ƁA�O�l�͂��ǂ낫�A���ʼn����������B
�@�r�X�R�͂��炢��ƁA�u�����A���������ȁB�l�ɚk��������B���������A��Ԃ͊O�o�֎~�̂͂������v
�u���͂ǂ��Ȃ�v�ƃp�[�V�o���B
�u���܂�v�r�X�R�͎O�l���Ȃ��߂킽���A�u���܂������A���傤�ǎO�l���ȁv
�@�r�X�R�̓}�[�T�ɂ�����������b�N���A�p�[�V�o���ɉ��������B���~�ɂ͂����ċA��Ȃ����炾�B�y�b�N�ƃm�[�}�������b�N���킽���ƁA�O�l�͋}�ɏ�@���ɂȂ����B�����A�q�b�s�͂��߂�邩�킩��Ȃ��Ƃ�����ƁA�O�l�̋@���͋}�ɂ�������B
�u�����˂���A���܂������A������X�ɒu���Ă����܂����̂��H�@�}�[�T���Ă̂́A�������˂������Ȃ�H�v
�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�}�[�T�͗��h�Ȑl�Ԃ��i���̌��t�Ƀm�[�}�ƃy�b�N�͎�����������j�B����ɁA�q�b�s�̓}�[�T�Ƃ͌Â�����̒m�荇���������v
�u�������B�����̓}�[�T�̂��ƂȂ����Ƃ��b���Ȃ������v
�u�����ł͂Ȃ��B�q�b�s�̓^�b�g���̒�q�ŁA�C�j�V�G�̐X�ɏo���肵�Ă����B�}�[�T�ƒm�荇���ł������������Ȃ�Ƃ��Ȃ��v
�@�p�[�V�o���͕s���s�����Ȃ����B�r�X�R�͎O�l�ɂ������B
�u���܂������A�M���X�܂ŁA���S�ɂ��ꂽ����U���ł��邩�H�@�閧�x�@�ɂ݂���Ȃ��悤�ɂ����v
�u����Ȃ̊ȒP����B�ǂ݂̂��X�����͖��H�݂����Ȃ�����B�ł��A���炻�̂�����������߂����������ȁB�M�������āA�o���o�����c�c�v
�@�Ƃ͂����A����Ƃ��ɒ��p�����ϑ��p�̕��̓i�o�z���ɂƂ�ꂽ�܂܂Ȃ̂����炵�������Ȃ��B�ނ�̓p�[�V�o���̗p�ӂ����{���M���ɂ���܂�A��ǂ���A�X�̒��S�X�ɂނ��Ĉړ����͂��߂��B
�@�G�z�o�ɂ́A�_�ƌĂ�銲�̒��a���A��L���ɂ��Ȃ鋐��ȏ�Ύ�������B���Ƃ��Ƃ́A�����𒆐S�ɔ��B�����������Ȓn���s�s�������B���S�ɂ͋M���̊ق������Ȃ�сA�뉀�ɂ͗��ӂ�ɔz�u���A�X�̓s�Ƃ��Ă�Ă���B�ʐς̎����͋M���̓@��ł���A���������͋����~�n�ɉ������߂��Ă����B������ނ�̕���ɂ�����Ă����̂��B
�@�����X�̍r��悤�͗\�z�ȏ�ŁA�Z���O������w�Ђǂ��Ȃ��Ă����B�����炱����Ŕ����̎��̂����̂܂ܕ��u����Ă����B�Z�l���؉A�ŋx�����Ƃ�ƁA�}�ɂ͎��E�̂��Ԃ牺�����Ă���n�����B
�@�҂ɂ͓�����ӂ�A�Ώ�̏�ɂ���Q�����Ă���B���̂������͎��̂̂悤�������B�^�钆���Ƃ����̂ɁA�����̐��������������畷�������B���H�ɕ����ԓM���̂��������B�X�ł݂����o���A�����ł͌����ƂȂ��Ă����B
�@�s�̉ЁX�����ɂ���ׂ�A�C�j�V�G�̐X�̕����܂������~��������C�������B�p�[�V�o����͂����Ɖ��s�ɂ��ē݊��ɂȂ��Ă���悤�����A�s�𗣂�Ă����y�b�N�����ɂ́A���ӂ������悢�����h���悤���B
�@�M���X�̋߂��ɂ����B�����X�Ƃ͋���ȓ��H�ł킩���Ă���A�ȒP�ɂ킽�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B���������͂��̓��H���A�ǁA�Ƃ��A���̓��A�Ƃ��Ă�ŁA���̂��Ă�����������Ă������B���~��`���ċM���X���͂��Ă���A���������͂ǂ̕��p���������Ȃ������B�钆�ɔE�т��������̂Ȃ瑦���ɎˎE����Ă��܂��B���ʂ����悷���āA�i�D�̓I�ɂȂ�̂��B
�@��������͊Ď��̖ڂ��������Ȃ�B����������₵���l�e�ɖڂ����点�Ă����B�m�[�}�������钆�͋߂Â����Ƃ���ł��Ȃ������B
�@�O�l�͒�������܂łɉ��ꂽ�̂�A�g�x�x�𐮂��邱�Ƃɂ����B�����ł��p�[�V�o�����𗧂����B�ނ͔�������������قǒm���Ă���A�m�荇���̏h�ɂ��낪�肱�ނ��Ƃ��ȒP�������̂��B
�@�p�[�V�o���́A�Z���O�ɉB�����������̂܂ɂ��Ƃ��Ė߂��Ă����B�͂��߂͉�����ł����r�X�R���A���ʂ̍ˊo��F�߂���炴��Ȃ������B�r�X�R�ƃm�[�}�ɂ́A�k���Ȍv�搫���s�����Ă������炾�B
�@���C�ɂ͂���A�����𒅂�����ƁA�悤�₭���������B�y�b�N�͖閾����҂��Ȃ���A�p�[�V�o����Ƌv���Ԃ�̍ĉ���y���B�ނ̓C�j�V�G�̐X�ł̏o������ʔ�������������ĕ��������B�������A�r�X�R�̒��ӂ������ė��̂��Ƃ͂���Ȃ������B�p�[�V�o�������́A���̖`���ɎQ���ł��Ȃ��������Ƃ�������Ɖ����������̂������B
�@���������B�y�b�N�����͂��m��ʊ�ŁA�M���X�ɖ߂��Ă������B������̎�蒲�ׂ͂�����낵���������A�r�X�R�̂������ł���Ȃ�ƒʂ邱�Ƃ��ł����B������ɂ���ȉ����Ȍ��𗘂����̂͂��Ȃ�����A�t�ɐM�p���ꂽ�̂��B
�@�y�b�N�͓��H�̌��������������������A�p�[�V�o�������͎p�������Ă���B�M���X�ɋ߂Â������ł��܂鋰�ꂪ���������炾�B�y�b�N�͎���̂��A���Ԃ̎p�����������B�����ƕʂ�����������������A�����ނ�ɉ�Ȃ��悤�ȁA���������ɂ��Ȃ��Ƃ��̎O�l������ł��܂��悤�ȁA����ȋC�������̂������B
�@�����̉��~��ڂɂ���ƁA�y�b�N�͋��E���Ă��܂����B�C�j�V�G�̐X�ɍs�����Ƃ����܂��Ĉȗ��A�C���͂�ǂ����������̂��B����ǁA�q�b�s���������݂��܂����ނ�X�Ɏc���Ă������ƂɁA�߈��������ڂ����B
�@�y�b�N�͋}�Ɍ��߂������������B�p�[�V�o�������͊댯�ȕ����X�ɂ��邵�A�q�b�s�͍����C�j�V�G�̐X�̉��ɂ��āA�������Ȗ����ƁA���т����C�s�����Ă���͂����B�ނ̐S�͏d�����݂��B�y�b�N�ɂƂ��āA�p�[�V�o�������͂���܂łɂȂ��F�����������B�{���ȏ�ɑ̂łԂ��肠�����F�������B���������F�����́A�����Ɠ��ʂȂƔނ͎v���B�Ȃɂ����c�c
�@�ނ�͉^�������̂��B�W�u��������ł���Ƃ������́A�ꓯ�͂܂��܂����̎v�����������Ă����B���o�⌶���ɗ����ނ����A��Ȃ��������ɓn���Ă����B���������̎���ʼn������N�����Ă��āA������͂���ɗ����ނ������Ƃ��A���ꂼ��Ɋ����Ă����̂��B�y�b�N�́A�O���[�v�̖ʎq�ɍD�ӈȏ�̋C����������Ă����B���`��������F�����Ƃ����̂́A���ʂȂ�Ȃ����낤���H�@����a������قǐM���ł��A�����̈ꕔ�̂悤�Ɋ�������F�����Ƃ����̂́B
�@�ł���A�F���������~�ɌĂъ��������B�����ǁA��̏Ί������ƁA���̌��t�����݂���ł��܂����B�ނ͂܂��q�ǂ����������A��e�Ƃ������ĉ߂������Ԃ́A�������܂�c����Ă��Ȃ��ƒm���Ă����̂��B
�@�m�[�}�͑҂����Ă����n�Ԃɏ�肱�݂Ȃ���A���̂Ԃ�Ȃ�S�z�����قǂ��Ȃ��A���~�ɖ߂�邩������Ȃ��ƍl�����B�ȍ~�̓r�X�R�ƘA�����Ƃ肠���A�ׂ̎藧�Ă��l���邵���Ȃ��B�g�D���[�V���h�E�����ɂ͂������������A�ނ͐푈���~�߂�ǂ�Ȏ藧�Ă��v�����Ȃ������B�ނ�̌R���͑嗤���ɎU����Ă��܂�����Ă���B�~�߂邱�Ƃ��o����Ƃ���A����̓n�t�X���̂����Ăق��ɂȂ������B
�@�����X���������A�g�D���[�V���h�E�����̗܂��l����B�T�C�|�b�c�̍��𗧂Ē������Ƃ���l���Ă������A�r�p���Ă���̂͂��������ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�m�[�}�̓n�u���P�b�g�̉e�����炩�A�������l���Ɛ������������Ă���A���Ȃ炸�V�������Ă����͂����ƐM���Ă����B�r�X�R�����Ȃ��̂悤�������B�����A��l�̐N�ɂ́A����ɉߍ��ȉ^�����܂��Ă����̂ł���B
���@�@�r�X�R
���@�@�@�@��
�@���~�ɖ߂����Ƃ��A�r�X�R�͂����ɂ��ٕ̈ςɋC�������B�ŏ��̂����A�ނ͂��ٕ̈ς����ł���̂��𗝉��ł��Ȃ������B�����͐[�X�ł���B���g���̑����͉Ƃɖ߂����낤�B����ȊO�̎҂��Q�Â܂��Ă���͂��ł���B����łȂ��Ƃ�����ȉ��~������A�Â܂��Ă���͓̂��R���B�r�X�R�͍ŏ��̂����A���݉��낷�����炻���ƒu���A�N�̒��ӂ������Ȃ��悤�C�����������A�����ɓ��X�ƕ����n�߂��B���l�̋C�z�B
�@��C�͒���A�������l�̓������Ȃ��������̂悤�������B�]�����悬�����̂́A��a�ɖ������m�[�}�̐��������B���ł͉��~�������[�A���k�ƂȂ��Ă���ƍ��������Ƃ��̔ނ̐��B
�u����c�c�v
�@�r�X�R���O�~�̏���}�����B�g�[�}�X�͐Q������ł���B���e�����M�����ȂǂƐM���������Ȃ����A����ǁA���l�̉��~�ɕ��u���ꂽ�̂��Ƃ�����H
�@�r�X�R�͕��̐Q���ɒH�蒅���ƁA�L���̍��E�����āA�����Ɣ����J�����B��C�͂�ǂ݁A�����݂Ă����B�������˂��J���Ă��Ȃ��̂��낤�B�r�X�R�͉�����ȈՃ����v�����o���ƁA�����Ɠ�����ꂽ�B�x�b�h�̏�ʼn��҂����g���������̂ŁA�ق��Ƃ����̂����A���̂Ƃ������ɕY�����A�̓�����k�����B���̒��ŁA�{��Ǝ��]�Ƌ��������̂��������B�r�X�R�̓����v�������グ���A����ȕ����ɂ���傫�ȃx�b�h�̏�ŁA�g�[�}�X������X���Ă���̂��������B
�@�r�X�R�̓V���b�N�����B���e�͂��̘Z���ԂŁA����ɂ��ڂ悤�������B����͎��ɂ����Ă���B
�@�������A������͂��������ǂꂾ��������������̂��A�Ɣނ͓{��ɔR���Ă����v�����B
�@���e�����ʂ�������Ȃ��B�����v���ƁA�S���X���̂悤�ɗ₦�Ă����B�ނ͂���܂ŐS��������F�l�������Ȃ������B��e�͑����Ɏ���ŁA���e�ɂ����ʂ��܂��Ă�������L�����Ȃ��B�ނ͂���܂Ŏ������ǓƂ��ȂǂƎv�������Ƃ͂Ȃ��������A���̂Ƃ��͂��߂ČǓƂ��������B�Z�̃p�p�X�����ɁA�c�������e�͕��e�������B�����A�p�p�X������ł���A�g�[�}�X�͔����k�̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B�r�X�R�́A�����Ƃ������݂͉��Ȃ̂��Ǝv���B���e�ɂ���S��������Ȃ��A���p�ȑ��݂Ȃ̂��낤���H�@�r�X�R�͌�����@���āA�Ȃ�����Ȃ��Ƃɂƙꂢ���B�x������v�������āA�ނ͎�������������B�S�Ă͎��������\����������ł͂Ȃ����B
�@�p�p�X�́A�Ȃ�ł��悭�ł����j�������B�l�D���̂���N�ŁA�N���������Ă����B����ɔ�ׂ�ƁA�r�X�R�͒N���ɍD�����Ƃ������Ƃ��Ȃ������B�����������ŁA�������ᛂ��N�����悤�ȓz�������B�����ł������Ƃ���͂킩���Ă��邪�A�Ӓn�����肾����A�����F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�r�X�R�̓p�p�X���D�����������A�D�ӂƓ������炢�ɑ����݂������Ă����B�Ȃɂ��ɂ��p�p�X�ɓG�����B�p�p�X���������Ƃɂ͂Ȃ�ł�������̂��킾�������A�Z�͂���Ȓ�����e����A�x�ʂ̂���l�Ԃ������B�����S�������A���l��M�p���Ȃ��r�X�R���A�ɓ����ɏ����Ă��ꂽ�B���̂��Ƃ��ނɂ͕��������������B���肪�����v�������ɉ����Ă����B���͂��̂��Ƃ�������Ă���B
�u�p�p�X���c�c�v
�@���e���ڂ��J���A����������ƌX����B�����v�̂������ȓ��̒��Őe�q�݂͌��Ɏ�X�������������킹���B�g�[�}�X�̓��͑���A�ڎ�������ɑ傫���������B
�u�������ܖ߂�܂����v
�@�x�b�h�̘e�ɕG�����ƁA�g�[�}�X���ѕz�̉�����r���o�����B�r�X�R�͌Z�������悤�ɐU�镑���̂��킾�����B�����o���ꂽ�r��D�����������B
�u�����͂���܂��H�v
�u���܂��͐S�z�����ȁB���͐Q�Ă������������v
�@�f���܂���ɏ����B�r�X�R�͋}�ɗ܂��āA�����ł�����������B�g�[�}�X�͎����̏��킩���Ă��Ȃ��̂��B�z�ł�ƁA�M������悤�������B����قǑ��������āA�����������o���悤�Ȃ̂ɁA�����Ƃ�Ɗ��������Ă���B
�@�g�[�}�X�͑��q�������Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��B�ڂ̑O�ɂ���̂��A�r�X�R�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��悤�ɁB
�u�r�X�R�͂ǂ������H�v
�@�r�X�R�͋������B�܂�@���Ȃ���A
�u���͖����Ă���܂��c�c�v
�@����ł�����������ꂵ�߂�Z�ɁA���݂��܂����C�������o�����B����Ȏ��������Ƃ܂����B���l�ɂ܂ő����݂�����������A�����ۂ��ŁA�ڏ��ȑ��݂Ɏv���Ă����B
�@�g�[�}�X�������������ƌ��W��������B�����̎������߂�悤�ɁA�������ƁB
�u�����́c�c�v
�@�r�X�R�͋����Ċ�����B���e�������̂��Ƃ�b�����Ɗo�������炾�B
�u�����͂��܂��Ƒ����Ă��肢��B���܂��͌Z�ŁA���藧�ĂĂ����˂Ȃ��Ƃ����̂ɁA�ӂӂӁv�ƁA�Q�������B�u���܂��̑������������ƂɂȂ�������v
�@�r�X�R�͕��e�̌͂ꂽ���𗼎�ŕ�B
�u�킩���Ă���܂��v�ނ͋����Ă�������A���̊炪�D�����݂������ǂ��Ă������ƂɋC�Â��Ȃ��B�u���������Ă��˂c�c�v
�@�g�[�}�X���r�X�R�̎���y���@�����B
�u���܂��炵�����Ȃ��c�c�����͂���ł����̂��B���ꂪ����̂����Ƃ���Ȃ̂��B���_�ɂȂ�ʂ悤�ɁA�C�����Ă��B�Z��Ȃ̂�����ȁB���܂����킩���Ă���͂������v
�@�r�X�R�͕�R�ƕ����݂��B�ܐ��̌������œ�l�̎肪�h��Ă���B���ƌZ�̂��Ƃ��A���ɂȂ��Ă킩�����C�������B�r�X�R�̓x�b�h�ɓ˂�������ƁA�ѕz�Ɍ��������������E���ċ������B�r�X�R�͐g�𝀂苃���������B���̎肪�����ȂłĂ��邱�Ƃɂ��C�Â��Ȃ������B
�u����́c�c�v��������A���ڂ肾���悤�Ɍ����B�������A��𑱂����Ȃ��B����ȏ�A���̐S���u���o���̂́A�������܂������Ƃ̂悤�������B�Ȃɂ�莖�����̂��|���������A�����\���ł��������̂��B�u����͂��₳�����c�c�v
�u���҂��H�v
�@�g�[�}�X�̋ٔ��������Ƀr�X�R�͊���グ�ӂ�ނ����B�����̓�����ɐl�e�������Ă����B��u�p�p�X�̎p�Ɍ����邪�A����U���Č��e��U�蕥�����B���t�����Ă����̂��A�Ɖ�����i�C�t�����o���B
�u���[�A���c��!?�@���~����o�čs���I�@�l���ĂԂ��I�v
�@�r�X�R�͕��e�������ƃx�b�h�𗣂�A���_�ɂ��j�����Ɍ������Ă������B
�@�����Ă����͎̂O�l���B��l�͕��ʂ����A�������̈ߑ������Ă���B���̂����A�������ڂɂ������Ȃ������Ŕ����Ă����B�r�X�R�̓i�C�t���グ��ɂ��Ȃ��B�I�ł����{�ɂ��炢������Ƃ���ցA�j���̂��������Ă���B���ɏ���ł����A���ɂ�����������A�w����ɑł��āA�ċz���ł��Ȃ��B�ꂵ��ł���ƁA�j���w��ɂ܂��A�芵�ꂽ����Řr��P�������߂�����B
�@�r�X�R�̓��_���𐂂炵�A���E�������点�Ȃ���A���e�����Ȃ��������Ƃ�����B�푈���~�߂邱�Ƃ�������邱�Ƃ��A���ɂȂ������B�����Ȃ��Ă݂�ƁA�����͂����ۂȑ��݂������B
�@�ӂƁA�A���i�߂�j�̘r�����݁A�r�X�R�͑������ĊP�����B����ƒm�o���߂��āA�ނ̋ꂵ�݂͂��悢��[���Ȃ����B�j�͍A���i�߂�̂͂�߂����A�ނ̊{�������グ�āA�w�����ւ��Ȃ��n�߂�����A�r�X�R�ɂ͖ڂ̑O�ɗ��┯�̒j���ڂ���Ƃ��������Ȃ������B���̒j�����́A���ʂ����Ă��炸�f�������炵�Ă���B�r�X�R�͂ǂ��ɂ����o���m�ۂ��悤�ƁA�S�g�ŋ����ɂ����炢�A�����������悤�Ƃ����B�j�����Ă���̂͂ǂ���狳�c�̐_���߂̂悤�������B
�u�p�p�X�A���̎҂����͂ȂB�r�X�R�I�@�r�X�R�A�ǂ��ɂ���I�v
�u����Ɏ�������ȁv
�@�ƃr�X�R�͂�����鐺�ł������B�┯�̒j�͕G�����ċ߂Â��Ă����B
�u�N�ƐX�ɍs�����B����������B�N���Ăъ��̂��v
�@���̏u�ԁA�Ɋo�����̂��āA�r�X�R�̔]���ɑŎZ���߂��Ă����B���J�X�̓n�u���P�b�g��͂������A�m�[�}�����̌v��܂ł͒m��Ȃ��͂��ł���B
�u���A�m���v�܂��͂������Ȃ����B�r�X�R�͐Ґ��̐��悤�ȋꂵ�݂Ɉӎ����Ȃ��������ɂȂ�B
�@�͂����B�r�X�R�͂������Ȃ���A
�u�X�ɂȂǍs�����̂��B�Ȃ��s�����Ǝv���v
�u�Ȃ�Q�[�g���J����҂����܂������ȊO�ɂ���Ƃł������̂��v
�@�r�X�R�͎v�킸�ꂵ�݂�Y��Ċ���グ���B���ɂ������̂́A�X�ł݂��Q�̂��Ƃ������B�j�͂��̏�ŋN���������Ƃ�m���Ă���炵���B�܂��āA�Q�[�g�Ƃ͌������Ė��ł͂Ȃ����B���̉Q�͓�̐��E������ŁA�ِ��E�̖����Ăъ��̂�����B
�@�����A�N�����������Ƃ܂Œm���Ă���B
�@�r�X�R���v�����̂́A�m�[�}�ƃy�b�N�̗��肾���A���Ƃ�����A�ނւ̎���͊�ł���B��͂草������̂�������Ȃ��B��l�̕ԓ����^���Ă̎��Ȃ̂��낤���H
�u���A��������E���ɂ�����肾�����낤�B�ڋ��ȁc�c�v
�@���������牣���A�r�X�R�͏��ɓ˂��������B�w���ɏ�鋐�����̏d���|���Ă����̂ŁA�ނ͂܂����������B�������������̂́A�┯�̘e�ɂ��鑉�g�̒j�̂悤�������B���ʂ̂����Ŋ�͒m��Ȃ����A
�u�����܁A���J�X���ȁB�����ł��܂���Ǝv���ȁv
�u�I�b�g�[���C�h�A�������E�����B��X�̖��ɗ��悤�Ȓj����Ȃ��v
�@�����炵�Ă�͂胋�J�X�̂悤���B
�@�┯�̓I�b�g�[���C�h��
�@�ƃr�X�R�͔]���ɂ��̖������݂������A���̂ǂ���T���Ă��o�Ă��Ȃ��B�i�D���炵�Ă��A�����̒n�ʂɂ���͂��ł���B���̒j�͐��C�݂̂Ȃ���ڂŁA�ނ��������Ă���B�����┯���Օ��̍��E�ɗ���A�j�ɂ͐[��ᰂ����܂�Ă���B�Ќ��̖��������ɔ����āA���Ȃ�̍���̂悤�������B�r�X�R�͂��̒j�Ɉؕ|���o�����B�w��͔ނƕς��Ȃ��B�Ȃ̂ɁA��ȂقNj���Ɍ�����A�ނ͓���U���āA�j�̈Ј����̂��悤�Ƃ����B
�u�܂��A�҂āB���̒j����͒T�邱�Ƃ�����v
�@�I�b�g�[���C�h�̓r�X�R�̓��ɉE����悹���B���̏u�ԁA�r�X�R�͐��g�̔]�����҂����܂�����̂��������B�܂�Ŕ畆�������ꋓ�ɗn���āA���ڑf���ł�����Ă���悤�������B
�u��߂�I�v�Ɣނ͂��̌��t��A�Ă����B�����A�]���x�z����Ď��ۂɂ͐����痧�ĂĂ��Ȃ������B
�@�I�b�g�[���C�h�͂ԂԂƉ����������Ă���B�Q�[�g���J�����̂͂�͂肫���܂��c�c�N���Ăъ��̂��c�c���₷�邽�тɁA�I�b�g�[���C�h�͎��݂ɓ����Ă���悤������(�Ƃ����Ă��r�X�R�̒m��͈͂ł݂̘̂b����)�B�r�X�R�͎��o�������A�����������Ȃ��Ȃ��Ă����B���̒��ŁA�Ō�́A
�u�}�[�T�ɖ���a�������Ɓv
�@�Ƃ������t�����͕��������B�I�b�g�[���C�h������ǂ����B
�u�������B�}�[�T�̉ƂɂȂǍs���Ă��Ȃ��v
�u���������ȁv
�@�I�b�g�[���C�h���������ݏグ��B����͊���ɔ����āA�Â��Ȍ��Ԃ肾�����̂ŁA�r�X�R�͂��������̋��|���������B���J�X�����������łɔނ��痣��Ă���B�r�X�R�͐Ԏq�̂悤�Ɏ葫��g�ɊĂ���B������R����C�͂��玸�������Ƃ�m���Ă���̂��B
�u�S�Ă�m��ꂽ���Ƃ͂킩���Ă���͂������B�����܂̍l�����ȁv�I�b�g�[���C�h�͔n���ɂ����悤�ɕ@���Ȃ炷�B�u�����܂�Ȃǂɉ����ł���B���܂��Ȃǂ�������Ȃ������B���e�͂����܂��p�p�X�Ƃ����v���Ă��Ȃ��c�c�v
�@�r�X�R�͎��̒��ŃI�b�g�[���C�h�̌��t����ῂ̂悤�ɃO���O���Ɖ���āA�����A�����A�����A�Ƃ����ꂭ�����Ȃ������B�I�b�g�[���C�h�̚������͖��@�̎����̂悤�ɔނܑ̌̂ɍ����n�����B�}�[�T�Ɨ��Ƃ����������s�v�c�ȗ͂��g�������A���̃I�b�g�[���C�h�͂���ȏゾ�����B
�@�┯�̒j�͉������Ȃ������悤�Ȏ��R�ȓ���ŗ����オ��B���J�X���߂Â��đ����݂����߂Ă����₢���B
�u�E���܂���̂Łv
�u�܂����ɗ���������B�j������v
�@�I�b�g�[���C�h�͂��������Ȃ���A�r�X�R�̃i�C�t���E����Ɏ��������B
�u���c���Ƃ͎v��H�@���q�����҂����킩�炸�A��R���ł���B���e������ɓ�x�����A�𐂂ꗬ���̂�m���Ă������H�v
�@�r�X�R��������E�ɂӂ�ƁA���ꂽ�������E�ɗh�ꂽ�B
�u�����܂͘����ŕ@�����Ȃ��z���������ȁB�����A���e���v���C�����͂��邾�낤�B���̂܂܂ł͋ꂵ�ݎ��ʂ������B���l�ɎE�����O�ɁA�����܂�������n���Ă��v
�@�I�b�g�[���C�h���ނ̌���F�l�ɂ���悤�ɗD�����@�����B����ł��܂��͂���̕����ƌ������肾�����B
�@�I�b�g�[���C�h�͋�������ĕ��������肬��A��ŘA��Ă����A�ƃ��J�X�ɚ������B���J�X�͊�F���ӂ�܂��Ȃ���A�r�X�R���x�b�h�ɂ���������B
�u���r�X�R�I�@���e���E���I�v
�@�r�X�R�͏d���邢�̂��ǂ��ɂ��x���Ȃ���A�x�b�h�̘e�ɗ������B���e���E���A������n���A����Ȓj�̎w�߂��Ȃɂ����ŗD�悷�ׂ����̂��Ǝv�����B���f��������Ȃ��B�ނ͌���ꂽ���Ƃ����s���閳�@���ȋ@�B�̂悤�Ƀi�C�t���f���ĕ��e�̊��`�����B����������قǂɊ���߂Â���B�ω����N�������̂͂��̂Ƃ��������B
�@���J�X�͋C�̋����悤�Ȋ�т��ׂāA�r�X�R�̗����Ɏ���悹���B
�u�ǂ������r�X�R�H�@��H�@�����͂����Ȃ��B�I�b�g�[���C�h�Ɍ���ꂽ�ʂ�ɂ���B���q�����҂��킩��e���Ȃ��K�v���H�@���ꂩ��̐��͂ȁA���́c�c�v
�@���̂Ƃ��r�X�R���ӂ�ނ����̂ŁA���J�X�͖ق����B�ނ��ق����̂́A�r�X�R�̖ڂɖ��m�Ȓm�o��������ꂽ���炾�����B
�@���J�X�������グ�悤�Ƃ����Ƃ��͂����x�������B�r�X�R�͐U��グ���i�C�t�����̂܂ܔނ̍A�ɓ˂����Ă����炾�B���J�X�͋����ɖڂ����J���A�J�̉��𗧂ĂȂ���A�A�ɗ��i�C�t��~���ނ������B
�u�c�O�������ȁB����Ȃ��������ł���
�@�r�X�R�͑����݂Ɣ߂��݂����߂Ě����B���𗧂ĂȂ��悤���J�X����������|���A�i�C�t�ōA�������܂킵�^���Ɉ����������B���J�X���m���Ɏ����Ƃ��m�F����ƁA���e�̈�̂ɖѕz�����Ԃ��A�}���Ńo���R�j�[��ڂ����ċ삯���B���e���c���čs�������͂Ȃ��������A�I�b�g�[���C�h���ׂ�����Ɣw���ɓ\����Ă���悤�ȋC�����Ė����ő��邵���Ȃ������B�����Ă���A����͋��|�ɕ����Ă���Ɨ܂𗬂��Ȃ���A�ł̒��ɔ�яo���A�L���������ɒ뉀�̗тɌ��������B�M���̓@��͒ʏ�A���ň͂܂�A���̓����ɂ͍L��Ȓ뉀���������̂��B�r�X�R�̓��ɂ͕��̎��Ɋ�ƃI�b�g�[���C�h�̐������Ȃ������B������A���肩��N�����ꂽ�Ƃ��ɂ͔ߖ��グ�Ė݂ɔ�э��B
�u�����A����������v
�@�ƃx���g��߂܂��B�p�[�V�o�����B�p�_���ƃ��^������B�q�ǂ������������v���g�����Ƃ����̂ŁA�r�X�R�͂͂������Ƃ����B�R�c���グ�悤�Ƃ�������ӂ����A
�u���[�A���c������B����͓����Ă����Ƃ��낾�v
�@���N�����̊�ɋ��|�̐F�������сA�łɂƂ��Ă����̂��������B�p�[�V�o���̓r�X�R�̎���Ђ��ėU�����͂��߂��B
�u�����܂牽�ł����ɂ���B�ǂ����痈���v
�u��������A��o������B�}�����v
�@�p�[�V�o���������͖݂̂̈�p�ɂ���}���z�[���������B�ނ�͎茳���낭�Ɍ����ɒ�q�����肽�B�I�b�g�[���C�h�̊�͂��v���ƁA���ǂ������Ă��Ă����������Ȃ������B
�u�q�b�s����������ꂽ�v
�@�p�[�V�o���������ɂ́A���̏��N�������ꂱ�̂悤�Ȏ��Ԃ��N���邱�Ƃ�\�����āA�O�l�̉Ƃɍs���n�}��n���Ă����̂��ƌ����B
�u���炪��Ȃ��ڂɂ�����������Ȃ����āB�Ȃɂ���������A�����Ƃ���Ă����Ă��B�l���������ꂽ�v
�u�����B���Ƃ�����A�m�[�}����Ȃ����v
�@�r�X�R�͋}���Ńm�[�}�̌��Ɍ��������Ƃ����A�����������Ƃ����̂����A���̑O�ɚj���ӂ�āA�ނ͂��̏�ɂ���肱��ł��܂����B����m�[�}�̌��t���������삯����A�����l�����Ȃ��B���ǂ͔ނ������Ă��ꂽ�̂́A�M���ł͂Ȃ������̏��N�����������B�����Ȏv���⊴������荇���A�r�X�R�͊z��}����Ƃ��Ɏq�ǂ��̂悤�ɋ������Ⴍ�����B�p�[�V�o����́A�r���ɂ���ė����s�������B����Ȕނ�ɁA
�u�������c�c�v
�u���A���������ɎE���ꂽ�̂��H�v
�u�����ł͂Ȃ��B���͂������B���Ƃ��Ɛ��サ�Ă�������ȁB�����A������͕����E���ƁA����ɂ������v
�u�Ђł��ȁc�c�v�ƃp�[�V�o���B
�u����͕���������Ă����B����͑�n���������B�����ƌ������킸�ɁA�N�̋C�������˂��ς˂��̂��c�c�v
�@�r�X�R�͂ۂ�ۂ�Ɨ܂̍��Ԃɘb���A�O�l�̏��N�����͂��ƂȂ������̌��t�����B�O�l�ɂ͂킩��Ȃ����Ƃ����������B����ł��A�r�X�R�͕����������邱�Ƃ����ӂ����B�g�[�}�X�́A���玀�ʂ��ƂŔނ��~���Ă��ꂽ�悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B������r�X�R�͐��܂�Ă͂��߂ċC�����ނ܂ŋ������̂������B
���@�@�m�[�}
���@�@�@�@��
�@�@��̔����J�����u�Ԃ������B�m�[�}�͉��������������Ɗ������B�����̐l�̋C�z�ƕs���R�ȐÂ������������̂��B�Èł������B����ߐ��Ă���̂��B���̓������Y���Ă���B
�����悤�Ɛg��|�����A�s������ǂ���A���E����H�������߂ɂ������B�����ǂ���A�������Ă��Ȃ��B�����̘r�Ɉ�������|���ꂽ���Ǝv���ƁA������܂����Ԃ���ꂽ�B�����ł��������A���\�l�Ƃ����l�Ԃɓ��݂��ɂ���A�{�[���̂悤�ɏR������B
�@�m�[�}�͑����l�܂点�A���|��������B�N�O�Ƃ���Ȃ��ŁA������̂�������B
�@�̊i�̂����j���i���Ƃ̓}�I���Ƃ������̉Ƃ̉��j�������B�m�[�}����������̂́A���̉Ƃ̏��g�������j�A�ނ��ו��̂悤�ɒS���グ��B�m�[�}�͑܂̒��ŁA�f�������A���𗬂��B�j���������тɏ��߂��������h��A���̋�ɂɂ��߂����B�����قǂ̐l�e�ɂ́A�����͂o�����������B�������炢���悤�������B
�@�̗̂h�ꂪ�傫���Ȃ�A�m�[�}�͊K�i������Ă���̂��Ƃ�m�����B���̂����̑���ɂ͉�����Ȃ��B�l�X�Ɛi�ސl�̑����B�L���̉��ɂȂ����B���̊J�����B
�u��߂�c�c�v
�@���ɓ����o�����B���߂��̂��������Ɠ������A�܂�E�����Ƃ���ƁA�ォ��͂��Ƃ�ꂽ�B�낤�����̉��A���܂݂�̔ނ��Ƃ炷�B
�@�m�[�}�����ꂽ�Z���̊ԂɁA���~�͂�������͗l�ւ����I�����炵���B���[�A���c�������^�y�X�g���[���l���ɉ������Ă���B�g�F�̏�ɂ́A���c�̊����������B�Ԓn�ɉ����̃��V���h�J����Ă���B�X�ʼn��x���������̂������B
�@�����āA�ڂ̑O�ɕ��������B
�@��R�ƌ��グ�鑧�q�ɁA�j���x�͌������B
�u�߂������A���̔��t�҂߁v
�@�m�[�}�͍r�����������B�����������A�Ɣނ͎v�����B��������A����͓{����B�����߂������B�푈���~�߂悤�Ƃ��Ă���̂�����A���̐��̔��t�҂ƌ����Ȃ����Ȃ��B�����A�u���Ȃ��́A���[�A���c�ɗ^���Ă���c�c�v�Ɣނ͌������B���͖������B�m�[�}�͎��͂����͂ޏ��g���ɂ݁A�u���܂����������I�@�p��m��B�푈�������N�����A�����r�p�����A�������������_�����I�@�����X�����Ă݂�A��Ǝ��̂ł��ӂ�āc�c�v
�@�}�I���̌�����сA�m�[�}�͏��ɓ˂�������B�ނ�����f���Ă����͖͂����̂܂܂������B�ߋ��͂����ł͂Ȃ������B���̃}�I���Ȃǔނ̈�Ă̐e�Ƃ����Ă����قǂ������B�m�[�}�͋��|�����߂��݂Ɠ{��������ĉ����B
�@�j���x���A�u���܂����A���[�A���c�ɓ���v
�@�m�[�}�͕��e���ɂ�ݏグ�����A�ނ������낷�ڂ��₽�������B���̏u�ԁA�m�[�}�͌������������o�����B���܂ŕ��e������ƉB���Ă������A�����͂��̒j�����������̂��B
�u��b�̍��ɂ���Ȃ���p���������Ȃ��̂�!?�@����Ȃ��ƁA�����͑����Ȃ����I�@���Ȃ������l�������炽�߂�ׂ����I�v
�@�j���x�����U���ƁA�{���͂������B�����ɓ|��A�㓪�����������łB�]�kṂƌ������f���C���������������Ă����B
�@�j���x�͂������ɕG�����A����߂Â��Ă���B���g���ނ������N�������B
�u�l�������炽�߂납�c�c�����܂͉����킩���Ă��Ȃ��v
�@�m�[�}�͎����������Ȃ�����A�u�����̕����Ƃ͒N���c�c�v
�@�j���x�͖����ŗ����オ�����B��u�`���������́A���̕\�������Ă����B�u�A��čs���B�S���ɕ��肱�ނv���q�̖ڂ��̂������݁A�u�l�������߂�܂łȁc�c�v
�@�m�[�}�͉��~�̒n���ɂ���S���ɕ��荞�܂ꂽ�B����ȘS�������邱�Ƃ�������������B�}�I����͊������ʂ����d���n�ʂɁA�ނ𓊂��̂Ă�B�S���̓S�����܂����B�����|��������ƃ}�I���͕@��炵�A
�u���ɂ��킩��Ƃ�������B���̕��̗͈͂̑�ɂ��āA���̗��z�͐����Ȃ��̂��I�v
�@�m�[�}�͋ꂵ�����̉��ŋ��B�u���܂������͑����Ă���B���C���Ȃ����Ă���v
�u�ȑO�̂��ꂱ�����C���Ȃ������̂��B���͂������������݂����v
�u���푰�ɐ푈���������A�l�����ꂵ�߂�̂������������I�v
�u���̂Ƃ���v��邬�Ȃ��M�O�ɖ�������ł��Ȃ����B�u���̐��͋ꂵ�݂ł����ς����B�����A���̔^�݂�f���o�����Ƃ��ɑS�Ă��I���v
�@�}�I���͏o�čs�����B�m�[�}�͈ÈłɎ��c���ꂽ�B�ނ�̓m�[�}�����o�ɏP���Ă��邱�Ƃ�m���Ă���̂��낤�B�ނ�����[�A���ɗ^����܂ł́A�����ꂵ�݂𖡂���Ă����̂��B
�@�m�[�}�͐�]�̒��Ők�����B�n���ɂ͂킸���Ȗ�������������A�₪�Ă͌��o���͂��܂邾�낤�B����������ɂ������Ȃ��B�m�[�}�͂�邢���̂̂��Ƃ��l���������B������͐M����͂�H�����ɂ���B�|���̂́A����炪�����������Ƃ��������B
�@�g���N�����A�w����ǂɗa����B��Ղ��������H���A�҂����A�Ɖ������Ăė������̂������B
���@�@���X�^�[�T
���@�@�@�@��
�@�T�C�|�b�c�̑S�R�͎l�\���ɒB���Ă���B���̂����\���l���C�j�V�G�̐X�ɂ����B�X���Ő���Ă���B���X�^�[�T���R�͑��߉q�t�c�𗦂��A���łɔ��N�Ԃɂ킽��킢���Â��Ă����B���m�����̂��ׂĂ��A���[�A���c�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��������A�R�������������c�Ɏx�z����Ă���B�N���܂Ƃ��Ȃ̂����킩��Ȃ����B
�@�ŏ��̂����A���X�^�[�T�����̓i�o�z��S���A�e�Ƃ������X�̔ؑ��Ɛ���Ă����B�����A���ł͂܂������ʂ̐킢�ɋꂵ��ł���B���o���݁A�������A�����̂��߂ɖ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����B���|�̂��߂ɔ���������̂����������B���m�����ʼn�ł�������������B�r�ō��͐X�̖������łȂ��A�T�C�|�b�c�̌R���������ݍ���ł����B�ꖜ�l�����t�c�͎U��U��ɂȂ�A�ؑ��Ƃ̐킢�ɑ唼�����𗎂Ƃ��Ă����B���E�҂������A�������ł̏��������s���Ă���B���͂�ړI���������g�D�Ƃ͂����Ȃ������B���m�����͌��ɋQ���A���߂��Ȃ��܂܂ɂ���Ȃ�E�C�𑱂��Ă������炾�B�����҂̂����A�ӂƂ������q�ɐ��C�ɖ߂�҂������B���������҂͎���̋N�������߂̏d���ɋꂵ�݁A�ς����ʎ҂͎��疽��₿�A���ɂ���ʂ��͍̂Ăє������邵���Ȃ������̂��B�m�[�}�������R���ɏ��������߂Ȃ������̂́A���܂��܂ȈӖ����琳���������Ƃ�����B
�@���X�^�[�T�̎茳�ɂ͎O�S�l�̕������c���Ă������A���̎O���ŕS�l������܂łɐ������炵�Ă���B�S�l�͐퓬�Ŗ��𗎂Ƃ��A�c��̂��̂͐��C���Ȃ����A�X�̉��[���ւƎp���������B�C�j�V�G�̐X�́A���C�̉Q�Ɉ��܂�Ă����B���X�^�[�T�ɂ��l�Ԃ炵���v�l���c���Ă��Ȃ��B�ނ�͋���ȖړI�ӎ��݂̂œ����Ă���B�B��l������̂́A�łڂ��A�Ƃ������Ƃ����������B�����X�[�Ɩ����C�j�V�G�̎푰���E�C���Ă����Ƃ��낾�����B�i�o�z���͋��낵�����肾�B���̎萨�ł͕Ԃ蓢���ɂ�������������Ȃ��Ƃ����̂ɖ��d�ȍ��s�������Ƃ�Ȃ������B���X�^�[�T�ɗ�ÂȔ��f�͎͂c���Ă��Ȃ���������ł���B
�@�i�o�z�����́A���łɉ��҂��ɏP��ꂽ�ゾ�����悤�ŁA�����͕��S��Ԃɂ������B���X�^�[�T�ɂƂ��Ă͂��ɒP���ȎE�C�������̂��B�����I������A���X�^�[�T�͕��ɋx�����Ƃ点���B
�@�e���g�ɓ��萇�����Ƃ����B���̍��͂낭�ɖ��ꂸ�A�����Ă��������݂���肾�B����ǁA����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B�͔̂�J�������Ă������炾�B�ނ͖���Ƃ������Ƃɋ����ϔO�ɂƂ���Ă����B�x�����Ƃ�˂Ō�Ɏc�����킸���Ȑ��C����A�����Ă��܂��ɂ������Ȃ������B
�@�����݂��B�ނɎc�����l�Ԃ炵�������́A�������邱�Ƃ����ۂ��Ă����B���҂�����A�����̂������Ƃ�����܂˂Ȃ�Ȃ����炾�B����ɂւ�����Ō�̃V�`���[�̂悤�Ȋ������������A���̎��Ԃ�N���ɓ`���˂Ƒi���Ă����B�ނ͍��ł͂悫���e�ł��������A��������́A���̐e���A�Ƃ��Ă��M���̂����j�������B�ؑ��Ƃ̉v�̂Ȃ��푈�ɂ͔��������B���ꂪ�A���܂ł́c�c�B
�@���̒��ɂ͂��������ȊO�̒N���������B���X�^�[�T�͂��̒j�̂��Ƃ��A���̕��ƌĂ�ł����B����Ȃ�����A�S�̒�ł͐M�Ă����̂ł���B���̕��͋��|�����炰�A���ׂ����Ƃ������Ă����B
�@���X�^�[�T�́A�V�k�Ɩ��A���N�̎p�Ō����B�}�[�T�̂��Ƃ͒m���Ă������A��̓�l�͌��o�����Ȃ��B���X�^�[�T�͏��N�������勾�ʼn����s���������ł���������m�炳�ꂽ�B�d�����A�ƒN���������₢���B�������}�[�T�͋{�얂�p�t���A�ƃ��X�^�[�T�͍l�����B���A���̖��������ǂ�ꂽ���Ƃ��v���o���B��l�̎q�ǂ����A�}�[�T�̒�q�ł��邱�Ƃ�m�����B�}�[�T�͂���܂Œ�q���Ƃ������ƂȂǂȂ��B���{�̋��Ă��Ȃ��̂��B
�@���̕��́A�V�k��߂炦�A�q�ǂ����E���ƌ������B�����W�̂Ȃ��҂��E���̂͂��₾�A�ƃ��X�^�[�T�͓������B������͎q�ǂ����B�q�ǂ��ɖd���Ȃǁc�c
�@�����A���̕��͎O�l�̎�����M���ۂ�������B���X�^�[�T�̎c�������C�͏������ڌ��肵�Ă������B�₪�Ă͎����̂��ׂ����Ƃ��悤�₭���������̂��ƍl����悤�ɂȂ����B���̐X�ɂ����ړI���悤�₭�킩�����B���������̎����A���ʂł͂Ȃ������̂��B
�@�C�����ƁA���X�^�[�T�̂܂��ɂ́A�߉q���t�c���������Ă����B���X�^�[�T�͎��l�𗦂��āA�}�[�T����P�����B
�@���̒��ŁA�O�l���E�����B���x���B���x���B���x���B
�@���x�ł��B
�@������o�߂��Ƃ��A���X�^�[�T�̎c�������C�͏������ł����B�]�̌��ǂ��j�ꂽ�炵���A�ڂ͐Ԃ��[���������Ă����B�ނ̖����A���������Ȃ��B
�@���X�^�[�T�̓e���g���o��ƁA�������W�߂��B���̕��̌P�����ꓯ�Ɏ������߂ł���B�ނ̕����́A���͂⎩�������ŖړI��T�����Ƃ���ł��Ȃ������B�E�C�̏�M�ɐg��C�������ŁA�v�l����ӎu���c���Ă��Ȃ��̂��B�����A�ړI������Εʂ��B
�@���X�^�[�T�͂��̎O�l���ǂ�قNjɈ�����M�S�ɂƂ��A�����k���������������̖ڂɁA�����̉���������̂����ɒ��߂��B
�@���߉q�t�c�́A�V���ȎE�C�����߂Đi�R���n�߂��B����͋߉q�t�c�̍Ō�̍s���������B
���@��\�́@�}�[�T�̍r�C�s
���@�@�@�@�\
�@�m�[�}����������������A�q�b�s�͑�Z���������B�X������Ƃ��Ă܂��A���ꂽ���̕��������B�߂��̏��삩�琅�����ނ̂��ނ̖�ڂ������B�}�[�T�͍���Ƃ����̂ɁA������l�ł��������Ă���̂������ςȂ��Ƃ������B
�u���̖����ڊo�߂���A�����ɏC�s���J�n�����v
�@�ƃ}�[�T�͌������B�}�[�T�͈ӊO�Ȃقǂ܂߂܂߂����A���̐��b���Ă����B�����x�����܂��A�����̎w�������C�悭�������B
�@���̓}�[�T�̕��𒅂���ꂽ�܂܁A�ڊo�߂�l�q���Ȃ��B
�@���������x������ڂ��o�܂����̂́A���̓����̂��Ƃł���B
�@�ڂ��J�����u�ԁA����̃}���V�����ɂ���̂��Ǝv�����B�z�c�ɐQ�Ă������炾�B�����ǁA�V��ɂ����̌u�������Ȃ��B�p�W���}�łȂ��A�ւ�Ă��ȃ��[�u�𒅂����Ă����B�e�ɂ́A�������Ƃ��Ȃ���������B���́A�܂����̐��E�ɂ���A�����玸�s�����A�Ǝv���ƁA�{����o�����ɂ͂����Ȃ������B�Ȃ�قǁA�i�o�z�����瓦���o���A�N���̉Ƃɂ͓������߂����̂炵���B����ǁA����ł͏��D�]�����Ƃ͂ƂĂ������Ȃ��B
�@�s�v�c�Ȃ��Ƃ͑��ɂ��������B����U��Ɠ��ɂ͎c���Ă������A���̂Ƃ��̂Ђǂ���J���܂�łȂ��B�]���܂邲�Ɛ�ꂽ�悤�������B
�u�ڂ��o�߂��̂����H�v
�@���͓��˂Ȑ��ɋ������B������������ƁA�M�����Ȃ����炢�ɔN�V�����V�k����l�ň֎q�ɍ��|���Ă���B���̒��Ă��镞�Ɠ������̂��B�ޏ��͋}�ɋL�������߂��āA
�u���Ȃ����}�[�T�H�v
�u���̂Ƃ���v
�u�����Ă��ꂽ�́H�v
�u�������Ȃ��ˁv
�u���肪�Ƃ��c�c�v
�@���C�Ȃ������ƁA�z�c�̒[���M���b�Ƃ˂������B�V�k�͗��̊�������Ɣ`���Ă���B
�u��͂ǂ����ˁv
�u�悭�Ȃ����Ǝv�����ǁc�c�v
�u���ǁH�v�Ɩ₢�Ԃ����B�u���ǂȂ��B�͂����肢���ȁv
�@�������������B���͊�������߂��B
�u�����̑̂���Ȃ��݂����ŁA�C����������ł��v
�u���낤�ˁB���܂��͖���������������B���̂����v
�u�������A�����ƐQ�Ă��H�v
�u�������ˁv
�u����ȂɁH�v�Ɛg���N�����B�u���肢���c�c�I�v
�u�҂����A���̐�͕��������Ȃ���v�ƃ}�[�T�͂�������B�u�����������肩�͂킩���Ă邩��ˁB������A��ɂ����Ă����B�������͂��܂������̐��E�ɂȂ�Ė߂��Ȃ��B�߂����@���m��Ȃ��B�������ˁv�Ɗ{�ōl�����ސU�������B�u�������̎t���Ȃ�A���Ɉ�m���Ă�����������Ȃ����c�c�v
�u���̂��t������́H�v
�u�Ƃ����Ɏ��܂�����B�����Ԃ�̂̂��Ƃ��v���������ڂ����A�w������Ɋ�肩����B�u�t�������܂�������A�ւ���Ă����������{�t���̖����ɂȂ����v
�@���{�ƕ����ė��̓}�[�T�ɂ�������y���A�]�ƁA�������]���o�����B�}�[�T�����{�̂������Ƃ������炢�n�ʂ̍��������Ȃ̂Ȃ�A�ޏ������閂�@�g���̓T�C�|�b�c�ɂ͂��Ȃ����ƂɂȂ邩�炾�B
�@�}�[�T�͋C����蒼���悤�ɗ����ς��B�u���ƌ������ˁB���܂������̐��E�ɗ����̂͋��R�Ȃ낤�B�ԈႢ�Ȃ������v
�u����v
�u����Ȃ��A�͂����v
�@���͐O�����B�Ȃ�ł���Ȃ�����Ɉ̂����Ɍ����Ă�낤�Ǝv�����B�u�͂��v
�u��������������B���d�ɂ���ׂ�ȁB�������͖ڏ�Ȃ���ˁB�\�\���āA���܂��͌��̐��E�ɖ߂肽���Ƃ������A�����߂�Ȃ������ꍇ�͂ǂ�����H�v
�u����ȁv������𗧂Ă��B�u���̐l����������Ɏ����������ɌĂ�Ȃ��v
�@�}�[�T�͂҂����Ɗ���@�����B�u�l�̂����ɂ��ĂȂ�ɂȂ�B�����炾���ČĂт����Ă��܂����Ă�Ȃ��v
�u���̐l�����͂ǂ��ɍs�����̂�v
�u���ɖ߂����\�\�v
�u����ȁv���Ɏ�āu�������̂ĂāH�v
�u�l�����̈������Ƃ�������Ȃ���B�����炾���đ�ςȂB���ɖ߂������������Ɗ댯��������Ȃ�����ˁv
�@���͂܂��q�b�s�̋L�������ǂꂽ����A�}�[�T�̂��������Ƃ͂����ł͂Ȃ��Ǝv�����B�ޏ��͂��Ȃ������B
�@�}�[�T�͗����w�ł����A�u���̂����A�q�b�s�͎茳�Ɏc���Ă���B���܂��Ƃ͐��_���Ȃ������܂��Ă邩��ˁB���܂��͂����킩���Ă邾�낤���A���̂ւ�̂Ƃ�����R���g���[������p��g�ɂ��Ă��炤�B�ȒP�Ɍ����A�������Ȃ�̏C�s���Ă��Ƃ��B���肪�����v���ȁv
�u�����ɂȂ���Ă����́H�v
�u����Ȃ����m��Ȃ��ˁv
�u��k����Ȃ���B�킽���͑������Ƃ̐��E�ɖ߂肽���̂�I�v
�u���ق�I�v
�@�}�[�T�͘V�l�Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȑ��ŗ���ق点��B
�u�߂���@��������܂ł͎d���Ȃ����낤�B����Ȃɖ߂肽����Ⴀ�����łȂ�Ƃ�����Ⴀ�����B�������͂��܂��̎菕���Ȃ�āA�܂��҂炲�߂�Ȃ���ˁv
�@���͉������Ėj�����B����ȏ�N���̓s���ŐU��ꂽ���Ȃ�ĂȂ��������A�}�[�T�̏������Ȃ��͍̂���B���̐��E�ł͈�l�ڂ����ŁA���܂��ɂ������ǂ��Ȃ̂���������Ȃ��̂ł���B����ł��A���ꂾ���͂������������B
�u�������̐��E�͂ǂ������m��Ȃ����ǁA���̐��E�ɂ͖����Ȃ�Ă��Ȃ��̂�v
�u�����ǁA�\�z�����Ȃ����Ƃ��N�����Ă��܂��͂����ɂ��邶��Ȃ����v
�@���͂܂��ق�B
�u�����Ƃ��A���܂������@�Ȃ�Ă��̂�M���Ă��Ȃ��Ƃ�����Ȃ�A�Ȃ����炯�������A�]�v�Ȑ����������Ԃ��͂Ԃ���B���܂������@��s�v�c�Ȃ��̂ƍl���Ă�낤�B���܂����l���Ă�悤�Ȗ��@���������͎g��Ȃ��\�\�g���Ȃ���B������A���܂������̑z�����閂�����Ă̂́A���̐��E�ɂ����Ă��Ȃ��B��������������̂́A���_��ӎ��𑀂�p�Ȃ�B����͂��܂�������܂ł���Ă������Ƃ̉����ɂ����Ȃ��B���|���̂��悤�Ƃ�����A���o��}���������Ƃ������Ƃ̂���B����͂킩��ˁH�v
�@�������Ȃ����ƁA�}�[�T�͉s���A�u�Ԏ������ȁv
�@���͂���ȘV�k�ɓ{����̂��������āA�͂��A�Ƒ吺�ł������B
�u�������������B�������������������Ă����ȁB�������ɖ߂肽���Ƃ������A�������̏C�s�́A���܂������̂�����邢���̂ɑ��Ă����āA�����ƌ��ʂ�����͂����B�S���Ւf����p���o���Ȃ����A��邢���̂ɂ����ɉe�����ꂿ�܂���B�����̐��E�ɖ߂��Ă��A���܂��͂����ɎE���ꂿ�܂���Ȃ��̂����H�@�q�b�s�̂����Ƃ���Ȃ�A���X�͕��ʂ̎q�ǂ��ɉ߂��Ȃ�����ˁv
�@���͂��Ȃ������B���ꂩ�炷���ɁA�͂��A�ƌ������B�}�[�T�͖ڂ����s���āA�Ȃ��|�������B�ޏ��ْ͋��ł�����Ɩѕz��������߂��B
�u���ĂƁc�c����������q�����������Ƃ͂Ȃ�����ˁB�t���������̂������Ɛ̂��B�l�ɕ���������Ȃ�Ăł��邩�ǂ����킩��Ȃ��B����ł�����Ă݂邵���Ȃ��B����́A�킩��ˁv
�u�͂��v
�@���͂�����ƕ��S���Ă������A����ł��������O�ɐi�߂��C�������B����Ƀ}�[�T�͊J�����҂낰�Ȑ��i�̂悤���B�����������������Ă���邱�Ƃ��A���͂��肪�����B�B���������������A�����Ƃ悩�������炾�B
�u������������B�������̑O�ŋ����Ȃ����ƁB�䂪��������Ȃ����ƁA�ނ�݂ɂ��̂�q�˂Ȃ��A��������������Ȃ���������A�������̂������Ƃ��悭�������Ɓv
�u���ꂾ���H�v
�u���Ƃ͐����lj����v
�@�����֊O����q�b�s�������Ă����B��������Ă���B�N���オ���Ă��闘�����āA�����𗎂Ƃ����B
�u���B�����������肢���́H�v
�@���͂��Ȃ����A���ŋ����o�����B���m�����炪������āA�ǂ��ƈ��S�����̂��B�q�b�s�͂�������Ă������ɏƂ�A�����������B
�u�������ڂ��o�߂Ȃ���ŐS�z������B�����ɗ��������邩��c�c������H�ׂĂȂ��A���Ȃ�������H�v
�u�������̕�������v
�u�����H�ׂ�����Ȃ��ł����B�d���Ȃ��ȁc�c�ޗ�������ȂɂȂ��̂Ɂc�c�v
�u���܂����Ƃ��Ă��������v
�u���ق��Ă���������B�X�͊댯�Ȃ���v
�@�q�b�s�͂Ԃ��������Ȃ�����A���ɂ��邩�܂ǂɗ������B
�@�}�[�T�͗������Ă������B
�u���܂��A�����͂ł���̂����H�v
�@���͎��U�����B���ꂩ��}���ŁA�u�������v�ƌ������B
�u���̂����ɂ����B����́H�@�|���́H�v
�u�ł���Ǝv���܂��v
�u�}�[�T��������A�a�ݏオ��ł���v
�u���ق�B�H����Ȃ瓭�����Ƃ��B�����Ȃ��Ȃ�A�H��Ȃ����Ƃ��B�т�H��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA��ꂽ�Ȃ�Ă����Ă��邩���H�@����������A�����ɂȂ�̂��H�v
�u�}�[�T��������͂���ŋC������ł�����ł���v
�u���ق�v
�@���͓�l�̌��_�������Ȃ���A�x�b�h�ɉ��ɂȂ����B���̃K���X�z���Ɍ��m��ʐX�������B����ŁA�܂������܂��o���̂������B
���@�@�@�@�\��
�@���̓x�b�h�ɍ������܂܂ł���B�q�b�s�̎����Ă����H����H�ׂ悤�Ƃ����Ȃ��B�H�~���킩�Ȃ��̂��B�����̊W�ŁA�A���ǂ���Ă���݂������B
�@�����͍��������Ă���B�ł��A����q����������Ȗڂɂ����Đ����Ă���Ƃ͎v���Ȃ������B���̂Ƃ��ޏ���́A�����𐬂������邽�߂̃O���[�v�������B�����ǁA���܂��肳�܂�������Ԃ��ƌ��߂����_�ŁA�Z�l���ۂ����p�Y���͉����������Ă����B�������Ȃ��Ȃ邱�ƂŁA�s�[�X�������邱�Ƃɂ��Ȃ����B�����ƂȂǂ��Ă����Ȃ��̂ɁA�̂����C�͂��Ȃ��B�������邪�A���܂��肳�܂ɖ߂邱�Ƃ����낵�������B����q�����ɂ͉�����B����ǂ���Ȗڂɍ����̂͂������₾�����̂��B�������ċ����邱�Ǝ��̂�����q���������̂Ă邱�ƂɂȂ肻���ŁA���C�������B
�u���͂ǂ��Ȃ�́H�v
�u�ڂ��ɂ͂킩��Ȃ��v�q�b�s�͐����Ɍ�����B���_�̂Ȃ������ޏ��ɂ���������͂����Ȃ��������炾���B�u�}�[�T��������ɂ��A�N�����̐��E�ɖ߂�����@�͂킩��Ȃ��炵���B�V���̐_���͂��̎O�l�ȊO�ɂ��Ȃ����c�c�v
�u���Ⴀ�A���̂܂�܂Ȃ́H�v
�@���͗ܐ��ł���B�q�b�s�͐S���ɂނ̂���������߂Ă���B
�u�킩��Ȃ���B�����ǁc�c�v
�u����q�����A��������ł邩������Ȃ��v
�@�Ɨ��͓��˂ɂ������B����͐S�̒��ɂ����Ƃ����čl���������Ȃ��^�₾�����̂����A���ɂ����u�Ԃ���ق�Ƃ̂��Ƃ̂悤�Ɋ�����ꂽ�B�ޏ��͈ꑧ�ɂ���ׂ����B
�u�����āA�������Ȃ��Ȃ�������B��l�ł��������炾�߂Ȃ̂ɁA������ȂƂ���ɂ���B����Ƃ��A�݂�Ȏ������̂Ă��́H�v
�@�����ӂ�ނ����̂ŁA�q�b�s�ɂ������炪�������B����ǖڐ������炵���̂́A�q�b�s�̂ق��������B
�u����Ȃ͂��Ȃ���v
�u���Ⴀ�A�݂�Ȏ��B�����������ɖ߂��Ă��A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��v
�u�܂��A�킩��Ȃ�����Ȃ����v
�u�����āA�������ɖ߂��Ă��A�܂��������Ȃ��ڂɍ����Ɍ��܂��Ă�B���A����Ȃ߂ɑς����Ȃ��v�ޏ��͐ӂ߂��Ȃ�ӂ߂�Ƃ����݂����Ƀq�b�s���ɂށB�u�ꂳ��╃����ɂ��A�������B�ƂɋA�肽�����ǁA���ʂ�ɂȂ��Ă�͂��Ȃ�����B���܂��肳�܂ɍs���Ă��A���ɂ��킩��Ȃ���������v
�u����͂ǂ����낤�ˁv�}�[�T�������B�u���܂��͂��̐��E�ɗ�������Ȃ����B����͋��R�Ȃ낤���ˁv
�@���͔����Ђ��߂�B�q�b�s���A
�u�ڂ���͌��o�����Ă��낤�B�}�[�T����������ȂB����ɂڂ���݂͂�ȁA�������t���Ă���v
�@���͌�����������B���̉ĉ��x�����������t�A���E�͂˂��܂����Ă���A�Ƃ������t���܂����������C�������̂��B
�u������āA�������A�Z�l�Ƃ������Ă��v
�u�}�[�T���������������v
�u�ǂ��������ƁH�v
�@�q�b�s�͌��ɂ���̂�����悤�ɁA�����Ԃ�u�����B�u���ꂪ����Ȃ錾�t����Ȃ��Ƃ�����A�ǂ����낤�H�v�ƌ������B�u�����ɋN�����Ă��邱�Ƃ��Ƃ�����H�@���������C�������B�V���͎��s������Ȃ��A�˂��܂���ꂽ�B������A�N���o�Ă����B�܂�c�c�v
�u�n���n�������A����Ȃ��Ƃ��Ȃ��N����v
�@�}�[�T�͖����Ȃ̂ɐM���Ȃ��悤���B
�@�ł��A���ɂ͂҂�Ƃ����B���܂��肳�܂ł́A�F��Ȏ���̎��̂��݂��B�F��Ȏ���ɍs�����Ƃ��ł����B��Ԃ��˂��Ȃ����Ă����̂��Ƃ�����m���ɐ����̂��C������B
�u����ɁA����͂����̌��o����Ȃ������v�Ɣޏ��͂Ԃ₢���B��l�̎��������ɏW������B�u����͌��o����Ȃ�������B�F�߂����Ȃ��������ǁB���������x���b�������B���o�Ȃ�A�G�ꂽ��A�G���Ă����肷��͂����Ȃ��B����q�̂�����A����q�̂��ƂЂ��ς���������v
�u�ǂ��������Ƃ����H�v
�u�m���Ă�ł���H�v�ƍ��x�̓q�b�s�Ɍ�������B�u�؈�̉ƂŁA��邢���̂́A������ɂȂ����B������A�݂�Ȏ��炪�|�����Ă���̂ɕϐg����B����q�����́A�z���������ɂȂ�Ǝv���Ă��c�c�B����ɁA�؈���Đl�͂Ȃ�ł������܂��肳�܂ɂ����B���܂��肳�܂ɂ��āA���̘r�����Ă�����B�������Ă����B��������Ȃ��v
�@�}�[�T�ƃq�b�s�͌��t���Ȃ������B�ł��A�q�b�s�͗��ƋL���̈ꕔ�����L���Ă������A���ł����_�������������Ă����B���͂����������Ă��Ȃ��A�S���{���ɂ��������ƂȂƔނ͐M���邱�Ƃ��ł����B�q�b�s�͂��Ȃ������B
�u���A���Ȃ�M������v�Ɣޏ��͒��߂�����B
�u�ł��A�������v�ƃq�b�s�͌������B���͕����Ԃ����B
�u�����������������B�ڂ���̐��E�ł́A�z���̌������Ȃ�ċN�����ĂȂ��v�q�b�s�͌����������B�u������Ȃ��ł���B�N�̌��t���^���Ă�킯����Ȃ��B�ڂ��͌N�����܂��肳�܂Œ؈���Đl�ɉ�����̂��m���Ă�B�������ʼn����������̂����v�����炱���A���E�̂˂��܂���ɍl�����y�̂��̂����B�u�ڂ��͌N�̘b��M�����邯�ǁA����ł��킩��Ȃ��v�}�[�T�Ɍ������āA�u��邢���̂��Ă����̂͂Ȃ�Ȃ�ł��B�Ȃ��ڂ���ɂ́c�c�v
�u�܂��A�҂��Ȃ�B��邢���̂��Ă������t���̂́A���̎q�炪�l�������̂��낤�v
�u�ł��A�����Ɂv
�u�܂��A���������Ȃ�B���ꂩ��A�������̍l����b����B�������͂��܂�����A������x�̂��Ƃ��Ă邩��ˁv�ƃ}�[�T�͍��𗎂������������B�u���������t���ɂ͂��낢��w���̂���B�����ɃG�r�G�����Đl����ꂽ�킯����Ȃ����ˁB�m�����\�͂��G��Ȃ��܂܂��B������A�����t���Ȃ�Ȃ�Ɠ����邾�낤���A�Ƃ����ӂ��ɍl���邱�Ƃɂ��Ă���B�܂��A���̕Ȃ݂����Ȃ��ˁv
�u�G�r�G���Ȃ�A�Ȃ�Ƃ����Ǝv���܂��H�v
�u�t���Ȃ�A���������̌��̋��L���A�����o���Ƃ������낤�ˁB�Ƃ����̂��A�l�̈ӎ��͒�̕����ł����������Ă���Ǝt���͂����Ă����B����ȏW���ӎ����`�����Ă���Ƃ����ˁv
�@�q�b�s�͕s�R�Ȋ���������A���͂��Ȃ������B���̐��E�ɂ�(���@�ł͂Ȃ��A�S���w�ɂ���)�����悤�ȍl�������������炾�B
�u�����A����q�����ƌ������̐}���قŒ��ׂ��B�W�����ӎ��Ƃ��A�S�̈ӎ��Ƃ��A�����Ă������v
�@�}�[�T�͂��Ȃ������B
�u�������ˁB�ǂ�����t�͂��������A�������Ƃ��Ă��邱�Ƃ͓������Ǝv���B���ׂĂ̐l�Ԃ̈ӎ��́A�O�i�K�̑w�ɂȂ�(���݈ӎ��A���݈ӎ��A�W�����ӎ��̂��Ƃ炵��)�A��̕����łȂ����Ă���B�����āA�ӎ��Ƃ������̂́A���܂���̂��B�����̎t���́A����܂Ő������S�ẴT�C�|�b�c�̈ӎ���L���́A���ӎ��̑w�ɗ��܂葱����ƍl���Ă����B�������͎t���̂��Ă������ɉ߂��Ȃ����ˁ\�\���������[�������A���i�͊�����ꂸ�l�������Ȃ��ꏊ�ɁA�ǂ�Ȏ҂��Ȃ����Ă���̂��Ƃ�����H�@�\�\��͂肻�̏ꏊ������A�l�͉e�����Ă��邱�ƂɂȂ�v�Ɠf�������B�u�����ł��B�S�̈ӎ��ɗ��܂��Ă�����̂��A���������肾�Ƃ�����H�@���������ӎ��̕��������Ƒ���������H�@���̎����ɂ��邠���������ɂ��A�����e�������邩������Ȃ��v
�u�ł��A���̌�����邢���̂́A�����̐��E�ł̘b�ł���B�W���ӎ����[�������̘b�Ȃ�A�����̐��E�Ƃ͖����Ȃ͂��ł��傤�H�v
�u�����ŁA���܂��̂������˂��܂����ˁv
�u�M�����ł����H�v
�u�M���Ă���킯����Ȃ���B�����A�t���Ȃ�l���ɂ͂���邾�낤�ˁB�ǂ�Ȃ��Ƃ��\��������̂Ȃ�A��l�͂����ɂ������Ȃ���B���E�⎟�����˂��܂����āA�ʒ�ӎ��̎������A�����������̎����ɁA��苭���e����^���n�߂��̂��Ƃ���Ȃ�A�ꉞ�̐����͂����낤�ˁv
�u���������ǁA�\���͂���Ƃ������Ƃł��ˁv
�@�}�[�T�͂��킢��������B
�u���܂��͂���ς�^�b�g���̒�q���ˁB�c�_�D���Ȃ͍̂l��������v
�@�q�b�s�͏Ƃꂽ�悤�ɂ��߂��݂��������B
�u�Ƃ�����A���ꂪ�����Ȃ�A�T�C�|�b�c�����܂��������A���j�̂Ȃ��ŁA�����ӎ��𗭂߂��������ƂɂȂ�B�W�����ӎ��̉e��������������Ȃ���B����ɗ��́A���������e�����A��邢���́A�ƌĂ�ł���v
�u�ł��A����Ȃ��ƂɂȂ��Ă�Ȃ�āA�l���Ă��݂Ȃ������v
�u�������ˁB�����ǁA�l�Ԃ��Ă̂́A������������Ȃ����ςł������Ă���̂����A�^�������̂͗��������Ђ�߂��������Ǝv���B���@���Ă����̂́A�M���ɂ�钼�ϗ͂�{�����̂ł��������ˁB�������A�����������������������������Ƃ����킯����Ȃ����v
�@���͂�������������B�����Ƃ͂����肵���������~�����������A���ɂ����Ȃ����Ƃ��L�ۂ݂ɂ��Ă͂����Ȃ��Ƃ����}�[�T�̍l���������ł����B
�u�������͂��܂������̐��E�ɗ����̂����R����Ȃ��悤�ȋC�������B���܂������͎��������ɍ~�肩�������Ђ����A���������ƌĂ�ł������ˁv
�@���͂��Ȃ����B
�u���̐��E�ւ̗U���������Ƃ������Ƃł����H�v
�u�킩��Ȃ��B�����N���������Ƃɂ͕K��������������̂Ȃ�B����肠�����́A�����̊��Ƃ������̂�M���Đ����Ă��邵�ˁv
�@�q�b�s�͎�𐂂�Ē��v�ٍl�����B�}�[�T�����E�̂˂��Ȃ����M�������Ȃ����̂킯�́A���ꂪ�����������ꍇ�ɁA�Ώ��̂��悤���Ȃ�����ł͂Ȃ����Ǝv�����̂��B�}�[�T�͗������̐��E�ɗ������Ƃ����R�ł͂Ȃ��Ƃ����Ă���B�����ɐ��E�̂˂��܂���������������A�Ɨ��ł͌��������悤�������B
�@�}�[�T�́A�N���������Ƃɂ͌���������Ƃ������Ă���B���E���˂��Ȃ���͂��߂��̂Ȃ�A����������̂ł͂Ȃ����낤���H�@�}�[�T�́A�W���ӎ��̈��̕������l�ɉe����^���A�s�M���ȋ^�������Ă���A�Ƃ����b�������B�ƍ߂̑��������Ȃ�����b���B�����Ɨ������͋��|�������邱�ƂŁA�W���ӎ��̈��������ĂъĂ����̂��낤�B���ꂪ�l�̈������ƁA���������̂�������Ȃ��B
�@�}�[�T�́A�����Řb��ł���Ƃ����B
�u�����A�т�H���đ̗͂�������B����ȏ㋃�����͕��������Ȃ���B�����o������ꂵ���B�������Ȃ��̂�U�蕥�����������痧�����������Ƃ��B�������������߂ɂ͗��K�����Ȃ��B�����A�Ƃ��ƂƐH�����܂��ȁB�����������Ă鎞�Ԃ͂Ȃ�����ˁv
�@���͍Q�ĂăX�[�v�����ƁA�łł����X�v�[�����g���Č��ɉ^�B����ł��A�܂��܂��o�āA�����ƁA�P�����B
���@�@�@�@�\��
�@�������炦�����ނƁA�}�[�T�͓�l��ǂ����悤�ɊO�ɏo�����B�Ƃ̎���͂��ꂢ�ɎG���������Ă���B�ޏ��͐芔�̈֎q�ɍ������낵�A�������͂��߂��B
�@�}�[�T�͂܂��͓�l��n�ʂɍ��点��ƁA�p�����`�F�b�N�����B�����ł��A�������ȍ����������ƁA�������}�ł͂����ꂽ�B���ʂȗ͂�����ƁA�}�[�T��������@���̂ł���B���ꂩ��A�}�[�T�͌ċz�̎d�����������B����w�ɂ킴�Ɨ͂����āA�ċz���������B����ƁA���₨�Ȃ����c��܂��A���܂����������Ă��Ȃ������B�͂���ꂽ�������ǂ̂悤�ɂȂ��āA��������Ȃ��̂��B�ċz�̂��߂ɂ��A�͂��̂���Ȃ�A�ƃ}�[�T�͌������B�Ƃ�����A���łȂ��̂ŗ�������A�Ƃ����s�ׂ͐V�N�������B�m���ɁA�ނ��ȗ͂�������Δ�����قǁA���̂Ԃ������Ă����B����ɁA�}�[�T�̂������S�������������������Ă���ƁA�̂��y�Ȃ̂��B
�@���ƃq�b�s�͂���܂łɂȂ����_�̗����������������B�}�[�T�͍��������݂āA���̒i�K�ɐi�B
�u�����������ė���B�܂��́A�U���Ɩh��̌P�����ɂ��B�U�����͈ӎ����W�����đ���̐��_�ɓ��肱�ނB�ۑ�͑���̋L�����̂����Ď�݂��݂��邱�ƁB�h�䑤�́c�c�v
�u���A����Ȃ��Ƃ������Ȃ��v
�u���ق�B�{�C�ōU�����Ȃ���A���K�ɂȂȂ�Ȃ���B�����������܂��������U�����邩��ˁB���܂���̎v���o�������Ȃ��L���܂Ŏc�炸�����ς�o���Ă��B���ꂪ����Ȃ瑁���h����o����v
�u�ǂ��������h�����ł��H�v
�u���ށv�ƃ}�[�T�͂��Ȃ������B�u���̈ӎ����Ւf���悤�Ƃ����ƌ������ˁB�勾�̂����ł��܂������̐��_�͂��������܂��Ă�B����̋L���⊴��A���o���A�ق����Ƃ��Ə���ɓ����Ă����܂��낤�H�@�܂�U���Ɋւ��Ă͊ȒP�Ȃ�v�}�[�T�̎w�����ƃq�b�s���s�����藈���肵���B�u���݂��Ɋւ��Ă͂ˁv
�u�}�[�T��������̂��Ƃ́A�U�����Ă�����ł����H�v
�u�s�\����Ȃ����A���ɑ��Ďd�|������͂����Ɠ���͂����B����A���܂��̓q�b�s�̐��_��T�����Ƃ��A�ǂ�Ȋ����������H�v
�@���͓���O�̂��Ƃ��ꐶ�����v���o�����B����ǁA���o���v���o���͓̂�������B
�u����Ă������A�G��݂����Ȃ̂��A���[���ƃq�b�s�Ɍ������ĐL�тĂ��݂����Ȋ����������B���̋C�ɂȂ�����A����q�̂��Ƃ��A�ǂ��ɂ��邩�킩�����肵������v
�@���͂킩��Ȃ�����ǁB
�@�}�[�T�͂��Ȃ������B���͎����̑̌��𐳊m�Ɋo���Ă���B����͂����X���ŁA�}�[�T�͐��_�̍��g���o�����B�˔\����ʂ�ł͂Ȃ��B��l�͏㋉�̖��@�g�������m��Ȃ��悤�Ȋ��o���A���̌����Ă���̂ł���B
�u�������ˁA�G��Ƃ����̂͂����\�����v
�@�}�[�T���������ق߂��̂ŁA��l�͋��S�n�������Ȃ����B
�u�ӎ���_�Ȃ�Ă��͖̂ڂɌ����Ȃ����낤�H�@��������������̂͌����Ȃ����̂������p�ȂB�����Ȃ����̂��m���Ȃ��̂ɂ�����Ă̂́A�{���ɑ�ςȂ��Ƃ��B���o�Ȃ�Ă��̂́A�l�ɂ���ĈႤ��ɂ����ɂ����܂��ɂȂ��ď������܂��c�c�o���Ă����Ȃ��ˁB������O�����B������A�����������o��厖�ɂ��邱�ƁB���t�ɂ��āA�������ɐ��������邩��A�����̓��ʂɒ��ӂ������邱�ƁB���o���Ɍ������܂��̂��ۑ�̈����B�U���̊��o���A�h��̊��o���A���܂������͂��łɒm���Ă���B����͖{���ɂ߂��܂ꂽ���Ƃ���B���������āA���������Ȃ��܂܂̓z���唼�Ȃ���ˁB������A���̊��o��Y�ꂸ�ɐ[���̂ɍ��ނB���ł��ǂ��ł��ł��邮�炢�ɍČ��������������ƁB���ꂪ�ڕW���v
�@��l�͊�������킹���B���o�����ڂ���Ȃ�āA���܂ł�����������Ȃ��B
�u�܂��A���������������Ȃ���B���o��Y��Ȃ����߂ɂ́A�����̌������肩�������Ƃ��ˁB�悤����ɔ������K����������̂��B���̓_�����܂������͌b�܂�Ă��B�l�Z�����A�C���ĂȂ����A�����ɐS���������������܂�����ˁB�����݂��ɐ��_���Ւf���Ă����Ԃ��Ǝv���v
�@�����Ă݂�Ƃ����������B�}�[�T�͂��̎Ւf���銴�o�͂ǂ�ȋ���A���@��t�@�肫�����B���͕ǂ����銴���������B�w���̂��A�Ƃ����̂��L���ȕ��@�������B�q�b�s�͗��̂�����^�����̂��ƌ������B�}�[�T�́A���_���R���g���[������̂ɁA�̂������̂͂������@���Əq�ׂ��B
�u���o�͂����܂����ƌ������ˁB������A����m�ɂ���ɂ́A�����ȍH�v������B���o�ɂ킩��₷�����O������̂��A�悢���@���ˁB�C���[�W��`���̂��L���ȕ��@���B�����A�����G�ɂ����܂��͍̂l�����̂���B�厖�Ȃ̂͂����܂ł����o�Ȃ���ˁB���G�Ȃ��Ƃ��V���v���ɂ��đ����邱�ƁB���G�Ȃ܂܂��Ƃ킯��������Ȃ��܂܂ŏI���B������A�P���ɑ����āA�[�����������ƁB�P���ɂƂ����̂́A�|�C���g���������Ƃ������Ƃ��B�����A�͂��߂悤����Ȃ����v
�@�ȒP�Ȑ������I���ƁA�����Ɏ��H���͂��܂����B����̐��_���U�����A�����h�䂷��B������J��Ԃ��̂ł���B�Ƃ��Ƀ}�[�T������ƂȂ����B�������͔]�݂����܂�������C���̈����ɂ̂��ł�������B�}�[�T�Ɏv���o�������Ȃ��L���܂ł܂�������̂��B
�@���ɂ̓}�[�T������邢���̂���Ȃ����Ǝv�������A�ޏ��͂��날�������Ďq�ǂ������ɋx�e���Ƃ点���B��l�͖ƕ�����̂݁A�}�[�T�������ƌĂԎw�������B������̂͏��߂Ă��ƃ}�[�T�͌��������A�ޏ��͂����ނ˂͂������t�Ƃ������B�����A�Ë��Ƃ������̂�m��Ȃ����A���̋���͂Ƃ��Ƃ��������B�Ȃɂ��A�����Ȃ��Ǝ��ɂ��˂Ȃ��قǂ̏C�s�Ȃ̂�����A�������̐h���͌����₵���B
�@����ł��A�S�̈ӎ��Ɛ���Ď��ȂȂ����߂ɂ́A�C�s���邵���Ȃ������B�}�[�T�́A�������������̐��_����ɂȂꂽ�Ƃ�������ĂƂ�ƁA������퓬�������A�Ƃ������̂����n�߂��B����͂������Ȃ�Ƃ����A���肪�C�����Ƃ��ɁA�P���Ă����Ƃ������̂������B�������A�}�[�T��������Ă��������A�}�[�T�̕�����U��������������������B
�@�C�s�͏�Z����ƂȂ����B
�@�}�[�T�͐H���ɂ��C���g���A�����͖��ӂ�Ɏg�������̂�H�ׂ������B�}�[�T�͂��̂��߂ɁA�q�b�s�ɖ���W�߂����Ă����悤�������B
�@���͂Ȃ�Ȃ����܂ǂł̎ϐ������q�b�s�ɋ�������B�ނ̓^�b�g���Ɠ�l�邵�����Ă��邹�����A�Ȃ�ł��ł��鏭�N�������B������ꖇ�ł��܂��Ă��܂��B
�@���͉���q�������S�z�Ŏn�I�₫�������Ă�������A�}�[�T�ɂ����₢�Ƃ𐘂���ꂽ�B���@�ő厖�Ȃ̂́A�W���́A�ƃ}�[�T�͌������B��B����ɂ́A�W���́A�W���A�W���A�W���A�W������A���̂���������B
�@�������Ĉ�����߂��A���ɂƂ��āA���̐��E�ł́A�����ڂ̗[�����߂Â����B
���@��\��́@�P��
���@�@�@�@�\�O
�@�����\�\
�@���X�^�[�T�����́A���ɉ��{���p�t�̏Z����T�����Ă��B�Z���Ǝv�킵�������肪�������B�������������A���҂��ɑ����Ă���Ƃ͂����A�������P�������̂������āA�ނ�͕��m�Ƃ��Ă̍s����Y��Ă��Ȃ��B
�@�ڕW������ɂ����߂�ƁA���m�����͎U�J���A�e�ɒe������ߎn�߂��B�e�X���K�E�̈ʒu�ɐg����߁A������߂Ă��̏u�Ԃ�҂���B��́A���R�̍��߂�҂����ƂȂ����B
�@���X�^�[�T�͐�Ȃ߂���������B���Ƃ��������낤�ƁA�e�e�ɑ_���ẮA�ЂƂ��܂���Ȃ��ɂ������Ȃ��B
���@�@�@�@�\�l
�@���̓X�[�v�̓������M�ƃX�v�[�������ɒu�����B�ԉ̂悤�ȉ������āA�Ƃ̕ǂ�����Ɩ�n�߂��B�}�[�T�ƃq�b�s�́A���₭�e�[�u���̉��ɐg���B�������A�e���Ɋ���Ă��Ȃ����͕�R�Ƃ������Ă���B�A�������������Ȃ芲�̍ӂ��鉹������B�q�b�s�͍Q�Ăăe�[�u�����яo���A�ޏ������Ɉ�������|�����B
�@���X�^�[�T�̌R���͂킸�����������A���Ɣ��߂����ďW���C�𗁂т�������A�����܂�����͍ӂ��ďe�e����э���ł����B�J�̂悤�ȉ����l�����狿���A�e�ۂ����ē�����ь������B
�u������Ă�́H�v�Ɨ��͂��Ԃ��ɂȂ�B
�u������O���낤�B�����������߂ȁv
�@�}�[�T����ɂ̂�������A������������B
�@�q�b�s�̓e�[�u����|�����ƁA�����Ɏ����A���^���Ԃɂ��ĉ����グ�͂��߂��B���݂��ꃁ�[�g�������錘�łȑ��肾�����B���ɂ͂ƂĂ��|����Ƃ͎v��Ȃ��������A
�u�����Ă�I�@���������|���I�@�E����邼�I�v
�@���ƃ}�[�T�́A�q�b�s�ɋ��͂��āA�����������B���̊Ԃ��A���X�^�[�T�����̍U���͂܂��܂����x���܂��āA�O�l�̑��̋�Ԃ������ߎn�߂��B��C�̏ł���������͂��A�畆�ɉΖc�ꂪ�N���o���ƁA�������̎O�l���Ύ���͂��N�����āA����Ȋ��������|�����B�����ӂ���قǂ̏Ռ����������A�ǂ��ɂ��e�ۂ͖h����悤�ɂȂ����B
�@���ɂ͐M�����Ȃ������B�q�b�s�����͔n�������_�����𒅂āA�V�����Ȃ�Ă����Ă����B���̐��E���A���������̕������x�ꂽ���E���ƁA����Ɏv������ł����B�i�o�z����X�̗d��(�Ƃ����v���Ȃ�)�����ł������ς������ς��Ȃ̂ɁA���e�Ȃ�Ď����o���ꂽ�炽�܂�Ȃ��B
�@�q�b�s�����̊p������`������ƁA�X���ʼnΉԂ��オ���Ă���B�ؗ��̍��ԂɌR���𒅂��j�������������B
�u�}�[�T��������A�������I�@���ʂ̗тɑ吨���܂���I�v
�@�}�[�T���e�[�u���̂����œf���������B�u������́A����Ȃ��ƂɂȂ��Ȃ����Ǝv�������ˁv
�u�������ăT�C�|�b�c�́H�@��������Ȃ��́H�v
�u�Ƃ�������Ȃ��B�������͏邩��ǂ�ꂽ�悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă邩��ˁv
�u������A�����ƃ��[�A���c����v�ƃq�b�s���������B�u�������̂���Ȃ��B�Ԓn�Ƀ��V���`���Ă���I�v
�u���悢����ɂȂ����ˁv
�u���₾��c�c�v�Ɨ��͌������B�\�����������ǂ������E�ӂ��ڂɌ�����悤�������B�O�ɂ���̂͐l�ԂȂ���Ȃ��B�܂������Ȃ���邢���̂������B�����������āA��邢���̂Ɏx�z���ꂽ�l�X�A�������؈�Ɏ����l�X�B���̎E�ӂ͕����I�ȏe�e�ƂȂ��āA�}�[�T�̉Ƃɔ�э���ł���B�e�e����������Ȃ����A���̎E�ӂ͔ޏ��̐g�̂��т����B
�u����Ȃǂ������킩��Ȃ��悤�ȏꏊ�ŁA���ɂ����Ȃ��B�������Ȃ��́H�v
�u�����ē�����̂����H�@���e�Ō����ꂽ�炽�܂���v
�u���@�łȂ�Ƃ����Ă�I�v
�u�܂�����Ȕn���������Ƃ������Ă�̂����v�}�[�T�͂����������B�u�C�s�����Ă킩�����낤�B���������g���̂́A���_�̗͂ɂ����Ȃ��B�W���͂ƍ����Œe���h����Ȃ�āA���֍ۍl�����Ȃ���B���𗎂Ƃ����Ƃ�����ˁv
�u�܂����ɂ����Ȃ���I�@����ȂƂ���Ŏ��˂Ȃ��I�v
�u�����������Ă���Ȃ����ˁv
�u�T�C�|�b�c�̕����Ȃ疡������I�v
�u���[�A���c�͋��낵�����Ȃv�q�b�s���������B�u�ڂ��̗F�������E�����̂́A�����炾�v
�@���͂�����Ƒ������B���̖��O�ƋL���͒m���Ă���B�u�W�u���̂��ƁH�v
�u�������v�ƃq�b�s�����Ȃ������B�u���̒��������Ȃ��Ă�̂����ă��[�A���c�̂������B�ڂ��炪���o������̂����āc�c�v
�u�u�`���������ˁB���݂��Ă���Ȃ������H�v
�@�}�[�T�����ɎU������ו����ǂ����Ă���B�悭����ƁA���ɐ^�l�p�̔����������̂��B
�@����ŕ\�ɏo����Ǝv�����u�Ԃɗ��͓f���Ă��܂����B�E�ӂ��O�l�̓��̂�ł��Ă���B�e�[�u���͕������������A�e�e�������邽�тɂ��̓�������Ă����B�ؕЂ��ォ�畑�������Ă����B�₪�ӂ���A�{�͈����ꂽ�B�ǔ��ӂ��āA���o���������B����юU��A�M�̐������ɗ����B�t���C�p���ɏe�e���������Ē��˕Ԃ�̂��������B
�@�q�b�s���S�̎������������������グ���B���������Ǝv�������A�ꂪ�ӂ�����Ă���B
�u���͎t�����������������Ȃ�v�ƃ}�[�T���Ԃ₢���B
�u�Ȃ�łӂ������̂�I�v
�u������A������������A�N���������Ă��悤�Ƃ����肵����A����ł��ӂ������낤�v
�@���͂��Ȃ������B�Y��Ă������A�}�[�T�������������Ă����̂��B�q�b�s���}�[�T�ɚ������B
�u���ɓ����ė���ꂽ��݂�ȎE����Ă��܂��B�ł��A�O�ɏo�����ē����������Ȃ��ł���v
�u�������ɍl��������v
�u�}�[�T�I�v
�@�Ƒ吺�������n��A�O�l�͍�Ƃ̎���~�߂��B
�u���X�^�[�T�̐����B����Ⴀ�A���R�̈�l����v
�u�m�荇���Ȃ́H�v
�u�m�荇�������A�匙�����v�ƃ}�[�T�͎����ނ����B�u�������������E�����Ƃ��Ă����ˁv
�@���X�^�[�T�́A����܂ł̎g�҂�ɂ����Ȃ������}�[�T�̔����U�߁A�����ɏo�Ă���悤�ɂ����Ă���B�}�[�T�́A�Ȃɂ����������邠�̂������A����𗧂Ă��B���̊Ԃ��e���͂�߂Ȃ��̂��B
�u����Ȃ̂܂Ƃ��ɑ��肵�Ă��Ȃ���B�o�čs�����瑦�����E�����肳�ˁv
�u������v
�u���ꂵ�����ɂ�����Ȃ���B�͂����E����v
�@�q�b�s�����ɓ����ď����͂����������B�}�[�T�͗��̌���������B
�u�����������ŕ\�̘A�����ǂ��ɂ�����B��납��_���������̂͂��߂���ˁv
�u�ǂ������ł��v
�u���܂��͌����Ђ낰�Ȃ��v�ƃ}�[�T�̓q�b�s�ɓ{���Ă���A�u�ł��邾���S�������߂�B�����A����o���ȁv
�@�}�[�T�͂�����������āA���̗�����������B���ꂩ��A�{���̎��H���A�ƃ}�[�T�̐����S�ɕ����������痘�͂т����肵���B�}�[�T�͖ڂ���āA�����������Ă��Ȃ��B�q�b�s�ɂ����������炵���A�ނ��ӂƎ���~�߂Č��グ��̂��킩�����B
�u���܂������A���@���������悤������A�����Ă�낤����Ȃ����c�c�v
�@���̓i�o�z�����v���o���A�u��邢���̂��Ăт����́H�v�ƌ������B�ޏ��͌����̓f�b���𐁂��Ȃ�����߂��B����ȏ�̈��ӂ�g�ɗ��т���A�C�������ɂ������Ȃ��Ǝv�����̂��B�}�[�T�͎���ӂ��Ĕے肵���B
�u������ɂ͌��ʂ��Ȃ���v
�@���͂�����畏��̂��Ƃ��Ȃ������B���������͂��łɏW�����ӎ��Ɏx�z����Ă���B�ނ�͈����҂��̂��̂������B
�u�ǂ����A��邢���̂Ƃ�������Ȃ������܂��Ă�ˁB�����̖{�����������Ă�v
�u�S�̈ӎ����āA�݂�Ȃ̈ӎu�ł���v�Ɨ��B�u�݂�Ȏ��˂��Ďv���Ă���Ă��Ƃ��v
�u��������Ȃ��B�������͂ˁA���������A��������B���̍������ɂ͑P������ƐM���Ă�B�����͂��Ȃ炸�I�������������̂ȂB���X�^�[�T�����āA�̂͐l�i�҂������B�����푈�Ő��C���ӂ��Ƃ낤�c�c�v
�@���͎������x�z����Ȃ������M���Ȃ������B�����̂��Ƃ�P�l�Ƃ��v���Ȃ��B
�u�������Ƃ���̌ċz�����肩�����B��������������ۂB�c�c�ł��邩�ǂ����킩��A��l�Ԃɂ�����������Ȃ�A�^�l�Ԃɖ߂��Ă�낤����Ȃ����v
�u��A�킩������v
�@�}�[�T�͈ӎ����W�����Ă���悤�������B�e�������̂��đ̂̊��o�������Ă����B�̂������Ƃ�Əd���Ȃ�A�₪�āA�ċz����������Ȃ��Ȃ�B��l�̐��_�͑̂��牓������A�ӎ��̐[�������ɓ��肱�B�C�s��ς��ł́A��u�ł��̏�Ԃɓ����悤�ɂȂ��Ă����B
�@���̓}�[�T�Ɉ��������A���������Ɛ��_�̐[�������ɂӂ݂���ł������B�C�s��ʂ��}�[�T�̗͖͂ڂ̓�����ɂ��Ă������A����قǂ̂��̂Ƃ͎v��Ȃ������B�}�[�T�͐��_�����݂ɑ����Ă������A�ӎ��̓͂��͈͂��L�������B
�@���݈ӎ������܂�A���ݖ��ӎ��Ƃ̓������n�܂�B�}�[�T�ɂЂ�������悤�ɂ��āA�[���w�܂ŗ����Ă����B����͖ڂ��o�܂����܂ܖ����Ă��邩�̂悤�ł��������B
�@�}�[�T�͈ӎ��̎��L���A���m��̐��_��߂܂������A���܂�̖���R�ɔ��q���������B���m�����̐S�͂�����ۂŁA���ӎ��������Ȃ������̂ł���B�Ö���Ԃɋ߂������B��l��l�̍����A�����E�ӂƊQ�ӂɂ݂�����Ă���B�S�̈ӎ��̈����w�ɁA�ǂ��Ղ�Ƃ����Ă���悤���B���ƃ}�[�T�͎�����ۂ̂��ނ������������B���m�ƂȂ������Ƃ���A�ނ�̊����L�����ǂ��Ɨ��ꍞ��ł������炾�B���̈��s�̐��X�ɂ͐g�k�����ւ����Ȃ��B���ꍞ�ސ��X�̐��S�Ȏ��̂ɂ́A�f���C�����您�����ɂ͂����Ȃ��B�ڋʂ���яo���A�荏�܂ꂽ���́B���C�Ăӂ���݁A���肫�������́B���������������ŁA�����̒��̑厖�ȕ���������ł��܂����悤�Ɋ�����ꂽ�B�}�[�T�̂������Ƃ���A���̍��������P�Ȃ�A���̍������͊m���ɏ�����ꂽ�Ɗ������̂��B���͎��������̐��E�̔ƍ߂��A�ǂ̂悤�ɂ��ċN�������̂������ł����悤�ȋC�������B�}�[�T�����Ȃ���A�������ĂƂ����ɂ�邢���̂Ɉ��݂��܂�Ă������낤�B
�@���N�C�s��ς��������āA��邢���̂ɐG��Ă��C�����킹�邱�Ƃ��Ȃ������̂��B�}�[�T���������������́A����͕��m������l��l�̋L���������B�����ɂ͌��ꂵ�������݂��������B����ǂ������ł͂Ȃ��B�e��Z��̈���A�F�l����l�Ƃ̊m���ȂȂ��肪�������B����ǁA�}�[�T���������Ƃ͂悢���ʂ������炳�Ȃ������B����̗����ɐG�ꂽ�l�X�́A���̍߂̐[���ɕ����Ď���̖���₿�n�߂����炾�B
�@�}�[�T�̌�Z�͂܂��������B�ޏ��̓��X�^�[�T�����𗠂ő���҂̑��݂�m��Ȃ��������炾�B�����́A���m��ɓ����������҂̑��݂ɂ����������Â����B
���@�@�@�@�\��
�@���m�����̉��ꂩ�牽��������Ă���B�ǂ������ċ���ȑ��݂��B�}�[�T�ł��炬����ƂȂ����B�����͂�������ڎw���Ĉ꒼���ɓ˂��i��ł���B�G�r�G���ɂ��犴�������Ƃ̂Ȃ�����ȗ͂������B�}�[�T�̐L�����ӎ��������܂������o�����B�c�c�}�[�T�͂������Ȃ����m���Ă���Ɗ������B
�@�}�[�T�͂�����ɂȂ��Ėڂ��o�܂����Ƃ���B�ޏ��̈ӎ��͈������̂悤�ɑ̂ւƖ߂��Ă������A�����͂������ǂ��������Ă���B�����ߖ������A�}�[�T�����𗣂����B�}�[�T�͎��R�ɂȂ�����������������_���Ւf�����B��������f���o���ƈӎ��̕ǂ��͂�߂��炵�A��������̂Ƃ���ł����̐N���������Ƃ߂��̂��B
�@�}�[�T�͌��𗎂Ƃ��ēf���������B�������݂�ƁA�������ɓ]���Đ��߂Ă���B
�u���̂͂Ȃ�Ȃ́H�@�����́c�c�v
�@�}�[�T�͓������Ȃ������B�������瓦���o���̂��挈���B�������̂���ǂ��ɂ���̂�����Ȃ����A�ƂĂ������ł��ł��鑊��ł͂Ȃ����Ƃ�������̂��B
�@�e���͂҂���Ƃ��ł����B�}�[�T�́A�q�b�s�̌���@���A
�u���܂�����s���B����������A�O�ɏo����v
�@�q�b�s������������p���������B�����������B�q�b�s�̍�������͔ޏ��ł��M���M���ʂ�邩�ǂ������B
�@���͐T�d�ɑ̂�ʂ��Ă������B����ȂƂ����Ƃ����̂ɁA�����̕��������Ă����Ȃ����Ƃ�����B���ł͌������̐��E�Ǝ������Ȃ��B��̂��̂������B
�u�킽���̕��v
�u������߂�A���͖������Ă̕��킾�낤�v
�@���͂����т�����ނƁA�������������B
���@�@�@�@�\�Z
�@����������ƁA�����͖̓��������B�Â������J�r�Ǝ������C�̏L���������B�̍��ɑ��������Ȃ����э~���B���܂������t�y�̂����ŁA�X�j�[�J�[���O�Y�O�Y�ƒ��B�����͌��ւƂ͋t�̕��p�ŁA�[���̂����X��������B
�u���̕��p�ɂ́A���������Ȃ��݂������v�ƃq�b�s���������B
�@���̓q�b�s�̑��Ɋ���āA�u�������̊������H�v
�@�q�b�s�����Ȃ������B
�u�������z��������ˁv
�u�����̐��̂����Ƃ߂Ȃ��ƁB����������������������Ă�v
�u����Ȃ̖�������v�Ȃɂ��}�[�T�����X�̑̂œ����o���قǂ̑���Ȃ̂ł���B
�u�ł��A���E���˂��܂��Ă�̂����āA������������Ȃ��v
�u����ȗ͂��������z�͂��₵�Ȃ���v
�@�}�[�T�̐����ォ�痎���Ă����B�q�b�s�����݂����B���͊������ɘr���������Ă������A�}�ɓ��������Â��Ȃ�ӂ�ނ����B�����̓����������ȉe���ǂ��ł���B���͂����̓f���o�����̏L����k���ߖ��グ���B
�@�^���ԂɌ���ڂ��������B���X�^�[�T���A�ƃ}�[�T�����Ԃ��A�����͂��͂⃀�X�^�[�T�ł��炠�肦�Ȃ��B�i�o�z���Ȃ݂ɑ傫���Ȃ��Ă������A�p���ς���Ă���B���ڂ������^�͂��邪�A�킸���Ȃ��̂������B���[�����肦�Ȃ��قǂɗA�����オ�����Ƃ̂����BᏋC�łӂ���オ�����̂��A���ɉ������ށB���ƃq�b�s�͔ߖ��グ�āA�}�[�T�ɂ����݂����B
�u�݂������I�@�G�r�G���I�v
�@���X�^�[�T�͋��сA��ɂ����e����^���ɂӂ�����B�O�l�͕��t�y�ɓ|�ꂱ�B���X�^�[�T�̏e�́A�����ē��̕ǂ�˂������B���̂͂��݂ň������������A�ۖ����j���悤�ȍ����������n�����B
�@���������Ɩڂ��J����ƁA���X�^�[�T�̓}�[�T�Ɍ������Ă����݂���ł���B
�u���C�͂ǂ����v
�u�m��Ȃ��ˁv
�@�}�[�T�̓��X�^�[�T�̒��ɂ����قǂ̒j�������B���X�^�[�T�͌�던�Ɏ���A����ȃi�C�t�������������B�����Ђ��Ƒ������B�i�o�z���������Ă��������B�q�b�s�������グ�Ĕ�т����邪�A���X�^�[�T�͕I�ł��Ńq�b�s��˂�����B�q�b�s�͒n�ʂɓ˂�����ŁA���t�y�̑w�ɖ�����Ă��܂����B
�@���̓q�b�s�Ɛ��_���Ȃ��ČĂт����邪�A�ނ͓����Ȃ��B�����̋����������ɒɂނ̂�������B���X�^�[�T�̓}�[�T�̍A��ɂт���ƃi�C�t���������B�}�[�T�̘V�����������������B
�u�����܂͒m���Ă���͂����B�m��ʂƂ͌��킹�v
�u�������̓G�r�G�����Ⴀ�Ȃ��B���܂������N�Ȃ��v
�@���͐k���Ȃ��痧���オ�����B���X�^�[�T�̎����Ɖ��A�ޏ����ɂߕt����B���X�^�[�T�̎�͂��łɐ܂�Ă���悤�ŁA�w���Ƌ����t�ɂȂ����B
�u�勾�̖����ȁv
�@���͉����������Ƃ����B�������炱���́i�܂胀�X�^�[�T�̓����ɂ����́j�ǂ��܂ł��ǂ��Ă��āA������͐S��ł��ӂ��̂��킩���Ă����̂��B�ł������o�Ȃ��A�r���オ��Ȃ��B�����o���������ł����A�܂ƕ@�������ڂ�āA���͂Ƃ��Ƃ��K�݂������B
�@���X�^�[�T�̓��̂�����āA�ޏ��Ɛ�����B���W���ӂ����ƃi�C�t��U�肩�Ԃ�B�}�[�T����������ł���B���͗���œ��������k���܂����B
�@�����Ŏ��ʂA����ōŌゾ�I
�@���͂��ɊϔO�����B�����A�Ȃ�̏Ռ����`���Ȃ��B
�@�����Ɩڂ��J�����B�r���ǂ���ƁA���X�^�[�T�̓i�C�t��U��グ���܂܁A�������~�߂Ă����B���͑̑��ɘr�𗎂Ƃ��Đk���オ�����B
�@���X�^�[�T�̕�������͌��h��ꂽ������яo���Ă���B����������������ƁA��������яo���A���̒��ɗ��܂肾���B���X�^�[�T�͂������Ǝ���߂��炵�A���������h���ɂ����j�̐��̂��m���߂��B�ނ͎���˂��܂����܂܁A
�u�ؑ��߁c�c�v
�@�ꂵ���ɑ����݂ɖ��������������B���������������B���X�^�[�T�͂������ƕG�������B���R�����h���ɂ����j���A���ɂ��������B
�u�g�D���[�V���h�E�I�v
���@��\��́@�@�V��������
���@�@�@�@�\��
�@�g�D���[�V���h�E�́A��������l�ŌR���̌��ǂ������Ă����B�ڂ�z�̂悤�ɂ͂�����Ȃ���A�����ʂ葐�I���������Đ������т��B�傫�ȏ������ł��܉ӏ�����B�Ƃ��ɂ�������Ǝa��ꂽ���̂��߂ɁA���s������ɂȂ��Ă����B
�@�ނ͖ŏ���������B���x�ƂȂ����̕������܂�����B�Ƃ��ɖ�l��H�ׂ��B���i�o�z��X�̖����A�Èł̒������܂悢�A���j�͋����A���E�͕ϓ]���J��Ԃ����B�g�D���[�V���h�E�́A����͐��E�̏I���Ȃ̂��Ƃ��Ƃ�悤�ɂȂ�B
�@������ƁA�����������n�߂��B�g�D���[�V���h�E�̗͑͂������Ȃ���A���m��̒ǐՂ𑱂����B�g�D���[�V���h�E�͂��̋C�ɂȂ�A���S�ɐX�ɂƂ����ނ��Ƃ��ł����B�g�D���[�V���h�E�͒��Ӑ[���A���������̗l�q���ώ@�����B�@
�@�T�C�|�b�c�́A���S�ɋC���G��Ă���B�E�l�̔M���ɂ͂܂肱�݁A���������ł��ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�q�������B�ނ�͎���̊댯��������݂��A�Ђ����瑊����E�Q���悤�Ƃ���B���������ʂ��ƂɁA���̋^��������Ă��Ȃ��悤�������B�m���◝���Ƃ������̂��������Ȃ��B�g�D���[�V���h�E�͈����ƂƂ��ɁA����͂��͂�T�C�|�b�c�ł���Ȃ��ƌ�����̂������B�m�[�}�����͐푈���~�߂�Ƃ����Ă������A�����ȈӖ��ŕs�\���ƃg�D���[�V���h�E�͎v�����B�C�̐G�ꂽ�l�Ԃ̐����ȂǁA�ł��͂��Ȃ�����ł���B
�@�g�D���[�V���h�E�͎ᒷ�Ƃ��āA���Ԃ̂��Ƃɖ߂�ׂ����ƍl�����B�����A�T�C�|�b�c�̑��𗣂��C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�ގ��g���܂��A���m�����̓����ɍ�����̂ɁA��������Ă�������ł���B
�@�g�D���[�V���h�E����ɕԂ����̂́A�X�ɂƂǂ낭�e���ɂ���Ăł���B�R���̓}�[�T�̉ƂɍU���������Ă���B�ނ͂��̂Ƃ��A���V��������Q����ɕ������ꂽ�}�[�T�̓`�����v���o�����̂������B
�@�g�D���[�V���h�E�͌��������������B�����Ȃ��삯���A���m���������X�ƎE�����n�߂����A�ނ�̑������A�����Ȃ������ɋꂵ�݂͂��߂��B�g�D���[�V���h�E�ɂ͐�D�̋@������B��l�������Ȃ��g�D���[�V���h�E���R����|���@��́A�������Ȃ��B���߂̐S�͔��o���킩�Ȃ��B�����̔M���A�}�O�}�̂悤�ɑS�g���ł����Ă����B�����̓��E�����ɒǂ�������A���ł���B�����A�_�Ɏ��߂������A���疽���҂��������ƁA�g�D���[�V���h�E�̎�͂Ƃ܂����B
�u���ȁc�c�v
�@�g�D���[�V���h�E�͓��̕��p����A����������̂��������B�ނ͂Ƃ����ɐg�����B���̋C�z�͈�u�ŏ����������̂����A�����Ɩڂ������j���A�G��܂�ꂵ��ł���B�ڂ͐^���ԂɂȂ�A���𐂂炵�Ă���B���p����́A�ǂ�����ᏋC������������B����ᏋC���A�̂̂����������炠�ӂ�͂��߂��B�j�̑̂́A���X�ɔ�債�n�߂��B
�u����ȁA���ȁc�c�v�@
�@�g�D���[�V���h�E�͖ڂ��^�����B���m�����̑����́A�S�g���猌���Ď��Ɏn�߂��B������J�̋ɒn�ƂȂ莀���������悤�ɁA�ނ�̓��̂͂������E�������̂��B
�@�ނ�ɂƂ��āA���قǍK���Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B���˂Ȃ��̂͂�������l�������B�j�̑����ł͑����͂�y�͕������B�j�͕ω��ɋꂵ�݂Ȃ�����A�Ƃ̗���ւƉ���Ă����B
�@�g�D���[�V���h�E�͌��ǂ����B
�@�ނ��Ƃ��߂镺���́A�N�����Ȃ������B
���@�@�@�@�\��
�@���X�^�[�T�̌��������ɗ���Ă����B���͑��ݕς��A���̐�����킵���B����グ��ƐX�̉��ŕʂꂽ�g�D���[�V���h�E���A�����ɂ����B
�@�q�b�s���ӎ������߂��ė����オ�낤�Ƃ��Ă���B���ƃq�b�s�͋��|�ɐk�����B�g�D���[�V���h�E�͂����܂Œǂ������Ă����B��l�����ꂳ�����̂́A�߈����ł�����B�����邽�߂Ƃ͂����A�i�o�z�����Ђǂ��ڂɍ��킹���̂��B�l���Ԃ�̍ĉ���A�g�D���[�V���h�E�̓��̓��X�^�[�T�̂悤�ɐԂ��͂Ȃ��A�ُ���������Ă͂��Ȃ��悤�������B����ł��ؑ��̖ڂ̉���ɁA�m���ȑ����݂������C�������B���X�^�[�T�̎��[�����z�������Ă����B
�u�g�D���[�V���h�E��A���܂Ȃ����ˁA�������ǂ����Ă���Ȃ����ˁv
�@�}�[�T�̓g�D���[�V���h�E��m���Ă���悤�������B�}�[�T�̓q�b�s�̋��Ɏ�����āA���̋���m���߂�B
�u�Ђǂ��Ŗo�����A�܂�Ă͂��Ȃ��ˁv
�@�g�D���[�V���h�E�̓��X�^�[�T�̐g�̂ɘr����������āA�O�Ɉ�������o�����BᏋC���܂��u�X�u�X�Ƃɂ��݂łāA�ǂ����������������̂悤�Ƀg�D���[�V���h�E�̎�ɂ܂Ƃ������B���E�̕ϓ]�����̒j�ɋy��ŁA���̂���ω����������̂悤�������B
�@�O�l�͓��̊O�ɏo���B�q�b�s�̓g�D���[�V���h�E�����グ�Ă������B
�u���݂̂�Ȃ́H�v
�@�g�D���[�V���h�E�͎��U�����B�u�����ɂ���̂͂��ꂾ�����v
�u���܂��͂�����ɏP��ꂽ�ˁv
�@�}�[�T�������ƁA�g�D���[�V���h�E�͂��Ȃ������B
�u�݂ȕs�ӂ�����ĂȂԂ�E���ɍ������B����͒��Ԃ̋w���Ƃ邽�߂ɁA������̌��ǂ��Ă����̂��v
�u��l�łǂ��Ȃ����ł��Ȃ����낤�B���ɖ߂邱�Ƃ��ˁv
�@���ꂪ��������A�ƃ}�[�T�͌������B�g�D���[�V���h�E�̌��Ԃ��ڂ͐ÑR�Ƃ��Ă���B
�@�}�[�T�̓��X�^�[�T�̈�[�������낵�A
�u�����͂Ȃ����t���̂��Ƃ�m���Ă����B����ǂ��납�A���������t�����Ǝv�����悤���B�����Ƃ͈ȑO����̒m�荇���������̂ɂ��ւ�炸�A�G�r�G���Ƃ��������Ă���ˁv
�@����������ׂ����̂́A���X�^�[�T�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ��ƃ}�[�T�͂Ԃ₭�B�g�D���[�V���h�E�͗��ƃq�b�s���݂��B�m�[�}�����̎p���Ȃ��B
�u���̎O�l�͂ǂ������̂ł��H�v�v
�u�ꑫ��ɍ��ɖ߂�����v�ƃ}�[�T�B�u�푈���~�߂�Ƃ��A�n���Ȃ��Ƃ������Ăˁv
�u����ɂ������Ă����v
�u�q�ǂ��̋Y�ꌾ�ɂ����v�ƃ}�[�T�͒Q������B�u�g�D���[�V���h�E��A���܂Ȃ������ˁv
�u���Ȃ��̂����ł́c�c�v
�u�����A�����T�C�|�b�c�̂������Ƃ���B�i�o�z���̂��ׂĂ̎��p��ɂ������A�Ӎ߂������Ă������������B����ƁA���ꂵ��ł���X�̎҂����ɂ��ˁv�ƃ}�[�T�͓����������B�u�C�j�V�G�̖���(�T�C�|�b�c�͖{���A�X�̎푰�������ĂсA�،h���Ă���)�A�������킯�Ȃ������v
�@���ƃq�b�s�͎��������킵���B���i�T�ᖳ�l�Ȃ����ɁA���̌��t�ɂ͐����݂��������B�g�D���[�V���h�E�͎Ӎ߂������悤�ɂ��Ȃ������B
�u�O�̕����͐S�z�Ȃ��ł��傤�B�ˑR�ꂵ�݂������̂ŁA�����܂������B�݂Ȏ��疽�������悤�ł��c�c�v
�u�Ƃ�����A�����𗣂�悤�B�댯���������Ƃ͌����Ȃ�����ˁv
���@�@�@�@�\��
�@���炭�����ƁA�g�D���[�V���h�E���������B
�u���������ŏ\���ł��傤�B�ڂ����b���Ă����������v
�@�}�[�T�͓|�ɍ��������A�O�l���͂B
�@�}�[�T�͘b�������B��̐��E�ŋ��ʂ��ċN�������ϓ]�B���X�^�[�T�̉e�ɂ������̒j�B�q�b�s�����́A�g�D���[�V���h�E���܂��{��o���̂ł͂Ȃ����Ǝv�������A���̎ᒷ�͋����قǑf���ɘb���Ă���B�����O�Ȃ�M���邱�Ƃ͂Ȃ������낤���A���̃g�D���[�V���h�E�ɂ͔[���̂����b�������B
�@�g�D���[�V���h�E��������B�C�j�V�G�̐X���L���ɂ��������̂Ƃ͕ω����Ă��邱�ƁB�y�n�����łȂ��A���A���ł��������Ƃ̂Ȃ����̂������Ă���B�i�o�z�̏W���͈ړ������Ȃ����A�~�I�̏W���Ɍ��������Ƃ��A����܂łȂ����ł��������̂��ܓ������Ă����������A�������ɓ��ɖ����Ƃ����̂��炭���������̂��B
�u��X�̓T�C�|�b�c�̂悤�ɒn�}������͂��Ȃ��̂ł��B���̒��ŋL�����Ă��邾���Ȃ̂ŁA����������B��������قǖ��m�ȕω��ƂȂ�ƁA�n�`���ς�����Ƃ����v���Ȃ��v
�@�}�[�T�͂��Ȃ������B�X�̂��܂��܂Ȏ푰����d���ꂽ�b�Ƃ����v���Ă������炾�B
�@�g�D���[�V���h�E�̓}�[�T�������낵�A�u������낵���ł����H�v�@
�@����������A�g�D���[�V���h�E�͔ޏ���ق��Č��߂����ƂȂ����B
�u�������낤�B�������������ˁv
���@�@�@�@��\
�@���炭�����ƁA�g�D���[�V���h�E���������B
�u���������ŏ\���ł��傤�B�ڂ����b���Ă����������v
�@�}�[�T�͓|�ɍ��������A�O�l���͂B
�@�}�[�T�͘b�������B��̐��E�ŋ��ʂ��ċN�������ϓ]�B���X�^�[�T�̉e�ɂ������̒j�B�q�b�s�����́A�g�D���[�V���h�E���܂��{��o���̂ł͂Ȃ����Ǝv�������A���̎ᒷ�͋����قǑf���ɘb���Ă���B�����O�Ȃ�M���邱�Ƃ͂Ȃ������낤���A���̃g�D���[�V���h�E�ɂ͔[���̂����b�������B
�@�g�D���[�V���h�E��������B�C�j�V�G�̐X���L���ɂ��������̂Ƃ͕ω����Ă��邱�ƁB�y�n�����łȂ��A���A���ł��������Ƃ̂Ȃ����̂������Ă���B�i�o�z�̏W���͈ړ������Ȃ����A�~�I�̏W���Ɍ��������Ƃ��A����܂łȂ����ł��������̂��ܓ������Ă����������A�������ɓ��ɖ����Ƃ����̂��炭���������̂��B
�u��X�̓T�C�|�b�c�̂悤�ɒn�}������͂��Ȃ��̂ł��B���̒��ŋL�����Ă��邾���Ȃ̂ŁA����������B��������قǖ��m�ȕω��ƂȂ�ƁA�n�`���ς�����Ƃ����v���Ȃ��v
�@�}�[�T�͂��Ȃ������B�X�̂��܂��܂Ȏ푰����d���ꂽ�b�Ƃ����v���Ă������炾�B
�@�g�D���[�V���h�E�̓}�[�T�������낵�A�u������낵���ł����H�v�@
�u�������v
�@�g�D���[�V���h�E�͏����Ԃ�u�����B�l������ł��镗�ł��A�S�O���Ă��镗�ł��������B�₪�Ċ���グ���Ƃ��ɂ́A����ɃX�b�L������������Ęb���o�����B
�u���̓X�[�̒��V��������A�X�̎푰�ɓ`��錾���`�����A���x�ƂȂ���������Ă��܂����B���A���̖��ʂ������������Ǝ����͎v���Ă��܂��v
�u�Ȃ�̂��Ƃ��ˁH�v�ƃ}�[�T�͂��Ԃ������B
�u�O�S�N�O�A���ʊԍۂ̃G�r�G�����⌾���c�����̂ł��B�������E�Ɉٕς�����Ȃ�A�}�[�T�������Ă���Ă���ƁB��X�͂��̈⌾�ɏ]���Ƃ��������̂ł��v
�u����͂��������B����͎O�S�N���O�ɐ����Ă��l���v
�@�ƃq�b�s���������B����ǂ��A���X�^�[�T���g���}�[�T���G�r�G���ƌĂ̂ł���B�g�D���[�V���h�E�͉��߂ă}�[�T�Ɛ������B
�u���Ȃ��̓T�C�|�b�c�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł����H�@�T�C�|�b�c�Ȃ�ΎO�S�N���̊Ԑ����Ȃ��炦��͂����Ȃ��B�G�r�G�����猾�t�������Ƃ����i�o�z�̒��V�������F����ł���̂ł��B���̓`�������̓G�r�G���̎c������Ƃ��āA�p����Ă��܂����v
�u����́c�c�v
�@�g�D���[�V���h�E�͏����������������B�u���Ȃ������������玀�ȂȂ��Ƃ��������Ȃ�A���������ł������G�r�G���������Ȃ��炦�Ă���͂����B�Ăѐ��E�̏I��肪����Ȃ�A�}�[�T�������Ă���Ă���B�G�r�G���͂����������B���������̐��E�̏I���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł����H�v
�u�t���������������Ƃ����̂����H�v
�@�}�[�T���ڂ����点��B�g�D���[�V���h�E�͂��Ȃ����āA�u�Â��푰�͂���܂Ō������Ă����B�G�r�G������̌����`��������Ă������炾�B���Ȃ��������オ��Ƃ����Ȃ�A�C�j�V�G�̖��͍��������Ȃ��̂��߂Ɍ�������ł��傤�v
�u�n���ȁB�������ɂ͉��̘b�����킩��Ȃ���v
�u���Ȃ��͒m���Ă���͂����v
�u�킩�����̂͂킩���v�}�[�T�͔ߖ��グ�����C���������B�u���X�^�[�T�����������C�̂��Ƃ����āA���̂��Ƃ����킩��Ȃ���v
�@����ǁA���C��~�������Ă����̂��A�}�[�T���G�r�G���ƌĂ̂��A�{���̂Ƃ���̓��X�^�[�T�ł͂Ȃ��̂ł���B
�u����Ȃ���������~�����������ĂȂ�Ȃ́H�v�Ɨ��B
�u���������[�A���c�𑀂��Ă���Ǝv���܂����H�v�q�b�s���u�����B�u�M�k�����̂��������̕������Ɓv
�u���̉\���͍����Ǝv�����v
�u�r�X�R�����̂����Ă����g���C�X�Ƃ͊W�������ł��傤���v
�u����Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ��ˁB���{�ɂ����̂͂��܂��̂ق����낤�v
�@�}�[�T�������ƁA�q�b�s�͌��𗎂Ƃ����B
�@�^�b�g�����S���Ȃ��Ă���́A���{�ɂ͌������͑{���������A�^�b�g���̎c���������i���̏W�i���ނ��Ⴍ����ɂȂ��Ă��܂����B�q�b�s�͕����̒����ɍs���ƁA�I�������H�킸�ɍl������ł����B�q�b�s�͂��̓��̓��Ɍ���������ɂ����B�ȗ��A�X�ɏh����āA�^�b�g���̂킸���ȍ��Y�ŐH���Ȃ��ł���B
�u�^�b�g���͂���������ł���͉����������ς������ł��B�͂����͉��{�ɍv�������̂ɁA�g���C�X�̂����ʼn��������ς�����v
�@�q�b�s�͓{��ɔR����ڂœ�l���݂��B�y�b�N�����͔ނ�̋��ꏊ��m���Ă���A�C�j�V�G�̐X�ɍs�����߂ɉ�ɗ����̂��B�q�b�s���O�l�ɋ��͂����̂́A�l�I�Ȏ�����������B�^�b�g��������Ȃӂ��ɗ�����鉤���̂�������邹�Ȃ������̂��B
�u���܂��܂ł���Ȃ͂߂ɂ����Ă�Ƃ͂ˁv
�u�r�X�R�̂����Ă��Ƃ���ł���v�q�b�s���������B�u�͂����́A�ؑ��Ƃ̂Ȃ�����^��ꂽ�v
�@�q�b�s�̓g�D���[�V���h�E�ƃ}�[�T�̓�l���ɂB�^�b�g���̌��͋^���ɉ߂��Ȃ��B����ǁA�g�D���[�V���h�E�͂ǂ�Ȍ`�ɂ���A�}�[�T�ɉגS����Ƃ����Ă���B
�u���̂��ƂŁA�܂������ɔ��ᎋ�����̂́A�������Ƃ���������ˁv�ƃ}�[�T�͌������B�u���܂��������A�n�t�X�ɋ~�������߂悤�Ƃ����̂͊ԈႢ����Ȃ��B�閧������̂́A�����������A�����炭�n�t�X���c�c�v
�@�}�[�T�͍l�����B���ƃq�b�s�́A�ޏ��̌��t��҂���B
�u�Ȃ��Ȃ�A�n�t�X���������Ɠ��������炾��B�n�t�X�ƁA�X�~�X�Ƃ����j�B�����������O�l�́A�����ƎO�S�N������Ă����v
�@�q�b�s�͕\��𓀂�t�������B����܂Ń}�[�T�̒����͂��킳�b�ɉ߂��Ȃ������B����Ŗ{�l���F�߂����ɂȂ�B
�u�ł��A���ʂ͂���Ȃɐ������Ȃ��v
�u���̐��E�ł��A����Ȃɐ����Ă�l���Ȃ��v�Ɨ��B
�u��������n�t�X�̎������Ȃ��s���Ȃ��̂��͂킩���v
�@�ƃ}�[�T�͓������B�q�ǂ������̕s�M���悻�ɗ����������������B
�u�t���̂����Ă���̂͌����푈�̘b���낤�B�����A���E�̏I���Ƃ́c�c�v
�u����Ȃ��ȁv�ƃq�b�s���������B�u�g�D���[�V���h�E�͂��Ȃ��̂��Ƃ��T�C�|�b�c����Ȃ��ƌ������B�������Ƃ�����A�n�t�X�剤�����ăT�C�|�b�c�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�v
�@�q�b�s�̋^��ɓ�����҂͂Ȃ������B
�u�C�j�V�G�̐l�����́A�G�r�G���₠�Ȃ��ɋ��͂��Ă���ł����H�@������A�����͔ؑ��ɍU�����n�߂���ł����H�v
�@�Ō�̋^��̓g�D���[�V���h�E�ɂ��������Ă����B
�u�O�S�N�O�̌����푈�łȂɂ��c�c�v
�@�}�[�T�͒��ق����B���̖₢�ɂ́A�X�̔ؑ���������������ꂽ�悤�������B
�u�킩��Ȃ��B�������ɂ͋L�����Ȃ���v
�@�g�D���[�V���h�E����������߂��B�u�o���Ă��Ȃ��ƁH�@����͊m���Ȃ̂ł����H�v
�@�}�[�T�͖ق��Ă���B
�u���Ȃ��͋L�����Ȃ��ƌ����܂����ˁv�ƃq�b�s�B�����͒Ⴂ���A�قƂ�Nj����̂悤�Ȍ������B�u�����ł͂Ȃ��Ƃ͌���Ȃ������v
�@�q�b�s�͂����Ŗق�A�}�[�T�ɔ����̋@���^�����B����ǁA�ޏ��͉�������Ȃ������B
�u�ł́A���Ȃ����O�S�N�Ԑ����Ă��āA���̂Ƃ��N����������̋L�����Ȃ��Ɖ��肵�Ęb���܂��傤�B���Ȃ��ɂ͋L�����Ȃ������ŁA���E�̏I���悤�Ȃ��Ƃ��m���ɂ������Ƃ���Ȃ�A���X�^�[�T�̂��������C�����āA���݂��Ă��Ă��������͂Ȃ��B�ƂȂ�ƁA���R�̔w��ɂ����̂́A�O�S�N�O�̎����̊W�҂ƍl���Ă������ƂɂȂ�v
�u���܂��͐M�������Ȃ̂����H�v
�@�q�b�s�͖ڐ��𗎂Ƃ����v�ٍl�����B�u�M���܂��B���̐��E�ŋN���������ƁA���̐��E�ŋN�����Ă��邱�Ƃ͋��ʂ��Ă���B�ڂ��ɂ̓G�r�G���̂������E�̏I���Ǝv���ĂȂ�܂���v
�@���͊�����ނ����B�낵���Ȃ����̂��B
�u�ł��A�Ăт��Ăǂ��������ƁH�v�Ɣޏ��͐u�����B�u����Ȑ̂ɁA���Ɠ������Ƃ��N���������Ă��ƁH�@���E�̏I�����āA�Ȃɂ��������H�v
�u�����͂��Ԃs�ɂ���B���Ȃ��̂����Ƃ���Ȃ�A�n�t�X�剤���W�҂�����B����ɂ��Ԃ�g���C�X���v
�@�}�[�T�͂��Ȃ������B
�@���ق��Ă����g�D���[�V���h�E���A�v���Ɍ����J�����B�u���ł͂���܂��A�肢�����Ȃ��鏬���̓`���Ȃ�A�X�̂�����Ƃ���œ`����Ă���܂��v
�u����Ȃ��̂́A�����̓`���ɂ������v
�u���ƂĂ���܂œ`����M�����킯�ł͂���܂���B�ł����A���̌������⌾�𗠕t���Ă���v�ƃg�D���[�V���h�E�͌������B�u���Ȃ������s�ɍs�����̂Ȃ�A���͂��Ă����܂��v
�u�n���ȁA���֖߂�B����Ȃ��ƂɊ������܂�邱�Ƃ͂Ȃ��v
�u�A�����Ƃ���łǂ��Ȃ�܂��傤�B���̘A���͉�X������₵�ɂ������ł��v
�@�g�D���[�V���h�E�͋ꂵ�B�ꍏ�������W���ɖ߂�A���E�̖������m�F�����������B�������A�����ŕʂ��A�}�[�T�̖��͂Ȃ���������Ȃ��B�O�l�͕����ɖ���_���Ă���A�T�C�|�b�c�Ƃ������ƂŐX�̎푰�ɂ��P���闧��ɂ���B
�u�A��ꏊ���Ȃ��Ȃ��Ă��邩������܂���v
�@�g�D���[�V���h�E�̓q�b�s�Ɏ�������������B
�u���܂Ȃ������B����͑����݂ɉ��Y�ꂨ�܂������̘b�������Ȃ������B�X����܂ł��ꂪ�ی삵�悤�B�����Ԃ�������̂��ނ͂����v
�@�q�b�s�̓g�D���[�V���h�E�̎���Ƃ����B�u�ڂ���̕��������Ȃ��Ɏӂ�Ȃ��Ắv
�@�g�D���[�V���h�E�͎��U���Ĕے肵���B���������āA
�u���܂������̂����ł͂Ȃ��B�G�͑��ɂ���v
�@���͂��Ȃ������B�}�[�T���������B
�u���ɖ߂�Ƃ����̂ɁB�ǂ����������������̂������Ƃ͕����₵�Ȃ�����ˁB�����Ƃ�����������푈���~�߂�C�����M���Ȃ���B����ȔN���ɂȂ��Ė��ƂɊ������܂��Ƃ́A�v�������Ȃ�������v
�@�}�[�T������܂�Ԃ��������̂ŁA���ƃq�b�s�͕���Ă��܂����B
�@�g�D���[�V���h�E���ڂ��ׂ߂��B
�@���ɂ͂��̌�����ʎ푰���A�����悤�ɂ��������̂������B
���@�@�@�@��\��
�@�ނ�͂قƂ�ǖ��邱�Ƃ��Ȃ��i���ǁA����͈����ł����Ȃ������̂�����j�A�T�C�|�b�c�̍����߂������B�r���ɂ͐��̐Ղ��������B���m�̎��̂�����A�O�l�͖ٓ������������B�g�D���[�V���h�E�͊��w�����B
�@�C�j�V�G�̐X�̕ω��́A�͂�����Ɗ�����ꂽ�B���܂��肳�܂Ɏ����тɏo�邱�Ƃ��������B�����Ƃ����v���Ȃ��悤�ȈÍ����ڂɂ����B����ł̓y�b�N�����������ɉ��s�ɖ߂ꂽ���ǂ��������������̂������B���̕��p���犴����s���ȋ�C�́A�ǂ�ǂ��Ȃ��Ă���B���ɂ͂��̓s�Ƃ�炪�A�_�ے��₨�܂��肳�܂Ɠ����A���ȏꏊ�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B
�@�����A�Ƃ��Ƃ��X�����B
�@�ꓯ�͌ő���ۂB�u�̏ォ��͍�����ǂɈ͂܂ꂽ�X�����n����B�ԋ߂Ɍ���Ɖ��s�̂���ȋC�z�́A�Ђ��Ђ��ƈꓯ���Ƃ�܂��悤�������B�����Ă���̂Ɏ��ɕБ���˂�����ł���悤���B
�u���������A���܂�͂͂�����Ȃ���B�C�z�������Ƃ����ɂ݂��邩��ˁB�Ȃ�ׂ��ӎ����Ւf���āA�C�z���o���Ȃ��悤�ɂ���v
�@�}�[�T�̓��X�^�[�T�𑀂��Ă����j�̂��Ƃ����̍��A�����A�Ƃ����Ă���B
�@���͕����܂܂ł���B��ǂ̏�ł͖�Ԃ̊Ď����镺���̎p���������B�}�[�T�͂Ƃ����臀�͇��������āA���������̒��ӂ����炵���B
�@���͂قƂ�Nj����ׂ��������ĎO�l�̂��Ƃɂ��Ă������B����ȓs�ɏ�荞��ŁA�_���̐����c���{�������Ȃ�āA�C�̉����Ȃ�悤�Șb�������B
�@������n�肫��ƁA���s�̏�ǂ͍L���x�Ɉ͂܂�Ă���̂��Ƃ킩�����B��������ƁA���͂߂����k����������オ���Ă���B���ِ͈��E�Ő��j�����Ƃ͎v��Ȃ��������A���𒅂��܂܉j�������ƂȂ�Ă������Ȃ��B�v�����Ĕ�т��ނƁA�����Ԃ��Ɣg�䂪�����A�������܌��̋C���Ђ����B�ޏ��̓K�^�K�^�k���Ȃ���A�����������B
�@�Ί݂͊�ǂɂȂ��Ă���B�����ɂÂ��S�i�q�͓���ꃁ�[�g������̂Ƃ���ɂ���B�����ɂÂ��S�i�q�͎��O���ꂽ�܂܂��B�ƂȂ�ƁA���̎O�l�͖����ɂ��ǂ�����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�g�D���[�V���h�E���A���Ńq�b�s�����H�ɂ͂�������A���ƃ}�[�T������������B���̃��[�u�͐����z���Ă�������d���Ȃ��Ă����B�������ڂ�ƍׂ������̂����A�q�b�s�͖ڂ����炵���B
�@���H�͗����ŏo���Ă������A�u���b�N�̔����������ӏ�������A�q�b�s�͂����ɘr��˂�����Ŗ����ɕ�܂ꂽ�ו������o�����B��݂��قǂ��ƁA�����v�ɗr�玆���o�Ă����B�o���̂Ƃ��Ɏc���Ă��������̂��B�莆���lj�����Ă���B
�u�p�[�V�o������̓`���ł���B�������ו���߂��Ă��ꂽ�v
�@�q�b�s�̓����v�ɉ����āA�l�ɐ܂�ꂽ�莆���J�����B
�u�݂�Ȗ����炵���B�ł��A�y�b�N�������������r���a�͏o���ɂ����Ȃ��B���[�A���c�����{���ڂ���̌��ǂ��Ă���v
�@�����u�����B�u�ߕ߂����́H�@�X�ɍs��������H�v
�u�勾�Ńn�t�X�剤���Ăяo���v��́A�_�����̃n�u���P�b�g�����Ă����̂ȂB�n�u���P�b�g�͂��ꂪ�����ł��܂����B����ɁA���s����O�ɏo�邱�Ǝ��Ԃ��֎~���v
�u�ł́A�ǂ�����H�v�ƃg�D���[�V���h�E���u�����B
�u�p�[�V�o�������Ƃ́A���̏o�������߂Ă���B�����ɍs���܂��傤�v
�@�Ƃ����萅������Ă��邩��A�}���Ői�ޕK�v���������B���H�͂��яL���B����łł����ʘH�͂����Ƃ�Ǝ��C��A����C������B�����r���̈��L���A�[�����Ă����B
�@���炭�̂������A���̗���鉹�ƁA�����v�̖����R���邶�肶��Ƃ�������������������B
�@�\���[�g������i�ނƁA���H�̍����n�_������A�����͗����Ƃ̂ł���G�B�ƂȂ��Ă����B�V��̍����͎O���[�g������B�召��\����̔z�ǂ����܂��Ă���B
�@�q�b�s�̂������Ƃ���A���H�̂�����������A�����Ƃ����藬�ꂱ�B�C�����Ⴂ�B
�@���R�ƕ��z�ǂ��݂߂邤���ɗ��͂߂܂��������B���̌������ɂ͐�]�����Ȃ��悤�ȁA����ȋC�������B
�@�z���ǂ�O�ɁA�����Ɨ����s�����Ă���ƁA���D�̏L���ɂ����Ȃꂽ���̂�������̂��������B����́A���̏L���B���E�̂˂��܂����n�܂��Ă��炱����A�����Ƃ��������Ă����A���̏L���������B
�@����ȗ\���Ɍ������āA���ƃq�b�s�͎��R�Ɏ�����荇���B
�@�q�b�s�͎O�{���z�ǂ̈�{�Ɍ���������ƁA�����ɔ�������ł������B���͂܂��������ڂ�Ȃ���A��ɑ������B