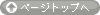「ねじまげ物語の冒険」へようこそ
この小説は、ねじまげ三部作の第二弾です。
伝説の書を胸に、本の世界の登場人物たちと奮闘する少年の姿を描いたファンタジック冒険小説!
侍の少年との友情を軸に、洋一がロビン・フッドの世界を冒険します。
◆第三部 果てしない物語のちょっとした終幕
◆ 第一章 ノッティガムを攻めたロビン・フッド
□ その一 シャーウッドのロビン、ノッティンガム州長官にふたたびおまみえすること
○ 1
ロビンは三艘の船を率いて、シャーウッドを目指していた。彼は十字軍の男たちを甲板に集めた。その船にはギルバートもふくめて五十名ばかりの騎士たちがいる。
どの顔も憔悴し、ジョン王の謀略に腹を立てていた。国王は、十字軍で勇敢に戦った貴族たちの領土を没収していたからだ。騎士団の身分は剥奪され、家族は散り散りとなっている。大陸での浮浪は、イングランドにもどっても変わることはなかったのだ。
イングランド各地では諸侯が反抗し、田畑の荒廃は著しい。そこにモルドレッドが加わっている。ギルバートたちの絶望は深かった。
さて、ロビンのかたわらにはシャーウッドの男たちが控えている。目前には、獅子十字軍の騎士たちが居並ぶ。みな地べたに座りこみ、立つ気力もないように見えた。
ロビンは騎士たちを前に、箱の上に立ち、じっと目を閉じていた。やがて、怒りに満ちた空気は静まり、どの男もロビンの言葉を待つようになった。
「どうするんだ、ロクスリー」とギルバートが言った。彼はもはや立つこともできない。「俺たちは領土を没収され、もはや騎士ですらない」
お主も今ではただの人だ、とは、ギルバートも言えなかった。しかし、伝説の男ロビン・フッドの周りにも、今や傷ついた二百名ばかりの人しかいない。
我々だけで、国王軍と戦うのか、と誰かがつぶやいた。ざわめきが起こった――ジョン王はロンドンにいる。王都を落とせるはずがない。いや、王都はすでにモルドレッドに制圧されたという噂だ――心配が次々と皆の口に上りだし歯止めがなかった。
ロビンが目を開くと、人々は一人また一人と口を閉ざす。彼はそのざわめきが尽きぬうちに言った。「なにを騒いでいるのかわからんな」
ギルバートたちは殺気だった。彼らは口々に反論したが、ロビンは負けずに騎士たちを沈めた。
「シャーウッドにいたころから、我々が優勢だったことはただの一度もない。こんなことはざらにあることだし――お前はもう慣れっこだな、ちびのジョン」
いかにも、とジョンは言った。長い付き合いのジョンはわかっていた。ロビンは外見に似合わず、短気な男である。不遇の時代を長く過ごしたせいと、その強い意志の力で押さえこむことはできるが、不平不満ばかり述べる騎士たちにすっかり腹を立てていた。ロビンは口辺に怒りをみなぎらせ、力強く次のように述べた。
「不満や愚痴を口にするものは、人のせいにしはじめる! それではなにも変わらない! 今必要なのは沈黙、後は行動あるのみ! 十字軍で勇敢に戦った君たちが、なぜ今になって臆病風に吹かれている! 足りないのは身分、兵力、大儀か! 人が行動を起こすのに必要なのは、そんなことではない!」
ギルバートたちはロビンの言葉に傾聴しはじめた。ロビンの声に宿る熱気が人々の身を今一度振るい立てようとしていた。
傷ついた騎士たちの心に、ロビンの言葉が熱した鋼を打つ槌のごとく響いた。
「兵がいないというなら外を見ろ。イングランドに心ある人々はいくらでもいる。シャーウッドに集まった義賊はじつに多くたのもしかったぞ。俺はイングランドを救うために立ち上がる人たちはかならずいると信じている。俺はそれらの人のために力を尽くしたいのだ。彼らが俺を信じるなら、俺はこの身が滅んでもかまわない!」
ウィル・スタートリーが折れた腕を抱きながら、おごそかに告げた。「俺はあんたに従うぜ、ロビン・フッド」
「供が必要だろう、おじき」
とガムウェル。アランたちが、それぞれ武器を取り上げこれにつづいた。最後にジョンが一同を代表して進みでた。
「俺はロビンとともに死にてえ。俺が言いてえのはそれだけだ。俺は生まれてこの方、ヨーマンでしかなかった。そのことに誇りをもってる。だから、俺を育ててくれた人に誓いてえ。イングランドのために、働くって。俺のこの身は正しい事をするためにあるんだから。ロビンといれば、それができるんだって信じてる」
一座はしんと静まった。人々は口を閉ざし、けれどその奥底では何万という言葉が声となってうねっているようだった。彼らは口を閉ざしているけれど、ついに目を覚ましたとみてとれた。
ギルバートが剣をついて立ち上がる。
「ロクスリー、許してくれ。俺は身の不運を呪うばかりに自分が騎士であることを忘れていた。騎士とは剣を肩に受けなるのではない。行いで騎士たることを示すのだ。俺は騎士の家に生を受け、騎士として訓育を受けてきた。両親、先祖のために今は戦いたい」ギルバートは騎士たちをかえりみた。「俺はロクスリーとともに行く!」
「俺もだ!」
「俺もだ!」
賛同の声は重なり合い、大空に轟くようだった。獅子十字軍で立派に戦った人々は、ついにその勇気と義侠心を取りもどし、口々に雄叫びを上げ、互いの体を叩き合ったのだった。
マストの上では太助と洋一が、そんな大人たちの様子を見おろしていた。
こうしてロビン・フッドは呪われたこどもたちを連れて、ようやくシャーウッドへの帰路についたのだった。
○ 2
ロビン・フッドが海上にて旗揚げをしたころ、ロンドンは落城しかかっていた。国王軍はわずか三千名ばかりのモルドレッド軍をいともたやすく弾きかえしたが、夜間になり形勢は逆転した。城壁をとり囲んだ黒衣の軍隊は、無敵の強さを発揮しはじめた。その部隊が王都に進入すると、城門は閉じられ、王都は阿鼻叫喚の地獄図絵と化した。その兵にはわずかな明かりすら必要なかった。伝説に聞く悪魔の数々が市民を襲う。彼らが血肉を食らいはじめると、国王軍の大半が戦意を喪失した。ロンドンの民間人は逃げ場すらなくし屋内に閉じこもった。
闇と殺人の猛威の中で、人々は暗闇に息を潜め、隣人の悲鳴に耳を閉ざし、こどもたちの口をふさいだ。パレスチナでサラディンの味わった恥辱の数々が、イングランド人の身に降りかかった。
モルドレッドの正体を知っていたのは、たった一人だった。
国王軍を蹂躙すると、軍隊は市民の殺戮を繰りかえした。銃士隊がついに王宮へと迫ると、彼女は王宮の地下へと逃げこんだ。
○ 3
「あ、あやつここまで追ってくるのか。どういうつもりじゃ」
モーティアナは二匹の蛇をつれ、地下水をはね散らかし、もつれる足を急がせていた。立ち止まると、背後をかえりみ、男の存在を感知する。懐をまさぐり、水晶球をとりだした。体温が異様に上がり、彼女は苦痛に喘いでいる。老いさらばえた心臓が血液の流れる速度に耐えかねる。体温を上げているのは血液自体。管が焼けるようだ。その事実のすべてが、マーリンに呪われし、もう一人の帰還を告げていた。まちがいない、あやつ本物じゃ――
「ああ、尊師、やはりあやつめであります。あなた様のおっしゃるとおりでありました」
モーティアナは水晶球をなでながら、そちらを向いていなかった。洞穴の入り口側に目を向けていたのだが、水晶が輝き、ウィンディゴが姿を現すとそちらに向き直った。
「わたくしめはどうすればよいのです。あやつは化け物、何者にも従わないとあなたが申したとおり……」
「手筈ならばすでに申したはずだ、モーティアナ」
底響きのする声を聞くと、モーティアナは不思議に落ち着きをとりもどした。
「忌々しいのは小僧どもよ。本当にロビンを復活させおった」
「まさか、あの小僧がそうしたとでも」
「すべては本の力よ。よいか、伝説の書のことは、モルドレッドには申すな。わしが出ればあやつは従うまい。やつに取り入り、背後から操るのだ。うまくやれ」
「はっ……」
モーティアナは深く頭を垂れた。それよりも、モルドレッドはすぐそこまで迫っている。彼女は水晶球を大切に布に包み岩棚に押し上げると(岩に置くときは、失礼いたします尊師、と労りをこめて口にした)、自身は別の物を抱え、モルドレッドを待ち受けた。
○ 4
モルドレッドは怒りにくれながらも謎の女を追っていた。モルドレッドは五百の魂を体内に巣くわせる男である。体に対する感受性も五百人分だ(だからこそ人並み外れた身体操作能力を引きだすことができるのだが)。だが、痛覚もおなじだ。なぜだ? いったいなにが起こっている? なにがあったというんだ?
そのとき、彼の脳裏に浮かんだのはたった一人、三百年前に彼を闇に葬った男であった。
「マーリンか? やつが生きているとでもいうのか?」
だが、そのはずはない。マーリンが死んだからこそ、彼は自由になったはずである。モルドレッドは全身に跳ね返る焔を押さえながら、女の元に急いだ。彼はそやつに会ったこともないというのに、老婆であることを知っていた。マーリンから受け継いだ呪われた血液が相手が老婆だと教えているかのようだ……。
モルドレッドは足を止めた。視界の先に小柄な人影が現れたからである。
「何者だ?」
怒りとともに黒剣を抜くと、彼の筋肉は反するようにして痙攣を起こし剣を取り落とす。
「モルドレッド卿……」
と老婆は言った。両手でなにかを抱えている。布に包まれているようだった。
「ほう、俺を知っているか」
モルドレッドは剣を拾わなかった。老婆の並々ならぬ力を感得したからである。彼は足を滑らせつつ、老婆の正面から身を外した。無駄と知りつつもより深き影へ身を潜ませる。
「そうか、お前が王家に仕えるという魔女か。ここでなにをしている。なぜこの洞穴に逃げこんだ!」
「お気づきでありましょう。アーサー・ペンドラゴンが遺子、モルドレッド・デスチェイン卿。いや、円卓の騎士、最後のお一人と申すべきでありますかな」
「なんだと?」
こやつ、なぜ俺の正体を知っている?
モーティアナは話を進めた。「あなたはお気づきなのではありませぬか。ここは師マーリンの残せし洞居にございます」
「師? 師だと? お前がマーリンの弟子だと申すか!」
「御意。ようやく仕留め申した。それというのもあなたを解放せんがため――」
「ふ、ふふふ、なにをいう。マーリンの弟子だというなら、貴様もただの年ではあるまい。俺を知る貴様が、俺の味方だと申すのなら、なぜこれまで行動しなかった! 何百年も放擲したのはなぜだ! なにを企む!」
「お気づきなのではありませぬか」
モルドレッドはハッと黙りこんだ。モーティアナは彼の気をこめた怒声にもまるで動じていない。
「わたくしめはマーリンの血を受けただけの者。あなたとおなじく。師にかのうたのは師の力が弱まりしため。ゆえにあなたを救いだすことに成功いたしました」
モーティアナの声は左からした。モルドレッドがくらむ視界をそちらに向けると、老婆はすぐ脇に立っていた。
「あなた様にはこれを……」
モーティアナが手にした物から布をはぎ取る。そこにあったのは人の生首であった。
「ジョンか?」
「いかにも、宿敵リチャードの弟であり、現国王、ジョンにございます。くだらぬ、フランスから渡りし、似非王朝の血筋の一人……」
モルドレッドは黒剣を拾った。モーティアナが飛び退き、その手からジョンの生首が落ちた。
「ジョンの首は差し出し物に過ぎませぬ。あなた様はお気づきでありましょう。我らの体に流れし血の巡りを。この血の響きがあなた様の力を強くする」
「マーリンの力か。俺には不要なものだ!」
モルドレッドは黒剣を振るったが、モーティアナも幻術を使い、その剣先から逃れた。モルドレッドがその姿を追ったときには、モーティアナは遙か後方にいた。
「わかっておられませぬな。あなたの敵は現王朝などではない。あなたとおなじ古の血族どもにござりまするぞ! あなた様も魔術は使えぬ。ゆえにわたくしめの微力が必要ともなりましょう」
「やはり解せんな」
モルドレッドが腕を振るうと、モーティアナの体内で、マーリンの血が荒れ狂った。細い血管をかけめぐり、年老いた心臓を破裂させようとする。血流が脳に集まる。ふくらむ。ふくらむ。頭蓋骨の中で二倍にふくらむ。目玉が押し出され、モーティアナは身を反り返らせ、
「お、おやめ下され! わたくしはあなたの味方……」
モルドレッドは術を解き、モーティアナの体は地に落ちた。モルドレッドは腕を返す返す見つつ、
「力が強くなったとは嘘ではないとみえる。お前の望みはなんだ」
「宿敵の抹殺……」
とモーティアナは長い爪を舌になすり、そこから流れでた血を指先にすくいとると指輪をさすった。闇の中に二人の少年と老人、もののふの姿が浮かび上がる。
「こいつは……?」
「憎むべき小僧共にあります」
「だが、この者は」とモルドレッドは少年の一人をさした。「この者ならば俺の呪いで死に瀕しておるわ。貴様の宿敵とはこんなやつらか」
「あなどるなかれモルドレッド卿。いや、真王。あの小僧めは只者ではありませぬ。ロビンを蘇らせたのはやつとやつの三人の守護者にあります」
なんだと? モルドレッドの心に疑念が差した。確かに妙だ。ロビンは魂を抜かれあのまま死に至るはずだった。なぜ呪いを跳ねかえすことができたのだ。
「俺の力を跳ねかえしたのはこやつの仕業だとでもいうのか」
「御意」モーティアナは取りなすように言った。「わたくしめも古のイングランドの血筋、フランスより渡り来たプランタジネット朝など認めておりませぬ。この国の真の王たり得るのは今は滅びしアーサー・ペンドラゴンの血を引く貴方様のみでござります」
モルドレッドは黙りこんだ。慎重な目付きでモーティアナの顔を舐めるように見た。確かにロビンは魂をなくしあのまま死に至るはずだった。俺の力を跳ね返したのはあの小僧か。
モーティアナは五百の目玉に深々と心を覗かれるようだった。
「よかろう」と彼は黒剣をおさめた。「だが、貴様を信用したわけではないぞ。逆らえば必ず殺す。マーリンの力ならば、奪い取ればすむことだ。俺が聖杯の力を得ていることを忘れるな……」
モーティアナは応えず、深々と頭を下げた。モルドレッドはやや薄気味悪げにその場を後にした。モーティアナの側にウィンディゴが現れほくそ笑んでいることには最後まで気づかなかった。
○ 5
シャーウッドに帰り着いたロビンにもたらされたのは、ロンドン落城の凶報だった。モルドレッドはイングランドを大混乱に陥れている。
多数の噂がロビンの元にもたらされた。が、ロビンの周りにもシャーウッド以来の仲間と十字軍がいるばかり。ジョンら義賊一党は歯噛みをして手をこまねくしかない。
ロビン・フッドは、兵力が整うのを待つしかなかったのである。
シャーウッドの状況は悲惨だった。なつかしい森はアジトを中心に焼き討ちにあい、立派なブナや樫の巨木も炭となって無惨な姿をさらしている。ロビンは以前のアジトよりさらに奥深くへと拠点を移した。ロビンの新しいアジトは(古いアジトもそうだったが)森役人が近くに寄ってもおいそれとはわからないよう、樹木の合間に網を渡して蔓を這わせ、アジトの内部がのぞかれないよう何重にも封鎖してあった。ロビンがいざというときのためにあらかじめ用意して、そのまま放置されていた古いアジトだったが、作った本人たちもすっかり忘れていたのだからなんとも具合がよかった。モーティアナに告げ口する者もなかったし、蔓草がすっかり成長して分厚い壁となっていたからだ。ロビン帰還のうわさが伝わると、さっそくノッティンガム州における困窮した貧民たちが彼を頼って集まりはじめた。それとともに、タック坊主たちの現状もわかった。彼らはモーティアナの襲撃をうけたあと、バーンズデイルの森に退き、そこで、リチャード卿の息子の保護を受けていたのである。
洋一と太助は森を歩きながら今後の方針を話し合っていた。まずは奥村とミュンヒハウゼンに会わなければならない。モーティアナやウィンディゴには殺されていない、きっと生きているはずだった。その上で、モルドレッドのことを伝えなければ。少年たちの悩みはつきない。
太助は急に立ち止まった。「その右手は大丈夫なのか?」
洋一は右手を持ち上げて(まるで腕自体が錘になったみたいだ)、呪いの箇所を見た。
「海に出てから痛みもましなんだ。たぶん、モルドレッドが近くにいないせいだよ」
太助は安心したようにうなずいた。それから周囲に誰もいないのを確かめるように後ろをみた。大人たちはみんな離れた場所にいる。ともあれ森中に難民がいて二人は過ごしにくかった。異相のこどもはとにかく目立ったのだ。
太助は首を戻し、
「その呪いを解くためにもウィンディゴを倒そう」
太助は洋一をうながしてふたたび歩いた。
「リチャード卿の城は州長官に攻められてるって。きっとウィンディゴだよ」
と洋一は言った。落ち延びた森の仲間に、二人の異国人が混じっていたという話を聞いていた。
「男爵と父上はきっとリチャードのお城にいるにちがいない。タック坊主たちと城に立てこもっているんだ」
「だから、ウィンディゴは州長官に攻めさせたんだよ。ロビンたちは作戦会議をしてる。みんなを助けに行くつもりだ」
「ぼくらも絶対に付いていくぞ。ロビンだって、ウィンディゴや魔女と戦えるわけじゃない。魔術に対抗するなら、男爵と伝説の書が絶対に必要なんだ」
洋一はうなずこうとしたが、不安のあまりうつむいた。
「男爵はもう創造の力が使えないじゃないか。ウィンディゴがいってたんだ。創造の力でわしと勝負だって。だけど、ぼくは……」
「洋一、男爵は力をまったくなくした訳じゃない。それにあの人の知識があればうんと助かるはずだ。恭一おじさんとだってつながりがあったんだ。君の名付け親だぞ。伝説の書にだって詳しい……どうしたんだ?」
と太助は急に涙をためた洋一に驚いた。彼が涙ぐんだのは太助の言葉がありがたかったからじゃない。恭一おじさん……。よく考えると、この少年の口から父親の名前が出たのはこれが初めてだ。それに父親のそんな呼ばれ方を耳にしたのは初めてだった。彼はただ、父親と深いつながりのある友人がすぐ側にいることが分かって急に心がゆるんだのだ。
「ごめんよ、泣くつもりなんかなかったんだ。ただ、ぼく……」
「いいんだ。君にばかり任せてすまないな」と太助も肩を落とした。「ただぼくの剣術はあいつには通用しない。ロビンだってあいつには敵わない」吐息をついた。「それにイングランドにもどってから、ぼくも変な感じなんだよ」
洋一はふいに涙が引っこんだ。
「モルドレッドはロンドンを攻めてるんだろう? ロビン・フッドは軍隊を集めてる。規模がどんどん大きくなってるだろ?」
つまり太助はもう個人の戦いを超越して手に負えなくなってきている、ということをいっているのだ。
洋一も気落ちしていった。「こうなったら、ぼくらじゃあ……」
「うん。だからこそロビンから離れずついて行かないといけないんだ。要するにウィンディゴは悪い方に物語を創造してるんだろ? ぼくらも創造の力で対抗するしかない。あいつはその勝負をしたがってる」
洋一は少し驚いた。勝負をしたがっているとは変わった物の見方だ。太助が顔を上げて洋一を見た。
「ロビンをフランスに呼び寄せたように、物語を導くことはできるはずだ」
「うん……」
と洋一は返事をしたが、その声に力はなかった。肩も沈んで目も地面ばかり見ている。太助の役に立ちたいとは思った。でも、あまりに責任が重すぎる。ウィンディゴの恐ろしい姿が頭に浮かぶとそれだけで胸が締付けられる、足が震えてしまう。
太助が励ますように肩をつかんだ。
「大丈夫だ。今度は男爵がいる。君はぶっつけでもうまくやったんだ。先生がいればきっと大丈夫だとも」
「先生? 男爵が?」
「そうさ。男爵なら本の使い方を教えてくれる」
「う、うん」
今度はもう少し強くうなずいた。
太助は先を急ぎながらつぶやいた。「だけど、不気味なのはモーティアナだな」
洋一も気がついた。「あいつ、ぼくらがシャーウッドに戻ったのに手を出してこない」
「ウィンディゴはモルドレッドとモーティアナに手を組ませるはずなんだ。あいつの魔力に銃士たちが加わったら厄介だぞ」
「それに二人ともマーリンと関わりがある」
「あいつらに手を組まれたら厄介だ。もどって食事をとろう。すんだらすぐに出発の準備だ。ウィンディゴは男爵のことを憎んでたから。きっと自分の他に創造の力を持つ人物を許せないんだよ。早く助けに行かないと」
「州長官もやつらの手先なのかも」
二人はさきほどよりずっと急いできた道をもどっていった。だけど、洋一は気づいていなかった。その右手の黒みが増して、モルドレッドの元を離れて以来弱まっていた痛みが僅かずつぶりかえしてきたこと、死の呪いが膿があふれるようにして皮膚から浮き出てはあらたな宿所を求めてのたうっていることに。
○ 6
サー・リチャードは自らの城が包囲されていると聞いて、真上を見たまま沈黙してしまった。口にこそ出さないが、動かない体が歯痒かったのだろう。
「ロビン、シャーウッドには街の者たちも集まってる。森を空けるわけにはいかねえぞ」
「仕方ない。ギルバートら半数は残そう」
「モルドレッドの前に、州長官と戦うのか」
リチャードはほんのり笑った。イングランドにもどって以来のロビンの忙しさがおかしかったのだろう。
ロビンは城に立て籠もったという昔の仲間をタックたちだとみた。森に残っていたという話をジョンが聞いているし、ミドルはタックを頼ってシャーウッドに向かったからだ。
「わたしの城にいた兵隊は四十人ほどだった。タック和尚たちを加えても百名とはいまい」とリチャード卿が言った。
「今は、イングランドの貴族に檄文を回しているところだ。彼らが集まるまで待った方がいいのではないか」とギルバート。
「彼らが集まるのか俺にはわからん。貴族たちはみな十字軍の遠征で疲弊しているし、そのうえジョン王に反乱を起こした者も多いと聞く。それに彼らはモルドレッドと戦うために集まるのだ。リチャード城の奪還に手を貸すとは思えない」
「結局頼りは俺たちだけか」ウィルが吐息をついた。彼は自慢の腕をへし折られて弓も使えない。「あの男に首を刈られるのだけは勘弁だぜ。州長官を破るいい方法は?」
「状況をみないとなんともいえん」とロビンは心許ないことを言った。ともあれ、相手の数もわからないのだからいたしかたない。「この場はギルバートに任せて、我々は出発しよう。州長官側の布陣をみたい」
□ その二 呪われた一座の再会について
○ 1
午前十時を過ぎたころ、事態は変わりはじめた。シャーウッドの森は、石を畳んだ古代の街道や獣道が縦横に走っている。東南の街道でアーサー・ア・ブランドは見張りに立っていた。木の根元で疲れた体をいやしていたが、騎士たちの騒ぎ声を聞きつけて目を開けた。
生け垣に駆けつけたアーサーが目にしたのは、草原を連れ立って歩く難民の姿だった。服はズタボロに裂かれ、乾いた血もそのままだ。まだ血を流している者もいた。戦闘に巻きこまれたものとアーサーは見た。騎士たちがそれらの人を保護している間にも、一人また一人と難民はやってくる。
時間が経つほどに難民の数は増えていった。数十、数百の単位でまとまってやってくる。荷車に家財道具を積んだものもわずかにいたが、彼らのほとんどは無手で命からがら逃げだしたものと見受けられた。
アーサーは彼らがどこからやってきたのか尋ねさせた。彼らの多くが答えた場所は、ノッティンガム。
○ 2
ロビンは出発を前にして難民の対応に追われることになった。甥のガムウェルが、
「難民の数が多すぎる。アジトに入れるわけにはいかないぞ」
アジトの小屋に一味の残党が集まっている。
「この状況で外に放りだすわけにはいくまい。君とアジームで鹿狩りを行うんだ。まずは飢えたものを食わせてやれ」
「やつらノッティンガムから来たといってる」とジョンが言った。「州長官も銃士隊とは戦ったみてえだ」
「城を空けた隙をつかれたと考えるべきだろう。落城の前に引き上げたのなら、タックたちも落ち延びることができたはずだ」
「銃士隊がノッティンガムを襲ったんだ。パレスチナでサラディンがやられたことを、こっちがやられてる」
ウィルの言葉に、ロビンはうなずいた。ちびのジョンに、
「君とアランは銃士と戦ったんだな。やつらはサラディンのいうとおり、化け物に変わったのか?」
「ああ、まちがいねえ。太助と洋一も一緒だった。首を狩らねえ限り死ななかった」
「ロンドンを落としたのもおなじやつらにちがいない」とアラン・ア・デイル。
「たった数十人でノッティンガムを落としたって噂だぜ」
「あいつらならやる。普通の兵隊にあいつらを殺せるはずがねえ。サラディンも、リスベをとれなかった」
リスベはモルドレッドが死守したパレスチナの小都市である。
「ロンドンが落ちたのも夜間だ」アランが言った。「だが、あの処刑台では、やつらは変わらなかった。サラディンの話と符号する。やつらも昼間はただの人だ」
「長期戦ができないなら、陽のある内に決着をつけるしかない」とガムウェルが一座を見渡した。「となると、これだけの人数では……」
ロビンは黙った。アーサー・ア・ブランドが庵に入ってきたからだった。
「ロビン、来てくれないか」
「少しまて。今――」
「すぐに来てくれ。州長官が君を待ってる」
○ 3
最初のうち、ロビンはそれが誰であるかわからなかった。身に付けているのは下着だけで、それも泥と血で汚れている。カールを巻かせていた髪は無惨に刈り取られていたし、そこからのぞく耳は片方がない。上着はぼろ布同然となって首の周りを垂れていた。かつて州長官であった男は森の隙間から落ちる陽光さえ恐れるかのように、木の根元に這い寄って、手足を抱きガタガタと震えている。
ロビンが目の前に立ったとき、ロバート、と州長官は言った。
「お前か」
州長官は目を見開いてロビンを見つめた。震えは止まったが、州長官は目を伏せてぶつぶつと呟きはじめた。生きていたのか、いや、しかし、などという単語だけがわずかに聞き取れる。ロビンは彼のすぐ側に膝を落ち着ける。州長官はビクリと肩を震わせ呟きを止めた。わずかに体を傾けて、ロビンを見ようとした。
「一体、ノッティンガムでなにが起こったのです。あなたの軍はどうした?」
ロビンが尋ねると州長官はバッと顔を上げ表情をゆがめた。かと思うと唸りを上げはじめた。
「お前のせいだ。お前のせいで私の城は無茶苦茶になったんだぞ。来い、あそこへ行って全部見ろ! あの魔女がやったことを確かめろ」
州長官はロビンにつかみかかったが、その腕はおかしな形に曲がっていた。アーサーたちは州長官を諫めようとしたが、よく見ると長官の指はすべてへし折られているのであった。ちびのジョンは、そっと脇を抱くようにして州長官を引き離した。長官は彼のことすら気づかないようだった。難民の人々が見つめる中、長官はおいおいと泣きはじめた。
「やつらは引き裂くんだよう。私の周りにいた者も全部なんだ。おい、あれを見ただろ!」
と長官は立ち上がり、自分を遠巻きに見る群衆に言った。
「お止しなさい。みな怯えている」
ロビンがいうと長官は荒い息をつきながら、地面をにらむ。その様子は自分の見た物をなんとか理解しようとしているかのようだった。
「やつらは叩いた。そうだあいつら私の部下を叩いたぞ。豚の肉かなにかみたいに叩いてつぶして、それだけじゃない。やつら噛みついたんだ。人を食ったんだ」
その痛ましい話に、ロビンの部下たちも互いに顔を見合わせた。そして、そのような話を聞いたこと、その場に居合わせなかったことを恥じるみたいに顔を伏せた。
ロビンはノッティンガムの落城を信じる気になった。果たして人はそんな目に遭ってまで戦意を駆り立てられるものだろうかと。最初は憎しみに駆られたかもしれない。けれど、その憎むべき相手が不死だとしたら。死人を相手にする恐怖ならジョンとアランは骨身に徹して知っていたし、サラディンの勇猛な兵ですらわずかな銃士に敗れ去ったのだ。
「ノッティンガムにモーティアナがいたのか。そいつが俺にロンドンに来いと言ったんだな」
州長官は左手で髪をかきむしり、右手ではロビンを指した。
「ロンドンには行ってはならん。どんなに急かされても行っては駄目だ」長官は木の幹に寄りかかり、こどものように目を拭った。「みんな死んでる。モルドレッドには従うしかないんだ」ギョロギョロと視線をさまよわせる。「お前でも、きっと無理だ」
「それはあなたの本心か」
ロビンは訊いた。それは悲しげな口調でもあったので、長官は鼻を拭いふりむいた。
「あなたとは長年いがみあってきた。私はあなたを憎み、あなたも私を憎んだ。だが、私はあなたのそんな姿を見たいとは思わない。私に言いたいことはそんなことではあるまい。州長官、あなたに訊こう。あなたが私に望むものはなんだ」
州長官はロビンの頬を張った。
「やるというのか! 私の願いをお前が聞くのか! 私はお前を殺すことばかり考えてきたんだぞ!」
ロビンは張られた顔を上げた。その頬は州長官の折れた骨のせいで、赤く腫れ上がっている。
「過去にこだわるには、我々はあまりにも無くしすぎた。積年の怨讐も今は置こう」
「私を許すのか」
ロビンはうなずいたが、州長官は折れた腕で両目を覆っており、彼のことを見ていなかった。けれど、その無言の間を彼は了解と心得た。
「ロビン、あいつらを追い払ってくれ。妻や娘の敵を討ってくれ。頼むよ」
州長官は膝を折り、天に向かい戦くようにして泣いた。皆は州長官の家族に起こったすべてを察し、ある者は帽子を取り、ある者は胸に手を当て哀悼の情を示した。
「みんなの仇を討ってくれよお。私は、私だってやりたい。憎いあの魔女を殺したいんだ!」
「いいだろう州長官」とロビンは言った。「俺はロンドンに向かい、モルドレッドとやつの軍隊を打ち払う。ロビン・フッドが、やつらをイングランドより閉めだしてやる!」
最後の言葉は周りの群衆に向けられたものだった。傷ついた人々は歓声を上げることすら控えているようだった。事の困難をわかっていたし、喜びを受け入れるには心が疲れすぎていた。けれど、人々は自らの希望の光をみた。ロビンはその光となるべく、また歩みはじめたのだった。
○ 4
ギルバートはロビンの行動に難色を示す。
「本当にロンドンに行くのか。どう考えてもまずい。それは罠だ。いいか、昼間なら、やつらも化け物に変わりはしない。だが、ロンドンではすでに変わってしまっている」
ちびのジョンは恐れるように身をすくめた。変わっている、という言葉はなにか不気味な気がした。
「行かなければやつらはイングランド中の町や村を襲う。そうなったら手がつけられん」
ロビンの言うとおりだ。ギルバートは黙る。
「やつらの兵力はいかほどだろう」とアーサー。
「三万人とも聞いたが?」とアラン。
「それは誇大だろう」ロビンは言った。「ロンドンを攻め落としたので数が誇張されているのだ。十字軍のころとさほど数は変わっていないはずだ。おそらくは三千から五千といったところだろう」
「実際の兵力は数倍と見た方がいい。数人掛かりでなくてはあいつらは倒せない」とジョンが言った。
「ともあれ、タックたちは無事のようだな。生きていれば、噂をきいていずれはここに現れるはずだ」
「それにしても、数が足りない」ギルバートが言った。「卿らの軍を入れても五千人を少し越えるばかりだ」
「これ以上の数は望めまい。俺に作戦がある」
太助がテントの幕を払って乗りこんできたのはその時だった。ジョンは驚いて少年を見た。
「なんだ、おめえ、今は入ってきちゃだめだ」
「ちがうんだ。洋一の様子がおかしいんだよ。すぐに見てくれ。呪いに取り殺される」
ジョンが息を飲むのと、男性に抱えられた洋一が天幕に入って来るのは同時だった。洋一は右腕を腹の上に乗せ、それを左手で抱えている。まるで大事なものを隠しているようだったが、ジョンはその指の隙間から真っ黒な呪いがヘドロのように滴るのを見た。
「ちくしょう、モルドレッドか!」
ジョンはそんなものは役に立たないのに大剣を掴み上げて洋一の元に走った。洋一は、血走り涙ぐんだ目で彼を見上げた。鼻水が垂れ、辛そうに呼吸をしている。
「ちくしょう、ロビン、この子を助けてやってくれ。どうにかしてくれ!」
ジョンは大喝したが、手だけはやさしく洋一の額を撫でている。
「誰かなんとかしてくれ。なんとか……」
ジョンがふりむいたとき、天幕にいた者は誰も彼の方を見ていなかった。太助が濡れた目を光らせて大刀を抜きはなった。
「なぜお前がここにいる!」
天幕の奥から進み出てきたのはモーティアナだった。ロビンたちはみんな老婆のことを見ていたのだ。一番近くにいたウィル・スタートリーが、鋭く短剣を抜いて老婆の胸を突き刺そうとした。
「そう急くでないよ」
モーティアナは一瞬でヘビに変わり、スタートリーの二の腕を這い上りだした。ロビンが帯剣用の剣で抜き打った。正確に頭部を薙ぎ払ったが、ヘビはロビンの太刀筋を読んでいたように身をひるがえし、天幕の奥に飛んだ。みなの目が後を追ったときにはまた元の姿にもどっていた。
「みんな、待ってくれ、そいつはただの使い魔だ」と太助が鋭く静止した。「それに呪いをかけたのはこいつじゃない。こいつを斬ってもどうにもならない」
蛇は、きえ、きえ、きえっと笑った。
「一番頭をつかうのがこの小僧だとわね。ロビン・フッドが笑わせよる」
「お前がジョン王の宮廷魔術師か」とロビン。
「ちがうね。モルドレッド卿の魔術師さ」
「やっぱりお前が」太助は前に進み出ようとしたが、今度はジョンに止められた。「モルドレッドと組んでたんだな。後ろにいるのはウィンディゴか。知ってるぞ!」
モーティアナはケケケケッと、細首をのけぞらせて笑う。
「だから、なんだと言うんだい。それが重大な秘密だとでも。あたしゃね、こう言いに来たのさ。新しい王からの伝言だ。兵を連れてノッティンガムに来い。そこで再決闘をやろうじゃないか。フランスじゃあお前を取り逃がしたからね。そこの小僧もだ! 二人とも連れてこい!」
モーティアナは唾を飛ばし、蒸気を吹き上げ、鬼の形相で太助を指さした。
ロビンは帯剣を捨てると、愛剣を取り上げて、スラリ抜き放つ。
「呪いをかけたのはモルドレッドだろう。貴様ではない。殺しても問題はあるまい」
と歩み寄った。モーティアナが手を挙げると、洋一が苦しみだし、呪いが一気に吹き上がった。洋一を抱えていた男は思わず彼を突き放した。ジョンと太助が互いに武器を放りだして、洋一の体をつかまえた。
「忘れたのか。あたしもマーリンの弟子なんだよ」
ロビンはその様子をみて、憤怒の形相でふりむくと、気合いとともに老婆の首を薙ぎ払った。
モーティアナの首は天幕の隅に飛び、柱の一つにぶつかり、ドン、と鈍い音を立て地面に転がる。生首はしかし、生きているようにロビンの足下まで転がり、真っ赤な目で彼を睨み上げた。
「お前も直に死ぬ。次に転がるのはお主の首だ」
ロビンが両手で剣を持ち上げ、止めを刺そうとしたときには、モーティアナの生首は激しい煙を上げて(金属と硫黄の臭いがした)、パチパチと音を立てながら、元の蛇に戻った。
「どういうことだ。やつはロンドンを攻めていたはずだろう。ノッティンガムにいるのか?」
とアランが訊いた。アジームが、
「だめだロビンどう見ても罠だ」
「だけど、あいつがノッティンガムにいるならチャンスだぜ。銃士の主力はロンドンだ。今ならあいつをやれるかも……」
ウィル・スタートリーは沈黙した。洋一の少年のうめき声が空気を引き裂くように伸び、少年を心配して名前を呼ぶジョンの声が部屋中を満たしたからだ。
「大丈夫か、洋一」
洋一はどうにか目を開けた。まぶしい物を見るように、太助とジョンを見た。
「ありがとう、ジョン。ましになったよ」
「よかった。死んじまうかと思ったぞ」
「呪いはどうなったんだ」太助は一瞬片手拝みをすると、洋一の胸元をそっとめくった。昨日見たよりもいっそう広がっている。洋一の乳首が見えないほどだ。
太助は無言で服を下ろした。洋一の目をじっと見た。洋一が弱々しく、だけどなにかを伝えるようにしてうなずいた。太助は立ち上がった。
「ロビン、ぼくらを連れて行ってくれ。あんたも見ただろ。あいつらがつかうのは本物の魔術なんだ」
「馬鹿な」ガムウェルが叱りつけるように前に出た。「本で対抗するとでもいうつもりか。相手はあのサラディンも叶わなかったやつだぞ」
「あいつの裏にいるのはウィンディゴなんだ。それでモーティアナもモルドレッドも力が強くなってる」
と少年は言った。みんななぜか話している太助よりも洋一少年の方を眺め下ろした。洋一は力なくジョンの腕の中。みんなのことを見上げている。
「男爵と父上ならウィンディゴと対抗できる。ずっとあいつと闘ってきたから」
「おめえたちの親父のことか」とジョン。「だが、今どこにいる?」
「タック和尚たちといるはずなんだ」
「その連中なら、魔術に対抗できるのか」
とロビンが割りこんだ。
「もちろんだ」
太助は胸を張って応えたが、洋一がそっと目を反らしたのをロビンは見逃さなかった。ロビンは言った。
「いいか、城の包囲は解けている。すでにタックたちにはこちらに来るように使いをだした。その中にお前たちのいう二人が混じっているならよし。いなければ我々だけで闘う」
「でも、ロビンだって、パレスチナであいつに魂を盗られたじゃないか。普通に闘ってもあいつには勝てないんだ。みんなみんな、あいつに殺されたんだぞ。剣や弓じゃ殺せない、殺せないんだ!」
「だめだ」
ロビンの声は厳しく表情は冷たいものだった。太助は上から突き放されたように感じて黙りこんだ。
「ノッティンガムでもロンドンでも大勢人が死んでいる。一刻も猶予はない。兵が集まるまで一日だけ準備を整える。その間に、お前たちの親父が現れることを祈ろう」
太助はおや? となった。ロビンは本に頼らないと言ったのに、二人が現れるのを祈るような口ぶりだったからだ。モルドレッドの魔術を一番に受けたのはロビンだったし、モルドレッドの体内にいただけに、洋一の力はなんとなく感じていたのかもしれない。
「ジョン」
と太助は声をかけて、洋一の体を無理矢理背負った。彼は大人たちの静止も聞かず天幕の外に出て行った。二人で男爵と父親を捜すつもりだったのだ。
○ 5
太助は洋一を連れて北の街道を目指した。リチャード卿の城はその方角にある。ロビンの連絡を聞いたタックたちはその街道を通るはずだ。ウィル・ガムウェルとスタートリーもついてきた。太助は洋一を背負ったまま森を出て行こうとしたが、ガムウェルが止めた。
「タックたちは必ず来る。その中に親父がいることを信じろ」
「いなかったら」
太助はさらに歩こうとしたが、ガムウェルは前に回りこみ、膝をつくと、その肩を押さえた。
「外は敵だらけじゃないか。洋一はまともに動けないんだぞ。またモーティアナに襲われたらどうする」
太助は強情に顔を背けた。洋一がおろしてくれと背中で言った。
太助は心配げにふりむいた。「大丈夫なのか?」
「大丈夫だ。病人扱いするなよ」
太助は木の根元に彼を下ろした。洋一が幹に背をもたせかけると、ガムウェルが乾いたパンを千切って少年たちに渡した。スタートリーが銅の筒から冷めたスープを椀に注ぎ、やはり二人に渡してくれた。
「焦るのはわかるが、もう一日しかない。それにモルドレッドのことは俺たちに任せておけ」
「分かってないよ」太助は怒ったようにパンをほうばりながら(口いっぱいにほうばったので、しゃべるとパンの欠片が散った)、「モーティアナはぼくらにもこいって言ったじゃないか。あいつは使い魔を斬られて怒ってる。ウィンディゴの手下だから、ぼくらが何者か知ってるんだ」
ガムウェルは少年がなにを言っているのか分からずに不審げに眉を寄せた。スタートリーは吐息をつきながら少し離れた幹にもたれてしまった。
ロビンの部下たちも見張りに出ていた。洋一と太助は無言でパンを食べ、ときおり街道を見た。本の世界に入って以来、一体どれほどの時間が流れたのかさっぱりつかめないほどだった。ガムウェルは洋一の右腕に包帯を巻いて首から吊すようにしてやった。呪いの影響で彼の右腕は動かなくなっていた。
「動くようになるかな」
と彼はこの父親ともとれるほど年の離れた青年を見上げた。「腕が右腕が動かないと文が書けない。そうなったら……」洋一はまた涙ぐんで目を落とした。ガムウェルは励ますように肩をはたいた。
「今はあせるな。養生するんだ」
太助はそんな二人を見られなかった。洋一を心配できる心の余裕がなかった。ピタリとも街道から目が離せなくなっている。父上は死んでいるかもしれない。太助はふてくされたような気持ちで、側の草を千切り葉を落として茎を噛みはじめた。自分でもどうしていいものやらわからない。彼の精神は行動的に出来ていたからだ。じっと立ち止まって考えこむなんて、父親か誰かがすべきことだった。けれどこれまでそれをしてきた人たちは一人また一人と彼の元から去っていったのだから、父親がそうなってもちっともおかしくはない。そのことが恐ろしく、その恐ろしさを吐きだすみたいにちびちびと草をはんだ。
太助がその草を捨てたのは街道の遠くに大勢の人の姿を見たからだった。
「洋一、人だ!」
と彼は大人たちが飛び上がるほどの声を上げて友人を呼んだ。洋一もガムウェルを突きのけるようにして(実際にはこの青年に支えてもらわなくては立てなかったが)立ち上がった。
太助は街道に向けて駆け出そうとしたが、すぐに気がついたように駆け戻り呆けたような顔をして洋一の手をとった。人の群れ目がけて走り出そうとしたが、また二人のウィルに止められだった。
「落ち着け、みんなすぐに到着する。親父たちがいるか、すぐに分かる」
「でもっ」
「落ち着け。洋一を見てみろ」
スタートリーに言われて太助はふりむいた。彼に引っ張られて洋一は転んでしまっている(そんなに強く引いたつもりはなかったが)。太助はごめんよと謝罪しながら街道を見た。
太陽が差しているようだった。曇天で風も冷たくなっているのに穏やかな光が当たりいっぱいに降り注いでいるみたいだった。街道の人の群れはどんどん大きくなっていく。ガムウェルは森の中で待つようにいったのだが、太助はその手をふりはらい洋一の手を引いて彼を助けながら下生えを越し、街道の石畳の上に足を置いた。
太助はずっと不安だった。父親が死ねば、中間世界の侍はすべて死に絶えたことになる。自分が生き残ってこられたのだから父親も、とは思いたかった。けれど、侍が敵なしの存在であるならば、鬼籍に入った人たちも、いまごろみな自分の側にいてくれたはずである。
太助には目に映る父親の姿が一人でなく、百人の侍の姿に見えた。もどってきた、父上が、侍たちがもどってきたと思った。草原の葉がパラパラと鳴った。その街道が大昔からあってあの群衆も遠い過去から来るようだった。彼は遠い未来にいるからあの人たちもここにはたどり着けないんじゃないかと思った。彼はこう叫びたかった。おおい父上、ぼくはここにいる、ぼくはここだ!
それから彼はやってくるのは死んだ侍たちで、ともに死んだ洋一と彼を迎えに来ているのだと思った。それならまあいいかと思った。ウィンディゴのこともモルドレッドのこともまあいいかと思った。そんな自分をおかしく思い、二の腕で眼を拭った。洋一に覚られぬようにしたが、つい鼻をすすってしまった。
洋一は呆けたようにしてまるで初めてお座りをした赤ちゃんのように足を投げ出して座っている。
人影が大きくなった。そのうちその群衆の中に動揺が起こった。群衆の後ろから誰かが前に出てこようと人を押しのけているのだった。太助は一瞬我慢して下を向いた。顔を上げたときには我慢できずに走り出していた。
「やっぱりだめだ。ごめんよ、洋一」
だから、もう我慢しなくて良かった。涙も流れるに任せてしまった。彼は袴を振り乱し股立ちをとるのも忘れて精一杯に体を運んだ。遠くで父親が群衆の列を抜け、彼に向かって腕を広げおなじように駆けてくるのが見えた。
洋一は、二人のウィルと一緒に歩きだした。走ろうとしたが、その度に膝が抜けてまた歩いた。まるで呪いの粒が全身の関節で遊んでいるみたいに頼りない。遠くで太助とおじさんが抱き合うのが見えた。おじさんが太助を小さな男の子みたいに振り回しているのが見えた。洋一はそれをまぶしい物を見るみたいに見た。本当にまぶしかったから、腕で目を覆って泣いた。ぐしぐしと音を立てて泣いた。悔しくて腹立たしくて、そして嬉しかった。
「父さん、父さんの馬鹿野郎」
と彼は言った。誰かがやさしく背を叩いたのにも気づかなかった。親子の側で陽気に騒いでいた男爵が洋一に気がついて駆けてくると、洋一は肩の手を払って走った。なんどか転んだが、その度に立って走った。
男爵は老体にむち打って走っていたのだが、そのうち洋一が近くになり、この名付け子の様子が分かるにつれて胸を刺したのは純然とした恐怖の錐だった。なんということだ。この子は今すぐ死のうとしておる。驚愕の余りこの老人はその場から一歩も動けなくなった。
「洋一その姿はなんだ、まさか本をつかったのか、ウィンディゴめにやられたのか、くそおあやつめ」
男爵は金切り声を上げるみたいに一気にまくし立てた。その声に驚き、太助と奥村でさえふと顔を上げたほどだった。男爵は腕を上げると、洋一につかみかかるみたいに走った。洋一も駆け寄ろうとしたけれど、数歩よろめいただけだった。
「まったく今までどこにいた。無茶ばかりしおって一体なにをやっておったんじゃ!」
男爵は形相もすさまじく迫ってきたから、洋一はとっさに身を固くした。彼が喜んでいると分かったのは、洋一が強く男爵に抱かれて胸にかき抱かれてからのことだった。
「もう無茶をしてはいかん。もう無茶をしてはいかん。二度とわしの側を離れるな。二度とわしの側を離れるな」
「ぼ、ぼく……」
と洋一は言った。彼は言おうと思った。男爵がいなくなってどんなに不安だったか、どんなに心細かったか。これまであった苦しいことも。自分がどんなに立派にやったか、太助と協力しあったかを。けれどそのことを思うたびに彼の心は詰まり、ついには声を上げて泣いたのだった。そして、洋一がこんなに盛大に声を上げて泣いたのは、この世界に来て以来のことだった。太助もおなじなのかもしれない。
○ 6
リチャード城の攻防戦は激しいものだった。州長官のみならともかくモーティアナも加わっていたから、苦闘もはなはだしく戦死者も大勢出していた。今も旅の一座は(リチャード卿の子息、スティーブンも城を放棄して駆けつけている)怪我人だらけ満身創痍の者ばかり。ミュンヒハウゼンと奥村の力添えがなければとっくに落城していただろう。
二人はやはりシャーウッドの森に出ていたようで、そこでモーティアナの焼き討ちに合い窮地に陥っていたタック坊主らの戦闘に加わった。もともとミュンヒハウゼンは自分の物語でも騎兵隊長だったし、奥村にいたっては百戦錬磨の侍をまとめ上げてきた男である。
出先にモーティアナがいたことでも、本の世界への進入にウィンディゴが手を加えていたことが分かる。一つまちがえば四人ともいまごろ命を落としていたかもしれない。よく助かったな、と洋一は今更ながらひやひやした。
男爵と奥村は今では攻城戦の将軍格に祭り上げられていたから、そのこどもらが見つかったことで、みな疲れと痛みを忘れておおいにさざめきあった。洋一は周りの大人たちの興にものせられて、イングランドについてこの方の冒険を多少の腹立ちも交えて語って聞かせた。泣き虫ジョンに会ったこと、ロビンを助けるための数々の戦い。そして、モルドレッドとの苦闘。
太助は父親に会えただけでもずいぶんと満足したらしく(それに危険をくぐり抜けるのも慣れていたから)話すのは洋一に任せておとなしかった。周りの大人たちと他人事のように笑っているものだから、洋一はますます腹を立てたが、それでも彼は楽しかった。ようやく雁首が揃った。こうして役者は顔をそろえたのである。よく考えるとその世界に来て四人が顔をそろえたのはこれが初めてのことだった。洋一は奇妙に心強くなり、今では伝説の書だって自在に使いこなせる気がした。
笑いさざめく人々の声が途絶え、足も止め、激しい感情の波にその身を震わせはじめたのは、アジトまでの道中半ばを過ぎてのことだった。騒ぎを聞き付け駆けつけてきたのは、ロビン・ロクスリーとその一味の者たちだ。リチャード軍に加わっていた古い一味の面々も、ロビンと親交のあるリチャード城の騎士たちも、信じられないものを見た。
ロビンだ、ロビンが生きてた。本当にロビン・フッドが生きていた。
「あれがロビンか……」
とミュンヒハウゼンは感に堪えたように首を振った。
みなはようやくもどってきた首領の元に一散に駆け出し、イングランドの人民に希望と絶望をもたらしつづけた男をもみくちゃにした。
洋一はその様子をみてニコリともせずうなずいた。物語が悪い方にねじまがっても、この人たちはみんなロビンの味方なのだ。
「やっぱりだよ、男爵。ウィンディゴはこの世界に手を出せるけど、支配してるわけじゃない。あいつの創造の力だって、なんでも自由に作り替えられるわけじゃないんだ」
「わしもそう思う。ウィンディゴとてロビンの世界観には縛られておる。無理をすれば矛盾が起きるのは当然のことだ」
と男爵はうなずき、それはこちらもおなじことだ、と言った。
奥村はこどもたちの頭をそれぞれ一つずつ叩くと、ロビンの方に歩いていった。ロビンフッドが部下を従えてこちらにやってきたからだった。イングランドの義賊は手を差し出し、侍はその手をとった。奥村はその手の先に並々ならぬロビンの力量を感じ取っていた。
「部下がまことにお世話になり申した」
とロビンは言った。奥村はすぐには答えず、唇をわずかの間噛み締めた。「二人の息子に無事会えたのはあなた方のおかげだ。私の方こそ礼を言わねばなりません」
ロビンは笑顔で頷いた。ちびのジョンがいそいそと近づいてきたが、ロビンが胸を叩いて止めた。
「もういい、ジョン。互いのあいさつはすんだ」
ジョンは不満に口をへし曲げながらも引きこんだ。ロビンはきらりと目を光らせた。
「さっそくだが、ノッティンガム攻略戦について話し合いたい。これまでどおりご助言願えますか」
□ その三 罠にはまったロビン・フッド
○ 1
「モーティアナがつれていた銃士は百名足らず。大方は死人となったと見ていいでしょう」とロビンは現況を説明した。「だが、やつらは昼間を嫌う。陽の高いうちは屋内に閉じこもって出てこないのです。すくなくともパレスチナではそうでした。攻めるとしたら早朝。が、疑問がある。我々の闘ったモルドレッドは慎重な男でした。やつがロンドンを捨て、単身で出向いてくるとは思えない」
「モーティアナのでたらめなのかも」
洋一は無意識のうちに右腕を撫でている。その言葉には多少の期待がこもっていたが、男爵は否定した。
「ウィンディゴは何重にも策を巡らすやつだ。裏にやつがいることを忘れるな。そして、ノッティンガムにはモーティアナがいる。やつは魔女だ。おそらく魔術の力でロビンと我々を引きはがそうとするだろう。不信を植えつけ分断し、各個撃破するのはやつのよくつかった手だ」
「しかし、死人になった銃士は知能がなくなるようだった」とアラン。「モーティアナのいうことを聞くはずがない」
奥村が、「ノッティンガムが堕ちてどのぐらいが経ったのです」
「二日は経っています」
「ウィンディゴには十分じゃ」と男爵。「ウィンディゴはのう。かつてのマーリンかそれ以上の存在だといえばわかりやすかろう。やつは直接手を下せんが、配下の者に力を与えておる。モーティアナは力を増し、モルドレッドもまたそうじゃ」
「ノッティンガムの危険よりもモルドレッドとモーティアナに手を組まれることの方が厄介だ。危険だが、ノッティンガムのモーティアナをまず叩くべきだ。モーティアナが倒せないならば、モルドレッドも倒せまい」
なぜならば、モルドレッドの方がウィンディゴの力を色濃く受けている可能性が高いからだ、とは奥村もいえなかった。
「だけど、あいつはロビンを狙ってるぜ。どんな手をつかってくるか……」
スタートリーは不安のあまり言葉をきってロビンを見た。ロビンは一同の意見を吟味するように目を閉じている。彼はいいだろう、といって目を開けた。
「ギルバートとタックはここにのこって、引きつづき諸侯と連絡をとってくれ。ロンドン奪還の準備を進めるんだ。我々はノッティンガムでモーティアナを討つ。攻撃は明朝――」
明日――
洋一は愕然となった。その暗澹たる思いは、兵士たちの恐怖心をすべて飲みこむほどに深かった。モーティアナとやる。そう聞くだけで、洋一の手足は一挙に冷えていった。そして、冷えた体のうちを妙に熱い息が流れていった。明日……
洋一は待ってくれと言いたかった。ぼくはなんの準備もできていない。それをいえずに唾を飲んだ。今、モーティアナと闘うなんて無理だ、と洋一は思った。あいつはロビンだけじゃなくて、太助とぼくのことも狙ってる。あいつの使い魔を斬ったから。洋一は伝説の書に力を吸われてやせ細った自分の体を見おろした。彼にとって唯一戦う手段は本しかない。伝説の書と、創作の力。
洋一だって、最終的には本に頼らざるを得ないことは分かっている。でも伝説の書は彼をいったんは拒絶したのである。
洋一は不死身の男まで登場させたウィンディゴの力を恐れていた。男爵たちが戦いの場に本の世界を選んだことをようやく理解した。みんなウィンディゴにはかなわないからだ。でも、あいつが手を出せなくとも、モーティアナが、モルドレッドがいる。彼は伝説の書を胸にかき抱いたが不安は去らなかった。たかが小学生の想像力で、あんなやつらと戦えるのかはなはだ疑問だった。自分が伝説の書に呪われているとわかってからはなおさらだ。
意識の混乱する耳にロビンの声が聞こえた。
「みな、今日は疲れた体を休めろ」
洋一はよろめきながらも顔を上げた。ちびのジョンらがロビンの命をうけて森の奥へと引き返していく。洋一はミュンヒハウゼンの後に付いていく。その顔からは、保護者にあえた喜びは完全に消えていた。こどもには似つかわしくない切迫した表情でつぶやいている。
書かなきゃ。伝説の書が使えるのはぼくだけなんだから。と洋一は考える。書くんだ、ぼくは書くぞ……
書くぞ……
○ 2
男爵と奥村はこの勇敢な少年らの育て親として、ロビン一味の歓待を受けた。二人の前には食料が山と積まれ、泡立つビールが用意された。
「しかし、モルドレッドが物語に加わるとはどういうことだろう」
「それに、あの手の痣はひどい。あの呪いは本物に見えます」
男爵は怒りもあって力強くうなずいた。「あれはかなり痛むといっておる。呪いはやがて全身におよんで、死に至るという話だぞ」
「モルドレッドを倒せば、呪いはとけるのでしょうか?」
「わからん。だが、ここは物語の世界だ。必ず世界観が存在する。アーサー王の伝説と混じり合っているようだが、二つの話が関係してくるはずだ」
奥村は男爵の言葉をよくよく考えた。「アーサー王の伝説の中に、呪いを解く鍵があるかも知れないということですか」
「そう思う」
「ともあれ、ロビン・フッドはモルドレッドと対決するつもりのようですな」
「我々も参加するしかあるまい」
「洋一と太助はどうします」
「連れて行く。わしはもう片時も二人をそばから離したくないのだ」
奥村も同感だった。
「洋一はやはり伝説の書に呪われてしまっていたのだな」
不憫なことだ。と男爵は言った。哀れむように洋一をみた。
奥村はモルドレッドの謎を解く鍵は伝説の書にこそある気がした。いや、もうやるしかない。方法がなかろうとも、自分が中世の王を斬り殺すまでだった。
○ 3
日没の荒野を走っていた。だだっ広い草原で隠れるところはどこにもない。太陽はもう沈もうとしていて、丘の起伏の影からは死人たち。彼が弱るのを待っている。洋一は沈む太陽に向かって叫んだ。待ってくれ、まだ沈まないで! 陽が消えたらあいつらに殺されるんだ!
洋一は草に足をとられて転んだ。すると、太陽から黒点のようにウィンディゴが飛んできた。
「小僧!」
ウィンディゴが彼を追い抜き行く手を塞いだ、その暗黒のベールは大空を覆うカーテンのようにでかかった。彼の恐怖でふくれた世界一巨大な兵士だった。洋一は後ろを向いて逃げだそうとしたが、細腕が腰に巻きつき食い止められた。モーティアナだ。老いさらばえた手で彼の足にからみついてくる。モーティアナは下半身が引き千切れており、ローブの下からは大腸が垂れ下がっている。あやうく失禁しそうになると、硬い指が彼の股をまさぐった。
「やめて、やめてくれ!」
背中になにかが被さる。小僧! と呪いの声を上げて彼の肩に上膊を投げだす。洋一が悲鳴を上げるたびにモルドレッドの体がとけた、それは死の呪いとなって体の中に染みていく。
「助けて誰か助けて」
と洋一は自由な腕だけを前方に伸ばして悲痛な声を上げた。
「助けるのはお前だ!」
ウィンディゴが落雷のような声を落とす。洋一が恐怖に耐えかねて目を開くと、目の前に伝説の書が浮かんでいる。本だ、ぼくの本だ、と手を伸ばした、すると、つかもうとするたびに、本はヒラヒラと彼の指をすり抜ける。
「どこへ行くんだ、こっちに来い!」
洋一が叱りつけると、突然本の表紙が開く。ページの中央から血がしみだして、それはたちまち紙いっぱいに広がってボタボタと垂れ落ちだした。その血液の真ん中に目が開き、誰かの頭がぐっと突き出てくる。
「本が欲しいか? でもお前もこうなるぜ」
洋一はギャアとわめいてたちまち失禁してしまった。モーティアナがゲラゲラと笑いながら、彼のふくらはぎに食いついた。
ウィンディゴが言った。「どこへ行く小僧。お主の目的はわしを討つことのはず」
「仇討ちなら……」
と洋一は震える声で言いかえした。本当は叫びたかったのだが、情けのない声しか出てこない。仇討ちならもういい、なんて口が裂けても言えなかった。言いたくない、言うもんか、と強情をはる。拒否だ、断固拒否するぞ
体の内に入りこんだモルドレッドが彼の体を操作しているのだ。瞼が勝手に開き、目玉がひとりでに動く。前方から、ヨタヨタとゾンビのように不格好な歩きでやってくるのは、誰あろうロビン・フッドその人だった。体中に銃痕があり、どうやらすでに死んでいるらしかった。「俺を助けるんじゃなかったのか小僧」
「ぼく、ぼく助けるつもりだったよ、書くつもりだったんだ!」
目玉がまた動いた。左からやってくるのは、ミュンヒハウゼン男爵だ。こちらは頭蓋骨が半分むき出し、やはり死んだ後だった。白目をむいて、彼を指さし、
「お前にはがっかりだ。これが名付け子だとは嘆かわしい」
洋一は反論しようとしたが、もう息も出てこない。ちびのジョンが右からやってきて(モルドレッドはご丁寧に、そちらに首を向かせた、鎖骨を肉の中で自由に動かし、添え木のように据え付けている。もう首も動かせない)、血を反吐のように吐きながら彼を非難した。
「おめえは嘘つきだ! おめえのやってきたことは全部嘘だった! この大嘘つきのコンコンチキ! おめえはヨーマンでもなけりゃ侍でもない! ただの薄汚い小僧っ子が、みんなを騙しやがって! みんなをお前が巻きこんだんだ! 両親の敵を討つなんて笑わせるな!」
洋一は今では大粒の涙を流していた。だけど、モルドレッドが目を閉じさせてくれない。だから、彼は最悪の罰のように仲間たちの死体を脳裏に刻みつづける。
「ぼくはやるつもりだった! ぼくは……!」
最後まで洋一が気に掛けていた少年は、すぐ足下のぬかるみにいた。モーティアナはいつのまにか死んでいたが、太助は傷つきながらもまだ生きていた。太助少年は泥の沼に下半身をずっぽりと埋めながら、洋一に向かって手を伸ばしている。
「洋一、ぼくを助けてくれないのか?」
それはあまりに痛々しく悲しげな声だったので、洋一はひゅっと息を吸いこんでしまった。太助の背後から腕を伸ばし、底なし沼に引きずりこもうとしているのは、実の父親なのだった。
「やめろ、やめろ! おじさん、太助を連れて行かないで」
身をよじると、腰に寄りかかっていたモーティアナがブラリと腕をひねって落ちた。洋一に同化したモルドレッドが、背骨の真ん中から第三の腕をはやしている。彼の頭を抑えつけ、友人がよく見えるようにした。
「ようく見ろ小僧。これが事の顛末だ。みんなお前のせいだ。お前はしくじった。なんの役にも立たない無能なガキだ。俺たちに逆らうなどと大それた事だったんだ。その結果がどうなったか、ようく見ろ!」
モルドレッドの絶叫は最後には団野院長の声と重なった。モルドレッドと院長、それにウィンディゴまで加わって、彼の頭を抑えつける。太助の顔が近くなる。
洋一は涙の海におぼれるようにして意識を無くしこうつぶやいたのだった。
もうやめて、ぼくの降参だ、もう降参だ……
○ 4
洋一が、激しく吐息して目を開けたのは、太助の死に顔を見た後だった。夢だったのか、と彼は声に出さず口の中でつぶやいた。洋一は毛布にくるまって寝ている。もちろん暖房には足りなくて、地面と接した背中はすっかり冷えていた。中央の焚き火は真っ赤に燃えている。脇を見ると、先ほど死んだ太助少年が、毛布にくるまりスヤスヤと寝息を立てている。
洋一はホッと息をついた。闇の中で顔を赤らめながら股間を確かめる。良かった。どうやら失禁してはいないようだ。洋一はもう一度太助を見る。いつもなら、すぐに目を覚ますのに、今日はワインを飲まされたせいか、それとも父と会えた安心からなのか、グッスリと眠っている。洋一は羨ましさと安堵感が入り交じった複雑な顔をした。太助がそんなふうに気を抜いてくれて、本心は嬉しかった。
その後すぐに伝説の書を確かめにかかった。
彼は布を腹巻き代わりに巻き付けている。本の感触を布越しに感じた。大丈夫だ、本は盗られてない。でも、今にも本の表紙からさっきの男が飛び出し彼の腹を食い破りそうで、ちょっと怖かった。
洋一は身震いをした。
周囲にはそうした焚き火のグループがいくつもあった。歩く人の姿が見える。モーティアナの夜討ちを警戒して、見張りがたっているのだ。
毛布から抜けだすと、悪夢から逃れるようにして焚き火に背を向ける。見上げると、梢の隙間から大きな月が複雑なモザイクに切り取られて彼を見おろしていた。洋一は本の世界の月は不思議に大きく見えるなと思った。現実の月とこの世界の月がおなじである必要はまったくないことに思い至って、軽く首を振り笑みを漏らす。それから、ウィンディゴは次はどんな仕掛けをしてくるだろう、どんな創造をするつもりかと考えて、また身震いしたのだった。
焚き火を少し離れると、土地が下り、土手のようになった場所に出た。そこに腰を下ろした。土地が起伏しているせいか、そこからだと空の隙間がよく見えたからだ。さきほどの月とは反対方向で鮮やかな星だった。洋一は学校で良くそうしていたように体育座りをして息を吐き、一人になったなとぼんやり思った。星を見上げていると、目尻から自然と涙がこぼれたが、自分ではそのことに気づいていなかった。あれが夢であったことに馬鹿のように安心していた。まだしくじったわけじゃない。まだ取り戻せるんだ。
後ろでカサカサという音がした。夢の帳は遠くなった。彼は目尻の涙を急いで拭いてふりむいた。ミュンヒハウゼンだった。
男爵は奇妙なほど悲しげで冷静な目をして彼を見つめながら、更地を行くような滑らかな足取りで森を横切った。洋一は男爵が軍人で騎兵隊長も勤め、トルコ軍とも戦ったことを思いだした。いずれも物語の世界での話だった。
男爵は隣にきて実の祖父がそうするように彼の隣におなじ格好で腰掛けた。
「男爵は月に行ったことがあるんでしょ?」
男爵はうむと頷いた。
それから男爵は月の話やそこでの仲間たちとの活躍をひとしきり話してくれた。彼は座談の名人で話は面白かった。けれど、二人を見おろす星々と周囲の冴え冴えとした空気はすぐに彼の心を現実に引き戻した。
眠らないのか、と男爵は訊いた。
眠れないんだ、と洋一は応えた。
「男爵、ぼくに本の使い方を教えてよ。明日はきっと本を使わなきゃいけなくなる。そんな感じがするんだ。男爵もそう思うでしょ?」
ミュンヒハウゼンはこどもように膝を揺すって微笑んだ。なぜか悲しそうだった。すぐに下を向いた。
「お主はのう、伝説の書に少しこだわりすぎだと思う」
洋一は真っ赤になってうつむいた。「でも、ウィンディゴがぼくに言ったんだ。どちらの創造の力が勝つか、勝負だって。あいつはモルドレッドをロビンの世界に連れてきた。物語を悪い方に作り替えてる。不死身の兵隊まで創ったじゃないか。それに対抗するって事は、伝説の書をつかうことだと思うんだ」
ミュンヒハウゼンが洋一の肩を揺すった。洋一は顔を上げた。
「わしはそうとばかりも思わんのだ。なぜならば、わしもお主も、本の世界で行動することで、ウィンディゴの策略を打ち砕いてきたからさ」
「どういうこと?」
「では、泣き虫ジョンが本来の姿をとりもどし、ノッティンガムを出たのはなぜだね? ここにロビンを信じる多くの仲間が集まったのは? シャーウッドの無辜の民がモーティアナの魔術にも命を落とさず生きながらえたのは?」
洋一は涙がみるみる乾いていくのを感じた。
「それはのう、わしやお主が登場人物と一緒になり、敵と戦うことで物語をよい方向に導いてきたからじゃ。――もちろん本を使わないということではない」
ミュンヒハウゼンは洋一に向けてやさしく微笑んでいた顔を、ふいに正面に向けた。洋一もおなじ方を見た。
「だが、本を使うことばかり考えてはだめだ。ロビンや仲間たちを救ってきたのはこの本ではない」とミュンヒハウゼン男爵は洋一のおなかを叩いた。「お主の知恵と」と言って額を指で突く。「勇気だ」
そうして胸を突かれると、洋一の心にも男爵の心がポトリと落ちた。洋一はさっと顔を背けて下を向いた。涙がにじんだからだ。
「その本のせいで恐ろしい目にも遭ってきたろう」
とミュンヒハウゼン。洋一は驚いて顔を上げた。
「知ってるの? この本に閉じこめられた人たちのこと」
「大勢見てきた」と男爵はうなずいた。「その本はあまりに魅惑的だ」
洋一も無言でうなずいた。その沈黙には本に飲みこまれた人物たちへの深い共感があった。同情も。
「お主にはおなじ末路を辿って欲しくない。どうしても本を使わねばならん時は自ずと来るじゃろう。わしとて本の力を使わずにロビンが勝てるとは思っておらん」とミュンヒハウゼン。「だから最初の質問に戻らねばならん。お主はわしに本の使い方を教えてくれ、と言った。わしは生憎と本の使い方は知らんと答える。というよりも、その本は誰にでも使えて、誰にとっても危険なものなのじゃ。むろん作家の持つ創作の手段は非常に有効じゃ。じゃがのう、ここには生憎と作家と呼べるのはお主一人しかおらん」
作家と言われて洋一は妙に気恥ずかしくなった。なにやら一人前の大人みたいだ。
「本を使いこなす唯一の方法があるとするならば、それは本に負けぬ強い心というほかない。そして、これはおおむね心の問題であって、使い方ではないという事じゃ」
「じゃあ、ぼくには本は使いこなせないじゃないか」
「父親を信じることじゃ」と男爵は言った。「お主をちゃんと育ててくれたとな。これまでの自分と人とのつながりを思いだすんじゃ。伝説の書の力を執行するのは、お主の信じる力だからじゃ」
「自分を信じろって、どうやって?」
「お主に秘めた才能を信じろなどとはいわん。それでは慢心にしかならん。それは自信とは似て非なるものじゃ。これまでやってきたこと。人がこれまでやってくれたことを思い出せ。みんなに感謝せい。そうすればお主は一人ではない。お前が生まれてこれまで何千何万という人がお前に関わり育ててくれたじゃろう。それこそがお主の力なんじゃ」
洋一は自分の人生を振り返ったが、おおむね出てくるのは学校生活ばかりだった。友人や先生のことを思いだした。洋一は自嘲するように笑って首を振った。
「大切なのは、なにを書くのか、どう書くかということだ。おそらく実現不可能なことでは本は願いをかなえまい。無理なことがらでは、世界に亀裂が生じることと思う。本は無理を埋めるためにつじつま合わせをするじゃろう。ウィンディゴがモルドレッドを登場させた。それはいい。だが、モルドレッドは強く元の世界に縛られておるじゃろう?」
洋一は思いだした。ロビンをイングランドに呼ぶそのつじつま合わせがどうなったのかを……。
最後にミュンヒハウゼンは、物語を生みだすとは空白を埋める作業なのかもしれんな、と言った。けれど、その空白という名のピースを埋めるにも、周囲の形に合わせなければならない。
できるだろうか……?
二人は元の場所に戻り眠った。当然のことながら、洋一に押し迫る不安と重圧の重しは減らなかった。頭の中では様々な想念が渦を巻いていた。ロビンはモーティアナをやっつけられるだろうか? ロビンを守らないと。でもあいつは太助のことも狙ってる。モーティアナはどうやってみんなとロビンを引きはがすつもりだろう。食い止められるのかな? 洋一は、そうして、雑多なことを思い浮かべては不安をかきたてていた。けれど、眠りに落ちる直前に彼が思いだしたのは、男爵の次のような一言だった。
最後には本の力が必要になるじゃろう。
○ 5
洋一はほとんど眠れず、しょぼつく目を開けた。周囲は闇が消えて、鳥が梢を渡り、梢の隙間から木漏れ日が落ちている。その光の光線は四辺形の不思議な図形を幾つも伸ばしている。美しかった。物語の世界がこんなにも美しくて、洋一はふと涙が出たのだった。横たわったまま、目尻を一筋また一筋と涙がこぼれる。ぼくはもっともっと世界を見てみたいこんな所で死にたくないと強く思った。ぼくはあんなやつらに殺されない。父さんと母さんはずっとぼくを守ってた。ウィンディゴに狙われたのはそのせいだ。彼は遠の昔から自分が呪われていたことを知っている。両親はそのことを隠匿し、使命を擲ってでも息子を守ってきたのだ。洋一は、お父さんお母さん、と心の中で呼びかけて、赤子がするようにもどかしげに手足を捩った。仇を討つぞ絶対にあいつをやっつけてやる。
ふいに視界が遮られ、太助の目玉が彼を覗いた。「大丈夫か」と彼は訊いた。
洋一は無言でうなずいた。
「でも泣いてる」
洋一はうなずこうとしたが、分厚い涙と鼻水の固まりがどっと出口に押し寄せて、彼は溺れないよう顔を背けた。少し咳きこんだ。
「ぼくは怖い……」
しぼりだすと、もう我慢できなくなり、洋一は両手をついてまるで吐瀉するように嗚咽を上げた。
太助は困ったように、でも慈しみをこめてその背を撫でた。
「しっかりしろぼくが付いてるぞ。ぼくが手助けするとも。一緒にウィンディゴをやっつけるんだ」
太助は小声で、けれど友人にちゃんと聞こえるように耳に口を近づけて囁きつづけた。だから彼は気づかなかった。彼らの守護者とでもいうべき二人の人物が、そんな少年たちを温かく見守りつづけていたことに。その悲しいけれど素敵な朝だけはウィンディゴの脅威が遠ざかっていたことにも。こんな朝はもう当分訪れないのだけれど……。
○ 6
曇天から、夜は立ち去った。牧村洋一と奥村太助は何日かぶりにノッティンガムにもどってきた。思えば、あの日は下水をつかっての逃避行で、街の上部をみる余裕もなかった。けれど、これほどまでに様変わりをしたのでは、かつての城塞都市を知る人たちもその比較は難しかった。
戦いの到来を告げる不気味な空の下、ロビン・フッドと主な人たちはノッティンガムを下方にのぞむ丘まで来ていた。ノッティンガムはその空の下で沈黙している。城門は開け放たれたままだった。慌てて逃げだしたらしく、街道には大八車や家財道具が散乱している。そして、その隙間を埋めるように死体がいくつも転がっているのだった。その城塞都市は所々から黒煙を上げているが、それも霞のように薄く、家々の帳を抜けると空と混じり合って見えなくなった。あの下に何千という死体があるのを感得して、洋一は懐を抱いた。
そのうちロビン・フッドの命令が人々の口から伝わってきた。
「死兵とは戦うな。狙うはモーティアナだ。老婆を見つけろ」
兵士らの大声に洋一は無意識にうなずいていた。
「いよいよだ。あの宿での決着を付けるぞ」
と隣で太助が言った。洋一は小さくうなずいた。もうずいぶん泣いたから気持ちはすっきりしていた。後ろ向きになったり逃げだそうとすることもなかった。けれど、恐怖心だけは漬け石のように乗っかってどこうとしない。奥村にいうと、恐怖心だけは決してどこにも行かないものなんだそうだ。
「恐れと縁を切ることは出来ないよ。うまく付き合うしかない」
とおじさんは言った。そのとおりかもしれない。
洋一は震える胸をそっと撫で下ろす。彼は蛇が嫌いだが、もう一生ものになりそうだった。
進軍は始まった。
ロビンフッドと三百の兵隊は、ノッティンガムの城門を抜けた。ロビンの周囲ではその閣僚たちがすわ死兵かと武器を抜いて身構えたが、街はそれ自体が死体と化したようにシンとしている。
「みろよ、ロビン」
ウィル・スタートリーが戦くように言った。路傍に石のごとく転がるのは死体だ。女性も幼児もたくさん混じっている。口は悪いが女こどもに優しいスタートリーを痛く傷つけた。スタートリーは剣と歯を食いしばりみんなを追い抜くように足早になった。つられて全軍の速度が上がる。ロビンはスタートリーを諫めようとした。なんの罠があるか分からない。列の後尾が門を抜け終わったとき、ロビンがふりむいた。
「おい、待て! 門を閉じるな! 開けるんだ!」
ノッティンガムの城門が凄い速さで閉まっていく。大地を削る音がロビンの耳にも聞こえたが、門を閉める者は誰もいなかった。近くにいた兵士たちが、門扉に取りつき突然の閉門に抵抗した。城門に働く力はすさまじく兵士たちは弾かれあるいは引きずられた。挙げ句の果てには三人の男たちが門に挟まれ圧死するのが見えた。胴体を引き千切られた仲間の上半身が地に落ちる。騎士たちはまるでなにかにすがるようにロビンに目をやった。ロビンはもうその方角を見ていなかった。彼は前方に目を向けていた。「くそ」と彼は言った。道に転がる無数の遺体が、起き上がり始めていたからだ。
どう見ても死体である。半ば腐敗が進んでいるし、みな白目を剥いている。内蔵を垂らしているものもいる。動かないのは首がもげた者だけだ。あんな大けがを負って生きていられるならば、この世で死ぬ者はいないだろう。どういう理屈かしれないが、あの老婆、死体を操れるものらしい。
ロビンがとっさに剣に手を掛けると、固い鞘の感触はなく、どろりとした粘着質の液体が彼の右腕を飲みこんだ。ロビンが目を見張って見おろすと、剣を中心に、まるでコールタールのように真っ黒な液体がしたたり落ちて、彼の下半身を飲みこんでいる。ロビンはその液体から足を引き抜こうとしたが、膠のようにへばりつきピクリともしない。
「ちくしょう、ジョン!」
そう叫ぶわずかな合間に、その黒いヘドロは津波のように立ち上がり、真上からロビンの体を飲みこんだ。
「ロビーン!」
ロビンは息も吸えず、動くことも出来なかった。
ジョンは夢中でヘドロをかきわけた。他の仲間たちも、黒泥をいやとかぶりながら、泥をかきわけロビンを救い出そうとする。けれど、ロビンに近づくことは出来なかった。ヘドロが後から後から湧いてくるのだ。ジョンは大きく息を吸いこんで、頭からヘドロに突っこんだ。夢中で手足を振り回し泥の海を泳いでどうにかロビンの手を掴んだが、その時にはジョンも力つき、意識が遠くなっていた。二人はヘドロの中で、体が引っこ抜かれるような感覚を覚えた。そして、臀部に固い地面の感触と痛みを感じて目を開けた時には、ヘドロに包まれたまま見知らぬ場所に舞い落ちていた。モーティアナの術中にいとも容易く嵌ったことをどちらともなく呪ったのだった。
□ その四 呪われたこどもたち、狂った魔女と対決すること
○ 1
ロビンが消えると、ヘドロは一瞬で地面に染みこむ。石畳に茶色の跡を残すのみとなった。アジームは真っ黒なままロビンの立っていた場所に飛びこんで、変色した石畳を手のひらで激しく打った。
「ロビンがいないぞ! モーティアナの仕業だ!」
と彼が叫んだ時には、後方から駆けてきた奥村真行が、愛刀を振りかざして、呆然自失とする仲間を叱咤していた。
「グズグズするな! 隊列を整えろ! 隊伍を組むんだ! なにをしている!」
彼の呼びかけにもロビンの部下たちは、唖然とした表情を隠さなかった。そりゃそうだ。目の前で頼りとする首領が消えたのだから。アランもウィル・ガムウェルも、泥を頭からかぶってアジーム以上に真っ黒になっている。
そして、部隊の中央では牧村洋一がやはり呆然とつぶやいたのだった。
「あのときだ。ロビンは使い魔を斬った。あんなに簡単に斬れるのはおかしかったんだ!」
モーティアナはあの瞬間に、ロビンの剣に仕掛けを施していたのだろう。だが、洋一の叫びも後の祭りだった。
「貴様ら言うことを聞け! 戦わんか!」
奥村は必要とあれば、仲間を殴ってでもシャンとさせようとしている。ロビンの閣僚たちが目を覚まさなければ、三百名いる騎士たちも烏合の衆だ。
アジームが真っ先に立ち直った。兵士たちはじわじわと迫り来る死体から遠ざかるようにして下がり自然に円陣を組んでいく。ズタズタに引き裂かれた女も、どこにも外傷がないように見えるこどもも、頭部の砕けた男も、胸ごと腕のない老人も、出来損ないのからくり人形のようにギクシャクした動きで近づいてくる。
「話がちがうぜ、死兵はいないんじゃなかったのか!」
と騎士が言った。
「あいつらはただの死体だ。ノッティンガムを襲った化け物とはちがう」と奥村は答えた。
「こりゃあ、まるでゾンビだぜ」粉屋のマッチが十字を切った。
「動かしているのはモーティアナだ」奥村はアラン・ア・デイルの肩をつかむ。「いいか、モーティアナはノッティンガムでモルドレッドが待つと言っていた。ロビンはモルドレッドの元に送られた公算が高い」
「だが、どうすればいい? ロビンを探すのか?」
奥村は首を左右に振った。「モーティアナを殺すんだ。ロビン・フッドの言葉を忘れるな。我々の目的はモーティアナを倒すことだ! お主らの隊長をとりもどしたくば、魔女を討ち取れ!」
「でも、あいつらはノッティンガムの市民だぞ! それを斬れってのか!」
「今はちがう! 攻撃しろ!」
「そんな……」
奥村は仲間が逡巡するのをみた。みなキリスト教徒で、死体を痛めつけることを恐れているのだ。
「なにをしている、死にたいのか! 剣を構えろ! よく動きを見るんだ! あれが生きた人間か! 引導を渡すのは貴様らだ! 見てろ!」
奥村は真っ先に列を飛びだすと、手近にいた老人を見事袈裟斬りに斬って落とした。老人は肩から胸まで一刀、両断にされて、地面に転がったが、まだ手足をばたつかせて奥村に指を伸ばしている。
「わかったろう! 動きは速くはないが死なないのだ! 群がる前に動けないようにしろ!」
奥村が言う間にも、アジームが生来の剛胆さで、三人の死体の足を狙って次々と斬り飛ばし。
「首だ、首を狙え! 首を切り落とせ!」
騎士たちは奥村の言葉に突き動かされるようにして、死人の首を切り落としていく。ミドルが近づいてきて、「すまねえ、奥村」と言った。奥村はうなずいた。
「こいつらは死体だ。が、後味は悪いな」
奥村は左右の敵に身を寄せては首を刈りとったが、死人はそれでも動いている。闇雲に襲いかかって、しまいには同士討ちすら始めてしまった。
騎士たちは心を鬼にして死人たちに斬りかかる。騎士らしからぬ戦いの中で、兵士たちの中には涙する者まであった。死人を動けなくするには五体を切り刻むしかなかったからだ。死体だから血を噴き出さないが、家畜にするよりもひどい人肉の解体である。どれも肉が腐り軟らかくなっているから、斬りにくいといったらない。奥村はいよいよ怒りを深くしたが、部隊を統率するためにどうにか気を静めた。
「おかしいぞ。こいつらは動きが鈍い。こんなやつらで我々の足止めをしようとはしないはずだ」
アジームが容赦のない殺戮に閉口しながら側に来た。「数で押すつもりなのかもしれんぞ」
「いや、モーティアナの力とて無限ではない……」
奥村は言葉の途中で身を伏せた。突然の銃声に体が無意識に反応してのことだった。アジームはほとんど彼の体にかぶさっている。どうもこの侍を守る役目を買って出たらしい。二人の真上を銃弾がどしどしと行き過ぎていった。
「まずいぞ、奥村!」とアジームが耳元で言った。「銃士隊の生き残りがいやがった! 厄介なことになるぞ」
アジームのいうとおりだった。こっちの動きは鈍るのに、死人たちは飛び交う銃弾をものともしない。
奥村は兵に指図して、仲間を左右に散開させようとしたが、死体に行く手を阻まれてうまくいかない。銃士たちはそのまごつく所を狙い撃ってきた。
奥村もこの世界で銃撃を受けたのは初めてである。洋一のいったとおりか! ウィンディゴめ、この世界に銃戦をもちこみおった!
奥村は騎士たちを統率すると、建物を背中に負って、銃弾をさけては死人たちと戦った。
「弓隊を前に出せ! 銃士共に反撃しろ!」
奥村の指図に駆けこんできたのは弓矢を大量に抱えた連中である。騎士たちもこんな銃戦が初めてだが、奥村はいやというほど経験してきた。戦い方を知っている。
「まずは銃撃を黙らせるぞ! 弓隊を援護するんだ!」
みなはこの隊長が銃弾も怖れず、弓隊の前に出ては死人の急襲から守ったから、勇気を起こして奥村に続いた。
ロビンは三百名を六つの部隊に分け、内の五十名は選りすぐりの射手を集めていた。この連中も仲間の援護に勇躍してさかんな射撃を行った。銃士たちの姿が即興のバリケードの向こうに見え隠れする。死人どもを前面に出し、矢ふさぎにしているのだ。無数に矢を受け蠢いている死人の姿はなんとも酷い。奥村たちは手こずったが、弓の名手ロビンが考案した作戦も巧妙だ。射手たちは数列に分かれては交代射撃を行った。彼らの飛ばす矢は銃士どもの銃撃の数を上回って、ついにその射撃を弱まらせた。
奥村はこの機を逃さじと叫んだ。
「アラン・ア・デイル! 五十名を連れて脇道から回りこめ!」
奥村はその隙にモーティアナの姿を探す。あの老婆がウィンディゴから与えられた力も無制限ではないはずである。これだけの数の死人を動かすなら、どこか近くにいるはずだ。どこだ?
そのとき、アジームが彼の肩をつかんで、
「いかんぞ奥村! 部隊がすっかり間延びしてしまった! 洋一と太助が危ないぞ!」
「しまった!」
奥村は部隊の統率に夢中で少年らの姿をすっかり見失っていた。
ウィル・ガムウェルが側に来て、
「ここはもういい! 小僧共を助けてやってくれ!」
みなあの少年の重要さをわかっているのだ。奥村とアジームはともに後方に駆けだした。
「俺たちはあの二人にはりついて、モーティアナを狙うんだ! 必ず出てくるぞ!」
「わかった! だが、モーティアナの力がこれほど増しているとはな! やつを斬れば死人もおさまるか!
「そう願うしかないあるまい!」
若者が二人がかりで死体に抱きつかれている。アジームと奥村はたちまち救いだした。そうする間にも中央道にやってくる死体は次々と数を増している。
「こうも数がふえては厄介だ。みな集まれ! ばらばらに戦うな!」
奥村は道々で各個戦う騎士たちを手近に揃えた。
「あの女は近くにいる。遠隔からこれだけの力を振るうことは不可能だ。モーティアナと太助らの姿を探せ!」
奥村は死体と戦う愚をなるたけ避けた。騎士たちは奥村を守りながら後方へと進撃した。そのうちに、死人の群れに囲まれた一団を見いだした。その中央にいるのはミュンヒハウゼンと少年らである。
「いたぞ! 救い出せ!」
奥村は夢中で死体の群れに飛びこむ。手練の血刀は無数の煌めきと化して、死人らの手といわず胴といわず斬り飛ばしていく。洋一まであと少しというところで、奥村は驚愕に身を凍り付かせた。洋一の姿がたちまち変化して、眼球をくり抜かれた西洋人の少年に変わったからだ。太助もミュンヒハウゼンも見知らぬ死体で、まるで奥村をあざ笑うかのように牙を剥いてくる。腐った血と唾液が、口中でネバネバと糸を引いていた。
「くそ」と奥村は言った。「幻術だったのか! 洋一じゃない!」
隣にいたアジームもおなじものを見たようだ。二人は錯愕の顔を見交わす。
「まずいぞ奥村。幻覚を解いたということは二人が捕まったのかもしれん」
奥村はアジームの声さえ遠くに聞いた。顔面は蒼白になり、今にも愛刀を取り落としそうだ。彼は近くに寄ってきた死人を突き飛ばすと、道の奥へと走りだす。自分の迂闊さを呪いながら。
洋一、太助、死ぬな……!
○ 2
最初から罠だったんだ……
ロビンもとられた。自分たちはゾンビに囲まれている。暗澹たる思いというのが、血の気をすら引かすということを、このとき洋一は初めて理解した。彼は部隊の真ん中にいて、死者たちの人影は兵士たちの体の隙間からしか見えなかった。けれど、嘔吐するには十分だった。これは内蔵の臭いなんだろうか? と洋一は思う。彼の冴えた嗅覚はなかなか麻痺してくれない。
死人たちは剥き出しの臓腑をものともせずに向かって来る。歴戦の騎士たちですら恐怖に凍り付き、剣の冴えを鈍らせる。洋一は口元を拭い、懐から伝説の書をとりだした。その手を押さえたのは男爵だった。彼は激しく怒った顔で本をむりやり懐に戻す。
「しまえそんなものは!」
「なんで! 今こそみんなのピンチだ! この連中を見てよ!」と洋一は言った。「伝説の書を使わなかったら切り抜けられないじゃないか!」
「どう書くつもりだ! ロビンがどこにやられたのかもわからんのだぞ。状況に不明な点が多すぎる。どう書くつもりだ!」
洋一は昨晩の言葉を思いだした。彼には本にどう書きこむべきなのかがまったく見えなかった。こんな状態でいい知恵なんて出るはずがない。
ミュンヒハウゼンは洋一の耳に口を寄せた。
「今、本をつかうのは危険だ。万一のためにとっておけ」と言って、洋一のすっかり細くなった腕をとる。そのとき老人の瞳が揺れていたので、洋一はそれ以上反論できなかった。「お前はもう一度本に生命力を吸い取られておる。二度目は命を落とすかもしれんのだぞ」
「でも、モーティアナはきっと出てくるよ」と太助が囁いた。「あいつはぼくと洋一のことを怨んでるんだ」
最後には本を奪うつもりだろう、と太助は思った。
その言葉通りに、三人を狙う死体はどんどんと増えていった。まるでノッティンガム中の遺体を操っているかのようだ。大人たちが押されて戻り、中央にいた洋一と太助は鉄の鎧に押しつぶされそうになる。太助は父親の元に駆けつけたかった。せっかく会えたのに死んだらどうするんだ。ところが、男爵が肩を押さえて許さない。モーティアナは死体から本を奪うつもりなのかも知れない。自分で手を下す気がもうないのかも知れない、と彼は思った。洋一と伝説の書を守らないと。
死人は素手だが、あまりに数が多すぎる。そのうち、銃士隊の射撃が始まると、円陣はみるみる崩れて、死人と生き人入り乱れての乱戦になった。
周囲の鎧が引っぺがされて、太助はようやく人心地をついて、刀を抜いた。
「洋一、ぼくの背中に回れ!」
彼の背に洋一が手を置いた。ミュンヒハウゼンはどういう因果か、おなじ年格好の男性を退けている。悪気が充満しているのか、今朝よりもずっと年老いているように見えた。
「ぼくの側を離れるなよ。二人でいなきゃだめだ」
と太助は言った。洋一がうなずいているのが、見なくてもわかる。そうして互いを守るようにして立つ二人のこどものところへ、ヨタヨタと女の死人が近づいてくる。太助は急に気後れをして刀を引いた。洋一が太助の背に押されて、不審に声をかけた。太助はそれでもジワジワと下がる。なぜ金縛りにあったように斬りかかれないのか、自分でも理由が分からない。母上など見たこともないだろうしっかりしろ、と彼は自分に言い聞かせた。母親の悲惨な死もあって、母性に対する憧憬がどうしても抜けないのだ。第一、侍たちは女こどもを守るためにずっと戦ってきたのではないか。斬るのか? と太助は自分すらをも疑った。
背後で、父さんと母さんだ、と洋一が言った。太助は一瞬だけふりむいた。洋一は、左手からくる男女の死体に釘付けとなって震えている。洋一にはあれが両親の死体に見えているのだ。
「洋一! しっかりしろ! 見ちゃだめだ!」
太助は洋一を背後に抱えたまま斬りかかれずにいる。女は血まみれの腕を上げて襲いかかってきた。
「くそ!」
太助の頬を爪が切り裂いた。刀を上げたが、斬れない。武器をもたない女は太助の喉元に食らいつこうとした。太助は硬直したまま、女の血塗られた犬歯をみた。そのときになって、ようやくこの女が金髪碧眼で、母とは似るはずもないことに気がついた。
ミュンヒハウゼンが脇から女を蹴転がしたのはそのときだった。その勢いのまま身を寄せて、サーベルを一閃、女の首を斬りとばす。太助の目線は地面を転がる女の首を追った。
「あれはもう人ではない! ためらうな!」
太助は悔しがり、周囲の建物にむかって叫んだ。「モーティアナめ、卑怯な幻術をつかうな! 隠れてないで出てこい!」
戦場はもう節度のない殺しの場である。騎士たちも死人のあまりの多さに、目の前の敵を退けるだけで精一杯だ。太助はミュンヒハウゼンと一緒に洋一を挟んだ。
「洋一、しっかりせい! 幻を見るな! 自分を保て!」
男爵はもう洋一の頬を引っぱたいている。
太助は半眼をとって、無心になろうと勤めた。脱力だ、居着くなよ、と自分に言い聞かせる。
「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」
と太助は口の中でつぶやいた。なにかに集中しなければとてもやっていけない。
「南無阿弥陀仏、観世音菩薩」
太助は表情を変えていなかったが、内心嫌悪せずにいられない。けれど、自分よりも小さなこどもの首を切るには心を無にするしかないと思った。彼は古伝の正中線に集中しながら、居着かぬように居着かぬようにと努めた。死人の背後にモーティアナを見ようとした。あの魔女め、絶対に揺るさんぞ! 太助はいつもの度胸をとりもどすと、迫り来る敵を斬りたおした。
「モーティアナ、モーティアナはどこだ!」
敵を蹴倒し、洋一の側に駆け戻ろうとする。その視界の隅に、なにかが入った。背筋に寒気が走った。斬り結び合う騎士たちの向こうにフードをかぶった老婆がいたのだ。邪悪な笑みを口元に浮かべ(目は影で見えない。でも見ているのは自分の方だ)彼を手招いている。宿で斬った使い魔とおなじ姿だ。そのとたん、魔女の高らかな笑い声が頭に響く――
ウケケケケ……
「男爵、いたぞ! モーティアナだ!」
ミュンヒハウゼンが顔を上げなにかいったときには、太助は夢中で走っていた。あいつを、あいつを殺せば死体も止まるぞ!
「洋一! 待ってろ!」
老婆は側の屋敷に退き、扉をそっと開けると中に身を隠す。
「待てえ!」
太助は掴みかかる死体の手をすり抜けて、屋敷を目指した。洋一の呼び止める声も、血気にはやる少年には届かない。
「逃がすもんか、今度こそ仕留めてやる!」
太助は死体を飛び越え、モーティアナを目がけて一散に駆けた。
○ 3
モーティアナの逃げこんだアパートは、周囲の建物とは画然としている。まず戦場のまっただ中にあるというのに傷がひとつもない。その一軒だけが夕暮れの中にいるように曇って見えた。そして、建物を囲むように白い灰が蒔かれている。右足がそれを踏みつけたのに、太助は気づかなかった。わずかな階段を駆け上がると、刀を眼前に立てるようにして、気息を整える。必殺の意思を刀にこめた。
「待ってろ洋一、今あいつを仕留めてやるぞ」
そして、わずかに開いた戸の隙間から、モーティアナの待つ暗闇の中に押し入った。戸口に体を滑りこますと、壁を背にして大上段に振りかぶる。おかしいぞ――
視野を広げ左右の闇を推し量るが、伏せている人はない。そして、奇妙なことに気がついた。戸を閉め切った様子もないのに、そこはわずかな光も差さない真の暗闇だったからだ。
「モーティアナ!」
「来たかえ、小僧……」
「モーティアナ……」
後ろで戸がカチリと閉まった。太助は思わずノブを回そうと剣を片手に背後を探ったが、そこにはなにもなかった。なんの手応えも。扉は消え、ノブは消え、家の中ですらなくなっている。
太助はついに自分が罠に落ちたことを知った。迂闊だった。死体共を止めたくて焦っていた。あの宿で魔女の力は熟知していたはずなのに、使い魔を斬ったことで慢心したのだ。男爵も洋一も入ってこれないだろう。魔女はまんまと彼を罠にはめ、彼をひとりぼっちにした。
太助は落ち着けと自分に言い聞かせながら、背筋を伸ばし刀に両指をはわして、正眼に置いた。三白眼で闇を透かしてもなにもない。
奥から声が響いてくる。
「ぬけぬけと追ってきたね。あたしを斬り倒したいのかい」
「ああ、やってやるぞ!」闇の恐怖を払うべく声を上げる。胸は声に呼応し、激しく震えた。心臓の高鳴りはこらえようもない。モーティアナが、あいつが見えない。見えなければ斬ることは不可能だ。太助はモーティアナの気配を探りながら挑発した。
「卑怯者め、隠れなくてはぼくの相手も出来ないか!」
モーティアナは、キャハハ、と笑った。それは心底意地悪で、それでいて華やいだ声だった。魔女は念願を叶えようとしている。彼女の少年を殺そうとしている。
「小僧、よくもあたしの蛇を殺したね!」
モーティアナの声は四方から聞こえた。これでは出所が探れない。太助は無念さを噛み殺して、剣先をわずかに下げた。モーティアナの声は喜びと怒りで震えていた。彼女はにじり寄りながら涙すらこぼしていたのだが、太助の目には見えなかった。
恐怖で呼吸が速くなる。彼はもはや両眼を閉じた、必死に直感を働かせようとした。モーティアナの匂い、少しでいい、魔女の熱をさぐりたかった。時間を稼ぎ、柄に這わせた指をそっと振り、緊張をゆるめようとする。心身がこわばって平常心ではいられない。彼は北辰一刀流にいう鶺鴒の尾を無意識の内にやっている。剣尖を揺らめかしながら、モーティアナの先を切って落とそうとしていた。見えないならば、気配を探って斬り裂くまでだ。
「さあ、来い!」
「お前はウィンディゴ様の信頼を奪った。たかが小僧があたしの邪魔をした。許さない。許さないよ。お前は許さない。どうなるかわかるかい。どうなるか教えてやろうか。お前のせいで。お前のせいで、あたしがどんな目にあったか、その恨みを五体に受けるがいい! お前の恐怖をあたしにくれ。骨を砕かせろ。筋を千切らせろ。毒と恐怖でお前の肉をめちゃめちゃに搾ってくれる! ああ柔らかい子羊よりも、柔らかいシチューにしてやる。お喜び下さるだろうよ。ああ、ウィンディゴ様はお喜び下さるとも」
モーティアナの声は不可思議にどんどん大きくなっていった。まるで洞穴で木霊する声のようだ。あちこちで反響して太助の身体を激しく打った。彼は幼い身体を蹌踉めかせながら、それでも必死に立っていた。呼吸を整え、気力を剣に託し、必殺の一撃に備えたのだった。
「手土産はお前、次は小憎らしい侍の父親、ミュンヒハウゼンとかいうじじいも目玉をくり抜いて殺してやるとも。生きたまま舌を抜いてやる。次は洋一とかいう小僧だ。あいつはただではすまさん。ウィンディゴ様の持ち物を奪い、馬鹿げた力であたしの計画を食い止めおった。だから、指を引き千切るんだ。馬鹿げた文が書けないようにだよ。足の指もだ。逃げられないようにだよ。そうしてやってやる。あいつの皮をはいでやる。小さなちんちんを磨り潰してやったら、どんな顔をするかね。ハハハ、玉もだ。玉もやってやる。そうなったら、生かしておいてやるさ。たった一人で生かしておいてやる。そうなったら、あいつは死ぬかね? ああ、首を括ればいいのに。見物だ。見物だとも」
「お前の思い通りにはならない」太助は言った。その声は緊張と興奮で震えてもいた。「ここで死ぬんだ」
「どうかな?」
その声だけは奇妙に小さくなり、驚くほど近くでした。シュルシュルと地を這う音が聞こえたとき、太助はついに目を開けた。なにも見えないが、巨大でザラザラした物体が自分の身体に巻き付くのを感じる。その蛇の長い総身は、彼の全身をすりあげ締め上げる。鼻をつく生臭い匂い、嘔吐きが起きた。腕を封じられ、骨をきしませる、激痛に大刀が落ちた……。彼は敵の術中に嵌ったのだった。
「死ぬのはお前だ」
○ 4
太助は万力の中に身を挟まれているようだった。このままでは強大なローラーの下敷きになるみたいにペシャンコにされてしまうだろう。肺が押されて空気が抜けた。横隔膜が圧迫されて激痛が喉にまで走る。全身の骨が音を立てる、肋骨が変形し内臓が切られそうだ。幼い体が柔軟性を持つのを幸いモーティアナは歓喜の雄叫びを上げながらギュウギュウと締め上げた。太助の目は力なく、液体が零れる。朦朧としながら、洋一や父のことを思った。これの次は――次があるんだ。
真っ赤な茹で蛸のようになり――脳が酸欠で空気を求めて体中の血液を集めている。もう目玉が飛び出しそうだ――そんな状況だというのに、友人のことを思った、父親のことを思った。彼らを助けるんだと彼は思った。血液が抜けて痺れる指を動かし、ドサリと鞘に引っかける。モーティアナは絶叫を上げ、さあ、いよいよだ、まだ死ぬなまだだ死ぬな毒を回して肉を溶かしてやる、生きたまま身を焼かれるがいいや! と真っ赤な口から鋭い牙を生やして、彼の喉元に噛みついた。太助は一瞬目を見開き、次にあきらめたように力を無くすと声にならぬ声を発した。これ以上の激痛があるとは信じられなかったが、本当だった。老婆の牙は食道を食い破るほどに深く刺さって、熱い毒を流しこんだのだ。
太助は舌を垂らして(その首はほとんど無気力となってブラブラと揺れた)、それでも柄に手をかけた、手首だけでそろそろと抜いた。蛇は生きたスプリングのように彼の体を巻いていたが、刀を持っていた右腕だけは、その隙間から突き出ていたからだ。意識はないのに、身体を必死に突き動かす。脇差しが鞘から伸びて刀身を露わにしたが、老婆は狂った犬のように太助の首に噛みついてグルグルと首を振り回している。舌で夢中で血を吸い取っている。うまい、うまいぞ!
太助は身体を振られていたから、鯉口をどうにか切ると、体が左右に揺らめいて脇差しがぐっと抜け出た、後は重みで鞘から落ちた。指を引っかけるようにしてその確かな感触を掌に包む。体はもう真っ赤にむくんでいた。ああ、と声を上げたような気がしたが、実際には息すら漏れていなかった。
洋一……と彼は最後に思う。彼にとっては最初にして最後に出来た友人だった。鼻と口から血が噴き出し、声すら上げられない。手の内で刀を回して、モーティアナの身体に押し当てたときだけは、開ききった瞳孔に光が戻った。
太助は倒れこむようにしてモーティアナに身を預けながら、無理矢理腕を伸ばし、老婆の首元に刃を押しこんだ。
蛇の目を見開いたのは、今度こそモーティアナだった。
○ 5
洋一と男爵は無駄と知りながらも、建物を包む結界に拳を打ち当てていた。二人は夢中で体当たりを繰り返している。剣を打ち付け、蹴りをくれるが、人骨の粉を巧妙に配した魔方陣は、強固な障壁をつくり、彼らではとても突き崩せない。
「なんということだ。太助は殺されてしまうぞ!」
「そんなことない! あきらめちゃだめだ!」
周りに目をくれようとしない洋一とミュンヒハウゼンに手を伸ばしていた死人たちが、もう一度ただの死体に戻ったのはその時だった。辺りの喧噪が突然静かになった。聞こえるのは遠くで響く銃声と剣戟の音。アランたちがまだ銃士らと戦っているのだった。けれど、死人たちはまるで自らを吊る糸が切れたようにクシャクシャと、どれも地面に倒れている。洋一が手を伸ばすと、障壁が消えていた。そこへ奥村左右衛門之丞が血刀を手に鬼をも斬らんばかりの勢いで駆けこんでくる。
「おじさん、太助はこの中だ!」
洋一の声がやむ間もなかった。奥村は彼の息子がそうしたようにわずかな段を踊り越え、その勢いのまま、足を伸ばして固い扉を蹴り開けた。
「太助!!」
奥村は敵の待ちかまえる予感にも関わらずに大声を上げた。家屋はいまだに暗闇――モーティアナの魔術が残っている。奥村は視線を伸ばした。戸口の光は黒煙にも似た闇をわずかに払っている。その光の先で、袴を巻き付けた小さな脚が倒れている。
「太助!」
奥村は夢中で息子の傍らに膝をついた。男爵が周囲を警戒しながら後につづく。「なんということだ」
太助は刀を握ったまま、自らの流した血の海に舌を垂らしている。目は閉じ。剥き出しの腕には、なにかに強く締められた痕。のど元には大きな穴が真紫に開いている。
「モーティアナだ。モーティアナにやられたんだ。毒にやられてる」
と洋一は呆然として、けれど無意識に足を踏み出していた。闇に入った。彼が思いだしたのは今朝の太助の姿だった。一緒にウィンディゴを倒そうと彼の背を優しく撫でた小さな手が力なく伸び、自らの血にまみれて落ちている。彼に様々なことを語った唇も真紫に染まり乾いていた。強く優しい友人が、今孤独にも死の床に就こうとしている。
「太助……」奥村は、そっと息子の顔に指を這わせる。体の下に腕を入れて、息子を抱き上げた。あんなに元気だった、あんなに勇敢だった息子が全身の力を無くして、別人のように手足を垂らしている。もう言葉もない。
太助を側の客間に運び入れた。狭い部屋の中央で、奥村は息子を抱いて座った。
太助の息はかすかだった。奥村はふと色々なことを思いだしていた。息子が生まれたとき、今とおなじように抱き上げたこと。妻の亡骸に立派な侍にすると誓ったことや、死に行く仲間から息子の後事を託されたことを思った。なによりも息子との思い出が幾重にも頭を巡る。彼は頭を傾け、そっと涙が流れるに任せた。ああ、この息子がどんなに自分に尽くしてくれたことか。自分がどんなに息子を思ってきたか。その積年の思いが胸を塞いで彼はなにも言えなかった。その人生がどんなに得難いものだったか、ついに彼は息子に伝えず仕舞いだった。息子が生まれてこの方どんなにありがたいと思ってきたことか、その事の万分の一も彼は息子に伝えられなかった。申し訳なさが涙となり、ポトポトと頬を流れた。息子の顔に落ち、彼の息子が、泣いているようにも見える。
「息子は、息子は天下一の孝行者でござんした。これほどの、これほどの息子がいて、拙者は天下一の果報者にござんす。その息子に報いることが一度たりとも出来もうさなんだ。そのことが悔やまれて、悔やまれて。積願が果たせずともかまいもうさん。拙者息子のためなら、腹を切り申す。主君を持たぬ浪人ゆえ、せめて家族のために腹を切り申す。なのに、何故息子が父より先に死なねばならんのか」
ミュンヒハウゼンは老いた手で顔を覆う。彼は一息に何十年も年を食った。
洋一は呆然とその光景を見つめている。目の前にいる三人は何万光年の彼方。現実の事とはかけ離れて見えた。
「拙者は、拙者は我が儘でござんした。息子はどんな生き方でもできるのに、拙者の我が儘で側に置き申した。命を狙われていることも、預ける場所がないこともすべて言い訳でござんす。息子を手放すのが耐えられなかった。それ故に、このような若輩の身で死なせることになり申した。不憫でなり申さん。拙者の息子でなければと思い申す。かような苦労も、かような死に様もせずにすんだろう。申し訳、申し訳なく」
洋一は急に腹が立った。奥村がなぜそんなふうに謝るのか彼には理解しがたかったのだ。あんなに強くてあんなに頼れたおじさんが、別人のように力をなくして肩を垂らす――うそだ、こんなの現実じゃない、目の前にある光景、あれこそがデタラメだと彼は思った。だって、彼は知っている。太助という少年がどんなに父親のことを誇らしく語っていたか、どんなに親を愛していたかを。太助の口が恨み言を発したことなんてあったろうか? 断じてない。いつも前向きだったじゃないか。
それは彼が真っ直ぐな人間だからで、真っ直ぐな人間に育てられたからだと洋一は思った。太助を育てたのは今はひとりぼっちで泣きにくれている侍である。洋一はこんなのだめだと拳を握る。こんな結末誰も望んでるもんか。これが物語の世界なら、絶対に幸せな結末にするんだと。
「太助はおじさんと一緒に居られることを喜んでた。おじさんが育ててくれたことをずっと感謝してたんだ。太助は誇りを持って生きてた。だから、こいつは、ぼくなんかよりずっと偉いんだ」
奥村が泣き顔を上げる。その泣き顔を見ると、洋一は今よりもっと腹が立った。太助は父親を尊敬してた。父親のこんな姿は見たくなかったろう――それが自分のせいというなら尚更だった。
「太助は死んだって後悔なんかしない。おじさんがしても、こいつはしない。後悔しない生き方はおじさんが教えたんじゃないか! 人を羨んだり、生まれを悔やんだりしない生き方の方がずっと大事だ! 学校に行くよりずっと大事だ! だから、ぼくは……!」
洋一は、その幼い友人をどんなに尊敬していたか、言葉に出来なかった。だから、彼は唇を噛みしめて涙をこらえた。
洋一の言葉が胸に刺さり、その言葉は奥村の胸につかえていた感情をどっと押し流した。それですべてが報われたわけではない。ただ洋一のことがありがたかった。そのようにして息子に接してくれた初めての友人のことがありがたく、ひとえに頭の下がる思いがした。それが太助にとってどれほど支えになったことか、このときハッキリと分かったからである。
沈黙が影に落ちた。奥村はがっくりと肩を落とし、息子の腕に手を添えている。洋一は伝説の書を懐からとりだし(胸当てを固く縛っていたから苦労してとりだした)、上から手を当てる。自分になにができるのかはわからなかった。でもなにをすべきかはわかっていた。洋一は奥村の、優しいけれど血に塗れた手を見ながらつぶやいた。
「男爵、ぼくを太助と二人っきりにして欲しいんだ」
「書くつもりか?」と男爵は尋ねた。「だがどうやるというのだ。太助はもう……」
「太助は死んでない! 二人にして欲しいんだ。ぼくと太助二人きりだ!」
奥村は太助をそっと床に寝かせると、洋一に膝を向け、深々と頭を下げた。
「お頼み申す」
男爵は迷ったが、ややあって、
「わかった。奥村部屋を出るんじゃ」
奥村は力なく首を垂れる奥村はさ迷うように出て行く。最後に洋一を見て微笑む。男爵は残った。背の高いミュンヒハウゼンが膝をついて、洋一と頭の位置をおなじにした。
「いいのか?」
洋一はうなずいた。ミュンヒハウゼンはやや不安げな表情をその皺顔に貼り付けて、洋一の肩に手を置く。男爵は迷っていた。洋一にやらせるべきか、けれど、太助が蘇るのならばわずかな可能性にも賭けたい思いだ。この少年はひ弱に見えながらも、伝説の書をどうにか使いこなしてここまでやってきた。男爵はその可能性に賭けたかった。本来ならば自分はこんな事をいうべきではないと思う。洋一は、太助とおなじく忘れられた一族の最後の生き残りである。下手をすると、ミュンヒハウゼンはその二人共をも失うことになるだろう。けれど、彼は言わずにはおられなかった。この二人は力を合わせ、どんな艱難をも乗り越えてきたのだから。この窮地にすら期待するなというのは無理というものだ。彼はこの名付け子まで失うかもしれないという恐怖心を脇に押しやった。
「ここが本の世界だということを忘れるな。物語には世界観が必ずある。ウィンディゴですらその世界観に縛られておる。お主は本の書き方を父親から教わっておろう。その鉄則を守るんじゃ。物語を作るとき、自分がどうしてきたかを思い出せ」
「ぼく、ぼく、やれるよ。大丈夫だ」
「物語の世界に法則があることは分かったはずだ。あの魔女が実際の魔力をつかったように、ここは現実の世界とは大きく相違する。その法則を見抜くことだ。そしてここはあくまで物語の世界。実現するアイディアがあるならば、書きこんだことは必ず現実になるはずだ。残念ながら、わしには文が書けん。お主にすべてを任せるのは、申し訳ないが……」
立ち上がり、背を向けて歩きはじめたミュンヒハウゼンを、
「男爵」と呼び止める。「ぼく、太助と話してたから、あいつの気持ちがわかってたんだ。こいつがおじさんや男爵に感謝してたの、嘘じゃない」
ミュンヒハウゼンは振り返り、淡く優しい顔をした。洋一は顔を下げていたからその笑みは見えなかった。
「でも、怒鳴ったりして悪かったよ。このことが終わったら、おじさんに謝ろうと思ってる」
「わかった」
男爵は出て行った。洋一は改めて奥村太助を見下ろした。その顔はまったく青白い。死体かゾンビでもこれほどひどくはないだろう。彼の友人は呼吸もほとんどしていないように見えた。狭い路地に面した窓から、明かりがかすかに落ちて、彼は懐から伝説の書をとりだした。
○ 6
あれは今朝のことだった。洋一は太助とのやりとりを思いだした。自分を励ますように背中を撫でてくれたこと。彼の語った言葉を逐一思い出していた。洋一は太助の死を悲しんだ。ああ、こいつはこんな所で死んじゃ駄目だ――この一人ぼっちの友人に、いろんなものを見せてやりたい、自分の持っているものを分けてやりたいと思った。太助がなにも望まないのは、元もとなにも持たないからなのかもしれない。だけど、もっと求めていい。いろんなものを手にしていい。誰にでもある権利を行使して欲しかった。ささいなことで、おだやかなことでいいから、戦いや痛みや血や涙のないところに彼を連れ出してやりたかった。生まれて死ぬのが平等なら、普通に生きる権利だって持っているはずだ。蘇れ、と洋一は太助の肩を撫でながら思った。彼は声に出さず、口の中で舌を動かし奥村太助に訴えかけた。二人でウィンディゴをやっつけるんだろ? 一緒にやってくれるっていったじゃないか。いつものように立ち上がり、いつものように前向きに、自分を導いて欲しかった。洋一は太助が平凡に生きられないのなら、一緒に歩いてやるつもりだったのだ。
そうして牧村洋一は、また奥村太助と二人ぼっちになった。戸を閉め切り、日中の湿った空気の中で、父親が教えてくれたことを思い出そうとした。自分の指を見たが、情けなくも震えている。彼は、くそっ、と小さな声でつぶやいた。泣くつもりなんかないのに、涙がにじんでいる。彼は自分のことを情けないと思った。おじさんや男爵にはあんな啖呵を切ったのに、自信がないのだ。太助が死ぬのも自分が死ぬのも恐れている。こんなことをしてる場合じゃない、うまくやるアイディアを練らなけりゃと思ったけれど、体の奥底が震えてそれで全身が強張っている。喉がカラカラだ。
お父さん、お母さん……、と彼は思った。けれど、もう代わりをしてくれる誰かはいない。この部屋にいるのはかれと太助だけだった。
「才能なんてないじゃないか……」
洋一はびくりと腰を上げた。今聞こえたのは自分の声なのに、自分がつぶやいたことにも気づいていなかった。彼は泣き出してしまった。
「やっぱりぼくには無理だよ。太助ごめんよ」
「お主の友人は死ぬ」
洋一はまたぎくりと身を起こした。低い声がすぐ側で聞こえた。「ウィンディゴ……?」辺りを見回すが誰もいない。彼の身動きで塵が舞うばかりだった。ウィンディゴがここにいるはずない。あいつは本の世界には入れないんだ。
洋一は立ち上がって、部屋を見回した。薄暗くて、それに死の臭いがちょっぴりする。その死の臭いは足下の少年が発している。洋一はもう一度、太助……とつぶやいた。太助のすぐそばに自分の置いた伝説の書が落ちている事に気がついた。
――本だ。ぼくは伝説の書の悪い部分とも向き合っている――さきほどしゃべったのは、この本だったのだ。そうしてみると、赤い表紙は邪悪にもニタニタと笑っているようにも見える。彼に創作をさせたがっているのはまちがいないが、本を形成する大半の部分は彼に失敗させたがっている。そのうち、伝説の書が一人でにパラパラと開き、洋一はひっと尻餅をついた。耳の奥でブンブンと唸る声がし始める。大半が意味不明な外国語だ。伝説の書に飲まれた人物たちが、彼が本を使おうとそして弱い心に負けようとしているのを見取って出てきたのだ。洋一は鼓膜に噛みつくような無数の声に耐えかねた。
「うるさい、誰も死ぬもんか、向こうへ行け!」
叫び声とともに、鼓膜に巣くう無限の音は追い払った。背後でカチャリと音がする。誰かがノブを回そうとしたが、また元の位置に戻った。洋一はほっと息をついた。二人は彼を信じて、事を託している。
「心だ、伝説の書を扱うのは、強い心なんだ」洋一は伝説の書に手を伸ばし、本を閉じると、固い表紙の角を掴み上げた。その本を顔の高さにまで持ち上げると、「本の持ち主はぼくだ。主人はぼくだ。まちがえるな。わかったら、いうことを聞け」と囁いた。洋一ははっと足下を見おろす。太助がうめき声を上げている。彼は膝を滑らすようにして、顔の側に手をついた。
「しっかりしろ。目を開けろよ」
と耳に近づき囁く。喉元からあふれる血を目にし、肩を揺するのだけは我慢する。洋一はふいに、自分がどんなに太助を大事に思っているかに気がついた。共にすごした時間はわずかなものなのに、血を分け合った兄弟のように感じている。そして、実際に血を分け合った肉親はもういない。洋一は二人がいなくなったときのぽっかりとした空虚感を、今もまたおなじ強さで味わった。
いやだ。頼むから、いなくならないで。
洋一は言ったが、喉からは息すらでない。
そうした大切な人間が、まるでちっぽけで、まったく価値のないやつみたいに、あっけなくも死のうとしている。彼に様々なことを語った口から血を流し、頬に涙の筋を残し、あっけなく死のうとしている。洋一は太助の死を受け入れられなかった。いつの間にかこの侍の少年を決して死ぬことのない無敵の存在のように崇めていた。だから、そんな人間が無言で力なく横たわっていることを信じたくなかったのだ。
しっかりしろ、ぼくなら太助を救えるんだ。夢のとおりにするつもりか。
ああ、そういえば、父親は、書くときは心を鎮めるようにいっていたっけ。
「だけど……」
脳裏には父親の残像が居残っている。洋一は必死に考えをまとめようとしたが、ヘドロが脳の回路をせき止めたみたいになにも出てこない。
このままじゃだめだ。やり方を変えないと。
洋一はよろめくように立った。彼は自分に言い聞かせた。この臆病者、しっかりしろ。男爵は期待してくれたじゃないか。太助だってそうだ。おじさんだって信じてる。本の力を引きだすのは信じる力だって男爵が言った。
そういえば父さんはいろいろ教えてくれたな、と彼は思った。母親が持ってきてくれた、コーヒーとジュースの甘い香りを、ふと思いだす。
駄目になったときのことは、駄目になってから考えればいい、と奥村少年ならいうかもしれない。だけど、洋一は言い訳がしたかった。頭は結果を考えたがっている。恭一は思考の流れをコントロールする方法を彼に教えたが、洋一にはついに理解できなかったし、今もってそうだ。結局のところ、恭一がなにかを伝えるには、彼は幼すぎたのだ。洋一はもう無理だと思った。なんども助けてくれた少年が、目の前で毒を盛られ血を流し死につこうとしているのに、落ち着いて文をまとめるなんてできるだろうか? そんなの無理だと彼は思う。うまくいかなかったときの恐怖、おじさんや男爵らの落胆を思うと吐き気がする。それどころか文を書き終わったとき、彼の肉体は骨しか残っていないのかもしれない!
奥村の落胆を思いだすと、洋一は暗澹となった。つまりあれは自分自身の姿だった。両親を失った自分自身と重なり合ったのだ。
だからこそやらなきゃ駄目だ。太助が義兄弟だというんなら、今度こそ家族を救うんだ。
洋一はカッと目を開いて、太助を見る。ぽとぽとと涙をこぼしながらも本を開いた。
「書かなきゃだめだ……、ぼくが文を書かなきゃ太助は死ぬんだから」
そういえば、こいつはいっていたっけ、いつでも最高の力を発揮するために、いつでも準備をしておくんだって。
Qを出せ。Qをだすんだ、洋一は我知らずつぶやく。洋一が口を酸っぱく教えられたのは、Goサインが出るまで書くな、ということだ。書いていてつまらなかったら、それはGoサインの出ていない合図である。Goサインが出るまで、Qを出せ。いいQを出せば、いい答えは必ず出るからだ。
恭一は、こどもにもわかりやすいよう、Q&A方式という言葉で教えてくれた。今思うと、彼の父親はなかなかにいい教師だった。行き詰まったときは、Qを出せ。答えを探すのはそれからなのだ。
洋一は恭一のように、頭で理論的に理解しているわけではなかった。けれど、感覚的にはそのことがわかっていた。記憶にむかってうなずくと涙を拭った。
「Qをだすんだ」
喉は焦りにヒリヒリしている。そこに唾を押しこんだ。図書館のどでかい机に座り、恭一の教えを受けているつもりになる。そうして父の教えを思い出そうとした。
漠然と考えちゃだめだ、ポイントはなんだ? どうすればいい?
小説を教えるとき、恭一はいつも右隣にいて優しく彼に語りかけてくれた。洋一はソファに座り、友人から流れ出る血液がじっとりと絨毯を濡らすのを見ながら、自分のすべてを賭けようとした。
「ぼくは書く。ぼくは書くぞ」
洋一は父親の万年筆を握りしめた。このとき、大人用の立派な万年筆が、いやにか細く感じられたのだった。
□ その五 ロビン・フッド、不死の王と対決すること
○ 1
「ジョン、大丈夫か?」
とロビンはその見知らぬ土地で起き上がった。ジョンも剣を支えに立ち上がる。
「ああ」
「どうやら、武器は持ってきたようだ。が矢のほとんどをなくしてしまったな」
ロビンが体を確かめると、腰の剣はある。が矢筒の中身はほとんど落としてしまっていた。自慢のイチイの矢も二本きりしかない。彼は肩に引っかけた弓を外して、矢を番えた。ジョンは大剣をジョンは大剣を左脇に引きつけるようにして立てて構え、ロビンの背後を守っている。
「一体、ここはどこだ?」
「わからねえ。どこかの部屋みてえだ」
が、それがただの部屋でないのはすぐに知れた。下は豪奢な絨毯、右手には暖炉もあり、側には高級なソファーもあるが、すべてが霞がかっていて、おまけに壁だろう場所には真っ黒な影が漂っていた。ロビンが見上げると天井がなく、真っ黒なオーロラが揺らめいているようにも見える。モーティアナが生みだした異空間にいようとは、ロビンには知るよしもない。そして、その空の一角を切り裂くようにしてなにかがやってくるのが見えた。見えたというよりも、彼らが感じたのは邪悪な気配そのものだった。その怪鳥の影は速度を増し巨大になり、彼らの前に舞い降りた。
「モルドレッド……」
ロビンはわずかに顎をだす仕草をした。ジョンがすばやく周囲を見回す。その間ロビンはモルドレッドの眉間に狙いをつけたまま、視線をそらさない。
「やつの他は誰もいねえ。一人だ」
ロビンはかすかにうなずいた。
「どうやらモーティアナは本当にお前の部下だったようだな」
モルドレッドが歩を進めてくる。「その部下に貴様は嵌められたのだ。イングランドで死ねるのはうれしかろう。この世界の王は俺だ!」
「ちがう。貴様はアーサー王の息子などでは断じてない! たとえ、貴様が真の王だろうと、俺は認めない。市民を虐殺し、化け物を飼い慣らしてなにが王か! 貴様がイングランドになにをもたらす! 王とは民のために存在すべきもの。貴様は死しかもたらさない……」
「言うことはそれだけか、ロビン・フッド……」
モルドレッドは動いたとも見えない動きでいつの間にか剣をとりだしていた。その黒剣は周囲の黒気を身に纏い、吸い取るかのように巨大になっていく。モルドレッドは巨大な剣を軽々と操った。
「どのみち、貴様はここで死ぬのだ。諸侯を集め、俺への反撃を企てていたようだが、それらもすべては無用のことだ!」
周囲の邪気はモルドレッドに反応するかのように伸び縮みしている。そのたびにロビンの視界は眩んだ。ロビンとジョンは方向感覚をなくしてよろめいた。
ロビンはそうはいかんと呟き、なんとか身をまっすぐに立てた。
「悪略もここで終わりだ、悪童。貴様はここで殺す」
「あいにくと私は死なない。お前たちの小僧が言わなかったか。私が死なないのではなく、死ねないのだと。聖杯の力――」とモルドレッドは言った。「――神の力はいまだ私の体に宿っている。お前たちに私は殺せない」
ジョンが否定するように鼻から強く息を吹く、首を左右に激しく振った。彼の全身がモルドレッドを否定している。
ロビンは気合いの威声を放ち、弓弦を離した。その矢は部屋に満ちる黒気を飛ばした。
ロビンはモルドレッドが手を振るのを見た。光と風が半円に広がり、ロビンの矢は幾重にも割れて吹き飛んだ。
ばかな、とジョンが側で言った。ロビンの指は無意識に二矢目をつかんだが、残るのは一本切りだ。ジョンがそれを押さえるようにこう囁いた。
「あいつに矢は通じねえ。だが、太助はモーティアナの使い魔を斬ってる」
モルドレッドが口元に拳を当て、ゲタゲタと笑う。ジョンはカッとなったが、今度はロビンが抑えた。
「お前たち、この俺をあの女の使い魔などと同一視するつもりか。ロクスリー、お前はかほどに間抜けなのか!」
ロビンは弓を捨て、矢を腰に差すと、愛剣を引き抜いた。正直なところ彼には自信がない。まともに手を合わすのはこれが初めてだが、モルドレッドが驚異的な力を発揮するところはパレスチナでいやというほど目にしてきた。
「イングランドの人民が貴様ごときに希望をかけているとは、嘆かわしいどころか腹が立つわ! さっさと八つ裂きになり、この世からいぬがいい!」
モルドレッドの怒声は衝撃となって二人の体を打ち据えた。ロビン・フッドが片膝をつき、ジョンが巨体を泳がせる。
「あのやろう、ほんとに魔法を使いやがる」
「あいつを殺るぞ! 右にまわれジョン!」
ロビンは勢いよく跳ね起き、左に向かって駆けだした。ジョンは右へ。二人はモルドレッドの左右から呼吸をあわせて斬りかかる。ロビンが今ややつの首を斬り裂かんとしたところ、モルドレッドがマントを払い、黒光りのする大剣を手にとった。かと思うと、二人の剣をいともたやすくはねのけた。
ジョンは負けじと体当たりせんばかりに斬りかかるが、モルドレッドの剛剣は彼の一撃をたやすく打ち落とした。激しい金属音がたち、折られると直覚したジョンはモルドレッドの威力を利用し体をひねると、剣を抱くようにして地面に転がる。ジョンが確かめると、両刃の剣は片側だけが無数の刃こぼれを起こしている。まるで戦場をいくつも渡り歩いたような有り様だ。ちびのジョンは目をしばたたく。モルドレッドの剣速は太助の抜刀術にまさらんばかりだったし、その力強さは比べものにならない。「なんて野郎だ」
一方、ジョンの一撃を跳ね上げた黒剣は、ほとんど稲光となって片膝をつくロビンの頭上に降ってきた。ロビンは左に転がる、脇腹をかすめるようにして黒剣が滑り、大理石を切りとった。腹部に痛みを感じるが、かまっていられない。モルドレッドは丸太のようにでかい黒剣を風車のごとく回して後を追ってきたからだ。ロビンは夢中で床を転がる。もう顔を上げていられない。ゴオゴオという黒剣の唸りが耳を満たし、恐怖が五感を支配する。
ジョンがモルドレッドの背後にまわるが、モルドレッドはすぐさま気づいて剣を飛ばした。ジョンはあやうく剣で受けたがたたらをふんだ。鉄片が飛んで、靴の下で音を立てる。
「くそ! なんだこの力は!」
ロビンはその隙に大あわてで立ち上がる。
モルドレッドは二人を威嚇しつつ、ゲタゲタと笑った。その表情の奥には五百の赤子が潜んでいて、二人の背筋は冷え冷えとした。
あの剛力は赤子の力でも借りてやがるのか。
「俺は円卓の騎士の内でも最も強かったろう! ガウェインよりも力強く、トリスタンよりも速かった! 俺とまともに戦えたのはランスロットぐらいなものだ!」
ロビンはモルドレッドの言葉が終わらぬうちに、真っ向から剣を振り下ろす。ロビンとて剣術は達人の腕だ。だが、モルドレッドは軽々と受けたばかりか、両腕を突き上げ、ロビンを宙に放り上げた。
ロビンは鎖帷子を鳴らして地面を転がる。彼はすぐさま起き上がって、モルドレッドに駆け寄った。
ロビンとジョンは互いに身を入れ替えながら、モルドレッドの体といわず足もいとわず、数十合と剣を見舞った。そのたびにモルドレッドの剛剣に押し返される。ロビンはもう大汗をかいている。肩で息をしながら、目をしばたたき、頭を振った。モルドレッドの姿がロビンの中でどんどん大きくなってきた。おそろしいことに、モルドレッドの懐に隠れて、こどもたちが幾人も自分を見返しているようだった。
ロビン・フッドは自分自身を叱咤した。目を見開いて、あいつをようく見ろ! ここで殺さなくてどうする! だが、ロビンの目眩はどんどんひどくなる。視界の中で五百の目玉がグルグルと回りだした。ロビンはついに剣を取り落とした。
ロビンが惑ううちに、ジョンは再度攻撃をしかけている。剣を上段に舞いあげると、黒剣がついてきた。男たちの頭上でふたつの剣がからみあった。
ジョンは目をみはった。自分は両腕だというのに、片腕のモルドレッドが剣をやすやすと押しかえしてきたからだ。あまつさえ腰が浮き上がるのを感じる。この男の怪力と来たら、自分をこども扱いだ。ジョンは顔を真っ赤にして剣を押し返そうとした。そのとき、モルドレッドの空手がふところに伸び、さっと短剣を引き抜いたかと思うと、ジョンの肋を深々と刺した。
「あうう、あう」
「ジョン!」
ロビンはハッと目を覚まして剣を拾った。
モルドレッドはジョンの体を仰向けにすると、ブーツの底であばら骨を砕き、投げ出された片腕を踏みつけへし折った。ロビンは夢中でジョンを助けに行く。すると、モルドレッドはふりむきざまに、短剣で彼の頬を切り裂いた。
「他人の心配をしている場合か、ロビン・フッド!」
「くそっ」
頬を拭い、その血を柄になすりつけ、モルドレッドにうちかかる。だが、モルドレッドの鉄壁をやぶるにかなわず、剛剣におしかえされて、否応なく腰が浮いてきた。
まともにうけられん! だめだ剣ではかなわんぞ!
ロビンは必死で攻撃をかわしながら一計を案じた。
モルドレッドが斜斬りを繰りだしたところで、ロビンはわざと両手の力を抜いた。剣が勢いよく吹き飛び床をすべっていく。モルドレッドが虚をつかれその体が流れると、すぐさま懐に飛びこみ、腰にさした矢を引きぬいて、モルドレッドの目玉をしたたか刺した。
モルドレッドが悲鳴を上げてよろめく。
「どうだ、悪童! 恐れいったか!」
ロビンが剣を拾おうとすると、その手を小さな手がつかんだ。
ロビンが見下ろすと、彼の腕をつかみあげているのは数人のこどもたちだった。ロビンはあやうく剣を離すところだった。その子たちは呪詛のこもる眼でロビンを見上げている。ジョンが、まさか、とつぶやくのが聞こえた。
「くそ、離せ」背後では目玉をつぶされたモルドレッドが盛大に呪いの声を上げている。ロビンはほとんど懇願するように、「かわいそうだが、お主らは死人だ。手を離せっ」
「ロクスリー!!」
モルドレッドが右目を押さえて駆け寄ってくる。指の隙間からは血がダラダラと流れている。残った目玉は血走り、怒りの形相もすさまじい。ロビンは喉をつかみ上げられる、剛力がぎりぎりと筋肉をおした。気管がおしつぶされそうだ。
「ロクスリー、俺の体に傷をつけたな!」
ロビンが膝をつく、ゴボゴボと喉音がたつ。それでもしゃにむに剣をつかんだ。こどもたちがしがみつくのも構わず、じわじわと腕を上げた。モルドレッドは両腕をつかってロビンの首を締め上げていたが、血で滑っているのが幸いだった。ロビンはその間に、歯を食いしばり、こどもたちの亡霊を引きずりながら、モルドレッドのみぞおちに深く剣を突き入れた。
モルドレッドが目を見開く。けれど、ロビンの喉にかかる力は弱まらない。モルドレッドは血を吐きながらもさらに怒りを増し、ロビンの喉を揺すり絞め殺そうとしはじめる。
「ジョン……」
長剣は確かにモルドレッドの脇腹を深く突き貫いている。その刃を伝う血液はロビンの指まで届いていたが、その血液が変化をはじめた。血溜まりから小さな腕が何本も生える。ロビンは眼を見開いた。その小さな手は刃にベトペタとまとわりつき、剣を押し戻しはじめたからだ。
くそ、聖杯の力か
「ジョン、こいつの首を落とせ……!」
「首を落としても死ぬものか、聖杯の力を侮るなよ!」
ロビンはついに屈して両膝を折った。ロビンは酸欠で真っ赤になりながら、押し戻そうとする力と戦った。
「貴様に俺は殺せんぞ。あのアーサーも俺は殺せなかった」
ちびのジョンは隊長を助けようともがいた。だが、ロビンを邪魔したこどもたちが、今度は彼の体を抑えつけている。
「やめてくれ、俺にロビンを助けさせてくれ!」
こどもたちは数人しかいないのに、五百人分の重さがかかっているかのようだ。こどもの一人が(女の子だ。五歳ぐらいの)彼の首に腕を回して何事かささやく。彼に死者の声は聞こえなかったが、唇の動きだけは感じた。古代の英語で彼に呪詛を吹きこんでいる。体温が急速に下がり、体が震えだした。そのとき、異様な気配を感じて、ジョンは顔を上げた。なぜかこどもたちもそちらを向いた。
モルドレッドの背後になにかがいる。いるとしか思えない。それは空中に立ち上がる影のゆらめきのようだ。その妖気は、真っ黒なオーロラだった。モルドレッドの頭よりはるかに高い位置に、引き裂かれた赤い目がのぞいている。引き裂かれた口が見えた。いまや暗黒の男を形作ろうとしている。
「まさか……」
ジョンはその男に畏怖を感じつぶやいた。思い出したのは、洋一と太助のことだ。あのこどもたちが言っていたことは、本当だったのだ。
「ウィンディゴか――」
○ 2
ロビンとジョンが死の危機に瀕するころ、牧村洋一も苦しんでいた。
手の関節が白くなるほどに万年筆を握りしめている。足下にはちっぽけな少年が手足を投げ出して横たわっている。絨毯にジュクジュクと広がる血液の染みが、奇妙なほどに大きく見えた。ふいに初めて会ったときの太助の光景、船の上でともに甲板掃除をしたことや、暗い倉庫でいがみ合ったことが思い起こされた。それらはけして楽しいことばかりであったはずがない。なのに二人の絆を深めているように思われた。ともに楽しんだわけじゃない。ともに苦しんで、時に命を預け合ってきた。だからこそ、洋一はやろうと思った。彼はソファに深く腰掛け、膝に両肘をつき、腕を垂らし、首も両肩の隙間に潜りこませるようにした。そして、全身を垂らして力を抜いていったのだが、それは恭一がよくやっていたリラックス法でもある。父親が無意識にしていた仕草を、その息子も無意識の内に真似ていたのだ。
どうする? と彼は自問する。目の前にある事態は、アイディアの煮詰まりにも似ている。太助は喉を食いやぶられ、全身に毒が回ろうとしている。時間はない。つまり、彼は半死人を魔法めいた力で救わなければならないのだ。
父親は登場人物を窮地に追いこめと言っていた。それはおもしろいストーリーづくりの基本なのだけど、その窮地から脱する解決法を彼の頭は思いつかない。
つまるところ、洋一がやろうとしていることは、伝説の書をつかって新たな物語の流れを作ろうということなのだ。足下を見つめ、もし、これが小説なら、と考えた。状況が行き詰まったときにこそ、Qを出さなければならない。
よく考えてみると、Qをだすということと、状況を見抜くということは似ている。Qをだすというのは、つまりはポイントをつかむということだった。ストーリーも言葉とおなじで、一つ一つ積み上げていくことに変わりはない。肝心なのは、いい加減で安易な解決策を求めないことだ。ていねいにやりさえすれば、前半に広げた話もうまくまとまるものだった。
洋一が考えるに、小説としての状況は今では広がりきっている。ストーリーでいえば、後半も後半の大詰まりで、話を纏めに入らなければならない段階である。だからこそ、ヒントはこれまで広げた話の中に見つけるべきだった。解決策はこれまで起こったストーリーにあるはずだった。そうでなければ、伏線などというものはなりたたない。
問題は、これが彼が書いた話ではないということだった。いいストーリーは前後の話が密接につながっている。そう父親は言わなかったか? 洋一は父親の語った言葉を不完全にしか理解していなかった。彼には知らない言葉、理解できない概念が多すぎたし、洋一がそうした言葉を完全に掌握するには、もう十年ばかりかかりそうだ。けれど、彼の才能は、恭一の伝えたかったことをまさにボディ感覚で咀嚼していたのだ。
「だけど、どうしたらいいんだ?」
とつぶやく。今までと違って、ボンヤリとはしているが、冷静な声でもあった。男爵は物語の世界観を見抜いてそれを利用しろと言った。ロビンの世界でだって、死人が生き返ったりはしないのだ。確かにこの世界に魔法は存在するし、蛇に化ける魔女だっている。問題はこの場に味方となる魔法使いがいないことだろう(その魔法使いが死者を復活させられるとは限らないが)。小説ならその前後を書き直すことはいくらでもできる。だけど、この世界のコマはすべて出そろっている。そのコマの中に利用できるものがあるはずだ。なければ太助は救えない……。
「どう書きこむ? どう書けばいい……」
傷が塞がって毒も抜けたと書くのか?
洋一は駄目だと首を左右に振った。それだったら、裏付けがなくちゃいけない。アイディアを底支えするアイディアがいるのだ。脈絡のない話が現実化しないのは、シニックで証明済みだ。洋一の深層意識は、そんなアイディアはボツだと叫んでいた。彼は確かにちびでプロ作家でもなんでもないが、それでも正しいアイディアのなんたるかは知っている。
「なにかあるはずだ……これは物語なんだから」
だんだんと没頭してきた。創作という行為が彼の心をつかまえかかっている。洋一は相変わらず太助を見ている。けれど、心はまったく別のものを映し出そうとしていた。周囲の音も遠のいて、耳鳴りだけが残っている。ひらめきがくるのは決まってこんな時だった。
利用できるものか……
洋一はブラックアウトのように視界がぼんやりとなるのを感じた。彼は観察眼に優れた少年だった。父親が鍛えた部分はあるにしろ、それらはおそらく天性の物だ。その観察眼の中に、なにかが引っかかていた。
右腕だ――
洋一は自分の右腕をじっと見つめた。視界がだんだんとはっきりしてきた。人を蘇らすことは出来ない。でも、太助はまだ死んでないぞ、と洋一は思う。死にかかっているけど――でも、ぼくも死にかかっているんじゃないのか?
「呪いか……」と彼は言った。意識がまたしゃんとした。「呪いだ。こいつは死の呪いじゃないか!」
右腕をわずかにもちあげる。そのせいで、掌から肘へと伸びた亀裂がよく見えた。アジームの言ったとおりだったのだ。死の呪いはどんどん広がっている。今もだ。亀裂の縁からは、暗黒の気体が小さな手のように触手を伸ばしている。その勢力を広げ、彼を死に至らしめようとしている。
モルドレッドのことを思いだした。あいつはこう言わなかっただろうか? お前の体に死を植えつけてやると。つまりこの黒い気体は死そのものなんじゃないだろうか? だから右腕が動きにくいのでは?
ぼくは生きてるけど、右腕は死にかかってる。
洋一は右腕をさすった。今までは気持ち悪くて素肌はろくにさわらなかった。亀裂の気体は思った通り、ハチミツのようにドロリとして、砂漠よりも乾いている。洋一はもう一度モルドレッドの姿を思い起こした。
ここには死が集まってる。
あいつは死を操ってる。
この世界では死を操るやつがいる。
「ぼくは死とつながってる」
なにかが頭の中ではじけていた。洋一は興奮に目を開く。ひらめきが脳髄を叩いてはやし立てている。いけるかもしれない。これならいけると洋一は思った。ひらめきのもたらし手は(それがなんであるのかはわからないが)今や祝いの鐘を打ち鳴らしている。直観の力強さが彼のハートをうっていた。頭は不安を、不確定要素を考えたがっていたが、彼の胸はGoサインを出していた。洋一は、これならやれるかもしれないと思った。
「太助にあるのも死だ。だったら死を移せばいいじゃないか」
問題は処理の仕方だ。このアイディアを実行すれば、かれ自身が死を引き受けるということになる。今度はこっちが死ぬだけだ。
「いや、大丈夫だ」と首を左右に振った。「ぼくはあいつともつながってる。やれる、やれるぞ!」
洋一は床に手をついた。伝説の書をその場に起き、もどかしい手つきで乱暴に開く。ページは風もないのに独りでに捲れて、止まった。おいでおいでをしているようにも、欲望の熱を放っているようにも見える。彼はわずかに怖じ気づく。
「落ち着くんだ……」
洋一は万年筆を持ったまま固まり、喉を湿らせようとした。これから最高の文章を書かなければならない。よい文でなくともいいから、力のある文章をひりだす必要がある。
父親の懐かしい声がいう。文にするということは客観的に見るということだ――
「わかってる。やれるよ!」
と洋一は久々に恭一に向かって答えていた。わかってるよ、お父さん。落ち着いて、淡々と書けっていうんだろ。タンタン、タンタン
洋一はタンタンと呟きながら目を閉じまた開いた。いつもの文章とはちがうぞと思った。こいつはかれ自身のことをふくめて書かなければならないからだ。それも少し先の自分の姿を。「わかりやすく、わかりやすくだ」
「そうでないと、本はお前を取り殺すぞ」
後ろから声がして、洋一はふりむいた。部屋の隅の天井の陰になにかがいる気がしたが、目をしばたたくと誰もいなかった。また伝説の書に目を戻した。
洋一の発想は奇抜だったが、この世界では至極まっとうなものだった。モルドレッドは彼を呪うために、彼の体に死を植えつけた。それが太助を救う最後のピースだった。
創作の興奮と死の恐怖で首はこわばり、気道が細くなる。指はやはり震えている。
外からギャア! と悲鳴が聞こえた。洋一は驚いて飛び上がった。洋一は胸を押さえ、すぐさま本に立ち向かう。今は駄目だ。静かにしてくれ――彼は気を静めよう、大きく息を吸おうとしたが、唾を飲むばかりでそれすら喉につかえてしまった。
ほとんど夢中で無心で書いた。本は狙い通り、文章を吸い取りはじめた。
『牧村洋一はモルドレッドの手により、その身に死を植えつけられていた。彼は死と密接につながっている。友人が目の前で死にかかる中、洋一はこう考えた。自分の身体が死とつながっているのなら、死の亀裂を通して太助の死をその体で引き受けることは出来ないだろうかと。つまり、彼はその死を自らの腕に引き寄せることにしたのだった。それは――』
「待ってよ……」
震える声が喉から漏れた。洋一の腕から、死の霧が黒々と立ち上っている。その身に開いたどんな海溝よりも深い亀裂は、手首を遡り前腕を断ち割って肘を侵しだす。死の気配は煙のようにグワッと伸びて、体を取り巻きおいでおいでをするように頬を撫でる。
「待ってくれ、まだ早すぎるまだだ!」
文を現実にする力は思いのほか速かったのだ。死が体をのっとりだしていた。太助に舞い落ちた死の力が、彼の体を戒めはじめた。
続きを書かなきゃ!
洋一はブルブルと震えながらも腕に力をこめる。ペンを取り落とさないよう、しっかりと掴む。紙が破れんばかりの筆圧で書いた。彼は自分の書く字を見て呻いた。ああ、なんて下手くそなんだ。
『果たして死の呪いは洋一の思惑通り、右腕の亀裂を通って洋一の体を立ち上りはじめた。そして、その死は洋一を死に至らしめるはずだったが、けれど』
「ああ――」
洋一の呟きは残酷ほど絶望に満ちていた。太助はあまりにも死に近づき過ぎていた。その死を引き受けた洋一に広がる呪いもまた凄まじく性急だ。右目が白濁し、霞んできた。まるで眼球が弾けたみたいに、大粒の涙がこぼれだす。死をともなう黒い気体は右腕を冒し、黒い粘膜のように首を這い登り、体内に深く深く入りこむ。洋一は内臓がジワジワと死滅していくのをクッキリと感じていた。末期症状を迎えた負傷者よろしく震えながら、それでも文を書こうとしたが、指先はついにペンを取り落とした。
腕が動かない。
洋一はかすむ目でペンを探す。ない、ない! ペンを拾えない!
死が肺を冒し、血を吐くに及んで、彼はついに絶望したのだ。
「ああだめだ」と洋一。「駄目だ駄目だ! もう、死んじゃう……」
○ 3
ああ、ウィンディゴ様……。
モーティアナは血の海に倒れ伏していた。太助の最後の一撃はこの魔女の心の臟を貫いていた。マーリンから与えられた力も、血液と一緒に流れ出していくかのようだ。モーティアナはどうにか階段に辿り着き、外気をしぼんだ肺に吸った。彼女は懐から血にまみれた水晶球をとりだし、一段下の階段に置く。もう限界だ、もう動けない、ウィンディゴ様……。と彼女は自らが尊師と呼ぶ人物を呼び出そうとする。なぜ助けて下さらないのです――
ウィンディゴは水晶球の先にはおらず、最初から彼女の内側にいた。そうして、彼女が苦しみ死ぬのをまるで愉快な道化を見るようにあざ笑っていた。貴様はもう用済みだ、とウィンディゴは言い、モーティアナは薄れゆく視界を、閉じようとする瞼をこじ開けようとする。
お前では小僧を殺せなかったな、だが、牧村の小僧を追いこむことはできた。小僧はまたも本をつかった。貴様の力をもらうぞ、モーティアナ
モーティアナは悲鳴を上げたかったのだが、その胸はああ、ああとかすかな蠕動を繰り返すだけだった。モーティアナは残った力をウィンディゴに奪われた。彼女は小さな小動物のような頭をことりと階段に落とし、意識を薄れさせていったのだ。
○ 4
ミュンヒハウゼンは走っていた。急速に年老いたせいで、心臓は焼けるような痛みにあえいでいる。膝はそんな老人をあざ笑う。水分はなくなり、筋肉は固くなり、それでも彼は走っている。まるで、速く走れば少年たちの死を追い抜けるとでもいうかのようだ。実際のところ、あの魔女さえ死ねば奥村少年を救えるのではないのかと、ありえない願いをかけて走っていた。
彼はモーティアナの残した血の痕を追っていた。部屋の守りは奥村に任せてきた。いまの奥村には復讐すらもきつかろう。待っていろ、三人とも待っていろ、と男爵は思う。わしがあやつをやっつけてやるぞ。
廊下の先は行くほどに明るさを増していく。勝手口が開いて、外気が内部のよどんだ空気を追い払っているのだ。モーティアナが階段に、醜い猿膊を伸ばしている。
ミュンヒハウゼンはひゅうひゅうと息を吐きサーベルを引き抜いた。
男爵は戸口にぶつかりながらモーティアナの真上に立った。老婆はかすかにふりむいたが、その瞬間に太助の刺した傷が醜く裂ける。老婆の苦痛の顔は、なぜか笑っているようにも見えた。
この老婆が数百年を生きたマーリンの弟子であるとはもはやかれも疑わない。小さな頭蓋の下で、魔女とは思えぬ赤い血が階段をそめ滴り落ちていた。髪はごっそり抜けたようだが、右腕だけは救いを求めるように空中に突きだされている。ミュンヒハウゼンは荒い呼吸を懸命に胸のうちにおさめながら老婆をみおろす。老婆の腕は力なく階段に投げだされ、もはや魂を失ったようにも見える。ミュンヒハウゼンは背後に異様な気配を受け、名を呼ばれたような気がした。ウィンディゴか? と心に疑ったが、彼はふりむかない。女の胸元につるぎを当てると、すばやく振り上げる。
心臓を突き刺した瞬間、モーティの背中から、笑声を上げる巨顔が突風のように吹き上がり、男爵の体に飛びこんだ。ミュンヒハウゼンは、「ウィンディゴ……」と叫びを残して、大きく後ろへ跳び、モーティアナの残した血の中に倒れこんだ。
「ミュンヒハウゼン、貴様は邪魔だ! 眠っておれ!」
男爵は無言の悲鳴とともに、背後にどうと倒れた。そして、二度と動かなくなった。ウィンディゴの陰は、その上で優雅に漂い、ミュンヒハウゼンの様子を確かめた。
牧村の息子は着実に力をつけておる。だが、お前はじゃまだ。
そして、家の奥に目を向ける。
ふふふ、侍の小僧を復活させおったか。まあいい。お前の名付け親は封じたぞ。どうする小僧……
そうして、ウィンディゴの姿は宙に消えた。アジームが戸口に駆けつけたときは、息すらせずに眠るミュンヒハウゼンと、モーティアナの死体があるだけだった。
○ 5
その名付け親が死したころ、牧村洋一もまた自らの血の中に倒れていた。手足がビクリビクリと震えている。洋一は無念な思いの中で死のうとしていた。ただ両親に謝りたかった。お父さん、お母さん、せっかく助けてもらったのに、ごめんなさい……と。
死を吸いとるなどばかげた案だった。太助の味わった苦痛が彼の中にどんどんと入ってくる。洋一は身動きもせずに涙を流している。気がつくと真っ黒な影が目の前に立っていた。彼を見下ろしている。
「助けて、助けて……」
彼は悲しい悲鳴を聞いた。それはかれ自身の喉が上げる狂おしくもか細い悲鳴だ。洋一はその悲鳴に目を覚まし、それでもまだ悲鳴を上げゴロゴロと喉を鳴らし、血を吐きながら左手で落とした万年筆を探り当てている。
死にたくない。まだ死ねない。
だが、もう目が見えなかった。太助の苦痛が全身を支配して、ついに意識が遠のいていく。
○ 6
そして、それとおなじくして、この物語の主人公ロビンもまた死に瀕していた。
モルドレッドの左腕はロビン・フッドの命を奪おうとしていた。剛強のロビンもその喉首をへし折られんばかりだ。モルドレッドは傷の痛みに呻き、苦痛をもたらすロビンの存在を呪い上げた。普通の人間ならばモルドレッドをここまで傷つけることはなかったろう。やはりこのロクスリーという男には不可思議な面がある不確定要素がある。いっそこのままここで殺すべきだ!
「お前はおろかだロクスリー。真の王たるこの俺に逆らうなどと俺を討ち果たそうなどと。貴様の夢物語はここで終わりだ!」
そのとき、ロビンは見たのだった。モルドレッド・デスチェインの背後に闇の男が立ち上がるのを。ウィンディゴだった。モーティアナの元を離れ、モルドレッドを籠絡するべく暗黒の部屋にやってきたウィンディゴの姿を、ついにロビンとジョンも目にしたのだ。
こどもたちに身を塞がれたちびのジョンは言葉をなくし、ついでロビンを救おうと躍起になって腕をついた。しかし、死人となったこどもたちは、一人また一人と増え、彼の背中にまとわりつく。万鈞の重みが掛かり、ジョンは肘をついて苦痛に呻いた。赤子たちの泣き声が頭蓋を震わし轟くと、ジョンは一歩も動けなくなる。
モルドレッドの体はウィンディゴと共に膨れ上がっていく。ロビンの体は宙に浮いた。モルドレッドはウィンディゴの力を受けて強大となっていた。ロビンの体に死の呪いを流しこむ。その呪いは急速にロビンの身を引き裂いた。そして、異空間の部屋が崩れだしたのはその時である。術者であるモーティアナが引き裂かれた心の臓を止めために、その魔力も潰えたのだ。調度がガラガラと崩れる。部屋はまるで墜落する飛行機のように揺れ、激しく傾いた。
ロビンが地を蹴ろうと虚しく足を動かす。ロビンは胸に広がる激痛にあぶくを垂らしだす。ロビン・フッドは無音の絶叫をした。死の亀裂が喉から胸に降り、ついで四肢を引き裂きはじめたのだ。
「やめろお!」
モルドレッドはジョンの悲しげな声を喜ぶ。声を大にして笑う。仇敵どものもがき苦しむさまは愉快この上ない。
「我が苦痛を貴様も受けろ、ロクスリー!」
モルドレッドが異変を感じたのはその時だった。異変は体内にあった。何者かが彼の魂に働きかけている。モルドレッドは驚いて左右を見たが、侵入者はいない。当然だ。その者が入ろうとしたのは、彼の心の中だったのだから。
モルドレッドの笑みは消え去った。彼は精神に意識を集中した。どうやら何者かが自分とつながりを持とうとしている。
なんだ?
脳裏にうかんだのは、古ぼけた本をもつ少年の姿だ。モルドレッドは顔を上げ、呆けたようにつぶやいた。
「あの小僧か……」
ジョンは大勢のこどもたちの下、もがくのも忘れてその光景に見入っていた。なぜかこどもたちも呆然としていた。
死がやってくる。
モルドレッドはロビンを締め上げていた腕を離す。突然開いた傷口に驚いてのことだった。それは太助に空いたのとおなじ蛇の牙痕だ。モルドレッドは紫に染まる首の穴を押さえこもうとした。鮮血が指の隙間から吹き上がった。ビチャビチャと床に散る音が聞こえた。ロビンは力なく床に落ち、頭を痛打して跳ね返る。その体は死の呪いで真っ黒だ。それとおなじ禍々しい亀裂が、モルドレッドの体を覆いはじめた。
ちびのジョンにとっては最後のチャンスだ。ロビンを救うには今しかない。
「ちくしょう、離せえ!」
ジョンは声をかぎりに絶叫し、モルドレッドはその声に応じてジョンを向く。だが、彼の目玉は白濁し、涙が滂沱として流れるばかり。足下のロビンにすら蹴躓き、激しく打ち倒れてしまった。
ジョンはこの隙にロビンのもとに向かおうとした。こどもたちは口が裂けるほどに大口を開け、髪をつかみ皮膚をえぐる。ジョンはすっかり恐ろしくなった。彼らは何事か激しく叫び立てているのだが、彼にはちっとも聞こえないのだ。
ロビンだ。ロビンを助けるなら、今しかねえ。
ジョンが叫ぼうとすると、こどもたちは小さな手を喉に押しこむ。ジョンは唾を散らしながら、喉の奥までまさぐる冷たい手に苦しんだ。
ジョンの揺れる視界にあるのは、死の呪いに苦しむモルドレッドと人以外のぼろ切れのように倒れ伏すロビン・フッドのみだった。ジョンはモルドレッドの背後で暴風雨を喰らった樹木のように揺れる影に見入った。
ジョンは片腕で身を起こしながら、洋一の言葉を思い出していた。こどもたちの命を狙う男の存在を。同時にこの窮地を救ったのが誰なのかはっきりと悟ったのだ。
ジョンは折れた肋をきしませ立ち上がる。迷っている時間はない。時空間はすでに歪み、彼の体を放りだそうとしている。モルドレッドは太助や洋一とはちがう。やつはどんな傷でも死なないからだ。飛び散った血液は持ち主の元に集まって、その肉体の傷を塞ごうとしている。復活の力が死の呪いと争っている。
殺せる? いまなら殺せるんじゃねえのか?
ジョンはくじいた足首を引きずりロビンの元に駆けつける。ロビンは死の呪いに覆われ、全身の亀裂から黒い気体を吹き上げている。地獄の番人共が彼の肉体に巣くって呼吸をしているみたいに、その気体は出戻りを繰り返している。ジョンは、ロビンが落とした剣をのろのろと拾った。
こいつは死兵とおなじじゃねえのか、首を落とせばこいつだって
モルドレッドの背後にいた暗黒の男が襲いかかってきたのはその時だった。ジョンは慌てて身を伏せる。その背中をウィンディゴがかすめ飛んだ。
「どうしたちびのジョン!」その声は太鼓から発せられたかのように不気味に震え轟いた。ジョンは恐怖のあまり這いつくばる。「来い、泣き虫ジョン! 俺と勝負をしろ!」
ジョンは頭を抱えて、ロビンの体に手をのばし、その安否を確かめるようにペタペタとさわった。
「すまねえ、ロビン。俺にあいつは殺せねえ。だってあいつは……」
ジョンがロビンを肩に担いだとき、今やうつぶせとなり、額を床につけていたモルドレッドが血まみれの顔を上げた。
「ロクスリー、お前は俺から逃れられんぞ。その答えはすぐわかる!」
ジョンはなにか答えようとしたが、なにも言いえなかった。揺れる床の上でロビンを抱えて立つのが精一杯。彼は逃げだそうとしたが、その部屋には出口などもちろんない。そのうち地面が割れてモルドレッドとちびのジョンは二つの方向に分かれていった。ジョンはモルドレッドの、おのれ、モーティアナめしくじったな、という声を聞いた。
ジョンはロビンにかぶさるようにして絨毯に身を伏せた。が、わずかに残った部屋の床面も、端から削り取られるようにして小さくなっていく。暗黒がごおごおと風音をたてて二人を襲った。
ちびのジョンが目を閉じるうちに、二人の姿は暗闇に投げ出されていたのだった。
◆ 第二章 ロビン・フッド、アヴァロンにいたる
□ その一 牧村洋一、グラストンリヴァーをさか上ること
○ 1
洋一は猫が日向でそうするように手足を丸め、なにかを請い願うようにうずくまっていた。そうして死ぬのを待っていたのだが、彼の予想した死はいつまで経っても訪れなかった。洋一は恐る恐る顔を上げた。目はかすんでおらず、ソファーの足もはっきり見える。洋一はゆっくりと身を起こした。伝説の書は目の前にあり、気絶する前とおなじページを開いていた。本を手にとった。文は消えていた。書いたのか? と彼はつぶやいた。左手で、あの苦痛の中、まともな文が書けたのか疑問だったが、どうやらうまくやったらしい。自分は死体じゃない。そして――
「太助!」
と友人のもとに駆けつける。洋一は心臓に耳を当てた。動いている。息はあいかわらずか細いが、まだ継続しているようだった。それから彼は服の袖で、太助の首元をもどかしげに、だけど慎重に拭っていった。
傷が塞がっている。
「勝った」
と彼は言った。後ろによろめくと手をついた。
「やったぞ、勝った……! おじさん、やったよ!」
奥村は部屋に一歩踏みこみ、そこで立ち止まった。
「おじさん……」
奥村に呆然たる時間が訪れた。死人か彫像になったようにも見える。まさにそのとおり。息子が死んでいたら、彼の時間も今ここで止まっていたにちがいない。
奥村は洋一を見る。生きている。ついでその視線は息子の上に釘付けとなった。彼は唾を飲んで、
「太助……」
と血にまみれた息子に近づく。夢遊病者のように不確かな足取りで、枕元にひざまずく。そっと首に手を当てている。なにも感じなかったが、もうすこし強く指を押しこむと、脈動があった。彼は呼吸を止め、すこし震えながら、息子の胸に耳を当てる。衣服は血に塗れていたが、その奥にある肉体は温かく、確固たる心臓の音が聞こえた。生まれ落ちたときからしてきたように、息子の小さな心臓は脈打っていた。そのとたん、奥村の目からぽとりと涙がこぼれたのだった。
「生きている」と奥村はつぶやく。左顔を朱にそめ、息子の顔を見つめる。血色がさし、太助の肌は温かい。呼吸はひっそりとしているのに、今の彼にはむやみに力強いものに思えた。生まれたての赤子を見るように、息子の呼吸をじっと見た。やがて、首をがっくりと垂れ、はらはらと涙をこぼす。太助、太助、お前生きていたか、とそのことだけを噛みしめた。熱い固まりが胸におしよせ、彼はそれを嘔吐するように吐きだした。涙がどっと出て、今は静かに眠る息子の顔にかかった。太助お前生きてたか、とそれだけを思った。後は言葉にならなかった。
洋一は疲労と痛みの中を漂っていた。自分が立っているのか寝ころんでいるのか、そのことも判然としなかった。呪いがついに脳におよんで、判断力の大半をかすめ取ってしまったかのようだった。奥村の歓喜を確かに味わった。自分のしたこと、自分の存在が、ようやく価値のあるものに思えてくる。その一方でひどく疲れ切ってもいた。本の力は太助に下った死そのものをモルドレッドに移しはしたが、彼の呪いは消えなかった。だから奥村の歓喜を噛み締めながらも心の奥底では楽しめずにいた。自分が早晩死に至ることをわかっていたからだ。
洋一は無言でその歓喜の様を眺めていた。それから洋一は右手の呪いが消え残っていることをしげしげと眺めた。それどころか彼の呪いは肩まで広がり半身まで届いている。顔の半分を覆いつつある。洋一は今度は安堵ではない観念のため息をはいた。伝説の書は二人のこどもにかかる死を、伝説の王に移しはしたが、呪いを止めるにはいたらなかった。彼は呪いが消えるようには書かなかったし、もう一度挑むつもりもない。右半身に広がった呪いから目をそらすと、もう一度ため息をつく。それから口元を手の甲で拭い(血がべっとりとついた)、おそるおそる指で喉に触れ(血がべっとりとついた)、もう塞がっているが、蛇の傷口が醜い肉腫のように盛り上がっているのを感じた。
奥村は息子の体を幼子のように抱いて立ち上がっている。洋一にはそんな太助がひどく小さく見えてまた少しうらやましくもあった。
洋一は呪いが半顔におよび、唇が麻痺してうまくしゃべれない。
「息子のために命を張ってくれたのだな」
洋一はどう答えていいかわからなかった。大人が泣くのにもなれていなかったし、自分が大それた事をしでかした気分でもあった。
「おおげさだよ。太助だってぼくを助けてくれたんだ」
奥村はひどく優しい目になった。「このことを俺がどう感じるかだ、牧村洋一。俺はこの恩を生涯忘れない。お主は息子を命をかけて救ってくれたから、俺もお主のことは命を懸けて守る。我が息子にして我が主君と心得た」
「でも、ぼく、そんなに大したことやってない。文を書いただけだ」
洋一はとうとう困って助けを求めた。
「男爵は、男爵はどうしたの?」
奥村は目を背けた。洋一は妙な胸騒ぎがした。
「男爵は? 男爵はどこ? 男爵は……?」
そのとき部屋に入ってきたのはアジームだった。
「洋一、男爵はだめだ」
そのとたん洋一の胸を空虚な痛みが引き裂いた。
「だめ? だめってなに? ぼくはちゃんとやったんだ! 男爵に会わせてよ」
アジームは部屋を出ようとする洋一の肩を押さえた。
「離して離してよ、男爵に会うんだ」
洋一はアジームの手をふりはらい、部屋を飛びだした。廊下はモーティアナの魔術がまだ残っているのか、真っ暗なままだ。洋一は男爵を捜して廊下を走った。男爵のあの老人の顔が見たい。今思うと彼はミュンヒハウゼンに褒めてもらいたくて、この難関にも挑んだのだ。
廊下の先の外階段、ほらふき男爵は青白い顔をして横たわっている。ロビン・フッドの仲間たちも集まっている。そばに膝をついていたアランとガムウェルがふしぎと落ちついた顔で彼を見る。
「男爵……」
アジームが追いついてきた。「モーティアナにやられたのだ。やつは男爵が倒したようだが」
「心臓は動いているが、目を覚まさない」とガムウェルが言った。「モーティアナの呪いが男爵に入りこんだとしか思えない」
洋一はミュンヒハウゼンに近づくことが出来なかった。名付け親のありさまを認めたくなかったのだ。
「ぼくはちゃんとやったのに、なんで……」
アランが剣を鞘におさめながら立ち上がる。
「もう、ここを出よう。ロビンを探しに行かないと。さきほどの場所を見たが、ロビンは帰っていなかった。だが、モーティアナは死んだのだから、どこかにいるはずなんだ」
アランの声は切実な願いをふくんでいる。アジームらがこの年老いたほら吹きな男を担ぎ上げた。モーティアナは倒したが、ロビンとちびのジョンは消え、男爵もまた目を覚まさない。結局この戦いは痛み分けとなったのだった。
○ 2
そのころ、ロビン・フッドもまたちびのジョンにおぶわれてあてどもない旅路についていた。二人は暗黒の部屋を放りだされて、見知らぬ土地に放りだされていた。けれど、ロビンの身に巣くった呪いは、おなじ呪いをもつ人物を感得していた。牧村洋一だ。
ロビンは背中からジョンに指示して、洋一を感じる方へ彼の足を導いた。
そうして、ロビンはかつての仲間と再会したのだが、そのときには彼の身を裂く死の呪いはあまりに深く、生命力は幾ばくも残されていないようだった。ロビンはそこで牧村洋一の話を聞くことになるのだが、それはまだ少し先のお話である。
○ 3
話は洋一少年が、奥村たちに連れられて、モルドレッドの目を逃れ、とある河原に身を隠した所からはじまる。
洋一はその小屋の中央に太助とならんで寝かされていた。すぐ隣には奥村がすわり、小刀でオレンジを剥いているところだった。太助はまだ目を覚まさない。
洋一はときおりぶつぶつとつぶやく。奥村はときおり手をとめて二人の様子を確かめる。
洋一は太助の死をどうにかモルドレッドに移すことができた。けれど、かれ自身の呪いはより一層深まってほとんど動くことが出来なかった。亀裂は半顔にまで広がって、口もうまく動かず片目は見えなかった。そんな状態だったのだが、洋一は考えなければならなかった。この状況を打開する方法を。脳に死がおよぶ前に、思いつく必要があった。せめて、文字が書けなくなる前に。
洋一は、ロビンが自分の元に向かってきているのを知っていた。二つの呪いは響き合い、それが互いの呪いを深める結果ともなっていた。けれど、彼にはロビンが必要だ。物語にはロビンというピースがいると、なぜかこのとき感じていた。ロビンがいれば、この状況を打破できる気がする。そのトゲのようなひっかかりは、抜けばアイディアがあふれだすことを彼に教えている。
洋一は棘がだんだんと抜けていくのを感じた。理詰めで考えていくことで、無駄なアイディアはどんどん削られていった。そして、トゲはあるときポトリと抜けた。洋一は奥村を見上げて言った。
「おじさん、本を持ってきて。モルドレッドを殺す方法をずっと考えてたんだ」
正確にはあいつが死ぬ設定を考えていた。あいつが不死身なのにはちゃんとした理由がある。聖杯の力、赤子の魂、マーリンの呪い、それらはいずれもアーサー王の世界のものだ。ロビンの世界にはモルドレッドを倒す方法がない、と彼は考えたのだ。そもそも元のロビンの物語にはモーティアナさえいなかったし、魔術もまったく登場しない。あいつはアーサー王の世界の人間だから、あいつを倒す方法もアーサー王の世界にあるはずである。そして、モルドレッドという宿敵を倒すのは、やはりアーサー王その人でなくてはならないのではないか? すくなくとも、アーサー王の持ち物をつかうべきなのでは? 洋一は今度もGoサインが出たのを知った。サインが出たら、すぐに書くべきである。時期をのがすということは、作品の風味までのがすということになりかねない。洋一は早く書きたくて苛々としたが、奥村にひととおりの話をした。
「洋一、まさか……」
「エクスカリバーだよ。アーサー王の力を借りるんだ。あいつを殺しそこねたのはアーサー王じゃないか」
「ああ――だが、洋一、アーサー王自体は死んだことになっている。ロビンのように蘇らせる気なのか?」
「ちがうよ。もっといい方法を思いついたんだ。アーサー王を蘇らせることもできるかもしれないけど、これは小説のようで小説じゃないでしょ? つまり、下手なアイディアなんか伝説の書が相手にしてくれないから」
洋一は本を持ってきて、と言った。奥村はやれるのか、と訊いた。
「やれなきゃぼくら本の世界を抜けだせない。みんなモルドレッドに殺されておしまいだ」洋一は、「ロビンが近くにくるまで待とう。それで、文を書く。それまで、力をためておかないと。アイディアはいけると思うんだけど、伝説の書がどんなつじつま合わせをしだすか、読めたもんじゃないし……」
洋一は奥村が妙にニコニコとしているので奇妙に思った。「どうしたの?」
「いや、ずいぶんたくましくなったものだと思ってな。お主は伝説の書をすっかり使いこなしているように見えるぞ」
洋一は照れたように笑いながら、頭を枕にもどし、妙にまじめな顔をして天井を見上げた。ノッティンガムでの一件が洋一に自信をあたえているのだ。洋一は離れて眠る名付け親を見た。口には出さずこう言った。待ってて男爵、今度はぼくが男爵を助けて上げるからね。
○ 4
洋一が書いたわずかな物語はまたしても本の力が吸いこんでいく。初めて目にするアランたちは、その不可思議な力に驚いた。伝説の書がすっかり文を吸いこむと、辺りに霧が漂いだした。突然のことに表の兵士たちが騒ぎはじめた。
「うまくいった」と洋一は言った。「後はロビンがやって来るのを待つだけだ。そんで、ぼくと行ってもらう。どうなるかわからないけど。もうこれしか方法がないと思うんだ」
奥村は無言でうなずいた。胸裏ではもちろん不安と疑問が渦を巻いているが、もはやこの少年が伝説の書に書きこんだ以上、そのとおり行動するほかない。反すれば、痛いしっぺ返しを喰らうだけのことである。
ロビンとジョンは洋一の言うとおりの方角から、言うとおりの時刻にやってきた。二人ともひどい格好で、ジョンはあちこち骨を折っているし、ロビンにいたっては呪いで死にかかっている。
二人はその足で洋一の説明を聞くことになった。そのころには目の前のグラストンリヴァーにアジームらの手によって、ボートが用意されていた。
洋一が久方(のような気がする)に見るロビンの様子はまずかった。呪いは彼以上の勢いでロビンを襲ったらしい。ロビンは担架に身を横たえてろくろく身を動かすことも出来ない。呪いに支配され、体の自由がきかないのだ。結局、太助と男爵の隣に寝かされることになってしまった。
そこは川にほど近く、小川につくられた小さな水車小屋である。ロビンは藁の上でまさしく川の字となって洋一の話を聞いている。
「アヴァロンに行くだって? ばかげてるぜ、そんなもな!」ウィル・スタートリーはイライラとして言った。「もうアーサー王はたくさんだぜ。みんなアヴァロンがなんなのか知ってんのか。まともな話をきいたことがあるのかよ」
「お前の話を聞こうか」とロビンは言ったが、声はまったく弱々しい。
「黙ってくれよ、今話してるだろ。考えをまとめさせてくれよ、まったく。アヴァロンの話なんてよ、ガキのころ寝物語に聞いたきりだぜ。そんな島、現実にねえけどな」
「だが、モルドレッドはいたろう。死の呪いもあった。あいつは本物だ」
「アヴァロンってのは死者の島だろうが。アーサー王が埋葬された島だろ? そんなとこ行ってなんになるんだよ。なんで行かなきゃならねえ。だいたい、そんな大昔のよ、ことによりゃモルドレッドの味方かもしれねえ野郎の了見を、なんで俺たちが飲まなきゃならねえ!」
「エクスカリバーだよ。モルドレッドを殺せるのはエクスカリバーだけなんだ」
洋一が言うと、スタートリーは血相を変えて首を上げたが、物憂げに考えこむ洋一をみて黙りこみ、頭を元の位置に戻した。まったく半死人ばかりじゃないか。
アジームが、「この川をさかのぼればアヴァロンに行けるのだな?」
と言ったので、みなは驚いた。異国人の(それも異教徒の)アジームは、一番にこの話を信じまいと思っていたからだ。
「たぶん」と洋一も心許ない。「ぼくは本にそう書きこんだ。でも、問題もある。アヴァロンは死者の島だから、死人しか入れないんだ。この中ではぼくとロビンだけだ」
「なんでおめえとロビンなんだ」
ジョンが目を剥いて言った。洋一は話した。自分とロビンだけが死の呪いに冒されたこと。それにより半分死に浸かっていることを。
「エクスカリバーなら」とロビンが真上を見たまま言った。「モルドレッドの首をとれるんだな?」
洋一は迷った。そのことについては彼にだって確証がなかったのだ。この手の古い話に詳しいのは男爵の方なんだから!
ウィルはとうとうすねてしまった。「ちぇっ、他の仲間が生きてるかどうかもわからねえのによ。アヴァロンに行きたあい、だなんて、正気の沙汰たあ思えねえや。つまんねえ連中についてきたもんだよ。俺のこと笑えたのはどの口だよ。どれもこれもあほ面下げて、アヴァロンでもどこにでも行くがいいや! 俺はここで釣りでもして待ってるからよ。片腕だってなんだってできるんだ。みやげでも持ってきてくれよな。食い物だってみつくろえ。せいぜい腹空かして待ってら」
スタートリーはみなに背を向けた。みなこの男の口をもてあまして、苦笑をみかわすのみだった。ウィル・スタートリーはその後もぶつくさ言っていたが、
「で、いつ行くんだよ」
と最後にはこのひねくれ者も折れて言った。彼らは魔女とも対決したし、スタートリーにいたっては、モルドレッドの邪法に腕を砕かれている。伝説のエクスカリバーも今では信憑性がある気がした。
「古の力に対抗できるのは古の力だけかもしれん」
ロビンは観念したように吐息をついた。アランが立ち上がり、外気をとりいれようと、大きな両開きの扉を開けにいった。
「ちくしょう」
とウィル・スタートリーがうめくのが聞こえた。汗にまみれた彼の額を冷えた風が吹きさらす。小屋の外は濃密な霧がおおい、一寸先すら見えなくしていた。その霧は真に濃く、真の暗闇のように白かった。
「見ろよ、伝説の書とやらあ、俺たちをとっぷりと捕まえてるらしいぜ」
○ 5
ようやく目を覚ました太助ともすぐさま別れとあいなった。出発前、洋一は奥村と太助の三人で話をした。
「どう思う?」と洋一は二人の考えを訊いた。
太助はまだ動けずに伏せっている。彼は隣で眠る男爵に目をやって、
「君だけで行くのは反対だ。ロビンは動けないし、もどっても来られないかもしれない」
「ジョンみたいなことは言うなよ。ぼくらしか行く資格がないんだ」と洋一は言った。「伝説の書にはそう書いたし、それが一番いい方法だ」
奥村が、「が、エクスカリバーで本当にモルドレッドを殺せると思うか? ジョンとロビンの話ではあやつ本当に不死身らしい」
「男爵は物語を利用しろって言ったでしょ。今回は……」と太助に目を落とす。「それでうまくいった。モルドレッドはアーサー王の物語の登場人物だから。エクスカリバーは絶対に利用できる。もちろん、もう一度本をつかうことになるかもしれないけど」
奥村はうなずいた。確かにこのまま座していても、ロビンも洋一も死を待つばかりだった。
太助は寝床で汗を滴らせている。
「ありがとう洋一。命を救われたな」
洋一はなぜかどきりとして目を伏せた。「今回はな……」
「次回もあるように言うな」
太助は苦笑をして、愛刀を差しだした。洋一は手を振って退けようとした。
「いらないよ。向こうにいるのはどうせ死人だ」
「それでも持っていて欲しいんだ。持って行け」
と刀を振った。洋一はなんとなく太助の気持ちがわかったので、受けとった。
困ったのはジョンだった。寝転がって首も動かせないロビンにくどくどと反対をはじめたからだ。
「おめえはろくすっぽ動けもしねえんだぞ。洋一と二人で行かすなんてとんでもねえ。なにがあるかもしれねえんだぞ。そんな所におめえらだけでアーサー王に会いに行くなんて正気の沙汰じゃねえ」と言った。「なあロビン。あいつはまだこどもじゃねえか。弓矢をとって戦ってくれるわけじゃねえんだぞ。一体誰がお前ら二人を守るってんだ」
そのこどもを偉く買っていたのは、どこのどいつだとロビンはおかしがった。
「死者の島に弓は不要だよちびのジョン。洋一はいざとなれば役に立つ男だ。俺のことはあいつに任すさ」
「もうあきらめろジョン」とアジームが見かねて口をだした。「お主には行く権利がないのだ」
ロビンがやさしい声で、「お主はここにいて準備を頼む」
「準備ってなんだ。おめえ、動けもしねえじゃねえか」
「それでもだ、ちびのジョン。後のことは任せたぞ」
ちびのジョンは泣きたくなるのをぐっと堪えた。「わかったよ、ロビン・フッド」と寄る辺のないこどものような声で言ったのだった。
仲間たちはやれやれと肩をすくめた。
○ 6
グラストンリヴァーの濃霧は薄れることがなかった。液体のように肌にまとわりついてくる。
ロビンと洋一は四人乗りの大きなボートに乗りこんだ。ロビンは船底に横たわる。洋一はボートを漕いだことなどなかったのだが、それでもともかくオールを握った。船縁で仲間たちが見下ろしている。太助は父親に背負われ、その肩の隙間から心許なげな顔を覗かせている。洋一はその友人の刀を足にたてかけた。なんだか自分が馬鹿になったように感じる。オールはやたら太かった。ミニチュアのおもちゃになった気分だ。
「洋一」とジョンが言った。「ロビンのことは頼んだぞ」仲間を振りかえり、「洋一だって体がきかねえんだぞ。川上なんて辿り着けるはずがねえ」
「こんな霧が出ていてもかね、ちびのジョン」と奥村が言った。彼にはこの霧こそがアヴァロンへの道しるべのように思えたし(あまりにも魔術的な出来事だ)、洋一の確信に満ちた態度も信頼をよせるには十分なものだ。この少年には、その直観で、なんども命を救われてきたのだから。
ロビンは濃霧にのみこまれている。弱々しい声で言った。「俺たちは必ず戻る。お前たちこそ、身辺には気をつけろ」
「今のあんたに心配されちゃ、世話ねえや」
とスタートリー。ロビンが合図にうなずくと、アジームは杭のそばに身を屈め、三日月刀を勢いよく振り下ろしてロープを斬った。
ボートが恐ろしい速さで動きだしたのはそのときだった。ちびのジョンには手を伸ばす余地すらなかった。ボートはあっという間に霧の中に飲まれていく。「洋一!」と太助の声がした。
「おじさん、太助、ジョン!」
と洋一は言ったが、目の前では霧が流れるばかり、みんなの姿はたちまち見えなくなり、自分を呼ぶ声も聞こえなくなった。洋一は恐ろしくて、太助や奥村の名を幾度も呼んだ。
「ロビン、ロビン、船が勝手に動いてるんだ! ぼくらすごい勢いで流されてる!」
「川上か? 川下か?」
「わからないよ。でも、向きは変わってないから、川上だと思う」
「ならば予定通りだろう。心配するな」
とロビンは言って長い吐息をついた。洋一はオールを握りしめながら、舳先を見つめた。
□ その二 アヴァロン島のアーサー王
○ 1
モルドレッドはロンドンの王城に舞い戻る。右目を押さえ、うなり声を上げる。が、その目玉からは煙が噴き上がりどんどん回復してもいた。
「おのれ、ロクスリー! ゆるさんぞ!」
背後に何者かの気配があった。モルドレッドが振りむき、ぎょっと残りの目玉を剥いた。背後で悠然と椅子に座っているのは、かつての師、マーリンではないのか?
「ウィンディゴか……」
とモルドレッドは冷笑した。身内のマーリンの血が騒いでいる。さきほど彼を助けたのはこの男のようだ。
「モーティアナは死んだようだな。俺に憑依を鞍替えか」
「そう言うな。あの女の持っていたマーリンの力を貴様に譲りにきたのだ」
モルドレッドはロビンに受けた傷が完全に回復し、あまつさえ、強力な呪術が身内にやどるのを感じた。が、彼は鼻で笑い、
「悪趣味な男だ。今更なぜマーリンの姿で出てくる」
「モーティアナは確かに死んだ。が、ミュンヒハウゼンの動きは封じている。侍共もたった二人ではなにもできまい。小癪なのはあの小僧よ」
「ばかな」とモルドレッドは吐き捨てる。「あんな死にかけの小僧になにができる。ロビン・フッドとていまごろ朽ち果てておるわ」
「だといいがな」
嘆息したのは今度はウィンディゴの方だった。
「癪に障る男だ。いまさらやつらになにが……」
「小僧どもが、エクスカリバーを取りに行ったと言ったら?」
モルドレッドは瞬息呼吸を止めた。「エクスカリバーなら俺を殺せるとでもいうのか」
「案ずるな」
「だが、どうやってだ? エクスカリバーは五百年の間歴史の表に出ていない。どうしてやつらが手に入れられる?」
「アーサーだ。エクスカリバーはアヴァロンのアーサー王が持っている」
「アーサー? やつか。だが、アヴァロンは死者の島だぞ」
「小僧の力――伝説の書の力を侮らんことだ。あの小僧は死の呪いを利用してアヴァロンに向かっている」
モルドレッドは意識を洋一に併せた。彼と洋一は呪いを通じてつながっている。
「どうやら本当らしいな。呪いを利用しおったか」
「やつもある程度の修行を積んでいる。創造の力――を身に付けていると言っておこうか。が、伝説の書さえ奪えばあの小僧にはなにも出来ん。しかもだ」
とウィンディゴは言葉を切る。
「エクスカリバーを手に入れればお前は堂々と王権を主張できる。聖剣の力はお主も知っていよう。問題は銃士の大半が使えなくなったことだ。真昼に動ける銃士は千名もおるまい。いくら不死身の貴様でも、大軍を一人で相手には出来まい。死なずとも勝てなくては意味がない。やつらは死兵が昼間は使えんことを知っている。そこで提案だ――」
とウィンディゴは自分の考えをモルドレッドに伝えた。聞く内にモルドレッドの目玉は大きくなった。
「そんなことが可能なのか?」
「俺が牧村とおなじ創造の力を有していることは知っていよう」と鼻で笑い、「この世界ではお主の影でしかないがな」
忌々しいことだ、とウィンディゴは自嘲した。
「実のところ、俺が欲しがっているのは、伝説の書よりも実体を持つあの小僧の肉体よ。二つを手に入れるためにもお前の力がいる」
「ふん。互いに利用価値があるということか」
「互いを信用していないところもおなじだろう?」
モルドレッドは快活に笑う。
「気に入ったぞ。貴様のいうとおり事を運ぼうではないか。ロクスリーめ、俺のためにわざわざエクスカリバーを運んでくるとはまぬけな……」
モルドレッドがふりむいたとき、すでにウィンディゴの姿はなかった。
「もう消えおったか。せわしいやつだ。が、アヴァロンに向かったのは、牧村という小僧だと言ったな……」
○ 2
「ロビン、なにも見えないよ!」
「落ち着け、洋一」とロビンが言った。「こうとあっては、身をあずけるより他はあるまい」
「そんなのいやだ」
洋一は必死にオールを動かした。得体の知れない連中に行く手を決められるのがイヤだったし、真っ白な景色の中にいると気が狂いそうだ。それにすごく寒い。あらゆる角度から風が吹いて、体に当たっている。まるで、誰かが息を吹きかけているみたいだ。洋一はもちろんそれは死人だと思った。呪いに冒された真っ黒な顔で、このままじゃぼくらも死んじゃう、と歯をガチガチ鳴らしてつぶやいたのだった。そして――
「声がする。ロビン、誰かいるよ」
ロビンはもう答えない。死の呪いが深くなり、意識が混濁しているようだ。洋一の恐怖が深くなるにつれて、それらの声は高まってきた。死者の声だった。
「ロビン、ロビン、起きてよ」
洋一は悲鳴を上げてオールを落とした。オールの先が、なにかに当たったからだ。洋一はおどおどしながら、オールを置いた。ロビン、絶対なにかいるよ……。
だが、ロビンに行動させるのは無理だ。洋一はおっかなびっくり舟の縁に手を突いて、中腰になり水面をのぞく。洋一はギャア! と自分でもだしたことがないような野太い声を上げて尻餅をついた。刀がぐらりと傾いて船底にガラガラと転がった。腐りきった死体がオールにしがみついている。
「ロ、ロビン……」
洋一は腕を伸ばして揺すったが、ロビンはもう完全に気絶してしまっている。洋一は驚いた。ロビンの呪いが深くなって、顔まで覆っていたからだ。それは彼もだ。右腕は闇に覆われて素肌の部分が残っていない。右半身には感覚すらなかった。立ち上がろうとすると、足がこんにゃくのようにゆるんで、船底に倒れてしまった。洋一は懐を抱えて、
「くそ、伝説の書をとるつもりだな。わかってるぞ!」
洋一は夢中で立ち上がると、オールを金具から抜きとった。立ち上がり高い位置から川を見おろしてみると、驚いたことに死体は魚並みに大勢で、ボートをとり囲んでしまっている。洋一は無我夢中で群がる頭をめがけて突きをくりだした。巨大なオールは重かった。洋一は振り回されながらも、体全体でオールを操り、酔っぱらいのように踊り狂った。その死体は水の中にいたから、すっかりふやけて腐っている。オールが当たるたびに、肉がずるむけになった。だから、洋一の視力が極端に落ちていたのは幸いだったのだ。けれど、体力も極端に落ちていて、筋肉もこわばり、体がうまく動かない。全身のあちこちに開いた亀裂が動きの邪魔をしている。それに動けば動くほど呪いが深くなるみたいだ! オールは鉄のように重くなり、死者を押しのけられなくなった。
「だ、だめだ、来るな」
洋一はオールを捨てて本をつかむ。ボートの縁を皮膚のない指がつかむ。洋一は伝説の書で夢中で叩いた。死体の肉がびちゃびちゃと飛び散り、骨がむきだしとなったが、夢中で打った。そのうちボートをつかむ手は退いていったが、その作業は彼にとって多大な負担となってしまった。喘息にかかったみたいに胸の中心が熱くなる、痛みをともなう咳が出た。死の亀裂が猛威をふるって、内臓まで喰らいにかかっているのだ。それでこう考えた。アヴァロンには本物の死体しか行けないのかもしれない。
伝説の書のやつ、きっとまたぼくを裏切ったんだ……。
洋一が声を上げて泣くと、その声に腹を立てたみたいに猛烈な風がまともに吹き付けてきた。洋一はびっくりして、涙も声も引きこんでしまった。
洋一はロビンのそばに身を屈めた。右腕をかばうように、左腕を下にして横たわると、幼児のように身を丸める。しくしくと泣いて、やがては眠ったのだった。
○ 3
洋一はそうして気絶していたのだが、冷や冷やとした風に目をあけた。彼はロビンの脇に倒れている。
頭上を白い影が舞っている。ひらひらとはためくのは、真っ白な服のようだった。霧の中にうかぶその女は天女めいていたが、その顔はひどく恐ろしく、鬼のような三白眼に裂けた口で、怪鳥の叫びを放っている。
「モーガンルフェイだ……」と洋一は言った。それはアーサー王の異父姉の名だが、なぜか口を突いて出た。あながちまちがいではないかもしれない。彼らはロビンの世界を遠く離れ、本格的にアーサー王の世界へと彷徨いこんでしまったのだから。洋一は自分がウィンディゴの策略にはまったのか、それともこの物語の鍵を解こうとしているのかわからなくなってきた。
ボートの舳先と船尾には真っ黒な人影がいくつもあって、死者の島への相席としゃれこんだものらしかった。洋一はロビンを守るために刀を抜こうとしたが、右腕には骨の残滓すらなくなって醜いゼリーのようにぐにゃりと体側に垂れ下がる。彼は刀と本をむなしく胸に抱きながら、また力尽きて倒れてしまった。
「ぼ、ぼくらはアヴァロンに行くんだ。アヴァロンに……」
視野がぼやけ、視点はいくども回りつづけた。モーガンルフェイはそんな洋一を慈しむようになんどもキスをした。冷たいその口づけをあちこちに受けながら、洋一はふたたび意識を失ったのだった。
○ 4
波の音がする。
それは寄せて、寄せては返し、洋一を眠りの縁から呼び覚ます。ロビンの胸の上で、眠っていたようだ。頭をもたげると、霧は幾分薄れ陽光も射している。ロ、ロビン、と洋一は言った。
「ロビン、波の音がする」
今度も応えまいと思ったが、驚いたことに、ロビンが髪を撫でた。
「ここはどこだ?」
声はか細くとぎれとぎれ。でも意識ははっきりしている(二人ともすっかり体温が下がり、呂律が回っていなかったが)。洋一は幾分勇気づけられ、どうにか片手をつくと身を起こした。ボートの人影はいなくなっている。
「洋一、どこにいる?」
と訊かれた。洋一が下を見ると、驚いたことにロビンは目を開けている。
「ロビン、目が見えないの?」
ロビン・フッドはかすかに首を縦に振る。
「ああ、見えない。そこからなにか見えるか」
洋一は視野を巡らすが、すべてがぼやけて、薄ボンヤリとした陰にしかならない。彼にも視力は残っていなかった。それでも船壁から身を乗りだす。真下に砂浜が見える。波が寄せては返している。ボートはそこに打ち上げられていた。
「ロビン、砂浜だ。島に着いたよ」
洋一はほとんど麻痺してしまった顔をゆがめてふりむいた。そのときまで、ボートの外に誰かが立っていることに気づかなかった。洋一は驚きで体勢を崩し、ボートの壁面に背中を打ち当てた。
「ろ、ロビン」と洋一は言った。そして、船底に転がっていた刀に目をとめ、身を投げだすようにしてつかんだのだった。
牧村洋一は見知らぬ男たちと睨み合った。
「誰かいるのか、洋一」
とロビンが身じろぎする。やはり動けないのだ。
洋一は柄巻きを指に絡めようとしたが、呪いの亀裂は指先にまで及んでいた。刀を取り落とし、うめき声を上げる。このままでは自分もロビンのように寝たきりになるだろう。
無理をするな、洋一、とロビンが言った。真上から声が落ちてくる。
「生者が島に来られるとは驚いたな」
「た、助けて……」と洋一は言った。それは疲れきった弱々しい声だった。「やめろ……」
男たちが身を屈める、彼との距離がすごく近くなる。それでド近眼となった洋一にも男たちの人相がよく見えた。見事な金髪で豪奢なカブトをかぶっている。洋一がみたどのイングランドの騎士たちより立派な姿だ。カブトにはルビーや宝石がちりばめられていて、側面には深紅の羽根がはえている。死人にはとても見えない。
円卓の騎士だ、ロビン、この人たちは円卓の騎士だと洋一は感動にほほを赤らめてロビンに告げたが、もう疲れきって声もでない。洋一は身は倒れるに任せ、また船壁にもたれかかる。
「あなたは円卓の騎士でしょう。ぼくらを助けて……」
譫言のようにつぶやく。男が後ろを向く。なにかを受けとったみたいだ。
「これを食べたまえ」
と男は腕をボートに差し入れる。洋一が目を瞬くと、真っ赤なリンゴが見える。洋一は途端に目眩がした。腹もぐううっと鳴ったけれど、それ以上に全身の細胞がそのアップルを欲しがっていたのだ。
洋一はロビンと目を見交わした。驚くべきものを見た。二人の体を食い尽くし、収まり切ったかと思えた死の呪いが、活火山に変わったみたいに黒煙を吹き出しはじめたからだ。
「いやなら別にかまわんが」
男がリンゴをひっこめようとする。気がつくと、洋一は夢中で手を伸ばしていた。
「ぼ、ぼくは食べる! 食べるよ!」
死の呪いはいまや全身から煙を吹き出し、彼のリンゴをはたき落とそうとする。洋一は夢中でリンゴを抱きしめると、体を折り曲げ死の煙からリンゴをふせぎ、動かない口をいっぱいに広げてかぶりついた。死は怒り、腹を立て、無数の拳固をつくって、顔と言わず体と言わずにぶちはじめた。洋一は青あざをつくりながらも目を閉じてかぶりつづけた。
右手の感覚がもどってきた。骨が生えて、筋肉もちゃんと動くようになっている。気がつくと両手をつかってリンゴをかじっていた。ロビンも騎士たちの手を借りてリンゴを食べている。二人から死の黒煙がズルズルと裂け目にひきこんでいき、その裂け目すらじわじわと小さくなってきた。それにつれて、視力や体の感覚ももどってくる。痛みもだ。洋一はその痛みを喜び、ふたたび活動をはじめた筋肉を使い立ち上がった。呪いがとうとう弱まったのだ。
「驚いたな」
ロビンも自分の力で起き上がった。リンゴの汁を垂らして洋一を見た。
「ロビン、目が見えるんだね」
「ああ。このリンゴのおかげのようだ」
ロビンはあらためて騎士たちに向き直り、
「あなたはランスロットですか?」
と目鼻立ちの整う美形の騎士に尋ねた。
「いかにも、後ろにいるのはトリスタン。こちらはパーシヴァル卿だ」
トリスタンはランスロットよりも大柄で、肩幅の広い戦士然とした騎士の顔立ちだ。頬骨が高く、立派な口ひげを生やしている。一方パーシヴァルと呼ばれた騎士は、先の二人よりもずっと年が若かった。透明感のある金髪をなびかせ、おだやかそうな人だ。
ロビンと洋一はあからさまに喜色を浮かべて顔を見合わせた。とうとうアヴァロンにやってきたのだ。ロビンは本当にエクスカリバーが手に入るかも知れないと思ったし、洋一の感慨はロビンとはまたちがうものだった。洋一はパーシヴァルという名前が聖杯探索に成功した円卓の騎士の名と一致することを知っていた。彼は伝説の人物たちと本当に対面していたのだ。それも自分で書きこんだ文の力によって。
「我々に用があるらしいな」
トリスタンは物憂げに船縁を叩く。
「そのとおり。我々はあなたがたに会いに来たのです」
「だが、君たちは死人でないはずだ」とトリスタンが言った。「なぜ我々を知っている。イングランド人なのか?」
「私はそうだが、この少年はちがう」
「そのようだな」
「あなた方は私を知るまい。我が現在のイングランドも。だが、あなた方はこの名を知っているはずだ。モルド……」
ランスロットは手を挙げてロビンの言葉をさえぎった。
「もういい。続きはアーサー王とともに聞こう」と言った。「二人ともリンゴを食べきった方がいいな。その呪いはこの場所ではすぐに活性化する。リンゴの生命力が君たちにすぐさま作用したように」
「生命力? これは生命なの?」
「そうだ。地上に生まれる前のな」
洋一は驚いてロビンと目を見交わした。
「じゃあ、魂じゃないか! ぼくら魂を食べちゃった」
ランスロットたちは軽快な笑い声を上げた。
「リンゴは魂ではない。魂になる前のエネルギーそのものと言っていい。リンゴの姿をしているだけだ。安心して食べたまえ」
洋一は少しほっとしてリンゴをかじった。不思議なほど甘かった。リンゴの姿をしているだけと言ったが、確かに洋一の望むとおりに味を変えるようだった。甘さはどんどん増していくし、囓ったときの感触も滑らかになっていた。そして、彼が望めば食べた場所もすっかり元通りになるのだった。ロビンと洋一は、アヴァロンのアップルを思うさま食った。
ロビンが立ち上がると、洋一も刀を拾って、本を懐に押しこんだ。ロビンはボートを傾けながら砂地に飛び降りた。呪いはまだ残っていたが、激痛すらなくなっている。洋一が降りようとすると、騎士たちが手を貸してくれた。
「洋一、見てみろ」
とロビンは指し示した。二人の食べているリンゴが島中になっている。
「これがアヴァロンのアップルか」
とロビンは言った。アヴァロンはリンゴの咲き乱れる楽園という、伝説のとおりだ。
五人は花咲き乱れる丘の小道をたどりはじめた。動物があちこちにいて、空には鳥もいる。気候は穏やかで過ごしやすい陽気だった。洋一がのぞめばそのとおりに風が吹いた。なによりも思い通りに体を動かせるのがうれしかった。
丘を登り切った洋一は、「ロビン見て……」と言う。丘を下りきった平地にある大きな木の下に、巨大な円卓がある。円卓には一人の男性が座っており、周囲には数人の騎士たちが従っていた。ロビンが洋一の隣にきて、
「アーサー王か」とつぶやいた。ロビンはふりむいた。「死してあなた方は和解したのですね」
ランスロットは無言で微笑んだ。五人は連れだって丘を下りはじめた。
○ 5
洋一は自分が勘ちがいをしていたのかと思った。アーサー王が死んだとき、彼は老人だったはずだ。それともここでは思い通りに姿を変えられるのかしれない。今のアーサー王は三十代の壮年で、年もロビンとかわらない。栗色の髪は耳に掛からない程度に刈られて、トリスタンとおなじ形の口ひげが威厳を持たせてもいた。兜はかぶらず、円卓に深く身を預け、この奇妙な来訪者たちを出迎えた。
ロビンと洋一は誘われるまま円卓に腰を落ち着けた。円卓の椅子は不思議な材質で、まるで生きているみたいに洋一の体を包みこむ。円卓は様々な意匠で彩られる。そして、洋一が見る度に模様がちがうのだった。
ロビンは語った。今のイングランドの現状、そして、モルドレッド・デスチェインを名乗る男の存在。アーサー王はときおり少し首を頷かせるだけで、口をはさむことは一度もしない。周囲にかしずく円卓の騎士らも王の言葉を待っているようだった。洋一の側にはトリスタンたち三人がいた。
「モルドレッドか。あの男は生きていたのだな」
キング・アーサーは初めて口を開いた。それは少し嗄れて、それでいて洋一が聞いたどんな声より艶やかで深みがあった。
「あやつはいまだエクスカリバーを欲しがっているのだろう。エクスカリバーは王権の証なのだ。それを君は持ち帰るというのかね。あやつを倒すために」
「ご存じのようにモルドレッドは聖杯を使い、ために不死身なのです」とロビンは言った。「アーサー王、そのつるぎなら、あの男を死にいたらしめることができますか」
「我々にはわからない」とアーサーは首を左右に振る。「この中でいまだ死んでおらんのはあの男だけだ。それも我々のしくじりが原因だと言えるがな。だから、ロビン・ロクスリー。イングランドの現英雄よ。お主には我がつるぎと王権を委譲しよう」
「王権を?」ロビンはちらりと洋一を見た。「どういう事です?」
「エクスカリバーは王権を認められた者にしか、触れることができない」
とアーサー王は、円卓にもたせかけていた剣を手にとった。鞘は黄金に輝き、深く彫りこまれた意匠を中心に光り輝くようだった。柄には剣の力を象徴するかのごとく、光芒をはなつ宝石がはめこまれている。どうも、王らのつかうのはただの宝石ではなく、不思議な魔力を持っているようだった。そして、大きな柄の滑り止めにはダイヤモンドが使われているようだ。反対にいる洋一の目にもそれらはキラキラと輝いて見えた。
「では、モルドレッドはその剣を扱うことは出来ないのですね」
「それはわからぬ。すべては剣の決めることだ。それよりもその少年」
とアーサー王は洋一のことを指で差した。洋一はどぎまぎして、自分の指で自分を指した。
「ぼくですか?」
アーサー王はうなずいた。「あの男の呪いが治りきっておらんと見える。こちらに来たまえ」
ロビンは驚いて洋一の右手をつかんだ。掌にはいまだ亀裂が黒々と穴を開けていた。それは小さな十字星のようだったが、まちがいなく死の呪いだった。洋一は顔を上げた。
「リンゴを食べたのに、消えてない」
ランスロットが背を押して、洋一はとまどいながらも円卓に沿ってまわった。ロビンが後についてきた。アーサー王は無言で右手をさしだす。洋一には意味がわからなかったが、そうっと自分の手をさしだし、アーサー王の暖かくて分厚い掌に指を沿わした。アーサー王はされるがままだった。やがて掌同士が寄り添うようになると、優しく洋一の手を握りこんだ。
洋一はよろめいて、左手に持っていた刀を取り落とした。円卓の騎士たちがつるぎに手をかける。アーサー王の握る手の隙間からは輝くような死の黒煙が猛然たる勢いで吹き出してきたからだ。洋一はウィンディゴかと思った。そうではなかった。
洋一は、黒風の勢いに負けよろめいた。ロビンがその背を支えた。
「この少年にとりついていたか、モルドレッド・デスチェイン!」
アーサー王が始めて怒鳴った。瞬間に、洋一はすべてを理解した。死の呪いをうつしたあの時だ。洋一は伝説の書を通じて暗黒の王子と深く深くつながった、ロビンよりもずっと強く。死の呪いを逆用してあの男を殺害しようとさえしたのだ。モルドレッドの一部はその呪いをさらに逆用して、洋一の体に住み着いたのだ。
「アーサー!」
邪悪な黒風はとぎれずに吹きつづけ、その黒い幕の中に裂け目ができ、両の目と口になった。聞こえてくるのはまちがいなくモルドレッドの声だった。
モルドレッドはゲタゲタと笑い声を上げた。
「ちっぽけな島だ。お前の領土はこんなものか。円卓の馬鹿共を連れて御隠遁かね。俺はまだ生者の国にいるぞ。お前のいた島の真の王となっているとも」
「お前は王ではない!」とロビンは言った。「イングランドの人々が貴様などを認めるものか! 俺がおらずともちびのジョンやガムウェルたちが残っていることを忘れるな!」
モルドレッドはさらに高く哄笑を上げた。「あんな普通の人間どもになにができる。犬のように吠えるとでもいうのか。みじめなのは貴様もおなじだロクスリー! さあ、俺様にエクスカリバーを献上しろ!」
「エクスカリバーは持ち帰る。だが、貴様のためなどではない」
ロビンの声は小さなものだった。だが、怒りからくる闘争心に紛れもなく満ちていた。
「いいだろう、ロクスリー、呪われし小僧よ! 俺は現世にて貴様らの帰りを待つ! だが、いつまでもこの世の人々が貴様を支持すると思うな! 貴様らがたった一人でも立つことができるかどうかこの俺が見届けてやる!」
「俺は勝つまでやめない! それは貴様が現世を立ち去るまでだ!」
モルドレッドは悲鳴を上げて身をくねらせた。トリスタンが手にした弓でモルドレッドの眉間を射貫いたのだ。モルドレッドはその矢に引きずられるようにしてグルリと回り、矢と共に空へと吸いこまれた。風は途絶え、洋一の身を震わし腕の腱をこわばらせていた圧力も消えた。
洋一は乱れた息を整えるように胸に手を当て、アーサー王の掌からそっと右手を引き抜いた。掌を見た。じっとりと汗をかいているが、亀裂はもう無くなっている。呪いの痕が古い傷跡のように残っているだけだった。
ロビンはモルドレッドの消えた虚空を見つめていった。
「アーサー王。失礼を承知でもう一度お聞きしたい。聖杯の力を得、五百の魂を縛るあの男を、聖剣の力のみで殺めることができるのでしょうか?」
アーサー王は胸前に剣を掲げる。
「あの男を殺す武器はエクスカリバーをおいて他にない。これでやつが死なんのなら、お主が死者の島に舞い戻るまでだ」
アーサー王もまた立った。円卓の騎士たちはわずかに退き、跪いた。
「ハンチンドン伯(ロビンのこと)、お主に我が不義理の息子を討つよう頼みたい。我らが長き因縁、五百年の年月死ねなかったあの者に最後の時を与えるよう、今ここで頼みたい。死者の島にいる我らにはその任を果たせぬ故」
アーサー王の眼光は強く、その表情は一糸も乱れていなかったが、ロビンには奇妙に悲しげに見えた。
「我が王は死に申した。が、あなたは彼に劣らず偉大な王だ。このロビン、イングランドの人民に成り代わりお受けいたす」
ロビンはわずか会釈しつつ、両腕を伸ばし聖剣エクスカリバーを手にとった。ここにアーサー王の王位は委譲され、ロビンは聖剣エクスカリバーを身に纏うことを許されたのだった。
○ 6
円卓の騎士たちはアーサー王を囲うようにして、ロビンと洋一を送りだした。この珍客が立ち去ることを惜しんだのだった。トリスタンは自慢の弓をロビンに貸し与えた。
モルドレッドが洋一に取り憑いていたということは、こちらの動きはすべてわかっていたということだ。ロビンと洋一は急いでボートに乗りこんだ。
「ここから先は我らの領分ではない」
「十分です。世話になりました。必ず吉報をお届けします。が、死んだとしてもここに来られるわけではないのですね」
アーサー王はうなずいた。アヴァロンは死者の世界の一領域にすぎないのだ。
「我々は君たちが来ることを望んでいる」
アーサー王が言うと、円卓の騎士たちが笑い声を上げた。
「君の持つエクスカリバーの鞘には傷を癒す不思議な力がある。私は鞘を奪われることでモルドレッドに敗れた。必ず鞘を失わぬようにしろ」
「必ず」
とロビンは言った。円卓の騎士たちがロビンを囲み、手荒く抱擁をした。その間に、アーサー王は洋一の前で屈みこんだ。
「その刀もすばらしいが、お主は不思議な本を持っている。その力がモルドレッドと戦うには必要となるはずだ。ロビンの補佐を頼んだぞ」
洋一は頬を紅潮させてうなずいた。伝説の王にこんなお願いをされるとは、まったくすごかった。
「あなたと会えなくなるのは寂しいです」
「じきに会えるさ」とアーサーは笑った。
騎士たちがボートを押し、船尾が砂浜を離れるとボートは瞬く間に霧の中に入っていった。洋一とロビンを乗せたボートは死者の川を下り、アヴァロンを離れていく。洋一は背後を振り返ったが、アヴァロンの姿はすでに霧に飲まれた後だった。
「アーサー王がじきに会えると言ったけど、あれはどういう意味かな」
「いずれ人は死ぬということさ。そう案ずるな」
霧はどんどん濃くなり、視界は真っ白なベールに覆われた。
洋一とロビン・フッドはこうしてアヴァロン島を後にした。もちろん洋一の長い冒険譚では様々な王に会うことになるのだけれど、それはまた別のお話。別の機会に物語ることにしよう。
◆ 第三章 ロビン一味、最後の戦い
□ その一 イングランドのロビン、呪われた都に討ち入ること
○ 1
太助とジョンは毎日河原に出て洋一たちの迎えに出ていた。二人が旅立ってもう一週間が過ぎていた。異変が起きたのは正午過ぎだった。あのときとおなじ濃い霧が川面を中心に張りだしたからだ。
ロビンの仲間たちがすぐさま外に飛び出してきた。太助とジョンは川上を目指して走った。
「太助、ジョン!」
洋一は声を聞きつけてボートから身を乗りだした。霧は洋一の周りではどんどん薄まっている。霧の向こうに透けて見えるのは懐かしいイングランドの景色だった。川に沿って走る土手、道の先には彼らが短い休息をとった小屋がある。そこで待つのは懐かしい仲間たちだ。川に沿って懸命に走る太助の元気な姿だった。
○ 2
ロビンはすぐさま行動を起こさねばならなかった。まずモルドレッドはロビンの首に懸賞金をかけ、彼の持つエクスカリバーを差しだすように命じている。この間にロンドンの周辺都市はモルドレッドの勢力下に置かれている。対して、タック坊主らが集めることのできた諸侯は、ウィリアム・ダンスター、トマス・ボーフォート・ウォリック、ロバート・ウォレスの三名だけである。残った諸侯は、モルドレッドに恐れをなしたか、日和見を決めこんだようだった。
ロビン・フッドは夜を徹してロンドンに向かい、二日後の明け方には、市街を見下ろす丘に到達した。街道につづくすべての大門は固く扉を閉じている。城壁にはモルドレッドの銃士たちの姿がわずかに見えた。火事が起こっているのか、市街からは煙が幾本も立ち上っている。風とともに、死臭がおよび諸侯たちは顔をしかめた。
「ロビン、一万名でロンドンを奪うのは無理だ」とアランが言った。「こっちは死兵じゃないんだぞ」
「そこが付け目だ」ロビンはロンドンを指し示し、「あの城壁の広さをみろ。今は陛下の軍もいない。誰が守るというのだ」
みなはあっと気がついた。城門の堅固さに気をとられて敵の少なさを失念していたのだ。
アーサー・ア・ブランドはうなずいた。「銃士は化け物になると、知能がなくなるようだった。城門にいるのは生きている銃士だけだ。確かにあの数では門を固めることさえ容易じゃない」
「となると、問題は中に入った後だぞ」とウィル・ガムウェル。「化け物どもは光をいやがるから、屋内に隠れていると思う。しらみつぶしに狙うのか」
「ロンドンで生き残った人はいかほどいると思う?」
ジョンが訊くと、ロビンは無言でロンドンを見下ろした。王都は深閑として、声も立てない。
○ 3
ロビンは天幕に四人の貴族を招き入れると、円卓を囲み協議をはじめた。ウィリアム・ダンスターは白髪の老人だが、息子を十字軍に出している(パレスチナで戦死している)。ロビンともわずかに面識があった。トマス・ボーフォート・ウォリックと、ロバート・ウォレスはもっとも若く、ともに三十代の壮年だ。二人は領地の守護は息子たちに任せて駆けつけている。ギルバートは家格こそ低いがロビンの隣にいた。みなロビンが膝に立てかけるエクスカリバーにチラチラと目をやっている。モルドレッドが懸賞金を賭けているだけに気になるのだ。
口火を切ったのは年長のウィリアムであった。
「我々が布陣しているのに、モルドレッド側にはなんの動きもない。どういうことだ」
「私の聞いた話では、敵側の軍隊は一万に満たないそうだ」と、トマス・ボーフォート・ウォリックが言った。「あの数でロンドンを落としたのだ。野戦を行う兵力がないのではないか」
「それは妙だ。やつの軍隊は各地に散らばって戦っているではないか」ロバート・ウォレスが言った。「やつらは新兵器をつかうというがその威力はいかほどなのだ。ギルバート卿。あなたはフランスで戦ったはずだが」
ギルバートはわずかに顔を背けた。そんなことは問題ではないと思った。が、沈黙を守り、ロビンに目を向けた。自分にはモルドレッドの銃士隊を打ち破るどんな策もないが、ロビン・フッドには作戦があるらしい。
ロビンは一同の視線を受けると、やや厳しい顔つきで切りだした。
ロビンはパレスチナとフランスで戦った銃士隊について説明した。昼間は並の人間とおなじように死ぬが、夜は無敵の兵として蘇ることも含めて話した。
ウィリアムらイングランドの貴族はその話をにわかに信じることができないようだった。
「馬鹿なことを。死体が動きだすなど本気で言っているのか」
「だが、そのような兵隊をあの男が持っているならロンドンを落としたことも納得がいく」ロバート卿が言い、ロビンに向かってうなずいた。「私はその死兵とやらをじかに見たことがある。ロクスリーの言うとおり、あれは人ではない」
「問題は彼らが人間離れした身体能力を発揮することです」とギルバートがはじめて口を開いた。「しかも、斬っても傷がふさがってしまう。サラディンもついに打ち破ることはできなかった」
なんと。あのサラディンが。
天幕の外でもざわめきが広がった。サラディンの強さは音に聞こえている。ロビンが言った。
「私の部下が実際に死兵と戦っています。やつらは首を落とせば死ぬ」
「あなたの部下は死兵を倒したのか?」とロバートが食いついた。
ロビンはうなずき、「サラディンがパレスチナで実証したことです。首を落とせば彼らも死ぬ」
「ロンドンから逃げだした兵らから、化け物と戦ったという話は聞いていたが、死人が動きだすなどと……」
「パレスチナでは我々もサラディン軍の虚報とみて信じていませんでした」
ギルバートが言った。ロビンは少し声を大きくした。
「モルドレッドの死兵は今現在王都にいる。兵に化け物と出くわしたときは、首を落とすよう徹底してもらいたいのです。なんの知識もなく戦っては我々の兵は潰走することになる」
トマス・ボーフォートが立ち上がった。「私は銃士と戦うことに賛同したが、化け物と戦うために貴重な兵を連れてきたわけではないぞ」
「彼らは光をいやがって隠れている。戦うとしたら昼間の今しかない」
「私の兵は化け物と戦うためにあるのではない!」
ウィリアムが言った。「彼らはあなたをロンドンに呼んでいるのだろう。罠を張り巡らせていると思うが……」
「行かない限り、彼らはイングランド中の街々を襲うだろう」とロビンは言いかえした。「それともあなたはモルドレッドに屈するおつもりか。彼の言うとおり、正統な王権を認め、国王に戴くというのか。数万の市民を虐殺した男のなにが国王だ!」
「ノッティンガムも銃士たちに襲われたのです。市民の大半が難民となってしまった」ギルバートが言った。「市民はみな怯えている。私は後手をとるべきではないと思う」
長い沈黙の後、ウィリアム・ダンスターは身を乗りだした。
「それで」と老人は言った。「そんなやつらとどう戦う」
ロビンの作戦はこうだった。東門に戦力を集中させ、城門を奪取する。王都に進入した後は、部隊を三つに分割して進む。生存者を救い出し、ロンドンに火を放つ。
すでに大量の油を乗せた大八車が大量に用意されている。城門にそい王都を囲うように火を放たせる手はずである。が、中央道には市民の脱出路とするために火を放たないことになった。
問題はモルドレッドの居場所である。
「銃士隊もすべて死んだはずがない。城門にも姿は見えるが、こちらと決戦するつもりなら、手元に置いておくはずだ。後は夜になるのを待てばいい。が、やつは広い王都を守るだけの兵力がない」
「籠城戦か?」ウィリアムが訊いた。「王都の防壁は捨てて、内部の城にこもるつもりだというのだな。だが、どこだ」
トマス卿が言った。「防備の固いのはチェスター城だ。大きくはないが堀もある」
「夜までに落とせるか」とウィリアム。「おとなしくやられる男ではないはずだ。罠を張り巡らしているだろうし、そこまで行き着けるかどうかもわからんのだぞ」
「決着がつかなければ、いったんは王都を出るべきでしょう」とロビンは言った。「夜間に彼らと戦うのは得策ではない。焼き討ちを行えば、モルドレッド側にも損害はでる。死兵は可能な限り殺しておくに限るのです」
貴族たちは王都に火を放つことになかなか賛成しなかった。ロビンは粘り強く説得した。
「死兵とまともにやりあうのはかしこいやり方とはいえない。それに昼間は屋内に潜んでいる。すべての家屋を虱潰しに戦うことはできない」
街を焼き払うのはパレスチナでサラディンが実際にとった戦法でもある。ロンドンは灰燼に帰すが、死兵を殺すことはできる。
「だからと言って、我々の手で王都に火を放つなど」ウィリアムは耳を疑った。「ばかな。そんな真似ができるか」
貴族たちは王都への放火に抵抗を示した。第一これを命じているのは国王ではない。草莽の義賊であったロビン・フッドただ一人である。
「ヘンリー王子にお伺いをたてるべきではないか」とウィリアム。「戴冠をしてないだけで、今やイングランドの王はヘンリー王子ではないか」
「ジョン王が死んだと決まったわけではあるまい」とトマス。
「そこがやっかいだ」とロバート。「そもそもヘンリー王子のもとにはろくな兵がいないし、ジョン王を救うための招集に応ずる貴族などいるはずがない」
「ロンドンを焼き尽くして、その後の市民生活を誰が保証するのだ」ウィリアムが言った。
ロビンは背後のロンドンをかえりみた。
「ロンドンからの難民が少なすぎる。あの男は門を閉ざし出さないつもりだ。王都に生きている者はほとんどいないかもしれない」
「なぜだ?」とウィリアム。
「モルドレッドは王になりたいのです。だが、彼の誤算は王都を奪うために銃士隊をつかったことだ。ロンドンの人々は彼の兵士が一度死んで化け物に変わり虐殺するところを目撃しているはずだ。そんな話が出回って、誰が彼を信奉するというのか」
「すべて隠蔽するつもりなのか……」
「ばかな、いつまでも隠しおおせるものか。ロンドンの市民は何万人もいるのだぞ」
「だからこそです。生きている者がいるうちに救うんだ」とロビンは言った。「王都をその目で見られるがよい。我々はパレスチナの戦場でこの目にしてきたのです。ロンドンでは八つ裂きにされた肉塊が放置されたままだと聞く。もはや屍殺場でしかないのです」
貴族たちは黙りこんだ。ロビンのまわりでは草がはためく音しかしなかった。長い沈黙の後、ウィリアムが痩せた首を振った。
「やはり賛成できん。王都を今度は火葬場にするつもりか」
「死人になった銃士隊を一掃する手は他にない。夜になればやつらには敵わない」
ロバートが訊いた。「ロクスリー、その作戦でモルドレッドに勝てるか」
「私はやつに一度負けた。二度負けるつもりはない。それに――」とロビンはエクスカリバーをとった。「聖剣はやつを討ち果たすことを望んでいる」
この言葉にロバートは椅子を蹴立てて立ち上がる。
「よかろう。私はロビンに手を貸す。市内にもぐりこむことは可能。敵兵は少ない。死兵らが屋外に出てこられない昼間なら、勝てる見こみはある」
ロビンは首をめぐらした。天幕の外にちびのジョンらの姿が見える。ロビンには貴族たちがひっそりと静まりかえり、互いの出方を窺っているのが見て取れた。このような不気味な話をするには、今日はよく晴れている。現実感がないのだろう。
「ロクスリー」とウィリアム・ダンスターは痩せこけた鼻柱をもみ上げた。「リチャード王はやつの策略にかかり死んだと申すか」
ロビンは無言。ただうなずいた。
「私の息子は国王に従っていた。仇はモルドレッドということになる」ウィリアムは、痩せた体を力なく立てた。「私もロクスリー卿に助太刀いたす。心ある者は戦の用意をなされるがよい」
ウィリアムは配下を引き連れ立ち去った。残る卿らも無言で天幕を去り、兵の元に向かった。
○ 4
ロビンは騎上、将士たちを鼓舞してまわった。彼の目前には歩兵射手が居並び、その後ろに長大な槍をもった軽騎兵がいた。ロビンの呼びかけに応じて集まったヨーマンらも三千名ばかり。総数は一万を超すが、史上この数でロンドンほどの大都市を攻めた例はないだろう。ここで敗北すれば日和見の諸侯はモルドレッドにつき、王太子の勢力は大陸まで駆逐されるはずである。
ロビンが馬上で身を揺らしていると、春先の風がふわふわと漂ってきた。その風は春心地がしたが、硝煙と死の臭いがふんだんに混じっている。彼は戦場にいるのだった。
ロビンは長らく戦いの人生に身を置いてきた。そんな彼を支えたのは、ちびのジョンやアラン・ア・デイルたちである。彼は自分がなんども敗北したのを知っている。だというのに長い盟友となったヨーマンらや目前に居並ぶ将士たちの期待に満ちた目線はどうしたことだろう? ロビンは遠くを見やる目付きをして、この苦闘をすらありがたいと思った。ジョンやスタートリーたちの助力がただひとえにありがたかった。その期待に応えるために身を捨てようと彼は思った。
ロビンの背後には、ジョンやアランといった長年彼に付き従ったヨーマンたちがいて、彼の言葉を拝聴している。雑多な武器を持ち寄りロビンの元に馳せ参じた歩兵や弓隊の人々もおなじだった。人々のざわめきや角笛の音がロビンの身体を打った。
ロビンは馬を左右に走らせ、大声を張り上げた。
「今日我が元に集った勇敢な男たちよ! 例え敵が化け物だろうと、我々は負けない!」
ロビンが聖剣を引き抜くと、真昼だというのにその輝きは遠目にも明らかだった。エクスカリバーの放つ光芒は、伝説に聞くアーサーのみわざとおなじく、騎士たちの心を奮い立たせた。
「エクスカリバーは真の王を示しはしない! ただイングランドの国土と人民を守るためにある! 今日聖剣を手にする私が諸君に誓おう! イングランドのために死力を尽くすと! 身が朽ちても祖国を守り抜くのだ! 先祖のために、ともに生きる同胞のために! 我らの未来の子らのために! 君たちは中で異様な光景を目にするかも知れない! そのことに臆するな! 我らが敵を打ち払うのだ! ロンドン市民が無益に殺害されたのなら、その魂を天へと返すのは我らの役目だ! 敵は死者の肉体に辱めを与えている!」と言った。「私にはあそこに横たわる者たちが我らの父母兄弟、娘に見える! なぜならば、彼らが我らと血を共にする同胞だからだ! 私は彼らを道に迷わせぬために火を放とう! そのことに責めを負うなら、このロビンが引き受けよう! 我々は死兵を倒すためにロンドンを焼き討つ!」
この言葉に、兵たちは動揺した。話に聞かされてはいたが、いよいよその時が来たのだ。兵たちはざわめかず、ロビンの言葉に耳を傾けている。馬上のロビンには彼らの覚悟が固まっていくのが分かった。
「あそこには異様な化け物がいる! 諸君も噂に聞いたことだろう! よいか、屋内に飛びこむことはまかり成らん! なれど、万一異形の者に出くわしたとき、その時は必ずやつらの首を落とせ! イングランドに化け物はいらぬ! 今ここに駆けつけた勇敢なる諸君、私は君たちに問いたい! イングランドは誰のものか! イングランドは王侯貴族のものでも、ただ生き物を殺害し、その肉を無用に喰らう化け物のためにあるのでもない! イングランドは我々一人一人のもの! ここに暮らす動植物のものだ! なれど、動植物は物を言わぬ、我らが敵と戦わぬ! ならば我々がイングランドを守るのだ! 今日イングランドを救うのは、他の何者でもなく、ここにいる我々だ! イングランドに平和を! 民に自由を!」
歓声は瞬々大きくなり、大地を轟かす雷鳴となった。馬はその声に打たれたように歩足をゆるめる。ロビンはその声に応えるように腕を広げ、拳を握り、兵たちに負けじと声を張った。
「なかんずく今日はリチャード陛下の弔い合戦である! なぜならば、獅子心王を奸計に貶め、死に至らしめたのは、王都に居座るモルドレッドなる兇漢の輩! 私は彼が我が同胞とは認めぬ! 我らの上に立つのはあの男では断じてない! 彼が我が領域を侵し、我が先祖を愚弄し、我が同胞を辱めるのならば、私は彼を討ち果たそう!」
賛同の声が立ち、兵らはそれぞれの武具を掲げた。
「私に必要なのは、諸君らの手助けである! 心に臆病者が兆したときは、祖父母のためにその者を打ち倒せ!」
ロビンはジョンらのもとで馬を降りると、王都ロンドンに向き直る。ロビンがエクスカリバーを掲げると、兵士たちの熱狂は最高潮にたっした。イングランドに生き残るただ一人の英雄ロビン・フッドは、王都への攻撃を命じたのだった。
○ 5
王都の城壁に長大な梯子が幾本も立てかかり、それに倍する数の縄が投じられた。決死の兵士たちが矢弾にさらされながらも、それらに取り付く。銃士たちの抵抗は激しいものだったが、数百名ではとても防ぎきれない。破城槌で大門を攻められるとそちらに兵のを割かれた。ロビン軍は城壁上の通路に次々と躍りこみ銃士たちを討ち取っていく。
軍勢は内側から門を開こうと、城壁内部に進入した。階段を下り通路に至った騎士たちは、遠雷のようなうなり声を聞いた。まるで彼らの到来を喜ぶように喉を鳴らしている。それに明かりがない。真っ暗だった。銃士たちの反撃もない。攻撃隊の隊長は背後の仲間に手を振って、
「死兵がいるぞ。松明を用意しろ」
城壁の窓を突き破り、兵士たちが落ちてくる。咆哮がロビンの元まで届いてきた。騎士たちは大量の槍を持ちこんで悪霊を串刺しにしようとしたが、化け物はなかなか死なない。
「ロビン、城壁内を抜くのは無理だ」とアランが言った。
「縄を逆側にかけて降りるようにいえ。内部の兵は撤退させろ」
ロビンの目線は自然ギルバートの攻める城門に集中した。
ロンドンの城門はモルドレッド自身の攻撃で疲弊していたが、それでも破城槌の部隊は手こずっていた。ロビンの隣にきたウィリアムが、
「夕まぐれでも死兵は動けるか?」
「やつ等が恐れるのは真昼の光です。夕刻もしくは暗がりなら力を発揮してきます。こちらの動ける時間は限られている」
「もし昼の内に決着が付かなければ撤退すべきと思うか?」
ロビンは不敵にうなずいた。「この数で化け物共を相手にするのは自殺行為ですよ」
「しかし、君の部下が死兵を倒したと聞いたが?」
「やつ等は集団になったときが厄介だ。群れで襲われたら、とても首を刈ることはできんでしょう。だから、サラディンは自国の都市に火を放ったのです。兵を殺さぬためには焼き殺す以外に手はない」
「では火を放つだけで兵をいれなければいいのでは?」
とトマス・ボーフォート・ウォリックが言った。
「それをするには王都はあまりにも広すぎる。それに外に出たところで奴等は自由に動ける。兵に恐怖心が生まれる前に初戦でやつらを叩くべきだ」
「決戦は避けられないと見るべきか」
とウィリアムはため息をついた。
そうしている間にも、兵士たちは城門の内側にたどり着いていた。彼らは銃士隊の銃撃を受けながらも、巨大な巻き上げ機を懸命に降ろしていく。モルドレッド軍の銃撃も激しかった。鎖に銃弾がはじけ激しい火花を散らしている。ロビン側はこのため、巻き上げ機に近づくのもままならない。後続の弓兵が隊伍を組み、街側にいる銃士に向けて応戦を始めると、ようやく作業にも人心地がついた。
○ 6
大門が地に降ろされると、ロビンの軍勢は一つの大きな矢のようになって雪崩れこんだ。トマスとロバートの軍勢が左右に分かれ、ロビンはウィリアム・ダンスターと共に中央道に乗りこんだ。ロビン・フッドは異様な光景に息を飲んだ。「なんてことだ……」ノッティンガムなど比較にならない、あまりにも悲惨な情景だ。王都の壁面や街路を、どす黒いペイントが覆っている。それは元は人の体内にあった血液が、なにかの拍子に散らかったものだった。辺りには千切れた肉塊が転がり、臓腑をまき散らしている。小路は足の踏み場もなく、腐った肉だらけとなっている。犬や家畜すら死に絶えていない。手足生首が無造作に転がり、そのうちのいくつかにはハッキリと食われた痕跡があった。戦闘で死んだ兵士も多くいたが、そのほとんどは、王都から脱出しようとし、果たせず死んだ市民たちだった。
最初のうち、ロビンが感じたのは激しい憎しみだった。けれど、歩くたびにその怒りは足下から抜け落ちていき、抜け落ちた後から悲しみが支配するようになっていった。むき出しの骨、むき出しの脳に蠅が真っ黒にたかり、道路は腐った血痕で真っ黒だ。余りの臭気に人々はむせこみ、おおかたの者が糧食を吐いてしまった。隣に立つジョンがはっと息を飲んで目を伏せる。ロビンがその方角を見ると、へし折られた街路樹に人の腸が垂れ下がっていた。強烈な力に引き裂かれたとしか思えない遺体の数々に、ロビンはパレスチナの地獄が、いよいよイングランドに及んだのだと自覚した。自分たちはその地獄にもどってきた。
ロビンはロンドンを進みながら遺体に手を合わせ、十字を切った。燃え草となるものには油をかけてまわらせた。街路には家財道具や壊れた家の残骸も散らばっている。火を放てばあっという間に広がるだろう。死んだ人たちを手向けるのには、炎をつかうしかなかったのだ。
ロビンが感じたのは、これはひどくなっている、ということだった。モルドレッドの死兵に壊滅させられた都市は数多あるが、ロンドンの規模はそれらの比ではない。これほどの規模の攻撃を仕掛けたのはやつ自身もかつてないことのはずだった。いくらモルドレッドでも、これだけの数の死兵を統率できるのか? ミュンヒハウゼン男爵は、死兵とはモルドレッドが銃士らにまったく異なる悪しき魂を埋めこんだから起こるのではないかと推測していたが、もしそのとおりならその魂はまったく悪辣きわまっている。ロビンの心を埋め尽くした悲しみは、彼をこれまで突き動かしてきた闘争心とはほど遠かった。女こどもも老人も、みんな余さずに死んでいる。結局自分は王都を解放しに来たのでも誰かを救いに来たのでもなかったのだ。新たな死を生み出しに来たのである。
ロビンに古くから付き従う人々は、彼を守るように、あるいは彼を頼るようにしてロビンの周りに集まった。粉屋のマッチは目玉を踏んで悲鳴を上げ、赤子の死体に十字をきり、背後の死体が生き返るのではないかとふりむいた。大方の者がおなじような気持ちでいた。ロビンの軍隊は戦う前からすっかり怖じ気づいていた。
アーサー王が未来の我々になにを託したのかロビンは分からなくなった。だが、道路の中央に転がるこどもの完全な遺体を見たとき、それが牧村洋一の姿と重なったとき、ロビンの決意は急速に固まったのだった。
「アーサー王はこんなことのために、エクスカリバーを託したのではない!」
ロビンは立ち止まると、部下たちを叱りつけた。
「目を背けるな、ここでなにがあったかようく見ろ!」
みんなは今こそロビンのいった言葉を理解した。ロンドン市民が辱めを受けた。そのとおりだ! 王都に火を放ち、亡くなった人たちを火葬する。そうすべきではないか! このような惨い殺し方をするべきではないし、また受ける謂われもないとみな思った。ロンドンを焼き撃つことに異を唱える者はもはやいなかった。死者を悼む気持ちがあるならばそうすべきだと考えたのだ。
「これが我らの敵のなしたことだ! これを許してはならぬ! 目の前の光景に臆するな! 二度とこのような事が起こらぬように戦うんだ! イングランドを救うのは、今ここにいる俺たちだ!」
ロビンは予定通り、生存者の捜索と焼き討ちのための部隊を市内に散開させた。ジョンがロビンの耳にささやいた。
「これでは生きている者がいるはずがない。探すだけ無駄だ」
「よく見るんだ!」とロビンは叱った。「壊れていない家、戸締まりが確保された家を中心に声をかけて回れ。市民が立てこもっている可能性が高い」
□ その二 イングランド、暗闇に遭うお話
○ 1
ミドルとアーサー・ア・ブランドは、騎士たちと協力して被災者を探して駆けずりまわった。アーサーは三百人の騎士を率いている。そのうち声のいい者を数十人選んで、王都に喧伝させた。
「ロビン・フッドが帰ってきた! シャーウッドのロビンが王都を解放したぞ! 生きている者は家を出ろ! 東門を目指せ!」
彼らは無事な家屋を調べ、地下のある家を慎重に探っていった。ロビンの予想通り、じっと息を潜めていた者たちが徐々に現れた。アーサーは生存者の様子に、喜ぶよりもショックを受けた。彼らは魂を消されたこどものように震えている。逃げることも叶わず、外に出ることもできず、闇を恐れてじっと隠れていたのだった。怯えて半狂乱になっている者が多かった。食う物もなく、排便にも事欠き、腐臭の漂う中息すら潜め、ただ救出のときを待った姿に、アーサーは心を痛めた。
あちこちで遺体の火葬がはじまった。最初は抵抗のあった騎士たちも、遺体が火に包まれ屍肉が見えなくなると、積極的に火をつけて回るようになった。みなあのような憐れな残骸をいつまでも見ていたくなかったのだ。
アーサーたちは獅子心王の紋章を緋色に染めた旗を掲げている。家を固く閉ざし、地下に隠れていた者たちも、声に誘われ這い出てきた。この二十日間、飲まず食わずだ。思考力すら尽き果てていた。彼らは、詩人の声に聞き、自ら噂にのぼらしめた懐かしい名を口にした。
ロビン・フッドが帰ってきた。
ロビンがまだ無法者だったころ、弓術大会で見事優勝を飾ったことを覚えていた者も多くいた。その名が人々の心から消えかかっていたとはいえ、生死の権利すら奪われた市民にとっては、希望のもたらす救いの光だった。人々はその一筋の光にすがりつくために、往路に進み出たのだ。
「声を上げろ! ロンドン市民はあの化け物と二十日間も付き合ってきたんだぞ! 俺たちの苦労などなにほどのことがある!」
アーサーは市民の救出にかまけてもいられなかった。一見市民が隠れていると見越した家屋にも死兵が潜んでいたからだ。そこではたいてい人肉を喰らう宴が催されていた。騎士たちは怒りに燃えて立ち向かったが、この勇敢な人々も引き裂かれあるいは殴り殺されて、市民たちとおなじ命運をたどった。
「死人が出やがった! 死兵どもが出やがったぞ!」
廃屋の窓を突き破り、戸口を転がるようにして、騎士たちが放りだされてくる。
「みな家屋から出ろ! 不用意に戦うな!」
アーサーは油樽を用意させた。それを騎士たちがひしゃくですくい、戸口に投げこんだ。化け物共は、顔面に油を喰らい、顔をしかませる。そのあまりの醜悪さにみな嫌悪の呻きを上げた。
「火矢をかけるんだ!」
アーサーは布の巻かれた矢を油樽に浸した。それに若い兵士が火をつけようとするが、手が震えてまともに火打ち石が打てない。
「急げ」
アーサーが叱咤したのと、死兵が窓越しから巨大な手を伸ばしたのは同時だった。若者が背後から頭を砕かれる。手元に血と脳漿が降ってきた。
アーサーが真っ青な顔を上げると、屋内からテーブルや煉瓦が飛んでくる。死兵どもは確かに陽の光を怖がるようで、全身を往来にさらそうとしない。代わりに腕を窓から突きだし、舌を鞭のように飛ばしてくる。アーサーはやつらと戦うのは初めてだった。およそ人間ではない。教会で聞く悪魔そのものだ。
「くそっ」とミドルの声が近くでした。「出てこないが、攻撃してくるぞ!」
アーサーは夢中で血肉を払い落とすと、死んだ男の手から火打ち石をもぎとった。右膝の裏で矢をはさみ、煉瓦が飛び交うのもかまわず夢中で石を打った。血に塗れたせいで火がつかないのだ。やがて、火打ち金が、石英を正確に擦ると、火花が飛び、矢の先端が煌々と燃え上がる。アーサーは無惨に倒れた兵士の死体を横目に、素早く矢をつがえる。
「待ってろ、今仇をとってやる」
アーサーはこの土壇場でわざと一呼吸を置いた。弓の名人ロビン・フッドに厳しく仕こまれた射弓術はこの日も物をいったのだ。醜い目玉にはさまれた毛むくじゃらの眉間が、彼の視界に飛びこんでくる。アランはこのときまったくの無心でいた。指が矢筈から離れたのにも気づかなかった。矢は煙を巻いて飛び、正確に化け物の眉間を打った。炎が化け物の体毛をテラテラと流れだした。油を舐め、燃え広がっているのだ。やがて、炎は建物に燃え移って盛んに燃えはじめた。
「みんな、下がれ!」とアランは自分も炎を避けながら呼びかける。「化け物の手の届かないところまで退くんだ!」
「あれは炎で死ぬのか?」
と側に来たミドルが彼にささやいた。その声は震えている。死兵らは屋内で絶叫を上げ暴れている。外に飛び出して来た者も、陽に焼かれて死にはじめた。
「みな落ち着くんだ」アーサーは困惑する騎士たちにいった。「俺たちの役目は市民を逃がすことだ。死兵と戦うことではない。一人でも多くの市民を……」
「アーサー、見ろ」
とミドルが言った。アーサーは辺りに急に影が差したことに気がついた。雲が出たのかと思った。アーサーは雨が降ることを懸念して空を見上げたが、彼の目線の先にあるのは三日月型に欠けた太陽の姿だった。闇に食いちぎられたようだとアーサーは思った。
「なんだ、あれは……?」
○ 2
胃の中身はなにも残っていないのに、まだ吐き気がこみ上げてくる。鼻はもう馬鹿になっていたが、目に見える光景はひどかった。正直なところ、人肉や血痕をさけて歩くのは難しかった。洋一は自分がなにかを踏むたびに心の中でごめんなさいと謝った。これまで自分が平和な日本にいて、死体すら見たことがなかったことを思い知らされた。あの太助でさえ顔が青ざめ、彼を気遣う余裕がない。
「洋一、しっかりしろ」
と奥村が言った。洋一は口端の唾を拭って頷いた。男爵がここにいればいいのに。あの人が側にいて背を撫で慰めてくれればどんなにいいか。けれど、ミュンヒハウゼンは伏して二度と目を覚ましそうにない。洋一は目尻にたまる涙を自分の拳でぐいぐいと拭いた。
「二人とも気を静めておけ。ウィンディゴはいつ仕掛けてくるか分からんぞ。見えるものにとらわれるな」奥村はそこで言葉を切った。慎重に言葉を選んでいるようだった。「ロビンがモルドレッドに勝てるとは限らん。そして、モルドレッドを殺す武器がエクスカリバーしかない以上、誰にもモルドレッドを倒すことは出来ない」
それはこれまでなんども話し合ってきたことだった。エクスカリバーを持てるのは王権を委譲されたロビンだけだ。伝説の書をつかうにしても、エクスカリバーを持てる理由を考えなくてはいけない。洋一たちはこれまでその方法を考えあぐねていた。ウィンディゴがなにを仕掛けてくるのか、見抜くことができなかったからだ。
行軍の列が止まり、兵士たちが騒ぎはじめた。奥村は足をとめ、刀に手をかけたが、すぐに彼らが頭上を見上げていることに気がついた。太助が洋一を守ろうと鯉口を切りつつ前にまわった。
「洋一、おかしいぞ」
と太助が言った。洋一もそのときには大人たちがみんな上を見ているのに気がついた。太陽の光線が変化している。辺りの影が急にゆがんだ。洋一が空を見上げる。おかしいのは太陽だった。太陽の端が黒くなっている。洋一はすぐに目をやられて顔を背けたが、自分の気づいたことに愕然とした。
「日食だ……」
と彼は言った。太助が驚いて彼を見た。太陽の端が月の影に喰われている。それで地上の光も変化しているのだった。
「まずいぞ、洋一。皆既日食だと真っ暗になるのか?」
「わからない」
と彼は言ったが、同時にミュンヒハウゼンと過ごした夜のことを思いだしてもいた。あのときの月は元の世界で見るものと違った。
「おじさん、月だよ! この世界の月は大きいんだ! きっと日食の間は死兵が使えるんだ!」
「日食で陽の光をさえぎるつもりか」
やつの狙いはこれだったのか。奥村は呆然とつぶやいた。周囲の騎士たちも不安がっている。みんなこのまま太陽が消えて、暗闇になることを恐れているのだ。洋一はうかつさに地団駄を踏みたい気分だった。ウィンディゴがなにか仕掛けてくるのは分かっていたのに、なんの準備もしてこなかったのだ!
「ロビンに知らせよう。二人とも俺の側を離れるな。洋一、伝説の書を使えるか?」
洋一はとっさに返事ができなかった。喉が干からびてしまっていた。思いつけるだろうか? けれど、ウィンディゴの出方を見なければ、対処のしようがないというのは彼らのだした結論でもあった。
「太助、お前は洋一の側を離れるな。伝説の書に書くのを助けるんだ。俺はロビン・フッドに助太刀する」
奥村はもう一度空を見上げた。
「月の動きが速い。死兵どもが出てくるぞ。ついてこい」
○ 3
奥村が前方にいたロビンの元に駆けつけるころには、周囲の建物や路地裏から死兵らの咆哮が轟いていた。
「奥村、なんだあれは?」
とロビンが太陽を指さしていった。
「月が太陽とかぶさっているんだ。すぐに地上は暗闇になる。死兵が出てくるぞ」
「なんだと? 今に限ってか」
「くそ、どんどん暗くなるぞ!」
ロビンは周囲を見渡して、「死兵が騒いでいる。日食なら動けるのか?」
「ただの日食のはずがない。周りに火を放つか?」
とアジームが言った。ロビンは首を左右に振った。
「だめだ。こんなに密集していてはこっちも焼け死んでしまう」
「だが、王都の死兵は千や二千ではない! 全滅するぞ」ウィリアムが言った。「撤退すべきではないのか?」
ロビンは一瞬逡巡した。
「それもだめだ。この状況で撤退したら、総崩れになる。それこそ全滅だ」
逃げるには死兵の足は速すぎる。ロビンはエクスカリバーを引きつけた。
「全軍、その場で戦闘準備をしろ!」
ロビンの言葉と共に各隊長たちは部隊の元に散り、ちびのジョンらは、ロビンを中心に円陣を組んだ。
「円陣だ! 各小隊、密集隊形をとれ! 互いをかばって戦うんだ! 死兵が出るぞ!」
そうする間にも太陽は三分の二が闇に隠れた。地上の光はどんどん薄くなっていく。日食は凄い速さで進んでいった。そして、太陽はついに月の裏へと隠れきった。空は真っ暗になり、星すら瞬きだした。
「落ち着け、いつまでも陽が陰っているはずがない!」
奥村はこどもたちの肩を抱きながら、頭上の窓から死兵が身を乗り出してくるのをみた。その目が赤く光るのをみて洋一の肩は震えている。
「来るぞ! 太助、刀を抜け!」
○ 4
死兵の群れは闇を利用してロビン軍に忍び寄った。モルドレッドは最初から東門周辺に死兵を結集させていたのだ。
ロビンがエクスカリバーを鞘から抜き放つと、その光芒は闇夜を払い、仲間たちを照らしだした。死兵はその光を恐れて容易に近づかない。
「槍で動きを止めろ! 首を刈り取れ!」
そのうち城門付近にいた部下たちがどこをどう通ってきたのか、ロビンの元にたどりついた。
「ロバート卿の部隊が城門を占拠してる! もう東門からは出られない!」
「なんだと!?」
とさしものロビンも瞠目した。
「あの野郎、モルドレッド側につきやがった!」
ジョンが耳元で怒鳴ったが、死兵の咆哮で互いの声も聞こえない。ロビンの軍勢は道幅に阻まれて、数の利を活かせなかった。ほとんど一方的な殺戮の場とかしはじめたのだ。
ロビンの周辺にいた騎士たちも死兵に群がられてたちまち数を減らしていった。洋一は仲間の血をかぶり、太助は彼の前で刀を正眼に構えている。味方の体が邪魔をして、思うさまに刀を振るえないのだ。奥村が彼の肩をおさえて、
「無理をするな。モルドレッドが出てくるまで待て!」
ロビンはトリスタンの弓を射、手近にきた死兵にはエクスカリバーを振るって戦っている。円卓の男たちの武器はすさまじかった。首を刈ったわけではないというのに、エクスカリバーに斬られた死兵たちは煙を吹きながら人へともどっていく。ロビン・フッドらは松明に火をつけ、死兵を退けながら戦った。
ロビンは空を見上げ、月が去り、太陽が少しずつ顔を出してきたのに気がついた。やはり、ウィンディゴでも月の動きを食い止めることは出来なかったのだ。死兵らは陽の光を浴びて苦悶の咆哮を上げたが、太陽が顔を覗かせたのはほんのわずかだった。動きがひどくゆっくり感じられる。空はまだ暗く星もある。死兵も決戦を自覚しているのか退かなかった。
ロビン軍の前方ではモルドレッドの軍旗が翻る。モルドレッド直属の銃士たちだった。ロバート卿の部隊も混じっているようだった。ロビンはあの先にモルドレッドがいることを確信した。敵勢の出現と共に、エクスカリバーが轟々と輝きはじめたからだ。
「兵を集結させろ! モルドレッドがいるぞ!」
死兵の囲いを抜けてロビンの回りに集結した男たちは数百名に過ぎなかった。ウィリアム・ダンスターの姿もない。
「くそ、たったのこれだけか」
ジョンはロビンの体をみて驚いた。
「おめえ、傷が」
「ああ、エクスカリバーの鞘の力らしい」
戦闘は始まったばかりだというのに、ロビンの傷はもう完治していた。
ジョンはうなずき、これなら勝てるかも知れないと思った。アラン・ア・デイルが死兵の手を逃れて退いてきた。
「ちくしょう、どうするロビン!」
「向こうだって、数は少ない、決戦だ! やつも総力をぶつけてきている、退くな!」
とロビンは言った。
「いいか、あの銃士どもに死兵になられては厄介だ。油樽を引いてこい! 死体に火をかけて燃やすんだ!」
ロビンの命に部下たちは迅速に動いていく。そのうち、モルドレッド側の銃撃が始まりだした。
「動ける者は集まれ! モルドレッドの本陣を目指すんだ!」
○ 5
そうした戦いの真っ最中、洋一はずっと考えていた。死兵の腕を逃れ、血を浴びて真っ赤になりながらも、本を抱えて考えていた。なるほど彼らは見事エクスカリバーを手にすることが出来た。けれど、モルドレッドにはウィンディゴがついてる。二対一じゃいくらロビンとて危うい……。
洋一はそこでピタリと立ち止まった。太助が死兵から彼を守ろうと背を押した。
「そうだ、二対一だ。ぼくにだって、モルドレッドが取り憑いていた……」
そのとき、千切れた腕が懐に飛んできて、洋一は図らずもその腕を抱えこんだ。洋一は悲鳴を上げて放り上げた。後方を見ると、人間がまるで風船人形のように宙に舞っている。
「洋一、なにをしてる。もっと下がれ!」
「太助!」と彼は友人の袖を捕まえた。太助はふりむいたが、その顔も炎の中で真っ赤に見えた。「ぼくは集中したいんだ。本を書きたい。時間をくれ!」
「なにをいってるんだ。今は……」
「おじさん!」
と洋一は太助を無視して奥村を呼んだ。
「おじさん、思いついたんだ! エクスカリバーを持つ方法! たった一つだけどこれなら行ける!」
洋一は手短に二人に話した。洋一はモルドレッドが右手に棲み着いたのを利用して、アーサー王を呼び出そうというのだ。奥村と太助にもそれならいけるかもしれないと思えた。けれど、そのときにはモルドレッドが部隊の前方に出現して、ロビンはこれと戦うために兵を集め始めていた。
奥村は迷った。洋一について悠長に本を書かせている時間はない。それに洋一は創作の興奮で我を忘れている。アーサー王を呼びだした所で、剣をとって戦うのは洋一なのだ。奥村は決心をしていった。やはりロビンを助太刀してモルドレッドを倒すしかない。
「太助、お前は洋一を守れ」
「父上!」
「俺はロビン・フッドと共に行く。もしもの時は任せたぞ。二人とも死ぬな」
洋一は責任の重さをずっしりと感じた。ロビンがやられたら、次は自分たちだ。胃の腑の奥が石になったようだった。けれど、二人の少年は立派な大人、しかも自分たちの尊敬する本物の侍から重大な任務を任されたことに高潮してもいた。
「おじさん、ぼくら絶対後から駆けつけるから」
奥村はうなずいた。
「父上、金打を」
と太助が言った。奥村は思わず頬がほころんだ。仲間が死んで以来、金打などひさしくしなかった。むろん金打は侍以外でも誰でも打つが、太助がそれを求めるということは、自分も一人前だと証明したいのだ。
二人は静かに鯉口を切り、刀を半ばまで引き抜くと、高く鍔を打ち合わせて金音を鳴らした。
○ 6
奥村はあせっていた。ロビン・フッドは突出しすぎている。銃士たちの攻撃はむろんロビンに集中していたが、エクスカリバーの鞘の力が瞬く間に彼の傷を癒してしまうのだ。ロビンは超人的な力を発揮して、包囲陣を打ち破っている。仲間たちはその動きについていけないのだ。
奥村は違和感を感じずにはいられなかった。モルドレッドの行動には強力な意図を感じる。なぜ死兵に任せず自ら打って出てきたのか? エクスカリバーを手にしたロビンを殺せないと知っていたからではないのか? そして日食をかけ死兵をつかったこの攻撃は紛れもなくやつの罠のはずである。やつは勝算を持っている。ロビンを殺す算段を積んでいるのだ。
「ジョン、アジーム!」
部隊は、銃士とみるや、油をかけて死体を燃やしている。死人と化した銃士は黒い煙を吹き上げて別の物に変化しようとしていた。流れ出た血液を結集し、化け物に変わろうとしていたが、火をかけられてはたまらない。炎の中では真っ黒な魂が苦悶の絶叫を上げていた。だが、こうした行動のせいで部隊の行動が遅れている。奥村は側にきたガムウェルらに、
「部隊を分けろ! 油樽の方にそんな人はいらん! 四台あるなら、一カ所にまとめるな、先を急がせろ! ロビンを守るんだ!」
と言って、ジョンとともにロビンの後を追いはじめた。彼らは周りに呼びかけつつロビンの後を追ったので、奥村の後方にはたちまち一部隊ができあがった。
奥村が見上げると、空はまるで黄昏のようにもの悲しかった。太陽が明け切らない。
「ジョン、君はウィンディゴの姿を見たんだな!」
「そうとも! ロビンも見た!」
「ならば今度も出るぞ! 油断するな!」
奥村は銃士どもに肉薄しては、右に左に斬って落とした。銃士たちは銃剣を繰りだすが、奥村はすり抜けざまに頸動脈を斬り捨てていく。今度はロビンに変わって彼が仲間たちの道を切り開きはじめた。そのすぐわきで、ちびのジョンが喚いている。
「ロビン、ロビン、待ってくれ!」
だが、トリスタンの弓とエクスカリバーを手にしたロビンは神さまみたいな活躍振りだった。それに、エクスカリバーで斬ると、銃士たちは死兵にかわらない。死体から苦悶する人魂が抜け出ていく。モルドレッドが銃士たちに埋めこんだ悪霊のようだった。
軍勢の勢いは何段にも敷いた包囲陣を次々と打ち破って陣中深くに食いこんだ。アラン・ア・デイルが銃弾に腹を射貫かれ、それをウィル・ガムウェルが支えている。退くな、突き進め、とアランは叫び、仲間たちは共に助け合いながら突き進んだ。
「ロビン・フッド!」と奥村たちはようやくロビンの元に駆けつけた。奥村は彼を銃士たちの積み残した土嚢の裏に引っ張りこんだ。
「君はやつとおなじ罠にはまっているぞ。傷が治るからといって無茶をするな!」
「わかっている! それよりも周りの銃士たちを頼めるか?」
奥村が見ると、銃士たちはかなわじと見て弾ごめの準備をはじめている。その中心にはモルドレッドがいて、さかんに檄を飛ばしている。もうこんな近くまで来ていたのだ。ロビンは仲間に弓を射させてこの動きを牽制させた。奥村はロビンに向かってうなずき、
「ああ、だが、ウィンディゴには気をつけろ。この世界では直接手を出せないが、人の心を惑わそうとするやつだ」
「見ろ、奥村!」
とちびのジョンが奥村の痩せた背をどやしつける。トリスタンの矢がモルドレッドの頬をかすめると、暗黒の陰がドロドロと吹き出し、彼の全身を取り巻いたからだ。
「闇の男だ。あの部屋で見たやつだ」
「やはりウィンディゴだ」
奥村は決着を付ける時が来たようだ、とつぶやいた。ちびのジョンが顔を近づけて、
「洋一たちはどうした? 安全な所にいるのか?」
「事は済ませてきた。大事ない」
「それじゃあ、わからんぞ」
「俺たちがモルドレッドを倒せば大事ないのだ!」と奥村は言い返す。
「奥村、火矢だ!」
とガムウェルが言った。奥村が見上げると、星空を裂くようにして火の玉が飛んでくる。奥村は土嚢から身を乗りだすと、大刀を一閃して火矢を叩き折った。火の玉は路面を滑るようにしてロビンたちの足下を転がった。
「まずい、油樽を狙っているぞ! 叩き落とせ!」
モルドレッドが手近にいた銃士を惨殺しはじめたのはそのときだった。黒剣は暗黒の男をまといながら愚風をおこし、銃士たちを引き裂く。
「死兵にするつもりだ! 油樽をひけ! 変わる前に殺すんだ!」
ロビンの手元には二台の荷車があったが、一つは火矢をまともにうけて、轟々と火柱を上げはじめた。
「エクスカリバーを渡せ、ロクスリー!」とモルドレッドの声がした。「貴様には不要のものだ!」
モルドレッドの叫び声とともに空間がゆがみ、その声はまるで波紋が広がるように四方から押し寄せてきた。奥村たちは鼓膜の奥をまともにやられて這い蹲る。だが、奥村が見上げると、ロビンは平然と立ち敵陣を睨んでいた。
「平気なのか?」
「ああ、エクスカリバーのおかげらしい」
ロビンは土嚢の陰を出た。奥村たちが後につづいた。モルドレッドはすでに死兵を解き放っている。
ロビンとて不安はあった。初戦では二人がかりでまるで歯が立たなかった。やつの剛猛ぶりは身に染みてわかっている。
「この輝きが見えんかモルドレッド! エクスカリバーは貴様に味方しない!」
「ロクスリー」
「侍の男」
モルドレッドの声とウィンディゴの声はまったく別の言葉を発しながら、同時に聞こえた。ロビンと奥村の目には、モルドレッドとウィンディゴの姿が急にふくれ上がって見えた。奥村たちは津波のように押し寄せてきたウィンディゴの陰に押し戻された。
「貴様で最後だ奥村! 侍の世界も今日で終わりだ!」
「なにが最後だ! 太助がいることを忘れるな!」
彼の怒声もウィンディゴの喚笑にかき消された。奥村は怒りのあまり、我を忘れた。アジームが必死で彼を救おうとしているのも見えなかった。
俺で最後だと、仲間を殺したのは貴様ではないか! 彼はやつを一刀斬り伏せられない自分が歯痒かった。卑怯者め、地獄を見ろ――
「待て! 待てウィンディゴ!」
奥村は闇の陰を追おうとしたが、死兵に囲まれて追えない。アジームが脇にきて、肩をぶつけた。
「落ちつけ、奥村! 我々の役目は、ロビンを助けることだぞ! モルドレッドを倒せるのはロビンだけだ!」
「ああ、わかっている」
奥村は自分をとり戻そうと、剣を正眼にとった。ロビンが殺されれば、どうしても洋一に頼るしかなくなる。それだけは避けたかったのだ。
モルドレッドは傷こそ回復するが、武器がきかないわけではない。奥村は仲間を呼んで隊伍を組んだ。
その間、ロビン・フッドはたった一人でモルドレッドと対峙していた。エクスカリバーの輝きは闇の男すら打ち払うほどだった。それで死兵どもも近づけないのだ。モルドレッドは黒剣を抜き、その黒剣にはウィンディゴの闇がまとわりついた。二つの剣は先端をチャリチャリと合わせながら、互いに攻撃の隙を探り合っていた。
「鞘で傷は回復しても、体力までは回復しない。エクスカリバーを持てるのはお前だけだ。ちがうかロクスリー?」
確かに、ロビンは戦いつづけで肉体の疲労ははなはだしい。すでに呼吸は荒く、全身は汗で濡れネズミとなっていた。彼らの狙いはロビンの命よりも、その力を削ぐことだったのだ。
「周到なことだな、モルドレッド。不死の男がなにを恐れる?」
「恐れる、俺がお前をか?」モルドレッドはわずかに笑んだが、その表情は固く、眼の奥には憎しみがあった。「お前は聖剣の正統な持ち主ではない。お前では聖剣は力を発揮しない。賊徒に聖剣は無用なはず!」
モルドレッドは黒剣を上段から真っ向振り下ろした。ロビンは受けた。光の裏でモルドレッドの瞳を睨めつける。
「聖剣なら死体の貴様にくれてやる」
「貴様に俺は殺せんぞ。聖杯の力をまだ学習せんか!」
「不死に自信を持ちすぎだ。エクスカリバーはお前に味方しない! 貴様の父親はエクスカリバーこそが貴様を殺すといったぞ!」
モルドレッドは顔面から怒気を放って飛び退ると、瞬く間にロビンの懐に飛びこんだ。そのまま胴を狙ったが、エクスカリバーの鉄壁の防御を崩せない。
ロビンは喜びににた驚愕を覚えた。以前は剣を砕かれるほどであったモルドレッドの剣圧が、風にたなびく柳のようにしか感じないのだ。モルドレッドは数十合を打ち合うが、ロビンはそのたびに押しかえした。ロビンの攻撃もまた、地面を裏返すほどに重かった。
二人は聖剣と魔剣をからみあわせて、互いの剣越しに睨み合った。
「聖剣は正統の王にこそ仕えるのだ!」
モルドレッドはロビンを押したが、ロビンは五百の魂の圧力によく耐えた。
「本当にそうか?」
ロビンの問いにモルドレッドは飛び下がり、着地とともに勢いをつけロビンの胴をめがけて突きをくれた。ロビンは剣の先でやすやすとこれをいなした。モルドレッドは瞠目した。かつてこれほどたやすく自分の剣をいなした者はいなかった。父親を殺す機会を狙い、中々それを果たせなかったのも、アーサーが聖剣を持っていたからだ。だが、ロビンは王家の血筋ではない。いかな英雄といえど、一介のヨーマンであった男である。
ロビンの攻撃が肩に触れると、その傷口から乳白色の人魂がいくつも抜け出てきた。彼の内に閉じこめられた魂たちだった。
「貴様、アーサーに何事か施されたな!」
「これは聖剣の力だ! エクスカリバーはお前の血を否定している!」
ロビンとモルドレッドは互いに剣を立て、グルグルと回りあった。周囲では、仲間たちが死闘を繰り広げていた。隙を見せるな、とロビンは自らに言い聞かす。仲間を救うことは後でもできる。モルドレッドを倒す機会は今しかない!
ロビンは言った。「呪われた貴様に聖剣が味方するものか! お前に王たる資格がどこにある。真の王者を示すものは血統などでは断じてない!」
「王権を否定する気か! 傲慢だぞ、ロクスリー!」
「俺は俺の信じるものに仕える。エクスカリバーもまたそうだ!」
ロビンの叫びに呼応するように、闇の力が彼の全身を取り巻いた。ウィンディゴがモルドレッドの元を離れ、ロビンにまといついてきた。
「くそ、離せ!」
モルドレッドは好機と壮絶な笑みを見せ、彼の腰骨をしたたか打った。ロビンが息を詰まらせる間に、聖剣の鞘が音をたてて地面に転がる。
「しまった!」
「これで回復も無理だ、ロクスリー! アーサーも鞘を失い結局は死んだのだ!」
「死ぬのは貴様だ!」
ロビンが雷光の突きを見舞うと、モルドレッドは剣を引き上げながら身を躱すのがやっとだった。黒剣の刀身をエクスカリバーが削り取り、その火花と流星の輝きがモルドレッドの頬を打った。
「おのれ!」
モルドレッドは腰を伸ばすと、右に左に斜剣を繰り広げる。彼の体はウィンディゴの力をうけて二倍に膨れ上がっている。ロビンは脳天をめがけた攻撃を受けたが、これすら余裕をもって受けることができた。ノッティンガムではその威力になんども体を弾かれたというのに、まるでこどものおいたをいなしているようだ。エクスカリバーがモルドレッドの剛力を吸い取っているのだ。
モルドレッドは怒りの声を上げて距離をとった。ロビンは後を追わず気息を整えた。
「エクスカリバーを持ったところで人民は貴様を支持などしないぞ!」
「だまれロクスリー!!」
そのとき、モルドレッドの声に何者かの声が重なった。同時にモルドレッドの体から巨大な影が抜けだした、それとともに、モルドレッドの体はしぼんでいく。
「ウィンディゴか!」
聖剣を振るう間もなかった、ウィンディゴは聖剣ごとロビンを闇の中に飲みこんだからだ。ロビンは真っ暗闇の中にいて視界を奪われた。聖剣のみが光を放っているが、ウィンディゴの邪術はドロドロと黒液となりエクスカリバーすらをも包みこもうとしている。そして、ロビンは邪悪な声を聞いた。人の苦しみを喜ぶ声。この世の邪悪を凝り固めた笑い声だった。
「小僧共もお前もここで終わりだ。古の物語など滅ぶがいい!」
「邪魔をするな!」ロビンは憤怒を上げた。「赤子や洋一の魂を弄ぶだけではまだ足りないか!」
ロビンの絶叫と共に、モルドレットが黒衣を切り裂くようにして現れた。ロビンは聖剣を上げ、モルドレッドの攻撃を受ける。だが、モルドレッドの一撃にはなんの手応えもなかった、その体もロビンの体をすり抜けるようにして崩れていった。ロビンがウィンディゴの幻にしてやられた時には、すでに遅く、本物の黒剣はロビン・フッドの背中を貫いていた。肉を裂かれ、肋を断ち割られ、肺を貫かれた。肺胞がブチブチと弾ける。黒剣は胸骨を掠めながら、ロビンの胸筋をも切り裂いた。暗黒の刀身が、ロビンの血液を滴らせながら、左胸から突き出てくる。
「うああ」
ロビンが唸ると、モルドレッドは牙を剥いて、剣を回した。ロビンの手から聖剣は落ち、回転をしながら地面に突き刺さる。そして、彼の骨を断ち、肺を食い破る黒剣の刃からなにかが流れこんできた。何者かの魂が。
「貴様も死兵と化すがいい! 真の王はこの俺だ!」
□ その三 呪われたこどもたち、伝説の幕を下ろすこと
○ 1
奥村がロビンと共に立ち去ってしまうと、洋一と太助のいる地点はちょうどブラックスポットのように戦場にぽっかり空いた空白地帯となってしまった。後方では城門付近からの火災が、激しく天を焦がしている。その火に照らされて死兵と騎士たちが激しく対立するのが見えた。
その空白地帯にはときおり路地裏から死兵が迷いこんできた。二人は油樽を積んでいた荷車の下に這いこんだ。
「洋一、ここでも書けるか?」
「うん。紙は見えるよ。早くしないとウィンディゴがこっちに来るかも……」
「だけど、洋一、いいのか?」と太助が訊いた。洋一は顔を上げた。「その手にアーサー王を呼びだすということは、君がエクスカリバーを持つということだぞ。エクスカリバーを使えるのか?」
太助は本気で心配している。それに多少困惑してもいた。剣を振るう洋一が想像できないのだ。洋一は茫然自失となった。とっさに太助ににじり寄り、服をつかんだ。
太助は首を左右に振って、「ぼくは駄目だ。ぼくではエクスカリバーを持てないじゃないか」
「ぼくは剣術が使えないじゃないか」
太助と洋一は荷車の下で激しく見つめ合った。二人は困りきって今にも泣きそうな顔をしている。やがて、太助は硬い表情をとき、
「アーサー王を信じよう。きっと力を貸してくれるはずだ」
でも、つかうのはぼくの体じゃないか。と洋一は思った。腕力も体力もふつうの小学生だ。いや平均以下かもしれない。モルドレッドどころか、普通の兵隊にだって勝てやしない。
洋一はそのことを伝えようとしたが、そのとき地響きがして、荷車も地面も激しく揺れた。ひときわ巨体の死兵が、荷車のすぐ側を歩いているのだ。
太助は大刀を納め、脇差しをそろそろと抜いた。彼なりに死兵と戦う覚悟を固めたのだ。こんな場所で楽々と納刀をすませるのだから、父親に劣らず大した腕だった。太助は囁いた。
「洋一、ぼくもあんなやつの首は刈れない。父上を助けたいんだ」と肩をつかんだ。「書いてくれ」
自分が無理を言っているのはわかっていた。けれど、彼も必死だったのだ。
洋一はほとんどやけくそになって、固い路面に伝説の書を広げた。万年筆をポケットから引き抜いた。その硬い芯先は、彼の人肌で温かくなっている。けれど、彼が王都で見た人々の肉塊とおなじ命運を辿るのならば、この父の形見だって温かくなることはないだろう。
洋一は吐き気と戦い頭を振って恐怖心を追い払いながらも、だめだこのままじゃ失敗する、と思う。だって彼は恐怖に負けてる、心を鎮めていない。文を書くための、自在を得ていないのだ。
駄目だ。殺されるかもしれないなんて考えるな。これからのことは忘れろ。
「太助、太助、ぼくの側にいて。ぼくを守って欲しいんだ」
太助は先ほどよりずっと強く、洋一の服をひっぱった。
「そんなの当たり前だ。刀にかけて。父上にかけて誓うとも」
洋一はようやく顔を上げてうなず。恐怖よりも感動が先に立っている。けれどその目は暗闇でもはっきりとわかるほどに濡れている。
洋一はなんどか目を瞬いた。アーサー王は確かに死者の島にいる。だけど、モルドレッドが洋一にくっついてアヴァロンに現れたということは、逆も可能ということだ。
洋一は祈るような気持ちで文章をしたためる。
『アヴァロンにいたアーサー・ペンドラゴンは、エクスカリバーをロビン・フッドに託しただけではなかった。彼は自分自身で闇の皇子と決着を付けるつもりだったのだ』
太助の見守る中、伝説の書は文を吸いこみはじめた。洋一は自信を得て――無意識に息を吸いこむ、胸が思い切りふくらんだ――書いた。
『アーサーは、洋一の右手の痣に巣くったモルドレッドを追い払ったとき、ある仕掛けをしておいた。闇の男を追いだした後、洋一の魂にぽっかりと出来た空白、そこに自らの魂を滑りこませておいたのだ。今彼は洋一の右掌に棲んでいる。洋一の体を喰らい尽くす死の呪いとしてではない。こどもたちを救い、三度イングランドを救済するためだった』
洋一はそこでピタリと動きを止めた。万年筆のインクはスルスルと染みこんで、彼の書いた文章は薄くなり消えつつあった。洋一は右手を見おろす。
太助が心配をして、「もう終わりなのか? そこまででいいのか? もっと――」
「ちがう、右手が、ぼくの手……」
洋一は万年筆を取り落とし、それを左手で素早く受けた。太助が右の手首をつかみ、掌をひっくり返す。「肉腫だ」
洋一は骨を押しのけ、肉を裂く激痛に絶叫した。大粒の汗をにじらし、口端からは涎が垂れている。手が真っ赤に腫れている。膿がどんどんたまるみたいに、掌が盛り上がってくる。血流がそこへと流れこんで、視界が一瞬暗くなった。ブラックアウトだ、と彼は思う。言葉が頭蓋をくるりと回って彼の脳神経をつついて回る。意識が遠くなる――背を荷台に打ち当て、頬を地面に打ちつけのたうちまわった。
「洋一、駄目だ、静かに……」
太助の言葉もそこまでだった。声を聞きつけた化け物共が走り寄ってくるのが見えたからだ。
荷車はまるでおもちゃのように軽々と宙を舞い、二人の体は剥き出しとなった。洋一は手首を押さえてまだ苦しんでいる。太助は威嚇に刀を煌めかしながら、彼を立たせた。
「洋一、走れ! ロビンの所に!」
そういう間にあちこちの窓から死兵が飛び降りてきて、その醜さにも関わらず華麗に降り立つ。道にいる化け物の数は増えていった。先頭にいた死人が猿膊を伸ばすが、太助は腰をひねり、かろうじて躱す。二人は一散に駆けだしたが、死人らは辺りの物を蹴散らかしながら後を追ってくる。
「追いつかれる! 洋一、先に行け、父上を救ってくれ!」
太助が身を翻そうとし、死兵に立ち向かおうとしたときだった。路地から騎士の一団が現れて、槍衾をつきだしては死兵どもと争いだしたのだ。
「小僧ども! ここでなにをしてる! ロビンはどこだ!」
「アーサー!」
路地から現れた一団は、アーサー・ア・ブランドだった。ロビンを目指して命がけでここまで駆け参じてきたのだ。
太助は喜びに仰天したが、彼と話している暇はなかった。彼は洋一の肩を抱いてロビンの元を目指しはじめた。二人は死兵のいないのを確かめ、路地を使い、少しずつ戦場の中心に近づいていった。洋一はその間も右手の痣にずっと話しかけている。その肉腫は傍目にもはっきりと分かるほど人顔の形をなしてきていた。
「アーサー王、ぼくらに力をかして、ロビンやおじさんを助けたいんだ」
「洋一」
口の部分がさけて、声を発した。二人は驚きのあまり、まとめて転んだ。
洋一は、「この声はアーサー王だよ」と言いながら物陰に這いこんだ。
「洋一、急げ、ロビン・フッドは死にかけておる」
「じゃあ力を貸してくれるんだね。ぼくたち……」
「時間はない。もうロビンはやられてしまったのだぞ」
洋一、と太助が肩を叩いた。彼は顔を階段の隙間から出し、前方をうかがっていた。まだ闇が深くて前方で争っている人影がどうなっているのか、果たしてロビンとモルドレッドのどちらが優勢なのかは分からない。でも、エクスカリバーの輝きだけは、ここからでもはっきりと分かった。エクスカリバーは地面におち、石畳に突き刺さっている。誰も所持していないのだ。
「ロビンはほんとにやられたんだ。ぼくが注意を引いてやるから、君はエクスカリバーを拾え」
太助は洋一の返事を待たずに駆け出してしまった。
「ど、どうしよう」一人になってしまった。おどおどと物陰に引きこみ、右手のアーサー王に囁く。「無理だよ、ぼくなんかじゃエクスカリバーを持っても戦えない!」
「洋一」とアーサー王は深く重みのある声で言った。それで洋一も我にかえる。「お主も知ってのとおりだ。普通の武器ではモルドレッドは死なない。お主の友人と義父ではやつを殺せないのだ」
「アーサー王はわかってな……」
「いやわかっている」とアーサー王は厳しかった「お主は臆病風に吹かれている。言い訳を考えて決断するのを忘れている。座して泣くことはいつでもできる。それはあの世でとておなじ事だ」とアーサー王は言った。「ロビンはもうだめだ。やつに期待することはできん。だが、やつを救うことはできるのだぞ」
「そんなこと分かってるよ!」と洋一は右手に向けて怒鳴った。そのとき道の後方から凄い叫び声がして、洋一はビクリとそちらを向いた。「ぼくは……」
「男が剣を持ち戦うことに、年が関係あるか! 泣き言をいうのか、勇気を示すのか、どちらか決めろ牧村!」
洋一は怯えてうつむいた。「わかったよ――でも、ぼくに力を貸してくれるんだね?」
アーサー王は動けぬ身ながら頷いたようだった。
洋一は勇気を出して立ち上がった。アーサー王の一喝がどうも恐怖を払ったようだった。
階段の陰から顔を出し、あらためて戦場の様子を確かめた。
「わしはお主を信じている、それは彼らもだ」
とアーサーは言った。洋一は頷いた。太助もおじさんもぼくのことを信じている。
「お主ならやれるぞ。わしが肉体に憑依してもお主は自分を保っている。死人になることもないのだ」
「銃士たちのことをいってるの? でも、どういう……」
「残念ながらロビンではマーリンに敵しなかった。だが、お主――お主は面妖よ。ロビンともわしともちがう。一人でない人間だ。モルドレッドに取り憑かれても、己を失うことはなかった」
「それはどういう意味……?」
「早くしろ、みな死んでしまうぞ!」
その一言が決定打だ。洋一は意を決して立ち上がる。
○ 2
奥村たちがロビンの元に駆けつけたときはもう遅かった。
あの瞬間、地面に倒れ伏すロビン・フッドの無惨な亡骸を見たのは、奥村左右衛門之丞のみだった。
「ロビン・フッド! ロビン・フッド! 立て!」
奥村の絶叫で、仲間たちもそんなロビンに気がつく。奥村は敵を躱してモルドレッドに駆け寄ろうとする。
「もう遅いぞ、異国の男!」
モルドレッドはニタニタと笑い、エクスカリバーの柄に手を伸ばした。自分が苦痛を与えた少年らの父親だと看取ってのことだった。少年らの父親は死兵にふたたび進路を阻まれている。モルドレッドはロビンの部下たちの悲痛な叫びを横手に、ついに聖剣を手にとった。
モルドレッドが手の内に鳴動を感じたのはその瞬間だった。まるで魂の奥底から激震が走るようだった。エクスカリバーが灼熱し、皮膚を焼いた。モルドレッドは全身を振るわせながら聖剣から手を離した。
「なぜだ、エクスカリバー!」
右手は焼けただれ、肉の焦げた臭いと紫煙を立ち上らせている。
「俺以外の王がどこにいる! なぜなのだ!」
モルドレッドはふりむいた。仲間の助けを借りて、死兵の脇をすり抜けた奥村とアジームが自分目がけて迫ってきたからだ。
奥村はモルドレッドの焼けただれた手を見た。刀に目を落とし、聖剣に視線をうつす。
「だめだ、俺たちもエクスカリバーには触れない。あいつの二の舞だ」
「ならば、自らの刀で殺すまでだ」
とアジームはいう。奥村の返事を待たずに、暗黒の王に打ち掛かっていく。
「父上!」
奥村の耳に、幼い叫び声が届いたのはそのときだった。奥村は目の前の敵すら忘れて左方を見た。彼の息子が、死体を飛び越え、剣風をさけつつ、父親の元に駆けてくる。奥村は胸が張り裂けそうになるのを感じた。ロンドンでの悪夢がいちどきに蘇ったのだ。
「太助! なぜここに来た! 下がれ!」
「いやだ!」
太助は父親の隣に来ると、刀を両手に、モルドレッドと対峙する。父親の視線を避けながらも、その顔は緊張と安堵の色に満ちている。
親子はまるで大小の作り物のようにおなじ構えをして、モルドレッドと向かい合う。
「ばかもの、洋一を守ってやらんか!」
「ぼくと洋一で父上を守ると誓ったんだ。それに洋一はうまくやったよ」
「だが――」
「あいつならうまくやるよ!」と太助が言った。奥村は驚いて息子を見た。「あいつはちゃんとアーサー王を呼びだしたじゃないか! あんな状況でも本を使いこなしたんだ! だったら、今度はぼくらの番だ! あいつを助ける番だ!」
奥村の胸は息子の一喝に熱くなった。最悪の自体だが、モルドレッドがロビンから受けた傷は回復していない。エクスカリバーならモルドレッドを殺せるのだ。もうやるしかない。
奥村は息を整えて、それでもにこりと笑みを見せた。彼には太助の心情がよくわかった。言いつけこそ守らなかったが、それでも彼には期待通りの息子の姿だった。強情にも息せき切って駆けつけたその様は、まさしく古の侍そのものではないか。彼の息子は父母の期待に違わなかった。奥村は助太刀が武門の誉れなら、今ここで二人で死んでも構わないとさえ思った。
「いいだろう。こいつを弱らせて洋一に止めを刺させるぞ」
アジームがモルドレッドの剣威におされて、たたらを踏み下がってきた。モルドレッドの足下にはすでに三人の騎士が転がっている。エクスカリバーに拒絶されたモルドレッドの怒りは凄まじかった。
奥村たちはモルドレッドを弱らせるべくこの呪われた男を取り囲んだ。そして、そこから離れた戦場の一角では彼らの少年が聖剣を目指して走っていた。
○ 3
ちびのジョンだけは真っ先にロビンの元に駆けつけた。けれど、ロビンは黒霧にとりつかれている。その体から流れ出た血液は生き物のように蠢いて、傷口を塞ぎはじめていた。ロビンが苦悶し、手足を引き攣らせる。ジョンは傍らに膝をつくと、重病人に対してそうするように、彼の右手をその大きな掌に持つ。
「だめだロビン! 死ぬな! 死兵になどなるな!」
ロビンはジョンの声に応えるように手を握りかえしてきた。
「そうだ、逆らえ、がんばれロビン!」
ちびのジョンは死んだ友人を守ろうと、ロビンの頭を抱えこんだ。ロビンの端正な顔が醜く引きつり、牙と剛毛を生やしはじめている。ウィンディゴが、お主のロビン・フッドはもう死ぬといい、モルドレッドの体から抜けでた古のこどもたちは彼らを指さしケタケタと手をうって笑いだした。ジョンには腹立たしく悲しいことだった。
「死んでからもモルドレッドのところでお勉強か。でもなあ、そんなのはまっとうな人間のするこっちゃねえ。人の不幸を笑うなんて、心のねじくれた人間のするこった。そんなこっちゃいけねえんだぞ。おめえたちだって別の場所でまっとうな生を受けてたら、別の魂にだってなれたろうに。でも今からだって遅くはねえんだ」
ジョンはこどもたちに頬を張られ、小さな手で髪を引き回されながらも諭しつづけた。頭にあるのは自分を救ってくれた二人の少年のことだった。あの連中だったら、モルドレッドの邪悪な魂にだって決して屈することはなかったろう――そして、その二人の少年は、ともに古の皇子に立ち向かっていたのだ。
少年の一人がジョンの視界に飛びこんできた。ジョンは驚いた。体にのしかかる重圧が軽くなるのを感じた。ウィンディゴも少年の意図を察して飛び去ったからだ。
「洋一、こんなところに来ちゃ駄目だ! ひっかえせ!」
とちびのジョンは言った。けれど、少年はなおも駆けて戦場の中心に近づいていく。彼が目指すのが聖剣と知り、ちびのジョンは瞠目したのだった。
「まさか、あいつ……!」
○ 4
右手はまだ痛んでいる。けれど洋一は走っていた。ともだちを救い、物語の世界を救うために。洋一はこのことで父と母も救えるんだと信じた。だって彼は元気な二人を最後に、遺体には顔すらあわせていない。彼の中では両親はいまだに苦しみの真っ最中。彼はそれを助けたくて一生懸命に走っている。遺体を飛び越え、剣林弾雨の中、金色の光目がけて駆け抜けた。
「アーサー王、モルドレッドだ!」
「わかっている」
とアーサーは言った。アーサーの顔は洋一の胴体を向いていたが、視覚は少年と同化している。
「洋一、来ちゃ駄目だ!」というジョンの声が聞こえた。
「ジョン、エクスカリバーの鞘を……!」
と洋一はそちらも見ずに叫びかえした。息が切れて脇腹が痛い、こんな状態でモルドレッドをやっつけられるなんてまったく信じられなかった。
モルドレッドは奥村、アジーム、太助を相手に大立ち回りを演じている。他の仲間たちはみな倒れ、あるいは銃士たちと奮戦している。モルドレッドは、三人の剣の達人をものともせずに戦っている。むろん傷は受けているのだが瞬く間に回復している。確かに普通の武器では死なないのだ。
洋一はより一層身を屈めて転がるように駆けていった。それは砂浜で旗をとるビーチフラッグの選手のようだった。彼は右手を伸ばしエクスカリバーの柄を目がけて飛びこんだ。洋一は聖剣を支点にグルリとまわった。その拍子に聖剣は地面から楽々抜けたが、聖剣はまたその先端を地面につけた。
「お、重い!」
エクスカリバーを地面から引き抜いた瞬間、洋一の腰は重みに負けて砕けてしまった。彼はほとんど膝をつきかけてよろめき、
「力を貸すって、右手だけじゃないか!」
と文句を言った。まさしく、アーサー王の意力がやどったのは、彼の片腕のみだった。聖剣をわずかに持ち上げるだけでも、彼の全身はブルブルと震えている。左手を使おうとすると、エクスカリバーはたちまち彼の皮膚を焼いた。アーサー王は彼がエクスカリバーを持てると言ったが、それはアーサーの宿った右手のみの話だ。
「これじゃあ、剣なんて使えないよ! アーサー王、もっと力を……」
「洋一!」
右手が鋭く叫んだ。アーサー王だった。洋一が顔を上げると、黒い影が星空をさざめかせながらまっすぐに飛んでくる。
「ウィンディゴだ!」
ウィンディゴは竜巻となって彼を襲った。風が彼を取り巻いて、洋一は息も吸えなくなる。洋一は聖剣にしがみつき、懐の本をまさぐった。
「くそ、伝説の書を使えばいいのか……」
と洋一は言ったが、この状況で書きこむなんてできない。だめだ、そんな暇はない。と彼は言いかえした。同時に思いだしたのだ。自分たちが行動でも物語を導いてきたのだということを。そう男爵が言ったから、洋一は左手を本から離した。ぼくはお前に頼らない。行動で物語を変えられるんなら。
やってやる、やれるぞ!
「アーサー王、二人であいつを殺すんだ! 力を貸して!」
洋一は胸の内にこう叫んだ。
男爵、ぼくはもう本に頼らないぞ。
アーサー王が何事か答えたようだが、ウィンディゴは彼の五感を奪い、その耳にはなにも聞こえなかった。洋一はエクスカリバーを引きずりモルドレッドに近づいた。ウィンディゴの力も彼を食い止めることはできない。様々な幻術も、アーサー王の加護の元では十分な力を発揮しなかった。
ウィンディゴは人外の雄叫びを上げ、モルドレッドも洋一に気づく。
「小僧、なぜお前が聖剣を使える! なにをやった!」
モルドレッドはアジームを斬り飛ばし、奥村を足ではじき飛ばした。
「洋一!」
と奥村。
モルドレッドが洋一の心臓目がけて、黒剣を突きだした。奥村は夢中で立ち上がると、二人の間に身を割りこませる。愛刀を眼前にたて、刺突を受け流そうとする。だが、黒剣はその刀身を削り、奥村の左胸を貫いた。奇しくもロビンとおなじ箇所だった。
「おじさん!」
「父上!」
奥村は刀を放りだすと、モルドレッドの右腕を抱えこんだ。
洋一はどうしていいかわからなかった。奥村の背中から黒剣が突き出て、血をしとどに垂らしている。
「貴様、離せ!」とモルドレッドが言った。
「洋一、こいつを刺せ、刺すんだ!」
洋一は我に返ると手首を押さえて、エクスカリバーを引きずりだす、奥村の左へとまわった。右側からだと、モルドレッドの腕と剣がじゃまでうまく刺せないと思ったからだ。洋一は奥村の脇をすり抜けると柄を持ち上げ、倒れこむように剣を突きだした。モルドレッドにとっても咄嗟のことだった。左腕で聖剣をふせごうとするが、エクスカリバーは刀身をしならせ、モルドレッドの上腹部に突き立った。アーサー王は本当は心臓に突き立てたかったのだが、洋一の背が低く、下から突き上げる格好になったのだ。
洋一は驚いた。エクスカリバーが突き立った箇所からは、赤子たちの魂が次々と飛び出してきたからだ。それは金色の輝きをもって洋一の体を突き抜けていった。その魂はひどく冷たい。洋一はそれにもめげずに剣を押しこむ。けれど、刺さらない。洋一の脚力が不足して、腹筋にわずかに埋まっただけだ。それでも、エクスカリバーは灼熱し、モルドレッドの身を焦がしている。彼は身を引こうとするが、奥村が腕を抑えている。聖剣の光に生き身を焼かれ、モルドレッドはうわっと呻いた。その背後ではウィンディゴも苦悶している。
「アーサー王、もっと力を貸してくれ!」
洋一は足を突っ張りながら叫ぶ。モルドレッドは右腕では黒剣を握ったまま奥村を突きのけようとし、左腕では洋一の頭をつかんだ。
太助がその隙をついて、モルドレッドの右手に回る。上段から刀を振り下ろし、モルドレッドの利き腕を真っ二つに切り落とした。右腕が鮮血を散らし、奥村とともに地面に突っ伏する。
「父上!」
太助は父親を横目に刀を構える。洋一は、おじさん、とつぶやいた。奥村は黒剣を墓標のように抱えたまま動かない。洋一は上体を聖剣にかぶせる。火傷にもかまわず剣の柄頭に左手を添えた。モルドレッドは左腕で洋一の顔面を殴った。木の枝を折るような音がして鼻が砕け、歯の破片が口中に散った。洋一はボトボトと血を吐きだすようにして咽せ、それでもかまわず一歩一歩と地を掻いた。歯の欠片が飛び散る。舌も切った。右顔に拳を喰らって頬骨が折れた。洋一は信じられないほどの痛みに失神しかけるが、折れた奥歯を噛みしめまたそこで炸裂した痛覚の激しさに意識を遠のかせる。
痛みだ、痛みのスパークだ!
ウィンディゴがまとわりついてくる。あきらめろ小僧、そんな体ではもう無理だ。洋一お前まで死ぬつもりかと父や母の声色を真似て、洋一を説得しにかかる。けれどウィンディゴがそうしたのは失敗だった。父や母の声を聞くたびに洋一は意識をとりもどしたし、目前のモルドレッドと自分を取り巻くウィンディゴの影に憎悪を燃やして足を進めたからだ。
ぼくはお前らを許さない。父さんと母さんの敵をとるぞ。殺せるもんなら殺してみろ!
太助がむちゃくちゃに剣をふりまわし、モルドレッドのところかまわず斬りつける。モルドレッドは全身に傷をおって血を吹き出し、奥村少年を睨み、血まみれとなったこどもたちを呪い、エクスカリバーを押しこんでくる牧村少年の髪を掴み上げた。
洋一は意識を遠のかせながらも思い出していた。それはこれまで出会ってきた人たちのことだった。男爵の言うとおりだ。これまでどれだけの人に育てられてきたことか。洋一はともだちのカッツンや、学校の先生や、街の駄菓子屋のおばさんも、ホームセンターの店員のお姉さんも、そして、なにより両親のことを思い出していた。その人たちのために死んじゃ駄目だと彼は思った。彼は一歩また一歩と、わずかずつ、けれど着実に足を踏み出していく。モルドレッドはそのたびに苦悶の呻きを上げ、血を吐き、かつ彼を殴りつける。洋一は急に団野のことを思いだし激昂した。殴られるのならもう慣れた。なにをしたってきかないぞ
「死ぬ覚悟ならしたってもう言っただろ! お前の方こそあきらめろ!」
「くそ餓鬼め小僧め、五百年生きつづけた俺を殺すというか!」
彼は日本刀の刃に切り裂かれ、右の目玉を地に落とす、中途から切れた右腕からは噴水のように血が噴き出している。傷はあちこち塞がろうとするものの、太助が狂ったように刀を回して、新たな傷を作りつづける。
「こいつら、俺に逆らうか! 剣を抜け! 下がれ小僧!」
モルドレッドは洋一の腹を打った。その後頭部に鉄槌を振り下ろした。洋一の意識はまた遠くなる。内臓がひしゃげるほどの痛み、それにも彼は良く耐えた。けれどもう限界だ。
「洋一、死ぬな洋一!」
太助は洋一を救おうと、とっさに刀を下げた。真下から伸び上がるようにして剣を突きだし、父のお返しとばかりに、モルドレッドの喉首から脳天を貫かした。
モルドレッドは血走った目で少年らを見た。その喉からは声は立たず、ゴボゴボという血泡の音がした。洋一はほとんど意識をなくしながら、モルドレッドの体から赤子たちが抜け出してくるのを感じた。洋一はさらに一歩足を踏み出してエクスカリバーをモルドレッドの体に突き立てた。
「がんばれ、洋一、体を立てろ」とアーサー王は言った。
「無駄な抵抗をするな! 死に絶えろ、小僧!」とウィンディゴは言った。
洋一はウィンディゴが彼の精神を捕まえにかかるのを感じた。洋一の意識が薄らいでいるのを利用して体を乗っ取ろうというのだ。させるもんか、と洋一は思った。ぼくは本の世界を守ってきた一族だ、父さんに代わってぼくが本の世界を守るんだ――
「エクスカリバー、こいつをこの世界から追い出してくれ。こいつと本の絆を断ち切るんだ」
と彼は言った。エクスカリバーはさらに輝きを増した。アーサー王が死者の世界からさらに力を送りこんでくる。洋一がまた一歩踏みだす、モルドレッドに近づき右腕が屈曲する。アーサー王はその隙間を利用した。聖剣をねじり、モルドレッドの心臓目がけて突き入れていく。
聖剣が食いこむたびにモルドレッドの傷口からは赤子たちの魂が抜け出ていく。モルドレッドは首を仰向け、天を仰ぎだした。もう全身の穴という穴から血が流れている。聖剣の輝きが聖杯の力を押しのけ心臓を焼いた。復活しない。細胞たちはそのまま死につづけた。復活しない――聖剣の傷口は塞がらなかった。モルドレッドが身を起こそうとするままに洋一の体に被さったときには、古代より生きつづけ、無用の死を生み出しつづけた男はついにその命脈を途絶えさせていた。そして、ウィンディゴの断末魔が――
「牧村! 忘れるな! わしがこの世界を去ってもお主との勝負が終わったわけではないということを!」
洋一はモルドレッドの重みを支えられない。暗黒の王とともに倒れた。ウィンディゴの絶叫が聞こえた気がした。太助の声も。洋一は確かに微笑んだ。
牧村、だって。あいつようやくぼくのことを認めたな……。
そして、視界は暗くなり、意識は遠のいていく。
○ 5
牧村洋一は夢の中にいた。けれど、そこはウィンディゴのもたらす闇ではなく、輝くような純白の世界だった。洋一はアーサー王の声をきいて目を開けた。
そこはシャーウッドの森だった。モーティアナに破壊される前の森の姿だ。雨が降った後なのか、森はしとどに濡れていた。ひどく幻想的な風景だった。アーサー王は彼のすぐ側に立っていた。疲れたな、ひどく疲れたと洋一は思った。夢の中なのに、もう指一本すら動かせない。苦痛のない世界ではあったが、彼にはいささか居心地が悪かった。
「よくやったぞ洋一」
「アーサー王、モルドレッドは死んだの……?」
「ああ、我が息子は死に絶えた」
「ウィンディゴは?」
「やつもこの世界を去ったようだ」
洋一は微笑んだ。
「ぼくらやったんだね……」
「ああ、やったとも」アーサー王はしゃがみこみ、涙に濡れた洋一の頬を拭った。「だが、お主の人生は、俺とちがって、まだまだ苦難に満ちているようだな」
「アーサー王だって、アヴァロンの暮らしを捨てて来てくれたじゃないか」
アーサーはニヤリとこどもっぽい笑みを見せた。
「人は退屈よりも困難を求めるものさ。お主もまたそうなのかもしれん。そして忘れるな。自分が困難に真向かい乗り越えることの出来た人間だと」
アーサー王は立ち去った。首を向けた洋一が見たのは、アーサー王を迎えにきた円卓の騎士たちの姿だった。トリスタンがランスロットが、彼に向かって手を振った。洋一は微笑んだ。
洋一はアーサー王の言葉になにか応えようとした。けれど、彼の意識は酩酊状態のようにぐるぐると回りはじめ、それで昏倒したときとは逆に夢から覚めていったのだった。洋一は、いますぐに目を覚まさなければならないと知っていた。深い意識の底にいながら、大事な友人が悲しみの底にいてひどく困っていることを知っていたからだ。
○ 6
洋一が目を覚ましたとき、頭上を真っ黒な人魂がいくつも飛び交うのが見えた。視界は眩んで吐き気もした。実際に横をむいて胃液と血を吐きだしたが、おかげで目はふだんどおり見えるようになった。明星の大空を舞うのはモルドレッドの残した五百の魂たちだった。まるで猛烈に回転するドーナツみたいだ。
モルドレッドは死に、ウィンディゴの魂も去った。赤子たちは行き場をなくして泣き叫んでいる。この世を悲嘆と憎悪の絶叫が満たしている。赤子たちは生存者を憎むようにその身めがけて突進する。ロンドンでようやく生き残った人たちも、魂が身を通りぬけるたびに、内臓を毒す悪寒を感じ、生命力を吸いとられていった。それは、父親の手を握り悲嘆にくれる奥村少年もおなじだった。彼は赤子の魂が身を貫くたびに身をのけぞらせている。その体には死の亀裂がいくつもあらわれている。
洋一は、自分には赤子の霊が影響しないと感じていた。赤子たちが彼の体を通り抜けても、呪いが彼には生じなかったからだ。結局は、アーサー王の言うとおりらしかった。なにが原因なのかはわからない。けれど、彼は霊という霊に強いようだ。
洋一はヒビの入った肋に顔をしかめ、二倍にふくれて、血の流れる顔面に苦しみながら地面に腕をついて身を起こした。口の中で舌が膨らんでいる、なんども嘔吐いた。赤子の悲鳴に街中が満たされる中、太助! と友人の名を呼んだ。太助が涙にくれた顔を上げた。その顔は死の呪いに半分方覆われている。
「洋一、父上が……」
「太助、大丈夫なんだ……」と呂律の回らぬ舌でいう。「エクスカリバーだ、エクスカリバーの鞘だよ! あの鞘には傷をいやす力があったじゃないか……!」
それは、アーサー王の最後の贈り物めいていた。太助はわかっていると答えた。その顔は希望に満ちていたが、魂がまた身をつき抜けて、父親の体に突っ伏する。奥村の体からはまだ黒剣が立っている。出血を恐れて剣が抜けないのだ。洋一は自分が鞘を取りに行くしかないと感じた。アジームたちも赤子にやられて立つことができないでいたからだ。
洋一はちびのジョンが鞘を拾ったかも知れないと考えた。必ずそうしたはずだ。鞘がなければ、いまごろロビンは死んでいる。モルドレッドの死とともに、死兵からは悪霊が抜けて元の死体にもどっている。洋一はロビンのそんな姿など見たくなかった。死人ならもうたくさんだ。
洋一はくじいた足を引きずり、鼻血にフガフガと息をし、まるでノッティンガムで見たゾンビのようにヨタヨタとロビンの元を目指した。生き残った騎士たちも、みんな死の呪いにやられて死にかかっている。赤子らの力はどんどん強くなってきている。このままではみんな無駄死にだ。
「ジョン!」
と洋一は呼んだ。ちびのジョンはロビンの側でうつぶせに倒れている。洋一の声に気づいて顔を上げた。洋一はフラフラとジョンの元に行き、顔のそばに膝をついた。
「ジョン……」
しかし、屈強のヨーマンも死の呪いには勝てない。亀裂に唾を垂らして苦しんでいる。
「ジョン、しっかりしてよ。こいつらをどうにかしないと……」
「洋一……」
とジョンは洋一の腕に手を伸ばす。死の呪いに覆われた腕はすごく冷たい。亀裂から噴きだす黒い気体も。ジョンは急速に死につつある。洋一の身内はゾオッと冷えた。
「確かにこのままじゃみんなくたばっちまう。でも、こいつらが悪いだなんて俺には思えねえ。こいつらを救ってやりてえんだ。こいつらは赤子のうちに殺されたんだぞ。このまんまじゃ、かええそうだ。かわいそうだと俺は思うんだよ……」
「でも、どうすりゃいいのさ!」と洋一は癇癪を起こした。「こいつらをみんな鎮めるなんて、ぼくには出来ないよ!」
洋一は胸を抱える。自分は本になにかを書きこむべきなんだろうか? でも、Goサインは出ていなかった。それに彼にはなにか引っかかることがあったのだ。
それはロビン・フッドだ。ジョンの脇で気絶しているロビンには、死の呪いがまったく発生していない。
「ロビン!」
洋一はロビンの肩を揺すった。ロビンのベルトには金色の鞘がさしてある。ジョンが拾ってロビンの腰に戻しておいたのだ。ロビンの胸元は真っ赤に染まっているが、衣類の下の傷はすっかり塞がっている。
「傷が治ってる」
洋一は鞘を抜きとってみた。無限の治癒の力が働いたのはその瞬間だった。彼は驚いて両手を見おろし、顔に触れた。骨の砕けた激痛も、肉の裂けた激痛も、内臓の死滅した激痛も、みんなまとめて引いていった。まぎれもなく、鞘の力だった。モルドレッドがエクスカリバーを持つアーサー王を殺せなかったのもうなずける。鞘の力は、洋一の細胞を活性化させ、だけでなく、死んだ細胞も蘇らせていた。呼吸とともに、復活の力が出入りしている。それは身内の六十兆個の細胞に、すみやかに行き渡る。内臓や首の痛みが退くと、彼は胴体を真っ直ぐに伸ばせるようになった。生まれたてのように快調だ。それで気がついた。ロビンもアーサー王の力を受けていたのだ。彼は王権を委譲されている。それは今もだ。赤子たちの呪いにかからないのもそれならば説明がつく。自分の元からはアーサー王は去ってしまったけど、ロビンなら――
「ロビン、起きて! 起きろ、こいつ!」
と洋一はロビンの肩を揺すった。ロビン、ロビン、と名を呼んだ。ロビンはおとなしく揺られるばかり。眼を開けない。洋一は最初は慎重に、やがては力任せに揺すりだした。
「ロビン、目え覚ませ! こいつらを死者の世界に送るんだ! そうだよ、ジョンのいうとおりだ! みんな行き場をなくしてるんなら導けばいいじゃないか!」
ああ
とロビンが痴呆のように力のない声を発した。洋一はロビンの顔をつかんだ。顔をうんと近づけて、瞳を覗いた。目玉の奥のその奥にアーサー王がいる気がした。
「アーサー王、力を貸して。こどもたちを導きたいんだ。元々はあなたが命じて殺したんじゃないか! 責任をとるべきだよ!」
「あいつが閉じこめていた魂か」とロビンの瞳が動き、天を見て言った。二人はともに驚いた。ロビンの右腕が勝手に動き、側に落ちていたトリスタンの弓を拾い上げたからだ。
「弓を使えばいいの?」
と洋一はアーサー王に訊いた。
「弓で導けとでもいうのか」ロビンも戸惑っている。彼は洋一と目を合わせて、「だが、死者の島などどこにある。どの方角だ」
そのとき、無数の魂がロビンと洋一の体をすりぬけて、二人はわっと喚いて突っ伏した。
「くそ、こんなもの喰らいつづけていたら、身がもたんぞ」
実際、ちびのジョンはすでに意識をなくしている。洋一は、
「ロビン、死者の島はこの世界にはないんだ。あのときは本が導いてくれた。きっと方角なんて関係ないんだよ」
ロビンは途方にくれて天を仰いだが、顔を戻したときには何事か決心したようだった。わかった、と彼は言った。
「アーサー王を信じよう。彼はこの子らのことで確かに心を痛めていた。俺には分かるんだ。洋一も、そう思うだろ?」
洋一は力強くうなずいた。一時はあの人と一体となったのだから当然だ。アーサー王の気持ちなら嫌というほど知っている。モルドレッドに抱いた、憎しみと愛情のことも。贖罪の意思も。
「アーサー王!」とロビンは身内に語りかける。「俺にもう一度力を貸してくれ。今こそ借りを返すときだ。赤子たちを導いてくれ!」
ロビンはトリスタンの弓を支えに立ち上がる。天を舞う狂った魂どもに呼ばわった。
「赤子らよ! 昔日に死に絶えし不幸の子らよ! 話を聞いてくれ! 俺はこれよりこの弓で天を射る! 汝らの苦しみも、不幸な旅ももう終わりだ! さまよえる子らよ! 戒めはとかれたと信じよ! 恨み言があるならば、あの世でアーサー王にいうがいい! だがここはお主らの居場所ではない!」
赤子たちは発狂したように飛び狂い、ロビンと洋一の邪魔をした。死の呪いは黒雲となり、地上の嵐となり、二人をのみこんだ。洋一はロビンの右足にしがみついた。ロビンはただ無心で足を開いた。これまでの過去、何万回とそうしてきたように、両腕を四方に開く。この地上で最も美しく弓を射る男は、今一度強く弦を引いた。
ロビンが天に向かって矢を射ると、その矢は黒雲を消し飛ばし、一条の光となってどこまでも高く上っていった。弓矢の残した軌跡は光の帯となり、周囲の死の空気を取りこんで、どんどん太くなっていく。ロビンはつづけざまに矢を打った。矢は光の尾を引きながら天をつん裂き、雲へと吸いこまれていく。天が割れた。矢は消えたが、金色のカーテンを残していく。
その漏斗状の光は、死の呪いを吸いこみ、地上には激しい風が起こった。洋一は身を屈して伝説の書をかばい、どうにか天を仰いでいた。ロビンの真下からだと、それは光で出来た道路に見える。ロンドン中を飛び交っていた魂が一つまた一つとロードの中へ吸いこまれていく。その間もロビンは必死で弓を射つづけている。赤子らにはロビンを憎み、いまだ攻撃する者たちがいた。だが、その者たちも、ロビンの魂に触れ、その奥にいるアーサーの心情を知り、次第に数を減らしていった。ロビンは何百回と矢を撃つつもりだった。トリスタンの矢は、その期待に応えて、次々とロビンの手の内に現れたが、彼ももう限界だった。ロビンはぜいぜいと荒い息をつき、さも重そうに弓を下ろした。彼が光道を仰ぐと、その光はなにかを感謝するようにロビンの顔を撫でた。ロビンは疲れ切った顔でうっすらと笑った。そのまま仰向けにばったりと倒れてしまった。洋一はロビンの側に這い寄った。呪いの雲は消えている。
「さあ、洋一。奥村を助けに行ってこい。赤子らはもう大丈夫だ」
「うん」
と洋一は返事をしながら天を見た。光の道は最後の赤子を取りこむと、その端から氷が溶けるような自然さで闇の中へと還っていく。
洋一は走った。彼が走るたびに太陽からは月が除かれ、地上をさす光糸は増えていく。洋一は日溜まりの中を飛ぶように走った。地上に次々生まれる影を追い抜くようにして彼は走った。奥村の元では死の呪いの解けた奥村太助がいまだ父に取りついて、洋一早くと叫んでいる。
二人はもどかしげに奥村の帯をひっぱると、大刀と脇差しの隙間にエクスカリバーをねじこんだ。
「利くのか……」
と太助は不安げにつぶやいた。でも、あれほどボロボロだった洋一が、走れるほどに回復している。彼は意を決して立ち上がると、黒剣に手をかけ呼吸を整えた。洋一は奥村の体が揺れないよう肩を押さえた。
「いくぞ」
「うん」
太助は呻きを上げながら、父親を戒める呪いの剣を慎重に引いた。締まった肉が抵抗し、太助は傷口を広げないよう注意深く剣を抜き取っていく。
洋一は黒剣の抜ける側から奥村の傷口が塞がっていくのを見た。黒剣は血の一滴すらついていない。
「いいぞ太助! 治ってる治ってるよ!」
太助は黒剣を引き抜くと急いで跪いた。「父上!」
おじさん、と洋一も言った。
「おじさん、死んじゃだめだ。ここまで頑張ったんじゃないか! みんなでそろって帰るんだろ!」
傷つき、あるいは勝利に浮かれる騎士たちも、こどもたちの様子に気づいてやってきた。アジームも、アラン・ア・デイルも、ウィル・ガムウェルらも。ロビンにジョンも。タックにミドルもやってきた。こどもたちの周囲には人だかりが出来ていた。みなこどもたちの父親が蘇るのを祈っている。
太助は自分が死にかかったとき、父親がどんな思いをしていたかを知り、申し訳なく泣けてきた。父にその罪を謝りたかった。洋一のおかげで親より先に死ぬ愚は犯さずにすんだ。けれど、父がこの世からいなくなるには彼にはまだ早過ぎる。教わることも、見てほしいこともまだまだあった。なによりも彼は父の声が聞きたかったのだ。
奥村が一声呻いて目を開けるともうだめだった。太助は父の胸に突っ伏し大声を上げて泣きはじめた。
ちびのジョンが、ほっと胸をなで下ろしている洋一の胸をつかんで、手荒に宙高く放り上げた。ジョンは落ちてきた少年を力任せに抱きしめるとグルグルと回りはじめた。初めは痛いやめてと言っていた洋一も、そのうちに大声を上げて笑いはじめた。
それは呪われた都に響く、実に久方ぶりの笑い声だったのである。
◆ そして、エンドマークの鐘は鳴る
ロビンとちびのジョンが臨時政府のあるノーフォークに戻り、ヘンリー王太子にすべてを報告したのは、それから少し後の話だった。城では宴が催されたけれど、ロビンとちびのジョンはすぐにそこを抜け出して堅苦しい衣服も脱ぎ捨て昔のように乞食よろしく自由気ままな格好をして近くの森で待つ仲間の元へともどっていった。そこでは仲間たちが昔日のシャーウッドがそうであったように、森で鹿をうち、思い思いの腕を振るっては料理をこしらえ、ビールにワインの飲み物に、王侯貴族の食卓にも負けないとびきりのごちそうを持ちよって酒宴を開いていたからだ。ロビンとジョンはすぐにその輪に飛びこんで、苦しいことも痛かったことも、辛かったことも悲しかったこともみんな忘れてしまったのだった。
男も女も老若も、すべて等しく朗らかに、笑声を上げ人生を称えこの一時を楽しんでいる。こうでなきゃならねえ、とちびのジョンは腹の底からそう思う。そう思って盛大な笑い声を上げる。ロビンと俺のまわりはこうでなくちゃ。こうでなくちゃなんでみんなが集まるもんか。人間は楽しいことしかしたくねえのだから。ちびのジョンは喜びと嬉し涙をかみしめる、気持ちに一区切りがつくと大きな足音を鳴らして踊りの輪に加わる。
その宴の最中、ずっと走り回っていたのは二人の少年たちだった。男爵も元気になった。すべてが元通りだった。もうウィンディゴの心配もない。
洋一と太助は初めて出くわす盛大な酒宴に驚き喜び、夢中で走り回っていた。その騒ぎにもいつか疲れて、いつの間にか樫の根元に二人、思い思いの食料を掻いこみ座りこんでいた。洋一は大きな葡萄をつまんでは口に運び、太助は幹にもたれて、ワインをちびちび。生まれて初めてのほろ酔い気分でいる。騒いでいる騎士たちの姿が見える。ギルバートら堅苦しい人たちも、この騒ぎに参加していた。ああ、ロビンやジョンも見えた。みんな本当に楽しそうだ。この世界に来ていろいろと苦労もあったけど、最後はこんな風で良かったと彼らは思う。ハッピーエンドにもいろいろあるけれど、ロビン・フッドの物語の最後がこんな具合で彼らは満足した。悲しみも冒険ももう十分だし、それもみんな帳消しになった気がした。
そして、二人はいつしか仲の良い本当の兄弟のようにして眠りこんでいたのだけれど、その夢から覚めたのは奥村と男爵が緊迫した顔で側に来ていたからだ。二人とも慌てた様子で少年たちの肩を揺り動かし目を覚まさせようとしている。
「お前たち急げ」
とすっかり元気になった男爵が言った。彼は宴のせいかまた十歳ばかり若返ったようだった。
「エンドマークの音じゃ。もう物語は終わってしまう!」
「エンドマーク?」
と洋一が訊いた。二人は耳を澄まして聴いた。太助がこう言った。
「本当だ。鐘の音がする」
「物語が終わりに近づいておるんじゃ。我らはもう去らねばならん」
ミュンヒハウゼンの言葉に二人はいっぺんで目が覚めた。よく見ると、周囲の景色は薄れて白っぽくなっている。洋一は自分の目が白内障にかかったのかと思ったが、男爵と奥村の姿はよく見えた。
「もう行くの? みんなとはこれでお別れ?」
と彼は訊いた。男爵は厳かにうなずいた。洋一はエンドマークの音に耳を澄ました。その音は鐘の音のようでもあり、太鼓のざわめき、オーケストラの潮騒のようでもある。ざわざわと心をくすぐる素敵な音だ。それは物語が素敵な終わりをしようとしているからだと洋一は思った。
男爵は真剣な顔で洋一の顔をのぞきこんだ。
「みなに別れを告げる暇はないぞ」
洋一は名残惜しさを一瞬顔に見せたけれど、次の瞬間にはさっぱりとした顔をした。
「いいんだ。みんなとはたくさん話をしたから」
太助も森を振りかえった。
「本当に良くしてもらった。素晴らしい本だった」
二人の少年はいつのまにか手を取り合っている。そして、寝静まる仲間たちの光景、この世界で見る最後の景色を視界に納める。洋一は言った。
「これでいいんだ。だって全部丸く収まった。別れの挨拶なんてしたら、ハッピーエンドも台無しだよ」
「いいのか」と男爵は訊いた。洋一は森を見たまま答えた。
「うん。最後は笑顔でおしまいにしたいんだ。昔読んだロビンの最後は悲しかったから。今度の本はこれでおしまいにしたい」
「洋一がいいんなら、ぼくも文句はないよ」
と太助が言った。
「えらいぞ、二人とも」
と奥村。
四人が同時にふりむくと、そこに物語の世界はなく、外へとつづく真っ白な道が延びていた。洋一はその道を歩きはじめた。その道は色のない割りに固い感触で、高い靴の音がした。やがて四人の歩く道はなくなり、彼らは真っ白な世界をふわふわと飛び歩くようになった。エンドマークの楽曲は高らかに鳴りつづけた。
ロビンの物語はこうして幕を閉じた。けれど、牧村洋一と仲間たちの冒険はまだまだつづく。けれど、それはまた別のお話。別の機会に物語るとしよう。何事にも幕引きはあるし、そうでなくては次の話は始められない。物語はまだたくさんあるし、それに物語を紡ぐ口もまだまだたくさん残っている。
ともあれ、この物語がこれで最後でないのは喜ばしい。洋一少年はこどもだし、こどもは駆け回るのが大好きだ。物語を駆け回る少年の姿はいつだって魅惑的だから。
語ったことは多いけれど、語り残したこともまた多い。
それでは、物語の幕がまた開くその日まで。
ご覧になる方が、たくさんあると、いいのだけれど。
◆ お し ま い