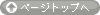�u�˂��܂����E�̖`���v�ւ悤����
���̃y�[�W�́A�l�b�g�ŏ�����ǂ܂����p�ɗp�ӂ��܂����B
���ҁA�Z�҂Ƃ��낦�Ă��܂��B�Â���i������̂ŁA�ł��ɂ͖ڂ��Ԃ��Ă���Ă��������B
�˂��܂��O������A��낵���I
�˂��܂����E�̖`��
����l���@�˂��܂����E����
���@�͑O�@��Z��Z�N�@�\�\�˂��܂����E�@�����\�l���@�ߑO�㎞�\�l���\�\
���@�@����B�Y�A���������
���@�@�@�@��
�@�V���͎���̃��O�n�E�X�Ŗڂ����܂����B���̏�ɁA���Ԃ��œ|��Ă���B�̂̐߁X���ɂށB��������߂Đg�����������B�Ȃ�ł���ȂƂ���ŁA�Ƃ��Ԃ��������A����Ƃ��Ă���Ђ܂͂Ȃ������B�`���̎o�Ɖ��̗T�����A���O�n�E�X�̃K���X����͂����ς��@���Â��Ă�������ł���B
�u�o����A�ǂ������H�v
�@�V���͂���ĂČ����J���ɂ������B�ق����Ă�������A�K���X�����肩�˂Ȃ��������B
�@�`�o�̎j�b�́A�|���悤�ɒ��ɂ͂���ƐV���̘r�����B
�u�B�Y�ɐԎ��������̂�I�@���W�ߏ�������������������ς����Ă�I�@���̂ЂƁA�E���ꂿ�Ⴄ��I�v
�u�ȂɁH�v
�@�V���̋^��̌��t�����������ɗT�����吺�ŋ����͂��߂�B�j�b�͗T��������Ă��₷�B
�u���W�ߏ�H�@�Ȃɂ������āc�c�v
�u���܂܂ł��Ȃ������̂��s�v�c�������̂�B���̐l�A��R��������A�����ɂ͂���������Ⴂ���Ȃ��̂Ɂv
�@�^����Ƃ��Ă���Ђ܂͂Ȃ������B�V�����\�ɂƂт����ƁA�J�[�L�F�̌R���炵���̂������j�������A�吨�B�Y�Ƃ̌���ɂ��܂��Ă���B���ɋ��������̂͂ЂƂ̌��t�������B���E�͂˂��Ȃ����Ă���c�c�B
�u�V���A�Ȃ�Ƃ����Ă���āI�@���̐l���E�����Ȃ��ŁI�v
�u��l�Ƃ��A�����ő҂��Ă�I�v�V���͋삯�����Ȃ��炢�����B�u���������Ă�I�@�N���Ȃ��ɂ����ȁI�v
�@�j�b�����Ȃ����̂��m�F����ƁA�V���͏����������������B�B�Y�̉Ƃ̂܂��ɂ͌��������łȂ��A�u�̉��ɂ��ޏZ�����吨���܂��Ă����B�ނ͏Z���̌��������킯��ƁA�����̂���l�_�ɂ����Â����B
�u�Z�M�I�v
�@�B�Y�͌����ɘe���Ƃ��āA�͂��т������Ƃ��낾�����B�C�₵�Ă���̂��A��������Ƃ��ނ��Ă���B
�u�ȂI�@�����܁I�v
�u�܂Ă�A�Z�M���ǂ��ɂ�Ă��C���I�v
�u�Z�킩�B������݂�v
�@���N�̌������A�V���̂܂��Ɏ������������B�j�b�̂��������W�ߏ����B�ł��ł��Ƃ������q������A�����ɂ́A����{�鍑�Ɠ悳��Ă���B�ނ͕�R����ʂ����ŁA���ƌ��ւɂ͂�ꂽ�Ԏ����݂���ׂ��B
�@���������͏\�l���肢��B�r�͂������j���A�V���̌��������̂��A
�u����ł킩�����낤�B�ǂ��A�����܁I�v
�u�҂Ă�I�@�Ȃ�Ȃ��܂���́I�@�Z�M���ǂ��ɘA��Ă��I�v
�u���̒j�͒��������ۂ����I�@�������ۂ͏d�߂��I�v
�u�n���Ȃ��Ƃ������ȁI�@�����Ȃ�Ă��͂��܂����I�v
�u�n���҂��I�v
�@�r�͂̒j�́A��ɂ����R�_�ŐV���̂��߂��݂��������B
�u��O�鍑�́A�������ĂĂ����܂ŗ��Ă���̂����I�@���̑���Ȃ���ɁA�����܂�Z��͒��������ނ��肩�I�v
�@�|�ꂱ�V�������͂�������݂�ƁA�W�܂��Ă���̂͏��V�l���肾�����B
�u��O�鍑���Ɓc�c�v
�u���{�鍑�̒j�q�Ȃ�A���܂ꂽ�Ƃ����獑�̂��߁A���̂��߂ɁA�����Ȃ������o�傪�ł��Ă���͂��ł���I�@����������܂�Z��́A���̔N�ɂȂ�܂ł̂��̂��Ɖ߂��������肩�A���������ނȂnj��ꓹ�f�ł���I�v
�@�V���͂��U�炵�Ă�߂��r�͂̒j�����߂��B�C�������Ă���̂��Ǝv�����B�ŏ��̂����A�\�l�̌����݂͂ȔN�V���Ă݂����̂����A����͕E�₵�Ă�������ŁA�悭����ƁA�݂ȓ�Z��ɂȂ邩�Ȃ�ʂ��̎Ⴓ�Ȃ̂������B
�u�䂪����{�́A�ꍑ�ɂȂ낤�Ƃ��A����A�ꕺ�ɂȂ낤�Ƃ��A��O�鍑�ɂ��炢�������ł���I�@�����܂炪��������ނƂ����̂ł���A�鍑�l��̐l�ޖ��E�v��ɗ^������̂Ƃ݂Ȃ����I�v
�u�����I�v
�@���������B
�@������݂�ƁA�l�_�̏��������܂Ȃ���ɋ���ł���̂������B�ނ�������ɕv��Ƒ����Ƃ�ꂽ�̂��B
�@�V���͂Ђ������ƂȂ�i�����B
�u�܂��Ă���B�b�������Ă���A��O�鍑�Ȃ�āA����Ȃ��̂̑��݂́c�c�v
�u����������ɂ���I�@�����܁I�v
�@�j�͐V���𑫂���ɂ��A�����|�����B�r�͂͌R�_�ŐV��������͂��߂��B
�u�鍑�ɂ���Ėł��E�̉p��ɂ�т�I�@�鍑�Ɛ킢�A�l�ނ��܂��낤�Ƃ��镺�m�����ɂ�т�I�@�����܂̑̂ɘA�ȂƂȂ�������{�̉p���ɂ�т�I�@��c�ɂ�т�I�@�e�ɂ�т�I�@�����̎q�ǂ������ɂ���܂�I�v
�@�V���͂��͂�|��ӂ��A��R���ł��Ȃ������B�j�̖_�ꂪ�ӂ肨��邽�тɁA�n�ʂ̏�œ����͂˂��B
�@�����ނ̓������݂����A���Ɉӎ������̂��Ă����B�Q�O�́A���A�ƌZ���l�|���A���Ɩ\�͂ɋ����̗Y���т�������B
�@�̂������d�������I���āA���悢��R�ɂ̂肱�����Ƃ��Ă�������������B����͂���ȂƂ���ŁA���������ɎE�����Ȃ��A�Ǝv�����B�\�z�ǂ���A���̎��̗��R�Ƃ͂킯�̂킩��Ȃ����̂������B�����ǁA��邢���̂ł͂Ȃ��A�C�̋������ӂ��̐l�ԂɎE������Ȃ�A����������Ԃ�܂��Ȏ��ɕ������Ȃ��A�ƐV���͍l����B����ȂƂ��A�l�_�̂�����ŁA���X���S�Ɣ�ђ��˂�Ȃߑ��Y�̎p���A�ڂɂƂ܂����̂������B
���@��́@�i�o�z��
���@����ܔN�@�\�\���܂��肳�܂ɂ�
���@�@�@�@��
�@�q�ǂ������͂Ȃɂ��ɒǂ����Ă���悤�ȋ}�����������B�ڂɂ���̂͐^�����Ȗ��������B�ꍏ���͂₭�т��ʂ���悤�A��̂߂�Ȃ�������B�}�t�ɂق�������������A�����⎀�̂ɑ����Ƃ�ꂽ�B�A�蓹�����ǂ�Ă���̂��A�S���킩��Ȃ��B
�@�Ƃ�����A�����̂����~��ɂł��킵���B��̂悤�Ȉł��A���邭�Ȃ�B��������Ă����B�B�Y���j���Ȃł镗�ɋC�������Ƃ��A�݂�Ȃ̖ڂɓ�����ł��閠�Ԃ��݂����B�������Ȃ����ƂɋC�Â����̂́A����ς萙�Y����q�������B
�u���́H�v
�@�B�Y���ӂ�ނ��B���ɂ������Ă����͂��̗����A�p�������Ă����B
�u�͂��ꂽ�̂��H�v
�@�����́A�����Ȃ��̂��H�@�Ɠr���ɂ���ČJ�肩�����B
�u����ȁc�c�v����q�͕�R�Ƌ��Ɏ�����Ă��B�u�������������̎q�����Ă���������́H�@���̎q�킷��Ă���������́H�v
�@�B�Y�݂͂�Ȃɋ}���Ŏ���Ȃ������B�ނ�͈�l����Ȃ��ɂȂ����B���̗͂͂̂����Ă���B�ł��A���������B���̂��Ƃ��������Ȃ��B
�@�݂�Ȃ͈ӎ��̐G����̂��A�X�̂��������������������A���̋C�z�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B
�@�B�Y�͕�R�ƐX��������݂�B�u�����ւA�����Ƃ�ꂽ�c�c�v
�@�ނ�͗�����������ĂĈ����������B���͒��������݂����ɁA�����Ƃ����ԂɂȂ��Ȃ����B���̂��Ȃ��B�����͂������܂��肳�܂ł͂Ȃ������B���̕s�v�c�ȃW�����O���͏������B�ӂ���̎G�ؗтɂ��ǂ��Ă����̂��B
�@����T���Ă�����܂��Ԃ��A������͂Ђǂ��Ȃ����������B�ނ�͂��Ȃ�̋������������������B�吺�ŗ����Ă��A���͂���ɋ�������ŁA�Ԏ��͂Ȃ��B�B�Y�����͂��̎G�ؗтɁA�������Ȃ����Ƃ��m�M�����B���܂��肳�܂Ɏc���Ă����̂��B
�u���߂��A���ǂ�Ȃ��I�v
�@��������]�����悤�ɋ��B�ނ͉����d���������܂܂��B�B�Y�͂���ɋC�Â��Ď����̃f���`�̖�������������B�������܂˂����B
�@�^���Â������͂��̗т́A�����̖�������Ƃ���ǂ��Ă����B�M�C���ǂ��ƏP��������A�ܐl�͊������ɂȂ��Ă���B
�u�����Ƃ���������Ƃɖ߂����B������A�����������ɂ��̎q���������Ȃ��C����v
�@����q�͔��ׂ��Ńq�X�e���[���N���������Ă���B�щp���r���Ƃ낤�Ƃ������A�ޏ��͂��̎���ӂ�͂炢�A�݂�Ȃ��痣��Ă��܂����B����q�͎����������݂��Ă��݂����ȋC�ɂȂ����B���̂��Ƃ��v���A�ޏ��͋������B
�@�B�Y�͂܂�����A����q���݂��B�����̂����ėт��o��Ȃ�āA�[�����Ȃ��ɂ������Ȃ��B�ł��������ق����A��l�̏���������B���������́A�����ӂ��̎q�ǂ��ɖ߂��Ă���B���̏؋��ɁA���o����݂Ȃ��Ȃ��Ă���B
�@�B�Y�́A���܂���Ȃ���C�������B�����������M��������A���o�͌��������Ă������B����ȋC�������B�ł��A�����M������������Ȃ��B�w�g�w�g�ŁA�킸���Ȉӎu�͂����Ȃ��Ȃ��Ă����̂��B
�@���܂��肳�܂̊O�ɂ͑�l������B���̂Ƃ��͗l�q�����������������ǁA�ł����Ȃ�c�c
�u�݂�ȊO�ɂł悤�v
�u���͂ǂ�����̂�I�v
�u���ꂽ������݂���Ȃ��A�������Ȃ��B�{��������Ԃ����Ȃ�����v
�u�B�Y�����܂������Ă��c�c�v�Ɖ���q�͌������B�u�����������ɂ݂����Ȃ���Ȃ�A��l�ɂ����Č����������Ȃ��B�����ė��͂��܂��肳�܂ɂ����A�����ɂ͂��Ȃ��́B���ꂪ�킩��Ȃ��I�v
�@�B�Y�͂����Ƃ��܂����B�������������̂��A����q���������̂��A�����킩��Ȃ��Ȃ����B
���@�@�@�@�O
�@���̂���A�����ƐV���́A�����������āA��݂����ɕ����܂���Ă����B�����Ǝ��C���A��l�̏��w���̗̑͂������B���̂��Ȃ��Ȃ����Ƃ͂����A���������܂��肳�܂Ȃ̂ɂ͂������Ȃ��̂��B�ǂ����ɂ��̃W�����O���ɂ�����ʘH������͂����B���������ɂ́A���̒ʘH����������Ǝv�����B
�@�ނ�͎Ζʂ��̂ڂ����B�ڂ̑O�ɖ��Ԃ��݂����B����ڎw���Ă����͂��Ȃ̂ɁA���̂܂ɂ������������Ă��܂����炵���B
�u�������A����v
�@�V�����w�������B���Ԃ̑O�ɁA�N�����|��Ă���B�V���́A�����A�Ƌ삯��肩�������A�����ɑ������߂��B�삯���������ɂȂ�\�\�₪�ĕ����Ĕނ͗����~�܂�B
�@������Ȃ��A����͎��̂��B
�@�Ԃ�Ԃ�Ƃ����n�G�̉H��������B����ɂ��̂��������L���B
�@���̐l�����Ă��镞�ɂ́A�݂��ڂ����������B
�u�������c�c�v
�@�ƐV���͌������B
���@�@�@�@�l
�u�����A�����ւA�݂�ȗ��Ă����I�v
�@��������������B�Y�Ɖ���q�̎��Ɂi�B�Y�͂������܂��肳�܂ɂ��ǂ�̂͂ނ肾�ƍl���Ă��āA�������q�͂��Ȃ炸���ǂ��͂����ƐM���Ă����j�A�����̐����Ƃǂ��Ă����B
�@�ނ�͂����邨���鍑���̂��ɂ�����B
�@�Ō�̌܃��[�g�����̂����ė����~�܂����B���܂��肳�܂ł͎��̂Ɏ���ӂꂽ�������A����ǂ͖����������B�����̈�̂́A�^�Ă̗z�C�Ŋ��S�ɕ��肫���Ă���B�Ԃ�Ԃ�Ƃ����H���������Ђт��B�Â����邢�L�����B�l�Ԃ̑̂��A����Ȉ��L���͂ȂȂ�āA�M�����Ȃ������B
�@������͍�������𑃔��ɂ��Ă�A�Ǝv���ƁA�V���͓f���C�������B�����̑̂̂Ȃ��ł́A�v���������߂��Ă���̂��B
�@����͂�����������Ȃ��B�щp�͋����Ȃ���A�B�Y�̔w���ɂ������B����q���r�����B
�u�͂₭���Ȃ��ƁA��������ȂɂȂ��v
�@�B�Y�͂������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��������ڂ������Ȃ��B
�@�V�����������B�u��������͂��̂Ƃ�����ł��B������������܂�����v
�@�B�Y�͉���q���݂��B�u���̂��Ƃ������Ȃ��ƁB�x�@�ɂ��点�Ȃ��Ɓc�c�v
�u�����I�v����q���{��A���̐����݂�Ȃ̑̂��т�т�Ɛk�킹���B�u���͂����I�@�����ɂ����I�@���������Ă��Ȃ��I�v
�u�ł��A���ꂽ������A�����ނ肾�I�v
�u����Ȃ��ł�v�Ɖ���q�͌������B�u����Ȃ��ł�A���܂��肳�܂ɖ߂����I�v
�@�B�Y�͂��Ԃ��Ԃ��̎���ɂ������B�݂�Ȃ����������B
�@�ނ�͖ڂ��Ƃ��āA����O�����B�Ȃɂ��������Ȃ������B�ܕ�������A��⊾�������Ă����낤���H�@���������ꂫ���āA�ӎ��̏W�����ނ����������B�]�݂�����J�����ł������܂��Ă���B���̓��������͂́A�̂��Ȃݑr�����Ă����B���͊������Ȃ��B
�u�ǂ������炢���́c�c�H�v
�@�Ɖ���q�͌������B���̐��́A�����Ƃ���r�����ɂӂ邦�Ă����B
�@�B�Y�͑Ë��Ă��������B�ނ͊����ƐV���ɂ������B
�u��l�Ƃ�����������āA���̐e��������Ă�ł��Ă����B����ʼn���q�̂�����ɂ́A�x�@���Ă�ł��炤�B�������Ȃ��Ȃ������āA��������̎��̂��݂������āA�����Ƃ������B�������܂ōs���āA�{������h�����Ă��炦�B���ꂽ������������Ȃ�A�����݂����邩������Ȃ��v
�@�����ƐV���͂��ƂȂ������Ȃ������B�B�Y�̐^���Ȋ፷�����˂��h����݂������B�ނ����āA�����~�����߂ɁA�K���������̂��B
���@�@�@�@��
�@�т��ł���l�́A�Ђ܂�肪�����Ă���̂������B�A�X���`�b�N�͑��ɋ�炢����ꂽ�܂܂��������A���ꂾ���Ăق��̐l�ɂ͌����Ȃ��̂�������Ȃ��B�����ƐV���́A�r�������ĕ��̏L�����N���N���ƚk�����B�����̏L�����A���܂�ɂ����������߂��B
�@��l�͒��ԏ���߂����đ������B�������삯�������Ă���r�Y�Ɠo���q���݂����B
�u��������I�v
�@�������Ăт�����ƁA�q�Y������������B
�u�����v
�@�Ƃ�������͌Ăю̂Ăɂ����A�ӂ���͒|���N�Ƃ����̂ɁB�����ƕK�����������炾�낤�B����Ŋ����ɂ��q�Y�����Ƃɖ߂��Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�u��ςȂA�����тł܂������v
�@��������ɋ����Ƃ��ꂽ�B����܂ł̔ނƂ͂������āA���ɐl�Ԃ炵���\������B�r�Y�͖������Ȃ��Ȃ����Ƃ����āA䩑R�����ƂȂ����̂��B
�u�������A�Ȃ�ł���ȂƂ���ɍs�����́v
�@�o���q����l���Ȃ��������A����������Ă���Ђ܂��Ȃ��B
�u���ꂽ����������̎��̂��݂�����v
�@�r�Y�̖ڂɈӎ��̌������ǂ����B
�u�������āA���̍������H�@���̐l�����̂��H�v
�@�q�ǂ����������Ȃ����ƁA�q�Y�͗тɂނ����đ���͂��߂��B�V�����Â����B�o���q����ɂÂ����Ƃ������A�������̂��͂��Ď~�߂��B���O�r�[������݂����ɓo���q�̍��ɑg�݂����B
�u������A�l���Ă�ł����A���������Ă�ł����v
�u�|���N�H�@����q�͂��̒��ɂ����ł���H�@�тɂ���́H�v
�@�o���q�͊����̘r���Ƃ��Ă������B�ь����J���悤�ȁA�S�C���܂�\������B
�u�����ǁA����������ł�v
�u�Ȃ�ł���ȂƂ���Ɂc�c�v
�@�o���q�͌������B�킽���͂Ȃ�ł���ȏ��Ɂc�c�H�@�Ƃ������t���Â��Ă���悤�������B
�@���܂��肳�܂ɔw���ނ���ƁA�Ԃɂނ����ĕ��������B�����́A��l�Ƃ��ڂ��o�߂���i�Ƃ����Ă��A�����Ă����킯�ł͂Ȃ������̂����j���_�R�ɂ�������A�������낤�ȁA�ƍl�����B�ނ͂ӂ肩����ƁA�����ɂ��ǂ��Ă��邩��҂��Ă��A�ƔO�����B�݂�Ȃ����̎v���������Ƃ��Ă���邱�Ƃ�������B
�@���ꂩ��A�o���q�̌�������đ������~��Ă������B
�@�q�ǂ������͂��̂��Ƃ��A���̎p�����������Ƃ߂����A�݂��邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@���̂Ƃ���A�ޏ��́A���̐��E�ɂ��炢�Ȃ������̂ł���B
���@�W�m�r����O�N�@�\�\�C�j�V�G�̐X�ɂ�
���@�@�@�@�Z
�@����͐�N�������A�����͕S���[�g���������Ă���B�ƈꌬ���͂���قǂ̎������������B����ȑ���A�V�����悤�ɗ����Ȃ��ł���B
�@�X�̂����܂��A�[�g���͂��肻���ȋ���Ȓ������Ă����B�����D���̉���q���݂���A�v�e���m�h�����Ƃ����Ċ�낤�B��n�͑ۂނ��A���܂��肳�܂̌i�F�ɂ��������Ă����B�C�j�V�G�̐X�ƌĂ��A�嗤�̎O���̈���߂�A�L��ȐX���B
�@�тނ������̐��������A�|�̂����܂ɂ����߂��Ă���B���̖ڂ͐l�Ԃ̂悤�Ȓm�������������邤���ɁA��{���ŕ����Ă����B�C�j�V�G�T�}�Ƃ���A���Ɏ����^�����Ȑ������A���Ɏ����N���G�c�{�c�c���ɑ��ʂȓ��������܂��Ă������A�ނ炪�݂܂����Ă���͎̂l�l�̃T�C�|�b�c�̏��N�������B
�@���̂����̓�l�́A�N�Ƃ����Ă����N��B��l�͒������w�ŁA�r�X�R�ƌ������B�ؓ����ŁA�����Ȋ�����Ă���B������l�̓m�[�}�Ƃ����āA�ƂĂ��₹�Ē��g�������B��l�̏��N�̂����̈�l�́A�y�b�N�Ƃ��Ă����B�ƂĂ������Ă���B���̎O�l���M���ŁA�q�b�s�Ƃ������N�������A�������B
�@�T�C�|�b�c�����́A�C�j�V�G�̐X�̐������ɋC�����Ă��Ȃ��B���������͋C�z�����낵�A�l�l�̍s����݂܂����Ă����B�����A�q�ǂ������̗l�q�����������Ȃ�ƁA�ނ�͉B���̂���߁A�g���̂肾�����B
�@�l�l�́A�勾�Ƃނ��������Ă����B�[�g�����������A�ȉ~�`�̋��ł���B��̑������قǂ����ꂽ���́A�ۂ�����Ƃ������n�ɁA�Α�ƂƂ��ɂ������B�ނ�͎��Ǝv���Ă���A�n�b�c�����Ăт������Ƃ��Ă���B
�@��l�̐N�Ɠ�l�̏��N�́A���|�ɑ����߂Ă����B���ł������̒����A���Ⴀ���Ⴀ�Ƌ�����߂��Ă����B
�@�勾�ɂނ����Ă��鏭�N�\�\�q�b�s�͂ЂƂ��포�����������A���̖ڂɂ͂悢�D��S�ƁA�l�����ʈӎu�̋P���������������B���邢�u���[�̓����A���܂͋��|�ɂ݂Ђ炩��Ă���B�ނ͑勾�ɂނ����Ď���̂��Ă���B�w�͋��ɂӂ�Ă���B���̗₽���ɔ]�����тꂠ���邪�A�������Ƃ��ł��Ȃ������B���͂ȔS���܂ł҂�����Ƃ�������ꂽ���̂悤���B
�@�勾����͂ǂ����낢���ƂƂ��ɁA�˕����ӂ�����B�q�b�s�͕��ɂ������āA�w��傫�����炵�A�ċz�������ɂł��Ȃ������B���̂Ȃ��܂ŕ��������r��A���Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ��B
�u�q�b�s�A��������͂Ȃ��I�v
�@�y�b�N���������B�q�b�s�͂Ȃɂ������悤�Ƃ������A�҂���Ƃ������Ȃ��A������������̂ނ����ɋz���Ă����B�˕��œ��������A���ڂꂽ�܂��ӂ��Ƃ��ꂽ�B
�@�N������c�c�ƃq�b�s�͍l����B�������������̂ނ����ŁA�Ȃɂ���忂��Ă���B�����Ȑl�e���B�Ђǂ��Q�ĂĂ���݂������B���̎q������̂��Ă���B�q�b�s�͓���悤�Ƒ̂��悶�������A���̋z���͂͂܂��܂������Ȃ�B���̎q�̎w���A�ނ̎w�Ƃ����Ȃ肠���B���̂Ƃ���A�E�G�Ƙr�ɂ���ǂ��ɂ݂��͂������B�߂������݂������A�q�b�s�͊�������߂�B�]�ɂ͂���ɂ݂ɁA�q�b�s�͂������B
�@���肪�Ȃɂ����������B
�@�q�b�s�́A���̏��̎q�̈ӎ��⊴��A�����ɂނ����ė��ꂱ��ł���̂��������i���̎q�A���̎q���I�j�B���̎q�͗F�����Ƃ͂Ȃ�ēƂ�ڂ����ɂȂ��Ă���A�Ȃɂ��ɒǂ��Ă������Ƃ��킩�����B���̎q�̋��|�������A�q�b�s�͂��ɔߖ��������B���Ԃ��ނ̑̂Ɏ�������A�勾����Ђ��������Ƃ����B
�u�����I�v
�@�q�b�s�����ԂƁA�m�[�}�ƃr�X�R�́A�����̕\����݂��킹��B
�@�q�b�s�̎肪�勾����͂Ȃꂩ�����u�ԁA���̂ނ�������A�ɂ���Ǝw���˂��o�Ă���̂�������(�q�b�s�̎w�Ƃ́A�҂����肭�������܂܂�����)�B���ɁA�����勾���Ƃ���ʂ����B�O�l�͋V���Ȃ�����A�q�b�s�̑̂��Ђ��Â���B���̎q�������B����������Ɠ��ɂ͂���Ă��邪�A����͌��܂݂�̂����������B�y�b�N�͔ߖ������Ȃ���A�q�b�s�̑̂��Ђ��Â����B�����ł��B�����Ƃ������B�l�l�͐Ώ�̂����ɓ|�ꂱ�ށB�Ō�ɁA���������Ƃ���ʂ����B���̌��݂ǂ�̏��̎q�́A�ǂ���ƒn�ʂɂ����ꂨ�����B
�@�ނ�͕�R�Ƃ��̎q���݂��낵���B
�@���̎q�́A�q�b�s�̑����ɂ������܂��Ă���B�w�̍����m�[�}���A�������Ƃ������ǂ�ŏ��̎q�̘e�ɂ܂�����B��u�����A�勾���݂������B
�@���ʂ͐^�����ȉQ���܂��Ă���B���܂͂Ȃɂ��f���Ă��Ȃ��B
�@�ނ͏����̌����䂷�����B�������̌����ׂ�����Ǝ�̂Ђ�ɂ��A�m�[�}�͊�������߂��B
�u����ł���̂��H�v
�@�ƃr�X�R���u�����B��l�͂Ђǂ�������邢�B�m�[�}�͂����ƃr�X�R���ɂ�݂��������ŁA�Ȃɂ�����Ȃ������B
�u�勾����o�Ă������B�n�b�c������т����͂����낤�v
�u���̋V���͖{����������ł���v�y�b�N���e�F�̃q�b�s���A������悤�ɂ�������B�u�Â������āA���߂����҂��Ȃ��āA�����Ȃ��Ƃ��ڂ���͂�����l�Ԃ�����Ȃ����ǁA�{���������v
�u�Ȃ�A�Ȃ��������łĂ��Ȃ������I�v
�u�����������Ƃł͂Ȃ��ł����H�@�c�c�ڂ���̓n�b�c���̗썰����т������肾�����B�ł��A�n�b�c���͎���ł��Ȃ������v
�u���̎q�͂ȂH�@�����̂����ɏo�Ă����Ƃł������̂��H�v�ƃr�X�R�͌������B�u���l�Ȃ̂��H�v
�@�썰�ɂ͂ƂĂ�������c�c�Ɣނ͂Ԃ₢���B
�@�q�b�s�́A�����قǂ��̏��̎q�ƈӎ������L�����B������A�ޏ�������ł��Ȃ����Ƃ�m���Ă���B���܂݂�ŁA�ڂ�ڂ�A�ċz�����Ă��Ȃ��悤�Ɍ����邪�A�����Ɛ����Ă���Ɣނ͂��������B
�u���Ȃ��͂���ȋV���A�M���Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ��̂ł����H�v
�@�q�b�s�̓y�b�N�ɂ�������������Ȃ���A�Ђǂ����Ⴊ�ꂽ���ł������B�r�X�R�͏��N���ɂ�݂����B
�u���������N�Ȃ�ł��H�v�y�b�N���������B�u�ڂ���Ƃ��Ȃ��T�C�|�b�c�ł����H�v
�@�r�X�R���������ނ悤�ɂ������B�u�����̃T�C�|�b�c�Ȃǂ��Ȃ��B�����ƕʎ푰���낤�c�c�v
�@�m�[�}�͂��Ȃ������B�r�X�R�͂��������Ȃ����ʎ�`�҂����A���̂���͍����I���B
�u����ł��ł����H�v
�@�y�b�N���������B�m�[�}�������悤�Ƃ������A���̂܂��ɁA���̎q�͂��߂��������炵���B�l�l�������Ȃ��ŁA���̎q�͂������Ɛg�����������B
���@�@�@�@��
�@���߂��������ꂽ�c�c�����Ђ��Ⴐ�A���̗�ɂ݂��������B
�@�ӎ����܂��͂�����Ƃ����B�ޏ��͎������������炵�Ă���̂�m���Ă���B���܂��肳�܂ɂ������Ƃ��A�����œ��̋��ɋz�����܂ꂽ���Ƃ����ڂ��Ă���B�����A�Ȃ��A����Ȃ��ƂɂȂ����̂����킩��Ȃ������B
�@�؈�̉Ƃł݂��A�����Q���v���������B���̂Ƃ��͂��̌�����o���q���o�Ă����B�����͂��̌��������ɂ����Ǝv�����B
�@�Ȃ�Ƃ��N�������낤�Ƃ��邪�A���E��������łЂǂ��C�������������B�b���ɂ��������݂����ɁA�������܂��z���Ȃ��B����グ�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�勾���ʂ���u�ԁA�ޏ��͒N���ƈӎ������L�����i���N�c�c����͏��N�������j�B����q��щp�����Ǝ���Ȃ����Ƃ����A�����Ƌ������̏��N���J���������B
�@�f�������ɂȂ�A���͂������Ƒ̂������ɂ���B�킸�������A�f���C�����̂����B
�@�ڂ₯�����E���A�O�̊炪�̂�������ł����B���͂Ȃߑ��Y�ɕ߂܂����Ƃ��������B�Ȃߑ��Y�ƁA�M�����ƁA�؈�P�O�ɁB����Ƃ��A�܂��ׂ̎E�l����ɂ����킹�Ă���낤���B���͏e�����������������v���������B����ǂ͂��̎O�l�ɎE�����c�c�B
�@�œ_���������B���̎O�l�͂܂����N�Ƃ����Ă����N�Łi�Ƃ��ɂ��̒��̂ЂƂ�j�A�O���l�������B�O�l�Ƃ��݂��Ƃȋ��������Ă���B
�@���͐��ڋʂ��̂������ށB�����ɂ͋C�Â��킵���ȐF�����������B
�@����m�o���͂����肷��B�ޏ��͎O�l�̊�������āA�X�̌i�F���Ȃ��߂킽�����B�_�����悤�ȋ���ȖX���B�����͂����Ȃ��Ƃ����܂��肳�܂ł͂Ȃ��B���̐X�́A���؈�{�܂ł����͂����Ă������ȗd�C���A�����ł͊����Ȃ��B
�@���́A�s�v�c�ƁA�Ƃ���f��̃����V�[�����v�������ׂ��B�����ɂ������ꂽ���Â̐X�ɁA�ǂ������玗�Ă����B
�@���͂��̎O�l����邢���̂̌����錶�o���Ǝv�����B�ł��A�ޏ��́A���̏��N�ƁA�܂��ӎ������L���Ă���B���̏��N�̖ڂ��A�����̎��o�Əd�Ȃ�A���͌��݂ǂ�̎����̎p��ڂɂ���B���V���c���̂ɂ͂���A�c�����̂ӂ���݂��킩��B���ɂʂꂻ�ڂ������̂����ŁA�ł������Ȃ��̓M�����݂����ɂ݂����B
�@�ݑ܂̒��g���A���������A���͂܂����̏�ɂ��Ղ����B�d����̒n�ʂɓ����������āA���̒ɂ݂��܂��ޏ��̈ӎ����܂����������Ƃ͂����肳����B���͉���q�����Ƃ�����Ƃ��̂悤�ɁA�Ȃ�Ƃ��ӎ����Ւf���悤�Ƃ����B�܊��Əd�Ȃ肠���Ă������N�����������̂��A���͂ǂ��ɂ����������Ƃ���ǂ����B����ł����N�̊����l����ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł����B
�@������邢���̂Ȃ���Ȃ��A�Ɨ��͂������B���o�ł͂Ȃ��ƁB�Ȃ������̂��Ƃ��|�������B�����̒��ɂ������N�̖��̓q�b�s���B�܂����݂�����B�q�b�s�̂��Ƃ͊�������B�ł��A����q�����̂��Ƃ́A�ǂ��ɂ������Ȃ��̂��B
�u�����͂ǂ��H�v
�@�ޏ��͌���Ў�ł������悤�ɂ���B
�u�N�����A�N���H�v
�@�ƐN�̈�l���������B���O�̓r�X�R���B���͂��̐N��m���Ă��邱�Ƃ����낵�������B����q��щp�̂��Ƃ�m���Ă���݂����ɁA���̐N�̂��Ƃ�m���Ă���B���܂��Ƀr�X�R���A�܂������m��Ȃ��ٍ��̌��t������ׂ��Ă���̂Ɂi�����Ȃ��Ƃ����{��ł͂܂������Ȃ������j�A�����͂����Ɨ������Ă������B
�@��J����k����������O���A�������r�߂��B�r�X�R���M���ŁA�q�b�s�������Ă���̂́A���������炾�B�r�X�R�͕������݂������A����Ńq�b�s�͔ނ̂��Ƃ�������悭�v���Ă��Ȃ��B�܂�ŁA�����������Ă���݂����ȁA�Ђǂ��������������݂����ȋC�ɂȂ����B�L�������L���Ă��邹�����B�܂�ł����Ȃ����L�����A�Ƃ���ǂ����悤�Ȋ��o���B
�@�̂��ۂ̐N�̓m�[�}�ŁA�ǂ���炱�̐l�͂����l�炵���B�q�b�s�͌����Ă͂��Ȃ��i�������q�b�s����̂悤�Ȉ����������Ă��邩��Ƃ����āA���������̂悤�Ȉ�����������Ƃ͂�����Ȃ��B����ȍl���͊댯���j�B
�@���͏d�����������������B�O�l�Ƃ͗��ꂽ�Ƃ���ł������܂��Ă���q�b�s���݂�B�ނ͍����ʂ����قǂɋ����Ă���B���Ђ炢�����̉��Ɏ���������悤�ȋC�����āA�܂���ɓ������������B�q�b�s����Ȃ��ꂱ���́A�S�̂���݂�����ꕔ�������B����ł��������ł����ɁA�߂܂����N����B�S�Ȏ��T���A�ނ��蓪�ɂ߂��܂ꂽ�������B���̋t�����������Ǝv���ƁA�ޏ��͋t�サ���B
�u���������A���������Ăт������̂ˁv����ׂ�Ȃ���A���͎������ނ�̌��t�����ɂ��Ă��邱�ƂɋC�Â����f�����B�ނ�����f���Ă���B�u�������̂�������Ȃ��B���Ƃ����Ƃ��ɖ߂��Ă�I�v
�u�ڂ���̓n�b�c�����Ăяo�����Ƃ����I�v�ƃy�b�N���������B
�u�������͂��̃n�b�c�Ȃ���Ȃ��I�v
�@�r�X�R��������B�u����Ȃ��Ƃ͂킩���Ă���v
�u�Ȃɂ����������̂�A���̐g�����ʂ̃T�f�B�X�g��Y�v
�@�r�X�R�͍ŏ��ʂ��炢�A���ɐ^���ԂɂȂ��ē{�������킵���B
�u�����܂͂����������҂��B�Ȃ��T�C�|�b�c�̌��t������ׂ��Ă�H�@���̌��͂Ȃ��H�v
�@���̓r�X�R�ɘr���Ƃ��Ċ�������߂��B�r�̏��ɁA�w���ӂꂽ�̂��B
�@�����ɁA�q�b�s�������̐����������B�ނ��r���������Ă���B
�u��������Ă�̂��H�v
�@�r�X�R����𗣂��B�m�[�}���ޏ��ɂ����Â����B���̐N�����̂������j�O�������̂ŁA�ޏ��͂�����Ƃǂ��܂������B�q�b�s�̂����ŁA���S�������Ă��܂������ɂȂ�B�C�����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA���̎O�l�����Ԃ݂����ȁA����ȋC�ɂȂ��Ă���B
�@�m�[�}���������B�u���Ƃ����ꏊ�Ƃ͂ǂ��������Ƃ��H�@����A�勾����o�Ă������Ƃ͒m���Ă���B�����A����ꂪ�Ăт������Ƃ����̂́A���l���v
�u�킽���͎���łȂ��c�c�v�Ɣޏ��͊m�M�����Ă��ɂ������B�u�������āA�O���H�@�������������l����Ȃ���ˁv
�@�O�l�́A���f�̕\������킵�Ă���B
�@�������܂����܂܂̃q�b�s���A
�u���݂͂܂������ׂ̐X�ɂ����B���̎q�́A�T�C�|�b�c����Ȃ��v
�@����ς肠�����������̂��Ƃ��킩���Ă�B���͓{��ɐO�����݂��߂��B�m��Ȃ���ɁA�����̂��Ƃ��̂��炸�m����̂͌��ȋC���������B
�u�ڂ������Ă���Ȃ����v�ƃq�b�s���������������B�������̍l����ǂ݂Ƃ������̂炵���B�ނ͗������������B�u���̎q�͗F�����Ƃ�������ɂ�����ł���B���낵���ڂɂ������v�q�b�s�͈�u�L�������ǂ�悤�Ȃ��Ԃ���������B�u������A���܂݂�Ȃ̂��H�v
�@�������Ȃ������B�q�b�s�͑勾���Ƃ����āA���܂��肳�܂ŗ��̐g�ɋN���������Ƃ��A�܂������̂��Ƃ����đ̌������B�ނ͌��m��ʎq�ǂ������̋�Y��m��A�g�k��������B�����ǁA����͎O�l�̒��Ԃ̂������肵��ʂƂ��낾�B
�@�y�b�N���A�u�Ȃ�ł��̎q�̂��Ƃ�m���Ă�H�v�Ɛu�����B
�@�q�b�s�͐O���Ȃ߂��B��������͓̂�������B�ނ͌����Ɍ��t������B
�@���ɂ͔ނ̓������邮��܂���Ă��錾�t���ڂɌ�����悤�������B
�u�ڂ���͑勾���͂���Ŏ���������������B���̂Ƃ��A���̎q���ڂ��̂Ȃ��ɓ����Ă����v
�u�Ȃɂ������Ă�H�v�ƃr�X�R�͔����悹��B
�u���̎q�̊���Ƃ��A�ɂ݂��͂����Ă�����ł��A�L�����B�܂�ł��̎q�ɂȂ����݂����Ȋ����������B���O�̓��i���B�F�����̖��O���킩��v�ނ͘r����������B�u�������r�X�R����������Ƃ��A�ڂ����r���ɂ�ł��B���͂Ȃ��̂ɁA���܂��r���ɂ��B���̎q�̍l�����ǂ߂�悤�ȋC������c�c�v
�@�q�b�s�����ɘr���̂��A�ڂ��̂�������ł����B
�u��߂Ă�v
�@�Ǝ��������炷�B�ޏ��̓q�b�s�̂��Ƃ��|���Ȃ�B����Ȗڂɂ����Ă���̂ɁA�X�݂����ɗ�ÂȂ���B���͉���q�����ƈӎ��̋��L��̌����Ă��邪�A�q�b�s�͏��߂Ă̂͂����B����ɁA�ނ��݂Ă���ƁA�S�̉��܂œǂ݂Ƃꂻ���ȋC������̂��B
�@���܂��肳�܂ɂ����Ƃ����A�����Ɨ͂������Ȃ��Ă���B����ɂ����������������B�]�̔�J����S�̂ɂ���āA�畆�����킲�킷��B���܂����ɖ��肱���Ă��܂����������B����������̃}���V�����Ȃ�A�ǂ�Ȃɂ��悩�����̂ɁB
�@��������A����q�����͂ǂ��ɂ������낤�H�@���̎q�����������Ƃ�Ȃ��c�c�B
�u���̎q�͂ނ����̐��E�ł��A�F�����Ƃ���Ȃӂ��ɂȂ��荇���Ă��B�S���ЂƂɂ��Ă����v
�u�����v
�@�r�X�R���|��������āA�q�b�s�̌������B���͎����̌������܂ꂽ���G�����āi�������̓q�b�s�������Ă�����̂�肸���Ɣ��炩�Ȃ��̂��������j�A�E���ɖڂ����Ƃ����B
�u���܂��͂��܁A�������̐��E�ƌ������ȁB�������̐��E�Ɓc�c�v
�@����̓q�b�s�ɂ�������Ƃ������A����ɂ��������̂������B���͑����̂B�S���₽���Ȃ����B
�@�������āA�S�̂ǂ����ł͂��̉\�����l�����B�ł��A�Ƃ肠�������͂Ȃ������̂��B
�u�����Ƃ��������悤���Ȃ���ł��v�q�b�s���r�X�R�̘r���ӂ�͂�����B
�@�m�[�}���������B�u�����̌��o�ł͂Ȃ��̂��H�v
�@���͋����Ĕނ��݂��B�u���o���݂Ă�́H�v
�@�ޏ��̖ڂ́A�����̓�{���炢�Ɍ��Ђ炩���B���ǂ낫�ŐS���̌ۓ����͂₭�Ȃ�B�����ɂ������B�]�����ł͂Ȃ��A�S�x�@�\��������Ă���B�]�Ɏ_�f�������邽�߂ɁA�����Ȍċz�����Ă������炾�B���܂����ɖ��肱���邩���āA�������ł������Ƃ�Ȃ��Ƃ���Ɣޏ��͒��o����B�����ǁA���̎l�l�ɐu�����Ƃ�����B
�u���o���݂Ă�́H�@���͂ǂ��Ȃ̂�H�@���ӎ��ɍs��������c�c�����ōl���Ă邱�Ƃ��A�����ɋN�������肷��H�v
�u�Ȃɂ������Ă�c�c�v
�@�r�X�R�͔ے肵�悤�Ƃ������A���̐��͎�サ�������B�����ǁA�q�b�s�̖ڂ́A�ޏ��̎�����m�肵�Ă����B�m�肵�Ă���̂��A��������B
�u���������Ȃ́H�v�Ɣޏ��͂܂��u�����B
�u����͂ǂ������Ӗ����c�c�v�ƃm�[�}���������B
�@�����ᛂ����������B���Ɏ�����Ă��B�u�������ɂ��Ȃ̂�B�������ɂ��A���̎q�̍l���₢���ȋL�����Ȃ��ꂱ��ł����B�S������Ȃ����ǁB�����炠�����̂��Ƃ��킩��́I�@�������́c�c������������ƂɂȂ��Ă�B�܂��Ől������ł��ł���H�@�ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ��c�c�ł��A�ǂ��߂�ꂽ����A�����ɗ�����Ȃ��́H�@�����ŋV���������B�������H�v
�@�l�l�͔ޏ��̋��������ɁA������ނ���B
�@���̃A���e�i���ǂ�ǂ�ӂ��ꂠ�����Ă����B�����͂��܂��肳�܂���Ȃ��B�����ǂ�ȂɃA���e�i���̂��Ă��A�F�����̂��Ƃ�������̂��Ƃ��A�_�ے��̂��Ƃ������Ƃ�Ȃ��B�����͂����������Ƃ���ɂ����B������������A�q�b�s�̂����Ƃ���A�ق�Ƃɂׂ̐��E�ɂ���Ă����̂�������Ȃ��B
�@���͌������B�u����o���Ȃ�����v�Ǝ���Ƃ������B�q�b�s�͂��Ƃ��������B
�@�Ƃ܂ǂ��q�b�s�ɕ��݂��ƁA���̎���ɂ������B���̓q�b�s�ɂނ��Ă̋L���𗬂�����ł�����B�������������̉ĂɌo���������ƁA��邢���̂̂��ƁA�F�����Ƃ̊ԂɋN���������ƁA���܂��肳�܂ł̏o�������B�Ȃ�ł���Ȃ��Ƃ��ł���̂��͂킩��Ȃ������B�ł��A�ł��邱�Ƃ�m���Ă����̂��B
�@�q�b�s���z�����������A�������炵���B�ނ͂��߂����グ�Ă���B
�@�r�X�R��������������B
�u��߂�I�v
�@�m�[�}���r�X�R��˂��Ƃ����B�y�b�N�������������������B�ޏ��̌��̂͂����猌�������̂��݂āA�y�b�N�͌������B
�u�Ђǂ�����Ȃ��ł����v
�u����́A����Ȃ��Ƃ̂��߂ɁA�댯�ȐX�ɂ�����Ȃ��v�r�X�R�͑����̂܂Ȃ����Őg���N�����B�u�����܂�A�悭�l���Ă݂�A�勾����o�Ă����A���݂ǂ�̎q�ǂ������I�v
�u�o�Ă������ė�����Ȃ��I�v
�@���͌��̂Ȃ�������悤���B���Ƒ���f���ƁA�Ԃ����̂��n�ʂɗ������B
�u�q�b�s�A���v���H�v
�@�r�X�R���������B�q�b�s�͗�������ē����ӂ��Ă���B���́A���̎q�̂ق����ɂ�����Ȃ��ɂ݂��������A�Ǝv�����B
�@�q�b�s������f���ƁA��͂�Ԃ����̂��܂����Ă����B�݂�Ȃ́A�����Ƃ��̌��i���݂��B�q�b�s�͂��̑����݂Ȃ���A
�u�N�̐��E������Ȃ��Ȃ̂��H�@�ƍ߂��ӂ��Ă�ȁH�v
�@���͂��Ȃ������B
�u�e��܂��̐l�Ԃ����������Ȃ��Ă�A�������ȁH�v
�@�܂����Ȃ����B
�u�ǂ��������Ƃ��H�v�m�[�}���u�����B
�u���̎q���ڂ��Ɍ����Ă��ꂽ�B�Ȃ��킩���Ă������v
�@���ɂ��킩�����B���Ȃ����Ƃ��A�ʁX�̐��E�ł������Ă���̂��B�����ǁA�͂��̐��E�̂ق��������ƈ����悤���B�q�b�s�����́A�����ȍ��Ɛ푈�����Ă���B�����炯�ŁA���R�ɕ��������Ȃ���Ԃ��B
�@����ɂ��̎l�l�́A�ܜ����������\��B���̊�͒B�Y�����Ƃ���Ȃ����B���o��A���̂Ȃ��̋�z�������ɂȂ邱�ƂŁA�ǂ��߂��Ă������҂̕\��B
�@���͓������������B�����悤�ɒɂ������B�����Ă���̂�����Ƃ��B���̂Ȃ��ɂ͂܂��q�b�s����������A���̎l�l�����o�����Ă������Ƃ��A�f���ɐM����ꂽ�B���������̂��Ƃ��A�������̂ƌĂ�ł������ǂ����ׂ͂Ƃ��āA���Ȃ��̌������Ă���̂�������ꂽ�̂��B
�@�������ӂ�������B
�@�q�b�s�����ɂ�����Ă������B
�u���̎q���������o�⌶���������Ă�����ł��B�܂��̐l�Ԃ����������Ȃ��Ă邱�Ƃ܂ł���Ȃ����v
�u����Ȃ��ȁA����Ȃ������b���M�����邩�H�v
�u�ł��A�����Ƃ��Ă��̎q�͂���ł��傤�H�v
�@�r�X�R�ƃq�b�s�������������͂��߂��B
�@�q�b�s����Ƃ����m��������_�����Ă݂Ă��A���̎l�l�������ւ�Ȗڂɂ����Ă����܂ŗ����̂��Ƃ������Ƃ͂��������m�邱�Ƃ��ł����B�����́A�T�C�|�b�c�̍�����͉�������Ă���B���̐X�́A���܂��肳�܂̂悤�ȁA���̋ߕӂɂ���L�����v�X�|�b�g�ł͂Ȃ��āA�x�m�̎��C�̂悤�Ɋ댯�ȂƂ���Ȃ̂��B
�@���ɁA�ЕG�������B�y�b�N�ƃm�[�}���x�����B���͂��̂Ƃ��A��l�̂��Ă���̂��A�����Ȑ��n�łł����_���߂ł��邱�Ƃ�m�����B�{�C�Ŏ��҂��Ăт������ƍl���Ă����̂��ǂ����͂킩��Ȃ����A�s�ׂ������Ȃ������Ƃ����͂킩��B���̂������ŁA�����͂��̂������������Ƃ��ł����̂��B
�@���ꂪ�A�悩�����̂��ǂ����͂킩��Ȃ������B�����ǁA�����͂����Ȃ��Ƃ��A���܂��肳�܂قNJ댯����Ȃ��B
�@�m�[�}���X�̉������݂Ă���B������C�ٕ̈ς����Ƃ����B�s���R�ȐÎ₪�������B���̐Î�����������B
�u�����v
�@�ƃm�[�}�͌������B�X�̖X�̉e�ɂ́A����ȏb���Q����Ȃ��Ă����B���͌F���Ǝv�����B�ł��A�F�ɂ��Ă͓������ւB
�@���S�ȓ��s�����Ă���悤�Ɍ�����B
�u���܂����߂�B�i�o�z�����I�v
�@����ȑ������Ȃ�������Ĕ��A�r�X�R�̑����ɂ��h�������B���ۂ�V���o���̉����X�ɂЂт��A�킢������騂̐���������B
�@�X�̍��Ԃ���A�тނ������̒j���������łĂ����B
���@�g�D���[�V���h�E
���@�@�@�@��
�@�i�o�z���ɂ͏\�̎��������邪�A���̂����̂ЂƂł���X�[�̐�m�����͔��͂ĂĂ����B�T�C�|�b�c�Ƃ̐퓬���j���������Ղ������B�Q��̒����Ƃ߂�g�D���[�V���h�E�́A���Ԃ��͂��܂��̂�����Ƃ������B
�@�i�o�z���̓C�j�V�G�̐X�ɂ��ޑ��Â̎푰�ł���B�L��ȐX�̂��������ɁA���ꂼ��̏W���������Ă���B�i�o�z�̒j�����݂͂ȋ��̂ŁA�T�C�|�b�c�ɂ���ׂ�Ɛg�̂����͔{�قǂ�����B���܂���Ă̍��͂ɂ��킦�A�X�ł̕�炵�̂������A�݂ȕq���������B���̊�͘T�Ɏ��āA�܊��ɂ�����Ă���B�C�j�V�G�̐X�ɂ͐��\�ɂȂ�푰�����邪�A�i�o�z���Ɏ���������̂͂Ȃ������B�X�ɂ���T�C�|�b�c�͐������Ȃ��������A�ނ�̓i�o�z���̂��Ƃ��u�т̂���l�X�v�Ƃ�ьh���Ă����̂��B���ꂪ�Ȃ�����Ȃ��ƂɂȂ����̂��H
�@�͂��߂̂����A�i�o�z���͎������̂Ƃ��Ȃ������Ő�����B�g�D���[�V���h�E�͎�̂Ƃ��ɂ�����̉��ʂ��A���܂����Ă���B�T�C�|�b�c������Ȃ�A�O�l�ɂ������悤��������͂����Ȃ������B
�@�T�C�|�b�c�����́A�W�c�Ő퓬���������Ă���B�키���Ƃ���ɂ����R�����B�R���̂��Ă���͍I���ŁA�g�D���[�V���h�E�����͐퓬�̂��тɐ����ւ炵�Ă����B���Ԃ̑����͏����A�����̂ЂƂł��郂�m�̗���ɐS��ɂ߂Ă����B
�u���v���A�g�D���[�V���h�E�H�v
�@���g�����b�N�����ɗ����B�ނ͎�̕����ł���A�g�D���[�V���h�E�̐e�F�ł��������B
�u�ق��̎҂��݂Ă��B����Ȃ�A�ܑ̌��V���v
�u�ނ������ȁv���g�����b�N�͎��ɂ��������B�u��������Ă��邼�v
�@���g�����b�N�́A����Ԃ��������������Ă����B
�@�g�D���[�V���h�E�́A�������ʐF�̂قǂ����ꂽ�A���̉��ʂ��Ƃ�͂������B
�@�j�����͐����Ŏ���̖є����߁A�e�Ƃɂ����߂�g�ɂ܂Ƃ��Đ�����B�T�C�|�b�c�̂����Ζ�́A�����̈ߑ����ڂ낫��ɕς��Ă��܂����B��X������Ă����������A��x�Ƃ����ʂ��̂ɕς���ꂢ�炾���Ă����B
�u�o���E�Y���r��Ă���ȁc�c�v
�u�����̓V�����i�b�N�ƒ����悩�����v
�u��������ɐ���Ă����̂��v
�u���ށv
�@�T�C�|�b�c�Ƃ̐킢�������ނɂ�A�g�D���[�V���h�E�������A�`���I�Ȏ�̎�@�����Ă邵���Ȃ��Ȃ����B��͕K�v�ȐH�p�����邽�߂̂��̂ŁA�퓬�△�p�ȎE�C�Ƃ͖����̂��̂������̂��B�g�D���[�V���h�E�͎O�l���ЂƂ̒P�ʂɂ��Đ�킹�Ă������A������������ɂ�A������҂������Ȃ����B�g�D���[�V���h�E�͉��ʂ������Ƃ݂߁A�o���E�Y�̋ꋫ�����������B�ڂ̑O�łƂ��ɂ����������Ԃ����ʂ̂́A�ς����ʂ��Ƃ������B
�@�g�D���[�V���h�E�͋��������ʒj���Ǝv���Ă������A�����ł������v���Ă����B�����A���܂ł͋��|�ɂǂ��Ղ�Ƃ����Ă���B������݂��͔̂ނƃ��g�����b�N�A�o���E�Y�̎O�l�����������B�T�C�|�b�c�̕��������́A�~�I�̏Z�l���E�������Ă����B�����̎��̂��A�܂�Őd���Ȃɂ��̂悤�ɐς݂������Ă����B�i�o�z�̎��̂̎R�B�g�D���[�V���h�E�͂��̂Ƃ��̃o���E�Y�̌��t���Y����Ȃ��B������̖ړI�́A���ꂩ�\�\�H
�@�i�o�z�̊e�����́A�����悻�S�l����̏W���������Ă���B��l�ȏ�̐l�������݂��邱�ƂɂȂ邪�A�T�C�|�b�c�Ƃ̐푈���͂��܂��Ĉȗ��A�ܕS�l�قǂɐ����ւ��Ă����B���������N�̂��Ƃł���B�ނ炪����₵�ƂȂ�A���̐����������������A���������͂Ȃ��B
�@�s�E�ɂ����Ă����̂́A�Ȃɂ��i�o�z�����ł͂Ȃ��B�����������̂̂������I�u�W�F�͐X�̂��������ɂł��Ă������炾�B���̂�ɂ邵�A�Ȃ܂�����ɂ��A�������������肾���A���炵���̂ɂ��Ă����B�藣�����葫�������āA�q�ǂ��̍H��̂悤�ɂȂ��Ă������Ƃ��������B�T�C�|�b�c�̍s���́A����Ȃ�r�ō��Ƃ��������ł͑���Ȃ������B�ЂƂ̑����P�������Ƃ́A���q�ǂ��ɂ�����܂ŎE�������A�Ă��s�����������Ȃ��Ă����B�푰�̐����������Ղ�����������Ƃ��Ă��邩�̂悤���B�g�D���[�V���h�E�ɂ͂킩��Ȃ������B
�@�Ȃ��A������͂���Ȑ^�����\�\�H
�@�������Ȃ��Ƃ͂ق��ɂ��������B�g�D���[�V���h�E�����́A��������X�ł悭�����̂ł���B�T�C�|�b�c�Ȃ炢���m�炸�A���������������ȂǁA����܂łɂȂ��������Ƃ��B���o���������Ƃ������A�n�`���ω����Ă���悤�������B�������Ƃ��Ȃ��悤�ȓ��A�����o�����邱�Ƃ�����B
�@�g�D���[�V���h�E�͊��������ƁA�o���E�Y�̂��Ƃɕ��݂�����B
�@�����A�i�o�z�̃X�[�͕����B�������ăT�C�|�b�c�̌R��ɂ͂������B
�@�ނ̓��g�����b�N�ɂ����₢���B
�u���͂Ȃɂ���T���Ă���B���ꂪ�Ȃ�Ȃ̂���m�邱�Ƃ��ȁv
�u������Ƃ����āA���ꂽ�����E�����R�ɂ͂Ȃ�v
�@�g�D���[�V���h�E�͂��Ȃ������B
�u�����A�Ȃ������ꂽ���ɍ��݂������Ă���v
�u���ȁA���ɍ��݂���������邱�ƂȂǂ��邩�v�ƃo���E�Y�������Ƃ��߂��B
�u�T�C�|�b�c�����͂Ȃɂ��l���Ă���B���̂܂E�����Â�����肩�H�v
�@���[�N�o�C�X�������݂������Ă������B
�@�i�o�z���͍H�|�ɂ����݂ŁA�T�C�|�b�c�Ƃ��Â�������Ղ��������B����̕i�X�������ɑ��������Ƃ�����B��N�O�܂ł́A�ǍD�ȊW���������Ă����̂��B�����ɂ��郏�[�N�o�C�X���L�\�ȍH�|�ƂŁA�T�C�|�b�c�̋Z�p�҂��܂˂����Ƃ��́A�܂������܂ɔނ�̌��z�𗝉����A�����̌��݂ɐs�͂����B
�u������A�����̎푰�Ƃ��퓬�����Ă��邻������Ȃ����v
�@�N�����h�������͂����Ă��B
�u�T�C�|�b�c�͐�������������ȁB���ꂽ���Ɛ���Ă��A�����̓����ɂ͂��܂��̂��v
�u�~�I�̘A���͍s�����ꂸ�̂܂܂����B�݂�ȎE���ꂽ�낤���H�v�ƃ��[�N�o�C�X�B
�@�T�C�|�b�c�����́A�i�o�z�̃~�I���P���A�ނ�̂��z�R��D���Ƃ����B���V�������S�����̒j�����߁A�~���ɂނ��킹���Ƃ��ɂ́A�W���ɂ����唼�̂��̂��E����Ă��܂����B�c��̎҂͂��܂��������Ă��Ȃ��B
�@�T�C�|�b�c�͂ق��̏W���������P���A�s�E���J�肩�������B���m�ƃV�����A�}�C���̎O�������X�ƍ~�����Ă��܂����B�g�D���[�V���h�E�͗����������A���Ԃ̎����ƘA�g���Ƃ�Ȃ����肳�܂������B
�u���̂����ǂ��Ȃ�A�g�D���[�V���h�E�H�v���[�N�o�C�X���������B�u������͓���������Ă�Ƃ����v����B���ꂽ�����E���ĂȂ�ɂȂ�Ƃ����H�v
�u����͂��Ŗє����������̂��v�N�����h�����������B
�u���R�ɂȂ��ȁB�є�����A�H�|�����Ƃ肵���ق�����������v�g�D���[�V���h�E���������B�u������͍z�R���@�����Ƃ���ŁA�H������Z�ʂ��Ȃ��v
�u������A�~�I�̐����̂������čs�����̂��H�v
�u�T�C�|�b�c�̂������Ƃ������i�o�z�͂��Ȃ��v
�u���Ⴀ�A���m�̘A���͂ǂ��ȂH�@�V�������}�C�����T�C�|�b�c�ɍ~����������Ȃ����v�o���E�Y���������B��������i�o�z�̎����������B
�u���q�ǂ����E��������ł������Ȃ邳�v���g�����b�N���ڂ���Ɠ������B�u�ق��̑��������Ă���Ȃ����v
�u��k�ł͂Ȃ��I�@����̓V�����i�b�N��E���ꂽ���Ԃ̓G���Ƃ邼�I�@�T�C�|�b�c�̂������Ƃ��������炢�Ȃ�A���ق����܂����I�v
�u����͑����̃w�e�i���������߂邱�Ƃ��v
�u�]��I�v�ƃo���E�Y�͌������B�u����͏]���I�@�ЂƂ�ɂȂ��Ă��키�I�v
�@��������A��������A�Ƃ݂ȏ��a�����B�����ȃ��[�N�o�C�X�������������B
�u��߂�B�݂�Ȏx�x������B�ꍏ���͂₭���ɂ��ǂ낤�B���܂�����������Șb������ƁA����ɕs�g���v
�@�g�D���[�V���h�E���߂�������k�������ƁA�j�����݂͂ȋ�����B�������ɁA�W���̂��Ƃ��S�z�������B
�u�Ƃɂ����A�i�o�z�̑̂����Ă�����邱�ƂɁA����͑ς�����̂��v�ƃo���E�Y�͌������B
�u�g�D���[�V���h�E�v���g�����b�N���ނ̌��Ɏ���������B�u�b���������邼�v
�@�݂Ȃ́A����T�C�|�b�c���Ƌْ����߂��点���B�ނ�̒��o�̓T�C�|�b�c������R������Ă���B�ނ����ɂ͋C�Â���Ă��Ȃ��͂����B
�u�����t�b�h�̏W���ɋ߂����v
�u�݂�Ȏ������܂��Ă݂��B�T�C�|�b�c�̂���������Ȍ��p�ꂪ���ɂ����v
�u���p��Ȃ��B�����炪�������������ƌ��Ղ�������̂�����A���R�ɂЂ�܂����������v
�u�������v
�@�g�D���[�V���h�E���������B�ނ炪���ق���ƁA�X����͐��������������Ƃ������قǂɐÂ��ɂȂ����B�i�o�z�̒j�����́A�C�z�����S�ɎE���āA�X�̂͂��܂ňړ����邱�Ƃ��ł���B���̔\�͂��A����܂Ńg�D���[�V���h�E�����̖����������Ă����B
�u��肷�������H�v���g�����b�N���������B
�u����A�����t�b�h�̏W���ɂ������B�������Ƃ�����A�t�b�h���P�����肾�v
�u�����v�o���E�Y�̓n���}�[���Ђ낢������ƁA���g�����b�N�ɂ��������B�u�g�D���[�V���h�E�͂����肾�v
�u���̕��p�͑勾�̂ق����B�_���ǂ������Ă���̂ł͂Ȃ��̂��H�v
�u����ȂƂ��ɂ��H�@���̋V���ȂǁA���̈�N�������߂����Ȃ��v�ƃg�D���[�V���h�E�͔ے肵���B�u�������A�������͑ނ��킯�ɂ͂�����B�T�C�|�b�c���݂�����킸�E���B���q�ǂ����ȂԂ�E�����O�ɁA�����E���v
�@�g�D���[�V���h�E�����͉����Ȃ��삯�Ă������B���͂ǂ�ǂ�傫���Ȃ�B���̎��_�ŕ����̒N�����A���̎傪�������������Ă��āA���̐l�����ܐl�������Ȃ����ƂɋC�Â��Ă����B���̗D�ꂽ�k�o�́A���̏L���������킯�Ă����B���̂����ʼn��҂����\�\�T�C�|�b�c�Ȃ̂��i�o�z�Ȃ̂�����Ƃ��܂������ׂ̎푰�Ȃ̂��͂킩��Ȃ����\�\���𗬂��Ă���炵�������B
�@�g�D���[�V���h�E�����̓T�C�|�b�c���܂˂č������ѓ���̐��X�����܂����B�X�̂ނ����ɂ̂����n�ɂ́A�T�C�|�b�c�̎p���������B
�u�T�C�|�b�c���A�܂������Ȃ����v
�@�o���E�Y����������������B�g�D���[�V���h�E�͔ނ����������B�����āA�����̑�����������������ƁA�T�C�|�b�c�߂����ē��������B
���@�@�@�@��
�u�i�o�z�����I�v
�@�y�b�N���������B���͖ڂ��݂͂����B
�@�勾�̎��͂ɂ܂������܂ɌQ��ǂ��Ă����̂́A�є�ɂ�����ꂽ�l�Ԃ��B�F�Ƃ�ǂ�̍�����A�S�̋����ĂȂǂ����Ă���B�ǂ��݂Ă������Ȃ̂ɁA��{���ŗ����Ă���B����ȕ��⑄�A�N���X�{�E����ɂ��Ă����B
�@��\�l�͂���B
�@�Њd�̖�A�ܐl�̎��͂ɓ˂��������B
�u������Ƃ��푈���Ă�́H�v
�u�������v�ƃq�b�s�����������B
�u�T�C�|�b�c�͂��܂�����푰�ƌ�킵�Ă���v�ƃr�X�R�B�u������͂��̒��̂ЂƂɂ����v
�@�i�o�z���͐Α�ɂ̂ڂ�A�ܐl�̎��͂��Ƃ�܂����B�b�̂悤�ȏL�����@�������B�i�o�z�̌��t�ł��Ȃ���グ��B
�@�S���|�����j�A���̂悤�ɁA�J�[�������������������Ȃт����Ă���B�����Ƃ���̂�������֖҂������B�l�ԂƂ͔�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�ɔw�������A�؍����S�����̂悤�ɗ��X�Ƃ��Ă���B����ȘA���Ɛ푈������Ȃ�ĐM�����Ȃ������B�i�o�z���͐l�Ԃ̂悤�ɂ������Ɨ���������A���̎p�͂܂�ő�̂悤���B���͒ɂސS������������B�����ِ͈��E�ȂƁA�݂Ƃ߂邵���Ȃ������B
�@�i�o�z���́A�����ɂ���̂��q�ǂ��ł���̂��݂Ƃ��ĂƂ܂ǂ��Ă���B�q�b�s���ނ�̐����ɂ������Ă����B�r�X�R�����̌������B
�u�����܁A�i�o�z�̌��t���킩��̂��H�v
�@�q�b�s�����Ȃ������B�ނ͂����Ɨ����݂��B���͂������ɂ��Ȃ������ƂŁA�������i�o�z�̌��t�������ł��邱�Ƃ��������B
�@�r�X�R���������B
�u�Ȃ�Ό��p���b���悤�ɂ����v
�@�q�b�s���i�o�z�̌��t�Řb�������B����ƁA�j�����͂܂��܂������藧���ĕ�����ӂ肠�����B�m�[�}�����͂����낢���B�y�b�N���u�����B�u�Ȃ�Ă����Ă�H�v
�u�ނ�̓T�C�|�b�c�̌��t�́A����ׂ�Ȃ��Ƃ����Ă�v
�@���͂��Ȃ������B�i�o�z���́A�푈���̑���̌��t��b�������Ȃ��ɂ������Ȃ��B
�@�q�b�s���ߖɎ�������������B�u������A�ڂ�����E���Ƃ����Ă�v
�@�m�[�}���������B�u��k�ł͂Ȃ��B��X�͂���ȂƂ���Ŏ��ʂ킯�͂�����v
�@�q�b�s�����̂��܂ʼn��������B�y�b�N���u�����B�u�m�荇���Ȃ̂��H�v
�@�q�b�s�͂��Ȃ������B�ނ̓i�o�z�̂����ł��A�Ƃ��ɑ啿�ŁA�����ȑ����̂قǂ����ꂽ�������j���w�����A�u���ʂ����Ԃ��Ă���̂́A�ᒷ�̃g�D���[�V���h�E���B���g�����b�N������B���������Ă���̂̓o���E�Y���v
�u�����͉��̓y�n���B�T�C�|�b�c�͏o�Ă����I�v
�@�g�D���[�V���h�E�����ʌ�ł������B�j�����̋����͂܂��܂����܂����B�������Ƀi�o�z�̌��t�ł�����ɘ_�����Ă���B�ނ�̓T�C�|�b�c�̎q�ǂ����Ȃ����������̓y�n�ɂ���Ɠ{��A�T�C�|�b�c�̕��������ɂ���̂����������̂��A�Ƃ����Ă���B
�@���͑勾���݂��B�ǂ���炱��̓T�C�|�b�c�����������̂炵���B
�@�ޏ��͎������Ƃ���ʂ����Q���A�܂������ɂ���̂��݂Ƃ߂��B�勾�̌��͂��������Ȃ��Ă������A���Ă͂��Ȃ������B�^������ᏋC���A�Ƃ����蕬�o���Ă���B���͑勾�ɋ삯����Č��Ɏ�Ă��B
�@�Ȃɂ��N����Ȃ��B�ᛂ��������ċ������������A�������̐��E�ɂ͂��ǂ�Ȃ��B
�@�o���E�Y���{��̐��������āA���Ɍ���U�肨�낵���B���͊낤���a����Ƃ��낾�������A�q�b�s�������Ђ��Ēn�ʂɂ��낪�����B
�@�勾�͑�����炱�낰�������B�i�o�z���͋���ȒƂ������đ勾�X�ɍӂ��Ă��܂����B
�@���̊�O�ŁA���̒����ɂ��������������A�Ђイ�Ƃ��ڂ�ŋ�ɏ������B���͋��̌��Ђ��ЂƂЂƂE���������B�ޏ��͂���Ȑ��E��M�������Ȃ��������A�������������Ȃ������B�����ǁA���̐��E�ւ̓����������������ꂽ�B���ꂪ�Q�[�g�̂悤�Ȃ��̂������Ƃ�����A���������Ȃ��Ȃ����̂��B
�u�Ȃ�Ă��Ƃ��B�勾���ӂ��ȂǁA���C���v�ƃm�[�}���R�c����B
�u�ؑ��߁I�@�����܂�Ȃǁc�c�v
�@�g�D���[�V���h�E�̕X�̂悤�Ȏ������r�X�R���˔������B�q�b�s���������B
�u����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��ł���B�ނ����͂������̌��t���킩��v
�@���̂Ƃ��A�i�o�z���̊Ԃ���A���[�N�o�C�X�������݂łĂ����B
�u�g�D���[�V���h�E�҂��Ă���A�ނ̓q�b�s���v
�@�g�D���[�V���h�E���ӂ�ނ����B
�u�ނ̓^�b�g���̒�q���B�ܔN�O�ɑ��ɂ����낤�v
�@���[�N�o�C�X�����̏�̈ꓯ�ɐ������͂��߂��B�^�b�g���̓T�C�|�b�c�̋Z�p�҂ŁA�푈���͂��܂�O�͊e�n�̎푰���܂���Ă����B�������V���Ƃ����̂ɁA�����ȍs���͂ŁA�i�o�z���̑��ɗp���H���������A��p��_�앨���������̂��B�q�b�s�͂��̗B��̒�q�ŁA�i�o�z�ȊO�ɂ����̌���������܂�Ă����B
�@�o���E�Y�������݂������点�A�ǂȂ����B
�u�W���邩�A�T�C�|�b�c�݂͂ȎE���ɂ��Ă��I�@������̓i�o�z�̖є���͂����B�i�o�z�̑������Ђ����肾���A�i�o�z�̍������������̂��I�@���q�ǂ����E���A��X������₵�ɂ������Ȃ�A�T�C�|�b�c�ɂ����Ȃ��Ђ��������炵�Ă��I�v
�@�g�D���[�V���h�E���m�[�}�ƌ����������B�ނ͂���ǂ����ʌ�ł������B�u�����܂����͂����łȂɂ����Ă���B�C�j�V�G�̐X���T�C�|�b�c�����}���Ȃ����Ƃ͂킩���Ă���͂����B����Ƃ��A�ǂ����ɑ�l������̂��H�v
�u�N�����Ȃ��B���̐X�ɂ͂ڂ��炾���ł����v
�@�g�D���[�V���h�E�̓m�[�}�̐_���߂��w�łȂ������B�u�����܁A�V���̐_���Ȃ̂��H�@�n�u���P�b�g�͂ǂ������H�v
�u����͐��̐_�����B�ނ�݂͂Ȕ�ƂɂȂ����B�n�u���P�b�g�l�͂ڂ���ɋV����`���Ă������A���܂͗H����Ă���v
�@�g�D���[�V���h�E����������߂����B
�@�m�[�}���u�����B�u�n�u���P�b�g���܂�m���Ă���̂��H�v
�u�Ȃ�ǂ��A���̐X�ł��������Ƃ�����v
�u���ꂽ���̓n�u���P�b�g�������A�X�̊O�܂ő���Ƃǂ������Ƃ�����v
�u���[�N�o�C�X�A�]�v�Ȃ��Ƃ������ȁv�o���E�Y���ǂȂ����B
�u���������܂������ɂ��Ȃ����Ƃ����Ă�����͂Ȃ����v�g�D���[�V���h�E�͗��������Ŏw�����B�u���̎q�͂ȂH�@�T�C�|�b�c�ł͂Ȃ��ȁv
�@�g�D���[�V���h�E�������Ƃ���A���𗬂��Ă���̂͂��̎q�����̂悤���B
�@�m�[�}�͂���܂ł̂���������������B�n�b�c�����Ăт������Ƃ������ƁA����Ɨ����o�Ă������ƁB
�@�i�o�z���͂��̘b���̂�M���Ă��Ȃ��B
�@�m�[�}���������B�u�����Ă���A�푈���d�|�����̂́A�T�C�|�b�c�̂Ȃ��ł��ꕔ�̂��̂ȂB�ނ炪���������������āc�c�v
�@�o���E�Y���m�[�}���͂�Ƃ��B�ނ͖_�̂悤�ɒn�ʂɂ��낰���B
�@���͂����ƃo���E�Y���ɂ�݂�����A��J��Y��Ă��݂��������B
�u�������傤�A���̂������I�@�������͂ق�Ƃɂ��̑勾���ʂ��Ă�����I�@���������A�����߂�Ȃ�����Ȃ����I�v
�@�o���E�Y�͗������̎q�ǂ��ł���̂�m���āA���\�ɂ͂�����Ȃ������B�ނ͉E��ŗ��̓����������Ȃ���A�g�D���[�V���h�E�ɂ������B
�u���̎q�͂Ȃɂ������Ă�v
�@�g�D���[�V���h�E�͌��������߂��B���̓i�o�z���̌��t�œ{�����B
�u���܂���̂����ŁA���Ƃ̐��E�ɖ߂�Ȃ��Ȃ������Ă����Ă�v
�@���͒n�ʂ��������A���̏�ɋ��������ꂽ�B�ޏ����ᛂɒj�����͓ŋC���ʂ���Ă��܂����B
�u���܂��A�i�o�z�̌��t���킩��̂��H�v
�@�g�D���[�V���h�E���������B���͘r�ł܂Ԃ������������܂܁A���Ȃ������B
�u�ق�Ƃ��ɂ��܂��̒��Ԃł͂Ȃ��̂��H�v
�@���[�N�o�C�X���q�b�s�ɐu�����B�q�b�s�͂ǂ������Ă������킩��Ȃ������B
�@�o���E�Y�������ӂ肩�Ԃ����B�ނ̓m�[�}�ƃr�X�R�Ɍ������Ă������B�u�ǂ݂̂��A������͂�����l�Ƃ����Ă����N����Ȃ����B�T�C�|�b�c�͏��q�ǂ����e�͂Ȃ��E�������v
�@�q�b�s�̓o���E�Y�̑O�ɗ����ӂ��������B
�u��߂Ă���B���ł͂���Ȃɋ��͂��Ă��ꂽ�낤�B���m��ڂ��ɂ悭���Ă��ꂽ����Ȃ����v
�u����Ȃ��Ƃ́A�Y�ꂽ�B����ȋL���́A��������̂Ȃ��ɂ͂Ȃ��v
�@�o���E�Y�͕���U�肩�Ԃ��Ă͂������A�����U�艺�낹�Ȃ��ł����B
�u�푈�����������̂͂����܂炾�v
�u����܂��B�������ɂڂ��炪�������A����Ɂc�c�v
�@���x�̓o���E�Y���{�C�œ{�����B�u����܂��ĂȂ�ɂȂ�I�@��X�̒��Ԃ�����������̂��I�@�����܂玀�҂��Ăт����Ƃ����Ă������A�Ȃ�Ύ����̂��Ăт��ǂ��I�v
�@���͊���������Ă�������ǂ������B�o���E�Y�����̓{�肪�A�ꂵ�݂��킩�����̂��B�o���E�Y�̔�����{�C�͂��܂�ɂ���ǂ��A����͂��̂܂ܗ��̐S�ɓ����Ă����B�ޏ��͊���グ���B����ǁA��J�̂��܂�ڂ��悭�݂��Ȃ��B
�@�m�[�}�������オ��B�j�͂Ԃ�����Ǝ��オ���Ă���B�����ӂ���قǂ̌��ɂ̂��Ƃł������B
�u�g�D���[�V���h�E�B�n�b�c��������������Ȃ��A�H����Ă���̂�������Ȃ��B���̗v�E�ɂ��������̂́A�ÎE���ꂽ��A�S���ɂ����ꂽ�肵�Ă���B�M���̊Ԃ��ނ��Ⴍ���Ⴞ�B���������͔��������������Ƃ��Ă���B�ڂ���̍��͂������߂��v
�u���ꂪ�����ɂȂ�̊W������v
�@�����������B�u�W������v
�u�ȂƁH�v
�@���̓g�D���[�V���h�E���݂������B�����Ă�낤�Ǝv�����B����Ȃ��ƂɂȂ����킯���A�l�̐S�ɓ����������邢���̂����āA�����炪�݂�Ȃ𑀂��Ă���B�ł��A���͂��̑���̐��̂�m��Ȃ��āA���܂����t�ɂł��Ȃ������B�g�D���[�V���h�E�͗܂̂ނ����łɂ��B
�u��X�̓n�b�c���̎����������߂邽�߂ɑ勾�܂ł����v
�@�r�X�R�������ƁA�g�D���[�V���h�E�͏������������B
�u�����܂�̂悤�ȏ��m�������炵���_�����ƁB������������̌ܐl�ł��v
�@�r�X�R�͓f���̂Ă��B�u�O�l���B�_���ɂȂ��̂͋M���������v
�u�g�D���[�V���h�E�A������̂������Ƃ��ȁB�T�C�|�b�c�̐\���o�͂��ׂĉR����肾�v
�u�݂�Ȃ����Ă���v���[�N�o�C�X���q�ǂ�����������Ă������B�u���̎q�����͐������đ��ɂ�A��ׂ����B�l���ɂȂ邵�A�T�C�|�b�c����̂��Ƃ��u���o���邾�낤�v
�u�q�ǂ��̂������ƂȂǂȂ�ɂȂ�v
�u�����A�_���ɂȂ������̂Ȃ�A�T�C�|�b�c�̂����ł��g���͍����͂����v
�u���̈ʊK�Ȃǂ������B����ɂ͖��Ӗ��Ȃ��̂��v
�u�j�ꂽ�������Ē������߂ɂ��A�T�C�|�b�c�̋Z�p�҂��K�v�ɂȂ�v
�u���邵�������ȁA���[�N�o�C�X�v�Ǝᒷ�͌������B�u���̎q�̓^�b�g���̒�q�ɂ�����B�Č��̖��ɂ��Ƃ͎v���v
�@�g�D���[�V���h�E�̑����݂͒N�����ӂ��������B���[�N�o�C�X�͂���ɂ������B
�u���̎q�����͕�������Ȃ��B��l���N�������푈�ɂ܂����ނ��肩�v
�@�o���E�Y���Â��ɂ������B�u����͂�����S���̐�����͂��˂C�����܂B��X�̎������������ɂ݂��A���̏�ł����������̂��v
�u����ł��܂��̏���������Ƃ͎v���Ȃ��v�ނ͂��̏�ɂ���݂�Ȃɂ������B�u����Ȃ��Ƃ����Ă��A������p���邾�������v
�@���[�N�o�C�X�͖ق����B�������������Ȃ������B�i�o�z���͎����̐S�ɖ₢�������B�ނ炪�������Ƃ��ɂ���̂́A���Ȃ鐺�����Ƃł���A����ɐg���܂����邱�Ƃł͂Ȃ������̂��B
�@���l�����A�g�D���[�V���h�E�Ɍ��t���������B�ނ�͎q�ǂ��������W�߂�ƁA����ɔ��肠�����B
�u�����������ȁA���[�N�o�C�X�v���g�����b�N�����[�N�o�C�X�̌������������B�u���̑������K�v�ɂȂ����Ƃ��́A���ꂪ���܂��𐄋����Ă��v
�@���͍r��Ŏ�������������ꂽ�B�����ɂ݁A�����Ă������Ȃ������B���������̂��Ƃ��肱�����B�S�g�����т�A�ċz���Ƃ܂肩���Ă����B��J�̂��܂�A�]��������~���������Ă����B���E��������ŁA�ޏ��͂Ƃ��Ƃ��G�������B���o���Ȃ��Ȃ�A�S�g���₽�����тꂠ�������B�ӎ����Ȃ����A�ޏ��͓|�ꂽ�̂������B
���@��Z�́@�ܐl�̓����s
���@�W�m�r����N�@�\�\�n����L�ɂ�
���@�@�@�@�\
�@�L�����{�̈�p�ŁA�t���C�g�͂ЂƂ�ꂵ��ł����B���������C�Ɛ��C�̋��Ԃɂ���悤�������B
�@��������Ƃ͐����������̂��H
�@���̋^�₪���������̂����ɂ���B�ڂ����ނ��悤�Ƃ��Ă��A�^�f���A�������Ƃ��Ē��܂ʕ����t�̂悤�ɕ����т������Ă���B���k���悤�ɂ��A�܂��ɂ͂܂Ƃ��Ȑl�Ԃ����Ȃ������B��l���B
�@�t���C�g�́A�M���̂Ȃ��ł����M�ȉƕ��ɐ��܂ꂽ��҂ŁA�����炵���e�q���̈���ƂȂ��Ă���́A��N�ȏオ���B�͂��߂́A�����ȐR���̂���e�q���ɓ����ł������Ƃ��ւ炵�����������B�����A���܂ł͂��̊�����������A�������肤�����ꂽ�C������B
�@�t���C�g���X�~�X���E�����̂́A�e�q�������ƂȂ��āA�܂��Ȃ��̂��Ƃ������B
�@�X�~�X�Ƃ����̂��s�v�c�Ȓj�������B���{�̂Ȃ��Ő��Ȍ��͂��ӂ���Ă���ɂ�������炸�A�o�����K�����s���ŁA�����Ă�������E�ɂ�����Ă��Ȃ��B����ł��āA�����ł���n�t�X�̂��Ɍ��͂�����B�ǂ�ȑ�b���A�X�~�X�̌��t�ɂ͂����炦�Ȃ��悤�������B
�@�X�~�X�͉ǖقȐl�Ԃ��B�����̂����ЂɊS���Ȃ��A�����炱����b�����͂��̘V�l���ꂽ�̂��B�n�t�X�͂��̘V�l�ɑS���̐M���������A�d�v�ȑ��k�͑�b�����ނɂ��Ă����B���̃X�~�X���A����킩���t���C�g��M�����A���ʂȔC�������������̂́A���R�̏o�����Ƃ����ق��Ȃ��B
�@���̔C�������炽�ɐ����������̂́A�����ƃq���M�X�A�g���o�[���Ƃ����O�l�̎�҂������B�O�l�Ƃ����{�Ɏd���͂��߂�����Ƃ����ق��ړ_�͂Ȃ��A���ꂼ��̖�E���܂��������ƂȂ��Ă����B�q���M�X�͕����ł���A�g���o�[���͍ٔ����̖�l���B�X�~�X�����������C���ɂ��Ȃ���A������킷���Ƃ��Ȃ������͂��̐l�ނł���B���̓_�A�X�~�X�̐l�I�͍I���������B�O�l�Ƃ��g�����������A�Ȃɂ������������Ύ������̂����������B�閧�̂����댯�����Ⴉ�����̂��B
�@�Ƃ����Ă��A�t���C�g���A�����̂ق��ɔC���ɂ��Ă���҂�����̂�m�����̂́A�����ƌ�̂��Ƃ������B�X�~�X�́A�l��������������Ȃ������̂��B���ŔC���ɂ��ƕ����āA�t���C�g�͑��l�̑��݂�m�����̂������B
�@�X�~�X�͔C���ɂ��ɂ������āA�ق��̔C���҂̑F�����ւ����B�W�܂��Ęb�����邱�Ǝ��̂������Ă����B�����A���̂��Ƃ��O���ɂ����A�N�����炵�����ɊW�Ȃ��A����������p���������ƂɂȂ�ƌ������B�t���C�g�͂��̎��_�ŁA�e�q�������ƂȂ��������̖����ɁA�����������Ƃ�m�����B
�@�C���͕ς�������̂������B�ނ͖�ԁA���̑��݂�m�邱�Ƃ��Ȃ������n����L�ɍ~��Ă������ƂɂȂ����B���̉�L�̑��ݎ��̂��閧�Ȃ̂������B
�@���̏ꏊ�ɐH�����͂��B��L�͑����ȕ��͋C�ɂ݂��Ă����B�X�~�X�͂��̉�L�̂��Ƃ�����Ă���悤�������B�t���C�g������������������������Ȃ��B�����A�ڂɂْ͋����͂���A�ނ��͂������C�͋ٔ����ɂ݂��Ă����B
�@�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̉�L�ɂ͒N�����Ȃ������B�L���������ނƁA���ɖڈ������B�X�~�X�́A���̈����ɂ����ނ��Ƃ��ւ����B�H���������A��̂ނ����ɒu���Ɩ������B
�@�t���C�g�́A�H����u�����B�g���C�̃X�[�v����́A���C�������Ă����B�X�~�X�́A��͂��̏ꏊ���痧�����邱�Ƃ����𖽂����B
�@�t���C�g�ɂ͂킩��Ȃ������B�N������C�z���Ȃ������B�Ȃ̂ɁA�H����u�����B�N�����H�������Ă���͂��ł���B����ɁA��L�ɂ����ƁA�ʒu���o�������悤�ȋC���̈������������B
�@�t���C�g�͂��̎d�����A���܂���Ă̋Εׂ��łƂ߂��B���̎d���͎O���Ɉ��߂����Ă����B���A�e�q���m�̖{���ł͂Ȃ��B���̂悤�ȑҋ��������鎩�����݂��߂ł�����A�I�X�~�X�ɍ��݂��܂����C���������ڂ����B
�@���̂悤�Ȃ������Ȋ���A�{���̑����ɂ܂łƂ��ĕς�����̂́A��L�Ɋ�Ȍ��ۂ��N����͂��߂Ă��炾�����B
�@����̈ʒu�ɐH����u�����u�ԁA���Ȃ萺�����B���|����������������ɁA�w���|���̂������������Ă����B�g���Ђ˂点�āA�ʒu��������ƁA�댯�����������ƌ��Č����ʂ����B
�@�����A���̂Ƃ��́A��L�ɂ͒N�����Ȃ������B���̂Ƃ��́B
�@�t���C�g�͌������낤�ƍl�����B��L�ɂ���邽�тɊ�����A�������o�̂Ȃ����������낤�B���̏ꏊ�ł͂܂�Ŗ��̂Ȃ��ɂ���悤�ɁA�̂̊��o���A�������B�Ƃ�����A�N�ɂ��b�����Ƃ��ł��Ȃ��̂͋�ɂ������B�N�ɂ����k���邱�Ƃ��ł��Ȃ��܂܁A�t���C�g�͂��̉�ɁA�l�̎p���݂��B
�@�ނ͂��̒j�Ɩڂ��������B�啿�����A���ɂȂ���Ă���B�Ȃ����j�̂��邠����́A�ڂ₯�Ă悭�����Ȃ������B
�@�j�ɂ������������Ă���悤���B
�@�ނ�������������A�����オ�����u�ԂɁA�t���C�g�͂��̏���������B
�@�C�����Â��邱�Ƃ͍���ɂȂ����B
�@�t���C�g�͂Ȃ������̒j�̂��Ƃ�Y��邱�Ƃ��ł����A���Ɍ��A�����Ĕ������܂Ō���悤�ɂȂ����B�܂�ŁA�j�����̂Ȃ��ɂ��āA�ǂ��܂ł��ǂ������Ă���悤�������B
�@�����āA���̒j�̎p�́A�v���o�����тɑN���ɂȂ��Ă���̂������B
�@�t���C�g�͂������ɂ��̒j�̊T�e��m�邱�ƂɂȂ����B�j�̓X�~�X��������悤�ȘV�l�ŁA�₹�ق���A�d�����̂��߂Ɏ��ɏ��������Ă����B�����̂т�܂܁A���������܂܂ɂȂ��Ă���B�j������̂́A��L�ł͂Ȃ��A�ꎺ���B�̃x�b�h�A�r�������Ȃ������߂̊ȈՃg�C��������B�Ȃ�����ȏꏊ�ɂ���̂��A�����āA�����Ȃ��炦�邱�Ƃ��ł��Ă���̂����킩��Ȃ������B
�@����ڂɂȂ�ƁA�t���C�g�́A���̏ꏊ���S�i�q�łӂ�����Ă��邱�Ƃ�m�����B�j�͎��l�Ȃ̂��B
�@�����āA�܂��ނ̔Ԃ�����Ă����B
�@�t���C�g�͂Ȃ�ǂ���L�ɂ��肽�B�Ȃɂ����Ȃ����Ƃ�����A�j�ɉ���Ƃ��������B�V�l�̔��U����A���C�Ƃ��Ƃ��Ќ��ɂ�����A�t���C�g�͓��������̂��˂������B�j�͎��l���Ƃ����̂ɁA�e���̂悤�ȈЌ����܂Ƃ��Ă������炾�B
�@�t���C�g�͈����ɂ��Ȃ����悤�ɂȂ�A�₪�Ă͖���Ȃ��Ȃ����B���錾�t���A�Ȃ�ǂ��]���ɂ����B���E�͂˂��܂����Ă���A�Ƃ������t�B
�@�ނ͔C������߂����Ǝv���悤�ɂȂ������A��߂邱�Ƃ͕s�\�������B�C���͂�߂������A�܂����ɂ����͂Ȃ��������炾�B�����āA���̂Ƃ��������B
�@�n����L�ւ̔��́A����ʘH�̈�p�ɂ���B�O�~���߂����ꏊ������A���̉��ɁA��L�ɂ���邽�߂̔����������B�t���C�g�͂��̔��������̂悤�ɊJ�����B�E��ɐH���̂̂����g���C�������A����ɂ́A�䂢���̓���ƂȂ�C����������B
�@��L�ւƂÂ��K�i�́A���Ȃ蒷�����̂������B���̊K�i�́A����邽�тɒi�������������B�t���C�g�͂������A�����������邱�Ƃ��ӎ��I�ɋ��₷��悤�ɂȂ������A����A���̊K�i�̂����ɂ͉�L���Ȃ������B���̒j�ƁA�ꎺ���������B
�@���E�͂˂��܂����Ă���B
�@�t���C�g�́A�K�i���̂ڂ�A�ʘH�ɂ��ǂ낤�Ǝv�����B�������E���B���ׂĂ��X�~�X�ɘb�����B�����A����������������ɁA���̒j�̐����Ƃǂ����B���Ȃ萺�������̌��t���������̂́A���ꂪ�ŏ��̂��Ƃł���B
�u���͂ȂH�v
�@�j���������B
�u���͂ȂH�v
�@�d�˂Ă������B�t���C�g�͗E�C�������Ăӂ�ނ��ƁA�H���𓊂����Ă��B
�u�킽���̖��̓t���C�g���I�@�����܂������҂��I�v
�@�]�݂����ǂ��ǂ��Ɩ��ł��Ă���B�@�̕Б�����A�����Ȃ����B
�@�j�͍���炵�Ď��������ƁA�Ȃ����e�w�̐���łȂ߂��B
�u�悵�A�ʘH�ɂÂ��������߂�v
�@�t���C�g�͋}�ɍl���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�j�������܂܂ɔ���߂��B�Èł��Z���Ȃ����B
�@�C��̓���̉��ɁA���̒j������B
�u�H���͑厖�ɂ������B����ɂƂ��āA�䂢���̊y���ނ��̂��v
�@�t���C�g�͂킯���Ȃ����Ȃ������B
�u�~��Ă����B���܂��ɂ����ꂪ������Ƃ͊��S�̂����肾�B���̕����ɂ���Ă����̂́A�����܂��͂��߂Ă����v
�@�j�̐��͊���ɂ݂��Ă����B�t���C�g�͂܂�łق߂�ꂽ�悤�ȐS�n�����A���R�ɊK�i������Ă����B
�u���Ȃ��͉��҂ł��v
�u�����܂����A���҂��m�肽�����̂��B����ɂ͊O�̐��E�̂��Ƃ��܂�ł킩��ʁB���̎����̉�L�ɕ����߂��Ă��邩��ȁv
�u�����ł��B�����͉�L�̂͂��Ȃ̂ł��B�Ȃ̂ɁA���܂͂��̂悤�Ȉꎺ�ƂȂ��Ă���v
�@�t���C�g�ƒj�͓S�i�q�������Č����������Ă����B���l�ł��邱�Ƃɂ܂������̂Ȃ��j������܂��Ă���B���l�̑O�ɐ��������A�b�����Ƃ��Ă���B����͒j�̔����链�������ʖ��͂̂��������������A�t���C�g���g�̒m�肽���Ƃ����D��S�̂����ł��������B
�u���܂�������̂́A�����̋��Ԃ��B���̕����͂��̋��Ԃɂ���v
�@�t���C�g�͒j�̂����Ă��邱�Ƃ������ł��Ȃ������B�ނ́A�e�q���Ƃ͂����A�����ȕ����ł���A�{��̋V����`���ɂ͂��Ƃ������̂��B
�u���܂肱���ɂ͂���܂���B�A�肪�x���ƁA�X�~�X���܂ɉ����܂�܂��v
�u�X�~�X���v
�@�j���吺���͂������B�t���C�g�̂��C��̉���ꂽ�B
�u����A���܂�B���̒j�Ƃ͂ȁv
�@���̋����ɂ́A����Ƃ��{��Ƃ��Ƃ�ʐk��������B
�u�C�ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��낤�B�����̋��ԂɎ��Ԃ͖��Ӗ��Ƃ������̂��B��������A�����̂˂��܂��肪���ǂ����Ƃ��ɁA�����܂��ǂ���̐��E�ɂ��邩���v
�@�˂��܂���A�ƕ������Ƃ��A�t���C�g�͉ߏ�ɔ��������B�j�̂����Ă��邱�Ƃ��A�Ȃ�ƂȂ������ł����B�M�����Ȃ��C���������A�����ɂ͔ے�͂ł��Ȃ������B�ނ͂͂₭�����グ�����āA�����オ�����B�����A�m�肽���Ƃ����~�����������Ăł��B
�u���Ȃ��͂Ȃ������Ɂc�c�v
�@�j�͎���グ�āA�t���C�g�̎���������������B
�u�܂��A���ꂪ���҂ł��邩�ɓ����悤�v
�@�t���C�g�͒n��ւƂÂ��K�i�������Ă��Ȃ����Ƃӂ�ނ��B
�u���܂��܂Ȗ��ŌĂ�Ă������̂����A�����܂ɂ̓g���C�X�Ɩ�����Ă��B���̂ق����A��X�킩��₷���낤�B���ꂪ�����ɂ���킯�����A����̓n�t�X�ƁA�����܂̒m��X�~�X�Ƃ����j�ɂ͂߂�ꂽ�����B��������̏�ɕ������̂́A�G�r�G���Ƃ����������v
�@�t���C�g�̋����ɁA����Ȃ�^�₪�ӂ���B
�u���Ȃ��������A�n�t�X�Ƃ́A�O�����̂��Ƃł����H�v
�u�ق��A�������v�ƃg���C�X�͊�F�������ׂ�B�u���̒j���ȁB����̌㊘�ɂ�������킯���v
�@�㊘���ƁH�@�ǂ��������Ƃ��H
�u�������A���Ȃ��̂����G�r�G���́c�c�v
�u�݂�A�t���C�g�v
�@�g���C�X�͌������B�t���C�g�͔w���������݂��B�ނ̊�O�ŋ�Ԃ��䂪�݁A�Ⴍ���Ȃ�悤�Ȋ�ȉ��������B
�u�����̔������悤�Ƃ��Ă���B���ꂽ���̓Q�[�g�Ƃ��ł������ȁc�c�v
�u��A�킽���͂����A���炷��B���Ȃ��͎��l���B�����Ă��邱�Ƃ͂܂₩�����v
�u�������ȁB�ł́A�X�~�X�͂Ȃ����̏ꏊ��閧�ɂ���A���܂������ɐH�����͂�����B���ׂĂ�u���Ă݂邱�Ƃ��I�@����͂��܂��̎v�������傤�̎҂��I�@���������ǂ����ɂ����I�@���ꂪ�ق�Ƃ��͉��҂Ȃ̂����A�����܂ɋ����Ă��I�v
�@�t���C�g�͊K�i���삯�̂ڂ�͂��߂����A�}�ɐS�ς�肪���Ăӂ�ނ����B
�@�ނ́A�g���C�X�Ɍ������Ă����������B
�u�G�r�G���Ƃ����l�����A���͈�l�����m��Ȃ��B�O�S�N�O�ɐ����Ă����l���v
�@���̏u�ԁA�g���C�X�͂����܂����{�C���͂����A�������i�������A�t���C�g�ɂ͂��͂⎨�ɂƂǂ��Ȃ������B�ނ́A�����A�����炪�瓦���������̂ł���B
�@�t���C�g�̓X�~�X�ɂ��ׂĂ�b�������Ǝv�����B�n����L�ɁA�閧�̂͂��̘S�����o�����Ă���ƁB�����A�����ɂ���j�Ƙb�����Ȃǂƌ����邾�낤���H�@�������閧���ɂ������ƁH�@�ƂĂ��A�ł��Ȃ����Ƃ��B
�@�t���C�g�͔閧�����������܂h�ɂɂ��ǂ�A�g���C�X�Ƃ̉�b�A���̒j���͂��������t�̐��X���v�����������B
�@�g���C�X�͂������Ȃ��Ƃ������Ă����B�ނ̌��t�𐄑�����ɁA�������������������Ƃ����Ă���B�������A���̒j�������̂͂��̐��łȂ��ǂ����ׂ̐��E�B���̕������������̂́A�O�S�N�O�Ɏ��A�����̃G�r�G�����ƌ����B
�u���̖������Ƃ����߂��̂��Ƃ�����A���̒j�͎O�S�Ȃ̂��H�v
�@�z�c�̂Ȃ��ŁA�t���C�g�͐��������ď����B�����A�����A���Â����B
�@�₪�āA����ʖ邪����Ă����B
�@��l�����킵�����t�͐������Ȃ��������A�t���C�g�͂����ɂ��̘V�l���댯�Ȓj�Ȃ̂��Ƃ�������悤�ɂȂ����B�Ȃɂ����댯�Ȃ̂́A�v�z�����A�S�g����͂����閣�͂��B���̘V�l�͐l���䂫����A�l�S����������p�ɂ����Ă����B���̐́A�����ł������Ƃ��Ă����������͂Ȃ��B
�u���ȁA���̒j�̌��t�����݂̂ɂ���̂��c�c�v
�@�����A�������߂�K�v�͂���Ǝv�����B��l���鉿�l�͂���ƁB
�@�@��͂����ɂ���Ă����B��̖x�Ŏ��E�̂�������A�X�~�X����́A�H�����͂��ԉ��ӂ���ƍ�����ꂽ�B���ꂪ�q���M�X�Ƃ����j�ŁA���̒j���C���ɂ������Ă����Ɛ������ꂽ�B
�u�g���C�X�́A�����܂ɂ����ꂪ������̂��Ƃ����Ă����B�����܂ɂ��A�ƁB�q���M�X���A�g���C�X�ɉ�����Ƃ������Ƃ��H�v
�@�����̏d�݂ɑς�����Ȃ��Ȃ��āA���̂��낤���H
�@�t���C�g���C���ɂ��́A����Ɉ�x�ɂȂ����B�������A�g���C�X�͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B�ڂ���ƌ��������ɂȂ邱�Ƃ�����A�܂������������Ȃ������Â����B�܂�Ƃ���A���������̒j�ɉ�����̂́A���R�ł������̂��B�q���M�X�̎����A���邢�͋��R�Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�t���C�g�͂��̏u�Ԃ�҂����܂��A�������ƐH�����͂��тÂ����B�����āA���̎��͂���Ă����B
�@��L�̉��́A�S����ڂɂ���ȑO����A�t���C�g�̓g���C�X�̏o����\�����Ă����B�̂̏�Ԃ��A�V�l�̏o����\�����Ă����B�ۓ����������A���邢������Ԃɂ������B���̉�]�����܂��āA���ׂĂ����ʂ��邩�̂悤���B
�@�t���C�g�́A�K�i��T�d�ɂ���A�S�i�q�̒��O�ɒ��d�ɂ������B�������܂�ō����ɂ�������悤�ȏl�R�Ƃ����ԓx���Ƃ��Ă��邱�ƂɋC�����Ă��A���͂�����Ȃ������B
�@�g���C�X�͈ȑO�Ƃ���炸�A���R�Ƃ��Ă����B
�u�q���M�X�͎��ɂ܂����v
�@�g���C�X�͂��Ȃ������B�����A���܂��͐����Ă���A�ƌ�炸���A�`���Ă��邩�̂悤���B
�u���Ȃ��͍����Ȃ̂ł����H�v
�u����͉��ł͂Ȃ��v
�@�t���C�g�͐S����炮�悤�ɑ̂�h����B
�u�ł́A���Ȃ��́A���Ȃ��́A�Ȃ�Ȃ̂ł��v
�u���܂���������������炾���Ƃ����̂Ȃ�A���܂��ɁA����̖����A���z���A���ׂĂ������悤�v
�u���Ȃ�����������o���c�c�v
�@������̂悤�ȋC�������B
�@�t���C�g�ɂ������ɂ̂����������́A���̒j�����C�ł͂Ȃ��ƍ����Ă����B���̒j�͋C�������Ă���B�ȑO�͂܂Ƃ��������Ƃ��Ă��A����ȈÈł̈ꎺ�ŁA���\�N�����킩��Ȃ��N�����߂����Ă����̂��B
�@�t���C�g�͊z�Ɏ���������Ă�B�u�킽���̓��̂Ȃ��ɁA���t�������ԁB���E�͂˂��Ȃ����ĂȂǂ��Ȃ��̂Ɂv
�u����A���E�̕���͂�����ł���B�����ɂȁv
�@�g���C�X�͂��̂܂ɂ��S�i�q�̑��ɂ��āA�S�̊i�q�����̎�ł���ł����B
�u�����܂ɂЂƂ��������B�G�r�G���͖{���Ɏ��̂��H�v
�u�G�r�G���Ƃ��������Ȃ�A��l�������܂���B����ł���A�O�S�N�������Ă���v
�@�g���C�X�͓ˑR�A�z��S���ɂ��������B
�u�����ƁH�@���̖��������I�v
�@�g���C�X�͋��B
�u�Ȃ����̏������I�@���̏��͂��ꂪ�E�����I�@���̂��������ȘS���ɕ����߂��I�@�������A�T�C�|�b�c�ɂ����̏����I�@���̂���̂Ȃ邩���m��Ȃ�����炪�I�v
�@�g���C�X�͊i�q�������̂��B
�u�G�r�G��������ŎO�S�N�����������Ƃ��I�@�Ȃ�Ȃ��n�t�X�ƃX�~�X�������Ă���I�@�ق��̘A���͂ǂ��������I�v
�u����߂��������I�@����������Ă���Ӗ����킩��܂���v
�u�Ȃ�A�X�~�X���E���I�@���������A�������������o���I�v
�u���ȁA����Ȃ��Ƃ��ł���͂����c�c�v
�@���Ƃ����낤�Ƃ����t���C�g�́A�n�ʂɂ����ꂽ�H��ɑ��������A�]�B�g���C�X���A�i�q�̂����܂������̂��A�t���C�g�̋��q�����B
�@���̏u�ԁA�d�����������悤�ɁA�t���C�g�̎v�l��������B�܂�ʼn������Ȃ�����A�����̑̂��݂Ă���悤�������B
�@�N�����̂̂Ȃ��ɓ��肱��ł���B
�u�X�~�X���E���A����D���B��������A�����܂ɂ��ׂĂ������Ă��v
�@�t���C�g�͂��Ȃ������B�C����̂Ă�ƁA�������������A�K�i��������B
�@�����āA�X�~�X���E�����B
�@�t���C�g�͌��܂݂�̎�ŁA�k���Ȃ���A�����ɂ����������Ƃ������B
�u�ǂ�������܂���B�X�~�X�l�͌��������Ă��Ȃ������B����ȏd�v�Ȍ������������͂����Ȃ��v
�@��]�����悤�ɋ����Ă���B�g���C�X�͂������ނ悤�ɕ��ł��B
�u�Ă���ȁB�����܂͂悭������B����ɂ͂킩�邼�B���̒j������A������ɂ��Ă����ƁB�Ȃ��Ȃ�A���E�ɂ͂��ꂪ�K�v�����炾�B�����łȂ���A�Ȃ������̋��܂������܂ł���ԁB�����A����������B���̍��������͂ȂāI�@��������A���ׂĂ��n�܂�ɂ��ǂ��Ă��v
�@���̌��t�ƂƂ��ɁA�������A�J�`���Ɖ������Ă��B
�u���H�v
�@�t���C�g�͗܂ɂ��ꂽ�܂܊���グ��B�u�͂��܂�Ƃ͂Ȃ�ł��v
�@�����J���A�g���C�X�̎肪�A���ɂ̂����B
�u����������Ă��B�����A����f���邪�����I�@�I���Ƃ͂��܂肪��������A���I�v
�@�t���C�g�͌��ō���f����A���ׂĂ�������ꂽ�B����́A�g���C�X�̋L���A�g���C�X�ȑO�̒j�̋L���������B�j�̂������Ƃ���A�t���C�g�ɂ́A���̂قƂ�ǂ������ł��Ȃ������B�j�����肱��ł������̗ʂ͂ƂĂ��Ȃ��A���ꂾ���ŁA�]��H�̂��������Ă��ꂽ�قǂ������B
�@���ׂĂ��I������Ƃ��A�t���C�g�́A�C�������Ă����B�ڊo�߂�����A�p�l���R�ɂ����������B�����̔��͕��Ă����B��l�͂��̏�ŁA���̋@����A�Q�[�g���J���̂��܂����܂����B
�@���ꂩ��́A�����Ƃ����Ԃ̂��Ƃ������B�t���C�g�͏�̈�p�Ƀg���C�X�������܂��A����̗L�͎҂��������킹���B�g���C�X�͂����ƐM��҂��ӂ₵�A�N�ɂ��m���邱�ƂȂ��A���͂��܂��Ă������B�e�q����z���ɂ��킦��ƁA�������ł���_�b�^������x�z���Ă��܂����B��N���������܂ł́A��b�����������A�R�Ɛ����̑S�����ɂ����Ă���B
�@�ŏ��̂����A�t���C�g�ɂƂ��āA�g���C�X�̘b�͐����ł��炵�����̂������B�����A����ɂ��������āA�C�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����B
�@����N���̔N�����o�����̂悤�ȕ\��B����������낤�Ƃ������A���������͂����ɂ��Ă���B�S�g�̗������ӂ�܂��͐��C�ɂ݂��A���͔M�C�����тĂ���B�Ⴍ�͂�����̂ɁA�ӎ`�̊Ԃ���邪���悤���B�t���C�g��A�z���̐b�́A�͂��Ƃ��Ċ���ӂ����B�j���{���Ă�������ł���B
�u�_���͂��ׂĕ߂炦��ƌ������͂����v
�@��b���A��⊾�������Ȃ���A�i�݂ł�B
�u�G�z�Ȃ���A�É��B�_���E�ɂ�����������҂́A�̂��炸�H�������Ă���܂��v
�u�ł́A�Ȃ��A�Q�[�g���J�����̂��I�v
�@�g���C�X�̓{���ɁA�ꓯ�������낢���B
�u�Ɛ\���܂��ƁH�v
�u�_�����Ƃ炦���̂Ȃ�A�V����m��҂͂��Ȃ��͂����B�����A�يE����l�Ԃ��Ăт悹���҂�����v
�@�t���C�g��͍��f����(�t���C�g�ɂ݂̂̓g���C�X�̌��t����������)�B�ނ�͐e�q���ł���A�V���ɐ��ʂ�����̂����Ȃ��������炾�B�����ł���ނ�ɂ́A�Â߂������V���ȂǁA����Ȃ�V��Ƃ����݂Ă��Ȃ������̂��B
�u�V�����_���E�ɏA�C�����҂�����܂��v
�u���ȁB�n�u���P�b�g������ɂ��������̂́A�킸���Ȋ��Ԃɂ�����v
�@�g���C�X�͍l�����B�Q�[�g���J�����̂͂܂������Ȃ��B�C�j�V�G�̐X�ł̏o�����̂悤���B�������ɂ́A�勾������B�Q�[�g���J����_���͂��ׂĕ߂炦���͂����B�N���J�����̂��H
�u�C�j�V�G�̐X�ɂ́A�G�r�G�����Z��ł����͂����B���̖����́A�{���Ɏ��̂��H�v
�u�É��̂��������V�k���A��X�̒m��G�r�G���Ȃ�A�����Ă͂���܂��܂��B���������̂͐��S�N�Ɛ̂̂��Ƃł��v
�u�ł͂Ȃ��A�n�t�X�͐����Ă����c�c�v
�@�n�t�X���O�S�N�������Ă������Ƃ́A�ނƃt���C�g�ȊO�͒N���m��Ȃ��B
�@�g���C�X�ɂ́A�킩��Ȃ������B�����̃T�C�|�b�c�ł���n�t�X���A�O�S�N�����������Ǝ��̂��ُ킾�����B�����Ȃ��炦����@���������̂��Ƃ�����A�Ȃ��G�r�G���͎��̂��A�����Ȃ������B�G�r�G���̓n�t�X�ɂƂ��Ă��ł��d�v�Ȑl���̂͂����B
�u�G�r�G���ł͂������܂��ʂ��A���̐X�ɂ͂������ɖ���������܂��v
�u�ȂƁH�@���͂Ȃ�Ƃ����H�v
�u�}�[�T�Ɛ\���V�k�ł������܂��B������̂��킳�̂���l���ł����A���킵�����̂�������̂�����܂���B�n�t�X�剤�Ƃ������������̂͊m���ł����c�c�v
�@�g���C�X�͑�b�ɒ��ڂ����B
�@���̏��Ɠ��������c�c�B
�u�}�[�T�Ƃ����̂́A�G�r�G���̒�q�̂͂����v
�u����͖{�l�̐��������\�ɂ����܂��ʁv
�@�g���C�X�͍l�����B�n�t�X����́A�����b�͕����������Ƃ͂ł��Ȃ������B�G�r�G�������̂Ȃ�A�}�[�T�������Ă���Ƃ͍l���ɂ����B�����A������m��\����������̂́A�}�[�T�̂ق��ɂ͂������Ȃ��̂ł���B�}�[�T�������Ă���̂Ȃ�A�E�����ɕ߂炦��K�v������B
�@�N���V���������Ȃ����̂��͂������̂��ƁA���������N���Ăт悹���̂��ׂ�K�v���������B
�@�܂����A�ӂ����ю�������������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ����낤���A���C���ǂ��ɂ��邩�킩��Ȃ��ȏ�A���f�͂ł��Ȃ������B
���@��Z��Z�N�Z���\�l���@�\�\�@��ԓ�
���@�@�@�@�\��
�@�������Ɛΐ�щp�́A�V�����̍��Ȃŕ��v���ɂӂ����Ă����B��Ԃ͐�t�����߂����ĂЂ�����B����͋����̐_�ے��ɂނ������ł���ƂƂ��ɁA�L�������ǂ闷�ł��������B
�@��l�͉w�̃L���X�N�ŃL���b�v���̃r�[�������B�����Ŏԓ��͂����Ă����B�������l�����Ԃ���O����ɐ����ς炤�̂����Ƃ��߂�l�����Ȃ��B�����Ƃ��A����ȂƂ��ɐ����ς炤�̂͂܂�����������Ȃ��B���W�̂��������Ƃ��ɁA���̂��Ȃ����̂́B
�@�ł��A�������Đ����Ȃ��悤�ȋC�������B
�@�R���\�[���ɂ������}�O�i���h���C�����������A���͗�Ԃ̊O���݂Ă���B���̂ނ����ɓc�����Ђ낪��A������̉��ɂ͍H��Q�炵�����˂��݂���B
�@���͂낭�ȗp�ӂ������ɂ����B�ǂ�������q�̉Ƃɂ��낪�肱�ނ̂����A�����ނ����ɂ���̂������߂Ȃ��܂܂��B���߂��Ȃ����Ƃ����A�A��Ȃ���������Ȃ������B�ޏ��͂قƂ�ǎ�Ԃ�ŗ�������A�щp�͂�����Ă��܂����B
�@���́A�܂��G�Y�Ə��q�̂Ƃ���ɋA�肽�������B�Ƃ̂Ȃ��͂��̂܂܂ɂ��ė����B�������Ȃ��ƁA���̓�l��������Y��邱�ƂɂȂ肻���ŕ|�������̂��B�_�ے��ɂ��ǂ肽���Ă������Ȃ��̂Ɠ��l�A����ȋ����ϔO�ɂƂ���āA�ޏ��͂������k�����̂������B
�@�щp�̓v���^�u���͂����A����r�[�����Ȃ������ށB�����Ƀ^�o�R���ق��������B�L���b�v���������w���ӂ邦��B�����ł͋��|�������Ă��Ȃ����肾�������A�̂͂������蔽�����Ă����B
�u����q�ɂ͘A�����Ƃ����́H�v
�@���͖����������B
�u�Ȃɂ�����Ȃ��ōs������H�v
�@�щp�͏�k�ۂ����������A���͑��̊O���ނ����܂܂��B�ޏ��͂����ꂽ�悤�ɕ@��炵���B
�u����Ȃ��Ƃ��Ⴀ�A����������H�����ς���܂����v
�@�ƃr�[�������B�����������B
�u�ʂ��Ȃ������̂�v
�u�Ȃ��āH�v
�@�щp���������B
�u�ʂ��Ȃ������̂�B�d�b�����������ǁc�c���̎q�����ɏo�Ă��Ƃ�����Ȃ��āA�Ăяo�������̂���Ȃ������v
�@�щp�͎�サ���������B�u�d�b���������������Ⴀ�c�c�v
�u�w�ł����߂����v�Ɨ��͂��������B�u����Ȃ��v
�@��l�͂��܂肱�B���炭�r�[�������݂Â����B�\�z�ǂ���A�������܂��Ȃ��B�݂�Ȃ͂����ꑫ��ɂ��܂��肳�܂ɍs���Ă���̂�������Ȃ��B
�@�o���o���ɂȂ����炾�߂��B���͖����ɂ����v���B�����ɂ��ǂ�A�Ȃɂ����͂����肷��̂ł͂Ȃ����Ɠ�l�͎v���Ă������A�͂����肳���邱�Ǝ��̂����܂ł͕|�������B
�@���͉E��̂Ȃ��ł������ƃL���b�v���܂킷�B���ނقǂɓ������݂����Ă���B�ޏ��͌������B
�u����q�����͗��_�R�ɂ������̂�v
�@�щp�����ǂ낢���B
�u���H�v
�u���N�̎l���\�\���̎R�̂��ƁA�ǂ̂��炢�o���Ă�H�v
�@�щp������ӂ�B���͔ޏ��������ƌ����B
�u���̎R�ɃL�����v�ꂪ�ł��Ă���Ă����Ă���B�������Ђ낪���āA���b�W���ł������A�A�X���`�b�N���ӂ��Ă�炵���̂�v
�@�щp�͂����������ɘr�����������B
�u�Ȃɂ��������́H�v
�u�킩��Ȃ��B���킵�����Ƃ�����Ȃ���������B�ł��A����q�̂�A���������q�ǂ��̂���A��l�Ŗ��������Ă����Ă��v
�u�o���Ă�́H�v
�@���͓����������B�u�قƂ�NJo���ĂȂ��Ȃ��B����q�͂��̂Ƃ���������̎��̂��݂������Ă����̂�B�ł�����o���ĂȂ���ˁv
�u�����o���Ă�킯�͂Ȃ��̂�v�щp�̓r�[�����R���\�[���ɒu�����B�u���̎��ɂ͂����͂���Ă�����B�A�X���`�b�N���c�c������������������ˁv
�u����B���̂��Ƃ��A�����͂Ђ낪�����ˁv
�@�Ȃ��A���̎R���l���Ăт悹�Ă����悤�ȋC�����āA���͂����犦���悤�ȐS�n�������B
�@�щp�͌����B�u�����������͍�������̎��̂��݂��āA�x�@���Ă�ł�������̂�B���̐e�������܂��肳�܂ɓ����Ă��āA���̂��ƁA�������Ă���B����q�̂����x�@���Ă�ŁA�����������͂��܂��肳�܂̊O�ɏo���ꂽ�̂�B���ԏ�Ƀp�g�J�[���������܂��ĂāA�A��̓p�g�J�[�ɏ悹��ꂽ��Ȃ����ȁB�Ƃɂ����呛���������킯�B����q�͂�����ɂԂ��Ƃ���邵�ˁB���̐e������͌x�@�ɂ����Ă肵�ڂ��Ă��v
�@�ق�ƂɁc�c�Ɨ��͕�R�Ƃ���B�V�[�g�ɓ�����������B���̊O�ɓ����ނ����B�c�����J�ɂ��ނ��Ă���B�_�ے��ɂ����Â��قǂɁA�V�C�������Ȃ��Ă����悤���B�̋����A�������Ȃ��Ă����B
�@��\�ܔN�̌����������܂��Ă����悤�ŁA�|�������B���͂��̓��̓V�C������Ȃӂ��������Ǝv���o���B�����͐���Ă����̂ɁA�}���ɓ܂��Ă������A���̓��B
�@����ܔN�����\����\�\
���@���_�R
���@�@�@�@�\��
�@�B�Y�����͎R�ɂ͂���Ȃ������B�x�@�������\���قǂ̊ԁA�q�ǂ��������r�Y���A�������悤�ɗ������������B
�@�{�������R�ɂ킯�����Ă���ƁA���̑{���͌x�@�ɂ䂾�˂�ꂽ�B
�@���܂��肳�܂͕�����A�q�ǂ������͊O�ɂ����ꂽ�B
�@���ԏ�ɂ̓p�g�J�[���������܂��Ă���B����q�̕�e�́A���ɖ\�s�����킦�āA���܂͂��̃p�g�J�[�̂Ȃ��ɂ���B���d�ɒ��ӂ������Ă���悤�����A����͌��̉J���ӂ邾�낤�Ǝщp�͎v�����B�������ɁA���������߂Ă�����Ă���Ȃ�����B
�@���܂��肳�܂͖��Ԃ������A�傫�����̌����J���Ă����B�吨�̑{�����ƒn���̏��h�c���A��������o���肵�Ă����B��]���̂����肪�A����I�Ɏq�ǂ������̊���Ƃ炵�Ă����B
�@�݂�Ȃ͕s�����ɂ��܂��肳�܂����Ă���B
�@���ꂽ���������Ȃ���A�݂��������Ȃ��̂ɁA�Ɗ����������₢���B�B�Y�����Ȃ����B�x�@�͂�����E�l�����ƒf�肵�đ{�����Ă���B���̂��Ƃ́A�R�ɂ̂����Ă����E�l�Ƃ��A�ꂳ�����\��������Ƃ����Ă����B�����͂��������悤�ŊԈႢ�������B���̓_�ł́A�q�ǂ������̌����ƁA��l�����̌����͑啝�ɂ������Ă���B
�@�A�ꂳ��ꂽ�͖̂{�������ǁA�A�ꂳ�����̂͌x�@���l����悤�ȎE�l�Ƃ���Ȃ��B�l�Ԃł���Ȃ���������Ȃ��B
�@����q�͕�e�ɉ����āA�@�������邸�邷�����Ă���B�������́A�@����Ă�����͂����Ȃ������B�����Ȃ����Ƃ������͖̂{�����B����ɁA�R�ɂ͂������킯�Ȃ�Ă����Ȃ��B�����N�ɂ��������Ƃ��ł����A�q�ǂ������͂炩�����B�x�@����h�̎������ɂ��������A�Ȃɂ������̂��Ƃ��v���ƁA���Ă������Ă������Ȃ������B
�@�x�@�͑{���ƂƂ��ɁA���ꌟ�������߂Ă���B����q�͎�����킹�ċF�邵���Ȃ������B���̕�e�͂����ɂ͂��Ȃ�����A�������F���Ă�邵���Ȃ��B���̎q�͖��̂����Ŗ����������ŁA�����Ƃ��ǂ��Ă�����ƁA��ꂫ�������ŐM���邵���Ȃ������B�x�@�������Ă��邵�A��l������Ȃɂ��������X�ɂ͂����Ă���B������A���܂��肳�܂���A�߂��Ă��܂��悤�Ɂc�c
�@�����ǁA���Ԃ͂�������ɂ����Ă�������ŁA���̂��Ƃ͍��Ղ��猩���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@�ߌ�O���������A���ɐS�z���Ă����J���~��͂��߂��B酉J���R���������A�{���̖����͂肾�����B�x�@����͂�������ɂ��ǂ�悤�ɂ���ꂽ���A�������̂͂��Ȃ������B�p�g�J�[�̂Ȃ��ŁA���̖������v���ċF��Â����B�����ǁA�ނ�̌����́A�����o�[�������邱�ƂŐꂩ�����Ă����B�ނ�����̂��Ƃ�m���Ă����B���������́A���������܂����B
�@���̂���A���͗��_�R�ɂ͂��Ȃ��������A����q�������z�����邨�܂��肳�܂ɂ����Ȃ������B���m��ʐX�ɂ��āA���Ղ������Ă����B�ޏ��̔]�͏Ă��ꂩ�����Ă���B�Ђ炽�������A���ʐ��O�������̂��\�\
���@�W�m�r����O�N�@�\�\�C�j�V�G�̐X
���@�@�@�@�\�O
�@�m�[�}�����̌v��ł́A���̂����ɂ́A�V�����I���A�A�r�ɂ��Ă���͂��������B���ɋA����̂́A�����̗\��ł����B����ȏ�����̂т�̂͂܂��������B���~�ɂ��Ȃ����Ƃ����o������A�ǂ�ȍ߂ɖ���邩�킩��Ȃ��B���܂ǂ��́A�܂��Ƃ��ȗ��R�ȂǂȂ��Ƃ��A���Ƃ��߂��邱�Ƃ������������炾�i�t�ɂ������̎O�l�́A���̃h�T�N�T�ɐ_���ɂȂ����Ƃ���������邪�B����ƂĂ��ނ�̈ӎv�ł͂Ȃ������̂��j�B
�@�r�X�R�́A���̍�������ȂƂ��ɁA�i�o�z�̑��Ȃǂɂ����Ď����������킯�ɂ͂�����A�����܂炾���ōs���A�Ƃ����āA�N��̏��N���������܂点���B�m�[�}�́A�q�b�s���������炽���������A�܂������ɎE�����Ƃ�����A���ɂ�����Ƃ����܂��A�Ƃ����ăr�X�R�����܂点���B
�@�勾����łĂ������̎q�́A���܂��������܂܂��B���M�������A�m�[�}���w���ɂ��Ԃ��Ă���Ԃ��A�����Ƃ��Ȃ���Â��Ă����B������ʌ��t�����킲�Ƃ̂悤�ɂ���ׂ�A���N�������C����邪�点���B
�@�g�D���[�V���h�E�͑��ɋA������Ƃ��ł����ɂ��炢�炵�Ă���B�i�o�z�������Ȃ�A���v�܂łɂ��Ă����͂����B�T�C�|�b�c�̎q�ǂ��ȂǁA�������E���ċA���Ă��܂����������ɂ������Ȃ��B�q�b�s�̑��݂��Ȃ���A���܂��떽���Ȃ����Ă������Ƃ��A�r�X�R���݂Ƃ߂�������Ȃ������B
�@�C�j�V�G�̐X�ɓ��������݁A�i�o�z���͓����Ȃ��ɂ��ăL�����v�邱�ƂɂȂ����B�����̖����肪�A�ѕz�����Ԃ������܂݂�̎q�ǂ����Ƃ炵�Ă���B���̎q�́A�זE���ς�������悤�ȔM�U���Ă���B�т������Ɗ��������A�O�͂��킢�Ă����B�Ƃ������z�����������A���N������S�z�������B
�@�q�b�s�̓��[�N�o�C�X�����ꂽ�����^�I���ɂ��܂��A���̂Ђ����ɒu�����B�����̓����M���ۂ������B���Ԃ����ĂA���̕s���Ȑ��_�̂Ȃ�����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv�������A�Â����҂ł������悤���B����ȏ�A���̐��_���͂����Ă��Ȃ��悤�A�q�b�s�͋�J���Ĉӎ��̎Ւf�ɂƂ߂Ă����B���̂��Ƃ͋C�̓ł��������A���̂܂ܐ��_�̓������Â��A�����̋ꂵ�݂��Â��̂Ȃ�A����������ł����ƁA�s�����Ȃ��Ƃ��v���A����Ȏ�����p����̂������B
�@���͂Ƃ����肤�߂������グ�A���ꂪ�l�l�̏��N�����������s���ɂ����A�����߂����C�����ɂ������B���̐��E�ɌĂт��Ɛӂ߂�ꂽ���Ƃ��A�g�ɂ��������B�����ȂƂ���A�K�����ڂ�������̋V�����A����Ȍ��ʂ�����ڂ��Ƃ́A�l�������Ȃ������̂��B�n�b�c���ƌ�M���Ƃ�邩������Ȃ��B�����ėH����Ă���̂Ȃ�A�~���������Ƃ��ł��邩������Ȃ��Ƃ����p�Y�I�Ȃ�����݂́A�ȒP�ɂ����Ă��܂����B
�@�r�X�R�̓m�[�}�����̌��Ԃɂ̂��āA�����܂ł�������������B���Ȃ��_���ł���Ȃ���A���Ă��Ȃ������}�I������������i���̎l�l�͐M�p�Ȃ炸�A�U�������Ȃ������̂����B�ނ����Ēm��Ȃ��ق����������Ƃ�����j�B
�@�l�l�͂��������ē��������`�����X���������������A�g�D���[�V���h�E�����͂��������������ǂ��A�˂ɔނ�̖ڋʂ��͂���悤�ȐS�n�������B�ꌩ���낢�ł���悤�Ɍ����邪�A������ɒ��ӂ��ނ��Ă���悤���B
�@�����Ɏ}���ق���Ȃ���A�m�[�}�͍l���Ԃ����ɂ������B
�u�o���E�Y�̂����Ă������Ƃ͖{�����낤���H�v
�u�������s�E�������Ȃ����Ƃ����b���H�v
�@�r�X�R���Ԃ₢���B
�@�q�b�s�ƃy�b�N�́A��l�̐N�̉�b�����ƂȂ��������Ă����B�܂��q�ǂ��Ƃ����Ă�����l�ɂ́A�s�E�ȂǑz�������Ȃ��b���B
�u�푈�����Ă���̂͒m���Ă������A����͂��ŁA���q�ǂ����E�����Ƃ������v
�u�����߂�A���ɕ������v
�@������������ȁA�ƃr�X�R�͕t���������B
�@�l�l�́A���������Ɋ��蓖�Ă�ꂽ������������ł���B�i�o�z�̒j�����͕��������킸�ɁA�v���v���̏ꏊ�ł��낢�ł���B
�u�є�̔����Ȃ�A�b�ɕ��������Ƃ͂���B���������������Ă���B���̂Ȃ��Ƀi�o�z���������Ă����Ƃ͒m��Ȃ������c�c�v�m�[�}�̐��ڂ��A�����̖�����ŗh��߂��Ă���B�u���ꂪ�ق�Ƃ����Ƃ�����A�ň�����B�����͂Ƃ�ł��Ȃ����܂�Ă�B������̓{����݂����H�@�ƂĂ��R�Ƃ͂�������B�T�C�|�b�c���m�ł��A���Y����`���p�����Ă�B�����Â��ŁA�����̒��ɂ͑f���̒m��Ȃ������吨����B�����炪�����Ɣƍ߂��N�����Ă�v
�u�ǂ����ɂ���T�C�|�b�c�͂����I��肾�B�l���Ă��݂�A���ꂽ���͂�����푰�Ɛ���Ă�B�ߗׂ̂�����푰�Ƃ����B���܂͏����Ă��Ă��A���̂����܂������ɂ����Ɍ��܂��Ă�B�����̐����ǂ�Ȃɑ��������Ăނ��Ȃ�B�~�߂�ɂ́A���܍����̂܂��ɂ���ɑ�������S���ɂ���������ŁA�푈����߂����邵���Ȃ��B����A�S���ɂ͂���邾���ł͑���B�푈�̂��߂ɕ��������悵�āA�������Ђ��܂����Ă���B���̓{������炰��ɂ́A���̘A�������J�ŏ��Y���邵���Ȃ���B�Ȃ̂ɁA���ꂽ���͂������瓦���o�����Ƃ��ł���v�r�X�R�͖����Ă���悤�Ɍ�����i�o�z���̂ق��������B�u�����Ă���悤�ɂ݂��邪�A�ǂ������������ӂ����ł�B���̊��̂���ǂ��ُ͈킾�B����͓����悤�ƍl���������ň������肽�����ꂽ�v
�u�܂����A���R�ł��傤�H�v�y�b�N���������B
�u���܂��͂����̖ڂ����Ă��Ȃ�����ȁv�r�X�R�͕����ɐ��ق������B
�@�q�b�s�͍l���Ԃ����ɂ������B�u���̐X�ɂ��T�C�|�b�c�̕��������Ă����ł��傤�B�Ȃ�Ƃ��A�����Ƃ�Ȃ���ł����H�v
�u�Ƃ��Ăǂ�����H�@�����ł��Ȃ����ꂽ���������ɂ��邱�Ƃ��A�Ȃ�Ɛ���������肾�H�@�ɑ��ǂ���肳���ɁA�������������ɂ������v
�@�ƃr�X�R�͌��������A����������ȂƂ���ɗU�����O�l�̂��Ƃ�ӂ߂͂��Ȃ������B�m�[�}�͂����������ނ̂��Ƃ��݂Ȃ������B�r�X�R�����������̂́A�ނ����݂̍����ɕs���������Ă������炾�B����ȍ��ʎ�`�҂ł���l�����A���̋@��ɂ����Ă������������B�m�[�}�͐g���̍�������Ȃ���A�킯�ւ��ĂȂ��������Ă���q�ǂ������̎p���݂��邱�ƂŁA���R�Ɋ����ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă����B
�@�q�b�s�ƃy�b�N�͊���݂��킹��B���N�����́A�s�����Ɏ���ӂ���肾�����B
�@�l�l�͂���Șb�ɖ����ɂȂ��Ă�������A���̏��̎q�̂܂Ԃ����z�����A�����݂Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ������B�ޏ��͖����Ă��邠�������A���Ƃ̐��E�ɂ��ǂ���@���l���Â��Ă����B
�@���̔����݂���A�o�߂����Ă����̂��B
���@�@�@�@�\�l
�@�㌴���͍l���Ă����B���̖��ł͌F��T�ɏP���A�Ȃߑ��Y��M�����Ɏp��ς�����邢���̂ɒǂ��Â����B�؈�̉Ƃł͎���i�߂��A�����̉Ƃł͎E�l�S�ɔ������܂ꂽ�B����Ȗ��̂Ȃ��ōl���Ă����B�S�̂ǂ����ł́A�i�o�z���ɂƂ��ꂽ��J���A�����o����������Ƃ߂Ă����̂��B
�@���͂��܂��肳�܂̂��Ƃ��l�����B���̂Ƃ��͑z���������������B���̂Ȃ��̍l���Ȃ̂ɂق�ƂɂȂ����B
�@�Ö��p�ɂ�����ƁA�̖_�������Ă���ƈÎ���������ꂽ�Ƃ���ɁA�{�[���y���������Ă��Ă����ۂɂ₯�ǂ��炵���B�����Ă���̂̓{�[���y���̂܂܂Ȃ̂ɁA�Ԃ�����N�������肷��B�v�l������������B�����āA����͓`�d����̂ł͂Ȃ��̂��H
�@�щp�̂������ł���M�������A���鎞�_�ł݂�Ȃ̂��̂ɂȂ����B�����ł́A���̑z�����݂�Ȃɓ`�d�����B�ޏ����A�Ȃߑ��Y�̘b���ŏ��ɂ����̂��B�Ȃߑ��Y�݂͂�Ȃ̑z���������������āA���͂ɂȂ��Ă������B����ɂ����Ȃ����̂��B�ӎ����Ă�����킯����Ȃ��B�m��Ȃ������ɁA�݂�Ȃł�邢���̂���ĂĂ��܂����B
�@�ޏ������́A���o�⌶�����A������x�̓R���g���[�����邱�Ƃ��ł����B���������ނ��Ƃ��ł����B�ł��A���̋t�͂ǂ��Ȃ낤�H�@�ӎ��I�ɁA��邢���̂������������Ƃ͉\�Ȃ낤���H
�@�����āA�v�l�͓`�d����A�Ȃ��肠���c�c����q������q�b�s�ƂȂ����Ă����悤�ɁA�S�͂Ȃ��肠���\�\
�@����͂����肵�Ă����B���̒��̂Ђ�߂��ɉ߂��Ȃ��������̂��A�`���Ƃ��Ă�����Ă���B���������ƔM���Ȃ�B
�@�����̒��ŁA�ޏ��͂��̍l���𗝉������B�ǂ�����ē����������������킩�����B���͔�ꂫ�����]�݂��ŁA����Ȑ^�����ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��B�]���̔�J�����̋��e�ʂ́A���͂���E�ɂ������B���܂͎��ɂ������Ă��邾�������A����Ȗ����Ȑ^����������A�ق�Ƃ��Ɏ��ʂ�������Ȃ��B
���@�@�@�@�\��
�@���͂܂Ԃ����J�����B�ڂ��������A�^���Â������B�œ_�����������B���E�����ǂ����B�ڂ₯���܂܂ł͂��������B���o���Ƃ߂�قǂɁA�]�͂܂����Ă����B
�@����ł܂��͂����肵���B�������Ėڂɂ�����̂��A�]�����݂����Ă���̂��B�����銴�o���A�]�͐��݂����Ă���B
�@���͓f�������Ȃ������A�ݑ܂̒��ɂ͂Ȃɂ��̂����Ă��Ȃ��B����ɁA�f�����炢�������C�͂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����Ȏ��Ԃ͂������������B
�u�������c�c�v
�@�ƁA���ɍ������낷�A���N�����ɐ���������B�g���Ȃ�ʌ��t�����ɂ��邱�Ǝ��̂���ɂ��B�ċz�@�\���ቺ���A����f���̂��ꂵ���B
�u�������A�����Ƃ���ɂł���H�@�킽������ē����Ă����H�v�ƌ����B�u�{���̐_�������Ă�����Ȃ�c�c���Ƃ̐��E�ɖ߂���H�v
�u����͕ۏ�ł��Ȃ��v�m�[�}���������B
�@�r�X�R����������߂��B�u�Ƃɂ����A�l��������Ȃ炻���b���v
�@�q�b�s�������������B�����ڐ��ł�����Ƃ߂��B�ޏ��͂����₭�悤�Ȑ��Řb���Ă���B�����̂ނ����ɂ���y�b�N�ɂ͕������ɂ����悤���B����ł��A�q�b�s�͗��̍l����ǂ݂Ƃ��Ă����B�����Ȃɂ�������肩�A�������Ă����B
�u���߂��c�c�v�Ɣނ͂����₢���B�u����Ȃ��Ƃ��ׂ�����Ȃ��B�N�͂������E���B�����Ƃ��ł��Ȃ����B����ɁA�ڂ��炾���Ă����ł͂��܂Ȃ��v
�@�q�b�s�̓m�[�}�����ɘb�����B
�u�������ł��傤�B���̎q����������Ȃ��߂ɂ����Ă������āB�ڂ���̌������o�́A���̎q�����̍l���ł́A�S�̒��̕s����ꂪ�������������̂Ȃ�ł��B���̒��Ԃ͂������邢���̂ƌĂ�ł�B���������A�ӎ��̌ł܂�ł���B�������݂�Ȃɉe�����������Ă��ł��B������A�ƍ߂��������Ă�v
�u�����A���̎q�ׂ͂̐��E���痈���낤�H�v�ƃm�[�}���u�����B�u�Ȃ��܂������ׂ̐��E�ŁA���Ȃ����ۂ��N���Ă�v
�u���Ȃ�����Ȃ��c�c�킽���͂������ɗ��Ă���A���o���݂ĂȂ��̂�v
�u���ꂪ�{�����Ƃ��āc�c�v�y�b�N���������B�u�Ȃɂ��������Ȃ�ł��H�v
�@���͓����Ȃ������B�q�b�s�����Ă������B�u�킽���͂��܂������Ǝv���v
�u�ނ肾�B�N�̂����Ƃ���ɂ�����A�ڂ��炾���Č��o���݂邱�ƂɂȂ�B�N�̍l������������Ȃ�A����͂����̌��o�ł���Ȃ��B�ڂ���̎v���Ă��錻���́A�B���͌Ђ��ĂƂ����v
�u�ł��A������ɂ͂��ꂵ���Ȃ���v���͎�����������A�i�o�z���Ɋ���ނ���B�ނ�͂����A�����N���Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă���B�u�킽�������͖��ӎ��̂����ɂ�邢���̂��Ăт悹�Ă��B�ł��A��邢���̂��݂�Ȃ̑S�̈ӎ����Ƃ�����A�ӎ��I�ɌĂяo�����Ƃ����Ăł��邩������Ȃ��v
�@�ޏ��͐g���������A�g�D���[�V���h�E���������E�ɂ����߂�B
�u�����炾���āA���|�����Ă�B�킽���ɂ͂킩��B����𗘗p���邵���Ȃ���B������͂Ђǂ��ڂɂ����������v
�@�ޏ��͌������B�݂�Ȃ͂Ȃ�ƂȂ����̈Ӗ����݂̂��݁A�������B
�u�ł��A���Ƃ̐��E�ɂ��ǂ�Ȃ���A���������ĈӖ��ȂȂ��B�ق�Ƃɕ��@��m��Ȃ��́H�v
�u��X�ɂ͂킩��A�n�u���P�b�g���܂Ȃ�킩��͂����B���̐_�������v�ƃr�X�R��������B
�@���̓m�[�}�ɁA�u��������鎩�M�͂���H�v
�@�m�[�}�͎���ӂ�B�u�T�C�|�b�c�̍��܂ł͉������A�ו����Ƃ�ꂽ�B�X�͂ʂ����Ȃ���������Ȃ��B������A�}�[�T�̂��Ƃ�K�˂�Ȃ�Ƃ��Ȃ邩������Ȃ��v
�u�}�[�T���āH�v
�u�C�j�V�G�̐X�ɏZ�ޖ������v�����Ƃ����āA���͊�������߂��B�m�[�}���Ƃ�Ȃ��悤�ɂ������B�u�ڂ������Ƃ͉�X�ɂ��킩��Ȃ����A���������Ă�B������X�����̂Ă͂��܂��v
�u�}�[�T���Đl�Ȃ�A�q�b�s���m���Ă�v
�@�����������B�݂�Ȃ͂�����Ɣނ������B��������q�b�s�̕\��A���̓����������B
�@���͌������B���������͂�邢���̂ɏP���Ă���̂͂�������イ���B�i�o�z���Ƃ������̂͂����������B�ςȌ����������ǁA�����ɂ���q�ǂ������́A��邢���̂Ɋ���Ă����̂��B
�@�m�[�}���������B
�u�킩�����A�N�̂����Ƃ���ɂ��悤�B�N�̂��Ƃ́A�킽�����S���łł��A��Ă����v
�@�������Ȃ����ƁA�q�b�s���m�[�}�̘r�����������B
�u����Ȃ��ƁA������ׂ��ł͂Ȃ��ł���v
�u�Ȃ����H�@�ق��ɕ��@�͂Ȃ����v
�u���̎q�͂��Ƃ��Ƃ���ȗ͂������Ă����킯�ł͂Ȃ���ł��B�}�ɂł���悤�ɂȂ�����ł���v
�u�ǂ��������Ƃ��H�v
�u���S�Ȃ�ł��B���̎q�͔�ꂫ���āA�]�������������ɂȂ��Ă�B�ǂ�ȓ�������x�������Ă����A����ł��傤�H�@���̎q�͂����������ȂB����ȏ�A�ӎ��̏W����������A�ق�ƂɎ���ł��܂��v
�@���͂��܂��āA�������O���Ȃ߂��B���ǂ����������Ő�Ă���̂������ł��킩�����B�E���̂܂Ԃ�����������āA�ǂ����Ă��オ��Ȃ��B�q�b�s�����̌������B�ޏ��͂��߂����B
�u����Ȃ܂˂�������A�ڂ��炾���Ă����ł͂��܂Ȃ��Ƃ����Ă邾�낤�B�N�����Ă���Ȃ����B��邢���̂̋��낵���Ȃ�A���̐X�ł�����Ă����قǖ�������͂����v
�u������A���ɗ��݂����̂�v���͌������B�����̐؎����ɁA�q�b�s�͑����̂ށB�u��]������A�������͎������E�����Ƃ��邩������Ȃ��B�����Ȃ����Ƃ��A�~�߂Ăق����̂�v
�u�N�Ƃڂ��͐��_���Ȃ����Ă�B�N�Ɉ��������āA�ڂ������Ď��ɂ����Ȃ邩������Ȃ��v
�@�r�X�R�������͂��B�u����A�\���͂��邼�B�܂肻�̂�邢���̂��Ă����̂́A���̐��E�ƌN�̐��E�łׂ͂Ȃ낤�H�@�N�͂��̐��E�ɂ��Ă��猶�o���݂Ȃ��B�ނ����̐��E�̑S�̈ӎ�����́A�藣���ꂽ�B�N�ׂ͂̐��E�̐l�Ԃ�����A���̐��E�̉e�����ɂ����̂�������Ȃ��v
�@�m�[�}�̓r�X�R�̍����I�ȍl���ɐ���܂����B�ގ��g�́A����q�b�s�̂����Ă��邱�Ƃ��������킩��Ȃ������B���̂Ƃ���r�X�R�͊����̂����j�ŁA�����炱���f�߂���钇�Ԃ������A�̂肫���Ă���ꂽ�̂��B
�u���_�������̂͊ȒP����Ȃ����B��X�͌��o���Ȃ������Ƃ͂ł��Ȃ������v
�@�m�[�}���������B
�u�킩���Ă�B�킽������������Ȃ��������B�����Ȃ������邵���Ȃ��A��邵���Ȃ���v
�@���̓m�[�}�ƃr�X�R�Ɏ���ӂꂽ�B
�u�݂�Ȃ̂��Ƃ͂킽�������B����ɂ�����͂����C�Â��Ă�v
�@�ꓯ�͎��͂�������݂��B
�@�g�D���[�V���h�E�����́A���܂��ɂ�������͂�ł����B�i�o�z�̌��t�ł����сA������Ƃ肾���Ă���B���łɊ��l���͐X�ɗn�����悤�ŁA�p���������A�ǂ�����_���Ă���̂����킩��Ȃ������B
�@�m�[�}�����͗����܂���悤�Ɋ�肻�������B���͔�J���ӂ蕥���悤�ɓ����ӂ�Ɩڂ��Ƃ����B
�u�݂�ȗ͂������āv
�@������������ƁA�m�[�}���������̎���Ƃ����B���͍Ăъ̈ꕔ�ƂȂ����B���̗͂��A�ׂ̐��E�ŁA������ׂ̃����o�[�Ƃŏo�Ă���̂����������Ă������A����ȐS�z�͖��p�������悤���B(�݂Ƃ߂����͂Ȃ�������)�ޏ��̓q�b�s�ƂȂ��邱�ƂŁA�m�[�}�����Ƃ܂łȂ�������������炾�B����������̏�Ԃł�邢���̂ƑΛ������Ƃ��A������ۂĂ邩�ǂ����������B��邢���̂������ς肾���̂́A����ł͂��������A�s�\�ł͂Ȃ��B���̓q�b�s������ʂ��āA�S�̈ӎ��ɂӂ�邱�Ƃ��ł������炾�B�����͂��܂��肳�܂ł͂Ȃ�����ǁA����Ӗ��ł͂��܂��肳�܈ȏ�ɍň��������B�����A���̐X�͈����S�ł����ς����B�߂��݂ł����ς����\�\
�@����q��B�Y�𗊂肽���Ȃ�S��}���ĔO�����B�ӎ����W�����A��邢���̂��Ăт������Ƃ���B�]�̌������܂��A�̉����댯�Ȉʒu�܂ō��܂�B�����z�����ނƁA���̂Ȃ���ᎂ��͋��������B���͂��̐��E�̐����Ƃ�������҂�A����ł������҂����̗��߂��A���|�I�Ȉ��ӂ������ĕ|�C���ӂ�����B�����o�������Ȃ�S�ɔ����āA�q�b�s�ƃm�[�}�̎�����肱�ށB
�@�ӎ��̉��[���ւƍ~��Ă������B�����̐S�����ݏo�����C���[�W�̒����B����̂����ɂ́A���X�Ƃ����t�̂̂܂����L��ȊC���������B���͈ӎ��̂Ȃ��Ŏ��L�����̊C�ʂɎ��G���B���̂Ƃ���A�Ԍ���̂悤�ɐ������������藘�����݂��B�����A�A�i�݂��A�S�̉��ꂩ������̂悤�ɐ��������Ă���B
�@���̓R���g���[���͂������ڂ��J�����B
�@�~�̒��S�Ɍ����������N�����Ă���B�^������ᏋC���͂�݁A�Q�������Ă���B�������́A���̍����Q�Ɉ��݂��܂ꂽ�B
�@���͑����z���Ȃ������̒��ŁA�K���Ŗڂ��J�����Ƃ����A�ڂ̑O�ɋ��ł݂��������ۂ�����ƌ��������Ă������炾�B�����Ƃ��������悤�̂Ȃ��^�����Ȍ��������B�����Ȃ��������A����ǂ͋��̂ɂȂ��Ă���B
�@�A���A����ŋA���\�\�I
�@���͂��̒��S�ɔ�т������Ƃ����A�q�b�s�ƃm�[�}�����̎���Ђ��Ĕޏ��̍�������悹��B
�u�����āI�v
�u��߂�A�������ŌĂ�ł����͂��Ȃ����I�v
�@�q�s�������ƁA���͂������ܗ��������B�ޏ��͂��̎l�l�ɌĂ�Ă����B���̂Ƃ��ӂ��̐��E�͂Ȃ����Ă����B������Ȃ����Ă���Ƃ͌���Ȃ��B���̉Q���ǂ��ɒʂ��Ă���̂��͂킩��Ȃ��̂��B�q�b�s�̂������Ƃ͂킩��B�ł��\�\
�u�ł��A�ʂ��Ă邩������Ȃ��v
�@����ł����͂�����߂���Ȃ������B��l�̎�������̂��A�Q�ɂނ����Ď��L�����Ƃ���B�߂�Ȃ��ƁA�݂�Ȃ�����ĂȂ��Ⴞ�߂Ȃ���ƁA�܂����ڂ��A���̗܂������A�Q�ւƋz���Ƃ��Ă����A���ꂪ�ǂ��֍s�����̂���킩��Ȃ��̂����A����ł��ޏ��͘r��L�����B�q�b�s�Ƃ��݂������ƂŁA�~�w�͎��R�ɕ���Ă��܂����B���͏W���͂��Ƃ����̂������B�Q�͋���ɂȂ������z�����݂����B
�@���̖ژ_���͗\�z�ȏ�̌��ʂ������Ă����B�i�o�z���͕�����ق��肾���A�ꂵ�݂̐��������n�߂��B��邢���̂̉e���������A���o�����͂��߂��̂��B
�@�S�ɂЂ��ވ������̂��A���������܂��Ă������B�o���E�Y�͐�����͂���A���������Ƃ߂钇�Ԃ������B���[�N�o�C�X�͐��b�ɂȂ����e���ɂǂ₳��Ă���B����̂��߂ɍ�������̏��ɂ������҂͈����ɂ̂������Ă����B�i�o�z���̒j�����͂��ꂼ��̋��|���݂��B
�@�g�D���[�V���h�E�͂��낽���钇�Ԃ��W�߂悤�ƕK���������B�������Ȃɂ�������̂��m��Ȃ����A�݂Ȕ��������Ƃ����������Ȃ��ꂵ�݂悤���B�����āA�ނ͂������^�����B��͂�X�ٕ̈ς̓T�C�|�b�c�̂��킴�Ȃ̂��Ɓ\�\
�@���邮��ƍA���Ȃ炷���������B
�u�ǂ��������Ƃ��c�c�v
�@�ނ̔w��ɂ́A��\�N�O�ɎE������Ղ������B�q�ǂ��̂���A�f�B�����f�B�����ƌĂꂽ���̃f�J�u�c�ƁA�E�C�����߂����߂Ɉ�Έ�őΌ������̂��B�f�B�����f�B�����͎��܂܂�݂��������悤�ŁA�͕̂���A�ǂ�������������Ȃ����Ă���B
�@�g�D���[�V���h�E�͖����Őg���܂���Ɛ�����������̂������B
�@��邢���̂̉e���́A���N�����ɂ������ł����B�܂Ƃ��Ȃ̂̓q�b�s�Ɨ������������B��l�͐S���Ȃ����Ă�������A�������̐��_���x�������Ă����Ƃ��������B�N���̃m�[�}����������悤�ɉQ���݂߂Ă���B���|�̂������Z������f�������Ă���B
�u�m�[�}�I�v
�@�ƃq�b�s�͗��̍���������ނ悤�ɂ��āA�m�[�}�̘r���ɂ���B�m�[�}�͍ŏ��C�Â��Ȃ������B����ǁA�q�b�s�����ɂ��ꂽ�Ƃ��̗v�̂�(�����܂œ`����Ă���Ƃ����ׂ̂͂��Ȃ��̂�)�A�������肵��ƈӎ����ǂ₵��������A�m�[�}�͂悤�₭�ނ̕��������B�œ_�̍����Ă��Ȃ��悤��䩔��Ƃ����ڂ��B
�u�m�[�}�A�������肵�āA���̗l�q�����������v
�@�m�[�}�͂̂�̂�Ǝ���܂킷�B�q�b�s��������x�A�ӎ��������肱�ނƂ悤�₭�����Ƃ����悤���B
�u�Ȃ����C�ȂH�v
�@�m�[�}�͂Ђ����Ɏ�����Ă������U���Ă���B�ł��A���̐��͂����̂悤�ɖ��Ă������̂ŁA�q�b�s�͂ق��ƂȂ����B
�u�͂₭�����𗣂�悤�B�O�Y�O�Y���Ă���A�������Ȃ��I�v
�u���A�����v
�@�q�b�s�͎����̂��ł��������Ƃ����낵���Ȃ����B�C�j�V�G�̐X�S�̂������ɂ��Ȃ���Ă��邩�̂悤���B�ނ͗��̖ڂ��̂������ށA�����ɔ߂�����]���݂��B���̎q�͂Ȃ�ǂ�����ȑ̌������Ă���B���̒��ɕs�M��������Ƃ��Ă����������Ȃ��B
�@���̂Ƃ��A����������r�X�R���E�т��A�����Ă����Z���̕��ŗ��̌㓪������������B�m�[�}���{��̐��������A�r�X�R�����Ƃ����B�q�b�s��(�㓪���̂͂������ɂ݂�焈Ղ��Ȃ���)����������������A�ޏ��͋C�₵�Ă���B�܂������A�ƃq�b�s�͎v�����B�ڂ�����邢���̂̉e�����܂Ƃ��ɋ���Ă��܂��I
�@�m�[�}���r�X�R���ɂ�݂�����B�u�C���������̂��I�v
�@�����A�r�X�R�͂���ʂق��������Ă����B�q�b�s�ɂ��ނ����Ă��镨���������B�Ⴂ�j�ƘV�l�B����͌ܔN�O�Ɏ��Z�̎p�ł���A���̘e�ɂ���̂͐������Ă���͂��̕��e�������B
�@�r�X�R�͂��߂������炵�A�Z���𗎂Ƃ��B���܂�Ă��炸���ƌZ�Ƃ���ׂ��Ă����B�����̑��݂��݂Ƃ߂�ꂽ���Ƃ́A��x���Ȃ������B���͂��܂������˂悩�����A�ƌ������B�r�X�R�͐��߂��̏�ɂւ��ւ��Ƃ�������������B�m�[�}�����B
�u�r�X�R�A�������肵��I�v
�@�q�b�s�ɂ͂��̐����Ђǂ������ɂ��������B�m�[�}�̌������ɁA������Ď����e�����Ă����̂��B���́A���܂��̕�e���E�����̂͂��̂��ꂾ��A�Ɣނ�����Ă������Ƃ����ɂ���B���͎�r����ɂ��āA������������Ă���B�E�l���������B������̕��e�B�����āA�E��ɂ͌��h��ꂽ��������Ă���B
�u�������A�ق�ƂɎE�����̂����H�v
�@�q�b�s�͘Z�̂Ƃ��Ɏ����ɂ�����낤�Ƃ����B�m�[�}�͗���r�ɂ������܂܁A��J���Ĕނ������Ƃ߂��B
�u�݂�ȁA�o���o���ɂȂ�ȁI�v�ƃm�[�}�������B�u���ꂽ�������Ă���̂͌��o���I�@�S���������肽���āI�@���̏�𗣂��I�v
�@�q�b�s�ƃr�X�R�͋^�킵�����Ƀm�[�}������B�C�����ƁA�y�b�N���F��̌��t���������Ă���B�F��̑���́A��X�����Y��ł݂��ƍߐl�������B�m�[�}���l���������Ēj�̓����R�|���ƁA�˂���āA�����T���U�炵�Ȃ���n�ʂɂ��낪�����B�y�b�N�͔ߖƂƂ��ɁA���f��f�����B
�u�����A�ق�ƂɌ��o�Ȃ̂��I�v�ƃm�[�}�͌������B
�@���̐��̂����鈫�ӂ��A���̏�ɂ���ꓯ���Ƃ�܂��Ă����B�r�X�R���{�����B
�u�����ς�����B�͂₭�������痣��悤�I�v
�@�ނ�͈��ɂȂ��āA�D�Q��Ɖ������L�����v���������Ƃ����B���̍s������ӂ������̂̓f�B�����f�B�����������B���O�͂��Ȃ�Ȃ����������ɁA����͂��̎E������˂��ӂ��āA�q�ǂ��̏_������炨���Ƃ������Â���炵���B�y�b�N�͂��܂炸�݉t���o�����B���̕��鈫�L�ƁA�ӂ�܂����E�ӂɂ��Ă��Ă̂��Ƃ������B�m�[�}�ƃr�X�R�͗E���ɂ��f��ŏ��N�����̑O�ɏo���B�f�B�����f�B�����͗Y���т�������B���̐��ɂ͈����ɋꂵ�ރi�o�z�����Ɗ���グ���قǂ������B�q�b�s�ƃy�b�N�͎����o�債�āA���̑̂ɕ������A�m�[�}�ƃr�X�R�͘r���グ�Ċ�ʂ������B
�@�f�B�����f�B�����͂��܂ɂ��P���������ƒn�������Ă���B���̑̂ɃN���X�{�E�̖�˂������A��Ղ͋��̋��т��グ��B
�@���[�N�o�C�X���������B
�u������A�q�b�s�I�v
�@�f�B�����f�B�������O�����ӂ邤�B�m�[�}�̘r��쑾���܂����������B���[�N�o�C�X�̖���ڂɂ������܂��ƁA�f�B�����f�B�����͎��͂��Ȃ�����(�Жڂ͐��O����Ԃ�Ă���)�A���N�����ɘe�����݂����B���̐��ʂɃg�D���[�V���h�E�������Ă����B
�u�f�B�����f�B������A�\�s�������܂ł��v
�@�g�D���[�V���h�E���g�������܂��A����Ȍ������肩��Ђ˂肠����B�f�B�����f�B�����͘e�������h���ɂ���A���̕������̂͂قƂ�ǐ^����ɂȂ�B
�@�g�D���[�V���h�E�̓f�B�����f�B�������R�|���ƁA���C��тт��ڂŏ��N���������܂킵���B���̐�����킸���ɂ����A�Ԃ��߂Ă���B
�u���̏����̖ڂ����܂�����I�@������Ђ����߂�����I�v
�@�r�X�R�͎�������āA���̍s�i���Ƃ߂悤�Ƃ����B�u�܂āI�@�P�\������g�D���[�V���h�E�I�@���ꂽ���͍��ɂ������āA���Ȃ炸��푈���Ƃ߂Ă݂���I�v
�@�r�X�R�̂��������́A�g�D���[�V���h�E�̓{����������Ă��B
�u�����܂�ȂǂɂȂɂ��ł���I�@�a���Ȃǂ��ꂽ���͂����̂��܂�I�v
�@���[�N�o�C�X���g�D���[�V���h�E�̑O�ɗ����ӂ��������B�N���X�{�E���グ�āA�g�D���[�V���h�E�̋��ɑ_���������B
�u�Ȃ�̂܂˂��A���[�N�o�C�X�v
�u�����܂��q�ǂ����E���Ƃ���Ȃnj��������Ȃ��I�@�����������Ƃ����Ă�I�v
�@�g�D���[�V���h�E������U��グ��ƁA���[�N�o�C�X�͖���˕������B�g�D���[�V���h�E�̓��[�N�o�C�X�����������A���F�̖����̑̂��߂����������Ƃ�m�茕���Ƃ߂��B�ӂ�ނ��ƁA�h�G�̖���_�����Ƃ����f�B�����f�B�������A���Ԃɋ��|�������n�ʂɓ|��Ă����B
�@�r�X�R�ƃm�[�}���ڂ����킹��B�����o���Ƃ�����A���܂����Ȃ������B�m�[�}������w�ɂ������B�g���Ђ邪�����ƁA�����̎v���ő������B
�u���[�N�o�C�X�I�v
�@�q�b�s�͊댯�����m�ł�����݂��B���[�N�o�C�X�ƃg�D���[�V���h�E�́A�����̂悤�ɂ�������ł���B���N������ǂ����Ƃ����Ȃ��B
�@�q�b�s�͔ނ�ɂ������������B�푈���Ƃ߂悤�Ƃ����̂͂����ł͂Ȃ��ƁB���̂��߂ɁA�n�b�c�����Ăт������Ƃ����̂����A���̊댯�������Ă��A�C�j�V�G�̐X�܂ł���Ă����̂��B
�@�����ǁA�ނɂ͎��M���Ȃ������B�푈���Ƃ߂��Ƃ���ŁA�����݂͏����Ȃ����A���l���A�����Ƃ��ł��Ȃ��B�ނɂł��邱�Ƃ͉����Ȃ������B������A�Ȃɂ������Ȃ������̂ł���B
���@�掵�́@���N
���@�r�ō��
���@�@�@�@�\�Z
�u�������ǂ��A���[�N�o�C�X�I�v
�u�����܂������C�ɂ��ǂ�I�v
�u����͐��C���I�v
�u�q�ǂ��܂ŕ߂炦�āA�Ȃɂ����C���I�@�ُ�Ȃ̂́A�����������A���̎q�����Ƙb���Ă킩�����낤�I�v
�u����͂��������A���[�N�o�C�X�v
�@�g�D���[�V���h�E�ƃ��[�N�o�C�X�́A��������܂��Ăɂ�ݍ����B
�u�ٕς��������Ă���̂́A�����̐g�ɂ����v
�@���[�N�o�C�X�̊�F���ς�����B�ނ͉��������������������Ƃ������A�e�����킫�N����A���̂Â��͕����Ȃ������B
�@�g�D���[�V���h�E�͒��Ԃ������Ȃ����|���̂��݂Ă��A�܂����̂Ȃ��ɂ���悤�ȐS�n�������B�����Ƃŏe�e�����Ȃ�A�ނ̖є�𐁂����炷�B
�u���o����Ȃ����I�v
�@���قǂɐڋ߂����܂ŃT�C�|�b�c�̑��݂ɋC�Â��Ȃ��������ƂȂǂ���܂łȂ������B���̎ᒷ�̂Ђ�����W�c�́A�˂ɐ��������āA�s�ӂ�������邱�ƂȂǂȂ��������炾�B
�@�g�D���[�V���h�E�͏e�e�����킷���߂ɁA�g�������߂Ȃ���A�G�̋�����T�낤�Ƃ����B����ɂ��A���N�����̂��߂ɗp�ӂ����������A����I�ȎE�C���Ăт������Ă����B���ɏƂ炵������A�i�D�̕W�I�ƂȂ��Ă���̂��B
�u���[�N�o�C�X�I�@�����������I�v
�@�������܃��[�N�o�C�X���n�ʂ̍������肠�������ɂ������B
�@���̋C��ƂƂ��ɁA���̊�ȋ��̂͌`������Ă����B�����ɁA�ǂ��������ƂȂ��Ĕނ�̏h�c�n���Ƃ�܂��Ă���B�g�D���[�V���h�E�͒n�ʂɂӂ���ƁA���̐^���ɓ���A�Èł��������B���̕��p�ŁA�ΉԂ��������オ��A���������̎p�������яオ��B
�u�T�C�|�b�c���I�@�_���Ă��邼�I�@��������I�v�g�D���[�V���h�E�͂ǂȂ萺��������B�u�o���E�Y�A���g�����b�N�A���Ԃ����߂�I�v
�@���Ԃ͂܂���邢�̂��̂ɂ��܂����܂܂������B�e���ɋC�Â��Ă��Ȃ��҂܂ł����B�ނƃ��[�N�o�C�X�����́A���������̂��߂ɗ�Â������̂��B
�@�g�D���[�V���h�E�����́A�������ɂ������Ԃ��Ђ�����|���A���o�ɂƂ��ꂽ�҂͉�����Ăł����C�Â������B
�u�U���I�@���̏e�����邼�A�_������������ȁI�v
�@�g�D���[�V���h�E�����͎U�J���g�����������Ƃ������A���̂Ƃ��ɂ͖��͂ǂ�ǂ�Z���Ȃ�A��ڂ̂����g�D���[�V���h�E�ɂ����Ƃ����Ȃ��Ȃ����B���E�������鐡�O�A�T�C�|�b�c�������e�����Â��Ȃ���ˊт�������̂��������B���[�N�o�C�X���A���|�ɂ��̂̂������łԂ₭�B
�u�����A�����Ȃ����c�c�v
�@�g�D���[�V���h�E�����͈łɂȂ�Ă��Ȃ������B�ǂ�ȈÈłł���ڂ��������߂ɁA���E��D����Ƃ������Ƃ��Ȃ��̂ł���B�Ȃɂ������Ȃ��Ƃ����ɁA�i�o�z���͌��o���݂�ȏ�̋��Q�ɂ����������B���̂Ȃ��ŁA���Ԃ̔ߖ����������Əオ��B�g�D���[�V���h�E�͒��Ԃ����������ƁA�����Ђ���ė����オ�������A����ł͒��ԂɎa������˂Ȃ��B�������������������A�T�C�|�b�c�͂�����肪����ɍU�����������Ă��邾�낤�B�g�D���[�V���h�E�̂܂Ԃ��ɁA�ߋ��ɂ݂��s�E�̌��ꂪ�����ƕ����т�����B�F�E���ɂ����A���݂�������ꂽ���E�̎p���B���̍Ж�A���������̐g�ɂ��~�肩�����Ă����̂��B�Èł̂Ȃ��ŁA�g�D���V���h�E�͋��|�̋�C���z�����B�i�o�z���A�Ȃ��Ȃ�̂��c�c
�u���m������������I�@����Ⴍ����I�@���ɓ�����I�v
�@�g�D�[�V���h�E�̗��������h�������A���Ԃ�E�C�Â��͂��Ȃ������B�j�����悪�����߂�B�g�D���[�V���h�E�͂��߂����A�a���������������艞�����Ȃ��B���ɂ͒��Ԃ̔ߖ����������Ȃ������B
�@�T�C�|�b�c�ɂ́A�����Ă���̂��H
�@�����v���̂����̊Ԃ������B�S�g�ɂ������̑����������A�Ђ��܂������B�Ȃ����������A�����オ�낤�Ƃ������A�㓪���Ɉꌂ�����炢�A�ނ͂��̏�ɍ��|�����̂������B
�@�N�������ɗ����Ă���B�g�D���[�V���h�E�͂����ގ��E�̂Ȃ��ŁA���̐��̂�������߂悤�Ƃ��邪�A�����Č����͂��Ȃ��B�ނ��T�C�|�b�c����Ƃ����ӎv�͂������ЂƂ������B
�@��������c�c
�@�₪�āA�ӎ����Ƃ���ǂ����B�g�D���[�V���h�E�́A�����オ�낤�Ƃ������A�葫�����܂������Ȃ������B�ނ͎�������A���̗͂l�q���������߂��B���͂Ȃ��A�T�C�|�b�c�̎p���Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@�P���̂������m���邱�Ƃ�m�点��̂́A�������ЂƂA���Ԃ̎��݂̂̂������B
�@�g�D���[�V���h�E�́A�N�O�Ƃ���ӎ��̂Ȃ��ŁA�K���Ɏ���̂��A�T�C�|�b�c�̌��ǂ����Ƃ����B��n�Ɏw�����āA���܂��ɐV�������t��n�ʂɂ����Ȃ�����A�����ɔ����������B
�@�₪�āA�ӂ����шł��Z���Ȃ�A�ނ͈ӎ��������Ȃ����̂������B
���@�@�@�@�\��
�@�ނ�͖�̐X���J���e�����������ɑ���ɑ������B�i�o�z���͈ꎞ�Ԃ�40�L���𑖂�Ƃ������A���ǂ낭�ׂ��k�o�ƒT���̏p�ŁA�ȒP�ɋ��ꏊ����肾���Ă��܂��B�ؗ���}�ɂԂ���A�⍪�ɑ����Ƃ�ꉽ�x����������������Ȃ���i�B
�@����ł��������������K�v�����������A���N�����͂��������̋��s�R�ő̗͂����Ղ������Ă����B�y��A�q�ǂ������ŃC�j�V�G�̐X�����f���邱�Ǝ��̂��A�����Șb�������̂��B�Ƃ��Ƀq�b�s�̔��͂��̂����������B�]����J���A�������炭�炵���B���̂��Ƃ��A����ɑ̗͂������Ă����B�y�b�N�͐S�z�������B�q�b�s�͊�łȂ����ɁA�l�Ɏ�݂��������肵�Ȃ�����B�ނ�����Ă���Ɍ��܂��Ă���B�i�o�z������\���ȋ������Ƃꂽ���Ƃ����āA�m�[�}���x�e���Ƃ点��ƁA�y�b�N�͐S��ق��Ƃ����B
�@�m�[�}�͎����������������āA���ɂ������Ȃ������������߂��B
�u�H�����Ƃ�ꂽ�܂܂��ȁv
�@�ƃm�[�}�͂Ԃ₢���B���̓��͂킸���Ȓ��H�ȊO�͂Ȃɂ����ɂ��Ă��Ȃ��B�͐[���������B���̉ו��͂��ׂĒu���Ă��Ă��܂����B�y�b�N�̉B�������Ă����R���p�X�͖��ɂ����A�������X�̂ǂ̕ӂ�Ȃ̂��͊��ɂ���邵���Ȃ������B�q�b�s�͎�Ԃ�B
�@�r�X�R�͌C�����ɉB�����Z�����Ƃ肾�����B�ނ͂���������ƌ��߂��B���ꂩ��A�n�ʂɉ�������Ă��鏗�̎q�ɂ����Â��ƁA�����Ȃ肻�̋��ɓ˂��h�����Ƃ����B
�u��߂�I�v
�@�m�[�}�����ǂ낢�ăr�X�R���͂������߂ɂ����B
�u�͂Ȃ��I�@���̖����������Ƃ����Ȃ������̂��A�����͂ӂ�����Ȃ��I�@�����̎q�ǂ��ɂ���Ȃ܂˂��ł��邩�I�v
�@�r�X�R�͒��g�̃m�[�}�ɑg�݂�����Ȃ�����A�S�g�̗͂Œ�R���Ă���B�q�b�s�͖����Ńr�X�R�ɕ��݂��ƁA���̎肩��Z����D���Ƃ����B
�u����������ɂ���A�ڂ����������������̂͂��̎q�̂��������낤�I�@���͊댯���������Ă܂łڂ�������Ă��ꂽ�I�v
�u���������ȁA�����������邽�߂���Ȃ����I�v
�u���̎q�����āA�ڂ���Ƃ��Ȃ��悤�ɋꂵ��ł����B�킩��Ȃ��̂��I�v
�@�q�b�s�͐g���ӂ�����Ȃ�����A�C���Ńr�X�R�����܂点��B�y�b�N�̓��[�_�[�i����������̃q�b�s���v�X�ɂ݂��悤�Ő��ꂪ�܂����C���ɂȂ����B�O���[�v�ɂ�������A�q�b�s�͂���Ȃ�������̂��B
�@�m�[�}������߂����Ί���݂���B
�u�������邢���̂̉e���Ƃ�������B�q�b�s�A�i�C�t���悱���v�ƃi�C�t���Ƃ�B�u�}�[�T�̉Ƃɂ��ǂ���邩�ǂ������������B���܂͒��ԓ��ő����Ă���ꍇ����Ȃ��v
�u���ԂƂ������A���̃q�b�s�Ƃ�������́A�i�o�z���ƂȂ����Ă����ł͂Ȃ����B�����̂����ɁA�}�[�T�̂��Ƃ��m���Ă�B���ꂽ�����낭�ɒm��Ȃ��Ƃ����̂ɂ����v
�u�q�b�s�̓^�b�g�����m�Ɖ��{�ɏo���肵�Ă邶��Ȃ��ł����v�y�b�N���������B
�u�}�[�T�͂ȁA����ȂƂ��ł���A�C�j�V�G�̐X�ɂ������č��ɂ��ǂ낤�Ƃ����Ȃ��B���ꂽ���������Ă���邩�ǂ��������������v�Ƃ������ڂŃq�b�s���ɂ�ށB�u�����܂́A���̐X�̘A���ƂȂ����Ă�A����Ȃ��M�p�ł��邩�v
�@�r�X�R���������ƁA�q�b�s�͂��܂炸�|�ꂱ�B�m�[�}���ނ�����������A�z�Ɏ�����Ă��B�u�������M���c�c�v
�@�y�b�N�͏㒅��n�ʂɕ~���B�m�[�}�����̂����Ƀq�b�s��Q�������B�q�b�s�͋����ɂȂ�ԂɋC���������Ȃ�f���Ă��܂������A�o���͈̂݉t�����������B
�u�������肵��A�q�b�s�v
�@�y�b�N�͂������肵��A�ƃq�b�s�̔w�����ȂłÂ����B
�u�ڂ��̔w���̓^�I������Ȃ��B����Ȃɂ�����ȁv
�u�a�l���肾�ȁv�ƃr�X�R�͌������B�u����ȏ�ԂŐX���ʂ�������̂��B��Ԃ�łǂ�����ƁH�v
�@�r�X�R�͎��Z�������V���b�N����܂������Ȃ���Ă��Ȃ������B�m�[�}���y�b�N�̎��ɁA�q�b�s�𗊂ނ��A�Ƃ����₢���B
�u�r�X�R�A������Ƃ������v
�@�m�[�}�̓r�X�R�ɖڔz�������āA�q�ǂ��������痣��Ă������B���ƃq�b�s���Q�]�Ԑ^�ŁA�y�b�N�͍��肱��ł���B
�u�r�X�R�͂ڂ��������Ƃ��C�ɂ���Ȃ��݂������ȁv
�u�N�̂����Ȃ���Ȃ��B�r�X�R�͂��������v
�@�q�b�s�͂����ƓV�����߂Ă���B������͐^���ÂŃJ���e���̖����肾��������肾�����B
�@�y�b�N�͗����C�ɂ��Ȃ��珬���ł������B�u�܂����̎q�ƂȂ����Ă�̂��H�v
�@�q�b�s�͂��Ȃ������B�u���̎q�͂ق�Ƃɂڂ���Ƃ���Ȃ��ڂɂ����Ă��B�r�X�R����ÂłȂ��̂��A��邢���̂̂������v
�@���ꂩ�猶�o���Ђǂ��Ȃ邼�A�ƃq�b�s�͌������B
�u�ƍ߂��������Ă���̂́A�����̕����̂�������Ȃ��̂��ȁH�v
�u�킩��Ȃ���v
�@�ƃq�b�s�͌������B�����A�������̂����W�����ӎ��Ƃ͂����\���������B�q�b�s�ƃy�b�N�͘b���������B�T�C�|�b�c�͈����l���⊴������߂��݂����āA���܂͏W�����ӎ����̂������Ȃ��Ă���B���ꂪ�A�݂�Ȃɉe����^���Ă���炵�������B
�@�q�b�s�͂������C�����悭�Ȃ����̂��A���̂����ɒu��������A���̌��ł��B
�u����ȂƂ��낶�Ⴀ�A�p�V�B�������ɗ��Ă͂���Ȃ����낤�ȁv
�@�y�b�N�������ƁA�q�b�s�͂킸���ɏΊ���̂�������B
�@�p�V�B�Ƃ����̂́A��l�̋��ʂ̗F�����ŁA�y�b�N�͒�������������Ă��Ȃ��B�_���ɂȂ��Ă���Ƃ������́A�q�b�s�ɂ����Ċ�����킹�邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B�y�b�N�����̓n�u���P�b�g����V���̂������K���͂������A�勾�ɂ͗������Ƃ��Ȃ������B�q�b�s����Ă����̂́A�C�j�V�G�̐X�ɂ��킵���������炾�B
�@�y�b�N�͂��ނ��A�Ђт�ꂽ�����o�����B�u���߂��A�q�b�s�B�N�����邱�Ƃ͂Ȃ������B�ڂ����������ł���悩�����v
�@�q�b�s���ނ̘r�����B�u����Ȃӂ��ɂ����ȁB�N�����ɂ͂ڂ����K�v�������B�ڂ��������A�勾�܂ł̓���m���Ă����v
�u�����ǁc�c�v�y�b�N�̖ڂ�����ɗ܂����ڂꂽ�B����ӂ�ƁA���̗܂����E�ɎU�����B�u����ς肾�߂��B�N�̂��Ƃ��l�ɘb���Ȃ���悩�����B����Ȃ���A�m�[�}���������āA�����܂ŗ��Ȃ�������������Ȃ��v
�u����͂������B�ڂ���͂����܂ł���K�v���������v�ƃq�b�s�͌������B�u�W�u���̋w���Ƃ邽�߂Ɂv
�@�y�b�N�͋����ăq�b�s�������B�W�u���Ƃ����̂��A��͂��l�̐e�F�ŁA�ނ͍��N�̓Ɏ��̂��B
�@�q�b�s�͌������B�u�W�u���͂܂������Ă����E�Ȃ��Ȃ��B�����͎���Ȃ��v
�u���Ⴀ�A�ǂ��Ȃ�v
�u�����͎E���ꂽ�A���̗F��������邢���̂ɎE����Ă�A�ǂ��߂��Ă݂�Ȏ���B���̎q�����͑z�������������āA����Ől������ł�ƍl���Ă�B�ł��A�ڂ���͐̂��猶�o�����Ă��킯����Ȃ��B����Ȃ͂߂ɂȂ����̂́A�����ŋ߂ȂB��������������������Ƃ���͂����v
�u�m�[�}�����͂��ꂪ�g���C�X����Ȃ������Ă����Ă�v
�u�����炵���ɑ����ȁv
�@�q�b�s���m�F�ɖ₤�ƁA�y�b�N�͂��Ȃ������B
�u����Ƈ����̕������B���̕��̈ꖡ�c�c�v
�@�q�b�s�͔�J���ނ��Ă������A�������̓M���M���ƋP���Ă����B��l�̑�l�̑O�ł������Ă�����M���قƂ���悤�ŁA�y�b�N�ɂ��悤�₭�͂��킢�Ă����̂������B
�@���̂Ƃ��A�X�̈Èł̂Ȃ��ŁA�C�z���������B�ف[�ف[�Ƃ����A��ȋ��������N�������B��������̂������������Ȃ낤���H�@�q�b�s�ƃy�b�N�͐g���悹�����B�r�X�R�ƃm�[�}�͂ǂ��܂ōs�����낤�H
�@��l�͋��|��U�蕥�����߂ɁA�v���o�b���͂��߂��B
�@��l���o������̂́A�O�N����O�ɂȂ�B�T�C�|�b�c�̍��ł́A�M���ƕ����͕ʁX�ɕ�炵�Ă���B�������Ɋ�����킹�邱�Ƃ͂߂����ɂȂ��B�y�b�N�̓q�b�s�ɉ�܂ŏ��g�ȊO�̕����݂͂����Ƃ��Ȃ������B�Ȃ̂ɁA��l���m�荇�����̂́A�q�b�s�ƃ^�b�g�����A���{�ւ̓o�錠�������Ă������炾�B�y�b�N�̕��e����E�ɂ��A�g�����i�グ���ꂽ���Ƃɂ����R���������B�y�b�N�͂���܂ł�����h�ɂ���A�㋉�M���̎q�킵������Ȃ��A�{��̊w�Z�ɂ��悤���ƂɂȂ����B��N�O�̂��Ƃł���B
�@�y�b�N�͋{��ł̐����ɂ܂������Ȃ��߂Ȃ������B��h�ɂ̐��k�����́A�{��ɂ��悤���k�����̂��Ƃ��A�{��g�A�ƌĂ�ł�����Ă����B�C�ʂ��������A��h�ɂ̐��k�������������Ă����B����ȂƂ���ɒʂ����ƂɂȂ����̂�����A�S���͂��ނ͂����Ȃ��B�{��g�ɂ͓�\�l�̐��k���������A�ނ�̓y�b�N�������M���Ƃ��Ē��ԂƂ݂Ƃ߂Ȃ������B
�@�{��g�ɂ́A�����A�K���g�Ƃ������[�_�[�������B�K���g�����ɂ��ꂽ���Ƃ��v���ƁA���܂ł��݂��ɂ��Ȃ�B�����͐H�~����Ȃ������B���Ԃ̂��Ƃ��v�������A�Q�t�����Ƃ��ł��Ȃ������̂��B����Ȃ��ƂɂȂ�O����A�ނ͕s���ǂɋꂵ��ł����̂������B
�@�K���g�����͈����ЂƂ��Ƃ��Ă��A�ʂƌ������Ă�������͂��Ȃ������B�ʂƌ������Ă����Ă��A����Ȃ��̂͂��₾���A�w��ł��������Ƃ����₩��A�ӂ�ނ��ƃj���j���Ə���̂͂����Ƃ��₾�B�ނ�͕\���������Ƃ͂��Ȃ������ɁA�A���Ȃ��ƂȂ�Ȃ�ł�������B�������������̂����������A���𗘂��Ă��炦�Ȃ��̂͐g�ɂ��������B��h�ɂł͑吨�̒��Ԃ���������A�Ȃ��̂��Ɛh�������̂��B�{��ł̐����͂�����߂ŁA�������̋K���͍l���邾���ł������܂�قǂ������B���̂����ɁA�K���g�����̂��т�ɂ����̂�����A�y�b�N�͂�������_�o������Ă��܂����B
�@�q�b�s�ɏo������̂́A���ǂ͂��̂��т肪�����������̂��B
�@�{��g�͊�h�ɂ̐��k�Ƃ������āA�����̒ʊw��������Ă���B���̓��́A�K���g�����ɔn�Ԃ��o����Ă��܂��A���{�̂Ђ낢��łƂق��ɂ���Ă����B�����ċA��ɂ͉�������B���������ʊw�͓k���ōs���Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă����B�����ɒʂ肪�������̂��A�J���u�c���̔n�Ԃɏ�����q�b�s�������B�J���u�c���Ƃ����͉̂����̔n�ԋƎ҂ŁA�e�V�s�ƃJ���r�Ƃ����Z�킪�X����肭�肵�Ă���B
�@�q�b�s�������A����܂ŋ}篑����Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B�ނ̓^�b�g���ƂƂ��ɁA�����X�̒��O��ɂ��鎩��i�^�b�g���ƃq�b�s�͂��̃{�������������ƌĂ�ł���j�܂ŋA��Ƃ��낾�����̂��B�����ŁA�^�b�g���Ƃ���荇�킹�邱�ƂɂȂ����̂������B
�@����ȗ��A�q�b�s�Ƃ͊�����킷���тɘb������悤�ɂȂ����B�{��ł܂Ƃ��ɂ���ׂ��Ă��炦�鑊��̓q�b�s�������������A�q�b�s������ɂ���̂͑�l���肾�����B��l�͐g���̂����ŁA�炢�������Ă������A�q�ǂ����m�̉�b�ɋQ���Ă������B
�@�Ƃ��낪�A���e�͌��ǖ����Ƃ���āA���̔N�̉Ăɂ͊�h�ɂɂ��ǂ邱�ƂɂȂ����B�y�b�N�ɂ͂܂����Ƃ̐������߂��Ă����̂����A��h�ɂɂ��Ă��q�b�s�̂��Ƃ��C�ɂȂ����B�l���Ă݂�ƁA�q�b�s�Ƃ����̂͂����Ԃ�ǓƂȏ��N�������B�^�b�g���Ƃ͌��̂Ȃ��肪�Ȃ��B�{��ʂ������Ă��邹���ŁA�����̎q�ǂ���������͗���҂̂悤�Ȉ����������Ă����B�q�b�s�͋A��ꏊ���ǂ��ɂ��Ȃ����N�������B�����ł���Ȃ���A�����łȂ����N�\�\�ǂ��ɂ����Ԃ����Ȃ����N�B�y�b�N�͂��̂��Ƃ��v���Ƃ����Ƃ��Ă����Ȃ������B�q�b�s�͗��e������ňȗ��A��l�̎Љ�ɂق��肱�܂�ĕ�炵�Ă����B�y�b�N�͋x�݂̂��тɊ�h�ɂ��ʂ������悤�ɂȂ����B�q�b�s�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ���ȘA�ъ��ɂ�����������āA�^�b�g���̌������������˂�悤�ɂȂ����B���������ߋ��̏o�����������ǂ��Ɏv�������Ă���ƁA��ȂقǕ@�����M���Ȃ����B
�u�W�u���ɉ������c�c�v
�u�ڂ������v�ƃq�b�s���������B�u�ڂ����X�ɗ����Ƃ�����Ȃ�A�N�͂ǂ��ȂH�v
�@�y�b�N�͂����ۂ��������B
�@�M���ƂЂƖڂł킩�镞���ŏo�����������ŁA������ςȂ���X�����̎q�ǂ������ɒǂ��܂킳�ꂽ�B���܂��ɓ��ɖ����āA�^�b�g���̉Ƃɂ����Ƃ��͓������Ă����B���̓��̓^�b�g���̕����̒��ɏo�����������ɔ��܂邱�ƂɂȂ�A��h�ɂɂ�Ă��܂����B�����ɂ����Ă͂����Ȃ��Ƃ����K���͂Ȃ��̂����A�Ƌ��[�ɎO���Ԃ͂��炳�ꂽ�B�ŏI���ɂ͊w������P�����������B�y�b�N�͕����̎q�ǂ��̊i�D�����āA�ƂɋA��Ă��ŁA��h�ɂ��o���悤�ɂȂ����B�T���̂��������Ԃ��������Ƃɂ����B�y���͌������ɔ��܂邱�ƂɂȂ����̂��B
�u�e�h�����g�̂�c�c�v
�@�ƃy�b�N�͌������B�q�b�s�͂��̖��O���ӊO�������̂��A�����H�@�Ɩ₢�������悤�Ȋ�������B�����ɂ̓O���[�v�ƌĂ��q�ǂ������̒c�̂��������������B�s�ǂǂ��̏W�܂肾����A�O���[�v���m�͓G�s�����Ƃ��Ă��肢���������₦�Ȃ������B�����̏��N�Ȃ�����ꂩ�̃O���[�v�ɏ������Ă���̂��ӂ������A�q�b�s�͕����ł��M���ł��Ȃ��Ƃ݂Ȃ���Ă����B�q�b�s�͂��̃O���[�v�̕W�I�ƂȂ��Ă����B�Ȃ��ł��e�h�����g�̃O���[�v�͎��X�Ƀq�b�s��ǂ��܂킵�Ă����B��������ɂ���y�b�N���C�ɓ�����͂����Ȃ������̂��B
�u�ڂ��͂ȁA�����̂��Ƃ��K���g�Ƃ��Ԃ��Č������v�ƃy�b�N�͏킸�ɂ������B
�@�q�b�s�͂����������ɏ����B�u������A�Ӓn�ɂȂ��Ă��̂��H�v
�@�y�b�N�������B�u��������A���������点�Ă��̂��ɉ��������v
�u�e�h�����g���������肷����B���܂��Ȃ���ꂷ���āA�炪��{�Ɏ��オ���Ă������v
�u����Ȃ̂����������܂��B�N�����āA�����ׂo�Ȃ��Ƌꂵ��ł����v
�@��l�͐����Ђ��߂āA�N�b�N�b�Ə����B
�@�e�h�����g�͂���������O���[�v�̃��[�_�[������Ă���B�ُ�Ȃ܂ł̏�M�ŁA��l��ڂ̋w�ɂ��Ă����B�ǂ��܂킳��Ă����҂ǂ��ɂ߂����邱�Ƃ����т��т������B��l�̓^�b�g���̂����Œ��ɍs�����Ƃ����т��т������̂��B�q�b�s�͂����K�˂Ă���Ȃƃy�b�N��ǂ��������悤�ɂȂ����B�ނ̐g������������Ă̂��Ƃ������B�����A����̓y�b�N�ɂƂ��Ă̑Ό��ł��������B�����炵���t�������炯�ނ������Ă������ɏo�������B�����������Ƃ̐킢�ɂȂ��Ă����B�ނ�̓O���[�v�ɂ��܂�邱�ƂŁA�t�ɗF����ӂ��߂Ă������B
�@�q�b�s���������B�u�e�h�����g�̊���Ȃ��炭���ĂȂ��ȁv
�u�����̓S�����Ȃ�������v
�u���܂��͂����ɉ����邽�тɔn���ɂȂ�ȁv
�@�y�b�N�̓q�b�s�̂ƂȂ�ɐQ���]�������B�ނ�́A��l�̐N���������𗧂ĂĂ��邱�Ƃ��m�炸�ɁA�v���o�b�������B�����̗F�l��������l���A�e�F�ɂȂ邱�Ƃ��ł����̂́A�e�h�����g�̂������������B�ނ�͎q�ǂ��ł͂��������A�M���ƕ����̊_���͂������ɂ������B
�@�܂�Ƃ���A��l������������̂́A�e�h�����g�̓S���������̂��B
���@�@�@�@�\��
�@�m�[�}�͐���s���r�X�R��ǂ��������B�q�ǂ��������狗����u�������Ȃ������A�r�����B�r�X�R�͂ӂ�͂�����B�����A�����ɐi�����Ƃ͂��Ȃ������B��l�ɂȂ����������̂��B
�u�������肵��A�q�ǂ��̑O�����v
�@�r�X�R�͓����Ȃ������B�ނ͂ǂ�Ȃ��Ƃł�������F�߂����Ȃ��������A�m�[�}�ɕ��e�Ƃ̊W������ꂽ���Ƃ��A���J�ł��炠�����B�r�X�R�͐u�����B
�u�����܂͂Ȃɂ������H�v
�u�e�q�����̃q���M�X���v
�u�ȂƁH�v�r�X�R�͋������B�u��������̕����̈�h�Ȃ̂��H�v
�u����͂킩���B�����A������̂��Ƃ�K�˂�̂������v
�@�r�X�R�͔����グ���B�u�ǂ��������Ƃ��H�v
�u���͇����̕����̈�h�Ȃ̂��B���܂ł͉��~������̐M�k���v
�@�r�X�R�͂�����Ƒ����̂B����Șb���A�͂��߂ĕ������̂��B
�@�m�[�}�͉Ƃɂ��Ă��l�Z�����������Ă���C�������B��ɂ����ΒN���������킩��Ȃ��L�l���B�M���ł������Ȑl���͌����݂��܂����B����Ȓ��A�r�X�R�����������̌��̈����ŁA����ɕs���������Ă��邱�Ƃ��킩�����B���̐��j�����A������Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B
�u����͎������M�k�ɂȂ�ӂ�����āA�����̐��̂��m���߂悤���Ƃ��v�����B�����A���̂���ł͂���͖������v
�@�r�X�R�͂��Ȃ������B�m�[�}�͌��o�⌶���ɂƂ���A�܂Ƃ��ɖ��邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B�����A���c�̂��Ƃɍs���A������������ɂ������Ȃ��B
�@�T�C�|�b�c�̍��́A�r�p���Ă���B�ΊO�I�ɂ͐푈�����肩�����A�����I�ɂ����̎O�N�͎����̘A���������B�n�b�c�����ވʂ��A���q�̃_�b�^�����ƂȂ����B�������K������@�߂��������o����A��N�O����͌��J���Y���͂��܂����B��Ԃ̊O�o�͋֎~�ƂȂ����B�푈�Œj����Ƃ��A�ƍ߂������Ă������B�閧�x�@�����s���A�l�߂ł��܂���̂����₽�Ȃ��B�M���ƕ����̊W�́A�����������ƂȂ��Ă���B�푈�ɂ�鎀�҂����X�Ƃӂ��Ă������A�����ł̎��҂��܂����ɑ����B�����`�����퉻���A������g�т��Ȃ��Ă͏o�������Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�r�X�R�͋߂��̖̍��ɂ���肱�B�u���[�A���c���̂͌Â����炠��@�h���B�����A���ł́A�܂������ׂ̏@���ɂȂ��Ă���B����̖����킩���B�M�҂̌�����炻���Ƃ��Ă��A���̕��Ƃ��������̂��v
�u������炻���Ƃ����H�@�N�̌������H�v
�u���J�X���v
�u���J�X���ƁH�@�������H�v�m�[�}�͂��ǂ낢���B���J�X�͐_���̈�l�ł���B�u�ł́A�n�u���P�b�g���܂����܂����̂́A�������������������炩�H�v
�u�������v�r�X�R�͂��Ȃ������B�u�����܂͂Ƃ������A����͂��̂܂܍��ɂ��ǂ��Ă��A�����ł͂��܂낤�v
�u������A���Ă����̂��c�c�v
�@�m�[�}�͔[�������悤�ɂ��Ȃ������B�n�t�X���V���ŌĂяo�����Ƃ��v�������̂́A�n�u���P�b�g�������B���s�ɂ����O�ɁA�ނ͕߂܂����̂ł���B�r�X�R�͖�S�Ƃ����A�Âڂ����V���ȂǕ@�ɂ����Ă����Ȃ��B���͂ɂ����������Ǝ��̂��s�v�c�������̂��B
�u�����܂͂��ꂪ���[�A���c�̉҂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂ł͂Ȃ��̂��v
�u�����܂̂悤�Ȃ�ɂ���ȕ��|���ł�����̂��v�ƃm�[�}�͕��S�����悤�ɍ������낵���B�u����Ƃ����܂͏��߂��甽�肪����Ȃ������v
�u����͒m��Ȃ������v
�@�m�[�}�͏݂����炵���B�u���܂ł������܂̂��Ƃ͒����D����B�����A�����Ő܂肠��������Ƃ��悤�B���ǂ��Ȃ낤�Ƃ͂�����v���B������l�ł����͂��ق����̂��v
�u����Ȏq�ǂ��ł����H�v
�@�r�X�R�̓y�b�N�����̂�����������ł������B
�u����Ȏq�ǂ��ł����B����ɕ����̂���̂͂�����߂�B�i�o�z���ɂ�����ꂽ�낤�B���ꂽ���̈ʂȂǂ������̂��v
�u����͔ؑ��̂����������Ƃ��v
�u�����A���[�A���c���݂�A�������M�����݂̂���ł���ł͂Ȃ����B������̐��͂͋��Ђ��B�z��͓Ǝ��̊K��������グ�Ă���Ƃ������v
�u�Ƃ�ł��Ȃ��b���v�ƃr�X�R�͓f���̂Ă�B�u���܂̐��x��ے肷����肩�v
�@�m�[�}�͌��G�����g���̂肾���B�u�����̂Ȃ��ɂ����h�Ȏ҂�����B������ɉ���Ƃ��v
�u����͉���Ƃ͎v���v
�u�Ȃ��킩���̂��B�M���ƂāA���h�Ȃ��̂���ł͂Ȃ��B�o�����Ȃ��̂悤�Ȃ��Ƃđ吨���邼�v
�@�r�X�R�͒��ق����B�ގ��g�͎������o�����Ȃ��̂悤�Ɏv���Â��Ă������炾�B�m�[�}�͌������B
�u�l�̑P�������́A�g����܂�ł͂Ȃ��̂��v
�u���ꂢ���Ƃ��ȁv�Ɣނ͈Â��@�ŏ����B�u�����܂͂ǂ��������̂��B�M������߁A�����̂Ȃ��ŕ�炵�����Ƃ����̂��H�v
�u�����ł͂Ȃ��B�����A�������݂������l�������߂�Ƃ����Ă���̂��B���ꂩ��́A�ނ�̋��͂��K�v�ɂȂ�̂����v
�@�r�X�R�͒��ق����B�r�X�R�͂����قǍɑ����������J���Y�ɂ���ƌ��������A����Ȍ����͂����ɂ���Ⴂ��l�ɂ͂܂������Ȃ������B�_���ɂȂ�͂������A�����I�Ȍ������܂����������Ȃ���E����������ł���B��]�������ċ߂Â����n�u���P�b�g�͍s�����킩��Ȃ����肳�܂��B������������A�B�����ɏ��Y����Ă��邩������Ȃ��B���J�X�̒ʕ���������ł���B
�@��₠���āA�u�t�������[�A���c�ɗ^���Ă����Ƃ͒m��Ȃ������v
�@�m�[�}�͂ނ��Ƃ��Ă������������B�u�����܂̕��͂ǂ��Ȃ̂��H�v
�u����́A�Z�����Ƃ�����A�܂Ƃ��ł͂Ȃ��v�r�X�R�͂��̍����ɁA�����ł��Ƃ܂ǂ��悤�ɐO�����߂点��B�u����̂��Ƃ��Z�Ƃ܂������邱�Ƃ�����v
�@�ڂ̑O�ɂ���̂��A���̑��q�ƋC�Â����Ƃ��̕��̖ڂ��v���ƁA���܂��w��܂ŗ₦��S�n������B�ނ͊���グ�A�m�[�}�̊���݂�����B
�u�m�[�}�A�悭�l����B�����ƋM���͂����݂����Ă���B�a���Ȃǂ͂��肦�Ȃ��v
�u�����A����v�؉A�̂ނ�������b�������������Ă���B�q�ǂ������̖`���k�̂悤�������B�u�����ƋM�������悭���Ă���ł͂Ȃ����v
�u���܂��������̂��B���ꂪ�ꌾ���点�A�����܂��S���s�����v
�@�m�[�}���ɂ�B
�u�܂��c�c���炷�C�͂Ȃ����ȁv
�u�ǂ݂̂��A���ɂ��ǂ�邩�ǂ��������������B�����܁A������ʒu���A�X�̂ǂ̕ӂ肩�킩�邩�H�v
�u�����悻�̌�����������v
�u�H�����Ȃ��ẮA���ꂽ���͂Ƃ������q�ǂ������ɂ͂������낤�v
�u���ꂽ�������B�������낭�ɂƂ��Ă��Ȃ��v�ƃr�X�R�͋������������B�u����ɂ��̗��Ƃ����������B�O���͂��قǂȂ��̂ɁA�{���Ɏ��ɂ����Ă���B�q�b�s�̂������ʂ肩�������B�ǂ����Ă��A�}�[�T�̉Ƃ���ċx�܂���K�v������B����ɂ��̎q�͍��ɂ͂�Ă����Ȃ��v
�@�m�[�}�̓r�X�R���������̂Ă����̂Ȃ����Ƃ�m���Ăق��Ƃ����B
�@���̂��ƁA��l�͗��ɂ��Ęb���������B���̖��͖{���ɂׂ̐��E���炫���̂��A���Ƃ���Ζ߂����Ƃ��ł���̂����B���̎q�����Ȃ��ڂɂ����Ă����Ƃ������A����͂Ȃ��Ȃ̂��H
�@�����A��l�̐N�͓������o�����Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B
���@�@�@�@�\��
�@��l�̏��N�́A��N�O�ɏo������p�[�V�o�������̘b�ł��肠�������B
�@�p�V�B�A���^�A�p�_���A�W�u���\�\���̎l�l�́A�ǂ��̃O���[�v�ɂ�����Ȃ��݂͂����҂������B�ނ�͉��������˂���Ɏg���Ă����B
�@�y�b�N���_���������邱�ƂɂȂ����Ƃ����A���͂��Ă��ꂽ�̂͂��̌ܐl�������B�_���ɂȂ�Ƌ}�ɑ��Z�ɂȂ�A�����ɏo��������͂ł��Ȃ��Ȃ����B�p�[�V�o�������Ƃ́A���̔��N�A������킹�Ă��Ȃ��̂ł���B
�@��l�͂��̌�ɋN���������܂��܂Ȗ`���ɂ��Ă���ׂ�������B���ׂ����Ƃ͂܂��܂�����悤�Ɏv�����B�₪�āA�ꑧ�������B�y�b�N�͂ӂƂ�����������āA�Ԃ����ߔ����ꂽ�o���_�i���Ƃ肾�����B
�u�����Ă����̂��H�v
�@�ƃq�b�s���������B�O���[�v�̃����o�[�ɔz�������낢�̃o���_�i���B�����̎q�ǂ������̓O���[�v���m�̍R����������ƁA�N���ǂ��ɏ������Ă��邩�����߂����߂ɁA���ɂ܂�����r�ɂ����肵�Ă����B
�@�y�b�N�͂����͂Ȃ��������B
�u������ɉ���ĂȂ��̂��c�O����v
�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B����ĂȂ������āA�݂�ȌN�̗F�������v
�@�q�b�s�͂ނ��ɂȂ��Č������������B
�@����Ȃӂ��ɘb���Ă���ƁA�����]���̔O�ɂƂ���āA��l�͖ق肱�̂������B
�@�q�b�s�̓^�b�g���̂��߂ɂ��A�肽�������B����ȂƂ���Ŏ��ʂ͔̂ނɂ������Ă������킯�Ȃ��C������B�{��ō��ʂ�s�҂����Ƃ����A�ς���ꂽ�̂����悤�̓^�b�g���Ƃ������݂����������炾�B�ǂ�ȑ���ɂ����Ȃ鈵���������悤�Ƃ��A�����������e�͂��������B���������{�ł���A�������ڕW�ł���Â����B���ԂƂ���Ƃ����A�ނ̐^�����肵�Ă����C������B�ނ̎����N���o���Ă�����͕ς��Ȃ��B�q�b�s�ɂƂ��ẮA�O���[�v�̒��Ԃ��̂����A�^�b�g���Ƃ̐��������ׂĂ������B�����Ɖ��Ԃ��������������̂ɁA�ނƂ����炻��Ƃ͋t�̂��Ƃ��肵�Ă���B�y�b�N�ɂ����Ĉ��S������ׂ�����͂���B���ɂ����Ă��邾�낤�ƃq�b�s�͎v�����B
�@��l�͗��̂��߂����ʼn�ɂ��������B���͊������������������Ȃ���A��⊾�������Ă���B�q�b�s�͂��̎q�̋ꂵ�݂��v���Ă������Ƃ����B
�u���̎q�͂��ǂ��낤���H�v
�u����͂킩���v
�@���p���琺��������A��l�͊̂��Ԃ��Ăӂ�ނ����B�؉A���炱������̂����Ă����̂̓g�D���[�V���h�E�������B�y�b�N�͍����������ē������������A
�u�������肵��A�킽�����v
�@�m�[�}�������B
�u�킩��Ȃ��Ƃ͂ǂ��������Ƃł��H�@���������Q�[�g�͊J��������Ȃ��ł����v
�@�y�b�N�������ƁA�r�X�R�͍l���Ԃ����ɓ������B�u�߂�̂͂ނ肩�������ȁv�q�b�s�Ɍ����āA�u�����܁A�����Ă����낤�B���̎q���勾�Ɏ���������Ƃ��A�������ŌĂ�ł���҂����Ȃ��ƁB���̎q�������ꏊ�ŃQ�[�g���J�����Ƃ��Ă��A�ĂԎ҂����Ȃ���Ζ߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƁA�����������������̂ł͂Ȃ��̂��v
�@�킩���Ă������ƂƂ͂����A����ł��V���b�N�������B�q�b�s�͂����瑤�ŃQ�[�g���J�����̂Ȃ�A�����ЂƂ̐��E�ł��Q�[�g���Ђ炭�K�v������ƍl�����̂��B�������Ȃ�������A��̐��E���Ȃ��邱�Ƃ͂Ȃ��̂��ƁB
�@���̂܂܂����ƁA���͌��m��ʐ��E�ŕ�炷���ƂɂȂ�B�ޏ��̊O�����l����ƁA�T�C�|�b�c�̒��ɂƂ����ނ͓̂�����������B�q�b�s�͑勾������ꂽ�Ƃ��̗��̐�]��m���Ă����B�ނ̐S�͏d�������B
�@�y�b�N�͕���A�u�ł��A���Ƃ����ꏊ�ɂ��ǂ��Ɩ����ł͂Ȃ��ł����v
�u���ꂽ���͂ł������Ȃ��̐_�����B���̎q�����ǂ��Ă�肽����Ȃ�A�����c��̑O�_�������������Ƃ��ȁv
�@�r�X�R�̂������Ȃ����Ԃ�ɁA���N�����͊���݂��킹��B
�u��������A�����܃}�[�T�̂��Ƃ�m���Ă���ƌ��������A���������ǂ�ȓz�Ȃ̂��B�������Ɖ\����Ă��邪�A�{���ɂ���ȗ͂������Ă���̂��H�v
�u����ׂ�ƕ��������Ƃ�����܂��v�y�b�N���������B
�u��Ƃ����������͂��Ȃ��v�ƃr�X�R�B�u�}�[�T�͉��{�̂������Ȃ̂ɁA�����ܔN�����ɂ��Ă��Ȃ��B�t�ɂ����A���̕��̉e���������Ă��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ邪�ȁv�ƃr�X�R�B�u�����Ƃ��A���[�A���c�̂ق�����K�˂Ă����ꍇ�ׂ͂��v
�u�}�[�T������́A���l�ɂ�������Ɖ�l���Ⴀ��܂���B���l�̂������Ƃ������悤�Ȑl����Ȃ���ł��v
�@�q�b�s�͌������B
�u��͂�A�}�[�T��m���Ă���̂��v
�@�r�X�R���f���̂Ă��B�q�b�s�͂��炢�炵�Ă������B
�u�}�[�T������͂��̂������Ӓn���Ȃ�ł���B���̐l�ɗ��݂��Ƃ������Ȃ�A���̌��͂Ƃ��Ă������Ƃł��ˁv
�u�����܁A�ȂƁv
�u���������g�D���[�V���h�E������{�点���ł��傤�B�������ł������͂Ђǂ��߂ɂ������v
�u���̗��������l����B�����̕��ۂŁc�c�v
�u�₭�������̋M���߁v
�@�q�b�s���ʂƂނ����ēf���̂Ă�ƁA�r�X�R�͐ԍ�����ɂȂ����B
�u���܂͐l��̂ق����Ƃ�������䖝���Ă�邪�A���̒������Ƃɖ߂����炽���ł͂��܂��v
�u���̂܂��ɁA���ɂ��ǂ�邩���S�z�ł���c�c�v�y�b�N���������肵���悤�ɂ����ƁA�O�l�͂��܂肱�B�u�ڂ���͎����̋��ꏊ���킩��Ȃ���ł���B�}�[�T�̉Ƃɂ����āA���ǂ���邩���₵���ł���v
�u�������ȁB���@���������Ƃ��悤�v
�@�m�[�}���͂��܂��悤�Ƀy�b�N�̌���@�����B
�@���̂̂�C���͋M���̂Ƃ蕿���ȁA�ƃq�b�s�͎v�����B�Ƃ͂����A���l���Ȃ�Ƃ����Ă����ƍl���Ă���̂�����n���ɂ����Ȃ������B
�u�q�b�s�A�Ȃɂ��Ă͂Ȃ����H�v
�@���炫�����B
�@�q�b�s�ɂ͍l�������������A���̕��@�������Ă��܂��������M�͂��܂�Ȃ������B�����ǁA�r�X�R�̑O�Ŏ㉹��f���̂����Ⴍ�ŁA�C�����ƎO�l�ɁA����������������@��b���Ă����B�q�b�s�͗��̑̌����A���̐g�������Ēm���Ă͂������A�����ł���������͂Ȃ��̂�����A���܂���鎩�M���Ȃ��Ƃ����������Ȃ��B
�@�q�b�s�͈ꓯ�Ɏ���Ȃ�����ƁA�}�[�T�̋��ꏊ�������낤�ƈӎ����W�������B���̃O���[�v�͗������̂悤�ɂ�������M���������Ă��Ȃ��āA�͂͂����Ǝォ�����B
�@�q�b�s�͂Ȃ�ƂȂ������݂��B���̕��p�ɂ������������B����͂���Ȃ銨�ɂ������������A�r�X�R�̊���݂�ƁA�܂��܂��ӋC�n���킢�Ă����B�q�b�s�͌������ł��A�Ɠ��̂ق����w�����ƁA�擪�ɂ����ĕ����͂��߂��B���̕����Ƀ}�[�T�̉Ƃ����邱�Ƃ��A�F��悤�ȐS�����������B
���@�攪�́@�������}�[�T�̉�
���@�@�@�@��\
�@���ꂩ��}�[�T�̉Ƃ܂ł͈��������ƂȂ����B�邪�����A���ƂȂ�A�܂��邪���܂����B�q�b�s�͂قڈ꒼���ɐi��ł����B���H�b�������A�݂ɂ�����Ȃ���̓����s�ŁA�Ȃ�Ƃ��S�ׂ������B
�@�r���A�T�C�|�b�c�̕������̂����Ă������Ǝv����L�����v�Ղɏo���킵�����A��͂菕�������Ƃ߂�킯�ɂ͂����Ȃ������B������������������߂��Ƃ���ŁA���ɋA��߂ɖ����͖̂ڂɌ����Ă���B�ŋ߂̍�����������ƁA�S�������A�����ɂ������Z�̂ق������������B���������͂����������ĊԂ��Ȃ��炵���A�����̂��Ƃ�����̐�͂����݂������A�ނ��ڂ�悤�ɐH���Ă��܂����B
�@���͖ڂ����܂����A�r�X�R�ƃm�[�}�����ł������Ă������A������d�ׂɂȂ���肾�B�O�l�͐������Ƃ߂����������A�q�b�s�͉Ƃ܂ł̓����͂���邱�Ƃ����O�����B�}�[�T�̂�����p�͂܂�������ꂽ���A�C���͂Ȃ��Ɠ�x�Ƃ킩��Ȃ��Ȃ肻�����B
�@�y�b�N�͂Ƃ������A�M���̓�l�͕�������������B�ꓯ�͂�邢���̂ɂ��т₩����i�q�b�s�����̌��t���������̂�����A�ق��̎O�l���A���̌��ۂ���邢���̂ƌĂт͂��߂��j�A���痧���Ă����B�ނ�͌��o�ƌ����̋�ʂɂ��邵�B�Èł̂Ȃ����J���e�����������ɐi�ނ̂͂ނ��������B����Ƀm�[�}�����͂������_���߂������A�X�̊��C���g�ɂ��������B���̓����{���ɐ������̂��A�^�O���������B������A�ڂ̑O�ɖ����肪�������Ƃ��́A�S��ق��Ƃ����̂ł���B
�@�m�[�}�����Ԃ�������݂āA��т̐����������B
�u�����A�������v
���@�@�@�@��\��
�u����ȂƂ���ɏZ��ł���̂��c�c�v
�@�m�[�}����R�Ƃ����B�y�b�N�����Ȃ����z���������B�}�[�T�̉Ƃ́A����Ȗ̐芔������ʂ��Ă����Ă������B�t���̃G�r�G�����Z��ł����Ƃ�������A�ł��Ă���O�S�N�͌o���Ă���B���͂ɂ͋��������Ȃ�сA�܂������X�̂Ȃ��ɂ������B
�@�����̑��̂悤�ɂ��ł������Ȃ܂Ȃ܂����B
�@���̒����ɁA�Âڂ��������������B������̍��E�ɂ͑�������A�������疾���肪����Ă����B
�u����ȐX�̂Ȃ��ŁA�悭�������Ƃ����v
�@�r�X�R�������ꂽ�B�q�b�s���������B
�u�}�[�T������́A�n�b�c���������������Ă����ł���v
�@�n�b�c���̓~�c�o�`(�Ƃ����Ă��̒��̓T�C�|�b�c�Ƃقڂ��Ȃ��ł���)���������������ł���B�}�[�T�͉Ԃ���̂�����������Ă����B�r�X�R���@���Ȃ炵���B
�u�܂��A���̍��Ƃ́A�푈���Ă��Ȃ�����ȁv
�@�~�c�o�`�͋���Ԃ���A�푈�̂��悤���Ȃ��̂ł���B
�@�l�l�͂ꂾ���āA�����ɗ������B�m�[�}�̔w���ŁA���͂������肵�Ă���B�q�b�s�͋F��悤�ȋC�����������B�}�[�T�Ȃ�A�������Ƃ̐��E�ɖ߂����@��m���Ă��邩������Ȃ��B
�@����Ȗ̍��̍��ԂɁA�O�i�̊K�i���������B���ɒʂ��Ă���B�m�[�}���K�i�ɑ���������ƁA�Âт����g�݂����������Ɣߖ��������B�������������Ƃ������A�r�X�R�����̌��Ɏ�������A�҂āA�ƌ������B
�u����Ȗ钆�܂ŋN���Ă���̂͂��������B���ɕ��������邩������v
�@�݂�Ȃ̓r�X�R�̌��t�ɔ[�������B�X�̒��ɏZ��ł���Ƃ͂����A�}�[�T�͂�����Ƃ����T�C�|�b�c���B�������K�˂Ă��Ă����������͂Ȃ��B
�@�r�X�R�͊K�i����̍��ɂ������B�ׂ̍��ɔ�т���ƁA���g�Ɏw�������A�����̂������B
�@�Ƃ̒��͎v���̂ق��L�������B���ʂɂ͖{�̂܂����I������A�ڂ�r�����G�ɂ�����Ă���B���͑������A�������ς�Ƃ��Ă���B�傫�ȃx�b�h���E�̂͂��ɂ���B�������ɖ����̉Ƃ��ȁA�ƃr�X�R�͕ςɊ��S�����B�}�[�T�͋���Ȋ��ɂނ����č����Ă���B�֎q�̂ނ����ɑ����������������B�b�ɂ����������̂��̂̊i�D���B�Ƃ̒��Ȃ̂ɁA�t�[�h�����Ԃ��Ă��āA�r�X�R�ɂ͂����ɂ���̂��A�V�l�Ȃ̂��ǂ������킩��Ȃ������B
�@�r�X�R�͒��ӂԂ����ώ@�������A�Ƃɂ���̂̓}�[�T��l�̂悤�������B
�@�r�X�R�͖̍��ɗ������܂܁A�m�[�}���݂Ă��Ȃ������B
�@�m�[�}���h�A���m�b�N����B�Ԏ����Ȃ������B�}�[�T�͂ӂ�ނ����Ƃ����Ȃ��B�r�X�R�͖����Ă���̂��Ƃ��Ԃ������B
�@�m�[�}���ӂ����ю���グ��ƁA�N���ӂ�Ă��Ȃ��̂ɁA�������ɉ������ĂĂЂ炢���B�ނ�͌�������Ƃ������B������ɂ͒N�������Ă��Ȃ������B�r�X�R�͂܂��������̏�ɂ������A��͂�ڂ��܂邭���Ă����B�ނ̈ʒu����������������҂͌����Ȃ������B�}�[�T�͈֎q�ɂ�������܂܂��B
�u�Ȃ��A�T�C�|�b�c�̏��m�ǂ������v
�@�}�[�T���Ⴂ�A���킪�ꂽ���ł����ƁA�����������ƕ܂肩�����B�m�[�}�͎�������ĉ��������B
�u�܂��Ă��������B�ڂ���͏������ق�����ł��v
�u��������A���������Ȃ��ˁv
�@��������ɕ܂�A�m�[�}�͂����ƌ�ނ����B�r�X�R���Ƃт���Ď��݂����B���̂����ɁA�q�b�s�ƃy�b�N�͉����ɂ��ׂ肱�B
�@�Ƃ̂Ȃ��͖ƌÂڂ����̓����łނ��Ă����B�����v�̂��肶��Ƃ������肪��l�̖ڂ��₢���B�q�b�s�ɂƂ��Ă͈�N�Ԃ�̖K�₾�����B
�@��l�͂�����Ƒ����̂B
�@�}�[�T���ӂ�ނ����B���ǂ낭�قǂ₹���ۂ��ŁA���킾�ꂽ�炾�B�����͂܂������Ȃ��Ӓn�����A�ƃy�b�N�͎v�����B�傫�Ȗڂ����Ă��邪�A�l���������B���������F�̃��[�u����A�^�����ŃJ�[�����������������̂����Ă���B�}�[�T�͂��̑傫�Ȗڂ�������Ɠ������A�u�q�b�s���H�v�Ƃ������������悤�ɂ������B
�u�^�b�g���͂ǂ������H�@���܂��܂Ń��[�A���c�ɂ͂������̂����H�v
�u�����ɂ܂ŁA���[�A���c��������ł����H�v
�@�m�[�}�����̉A���̂����Ȃ��炢�����B���̉A�ɂ͒N�����Ȃ������B�r�X�R�ƃm�[�}�͊���݂��킹���B
�@���@���H�@�}�[�T�͖��@���������̂��H
�@�r�X�R�����h���������Ȃ��炫�����B�u������͂��Ȃ��ɉ�����������ł��H�v
�@�}�[�T������ӂ����B�����v�̉��h��Ă����B
�u�������߂ȁB�����͂������܂��v
�@�r�X�R�͂��ƂȂ����]�������A�}�[�T�̕������ɂ��ꂪ�������B����ł������͒g�������A�l�l�͂���Ɛl�S�n�������B�Y��Ă������A�}���ɂ�݂������Ă����B
�@�m�[�}�͂܂����Ɏ�ĂĂ���B
�u����Ȏ��Ԃɂڂ��炪�K�˂Ă����̂ɁA�����Ȃ���ł����H�v
�u�ׂɋ����Ⴕ�Ȃ��ˁB���܂̐��̒�����Ȃ�ł����肾�B����Ȃӂ��Ɏv���ˁv�Ƃ����āA�ܐl���݂�B�u���[�A���c���B������͎O�x�قǖK�˂Ă����ˁB�C���̈����A����������B�������ɂ����������Ă��邵�A�Ȃɂ��ɑ����Ă���݂����Ɍ��������ˁv
�@�}�[�T�͔w������ɐg�����������B�ւƂւƂ̎q�ǂ�������O�ɁA������邻�Ԃ���݂��Ȃ��B�������A���[�A���c�̈�ۂ́A�m�[�}�����̌����ƈ�v�Ƃ��Ă����B�ǂ����}�[�T�́A���[�A���c�ɂ͂��݂��Ă͂��Ȃ��悤�������B
�u���[�A���c��������Ȃ��B���̂Ƃ���͐X�̎푰�����������ƖK�˂Ă���B����������A�T�C�|�b�c�̗l�q���������������ˁv
�u����ׂ�����ł����H�v
�@�r�X�R�͔��߂��Ă����ƁA�}�[�T�͋}�ɂ����ƂȂ����B
�u����ׂ肽�����Ƃ�����ׂ邳�ˁB���܂������Ă������낤�B���̂��܂����Ⴍ�ꂽ�����A���Ă����Ȃ��l�q����Ȃ����v
�@�r�X�R�͂߂炢�A������ނ��{������炦���B�}�[�T�̕������ɁA�m�[�}�����͂����킸�r�X�R�̗l�q�������������B
�@�}�[�T�͂������C���ʂ��āA�u������̐g�ɂ��Ȃ��Ă݂ȁB�T�C�|�b�c�Ƃ͂���܂ŗF�D�I�ɂ���Ă����B���ꂪ�}�ɍU�߂��܂�ĎE���ꂽ��A�킯�̂ЂƂ��m�肽���Ȃ邳�v
�u�ڂ��炾���Đ푈�����Ă��闝�R���m�肽�����炢�ł��v�m�[�}���������B
�u������������v
�u�������A���Ȃ����T�C�|�b�c�ł��傤�v�r�X�R���������B
�u�ǂ����낤�ˁv�}�[�T�͓f���������B�u��������A�ǂ݂̂����ɂ͋A���ĂȂ�����ˁB�X�̘A������T�C�|�b�c�̋ߋ����Ă�����A������������Ȃ����v
�u���ɖ߂�悢�ł͂Ȃ��ł����v
�u�߂肽���Ă��߂�Ȃ���v
�@�}�[�T�̌��Ԃ�͌����܂��������B�q�b�s�͈ꓯ�̑O�ɂł��B
�u���o���݂��ł����H�v
�@�}�[�T�͂ƃq�b�s�̖ڂ��ɂ�B�Ȃ�Ƃ͂Ȃ��Ɍ��ɂ��Ă��܂����̂����A�q�b�s�͂��̊����������Ă����Ǝv�����B
�u�ڂ�������Ȃ��Ȃ�ł��B���o��A�������݂邵�A���ӎ��ɍs�����Ă�v�Ɣނ͂����Đk�����B�u�Ђ���Ƃ�����A�F�����͂��̂����Ŏ��̂�������Ȃ��c�c�v
�@�}�[�T�́A�ق��A�Ǝ����̓��h�����炷�悤�Ȑ����o�����B�y�b�N���������B
�u���̂Ȃ��Ő��������ł��B�������ڂ���𑀂낤�Ƃ���݂������v
�u�������A���ɂ��������Ă��܂��������Ƃ�����B�G�Ɩ������������̂Ȃ��ł���ׂ��Ă���݂������v
�@�݂�Ȃ̓r�X�R�������B�r�X�R�̈ӌ����ʔ����������炾�B���̒��ł͂�����I���˂Ă���悤�ȋC�������B
�u����ȂƂ���Ɉ�l�ł悭�����܂��ˁv
�@�m�[�}�����S���ĕ������݂܂킵���B�����Ȃ�A�Ƃ����Ɍ��o�ɂ���Ă������낤�Ǝv�����̂��B
�u��O�Ƃ��Ȃ��ɂ����Ȃ���B�����Ƃ�b���悤���������v
�@�m�[�}���������Ă��鏗�̎q�ɁA�͂��߂ċC�������悤�Ɋ{�����Ⴍ�����B
�u���̎q�́H�v
�@�m�[�}�͂����܂ł̎������������B���݂̍��̗l�q���Ȃ�ׂ��܂Ƃ߂Đ��������B�������Ȃ��Ǝ����������������Ă��܂��������B�r�X�R���Ƃ���������͂��B�����������_���ł��邱�Ƃ��������Ƃ��A�}�[�T�̓n�u���P�b�g�̂��Ƃ�u�����B�m�[�}�����́A�����͂킩��Ȃ��Ɠ������B�n�u���P�b�g�Ƃ͋��m�̒��̂悤�������B
�@�����勾���甲���łĂ���������ɂȂ�ƁA�}�[�T�͊{�����킵���Ȃł͂��߂��B�m�[�}�ƃr�X�R�̘b���I���ƁA�����ꂽ�悤�ɓf���������B
�u���܂������A���̎q�����܂݂�̂܂ܘA��܂킵���̂����H�@�̂������āA�M���o���Ă邶��Ȃ����v
�u�킩���ł����H�v
�@�m�[�}�͋������B�}�[�T�͈֎q���痧���オ���Ă����Ȃ��B���������A�w���ɂ��闘�̑̉�������ɔM���悤���B
�u�����̃x�b�h�ɐQ�����ȁB������Ȃ���v
�@�ƃ}�[�T�͎w�������������A���͌��܂݂�̂܂܂Ȃ̂�����A�����ȂƂ����͖̂����Ȓ������B
�@�y�b�N���z�c��������ƁA�m�[�}�͒��ӂԂ����x�b�h�ɐQ�������B
�@�}�[�T�͖����Ƃɂ����Ċz�Ɏ�����Ă��B�������߂����B
�@�q�b�s���u�����B�u������܂����H�v
�@�}�[�T�̓q�b�s�������ƌ����B�]�݂��܂Ō��Ă���悤�ȁA�ٗl�Ȍ��ߕ��������B
�@��₠���āA���Ɍ����Ȃ������B
�u���v���낤�B�����A�����낵���������������悤���ˁB�l�Ԃ�����Ȃɔ��邱�Ƃ͂߂����ƂȂ���v
�@�}�[�T�͗��̊z���Ȃł���A���߂��݂⓪�������肵���B���̊Ԃ��ꓯ�Ɏw���������āA���ݒu���̐����Ƃ��Ă������A���̐��ɖ��������ē��ꂳ�����肵���B�}�[�T�͗��Ɉӎ����W�����āA�l�l�̂��Ƃ͌��Ă��Ȃ��̂ɁA���̎w���͂��ǂ낭�قǓI�m���B�l�l�͂���Ă���̂ɁA���̂܂ɂ��}�[�T�̂����Ƃ���ɓ����܂���Ă����B�}�[�T�͉��ɂ͂������Ƀ^�I�����Ђ����ƁA���̌���@���Ƃ��Ă������B���������A�����������т��ˁA�ƂȂ��߂�悤�ɂԂ₢���̂ŁA���N�����͋C������邩�����B�}�[�T�̋��͂��K�v������A�r�X�R�����܂��Ă������B
�@�m�[�}�͂��덇�����݂āA���̖����͂���}�[�T�ɂ����₢���B
�u�������ق�����ł��B���܂����ɂł����ɋA��˂A�l�l�Ƃ��܂������ƂɂȂ�v
�u�܂��A�_���̂��܂������~�ɂ��Ȃ��ƂȂ�����܂������낤�ˁv
�u�Ƒ��ɂ́A��ɂ����Ƃ����Ă���܂��B�ł����A����ȏ�ɍ��̂��Ƃ��S�z�Ȃ�ł��v
�@�m�[�}�͐؎��Ȍ����ł����ƁA���Ƃ̓}�[�T�����߂Â����B�}�[�T�͗��̓������݂Â��Ă���B�₪�āA���ߑ��������B
�u�������Ȃ��ˁB�n�}�ƐH���͂���Ă��B���Ƃ͒m��Ȃ���B���܂������A�邪������܂ŁA�����ŋx��ł����v
�u�������c�c�v
�u�����܂�B�}�������Ď��ʂƂ��͎��ʂ���ˁB�Ȃ��āA�^���̐S�ȂB�^�C�����������������s�����������ˁB�����Ƃ��A�x��������Ȃ���Ȃ�b�ׂ͂��B�Â��铹������������A�D���ɂ��ȁv
�@�x���ƕ����ƁA�y�b�N�͂��܂炸�ɍ��肱�B������݂āA�}�[�T�͈Ӓn�����������B
�u�j�̂����ɂւ��肱�ނ�Ȃ���B�����Ƃ��ȁv
�@�}�[�T�̓q�b�s�ɖ����ĐH����p�ӂ������B�y�b�N���֎q��p�ӂ����B����ȂƂ���ɋq������̂��s�v�c���������A�Ƃ������֎q�͏�����Ă������B�����ɂ�����ŁA�ӂ��낢���B
�@�ꓯ�͒x���H���ɂ����������B���炭���ă}�[�T���Ȃɂ����B�q�b�s��������p�ӂ���ƁA�}�[�T�͏a�����ɂ��������B
�u���̎q�͂ǂ�������H�v
�u�ǂ�������Ȃɂ��c�c�v
�@�m�[�}�̓r�X�R���݂��B�r�X�R�͌ł��p�����ق���Ȃ���A�}�[�T�̂��Ƃ��ɂ�݂��Ă���B�}�[�T�̂��Ƃ��M�p�Ȃ�Ȃ��̂��B
�@�}�[�T�͂܂����ߑ��������B
�u�������Ȃ��A�����ɒu���Ă����ˁB���̖��͂��܂͓������Ȃ��ق��������B���ɂ͂��܂����������ŋA��B�q�b�s�A���܂����A��Ȃ���B�����Ɏc��ȁv
�@�q�b�s�͂̂ǂ��܂点���B�}�[�T�͂����������悤�ɂ������B
�u���܂��͂̂���B���ɂ͋A��Ȃ���B���̖��Ɛ��_�����������܂��Ă����ˁv
�u�킩���ł����H�v
�@�m�[�}���������B���ƃq�b�s�̘b�͂��Ă��Ȃ��������炾�B
�u������O���ˁB���ꂾ���Ă���������ȋV���̂������v�Ɛ�ł������B�u�n�u���P�b�g�͂Ȃ�ł��܂������݂����Ȃ̂��q�ɂ����낤�ˁB����ȘA���𐢂ɂ����肾�������̋C���m��Ȃ���v
�@�r�X�R����X�����ɂ������B�u�n�u���P�b�g�����܂��������ŁA�ڂ���͏C�s���I���Ă��Ȃ��B���Ȃ������������Ă��邠�����ɑ�ςȂ��ƂɂȂ����v
�u�^�b�g���͖����Ȃ̂����H�v
�@�}�[�T���b���������ƁA�q�b�s���������B�}�[�T�̓^�b�g������N�O�ɖS���Ȃ����ƁA�����ƂЂǂ����_�����悤�������B�q�b�s�͊�Ȉ��g�������ڂ����B�����ȊO�ɔނ̎���߂���ł����l�Ԃ����邱�Ƃɂق��Ƃ����̂��B
�@�m�[�}���u�����B�u���̎q�͂����������҂Ȃ�ł��傤�H�v
�u���҂��Ȃ�Ă������ɂ͂킩���B�������A�C�s�͂��܂���������ł�悤����v
�@�l�l�͗��̗͖͂ڂ̂�����ɂ��Ă����B������s���s�����Ȃ������B
�u���̎q�͂ނ����̐��E�̖��@�����Ȃ�ł����H�v�ƃy�b�N���u�����B
�@�}�[�T�͂܂������ƂȂ����B�u���@�����Ȃ�Č��t�A�������ጙ�����ˁB�����������܂��������A���������s�v�c�ȏp�������Ǝv���Ă�낤�H�v
�u����ׂ��Ȃ���ł����H�v
�@�y�b�N�̎����Ƀm�[�}�ƃr�X�R�͊�������߂����A�}�[�T�͑���������B�ӊO�ɐl�D���̂���Ί炾�����B
�u����ȉ\��M���Ă�̂����H�@����Ȃ܂˂��ł���͂����Ȃ����낤�B�܂����������˂��v
�@�q�b�s�̕������̌����悤�ɂ͂ނ��Ƃ����B
�u����ŁA���͖߂���ł����A�߂�Ȃ���ł����H�v
�u�킩���ˁv�Ƃɂׂ��Ȃ��B�u���R�ɂ���A���܂������ׂ͂̐��E�Ƃ̋��E���J�����܂�����B�Ƃ��낪�Ȃ��J�����̂��́A�킩���Ƃ��Ă�B���m�łȂ��V��������āA�܂����������ʂ��o�����܂�������B�܂�A���܂�������������͎̂��҂��Ăт����V���Ȃ낤�H�@���҂Ȃ�勾�ɂ���͂����B���ꂪ���ɖ��Ȍ�������������ɁA���g�̐l�Ԃ��łĂ�������ˁB����͗e�Ղ���Ȃ���v
�@�ƃ}�[�T�͌������B
�u�ׂ̐��E�Ƃ������̂́A�ق�Ƃɂ����ł����H�v
�@�m�[�}�������ƁA�}�[�T�͂��Ȃ������B�u�������͂���Ǝv���Ă�B�t���̃G�r�G�������������Ă�������ˁv
�@�l�l�͔[���ł��Ȃ��܂ł��A���Ȃ��������Ȃ������B
�u�Ƃ����Ă��A���������V���ɂ͂��킵���Ȃ��B����͉����̔�@�łˁB���Ƃ̐_�鐫�����߂����߂ɁA���������p����Ă������̂ȂB��������Ă�����i�����̌`�[�����ꂽ���̂ŁA���������ɂ͂����Ȃ����̂Ǝv���Ă����v�}�[�T�͊{�ŕǂ̂ق������߂����B�u������ɏ������R�ς݂���Ă��邾�낤�B�����������̔�@�ƌ������ˁB�����炠�̒��ɂ��ڂ��������Ⴂ�Ȃ���B���Ȃ��Ƃ��������̎t���͋������Ⴍ��Ȃ������B�_���E�̐��͂�͂�n�u���P�b�g���B�V���̂��ƂȂ炠���ɂ����ׂ��Ȃ�B�܂�Ƃ���A���܂������͂������̂��Ƃ�������Ă���B�������͂��܂��������l���Ă�悤�Ȃ������Ȃ���Ȃ���B���̎q���ӂ����т��Ƃ̐��E�ɖ߂��Ȃ�Ăł��Ȃ��B���Ԃ͖��@���Ȃ�Ă������A�������������̂��A���傹��͈ӎ��̗́A���_�̗͂ł����Ȃ��B�N�ł��ł��邾�낤���Ƃ����A�������ɂ����Ăł��Ȃ���v
�@�q�b�s�͂킩��C�������B���̒u���ꂽ��Ԃ�m���Ă������炾�B���͂ӂ��̎q�ǂ��������̂ɁA�ُ�ȏ�Ԃ̂Ȃ��ŁA�m�炸�m�炸�̂����ɗ͂����Ă����B����͂�邢���̂��瓦���̂т邽�߂ɕK���ł�������Ƃ������B�q�b�s�����̂��Ƃ�b���ƁA�}�[�T�͓��S�����悤�ɂ��Ȃ������B
�u�܂������A���H�ɂ܂���C�s�͂Ȃ����Ă��Ƃ��B�O����̓����������������ɂ���A���̎q�͎����̖��������������Ă���ȗ͂�g�ɂ����̂��B���܂����������đ�Ȃ菬�Ȃ肻�����B���̎q�̂�����邢���̂₨�������Ɉ����������āA�܂���Ȃ�ɂ�����ɒ�R���Ă�������ˁv
�@�m�[�}�����͂��������Ƃ������t�ɂ͔[���ł����B�ނ�͈ӎ��I�ɂ����ӎ��I�ɂ���������Ă���A���[�A���c�̗U���ɒ�R���Ă�������ł���B
�u���̎q�̂����̂��A�܂������ׂ̐��E�������Ƃ��āA�Ȃ���X�Ƃ��Ȃ����Ƃ��N�����Ă����ł��H�v
�@�ƃr�X�R�͂���ǂ͒��d�ɂ������B�m�[�}�����͊�������߂��B�r�X�R�̓q�b�s�ɂ������B
�u�����܁A�����Ă����낤�A���̖��ƒ��Ԃ��A���o�⌶���������Ă����ƁB���̎q��́A��邢���̂��Ƃ��A�����������Ƃ������Ă����悤�����c�c�v
�@�}�[�T�͂҂���Ɣ��������������B
�u����Ⴀ�A�ǂ��������Ƃ����H�v
�@�q�b�s���������B�u���؎��g���ڂ���Ƃ��Ȃ��̌������Ă����ł���B�̋��Ŕƍ߂��������Ă���Ƃ��������Ȃ��ł��v
�@�}�[�T�͓f���������B�u�Ђ����Ԃ�ɉ�����Ǝv������A���Ƃ��������ނ���Ȃ����v
�u�}�[�T���������ɂ�����A������Ƃ����ɎE����Ă܂���v
�@��������Ȃ��ˁA�ƃ}�[�T�͂Ԃ₢���B�u�������ɉ��s�ɂ��ǂ�ȁA�ƌ������̂́A�n�t�X�̂���v
�u����͂��̂��Ƃł��H�v
�@�r�X�R���������B
�u��N�قǑO�ɂȂ�ˁB�莆���悱���Ă����̂��v
�u���̂��A�����ƘA���́H�v
�@�����͂����A��������Ȃ���A�ƃ}�[�T�͂��Ƃ���Ă���A
�u�Ȃ��ˁB���̈�N�ԁA�A���͂Ȃ������B�������A�n�t�X���܂Ƃ��Ȃ�푈�Ȃǂɂ͔������͂����v
�@�݂�Ȃ͂��Ȃ������B�n�t�X�̕s�݂�s�R�ɂ������҂͑��������̂ł���B
�u�n�t�X�剤�́A�Ȃ����Ȃ��ɐX�ɂƂǂ܂�悤�������̂ł��傤�H�v
�u�킩���˂��B�������͂������ŁA�_�b�^�̂��Ƃł������蕠�������Ă�����łˁB���s�ȂA����������肢�������Ǝv���Ă�����v
�u���Ȃ��̐g���܂��邽�߂̌������Ƃ�����A�n�t�X�剤�͊댯��F�����Ă������ƂɂȂ�v
�u��Ȃ̂́A�g���C�X�Ƃ����j�ł��B���݂͍ɑ��Ȃ̂ł����A�����m�ł����H�v
�@�}�[�T�͂������l�����ނ��Ԃ���݂��A�u�g���C�X���A�������悤�ȋC�����邪�c�c�v
�u����Ȃ͂��͂Ȃ��ł���v�y�b�N���������B�u�M�����ӂɂ��ڂ��Ă��Ȃ����O�Ȃ�ł��v
�u������A�����ꂽ�̂́A���傤�Lj�N�O���v�ƃr�X�R�B
�@�݂�Ȃ͖ق肱�B�m�[�}���������B
�u�o�����܂������킩��Ȃ��l�����A�ɑ��ɂȂ����̂ł��傤���H�v
�u���ʂɍl������肦��b�����A�_�b�^�̉����������Ƃ������Ƃ��l������v
�u�M�����ӂɂ��ڂ��Ă��Ȃ��l�����ł����H�v
�@�m�[�}�͋^�킵�����ɂ������B
�u����ɍڂ��Ă���̂́A����ƒ��j�܂ł�����ˁB���j�O�j�ł��A�o����z�͂��邾�낤�v
�@�r�X�R���A�u���Ƃ���ƁA�n�t�X���̎��H�ɂ́A�_�b�^������������Ă��邱�ƂɂȂ�v
�u���邢�́A�_�b�^�����g���d���Ă���̂����c�c�v
�@�ƃm�[�}�B
�u�܂��A�����Řb���������Ƃ���ł������Ȃ����B���킩��Ȃ�����ˁv
�@�ꓯ�̓}�[�T�̗p�ӂ����є�̂����ɉ��ɂȂ�ƁA�x���A�Q�ɂ����B�}�[�T�̉Ƃɗ\���̕z�c�͂Ȃ�����A�ޏ��̃��[�u���͂���ƁA���Ƃ͓D�̂悤�ɖ������B
���@�@�@�@��\��
�@�}�[�T�͖��Ƃ�悹�A���̑̂��ӂ��Ƃ�͂��߂��B�����v�̂������ȓ��肪�ޏ��̎���Ƃ������������Ƃ炵�Ă���B��������Z�����Ȃ�ˁA�Ɣޏ��͎v�����B���̎O�l���ɍ��܂ŋA�����悤�ɂ��Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����A���ƃq�b�s�̏C�s���͂��߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ƃ��A���̗��Ƃ����������́A���炭�ڂ����܂������ɂȂ����B
�@�܂��͂��̖������Ȃ��Ȃ����Ƃ��Ɣޏ��͎v�����B
�@�}�[�T�͈يE���炫���Ƃ��������������낵���B���͍��M���͂����A�ʂ̂悤�Ȋ��������Ă���B�������������炯�����A�����������߂Ă���悤���B�����ɂ���܂ňُ�Ȃ܂ł̑̌������Ă����ɂ������Ȃ��B�}�[�T�͏����ɍp����͂�ƁA������ނ�����܂����B
�@�}�[�T�͖������Ă��āA�Ȃɂ��S�ɂЂ���������̂����������A���ꂪ�Ȃ�Ȃ̂��͂킩��Ȃ������B�يE���狫�E���������Ă����l�Ԃ��݂�̂̓}�[�T�����߂Ă������B�G�r�G���͌������Ƃ�����ƌ��������A�ڂ������Ƃ͕��������܂��������B�͂����肵�����Ƃ�����Ȃ������̂ł���B
�@�}�[�T�͌����ɂ������A�l�l�̎p���v�����������B���̂Ƃ��́A�ӂ����уn�t�X�������K�˂Ă����̂��Ǝv�����ǂ낢���B���ꂩ��O�S�N�������Ă���Ƃ����̂ɁA���܂���ߎ��lj��������낤�Ƃ͎v�������Ȃ������B
�@���̂Ƃ����A�ǂ����������Ƃ����G�r�G���ɁA�n�t�X��͗��݂���ŗ���Ȃ������B���̂����̂����ւ����ʂ��Ă���̂�������Ȃ������B�O�S�N�Ɛ̂̏o�����Ȃ̂ɁA�}�[�T�̋L���͂͂����肵�Ă����B
�@�G�r�G�����玀�ɂ���ɋ����������ƁA����͂܂��ɔԐl�̖�ڂɂق��Ȃ�Ȃ��B���傤�Ǘ��������Ă��邻�̃x�b�h�ŁA�G�r�G���͂����������̂ɂ����Â��̂ƌ��������Ȃ���A�ڂ����͂�������}�[�T�����Ă������B�u���܂��͐����ؐl���A�������茩�����Ă�����v
�@�}�[�T�����܍��ɂ����A�ǂ̐w�c���ɂ͂��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ȃ�B�����炭�̓n�t�X�̐w�c�ɂ����ƂɂȂ邾�낤�B�����A�n�t�X�����̂��Ă��邱�Ƃ��������Ƃ͂�����Ȃ��B
�@�n�t�X������ł���Ƃ�����A����͎c�O�Ȃ��Ƃ��B�̂�m�钇�Ԃ��ЂƂ�����Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł���B�}�[�T�͌ǓƂ������B��l�������������A�ߋ����킩���������̂��Ȃ��A�V���Ă������Ƃ���ɂ������B�Ђ���Ƃ���ƁA�����̓T�C�|�b�c�ł͂Ȃ��̂�������Ȃ����A���푰�Ƃ̍����Ȃ̂�������Ȃ������B���Ԃ̓}�[�T�̂��Ƃ�S�͂����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������Ă��邪�A���ۂ͂���ȏ�̒����Ȃ̂ł���B
�@�G�r�G��������ŁA������S�N�ȏ�ɂȂ�B�G�r�G���͂��܂̃}�[�T�ł���ǂ������Ƃ��ł��Ȃ��قLj̑�ȗ͂������������������B���̂������l��M�p�����A�킸���Ȑl�ɂ����S���J���Ȃ��A���݂����l�ł��������B
�@�͂��߂ăG�r�G���Ƃ����V�k�̂Ƃ����K�˂��Ƃ��̂��Ƃ��v���o�����тɁA�W������������ȉΎ�̂悤�ɐS�ɂƂ������B
�u�Ȃ�ł����������܂��Ȃ��q�ɂƂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���R�͂ȂˁB�����Ă݂ȁv
�@�G�r�G���͂��������āA�Ȃ�ǂ��}�[�T�̂��Ƃ�ǂ����������B�}�[�T�͈Ӓn�ɂȂ��āA�G�r�G���̂��Ƃɂ��������B���������������������ẮA�{���A���Â���A�ǂ��͂��ꂽ�B
�@�{���ɁA�J�̓������̓����A�댯�ȐX�̂Ȃ�������ăG�r�G���̌������ƂȂ����B���܂ƂȂ��Ă͗��R���v���������Ƃ��ł��Ȃ����A��ɂ��̐X�ŕ�炷�Ƃ��������M�O�ł����āA�G�r�G���ɍ��肵�Â����̂��B���̎��͔ޏ�����\��̎Ⴓ���������A�g�����Ȃ������E����Ȃ��A������ł��������ł����̂������B
�@�ŏ��̂����́A�Ƃт���J���Ă���Ȃ������B�G�r�G���̉Ƃł��������Ԃ́A�������ɉ��тĂ������B������A�Ƃ��Ƃ��G�r�G�����܂ꂽ�B
�u�܂������A���܂��݂����Ȋ�łɂ͂��������Ƃ��Ȃ���v
�@�}�[�T�̔]���ɁA��������ƈ֎q�ɐg���悱�����A�ԂԂ���������Ă���G�r�G����������ŁA�ޏ��͂ɂ��Ə����B�����Ȓ�q�ɂȂ�ƁA�G�r�G���͏�e�͂Ȃ��}�[�T�������������B���������������܂������ĂĂ͔l���Ă܂��A�C�s�͂����ւ�Ȑh���ƂȂ����B���܍l���Ă��A�Ȃ������o���Ȃ������̂��A�s�v�c�Ȃ��炢���B
�@�Ƃ�ɂ���Ȃ����_���A���܂͉����������̂������B
�@�C�����ƁA�}�[�T�̓G�r�G���̒�q�Ƃ��āA��ɓo��悤�ɂȂ��Ă����B�G�r�G���͌������Ĕ߂����l���������ǁA�}�[�T�ɂ����͂����S���J���悤�ɂȂ��Ă����B�G�r�G���͋��낵�����������B����艮�ł����Ȃɂ��ɜ|����������Ă����B���̂����A�Ђǂ����т������Ă������B
�@�}�[�T�͎����ɂ����͂킸���ɖ{�S�������܂݂���G�r�G�����A�����h������悤�ɂȂ����B�G�r�G���̓T�C�|�b�c�Ƃ��ẮA���l�Ɍւ��悤�Ȑl�ł͂Ȃ��������A����ł��̑�Ȗ����ł͂������B
�@�G�r�G��������ł��A�}�[�T�͈�l�ŐX�ɂ����B�ӂƋC�Â��Ă݂�ƁA�̐l�Ƃ��Ȃ���炵�����Ă����B�ޏ����g�������Ȃ邱�Ƃ�]�̂������B���̐X�ŕ�炷�Ƃ����M�O�������ƂÂ��āA�}�[�T�͂��̉Ƃ𗣂�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@����ɂ��Ă��A�s�v�c�Ȃ̂̓n�t�X�������B�}�[�T�̔������������āA���ʂ��䂸��A���܂ł͍s�����킩��Ȃ��Ƃ��Ă���B������Ƃ����v���Ȃ������B�������A���N�����̘b�ł́A�����̖\�������܂ɂ��N�����Ƃ��Ă���ƌ����B�ǂ����A�X�̉��ɂЂ�����Ō�����Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��悤���B
�@�Ƃ͂����A���ɂ��ǂ��Ă��ޏ����ł��邱�Ƃ͏��Ȃ��B���ʌp���ɔ��������ƂŁA�Ǖ��ɂ����������������Ă������A���܂̍ɑ������������̂������Ƃ��Ƃ͎v���Ȃ������B�{�얂�p�t�Ƃ����Ă�������̖�E�ŁA����Ȍ������̂��ޏ��ɂ͂Ȃ��̂ł���B
�@�{���̂Ƃ���A�Ƃق��ɂ���Ă����̂́A�}�[�T�������������̂��B