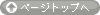「ねじまげ世界の冒険」へようこそ
このページは、ネットで小説を読まれる方用に用意しました。
長編、短編とそろえています。古い作品もあるので、できには目をつぶってやってください。
ねじまげ三部作も、よろしく!
ねじまげ世界の冒険
▼第十部 ねじまげ世界、最後の冒険 後段
○ 章前 二〇二〇年 ――ねじまげ世界
□ 一
薄暗い下水をさまよい、ライトの充電もあやしくなってきた。利菜は疲労困憊しながらも紗英をはげます。もう何十キロと歩いている気がする。何度も幻聴が囁いて、周囲を人の走る気配もあった。闇の中にいてほとんどわるいものに捕らえられていたから、前方に光が濃くなったときは心底ほっとなる。利菜と紗英は新鮮な空気を求めて足を急がせるが、すぐに膝がゆるんでしまった。煙と硝煙の臭い、肉の焦げる臭いが鼻孔を満たして二人は咽せる。丸い出口の向こうで炎が踊り、サイレン音と悲鳴がする。我に返ってみると、ときおりドォンドォンという音が規則正しく響いて、それで水面に波紋が立っているのだった。
腕が揺れている。それで手元をみると、紗英が腕を叩いて何かしゃべっているのだった。利菜はろくに聞かずに首を左右に振った。出口の側を人が走り回るのが、それも火のついた人が走り回るのが見えると、ほとんど思考が停止してしまった。ビスコが先頭にたつ。ランタンを掲げるそぶりをみせたが、すぐに火を消してしまった。
ヒュルヒュルという音がする。
三人はまるで海の底を歩くような足取りで出口に向かった。
下水の縁に立つと、外はすぐに川だった。コンクリートブロックに縦長の筒がカンカンと当たって転がっている。中からこぼれた液体が激しく燃え上がる。焼夷弾だ、と利菜は言った。川面は焼夷弾の直撃を喰らって即死した人や、うつぶせになったまま燃え上がる人であふれかえっている。その隙間を炎を衣服のようにまとった人たちが逃げ回っているのである。甲高い悲鳴が曇天を引き裂くように轟いた。利菜は人油の焦げる臭いに口元を抑える。彼らは声もなく立ち尽くす。ふと足元をみると、三歳ぐらいの子どもが頭に焼夷弾を突き刺して、川辺に腰掛けるようにして亡くなっていた。丈の長い草に腕がひっかかってそれで流れていかないのだ。重油に火がついて、それが流れとともに川下まで運ばれていく。紗英がその炎に向かって、ゲボゲボと吐いた。
エンジン音が轟き、利菜は配管の縁に手を付いて身をのりだす。上空を爆撃機の編隊が飛び、戦闘機のいくつかが地上に銃撃を加えている。そのうちの一機は真上から彼女を目がけるみたいに降ってきて、対岸の道路を射撃し飛び交った。上で逃げ遅れた人たちが機銃を喰らったのか、真っ赤な血液が噴水のように川に降ってきた。利菜は悲鳴を上げて、配管に戻った。
「どうなってるの!?」
今度は紗英の声も耳に聞こえた。
「これって空襲警報だよ……」
紗英と顔を見合わせる。神保町が戦争をしているとしか思えない。
「佳代子たちを助けに行かないと。早くしないとみんな殺されちゃう」
そうしている間にも、地響きは断続的に轟いてくる。神保町が爆撃を受けているのだ。こんな小さな街が焼き討ちにあうなんて信じられない。
「いったいどこと戦争を」
利菜は信じられないという顔で頬をなでた。
「おまえたち!」とビスコが言った。彼の背後には巨大な亀裂が口を開けている。「装置はどこだ! ここはもう駄目だ! 場所を言え!」
紗英が、ゲートだ、あんたが開けたの、と言う。足はもうゲートに向かって進み始めている。利菜は腕をひいて止める。その目を大きく見開いて。瞳の奥では疑惑が渦を巻いていた。ビスコは亀裂の黒煙を身にまといつかせながら、早くしろ、殺されるぞ、と怒鳴り声を上げている。配管の揺れはどんどん大きくなる。爆撃機が爆弾を降らしながら、こちらに近づいているのだろう。けれど、利菜は今そのことに関心がなかった。「あんたが開けたの?」と彼女も訊いた。「あんたがゲートを?」そう言えば、こいつは一人だ。「一人でこの世界に来たの?」
利菜はゲートに向かおうとする紗英を腕で制し、むしろ背後にかばうようにした。
「あんたは誰なの?」
紗英が、「利菜、今はそんな場合じゃ……」
「一人でゲートを開いたとでも言いうつもり?」
「仲間の力を借りたに決まってるだろう。生き残りの神官ならきさまも知っているはずだぞ」
「ペック? ペックのことを言ってるの?」けれど、彼女の疑惑は晴れない。「なんであたしたちの居場所がわかったのよ。偶然この配管に来たなんて言わせないわよ!」
「この馬鹿が! 疑うなら後に……」
川に着弾があり、爆風が水と死体をまき散らし、下水管の入り口まで砕いた。ビスコは亀裂の真下に倒れ込み、利菜と紗英も配管に叩きつけられた。彼女は後頭部をうち、血の海に倒れた。爆弾は次々と落下して川の地形を変えていく。底砂が水とともに噴き上がって、配管にまで押し寄せてくる。
利菜は下水管の奥で、なめ太郎が死体を引き連れ、手を打って喜びながら彼女を指さすのを見た。おまえの思い通りにいくもんか、と彼女は言ったが、鼓膜がばかになって自分の声も聞こえない。無音の中で(が頭の中はわんわんと反響が続いている)、ビスコが紗英をつかまえ、腰を抱えるようにしてゲートにおしこむのが見えた。彼もこめかみから血を流している、瓦礫をのりこえ引き返してくると、彼女の手首をつかまえる。利菜は、あたしたちだけじゃ無理だよ、と言った。仲間を揃えないと、装置はとれっこない。
だけど、ビスコが背中をおすとそうも言っていられない。着弾はしつこく配管を砕き、二人に迫っていたからだ。
天井が崩れて二人の真上に降ってくる。利菜とビスコはタッチの差でゲートに飛び込んだ。
□ 二
目を開けたときには指先しか見えなかった。紗英は泥水の中に倒れて凍えていたのだ。辺りは雹がぱらつき、それが彼女の体にも積もっている。体が冷え切ってもう焦点もあわなかった。立たなきゃだめだ、思考までも凍ったみたいに鈍くなっているが、それでも思った。このまま寝ていたら、おっつけ凍死するのは目に見えている。紗英は体を起こそうと手をついたが、あちこちに走る激痛にきつく目を閉じた。凍えているだけではない。怪我をしているのだ。
紗英はようやっとの思いで体を起こした。女座りをして肘をかかえた。どうやら森の中にいるらしい。梢を避けるようにして雹がおち、紗英の頬に辺り、凍った髪にはりつく。それでようやく思い出した。さきほどまで爆撃を受けていたことに。それとも数日が経っているんだろうか?
「利菜……」
と紗英は力なく呟いた。左右に目をやるが、独りぼっちだ。おまけにおまもりさまにいるらしい。
紗英はゆっくりと右膝をたてる。体は動くもののこわばりきっている。あんな状況で死ななかったのが不思議なぐらいだ。下水から逃げるあの一瞬、利菜とビスコは言い争いをしていたような気がするが、うまく思い出せない。それよりも今は利菜を見つけないと。あの子を見つけて、佳代子や達郎たちを呼び寄せないと。ここはねじまげ世界なのかもしれないが(そうでなければ神保町が空襲を受けるはずもないが)、だったらなおのことあの子たちの協力が必要だ。自分の力だって必要としているはずだ。だから紗英は痛みをこらえて歩き出す。左の足首は変な角度にねじれているが、もう痛みすら感じない。
「ハッ……ハッ……ハッ……」
寒かった。足元では、冷気が白い筋となって流れている。パリパリという音に気がついて下を見ると、地面の泥が凍って固まっているのだ。髪と服にも霜がみっしりとついていた。手足は冷え切り感覚がない。おさそいだ、あたしはおさそいにはまってる、と彼女はとりとめもなく考える。凍傷が脳にまで及んだのか、頭がはたらかない。
寒さと恐怖で歯の根が合わない。カチカチ、カチカチ、カチカチ。ああ、ここは本当におまもりさまだ。
彼女はわるいものに囲まれている。たいまつを持った村人たちがまわりを走っている。それが幻覚なのか、現実なのか、判断がつかない。村人の中には死んだはずの子どもたちがまざっている。彼らは、きっと、三郎とまさを捕まえに行くのだろう。
「三郎……」と彼女は言った。「助けて……」
紗英はとうとう立ち止まる。目の前に、グリズリーがいた。カナダで一度だけ死体を見たことがある。176センチの紗英より、ずっと背が高い。
「うそだ……」と彼女は言った。舌を何度もかんだ。「あんたがいるはずないよ……ここは日本じゃないか」
紗英は自分がみじめで泣いた。涙は、頬についた氷をとかす。涙の筋が白くなる。唇は真紫だ。子どものころさんざんプールにつかったときだって、こんな色はなかった。こいつにやられなくても、あたしは凍死しちゃうのかな、と紗英は考える。勢いこんで戻ったわりに、なんともあっけない幕切れだ。紗英は自嘲したくなる。子どももいなくて、恋人とも喧嘩別れ。職場の仲間にだって行き先を告げぬまま、こうして見知らぬ世界で死のうとしている。なんだか情けなくてまた涙が出た。華やかなフライトアテンダントとして世界中を飛び回っていた時が、遠い過去のものとなった。もう手足が、文字通り凍り付いてしまった。
そのとき、紗英は死を覚悟して顔を上げたのだが、目の前にいたのはグリズリーではなくビスコだった。紗英は安堵とばかばかしさの両方で大粒の涙をこぼした。ビスコをグリズリーと見間違えるなんて、いったいどういう了見だろう?
「ああ、ビスコ、よかった……」と彼女は言った。「あたし、一人ぼっちで、利菜もいなくて、それに寒いよ……」
ビスコはゆっくりと手をさしのべ、彼女を抱いた。ああ、暖かい。誰かに抱きしめられることがこんなに安堵するものだったとは、今の今まで知らなかった。紗英は、ビスコの胸に頭をあずける。
そのとき、背筋になにかが入ってきた。
「ビスコ……」と彼女は言った。もう息も絶え絶えだ。「ビスコ、助けて……」
「ここからは、あの女とおれとの勝負だ」とビスコは言った。「おまえは要らない」
背中に、また押し込まれた。深く、深く。肉を裂かれ、神経をたたれ、その切っ先は内臓まで達した。湯気のたつ腸をぶつりぶつりと断っていった。紗英は身をのけぞらし、はっと息を吸う。熱いものが背筋を伝う。血だった。それは瞬く間にシャツを濡らし、ジーパンを紺に染め抜く。ビスコは背中に突き立てたナイフをゆっくりと回す。紗英は新たな激痛に息を吐き出す。ごりごり。ごりごり。という感覚に、足を突っ張った。刃が脊椎を削っているのだ。
視界が眩んだ。体が痙攣し、声も発せない。
「ビスコ……何を……」
「おれは装置を手に入れる」
耳元で、愛を囁くように、いった。
ビスコがナイフを引き抜くと、紗英は膝を落とす。口端から、血が溢れだした。
利菜……
彼女は、旧友に、念を送ろうとする。気をつけて、と。あんただけは、無事に帰ってくれと伝えようとするが、彼女はあまりにも血を失いすぎて、もう思考をまとめることができない。
ビスコが体を離しても、紗英はしばらく膝をついたままの姿勢でいた。ぐるりを囲んだのは、死んだ人たち。ああ、これであたしも仲間入りかと倒れたときには、目の焦点すらおぼつかなくなり、声を立てることもできなかった。彼女は泥の中に鮮血を垂らし、命を無くしていったのだった。
□ 三
利菜はゲートを潜りながら、どうにか行き先を変えるよう念じるしかなかった。鏡の場所に行くのはまずい。ビスコをどうにか引き離さないと……
利菜は苔むした岩の上に落ち、肋を岩の縁にしたたか打ちつける。一瞬呼吸を失いながらも、どうにか顔を上げ、
「紗英?」
と言った。
ところが、そこには懐かしくもおぞましいおまもりさまの景色が広がるばかり。長身の紗英の姿はどこにもない。
利菜は寒さに震えながら、二の腕を抱える。薄着のシャツに冷気がしみた。辺りは霧が立ちこめている。空襲の音は聞こえなくなっていたが、鼓膜には悲鳴の残響があった。利菜は吐き気をこらえて、震える唇をかみしめた。
死体のように真紫な唇。闇夜に白い服が浮かぶ。ビスコもいない。あるのは死体ばかりである。古木からは首吊り死体が垂れ下がり、霧に隠れてよく見えないが、まるで蓑虫の集団のように何百何千と連なっている。軍服や昔よくあった国民服を着ている者もある。うちのいくつかには、非国民、とスプレーで大書されたものもあった。ラジオの音がどこからかする。気泡の弾けるようなパチパチという音とともに、第三帝国がシナを突き進み、関東軍と本格的な戦争を開始したと伝えている。
「何を言ってるの?」
利菜は腹立たしさと寒さに根負けしてしゃがみこむ。辺りはいつのまにやら夜になり、樹間をついて落ちる月光が見える。利菜はあのときと同じように一人になり、寒さに震えて肘を抱えながら、死体のすきまを歩きだした。岩に手をついて小休止をする。孤独は凍えと同じように彼女の心を震わせる。そして、彼女は紗英が死んだんだと感じている。背を岩にあずけ、涙を流した。
なんで気づかなかったんだろう……?
ビスコは仲間とゲートを開いたというが、だとしたら一人でこの世界にくるのは妙である。彼の口ぶりからすると、彼の妻はサウロンに殺されたはずだった。生き残ったのはなぜだ? それに大鏡からこの世界に来たのなら、出口はこのおまもりさまだったはずだ。彼が無事山を抜けて、神保町に到達したのは実に不思議だ。下水道にいた利菜と紗英に偶然行き当たったのも実に不思議なことだった。
彼女は震える唇でつぶやいた。「サウロンだ……あいつはサウロンなんだ……」
それならば、全てに納得がいく。利菜は悔しくて唇を噛み、一人ぼっちが怖くて涙した。佳代子も達郎も自分の所にはこれないだろう。この世界にあの子たちがいたとしても、あの空襲で死んだかもしれない。
利菜は死体たちに聞こえないよう、そっと嗚咽を漏らす。こんな森の奥深くで、ひっそりと死にたくない。彼女は生きているのが実に辛かったのだが、まだ人生を終わりにしたくはなかった。家族がいる。秀男と純子が待っている。だけど、もう……
絶望が深くなるとともに、霧はいよいよ濃くなった。ミルクの海にいるようだ。森は死体のように生気がない。一寸先も見えないのに、彼女が吐く息の向こうで、何かがうごめいた。複数の影だった。利菜はあれは死体なんだと気がつく。
あいつら、とうとう起き上がったんだ。
彼女はガタガタと震えながら、巡礼者のように首を垂れて歩く。死者に見つからないように、静かに足を踏み出すが、起き上がった連中は、心を持ち合わせていないらしい。むしろ彼女が怯えるのを喜んでいる様子だ。背中に貼りつかれて、ひっと悲鳴をあげる。行く手を遮られて左を向くと、そちらにも死者たちがいる。彼女は取り囲まれて、一歩も進めなくなる。
笑い声がする。悲鳴が上がる。それで霧が渦を巻いた。彼女の視界も回り出す。
利菜は最初のうち、恐ろしくて泣いていたのだが、そのうち癇癪を起こして怒鳴り声を上げた。
「用があるなら言いなよ!」
その途端、棒が霧を裂いて降ってきて、彼女の額を殴打した、背中を打たれ、利菜はよろめく、頬骨に一撃を喰らってたたらを踏む。彼らが振るっているのは棒ではなく千切れた手足だった。死者たちは四方八方から彼女をめった打ちにした。どす黒い血が、シャツにへばりつく。固い骨がぶつかりあって、意識が遠くなる。突き飛ばされ、小突かれ、ついに地面に倒れてしまった。それでも、死者たちは攻撃の手をゆるめない。利菜は、ほとんど死にかけになりながら、「三郎、三郎……」とつぶやく。
三郎、助けて
誰かが、手を握った。攻撃の手がゆるんだ。顔を上げると、手を握っているのは子どもで、それは瀬田英二だった。利菜は小学五年生に戻って、「瀬田くん……」と呼びかけた。
唾を飲む。その手を振り払えない。彼のまわりには死んだ子どもたちが大勢いる。その子たちが、死者を遠ざけていた。
彼らは月光を受けて、白い顔を光らせる。
瀬田英二のとなりには、作業服を着た老人がいた。
「国村さん……」と呟く。「いやだよ、迎えになんて来ないでよ……」
利菜はさめざめと泣きだす。体中が痛んだ。
死にたくない。まだ死にたくない。
英二たちが、彼女の腕を引っ張る。利菜は泣き顔をあげた。何かをうながしているようだったが、歩くなんてとても無理だ。骨が折れていないのが不思議である。
瀬田英二は、彼女の様子には委細関心がないらしい。起き上がる気がないのをみてとると、引きずりはじめた。
「歩く、歩くよ」
足を突っ張り、どうにか立った。死者とともに、霧の中を歩いた。
□ 四
何時間も経ったような気がした。利菜は霧の中で、たいまつを持ち歩く村人をみた。小道を駆ける、まさを見た。そして、二十五年前の自分たち、佳代子や達郎、紗英を見た。彼女の身は、過去と現在を行き来する。景色は移り変わり、いつしか霧は晴れた。利菜は山の小道を登り出す。楠の根につまずき転ぶ。
顔を上げると、目の前に、墓石があった。
利菜は呆然とその墓石を見つめた。三角錐のささくれだった石には、苔がみっしりとついている。献花もなく、詣でる人もないというのに、長い月日、装置を守ってきたのだ。左を向くと、あのお堂がある。いつのまにやら夜は明けていて、頭上には青空があり、木漏れ日が頬を差していた。もう、おまもりさまにはいないのだ。
涙がとめどなくこぼれた。あの子たちは、迎えなんかではなかったのだ。
まわりには誰もいなくなっていたが、彼女は小道に向かって頭をさげ、ありがとう、ありがとう、と何度もいった。傍らの墓石を何度も撫でた。
「三郎、ごめんね……」
と彼女は言った。小さな墓石を、そっとどかした。自分もあのときの三郎やまさと同じ年になったんだなあ、とぼんやり思った。佳代子たちとここを掘ったときのことが、昨日のことのように思い起こされる。
利菜はまた掘り始めた。最初のうちは木ぎれをつかっていたが、そのうち木ぎれを放り出して指を突き立てる。二十五年間で固まった土が、指の腹を食い破る。それでも夢中で掘り続けた。感謝の涙がわいて、頬を拭う。泥がつく。どんなに負けがこんだところで、あきらめないかぎり、終わりはないんだな、と、彼女はそんなことを漠然と考える。まだ一人ぼっちになったわけじゃない。子どもたちがそんなことを伝えてくれた気がする。
そのうち骨が見えた。あのときと同じように肋骨がでた。そこからは慎重に掘り進めた。指の骨が見える。そっと組まれた指の下に、装置はあった。
「三郎……」と彼女は言う。「まささん、死んじゃったんだって」泣けてきた。「あんたと約束したけど、今度は守れなかったよ。もう死んじゃったから、装置を使っても、どうにもなんない」
彼女はさめざめと泣いていたが、そのうち、どこからともなく声が聞こえた。三郎の声だ。彼女は耳を澄ませる。
そうして、彼女はその声に注意を取られていたから、小道を上ってきた男に気づかなかった。そいつは血塗られた手を隠して、女に忍び寄る。女は放心したように座りこんでいる。彼は女が装置を手にしていることを確認した。腰のナイフに指を走らせたとき、女がふりむいた。
「ビスコ……」
ビスコが二歩踏み出す。利菜は後に下がり、自分で掘った穴に落ちかかる。
「止まれ!」と彼女は言った。「あたしが装置を持ってるんだよ! それ以上、近づくんじゃない!」
「どうした?」
「紗英はどこ。あの子になにしたの」
「やつはもう来ない」
「殺したのね」
利菜が装置を掲げるのと、ビスコが走り寄るのは同時だった。
「吹き飛べ!」
彼女は怒りにまかせて装置に念じたのだが、何も起こらなかった。ビスコは滑るように滑らかな動きで、懐に飛びこんでくる。彼女を抱くようにして、脇腹に刃を突き刺した。その鋭利な刃は紗英の血をふくみながらやすやすと彼女の肉を斬り裂いた。彼女は何かを言おうとするが、舌が硬直して動かない。ひゅっと息を吐く、力が抜ける。ビスコの肩に身を預けた。
「残念だ。ようやく会ったきさまが、こんな腑抜けになっていようとはな」
利菜は罵声を上げようとしたが、肉を裂く痛みにかすれた息しか出てこない。
「あのときは子どもと思って油断した。今度は」
サウロンがナイフを引き抜く。利菜は丸まったまま後ろに転げた。押さえた指の隙間から血が溢れてくる。激痛とともに、命の水が抜けていく。さらに丸まりながらサウロンを見上げる。
サウロンが、脇に立った。「手加減無用」
彼女は這いずり、墓を越えて楠に身を預けた。脇腹を抑える手が、赤く染まっている。もうこれまでだと思った。
「もう、もう皇帝はいないじゃない! あいつは死んだんだ!」
「黙れ!」
「あんたはもうサウロンじゃない……」と言った。「本当は、皇帝が憎かったはずなのに、あいつを倒したかったはずでしょう? あいつが未来を支配したから。なのに、今のあんたがしようとしてることはなんなの? いったい、なんのために……」言葉が出なかった。「皇帝が過去を支配したみたいに、あたしたち、未来を変えられる」
「お笑いぐさだな。おまえが変えて見せるというのか」
「そうじゃない、そんなの間違ってる」と首を振る。「あんたは全部消えろって言ってる。でも、大事な物が残ってないんなら、世界を変える意味なんてない」
「このまま世界を続けたところで、また同じことを繰り返すだけだ!」
サウロンが近づく。
利菜は急に腹が立った。「理想国家なんてあるわけない! 誰だって欠点はあるんだよ! それでいいじゃない!」
サウロンが利菜の髪をつかむ。顎が上がり、さらなる激痛が神経を引き裂く。
「欠点ですむか! よく見ろ世界を!」
「あたしは生きてるんだ!」目を閉じたまま、叫んだ。「娘や旦那だって生きてるんだ! みんな努力してる! それでいいじゃないか! あんたなんかに否定されたくない!」
「その喉かっさばいて黙らせてやろうか!」
「あんたが正しいんなら、あたしを説得してごらんよ! あたしにはみんな大事なんだ!」
「装置を寄越せ!」
「駄目だ……!」
ナイフを横に振るおうとしたとき、三郎の骨が、土を食い破って起き上がり、サウロンの背中に取り憑いた。サウロンの手が頭を離れる、利菜は楠の根もとに倒れ込んだ。
「三郎!」脇腹を抑え、逃れようとする。「そいつをやっつけて! 紗英のかたきをとって!」
三郎は、サウロンをはがいじめにする。骨には、わずかな皮膚と、布の切れ端がまとわりつくだけ。なのに、すごい力だ。あのサウロンが手こずっている。
利菜は二人の元を離れ、よろめく足でお堂を目指した。激痛に喘いだ。出血がひどい。ベルトの上に溜まっている。階段をのぼるが、腐った床に足を取られ、倒れ込んだ。
仰向けになると、サウロンが骨の固まりとまだ格闘を続けている。茶けた骨のかけらが激しく散った。もうあいつを抑えられそうにない。
悔しくて涙が出た。またあいつに欺かれたのだ。そのせいで、大切な人が死んだ。東京で出会った紗英、決着をつけると、意気ごんだ紗英の姿。中学時代の彼女が脳裏をよぎる。
胸は怒りに燃えていたが、血液とともに、力が抜けていく。体を床に預ける、重だるい疲労感が全身をつつむ。血が止まらない。体は休みたがっているが、頭では、装置の始末を考えていた。
少し意識が遠くなる。
首を振ると、崩れた屋根の向こうに、昔出会った少年が見えた。
「ヒッピ、なんで死んじゃったの?」と訊いた。「あたしだけじゃ、あいつを止められない……」
うつぶせになる。涙と鼻水がこぼれ、床に落ちた。顔を上げると、部屋の奥に銅の鏡が見えた。目標を見つけると、少し力が沸いたのだった。
ありがたい
痺れた手を伸ばし、肘を使って這い進んだ。まわりでは、彼女の数々の友人たちが、がんばれ、がんばれと声をかけていた。そんな気がした。もう一歩。もう一歩。
角材の折れたささくれが傷口にふれて、彼女は、ギャア! とわめいた。
ちくしょう
ふりむくと、彼女の通った後には、べったりと血痕が伸びている。
ああ、こんなところで死ぬんだ。
意識を失いかける、頭をふって正気を保つ。あいつに渡すわけにはいかないのだ。彼女は装置を握りしめると、もう一度鏡を目指した。二十五年前に、寛太が立てかけたのと寸分たがわない場所にある。
彼女は鏡を膝に抱くと、柱にもたれた。目を閉じる。娘や夫の顔がまぶたに浮かぶ。もう会えないような気がする。ちゃんとお別れをしてきたか、そんなくだらないことが妙に気にかかる。
屋根のないお堂には、太陽の光が燦々と降っていた。暖かいことがありがたい。彼女は血を失って震えていたからだ。
「順子……秀ちゃん……ごめん、ごめんね」
鏡をみおろす。薄く曇った鏡面には、泣き顔の自分がうつっている。失った記憶と、その後の人生とが、脳裏を激しく駆け巡った。今日一日のことが、まるで夢のようだった。指で装置をつまむと、血に濡れて光っていた。文様が変わるたびにその筋を血が流れる。まるで、生き血を吸っているみたいだ。
気配を感じて脇を向くと、少年のヒッピが隣で片膝をついていた。後はあんたに任せたよ、と彼女は言った。これで全てが終わりなら、何かを成し遂げたかった。痛む体を起こし、鏡を壁にたてかける。両手をつき、鏡に向かっておじぎをするように首を垂れた。祈りをささげるような気持ちだった。
「念じ、念じなきゃ……」
サウロンの言葉が頭に響く。おまえでは装置をあつかえない――
「そんなことない。あのときはできたんだから」と否定する。「ひらけ……ひらけ」
サウロンが三郎のすきをついて、表から念動力を放ってきた。お堂の木材が吹き飛んで、側頭部を一撃される。利菜は横様に倒れ、
「ちくしょう、あのやろう……」
サウロンの一撃は、彼女の意識を断ち切るに及ばず、逆に闘争心をかきたてられる。けれど、ゲートが開かない。
どうやったんだ? あのときは、どうやったんだ?
リラックスだ、リラックスしなきゃだめだ。
朽ち果てたお堂は、屋根の残骸が散乱して、サウロンの視界から彼女の姿を遮った。利菜はエビエラの教えを思い出す。呼吸を深め、痛みを遮断しようとつとめる。傷口は悪いことに腹部にある。エビエラに習ったことを、マーサに教わったことを、今一度とりもどそうとする。装置を胸に当て、次元の歪みを捉えにかかった。
開け……
利菜は目を閉じていたが、周囲の出来事を観ることができた。きっと乗っ取られる前のビスコは、教えられた儀式を繰り返していたのだ。鏡はいまだにもう一つの世界とつながっている。
頬に風を感じると、重力が二倍になったかのように、体が床へと沈みこむ。鏡の中央に黒点が浮かび、渦を巻きながらその身を広げた。
利菜は目を開いたが、ゲートが小さい。大人の利菜は通れそうにない。だが、これ以上は無理だ。もう限界だった。頭痛がし、鼻血も吹き出している。二十五年のつけが、いちどきに吹き出たみたいだ。
出口、出口をどうするのか?
だが、もう迷っている暇はない。後ろで足音がすると、装置を指で押し入れるようにして、渦へと投げた。
「ヒッピ、お願い……」
彼女はついに気を失う。サウロンが駆けつけ、その体を裏返す。
「きさま!!」
女が装置を持っていないことを確認すると、サウロンは怒りにたけって、力任せに頭を蹴り飛ばす。
彼はゲートを広げると、装置を追って、渦へと飛びこんだ。
お堂では、意識をなくした利菜が、昏々と眠り続けた。
◆第二十二章 最初の対決
○ ジノビリ歴三年 ――牢獄の攻防
□ 五
ヒッピは牢獄に転がるものは何でも掻き集めさせた。通路の正面に簡易のバリケードを作り、その裏に這いこんで、隙間から銃口を突きだしたのだ。少年達はマーサを一番後手に回し、さながらクイーンを守る兵士のように散開していた。トゥルーシャドウがその中央から身を乗り出し、「まだ撃つな。撃つなよ」
カンテラをバリケードの樽の上に置く、その光は大振りな剣をテラテラと照らす。ヒッピはわかってる、と答えながら仲間と目線をかわす。どの顔も強張って、戦いの緊張に耐えている。
ほら穴の奥が明るくなる。ダンカン人の低い声色が大きくなってきた。ヒッピは今度こそ、利菜は間に合わないかもしれない、と思った。彼女が来たときに対面するのは、自分たちの死体かもしれない。
「トゥルーシャドウ、ぼくらの弾丸は四発しかない」と告げると、イニシエの男はひどく驚いた顔で彼を見おろした。とすると、この男なりに子どもたちを頼りにしていたわけである。
ダンカン人たちは彼らの言語で怒鳴り上げている。ヒッピもダンカン人の言葉まではわからない。意味不明の言葉の応酬に、少年たちの恐怖はいよいよ深まった。ヒッピは苛立って吐き捨てた。「いったい何の算段だ」
「きけ、ダンカン人!」とトゥルーシャドウは呼ばわる。「私はナバホもスーの若長、トゥルーシャドウである! ここには、古き人、マーサもおられる! あなた方は古き約定に従って、共にサイポッツの軍隊と戦うと誓ったはずだ! なれど、エホバの都において、ダンカン人は我々を裏切った! 今ここにいたっても、あなた方は我々を害しようとしている! いずれも申し開きがあるならば、ここにこられて開陳されたい!」
ダンカン人から声の応酬があった。今度はヒッピにも彼らの言葉がわかった。彼らはサイポッツの公用語を使っている。ナバホ族とダンカン人は言語がちがうからだ。少年たちにとってイニシエの民の古めかしいやりとりは奇異にうつった。
マーサが牢獄にいると聞いて、ダンカン人に動揺が広がった。
「スーの若長よ! 今一度確かめたい! 古き人、マーサとハフスは存命であるか!」
「いかにも、お二方とも健在である!」
ヒッピは驚いてトゥルーシャドウを見上げた。ハフスがすでに亡くなっていると知ったら、ダンカン人たちはどう出るだろう?
「我々はトレイスに国王を奪われた! 残念ながら、お手前方に力を貸すことはできない!」
「国王だと?」とマーサが目を開いた。
「ダンカン人の王様がつかまったってことか?」とヒッピはペックに言った。
「サウロンに? まさか、どうやって?」とペックは言ったが、この地下牢はダンカン人の都に通じているのだから、サウロンなら不意をついての誘拐ぐらい何でもない。
「ダンカン人の王が、王都にいたはずがない。いったいどこに幽閉するんだい」とマーサが補足した。ヒッピも得心して、「城にいたのなら、どこからか秘密はもれたはずだ。だけど、誰も知らなかった」と顔をしかめる。「フロイトも国王のことは言わなかった」
「じゃあ、もう殺されてるのか?」
パーシバルが問うと、その声の大きさに、パダルとモタが口をふさいだ。
ヒッピは銃を持ち上げる。必殺の弾丸が一発だけとはなんとも心許ない状況だ。
「あいつらまだ国王が生きてると思っているんだ。トゥルーシャドウ、この際だから、あいつらをだましてしまおう」
トゥルーシャドウは迷うようにヒッピを見おろす。ヒッピはこの勇敢なナバホ族が戸惑うのをみて驚いた。けれど、無理もない。一度は戦うと意気込んだものの彼が引き連れているのは、年端もいかぬ子どもばかりである。
「だってしかたないじゃないか。サウロンはすぐにここに来るかもしれない。あいつらに協力させるしかないよ」
「おまえたち」とマーサが言った。その呻吟に満ちた声に、話に夢中になっていた二人もふりむいた。マーサは脂汗をにじませて右を見ている。「まずいことになったよ」
ヒッピはふりむいた、パーシバルたちも銃を向けた。自分たちが出てきたのと同じ場所に、再びゲートが口を開けていたからだ。悲鳴のような音がして、空間がメキメキと裂けていく。最初赤子のさえずりのようにわずかだった裂け目は、女の絶叫のごとく大きく口を開け始めた。ヒッピは思わずバリケードの裏で立ち上がる、サウロンだ、もう誰も間に合わなかった。ぼくらだけで戦うしかない。
ゲートが空気を飲みこみ、地下牢に風が沸き起こっている。ヒッピは恐怖に目を見開き、銃を胸元に引き寄せてその瞬間を待ちかまえた。ペックがちらりと彼をみる。出てくるのは、利菜か? サウロンか?
今度のゲートはいつもと様子がちがうようだった。単なる亀裂であり、その奥では七色の光がうごめいている。その縁を指がつかんで、小汚い頭が覗いた。ヒッピは驚いた。利菜の言っていたなめ太郎だ。その顔を見た途端、モタは慌てて発砲してしまった。彼の弾はむなしく天井に穴をうがった。
「ダンカン人!」とトゥルーシャドウは言った。「協力しろ! サウロンがここにくる! 奴を倒せば国王を救うことは可能なはずだ! イニシエの約定に従い、ともに戦え!」
トゥルーシャドウがゲートの目前に躍り出る。ヒッピは、せまりくる吐き気をこらえた。自分のものではない痛覚を感じた。ちがうぞ、あれは利菜のわるいものじゃないかと思った。時間的には無理がありすぎる、利菜が来るとはむしがよすぎる。けれど、こちらとあちらの世界では時間の流れに狂いが生じるのかもしれない。
なめ太郎は顔だけを亀裂から覗かせ、犬のように笑っている。
ヒッピはその醜い顔を見るともなしに眺めながら、ああ、利菜だ、あいつが彼女のグループをつれてやってくる、とつぶやく。ペックも、今こそ、ゲートの向こうから来るのが誰かを理解した。
「トゥルーシャドウ、待ってくれ」ヒッピはバリケードを出てナバホの若長をつかまえる。「ゲートをつかっているのは利菜だ。サウロンじゃない」
「利菜だと?」マーサが言った。「馬鹿をお言いでないよ。今戻したばかりじゃないか」
「でもまちがいないんだ」ヒッピはその胸に利菜とのつながりが復活するのを感じた。装置をもってる……と彼は驚きと共につぶやいた。マーサが、まさか、と言うのが聞こえた。「くそ、サウロンの奴も感じる。きっと回廊まで来てるんだ。あいつも来るぞ!」
通路側から声がした。「トゥルーシャドウ、わたしはティムブロッサムだ! これから部下とともに、そちらに行く! 攻撃するな!」
地下牢のあちこちから黒々とした瘴気が噴き出してきた。なめ太郎はいつのまにか地下牢にいて、瘴気の側に寄っては、彼の兵隊を呼び出している。
ヒッピはまずいことになったぞ、と仲間を顧みる。利菜は戻ったが、状況が好転したとは言えないようだ。利菜が装置をもって戻ったことで、わるいものも戻ってきたからだ。あの装置は悪影響ばかり与えると彼は考える。けれど、それは正確ではなくて、悪影響を受けているのはあの装置の方かもしれなかった。
ヒッピは通路を見たが、すでに地下牢は次元の狭間に閉じこめられていて、ダンカン人の姿は見えなくなっていた。その出口では、黒気がとぐろをまくばかり。彼らは脱獄不可能の牢獄に閉じこめられた孤児となった。
この場所には自分たちの他に誰もいないけれども(わるいものを除けばだが)、けれど、ヒッピは第三者の存在を感じていた。そいつは彼らの対決を望んでいる。そして、他者の介入をこばんでいるのだ。
□ 六
三郎の加護がなくなっていく……
同時に復活したのはヒッピとのつながりだった。利菜はゲートの中で、別れた仲間たちがどうなったのかを知っていく、彼らがどんな窮地に陥っているのかもふくめてだった。同時に彼女にはわかっていた。自分が何千という名前を持ち、何千という顔を持つあの方と、あの男との対決に向かっていることを。彼女の頭はその経過がどうなるのかも、その結果がどうなるのかも想像できなかった。むしろ考えてはいけないような気がしていたのだ。自分たちは大きな流れの中にいたし(ゲートの中はまさしくそうだ)、もうそのことに身を任せる他はない。
利菜は渦の瘴気を身にまといながら、石畳に降り立つ。彼女の正面には毛むくじゃらの大男が不思議とも言える表情をして、彼女を見おろしていた。当惑と感動をないまぜにした顔をしていたのだ。「トゥルーシャドウ」と彼女は言った。口元にかかった髪を払ったとき、汚く伸びた爪がその小さな肩をつかんだ。ふりむくまでもなく、なめ太郎だとわかった。
トゥルーシャドウは無言でそいつの顔面を一撃した。なめ太郎は顔面に大剣をくらったけれど(顔面がひしゃげてひっくり返ったけれど)、こりずにまた立ち上がった。
「そいつを寄越せよ! 寄越せよ!」
と彼は言った。そうしてみると、彼は子どもの集合体のようにも見える。ひどく尊大でゆがんだ自我の固まりみたいだ。
「黙ってて」と利菜は静かに言った。目尻には涙が浮かんでいたが、ひどく落ち着いてもいた。「おまえなんかの出る幕じゃない」
ヒッピたちは瞠目した。次元の亀裂から利菜に続いて出てきた佳代子たちも。なめ太郎は黙って佇立し、居住まいを正したからだ。
達郎たちは無言でヒッピたちを見た。ヒッピたちもまた無言で見返した。不思議なことだった。達郎達もヒッピ達も出会ったのはこれが最初であるというのに、互いをよく知っている。幼い頃から共に育った義理の兄弟であり、友人であるかのように。利菜は全ての歯車がまわりきり、カチリと停止する音を聞いた気になった。ヒッピの言うとおりだ。ここにいるメンバーは確かに何かを成し遂げるためのグループで、そうして一夏つづいた狂想曲も、ついに終幕を迎えようとしている。二つの力がぶつかりあい、全てがここにいるメンバーに委ねられたのだ。
装置の到来と共に、次元の狭間の外、ヒッピの世界も利菜の世界でも――あるいは周辺にある全ての世界で嵐が巻き起こった。嵐が巻き起こしたものは、ある意味で静寂だった。人々は自然の猛威には勝てず、あるいは身を隠し、あるいはただただ身を縮めて、嵐の過ぎ去るのを待っている。でも……と彼女は思う。
あたし達は過ぎ去るのを待つだけじゃない。特大の嵐を呼んだあの男をどうにかしなきゃいけない――
ことによると、彼女自身がどうにかしなければならないのだが。そうした世界の重みもついに彼女をぺちゃんこには出来なかった。彼女はただ黙って装置をとりだし、それを仲間達に掲げて見せたからだ。
再会の喜びも祝いの言葉もなかった。子どもたちは何かの儀式を行うように装置を取り囲んでそれを眺め、互いの意思を確認し合った。利菜がうなずくと、メンバーたちもうなずいた。まるで一つの意思で動くクローンみたいに、顎の先端までピタリと動きが揃っていた。
そして、彼女の意思は全員に浸透し、重苦しい重圧と結束になったのだった。自分たちがこの瞬間だけはひどく偉大になった気がした。歴史上の異人になった気分。そんな気分は一瞬で過ぎ去ったのだけれど、心を支えるのには十分だった。やろう。今度はヒッピが無言で頷いた。利菜が頷き返すと、グループの腹は決まった。そうしてグループは、これまで鍵を握り続けた重要人物、このときのためだけに生き続けてきた古い女をその場に迎えた。メンバーが左右に開いて道をあけ、それで利菜とマーサは正面から向き合うこととなった。まささんだ、と佳代子が心の内で発する声が利菜には聞こえた。何百年もの長い旅を終えてきたメンバーには感慨深い思いだった。マーサは利菜に近づき装置を取った(このとき、なめ太郎たち――わるいものはどんどん数を増している。装置が世界の全てを引き寄せているみたいだ――は憎しむように牙を剥き、やがてそのことを恥じらうように歯を引っ込め口を閉じる)。ふいに風が――地下牢は運動場ほどの大きさになっており、佳代子が見上げると天井すら見えなくなっていた。ゲートもカンテラを置いたバリケードもひどく遠い、みんな闇の中で浮いて居るみたいだ――雨を交えて吹きつけてき、二人の女と仲間達の体を打った。
利菜が何かを言わなくても、マーサは大体のことを把握しているようだった。「師匠がこれをおまえに?」と彼女は言った。利菜はうなずく。マーサは悲しげで、それでいて決意に満ちた顔を嵐の中に立てていた。雨風はいよいよひどく彼女を打った。マーサはその顔を子どもたちに向けた。
「みなそばにおいで。心を一つに合わせるんだよ。おまえ達にはできるはずだ。心を合わせて、あの男と戦おう」
子どもたちはそうした。トゥルーシャドウも今や膝を折り、けれど武器だけは携えてこの最後の時を見守った。
「装置に念を送るのはあたしと利菜! みんなはあたしたちに心を合わせろ! 同じことを念じるんだよ!」
マーサが装置に指を置いた瞬間、ゲートはぐんぐんとふくれ上がり、天地を貫く巨大な門となった。その内幕は、モザイク画のようにも苦悶する人々のようにも見えたのだが、やがて扉が開くようにして、一人の男がコールタールのような、おどろおどろしい液体を身に垂らしながら姿を現し、ゲートは急に萎んでしまった。それは力が拡散したようにもその男に収束したようにも見えた。サウロンは銀髪をたなびかせ、雨の中で沈黙している。内心こそしれなかったが、その表情は実に静かなものだった。
「時間を稼ぐ! あの男をどうにかしろ!」
とトゥルーシャドウが言った。イニシエの種族が駆け出すのと、サウロンが腕を上げるのは同時だった。彼はひどい老人であったのに、ひどく若々しくも見えた。空間が波打って一同を襲い、トゥルーシャドウはその場にくずおれ、子どもたちはスクラムを組むようにしてこれに耐えた。
「きさまら」とサウロンは言った。このような対決を幾度も繰り返してきた男はいやに落ち着き、いやに高ぶってもいた。「装置を持っているな。渡して貰おうか。それはきさまらには過ぎたる物だ!!」
声はぐんぐん轟いて、地響きとなり、振動の津波となって子どもたちを打った(なめ太郎達も驚愕に口を開けてこれを受けた)。トゥルーシャドウは地を突き飛ばすようにして跳ね起きサウロンの元に向かう。サウロンはこの男が見えぬかのようにマーサ達を見据え、滑らかな足取りで真っ直ぐに歩き出した。
サイポッツとちがって、トゥルーシャドウは真っ暗闇でもある程度ものが見えた。トゥルーシャドウは音もたてずに、剣を振り上げる。じわじわとサウロンに近づく。死んだ仲間の姿が浮かんでは消えた。故郷の情景も。興奮と恐怖の極地の中で、彼は気息を整える。サウロンがくる。もう少しで刃が届く。トゥルーシャドウは、必殺の瞬間を待ちかまえる。
死ね!
真っ向から切り下げた瞬間に、サウロンの右腕が猛然と跳ね上がり、彼の右肘にふれた。肉の裂ける音がして、前腕が吹き飛び血がほとばしる。トゥルーシャドウは残った腕で剣を探し求めたが、サウロンの正拳が胸に叩き込まれる。トゥルーシャドウは内臓を吐き出すような苦悶の声を上げ、その場にどうと倒れてしまった。ヒッピ達が悲鳴のような声を上げて、彼の名を呼んだ。頑健なナバホ族が一撃で倒れるなど考えられぬことだった。
トゥルーシャドウは口元から大量の血を吐きながら頭をもたげた。胸骨を中心に肋骨の骨が軒並み砕け散っていた。不屈の精神を持った男も、これほどの怪我を負っては動くことは出来ない。それでもトゥルーシャドウはサウロンの右足に向かって手を伸ばしたが、男はマーサ達のもとに向かい彼の元から離れていく。
□ 七
あいつが来る……
胸におびえが走った。彼女は装置を手にしている。そいつをはさんでマーサと手を握りあっていた。子どもたちはこれが最後と円陣を組み、いつもより大きな環を作っている。
二つの世界のグループは、今や力を合わせてこの最後の男に立ち向かおうとしていたが、心には恐怖が起こり、目と耳は困惑で鳴動していた。最後の男――そうあいつは亡霊のような世界からやってきた最後の生き残りにして、唯一の男だった。そいつが亡霊の世界のために、亡霊となった皇帝に今もおびえて、この世界を壊そうとしている。利菜もその隣に立つヒッピも、自分たちのなすべきことに戸惑った。
これはあたしたちがやることなの? みんな子どもなのに?
彼らは無言で互いを見やる。十二の視界が環の中央に集まる。いくら心をつないで一つに出来るとは言え、そもそもが生身の人間なのである。
利菜は顔を滝のように流れる雨の中で目を見開いている。
サウロンが来る! 何かを念じないと! 利菜はふりむくが、雨で煙って何も見えない。サウロンを閉じこめようにも、ここはもはや牢獄ともいえなかった。
サウロンの起こした嵐はもはや竜巻の域に達して子どもたちの足を地面からひっぺがそうとしている。みんながそのチカラに耐えられたのは、利菜が体が重くなり地面にめりこむよう装置に念じていたからだ。
ヒッピが心の内で囁く。サウロンを気絶させるんだ……。達郎が意外なことを聞いたといった表情で見返す。その顔は、殺さない程度にダメージを与えて、あいつを縛り上げる? そんな器用なことできるもんか、と言っていた。
「みな、覚悟をし」とマーサ。これは声に出して言っている。
「そうだ、もうやれるのはおれたちしかいない。みんなの仇をとろう!」
とヒッピが言った。黙りこくっているより、大声を出した方がましだ。みんな縮こまった体をふくらますように背を伸ばし声を上げて互いを励ましあった。
そのとき吹きしぶる雨のカーテンを越して、サウロンの姿が見えた。マーサは真っ向から目玉の勝負を挑みながら、
「おまえは装置の扱いを知ってる。あたしとおまえでやるんだ。根性をみせな」
利菜は恐怖に身を震わせながらもうなずく。あの力、この夏彼女たちに味方してくれたあの力は今も流れこんでいたけれど、サウロンの恐気を払拭するには、いささかパワー不足のようだ。
「みんな力を貸して」
と利菜は全員の心に語りかけ、むしろ自分からみなの心を引きつけていった。その隙にマーサはサウロンの足元を泥沼に変えた。みんなはその思念を共有し、装置に送りこんでいく。
果たして、サウロンの体は一瞬にして地中に没した。けれど、彼もさるもので、意思の力で粘着質のある泥の海を体から遠ざけた。利菜は意思の力でサウロンの頭を上から抑えようとした。彼女たちは巨大な手をイメージして、サウロンの体を包みにかかった。寛太はあまつさえこの男を押しつぶそうとさえした。
かまうもんか、死ななきゃいいんだ――
サウロンはこの思念に怒気を発して、応復した。怒気はそのまま念動力となって寛太の頭を激しく打った。新治と紗英の手を握っていた寛太の腕がぐにゃりと下がり、彼は固い闇に膝をつく。紗英と新治は、思わず円陣の手を離して友だちを助けようとした。
駄目よ! と利菜は心中に声を発した。マーサも二人の体を引き戻し、紗英と新治の手をつながせる。寛太の体が地面に沈んで頭を打つゴツリという音がした。
今はだめだ、あの男を封じることが先決だ、とマーサはみなに告げたが、サウロンはこの動揺を逃さなかった。泥の海を這い上がると、憤怒の形相で子どもたちに迫ってきた。達郎が恐怖に耐えかねて叫んだ。
「あいつを動けなくしなきゃだめだ! あいつを……」
彼の思念をうけて、サウロンの左腕はゴム人形を捻るみたいにグルグルと巻き上がる。骨が砕け、その骨が筋肉や皮膚をやぶって突き出てくる。さしものサウロンも激痛に意識を失いかけた。が、意念を集中して耐えると、
「きさまら、この小娘どもが! 装置を持ったていどで甘く見るなよ!」
声の轟きとともに、巨大な津波が迫ってきた。全高十メートルに及ぶ巨大な波頭だった。その巨大さにその質量に、声もたてられない。利菜はそのとき、ふいに悟った。装置が側にあることで、影響を受けているのはあいつも同じなのだ。利菜はみんなを守ろうとしたが、心の片隅ではあんなやつにはかなわないと思っていた。心にできた一瞬の隙は、装置を扱う時間を与えなかった。一同の姿は津波に没し、何人かの手が引きはがされていく――
□ 八
利菜は津波に叩き伏せられ、水中を転げながら、それでもマーサとヒッピの手を離さなかった。三つの体は水中を複雑に乱舞し、腕がねじきれるかと思う。友だちの体がそばを離れていくのを三人はハッキリと感じていた。海水をたっぷりと飲み窒息しかかる。薄れ行く意識の中で、ヒッピの声が聞こえてくる――
ここを離れるんだ、別の場所に……
利菜は必死に念じた。全員をつれて、重い重い海の底を抜け出そうとした。そのとき、三人が思い浮かべた別の出口は一つしかなかった。利菜はほとんど神様に頼る気持ちで装置に願った。
お願い、どこかあいつのいない場所に、みんなが死なないところに……
□ 九
次元の狭間を飛び出した瞬間に、彼女をおおっていた海水は、水風船が弾けたみたいに四方に飛散し、まるで突然わいた湖のように広がる。その中心にいて手足を広げて伸びていた。半眼の目がピクピクとして朝の目覚めの瞬間のようにまどろんでいたのだが、ヒッピが頬をひたひたと叩いたので目を覚ました。
「すごいぞ」とヒッピが言った。「ここは森だ。大鏡に出られたんだ」
利菜は体を起こす。嵐は消え、晴れ間がのぞいていた。もう早朝だった。森はまったくの水浸しだ。その水森の中に、佳代子やパーシバルたちがところどころに転がっている。利菜の直ぐ側に鏡の置かれていた台座がある。そこから少し離れたところに、牢獄の檻が朽ちて転がっていた。石畳は土の中になかば埋まっている。地下牢はイニシエの森と同化したみたいに見えた。どうやら、牢獄自体を大鏡の場所まで引っ張ってきたようだった。
「みんなを集めないと……」
立ち上がろうとしたが、さきほど無理をしたせいかあちこちの腱が伸びて、ストレッチをしすぎた後みたいにうまく動かない。はっとして右手を見おろす。よかった。装置は手放していなかった。利菜はマーサを探したが、彼女は台座に寄りかかって意識をなくしている。
「マーサ……」
利菜が師匠の元に赴こうとしたときだった。二人はゲートの開く気配を感じてふりむいた。マーサの真上の空間、大鏡のあったその場所に、楕円形をしたゲートが口を開けている。
「サウロン……」
とヒッピが言う。サウロンは真っ赤な目をして子どもたちをみおろしている。
「下等生物どもが、手こずらせるな!」
サウロンの声が頭蓋に轟く。利菜はよろめいて腕をつき、ヒッピは腰から地面に倒れてしまった。
利菜の視覚は、サウロンの目玉だけになった、そいつがどんどん大きくなる。装置を寄越せ、と彼が言う。友だちはみんな目を覚ましていたが、サウロンの威力に抵抗できない。装置が手元にないからだ。あたしがなんとかしないと。
利菜はマーサを頼ろうとしたが、目を覚ましそうにない。もう死んでしまったのかと思うと、瞬間冷凍みたいに心が冷えた。利菜は装置を握りしめたが、全身の筋肉が硬直して動くことができない。
「もうおしまいだ……」と新治がうめいた。
サウロンが全員の心が十分に弱ったのをみてとったようだ。あいつが心に忍びこんでくる。利菜は友だちの結束がやぶられていくのを感じる。あんなに近くに感じていたのに、今では太平洋の端にいるみたいだ。その合間に立ちはだかるのはサウロンだった。彼は子どもたちの精神世界に入り込んでいく。その巨大な魂が一人一人の心を捕まえていった。甘い言葉をささやいて、苦しみを終わらせることを約束した。彼の声は強大で、その甘言は密のように心を溶かしていく。利菜はそんなのうそだ、でたらめだと反抗したが、佳代子たちはたちまち希望にみちた顔になり(目だけはちがう。そこだけ虚ろだ)、サウロンがまるで恋しい主人のようにしっぽを振って向かっていった。
利菜は懸命に抵抗した。あいつに同調しちゃだめだ、あやつられたりしたらだめだとみんなに呼びかけた。だけど、口がきけない。
利菜は装置に念じて、みんなとのつながりを取り戻そうとした。それを止めたのはヒッピだった。利菜の心に忍びこんでいたのは、サウロンだけではない。彼女にはずっと以前から同居人がいたし、だから心に同化するサウロンのことも客観視することができたのだ。心に住む他者の存在には慣れていたから。エビエラの言葉も今ならわかる。利菜とヒッピは、誰よりも深く精神が結びついていたのである。サウロンの強力な力も、二人を支配するには至らない。魂をくっつけ合った友人が、いつだって支えてくれていたからだ。
二人は偶然にも魂が同化したあのときの現場にいた。利菜は何か運命のようなものを感じる。あのとき、魂をくっつけ合った友人が、いつだって支えてくれていたから。ゲートをくぐったあのとき、利菜が意識をなくしていたせいかもしれない。心を閉ざす方法を知らなかったせいかもしれない。その両方の可能性があって、二人のつながりは切っても切れないものになっている。別の世界に離れたって、この絆が断ち切れることはなかった。そのことで苦しみもしたが、今は感謝したい気持ちでいっぱいだ。
けれど、友だちを取り戻すことはできそうになった。サウロンのかけた催眠術は完璧だった。彼女のグループは自意識をなくし、命令どおりに動く生き人形だ。利菜はつとめてうつろな目をしながら、ヒッピとともにサウロンに向かって歩き始めた。心の中で――気づかれちゃだめだよ、あいつの催眠術にかかったふりをしてと言った。ヒッピは利菜にだけわかるよう、かすかにうなずく。
友だちはよろめきつつサウロンに近づいていく。二人はその後に続いた。どちらからともなく手を出し、恋人同士のように手をつないでいる。その手の中には装置がある。
二人は装置に念を送り続けた。そして、力を解放する瞬間を待ち構えた。
□ 十
サウロンは油断していた。相手は子どもだし、装置をまるで使いこなせていない。マーサが気絶していることも、彼の気を大きくしていた。しょせんは下等生物の集まりだ。
彼は満足だった。これまでの苦しい時間も報われたと思えた。全てはこれからはじまる。子どもたちに苦しみを終わらせると言ったのはうそではない。苦悩に満ちた世界そのものがなくなるのだから。
彼は装置を受け取るために歩き始めた。子どもたちがやってくる。サウロンにとっては装置のもたらし手に過ぎなかった。そのとき、少年たちの後方で、利菜とヒッピが足をとめた。
□ 十一
利菜は大きく呼息しながら、その最後の時を待ちかまえた。
マーサはゲートのことをパワースポットだと言った。だとしたら、そのパワーはサウロンの真後ろで溜まりすぎるほどに溜まっている。足を止めると、サウロンが眉をしかめるのが見えた。その眉と利菜の間には友だちの傷ついた背中がある。彼女は友だちをこんな目に合わせたあいつに腹を立てながら、装置をもった手を翳した。
「ひらけ」
息のあった双子のように言った。サウロンの背後で、巨大ながま口のようなゲートが開き、そして、サウロンも首をねじきるようにしてふりむいた。利菜は想像する。ゲートがサウロンを吸い込むところを。ゲートはたちまち吸引力を発揮して、サウロンのいる数メートル四方の空間をたちまち吸いこみはじめた。土が剥げ、草は飛び、空気は真空となって、サウロンの体を浮かび上がらせる。彼はそれでも抵抗した。イニシエの銀河から生き続けてきたこの男は、驚異の精神力を発揮して、ゲートに抵抗しようとした。彼は叫ぼうとしたが、もう辺りに空気はなかった。サウロンは二人の子どもに向かって、念力を送る。巨大な衝撃が正面にいた達郎達を吹き飛ばし、利菜に迫った。
利菜は装置に命じて、空気の壁を作り上げた。それでもサウロンの力は防ぎきれなくて、かまいたちが頬を裂いた。彼女が血を流したのをみて、ヒッピが心を乱しかけるが、利菜はかまわず身をのりだす。もっと強く、もっと吸い込め!
き、きさまら……!
という声。サウロンの最後の念波だ。彼はとっさに後ろを向いて、ゲートを閉じようとした、利菜も脂汗を流して力を送る。ううっ、とオオカミのような唸りが口から漏れる。こめかみの血管が激しく脈打ち、血流がどんどん脳に溜まって、手足の末端が痺れ冷えていく。ゲートの周辺では、サウロンと利菜の力がぶつかって、巨大な振動が起こっていた。ヒッピがすぐさま加勢する。と、ゲートは振動と光芒を放つようになり、広大森を震撼させる。その震撃は、戦闘の終息した王都にも届き、眠る人を目覚めさせ、起きている者を怯感させた。まるで世界が砕けるみたいだ。
利菜とヒッピはそれでも力を送り続けた。手の中で、装置は暴れサイコロみたいに光を放って跳ね回る。脳みそが沸騰しかかっていたが(そんな想像すら、今は危険だ)それでもやった。
吹き飛べ! 二度と戻ってこれないような、遠くの次元に!
と声にならない絶叫を上げる。サウロンの腰がついに浮きあがった。彼はゲートを閉じるのをあきらめ、その念動力でもって、二人の心臓を止めようとした。攻撃に転じることで初めて見せた隙でもあった。
利菜たちの手だてはそれよりも早かった。ゲートが急に拡大し(サウロンの抵抗力が弱まったからだ)、生き物のように陰を伸ばす。飲みこめ、飲みこめ、と彼女はがんばった。陰はサウロンの衣服をとらえる。真っ黒な腕が男の頭をつつみこむ。
じゅるり
その舌なめずりのような音は、偉大な男の最後には全くそぐわなかった。サウロンはまるで肉まんの皮が具を包み込むように黒気に包まれていった。後は一瞬にしてゲートに飲みこまれる。サウロンをとりこむと、ゲートはその一点に自ら入り込むようにしてかき消えた。
利菜とヒッピは、手を握りあったままでいた。息を乱し、サウロンの消えた空間を見つめている。頭上からは森の葉が玉屑のように降ってくる。利菜はしばらく呼吸をとめて、その光景に飲まれていた。まるで自分という存在がなくなって、その光景に溶けたみたいだ。自分たちのしたことが信じられない――あいつがいなくなったなんて一生掛かっても信用できなかった。
風がやんで静寂が戻った。耳がガンガン鳴っていた。激しい頭痛がして、胸も大きく波打った。全身がぐっしょりと濡れている。
やがて音が戻り、森はこの騒動に文句をもらすように梢を鳴らした。鳥のさえずりがした。
二人は一瞬顔を見合わせて、また正面を向いた。ゲートの消えた場所に。
やがて長い時間がすぎ、みんなが呻きをあげて起き上がるころになると、ヒッピが、利菜の肩を、そっと抱き寄せる。二人は頭をあずけあう。利菜は少し涙を流し、少年は鼓動を胸に踊らせながら顔を仰向ける。
そのようにして、この長くも短い勝利を、噛みしめ合ったのだった。
□ 十二
佳代子たちは、順々に起き上がった。
ヒッピが、サウロンはもういない、あいつは消えてしまった、と言った後も、子どもたちは呆然としていた。森は惨憺たる有様だ。二つの力のぶつかり合いで、あちこちに虚無が生まれて二度と生命を生み出しそうにない。それも自分たちがしでかしたことだ。人の憎しみがこんな結果を生むのなら、サウロンの言ったこともあながち嘘ではないのかもしれない。それにサウロンが消えたところで、世界の崩壊は今もなお続いている。みんなは自分たちがしたことが何だったのか、疑問を持った。一同はこの勝利にも絶望しかけていた。結局は何も変わらなかったんじゃないのかな?
利菜は落ちこむ一同に言った。
「みんな、みんな聞いてよ。疲れてるのはわかるけど、あたしたち、やらなきゃいけないことがある」
みんなはその言葉を、言われなくても聞く気になった。なんと言っても、疲れている筆頭は利菜だったろう。今日一番の殊勲打を放った彼女がこっちを向けと言っている。
利菜はみんなの視線が心が自分に集中するのを待った。それから言った。
「あたしたち、装置をつかって世界のねじまげを食い止めなきゃいけない」とグループに呼びかける。「そしたら、おさそいやわるいものだってなくなるよ。みんな世界が壊れてるせいなんだから」
「そんなの無理だよ」
紗英は涙声だ。利菜は激昂して言った。
「駄目でもやるのよ! この森を見なよ! あたしたちがやったんだ。元に戻すことだって、きっとできる」
一同は利菜の言葉に心を打たれた。だけど、胸に去来したのは、崩壊は、宇宙の意志だと言ったサウロンの言葉だ。
「そんなことない、みんな、いいものだってあるってわかってるでしょ? 今までいいことがなかったなんて言わせないわよ」
利菜が装置をもった手をさしだすと、ヒッピが無言で手を重ねる。
「タットン博士は、崩壊なんて望んでなかった。世界はわるいものばっかじゃない」
「どうかな?」パーシバルはリーダーの言葉にも疑わしげだ。
「それじゃあ、おれたち、みんな悪人なのか?」
ヒッピの言葉に、達郎は軽い笑い声を上げる。その笑いはみんなに伝染した。虚無で満ちた森に、子どもたちの声が響く。再生を望むのは、いつだって明るい心だ。みんなには希望が必要だった。ユーモアも。
「わるいものが崩壊を望むのなら、あたしたちがいいものに働きかければいい」と利菜は言った。「もういっぺん環になろうよ」
みんなはそうした。手をつなぎあい、環を作った。すると、新たな力が生まれた。それは戦いのためではない、誰かをやっつけるためではない、何かを生み出すための力だった。みんなは毛穴が開くような感覚に酔いしれる。こいつは出力全開だ。
そう言えば、こんな様になっても、自然は美しさを保っている。森の巨木たちが、みんなを守るみたいに包み込んでくれている。
「これって、大仕事だよね」佳代子がみんなに笑いかける。紗英も新治も笑っている。
「全部終わったなんて知ったら、マーサばあさんも驚くぞ」とパーシバル。少しいたずらっぽく眠るマーサに目を向けた。「オレたち英雄になるんだ」
「こんなこと誰も信じないよ」ヒッピが言った。
「でもよう」パダルが不服を唱えると、
「いいじゃないか。みんなが無事で」とヒッピ。「友だちがこれ以上欠けることがなかったってだけで、おれは満足だ。それにほら、今日はこんなにメンバーが増えたじゃないか」
ヒッピの言葉にみんなは微笑みをかわした。彼らは大きく息を吸いこんだ。
生きてる。空気があって、呼吸をしている。互いの鼓動を感じる。見上げると、空には青空。今日はこんなに上天気だ。
その青空は涙でにじみもしたけれど、利菜はいい気持ちだった。気分を良くするためだけに、心に風がふいてるみたい。
憎悪に満ちて、絶望したこともあったけど、今はいい気持ちだ。みんなといると希望に満ちている。
○ 一九九五年 ――終刻
□ 十三
あれが最後だった。
あのあと、彼らはマーサとトゥルーシャドウの治療をした。寛太はどうにか命をつなぎとめた。
サイポッツの国がその後どうなったのか、利菜たちは知らない。戦争は続いていたし、どの民族も老廃していた。きっと、再生への道のりに向かいだしたのだろうが、王をなくした国もある。
そういえばサウロンの望んだものも再生だった。
装置の扱いに関してはすぐに決まった。マーサが元の場所に戻すことを望んだからだ。彼女の記憶が戻ったのかはわからなかったが、エビエラがそう決めたのならばそれが一番よかったのだろうし、三郎が装置を守っていることに、満足しているようだった。
利菜たちは、装置をつかって、元の世界に戻っていった。
鏡を抜けて、お堂に戻ったとき、彼女たちは今後どうするかを話し合った。ねじまげられた世界は、これからも続いていく。サウロンが死んだとも思えない。再び装置を取り出す予感が、みんなの胸に去来していた。
ただ、考えていたのは、一つのことだった。
おれは元の生活に戻りたい、と寛太が言った。それで、あたしは、あたしたちは……
○ 二〇二〇年 ――再会
□ 十四
「利菜、利菜……っ」
頬を叩かれて、目を覚ました。
利菜は目の前にいるのが、大人の佳代子や達郎たちであるのをみて微笑んだ。みんな、成長したんだなあ、あの後も、ちゃんと世界はつづいたんだなあ、と思って安堵したのだが、その瞬間、これまでの全てを思い出したのだった。
起き上がると、腹部に激痛が走る。痛みに耐えかねてうずくまる。血は濡れたまま。時間はたっていない。
「利菜、大丈夫なの? 動いたら……」
「紗英は? 紗英が、あいつに、サウロンに」
「紗英なら、途中で見つけた。でも、背中を刺されてて、意識が戻らないのよ」
利菜は視線を動かした。みんなお堂にいた。紗英のことは新治が抱えている。
ああ、これで全員そろったんだ、と彼女は思った。六人全員が顔をそろえるのは、いったいいつ以来だろう。
それから、話した。町に戻ってからなにがあったか、ビスコのこと、今みた過去の、夢の話も。
「今の今まで忘れてたけど。あたしたちはまた装置を三郎のお墓に埋め直したのよ」
「表に散らばってる骨は三郎のものなのか?」
達郎の質問に、利菜はうなずいた。
「記憶を消したあと、装置をちゃんと埋めるようにみんなに暗示をかけたのよ。山をおりて、自転車に乗るところまでね。目が覚めたとき、あたしたち、それまであったことはすっかり忘れてた。なんで、こんなところにいるのか、不思議がってたこと覚えてる?」
佳代子はうなずいた。
「世界のねじまげはあのとき、一時的にだけど食い止めることができたのよ。わるいものも見なくなって、おさそいも止まった。その後はみんなも知っての通り――でも、ねじまげはずっと続いてたんだね」そして、「サウロンが戻ってきた」
「本物なのか?」達郎が訊いた。「ほんとにサウロンだったのか?」
利菜にはうなずくことも、否定することもできない。
「紗英を医者に見せないと、だけど、もう神保町だってふつうじゃないんだよ」
達郎たちは、故郷でいま何が起こっているかを語ってきかせる。
「ねじまげを食い止めたせいかもしれない」と佳代子が言う。「川を堤防でくいとめても、力をためこんで濁流になるじゃない。それとおんなじなのかも……」
利菜は首を傾けて鏡を見る。渦がまだ残っていた。
「ゲートがまだある。あれを使わないと」
達郎が、「何をいってるんだ。紗英の治療が……」
「あれを使って、向こうの世界に行かなきゃいけない! あたしはヒッピのところに装置を送ったから、サウロンには見つかりっこないのよ。向こうの世界であたしを待ってる奴は、いつだってヒッピなんだから」
「でも、あいつは死んだんだろう?」
「わからない。サウロンは大鏡に装置を投げたと思ってる。でも、あのときは、ゲートの向こうにヒッピの存在を感じたのよ」
「ゲートが開いたままだってことは、すぐに戻ってくるのかもしれないぞ」新治が言った。
「だから、その前にここを離れないと。ゲートが閉じる前に。あたしたちじゃゲートを開けない、もう装置はないのよ」
みんなは顔を見合わせて逡巡する。
「ためらってる場合じゃない。紗英のことは、紗英のことは……」
「向こうの世界で医者を探すのか?」と寛太。「どうなってるかわからないぞ。ペックたちだって、生きていないかもしれない」
「それに医学だって、こっちほど進んでるはずがないよ。紗英の傷はおまえのより重いんだ」新治が唾を飲む。「ひょっとしたら、内臓が傷ついてるかも」
「もういい」と達郎は言う。利菜が彼を見た。「ここにいても、おれたちにできることは何もないよ」
「問題は、向こうでどこに出るかよ」と利菜は言った。「あいつがビスコと融合したんなら、たぶん大鏡を使ったはずでしょう? あそこに出たって、サイポッツの都からは遠すぎるし、すぐにつかまっちゃう」
「あのときは、パワースポットにしか出られなかった」と達郎。
「今じゃあ、世界中がパワースポットかもね」佳代子が言った。「わるいものであふれてる」
みんなは彼女の言葉に押し黙った。うすら寒い思いがする。
「できれば、向こうの世界で生き残ってる仲間のもとに出たい。あの子たちのこと、みんな覚えてる?」
佳代子たちはうなずきあう。
「みんな、大人になってるんだろうな」達郎が言った。
「パダル、モタ、パーシバル……」寛太はなつかしげだ。
「問題はまだあるのよ」と利菜は言った。「サウロンは、別の世界を征服して戻ってきたっていったのよ。どう戻ったのかはわからないけど、たぶん、一人で戻ってきたんじゃないはず。ヒッピたちの世界に戦争をしかけたんだから」
ならなおさらだ、と新治が言った。「大鏡に出ても、あいつの仲間がまちかまえているはずだ。別の場所さがさなけりゃ」
一つだけある、と利菜がいったので、みんなは彼女に注目した。
「ダンカン人の都よ。あの地下にあった牢獄を、あたしたちは大鏡にうつしたでしょう」
佳代子たちが視線をかわす。確かに、牢獄のあった場所にはぽっかりと空洞が出来ているはずだ。それも次元の空洞だった。ゲートが次元の裂け目ならば、あの場所には常にゲートが口を開けていることになる。
佳代子は利菜の背に手を回す。「行こうよ。あの子たちだって、あたしらの助けを待ってるのかも」
「そうだな」と達郎がうなずいた。「そうかもしれない」
彼らは傷ついた利菜と刻々と命をなくしていく紗英を抱えながら、ゲートが今一度、活動するのを待ちかまえた(けれど、そのときは、サウロンが戻ってくるときでもあったのだが)。
タッチの差だ。おれたちはタッチの差でゲートを駆け抜けるんだ。
達郎はタッチアップの心境で、その瞬間を待ち構える。手をつなぎ合い、出口を念じてそのときを待った。そして、彼らは今一度ゲートに飛びこみ、この世界から姿を消した。
彼らが消えたあと、お堂は音をたてて崩れていった。三郎の仕業とも、単なる崩壊とも見てとれた。
それは、世界の終焉だった。
◆第二十三章 過去と未来
□ 十五
もう一つの世界が近づくたびに彼女はあちらの仲間たちの存在を強く感じるようになった。サウロンのやつ、嘘をいってなかったんだ、あいつは真実を語ってたと彼女は思った。そして、自分はあいつの言葉を信じてた。彼女たちの相手はむちゃくちゃで相当いかれているけれど、ある意味ではつねに真っ当だったから。彼女がサウロンを恐ろしいと思うのは、そこかもしれない。あいつは信念をもっている。その信念にそってみると、あの男はつねに真っ当だのだ。語る言葉は、あの男にとっての真実だ。
利菜がこのとき向こうの世界に感じたのは、たった二人の友人だけだ。あいつはヒッピが死んだと言った。けど、言葉足らずでもあった。彼女は真実を知るのが恐ろしく、ゲートの中から逃げ出したくなる。それでも出口を目指して仲間と突き進んだのは、あの連中がそんな状態になっても、自分たちを信じて待っていてくれたからである。
出口が近づき、肉体が形をなしてくる――と腹部の疼痛は激しくなりのたうつ、あの世に向かっておいでおいでをしているみたいだ。サウロンに手をくだされなくたって、この怪我が元で死ぬかもしれないな、と思った。そう思いながら、ゲートを飛び出し、固い地面に着地したのだが、もう膝には力が入らず、その場にクタクタと頽れた。
「紗英……」と地面に手をつきながら彼女は言った。同時に厳しい光芒が彼女を照らし、視覚を奪い去ってしまった。サーチライトで照らしているみたいだ。光の周囲にはうごめく人影がある。サウロンの部下という最悪の結果も頭をよぎる。でも、彼女はあそこにいるのが誰なのかを知っている。
耳の中で唸り音が充満して、周囲の音が聞き取れない。利菜は紗英のことを心配してふりむいたのだが、そこにあるのは壁に大きく口をあけた巨大な洞穴だった。洞穴向こうは、暗黒の濁流が流れている。濁流は黒い飛沫を上げて、ライトの光を吸い取っていた。それはゲートとも呼べない。二十五年前に自分たちのおかした過ちによって(といっていいだろう。装置をつかって空間をひん曲げたのだから。それは世界のねじまげを助長する行為に他ならない)開けられた、暗黒であり、虚無だった。利菜は虚無の恐ろしさに目をみ開き、渇いた喉を鳴らした。その濁流を突きのけるようにして達郎たちが現れる。彼らは虚無にがっちりと捕まえられていたから、その水飴のように粘質な液体をひっぺがすのに苦労していた。達郎たちは、紗英と佳代子を抱えている。そして、雪崩を打つようにして利菜の足元に落ちてきたのだった。
「紗英! 紗英! 目をあけて!」
と気絶した友人にすがりつく。
「利菜!」
肘をとられた。ふりむくと、金髪碧眼の男が目をむいて彼女の肘をひいている。煤で汚れた団子っ鼻、太った体格、彼女の中で、子ども時代の友人の姿が、太った中年の男性と重なった。
「ペック……」と言った。とたんに、利菜の目の片方から涙が一滴、きれいな尾をひいて流れ落ちた。ペックの後ろからは、背の高い男性がやってくる。
「パーシバル?」
パーシバルは少し照れたようにうなずいた。あの頃は一番のちびすけだったのに、今ではすっかり背高のっぽになっている。そうしていると、彼はなんだかノーマに似ている。利菜はこんなふうにお互いが変わってしまったのに、すぐに相手がわかるとは奇妙なことだと考える。だけど、それはある意味で当然のことだ。彼女たちは未だに何かをなしとげるためのグループらしかったから。姿が変わっても、魂に押されたスタンプまでは変わらなかったものらしい。ああ、だけどここには――この世界にはこの二人しかいない。あの頃の仲間は彼らしか残っていないのだと利菜にはわかった。どっと涙がこみ上げたから、彼女は顔を伏せて、崩れそうになる膝を支えようと、ペックの肘をかわって握った。
「ペック、紗英を……あの子を助けてやって。サウロンに、あいつにやられたのよ」
見せてみろ、といって進み出たのはパーシバルだった。ひょろひょろの体を泳がせるようにして紗英に近づく。佳代子が紗英の頭を膝に乗せている。
「おまえたちが来るとおれたちにはわかっていた」
パーシバルが言った。利菜達はうなずいたが、彼は紗英に向かって顔を落としていたから、見えなかったみたいだ。
「残念だが、我々には医者が残っていない。みんなサウロンにやられてしまった」
利菜はそっと視線を背ける。ある意味でわかっていたことだ。自分たちの世界でさえあれほどの変質が起こっていたのだ。パーシバルは顔を上げたが、誰のことも見なかった。彼は閉じないゲートのことを眺めていた。ペックが変わって、
「ヤクトゥース」
と後ろに呼びかける。背後でこの再開を見守っていたヤクハタ人の中から、身なりのいい男が(それは過去の戦争でも活躍した隊長の年老いた姿だったが、利菜たちにはわからなかった)進み出てきた。
「おまえたちの医術でなんとか出来ないか? この人を助けてやってくれ」
「サイポッツと我々は体がまるでちがう。知っているだろう」
ヤクトゥースは腹を立てたようにいったが、それでも仲間を呼び寄せた。ペックがヤクハタ人の後につきながら、また後ろにむかって、「テドモント、担架を借りるぞ」
「好きなようにつかえよ」
利菜は驚いた。ペックとパーシバルをのぞけば、ヤクハタ人ばかりかと思われた一団の中に、サイポッツがまじっていたからだ。男は重傷を負っていて、おまけに片腕がない。一人では満足に動けないらしく、地面にへたりこんだまま近づいてこない。その男だけは過去のどの顔とも結びつかなかったのだが、名前はヒッピの記憶にあった。
「テドモント? あいつまでいるの?」
「今では仲間だよ」
とペックが苦笑した。昔を思い出したのだろう。
□ 十六
一同は疲れたように座りこんだ。事実、肉体も精神も疲弊しつくして、しぼりかすしか残っていない気分だ。崩壊する世界の中で、とりのこされた孤児となった。まるで、世界がこのわずかな洞穴だけになって、後は縮潰するのを待っているみたいに。
ペックたちはこれまで起こったことを話してくれた。利菜たちも話した。こんな場所で聞くにはいささか空寒いものばかりだ。
三ヶ月前、サウロンが空飛ぶ船で戻ってきたこと、その船からの攻撃で、王都が一夜にして壊滅してしまったこと。サイポッツたちはもう数百人しか残っていない。それでも評議会の議員だった彼らは生存者をまとめて、イニシエの森にあるヤクハタ人の都に助けを求めた。
サウロンが何を狙っているのかはわかっていた。マーサは殺害され、ビスコもまたその身を奪われた。ペックとパーシバルは、評議会の反対を押し切って、自分たちだけで、ダンカン人の都におもむいた。彼らにはゲートを開く能力がないが、空間がてひどくねじ曲げられた場所を覚えていたのだ。そういえば、ペックは儀式の神官でもあった。
つまるところ、彼女たちは狙い通りの場所に出られたわけだった。ここはダンカン人の都の地下なのだ。ただ、あのあと、イニシエの民同士でも戦争が起こり、ダンカン人は滅び、都も廃墟となっていた――利菜たちが戻ってくるというペックの意見に賛同してくれた者は、テドモントを除くと、少数のヤクハタ人だけだった。
サウロンの牢獄のあった場所までは、簡素な階段が掘られており、その上には石造りの神殿が設けられていた。が、歳月はここにも及んだようで、今ではあちこち草むして、ダンカン人の遺体も単なる骨とかしているそうだ。世界中の都市や町が、これと同じ結末を辿ろうとしている。
サウロンの軍隊は見たこともない武器をつかったそうだ。彼らの暴虐は周辺諸国にもおよび、世界で生存しているのは、イニシエの森のわずかな民族だけとなっている。こちらの世界もまた、壊滅したといっていいのかもしれない。
ともあれ、紗英はヤクハタ人の都に運ばれることとなった。佳代子たちは紗英について行きたがったが、利菜がここでやるべきことがあると主張したのだ。
「おまえだって、治療が必要だろう」新治が言った。
「いま必要なのは、もう一度装置を手に入れることよ。サウロンは戻ってくるに決まってる。装置がないかぎり、あたしたちどうにもならない」
ペックらの話を聞いた後だけに、彼女の発言には重みがあった。達郎は小さくうなずいた。
「ペックたちのいっているのは宇宙船のことだろう。おれたちの世界の軍隊だって太刀打ちなんかできないぞ」
結局のところ、彼女らはサウロンを別の次元に追いやったわけでも、遠くの世界に追い払ったわけでもなかったのだ。彼はこの次元の別の星に飛ばされただけで、それで戻ってくることが出来たのだった。
むろん疑問はあった。別の次元でないとはいえ、宇宙といっても広大である。なぜ正確に戻ってこられたのか? 狙いは本当に装置だけなのか?
「おまえたち、装置はどうした?」パーシバルが真剣な声音で訊いた。「サウロンに奪われたのか?」
「あいつのことも出し抜いてやったわよ」利菜は苦しげな表情で笑う。「結局、あたしたちのしたことは、時間の先延ばしでしかなかったのね。サウロンにそう言われたよ」首を回し、「ねえ、テドモント。ヒッピはほんとに死んだの? サウロンがあいつが死んだっていったのよ。でも信じられなくて」
テドモントはその話をするのを拒むように顔を背けた。彼女たちはしばらく待った。
ゲートからはわずかな風が吹いている。その風がみんなの心を落ち着けるようだった。悲しみまでは払わなかった。
「おまえたちが消えた後、おれたちは国を立て直すことで精一杯だった。ハフスも死んで、国をまともに支配する機関はなくなったんだ。戦争を完全にとめて、蛮族と和解するまで五年かかった。その間に、共和国ができて、議会政治がはじまった。おれたちとヒッピは、若手の政治家になったんだ。ヒッピはもちろん改革派だ。権益にしがみつく旧貴族の、優遇制度をやめようとしてた」とこのくだりではじめて笑った。「あいつは演説がうまかったよ。いつのまにか改革派のリーダーになっていたんだ。民衆を味方に世論を動かすようになった。だからだよ。反対勢力に、暗殺されたんだ」
「あのときは、テドモントも一緒だったんだよ」パーシバルがつかれたようにすわりこむ。「テドモントは見せしめに腕を切られた。ヒッピは助からなかったよ」
みんなは一様に言葉をなくして下を向いた。利菜は、そんな……とつぶやいた。驚きと喪失感が深い。彼がそんな死に様をしたなんて……涙も出なかった。彼女自身はテドモントの言葉を聞くまでもなく、友人の不在を知っていたのだが。この世界にきたあとも、ヒッピの存在を感じないのだ。このつながりがなくなるときは、片方が死んだときだと信じていたから、そのとおりになったわけだ。
「ヒッピとおれが襲われたのは真夜中だった」
犯人は、いずれも黒いずきんをかぶっていた。テドモントは真っ先に外に引きずり出された。刺客たちは、馬車の外から銃弾を撃ちこんだ。馬車に乗りこむと、兇刃を振るった。とどめを刺すために。ヒッピは馬車の中で、全身数十カ所を串刺しにされた。そのとき、二十五歳の若さだった。
テドモントは右腕を切り落とされたが、見せしめのために生かされることになった。
「ヒッピはあれだけやられたのに、まだ息があった。おれは戻ってきた馭者に助けを呼ばせた。三日はもったんだが、意識は戻らないままだった。あいつは、ふだんから、開けっぴろげだった。いま思えば強引だったよ。自分が正しいと思うと、絶対に後には引かない奴だった。若かったせいもあるが。もっと警戒するべきだったんだ。通り道も毎回ちがうように気をつかったが、暗殺者が本気になったら、ふせげるもんじゃなかった」テドモントはそこまで一息にしゃべると、少し間をおいた。「まだやりたいことも、計画もあったろう。それも残らず墓場いきになった」唇が震えた。「ペックのやつが、泣いてなあ」
テドモントは嘆息した。彼自身泣いているように見えた。この戦時中も旧友を忘れることはなかった。何度も渇いた喉を湿らせる。
「おれがあいつのかわりだったらよかったのに。おれがかわりに……」
利菜は立ち上がり、テドモントの腕に手を置いた。彼の痛みが、その手から伝わるようだった。「そんなこというべきじゃない。誰かの代わりなんていないし、代わりになんてなれないんだから。あんたが生きててよかった。そうでしょ?」
「ああ。ああ、そうかもしれねえな」と目頭をぬぐう。鼻をすすり、少し笑った。テドモントはうつむいて、涙がなくなるのをまった。「ヒッピは死んだけど、結局王都は壊滅だ。おれたちと敵対した連中だって、今は瓦礫の下になった。馬鹿な話さ。おれたちが築き上げたものは、一晩足らずで灰になったんだから。あいつらの兵器はすさまじいんだ。あちこちで、いろんな民族の、都や村が灰になってる。イニシエの森が焼かれるのも、時間の問題だろう」
「装置があるのは、森だと考えたのかもね。だから、無事なのかも」
サウロンは、別の世界に隠したことまでは知らなかったから、と利菜は言った。
あんなに勇敢だったトゥルーシャドウも、傷がもとでほどなく死んでしまった。とはいえ、あの大けがでは、その後に起こったイニシエの森での戦闘を生き残れなかったのではないか、とパーシバルはみんなをなぐさめた。
「マーサおばあさんも死んだんだね」と利菜はこのくだりではじめてマーサの名を口にして、涙をにじませる。「あの人にはもう会えないんだね。あたしは恩が返せなかったよ」
それに関して、テドモントは何も言わなかった。パーシバルが、
「マーサばあさんは、そんなこと望んでない。おまえが生きて帰ったことを、喜んでたんだ」
「そうだ。ぼくらはまだ生きてる」とペックも力強くうなずいた。「もう一度世界を救おう。ぼくらにはそれができると信じてる」
議長らしい発言だな、とテドモントが軽く手を叩いた。議長? あんたが、と利菜も大げさに驚いた。本当はヒッピになって欲しかったんだけどね、とペックは自嘲した。
「だけど、おまえはゲートの出口にヒッピを感じたんだろう」達郎がいった「ヒッピは生きてるんじゃないのか」
「それはない」とテドモントは否定する。「あいつは死んだ。おれたちが看取ったんだから、まちがいない」
けれど、利菜はゲートに向かい合ったあのとき、確かにヒッピの存在を感じた。現に装置は大鏡になく、サウロンが手にいれることもなかった。
どういうことだろう?
利菜は唇をなめる。血液が失われて喉が渇いたからでもあるが、考えに集中してもいた。
「ゲートの出口が過去だった場合はどうなるの?」と彼女は言った。「サウロンと最初に戦った時、あたしたちは牢獄に戻った。あたしが元の世界に戻ってから、どのぐらい時間がたってたの?」
パーシバルは少し考えこんだ。「すぐだったと思うぜ。一時間もたってないかも……」
「でも、あたしたちは元の世界で、三日以上過ごしてから戻ったのよ。過去に行ったとは言えないかもしれないけど、でも、あのゲートで、時間だって越えられるのかもしれないでしょう?」
パーシバルは思わずふりむいた。「ヒッピが生きていたころに、装置を送ったというのか?」
「わからない。なんともいえないよ。でも、あたしはヒッピのことを念じて送ったのよ。――装置をつかってね」
「利菜、それじゃあ、あたしたち、とりにいけないよ。今は装置がないんだから」
子どものころ、坪井の家に乗り込んだ佳代子は、過去に戻ったうえに、もう一人の自分に出くわす、という奇妙な体験をしている。しかし、あれとて偶然の結果であって、狙って戻ったわけではなかった。
利菜は、ふと、記憶を消さずに修行を続けていたら、どうだったかなあ、と益体もないことを考える。でも、それは現実的なことではなかったし、そうなったら、秀男とも出会わず純子もうまれなかったことになる。
利菜はゲート(とも呼べないかもしれないが)をかえりみる。
「あれを使って過去に行くことはできるんじゃないかな。つまりヒッピの居所さえつかめれば……あたしにはわかると思うのよ」
「おまえとヒッピが特別だからか?」とテドモント。
パーシバルが身を乗り出し、ペックと視線を交わす。「生きている頃のヒッピに会えるんなら、あいつに忠告だってできるはずだ。そしたらあいつは死なないかもしれない」
ペックたちは夢中になってその可能性を論じ始めた。達郎がそうはうまくいかないといっても、まるで聞かない。タイムパラドックスを心配しているのだ。
利菜は達郎の肩をつかんで、「今は過去に行くことが重要だよ」
「だけど、未来を変えるなんてどだい無茶な話だぞ」と達郎はささやいた。「あいつらだって消えちまうかも」
でも、こんな未来よりはましかもね、と利菜は心の内で答えた。
「それに戻るときはどうするの?」と佳代子。「過去にはそれで行けたとしても、戻る目印がないじゃない」
みんなは考えこんだ。けれど、時間がないのも事実だった。サウロンはもうこの世界に戻ってきているだろう。自身の軍隊をつかって、彼女たちを探し回っているに違いない――
「その装置を手に入れられれば」
背後からの声にみな飛び上がった。ヤクトゥースたちだ。彼女らを守ろうとここに居残ってくれたのだ。
「あの男に勝てるのか?」
みな黙りこんだ。あのとき装置を使ってサウロンを追い払ってくれたのは利菜とヒッピなのである。今はその片方が欠けてしまった。
「やろう」と眼鏡をおしあげながら新治が言った。地下の湿気で、彼のレンズは真っ白だ。「おれたち、もう帰る場所だってない。サウロンに見つかるのは時間の問題だ。装置がなけりゃ……」
そこで唾を飲み、新治は言葉をつまらせたが、仲間たちには彼の気持ちが伝わった。
それで利菜はもう一つの可能性について話した。自分がヒッピを見つけたのは偶然ではない。もしヒッピが、それがたとえ戦争が起こる前の時代にしろ装置を受けとったのなら、異常を感じ取って、自分たちを(別の世界の仲間を)呼び寄せようとするはずである、と。
「ヒッピのやつが過去でゲートを開いてるってことか?」と達郎。
利菜はうなずいた。「そうでなきゃ、あの装置を送れたはずがないと思うのよ」
利菜はもう一度濁流に向き直った。
「あれに入るのか?」と寛太が喉を鳴らす。
こうしてみると、そのゲートはいかにも邪悪な存在に見えた。彼らを手招くように闇を伸ばしてくるし、不気味な音まで漂っている。ぼおお、ぼおお、ぼおお。その音は利菜に台風の夜を連想させる。
一同はゲートに近づいた。佳代子が寛太にささやく。「いくらあの子でもヒッピを見つけられるの? こんどは装置がないのよ」
パーシバルが松明を濁流にいれた。ドロドロとした感触がする。向こうに誰かがいて、ひっぱっているようにも感じる。引き抜くと火は消えていた。先端はぼろぼろに腐り、指でつつくと崩れてしまった。
ペックが振りむき、利菜にいった。「これでは入れない。どうやってあいつに会いに行く」
「あんた入るのは無理だっていうくせに、ヒッピに会うのは諦めないわけね」
利菜はヤクトゥースの松明を受け取った。
「そいつまで消えたら真っ暗だぜ」とパーシバルがささやいた。
「松明には意志がない」と彼女は答えた。「あたしはちがう」
利菜は目を閉じると、松明が燃え上がるさまを強く描いた。両手で剣を突き出すように濁流へとつき入れる。闇は意志を持って彼女の腕にまとわりつく。利菜は不安を押さえ込みながら、力の充実を待った。すると、暗闇の先に確かにヒッピの存在を感じるようになった。ああ、あいつも待ってる、と彼女は思う。けれど、それはかすかな触覚でしかない。
昔のような力がなくて、今は装置すら手元になかった。大人になって、自分がだめになったと知るのはつらいことだ。彼女は自分をうけいれ、乗り越えようとする。師匠、と無意識のうちに念じている。この二十五年がまちがってたっていうんならあやまるよ。でも一度でいい、力を貸して。この連中をあいつに会わせてやりたいの。
利菜は祈りをささげるような面持ちで、松明を引き抜いた。その先端では、炎が燃え盛っている。佳代子が感嘆の声を上げ胸をなで下ろした。耳元で、だからって、過去に行けるとはかぎらねえぜ、とテドモントがささやいた。
利菜はふりむいた。
「ゲートを操るのは意志の力なのよ。ヤクトゥース、紗英のことは頼んだわよ」
「わかった。世界のことはおまえたちに任せたぞ」
ヤクトゥースの言葉は安易にうなずくには重すぎるようだった。それでも彼女は彼と握手をかわした。
「本当にこんなものが過去に通じてるのか?」と達郎はゲートを見上げている。それは彼らの不安をうつすように大きくなったようだ。
利菜は松明をペックに渡し、ゲートに向き直る。
「通じてるんじゃない。つなげるのはあたしたちよ」
「祈ろう」ペックは新治とパーシバルの手を握った。「ここまで来るのは賭けだった。今は成功することを祈るしかない」
「向こうには彼がいる」と利菜は言った。「ヒッピが待ってる。みんな信じて」
彼らは手を握りあい、心を一つにしようと精神を集中させた。数珠繋ぎとなり、過去の世界で自分たちを待つ友人のことを一心に念じた。利菜はずぶりと手を濁流の中につきこんでいく。細胞がとけだし、骨や血液が、ゲートに流れ出していく。そのまま濁流の中に腕をつきこませていった。
利菜がゲートにのまれると、彼らは一瞬のうちに姿を消した。
後には彼らの無事を祈るヤクハタ人だけが残っていた。
□ 十七
出口が近づくほどにヒッピの存在はますます濃くなってきた。利菜は大人になったヒッピにとまどう。自分より十才も若い友人に会うのは妙な気分だ。記憶を取り戻したことで自分が変わってしまうのが怖くもあった。純子、秀ちゃん……利菜は家族を思い、それから元の世界に二人が居ないことを思い出し涙ぐんだ。
ヒッピ、助けて
最初はか細いつながりだったものが、高速道路ほどに太くなる。ヒッピなら何とかしてくれるそんなあり得ない思いが彼女の心を急かしていた。これまで彼女を支えていたものはふっつりと倒れて、今心は揺れに揺れていた。そんなふうにヒッピを頼るのは、なんだか怖くもある。出口に向かうほどに自分がちっぽけになって行くみたいだ。古い友人の存在を感じるに及んで、彼女の心はすっかり折れかけていたのだった。
ゲートを抜け出たとき、彼女の目の前にあったのは、青年になったヒッピの若々しい顔だった。利菜はとたんに涙につまったけれど、夢中で駆けて彼の首に腕をまわした。
「利菜」とヒッピは驚き喜び戸惑う。利菜に続いて佳代子たちも出てきた。
彼の右手には装置がある。突然こいつが現れたときには驚いたが、すぐに自分のすべきことを悟って(疑問はやまほどあったが)、ゲートを開いて待ちかまえていたのだった。
利菜もヒッピの肩に手を置いてふりむいた。そこにあるゲートはヒッピの希望をうつすように七色に輝いている。ヒッピもまた大人になった利菜に戸惑っていた。
利菜の頬に手をやり、泥を拭う。
「君に会うときは、血まみれか、煤まみれかのどちらかなんだな」
「好きでなってるわけじゃないよ」と利菜は泣き笑う。
「君が、君たちが来ることはわかっていた」
とヒッピは古い絆で結ばれた仲間たちをかえりみる。それは利菜の存在を直接感じていたからだ。自分の肉体のように、あの子のことを感じるのは久しぶりのことだった。彼の戦友が、どのように変わっているのか、期待と不安がいりまじり、指先までしびれるようだった。だが、利菜がやってくるということは、サウロンが戻ってきたということでもある。ヒッピはこの十年あまりの年月、あいつをどうやって殺すかについて思いを巡らしてきた。冷静な自分をたもとうと、精神力を磨き上げてきた。その意味では、利菜とちがって準備万端ととのえていたと言える。
涙がにじみ、ヒッピはそんな自分にうろたえる。利菜が帰ってくるのはうれしい。また会えたのは。今となっては子どものころのイメージしかないのに、胸のざわつきは少年のようだった。けれど、彼はゲートの向こうに身近な三人の存在を感じてもいたのである。
「なぜ、あいつらがゲートを抜けて来るんだ?」とヒッピは眉をひそめて訊いた。利菜は答えることができなかった。その前に最後の三人がゲートを抜けてきたからだ。ヒッピはすぐにゲートを消したが、目前の男たちにとまどっていた。予想したとおりの三人だが、彼の知る人物とは違ったからだ。三人ともずいぶん老けてしまっていたし、おまけに傷まみれである。
「おまえたち」とヒッピは言った。「ペックに、パーシバルか? テドモント!」
ヒッピは床を飛び越えるようにして、テドモントの肩をつかんだ。右腕がない。おまけに重傷を負って、満足な手当もうけていなかった。
「誰にやられた!」
「こみいったことを訊くな」
テドモントが笑うと、口の端から血が垂れた。
「すぐに寝かせろ。あのソファがいい」
ペックとパーシバルはものも言わずに生き生きと動いた。ようやくリーダーの指示がきけて、むしろうれしいようだった。
「利菜……どうなってるんだ。さっき、この装置が、ぼくのてのひらに現れた。君が来るのは予感していたが、だが……」
「ヒッピ」利菜は大人になりすぎた自分を恥じらうように彼の腕をとる。「あたしたちは未来から来たのよ。あんたの身に何があったのかは、彼らから聞かなきゃ」
ヒッピは利菜の視線を追った。それですぐに悟ったのだった。
「ゲートを使ってか? 過去に来たというのか?」
利菜はうなずいた。
ヒッピは戸惑いながらもふりむいた。ペックとパーシバルが、ソファの前で立ち上がっている。みな無言で自分を見ていた。八人ともが、自分よりも十歳ばかり年をとっている。ペックとパーシバルは、幾分精悍さが増したようだ。彼らの苦労を思い、胸が痛んだ。自分の身に何が起こったか、予想できたからだ。そうかとヒッピはつぶやいた。彼らを守ってやれなかったことを、残念に思った。
□ 十八
まず話したのはペックだ。このちょうど一年後に、ヒッピが死ぬことをなるべく正確に語ってきかせた。
利菜たちも話に加わった、二つの世界がふたたび荒廃をはじめたこと、サウロンが戻ってきたこと。それは話していても心苦しくなるようなことばかりである。それでも一同が話を続けられたのは、真剣に耳を傾けているヒッピの姿があったからだ。リーダーを失ってからも、彼らのグループは結束を守り抜いた。そのことに、ヒッピは満足したようだった。
「今、話したとおりだ。君が襲われるのは、一年後になる。ぼくが話したことで、未来は若干変わるのかもしれないが……」
話の途中でヒッピは装置をとりだし机に置いた。彼らは部屋の中央のソファにそれぞれ腰掛けている。部屋のすみからはテドモントが横たわったまま、今や彼にとってもリーダーとなった、ヒッピのことを見詰めている。
一同はようやく手に入れた装置を眺めやる。
ヒッピは、「みんな死んだんだな……」
「そうだ。都は壊滅した」とパーシバル。「今度ばっかりは、都の民も生き残れなかった。だが、おれたちは過去に来ることができた。おまえは一年後に死ぬことはないんだ。生き延びておれたちとそのときを迎えて欲しい。いや、過去にいるおれたちに事情を話して、サウロンを迎えうつ準備を始めるべきだ」
達郎が何か言いたげにしていたが、利菜は二の腕に手をそえて黙らせる。ヒッピが何を言いたいのかわかっていたからだ。ヒッピも彼女に考えを伝えるみたいに顔を向けてきた。
「君が死んでから、パダルやモタも変わったよ」とペックは話を続ける。「急に大人になったっていうのか……頼れるやつがいなくなって、それぞれがしっかりしなけりゃって思った。君が見る未来ではちがうかもしれないが」
「違わない」とヒッピは言った。重い断定の口調だった。
「違わない? 何をいってる? ぼくらは未来をかえなけりゃあ……」
「ぼくはそうは思わない」
「なんだと?」ペックは本気で腹を立てた。「何をいってるんだ! ぼくらがここまでどんな思いで……」
「よくわかっているよ」ヒッピは席を立った。「少し待っててくれ。みんな少し身ぎれいにした方がいいな。治療も必要だ。テドモントの怪我は重い。医者を呼ぼう」
ヒッピは部屋を出て行った。ペックたちは呆然と彼を見送った。利菜は達郎たちをうながして、テドモントの様子を見に行った。ペックたちも信じがたげに首を振りながら、ついてきた。
ペックが彼の手を握った。「テドモント、しっかりしろ」
「おれのことはいい。だが、あいつはなんであんなことを……」
テドモントは利菜を見た。
「おまえはあいつの考えが読めるんだったな。今もか?」
利菜はうなずいた。誰よりも深くヒッピの心情を理解していたが、答える気にはなれなかった。ペックたちの落胆はそのぐらい深い。彼女は腕をくんで、ヒッピの消えた扉を見つめている。彼が部屋を出たのは、テドモントの治療が早急に必要だったこともあるが、ペックらの頭を冷やさせるためでもあったのだ。
過去に戻っても、利菜はヒッピとの深い心のつながりを保っている。だからこそ、このことは彼の口から言わせた方がいいと思った。そのことをペックたちも望んでいるだろう。
□ 十九
ヒッピはしばらくたってから戻ってきた。彼は召使いに、お湯や治療に必要なものを用意させた。信頼できる医者を呼んだ、と彼は言った。
ヒッピが自分の考えを話そうとしても、パーシバルは激しく怒っていた。
「未来がどうなってるか、おれたちの話をよく聞いたのか」
「過去を変えるなら、今いる君たちはどうなる」
パーシバルも言葉につまった。「だが、サウロンが倒せるなら、あいつらとまっとうに戦えるなら……」
「それはちがうぞ、パーシバル」
とヒッピはたしなめた。パーシバルは怒っていたのに、なんだかうれしくなるような胸のむずがゆさをおぼえて困った。彼はまた話ながら激昂した。
「おまえはあんな未来を肯定するつもりなのか。みんなが死んだ未来で満足か!」
「そういうことが言いたいんじゃない。起こったことは、変えるべきじゃない。おまえに必要なのは、受け入れることじゃないのか」
「死ぬのはおまえなんだぞ」
「仕方ない」
「仕方ないだと」パーシバルは立ち上がった。利菜が手を押さえたが、とまらなかった。「おまえが死ぬのが仕方ない? 未来で大勢死んで、王都もなにもかも壊滅するのが仕方のないことなのか!」
「パーシバル、どんなに辛かろうが、やっていいことと悪いことがある。おまえがやろうとしているのはやってはいけないことだ」
「おまえに生きてて欲しいって思うことが、そんなに悪いことなのか?」
パーシバルは涙をこぼした。彼はひっそりと泣き始めた。
ヒッピは少し黙り、膝の先で合わせた手を見つめた。
「おれが逆の立場でも、おまえに生きていて欲しいと思ったろう。だが、現実に生き返らせようとはしないだろう。その方法が自分にあったとしてもだ」
ヒッピの声はしだいに力強くなっていった。彼はだんだんと身をおこす。みんなは彼の言葉に引きこまれた。
「自分は起こったことは、全てが必然だと思っている。それが、どんなことだろうと、自分にとって必要だったのだと思ってきた。それでよかったと思っている。過去に戻りたいという人間は、今を否定する人間だ。そんな人間に建設的なことなどできはしないからだ」
「ヒッピ、これは政治の話なんかじゃない。何もない世界で何を建設するというんだ?」とペックは言った。
「おれを生き返らせることで、おまえたちは全て変わってしまうんだぞ。それでもいいのか?」
「もちろんだとも! いいに決まってるじゃないか!」
「それで世界の崩壊が進んだとしてもか」
と彼は言った。ペックは思わず利菜を見た。彼女はためらいがちに口を開いた。
「つまり、あたしたちのやっていること――ゲートを開いたり、こうして過去にきたりすることも、世界の崩壊に荷担していることになるのよ。子どもの頃だって、ゲートを開くたびに、世界のねじまがりはひどくなってた。過去を変えたりしたら、どんなことが起こるかわからないのよ」
ペックたちは納得していないようだった。
「おれは過去に起こったどんなことも否定するつもりはない。自分が一年後に死ぬのなら、世界にとってそれが必要なんだろう。おれはこのままでいい」
「何をいってるんだ」ペックは呆然とした。
「おまえの死が世界にとって必要だと? そんなことはくそくらえだ!」
パーシバルは若い友人にむかって怒鳴った。彼らは意外な展開にとまどっていた。サウロンと戦うには、ヒッピの力が必要だ。だが、当の本人が蘇りを拒否している。
「過去を変えること、おれたちだって、賛成じゃない」と達郎が言った。パーシバルは激しく彼を睨んだ。「だけど、サウロンに対抗するには、おまえと利菜が必要なんだ。子どもの頃だってそうだったろ? おまえぬきじゃ、あいつにはかないそうもない」
また沈黙が落ちた。
ヒッピは顔を上げ、一同に力強い視線を向けた。
「では、自分のためにみんなが変わってしまうのか? 過去にしてきたこと、がんばったことも、思いまでも――すべて無しになるのか? そんなことは認めない。おれは自分の過去を変えようとするやつがいたら、どんなことをしてでも戦うだろう。サウロンと同じように」
彼はみんなに向けて話していた。それは政治家になった彼の見せる新しい一面でもあった。利菜はなにやら満足したようにうなずいた。
「過去を変えるということは、そんなに簡単なことじゃない単純じゃない。考えてもみろ、帝国がやったのはそれだったろ。サウロンは、未来を支配する皇帝と戦っていた。そして、あいつに賛同する味方は大勢いた」
「あいつが正しいとでも?」
「そうだ。少なくともあの頃のあいつの考えはまっとうだった」
「そんな……」ペックは絶句する。彼は利菜に向かって、「この馬鹿になんとかいってやってくれ。こいつを説得してくれよ」
「無理だよ。あたしも彼と同じ意見だから」利菜は首を振った。「心がつながってるっていうのも、やっかいなものなんだね。あんたの気持ちが残らずわかるんだから」
「ああ」とヒッピはうなずく。「そう思うよ」
「君が生き返るんなら、なんでもしたかった」とペックは言った。「やっと巡ってきたチャンスなのに」
「チャンスがたとえあろうとも、なんでもしていいわけじゃない。それじゃあサウロンと同じじゃないのか。あいつはぼくたちを、そして、ぼくたちの世界を否定してる。自分を信じなければ、あいつとは戦えない。なのに、自分でも本当はまちがっていると思っていることをやるのか?」ヒッピは首を振った。「悪いがそれはすすめられない。それではどのみち勝ち目なんてない」
最後にヒッピは、ぼくらが正しいのなら、また味方する力もあるだろう、と言った。ということは、彼も自分たちに荷担する力に気づいていたということだ。
利菜はヒッピの意見に賛同しながらも、重責が自分の胸にのしかかるのを感じた。彼女は慎重に仲間たちを見た。みんなヒッピの言葉を噛みしめるように沈黙している。
ペックはうつむいていた。落ちた肩は、落胆を伝えている。ヒッピの死を誰より悔やんだのは彼である。けれど、だからこそヒッピの気持ちがよくわかったのだ。ペックは自分の考えに納得するみたいにうなずいた。彼はそういうやつだった。自分の死でも、受け入れようとするやつだ。だから、みんな従ったのだ。彼は欲のない人間で、そんな彼のことが大好きだった。
ヒッピは、親友のそばに行き、そして年老いた肩を抱いた。
「立派になったんだな、ペック」心なしか声が揺れたようだった。「今のおまえの姿をタットン博士に見せてやりたいよ」
「ぼくは同じ言葉を、未来の君に言いたいんだ……」
「悪いがそれはできない。今の君を変えたくないんだ。そのままがいい、そうだろう?」
「やっぱり、君はタットン博士の弟子なんだな」とペックは吐息をついた。
「ぼくだけか?」
ヒッピが手をさしだした。ペックはしばらくその手を見つめ、やがて握った。
「ぼくもそうだ」
二人はタットンの言葉や残してくれたものを、無言でかみしめ合った。達郎は首をふって、寛太は吐息をついて、ソファに身を沈めた。新治はくたびれたようにまぶたの上をこすっている。利菜と佳代子は少し視線をかわして、そろって額の生え際をかいた。
「わかったよ」パーシバルも諦めたようだった。彼はしばらく宙を見ていたが、そっと息をつき、ヒッピに目を向けた。彼らのリーダーに、「わかってるんだ。未来を変えるなんて、突拍子もない話だって。それが最悪の未来だとしても自分がなくなるわけだから。自分の過去がみいんななしなんて、おれは想像つかないね」
「だから、おまえはリーダーになれないんだ」テドモントが苦しげに言った。みんな彼の存在を思い出したように見た。「想像力の欠如、問題だな?」
けれど、パーシバルは破顔する。「だけど、おまえに会えてよかった。ずっと会いたかった。その願いが叶ったんだ。これ以上は……」
「分不相応ってことよ」利菜は立ち上がった。テーブルの上の装置を手にとった。「願い事は少なめがいいのよ。後は自分でなんとかしなけりゃね」
ヒッピがテドモントの枕元に行った。テドモントは無言で彼を見上げた。「おまえはこれから死んじまうのに、おれのほうが重傷ってのはどういうわけだ?」
「おまえは昔から慌て者だからな」
「ばかめ」テドモントはそっぽを向いた。泣いているようだった。
「おまえに会ったら、右腕に気をつけるよういっておくよ」
テドモントは笑いたかったが、笑えなかった。「よけいなことはいうな、馬鹿野郎」
ヒッピは黙って、彼を見ている。
「おまえじゃなくて、死ぬのはおれでよかったんだ」唇を噛む。「おまえが生きてたら、世の中はずっとましだったろう」
ヒッピが彼の胸をなでる。「おまえは見かけによらず、おセンチなやつだよ」
「……ばかめ」
医者が来たようだった。ヒッピは迎え入れるために玄関に向かった。
「みんなはがっかりするだろう」とテドモントが言った。
「ああ。だけど、満足もするんじゃないかな」とペックはうなずいた。「あいつらしいやり方だ。当たり前かもしれないが、あいつは変わってない」
□ 二十
テドモントの治療は夜までかかった。
みんなにとって、久しぶりにゆっくりする時間でもあった。利菜とヒッピは外に出た。考えてみると、二十五年の昔にだって、こんなふうに落ち着いた時間はなかった。利菜は照れたように笑って歩き出した。ヒッピは少し後からついてきた。
夜風があった。頬を吹かれ髪がたなびく。ヒッピは彼女の黒髪を、美しい、と思った。泥を落とし、傷の手当てもしたが、薄汚れているのは今も昔もかわらない。それでもだ。きれいになったな、と彼は思った。
道を歩くのは利菜と二人。辺りをはばかる人もない。石畳に靴音が鳴る。火照る体に、夜風がやさしい。
夜の都をゆく。月があって、通りには光と影。きれいな晩だな、と彼は思う。
「すまないな」と言う。「君に会えたら、百万言をつくしたかった。なのに言葉が出てこない」
「ばかね」利菜が言った。「あたしたちはここでつながってる」胸を叩き笑う。「気持ちだったら、もう伝わってるよ。言葉はいらない」
ヒッピはうなずいた。二人はまた歩き始めた。
「結婚してるのか?」
利菜はうなずいた。
そうか。
亭主はいい人か?
そうか。
今、幸せか?
そうか。
ヒッピは短い質問をして、利菜はただうなずいた。たわいもない時間だが、彼にとっては忘れられない一夜となった。
川沿いの道にでた。
ヒッピ……、と彼女はつぶやいた。利菜は川風に吹かれながら、ヒッピのことを見る。彼の青い瞳、風にたなびく金色の髪が好きだった。
「あたしはあんたのことを忘れてた。あのとき、サウロンがいなくなって、元の世界に戻ったときに、あたしたちは自分の記憶を消したのよ。元の生活に戻るために、あんたのことを……」
「利菜」彼が手をとった。「いいんだ。君の気持ちだって、ぼくにはわかってる」
「あたしは怖いよ。みんないなくなって、なのに自分はなんの準備もしてこなかった。あいつを倒す方法なんてない。ビスコものっとられちゃった。今度は、きっとあたしもサウロンに操られる。そうなるに決まってるって、わかるのよ」
ヒッピはしばらく無言だった。装置をポケットから出した。彼は利菜の手をとり渡した。
「これは君の手に」
「でも、あんたがいないんじゃ、きっとあいつには……あたしには耐えられない」
「そんなことはいうな。君が頼りだ」
「あんたが生きてたらよかったのに」
まぶたに手を当てる。
「ぼくも君とともに時間をかさねたかった。でも、それは叶わぬ願いだ」
ヒッピは川面に視線を向けた。水がたゆたい、月光が闇夜をあたたかく照らしている。二人でいるだけで、世界は美しい。
「やっぱり蘇る気はない?」
「ああ。すまない」
「未来に戻ったら、あんたはいないんだね。あたしはさみしいよ。マーサおばあさんにも、今は生きてるはずなのに、会いに行くこともできない。あたしは後悔ばかりしてる。情けないよ」
「だけど、ぼくは君を誇りに思ってるよ。二十五年がたっても、君は変わってない。精一杯やってる。だから、君に託したいんだ」
泣き笑いをした。「あんたは他人にも厳しい奴だよ。それが自分の欠点だって、知ってた?」
「ああ。死ぬまで治せなかったのが、残念だよ」
「馬鹿だね」利菜は泣いた。「あんたは損ばかりしてる。だから死んだんだって、わかってる?」
「ああ」とヒッピは言った。「今はよくわかってるよ」
二人は夜道を歩いた。いつまでも。二人とも、どこまでも歩ける気分だった。現にそうした。
◆第二十四章 希望の小箱
□ 二十一
最後の協議が始まった。彼女たちがこの最後の集会で持ち出した最初の議題は、未来にどう戻るか、ということだった。ゲートを開くのは問題ない。向こうの世界に残してきた最後の仲間――紗英のことを見つけることは可能かもしれない。中央のテーブルでは、装置が黒光りしていた。もしヒッピのいうような力が自分たちに働いているのなら、彼女らを元の時空に戻そうとするはずである。
問題は、サウロンとどう戦うのかだった。以前の戦いでも殺すことは断念した。
「装置を使って、乗り移りを阻止できないのか」とヒッピが訊いた。
「どうだろうな」達郎は首をひねる。「あいつが乗り移る原理がわからないだろ」
「いや、待てよ」ペックが額に手を当てる。ヒッピが何だと促す。「あのとき、ぼくらはサウロンに支配されかかったろう? あいつはぼくらの精神に入りこんできた。あいつが他人に乗り移る能力だって、その延長にあるんじゃないのか?」
「あれを強力にしたものだって言いたいの?」と利菜は訊いた。
「だとしたら、防ぐことは可能かもしれないぞ」とヒッピが身をのりだす。「ぼくたちはエビエラやマーサに、心を閉じる方法を習った。装置を通せば、同じやり方で防げるかもしれない」
彼らはヒッピの方法について吟味してみたが、実際に乗り移られた者がこの中にはいないのだから何とも言えなかった。
「子どものときみたいにはいかないよ。あたしは装置を使えなかった」
彼女はサウロンと戦ったくだりを話した。三郎がいなければ、今ごろ死んでいたはずだ。
ヒッピが装置をつまみあげる。「あいつの肉体はビスコのものだ。物理的には殺せるはずなんだ。二〇年前は、あいつを攻撃できないと思いこんでいた」
今度はあいつを殺すのね。利菜は装置を受けとる。子どものころ、彼らは心を合わせてサウロンに対抗した。神官たちの行った儀式も、心を一つにあわせることが根本になっている。問題は、サウロンと戦っている最中に、心を一つにしなければならないことだ。してやられるとしたら、心がバラバラになったときだから。
「エビエラのいったとおりだよ」と利菜は言った。ヒッピがこちらに顔を向ける。「装置を使うっていうことは、精神をコントロールすることなんだってあの人は言ったのよ。師匠は平常心を保てっていったけど、殺し合いの真っ最中に集中するのは難しい」
「そうなると、課題は三つになる」とヒッピ。「心を一つに合わせる、あいつを物理的に死なせる。そして、乗り移りを防ぐ」
「ゲートを開こう」ペックが言った。「まずは向こうに戻れなければ話にならないからな」
そう言いながらも、彼女らはしばらく無言で時間を過ごした。サウロンと戦う覚悟をかためるためだった。利菜は少し下を向いた。それでいて、何も見ていなかった。ヒッピがじっと見つめているのはわかっていたが。深海の気圧に押し潰されているかのようだった。手を握ると、冷たい汗に濡れている。かつての対決がよみがえり、本当に身内が冷えてきた。装置を使っても、万に一つも勝てる見込みはない気がした。自分の本心を裏切って、ついてきてとヒッピに言いたくなる。今度は追い出すわけではないのだ、みんなはあいつを殺す算段をしている。
自分たちが世界の命運を握っているような、そんな錯覚を覚えて、心が震えたのだった。
みんなの息が細くなっていた。部屋の空気が重くなる。
「まるでお通夜だな」と寛太が言った。ヒッピたちは顔に疑問を浮かべ、利菜は佳代子と笑顔をかわす。
ヒッピに肩を叩かれる、利菜はそれを合図に装置を取った。
「もう一度、手をつなごうか?」と彼女は微笑みながら言う。一同は、ほっと息をついた。利菜は指の中で装置を転がす、いつのまにかわるい考えに囚われていたのだ。どんなに悪い状況でも、明るい気分にはなれることを思い出していた。「今も昔もあんまり変わんないんだね。だって、やるしかないんだから」
だけど、今は周りに人もいなくて、なんともさみしい感じがする。サウロンを倒しても、世界の荒廃は取り戻すことができない。彼女たちは亡くなった人たちを思い、しばらく瞑目する。やがて思い思いに立ち上がると、互いに手をとり合う。環のつながりを通して、力が満ちてくるのがわかったからだ。あの頃に比べたら、めっきり弱い力ではあったけれど、この絆は確固としたものだ。利菜は自分より大きな存在に祈りを捧げたかった。世界が崩れかけても、仲間たちはここにいてくれる。この絆が断ち切れないよう、誰も欠けることがないように。「なんでもできそうな気がするけど……」と言う。「気のせいかな?」
みんなが声を殺して笑う。
「ぼくらは、まだ心を一つにできる」とペックが言った。「あいつに勝てるかはわからないけど、もう一度やろう」
「議長のいうとおりだな」とパーシバル。「この集いには価値がある、おれたちには。サウロンは納得しないだろうけど」
「これが最後だ」ヒッピは一人一人を見回す。「ぼくはこのグループを誇りに思ってる。ゲートを開こう」
利菜はヒッピに向かってうなずいた。姿勢をととのえ呼吸を深めると、力はますます高まっていった。目を閉じて装置に念じると、環の中央に黒点が浮かび、すぐさま渦を描き出した。装置を扱えたことにほっと息をつく。が、同時に異変を感じもいた。ゲートの向こうから、何者かが働きかけてくる。
サウロンだ!
仲間達が苦しむように膝を折った。利菜が呼びかける前に彼らの姿は薄れて、周囲の景色は乗っ取られていく。部屋の天井は大空に変わり、利菜は雲に近いほどの大空に浮いていた。足元にはイニシエの森が広がっている。幻覚だ、あたしは過去にいるんだから、と思ったが、サウロンが彼女の精神を呼び寄せたのも事実のようだ。上層の強い気流が吹き付いた。正面には映画で見たような巨大な宇宙船が浮かんでいる。船との間には、
「サウロン……」
と彼女は言った。
利菜は自分がまだ佳代子や達郎の手を握っているのを感じていたが、同時に彼らの姿は全く見えなくなっていた。利菜はそっと右手を見おろすが、装置は持っていなかった。本当に精神だけになってサウロンの前に引きずり出されたようだった。
サウロンの口端が少し上がる。「まさか過去にいくとはな。おれも失念していたぞ」褒めているようである。「きさまが装置を持っているのか。それでどうゆう算段だ。おれを殺すとでもいうつもりか」
「そうよ……」と彼女は言った。サウロンは突然激昂した。
「おまえはどこまで馬鹿だ! これ以上、世界に荷担してどうなる! 滅亡こそが人の意思だ!」
利菜はサウロンの畏怖に打たれて腰を折った。そんなことない、と彼女は言ったが、その声はか細く抵抗すら出来ていない。その声を励ますためにも、実体の手を強く握った。みんなはサウロンに痛覚を刺激されて苦しみのたうっていたが、それでも彼女を勇気づけた。
利菜は少しずつ背を伸ばし、腕を左右に垂らし、恐怖に高鳴る胸を張ろうとする。ヒッピの言いたかったことが、今こそわかった。自分たちは過去に行ったけれど、昔に戻れるわけじゃない。だけど、今を素晴らしくすることはできるはずだと信じていたのだ。現実の世界から、ヒッピが頑張れと念じている。利菜は気持ちを強くして、大きく息を吸いこんだ。
「そんなことが人の意思だなんてあたしは信じない! おまえが信じたがってるだけじゃないか!」と言った。「おまえのいうことなんか、あたしたちは信じない」
サウロンは鼻先で笑い飛ばす。「人のいない世界の、何を守るというのだ! なんの意味がある!」
「生きてる人ならまだいるわよ! それにみんなのことはおまえが殺したんじゃないか!」
ほう、と彼は言った。目が奇妙に大きくなる。利菜はその瞳に吸い込まれそうになる。
腕がさっと上がった。
「おれがこうしてもか!」
サウロンが右手を振り下ろすと、背後にあった宇宙船が急降下をしはじめた。利菜は彼の意図を悟って駆け寄ろうとする(すると現実の体も駆け出して、達郎と紗英に手を取られて転んだ)。
「やめろ!」
けれど、彼女は近づくこともできない。空中で手足を掻くだけだった。巨船の動きはゆるやかに見えたが、船首を大地にぶつけるまではあっという間だった。先端を森に押し込んで、中央からメリメリと裂け始めた。小さな爆発が裂け目で起こって、その爆発は次々と誘爆を誘い、重なり合い、巨船を飲みこむほどに大きくなる。。大気が膨張して強烈な爆風が巨大な柱のように立ち上って、彼女を飲みこんだ。
利菜は呆然と下界を見おろす。炎の津波は四方に広がって、森を飲みこむ。巨船は地上に崩れ落ち、大陸を震わすような振動が起こる。炎の波はどこまでも広がっていき、広大な森の先まで到達してしまった。
そんな、と彼女はうめく。あそこには紗英がいるのだ。ヤクハタ人の都もあったはずだ。
「こんなのうそよ……あんたが見せた幻覚に決まってる! あんたが……」
「残念だが、これは現実だ」
サウロンは頭上に浮いていた。利菜は眩しいものを見るように眼を細める。ついで辺りの景色は急速に薄れていった、意識が遠くなるのを感じる。
「世界の崩壊は進んでいる……もはやおまえ達では止められん」
急速に暗くなり、彼女はその闇の中をどこまでも沈んでいった。装置をもって戻ってくるがいい、と闇に轟くようにしてサウロンの声がする。いやだ、おまえなんかに渡すもんかと彼女は頑強に抵抗するが、心は悲しみに満ちて、悲しみは彼女を弱くする。あいつのいうとおり。何もない世界の何を守るというんだろう?
□ 二十二
真っ暗だった。それは彼女がきつく眼を閉じていたからだ。未来から過去の体に戻ってその落差についていけない。吐き気と目眩でしばらく頭を起こせなかった。ヒッピがそばに来て、彼女の肩を抱き起こした。
「あれは現実だったの?」と利菜は訊いた。ヒッピが無言で頷く。利菜はゆっくりと顔を上げた。サウロンは達郎たちにも働きかけていた。あいつに限界まで痛覚を刺激されて、廃人のように唾を垂らし、体を震わせている。不意をくらったとはいえ、なんの抵抗もできなかったのだ。ヒッピは彼女にだけ聞こえる声で、忘れるな、ぼくらが相手にしようとしているのはこういう相手だ。こんどは利菜が頷いた。あいつは強力になっているのだ。月日が経ち、弱体化した彼女のグループに比べて、サウロンはさらに複数の人格と融合を繰り返してきた。結果として手に入れたのは、途方もない意思の力だった。
佳代子の泣き声が静寂を破る。その泣き声で、利菜はようやく意識が醒めた。
「佳代子」と肩を抱く。
「どうしよう、利菜。紗英が、紗英まで死んじゃった」
利菜は佳代子の頭を肩に抱き寄せ、震える唇を閉じた。紗英のことを思い起こそうとしたが、出来なかった。そんなことをしたら悲しみにおぼれてしまう。ぐっ奥歯を噛んで、悲しみも涙をひっこめた。佳代子の頭越しに仲間達を見回す。
「サウロンが働きかけてる今なら、向こうに戻れるよ」と言った。「紗英の仇を討とう」
まるで彼女の意思を支持するみたいだ。もう一つの力が胸裏に流れ込んでくる。利菜も佳代子もその力に勇気づけられる。佳代子は額を肩に押し当てたまま頷いた。けれど、男たちは青ざめた顔でうつむいている。達郎が利菜をみた。瞳には弱気な光。彼の心は揺れて、くずおれかかっていた。利菜が睨むと、達郎は、
「あいつはあの軍隊をひきいて、帝国と戦うつもりなのかもしれない」
「何いってるのよ!」利菜は眼が眩むほどに腹をたてて、佳代子をおしのけ立ち上がる。ヒッピが止めるのも聞かず部屋を横切ると、達郎の腕をつかんだ。彼が振り払うそぶりをみせたので、爪が食いこむほどに強くつかんだ。「帝国なんてもうないのよ! あいつは亡霊にしがみついてるだけよ!」
「帝国が滅んだなんて、なんで言える?」と彼はいいかえす。「あいつが正しいのかもしれない。おれたちサウロンのじゃまをするべきじゃないのかも……」
「あいつは宇宙を滅ぼすつもりなのよ! あいつは何も救わない! あれを見たでしょう! あいつは一瞬でみんなを殺した、世界をめちゃくちゃにした。それが正しいっていうの」
利菜は達郎の腕をほうりだし、全員の顔を睨みつけた。どの顔も意気消沈し、生彩がない。意志の輝きがなくなり、悪い考えに吹かれている。
ヒッピはわずかに離れて静観している。利菜はそのことにまで腹がたった。ここまできて臆病風に吹かれた連中に、ほとほと呆れたのだ。おさそいなんて、今までさんざんくらってきたじゃないか、今さらなんだ、と彼女は思う。どの顔も、まとめて引っぱたいてやりたかった。性悪な口調でいった。
「邪魔をしなきゃいいの? 大人しく死んだらいいの?」
「だって」佳代子が言い訳するように顔を上げる。
「よく考えなよ……」利菜は怒りに燃えた声音でいった。佳代子ははっと目を伏せる。「あいつに好きにさせて、その結果がいいだなんてよく言えたわね! 外を見てごらんよ! これまで何が起こってきたか、思い出したらいい! それでもあいつが正しいっていうの!」
利菜は自分の下にいる達朗を見下ろす。自分の体が怒りを吸って大きくなったような錯覚を覚える。
「あいつは英雄なんかじゃない! やけっぱちになったテロリストとかわらない! 一分の理ぐらい誰にだってあるよ! だからって、何をやってもいいわけじゃない! 人を殺して、世界を滅ぼして、そんなことが正しいはずないじゃないか!」肩が震えた。「そんなことに荷担はできない。私たちは今いる人間なんだから。まささんは、今生が大事だって、そういったじゃない! あいつは全部否定してる。過去も未来も今も。それが正しいことだっていうの?」
「だけどあいつは……」
「宇宙がまちがった方向に進んだって? そんなの知ったことか! あたしは周りにいる人間の方が大事なんだ! 間違った方に進んだっていい!」
仲間たちは怒号に打たれて首を垂れた。どの顔も悪い考えに負けたことを恥じていた。ヒッピが言った。
「自分は未完全だからこそ成長していけるんだと思ってる。過ちも許しも認めないあいつはまちがってるよ」ペックの肩に腕を回し、「ぼくらが未来で死んだとしても、君たちはまだ生きているだろう。君は逃げることで負けを認めるような奴じゃないはずだ。向こうのことは頼んだぞ。ぼくのかわりに……」
「ぼくは君のかわりじゃない。君のかわりはいない」と彼は早口でいった。
「年をくっても頑固はなおらないな」とヒッピが微笑する。
ペックはさっと顔を上げた、息を吐き、少し震えたあとに笑顔をみせた。「ますます意固地になってるよ」
おれたちはグループだ、とパーシバルがつぶやいた。不確かな世界で、それだけが確かなことだった。みんなは自然に手を伸ばしあい、円環をかたちづくる。
「未来に戻ろう。あいつと決着をつけるのよ」
ちくしょう、と達郎が呻くように呟いた。「大人になっても、わるいものには慣れねえなあ」
みんなは笑顔にやって達郎を見た。
「あたしたちまだ心をつなげられる。装置だってある」
利菜がふりむくと、ゲートがまだ口を開けている。彼女の隣で同じようにゲートを見つめながらヒッピはつぶやいた。
「エビエラがいったように、思いが残るのなら、ぼくは君たちのために祈ってる」
□ 二十三
ヒッピは集められるだけの武器弾薬を用意した。サウロンは素手で蛮族と戦うような奴だから、接近戦はさけた方がいい。それにこっちに有利な点もある。数が多いということだ。サウロンは過去の戦闘でも、自分以外を頼らなかった。そこで銃を使う者と装置を使う者とに別れることになった。装置を使って、ゲートをあちこちに出現させれば、あいつの裏をかけるかもしれない。別の世界に行くわけじゃない。その場でなら、入口も出口も自分たちで用意できるはずだった。
「あいつがあんな真似をしたのは、君たちを未来に呼び寄せるためだ。きっとこっちをやっつける準備をしてる。もし一手めで仕留めることができなかったら、すぐに別の場所に移動して体勢をたてなおすんだ」
なにしろサウロンは帝国時代からゲリラ戦を行ってきた人物でもある。
ヒッピは奇妙な淋しさに捕らわれていた。胸がスルスルと抜けていく。本当は彼らについていきたい。自分が未来の人間なら、及ばずまでもどんな手でも使って荷担してやりたかった。このときだけは自分の命に未練をもった。そのとき利菜が彼の前を横切って、少し近くで足をとめた。その背中は物を言わずに何かを語っているようだった。利菜は準備を進める仲間たちを見つめている。その手には装置が固く握られている。ヒッピは無言で脇に立った。
このつながりが永遠のように彼には思える。この別れが永遠だとは、彼には思えなかった。
「答えは必ずある。あきらめずに考えつづけろ」と彼女に触れた。
「おぼえとく」と利菜はほほえんだ。
二人は手をとりあい、装置に念じつ、ゲートに向かった。渦の広がりとともに、風が強くなる。どす黒いものの中にかすかな光があった。それはみんなの心に芽生えたかすかな希望の光でもあった。利菜はこう考える。あの光のために、あたしたちは未来にいくんだ。
達郎たちは銃をかまえ、まるで竜の退治に向かう騎士達のようだ。テドモントのことは、パーシバルと新治が抱えている。何か軽口をいっているが、みんなの耳にはよく聞こえなかった。風が強くなっているのだ。
強風にカーテンがはためき、窓が揺れた。みなの不安を映すようだった、風は生き物のように部屋を回り出す。みんなは互いをかばうように寄り添う。見送りはヒッピだけ。かけがえのない時間が終わろうとしている。利菜がふりむくと、ヒッピは風に顔をしかめていた。
「もう一度、君に会えてよかった」
とヒッピが言った。
「苦労して、ここに来たかいがあったよ」
利菜は涙を拭いた。風が彼女の髪を吹き上げて、涙をさらっていく。仲間たちが見せた笑顔には不安が幾重にもからまっていた。
ヒッピは本当の意味で笑えるときが未来にくるよう、祈らずにはいられない。風に負けないよう、声を張り上げる。「期待に添えなくてすまない……!」
「もう十分そってるよ! あんたは、あたしが思った通りの人になってた!」
と利菜は言った。ゲートに手を伸ばしかすかにふりむく。
「さよなら、ヒッピ」
「さよなら、利菜」
仲間たちの姿がゲートに消え、風は途絶え渦も消失した。風圧がなくなり、彼の体は少し揺れる。カーテンはひっそりと降り、ガラスの揺れもおさまった。部屋はさんざん荒れているのに、いつもの夜であるように、静寂が彼を包んでいた。
何もなかったかのように。
誰もいなかったかのように。
ヒッピは立ち尽くしたまま、何もない空間を見つめ続けた。しばらくたつと、彼はランプの灯りを消し、ソファに座るようになる。組んだ手を見つめる。そうしていると、未来に消えた仲間の感触をいつまでも覚えていられるような、そんな錯覚を覚えた。
しばらくすると、ヒッピは組んだ掌に額をつけて仲間の無事を祈るようになる。
□ 二十四
旅は終焉へと近づいていた。利菜のグループは、時のジェットストリームに乗って、結末に向かって突き進んでいる。それがどんな終わりなのかはわからない。滅亡にしろ再生にしろ、世界はどちらかに傾き、自分たちはその均衡をなんとかとろうと頑張ってきた。世界を救うために必要なことは、明確な意思を示すこと。この宇宙が何を望んでいるのかなんて、彼女にはうかがい知れないことだ。ただひとつわかっていること彼女が望んでいることは、これ以上仲間が欠けないことしかない。でもあいつには、サウロンにはたった一人ではかないそうにない。彼女はこれまで会った人たちの名を呼んで、頼むしかなかった。自分に力を貸してくれるように。
ゲートを抜けると、轟々たる雨だった。彼女は丘の上、かつては王城であった城の一角にいる。城は半壊して、過去の情景とは似ても似つかなかった。
彼女たちのいるのはかつての大広間だった。けれど、今は天井もなく、周囲の壁も崩れ落ちて、すべてがむきだしとなっている。まるで、一同の憎しみをさらけ出すかのようだった。
下界にはかつての都がある。けれど、それは荒涼とした廃墟でしかない。廃墟からは色がなくなって、全部が土色に見える。空の雲は厚く、これが雲だとは思えないほど真っ黒だった。それにすごく近い。大気までが地上の異常を感じ取ったかのようだ。大地は微震をつづけ、それで半壊した城も微動を続けている。城を象る石もひどくもろくなっていたから、あちこちで砕けて砂になり、その砂が雨水にのって流されている。気温が異様に高い。宇宙船から放たれた兵器によって、未だに地表が熱を持っている。それで雨までもが生暖かく感じられた。熱の影響で、空気は対流し、雨は複雑な螺旋を描いて落ちてくる。利菜ははためく服を感じながら、しっかりと装置を胸に抱き、そして、少し高い塔の辺りで一同を見おろすサウロンを見上げる。あいつを見たら、きっとひどく憎しみを感じるだろう、平静ではいられないだろうと思っていたが、彼女の胸は奇妙な静けさを保っている。その胸に沸いたのは恐怖と羨望だった。何が起ころうとも信念を保ち、正々堂々の勝負を挑めるあの男の姿にかすかな憧憬を抱いていた。
「上原!」
怒号が落ちてくる。怒号は一種の力をもって、メンバーを叩く。そのときにはみんなは利菜の元に集まって手を取り合い、心を一つにして偉大な男を見上げていた。パーシバルと達郎新治は銃を持って一同のわずか後ろについた。
「もう終わりにしよう」利菜は彼に対抗するかのごとく背筋を伸ばす。「これで最後よ」
それは仲間にいったとも、サウロンにいったとも、どちらにも取れたが、サウロンは深くうなずいた。「いいだろう」
利菜は装置に念じる。サウロンの立つ足場が崩れる。達郎たちはその瞬間を見逃さずに、素早く銃を上げ立て続けに撃った。サウロンの身は一瞬中に投げ出されたが、わずかに手を挙げただけで全ての弾を食い止めるた。
「くそ、殺せない! 弾丸じゃあ無理だぞ!」
パーシバルは銃を投げ捨て円陣に加わる。サウロンが崩れた足場を駆け抜けるように降りてくる。新治はその光景に気をとられていたから、寒気が背筋をおそったときは、全てが終わった後だった。ダンプの衝突にも似た衝撃が、全身をくまなくおしつぶした。メキャリ、メキャリという音を聞きながら、死の淵を越えていく、経験したことのない痛みとともに、全身の骨がつぶれていった。彼はその場に崩れ落ちた。
「新治!」
達郎が銃を捨て弟を裏返す。新治が生きていることを願ったのだが、彼の口から漏れたのは、ああ、という短い嘆息だけだった。新治の前半身は無惨につぶされている。達郎は頭ではなく直観で、弟の死を理解した。達郎は無言で歯を食いしばり、雨の中に無音の罵声を吐き捨てて、仲間の環に加わる。
新治の死に胸が痛む。利菜は仲間と力を一つにしながら、装置に念じる。音速の衝撃波を描き出す。サウロンもまた力を解き放ち、二つの力は両者の中央でぶつかりあう。利菜たちは、空気の圧力に押されながらも足を地に押しつけて装置に力を送り続けた。二つの力はぶつかりあい大きな球体になり大気を振動させている。
利菜は雨の滝の中にいる。雷がいくつも走って仲間の姿を照らし出す。みんなの体が震えている。サウロンの力におされているのだ。装置に力をおくるたびに疲労が脳の中で噴き上がるようにたまっていく。眼は充血し顔は血膨れしたように腫れ上がる。
(駄目だ、このままじゃあ押し負けちゃう)
突然肩を叩かれてよろめいた。頭上の雨が凍って、雹が降ってきた。最初は小さな粒だったが、直ぐに巨大な氷塊となる。氷の固まりに頭を打たれると、意識の集中がついにとけた。
サウロンの衝撃波は一同の力を飲みこみ見えない津波となって一同を襲った。利菜はとっさにその波を砕こうとするが、とても間に合わない。全身を切り裂かれながら宙を回転し、地面にたたきつけられる。
「くそ!」
利菜は直ぐに跳ね起きようとした。雨と血が眼に入りこんだ。彼女は片目をしぶりながら、装置を手探りで拾い上げる。佳代子、寛太、ペックが手元に集まってきた。三人は利菜を守るようにして取り囲む。彼女は両手を組み合わせて、装置に念じる、両膝をついて、まるで祈りを捧げるようなかっこうだ。利菜は他の仲間が動かないことに焦りを覚えながら、床面の水流を操った。水は逆流して立ち上がり、サウロンの体を包みこんだ。利菜はさらに水を集めて、圧縮し、水圧をどんどん高めていった。
サウロンは水の球体の中に浮かんでいる。水の中で手を伸ばし、瓦礫を操りはじめた。石のつぶてが空を切った。
「くそ、平気なのか!」
寛太の額を大粒の石がうった。利菜たちは悲鳴を上げて、互いの体をかばいながら身を伏せる。利菜は三人の下敷きになりながらもサウロンを見上げ、水球を凍りつかせていく。周囲で渦を巻いていた瓦礫も、コントロールをなくして四方に散った。サウロンは熱を念じて氷をとかしている。彼女は負けじと力を送るが、そのとき足首で激痛がはしり、骨の折れる音がバキリと響いた。右足が真反対を向いている。腱もねじきれてその激痛で意念がとけてしまった。サウロンの体を取り巻いていた雨水は、水風船がやぶけたみたいに周囲に流れ落ちていった。
「力を貸して……」
と利菜は最後に残った仲間たちに呼びかける。彼らは跪いたまま、手を重ね合わせる。利菜は大気に満ちた電流をかきあつめた、巨大な電光が幾本もの竜のように大気を駆け、サウロンの頭上に落ちてくる。サウロンは中途で方角を変える。竜は広間の床をのたくった。
利菜は雷を抑えようとしたが、そうする前に足元が崩れ、下の階層に転がり落ちていった。
□ 二十五
すぐに目が覚めた。穴の開いた天井から、雨水が流れ落ちていたからだ。その小さな滝が彼女の体を打っている。利菜は瓦礫に埋もれていて、崩れた石場が山のようになってその上に彼女はいた。まるで自然の墓標か祭壇のようだった。体は傷つき、疲労もあって、もう動くことも出来なかった。
「利菜、しっかりして」
佳代子が瓦礫をどかしている。利菜は右手を意識したが、あんな目にあっても装置は離さなかったものらしい。
「みんなは……」と彼女は訊いた。自分の声の弱さに驚く。「寛太、達郎……」
と呼んで咳き込む。
「利菜、みんなはもう……」
といって佳代子は涙ぐむ。利菜もみんなの存在を感じないことに気づいていた。けれど、呼びかけずにはいられない。
佳代子は石を持ったまま涙を拭う。「こんなことになって……あいつは凄くなりすぎてた。あたしは、今度もなんとかなると思ってたけど」
辺りは真っ暗だった。天蓋に穴の空いたその場所以外は。広間に落ちてきたようだが、王宮に面識のない二人にはなんのための部屋なのかわからなかった。窓ガラスは全て砕けていたし、壁も方々で崩れていたから、風がビュウビュウと吹き込んでいる。その闇の奥にさらなる暗黒が生まれて大きくなっていく。
佳代子が立ち上がる。おびえながらも決然とした表情。
「佳代子、だめよ」
佳代子はいうことを聞かずに瓦礫の山を下りていく。ゲートは風雨を飲みこんでいる。そこからサウロンが姿をあらわす。荒れ果てた広間に彼の靴音が高く響いた。まるで死闘を交わした後ではなく、戸外を散策しているような静かな足取りだ。利菜は倒れたまま。目尻から涙がこぼし、その涙が雨のなかにとけていく。「ずっと側にいてくれたじゃない。今さら一人にしないでよ……」
その声が聞こえたのかどうか、佳代子は少しだけふりむいた。彼女はもう闇の中に踏みこんでいたから、利菜からは表情が見えない。「佳代子……」利菜は彼女の顔を見ようとしているのか、後を追おうとしているのか、手をついて身をおこし、足を引きずり山を下りようとする。
その間にもサウロンは直ぐ側まで来ていた。南から吹き込む風が彼の頬を打っている。「小僧の助けがなくばなにもできまい」かつてビスコだった男は、不思議なほど表情の消えた顔をもたげた。「こうなることはわかっていたはずだ」
「あんたには装置なんて必要ないじゃない」佳代子がたちはだかる。「装置なら渡す。だから……せめて、利菜だけでも……」
「だめよ、佳代子……」彼女は瓦礫を降りていく。「そいつに装置は渡せない!」
「だって……」
佳代子がふりむくのと、サウロンが歩み寄り、その心臓にナイフを突き刺すのは同時だった。大振りのナイフが佳代子の胸骨をたやすく貫いて、心臓を水平に割った。佳代子は声も立てずにサウロンの腕に寄りかかった。
「佳代子……!」
利菜は手をついて首を伸ばした。そのとき雨風の音が急に聞こえるようになった。友人の背中から、血塗られた刃が飛び出していた。利菜は夢中で地面をかいて佳代子の元に這い寄った。
サウロンはそんな彼女を冷たく見おろす。
「今さら一人助かろうなどと、どういう了見だ」サウロンは佳代子を投げ捨てると、利菜の喉首をつかむ。「おまえたちにはおれを止められなかった。それがどういうことかわかるっているのか」
利菜は装置に念じて、衝撃波でサウロンの頭を打った。けれど、それで仕留めるには彼女の力は弱まりすぎていたようだった。利菜は地面に叩きつけられる、サウロンから少しでも離れようと、そのまま夢中で這いずった。
サウロンは何事もなかったかのようにこめかみを拭った。
「みんな死んだんだ。そうだろう、上原」
ぎょっとしたようにふりむく。事実だった。装置をもつ彼女にはいながらにして外の様子をしることができる。彼女の仲間たちはみんなこの世にいなかった。紗英も。全てが灰になったとき、あの子だって死んだのだ。一度も、目をさますこともなく。本当は知っていたのだ。みんな知っていた。でも言えなかった。
「ちくしょう!」利菜は仰向けになり、左足をついた。その足に全身を引き寄せるようにして身をおこす。「おまえなんか――!」
巨大なハンマーで叩かれたような衝撃が全身を襲い、背後の壁に叩きつけられる。背中の向こうで、ガラガラと壁が崩れた。うっ、と利菜はうめく。自分が死んだと思う。
床にはいつくばったときも、彼女はまだ生きていた。けれど、内臓が破裂している。カッと血を吐いた。
「サウロン……」血塗られた歯の隙間から、彼を見上げた。
サウロンは激しく怒りに燃えて近づいてくる。
「きさまは馬鹿だ! いたずらに仲間を死なせて、それで世界を救ったつもりか! ガキのころの方がまだましだったぞ!」
「燃えろ!」
利菜は装置をにぎりしめて狂ったように叫ぶ。
燃えろ! 燃えろ! みんな燃えちまえ!
「本性をみせたな! それが人の本質だ! 破壊が本性だ!」
「黙れ! 燃えて消えちまえ!」
燃えろ!
激情をそのまま装置に叩きこむと、右腕の激痛とともに、紅蓮の炎が建物に燃え広がった。恐ろしいほどの高温が瓦礫を消し炭に変えていくが、サウロンの姿はすでになかった。
利菜は肩をおさえて絶叫した。右腕が、燃えていた。痛みに耐えきれずに彼女は突っ伏した。彼女は疲れた泣き笑いをした。あのときと同じだった。師匠には、さんざん叱られたのに、この土壇場でもうまくできなかった。皮膚が焦げ、肉が燃えている。血の滴る腕を抱えて、利菜は泣いた。炎を避けて、壁際にさがる。炎は壁のようになり、彼女の行く手をさえぎった。半径二メートルばかりの空間だけが燃え残っていた。佳代子の姿も、炎に消えた。彼女に残ったのは自らの生み出した炎だけだった。
サウロンの声が頭にひびいた。
「きさまにはがっかりだ。炎にまかれて死ぬがいい」
消し炭になったきさまから、装置を取り上げるさ、と彼は言った。
利菜は壁にもたれた。炎は、轟然と燃えさかる。岩を溶かすほどの高温に、やがては自分も巻かれて死ぬのだろう。溶けたがれきは溶岩のようだ。彼女をしたうように近づいてくる。しかり。それは彼女が生み出したのだから。慕うのも当然だろう。
熱が肌をこがす。利菜は汗にまみれながら、へっ、と笑った。
もうあきらめよう
と思った。佳代子も寛太も、みんないなくなった。自分は炎のなかに取り残されている。このまま生き身を焼かれて死ぬんだろう。いろいろあったけど、そんな人生もいよいよ幕だ。利菜は娘と家族を思い、これまでの人生を思い返そうとする。なにも出てこなかった。打つ手なし。これが最後なら、そんな最後もふさわしいのではないか。
利菜はぼんやりと炎を見詰めている。炎がゆらめいて、ヒッピの姿がぼんやりみえた。
ヒッピ、だめだった。うまくいかなかった。付け焼き刃じゃ、あいつには
――あきらめるな
「でも、みんな……みんなが」
煙を吸って、咳きこんだ。
「装置を渡して、逃げ出せばよかったの? でも、あたしは、あたしには……」
ここで焼かれて死んじゃうんだ。
考えろ、考えつづけろ。
ヒッピの声がこだまする。髪が燃えはじめた。燃えてとけた右腕の先に、装置がある。だから、感覚は鋭いままだ。利菜は肌の焼ける苦しみ、焼けた空気の感触を存分に味わっていた。全身の毛穴がひらいて、水分が流れ出す。それだって、体温を下げるにはいっかな役に立っていない。痛みに身をよじらすと、腹の中で血があふれ、即席のプールのように波打った。利菜は全身に火ぶくれをつくりながら、それでも考えた。炎のゆらめきはゆったりしている。
ふと疑問がわいた。
そういえば、あいつはなんでこの星がわかったんだろう。
佳代子のいうとおりだった。あいつなら、装置のかわりだってなんとでもなりそうなものだ。なのに、あいつは……あいつは――
なんでこの星にこだわったんだろう?
復讐が本願だったんだろうか? 帝国時代から続いた復讐心に、悪霊のようにとりつかれていたんだろうか? あるいはあいつ自身が、わるいものに憑かれていたのかもしれない。あいつは他人をくらって生きてきたのだから。
そこで思いついた。あいつは人に乗り移る。けれど、皇帝とはちがう。帝国時代には肉体を持っていた。
彼女は少し目を見開く。
そうか、あいつがここに戻ってきたわけは、固執したわけは……
過去に行ったあの時、彼女らはミイラになったサウロンを見た。寛太は、ここでこいつを殺せばいいじゃないか、と言った。彼女は、過去にいるこいつを殺しても、なんにもならないと言った。だけど、今は、今なら――
「馬鹿だった……なんで今になって……」
彼女は炎に囲まれて、もう逃げ場もなかった。涙がこぼれたが、その塩気すらやけどに染みて痛かった。熱が肺を焦がし、呼吸すら苦しかった。ゆったりと右腕をあげるが、指がくっつきあって、開くことができない。
それでも彼女は念じたのだった。
「お願い、あたしをサウロンのところに、サウロンの本体のところに、連れて行って……」
□ 二十六
目を開くと、頬の下には冷たい地面があった。彼女は座りこんだ姿勢のまま倒れていた。まわりに炎はなく、岩があった。身を起こそうとする、全身の皮膚が焼け、関節がうまく伸びない。それに内臓が……内臓がグチャグチャに潰れて、血が溢れているのが自分でもわかる。腹の中を焼かれたみたい。もう長くない。
彼女は顎を上げた。洞穴の奥を見ようとした。目がかすむ。まぶたを閉じた。開いた。何度かやった。焦点が合い始める。もう眉毛も髪も焼けて無惨な姿だった。生命の閉じる末期症状なのか、体が震えている。だから、目がうまく見えない。
早くしないと、サウロンが来る……
サウロンは、自分の体に戻れるのかもしれない。命の危険にさらされたら、なんだってやるだろう。そうやって、生きてきたんだから。
利菜はヒッピのくれたナイフをとろうと、体を探った。右腕はつぶれていたから、左腕だけの、苦しい作業だった。震える指で、留め具を外す。指に痛みが走り、爪が剥げた。早く、早く……と彼女は体を急かす。手足が冷たくなって、感覚がなくなる前に。死ぬ前に、やらなきゃいけないことがある。
利菜はナイフを手にとると、ゆっくりと膝を前に出した。腹の中で、つぶれた内臓が揺れた。血を吐きたかったが、そうしたら、たぶん気力が萎えて、一歩も動けなくなるだろう。利菜は吐き気をこらえて、また、一歩ふみだす。そのときになって、ようやくサウロンが見えた。ミイラになった帝国時代のあの男。
利菜は体を真っ直ぐに立て、膝立ちで進んでいく。唇からは血が零れる。だんだん量が多くなる。
「サウロン……」
と彼女はようやく呟いた。傍らに辿り着くと、左腕を掲げた。
サウロンの腕が蛇のような鋭さで飛んできて、利菜の喉をつかんだ。目が開いている。驚いたことに、目玉だけは瑞々しかった。サウロンの意志の輝きが、そう見せているのかもしれない。だが、サウロンにも首を絞める力はなかった。彼女たちは互いの命を握ったまま、睨み合った。
なんで、あたしたちをすぐに殺さなかったの
と利菜は言った。しゃべっているのか、そう思いこんでいるだけなのか、もうわからない。痛みは限界で、体は弛緩したがっている。もう死にたがっている。
本当はねじまげを食い止めようとしたんでしょう。自分たちの世界が大事だったから、守ろうとしたんでしょう。あんたの中にはいろんな人間がいるんだから。
自分でも迷ってるんでしょう
サウロンは目だけをぎょろつかせる。
あたしは救いたかった。世界じゃない。友だちやみんなを。あたしたちに必要なのは、隣にいる誰かだから。一生懸命生きるだけで、人生は十分幸せだって信じてる。佳代子だって、一生懸命だった。母親に虐待されても、それでも許そうとしてた。心にいいものがなきゃ、そんなことはできない。みんなが芯から悪人だったなんて、あたしには思えない。だって、あの子たちが大好きだった。大切だった。
サウロン……と彼女は言った。お願い。あたしたちには力がないけど――世界も救えない。だけど、こんなふうに終わりたくない。明日がないなんて、そんなのいやだよ。あんたもそう思ったから、皇帝と戦ったんでしょう。
あたしの心を覗いていい。あんたに見て欲しい。あんたが間違ってるのか、あたしにはもうわからない。でも、皇帝から守ろうと、守ろうとしたものは……
そのとき、口元から大量の血が溢れだし、彼女は一瞬意識をなくす。
あんたはこんなになってまで、世界を救おうとしたんだね。
だけど、希望があれば、あたしたちはやっていけると思った。
利菜は意識を取り戻し、もう一度サウロンを見下ろした。右腕をあげて、ナイフの柄にそえる。もう振り下ろす体力はなかった。彼女は重力に任せて、サウロンの腕に体を預けた。
ごめん、ごめんね、サウロン
そして、ナイフを振り下ろした。
◆ 終章 ね が い
□ 二十七
利菜はサウロンの隣で倒れていた。立てなかった。洞穴の冷たい地面が焼けた肌に心地いい。やがて、それも感じなくなっていったのだが、無念な思いだけは残った。今度も切り抜けられると信じていたからだ。仲間とともに元の世界に戻ることができる、ねじまげられた世界だって、元に戻せると信じていた。だが、現実には崩壊は音をたてて進んでいき、自分自身が誰にも知られぬ暗い洞穴で、死のうとしている。
残念だった。
もう終わるんだ……
冷たくなっていく。細胞から熱が引き、彼女は末端から死んでいった。もう血が溢れることも、心臓が鼓動することもなかったのだが、苦しみはまだ続いていた。
右手の中に熱があった。ああ、装置だな、と思った。
この装置はなんのためにあるんだろう?
疑問が、意識を少しつなぎとめた。彼女はほとんど死んでいた。けれど、心に残った魂が、装置とは別の熱を帯びたままだ。
それは、希望だった。
彼女はその死に際して、生命のきらめきを感じた。母親や友だち、自分に関わった人たちがしてくれたことを思った。そうした記憶は、感謝の心を生んだ。それは自分に対する感謝でもあった。
一生懸命やった。でも、まだ足りないのだ。
彼女の心は、この世のいいものとも結びついていく。彼女と仲間たちがずっと思っていたこと、この世はわるいものばかりじゃないということ、彼女たちを突き動かしつづけた、もう一つの意志をこのときはっきりと感じたのだった。
お願い……と彼女は念じる。このまま終わらせないで欲しい。こんなことのために造られたんじゃないはず。まだ終わりたくない。佳代子やみんなを返して、世界を取り返して。
利菜は必死で念じ続けた。
そして、彼女は死んでいった。
□ 二十八
「利菜、利菜」
誰かが頬を叩いている。揺さぶっている。だめだ、そんなに揺すったらだめだと思った。なぜなら全身の皮膚が焼けて爛れているし、内臓も潰れてしまった。そんなに揺すったら死んでしまう。
いや。もう、生きているのかどうなのかも……
そこで目を覚ました。
顔を上げた利菜は、そこに信じられないものを見た。洞穴に、朝日が射し込んでいる。傍らには佳代子や達郎たちがいる。全身の骨を砕かれたはずの新治も。首をつぶされたはずのテドモントも。みんなボロボロだが、生きている。
「うそだ……」と涙が零れた。
「あたしたち、生きてた」佳代子が言った。彼女も泣いていた。「死んだはずなのに……でも、みんな生きてて、それであんたを探したの。きっとここだと思った。なんで助かったの? どうやったのよ」
「あたしは……」
利菜は体を起こした。服は焼けてボロボロだった。なのに、体はなんともない。皮膚も内臓も。以前より具合がいいぐらいだ。利菜はサウロンを見下ろした。
彼は死んでいた。ナイフが墓標のように立っている。
「やったんだな?」
とペックが訊いた。
「ええ」
呆然と答えた。
彼女は右腕も元に戻り、自由に動くことに気がついた。まだ装置を握っている。生き返った右腕に、何かが乗っていることに気がつく。サウロンの手だ。利菜はその手をじっと見下ろした。彼の指を、そっと握る。頬を涙がつたい落ちた。装置をサウロンの乾いた手に握らせる。
「利菜?」
と紗英が訊いた。
利菜は泣きながら顔を上げた。洞穴の入り口には、ヒッピやマーサがいた。死んだ大勢の人たちがいて、九人を見守っている。そして、彼らは音を聞いた。つぼみから花が開くような澄んだ声音だった。
それは世界の再生だった。
○ おしまい