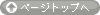「ねじまげ世界の冒険」へようこそ
このページは、ネットで小説を読まれる方用に用意しました。
長編、短編とそろえています。古い作品もあるので、できには目をつぶってやってください。
ねじまげ三部作も、よろしく!
ねじまげ世界の冒険
▼第六部 ねじまげ世界の最終戦争
○ 章前 二〇二〇年 ――ねじまげ世界 八月十五日 午前九時四十五分
○ 竹村寛太、窮地をすくう
□ 一
事の発端が、利菜と紗英の到着にあるにせよ、寛太はそのときを愛用のパジェロで迎えた。運転席で意識をなくしていたのだが、それが突然目を覚ましたのは、頭の奥がキインと鳴って、強い衝撃が、体と車を揺さぶったからだった。
目を開けたとき、フロントガラスの向こうでは朝日が斜めの線を描いて水滴を輝かせていた。ガラスにもボンネットにも、厚く落ち葉が積もっている。まるで、何ヶ月もその場に停まっていたかのようだ。
寛太は朦朧とする頭で外によろめき出た。目の前にジャスコがあった。彼の車は、その広い駐車場の中央に、たった一台で停まっていた。廃墟……という言葉が浮かんだ。今では年中無休の看板を降ろしたかのようだ。閉鎖されてずいぶん経ったようにも見えた。人気がないせいかと思ったが、それだけではない音がないのだ。いくら休日でも、周囲には住宅がある――
住宅がなかった。
寛太は周囲に首を巡らしながら歩き回った。ジャスコは神保町のほぼ中心にある。南には高速道路も通っているがそれもなかった。ないというよりも、ぼんやりとかすんで見えないのだ。
よろめくと、パジェロの助手席にぶつかった。言葉も思考もなくし、車に戻ろうとする。立っていられなくなるに決まっている。下手をすると吐くかもしれない。
寛太はシートに身を落ちつけて、ようやく言葉を口にした。
「どこなんだ、ここは?」
車の中で周囲を見渡す。駐車場にも、屋上に続くスロープにも、鎖がはってあった。いつジャスコに来たんだ、と寛太は考える。なぜこんなところで眠っていた。みんなどこに行ったんだ? 町はどこに行ったんだ?
「それとも、おれがどこかにきちまったのか?」
彼の目は助手席に置かれた新聞に引きつけられた。なぜそこにあるのかわからない。車で読む習慣はない。ただ、その新聞は奇妙だ。どこかちぐはぐしている。
手にとってみる。答えがわかった。文字が左右逆転しているのだ。大昔の新聞みたいに、右から左にかかれている。古風なレトリックをつかっていて、読みにくかった。じいちゃん、懐かしの古新聞があるぜ……と彼は思った。こんなときだが、寛太郎に無性に会いたい。すぐに会える気がする。
「そんなはずない」
寛太は頭をふって否定する。まだ死ぬべきときじゃないと思った。おれが死んだら、佳代子や達郎たちはどうなる?
手がわななく。寛太は情けない、しっかりしろと自分を激励しにかかったが、日付を見たとたんに震えはいっそうひどくなり、目までかすんだようだった。
解放三年、八月十四日――
「いたずらか?」
寛太は笑おうとしたが、口元から上にはのぼらない。彼はこう考えた。今ここで現実逃避するのはまずい。おれはおさそいに引っかかってる。きっと世界のねじまげに遭遇している。わるいものの巣の中にいて、背中には死が貼りついていた。彼は顔を撫でて、その馬鹿みたいな笑みを引っこめた。
記憶では六月二十五日のはずである。新聞の日付通りなら、太一のやつは夏休みじゃないかと寛太は考える。それに解放三年? なんだその年号は?
急に思い出した。この日の朝、いつもの行商をおえて家に戻った寛太は、届いたばかりの新聞を助手席に投げ込んで、佳代子の使いで町にくりだしたのだ。
恐ろしくなり新聞を投げ捨てる。ポケットから携帯を取り出すが、指が震えてうまく押せなかった。
「くそ!」と彼は言った。「みんな、どうなっちまったんだ! 佳代子は、新治たちはどうなったんだ!」
その瞬間、寛太は世界に存在するのは自分一人で、他の物は全て消えてしまったという強迫観念に囚われていた。携帯電話を耳に当てるが鳴りもしない。電池は十分。なのに、通じない。
寛太はハンドルに伏せた。泣いてすっきりしたかった。けれど、狂乱に陥るまえにすべきことがある気がした。
新聞だ。
その古風な新聞は、ずいぶんと彼の関心をひきつけた。解放三年、八月十四日の新聞。
四つ折りの新聞に何度となく目を落とす。中身が気になって仕方がないのに、決して読みたくはないかのように。けれど、四つ折りの下部に見慣れた文字のいくつかを見つけると、そうもいっていられなくなった。そこには、神保町の兄弟、銃殺される、とあったのだ。新聞の第一面だが、小さな扱いの記事だった。寛太はそのコラムを目に貼り付けんばかりにして必死に読んだ。ここはねじまげ世界かもしれないが、判読できることは救いだ。
『徴兵拒否と国家侮辱罪により、逮捕された神保町の兄弟が、今日銃殺される。二人の自宅に赤紙が貼られたのは、当月の十四日である。同日未明、憲兵隊は、召集令状の受け渡しに向かったが、二人はその憲兵に反攻を企てるという暴挙をしでかした。』
「うそだろ……」
今度こそ吐きそうになる。憲兵、召集令状、徴兵拒否
「助けてくれ、じいちゃん……」
これじゃあ、まるで戦時中の世界じゃないか。新聞を開いて中をよく読もうとしたが、文字はかすんで消え始めた。特有でいて魅惑的な紙の中に、新たな文字が浮かび上がってくる。ぼやけた文字がはっきりすると、寛太は食いつくようにむさぼりよんだ。新たな記事の中では、達郎と新治がすでに処刑されたことになっていた。新聞の見出しは、太いゴシックで、『徴兵拒否の兄弟、処刑さる』と書かれている。
『千葉県神保町出身の尾上兄弟は、スパイ容疑が確定となり、当月十八日に銃殺刑となった。処刑されたのは、神保町野上在住の尾上達郎38と、同地区在住尾上新治37。同町出身の参議院議員、坪井善三氏は、この国家危急のおりに、非国民を故郷が生んだことに、遺憾の意を表明し……』
「坪井善三?」
寛太は鼻で笑いながらつぶやいた。彼がその名を聞くのはずいぶんと久しぶりだが、何者であるかは覚えている。釈尊会の会長じゃないか。25年も前に死んだ男だ。そいつがよみがえった上に、新治と達郎の処刑に文句を垂れてるってのか?
「あの二人は死んでない、こんな記事はでたらめだ!」助手席に新聞を叩きつけた。「あいつらとは山に戻るてはずだったんだ。なのに何で死ななきゃいけない」
世界はねじまげられている。どうやら、あの言葉は真実をかたっていたらしい。ずっと警告を発していたらしい。無意味な言葉でも、気の狂った脳みその発する戯言でもなかったのだ。
「くそう。さっきまでは二人は死んでなかったじゃないか。なんでなんだ。この記事は――」
現実なのか?
寛太は第一面をおおざっぱに読んだ。第三帝国が半島に進出したとある。朝鮮半島の地図が載っていて、第三帝国と満州軍の戦闘の軌跡が簡略化されて載っている。寛太は新聞を投げた。これが現実だとしたらえらいことだ。まるで、歴史が……
「ねじまげられたみたいじゃないか」
とつぶやき、笑い声を上げた。ガタン、と枠の外れるような音がして車体が揺れた。タイヤが外れたのかと思った。車外に飛び出した寛太は、そこでデパートの解体現場に出くわした。まるで、時計の逆回しのようだ。ジャスコの看板がとれ、塗装がはげおち、外壁がぞくぞくと消えていく。ジャスコの存在が消えていく。尻餅をつくと、足下のアスファルトはみるみるうちになくなって、土の地面がむき出しとなった。ジャスコの上空には、真っ黒な渦が雷を鳴らしながら出現し、もはや鉄骨をむき出しているジャスコの材料を、渦の中へ吸いとっていく。砂埃が猛然とわき起こる。周囲の並木が根こそぎ吸い込まれる。
ズリズリという音にふりむくと、風の吸引力に耐えきれず、パジェロまで渦に向かいはじめている。
「くそったれめ!」
寛太は怒りの声を上げ、車に飛び乗る。扉をしめると風はどうにか遮断できた。キーを回すが、反応がない。
「くそ、かかれ、かかれ!」
二度、三度とセルがうなり出す。けれど、頭のどこかでは考えている。歴史がねじまげられたのなら、このパジェロだって存在しないことになる。
「そんなことはない!」と寛太は言った。「存在しろ! 主張しろ! こっちが本物なんだ! 負けるな! かかれ! かかれ!」
エンジンの回転音は、さながら天使の祝福のようだ。寛太は諸手を打ったが、車体はまだ引きずられている。ケツを振って回転している。寛太はギヤをローにぶちこんで、アクセルをふんだ。タイヤが土をまきあげだした。車体が浮いて、地面をつかまえ切れないのだ。寛太はハンドルを猛烈にまわし、車体を出口に向けていった。ふりむくと、サンルーフの向こうに見える渦にむかって叫んだ(その渦を子どものころ、何度も見たことを思い出す)。
「建物と一緒くたにするんじゃない、おれは人間なんだ! おれは全部覚えてるぞ! 元の世界を覚えてるぞ! ざまあみろ!」
新治たちもだ。あの二人も元の世界を覚えていたから、殺されるのだ。
「おれの仲間はみんな覚えてるぞ! おれたちがねじまげを食い止めたんだ! 今度だってやってやる! さあ、踏め! 地面を踏め! 進め、この野郎!」
渦は寛太が嫌いらしい。吸引力はますます強まったが、パジェロは寛太の精神と呼応して、気合いと根性、ガッツをみせた。基本性能と物理法則を無視して働いた。
出口の鎖が引きちぎられ、パジェロめがけて飛んできた。寛太はとっさに身を伏せる。その分厚い腐りはボンネットに打ち当たり、ランプを砕いてサイドミラーを破損させる。破片はすぐさま渦に吸い込まれていった。
ウオン、ウオオオン!
そのエンジン音はさながらパジェロのあげる抗議のようだ。
確かな加速を感じたかと思うと、パジェロと寛太は、時間の逆行現象に逆らって、ジャスコの敷地を飛び出した。
目の前に、柵があった。
「うわあああああ!」
寛太は絶叫とともに、ハンドルを左に切った。ブレーキもふみ、どうやらサイドレバーもひいたらしい。後になってみても、あの体勢でどうやってレバーを引いたのか、思い出すことはできなかった。ともあれパジェロは横転しかかりながらも、道の中央に留まることができた。
外を見下ろすと、地面をかなり深くえぐっていたのでゾッとする。
もうジャスコはなかった。今度も時の逆転現象が起こっている。時間がみるみる進んでいく。ジャスコの跡地には、高い木塀と木造の屋敷が建っていく。恐ろしく滑らかな早回しだ。こんなふうに自動で建物ができあがるのを知ったら、新治と達郎はどう思うかなあ、と彼は思う。門ができあがった。かと思うと、その脇には看板が立ち文字が浮かび上がってきた。大日本帝国憲兵本部……。寛太ははっとなる。憲兵と言えば、達郎たちを捕まえた連中である。門のあちこちで赤い点が浮かびはじめた。それはどんどん大きくなって炎をかたどり、門を包みこみはじめた。大火災だ。憲兵本部は現れたばかりだというのに、炎に包まれて消え去ろうとしている。無音の中で憲兵たちが門を開けだす。
寛太は慌ててキーを回した。かかった。寛太は喜びを爆発させてハンドルを叩いた。ねじまげ世界に来ても、変わらずガッツのあるやつだ。
ようやく音が聞こえだした。ウーウーというサイレン音に、人のささやくような声も。音が時間に追いついてきたと考える。どんどん大きくなり、炎の風巻く音も混じり出す。ヒュルヒュルという笛の音。重い炸裂音に、悲鳴と怒号。
「なんてこった……」
寛太は窓を開けた。憲兵たちは防空壕に逃げようとしている。建物から人が飛び出してくる。窓から身を乗り出し、空を見上げる。爆撃機だ。巨大な編隊が胴を開け、そこから何か落ちてくる。
焼夷弾だった。
「達郎!」
と寛太は憲兵本部に向かって怒鳴った。表に飛び出してきた憲兵たちがこっちを向いた。
「なんだあ、きさまは!」
「尾上達郎は!? 尾上新治はどうした!?」
「非国民など知るものか! どうせやつらは銃殺だ!」
男の声の合間にも、棒状の焼夷弾が火を噴きながら落ちてきて道に突き刺さる。兵士の体に突き刺さって、燃え上がり始めた。
憲兵本部は地獄絵図だった。あちこちから炎が噴き上がり、窓をつきやぶって人が出てくる。焼夷弾は屋根をたやすく貫通して、内部に炎を振りまいている。
「あいつら生きてるのか?」
男の口ぶりから察するに、まだ銃殺は行われていないらしい。寛太はパワーウインドウをあげた。寛太がアクセルを踏み込むと、門の前にいた男たちがあわてて飛び退く。パジェロは門をくぐって演習場を駆け抜ける。木造の平屋建ては火のまわりも早かった。寛太は歯噛みした。これじゃあ、二人が生きていても助けられない。
助手席の新聞にちらりと目をやる。記事では、二人は銃殺されたことになっていた。火で焼け死ぬとは書いていない。だけど、
「おれはあの新聞よりも過去にいるんだ」
そうでなければ、二人が生きているはずがない。
寛太は車を降りてドアを閉めた。炎の熱気が彼をあぶった。吸いこむ息が彼の気管を燃やしている。憲兵本部はこの空襲で真っ先に狙われたらしく、手のうちようもない。憲兵たちは消火もせずに我がちに逃げていく。寛太は煙に巻かれて咳きこんだ。逃げなければ焼け死ぬことを、冷静な本能が告げていた。
「だけど、あいつらがいなきゃ勝ち目がねえんだ……」
と寛太は言った。上着で口元を押さえると、憲兵本部に踏み込んだ。
□ 二
「達郎! 新治!」
寛太は炎に包まれる憲兵本部を探し歩いた。屋内がこれほどの熱だというのに、彼の頭は冴え冴えとしている。子どもの頃、幾度も感じたパワーが彼のご退院おめでとうございます。駆け巡っている。二人が生きていることがわかるのだ。どの方角にいるのかも。もはや闇雲に歩いているのではなかった。寛太は自分の家のように迷いのない足取りで屋内を突き進む。角を曲がったとき、座敷牢の向こうにいる二人の姿があった。
「寛太!」
「達郎! 生きてるか!」
寛太はゆっくりとそちらに歩いていく。熱と煙で呼吸ができないのだ。
寛太はやっとの思いで鉄格子に到着した。扉をひくが鍵が掛かっている。憲兵たちは二人をここに残したまま焼き殺すつもりだったのだ。
「おまえら生きてたんだな」
よく生きていた、と寛太は思った。二人の顔は煤にまみれて真っ黒だ。取り調べがきつかったらしく、皮膚は裂け青あざを作り、痛々しい姿だった。顔を腫らし人相まで変わっている。それでも生きていてくれたのだ。
「寛太、ここは燃えちまう」達郎は言った。見た目よりも元気なようだ。「ここはねじまげ世界なんだ。おれたちは……」
「黙れ」寛太は怒りに任せて、格子を揺さぶる。
「無理だ。鍵がかかってる」新治の声にあきらめがまざる。「おまえだけでも逃げろ。佳代子や利菜を助けてやれ」
寛太は呆然と彼を見つめた。「あいつが戻ってきてると思うか?」
「ああ」
新治がうなずいた。彼の目がいっている。見た訳じゃない。でもあいつを感じるんだ。
達郎が格子越しに怒鳴る。
「寛太、おれたちはもういい」
「いいなんてことがあるか! おまえらは助かるんだ! いいか、おれたちの味方してる奴だって……」煙を吸いこむ。咳きこんだ。「おまえらは銃殺されるはずだったんだぞ。あの新聞がなけりゃ、おまえらがここにいるなんて思わなかった。おれは……」
「だが、どうするんだ!この扉は開かない! おまえまで死んじまうぞ!」
「ここで待ってろ! 格子の側にめいいっぱい近づいてろ!」
寛太は床にはいつくばると、煙の下にある正常な空気をできるかぎり吸いこんだ。息を止めると玄関を目指して走り出す。視界は煙で見通しがきかない。寛太はなにかにぶつり、なにかにつまずいた。二人を助けたいという一心だ。その気持ちだけで外に出、車にたどりつくと運転席にとびのった。演習場には焼けこげた死体と逃げ遅れた兵士たちがいる。寛太が車を動かすと、目が覚めたように追ってきた。
どこに行けばいいかはわかっていた。二人のいる場所がわかるからだ。
建物の左手に行くと、そちらは火災がもっともひどい。ガラス越しにゆらめく炎に、寛太はおじけづいた。このやけこげた壁の向こうに二人がいるのだ。
ベルトをしめた。
「木造だ。コンクリートじゃない。ぶちぬけるぞ!」
寛太は両手で頬を叩くと、ほとんどシートの上で腰を浮かし、まるで駆け出すようなかっこうでアクセルを踏みこむ。壁が迫り、ぐんぐん迫り、ガラスにふれんばかりになる。頭は逃げるもんかと意地をはったが、本能が体を引いてペダルから足を離す。
車は壁に激突して、寛太はシートとエアバックに叩きつけられた。
呻きながら目を開けると、フロントガラスが砕け、その破片でエアバックもやぶれてブスブスとしぼんでいく。折れた外壁がハンドルに突き刺さっていた。あのまま、アクセルを踏みこんでいたら、彼を串刺しにしていただろう。
「お、おおい……」と寛太は言った。弱々しい声に驚いた。「おおい、新治……」
彼はパジェロが穴をふさいで、二人が出て来られないことに気がついた。シートに座り直すと、ギヤをバックにいれた。
□ 三
パジェロは外壁にくいこんでなかなか抜けなかった。動いた、と思うと、穴の向こうでは達郎と新治が車のフロントを押している。寛太は割れた窓から身をのりだす。痛む肋をこらえて怒鳴った。
「早く乗れ、憲兵がくるぞ」
周囲では焼夷弾がまだ降っている(本当は、なめ太郎が屋根の上から焼夷弾を投げていたのだけれど、寛太も憲兵たちも気づいていなかった)。憲兵たちの銃撃も始まった。鉄の車体に弾丸の当たる音がする。達郎がフロントガラスを乗り越えて助手席に乗り込み、新治も後部座席に座った。
裏手に回ろうとパジェロをまわすと、憲兵たちは横隊を築いて射撃をくわえた。達郎が、しゃがめしゃがめと叫んでいる。割れたガラスをはじいて弾丸が飛びこんでくる。寛太はハンドルに突っ伏しながら、アクセルを踏んだ。
「本物の空襲かよ。どうなってんだ」と新治が怒鳴った。
「事情が知りたきゃ、新聞を読めよ!」
口元を拭うと、腕には鮮血がべっとりとついた。
本部の脇を通り、裏口を出た。サンルーフのガラスに、焼夷弾が、ガン、ガン、と落ちた。
達郎が塀の向こうの町並みを見ていった。
「町中は火の海だぞ! こいつら第三帝国ってのと戦争してるんだ!」
「ああ、知ってるよ!」
「おれが徴兵されたんだぞ! 新治と一緒にリンチにされた!」
「それも知ってるよ!」と寛太は言った。車道に出ると道は舗装もされていない。「そんなことより、今日はいったいいつなんだ!」
「八月十五日だ!」
「十五日? だけど、おまえのけつの下にある新聞は、八月十七日になってたぞ」
達郎はあわてて新聞を取り出す。
「本当だ、日付は十七日だ」
「そいつには、おまえらが銃殺になったって記事が載ってた。今はなんて書いてある」
しばらく沈黙が続いた。達郎は揺れる車内で苦労して読んだ。空襲で破壊された家屋が、車道に破片を散らしている。車輪が暴れ馬のように跳ね飛ぶたびに、寛太は痛みに顔をしかめる。
「そんな記事どこにも……待てよ、待て待て。……両神山で女性の惨殺死体? こいつは……」
運転に集中していた寛太も、思わず道から目をそらした。新治が後部座席から身を乗り出した。「いったい誰のだ?」
「今あの山に近づく女の二人づれなんて、あいつらしかいないだろ」
達郎が言った。
寛太はスピードをゆるめた。「町内を出よう……」
道のまわりには逃げ遅れた人たちがいる。
「助けないのか」と新治が言った。
「新治、冷静になれよ。これは本物の世界じゃない」
「だけど、これは現実だぞ」
「おれたちの知ってる日本は、帝国と戦争したりしてない!」
寛太の叫び声と同時に左前方の家屋に爆弾がおちた。瓦礫と死体がパジェロのフロントに降り注ぐ。寛太は浴び血に濡れて怖気をふるう。「なんてこった……」
ボンネットには引き千切られた子どもの腕が乗っている。
「見ろよ、くそったれ!」新治が叫んだ。「これは現実だ! あれを見てもまだ幻覚だなんて言い張るつもりか!」
「誰も、そんなこといってないだろ! おれたちがすべきことはそうじゃないんだ! おれたちは……」
そのとき、サンルーフのガラスごしに空をみていた達郎が、「戦闘機だ……」とつぶやいた。「おい、上に戦闘機がはりついてるぞ!」
「こんな車で走ってりゃ、目立ちもすらあ」
「機銃で撃たれるぞ! 逃げろ、寛太!」
そのとき三人の頭にあったのは、寛太郎から何度も聞いた戦争話だ。その話は生々しく彼らの頭に残っていたから、機銃に腸を引き裂かれる自分たちの様がまざまざと想像できた。
新治の背筋に悪寒が走る。彼はサンルーフから空をのぞく。
土の地面にバツ、バツと穴が開く。戦闘機はまっすぐに後を追ってくる。
「寛太あ! 来たぞ! かわせえ!」
「ふざけんな、直線だぞ!」
達郎が右手を指さしていった。「あそこに飛び込め!」
そちらには、ばかでかい邸宅があった。ちょうど門が開いている。寛太が目一杯ハンドルをまわすと、パジェロは門柱にぶつかりながら庭園に入る。機銃弾が、新治の真後ろをかけぬけた。重い機銃の連撃に、パジェロの車体が跳ねる。寛太の手の中で、車がコントロールをなくしていく。
エンジンからギュルギュルという音がたち回転がとまった。頑丈なこの車も今の銃撃で、本当にだめになったのだ。
「二人とも無事か?」
と達郎は訊いた。見上げると、ひび割れたガラスの向こうで戦闘機が旋回している。ボンネットは焼夷弾の油でぬらぬらと光っている。達郎は車の爆発を妄想して二人をせきたてる。
「エンジンが燃えるぞ、降りろ」
ドアを開けた。寛太が後ろでうなった。「だめだ、足がはさかってる」
達郎は内心うめきをあげながら、寛太の左足をひっぱりにかかった。新治が後部座席から手を伸ばす。寛太の足はつぶれたフロントと、シートの間ではさまっている。ハンドルに圧迫されて身動きできない。
「抜けない。二人とも先に逃げろ」
寛太がいうと、新治が耳元で怒鳴る。「シートをずらせ、ばかやろう」
「そうか」
寛太は足下に手を伸ばして、レバーを引いた。シートが下がると、圧迫が消え、左足がすぽりと抜けた。
達郎が言った。
「二人とも出ろ」
三人が車外に転び出たのと、戦闘機の射撃は同時だった。圧搾機で叩くような音がし、パジェロは数発の弾丸をくらって完全にスクラップになった。
寛太と新治が地面にへたりこみ、ともに爆風をくらっていると、
「死んじまえよ!」
と背後で声がした。二人がふりむくと、縁側で溺死女が叫んでいる。炎のついた部屋の奥では、なめ太郎が踊り跳ねている。
新治が、あいつらこの世界まで追ってきたのか、とつぶやいたが、あの連中のことを彼ら三人ともが覚えているのだからいたしかたない。
寛太は座席によじのぼり、ひしゃげた車内に身をのりだす、シートの上に腹ばいになった。
「寛太、なにしてる。エンジンが燃えちまうぞ」
寛太が見ると、車の塗装がメラメラと燃えだしている。
「新聞だ、新聞がいるんだ!」
新治が寛太の服を引っ張るのと、寛太が新聞をつかむのは同時だった。二人は、芝生の上に転がった。達郎が怒鳴った。
「なにしてる! まだ、旋回してるぞ! こっちにこい!」
寛太がびっこをひいて達郎の元に走り出したとき、全壊したパジェロがメラメラと炎を吹き上げ始めた。三人は土塀の際に隠れながら、じりじりと庭園を移動した。達郎が庭園の奥にある土蔵を指さした。
「あの蔵に入ってやりすごそう。何か体に巻くものを見つけろ」
「何を巻くんだよ」
「座布団か、毛布だ。池の水にひたせばずいぶんましだろ? このままじゃ機銃の前に火事で死んじまうぞ」
本宅は焼け落ちる寸前だ。土蔵だけが無事だった。家人が空襲警報を聞いて運び出していたのか、扉があいて、中の荷物が散乱している。
土蔵に逃げこむとさすがに熱気はましになった。寛太は、しばらくひっかきまわしていたが、入り口近くで束にしばられた古新聞を見つけた。
「おい、二人とも見てみろよ」
「ありがたい、これでこの世界の状況がわかるぞ」
寛太と新治は無言で達郎を見返した。達郎が、なんだよ、と言った。達郎の、この世界、という言葉は、妙にリアルだった。
三人は、爆弾を懸念して、奥に行った。
新治がライターに火をつける。みんなは古新聞の束を前にだまりこんだ。
「なあ、妙な話だよな」と寛太は笑いかける。「こんな世界に来てさ、ここって、本多の親父の家だよな」
「そうらしいな」と達郎。
「利菜と紗英は、いつこっちに来たんだ?」
と新治は訊いた。この事態が二人が町にたどりついたことと関係しているのかと考えている。
「今日が十五日だってのはまちがいないのか?」と寛太。
「まちがいない。憲兵が召集令状を読むときに、そういったからな」
「おまえらは、元の記憶を覚えてるんだな」
「ああ」
「もちろんだ」
と兄弟は言った。
三人は、逆さ書きの新聞をむさぼり読んだ。寛太はつぶやいた。
「これが現実だってのか……」
新聞の記事は、第三帝国に関する記述がほとんどだ。第三帝国の手にかかり、ほとんどの国家が征服されている。寛太は目をしばたたく。ホロコースト政策すすむ、の文字が紙面におどる。記事が本当だとすると、帝国が進めているのは人類滅亡計画といって他ならない。彼らは帝国人種をのぞいて、人類を抹殺することに決めていたからである。計画は着々とすすみ、帝国は地上にいる人類の、三分の一を消すことに成功している。ざっとみても、二十億からの人が、百年に及ぶ帝国戦争で消失したのである。
絶滅危惧種は今や人類そのものだった。
戦争による貧困、疫病の蔓延が重なり、人口は五分の一まで激減している。
帝国の侵略はヨーロッパにはじまった。日本がまだ無事だったのは、大陸の端に位置していたから、という理由にすぎない。
「この第三帝国ってのはなんなんだ? どこからわいてでた。ヒトラーのナチスみたいなもんか?」と達郎が言った。
「おれたちの世界じゃナチスは負けた。こいつはもっと別のものだよ。最悪だ。こいつらは、ユダヤ人だけじゃなく、全人類をホロコーストにかけてる」と新治。
「サウロンだ。こんなことができるのはあいつだ。まちがいねえよ」
寛太がいうと、達郎と新治は、新聞から顔をあげた。
「そうだ、サウロンだ」
達郎がいうと、新治がうなずいた。「おれたち、いつのまにか記憶が戻ってる。元の世界の記憶が消えないのもそのせいだよ。おれたちは普通の奴らとちがう。ガキのころにも、似たような体験をしてる」
記憶をとりもどしてみると、過去を思い出すことは驚くほどたやすかった。
寛太は新聞を――元の世界の新聞を持ち上げる。
「おれたちはグループだった。おれたちが世界のねじまげをくいとめたんだ。今度もそうするのを期待されてる」
「なにからだ」
新治が訊いた。寛太は答えることができなかった。誰も答えを知らなかった。
「わるいものってのは、全人類の意志――なのかもしれない」達郎が顔を上げ、二人を交互に見る。「おれたちがグループであるように、全人類が全体からなる一なんだ。過去もふくめてな。その意志ってのは、たぶん……きっと一つに定まってない。この世から消えるか、存在しつづけるか……せめぎあってる」
と達郎。人類の意志、あるいは宇宙の意志なのかもしれない。サウロンが消そうとしたのは、この宇宙そのものだったからだ。
寛太はうつむいた。今や、町どころではない、世界が彼らに牙をむいている。新治がその手から新聞をとりあげる。
「だとしたら、利菜と紗英を助けないと」と彼は言った。「もう一度、世界のねじまげを食い止めるんだ」
そうしたら、世界は元に戻るのか?
疑問だった。今となっては、元の世界の方が夢のような気がしてくる。
寛太は言った。「疫病ってのは、エボラウイルスみたいなもんかな」
「どうかな。おれたちの世界とはずいぶんちがうからな。戦争のせいで、病気の研究ができないみたいだ。帝国のやつらは、旧人類――って勝手に呼んでるみたいだが、その文明も残す気がないんだよ。みろよ(と新聞をたたく)。研究施設を破壊……農業も満足にできないだろうな。これはえらいこったぞ」
「だけど、おれたちは覚えてる」
寛太の静かな宣言に、達郎はしばらく沈黙した。ややあってうなずいた。
「そうだ、おれたちは覚えてる。きっと、ガキのころの記憶のせいだ」
「寛太……」
新治が呼びかけた。その深刻な声色に、達郎も寛太も静かになった。
「なんだよ」
「佳代子の記事がある……」
新治は寛太に新聞をさしだす。震える指でうけとる。「うそだろう」
新聞は、神保町の主婦がナイフで刺され、重体であることを告げていた。おれのコメントだ、と寛太はつぶやいた。新治はよく見えるようにライターの火を近づける。煤だらけの顔に汗の玉をいくつも流す。
メラメラという音が間近に聞こえた。蔵の外壁が燃え始めているのだ。
呆然とする寛太の目の前で、文字が消え始めた。同時にその下から、インクがにじみだしてくる。
「内容が変わる……」
と達郎がつぶやく。三人は状況の好転を期待したが、新聞の記事は、神保町の主婦が絞殺されたことを伝えていた。佳代子が死んだ……と寛太は言った。
「待てよ」と達郎は寛太をはげました。「これは未来の新聞だろう。佳代子はまだ死んでない。そうだろ」
「あ、ああ」と寛太はうつろにうなずく。「そうだ、まだあいつを感じる。おれにはわかるんだ」
「利菜も、紗英もまだ生きてるはずだ」
と新治。達郎が言った。
「この新聞がここにあるのは、偶然じゃない。おれたちを生かしたがってるやつ、味方するやつもきっといるんだ。でなきゃ、二十五年も前に、世界は終わってたはずだ。そうだろ?」
寛太と新治は自分たちがそんな大それたことをしたのか自信がなかった。だけど、佳代子がまだ生きていて、あいつを助けなきゃいけないのは本当だ。そうしたいのだ。
「三人とも助けるぞ。弱気になるなよ。これは戦いなんだ」と寛太の肩を叩く。「これを体に巻け。頭にもだ。表の水をかぶりゃしばらくはしのげる」
達郎はいつのまに見つけてきたのか、かび臭いざぶとんをどさりとひっぱりだす。ビニールひもをひっぱりだすと、胴体に巻き付け手足にまき、頭にくくった。
寛太は新聞の詳細を読んだ。「あいつは伸子の部屋に行ったんだ」
「あのマンションか?」と達郎。「ここからだとずいぶんあるぞ」
「急ごう。もう時間がない」
三人は表の池にとびこんで、座布団に水を吸い込ませる。ずっしりと手足が重くなり、寛太は本物の鎧を着込んだような気分になる。
彼らは崩れた土塀から外の様子をのぞいた。往来には人の姿がなく、黒こげの死体ばかりが転がっている。左右からせまる炎に息をのんだ。
三人は意を決すると、道へ出て行った。佳代子たち、それにたぶん……世界を救うために。
◆第十三章 再会
○ ジノビリ暦三年 ――地下道にて
□ 四
配管の底は湿ってぬるぬるしている。天井回りは乾ききって、身体がぶつかるたびに砂埃が舞い落ちてくる。利菜は辟易としていたが、後ろをついてくるトゥルーシャドウの苦労を思うとでかかった文句も飲みこむほかない。
しばらく進むと、巨大な下水道に行き着いた。ヒッピが大通りとも呼ぶ巨大な排水路で、左右には歩道もある。ランプがなみなみと水を湛えた水路を照らした。
ヒッピはしばらく巨大な地下水道を見回していたが、やがて目当ての文字をみつけた。子どもたちは地図がなくても、地下水道を歩けるよう、長い時間をかけて水道のあちこちに文字を彫りこんでいた。
すぐに鼻は馬鹿になったが、ねずみの這い回る下水を歩くこと自体が信じられない。ランプの届かない暗がりには見たこともない生物がいるんだと思うと、足をおろすのも恐ろしくヒッピにくっついて歩いた。
そもそも、この世界では水の処理施設もないはずである。糞尿まみれの水が流れているのかと思うと、下水からは目を反らして歩いた。ヒッピはテシピたちのアジトまで下水を使うつもりだった。今では彼らもお尋ね者の一人である。ムスターサが利菜のことを知っていたということは、あいつにも正体が知れている、ということだ。まして、トゥルーシャドウを連れて歩くなど。利菜だって、そんな自殺行為を冒したいわけじゃない。
しばらく経つと、先頭にいたトゥルーシャドウが立ち止まって、おまけにランプのシェードを回して光を遮った。利菜がひっと声を上げると、ヒッピが口をふさぐ。
「誰かいるぞ」
彼はわずかに腰を屈めながら、視力に意識を集中する。前にいるのが子どもらしいことがわかると、それを聞いたヒッピが利菜を放りだして、トゥルーシャドウの脇を抜けようとした。腕の長い蛮族がちっぽけな少年をたやすく捕まえた。
「放してくれ!」とヒッピは言った。興奮してはいるが、声は抑えていたので、トゥルーシャドウも感服した。「あそこにいるのはパーシバルたちだよ。ぼくを迎えにきてくれたんだ」
トゥルーシャドウは夜目がきく。少年の瞳が光るのが見えた。マーサが、どうやらその子のいうとおりらしいよ、放しておやり。
マーサはまた奇妙な力を使ったらしい。トゥルーシャドウが手を放すと、ヒッピは一散に駆け出してしまった。トゥルーシャドウはシェードをまわして光を復活させると、やれやれとマーサと視線をかわした。利菜は、小さくなるヒッピの背中を見送りながら、きゅっと心臓を締め付けられたのだった。
□ 五
下水にいたのは、ペックの他、パーシバル、パダル、モタと言った、ヒッピのグループの生き残りの連中だった。利菜が会ったのはペックだけなのだが、記憶の共有のために、どの顔もなじみのあるものだった。少年たちは旧交を温め合い(離れた期間はわずかといえど、その間起こった事件を思うにこの言葉は適当であるだろう)、三人を迎えた。少年たちは蛮族にはさすがに怯えたようだが、顔には出さないよう注意していた。リーダーが連れているのなら、自分たちに危害を加えるはずもない。そのことからもヒッピに対する信頼のほどがうかがえた。
「みんな急いでアジトに来てくれよ」
とパーシバルがせかした。いってから、トゥルーシャドウのことをちらりと見た。彼がアジトに乗り込んできたときの騒ぎを心配しているのだ。
「ノーマとビスコは、みんなを集めて暴動を起こすつもりなんだ」
利菜たちは顔を見合わせた。ヒッピはすぐに尋ねた。
「王都には大人なんて残っていないだろう? 誰を集めたんだ?」
ヒッピはこの作戦に猛反対した。ビスコたちは、少年達のグループを集めて、決起を計画していたからだ。
カンブツ屋は元が馬車屋だから、敷地も店舗も広大である。ただ、現在では馬車も売り払って、反政府組織――とも言えない。集まっているのはおばさんや老人ばかりだ――の集会所のようになっていた。これだけ大きな建物だから、下水につながるマンホールも敷地内にあり、パーシバルたちもそこから出入りをしていた。
テシピのカンブツ屋には(主人であるテシピとカンビの兄弟もいない。ともに戦争にとられてしまった)、グループの主だつリーダーが集められている。その中にはテドモントの姿もあった。ヒッピは彼と目を合わせたが、すぐに視線をそらしてしまった。
少年たちはトゥルーシャドウの姿に怯えているようだが、老人たちは異種族を見慣れているから思ったほどの騒ぎにはならなかった。戦争前は交流が頻繁だったのだ。どちらかというと、魔術師のマーサと黒髪の利菜の方が目立っているようだった。ヒッピはずっと利菜の手を握り、心配するなと声をかけている。パーシバルたちは、初め利菜の出現にとまどったが、ヒッピの態度をみてすぐに利菜のことを囲んで守るようになった。
むろんビスコとノーマはぎょっとした。彼らに殺され掛かったのはわずか数日前のことである。が、ここはサイポッツの王都で味方も多い。今では平民たちのリーダー格になった二人は内心の動揺をつとめて隠していた。
なんであいつがここに? とビスコがノーマにささやく。ノーマはおっくうそうにうなずく。肋骨もつぶされて苦しいのだ。
利菜はノーマの様子に衝撃を受けた。三人が自分を見捨てたなどと腹をたてたが、彼らにとっては自分の国ですら(ことによると森にいるよりも)安全ではないのだ。
ヒッピはその二人に詰め寄った。拷問を受け、立つこともできず車椅子で生活しているノーマの姿には気をのまれたが、それでも言わずにはいられなかった。老人や子どもを集めて軍隊に戦争をしかけているなんて馬鹿げている――
「きさまはそういうが、では他にどんな手があるというのだ」この数日ですっかりみすぼしらい姿となったビスコが声をあらげた。「このまま手をこまねいても状況は悪くなるばかりだ。戦争に出た男手は戻ってくるめどすらたたんではないか。今勝負に出なければ我々はおしまいだ。平民も貴族もない。サイポッツ自体がだ」
驚いたことに集会所にいた老人も女性も、この二人の貴族のたてた計画に同意しているようだった。みな何十ヶ月もの長きに渡って苦渋をなめてきたのだから、破滅的な計画にすら希望をみいだしているようだった。
ヒッピはノーマを見たが、彼はビスコの意見を聞き、同意するように吐息したのみだった。唇も顔のあちこちも裂け腫らし、端正だった顔も無残なものだった。十数カ所で骨折をおこし、まともな思考すらできないのではないかとヒッピは疑った。
「ヒッピよく考えろ」ビスコは急にヒッピの側に寄った。肩に手を回すと耳に囁き始めた。
「王都にはまともな軍隊など残っていない。見かけるのは憲兵がほとんどだ。戦争にかり出された師団が多すぎるのだ」ビスコは他の者に聞こえないよういっそう声を低めて、「難民たちは、王都が安全と思って集まっているようだが、一番手薄なのはここだ。今、攻め入られたら、ひとたまりもない」
といって、ビスコはトゥルーシャドウを顧みた。
「彼は味方です。ぼくらを助けてくれたんだ」
「それはわかっている」
でなければ一緒にいるはずはないからな。とビスコは言った。
ノーマは視線をマーサに向けた。「話を聞かせてもらえないか」
みな、フードをまぶかにかぶった面妖な老婆に注目した。考えてみると、マーサは上にあがって以来、ほとんど発言していない。トゥルーシャドウも同じくで、二人は状況をじっと見守っていたのだった。とくにマーサはこの場にいる者の(おそらくは決起のリーダー格たち)、考えや態度を読み取っていたようだ。
とまれ、マーサは森で起こった出来事を可能な限り正確に伝えた。森の異変、そして、軍隊の身に起こったこと。幸いなことに、ビスコ自身が森の惨状は目にしたばかりである。話がムスターサを背後から操っていた男にいたると、ビスコが恐怖に顔を上げた。
「オットーワイドか?」
「なに?」
ビスコは語った。奇怪な術を使ったという点では、彼の知る銀髪の男も同じである。
ヒッピは必死に頭を働かせた。
ムーア教徒の語るあの方とは、トレイスのことではないのか?
暴動を起こした場合、勝算があるのか考えてみた。そもそも、ビスコが集めようとしているのは戦力とも呼べない。彼は下町のグループの面々を主力にしようとしているようだが、そもそも軍隊にとられなかったのは、年端のいかない子どもだからだ。彼はグループを誤解している。少年たちの集まりに過ぎないのだ。なるほど各グループはリーダーの号令で動くのが常である。しかし、戦争行動を行えるほど結束しているだろうか? そんな訓練を受けたこともないというのに?
ヒッピは不可能だと思った。ムスターサたちは教団の教旗を掲げていた。そのことからも、あの男が教団の人間であることは疑いがない。教団はわずかな間に、サイポッツをのみこむ一大宗教になりあがった。立役者は教祖とされるあの方である。あの方とムスターサを操っていた男は同一人物と考えて間違いないだろう。集まった平民のたいはんがムーア教の信者ということになりかねないが、相手があの方であったとしても、信者たちは戦い抜いてくれるだろうか? ムスターサのように操られているかもしれないのに。
老人にまじってグループのリーダーたちまで議論に加わると、話はまるでまとまりがつかなくなった。リーダーたちはヒッピの態度を臆病者と決めつけて責めた。暴動はもはや勝つための算段ですらなくなり、勇敢さをしめす度胸試しに成り下がった。ペックたちはこれに反発したが、リーダーを擁護したに過ぎなかった。びびったなんてあるもんか。こいつはイニシエの森まで出かけてマーサや蛮族を味方につけたんだぞ。臆病者はそっちの方だ――
ヒッピはテドモントたちを相手にせず必死に考えた。頭に血の上った連中には何をいっても無駄である。
タットンならこんな感情論はしない。はかせならぼくの考えを支持してくれる。そう思うと、タットンがたとえ死んでいたとしても彼は心強かった。彼に必要なのは同意ではない。暴動を成功させるための新たな知恵である。今、決起しなければならない、という点では彼もビスコに同意である。
ヒッピはみんなの意見を聞いていなかった。マーサに教わった意識の遮断を無意識裏に働かせていたからだ。ヒッピは灰色になった視界の中で、一同の様子を見渡した。
年配の者たちはどのみち老い先がない。女達も留守と子どもを守ることで必死である。明日の見えない生活は少年たちにしても同じ事だった。犯罪組織も若い者はみな戦争にとられて壊滅状態だ。
詰まるところ、どの階層の者も際際まで追い込められて、暴発するのを待っていたようなものだ。ビスコやノーマを頼り集まったのでもなかった。彼らは行動を起こすことが目的で、その先の考えが抜け落ちている。ビスコは戦争を起こすのを目的としていたはずなのに、今では暴動を起こすこと自体を目標としてしまっている。ハフスを救うのだと彼はいうが、そもそもハフスは生存自体が不明である。彼が生きていないのなら、ヒッピたちは是が非でも抗争に打ち勝ち、政権を獲得しなければならない。
だけど、どうすればいい? この面子で勝つのは見込みは一割とないぞ。
ヒッピは利菜を見たところで、はたと思考を止めた(彼女は彼女で、ヒッピの考えを読み取ろうと、必死で感覚を働かせていたところだった)。待てよ、と思ったのだ。ビスコも自分も王都にいるサイポッツ以外は味方がないと思っている。けれど、この利菜だけはちがうはずである。パーシバルは彼がマーサと蛮族を味方につけて戻ってきたと言った。それは正確ではない。彼は二人にくっついてどうにか戻ってきただけだし、トゥルーシャドウが味方するのはマーサのみのはずだ。
ヒッピはかたわらに立つトゥルーシャドウを見上げた。このナバホ族はサイポッツの議論に一切の関心を示さず、彼のことをじっと見おろしていた。テドモントらリーダーたちもついに薄気味が悪くなり、非難をやめたようだった。
「みんな聞いてくれ」
とヒッピはトゥルーシャドウを見上げたままいった。
□ 六
ヒッピはイニシエの民に伝わってきたエビエラの残した伝承のことを知っている限り話した。
ビスコたちの反応はそんなばかな、というものだった。
「おまえのいっているのは建国戦争のことなのか? あの戦いにイニシエの民が手を貸していたというのか?」
「そうなるね」
とマーサが言った。彼女は椅子に腰掛けている。頑健なように見えて、やはり彼女も高齢である。
「あたしも覚えているのはあるていどまででしかない。他人の話と入り交じっているしね」
「なぜ記憶がないのです?」
とノーマが訊いた。マーサは沈黙していたが、ヒッピには答えがわかる気がした。エビエラだ。そんな真似が出来たのは、マーサ以上の魔女だったというエビエラの他にはいまい。集会所の大人たちは、マーサが三百年生きていること自体が信じられないようだった。
「トゥーシャドウ、マーサの名前を使ったとして、イニシエの民は本当に集まってくれますか?」
と彼は訊いた。トゥルーシャドウはわからないと答えた。それはそうだろう。彼らとて森中に散らばって、軍隊と戦っているのである。まして、森の変化が激しすぎて、みなバラバラになってしまっている。
「サイポッツに反撃できるのだとしたら、みな集まるとは思いませんか?」
ばかな、とビスコが言った。「何を言い出す。都を滅ぼす算段のつもりか」
「そうじゃない。ぼくらはトレイスを倒すという点で利害が一致してるじゃないですか」
ヒッピは意識して、あの方、と言いたいのをひかえた。この中に(二十人はいるだろうが)信徒が混じっていないとは限らない。
「なるほど」とノーマが言った。「イニシエの民の力が借りられるのなら、勝つ見込みは高くなるだろう。だが、マーサに味方しているのは、その男だけだぞ」
ヒッピはうなずいた。ノーマは痛いところをついたが、これでノーマだけはこの作戦に疑問を抱いていると知れた。
「おまえは蛮族を従えて戦えというのか」とビスコはマーサを横目で見ていった。「それこそ荒唐無稽な話だ。我々は連中と戦争をしているのだぞ」
ノーマは車椅子の上で数度呼吸をした。みな静まっていた。ノーマは大きく息を吸い、可能な限り力強い声を出した。
「私は賛成する。このままでは、どのみち蛮族の手で我々は滅ぼされるだろう。軍隊が窮地におちいったのは知れている。放っておいても、やがて他種族が結集し攻め込まれるのは目に見えている」ノーマは深呼吸をした。痛みを堪えているようだった。「助かる道はただ一つのように思う。我々の主導で、蛮族に攻めさせるのだ」
みな言葉もなかった。攻められるのなら先に手を組んでしまえとは乱暴な表現だった。
「つまりは彼らの敵を我々ではなく、現政権――ひいてはトレイスにしぼるということだ。そういうことだな?」
ヒッピはうなずいた。
「うまくいくとは思えねえぜ」
テドモントが顔を背けた。ヒッピに反発したというよりは、純粋にトゥルーシャドウを恐れていた。大人たちがこんな怪物と戦ったとは想像もできない。それだけに軍隊が敗北しかかっていることが肌で感じられたのだ。
「今はサイポッツが滅びるかの瀬戸際のように思う」ノーマは言った。それは小さな声であるだけに、みんなの胸に奇妙に染み渡ったのだった。「あなたの前でこのような話をするのは心苦しいが、わかってくれ」
「滅びるのはサイポッツだけではないかもしれない」
トゥルーシャドウがつぶやいた。利菜が彼を見上げ、
「世界がねじ曲げられているから?」
座のほとんどがはじめて聞く言葉だったが、奇妙に現実味のある言葉でもあった。果たしてトゥルーシャドウは利菜に向かってうなずいてみせたのだった。
□ 七
ノーマとビスコは一同に断って、二人だけで別室に移動した。じっくりとこのことを話し合いたかったからである。また、蛮族であるトゥルーシャドウには聞かせられない話も多かった。ビスコは車椅子の側に丸椅子を引き寄せると、屈み込み、膝に肘をついた。
「蛮族を味方につけるのは賛成せん」
「だが、やれば勝てる」
「真実集まるかどうかはわからんぞ。トゥルーシャドウは本気で伝承を信じているようだが、他の者も同じとは限らん。蛮族を王都に招き入れて、今度は我々の支配者が奴らに変わるというだけだ。マーサ自体信用出来るのか」
「蛮族に王都を乗っ取らせて、彼女になんの得がある。奴らを倒せるなら一時的に王都を明け渡しても構わない」
とノーマは言った。彼は扉の方を向いて、ビスコとは視線を合わせなかった。
「イニシエの民が我々を怨み、報復活動にでるというなら致し方ないことだ」
そんなばかな。ビスコは身を起こして頭をかきむしった。ノーマは傷が深く、決着を付けたがっているように見えた。早急に。自分の生命に、もう自信がないのだろう。
「おれは父上の仇を是が非でも討ちたいとは思う。だが、森での惨劇が市民の身に起こることだけは看過できない」
「そうなれば王都の脱出も視野に入れよう」
「その後、師団を呼び戻して戦わせるのか? それこそ現実味のない話だ」
「どれもまだ起こってもいない話だ」ノーマはややうつむく。「おれはエビエラの残した伝承が今なら信じられる気がする」顔を上げ、はじめてビスコと目を合わせた。「あの娘のいったとおりだ。」
「世界の終わりだと? それは教団の妄言だ。昔からある神話にすぎない」
「おまえはこの一年、あんな目にあって、まだそんなことをいうのか!」
ノーマは大声を出した。ビスコはちらりと扉に視線を走らせた。ノーマのいうことはわかる。なにしろ彼らはイニシエの森に実際にいて、森の異変を目にしてきたばかりなのだから。ビスコはわざと自分から声を落として、
「エビエラのいう世界の終わりが本当にあったとする。とすると、それは建国戦争と時期を同じくして起こったということだ。あの男は、再びという言葉を使ったからな」
「つまり、食い止めたことがあるということだ」
イニシエの種族がマーサのために集まるかどうか、それはトゥルーシャドウにすら想像のつかぬことのようだ。なにしろ、エビエラのした約束とは、三百年と昔のことだ。
ただ、一つ。ビスコたちは王宮にまことしやかに囁かれていたうわさ話を知っている。ハフスがマーサと同じく、三百年以上にわたって生きていること、つまりハフスというのが、代々受け継がれてきた王名ではなく、一人の人間の名に過ぎないという噂だ。
むろんこれは口にするのも恐れ多い話だ。現にビスコは平民の前では口にできなかった。ハフスの威光はサイポッツにあまねく染み渡っている。王というだけではない、国民は彼に信仰心に近い感情を抱いている。それに、ハフスが建国戦争の英雄と同一人物であるならば、イニシエの民が彼を畏敬し、戴くのもわかる気がするではないか。
ビスコは唇を湿らし、額に汗をしながら熟考した。
「噂が真実として、建国戦争と同時期に今と同じことが起こっていたとしよう。とすると、マーサを襲った何者かは、大王と同じく、建国戦争の生き残りの可能性が高いのではないか」
ノーマはうなずいた。「その男は将軍の口を使って、エビエラの名を口にした。イニシエの民に伝わる小箱のこともな」
「マーサが宝の所在を知っていると疑ったんだ」
「マーサが知っているはずがない。その伝承はイニシエの民にのみ伝わってきたものだ。私は今日聞くまで知らなかった」
ビスコは首を左右に振った。「それはおかしい」
「なにがだ?」
「マーサは記憶がないといっているのだぞ。あの女の建国戦争時代の記憶はかなり煩雑としている。完全にうしなったわけではないようだが」
「記憶を消されたとでもいうのか」ノーマは鼻で笑おうとしたが、その笑みは途中で凍り付いた。「エビエラか?」
「そうだ。将軍はまず第一にエビエラの名を口にしたのだろう」
「とすると、小箱――その男はせいひつと言った。ようだが、それは実在していることになる。いったいなんだ?」
「わからない」
とビスコは答えた。わからないことはまだあった。その男――トレイスか、オットーワイドなのか知らないが――建国戦争から生きていたのなら、今までどこにいたのか? なぜ今になって戻ってきたのかがわからない。それにマーサから聞いた話を鵜呑みにするならば、男はハフスたちの敵であったようなのである。建国戦争でハフスが戦ったのはサウロンという男だった。
最終的にノーマは言った。
「我々に必要なのは行動だ。議論ではない。真相の解明は誰かがやるかもしれないし、わからないままかもしれない」
どうでもいいことだ、とノーマは言った。
「我々のなすべきことはこの馬鹿げた戦争をやめさせることだ」
「ハフス大王が生きていれば、国王の号令で戦争をとめることができるはずだ」
「ビスコ、ハフス大王に期待するな」とノーマは言った。悲しそうな声だった。「牢獄でずっと考えていた。ハフス王が存命ならば、なぜこの危機を救わない。できない、理由があるのだ」
「そんなばかな……」
「信じたくない気持ちはわかるが、もうおれは、ハフスに期待できない」ノーマは泣いていた。それはあきらめの涙だった。「父は、ハフスが退位していらい、ずっと苦悩していたようだった。ハフスが健在であれば、父もトレイスなどにそそのかされることなく、彼を頼ったはずだ」
「トレイスが、ハフス王を殺したのか?」
「わからない。父は何も言わなかった」傷が痛むのか、吐息をつく。「王都を巻きこんで戦うのなら、もう甘い期待を持つな。とりかえしのつかないことを、我々はやるのだぞ」
ノーマの絞り出すような言葉に、ビスコはうなずくことしかできなかった。
「大勢死ぬだろう。だが、これ以上の、戦争による被害の拡大は、食い止めねばならない。それこそ、取り返しのつかないことになる」
「では、どうする? 森の民は怒り狂っている。彼らを抑えることができるのはハフスをおいて他にないぞ」
「存命を装うしかない」
ビスコはノーマの言葉にぎょっとなったが、彼が唇を噛みしめているのをみて何も言えなくなった。
「その上で、師団に号令を出し、この馬鹿げた戦争をやめさせる」
「そのためには、トレイスたちを確実に殺す必要があるぞ。奴らに生き延びられたら、国はまた二分してしまう」
ましてこちらにはハフスに変わる王がいないのである。ダッタ王も行方不明のままだった。
「元々我々だけでやるつもりだった。覚悟を決めよう」
「わかった。みなに伝えよう」
ビスコは部屋を出ようとしたが、扉に手をかけた瞬間に気が変わったようにこういった。「これから一体どうなるんだ?」
わからない、とノーマは答えた。それはあまりに小さな声だったので、ビスコの耳には聞こえなかった。
◆第十四章 新たなグループ
□ 八
作戦立案に一日かかった。
王都の精鋭部隊はこぞって蛮族戦争にかり出されている、都の兵力は五千にも満たないだろう。陽動作戦が内と外の双方でとられることとなった。
ノーマはビスコとトゥルーシャドウが考え抜いた主案をきいて皮肉な笑みを見せた。これではまるで建国戦争の再来ではないか。
少年たちは得意の掠め技で武器弾薬をそろえつつあったが、むろんかっぱらい程度では足りない。決起の際は武器庫を襲撃するしかない。そのためにも計画がもれないよう隠密に行動する必要があった。リーダーたちは仲間にすら詳しいことを話さなかった。
トゥルーシャドウはイニシエの民をむかえいれるために王都をさり、ノーマたちは本拠を西地区にうつした。期限は一週間である。
「みながまんしろ」とノーマは病床でいった。「蛮族の手を借りねば、軍隊と戦えない。一週間のがまんだ」
期限をつけたのは、少年たちの精神にとってもよかった。そうでなければ、緊張のために誰もが耐えられなかっただろう。
「結局、ムーア教団のいうとおりなのかよ」とテドモントは言った。「世界は滅亡するのか?」
誰も笑わなかった。今では月並みとなったその言葉も、この場では力を持つように感じられたからだ。
「それをこの場で食いとめるのだ」
とノーマは言った。少年たちが無言でうなずいた。
イニシエの民がせめてくること、その軍隊をひきいるのは森の魔女だと流布してまわった。ムーア教団の語るあの方とは、マーサである、との噂を流したのだ。むろん、あの方の正体を誰も知らないことを見こしてのことだ。市民がどちらにつくかは、もはや賭というほかない。憲兵たちは、ビラをくばり、立て札をだして、噂の打ち消しにやっきとなったが、すべてがとろうに終わった。彼ら自体が、戦の準備にかり出されたからである。
森の魔女が戦争をとめる。世界を救うために立ちあがったという話は、噂として王都中をかけまわり、多くは好意的にうけとめられた。誰もがながい戦乱に飽き飽きしていた。戦争が始まって以来、政府の戒厳令が敷かれ、人々は情報に飢えてもいたのだ。
戦さの予感が、雷雲のごとく王都をおおった。人々は戦争がはやく終わることを祈るばかりだ。
政府はみせしめの処刑を断行している。主要な広場にはさらし首がならび、絞首台と死体がそのまま残された。暴動をおこした平民を処刑するために、王都そばちかくの草原に、巨大な穴をいくつも掘りすすめている。もし実行すれば、史上にも例がない大虐殺となるはずだ。
ノーマの心は焦った。五体が満足なら、駆け回りたいような気持ちでいた。自由な一般人のほとんどは、女子どもと病人ばかりだ。蛮族の助けがなければ、彼らものこらず鬼籍にはいることになるだろう。
□ 九
利菜があてがわれた居室は雨戸カーテンを閉めきって光も射さなかった。マーサの他にはヒッピたちしかいない。
王都にもどって以来、ヒッピは自分の立場にむず痒さをおぼえた。二人はその気もないのに、グループの一員として認められたようだった。下町の連中からは歴としたグループとは認められていなかったのだが、今ではリーダーの一人と扱われていた。ペックは妙に納得した。下町の少年というものは勇気を示すことに人生を賭けている節がある。頭が悪く、喧嘩が弱くても、勇敢であれば尊敬される。グループのメンバーが勇敢な者に従うのはなかば伝統によるものである。この二人が最大級の勇気をしめしたことは誰の目にも明らかだった。頭の固い大人からは忌み子とあつわれている利菜だが、少年たちからは尊敬されているようだった。
「いいのかい師匠?」
とパーシバルが言った。マーサが暴動の首謀者に仕立てられたことを心配しているのである。
「ビスコたちだって他に手があるのならそうしているさね」
と観念したようにいったが、マーサとてこのような事態を本意とはしていない。だが、状況がかほどに行き詰まっているのではやるしかないのである。
ヒッピは利菜のこと、むこうの世界で起こったことを詳しく語った。彼らはヒッピを知るように、佳代子たちや達郎たちのことを知っていった。わるいものと、数々のおさそい……。ペックたちはそんな目にあってもお守り様に乗りこんだ一同に、惜しみない尊敬の念を覚えた。利菜の心情をしると、むしろ彼女のために憤慨してビスコたちにくってかかった。今も護衛役を買って出て、部屋に詰めているのである。
下町には、グループがたくさんある。中でも、共通して賞賛されるのは、勇敢であることだ。利菜たちはいっぷう変わっているし、仲間に女の子もくわえているけれど、まちがいなくグループだとみんなは思った。
不安感はまるで見えない手のように彼女の両肩を押さえつけた。それだけにヒッピたちの支えがありがたかったのである。
「この子がこっちの世界に来たのはぼくらのせいだ。儀式のせいで、この子は一人きりになった。この子にもグループがいたのに、ぼくらが引き離したんだ」
「あたし、ヒッピたちのせいだなんて思ってない」と利菜は言った。「あのままだったらおまもりさまで死んでたかもしれない」
ヒッピはうなずいた。
「利菜も、ぼくらとおんなじなんだ。幻覚をみたり、夢にうなされてる。それがどんなことかは、みんなわかるはずだ」
四人の仲間はうなずいた。
「幻覚がうすらぐのは、仲間といるときだけだ。その仲間と、引き離してしまった」
ヒッピの告白は事実と多少ちがう。厳密に彼らの責任とは、利菜にも思えなかった。だけど、グループにとっては大きな衝撃のようだった。利菜が別の世界からきたとか、そんなことは三人にはよくわからない。彼らは神官ではなかったし、現場を見てもいない。だけど、もし、自分が仲間と引き離されて、一人になったとしたら……。
その結果は、ジブレの死が示している。みんなは内臓を根こそぎ抜かれるような思いであおざめた。彼らがよく理解したのはそこだけで、またそれだけで十分だった。
利菜は一同が自分を受け入れてくれたことを知ると勇気づけられた。「あたし、やっぱり佳代子たちを助けたい。元の世界に戻りたい」
「この子を仲間と一緒にいさせてやりたい」ヒッピが言った。「自分がもし死ぬようなことがあっても、そのときに、みんなと離れ離れになって死ぬのはいやだ。おれはこの子のこともおまえらのことも、ジブレみたいにはしたくない」
「メンバーがやったことは、グループのやったことだ」とパーシバルが言った。
「この子をおれたちのグループに入れてやろう」とペックが言った。
「この子は女だが、グループに入れるべきだと思う」とヒッピ。
ヒッピたちの世界では、グループに女は入れない。でも、この子は資格があるとみんなは思った。規約には、勇敢であること、仲間を裏切らないこと、困っているやつを助けること、とあるぐらいで、それも文章にしたためた物は、どこのグループも持っていなかった。
「パーシバル、バンダナは持ってきたか?」
ヒッピがいうと、パーシバルはポケットから三角に折った赤い布地を取り出した。模様が染め抜かれている。
「これはグループを証明するものだ。腕に巻くことが多いけど、持っていてくれればいい」
モタが不満げにいった。「でも、女の子を入れたりしたら、他のグループに笑われちまうよ」
「おれたちなんていつも笑われてるよ」
パダルが舌打ちをすると、みんなは苦笑した。
「ぼくらはなんとしても王城にたどりつくぞ。ハブラケットを助けるんだ」
ペックが言った。「ぼくらは口述で儀式を習ったけど、文献にも残ってるはずだよ」
「王族の秘宝だからね」
とマーサは言った。彼女は儀式には不明確な点が多いことを語った。そもそもなぜ危険な森で儀式を行い続けてきたかが疑問である。
「あの場所が特別だからではないんですか?」
「特別な場所ならいくらでもあるさ」
とマーサは笑った。利菜はナバホ族から逃げ出すときも、大鏡でみた渦を作り出したことを思い出した。
彼らは王城にたどりつくためにも、決起が計画されたのはよかったと考えるようになった。
それに利菜の世界とつながったことも偶然とは思えなかった。彼女たちはせいひつや消された記憶について話し合った。
ヒッピは、マーサの家で、自分たちを襲ったなぞの男のことを話して聞かせた。
パーシバルが訊いた。「そいつはなんなんだ? あの方なのか?」
ヒッピがうなずいた。「ぼくはそう思う」
「でも、おれたちに何ができるんだよ」とパダルが訊いた。「テドモントを相手にするのとちがうぞ。そんなすごい奴やっつけられるのか?」
誰も答えることができなかった。
「ぼくたち、力をあわせなきゃなんにもできない。グループがあるのはそのためだ」とヒッピは言った。「ぼくたちはずっとグループだった。ぼくたちのグループが本物なら、今こそ力をあわせるときだ」と彼は言った。「パーシバル。このグループをはじめたのは、おまえだ。結団式をしてくれ」
パーシバルは、折りたたみ式の小ぶりなナイフをとり出した。
結団式がはじまった。ヒッピがまず自分の手のひらを傷つけた。握りこぶしをつくって血をにじませる。ペックも、ジブレも。みんなが左手を一文字に開いていった。
利菜はこれからなにがはじまるのかを知っている、ヒッピの記憶を知っていたからだ。ヒッピが利菜の手をとり、彼女の緊張がとけるのを待った。
あたしは勇気をしめして、新しいグループに入るんだ。
ヒッピは切りすぎないよう、慎重に傷をつくる。手のひらで、血がにじんだ。彼らは互いの手をとりあう。小さな環ができた。
彼らは中央にバンダナをさしだす。パーシバルがみんなを代表して宣言した。
「おれたちは血を分けていないけど、これで血をわけた兄弟になった。兄弟は絶対に裏切らない、絶対にわかちあう、絶対に助け合うんだ。そして、自分よりも、仲間を大事に思うこと。卑怯な真似をしないこと。この規則を守れなかったやつは、地獄行きだ」
宣言の文句はとくに決まっていなかった。この言い回しはパーシバルの即興で、独特のものだったが、利菜には特別な効力を発揮するように思えた。
「でもよう」パダルが言った。「女だからって、特別あつかいってのはなしだぜ。おれだって、ちゃんとやったんだからな」
ヒッピは笑い出してしまった。
利菜が、どういうこと、と訊いた。
「度胸だめしのことだよ」
とヒッピがいったから、彼女は呆れてしまった。度胸試しならもう十分受けたではないかと思えたからだ。
少年たちは利菜の呆けた顔を見てますます高らかに笑い始めた。
マーサはやれやれとフードを目深にかぶった。
□ 十
トゥルーシャドウの旅は困難をきわめた。世界の変転はよりいっそう深刻なものになっていた。世界はねじまげられている、という言葉をなんどとなく思い起こすことになる。自分がどこにいるのかすらわからないことが多かった。仲間を集める以前に、再び王都に戻れるかすらおぼつかなかった。
出発前にマーサからもらったペンダントを胸に(それは大昔にハフスから贈られたものである)、幻覚を振り払い旅をつづけた。あるいはトゥルーシャもドウ(それは彼にとっても大それたことではあったが)世界を救おうとしていたのかもしれない。戦場跡や、虐殺の現場に出くわしたが、兵隊の姿はあまりみかけなかった。こぜりあいはあるようだが、大規模な戦闘は影を潜めていた。あれだけいたサイポッツの大部隊が、地上から消え去ったかのようだった。
トゥルーシャドウは、ミンダオ族とまず交渉し、彼らを伝令役に走らせた。ミンダオ族は、人間的な目を持つ他は、バンビに似ている。その四肢は長く、サイポッツやナバホ族のような器用さはなかったが、森を走破する速さは、イニシエの民でも随一のものである。昔はその特技を生かして、サイポッツの交易に手を貸していた。
ミンダオ族は、戦いへの参加に難色を示した。彼らの戦いぶりは原始的で、軍隊に虐殺された氏族も多かった。一族は、好戦派と傍観派とに分かれた。もともと、ミンダオ族は交易で栄えた種族で、日和見な風が身についている。トゥルーシャドウは、戦闘への参加ではなく、他種族への伝令を依頼することで、彼らの協力を取り付けた。
仲間は集まるのかトゥルーシャドウはわからなかった。森には数多くの種族があるが、すべてを集めるのは不可能だ。しかも、めぼしい種族はサイポッツの戦いに巻き込まれて消息もわからないのである。
森の異変がより顕著になったのは、あの神官たちが、儀式を行ってからである。
トゥルーシャドウは考えこんだ。トレイス、あの方、オットーワイド……そうしたものたちが裏で糸をひいている。彼らの狙いがつかめない。それに、異世界からあらわれたあの娘……
鍵を握るのは、マーサではなく、あの娘か? と考えてから、トゥルーシャドウは一人笑った。「まさかな」
□ 十一
ヤクハタ族はイニシエの森でも最大の種族で、湖を中心に巨大な都を築いている。土壁を粘液で固めた独特の住居が群れをなしている。その多くが破壊されたあとだった。
トゥルーシャドウは、ヤクハタの湖上王宮に案内された。ここだけは、サイポッツも攻めあぐね無事だったようだ。王宮の荘厳さは、聞きしに勝るものだった。若長は、そうした装飾のいくつかが、ナバホの手でつくられたものであることに目をとめた。
ヤクハタの王、ヤクターサは、老齢の大きな体を玉座に沈め、トゥルーシャドウを睥睨している。彼ですら一飲みできるほどの巨漢である。トゥルーシャドウは彼がすでに三百歳を超えていることに興味を持った。高齢であることと肥満も手伝って、立つこともできないようだった。
ヤクハタ人は飛び出た目玉が特徴で、体毛がまったくない。鼻も耳もなく、その場所には穴があいているだけである。は虫類を思わせる顔立ちだが、知能は高く、サイポッツとはまた違った独特の文化と文明を築いている。
「ナバホの若長よ、よくぞまいったな」とヤクターサは言った。「サイポッツの都を攻めるのに、兵をかせとは、豪儀な話だ。だが、我々とて森の軍隊との戦争に兵を裂かれている」
「存じております。ですが、その戦争を止めるためにも、兵が必要なのです」
「そう、マーサが申していたと?」
ヤクターサの巨大な目が光った。
「マーサは、サイポッツに囚われております。ハフスをおとしめ、サイポッツの軍隊を支配する男の名は、トレイス……」
ヤクターサは瞳を閉じ、そうか、と嘆息した。
「ならば、われわれは古い遺言を果たさねばならぬ。なによりも、今のような混乱は、古き人ハフスがお隠れになり、政治に関わらなくなったことに遠因があるとわしは思う」
とヤクターサは言った。イニシエの種族は、ハフスとマーサを古き人と呼んで、敬慕してきた。彼らが、世の終わりから世界を救ったと信じられてきたからである。マーサはハフスと区別して、森の人とも呼ばれている。
ヤクターサは言った。
「エビエラが世界の終わりを予見したとき、わしはまだ幼年であったが、父とともにその言葉を聞いた」
「ならば……」
「トゥルーシャドウよ。おぬしにわが軍の一部を貸し与えよう。さらに書状を書こう。この戦に参加すべき、いくつかの種族をわしは知っておる」
「三百年前にも、同じような戦争があったのですね」
「いかにも」とうなずく。「その戦争に、森の民とマーサは勝利した。あのときとて、サイポッツと我々はともに戦ったのだ」
「その相手は、トレイス……」
「トゥルーシャドウよ、答えをせくな。わしが思うに、世界の変転は足をはやめておる。もはやあのときより事態は悪化し、状況を把握することも容易ではない。おぬしは我が種族を連れ、その眼でなにが起こっているかを見極めてくるがよい」
トゥルーシャドウは膝をついた姿勢のまま、深く頭を下げた。
ヤクターサはそばに控える将軍や、大臣たちに目を向けた。
「ヤクトゥース、それにヤクハルムよ。トゥルーシャドウとともに、イニシエの仲間を訪ねるがよい――仲間をそろえ、サイポッツの都をたたくのならそれもよし。だが、本当の相手は、彼らでないことをゆめゆめ忘れるな」
□ 十二
トゥルーシャドウは、ヤクトゥース、ヤクハルムという、新しい仲間とともに、旅をつづけた。サイポッツの国に攻め入るというよりは虚無の森を逃げ出す脱走兵に見えなくもなかった。
二人の若いヤクハタ人にとっても、驚きの連続だった。森の変化は著しく、地図は役に立たなくなっていた。巨大な丘が隆起し、もしくは昨日まであった土地が消失し、壮大なる崖となっていたりした。それでも、彼らは古い仲間を訪ね歩き、反抗作戦への参加をうながした。
最後にトゥルーシャドウは、自らの出身であるナバホ族を頼っていった。氏族は気息奄々としている。
族長のヘテナムンは、まだ生きていたが、苦悩が老いを進めたようだった。
もう期日は迫っている。王都への帰途につかねばならない。
彼らは集落の、長の間に通された。
すぐさま、生き残りの氏族の長たちが集まってきた。
ヘテナムンは、無言でトゥルーシャドウを見つめるばかりである。少年のように輝く瞳は昔のままだった。だが、トゥルーシャドウは、その場にワークバイスやリトルロックの姿がないことを認めた。
「エビエラの遺言を果たすときが来たと、おまえはそういうのだな」
トゥルーシャドウはうなずく。ヘテナムンはかたわらの子どもたちをみた。
「ならばなにもいうまい。この子たちの未来を救うためにも、やれ、トゥルーシャドウ」
◆第十五章 反抗作戦
□ 十三
トゥルーシャドウの呼びかけに応じた種族は、数十に及んだ。主力は二百名のヤクハタ人であり、次にダンカン人が多い。残りは雑多な種族の寄せ集めとなった。一族を滅ぼされ、たった二人で参加して来た者たちもあった。
五百名の反攻部族が、平原に姿をあらわすと、王都の守備隊は騒然となった。彼らは王都の東にある、ファルカーク平原に移動している。
トゥルーシャドウは、サイポッツとの共同作戦を一同と謀らった。情報では、王都の守備隊の総数は二千名。十万人が暮らす都の防護としては驚くほど少ない。野戦には持ち込めないはずである。
彼らは、サイポッツの大砲の届かぬ位置で、ヤクハタ人が運んできた破城槌を組み立て始めた。六個の巨大な車輪の上に、鉄の固さをもつといわれるオークの巨木を乗せている。巨木の先端は鋭くとがり、鉄板に覆われている。いかな堅固な城門でも打ち破れぬはずがない。
破城槌の仕掛けは、防御にも及んでいた。サイポッツの銃撃を警戒してのことである。巨木の脇からは、分厚い鉄の板がひさしのように突き出て、下にいる押し手を守る。トゥルーシャドウたちはそれを押しの盾とよんで、まるで仏像か何かのように撫でるのだった。
車輪の隙間からは、横棒が左右に六本組まれた。これを多勢を頼りに押すのである。重量は相当なものだ。三人のタラハム族が頼りだった。彼らはヤクハタ人の戦いに長らく協力してきた。巨象とも思えるほどの巨躯をもち、その体は分厚い甲殻に覆われている。彼らの協力がなければ、ヤクハタ人もこのような思い切った武具を作らなかっただろう。サイポッツの攻勢は激しかったが、ヤクハタ人はこれまで武力を温存してこられた。それも、タラハム族との間に結んだ古い協定のおかげである。
さらに、トゥルーシャドウは重盾隊を組織して、前方からの射撃にそなえた。盾といっても一人で扱えるような物ではなく、上下左右に二メートルの分厚い鉄板である。これが三枚用意された。多少の砲弾なら跳ね返せるほどの厚みがある。
攻撃の不足を補うため、ダンカン人は別動隊となり、三台の巨大な投石機を組み立てた。破城槌の攻撃を後方から支援する手筈だ。
彼らは昼の合間を利用して、草原を活発に動き回り、戦の準備をすすめていった。城側からは、威嚇の砲弾が打ち上げられ、平原には灼熱した砲弾が転がった。そのいずれもが軍隊のずっと手前に落ちたが、轟音を上げ、大地をはねあげる迫力は見るだに十分だった。トゥルーシャドウたちは反撃の機会を待ち続けた。枯れ草が燃え、春風に硝煙のにおいが混じり合った。
□ 十四
ノーマにとってその一週間は途方もなかった。その長さと緊張感は、常軌を逸したのではないかと思われた。
彼らは情報と武器弾薬を集めることに忙殺された。ノーマとビスコは納得がいくまで作戦を練った。土地勘のある少年たちと彼らのもたらす情報がすべてだった。いくら話しても、わきおこる焦りはつきることがなかった。実際に始まってみるまでこの焦燥感は消えないだろう。
二人は強い不安やマイナスの感情にかられているせいだろう。以前より頻繁にわるいものを見た。わるいものを聞いた。それらを振り払って働いた。恐怖を覚えるには、心が凍えすぎていた。それは神経症の患者が自殺前に明るく振る舞うのにも見ている。二人は自分の生命に見切りを付けていた。
少年たちに武器の扱いも教えねばならなかった。ハブラケットたちはかかる事態を予想して、二人に武器の扱いを教えていた。が、皆銃器の扱いに関しては素人のようなものだ。何も一週間という時間を呪ったのは、トゥルーシャドウたちだけではなかったのだ。
トゥルーシャドウらが王都の周辺に陣をはって二日が経っている。政府の監視は厳しくなり、ノーマたちはほとんど連絡をとることができなかった。政府の手によって、反乱軍の襲撃がいくどとなく行われた。ノーマたちは内通者を恐れてアジトを転々とした。
マーサが王都に潜伏していることはすでに知られている。
もはや利菜の居場所はどこにもなかった。政府には、マーサの弟子がいて、その少女が黒髪であるということも知れ渡っている。マーサがひきいる(はずの)軍隊が勝利しないかぎり、この娘の居場所は、どこにもないのだった。
約束の日の当日、彼らの緊張は極限まで高まった。もはや軽口もない。誰もが押し黙り、攻撃の始まりを待ちかまえている。政府は平民の外出を禁じている。ノーマたちには、トゥルーシャドウがどのように集結したのか、知るすべがなかった。彼らが計画通りに行動してくれるのを信じるのみである。
ビスコとノーマは隠れ家の一室で、顔をつきあわせた。論点はたった一つ。どうする、ということだった。今となってはトゥルーシャドウたちの動向もわからない。すべてが賭けのようなものだった。
「平民たちは浅学で、文盲の者も多い。トレイスを知るまい。つまり、やつがムーア教だとは知らないということだ」
「すべての罪はトレイスに」
ノーマはうなずいた。「そうだ。そして、それが真実でもある」
ビスコは薄く笑った。「ハフスが死んだことにしなかったのは失敗だったな。当人がいなくとも、号令はかけられる。崩御の発表は、その後でもいい」
「ああ」
とノーマはつぶやいて、目頭を押さえた。貴族の彼には、王権を信奉するところが多く、ハフスの死が耐えられないのだろう。
だが、盲点がある。ハフスの死亡が確実になった場合、彼らはこの戦闘に勝利しなければならない。王都の完全制圧ができなければ、新政府を築くことも不可能だからだ。ノーマには、それがひどく難しいことに思えた。
期限はきた。
ノーマは長い沈黙のあと、口を開いた。
「行こう。トゥルーシャドウたちと連絡をとるのはもう無理だ」
ビスコはうなずき、グループのリーダーたちに指示をくだした。
二人は自らトゥルーシャドウたちを迎え入れることにした。それが作戦に参加してくれたイニシエの民に対する精一杯の誠意のつもりだった。仲間たちのほとんどは、西地区にむかい、戦いのために所定の位置についている。
彼らは、地下水道をつかって最後の行動を開始した。
□ 十五
王都の守備兵と憲兵隊は、東地区の城門に集結した。親衛隊士も十名が駆けつけ、攻城戦の指揮に当たった。
遠方では、ヤクハタ人を中心とした森の蛮族が、破城槌を着々と組み立てている。タラハム族の姿も見えた。甲殻におおわれた独特の肢体は、巨岩のようだ。数こそ少ないが、さながら小城のようでもある。守護兵たちは、彼らを相手に戦争を始めたことを、今更ながらに後悔した。
森の軍の進撃は、夜に始まるものと思われた。兵士たちは銃眼をうがち、銃に弾ごめをし、目標をねらって目をこらしている。夜間では銃撃が十分な効力を発揮しない。かがり火がいくつも焚かれた。
そして、夜になった。
□ 十六
城門が、かがり火で闇に浮かび上がっている。
ヤクトゥースとヤクハルムは、破城槌の進撃を開始した。王都からは砲弾が夜目にも赤々と撃ちあがる。車輪の音と砲撃音が鼓膜を満たす。大地の震えが足下に轟く。
ヤクトゥースは頃合いをみて、平原の起伏に潜んだ仲間に旗を振った。合図をみたヤクハタ人は、昼の間に仕掛けておいた煙幕に火をつけてまわった。ヤクトゥースのもくろみどおり、風は西側に向かって吹いていた。平原に、十色の煙がどろどろと上がり、軍隊の姿を覆い隠した。
「古き人、マーサとハフスを救うんだ! 全軍、進撃!」
ヤクトゥースが合図を送ると、ダンカン人たちの投石機も、射程距離まで移動を開始した。
ヤクハタ人と、森の部族は力を合わせて破城槌を押した。ごろごろと車輪の音がとどろき渡るなか、トゥルーシャドウたち、別働隊四百名は、王都の西を目指して、移動を開始した。
□ 十七
ダンカン人たちは、投石機にとりつき、射程の操作に躍起になっている。煙は彼らの目からも的を覆い隠したが、昼の間に、攻撃のために必要な仰角、距離の測定は終えていた。
投石機の傍らには巨岩が積み上げられ、さらに爆弾が荷台に積み上げられている。
ガオガランは爆弾の長い導火線に火を放つと、投石機の第一撃を発射した。砲弾が笛のような音を立てて夜空を駆け抜けた。同時に物見櫓に上った仲間が、下にいるガオガランに動向を伝えた。
「命中! 第二撃を用意されたし!」
□ 十八
ヤクトゥースは、ヤクハルムとともに、押しの盾の下で、仲間たちを叱咤激励した。ときに、押し手に加わって、進撃の手助けをした。サイポッツたちは、その間も煙のなかに砲弾をとばしてくる。彼らの砲撃は思ったよりも正確で、破城槌の脇を歩く歩兵の一部を、ときに吹き飛ばすほどだった。
タラハム人は、まさに五十名のヤクハタ人に匹敵した。二人は、破城槌の左右から、残りの一人は、真後ろから巨木のケツを押している。ヤクハタ人には太い押し棒も、彼らにかかっては擂り粉木のようだった。
風が吹き、ときおり煙が晴れた。まずいことに月が出ている。そのたびに守備隊からの一斉射撃が鳴り渡る。
押の盾に銃弾が炸裂し、その下にいるヤクトゥースたちは、鼓膜もやぶかれんばかりとなった。まるで鐘の中にいるようなものだった。これにはさすがのタラハム人も怒りのうなりを上げた。すぐさま盾隊が破城槌の前方に入り、銃撃をはねかえした。
ガアーン、ガアーン、ガアーン
サイポッツの攻撃はすさまじく、火花が轟とあがり、衝撃が波となってヤクトゥーの胴を震わせる。
「ひるむな! 近づけば大砲はうてんぞ! 中に入るんだ!」
「跳弾に気をつけろ!」
「みろ!」
と声がした。一同が息をのむなかを、ダンカン人の放った第一撃が、煙の尾を引きながら、城門の真上に吸い込まれていった。爆弾は、城壁の通路を転がったかと思うと、数秒後には炸裂し、上にいた守備隊と、堅固な城壁とを吹き飛ばした。
「ダンカン人がやってくれたぞ! 我らも続けえ!」
森の部隊は、勢いをまして城門に迫っていった。煙幕の保護がなくなっても勢いを増した。射撃はますます激しくなり、盾の隙間から入り込んだ銃弾が、ヤクハタ人や、森の種族の体を打ち抜いた。
ヤクトゥースは倒れた者に変わって押し棒にとりつきながら声を張り上げた。
「がんばれ! もう少しだ!」
東の門には、堀に石の橋がかかっている。栄えし頃は、数多くの商隊をむかえた巨大な橋を、破城槌が音を立てて渡った。ヤクトゥースは、部隊を鼓舞して、破城槌の勢いを増すと、高鳴る銃弾をものともせず、巌のような城門に第一撃を加えた。
◆第十六章 水門の攻防
□ 十九
トゥルーシャドウたちは、ファルカーク平原をよこぎり、西地区の城門前に集結した。
トゥルーシャドウは潜入隊を率いて、取り決めのあった水門へと急いだ。この日は雲一つない夜空だったが、東側から流れ出した煙が天を覆うようになっていた。トゥルーシャドウは部隊をいくつかにわけ、起伏に潜伏させると、自身はナバホ族の主だつ者を連れて小川の側に潜んだ。川幅は広くないが、深い。水を満々と湛えている。サイポッツの都は水の都でもある。王都からはこうした支流がいくつも流れ出ており、いずれも巨大な水門で固く閉ざされていた。
トゥルーシャドウは城壁の側まで近づいた。月は煌々としていたが、煙幕のために周囲はときおり暗くなった。彼のかたわらにはナバホ族カステカの若長スラブと、ダンカン人のクシュナがいる。水門の真上には、物見櫓が必ず備わっている。櫓には灯がともっているが、見張りの姿は見えなかった。西の城壁は驚くほど静かだ。一方東側からは、戦いを告げる鬨の声と、砲弾の炸裂する音が間断なく轟いてくる。
「ヤクトゥースたちの攻撃は始まっているぞ。サイポッツは何をやっているんだ」
眼をこらしたが、水門からあがるはずの合図は何もなかった。
スラブがトゥルーシャドウに語りかけた。
「トゥルーシャドウ、作戦は失敗したのではないか。彼らは水門を制圧できなかった。作戦をみなおすべきだ」
スラブたちは、水門を押さえる役目が少年たちであること、彼らに兵役の経験がないこと、また指揮官たる二人の青年が、文官にすぎないことも知っている。
トゥルーシャドウは彼らの非難をおさえ、じりじりと待った。しかし、水門からは、なんの応答もない。
□ 二十
ノーマたちが下水道を上がると、そこは西地区の外れだった。上水路の並木道で、梢を越して王都を囲う外壁が見えた。物見櫓も間近かった。兵の配置も把握している。ここは水門の一つにすぎず、兵隊も五名しかいなかった。
ノーマが連れてきたのは、テドモントとアンラールのグループである。射撃のうまかったものを厳選して二十名をつれてきた。さすがにリーダーの二人は射撃の腕も確かである。後は生きた標的を実際に撃てるかだった。
テドモントたちが車椅子をひろげ、ノーマを乗せた。ビスコが傍らに立ち、騒ぐ少年たちを落ち着かせている。攻城戦の音がここまで届いてきたからだ。守備兵は東地区に吸い取られるようにしていなくなっている。
ビスコは銃を受け取ると、「いいか、一斉に攻撃するんだぞ」と櫓を顧みた。まだ兵士を視認できる位置ではない。「反撃されたらまずい。訓練された兵士にはかなわんかもしれん。近くまで発砲を我慢しろ。遠くからは撃つな」
テドモントたちはふざけ口もきかず真剣にうなずいた。彼らは身を低くして慎重に移動した。ノーマの車椅子がたてるキィキィという小さな軋み音すら恐怖をさそった。
テドモントは昼間に櫓を偵察している。真下には詰め所があるが、歩哨に立っているのは三人だけだ。
「三人だ。三人しかいない。他の二人はどこだ」
櫓には誰ものぼっていない。ビスコは東の戦闘に駆り出されたのかもしれないと考えた。だが、周辺の巡回にでているだけなら、挟撃されるかもしれない。
ビスコがそのことを告げると、少年たちはパニックになりかけた。ノーマがすばやく命令した。
「テドモント、五人連れて行け。二人は見廻りに出ている可能性が高い。その二人、逃さず殺せ」
テドモントは泡を食ったようにうなずいたが、それでも仲間をつれて索敵にでた。ろくな訓練もなく、はじめての殺人だった。
「時間がない。探している間にこっちが見つかる。あの三人だけでも倒すんだ」
ビスコはアンラールたちに膝をつかせるとささやくように号令した。
「銃をあげろ。狙いをつけろ」
ビスコは自分も射撃姿勢をとりながら、呼吸が整うのを待った。
「撃て」
乾いた音が立て続けに起こった。少年たちの銃撃は、ビスコが期待した一斉射撃ではなくバラバラだった。
当たったのか?
ビスコは引き金の落ちる感触に怖気を覚えながら首を引き延ばす。みな、尻の穴がムズムズした。三人の兵隊は、しばらく立っているように見えた。が、やがてゆっくりと崩れ落ちた。
ビスコは銃を杖に吐息をついた。
「テドモントたちは?」
ノーマが車椅子の上で辺りを見回す。少年たちは闇に隠れ、姿も見えなかった。
□ 二十一
銃声が街路樹に響いたとき、テドモントはびくりとその場に立ちつくした。今の音で見つかったと思ったのだ。
はたしてそのとおりだった。
近くの茂みがざっとなったかと思うと、正面に巨漢の男が立っていた。テドモントはあっと声を上げた。後ろで二人が転んだ。昼間はこの男を倒そうと敵愾心を燃やしていた。夜間に見上げる兵隊はナバホ族かとみまごうほどの巨躯に見えた。
「おまえたちのしわざか、冗談ではすまんぞ」
と男は剣を構える。テドモントは恐怖に悲鳴を上げながら銃を撃った。銃先がぶれ、弾丸は男をかすめただけに終わった。
しまった!
テドモントは脇のレバーを引いて、空の薬莢を排出しようとした。振り返ると、仲間たちは転ぶか銃を抱えるかして震えている。彼らはこの期に及んでも人殺しをする度胸が出来ていなかったのだ。
「攻撃しろ、こいつを殺せ!」
「このがきども!」
兵隊が剣を振り下ろし、一人の肩を斬った。大人になりきれない柔らかな肌を切り、鎖骨を断ち、肺の中程まで達した。少年は泣き出しそうな表情を浮かべ、自らの体に食い込んだ刃の切っ先を見つめた。それから、あ、ああ、と絶望の声音を発すると、くずおれた。
テドモントは血飛沫をあびて凍り付いた。彼らの行動をうながしたのは、復讐心でも勇気でもなく、ただただ恐怖によるものだった。あの剣を自分に向けさせない一心で、銃をあげ教えられたとおりに引き金を引いた。四つの銃が闇雲に火を噴いて、兵隊の体に穴をうがった。右ほおから頭上に抜けた弾丸が致命傷になり、自らが殺した少年の上に倒れ伏した。
「伏せろ、もう一人いるぞ、攻撃される」
テドモントは仲間を伏せさせる。彼らは決死の思いで地面を求めた。寝転がったままあちらを向きこちらを向いて、ときに物陰に悲鳴をあげ銃を撃った。そこにいるのがノーマたちかどうかも確かめなかった。
そのとき兵士は彼らの左手にいたのだが、横手から現れた新たな少年たちによって撃ち殺されていた。
「テドモント、もう大丈夫だ。五人とも倒したぞ」
「ビスコか?」
「水門を開けるぞ。早く来い」
□ 二十二
トゥルーシャドウたちは水辺に群生する葦の影でやきもきとしていたが、そうするうちに、たてつづけに銃声をきいた。息をひそめていると、水門の向こうで松明が大きく左に右にふられた。トゥルーシャドウは仲間にいった。「行くぞ」
□ 二十三
ビスコたちは水門の鍵を奪うと、城壁の下にもぐりこみ、五層に渡る鉄格子を次々に開いていった。トゥルーシャドウを先頭に蛮族たちが冷たい水をものともせず陸続と都へ入ってきた。
「遅かったな」
少年たちはトゥルーシャドウの軽口にも反論する元気がない。もう心が鈍磨して、蛮族の集団にも驚かなかった。
ノーマたちは外の状況を聞き出した。東地区へのおとりが成功したことを知った。トゥルーシャドウが連れてきたのはダンカン人が半分、次にナバホ族が多かった。いずれも精鋭ばかりを集めてある。
ダンカン人は逃走経路を確保するために、西門を内側から攻めることになっている。ダンカン人らは少年らの導きで城壁に沿って走り始めた。
「二百名でとれるか?」走り去るダンカン人を目で追いながら、トゥルーシャドウが訊いた。
「西地区にはもう兵隊がろくに残っていない」とビスコ。「が、大通りの検問はとかれていないぞ」
「それら全部と戦うひまはないぞ」
「ついてきてくれ」
とビスコは言った。彼らはナバホ族を従えて、近くの運河まで走った。すでに三台の運搬船が舳先にランタンをつるし、彼らの到着を待ちわびている。
トゥルーシャドウたちが船に乗り込んだとき、爆音とともに北の空が赤々と燃えた。ここからでも火の粉が見えた。ノーマが始まったな、とつぶやき、ビスコがうなずいた。
トゥルーシャドウが訊いた。
「なんだあれは?」
「仲間に武器庫を襲わせている。検問は運河にもあるが、これで手薄になるはずだ」
ノーマが言った。「だが、戦っているのは少年ばかりだ。反撃をうければひとたまりもない」
「ならば、一刻もはやく手を貸すとしよう」
トゥルーシャドウの言葉とともに、少年たちが櫂をこぎ始めた。