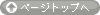「ねじまげ世界の冒険」へようこそ
このページは、ネットで小説を読まれる方用に用意しました。
長編、短編とそろえています。古い作品もあるので、できには目をつぶってやってください。
ねじまげ三部作も、よろしく!
ねじまげ世界の冒険
▼第七部 ねじまげグループの敗北
○ 章前 一九九五年 八月二十日 ――坪井宅 前段
□ 一
その日、おまもりさまに消えた友だちを救うために目黒区の坪井宅に向かったのは、尾上達郎、尾上新治、竹村寛太、杉浦佳代子、石川紗英の五人だった。佳代子は紗英と並んで自転車を走らせている。彼女にとっては大決断である。あのとき、坪井がどうなったのかは、彼女しか知らない。坪井宅に近づくほど、世界のねじまげは強くなった。肌に感じる空気が変わる――ペダルをふむ足が重い。恐怖と緊張感は一体となって胸を締め付ける。佳代子は自分が死に近づいているのを知っていた。利菜はおまもりさまに消えたから。普通のやり方ではあの子は救えない。そして、佳代子はこんな真実を知っている。出鱈目になった世界の中でこれだけは変わらないという真実を。佳代子はその真実を思って溜息をつく。
両神山がパワースポットだというのなら、坪井の家だっておんなじだ。
□ 二
再び目黒区に戻ったとき、佳代子は何かがおかしいと考えた。直感がここに来たことがあると告げているのだ。変だな、と佳代子は思った。来たことがあるのは当たり前じゃないのか?
五台の自転車は最後の角を曲がった。そして坪井の家を眼にしたとき、佳代子はその違和感の正体をみた。
ブロック塀に自転車が二台、寄りかかるようにして停まっている。みんなは近づくのをやめ、佳代子の自転車を見た。
おんなじだ。
手前にたてかけられた自転車は佳代子の物と瓜二つだった。彼女のは親戚からもらった赤いママチャリだ。似たものがあってもおかしくはない。しかし……
みんなは自転車を塀にたてかけ、そこからは徒歩で家に近づいた。二台の自転車も近くなった。佳代子はステッカーに書かれた数字を読んだ。まちがいない。神保南小5―46、とある。佳代子のステッカーと同じ数字だ。ステッカーだけでなく、傷もへこみも塗装のはげ具合もよく似ていた。寸分の狂いもなく似ていた。そしてブルーのチャリンコは、神保南小5―26。
「利菜のだ。なんでここに?」と紗英がささやく。「誰かが持ってきたのかな」
「でもこれはあたしのだよ」佳代子は自転車のサドルに手をおいて、それからもう一台の自転車を見た。ふいにあの日のことが思い出された。信じられないぐらい強力に。佳代子はコンクリートの染みや土の臭いまで克明に思い出すことが出来た。
空を見る。雲の形天気の具合、すべてがあの日とおんなじだ。門扉がかすかに開いている。利菜が開けたままなのだ、あの子は中の大人に気づかれるのが怖かったのか、わずかにしか開けなかった。彼女はそのことをみんなに話した。
「おれたち四日前に来たってのか?」達郎が言った。「中に佳代子と利菜がいるのかよ」
「行ってみよう」
佳代子は門を大きく開けて中に入った。洗濯物がはためいている。池では錦鯉の背びれがくねっている。来たんだ、あたしはあの日に戻ってきたんだ、と佳代子は思う。みんなも同じことを信じている、疑わしい、と、信じたくない気持ちも持っていたが、戻ってきたことを知ってもいた。みんなは互いの顔に目をやった。達郎はうなずくことで覚悟を決めろとうながした。
玄関に近づくと中から話し声がした。利菜の声だった。佳代子をぶったたいたら許さないよ、と叫んでいる。
「どうなるんだ?」達郎が佳代子に訊いた。
「あたしの母さんに利菜が怒鳴ってるのよ。このあと、坪井っておじさんが出てくる。どうしよう、あたしたちが出てくるよ」
達郎は二人に会うのはまずいと思った。タイムトラベルの問題なら漫画や映画で耳にしたことがある。タイムパラドックスというやつだ。
佳代子は急いで記憶をさぐった。「台所の脇に勝手口がある」
「そっちに回ろう」
五人は庭をよこぎって、裏口に回った。庭の洗濯物は家人のものではなく、川に流したあの服だった。しっかり血塗られているが気にしている暇がない。寛太は視線を感じて顔を上げた。周囲の窓という窓から住人がこちらを見下ろしている。熱心な目つきだ。必要以上に何かを念じているみたいな目付きだ。寛太はひっと短く息を吸いこんで、友だちの背中に張りつくようにして歩いた。池の鯉が、みんな死んでいた。
五人がようやく角を曲がると、玄関の扉が勢いよく開いて佳代子と利菜が飛び出してきた。ほんとにいた、と佳代子は驚いた。そりゃ彼女の直感は事実を明確に告げていたけれど(まったく脳みそをノックするほどの的確さだ)、この目で見るまで信じることができなかったのだ。
「利菜」
佳代子は飛び出そうとしたが、達郎が彼女を抱き留める。紗英が達郎の腕をつかんでささやいた。
「利菜をここで止めたら? おまもりさまにはきっと行かないよ」
「でも、おまもりさまに行った利菜はどうなるんだ?」寛太が言った。新治が、「それに佳代子が二人になるよ」
「みんなへんなこと考えるな」
達郎がぴしゃりとしめた。過去の利菜と佳代子は慌てふためくように自転車に乗って、坪井善三から逃げ去っていく。
佳代子は勝手口をみた。家は急にどでかくなった。恐怖でそう見えるんじゃない。実際に大きくなっている。ドアノブは腰ほどの高さのはずだったが、今では、背を伸ばさないと届かない。
おさそいだ。おさそいは始まってるし、あたしたちはおまもりさまの入り口にいる……。
佳代子は恐怖につばを飲む。細胞が泡だち身が震える。しびれるような恐怖、この夏に何度も感じた恐怖が彼女を襲う。
でも、利菜……記憶からも消え去ろうとする利菜の姿が、まだ目蓋にやきついている。佳代子はこう思う。利菜は確かにいたんだ、他の誰もが忘れても、あたしだけは忘れちゃいけない。あの子の髪着ていた服あの子がしてくれたことも、佳代子のなかに、戻ってきた。佳代子は自分が見たものを受け入れようとするかのように胸に手を当て服をつかむ。そうすると気が落ち着いて、震えが止まったのだった。
「利菜、あんなだったんだ、思い出したよ」
意を決して、取っ手をつかんだ。
鍵はかかっていたがカチャリという音がして、鍵が解けた。
「開けないで……」紗英がささやく。
佳代子は腕を引いた。レバー式のノブが下におり、ドアが開いた。
□ 三
中は薄暗く、八月の陽気だというのに冷たい空気が流れ出てきた。まるで家が死体になったみたいだ。あの日とちょうど同じ感覚、強烈な既視感、そして、聞こえてくるものも同じだった。
ズルズルッ
ビチャビチャッ
バリバリッ
「何の音っ?」
紗英が言う。男の子たちが息をのむ。みんなはこんなところに利菜はいないと思いたがった。もしいたらとっくの昔に食べられている。この家にいる、何者かの手によって。
達郎が桟に足をかけゆっくりと上にあがった。彼は見えない手に肩を押さえられているようだった。体が重たい。その家の空気は濃密で、何もかもが腐敗しているようだった。机の脇にある丸いペールのゴミ箱(燃えるゴミの袋がしっかりとかけてある)からは、子どもの物らしき頭が見える。その子がどうなっているかは考えたくもない。おまもりさまだ、と佳代子は考える。ここは両神山じゃないけど、あたしたちは確かにおまもりさまに戻ってきた。世界のねじまげがいっそう強く感じられる。
ズルズル、ビチャビチャ、バリバリ!
みんなは逃げ出すことを考えたが、行くべき所はどこにもなかった。残された道は前方にしかない。八月二十日当日、世界のねじまげはいよいよ強くなり、わるいものは勢力を増している。彼らはその最先端かあるいは末端にいて、現実の世界からずり落ちかけていた。
佳代子も土足であがった。最後の寛太になると、上がり框はいよいよ高くなり、上から引っ張ってもらわなければ登れなかったほどだ。寛太が登りきったとたんにドアが閉まった。色ガラスの向こうには子どもたちの影が見えた。
佳代子は死のもっともそばにいたが、利菜のそばにいることもわかっていた。もうすぐそばまでこれていた。そのことが、よくわかるのだ。
こんなに怖いのに、なんで意地をはるんだろう? 利菜に会いたいんだろう?
それはあの子が今も心に引っかかっているからだった。あの子が自分の中にいて、自分の一部になっている。あの子がおまもりさまの遠くに消えても、佳代子は未だにそのつながりを手にしている。そのつながりを、大事に思ってる。あの子がいっとう大切だ。そんな友だちのためなら、命を賭ける価値はあるんじゃないだろうか? 例えその命が風前の灯火だとしてもだ。
ズルズル、ビチャビチャという音はくぐもって聞こえた。脳の内側でどんどん強くなる。その音は物体みたいに彼女の粘膜を叩いている。音が醸し出すのは、明確な殺意に他ならない。
五人は知らず知らずのうちに手をつなぎ合った。おまもりさまを後にしてからこちら、はじめて再び心をつないだ。彼らは一塊の環となって、目の前にある悪意に立ち向かおうとした。
その先に進んだら死が待っていることを知りながら、それでも佳代子は声をかけた。
「利菜……」
廊下から聞こえた音が止まった。そして、台所から見える居間の扉の向こう。ガラスの影に、女の人影がすっくと立ち上がるのが見えた。佳代子は、うっと息をのんだ。母親登美子に間違いなかった。
○ 二〇二〇年 ――ねじまげ世界 八月十四日 午前十時十八分
○ 竹村佳代子、母親に会う
□ 四
携帯の、ベルが鳴っている。
佳代子はちゃぶ台の上で目を覚ます。机に肘をついて身をおこし、顔についた痕をこすった。座ったまま眠ってしまったものらしい。周囲が暗い。夜なんだろうか。
立ち上がり蛍光灯をつけようとしたが、ガラス戸の隙間から明かりが漏れている。雨戸が閉まっているのだ。
なんで閉まっているんだろう?
佳代子は自分が何をしていたのか思いだそうとした。それにしても部屋の中はクーラーをつけてもいないのにいやに涼しい。そのわりにうすいTシャツしか着ていなかった。今は夏なんだろうか? そんなことを考える自分に怯えて、ふふふと笑う。家計簿を付けていたのか、机にはノートが広がり手にはペンを持っていた。家計簿の脇に携帯がある。バイブで揺れている。
佳代子を照らしているのは、閉じた携帯からもれる淡い光だった。彼女はそれを手に取ることができず、立ちつくしたままじっと見つめた。
今しがたの夢を思い出す。夢の中では利菜と紗英につきあい、電車に乗っていた。三人とも小学五年生だった。なのにビールをかっくらっている。汗をかいた、マグナムドライを。利菜と紗英はむっつりと黙りこみ、佳代子はそんな気配なんてぜんぜんないのに遠足に行くのか? と訊いた。利菜は首を切り落とされた人間のようなゆっくりとした動作でふりむき、これから故郷に戻るのよ、と言った。そこで目が覚めた。
利菜からか?
その携帯はしつこかった。たっぷりと三分ばかりは鳴っていたろうか? 佳代子は蛍光灯のコードを引いたが、明かりはつかなかった。別に驚かなかった。
佳代子はゆっくりと手を伸ばし、携帯のはじっこを指で突いた。電流が走るかと思ったが、携帯はくるりと回転してテーブルの上を滑っていった。背後に視線を感じてふりむく。障子戸は閉まったままだ。寛太……と小声でつぶやく。返事はない。
手に取った。
携帯を開くと、画面の明かりが思わぬ強さで部屋を照らした。ディスプレイには妹の名前が書かれている。「伸子からだ」何かあったのか、と思った。あの子は一人暮らしだ。受話ボタンを押した。「もしも……」
「気に入らないね!」
怒声が耳をつんざいた。佳代子は背筋をしゃんと伸ばして凍りついた。伸子ではない。年老いて疲れ切った声だったが、酒焼けのした声音には聞き覚えがある。
「気に入らないんだ! おまえの全てが気に入らないんだよ! 幸せぶりやがって! こんちくしょお! おまえの全部をめちゃくちゃにしてやろうか!」
「母さん?」と佳代子は言った。その言葉に全身が総毛立ちいやな汗が出た。思わずパネルをみなおした。「母さんなの? 今どこにいるの? なんで伸子の携帯を……」
「なんでだと思う?」
腸のねじ曲がるような性悪な声だった。やいとをはじめる前には何度も聞かされた声だ。
胃が痛くなる。暗がりのせいかちっちゃな子どもに戻った気がする。佳代子はまだ母の暴力に怯えていたころのように、瞳孔をぎょろつかせてゆっくりと唾を飲む。彼女はほとんど泣きそうになりながらふりむいた。土間につづく障子戸がわずかに開いていて子どもたちの目が覗いていたからだ。これまで一度だって見たことがないような、性悪な目だった。彼女はその目にくじけそうになる、おさそいに負けそうになった。だけどここで引いたら――つまり自分の人生から一斉退去するならば――伸子はどうなるんだろう? そう思うと怯えがわずかに退き、立ち向かう勇気がわいたのだった。
彼女は等身大の自分に立ち戻るとこう言った。
「あの子に何かしたの? 何をやったのよ! 今どこにいるの!」
「どこだと思うんだよ! てめえが自分で考えりゃいい! あたしを探しゃいいよ! せいぜい探すがいいよ!」
「伸子を電話に出しなさいよ」
「命令するんじゃないよ! 何様だい、馬鹿野郎!」
怒鳴り声とともに、マグマのような怒りが携帯からふきだす。佳代子は耳が溶けたのではないかと左手を耳たぶに当てる。
登美子が言った。「あたしを叩きやがって! あたしに逆らいやがって! あたしにやいとをすえやがったな! あたしをこらしめやがったな! 何様なんだこの野郎!」
「母さん、話を……」
「育ててやったじゃないか! 食わしてやったじゃないか! 世話をしたのはあたしだぞ! 働いたのはあたしだぞ! こっちはさんざん働いたんだぞ! それを忘れやがって! あたしを痛めつけやがって、あたしを追い出しやがったな!」
「出て行ったのは母さんじゃない!」
「誰が出て行ったと言ったんだね!」
登美子は早くも支離滅裂だ。聞く耳すら持ちそうにない。佳代子は自分だけでも落ち着こうと必死になった。かっとなった母さんは、何をしでかすかわからない。佳代子の脳裏に包丁をふるう登美子の姿が目に浮かぶ。あれはたんなる想像ではない。実際にあった出来事のはずだ。佳代子は後頭部を手で触る。今の今まで忘れていたが、髪のない部分が未だにあった。
「伸子は母さんのことずっと待ってたのよ……」怒りはもう抑えきれない。「その娘に手を出す気」
「おまえにならいいんだね」
まるで獲物を狙う蛇のような声だ。佳代子は怖気をふるった。胃袋がでんぐりがえる。
「やってごらんよ」
やっとそれだけを言う。
「おまえの人生を奪ってやる! あたしがおまえになってやる! こっちにはね、あの方がついてるんだ! それなのにあたしに逆らうってのがどういうことなのか、おまえにたたきこんでやるよ!」
あの方?
佳代子は一瞬、恐怖を忘れて呆然とした。あの方? なにかを思い出しそうだった。
「ねえ、なにを……」
「非国民だ!」
「なに?」今度は本当に言葉をなくした。
「おまえの亭主は非国民じゃないか! 達郎も新治も、みんな非国民だ! 非国民の嫁は非国民だ! 非国民の仲間は非国民だ! 逮捕されるがいい! 拷問を受けるがいいよ! おまえらみんな苦しんじまえ!」
「わけのわからないこと言わないでよ……」胴震いが喉元を突き上げ、彼女は嘔吐きをのみこんだ。本物の気狂いなら、なんでもやるに違いない。
「あの娘っこたちがこっちに向かってる。あの二人の娘っこがね。だけどおまえはもうおしまいだ。坪井さまはぜんぶお見通しさ」
「二人の娘だって?」
利菜と紗英だ。
先ほどの夢がうかんで消えた。焦りと怒りで頭がどうにかなってしまいそうだ。脛を机にぶつけたが全く気にならない。あの二人がこっちに向かってる? 利菜と紗英が? 本当だろうか? 紗英はイギリスにいるはずなのに? それが二人一緒に?
「ほんとうだよ……」
部屋の中で誰かの声がする。佳代子がふりむくと太一が立っていた。まだパジャマを着ている。枕を抱きしめている。佳代子のことを、睨んでいる。
「なにをしてるの? 部屋に戻ってなさい」
と佳代子は言ったが、太一は佳代子を睨んだままだ。小学五年生にしては、背の高い息子。達郎のリトルで活躍して、真っ黒に日焼けしている。昔の寛太みたいな坊主頭。その息子が正気をなくしたみたいに母親を睨んでいる。そして、佳代子は信じた。あの二人はもうここに着くころだ。世界のねじまげはとどめようがない。だけど今は伸子のことが心配だった。たった一人の妹が、よりにもよって気の狂った母親といる。
登美子の声は一転哀れっぽくなる。「おまえだよ、おまえが、あたしから全てを奪ったんだよ。伸子も、伸子だ。あたしより佳代子になつきやがって。あたしの家でぬくぬくとしてやがったくせに……」
「マンションにいるの?」と訊いた。後ろで太一がうなずいた。「あの家にいるのね」
「ここは、あたしのもんだ! あたしのものをおまえらがとったんだ!」
「自分から出て行ったんじゃないか! 母さんはいつもそうだよ! 周りが悪いって、いつも思ってる! 自分がしたことは考えもしないくせに」
佳代子の怒りに悲しみがまじる。電話の向こうで、登美子が唸った。
「伸子を返して欲しかったから、うちに戻ってこい! 寛太はつれてくんな! 一人で来るんだぞ!」
登美子の、奇妙に甲高くて、しゃがれた声は、誰かの声に似ていたのだが、佳代子はようやく誰に似ているのか思い当たった。なめ太郎だ。声はなめ太郎に似ているのだ。
「あの子に手を出したら、許さない! 必ず地の果てまでだって追いかけてって、こっぴどい目にあわせてやる! やいとならあたしにだって据えられるってこと、忘れんな!」
「おもしろいね。のぞむところだ、馬鹿野郎」
通話が切れた。
佳代子は携帯を操作して、寛太を呼び出す。だが、つながらない、呼び出し音すら鳴らない。表示を確かめるとアンテナが一本もたっていなかった。
おかしい、なにかがおかしかった。さきほどの母の言葉。あの方? 非国民? いったいなんのことだろう?
太一を見る。彼女の息子は肉体だけの抜け殻になったかのようだ。佳代子の胸が張り裂ける。明るく笑う太一はもういない。たった一人の息子。何にもまして大事なものが壊れかけていた。彼女の指から、逃れようとしている。
「太一」
肩をつかむ。太一は遠くを見つめたまま首を揺らす。佳代子は息子をしゃんとさせたかったがもう時間がない。
利菜と紗英が、町にくる。
「太一、ここにいるのよ。外に出ちゃだめよ。母さんが出てったら、鍵をかけてじっとしてなさい」こう付け足す。「ここにくるやつは母さんと父さんの声を真似するかもしれない。ちゃんと確かめてからじゃないと開けちゃだめ。あたしたちしか知らないことを訊くのよ。聞いてるのっ?」
太一は口を半開きにしている。佳代子は冷え切った家で息子を抱いた。少年の体は、思いの外暖かい。
「必ず戻ってくるから待ってなさい」
佳代子は携帯を折りたたむと障子戸をひきあけた。土間にいた子どもたちがいっせいに逃げ出したが、佳代子は見てもいなかった。
「寛太!」
声が土間に吸いこまれる。佳代子は震えたが寛太を待っているひまはない。一人で行くのが危険だとはわかっている。登美子は一人ではないかもしれない。子どもの頃にみたわるいものは幻なんかではなかった。あれは確かな存在だったし、彼女たちには今もっておそさいがかかっている。
世界はねじ曲げられているという言葉が、何度となく頭に響く。だけど、伸子の窮地を思うといても立ってもいられない。気の狂った母親がたった今も信子を苦しめているようで、とても冷静ではいられなかった。
寛太家の土間は、壁で二つに区切ってある。壁の向こうのケートラに向かう。キーは差しこんだままだ。運転席に飛び乗ろうとする。かたわらの自転車が目にとまり動きをとめた。
「あたしのだ……」
二十五年の年月は、彼女の自転車をガラクタに変えていた。塗装は剥げあちこちへこんで、フレームが曲がっていないのが不思議なくらいだ。元は赤かったのに、この暗がりでは茶色く見えた。佳代子は、そう言えば乾いた血は茶色く見えたものだなあと過去をふりかえり考えた。壁に寄りかかったその姿は、疲れ切ったボクサーのようにも見える。ノックアウト寸前、けれどまだ試合が残っている。
中学の卒業まで乗って、その後は捨てるか人にあげるかしたはずだ。小学五年の夏何度も漕いだ、赤いママチャリ。ここにあるはずはなかったが、佳代子は自分のものであることを信じられた。世界のねじまげは彼女の自転車にも及んだらしい。大人になった彼女を運ぶために、健気にもここまで戻ってきたのだ。
子どもにとって思い出に残る相棒の一つは自転車なんだな、と彼女は思う。体をつかうという濃密さがそうさせるのだろう。こうして過去の自転車にふれてみると、あの頃の時間や空気が色濃くよみがえってきた。サドルの下にはこすっても落ちないお鍋のお焦げのように、ステッカーがしつこくこびりついている。神保南小、5―46。
「あたしのだ……」
自分たちの服がなんども戻ってきたように、自転車も時空の壁を飛び越えてここまでたどりついたかのようだった。きっとケートラは動かないんだろう。佳代子はあきらめたように吐息をつきながら、ハンドルを指でなぞる。自分たちを突き動かすものがいったい何なのか佳代子にはわからなかったが、その者は彼女たちの対決を望んでいる。
感傷が消え去るのと同時に、持ち前の行動力が佳代子の中でむくむくとわき上がってきた。対決だ、いよいよ対決のときを迎えたのだ。
「わかったよ」
佳代子は鬼の表情でハンドルを握ると、キックスタンドを蹴り上げる。自転車は主人の帰りを喜ぶかのようにまっすぐになった。タイヤは満タン、彼女のエネルギーメーターだってフルに回りきっている。わるいものと母親を向こうに回すなら、これでも足りないぐらいだ。
佳代子は納屋の戸をあけて、自転車を外に押し出した。外気は熱かった。記憶ではまだ梅雨のはずなのに、季節は八月の炎天下、腰の軽さは尻軽女。佳代子は初潮前の少女の軽やかさでサドルに腰をおろす。三十七歳となった今ではずいぶん低く感じられるはずなのに、目線は当時のままだ。まっすぐ目標を見据えている。
「太一、待ってなさい。母さんが全部なんとかしてやる」
胸から湧き起こるのは、あの当時なんども感じたパワーそのものだ。六人の子どもたちを結びつけたゆるぎない力。佳代子はそのパワーでもって自転車を漕ぎ出す。
心臓の音が高い。脳みそがフル回転している。佳代子はこう考える。利菜たちは戻ってきている、彼女たちは再び結集しようとしている。
私道から公道に出ると、アスファルトが消えて土の地面がむき出しとなっていた。二〇年前どころか。辺りの風情は昭和の時代もかくやといったところ。
佳代子は上等じゃないかとペダルを漕いだ。自転車は大海原を行く帆船のように、ねじまげ世界を横切り始めた。
□ 五
大森神社のある小高い丘のまわりを抜ける。この世界ではアスファルトは存在しないらしい。人々は、ガラクタ自転車にのったおばさんの姿を呆然と見送る。見知った顔もチラホラしているところをみると、戦前に迷いこんだわけではないらしかった。田んぼの脇を通って(稲は青々としげり、水田にはカエルがねぐらをはっている)溝をとおる風に吹かれながら町中に入った。のどかな田園風景と、けたたましいサイレン音とのギャップにぎょっと自転車を止めたのだった。
ダムの放流かと思った。それにしては音が近い。見ると街角のスピーカーから音が鳴っているのだった。道の中央にいる佳代子を尻目に家の中にいた人々は、いっせいに表に飛び出し群れをうって逃げ始めた。第三帝国だ、空襲警報だ、などと口々に叫んでいる。
空襲警報――?
胃袋がきゅっと縮む。人々はまるで佳代子がいないみたいに自転車を上手に避けて、一つの方向を目指している。声を聞いていると防空壕、あるいは学校を目指しているらしい。一瞬太一を避難させなければと引き返しかけたが、佳代子はその感情をかみ殺してしてペダルを踏んだ。幻覚だ、現実じゃない、そうに決まってる。
佳代子は自分に言い聞かせるが、心臓は恐怖に震えている。八月の外気に汗だくになりながらも道を急ぐ。町中を抜けた。川沿いの道を走った。爆音に空をみると、迎撃のための戦闘機がいくつもかっとんでいく。零戦によく似たプロペラ機だった。佳代子はおんぼろ自転車のスピードを限界ぎりぎりまで高めていく。彼女はわるいものを追い払おうと、耳も心も閉ざしていたのだが生家であるマンションを見上げたときそうした心の壁はいとも容易く崩れてしまった。
廃墟だった。
県営マンションの前にはもともと広い二車線道路があり、並木とともに歩道がのびている。そこだけはアスファルトの道が残っていたのだが、もう驚くにはあたらない。空は一挙に曇っていた。彼女の恐怖と感応するかのように風は早くも湿り気を帯びる。自転車を降りる。呆然と建物を見上げる。あの当時県営マンションは五棟あったのだが、左端は完全に崩壊して瓦礫の山とかしている。二号棟以下は無事だがいずれも迷彩柄にペイントされて、曇り空につきたっていた。
「こんなの、あたしの家じゃない……」
佳代子は自転車をおし、マンションに近づく。棟の間には駐車場と公園があったのだが、そこも雑草が伸び放題となっている。公園の時計がポールの上から彼女をみおろす。ガラスが割れて針も止まっている。五つあるランプも全て壊れていた。赤いタイルはあちこちで砕け剥がれている。佳代子は無意識のまま公園を横切り、駐輪場に自転車をとめた。駐輪場の屋根はコンクリートで出来ていたのだが、三分の一が崩落している。利菜の住んでいた三号棟が見えた。ガラスがほとんどない。カーテンが風に吹かれて外にはみだす。利菜のいた部屋を探そうとするが、マンションから人が見下ろしていたので目をそらした。
いったい何が起こっているのか?
佳代子は正気を失う崖っぷちにいた。伸子の存在がなければきっと逃げ出していただろう。達郎も寛太も、一人になるなと言った。だけど、気の狂った母親といる妹のことを思うと、佳代子はじっとしていられない。
佳代子は二号棟に近づいた。一階の中央には一号棟まで吹き抜けとなった通用道がある。左手にはエレベーターと階段があり、郵便受けのスペースになっていた。佳代子はコンクリートの歩道を横切り通用道に入った。子どもたちの格好の遊び場であったのだが、今は歓声も聞かれない。蛍光灯が割れ、残ったものも明滅している。光と影が不気味な陰影を生み出している。在りし日は住民の手できれいに清掃がなされていたのだが、今は空き缶とゴミが散乱している。そうした薄暗がりの中で、壁に吹き付けられたペイントが目に飛びこんできた。
落書きはスプレーで描かれている。くだらない絵と憎しみの言葉の数々、愛に関する記述は一つもない。第三帝国の記述もあった。そういえば、みんな口々にこの言葉を叫んでいた。空襲があるんなら戦争をしている相手がいるはずだが、壁の文字は多色なうえに重ね書きされていて、よく読めなかった。佳代子は壁に近づきペイントに手をふれようとした。
人類抹殺計画?
壁際にはられた一枚のポスターが目に入った。選挙演説をしらせるありふれたポスターだった。かなり以前に貼られたもののようだ。色落ちしていたし雨と湿気でよれよれになっている。候補者はカメラにむかって斜めにかまえる。佳代子はその顔に見覚えがあった。ポスターの下部に名前がある。
「坪井善三……」
佳代子は凍り付いたようにその名をみつめた。二十五年前にあの家でおこった数々の出来事が、急速によみがえってきた。この男はあの家で確かに死んだはずだ。死体だって見ている。
「いったい、何が起こってるのよ」
佳代子はポスターに背を向けると、エレベーターに急いだ。三階のボタンを、二度、三度と乱暴に叩く。彼女の行動に、マンションの主は腹をたてたものらしい。エレベーターのワイヤーが切れ真っ逆さまに落ちてきた。圧縮された空気が唸りを上げて扉を揺らす。佳代子が身を躱そうとした瞬間、地面にエレベーターが激突する。衝撃で扉がひしゃげガラスが割れ飛び、佳代子は真後ろに吹っ飛んだ。床を転がりゴミと壁に激突する。佳代子は驚きの顔で頬に貼りついた髪をはらう。エレベーターは、空き缶を押しつぶしたときのようにペシャンコになっている。扉の隙間から、大量の血が流れてくる。
佳代子はビニール袋に足を取られながら泡をくって表に飛び出した。思い出したのだ。坪井善三の家は、まるで家そのものが生きているみたいだった。ここもおんなじなのだ。生きている家、生きているマンション。窓という窓が目玉のように佳代子をみおろす。そのときになって、自分がずっと悲鳴を上げていることに気がついた。息がかすれて、途中からは声にもなっていなかったが。
佳代子は駐輪場に戻ると、ママチャリにすがった。なんとなくこいつだけは味方だと思ったのだ。
通用道にもどる勇気はもうなかった。佳代子はマンションの端まで行き、非常階段を駆け上がる。二階の踊り場に出たとき、田畑の向こうにのびる鉄道を、電車が通るのが見えた。
「利菜!」佳代子は手摺りから身をのりだす。
「紗英! 帰ってきちゃだめよ! 戻って!」
上を目指しながら呼びかけるが、声が届くはずもない。三階へとつづく非常扉に到達したときには、利菜と紗英をのせた電車は建物の陰に隠れてしまった。
「はあ、はあ、神様……」
胸の前で手を合わせる。周囲では空間が明滅している。ペイントされたマンションと、元の壁とが交互に現れる。佳代子の視界は波形のエフェクトを施されたみたいに歪んでいる。
「お願い、伸子のところに行かせて。あの子を助けたい、側にいてやりたいの」
そして、彼女はノブを回し扉を引き開けた。
□ 六
最初、佳代子は扉の向こうに黒い渦が広がっているのだと思った。目がなれてみると、三階の踊り場はちゃんとある。彼女は胸に手を当て呼吸を整える。意を決すると、踏みこんだ。
マンションが生きている、と感じたのがただの直観であるにせよ、佳代子は中に入った瞬間にそのばかばかしい法螺言葉が現実であることを知った。空気はまるで水飴のようだった。べったりとまとわりついてくる。過去と現在がチカチカと入り交じる、さらに七色の光が視界をおおった。
佳代子は落ちていた傘を拾った。ビニールはやぶけ、骨がむきだしとなっている。止めバンドには「杉浦」と縫い付けてある。
「そんなもの役にたたないよ」
男の子の声だ。ふりむくと非常階段に少年が立っていた。顔中で笑っているが、目だけは真剣そのものだ。彼が勢いよく扉を閉めると、猛烈な風が佳代子を襲って、彼女はしばらく呼吸ができなかった。
視界はついにねじまげ世界に落ち着いたようだった。佳代子はなんとなく、利菜と紗英が到着したんだなあと考えた。世界は閉じてしまった。もう戻れない。
「べつに、雨を心配してるわけじゃないよ……」
力なくつぶやき、傘を閉じた。
通路に出る。表札を確かめながら進む。301、302、303、ここだ。表札にはインクがべったりとついていたが、杉浦の文字がどうにか読める。佳代子は傘を胸元に引き寄せる。ここにきて自分がなんの覚悟もして来なかったことに気がついた。来ることに夢中になって、母親とどう話すかどう立ち向かうのかどこまでやるのかを考えてこなかった。母さんを殺すなんて想像もできない。だけど説得するのがむりなのに? 向こうはあたしをこっぴどく憎んでる。たぶん殺すつもりでいる……。母親との関係の終着点がこんな場所で佳代子は情けなくて涙が出た。怖くもあった。されることよりも何かをするのが怖かった。今度のやいとばかりは、魂までも焼き尽くされそうだ。
「だけど、伸子を助けてやらないと」涙声でつぶやく。「あの子があたしを待ってるんだ」
ビニール傘を片手に、ドアを開ける。窓の向こうの空が、目にとびこんできた。そんなふうに不気味な曇天ばかりが目に付くのは部屋が暗いせいだった。カーテンを開け放っているのに部屋は暗がりが多かった。それに見覚えのある伸子の部屋とちがう。あの子は物を増やすのがいやで、家の中はすっきりしている。大きな食器棚が通路にはみだし、カラーボックスには新聞の束。その新聞が通路にまではみ出している。部屋を間違えたのかと思った。右奥には洗面所と風呂場があるのだが、そこにかかったカーテンも記憶とちがった。子ども時代だった。目の前にあるのは、一九九五年当時の部屋だ。母さんと兄弟五人で暮らした家。だから足下には子ども用の靴が散乱している。佳代子はつま先の上にまるで歓迎するかのように乗った、紺色の子ども靴をどかす。チャックの付いた靴が抗議をするかのようにころりと横に寝転がる。
流しでは水滴がぴちゃぴちゃと垂れている。佳代子は傘を両手で握る。竹刀のように前方に垂らした。右手をそろそろと伸ばしわきにあるスイッチを押した。やはり妙だ。蛍光灯には灯りが点ったというのに、部屋は暗いままだった。まるで、マンションに沈殿した暗黒が、光を食らっているかのように。
佳代子は靴履きのまま台所にあがる。トイレの脇をとおり、伸子……、と呼びかけながら居間に入る。
「伸子!」
伸子はテーブルの向こうに倒れていた。佳代子が駆け寄ると、手足を縛られ気絶している。
「ああ、ひどい……」と彼女は涙声でつぶやく。伸子の頬を叩く。「伸子、伸子、しっかりしなさい」
□ 七
そのとき、登美子はトイレに隠れていたのだが、佳代子の声を聞きつけて、閉じた便座の上から立ちあがった。登美子は一升瓶を抱えている。中身が半分ほどへっているが、それは彼女がトイレの中で飲み干したからだった。やいとだよ……と彼女はつぶやく。彼女の唇はカサカサにひび割れて何かの禁断症状のように震えている。瞳孔がひらき、口端が上がる。歓喜していた。佳代子の野郎、これからいやってほどすえてやるよ。二度と立てないようにね!
□ 八
そのとき佳代子は伸子のかたわらに跪き、彼女を抱き起こそうとしていたのだが、こめかみを襲った強烈な一撃に昏倒した。伸子の体に覆い被さりながらも、それでもなんとかふりむいた。一升瓶を両手で振りかざす登美子の姿を血のにじむ目がとらえる。
「やいとだよ!」娘の腰めがけて一升瓶を振り下ろす。
佳代子は腰骨に痛打をくらって悲鳴をあげた。
「母さん……」額を血に濡らし呆然とつぶやく。そこにいるのは想像したような老婆ではない。登美子はおまもりさまの力で若返ったのか、三十代の若さに見える。
「ざまあみろ、この野郎」
登美子はまた瓶を振りかぶるが酔いも手伝って後ろにふらつく。佳代子はそのすきに、ビニール傘で母親の肩をついた。
「ギャア!」
娘の怪我とは比べるべくもないというのに、大げさな悲鳴を上げた。「やりやがったな、この野郎!」
「母さん……?」と佳代子は言う。足下で伸子が目を覚ます。一瞬ちらりと振り返りながら、「ほんとに母さんなの? 今、六十代のはずでしょう? なんで……」
登美子の年は、佳代子とほとんどかわらない。
「なんで?」と登美子はおどけていった。その顔はおどろくほど佳代子に似ている。「なんでだって? かわいそうだねえ、ちっちゃい佳代子。おまえはなんにも知らないんだ!」
「なにを知らないっていうのよ!」
「おまえはもうおしまいだよ! 達郎と新治はもうじきつかまる。赤紙が行ったからね! 坪井さまはなんでもお見通しだよ」
「坪井善三は死んだんだ! あいつはとっくに死んだんだ!」
「バチあたりめ!」
登美子は三度瓶を振り上げる。佳代子は傘を投げ捨て母親の腰に組み付いた。
「離せえ」瓶を縦にして、佳代子の体を打った。「離せ、この野郎!」
「二人ともやめて! もうやめて!」
伸子が縛られた手足をもたつかせながら叫んでいる。その声にますます憎しみが強まった。妹をこんな目にあわせやがって、悲しませやがって、「この野郎!」登美子の膝をとると床に転がす。瓶が登美子の手を離れる。
「何が坪井善三だ!」
自分でも信じられないような力がわいて母親の頬をぶった。
「なにがバチだ! なにがやいとだ!」
叫びながら、登美子をぶち続ける。このとき、佳代子は母親そのものだった。昔から、登美子のように他人に暴力を振るうことを恐れてきた。ここにきてそのたがが外れてしまったかのようだ。彼女は憎悪の力に酔いしれた。
佳代子は母親を打ったそのままの勢いで、登美子の首に手をかけた。
「おまえなんかもういるもんか! のこのこ戻ってきやがって!」首をしめる指が、汗ですべる。さらに力をこめた。「もう勝手はさせない。伸子にまで手をだすっていうんなら、この場で死ねえ……」
「やめて、姉さん! 母さんよ! あたしたちの母さんなのよ!」
「こんなやつ母さんじゃない!」
「母さんだよ! それはあたしたちの母さんだよ! あたしの母さんを殺さないでよ!」
その言葉で目がさめた。佳代子は呆然とふりむいた。伸子の脇には安っぽい立て鏡があったのだが、そこに映っていたのは佳代子ではなかった。登美子が二人いた。
「そんな……」
体の下で登美子が咳き込んでいる。苦しそうに喉を押さえている。まだ死んではいない。けれど、
「そんな……」
殺そうとしたんだろうか? 本当に? あたしが? 母さんを?
佳代子は呆然としている。その昔、利菜は、自分たちがわるいものに支配される危険性にだって言及しなかっただろうか? まさにそのとおり。たったいま、自分はわるいものそのものだったのだ。こともあろうか妹のその目の前で、実の母親を手にかけたのだ。
佳代子はゆっくりと視線を上げる。伸子はボタボタと涙をこぼし、それでも佳代子のことをはっしと見つめている。佳代子は唇がプルプルと震えるのを感じる。首がくきくきと固くなりわずかに顎を振った。「伸子……」
「姉さん、母さんを許してやってよ。一人なんだから、母さんは、一人しかいないし、一人ぼっちなんだから……」
一人ぼっち、というのが、登美子のことをさすのか、伸子のことをさすのか、佳代子にはわからなかった。だが、妹の涙をみるだに彼女は本来の自分を取り戻したのだった。佳代子は伸子の元に駆け寄ると、その縄をほどきにかかった。
「ここを出よう。みんなで逃げるのよ」
「姉さん……」
「母さんを殺す気なんてなかった。どうかしてた。あたしは……」
だが、その母親は娘を殺すつもりだった。なんとしてでも手にかけるつもりだった。登美子は呼吸を取り戻すと、娘の背中に忍び寄って、強烈なアームスリーパーをおみまいしたのだった。
「母さん、やめてえ!!」
伸子の絶叫にも、登美子は壮絶な笑みを浮かべるばかり。佳代子は苦しい息の下で、足をつっぱり身を振って登美子の体を引きずり倒す。すると、母親はその娘の体に馬乗りとなって、お返しとばかりに首をしめはじめた。登美子は娘を生むずっと以前からわるいものそのものだった。自分を取り戻すどころか。娘の首をしめて悦にいるその姿こそが彼女本来の姿だったのである。
「欲しいんだよう」と甘い声でささやく。まるで娘のことを犯してでもいるような表情だった。「おまえの人生が欲しいんだよう」そして、娘の頭を床に打ちつけ始めた。
「あたしがおまえになってやる! おまえの人生を奪ってやる! 坪井さまは大喜びだ! あたしのために死ね! 佳代子!」
佳代子は何度も後頭部を床に打ち付けられながら、今度こそ母親に情けをかけたことを後悔したのだった。
◆第十七章 貴族街の攻防戦
○ ジノビリ暦三年――東門にて
□ 九
二人のハクセン人は、もはや一族にとって最後の生き残りでもあった。そのイースターとラップルトックがともに弓術の達人であったのは何の因果かしれない。一族が滅んでからというもの二人は傭兵として各地で戦ってきた。彼らは盾の隙間から、何度も弓を射はなつ。油樽をもった男の目を射抜くと、落とし損なった油が城壁の上をダラダラと流れだした。兵士は城壁を転げ落ち堀に大きな水柱をあげる。塀の油がメラメラと燃え出す。彼らの弓さばきは目にもとまらない。まるで弓の上に矢が突然出現するかのようだ。次の瞬間には矢が消えて、敵を確実に葬っている。
ヤクトゥースはそうした雑多な種族をまとめ上げていた。さすがサイポッツとの戦争を戦い抜いた連中だけあって慣れない攻城戦にも実によく戦っている。が王都の守備隊も健闘である。
守備隊は灼熱した岩や、沸騰させた油を上から落としてきた。岩が堀に落ち、じゅうじゅうと水蒸気をあげている。油が土手の草を燃え上がらせた。ヤクトゥースたちは怪我人を続出させながらも城門への攻撃を繰り返した。破城槌をいくどとなく打ち込んだが、鉄の楔をうちこまれた城門は想像以上に堅固だった。
そのとき破城槌の後方にいたヤクハタ人が泡を食ったように叫んだ。
「攻撃だあ! 岩がくるぞお!」
ヤクトゥースはふりむいた。灼熱した岩石が、火の玉とかして飛んできた。石は橋桁にぶつかり何人かのヤクハタ人を吹き飛ばす、盛大な水しぶきとともに堀に落ちた。蒸気がモウモウとあがる中、ヤクトゥースはずぶ濡れになり立ち上がった。岩は後方から来た。あの方角から攻撃できるのはダンカン人に他ならない。
まさかなにかの間違いだ。ガオガランは射程を間違えたに違いない。
だが彼の思惑は、灼熱して迫る第二弾の到来によって断ち切られた。岩はクレーンから放たれた鉄球のように男たちを吹き飛ばし城壁へとめりこむ。
ヤクハタ人の若者が彼の肩を叩いていった。「投石機だ! ダンカン人が裏切ったんだ!」
「ばかな! 彼らがなぜ……!」ヤクトゥースは声をつまらせる。
「ヤクトゥース、思い起こせ」と別のヤクハタ人だ。「ダンカン人の爆弾は最初の一発きりだ! 彼らはなぜその後の攻撃をしない!」
そういっている間にも、投石機からは次々と岩が撃ちあがる。
「ダンカン人め、裏切ったな!」ヤクトゥースが怒りの叫びを上げたとき、投石機からは火だねのついた爆弾が放られるのが見えた。ヤクトゥースは重盾隊に号令する。
「盾を構えろ! 受け止めずに堀に落とすんだ!」
ダンカン人の攻撃は正確だ。橋の上で爆発すれば、みんなの命がない。彼らは力をあわせ必死に重い盾を傾ける。しかしそれ自体が重い鉄のかたまりである。本来は地面におき、壁として扱うものだ。
タラハム人のセルゲイが破城槌をほうりだしてその巨大な腕で盾を持ち上げる。重盾が土をこぼしながら持ち上がる。同時に爆弾が煙を流星のようになびかせながら落ちてきた。セルゲイは盾を左に傾ける。砲弾は盾の上を二度ばかりぶつかり転がると、土手にもんどり打って堀へと落ちた。
「爆発しない!」
「導火線の火が消えたんだ!」
「まだまだ来るぞ!」
投石機からは今では次々と岩が放たれている。中でも爆弾がやっかいだった。タラハム人たちは重盾にとりつきがんばったが、ついに防ぎきれなくなる。橋桁とともにヤクハタ人らが吹き飛んだ。
「ヤクトゥース、このままでは全滅だ!」
顔のすぐ側で誰かが喚いた。みな火膨れと煤にまみれて人別がつかない。
「うろたえるな!」ヤクトゥースは怒鳴りかえした。「おれたちの任務は王都を攻めることではない! こやつらをこの場に引きつけることだ!」
「まずいぞ、ヤクトゥース!」ヤクハルムが肩を叩いた。「トゥルーシャドウの部隊は、ほとんどがダンカン人だ!」
ヤクハルムの声を聞いて、ヤクトゥースは戦慄した。
すべてはトレイスの策略か
森の民はまだ見ぬトレイスの姿を思い浮かべる。このままでは全滅だ。
みな重い空気に沈んだ。そのとき若者たちにまじってついてきた老骨のヤクダンカンが、一同を叱咤した。
「なにをしとる! 人数を集めろ! ダンカン人を攻撃するんじゃ!」ヤクダンカンの言葉に、ヤクハタ人たちは目を覚ましたように隊伍をくみはじめた。「投石機は動くものの攻撃にはむかん。盾をかざして走るんじゃ!」
若者たちが駆け出すと、ヤクトゥースは決意したように森の民を見返した。
「ここに残るのは、ヤクハタ人だけでいい。イースター、君たちはたった二人の生き残りだ。なんとしてでも生き延びろ!」
「しかし」
「みな、堀に飛びこめ! 西を目指せ! トゥルーシャドウを助けに行くんだ!」
□ 十
ヤクトゥースは破城槌の攻撃を繰り返しながら、仲間たちの多くを堀から逃がした。破城槌は何度も門扉にぶち当たり、巨大な門に亀裂を走らせた。ついに城門を打ち砕いたのだ。だが、その裏では兵隊たちが荷車や家財道具を積み上げて、ヤクハタ人たちの進入を阻止している。
「油をかけろ! 中の物を燃やせ!」
ヤクトゥースの号令で、中の障害物に火がかけられた。城門の向こうで積み荷が音を立てて崩れると、タラハム人が力を合わせて門を押し広げていった。
弓隊の射手たちは隙間から次々と矢を射はなった。ヤクトゥースは剣の使い手を選りすぐると、砕けた門扉をくぐり抜け、王都に突入した。
○ 西地区にて
□ 十一
ビスコは多少気味が悪かった。不手際はあったものの作戦は順当に進んでいる。東地区への陽動が成功し、西側の防備は驚くほど手薄になっている。住民も戦火を恐れて家屋に潜んでいるようで彼らは中央にある大聖堂にむかう道すがら無人の野を行くがごとくだった。すでに少年たちは大聖堂を占拠して武器弾薬を運び込んでいる。女達が炊き出しに従事し、最後の食事をとっているところだった。脱走もあり数は八百名まで減っていたが、ここまでうまく運んだこともあり彼らの士気は高かった。
聖堂の前面には花咲き乱れる広大な庭園があるが、今は噴水も止まり不気味な静けさを保っている。遠方から砲撃の音が響くが、周囲は暴動が始まったとは思えぬほど静かだった。
森の種族が到着すると、少年らは無言で彼らを見やるばかりだ。彼らの親は蛮族と今もって戦っているし(生きていればの話だが)信用しろという方が無理な話だろう。
マーサがグループのリーダーを従えて彼らを出迎えると、トゥルーシャドウは拝礼をして恭順をしめした。本当にマーサを崇拝しているとわかって、少年らも安心したようだった。
ノーマは作戦を伝えるために最上階に連れて行った。大聖堂は西地区で最大の建造物である。上に行くほど砲音は高くなるようだった。そして、東の空が赤い。
バルコニーからは遙か王城を見渡すことができた。風は戦気をはらむようだった。王都は全ての灯が消えて混沌ととした闇に沈んでいる。
マーサは親衛隊がムスターサのようになることはあるまいと言った。兵士らの変化は、世界の変転が原因ではあるまいか。「トレイスの仕業とは限るまい。人の引き起こしたもののはずがないからね」
ともあれビスコは王城の護りを説明し始めた。軍隊の大半を東地区に引きつけたとはいえ、王城も丸腰になったわけではない。親衛隊が残っている。親衛隊はもともと王城の守護者である。ただの守備兵とはちがう。城の防備に関しては玄人である。攻めこまれたことこそないが、三百年間、王城の守備をかためてきた。
「城にたどりつくには貴族街を抜けねばならない」
ノーマは高台にたつ城をみやる。背後には巨大な神木があり、王城は神木の南に建っている。神木のある小高い丘に貴族街が円を描くように広がり、それ自体が敵の侵入をふさぐ要害となっている。
「大部隊の入れる通りは四本しかない。東西南北に走っている。幅は二十メートル。左右は邸宅の壁に囲われている」
「塀の高さはいかほどだ」とダンカン人が言った。
「三メートルだ。あなたがたはどうだか知らないが、我々では容易に越えられない」
「銃撃を受けるな」
「向こうはバリケードを築いて待ちかまえているだろう。城に着く前に決着をつけたがるはずだ。我々も弾丸をふせぎたい……」
そこでビスコらが容易したのは、鉄板を貼ったリヤカーである。子どもでも押せるし、弾丸をふせぐ盾にはなる。
トゥルーシャドウが貴族街を見ていった。
「斜面になっているな。上から狙い撃たれるぞ」
それに射撃の腕がちがう。トゥルーシャドウたちは銃の扱いなど知らないから、射撃は少年たちに任せきることになる。
「まともに撃ち合っては勝てる見込みがない。向こうは大砲も持っている」ビスコは大雑把な地図を広げた。「まっすぐのぼらせないために大道はまっすぐではない。3キロごとに道一本分ずらしてある。五カ所だ。親衛隊は坂道のどこかでバリケードを築いているはずだ。戦いに有利な位置をあらかじめ決めているのだ。本来足止めは守備兵がやる。今はその守備兵自体がいない。当人たちが出てくるぞ」
ノーマが言った。「装備は最新。剣術、槍術の達人揃いだ。接近戦にも強い。彼らが出張ってくると、接近戦ではとても戦えない」これはおまえ達に任すということである。「あなた方には左右の屋敷を乗っ取ってもらいたいのだ。銃隊も百名ずつ付いていかせる」
「上から射撃を行わそうというのだな」
とトゥルーシャドウ。ノーマはうなずいた。
「問題は親衛隊も同じ手でくるということだ」
「わかった。兵の排除は我々でやろう」
「親衛隊は精鋭揃いだが、数が少ない。五百名強だ。こちらはあなたがたを合わせれば千名はいる」
「子どもや老人がほとんどだがね」とマーサは手厳しい。
「そこでだ」とビスコは眉をしかめた。「心苦しいが、彼らの背後にまわって挟撃する役目をあなた方に任せたい」
「わかった。我々でやろう」とダンカン人の隊長が間を置かずにいった。ダンカン人ならまとまった人数がいる。別働隊として二百名をさけるし、迅速な行動がとれるはずだ。その動きに少年兵ではついていけないため、銃隊はあえて回さないことにした。
ありがたい、とビスコは頭を下げた。
屋敷に回す人数を抜いていくと、実際に大通りに立つ人数は五百名ほどになる。とくに森の種族を分隊にまわさなければならないのは痛かった。紛争に参加したことのある老人らはともかく、おおかたの少年は戦争の素人である。銃撃戦でもちこたえるしかない。
「親衛隊を退けたら、我々は王城に乗り込んで政治犯を解放するつもりだ。その上で新政府を築き戦争を食い止めたい。そのためには親衛隊がじゃまだ」ノーマは情熱的にしゃべった後は、食い入るように地図をみた。「同じサイポッツだが、死んでもらうぞ」
□ 十二
利菜にはかすかだが直観があった。あの城に行けば佳代子たちに会えるという期待めいた奇妙な確信である。ペックたちはその言葉を疑ったが、ヒッピは彼女の気持ちを慮って何も言わなかった。ともあれ彼としてはこの娘を守るばかりだ。
イニシエの民は約定通り、マーサの周囲に結束している。最初は銃撃戦になると予想して、森の混成部隊は後方に温存することにした。
「いいのかい、トゥルーシャドウ」とマーサは先を行くビスコとノーマを顎で示した。「あの二人は反乱の首謀者だが、政治の主導者ではない。政権の主導までは握れまい。戦後どうなるかはわからないよ」
「ハフスが生きていることを祈るばかりです」
マーサはうなずいた。「三百年前、あたしたちは勝った。今度もそうなることを祈ろう」
ノーマとビスコは部隊の先頭に出た。指揮を執るためだが、血気にはやる少年達を抑えるためでもあった。親衛隊を相手に力押しでは犠牲者が増える一方だ。
前衛は二十台のリヤカーで固めている。荷台の四方は厚い鉄板が張り巡らされ、移動式のバリケードとなっていた。貴族街に入ると、どの屋敷も灯が落ちて闇に巻かれている。みな戦闘の噂をきいて、逃げ出すか隠れるかしているのだろう。道は広大だが左右を塀に囲われて、少年たちは檻に放りこまれたような圧迫感を受けた。始めてくる貴族街に萎縮している。脇道が現れるたびに、部隊は立ち止まった。そこにも親衛隊がひそんでいるというかのようだった。トゥルーシャドウが叱咤するもなかなか足が進まない。
トゥルーシャドウはしびれを切らして言った。まごまごしている間にトレイスはどんな手を仕掛けてくるかわからない。
「ノーマ、進撃を速めた方がいい。城につく前に日が暮れるぞ」
「だめだ。みなおびえている」
ノーマも自分の焦りを抑えて言った。少年らにとってはこれがはじめての戦場なのである。ノーマは満足に動くこともできない体を呪った。荷馬車は野菜を運んでいた簡便なもので防御の板もない。荷台に打ち付けられた板に荒縄で縛り付けられている。腰の骨が砕けて尻を据えていられないのだ。馬が動くと体が揺れてまた痛みがぶり返した。拷問で受けた傷が開きじくじくと血がにじみ出る。そのうち膿みだすだろう。彼にはそのこともその傷によって生じる痛みも、どうでもいいことのように感じられた。死が訪れるのが今日ではないにしろ近いうちだ。拷問で内臓をやられたようだから。
ノーマが空を見上げると雲の隙間に星があった。荷馬車の揺れで、星空も揺れた。
トゥルーシャドウ、と彼は隣を走る蛮族に声をかけた。
「夜明けが来る前に片をつけたい。親衛隊は狙撃の名手が多い。明るくなれば、狙い撃ちに合うぞ」
ノーマはまわりを走る少年たちをみて心苦しくなった。しかし、年端がいかずとも銃さえ持てば大人と変わらぬ働きができることも事実だ。ノーマはそんなことを考える自分を恥じた。だが、同時にハフスを救い戦争がとまるのならば、自分たちの身が朽ちようともかまわない気がした。
□ 十三
大通りをいくと、三キロごとに直角の曲がり角にでくわす。ちょうど一本分、道が左右交互にずれているのだ。防衛のためだがこれが実にやっかいだった。先の見通しが利かないため親衛隊がどのような防衛策を用いているのかわからないし、角にくるたびに部隊の進撃がとまってしまう。
ビスコはときおりノーマの荷馬車に上がり込んで、斜面を這うようにして延びる大通りを観察した。斜面にいるせいか、王城を見上げているという感覚はより強くなった。
「親衛隊なんていないじゃねえか」と少年達の声が聞こえた。
「油断するな。貴族街の奥までさそいこむつもりだ」とビスコは言った。「弾ごめをしろ。装備の確認をしておくんだ」
果たして、丘の中腹で旗が幾本も立ち始めた。夜目にも鮮やかな黄金の鷲が、月光を受け金縁の刺繍が鮎の背光りのようだ。
「旗が揚がったぞ!」
「親衛隊旗だ!」
足元で少年たちが身を固めて、長銃を抱くようにかまえだす。トゥルーシャドウが部族の若者たちを偵察に出した。みな不安げに夜空を見上げている。ビスコはリーダーたちを呼びつけ、リヤカーを前に出すよう伝えた。大砲をうつにしてもまだ距離がある。けれど、夜風に激しくはためく隊旗は威嚇するかのようにも、力を誇示するかのようにもみえた。恐れおののくうちに、戦を告げるラッパ音が音高く夜空に響き渡った。
パッパッ、パラッパ、パッパッ、パラッパ
部隊の進撃は完全にとまってしまった。道の中央で右往左往するうちに、ナバホの若者達が戻ってきた。
「トゥルーシャドウ、先にバリケードがある。親衛隊がいるぞ」
みな色めき立った。ビスコもさすがに緊張をして、気を落ち着けようと胸を撫で下ろした。
「いいか、銃弾はまっすぐしか飛ばん。リヤカーより前には出るな! 作戦通りやれば必ず勝てる! 弾をくらって倒れん相手はいない! 銃を信じろ!」
オットーワイドがすぐそばにいて自分をわしづかみにしているようにも感じた。それはわるいものというよりもある種の死の影だった。ビスコはこの期に及んで自分の生命を惜しんでいる。そのこと自体に恐怖を感じた。どうやら大人しくは死ねないらしい……。
彼はその恐怖を振り払うように雄叫びを上げ、銃をかかげ、少年たちを鼓舞して回った。ノーマも荷台から声を張り上げる。「隊伍を崩すな。整列したまま進め」
「まずはリヤカーを出せ! 道の先でバリケードを築くぞ! 先制攻撃を行え!」とビスコは号令したが、リーダーたちはみな彼をにらむばかりで動かない。「どうした? 銃隊から前にでろ!」
と彼は訊いたが、動けない理由はわかっている。敵の姿を間近にみて、みな臆しているのである。
トゥルーシャドウが仲間を集めようとした。「仕方ない、我々が……」
「その必要はない!」ビスコはかっと腹を立てるとノーマの荷台に上がり、馬を操る少年に怒鳴った。「ニレビ、馬車を出せ! 先頭に立て!」
少年たちは驚いた。ビスコは脇にいた少年に向かって、「おいきさま。撃たんのなら、おれに銃をよこせ! きさまらよりはずっとまともに扱えるぞ!」
少年は赤子をとられるかのように銃を胸にかき抱く。ビスコは運転台に足をかけ、
「どうしたニレビ! すすまんか! 臆病者はまわりにいらん!」
この言葉に、テドモントらはかっとなった。
「行こうぜみんな!」
少年たちは前に進み始めた。重装備のリヤカーにとりつき、踵を滑らせながらも鉄車を押し出した。蛮族たちもくわわった。石畳の上を鉄板を巻いた車輪が重い音を立てて転がり出す。
ビスコは荷台を飛び降りると、少年たちと一緒にリヤカーを押し始めた。
□ 十四
彼らは曲がり角に集結すると、リヤカーを先頭に並べた。右端を支点にして、扇を開くようにしてバリケードを展開する作戦である。リヤカーにとりつく少年たちはみな一様に顔を強張らせている。親衛隊に狙われるのは真っ先に彼らなのである。
リヤカーを道に入れると、すぐさま射撃が集中して、鉄板が甲高い音をたてはじめた。貫通こそしないが、跳弾があちこちにとんで危なくて仕方がない。幾人かが肩や顎に弾をくらって昏倒した。少年たちは仲間の血をみてひるんだが、それでも空いた場所に別のものが滑りこんでバリケードを築いていく。
数多くの戦闘を経験してきたナバホ族は勇敢だった。少年たちを叱咤してたちまちリヤカーを並べ終わると、射撃を開始させた。
ビスコは自分も銃をもって、バリケードの中央に伏せた。鉄板の隙間から通りをのぞくと、親衛隊の築いた土塁が道路をふさいでいる。土嚢の上に軽装の親衛隊士が身を乗り出しさかんに射撃している。銃身が横並びになり火を吹くさまは、みなを怖じ気づかせるに十分だった。
「まだ遠い! これでは当たらん! バリケードを進めろ!」
ビスコは射撃を行いながらバリケードをじわじわと押し出していった。武器が同じでも、練度に差がありすぎる。
「全員、落ち着け! 撃つだけではなくもっと狙わんか!」
顔のすぐ近くで、火薬の煙と煤が散っている。彼はむずむずするような硝煙の香りをたっぷり吸いこむと、後ろでまごまごしている連中にいった。
「もっと人と武器を寄越せ! グループごとに分かれて射撃するんだ! テドモント、射撃の指令を出せ! リーダーどもはどうした!」
最初のうち、射撃はバラバラで親衛隊の攻撃を退けるのに十分ではなかった。数ではこちらが上なのに、敵の銃撃が激しくて満足に撃てないシーンが多かった。首を引っ込めるのに忙しくて、狙いをつけられないのだ。
そのうち、リーダーが各メンバーをまとめ始めたので、銃撃隊の少年らもようやく落ち着きを取り戻した。リーダーたちは各グループごとに一斉射撃を行い、それもビスコの指示で、甲と乙、二手に分かれて間断なく射撃をおこなったから、親衛隊側の攻撃もとうとう散漫になりはじめた。
「荷車の前には出るな! 手筈どおりやれ!」
ノーマが曲がり角から無理矢理荷車を乗り入れさせ、荷台の上に縛られたまま激しく号令をはじめた。こうなると、少年らの意気は大いに上がってバリケードの裏は熱狂に包まれた。
「ビスコ!」とトゥルーシャドウらが彼をつかまえていった。「小僧どもを屋敷に連れて行くぞ! 作戦通り上から射撃させる!」
「ああ、頼んだぞ!」
ビスコは怪我をした者は後方に下がらせて、手薄なところには人をまわし、必死の指揮をはじめた。親衛隊の中にいよいよにっくきオットーワイドがいるような気分になってきた。
戦場を眺め渡すと、操作はにぶいものの老人らの方が射線は正確のようである。ビスコは彼らを集めると、親衛隊の射撃の分厚い箇所に連れて行っては、敵を攻撃させた。
銃声はまるで晴れ間の雷鳴である。夜間の貴族街にとどろき渡る。屋敷に隠れ、あるいは自分たちのシェルターに非難した貴族たちは、その音にいっせいに耳をふさいだ。戦闘とこれから始まる略奪を思うと、おちおち隠れることもできない。
少年たちは、親衛隊を相手によくがんばっていた。正確な射撃に、数の多さで対抗している。一方で親衛隊側の銃撃も激しく、一斉射撃をくらってときにリヤカーが押し戻されるほどだった。
親衛隊は狙いを定めて撃っているようだ。鉄板の隙間にうごめく陰をみとめては、正確に発砲してくる。殺しにかけては玄人の連中である。ビスコの目にも違いは明らかだった。まるで狙撃手のように少年たちを淡々と殺している。
リヤカーに脇から銃をつきだしていた少年が頭蓋骨を砕かれ転がった。周りの少年たちがひるんで彼をみた。みな仲間の血を浴びて半べそ混じりだ。ビスコは声を励ました。
「頑張れ! ダンカン人が奴らの背後にまわるまで粘るんだ!」
◆第十八章 ねじまげグループ、裏切りに遇う
□ 十五
一方、屋敷に踏みこんだナバホ族も苦戦を強いられていた。親衛隊士とて蛮族との戦闘は初めてだ。彼らは数こそ少ないが、三人一組となり巧みに戦った。暗闇の中で、激しい剣闘が繰り広げられた。ナバホ族とて手練れの隊士を倒すことは容易ではない。少年らも銃撃で助太刀しているが、なにせ肝心の的が真っ暗闇のなかで激しく動き回っている。手探りで戦うような暗闘である。少年たちは小柄な連中を集めると親衛隊の背後に回りこんで銃撃を行ったから、ナバホ族たちもずいぶんと楽になった。屋敷を占拠すると通りに面した居室に乗りこみ、真上からバリケードの向こうを銃撃しはじめた。
□ 十六
頭上からの銃撃がはじまると、さしもの親衛隊も射撃の手をゆるめざるをえなかった。ビスコは好機と見てさらにリヤカーを進出させた。距離さえ近ければ、少年らの腕でも当たると考えたのだ。
ビスコとノーマはこれで優位にたてると淡い期待を抱いたが、異変が起こった。
平民の軍隊は曲がり角を挟んで二つの通りに二分されている。ビスコは負傷者は後方に回し、曲がり角から各グループを進出させては、撃ち手のグループと入れ替えながら戦っていた。なにしろ皆初めての銃撃戦ですぐさま頭に血がのぼる。少年らの疲労は著しかった。荷台の上にいるノーマが疲れた連中をみるとリーダーに指示して後方に下がらせ、変わって元気のある連中を呼び寄せている。このためビスコたちの攻撃はほとんどゆるまなかったのだが、その部隊の後方で騒ぎが起こった。
ビスコは声に気づいてふりむいた。通りの後方にいた者たちが人垣を押しのけるようにして進んでくる。「ノーマ、どうなってる!」と声をかけた。
ノーマも板に縛り付けられたまま、身をねじ切るようにして後方を顧みている。二人は部隊の先頭にいたから、曲がり角で何が起こっているのか読めなかったのだ。後方に控えていた少年が、
「後ろの連中が前に出てくるぞ!」と言った。しかし、前方にはリヤカーのバリケードがあってこれ以上進めない。現在も撃ち手のグループが盛んに発砲している最中である。中層はもう鮨詰めのようになり始めた。ビスコが見かねて立ち上がると射線が彼に集中した。側にいた少年らが彼の袖を取って引きずり下ろそうとしたが、ビスコは夢中で気づかない。
「なんだ、何が起こった!」ノーマが左右に身を捩っている。
「おかしいぞ! 人が来る! おい来るな!」ビスコは後方に駆け出す。「こっちはもう人でいっぱいだ! 下がれ!」
「ビスコ、戻れ! 銃撃の指揮をしろ!」ノーマは縄をほどこうともがいた。「おい、おれの縄を解いてくれ! 誰か後ろの連中を落ちつかせろ!」
そのうちにマーサがナバホ族に守られて彼の側まで逃げてくるのが見えた。利菜もヒッピたちに抱えられるようにして荷台の陰に這い込んでくる。もうどこも安全ではない状況である。周囲の屋敷も制圧できたのは半分で、同じ屋敷内から、敵味方の陣地に撃ち下ろしている始末だ。
ノーマは痛みと焦りで脂汗がにじんでいる。トゥルーシャドウが彼の縄をほどこうと荷台に上ってきた。「何を騒いでいる!」
「騒ぐなだと! 馬鹿を言え!」ノーマが叫ぶと口の端から血が飛び散った。「ダンカン人はなぜ親衛隊を攻撃しないんだ! 攻撃が集中しているぞ!」
彼の後ろでは、何かから逃げようとする少年たちと、下がらせようとする少年たちとでもみ合いが起きている。
トゥルーシャドウは大けがを負いながらも暴れるノーマをどうにか地面に引きずり下ろした。まったく狂人の態である。
「後ろから来ているのはそのダンカン人だ!」
とパーシバルが彼の膝に手をついて叫んだ。もう片方の腕は帽子をぎゅっとおさえつけている。その間も弾丸がちゅいんちゅいんと音をたて荷台の底板に穴を開けている。
「おい、屋敷側にも銃撃しろ! この攻撃を黙らせろ!」とノーマはパーシバルの肩をつかむ。ヒッピがすぐさまパーシバルらを手元にあつめて発砲を始めた。「ダンカン人だと? 奴らは遊撃隊のはずだろう!」
曲がり角からダンカン人らが銃撃しながら進んでくる。ノーマは呼吸がとまるのを感じた。
「ばかな、奴らがなぜこっちにくる!」
「間違いねえ! あれはダンカン人だ!」とテドモントが側にきて怒鳴った。グループの連中を連れている。ダンカン人を迎え撃つつもりなのである。「やつら裏切ったんだ!」
トゥルーシャドウが言った。「ノーマ、まずいぞ! 城門を守っているのも、ダンカン人だ! 城門をしめられたら、外に出られない!」
□ 十七
ビスコはノーマの側まで戻ってくると、予備のリヤカーを少年たちに引っ張り出させた。「残りのリヤカーを後方に回せ! 後ろの連中を守るんだ!」
「あいつら、仲間じゃなかったのか」
「今はちがう! 攻撃しろ!」ビスコは前方のバリケードに駆け寄ると、「親衛隊に攻撃をかけろ! やつらをバリケードから出させるな!」
通りの先が明るくなり、ダンカン人に気をとられていた者たちも一斉にふりむいた。親衛隊がバリケードの向こうでかがり火を焚きだしたのだ。
「なんだ、こっちから狙いやすくなるぞ」
とテドモントが言った。夜闇のなかで敵の動きが手に取るようにわかる。テドモントたちは夢中で銃をうちはじめた。ヒッピたちも彼らの輪に加わった。なんと利菜まで一緒だった。
ビスコは少年たちを叱咤した。「ちがう、大砲を撃たせるためだ! 全員砲弾にそなえろ!」
ビスコの言葉に、みないっせいに空を見上げた。同時にヒュルヒュルという花火を打ち上げるのに似た音が起こった。
「砲弾だあ!」
夜空に、砲が煙を巻いて落ちてくる。周囲は通りをさけて、邸宅に着弾する。ビスコたちは一瞬息を抜いたが、撃ち手が距離を修正しているのだろう。その軌跡は数をました上、しだいに通りに近づいてくる。
□ 十八
ビスコは砲弾の軌跡に眼をこらした。うちの一つが射線に入った。彼は泡を食ってふりむいた。
「くるぞ! よけろ!」
灼熱した鉄球が石畳を砕いて転がる。少年蛮族を問わず吹き飛ばす。
さらに笛の音がしたかと思うと、三つ四つ五つと砲弾が弧を描いて落ちてくる。とてもかわしきれる数ではなく、ビスコたちはたちまち陣形を崩した。リヤカーは砕かれ、鉄片が少年たちの上に降りかかった。
ヒッピが利菜をかばって彼女の上にかぶさると、彼の体に降りかかってきたのは仲間の体の一部だった。パダルとモタが彼の側に倒れこんできた。パーシバルがリヤカーから外れた鉄板をかかえて、一同の前に立てている。
利菜は血まみれになりながらヒッピの体の下でもがいた。おまもりさまでもひどい目にあったが、今度は生きていた人間の血なのである。少年達がパーシバルに強力してリヤカーの鉄板を立て直している。
ビスコは地団駄を踏みたい気分で空を見上げた。「くそ! さすがにやっかいだぞ!」
砲弾がリヤカーの陰にいる少年たちを吹き飛ばす。バリケードが破壊され、銃弾が次々と人を倒し始めた。
大通りは砲撃に引きちぎられた肉塊でむせぶようだった。正面からは砲撃と親衛隊の銃弾幕。後方からはダンカン人が湾刀を振り回して攻め寄せてくる。蛮族たちが後方に寄って支えていたが、あまりの混乱にまとまった行動がとれていない。ヒッピたちも攻撃のしようがなかった。砲弾を気にして十分な銃撃ができないのだ。そのうちに、親衛隊どもがバリケードの裏から乗り出す気配を見せ始めたからヒッピは仰天した。接近戦で彼らと戦うはずのナバホ族が後方でダンカン人と戦っているのである。ヒッピたちは慌てて射撃を開始した。砲撃でリヤカーが役に立たなくなると、地面に伏せ身をして銃撃した。が、その路面も仲間の血と肉塊でヌメヌメとしている。砲撃が周囲の塀を突き崩し、視界もきかないありさまだ。
「もうだめだ! あいつらバリケードから出てくるぞ!」
□ 十九
トゥルーシャドウはマーサをかばっていたが、こう攻撃の手が激しくては反撃のしようがない。ビスコとノーマは部隊を立て直すことも出来ない有り様だ。トゥルーシャドウは若者たちに指示して、利菜たちを連れ戻させた。
「マーサ様、どうされます?」
「信頼できる仲間を集めておくんだね」
とマーサは言った。トゥルーシャドウは疑問を顔に貼りつけて彼女を見た。
「負けをお認めになるのですか?」彼は毛皮の下で紅潮する。「だが、それでは世界は救えない!」
救えない? とマーサは言った。「それがなんだね? 負けたがどうした! おまえもあたしも負けっ放しじゃないか、何が変わったというんだい」
マーサがケタケタと笑ったから、トゥルーシャドウも少年たちも彼女が気が狂ったのではないかと思った。利菜はすっかり恐ろしくなり、彼女の腰にしがみついた。けれど、マーサの目は真剣だ。彼女は利菜に身を揺さぶられながら、
「まだ戦いは終わってない。ノーマとビスコをつれてこい!」
□ 二十
「このままでは、全滅だ……」
ノーマは動けなかった。ビスコとともにダンカン人をやっつけようとしていたが、彼ももう限界である。手をついて座りこむのが精一杯。
その彼のもとにトゥルーシャドウがやってくる。抱え上げようと手を伸ばすと、ノーマは激痛に苦悶している。傷口がとうとう破れたらしかった。
「私のことはいい。やつらを攻撃しろ」
「ノーマ、ここは捨てよう」
トゥルーシャドウが言った。ノーマがはっと彼をみた。
「全てはトレイスの策略だった。作戦は失敗だ。このままでは全滅する」
ノーマは我に返ったように顔を上げる。大通りは惨憺たる有様だ。人肉が飛び散り、石畳は人の血でぬめっている。死体と生きている人間が、半々の有様だ。彼は悔しさに歯がみする。
ビスコがどこにいたのか(彼は崩れた塀の下敷きになっていたのである)銃を杖に彼の側に戻ってきた。
「どうすればいい?」
とこの男も途方に暮れている。もはやこの状況を突き崩すどんな手立てもなかったのだ。
トゥルーシャドウはノーマを抱え上げると、マーサの元に戻り始めた。マーサは懇々と二人の貴族を説得した。
「戦いをしていれば負けることもある。ここはひくんだ」
トゥルーシャドウの言葉にノーマは顔を上げた。ふと脇をみると、利菜が彼の腕をつかんで震えていたのだった。ヒッピたちは彼女を囲むようにして銃を構えている。
そのとき突撃ラッパの音が高らかにし始めた。親衛隊がバリケードを捨てて攻撃をしかけてきたのだ。少年たちは恐怖に突き上げられめくらうちを始めている。ノーマはうなずいた。撤退を決意したのは、まわりにいる少年少女たちのためだった。これ以上死に顔には変えられない。
「わかった。トゥルーシャドウ、私を背負ってくれ。みんな、側を離れるな」
ビスコもうなずいて周りの少年たちに呼びかけた。
「脇道をつかえ! 貴族屋敷から逃げるんだ!」
こうなると、砲弾が塀を崩していたのは幸いである。少年たちは口々に撤退を叫びながら仲間にこのことを伝えて行った。こんな状況でもグループの結束はまだ確固としたものだった。
「おまえたち、バラバラになるんじゃないぞ! 固まって行動しろ! ナバホ族についていくんだ!」
屋敷を攻めていたスラブたちが、マーサの周りに集まってきた。大通りの窮地をみて降りてきたのだ。
ノーマがトゥルーシャドウの背中でいった。「みんなを逃がせ。我々は丘を登る……」
「ノーマ、城門の突破は無理だ」
とビスコが言った。マーサが彼の肩をつかんで黙らせる。
「考えがある。とにかく、この場を脱出するんだ」