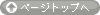「ねじまげ世界の冒険」へようこそ
このページは、ネットで小説を読まれる方用に用意しました。
長編、短編とそろえています。古い作品もあるので、できには目をつぶってやってください。
ねじまげ三部作も、よろしく!
ねじまげ世界の冒険
▼第三部 最初の七日間
○ 章前 二〇二〇年 ――東京
□ 一
結局41便は、予定よりはやく東京についた。到着予定時刻より、二時間もはやい着陸だった。
受けいれ側の管制塔も混乱がつづいた。機長のラルフと副長のエングルは、事情の説明におおわらわだった。乗客たちがみたという奇怪な現象、フライトレコーダにのこった動かぬ事実。お偉方は答えを知りたがったが、その答えを誰にもとめればいいのかもわからぬ始末だ。
だが、結局は、誰もが納得するしかなかったのだ。科学的な説明をつけようというほうが土台無理な話。このことは、誰もが心の片隅にとめながらも、忘れていくしかない。やがては、航空世界の七不思議として、語りつがれるだけになる。
語られるだけましというものだ。単に忘れさられる話よりは。
三日の査問会がおわると、紗英はすぐさま半年間の休暇を申しでた。こんどは、ナンシーも止めなかった。紗英が申し出たのは、退職ではなかったし、彼女に休職が必要なのは、仲間の誰もがみとめるところだ。同僚との亀裂も、紗英は辞さなかった。神保町にもどるつもりだった。はたすべき役目があるのなら、それを完遂するまでだ。
空港近辺のホテルをとり、高村利菜に連絡をとった。
電話のあと、タバコを片手に、ベッドに腰掛け、それから、おかしなことに気がついた。紗英が、半年間の休暇をとったことについて、利菜は驚きもしなかった。むしろ、当たり前のような口の利き方をしたのだ。
紗英は、服を着がえ、髪をといた。待ち合わせのカフェは、そう遠くないところにある。約束の時間には、まだはやい。だが、じっとしてはいられなかった。
ふと手をとめて、別れぎわのナンシーの、不安げな表情を思い出す。きっと、自分は、そんなナンシーよりも、ずっと不安げだったのだろう。エングルの、別れることをほっとしたような、よそよそしい態度。つかれきった、利菜の声。
電話ではなにも訊かなかった。神保町のことも、山のことも。近況すらも。
紗英はタバコに火をつける。あの光の渦をとおりぬけるときに感じた、超自然的な力はもはや消えていた。脳細胞が、隅ずみまで開ききったような感覚を思うと、不安でしかたない。自分でないなにかが、体にはいりこんだような感覚。それが麻薬以上の快感だったら、始末におえない。きっと、自分を抑えるなんてできなくなる (この一年間、彼女がとりくんできたのは、まさしく、自己統御の訓練だったのだが) 。
「利菜のやつ……」
組んだ手のなかで、タバコの火がすこしずつ位置を変えていく。吸えば吸うほど短くなるタバコとおなじで、こんな状態がつづいたら、自分が磨りへってしまうにちがいない、と紗英は思った。恐ろしいのは、これから会おうとしている旧友が、磨りへっているように感じられたことだ。
紗英はあの渦をぬける瞬間、その昔に起こった出来事を、ほとんど思い出しかけた。出来損ないの脳みそは、気絶している間にほとんど忘れてしまったけれど。
それでも記憶力だけはすぐれたほうだ。
幻覚や夢遊病といった症状が、きっと利菜にも起こっていたんだろうな、と彼女は思い、そんな話をどう切り出したらいいのかで、また頭を悩ますのだった。
□ 二
紗英が指定したのは、キャラバンという名のオープンカフェだった。いい具合の日差しで、風も気持ちが良い。十時を半分ばかり過ぎたころあいで、客の入りもよかった。さきに着いたようだ。窓際の、通りがみえる席に案内された。
コーヒーをふたつ注文した。携帯に着信があった。席を指示するうちに、利菜の姿が入り口にみえる。手をふった。利菜がふりかえしてくる。その明るい表情に、紗英はほっとする。
中学以降も、親友との連絡は、途絶したことがなかった。日本に帰省して、利菜や佳代子に会うのが楽しみだった。母親に会うよりも、この二人の顔をみるほうが、安心したものだ。ホームグラウンドにもどったような、そんな感じ。
フライトアテンダントになって、世界中をとびまわるようになった後も、東京にもどるたびになにかにつけて連絡をとり、利菜に会うのがつねとなっていた。たがいに社会人となり、昔のことなど多忙な毎日に埋没していたのに、いまだに親密な関係がつづいていたのは不思議なことだ。だけど、ここ一年ばかり。利菜とも神保町の旧友とも、連絡をとっていなかったのだ。紗英はそのことに気づき、身震いをした。
紗英は、親密な関係がつづいたのは当然だ、と考える。子ども時代にあんなことがあったのなら(たとえ記憶が欠落していたとはいえ)、自然なことではないのか?
なのにこの一年ばかりは、意識的にしろ無意識にしろ、旧友のことをさけてきた。おまもりさまでともにつかまった面子のことを、忘れていたのだ。
物思いにしずむうち、利菜が店員と二言三言かわして席にちかづいてきた。
利菜はすわりもせずに、紗英の肩に手を置いた。
「ひさしぶりじゃない、相棒。いつ東京にもどったのよ」
「まずは席につきなさいよ」と紗英は言った。「コーヒーたのんどいたから。アメリカンでよかったよね」
「なんでもまかすわよ。そこにかんしちゃ、あんたがプロだからね」
二人は声をころして笑った。利菜がすわった。
「秀雄さんはどうしてる?」
「元気よ」
「純ちゃんは?」
「バスケットはじめて張りきってるわ」髪をかきあげる。「あの子とも会ってないでしょう?」
「何年生になったっけ?」
すこし間があき、「五年生」
「そう……」
利菜に会ってふくらんだ気持ちが急にしぼんで、紗英はうつむいた。利菜の娘も、あの頃の自分たちと、おなじ年代になっていたのだ。紗英はすべてが符合しているようで、息苦しかった。
「ジョンとはどうなったの?」
紗英は鼻でわらった。「もうわかれたよ、あんなやつ。絵ばかり描いて、口ばっかでさ」
「絵で思い出したけど、わたしも本を出すことになってね」
「ほんと? すごいじゃん?」と目をまるくする。
「といっても、もう出版したんだけどね。絵本を一冊。とうぜんいってないよね」
利菜の質問につばを飲む。利菜が、この一年連絡すらとっていなかったことに気づいていて、それ以上のことを言おうとしていることに気がついのだ。
顔を上げ、表情に不安がまじらないことを祈りながら、利菜の瞳をひたと見つめた。佳代子になにがあったの? 寛ちゃんになにがあったの? あんたたちはなにを知ってるの? と訊きたくなったが、その疑問は瞳のなかで渦巻くばかりで、一言も口にすることはなかった。本当は、すでに事がはじまっていることを知っていたからだし、利菜が口にすることで、その現実とむきあうことが怖かった。
彼女はまた顔をふせ、ミルクティの揺れを見つめるふりをした。
「どんな本?」
と訊く。利菜が顔をあげたので、
「いやいい。内容はいわなくていい」と取り消した。
「なにが書いてあるか知ってるの?」
「知るわけないじゃない。楽しみはとっておきたいだけよ」
だけど、なにが書いてあるかは知っていた。これまでの経過をおもんばかるに、利菜の絵本があのときの出来事を題材にしていることは、容易に想像できたからだ。怖いのは、利菜がそれを書いたときに、まったく狙っていなかったことだ。きっと彼女だって、おまもりさまのことはすっかり忘れていたはずだから。
二人はそれから、とりとめのない話で盛りあがった。幼馴染が顔をあわせたら、かならずといってとりくむ話題。昔話と、当時の知り合いの近況について、花を咲かせたのだ。利菜は、小学生時代の恩師が、また神保小学校にもどったことを教えてくれた。中学時代にくっついた、吉田と熊谷という先生の間に、三人の子どもが生まれた話。初恋の谷村君に、三人目が生まれた話。だけど、どこかしら紗英はひっかかっていた。ながい付き合いのせいか、利菜がいろんな話をふせているように感じられた。悪い話は、全部。
ひとしきり笑った後、利菜は椅子にもたれかかって吐息をついた。ガラスごしに通りに目をやった。
紗英はそんな利菜を見つめている。二人は本題にはいる覚悟を決めたようだ。
「そろそろ帰ってくるころだと思ってたよ」
「わたしのシフト表でも持ってんの?」
利菜は笑わなかった。真顔で紗英のことをみかえした。「そんな気がしただけ」
利菜は話した。神保町でまた殺人事件が起こっていること、行方不明事件が起きていること、クラスメイトの子どもが殺されたこと。
「松本君の息子さんだったの? 良治君?」
利菜はうなずいた。
「うそでしょう。犯人は捕まってないの?」
「つかまってない。警察は連続殺人の犠牲者じゃないかっていってる。遺体の一部を切りとられてたんだって。佳代子が教えてくれた」
「佳代子とは連絡をとってたの?」
利菜は首をふって否定した。「ここ一年は、ぜんぜん」
紗英はまたティーカップに目をおとした。ふと二人が、カップをなでまわしたり見つめたりするばかりで、中身をひとつも口にしていないことに気がついた。
利菜の顔からは、笑みが消えていた。かたい表情だった。
「子どもたちが殺されてる。寛太や達さんの知り合いの子どもよ。私たちの知り合いの子どももいる」
「待ってよ。わたしは最近まで、五年生のときのことを覚えてなかったのよ。あんたはどうなの?」
ややあって、「おんなじ。五月に佳代子が手紙をよこすまで、あの山のことはすこしも思いだすことがなかった。でも、夢や幻覚ではずっと暗示してたのね」
「幻覚をみてたの?」
「おかしい?」
「おかしがってるように見える?」
「真剣なふうに見えるね。あんたも見てたの?」
利菜は取調官のような冷静な目で、紗英のことを観察している。相手の話を、じっくりと訊くときにみせる、冷徹な表情。
「見てた。溺死女をなんども」
「あたしも見たよ」
「不眠症にもかかった?」
「かかった。夢遊病にもかかった」
「帰りの飛行機でさ……」
と紗英はいいかけて、ふと口をつぐんだ。41便には仕事で乗りこんだのに、紗英はいま、帰りの飛行機と口にした。べつに、日本に帰省する予定ではなかったというのにだ。
「飛行機でなにがあったの?」
「おったまげるようなことよ」
紗英は笑おうとしたが、唇がふるえて中途半端に終わり、きゅっと唇を引きしめた。
話した。飛行機のなかで、溺死女があらわれたこと、コクピットで見た光、そのなかを通りぬけ、結果的にロンドン東京間のフライトを二時間ばかり短縮したこと。それは空間を飛びこえたことにほかならない。集団での瞬間移動といえなくもないが、そんな話は査問会ではいちども口にしなかったし、仲間と再度話しあうこともなかった。
そのとき利菜のみせた行動は意外で、それでいて利菜だからこそ納得のいくものだった。彼女は、さも納得したようにうなずいたのである。
「佳代子はね、またおさそいがはじまってるんじゃないかっていってる。それも、子どものときよりずっとひどいことが起こってるって。わたしはあのときのことを全部思い出したわけじゃないけど、でももう一度……なんていうのかなあ」
と言葉につまった。利菜にはめずらしいことだった。
「召集がかかってるってこと?」
「誰から?」と利菜は問いかえす。
「わかんないよ。でも、あんたはおさそいっていった」
「子どものころはそういってた……」
「わるいものって? 昔はあいつらのこと、そう呼んでたよね」
「幻覚のことを?」
紗英はうなずく。利菜は、
「でも、あれは幻覚以上のものだったよ。あれがなんだったのかは思い出せないけど、幻覚は人を殺したりしないし、佳代子をひっぱたいたりしないんじゃないかな……」
「みんなはどうしてるのよ?」
「まだ町にいる」
利菜は知っている経緯を、ひとつずつ話しはじめた。佳代子たちが山にもどったこと、自分に手紙をくれたこと。佳代子との電話のこと。
「もうひとつ困ったことがあってね」
と利菜は笑った。不思議な、笑いたくもないのにそうしているような、不思議な笑みだった。
「うちの両親と連絡がとれないのよ。あのときも母さんがいなくなったはずだけど、とにかく電話をしてもつうじないの」
「携帯は?」
「だめだった」
紗英は息をのんだ。思いだしたのだ。
「またあの家に?」
「どうかな……」利菜は眉根をよせる。「坪井って人が死んで、あの宗教はなくなったはずだよね。母さんも、足を洗ったはずだし。でもね……」
利菜は口をつぐんだ、訴えるような目で見つめてくる。
「わたしは両親とも連絡をとってなかったのよ。一年ばかりの間、神保町のことはいっさい考えてこなかった。無意識のうちになんだろうけど、わたしは逃げてたんだと思う」と彼女は言った。「でも、ここまできたら、そうもいってらんないよ。あんたはどう思うの?」
紗英は指をくみあわせた。「あんなことがあったのに、みんな忘れてのほほんと生きてさ、つけがまわってきたって感じよね」
「忘れたのはあんたのせいじゃないよ」
「ともかく……わたしはなんだかわかんないけど――」と胸に手をあてる。41便で感じた力のことを思う。あの女が発していた力のことも。「自分に働きかけてくるなにかがあるのを知ってる。わたしだってこの一年、わけのわからないまま生きてきたけど」
仲間やまわりの人間に、さんざん迷惑をかけたけど。
紗英は、男性ほどもある上背を精一杯のばした。
「それが私の人生なら、むきあうしかない」
「よくいった」
と利菜が微笑んだ。
とはいえ、石川紗英といえば、高村利菜が、上原利菜のままで、そのことに感謝したいような心持ちだった。
紗英はともに過ごした中学時代をおもい、そのときかわした友情も、その後に自立した人生を歩めたことも、全部小学五年生のあの夏に起因していたのだと感じたのだ。
利菜は、セカンドバッグを手にして立ち上がった。
「午後の便で千葉にもどろう。両親のことも確かめときたいし、こっちにいても、なにも始まんないからね」
「どんなことになるかわかる?」
利菜は首を左右にふった。
「わかんないけど……むこうにもどったら、思いだすこともきっとあるよ」
「出かけることはいってあるの?」
「旦那にも娘にもいってある。何日になるかわかんないけど、むこうにもどるって」
紗英は、利菜を追って立ち上がる。
「秀雄さんはなんていってた」
「秀ちゃんには、町の様子はいってないから。娘もいっしょに連れてけなんて、いってたけどね」
「殺人事件のことは知らないの?」
「知らない。話してないから」利菜は会計をすますために財布をいじくりだした。
「それっておかしいんじゃない。出版社につとめてるんでしょ? あんたの故郷で連続殺人が起こってるんなら、耳にも入ってるんじゃないの?」
テレビにもうつっているはずだし。
「知ってるだろうけど……」利菜がふりむく。「連続殺人の起こった神保町と、わたしの故郷がおんなじ町だとは思ってないのよ。わかる?」
「そんな……」
「つまりこういうことよ」紗英の肩を叩く。「あんたのいう力が働いてんのは、わたしたちだけじゃないってこと。秀ちゃんやみんなに働いてる」
「うれしそうね」
利菜は肩をすくめて、「公平ってことでしょ? それならわたし、納得できる」
紗英は不服そうに唇をかんで眉をひそめたが、心中では利菜の意見に納得していた。彼女だってこんな事態に巻きこまれるのが自分たちだけだとは、考えたくなかったからである。
◆ 第三章 バスツアー
○ 一九九五年 八月十九日――土曜日
□ 三
血を洗いながし、服を着がえた。
なめ太郎はいなくなったが、混乱は去っていなかった。紗英は、襖をあけ仁王立ちする溺死女を何度もみたし、ほかの面子もご同様だった。達郎は、布団の上に一同を集め、固まりあって座るようにした。パニックを、なんとか抑えようとしたのだ。
風がごおごおと吹き、ガタピシと、雨戸が揺れている。このままじゃあ、家が壊れるんじゃないかとみんなは思った。屋根の上をなにかが走り、軒下からは部屋をおとなう物音がし、隣室には誰かの息づかいがあった。
利菜はこんなことがつづいたら、ぜったいに気が狂うと思った。坪井の家では、杉浦佳代子をわるいものから守った彼女も、ここでは気持ちが切れかけていた。寛太郎がいない。心理的な防波堤が、なくなった感じだ。大津波がみんなの心を押しながしている。なんでもいうことをきくから、勘弁してほしいと考えていた。
長い夜が明け、雨戸のかすかなすきまから光がおちた。ばあちゃんとおばさんが起きて、みんなはしかたなくご飯を食べた。二人の大人は、子どもたちの不可解な様子にも、まったく注意をはらわなかった。六人ともが、出された食事の十分の一も食べなかった。ご飯を口にはこぶ箸はふるえ、爪のすきまに入りこんだ血の痕をみては、吐き気をもよおすありさまだ。おかずの味が、まったくしない。
食事が終わると、彼らはまっすぐに、岩野辺川までいった。その川は、寛太の家から歩いて二、三分のところにあり、自転車なら一分とかからない。川辺の草は、朝露にぬれていた。この日は雲もなく、岸辺もじきに干上がってしまうことだろう。
石ころだらけの土手からは、岩野辺橋の高い欄干がみえた。
血まみれの服を、川にながした。
やっぱり山にもどるしかないの? 佳代子が訊いた。達郎は無言だった。だけど、家にもどろうとむかった自転車のかごを見て、新治が悲鳴を上げはじめた。ホラー映画の子どもみたいな、理想的な悲鳴の上げ方だった。彼は口をОの字にあけ、絶叫しはじめたのだ。「ぼくんのだ、ぼくんのだ、ぼくんのだ!」
すぐさま達郎が抱きつくことで、その口をふさいだ。だけどみんなは見た。新治の自転車の荷台には、おまもりさまでなくした靴が、手際よくつっこまれていた。正確には、靴の片方は金熊川にながしたのだが。両方とも戻ってきていた。
「無駄なんだ」と新治は言った。「川に流しても無駄なんだ。こいつらはみんなもどってくる。なにをしてもむだだ」
「そんなこというな。そんなことない。そんなこと思ってもいけない」
達郎が言った。
「でも見ろよ」
寛太は自分の自転車から、なめ太郎にとられたはずの帽子をとりあげる。案の定だ、と利菜は思う。彼の帽子が、血に濡れていたからだ。
「あんたのせいよ、あんたがおまもりさまに行きたいなんていうからよ」
佳代子が寛太を責めはじめた。寛太は口のなかでもごもごいったが、その言葉はだれにも聞きとれない。
達郎が佳代子をとめた。「やめろよ。寛太が林にいこうっていったとき、おれたちは誰も賛成しなかった。そのときは行かなかった。気がついたら、いつのまにか林の前に立ってたんだ。そうだろ?」
「そうなんだよ……」
利菜がぽつりと言った。その確信をこめた口調に、みんなは彼女をかえりみた。利菜はしゃくりあげている。パニックの渦に、飲まれようとしていた。
「い、いつのまにか草原に行ったみたいにさ、いつのまにかそこに行ってるかもしれない。そこってどこかわかんないけど、でもおっかないとこなのに決まってる。あたしどんな目にあうか、わかる。英二君や、秀幸君みたいな目にあうんだよ! 人殺しがいて、そいつに殺されるんだよ!」
利菜は絶叫した。紗英が手をかけようとしたが、その手を振りはらう。彼女はみんなから離れて背中をむけた。
達郎は自分たちの結束が、いまここで崩れるんじゃないかと思った。だけど、利菜は必死の努力で涙をひっこめ、ふりむいた。
「どのみち行くんなら、あたしたち自分の意思でいくべきだよ。だってあのときのみんな、ほんとにおかしかったもん」
おまもりさまへの訪問を思いだす。友だちに、腕をつかまれたときのこと。
「いままで黙ってたけど、あたしのことおまもりさまにおしやろうとした。みんな、あんときあやつられてた。行くんなら、ちゃんとしてるときに行きたい……いつのまにかそこにいるなんていやだ、誰かに操られるのもいや」
利菜の告白は衝撃だった。自分たちまで操られるという考えは、頭になかった。
「そんなことがあったの?」
佳代子が訊いた。利菜はうなずいた。
「なんで言わないのよ?」
佳代子のなじるような口調に、利菜はきっと目を上げた。
「あんたなら言える? 達郎ちゃんがいったみたいにさ、友だちが……」とみんなのことを指しまわす。「みんながいたからわるいものにとっつかまんなかったとして、その友だちが自分のことうらぎったみたいなふうなこと、佳代子な言える?」
利菜は目をとじた。まぶたの端から涙がこぼれた。彼女は鼻水をこぼして泣いた。
「あんなめにあうの、もういやだ……」
胸元からしぼりだすような告白があり、佳代子と紗英が駆けよった。みんなも。彼らは抱きあって、一塊になった。
達郎はみんなをだきかかえるように、腕をひろげて言う。
「みんな、じいちゃんが帰ってくるのを待とう。明日はあの山にいくんだ。あの山になにかがあるんなら、決着をつけるしかない」
「なめ太郎が来いっていったのに?」紗英はしゃくりあげて泣いている。「ワナかもしんないじゃん」
「いまだって十分危険だよ。それに、じいちゃんならなんとかしてくれる」
だけど、寛太郎はその夜も帰ってこなかった。彼らは寛太郎の身にも、なにかが起こったのではないかと心配をした。
両神山には、いく必要がある。肝腎なのは、どう決意をかためるかだ。はやく決めないと、またなめ太郎がやってくる。あんなやつにもういっぺん出くわすなんて、誰でもいやだった。
彼らは山にいくにあたって、十字架やおふだなど、集められるものはみんな用意した。懐中電灯も。ろうそくも。食料も。必要とあらば、お堂の位牌だってむりやり引っぺがして持ってきた。ロープもラジオもコンパスもバットも、みんな寛太のリュックにつめこんだ。足りないのは寛太郎だけだ。その意味では、決意はかたまっていなかったが、用意だけは、万端ととのっていたといえる。
彼らはそれぞれの親に電話をすることにした。みんなでいれば、大丈夫なのではないかという甘い期待と、誰でもいいから反対意見を言ってくれ、という気持ちとでせめぎあっていた。
利菜の父親が、車を出そうと言いだした。佳代子の母はおらず(当然だが)、紗英の母親も、達郎たちの両親も、両神山行きを反対しなかった。瀬田英二がいなくなって、まだ見つかっていないというのにだ。
子どもたちはこれまでは話のなかだけの存在だったおまもりさまが、現実として迫ってくるのを感じた。両神山にいくというのがどういうことなのか、もういちど真剣に考えようとしたのだが、頭の中がぐるぐるまわって、考えはひとつもまとまらない。
利菜が電話をかけたとき、父の俊郎は待ちかまえていたように電話をとった。呼び出し音はいちどもならなかった。父さんは、もしもし、上原です、とも、どちらさまでしょうか、とも言わなかった。決まったか、といきなり訊いた。うん、と利菜はこたえた。その時点で、胸がふるえて、うまく答えることはできなかったのだが。
利菜はもちろんあんなところには行きたくない。けれど、坪井のおじさんちで見たモンスターみたいなのが母さんを捕まえたとしたら? あいつが母さんのことも食べちゃったとしたら? そんなこと思うだけでも嫌だ、考えてもだめだと思った。わるいものはそんな考えも喜んで現実にすると思った。そんなことになるまえに母さんをつれもどすべきだと思った。利菜は涙のにじんだ目をぬぐった。それから彼女はうつむけた顔を上げたのだった。父さんは当てにできないからあたしがやるんだと彼女は思った。
父さんは、明日の朝迎えにいくから、みんなで用意してまってなさい、と言った。母親のことをまったく話題にしないのと同様、利菜がいまどこにいるのか、どこにいくつもりなのかは、訊きもしなかった。訊かなくても、知っているようだった。
利菜は受話器をおき、父さんが車を出してくれるって、とみんなに言った。平静をよそおおうと必死だった。みんなのほうは、ひと目とも見られなかった。自分の父さんがモンスターみたいになっている、自分が今朝言ったみたいに、操られたみたいになっている。そんなことが言えるだろうか? 不信を招くようなことを?
彼女は言えないと思った。そいつは無理だ。
□ 四
後年利菜が思うのは、あの朝みんなが一睡もできずに、はやくから起きだし迎えを待っている間、ここにやってくるのは利菜の親などではなく、わるいものそのものだと気づいてたんだ、ということだ。
達郎たちは雨戸もガラス戸も開けはなち、廊下をぶらぶらしながら、畑のむこうにある道路の様子を気にしていた。寛太はパンパンになったリュックを抱えこんでいた。
午前六時で、台所では、ばあちゃんがみんなのために弁当をつくっていた。女の子たちは、ばあちゃんのことを手伝っていた。なんだか落ちつかない気分だった。
県道に父親のイプサムがとまったとき、みんなはいっせいにそのほうを見た。と同時に、車のホーンがいちどだけ鳴った。一同はびくりと身をちぢませた。
「きたな……」
と達郎は言った。確認の口調というよりは、呆然とした声音だった。このときにいたるまで、彼らの誰もが、引きかえす方法をさがしていた。だけど、その手段がなかったのだ。たとえ、いま行かなくても、べつの場所でべつの機会に、ひとりずつ連れさられるかもしれない。そのときの結果は、考えたくもない。
達郎は口にだしては言わなかったし、言葉にして考えていたわけでもないが、自分たちの信頼がくずれないうちに行くべきだ、と感じていた。にたような感じは、みんなが持っていた。わるいものは心に働きかけてくる。だったら、みんなをばらばらにするなんて、簡単じゃないのか?
達郎は立ち上がって、そこからみんなの顔をながめおろした。ひどく遠くにいるみたいに見えた。ひとつ年下の子たち――なんてこった、みんな幽霊みたいじゃないか。
「用意はできたか?」
と達郎は一息にいった。みんなとの距離が、もとに戻った。利菜は車をながめているうちに、イプサムの車体にひきこまれるような、引きずりこまれるような感覚をうけた。紗英も、佳代子も、新治も、寛太もおなじだった。
寛太はこう考えた、これはおれが考えてるみたいな、モンスターをやっつけるヒーローものの冒険なんかじゃないんだと(彼はこれまでの経験から、両神山行きのことをそんなふうに思っていた。だけど、このとき、自分の思いどおりになんていかないことを知った――あの白い車体は凶悪だ。とっても)。
寛太は行くのをやめようと、なんど達郎に申しでようと思ったかしれない。だけど、行かなかった場合におこることを思うと(それ以上に、自分たちの信頼にはいる亀裂をおもうと)、とても口にはだせなかった。これまでの人生で、まったく見せることのなかった分別でもって、みんなのあとに黙ってついていった。
達郎が寛太のリュックをせおった。ばあちゃんの弁当は、利菜がリュックにいれて持った。自分からすすんでその役を買ったのだが、それはばあちゃんの用意した弁当が、自分たちの用意したおまもりのようにみえたから、という、それだけの理由だった。
紗英は、家をでる間際に、ばあちゃんの丸々した腰に抱きついて(この子の背が急激に伸びるのは、この一年後のことだ)、みんなをどぎまぎさせた。なめ太郎には、誰にもいうなといわれていたからだ。
達郎は言った。
「い、いこう」
利菜は父さんが車のホーンを鳴らしたまま、いちども降りてこないことに気がついた。いつもはちゃんと挨拶するのに。膝のわるいばあちゃんは、玄関の踏み台に脚をおろして、申しわけなさそうに表をのぞいている。
利菜は畑の私道から、家をみようとふりむいた。みんなもそうした。あの家がわるいものからみんなをまもってくれるお堂みたいなもんで、自分たちは外にでちゃったんだ、という考えがうかんだ。頭をふって、その考えを追いはらった。
「行くよ」
みんなの先頭きって父親のところへちかづいた。わるいものに会うのに、弱気で行くのは最悪だ。だけど、ガラスごしに父親の様子をみたとき、利菜の強気の仮面はガラガラと音をたてて崩れた。
父親はすこしもこっちを見ずに、じっと前方を凝視してる。
「母さん……」
となりにきた佳代子が、息をのんだ。助手席には登美子がすわっていた。意外だった。父さんとおばさんは、ちっとも仲がよくないのに。二人は子どもたちの前では仲のわるい様子はみせなかったけど、利菜と佳代子は子どもの直感で、二人の不仲に気づいていた。
寛太は登美子が苦手だった。「おばさん来るなんていってなかったじゃんかよ」
「知らないよ。あたしだって聞いてなかったんだから」
佳代子が口をとがらせる。
「の、のろうよ」
新治が言った。彼は紗英と手をつないでいる(この二人が親しげにするのは珍しかった。どちらも恥ずかしがり屋だったのだ)。まるで決心がにぶらないうちに、いやなことはさっさとすまそうと言いたいみたいだ。
達郎が後部座席のドアを引きあけた。そこになにも乗っていなかったので、ほっとする。でも、車のなかにはいやな空気がただよっていた。臭い、とかではなくて、重苦しい雰囲気が。
達郎にはそれが濃厚に感じられたので、ふりむいて年下の子どもたちの様子を見守った。五人はなかの空気のことには気づいていないらしい。怪訝そうに達郎を見ている。
意をけっして、車内にのりこんだ。
「今日は、よろしくおねがいします」
達郎は頭をさげ、運転席の真後ろにすわった。となりは新治、そのとなりには補助席をおろして寛太。女の子たちは後ろにさわった。みんなは窮屈そうに身をちぢめている。必要以上にそうしていた。達郎の感じたいやな雰囲気を、感じとったのかもしれない。
二人は、そのあいだも無言のままだった。やがて、俊郎がゆっくりとギヤをドライブにいれ、イプサムを発進させた。
こうして、恐怖のバスツアーは、始まったのである。
□ 五
最初のうち、利菜と佳代子は、父親と母親の気をひく努力をおこたらなかった。信子はどうしたの? と佳代子は訊いた。登美子はこたえなかった。父さん仕事は? と利菜も訊いた。俊郎はこたえなかった。みんなは顔を見あわせた。
利菜と佳代子は意をけっし、思いつく話題をならべたてたが、二人はのってこなかった。
「だめだ、あの二人もどってこないよ」
利菜が言った。佳代子は、
「二人とも、まばたきもしてないように見えるよ」
とうらめしげにつぶやいた。紗英はその二人にはさまれて小さくなっている。
もういいよ。達郎が言った。こうなることを予想していたような口ぶりだった。
神保町をぬける直前、道路脇の畑に十人ほどの子どもが集まっていた。神保小の子らしく、みおぼえのある制服を着ている。そのうちの一人が、
「あれ秀幸君だよ」
利菜が言った。達郎たちは、押しあうようにして窓際にいった。車は時速六十キロで走っていた。その子どもたちはすでに後方になりつつあったし、固まって立っているから、斉藤秀幸のことは、よく見えなかった。ほんとうのところは、利菜たちのうち、誰も見たくなかったのかもしれない。だけど、それとおぼしき人影はあった。帽子を深くかぶり、うつむきかげんに立っている、ちいさな子。
「ほんとに秀幸だったか?」
達郎が訊いた。利菜は言葉につまった。彼女はよくわかんないといおうとしたのだが、そういうかわりにうなずいた。斉藤秀幸は、最初に殺された子どもだ。死んだ子どものうちでは、もっとも有名になっていたかもしれない。死んだのは一学期の途中で、学校中、その話でもちきりだったからだ。
二学期になったら、と利菜は考える。わたしたちも噂話の名前にくわわるんだ。
彼女はふるえた。
紗英が言った。
「秀幸君だけじゃないよ。美由紀って子もいるように見えた(小野田美由紀。さくら幼稚園年長組の女の子だ)。わたし、家が近所だから、知ってるんだよね」
寛太は目をみひらいて、なにか言いたそうにしている。英二のことを考えているのは(あのなかに、英二がいなかったかと、訊きたがっているのは)、だれの目にも明白だった。
新治が、「あいつら仇をとってほしいのかもしれない」
「そんなわけない。あれは、秀幸たちじゃない。幽霊のわけないだろ? 死んだやつらが、あんなところにかたまってたりしない」
「あれが生きてる子だったとして、あんなとこでなにしてたのよ」
利菜が言った。町外れだし、あのあたりは子どもがあまりいない地域だ。夏休みなのに、制服を着ているのもおかしかった。
達郎はふりむき、すこし固い目で彼女をにらんだ。
「でもさ……」佳代子が言った。「あれって大勢だったよ。十人以上いたもん。あれが幽霊だったとしたら、もうそんなに殺されたの?」
誰もこたえなかった。達郎はむっつりと前をむいて座った。窓の外に目をやり、もう会話には参加しなかった。彼はリュックを膝のうえに置いていたから、腕の震えを隠すことができた。
あたごにつづく峠にさしかかったとき、六人は、道の両端に、動物たちがあつまっていることに気がついた。みんなは仰天して、車の中を、左から右に行ったり来たりした。鹿や、狸や、狐にねずみ。山にこんなに動物がいたんだと、驚くぐらいにあつまっている。
彼らは道ばたに整列し、とおりすぎるイプサムを見おくっている。
みんなは唾をのみ、たがいの顔を見やった。それぞれの席にすわりこんだ。いうべきことはなにもなかった。言葉を封じるぐらい、驚きは深かった。
登美子はなにもいわない。
新治はポケットに手をつっこんで、十字架をにぎりしめた。
「父さん、あたごによって」
と利菜は声をかけた。俊郎はこたえなかった。
「よってってば!」
利菜はヒステリーをおこして絶叫を上げた。みんなが首をすくめるほどの大声だったが、俊郎は彫像みたいに、ぴくりともしない。
あたごを通りすぎ、T字路をまわった。
おまもりさまは、もうすぐだ。
□ 六
前席にすわる二人の大人のおちつきをよそに、子どもたちは終始うろたえた様子だった。固唾をのみ、周囲の変化に目をくばった。これだけおっかながっているのだから、いつ幻覚がはじまっても、おかしくなかった。
利菜は自分たちが、ビニールボールを捨てた池に目をこらした。ひょっとしたら、あのボールは、まだ水面に浮かんでいるんじゃないか? 家でみたボールは、ただのかんちがいで(どんなかんちがいなのかは知らないが)、まだこの池にあるんじゃないかと思ったのだ。
イプサムは大きなカーブをまわって、いつもの駐車場に到着した。先客はいなかった。獲物はぼくらだけだ、と思い、新治はふるえた。しょんべんをちびりそうだ。
駐車場はあいかわらずのぺんぺん草をはやしている。あのときから、五日しかたっていないとは、信じられない。
俊郎は入り口に車をとめ、エンジンをきった。
みんなは、まじまじとバックミラーをのぞく。俊郎も登美子も、視線をかえさない。
「お母さん、あたしたちもう行くよ」
佳代子が言った。返事はなかった。
達郎にうながされて、寛太がドアをひきあける。草原の空気はひえていた。早朝のせいか、光も重くしずんでいるようだ。利菜は曇っているのかと思った。こんなときに雨がふるなんて、最悪だ。あれだけ入念に用意したのに、傘だけは忘れたからだ。
だけど、空をみあげると雲はまばらで、太陽をかくすほどもない。
「もう七時半だよ」
紗英がつぶやく。達郎も時計をみた。六人は、空をみあげる。
「太陽がのぼってないんじゃないのか……」
達郎が呆然と言った。みんなはうろたえてうろつきまわったが、肌をさす寒気と光量をかんがえるに、真夏の七時をまわっているとは考えられなかった。まだ五時だといわれても、みんな信じこんだろう。
「達郎ちゃん……」
佳代子が後ろでいった。彼女だけはこの騒ぎにも参加していなかった。
「ねえ、みんな見なよ」
五人は太陽の行方さがしに夢中だったが、佳代子のわななく声にそちらをむいた。
草原の景色は、一変していた。ひまわりが、草地のいたるところを、埋めつくしていたのだ。
達郎は、ごくりと唾をのみこんだ。いつのまに生えたのよ。佳代子が口のなかでつぶやく。生えたはずがない。あれから五日しかたっていない。ひまわりはめいいっぱい成長して、みんなの背丈よりずっとおおきい。その茎は標識のポールみたいにぶっとくなっている。黄色の花弁も、めいいっぱい成長して、いまにも種をこぼさんばかりだ。
そいつたちは風に吹かれて、いっせいに首をかたむけた。
紗英が身をかがめ、こそこそと車にもどりはじめた。目はぎょとぎょと地面をみやり、あきらかに挙動不審だ。ドアに手をかけた。ノブをめいっぱい引いたが、あかなかった。「そんな……」
側にいた寛太がてつだったが、ドアはひらかなかった。利菜と佳代子もかけより、
「開けて、開けてよ!」ドアを叩いた。
がちゃり……
鍵の閉まる音がした。みんなは呆然と、ドアを見つめた。いま鍵が閉まったんなら、なんでドアは開かなかったんだろう。
ドクドクと、脳の奥そこが脈うつのを感じる。鼓動がはやくなる。一同は答えをもとめるように、達郎をみる。尾上兄弟は、うろたえてたがいの顔をみやった。子どもたちが騒ぐのに、おじさんもおばさんも、こっちを見もしない。じっと、フロントガラスを見つめている。
「い、いこう」
達郎がたまりかねてみんなにいった。新治がそんな兄貴を信じがたげに見あげた。
佳代子が達郎につめよって、ひまわりを指さした。
「行くって、どこに? あれが見えない? あれが幻覚? 消えてくれんの? じゃあ、いますぐ消してよ! あたしの頭からおっぱらってよ!」
「みんなもどってどうするんだよ、どこに行くんだよ。もうもどるとこなんてないんだぞ!」と達郎は言った。「あいつはどこにでも来るんだ。四六時中、気をはるなんて、そんなことおまえらにできるか? 親までおかしくなってるのに」
達郎はイプサムのほうを指でつきさした。寛太はバットをにぎって(ここにバッターボックスがあるみたいに構えをとる。見ようによってはこっけいだ)達郎を凝視する。ほかの子たちも。
「おれにはそんなことできない。おれには無理だ」
達郎はそういいのこすと、リュックを背負いなおし、草原に横たわる小道にむかいはじめた。みんなはその後をおいかけた。達郎をほうって帰れるはずがない。
利菜はいちどだけ、イプサムを見かえしたが、父親は凍りついたように姿勢をかため、娘のほうは見むきもしなかった。
父さんは、もうおまもりさまにつかまっちゃったんだ。そうおもうと、震えがきた。
でも行かないと、みんなが行くっていってる。
それにあそこ――
彼女はひまわりの向こうのおまもりさまを見つめる。あそこにはひょっとすると、母さんがいるかもしれない。
利菜はもっていたお札をにぎりしめると、みんなの後をおいかけた。
□ 七
子どもたちはひまわりの青くさい臭いをかぎながら、息をきらして頂上を目ざした。彼女たちは、茎をかきわけながら前にすすんだ。
アスレチックは、ひまわりに囲まれ、土台がみえない。ひまわりはあっというまに子どもたちの背丈をおいこして、すぐに小道もわからなくなる。
ひまわりの種が、バラバラと落ちかかり、紗英が悲鳴をあげた。
「こんなもんいつ生えたんだよ」
寛太が言った。その瞬間、頭上のひまわりが、首をまわすみたいにまわって彼を見た。人間の顔みたいな花弁から、あられみたいにおなじみの種をバラまいたからたまらない。
寛太は悲鳴を上げてしりもちをついた。達郎と佳代子がたすけおこす。
「おさそいが、おさそいは始まってる」
新治がいうと、
「当たり前よ、おさそいならもうのっかっちゃってるんだから」
と佳代子らしくない、だみ声みたいな悲鳴で怒鳴る。
「お、おちつけよ」と、達郎。「おれたちは自分の意思でここにきた。まだつかまったわけじゃない」
佳代子は、まだ怖い目のままだったが、うなずいた。
寛太が、ぺっと種を吐いた。「あいつ、おれたちをこんな目にあわせて、どうするつもりなんだろ?」
草原は、進むほどに草が濃くなった。
「みんな、ついてきてるか?」
達郎は、先頭にたって草をかきわけ、そのせいで傷だらけになっている。ふりむくと、ひまわりが深すぎて、全員の確認がとれなくなっていた。
「はぐされないように、注意しろよな」
達郎は仲間にきこえるよう、大声でいった。
みんなは達郎にいわれるまで、とっぱぐれに会う危険に気づかなかった。それからはたがいに注意して、丘をのぼりはじめた。
太陽はまだもどっていない。気温は低いが、子どもたちは汗だくになっている。利菜は変な想像をしないように、恐怖をふりはらおうと必死だった。ひまわりのジャングルを、息を荒くしながら、しゃにむにつき進んだ。
佳代子の体が急にしずんだ。下草に靴をとられたのだ。利菜が男の子たちに声をかけ、進行がとまった。佳代子は舌打ちをして、靴の紐をなおしはじめる。利菜と紗英は、彼女を守るかのように左右にたつ。
利菜にはひまわりのざわめきがまるで彼らのおしゃべりのように聞こえた。背の高いひまわりの花弁が曇り空の下で彼女をみおろしている。意思をもっているかのようだ。それもとびきりの悪意を(ありえない話だが、ひまわりたちは太陽の方角を無視して、みんな彼女のほうを向いている)。
利菜は大口をあけて、呼吸をはやくしながら、紗英にひまわりがどうみえるか訊こうとした。
紗英はじっと西のほうを向いたまま、体を震わせている。耳をそばだてているようだった。利菜が、どうしたの、と問いかけると、その発言をくいとめるように手をあげた。
「聞こえない?」
紗英は言った。きりつめたような口調だ。利菜はとっさに耳をすました。佳代子が顔をあげた。
「ほんとうだ……」
草をへし折る、がさがさという音が聞こえた。三人の女の子たちは恐怖に目をこわばらせてその方角をみた。
アスレチックだった。二階建てのアスレチックが、ブルドーザーみたいに動いてこっちにやってくる。
利菜は悲鳴をあげ、佳代子は尻もちをついた。アスレチックはひまわりを蹴ちらし、大地を削りとりながら突進してくる。そいつは両神山でも最もおおきい、なかは部屋のようになっている。子どもの頃はあのなかでままごとをしたものだった。こぶりだが屋上もついている。利菜はとっさに口を覆いかくしたが、すでに見つかった後だった。滑り台はまるであいつのベロだった。そして、下の空洞を口のように開いて、地面に噛みつく。網とスチールのはしごを引きずって、おし寄せてくる。
「大変だ……」達郎は、新治と寛太の前におどりでると、女の子たちの間にとびこみ、佳代子の腕をひいてたたせた。「おまえら、逃げろっ!」
利菜は後ろをふりむきながら、紗英の手をひいて走った。アスレチックはまるでラッセル機関車だ。土を跳ねあげ、ひまわりを砕く。
達郎は、上にあがるのをあきらめ、草原を横ぎりはじめた。ひまわりが身をよせあって、行く手をふさいだ。寛太と新治が、その妨害に、怒りをこめてパンチをあびせる。
目の前に巨大な岩があらわれた。ふだんは滑り台がわりにつかっていた大きな岩だった。寛太と新治は急いでその上にのぼり、おくれてくる達郎たちに目をやった。狂える生き物とかしたアスレチックは、いまにも四人を飲みこまんとしている。二人は、達郎たちに手をふって、こっちに来い、岩の影にまわれ、と声をかける。
利菜はもう後ろもむけない。アスレチックの跳ねちらかす草原の土が、ふくらはぎに当たる。どす黒い気配が、背中をたたいている。もう追いつかれると思った。彼女は寛太たちの声を耳にしながら、夢中で岩の陰にまわった。新治が寛太の腕をひっぱり、下へとひきずり落とした。二人の少年が利菜たちの頭におちてきた。達郎が突然ふりむいて、三人の女の子を抱えこむようにして身をなげだす。みんなは岩の真裏でひと塊になり、たがいの手足をかきあつめる。
そのとき、利菜は爆弾が炸裂するような音をきいた。高層ビルの倒壊現場のような音だった。彼女のうえには、達郎が乗っていて、その下には佳代子と紗英がいた。アスレチックが回りこんでくるこの鬼ごっこが一生つづくんだと彼女は思ったが、地震みたいな衝撃が体を震わしなにも考えられなくなる。アスレチックが岩にくらいついたのだ。横綱級の図体ではこまわりがきかなかったものらしい。一トンはあろうかという巨大な岩が、アスレチックのぶちかましで、その場から、ずれた。利菜たちの体をおしやり、みんなは悲鳴を上げ、大きな肉団子のかたまりが崩れた。上にいた寛太と新治がころげおち、皮肉にもおまもりさまのひまわりが受けとめてくれた。
木片がカラカラと落ちてくる。利菜は頭をかかえて固まり、振動が消えるのをまった。大音響がおさまると、あられのようにふりそそいだ破片も、ときおりからからと落ちてくるばかりとなった。おそるおそる目を開ける。あたりにはアスレチックがまきちらした埃がまいただよっている。達郎がどくと急に体が軽くなった。佳代子と紗英がもぞもぞと動いている。生きているようだった。利菜は生きていることが信じられなかった。ついさっきまでは、あの巨大な口に、飲まれかけていたのだ。
みんなはたがいを助けあいながら起きあがり、ほうけた顔をみせあった。
「みんな無事なのか……」
と達郎がばかな質問をした。彼はほっぺに大きな草汁のあとをつけ、ちっとも大丈夫そうじゃない。
寛太が岩の上にのぼり、ひゃあ、とたまげた声をあげた。利菜たちも岩の脇をまわりこんだ。
滑り岩は、アスレチックに半分がた飲みこまれていた。国村はよほど頑丈につくったようで、岩肌が砕かれている。利菜は金太郎がおにぎりにかぶりついて、途中でかたまるさまを想像した。そのぐらいやんちゃなありさまだった。寛太が岩をおりた。子どもたちが無言で手をにぎりあっていると、口とおもわれる部分から、血が噴きだしてきた。まるで生きているみたいに噴血をはじめたのだ。
利菜は、悲鳴をあげてとびすさる。すると、周りのひまわりが、のぞきこむように身をおって、巨大な顔から血をあびせかけてきた。身を折って、なんだかヘドをはいているみたいだ。ひまわりは生き物のようにうごめき、彼らをかこんだ。まっこうから血ヘドをあび、新治が転んだ。
「に、逃げろ」
達郎が新治をたすけおこし、上へ上へとみんなをおいやる。いつのまにか、ひまわりのトンネルができている。利菜はそこを駆けていったのだが、上からは血の雨がふり、ぐしょぬれになるばかり、悲鳴をあげどおしだ。目をあけるのも難しいなかでどうにかふりむく。彼女の真うしろでは、ひまわりがものすごい勢いでトンネルの出口をふさいでいる。まるでひまわりのシャッターだ。
たいへんだ、遅れたら、こんどはあの口に飲みこまれる。
利菜は、慌ててみんなの後を追いかけた。
□ 八
ひまわりの畑が急にとだえ、彼らはたたらを踏んでとどまった。
達郎は頬をながれる粘っこい血をぬぐった。靴も服もびしょ濡れだ。手をふると、血のしぶきがびしゃりと飛んだ。彼が顔をあげると、おまもりさまはすぐそこにあった。五日前に見た蔓壁が、滝のようにそそりたっている。ここだけが変わっていなかった。
国村のたすきがかかっていたススキ林がある。あのときは、まむしを追っぱらおうと棒ではたいて通った。地面を血が流れおちてきた。
でもいまはおれの体を流れおちてる、と達郎は考える。ぜんぜん笑いたい気分じゃないのに、にやにやと笑みをもらす。なんで笑っているのか、笑いたいのか、自分でもよくわからなかった。
「もういやだよ……」
佳代子の声がした。彼女はわななきながら、自分の体をみおろしている。服をはらうようなしぐさをみせたが、むだだった。きっとパンツまでぐしょ濡れになっているだろう。
「なにがおかしいのよ!」
佳代子がどなる。達郎はまだ自分が笑っていることに気がついた。紗英も利菜も新治も、寛太でさえも、非難するような目をむけてくる。
「まだいこうっての? どうしたいのよ」
紗英は子どものようにシャツをひっぱっている。目には涙をためていた。みんなは沈黙だった。ひどい目にあって、重くしずみこんでいた。
達郎はくじけそうになるみんなを引っぱってここまできたが、もう限界だった。彼は友だちが驚くような行動をみせた。突ったったまま、茫然と涙をながしはじめたのだ。
五人は唖然となった。達郎だって、自分の涙におどろいた。体を折り、指で涙をぬぐおうとしたが、その指も血で汚れていることに気がつきひっこめた。ここには蛇口も水もないことに気づき、そのことに泣きながら吹きだした。
「あれ、へんだな?」
強がったが、もう本物の限界だった。彼はその場につっぷすると、おいおいと、大きな体を揺すって泣きはじめたのだ。
子どもたちは、達郎の意外な行動を見てうろたえた。
寛太はおまもりさまをみた。誰かが蔓壁のむこうから自分たちをのぞき、このことを喜んでいるような気がした。だけど、これまでがんばってきた達郎が泣きじゃくるのをみて、彼はなにもいえなかった。いうべき言葉がみつからないのは彼にはよくあることで、つい口を閉ざしたのだった。
達郎をなぐさめたのは、寛太でも女の子たちでもなかった。これまで達郎とはずっとうまくいってなかった弟の新治で、おずおずと歩みよると、兄貴の肩に、手をかけたのだった。
新治はほかのみんなとちがって、泣いている達郎をずいぶんみてきたし(といっても、うんとちいさな頃の話だったが)、なぐさめたこともずいぶんあった。
「い、いこうよ」
新治は言った。達郎は腕に目をおしつけたまま、首を横にふる。
「もうやめるの?」
新治がいうと、達郎は首をはげしく縦にふった。
「じゃあ、さきにいっちゃうよ」
新治は言った。自分でも意外な言葉だったが、口にだしたとたん、ほんとに行きたくなったからおどろきだ。新治は泣いている兄貴を見て、ほんとに林のむこうを覗いてみたくなった。こんな目にあってまでいかなければならない理由があるとするなら、そのわけを知りたいと彼は考えたのだ。理由があるのなら、たしかめてみたい。
達郎がおどろいて顔をあげた。
「いくのか?」と彼は弟に訊いた。「おまえ、いくつもりかよ」
新治はうなずいた。達郎は信じられないといいたげに首をふる。
佳代子はもじもじといいにくそうにしていたが、
「わたしもいってみようかなあ」
まるで、むこうにいいことがあるみたいな口調でいった。達郎は、茫然と佳代子の顔をながめた。
佳代子が手をうしろにくんで、おしゃまなそぶりをした。
「ここまできたのにひきかえすなんて、もったいない気分」
利菜と紗英が、きゃあとふざけてその背中にくっついた。
達郎が咳きこみながらようやく笑った。
「お、おまえら、よく平気だな」
「女は血につよいのよ。知らないの」
利菜が意味もしらないくせに、聞きかじりをいった。これには達郎もみんなも笑いだした。
「よ、よし」と達郎はまぶたをぬぐいながら立ちあがった。「みんなが賛成なら、おれもいく。いいか」
達郎がリトルのチームばりに声をかけると、一同は、お、おう、といささか威勢の上がらない気合を上げた。
寛太はおっかなびっくり蔓壁のほうを見た。さっきまで感じた誰かの気配は、もうしなかった。でも、林のむこうのやつが、舌打ちをしたように感じて、彼は気分がよくなった。
六人はススキの前に立ちふさがった。達郎が鼻からおおきく息をすいこむと、いきおいこんで、
「い、行くぞ」
◆ 第四章 最初の訪問
□ 九
達郎はリュックの中からタオルをとりだした。丈夫なナイロンごしにも、血がかすかに染みこんでいる。そんなに血をあびたんだと知ってぞっとしたが、中身は無事のようだ。タオルや紙のへりについただけだ。
彼らはぬぐえるところだけはぬぐった。ぐしょぬれで、乾いているところなんてひとつもない。こんな目にあったのにひきかえすなんて、たしかにできそうもなかった。出なおして、一からやりなおすなんてこと、考えられない。
利菜はタオルをつかうあいだも、物しずかだった。みんなにたいして後ろめたかった。彼女だけは、母親をさがしに是が非でも中にはいりたかったからだ。正直なところ、達郎が気を入れかえてくれてほっとしていたのだ。
頬をぬぐうと、血が糸を引いた。ここの血は、粘り気がありすぎて、ぬぐいきれそうもない。だけど、タオルを真っ赤に染めた血よりも(泥んこバレーをやったよりもひどいありさまだ)、気になることがある――脳みそがやっぱり脈打っている。血流が三倍にもなった感じだ。閉じていた引きだしが、どんどん開けられていくようでもある。視界が大きく、広くなり、細かいところまでずいぶんみえた。なんだか病みつきになりそうな感じ。利菜はその感覚を歓迎した。坪井の家で感じたのとおなじだった、脳みそが全力疾走で駆けずり回る感じ。あの感覚に、ちかづきつつあった。
やっぱり、この場所はあそことおんなじなんだ。パワースポット。利菜は、みんなもおなじなのかと訊いてみたかった。
きっとおなじのはずだ。
□ 十
準備は終わった。達郎が先陣をきった。佳代子、紗英、利菜がつづいた。つぎに新治がいて、寛太はしんがりをつとめている。
ススキを途中までふみわけたとき、ざわざわと草が鳴りはじめた。まるでうなぎのように身をくねらせだしたのである。地面がゆれだしたかと思うと、ススキはぐんぐんと成長していき、あっという間にみんなの背丈をとおりこす。でっかい泥のついた茎しかみえなくなる。
利菜がススキの脇から身をのりだすと、蔓壁も杉の木も巨大化している。足下をみると小石が頭ほどの大きさになっている。友だちはあまりのことに悲鳴もだせない。おちついていたのは利菜だけだ。こんなことは、坪井の家でも経験していたからだ。
利菜は佳代子たちが、別々の方向にかけだそうとしているのをみつけた。紗英はススキのむこうに巨大なアリをみつけて悲鳴をあげている。新治は自分の靴が掘ったはずの穴に落ちかけている。
「みんな集まんなきゃだめよ」利菜は、手近にいた紗英と佳代子の手をつかまえる。「手をつないで!」
「でもアリが」紗英が言った。
「アリはあんなにでっかくない!」
佳代子と目があった。佳代子もあの家のことをおもいだした。坪井の家では、階段が斜面にかわり、手すりに油がぬられた。でも、あのときは、心をつないでもとに戻したのだ。
「あたしたち、おんなじことをすればいいのっ?」
佳代子が訊いた。利菜は、そうよ、と怒鳴りかえした。
地面の揺れはまだおさまらない。男の子たちがやってきて手をつなぎあった。利菜たちは自然円陣を組むかっこうになった。紗英はちかづいてくるアリの物音を聞きながらも、必死になって目をとじた。脳みそが破裂しそうだ。これまでが低速なら、いまのギヤは、オーバートップを突きやぶってる。達郎も、新治も、寛太も、そのことを感じて声をあげた。血流が脳に送りこまれると、もう呻きしか上げられない。
子どもたちの円陣を中心に、物すごい力がながれこんでくる。パリパリと髪が音を立て、皮膚が泡だつ。外から流れこんでくるのか、それとも自分たちが高まっているのか、わからなかった。
みんなの心がつながっていく。まぶたを開けていないのに、たがいのことが見えるのだ。
六人の感情がまぜこぜになり、達郎はわけがわからなくなる。それでも佳代子や新治が考えていることがわかった。達郎は弟のことを理解した。彼はいってやりたかった。おまえはそんなに気をつかうことはないんだと、誰も、誰もおまえのことを……
だけどそれはいわでものこと。新治はそんな彼の考えすら読みとっている。六人はたがいを理解した。利菜と佳代子が、なんで坪井の家から逃げられたのかもわかった。
「ああ、信じる、この力を信じる」
と彼はつぶやく。自分を信じる、自分たちを。複雑な感情のうねりのなかで、六人が感じていたことはこういうことだった。これはただの幻覚なんかじゃない、幻覚なんてこえている、みんながときおりつぶやき、考えていた言葉、世界はねじ曲げられている――あれがおこっているんだと。
自分たちは心をつなぎあわせて、世界のねじまげを食いとめるんだ。
パワーは高まりつづけ、足が宙に浮きはじめた。新治が感嘆の声がきこえた。ススキや大地、あらゆるものがドスンという音をたててもとに戻った。足がしっかり地につくと、一同は恐る恐る目をあけた。周囲の景色はまたもとに戻っている。彼らは手をつないだまま蔓壁の奥をみる。この森にはなにかある、と彼らは信じた。
「すげえ……」
寛太が言う。腕で口もとをぬぐった。いつのまにか鼻血があふれだしている。
利菜はみんなの凝視にあって、弁解をはじめた。「この前もおんなじことがあったのよ。例の家で。話したでしょ?」
「出力全開」
と佳代子はいって、くすくす笑った。紗英もこわごわしい笑顔を見せた。
利菜はゴクリと唾をのんだ。寛太の家をでたとき、結界をでたような放りだされたような感覚を味わった。でも、結界は自分たちそのものだったのだ。自分たちにこんなことができるんなら、わるいものもなんとかなるんじゃないかと思えた。精神をつないだあの瞬間、彼女たちのアンテナは、千倍、万倍ちかくに高まった。ここがいかに危険な場所なのかもよくわかったのだ。
世界はもとにもどったが、みんなは手をつないだままでいた。もうすこしこのままでいたかった。でも、他人の心をのぞくのは失礼なことだ。
「ふう、みんなもう手をはなそうぜ」
と達郎は言った。この高ぶりを歓迎しつつも、ちょっとそら恐ろしくあったのだ。
「え、もう?」
佳代子がまぬけな返事をする。この感じ、理解しあえている感じが消えるのはおしかった。みんなとつながる感覚はすばらしかった。
「手をはなしても大丈夫だよ」
新治が紗英にいった。
「そうだ、フォークダンスをおどりたいわけじゃない」達郎も寛太の心をよみとっていった。
「……どうやら、ほんとに手をはなしたほうがよさそうね」
佳代子がおとなびた苦笑で手をはなす。ほかの一同も。利菜は自分の手がどうにかなっているんじゃないかと思ってすりあわせる。無害な電流を死ぬほどながされたような感覚だ。
「すげえよ、こんなこと、誰も信じないぞ」寛太が言う。
「これまでだって誰も信じなかった」
達郎は、不機嫌にいうと、蔓壁とむきあった。自分が制御できないような感覚が、急に気にいらなくなったのだ。
「わたし、もとに戻ってほしいだけなのに……」
紗英が言った。
「おれだってそうだよ。でも、どうにもできないんだ。どんなに願っても、変わってくれなかったろ?」と達郎。「つまり願うだけじゃだめなんだ。おれたちなにかをしなきゃいけない」
「なんであたしたちなの?」
佳代子がうつむいて訊く。その声はしわがれていた。達郎はちょっと口をつぐんだ。ゆっくりと考えをめぐらせ、言葉をえらんでいる。
「きっと、おれたちが自分でえらんだからだよ」
彼らはたがいの顔色をたしかめるようにぬすみ見た。
「おれたちは、自分で決めてここにきたんだ。おれたち、秘密をつかもうとしてる。うんとやばいけどさ。それができるのは、たぶんおれたちだけなんだ」
みんなは、達郎の言葉に納得したものがほかにもいるか、確かめるみたいに互いを見あう。
彼らは蔓網を凝視した。こんどは国村の声もしなければ、なめ太郎の顔も見えなかった。
□ 十一
寛太が達郎のそばでバットをかまえる。女の子たちは十字架をにぎった。新治が達郎からリュックをうけとった。
達郎が屈みこむ。網にからまった泥や、腐った落ち葉に顔をしかめる。彼は顔をあげる。寛太と新治が蔓をはらってくれたおかげで、見やすくなった林の向こうをみた。
みんなはしばらく茫漠とした顔で、おまもりさまを眺めやった。杉の木が行儀よくならんでいる。日があまり当たらないのか、下生えはほとんど生えていなかった。これが話しに聞き、夢にも見たおまもりさまなのだ。
達郎は網を持ち上げ、上半身をくぐらせた。頭が網をくぐった瞬間、キン、という高い金属音がした。空気の層がまったく異質なものに変わった。それはあまりにもなまなましく感じられたから、達郎は一瞬うごきをとめた。
寛太がきいた。「大丈夫か?」
「大丈夫だ」
達郎は肘をついて、網のむこうに体をひきずっていった。最後に足がくぐった。新治からリュックをうけとり背負いなおした。
みんなにこっちに来るよういおうとしたが、ふと振りむいた達郎は、林の様子に目をむいた。鼓動がとまったようだ。外から見たのとちがう。杉は何倍もふとくなり、苔むしている。ジャングルみたいに草むしていた。まるで、邪悪な栄養で肥えふとったみたいだ。見たこともない草、見たこともない木がはえている。しかも、草むらの中からは、誰かの足がつきでていた。
「お、おい」
彼は急に心細くなった。さっきはおまもりさまに立ちむかえるような気になったが、それがただの慢心だったとしたら……おまもりさまは心をつないだ自分たちより、ずっとずっと強力かもしれない。
達郎は仲間がこっちに来るのをとめようとしたが、すでに寛太は体を半分くぐらせている。達郎は寛太をたすけて、起きあがらせた。
寛太は、おなじように目を見はった。「おい、向こうで見えたのとちがうぞ」
二人はのこった仲間をみた。みんな怪訝な顔をしてる。
「見えないのか?」達郎がきいた。
「なにが?」
佳代子がたずねた。
「こっちに来てみろよ」
そこで新治がきた。彼は自分が目にしたものをこう評価した。
「本物のおまもりさまだ」
女の子たちも、つぎつぎとおまもりさまにやってきた。佳代子がきて、利菜がつづいた。最後の紗英だけは、草原側から誰かに足をつかまれもたついたが、達郎と新治がひっぱって、ようやくこちらに来ることができた。
彼らは林の縁にとどまったまま、しばらくおまもりさまのことを点検した。林のなかは急速にうす暗くなってきた。寛太がリュックから懐中電灯をとりだした。ライトの部分にも血糊がついている。それをタオルでやっきに落とすと、明かりをつけた。
「あれは誰の足?」佳代子がきいた。
達郎は無視していった。
「ここは両神山じゃない。おれたちは本物のおまもりさまに来たんだ」
紗英もきいた。ヒステリーを起こしそうな危険な口調だった。「なんであそこに脚がつきでてんの?」
脚はここからすこし離れたところに生えている。生えている、というのはおかしいが、草に隠れてそんなふうに見えるのだ。
達郎が、確かめにいこう、というと、紗英がその腕にしがみついた。
「やめてよ、死体を確かめにいくなんて。悪趣味なことしないでよ。どうかしてるんじゃない……」
「だけど、あれが……」
と達郎は言いかけて口をつぐむ。六人ともがおなじことを考えていた。彼らはまだつながっていたから。あのとき、国村は(国村のまねをしたなめ太郎が、ということだが)、助けてくれ、と言った。国村はいなくなったままだ。でも、どこかにはいるはずなのだ。
あるいは、あれはもっとべつの死体なのかもしれなかった。大人の足に見えるけど、英二のものだという可能性だってある。
「死体じゃないかもしれない」
達郎はみんなを説得するようにいったが、成功しなかった。出力全開の脳みそは、あの脚から(あの足のさきから)生きている気配がしないことをつげている。
彼らは勇気をおこして、死体にむかって歩いていく。ぶよぶよしたコケを踏みながら。寛太がつよく踏みつけると、ぶすぶすと空気のぬける音がした。辺りをみたす苔むした臭いに、彼はあえいだ。
死体は草むらをなぎ倒して横たわっていた。きれいな死体、というものがあるならば、その死体には損傷もなく、血痕も見当たらない。眠っているようだった。呼吸をしていないことと、ありえないぐらい青ざめた皮膚の色が、男が死んでいることを告げている。
「外人だ……」と寛太が言った。
達郎が新治にきいた。「図書館で会ったやつか?」
新治は首を横にふった。見たこともない男だった。
「ねえ、それって本物なの?」利菜がきいた。「本物の死体?」
「うん」と達郎がこたえる。「そう見えるよ」
「じゃあ、なんでここにあるの? 外人でしょ?」
寛太がバットで死体の脚をつつこうとした。佳代子が上からおさえた。「よしなよ、動きだしたら、どうすんのよ」
「そしたら、こいつはゾンビだ」
「おれ、死体ってはじめてみた」
新治が言った。みんなも、はじめてだった。親戚の死体なら見たことはある。たいていは棺にはいった状態のままで。でもこいつは殺されたか、あるいは自殺したんだろう。
利菜はあたりを見まわした。森の様子は微妙に変化していた。起伏が多くなり、アニメでしかお目にかかれないような、へんてこな草木がふえていた。林というよりは、ジャングルという言葉がぴったりとあった。そんなところで、六人の子どもが死体と向きあっているなんて、うそざむい話だった。
「おい、ひとつだけじゃないぞ」
寛太が言った。死体はここだけでなく、あちらこちらにあった。それとともに、異臭が――死体の腐っていく臭いが、鼻腔にとどいてきた。
達郎は、こんなのうそだと思った。全部にせものだ。
でも、視界をうめる死体はなくならない。目にうつるだけでも、数十はある。
死体の群れはじつに多彩だ、国籍もバラバラだった。男もいれば女もいて、どう見ても江戸時代の農民としかみえないかっこうの男もいた。首吊り死体も、あちらこちらにぶらさがる。軍服をきた男、ひたいに穴を開けたドレスの女、白骨死体もある。真っ黒に焼け焦げたもの、ミイラみたいにやせ細った者もいた。
うわあ……と紗英はうめいて、口に指をつっこんだ。みんな、かたまれ、達郎が小声で言う。死体にきかれるのを、恐れるみたいな声色だ。
なによ、これ?
佳代子は泣き声だ。寛太が、
「ひでえ臭いだよ。マスクも持ってくりゃよかった」
「あれって、さむらいじゃないの?」
新治が言った。彼の左手には、腹に刀を突き刺したちょんまげの男が、顔のあちこちから血をながして倒れている。なます斬りにきられている。男はまぶたをかっとひらいていたが、その瞳はにごっている。
あちらこちらで、虫のうごめく音がした。
六人の心がひきかえそうかと、後ろをむきはじめた。
「なんで、こんなに死体があるんだよ。いろんな国のやつがいるんだよ」
達郎は茫然と言う。
「でも、さっきは見えてなかった」と佳代子。
「関係あるのかな」
利菜が言った。幻覚とはおもえない。後年の利菜なら、ここにいろんな死体があったって、少しもおかしくなんてない、と答えただろう。みんなの頭でおなじ言葉がぐるぐるまわっている。
世界はねじまげられている。
それは、まさしく時代も空間もこえて集まってきた死体だった。そのことに気がついたとき、利菜たちはぞうっと寒気がした。
怪鳥がさけぶ声が、森の奥からとどろいた。奇妙な動物が、あちらこちらで目につきだす。そのいくつかは、死体に食いついている。新治のそばで、死んだ女の口から、芋虫が這い出てきた。
「弱気になっちゃだめだ」
達郎は震える手をさしだす。彼らはふたたび手をとりあう。この死体が本物かどうかはわからない。でも、弱気になればなるほど、わるいものは集まってくる、悪いほうに変化していく。その力はみんなの心にも触手をのばしている。
子どもたちは想像いじょうに弱気になっていた。
達郎は心のなかで、このねじまげを食いとめるんだ、と呼びかけた。
利菜は母親をさがしたかったし、佳代子は外にいる母親自体がおそろしかった。紗英は、わるいものがみんなの心に手をのばしているのなら、両親の不仲はそいつのせいじゃないかと考えた。新治だっておんなじ気持ちだ。寛太はこんな臭いを嗅ぎつづけるのはうんざりだったが、英二のためにものこりたかった。背をむけるところを、友だちやじいちゃんには、みられたくない。
みんなはそれぞれの事情で、達郎の申し出を受けいれた。森の奥に目をむける。
パワースポットが、本当にあるとするなら、坪井の家とは比べものにならないぐらい強烈なやつだ。
六人は順々に手をはなしていく。達郎は手のなかの十字架やお札をみつめた。そっと指をひらく。
十字架はずるりと手のひらを滑りおち、苔むした地面に落ちていった。
「捨てよう……」
えっ? 紗英が顔をゆがめてききかえす。
「こんなもの役にたたない。だっておれたち、誰も宗教なんて信じてない」利菜に目をむける。
「それどころか、憎んでるやつだっている。自分でも信じてないものにたよったらだめだ。おれが信じてるのは……」メンバーの顔を順々にみまわす。「みんなだ。おれはみんなのことを信じてる」
六人は無言だった。やがて佳代子が、寛太が、新治が、持っていたおまもりや、位牌といった道具を捨てていった。達郎の足もとで、ちいさな山ができた。
利菜はごくりと唾をのむ。仲間の視線をさけるように目をおよがせた。みんながこんな目にあっているのは、自分のせいのような気がして、うしろめたい。そのせいか、みんなのこともこわかったのだ。
彼女は父親のようすがおかしいことをみんなにいわなかった。いえば、みんなは両神山行きをとりやめにしたかもしれない。もうすこし粘って、寛太郎の帰りを待ちうけたかもしれない。でも、彼女は母親をみつけたかった。ほうっておくのは危険な気がした。みんなに、ついてきてほしかった。
坪井の家に佳代子をつれていって、危険な目にあわせたというのに、ここでもおんなじことをしている。そのことがうしろめたかった。それに、彼女は友だちのことをうたがっている。みんながまたおまもりさまに操られて、なにかしてきやしないかと、不安をいだいている。仲間をうたがうなんて、自分の心がひん曲がってしまったようで、いやな気持ちだった。
身勝手なやつだ……
声をかけられたが、彼女はふりむかなかった。
利菜はおまもりを捨てたくなかったが、結局は友だちのことを信じてそうした。それをみて、紗英もあきらめたように、十字架から手をはなした。
□ 十二
寛太には名案があった。
リュックからスプレー缶をとりだす。近所のホームセンターで買ったやつを。それを木に向かって吹きつけた。その樹木は節くれだち、魔女の森にでてきそうな代物だったが、寛太がスプレーの中身を吹きかけた瞬間に、こぶの部分が大きく口をあけ、寛太のはなったペンキのたいはんを飲みこんでしまった。寛太は悲鳴をあげて、空中にバッテンを書いた。こんどはうまくいった。生きている木は、真っ赤な×印を描かれて、顔をしかめたように見えた。
彼らはたかまる悪臭に辟易しながらも、森のなかを進んでいった。ひどい死にざまの死体に、脂汗をにじませながら進んだ。この死体は幻覚で、消えるんじゃないかと考えたが、甘い期待にすぎなかったようだ。胸が悪くなるだけだ。
新治が立ちどまって吐きはじめると、紗英もたまらず吐いた。森のなかは寒かったが、みんなは汗だくになっていた。
「なんで消えないんだ、幻覚じゃないのかよ」
寛太の足下に比較的状態のいい死体があった。寛太はそれに触ろうとした。
「やめろ、寛太!」
と達郎が言った。
死体に手をふれた瞬間、自分の皮膚と死人の皮膚がとけあうような感触がした。視界が消え、五感がうばわれた。死者の記憶がながれこんできた。寛太は男の死を追体験している。彼の目は、死んだ男の目になった。体が硬直し、唾がたれる。のどを絞められる苦しさに、寛太はあえいだ。かすんだ視界のなかで、自分の喉を絞める男がみえた。
死んだんだ、こいつはこんなふうに死んだんだ!
そこは霧ぶかい湖畔のそばの草地で、ここじゃない、と寛太はおもった。この森じゃない、この男はべつの場所で殺されてる。でも、おまもりさまに行きついた……。
□ 十三
とつぜん膝をおり、苦しみはじめた寛太を目の前にして、達郎はどうすることもできなかった。寛太が左手を首にのばす、その指がヒフの直前をひらひらとただよった。達郎は、この少年がどういうわけだが、首をしめられて苦しんでいるんだと知った。寛太の右手は、死体の肩におかれたままだ。
達郎は、その手を力まかせに引きはがす。新治も寛太の体をひっぱった。二人の頭脳にも、記憶が流れこんできた。けれど、寛太の指が肩をはなれた瞬間に、その映像、痛み、感触はとだえた。だが、達郎たちは、死体をとおして、おまもりさまに手を触れてしまったらしい。
森中にちらばった死体から、色のついた気体がムクムクとわきだしてきた。それは雲のようにふわふわと宙にうかんだ。音こそしないが、人々が苦しみ死ぬさまが雲のなかに見える。寛太のもとに駆けよろうとした利菜も、目の前にうかぶ陰惨な殺害現場に怖じけづいた。
悪意にみちた記憶は、メンバーめがけてあつまってきた。六人の精神に、死者の記憶がとびこんでくる。子どもたちの脳は、パンクするほどの衝撃をうける。彼らは、その光景を見、その臭いを嗅ぎ、その死を体で感じた。彼らは被害者でもあり、加害者でもあった。
「やばいぞ、みんな手をつなげ!」
と達郎は言った。寛太と新治はとっさに達郎の手をとった。紗英と佳代子も。
遅れたのは利菜だった。彼女は特大の記憶にのまれて転んだからだ。頬が地面の苔をすり、擦り傷に顔をしかめたのは一瞬で、彼女はすぐさま記憶の奔流にのみこまれた。その記憶には無数の死がつめこまれている。行進する軍隊をみた。右手をかかげ、演説するヒトラー、銃弾に撃たれて倒れる少年。爆弾で人が死に、戦闘機の機銃で人肉が裂ける。利菜はその光景をうちけそうとするかのように、手をふった。あまりにもおぞましい光景だった。記憶はどんどん強くなる。一つにしぼられようとしているのだ。利菜は悲鳴をあげた。みんなも悲鳴をあげていたが、その声はひどく遠くに聞こえた。みんなが遠くに感じられる――
わあ、たいへんだ、あいつが、あたしたちを、ひっぺがしにかかってる!
気がつくと、彼女は血まみれの体のまま、硝煙のただよう戦場にうずくまっていた。あたりを銃弾がとびかっている。砲弾がちかくで炸裂して、体が震える。口のなかで奥歯がカチカチと鳴っていた。周囲に着弾があるたびに縮みあがった。びゅんびゅん、ばしんばしん、弾が風をきる音、弾が地をうつ音が、頭蓋をふるわし、鼓膜がおかしくなりそうだ。利菜は複雑な風に服をはためかせながら、佳代子、と言った。達っちゃん、助けて!
周囲をみまわしたとき、大柄な兵隊が銃剣をかまえて彼女をみおろしていることに気がついた。どこかの国の言葉でわめいている。さっきからずっと怒鳴っていたようだが、最初の砲弾で耳が馬鹿になり、まったく聞こえていなかったのだ。
「あたしに向かってわめいてる……」
彼女はガタガタ震えながらつぶやいた。両肘をかかえると、血まみれの体に砂埃がいっぱいついている。じゃりつく音が、骨に聞こえる。
兵隊がこっちに歩いてくる。ひどく興奮しているようだった。
うろたえてあたりをみまわすが、友だちもいなければ遮蔽物もない。利菜はこの期におよんで殺されるはずがないと思った。自分は子どもだから。でも、この夏は子どもがおおぜい殺されたことを思いだす。兵隊が銃剣を、槍みたいにつきだす。利菜は地面にふせた。
そうして、固い石ころだらけの地面に(その石ころは砲弾でくだけたらしく、鋭くささくれだっていた)頬をうちつけながら、彼女は兵士のすすだらけの若い顔、恐怖に血ばしった目を見、吐く唾を目にした。銃剣のさきが、血で濡れている。腕をみると、二の腕が大きく裂け、そこから真新しい傷口がのぞいていた。
「痛い……」
信じられないとつぶやく。傷口からは血があふれて布地をそめる。わるいものがすぐそばでささやいた。これは罰だ、みんなをだました罰だ。
戦車が荒れ地の丘をのりこえる。兵隊は仲間からもとりのこされ、敵にかこまれ、すっかり錯乱しているのだった。血まみれの子どもを是が非でも道づれにすると決めたようだった。利菜は逃げようとしたが、腰がぬけて這うことしかできなかった。デカ靴に背中をふまれて、蛙のようにうぎゃっと鳴いた。利菜は踏みつけにあったまま強引にふりむいた。男はとどめをさそうと銃剣をふり上げながら狂ったよう叫んでいた。それは外国語だったのに、利菜にはちゃんと翻訳されて聞こえた。死ねと
□ 十四
達郎はそのとき、若者同士の殴りあいの現場にいた。それは殴りあいというよりもリンチにちかく、殴られている少年はほとんど死にかかっていた。達郎はそんな場所にいたのに、戦場にいる利菜のことがなぜかみえた。背の高い兵隊とむかいあっている。止めを刺されかかっている――
「利菜!」
と仰天した口調でいった。彼が記憶にとりこまれず、自分をたもつことができたのは、仲間と手をつないでいたからだった。達郎はその手の感触を心づよく思いながら、
「みんな、心をあわせろ!」
達郎の声で、一同はようやく落ちつきをとりもどす。紗英は、子どもが母親にナイフをなんどもふりおろす現場にいたが、これは幻覚だと、いまいる場所なんかじゃないと信じた。友だちの存在がそうさせてくれた。となりにいるはずの利菜に手をのばし、その手をつかんだ。利菜は後頭部を串刺しにされる寸前だったが、危ういところでその空間からひっぱりだされた。子どもたちは間一髪で死の記憶からぬけだした。
子どもたちから引きはなされた記憶は、渦をまいて頭上をめぐりだした。寛太はそのなかに英二の姿をみる。わるいものに、引きずりこまれそうになる。
達郎は仲間をかき集めると、ふたたび手をつないで円陣をくませた。
彼らはふたたび環になって、おまもりさまを呼びもどそうとした。達郎は友だちと一緒にいれば、なんとかなると思った。でも、甘かった。おまもりさまは、とても、手に負えるしろものじゃない。
気がつくと、六人はもといた林にもどっていた。死体はおとなしく死んでいた。死の物語は聞こえてこなかった。彼女たちはゆっくりと唾をのんだ。秘密がわかった気がした。彼女は死体に触れることで、おまもりさまに触れることができたから。あいつのことを理解したのだ。子どもたちは自分たちにかかわっているなにかのことを、たんに、わるいもの、と呼んできた。それは人間が歴史や営みのなかでためこんだ、ありとあらゆる悪意のかたまりだ。それが自分たちにも影響をあたえている……。人間があんな悪いものだなんて、ショックだった。
利菜は胸元をみおろした。危うく心臓をひと突きされるところだった。でも、友だちが助けてくれた。みんな自分を見捨てなかったのだ。そう思うとじわりと涙がうかんだ。わるいものはいろいろいってくるけれど、でもそれは真実じゃない気がする
けれど、安堵感がない。心の中でわるいものが――不信がそだっていく感じがする。自分も他人も信じられない気がした。世界中で悪いことばかり起こっている。今もって。利菜はそれが怖くてふるえた。吐き気をこらえ、嗚咽をもらす。右腕をみると、傷は生々しく残っていた。
「あいつ、あたしの服を切っちゃった」
利菜は唇をかみしめて泣き声をこらえている。佳代子がハンカチをとりだし、利菜の腕にきつく巻きつけた。彼女もきゅっと口を閉じている。寛太をにらんだが、なにも言わなかった。
「あ、あいつだ……」寛太は喘ぎながらいった。鼻水をふこうともせず、死んだ男を凝視している。「わるいものに殺されたんだ。おれ、こいつが死ぬとこが見えた。おれも殺されるとこだった。こいつはべつの場所で殺されたのに、なんでか、この場所にいる……」
人類の犯してきたありとあらゆる悪いものを見せつけられて、みんなの気持ちは重くしずんだ。誰もが死んで当然のような気がした。だって、人間は悪い生き物だ。
利菜はみんなの心がくじけかかっているのを感じた。記憶をさまよっている間に、事態はさらにまずくなっていた。いつのまにか霧がでていた。わた菓子みたいな霧が群生している。
紗英はカナダでガールスカウトに入っていたから、遭難にかんしても知識があった。こんな樹海みたいな場所で、霧がでるのはまずい。寛太がつけた目印も見つけるのが難しくなる。このままだと、迷うことになるかもしれない。
彼女がそのことを話すと、みんなは顔を見あわせた。紗英はあちこち動きまわらないで、じっとしていたほうがいいと言った。みんなは紗英を見た。その目は、こんなところでじっとしていられるか、といっていた。
佳代子が足もとを見おろし、はっと息をのんだ。女の子がすぐそばに転がっていた。佳代子はその子を知らなかったが、見おぼえだけはあった。紗英が近所にいたといった子。なんども新聞をにぎわせた女の子。小野田美由紀という子。
「ひどいよ……」
と佳代子は言った。友だちもその死体に気がついた。紗英はありえないと口にした。美由紀ちゃんはすでに火葬されていた。彼女はこの子をのせた霊柩車のことも目にしている。
子どもたちは、今朝みた幽霊のことを思いだす。その子たちの仲間いりをするか、このまま進むかだ。
利菜はひたいの汗をぬぐった。傷がひどく痛んだ。
みんなは迷った。だけど、達郎が言った。
「い、急ごう」
一同は背中を刺されるような、純然たる恐怖をかんじた。でも、もどったところで結果は目にみえている。どこにいたところで、わるいものは彼らに関わってくる。わるいものが人類全体の悪意の塊とするのなら、どこにいったっておんなじだ。彼らは精神の奥底で、あらゆる人の意識とつながっているのを感じたからだ。
彼らは道なき道をすすんだが、霧はふかくなる一方だった。森のなかにスチームがあって、その蒸気を吹きつけてくるみたいだ。霧は足もとをおおい、膝まできた。そのあとは一気だった。霧は林自体をのみこんでしまった。
達郎がおごそかに、
「もうだめだ、迷うぞ」
「たっちゃん、引きかえそう」
寛太が言った。
でも、外には父さんがいるよ……。
そんなことを言いそうになり、利菜はだまって顔をふせた。父親のことをモンスターみたいにいうなんて、そんなことはできない。
実の親なのにな――
後ろから声をかけられ、こんどは利菜もふりむいた。だけど、そこには霧が広がるばかり、林の様子さえわからない。霧が視界をかくし、みんなの恐怖は頂点にたっした。見えないことが、こんなにも怖いことだは思わなかった。進むほどに、わるいものの力は強まっていくようだ。
六人はあれこれ話しあった結果、とうとう引きかえす決意を固めた。子どもたちは出なおすだけだと言いはった。自分たちを見すえる何かにたいし強がっているみたいに。本当は動かないほうがいいとわかっていたけれど、死体と我慢くらべをするなんてごめんだ。外にでて、態勢を立てなおしたかった。だけど、引きかえすことは逃げだすことにほかならない。
心が後ろをむいたら、とたんに恐怖は万倍になった。
彼らは懐中電灯をふやし、来た道をたどりはじめた。ここで引きかえしたら、戻るなんてもう無理だ。でも、そのときには疲れが限界で、まともに考えることができなかった。
脳みそが炎症をおこし、頭蓋骨の中でパンパンに腫れあがっている。これまでにないほど脳みそをつかいまくった結果、いまにも頭が破裂しそうだ。つないだ絆は切れかかり、みんなふつうの子どもにもどりかけていた。
「なんでおまもりを捨てちゃったのよ」
佳代子が達郎をなじると、たちまち罵りあいがはじまった。心を強くたもとうなんて、もう誰もかんがえなかった。言い争いに参加しなかったのは、利菜だけだ。彼女だけは心にかたりかけてくる声に、集中していたからだ。
罵りあいながら歩く五人のメンバーから、利菜の足どりは遅れがちになった。誰もがそのことに気づかず、その距離は十分にとられた。
利菜は肩をつかまれた。ふりむくと、坪井善三が立っていた。
□ 十五
達郎たちは、寛太のつけた印をさがすのに懸命だった。霧はちっとも晴れないし、あちこちの死体はそのままだ。懐中電灯の明かりが、サーチライトみたいに霧に吸いこまれた。達郎はみんなが離れないよう気をくばった。
おかしいのは利菜だった。彼女だけが一人遅れている。霧のむこうに、沈んだり浮かんだりしている。
達郎は怪我でもしたのか、ひょっとして腕の傷口からバイキンでもはいったんだろうかと心配した。いくにも倒れそうに歩いている紗英と佳代子に手をかしながら、「遅れてるぞ、早くこいよ」と言った。
わかってる、利菜はこたえた。彼女が小走りになったので、達郎はちょっと安心した。よかった、体はなんともないみたいだ。
だけど、へんだな、達郎は思った。利菜の声は、耳できいたというより、頭にひびいたように感じた。達郎は不安になった。
おかしいな、なんでこんなふうに思うんだろう?
達郎は恐怖のなかで、こう考える。きっと、山にいるせいで耳がおかしくなったんだ。高いとこに登ると、耳がつんとなるもんな。
それは自分の考えのようでいて、そうではなかった。達郎は自分で自分の気持ちをごまかしたのだけれど、このときは気づかなかった。
彼はもう一度ふりむいた。利菜はちゃんとついてきていた。彼は前をむいた。新治と寛太の背中を、目でおいはじめた。
達郎が、そのときみた利菜が幻覚に――わるいものが生みだした幻覚にすぎないことに気がついたのは、ずっと後のことだった。そのときには、利菜はおまもりさまに完全につかまっていて、とりもどすことは不可能だったのである。
□ 十六
坪井善三は完全に死んでいた。頭の半分が砕けている。ひらいた傷口からは、砕けた脳が露出していた。のこった目玉は、完全に白目をむいている。左腕は皮一枚を残してぶらさがっている。右足はありえない方向に曲がっていた。出血は止まっていたが、乾いてはいなかった。
この状態で生きている人間はいないとしての話だが、坪井善三は完全に死んでいた。それに利菜が坪井を最後にみたのは、彼の自宅だ。佳代子の母親に、連れてこられたんだろうか、とおもって身震いをした。坪井の腕をふりはらいたかったが、体が動かなかった。
あの家で見たときは、どこにでもいる冴えないおじさんだった。太っていたし、油ぎって、はげてもいた。あの日は宗教の集まりがなく、気をぬいてくつろいでいたのだ。えらい人にはぜんぜん見えなかったし、こんなに大きくもなかった。坪井善三は森の瘴気をすって、何十年かぶりに成長したかのようだった。
坪井の脳をみつめるうちに、うえっと嘔吐きがおきた。
「吐くのか?」と坪井が問いかけた。口からは、黒いものがにじみでた。「吐くのか? おれを殺したのはおまえじゃないか」
利菜は胃袋を飲みくだし、「違う、あたしは母さんを帰してほしかっただけだもん」と言った。「殺そうなんて思ってない!」怒鳴ってやりたかったのだが、声はひびわれ、涙も落ちた。いっときはこの男を心底憎みきっていたというのに、いまはただ恐ろしい。
坪井は、でもおれは死んだんだ、おまえも死ね、と言った。
「はなしてよ……」
利菜は懇願する。手にはさらに力がはいる。身動きをするとさらに強く。青白い爪が肩に食いこみだす。薄いシャツをこして、坪井のささくれだった爪が皮膚をつきやぶろうとする。利菜は痛くてまた泣いた。斉藤秀幸や他の子どもたちが、どんなふうに死んだのかがわかった。心を粉々に砕かれて絶望して死んでいったのだ。絶望は人の心だけでなく、体だって殺すんだと。そのことが彼女にはわかった。
カチリ
なにかが所定の位置におさまる音がした。坪井の白目がぐるりとまわって黒目になった。
利菜は膝をおった。逃げたいのに、体に力がはいらない。
「もう助けはないぞ……」
利菜は坪井の足もとにひざまずいた。手をあわせて、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、助けてください……とつぶやいた。それは無意識に出た言葉だった。母親がいつもしていたお祈りの言葉が、耳にのこっていたのだ。
坪井に空白がおとずれた。空白の時間が。彼は、生前自分が情熱をうちこんだ言葉を聞いて、考えこんでいる。口をあけたまま、動きを止めた。
顔をあげた利菜は、坪井が自分に覆いかぶさろうとしていることを知った。そのさきの結果は知りたくもない。坪井の口から真っ黒な血が、よだれまじりにたれ落ちてきた。利菜はそれを避けて、ぱっと立ちあがった。
「みんなはっ?」
彼女の身動きで、霧が渦をまいた。誰もいなかった。真っ暗だった。夜みたいに。
利菜は口に手をあて、大声を上げようとする、霧のなかから突きでた猿臂に、胸を一突きされてその場にころがった。痛みに顔をしかめながら見あげると、白い霧の幕をひきさいて、ついになめ太郎があらわれた。
「関心、関心」
「うわああ!」
利菜は声をあげながら、坪井のとなりをかけぬけた。なめ太郎が足音をならして追ってきた。
ふりむくと、クモみたいに長い手足を、猿のように振り動かして追ってくる。手足をつくたびに、ダッと土が舞い散った。利菜は死体をふみつけ(おなかをふみつけると、肉がさけて、なかにたまった空気が、ぶふう、と出てきた)、木の根に足をとられながらも必死に走った。その間も、なめ太郎が心に語りかけてくる。
「みんなおまえを捨てたぞ、よくがんばったが無駄だったな、父親も母親もみんなおまえをみはなしてる、おまえはここで死ぬんだ」
そんなことない、と利菜は言った。でも、みんなから遠ざかっているのがわかる。みんながいるのとは反対方向に走っている。だけど、後ろには、なめ太郎がいてひきかえせないのだ。
霧の中から溺死女があらわれた。利菜はあわてて方向を変えた。溺死女は死体の腕や足をちぎって投げた。利菜は死体の腕に顔をつかまれ悲鳴をあげた。それをむしりとると、助けて、と言った。誰か、助けて。
隠れるところをもとめて走る。呼吸をするたびに大量の蒸気が胸にはいりこむ。木にぶつかり、低木の葉に頬を切り裂かれながらも走った。
止まれ、小娘! もう逃げてもむだだ!
「うるさい!」
ふりむかずに怒鳴る。急に目の前に階段と扉があらわれた。利菜はとまれずに敷石に足をとられ、階段に身をなげだし、賽銭箱らしきものに身をうちあてて止まった。骨の節々に痛みが走る。折れたんじゃないか。利菜はすねをかかえた。だけど、痛がっているひまはなかった。顔をあげると、坪井となめ太郎と溺死女の三人がとびかってきた。
利菜は悲鳴をあげて、身をひるがえす。後ろからは三人が階段をかけあがってくる。利菜は一歩はやく、お堂の扉をあけ、中にすべりこむと、扉をしめた。
ドタン、ドタン
外の三人が扉に身をうちあてる。出て来い、出て来い、とわめいている。でも、扉を開けようとする気配はなかった。
利菜が恐る恐る格子のすきまから外をのぞいた。三人の目玉と視線があい、彼女は尻もちをついた。なめ太郎は格子にしがみついて、扉を前後にゆすっている。利菜は尻もちをついたまま後ずさった。出てこい、出てこい、出てこい!
「いやだ! ぜったい、出て行かない!」
そこはかなり大きなお堂だった。真っ暗だが、部屋の奥に飾り壇のようなものが見える。部屋はひとつきりだ。仏像のたぐいはなく、質素なつくりで、天井には蜘蛛が巣をはっている。窓はない。お堂の外からは、なめ太郎たちがうろつく音がした。なにかをぶつけているらしい。壁がときおり音をたてた。
利菜は、安全なお堂ですこし落ちつきをとりもどした。汗をかいたせいか、ひどい寒気を感じる。呼吸をととのえようとすると、吐く息は真っ白で、冷えた洞穴にいるみたいだ。全力疾走のせいで、肺が痛んだ。いろんなものにぶつかって、全身がぼろぼろだった。目暗闇のなかを走りすぎたのだ。
痛みにうめきながら、腰をおろす。体を点検すると、ズボンがやぶけ、膝こぞうがのぞいている。血がひかっている。
どんな目にあってもいいように、いらないズボンを履いてきたものの、それでも残念だった。擦り傷だらけで、打ち身も多かった。わずかな身動きでも痛みがはしる。
みんなのことを感じようと、意識を集中させた。だけど、なにも感じなかった。携帯の圏外にはいったような、そんな感じだ。
「どうしよう……デンチは達郎ちゃんがもってるし」
とつぶやいてから、自分がピンクのリュックを背負ったままだったことに気がついた。利菜はあわててそれをおろし、中身をたしかめた。はいっているのは弁当だけだ。
「食事か? くれよ」
格子の隙間からなめ太郎がのぞいている。利菜は怒って弁当をなげた。風呂敷がとけ、中身がちらばった。坪井善三が、外におちた中身をむさぼりはじめた。
利菜は弁当の風呂敷を膝にまきつけた。腕のハンカチをなぜると、涙がでそうになった。それをこらえて立ちあがる。お堂を再度みかえした。
その部屋は広くなったり狭くなったりした。まるで利菜の感情に、坪数をあわせているみたいだ。彼女は自分で自分の手をとって、みんなのことを感じようとした。なにも感じない。
大声をあげて助けを呼びたいが、外はわるいものでいっぱいだ。
このお堂、なんでこんなに新しいんだろう。両神山に村があったことは知っている。でもそれは江戸時代の話だ。その人たちが建てたお堂だとしても、とっくに朽ち果てているはずだ。
世界はねじまげられている……ねじまげられている……と彼女は考えた。でもなにかを考えるには、彼女は疲れすぎていた。
体育すわりをして、膝におでこを乗せると、すこし眠った。
□ 十七
彼女が目をさましたのは、なにかを感じたからだった。お堂のなかで、なにかが動いている。なめ太郎が入ってきたのかと思ったが、ちがうようだ。彼女は目をこすった。そんなには眠っていないはずだ。
時計をみる。十一時になっていた。おまもりさまを四時間ばかりもうろつきまわっていたことになる。みんなはどうなったんだろう? わたしをおいて外に出ちゃったんだろうか?
いけにえだ、となめ太郎が言った。
「佳代子はそんなことしない」といいかえす。
どうやら部屋の奥にあるのは、縦長の丸鏡のようだった。利菜はふらふらと近づいていった。ずいぶんうすぼけた鏡で、おまけにすごく曇っている。暗いせいもあるが、うつっているものがよく見えなかった。
やがて利菜は、
「銅だ、この鏡、銅でできてる」
でも、なにかがそこでうごめいているのは確かだ。自分が映っているんじゃない。利菜はよく見ようと、目をほそめて鏡にちかづいた。鏡面に息がかかって曇りがついた。曇りをぬぐおうと指を伸ばした。そのときだった。
その鏡は、磁石みたいに彼女を吸いよせた。利菜は鏡にはりつけになった。冷たい鏡に顔がはりつく。骨をのこして、皮と肉がひっぱられる。利菜は鏡に手をついて体を引っぺがそうとした。外でなめ太郎たちが歓声をあげた。
「なによ、この鏡」
利菜は手をつっぱるが、鏡の吸引力はさらにつよくなる。そのうち鏡のむこうがはっきりしてきて、誰かが手をついていることを知った。
「手を離しなさいよ!」
と利菜は言った。その人物は、うろたえたようだった。
そのうち鏡の色が変わり、坪井の家でみたあの真っくろな穴が鏡にひろがった。どろどろとした瘴気がただよいだし、腕や体にまきついてくる。その瘴気はわたアメみたいにしっかりしている。
「離して、離せ!」
その言葉は、この日、彼女がこの世界にのこした最後の言葉になった。吸いこみがぐっと強くなり、腕が鏡にめりこんだ。足をつっぱりこらえるが、カカトが上がってとても堪えきれなくなる。利菜は穴から身をはなそうと、ぐっと背をそらした。
その瞬間、穴はぐわりとその輪をひろげ、瘴気もろとも彼女をのみこんだ。
利菜がこの世から姿を消すと、黒い穴はなくなった。異界との鏡は、またもとの銅の鏡にもどった。
そして、なめ太郎や溺死女の狂喜の叫びも、同時に消えたのだった。