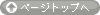�u�˂��܂����E�̖`���v�ւ悤����
���̃y�[�W�́A�l�b�g�ŏ�����ǂ܂����p�ɗp�ӂ��܂����B
���ҁA�Z�҂Ƃ��낦�Ă��܂��B�Â���i������̂ŁA�ł��ɂ͖ڂ��Ԃ��Ă���Ă��������B
�˂��܂��O������A��낵���I
�˂��܂����E�̖`��
����@��������
���@�͑O�@��Z��Z�N�@�\�\���
���@�@�@�@��
�@����q�͂��ł��d�b�������Ă����Ə����Ă������A�������͐����������Ă��A��b����Ƃ�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������B�g�ѓd�b��Ў�ɁA�A�h���X���Ăт����Ƃ���܂ł͂������̂����d�b��������ɂ͂�����Ȃ������B
�@���̉Ă̋L���́A������������݂��������B�莆���L���̈���������T�肠�Ă����̂悤���B�����A���̈��������͍��ׂƂ��Ă��āA�̂����݂�̂��e�Ղł͂Ȃ��B�Ȃɂ��A�ޏ����g���������Ȃт�����A���̋L���ɂӂ������悤�Ƃ��Ă���̂��B
�@����q�����ɉ���������B����đ��k���������������A���Ƃ̐^�����m�肽���B�Ȃɂ����S�z�������B����q�͂��₪�点���Ă���Ə����Ă����B�N�ɁH�@�E�l����������A�ƍ߂��������͂��߂����ŁA�N�ɂ��₪�点���Ă���̂��H
�@�F�l�̐g�ɋN���������ƁA�N���肤�邱�Ƃ��l����ƁA�ޏ��͐S�z�ł��܂�Ȃ��c�c�B
�@���̈�N�Ԃ́A����q�͂��납�A�_�ے��̂��Ƃ���v�������Ȃ������B���̒��ɂ���v�l�����ׂČ������Ă��������Ȃ̂ł���B�Ȃ̂ɁA���܂ł͌̋��ɋA��Ȃ��Ă͂Ƃ�������A�����ϔO�ɂ܂ō��܂��Ă���B���̒��ɂ��B���̎R�ɂ��B���̂Ƃ���A�Ƃ�ڂ����łƂ�̂�����Ă���悤�ȁA����ȍ��o���疡����Ă����̂ł���B
�@�ޏ��͂Ȃ�ׂ��_�����Ăčl���悤�Ƃ������A�����ł͂�肫��Ȃ����Ƃ����������B���ɋL���r���A���Ɍ��o�̂��Ƃł���B���o��L���r���ɁA�W�c�ł�����Ƃ͍l���ɂ��������B�����I�ɋL�����Ȃ����Ƃ������Ƃ͂��邾�낤���A�W�c�ł����Ȃ��Ȃǂ��肦�Ȃ��B������Z�l���Z�l�Ƃ��A���Ȃ������̋L�����Ȃ����Ă���B�W�c�Ō��o������Ƃ������Ƃ͂��邾�낤���A�����͏W�c�Ƃ����Ă��������ɉ����͂Ȃꂽ�ꏊ�ŋN�����Ă���c�c�B
�@����q�ɂ�����Ă���̂Ȃ�b�ׂ͂��B���̎莆���������A����Ȃ邢�����炾�����̂Ȃ炻��ł����B�����ǁA����͂��肻���ɂȂ��A�ƁA���͎v�����B
�@����q�ɂ�������S�z�̏�͋����Ȃ������B���͂��̎q���������Ȃ��Ȃ�����A���������̂��܂̏�𗝉����Ă����l���͂ЂƂ�����Ȃ��Ȃ邱�ƂɋC�������B�s���ǂ⌶�o�ɂ����Ȃ܂�鎩�����킩���Ă����l�́A�ނ�������Ăق��ɂȂ��B
�@�Ђ���Ƃ��āA�ނ�������͂������Ȃ�����������Ƃ�����c�c�B����q�͏����Ă����ł͂Ȃ����A�_�ے��ɂ͂��ǂ��Ă���ȂƁB�����œd�b�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���̎q�����̂Ă邱�ƂƂ��Ȃ�����Ȃ����ƁA�ޏ��͎����ɖ₢������B
�@���͉���q�̂��Ƃ��v���A�����Ƃ��Ȃ��ڂɂ����Ă���͂��Ȃ̂ɁA�܂��������v���Ă�������q�̋C�Â����ɗ܂����B�d�b���������̂́A���̋C�Â����ɂ������邽�߂ł��������B���Ƃɂ�������D��S������B�������B�����ǁA������R�[������d�b�̖��@���ȓd�q���������Ă����Ƃ��A�ޏ��͂��̈ꌏ���Ȃ�Ƃ������������Ƃ�����S�������B�s���ǂ��_�ے��ł̔ƍߎ������A�����ł���͎̂������������ł͂Ȃ����c�c����ȍ��o���炨�ڂ���̂������B
�@�R�[�����̂����ł́A����Ȑ����A�������ɂ����₭�̂�������B���E�͂˂��Ȃ����Ă���c�c
�@��b��̌������������q�̐������������Ƃ��A�Ȃ������ƈ��g�ŋ����������܂����B���������������ȏ�ɂ܂����Ă��邱�Ƃ�m�����B
�u����q�H�@��������A�㌴���v
�@���炭���ق��������B����q�͂����������B�u���܂͍������ł��傤�c�c�v
�@���́A����q�����}���Ȃ����Ԃ�Ȃ�����A���Ȃ��悤�ɉ��������������Ă��邱�Ƃ�m�����B
�u�ו��͂Ƃǂ������B�莆���ǂv�@��������B�u���肪�Ƃ��B�����Ԃ�������Ēm���āA�ق��Ƃ��Ă��Ƃ���v
�u�����ԁc�c�H�@�����c�c���Ⴀ�A�����s���ǂŋꂵ��ł���Ă킯�ˁv
�u������v
�u���̎莆��ǂ�ŁA�������������ꂽ�Ƃ́A���͎v��Ȃ������킯���c�c�v
�u���C���Ȃ�����Ȃ��v�@�����������B�Ȃ�ł���Ȃɗ܂��ł�̂��A�����M���Ȃ�̂��A�����ł��킩��Ȃ������B�ЂƂɂ͈��g�̂��߂Ǝv���B���ɂ��߂���ł����s�����A���ӂ�łĂ����悤�ł�����B�u�������́A�������͂ق��Ƃ��Ă�B���������������Ȃ����̂����ċ^���Ă��Ƃ��ɁA�a�C�ŁA���߂ɂȂ�����������Ȃ����Ďv���Ă��B�ł��A�������Ɓc�c�������̂��Ƃ𗝉����Ă������������Ďv������c�c�v
�u�ǂ��ƈ��S�����킯���v�Ɖ���q�͌��t�������B�u�������͂˂��A�����d�b�������Ă��Ȃ���悩�������Ďv���Ă��B�ł��A�����ꂱ���Ȃ邱�Ƃ́A�킩���Ă��悤�Ɏv����v
�u�щp�ɂ͘A�����Ƃ����́H�v
�u�Ƃ�ĂȂ��B�莆�͑��������ǂˁB�Z�����q������c�c�ǂ��ǂ����v�P�����������B�܂���ł��邱�Ƃ́A�e�Ղɑz���ł����B�u�q�ǂ��̍������A���͈�Ԃ������̂��Ƃ킩���Ă��ꂽ����A������A�d�b���������Ȃ������̂́A����������v
�u������������Ȃ���B�˂��A���炭���Ȃ������Ȃ�Ă����݂�������˂��v
�@��l�͓d�b�����ɏ���������킹��B
�@���͌����B�u�������͂�����Ƃ������悤�ɂȂ��ĂˁB���o���݂���ւ�����B�����݂͂Ă邯�ǁA�ł��A�O�قǂЂǂ��͂Ȃ��Ǝv���B�����A�d�b���������̂́v�����Ɛ����܂点��B�����݂̂������B�u���̂��Ƃ��S�z�����������v
�@���͂��܂肱�݁A����̔������܂B����q�͂Ȃɂ������Ȃ��B
�u���_�R�ɂ�������ł��傤�H�v
�@�Ɨ��͌��������A�d�b�͖������Â��B
�u�Ȃɂ������́H�v
�u�Ȃɂ����ĂȂ���v
�u�Ȃɂ��v���������́H�v
�u���͂ǂ��Ȃ́c�c�B�ǂ��܂Ŋo���Ă�́H�v
�u�ڂ������Ƃ͎v�������Ȃ��B�R�Ŗ������Ƃ��̋L�����łĂ��Ȃ��̂�B�ł��A����Ȃ��Ƃ��Ă��肤��̂��ȁH�@�����āA�݂�Ȃ����������ɋL�����Ȃ�������A���o���݂���A�s���ǂɂ���������c�c����ɁA�q�ǂ�����ɂ����Ȃ����Ƃ��������Ȃ�āA����Ȃ��ƐM�����Ȃ��c�c�v
�u�����A���͎v�������ĂȂ��̂ˁB���������̂��Ƃ��A�Ȃɂ��v
�@���������H�@���������ƌ������̂��H
�@����q�̐��ɂ��炾�����܂������悤�������B���͂Ƃ܂ǂ��������A��b����킸���Ɏ����痣���B
�u���̐g�ɂȂɂ��������ĂȂ���Ȃ�A�ق����܂܂ł��悤�Ǝv���Ă��B���͂������𗣂�Ă邵�A���_�R�̂������ɂ͂��Ȃ��B�q�ǂ������邵�ˁv�Ɖ���q�͂Â����B�u�����������͖������Ă���������Ȃ��B�^�����Ԃɂ����āA���o���݂Ă���B��\�ܔN���O�̂��Ƃ����A�킽�������ꂪ�����������̂��m�M�����ĂȂ��������ǁA�����͂��ڂ��Ă����A�V������A�B������ˁB���v���ƁA��l�ɂȂ��Ă���̌��o�́A�S���q�ǂ��̂���ɂ��邱�Ƃ������B���̓�l�ɘb�����ǂ����́A�������������B�V�����͂Ȃ�ǂ��߂܂������A���������Ȃ��ڂɂ����Ă�����v
�u���A�߂܂������Ă������H�v
�u������������v����q�͌������B�u���܂��肳�܂ɂˁB�����������͂��܂��肳�܂ɂ��������������Ă��B���������ǂ��܂ł��ڂ��Ă�́H�v
�@���ڂ��Ă���B�S�̉��[���ł͂��ׂĂo���Ă������A�����Ȃ��ǂ������Ƃ߂邩�̂悤�ɁA�ӎ��̕\�ʂɂ͂̂ڂ��Ă��Ȃ��B
�u���킵�����Ƃ͂Ȃɂ��v
�u�ނ�Ȃ������ˁB���͖{���ɂ��܂����킯�����v
�u�Ȃɂɂ�v
�u���܂��肳�܂ɂ�v
�u�c�c����������ɂ��āB�d�b��������v
�@���͂ق�Ƃɐؒf�{�^�����������Ǝv�����B��b��������痣���A�w���{�^���Ɏ����Ă������B�����ǁA���̂Ƃ��A��b��̂ނ������琺�����A����͉���q�̐��ł͂Ȃ��A�Ⴂ�ɂ��݂����悤�Ȓj�̐��ŁA�u��ȁv�Ƃ����������B
�@���͎�b������ɂ��ǂ��A�������Ɗ���Ȃł��B
�u������Ɋ���������́v
�u���Ȃ���B���������̂ˁv
�@����q�̓����͕����O����킩���Ă����B
�u�d�b�̍���������ˁv
�u���肦�Ȃ���v
�u�����������ł���c�c�v
�u�����Ȃ��Łv����q�͐̂Ƃ����ʂ₳�����������B���ɂ����甯���ȂłĂ��ꂽ���Ƃ��낤�B�K�v�Ȃ̂͂��ꂾ�����B���e�ƁA�����ƁB�u�����܂����Ă�̂ˁB������Ă��肵�Ĉ���������B�����͂��Ȃ���B���ɘA�����Ƃ�́A�����Ă�����v
�u�ǂ����āc�c�H�v
�u�킩���Ă�ł���v
�u�킽�������܂�������ˁv�Ɨ��͌������B����q���������悤�ɋ����Ă͂��Ȃ��B�ł��A������}���āA�܂����炦��K�v�͂������B�u�v���o���Ȃ����ǁc�c�Ȃɂ����������Ƃ͂킩���Ă�B�܂���Ȃ��ڂɂ������Ă����́H�v
�@�d�b�̌������ʼn���q�͉��x�����Ȃ������B�u��Ȃ���������Ȃ��B���̂Ƃ��̂��������́A����Ђǂ��Ȃ�������B�܂��n�܂����̂�v�Ɖ���q�͌������B�u���̂��ɂȂɂ��������Ă邩�A�������͒m��Ȃ��B�����������͓�����ꂽ�Ǝv���Ă��B�ł����������c�c�����������A���܂����܂܂������̂�v
�u�킽���͔��N�O���炢��Ȗ����݂Ă��B���o���݂Ă邵�B����ɖ钆�ɂ����Ăɕ����܂���Ă�݂����Ȃ̂�v
�@�܂͂��炦���Ȃ������B�����Ăɂ��ӂꂾ���Ă����B
�u�c�c�킩���Ă�v
�u�킩���Ă�H�@�Ȃɂ��H�v�@���܂�(����͂���Ȃ�@���Ƃ͂������Ȃ��قǂɔM������)�A���͌��t�ɂ܂�B�u�Ȃɂ��킩��́H�@�ڂ��o�߂���o�X�^�u�̂Ȃ��ɂ������ƁH�@�o�X�^�u�̂ނ����ɏ��������Ă����ƁH�v
�u�M�����c�c�v
�u�Ȃ��āH�v
�u�Ȃ�ł��Ȃ���c�c�B�ł����V�a���������Ă�̂́A��\�ܔN�O�Ƃ��Ȃ���B����ς�A���������������������������Ă�̂�v
�u�ł��A���́A���͊o���Ă���Ă�B�킩���Ă����̂ˁH�v
�u�킩���Ă��B�����������͂��Ȃ��ڂɂ����Ă�����v����q�͊Ԃ������A�u���܂����āv
�u�����́H�@�ǂ��Ȃ́H�v
�u���Ȃ���B�����������Ă�v
�u���ɂ́H�@���ɂ͂Ȃɂ��N�����Ă�́H�v�}�ɋL�������ӂꂾ���A�ޏ��͈�u���t�������Ȃ��B�u�v����������B���ӎ��ɍs�����Ă����Ƃ��������B�킽���͂������̂Ă悤�Ƃ������Ƃ���������v
�u����͂��̂�������Ȃ���v
�u������|���̂�B�܂��܂��A�������c�c�ǂ��ɂ��Ȃ�����H�@���ɂȂɂ�������H�v
�@����͂Ȃɂ�����Ȃ��B
�u�ے肵�Ă���Ȃ��̂ˁv
�u���̂���̂��������Ƃ͂������̂�B�������Ƃ������c�c�������Ǝv���B��l�ɂȂ������炻���v���̂�������Ȃ��c�c�����ǁv
�u�R�łȂɂ��������́H�v
�u�����Ȃ���B�������A���ɖ߂��Ă��ĂƂ����������Ȃ��B����Ȗ��ӔC�Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��B�ł��A�ǂ����Ă������킩��Ȃ��āc�c�v
�u���܂��Ă�̂͂킽��������Ȃ���v
�u����ǂ̂͂������̂�v
�u�Ȃɂ��v
�u�݂�Ȃ���B����ǂ̂��������͒��������܂��Ă�A����Ȋ����v
�@����Nj������͉̂��ゾ�����B
�u�c�c�����Ȃ��ł��Ă����̂͋C�x�߂ɂȂ肻���ˁv
�u�����ˁv
�u�ł��킽�������Ă��B�����킽���ɂ��Ă�݂����Ɂv
�u�����B�}���V�������Ԃ��J�͏����ĂȂ����Ă킯���v
�u���̂�����J�͂ˁv
�@����q�͂��ߑ��������B�u���Ɩ��Ȃ̂́c�c�щp�ˁv
�u���̎q���댯�����Ă��������́v
�u�킩��Ȃ��B�ޏ��ƘA���Ƃ��Ă�H�v
�u�ŋ߂͂��Ԃ����Ȃ̂�B�t���C�g�łƂт܂���Ă�݂��������v
�u�ł��A���_�R�ɂ��Ȃ�������͈��S��������Ȃ��ˁv����q�͂Ԃ₭�悤�ɂ������B���炭���܂�A�₪�āu�˂��A���ڂ��Ă�B�q�ǂ��̂���̉\�b�B���_�R�ł܂�����q�ǂ��̘b�Ƃ��v
�@�������ɏ��B�u���ڂ��Ă��B�������A�q�ǂ����тɂ͂���̂��������Ȃ����Ă�����B�����Ԃǂ����ꂽ��v
�u�����ˁv����q�͌������B�u�ł��A�����������|�������̂��ނ�Ȃ������̂�B����ׂĂ݂��B���_�R�̉\�B�m���Ă邱�Ƃ��m��Ȃ����Ƃ��B�l�b�g��}���قŋL�����������ĂˁB�x�@�ɂ����đ����͂���ŁA�b����������v�̂ǂ�炷���������B�u����͂ق�Ƃ������B���̐X�ŁA���l���q�ǂ�������ł�B���̂�������Ȃ��������̂��ӂ��߂āv
�@���͂Ȃɂ�����Ȃ������B�Ȃɂ������Ȃ������B��͐p�ɂȂ����B����q�͘b�����B
�u�ŋ߂����̂܂����Ԃ������łˁB�ƍ߂��悭����̂�B�Ђ�������Ƃ��A�E�l�����Ƃ��B����Ȃ������Ȓ��ł�H�v
�@�Ɖ���q�͌����B
�u�����ŋ߂̔ƍߋL�^������ׂ��̂�B�����n�}�ɂ�������ł������B����Ȃ�ۂ����������������ǁB����������A�������������Ă�̂́A���_�R���ӂ̒��������Ƃ킩�����B���̎R�𒆐S�ɁA�~��`���݂����ɂˁv�Ɖ���q�͌������B�u����ɂ��̎R�ŁA�܂��E�l�������������Ă�v
�u�����ł���c�c�v�Ɨ��͂Ԃ₢���B
�u���ꂪ�����Ȃ���������Ȃ��B���܂��肳�܂Ŏ��̂����������̂�v
�@��l�͒��ق����B���̒��ق͒P���ȋ��|���炾�������A����q�ׂ͂̈Ӗ��łƂ����悤���B
�u������Ȃ��ŁB����ǂ݂����̂͂���������Ȃ���v
�u����ǁH�@�ȂɁH�@����q�A�Ȃɂ������Ă�́H�v
�u�݂�������Ȃ��c�c��\�ܔN�O�A������������������̎��̂��݂����̂�v
�@���͌������B�u������c�c�v
�u�˂��A�����̂��Ƃ͂Ȃɂ��m��Ȃ��́H�@�V���ɂ����čڂ����̂�v
�u����Șb�ǂo���́c�c�v
�@���̂Ƃ��A�①�ɂ̔����ڂɂ����B�Ȃɂ����\���Ă���B���̎���ڂɂƂ߁A�u�������傤�c�c�v�Ɣޏ��͂��߂����B
�u�ȂɁH�v
�u�蔲����v
�u�Ȃ��āH�v
�@���͗����オ���āA�①�ɂ̑O�ɂ������B���Ɏ�����āA���e���������߂��B����͌Â����ŁA��������Ă��āA�S�~������E�������Ă������̂悤�������B���ɂ̓K���̐�[�����Ă����B�܌��ܓ��̓��t���B���łɏ����ɂ��������̂��B
�u�V���̐蔲���������Ɂc�c���̂����Ă鎖���̋L����v
�u�c�c�����\������Ȃ��̂ˁv
�u������܂���B�U�߂����Ė������āA����Ȃ���\�����肵�Ȃ��v
�@���͂͂��Ƃ낤�Ƃ����w���Ƃ߂��B�V���́A�Ⓚ�ɂ̔��ɂ͂���Ă���B�}�O�l�b�g�͂����Ă��Ȃ��B�ŏ��͌Ђœ\���Ă���̂��Ǝv�������A�����ł͂Ȃ������B�V�����̎��́A�Ԃ��ɂ���ł����B
�u����ꂾ��v�Ɣޏ��͌������B
�u���̂Ƃ��̂��Ƃ��o���ĂȂ��Ă��A���ɂ͂����������������Ă�\�\�݂�ȂɁv
�@�����A����q�͌������B�蔲���̂��Ƃ́A�ے肷�炵�Ȃ������B
�u�킽�������ǂ���������́H�v���͐u�����B
�u�킩��Ȃ���B����͂��Ȃ̂�B���̂Ƃ��A�������ǂ��Ă��āA�����������������v
�u�Ȃɂ��N�����Ă�̂�v�Ɨ��͐u�����B
�u����������v�Ɖ���q�͌������B�u�܂������������͂��܂����̂�v
���@�@��Z��Z�N�@���[���b�p���
���@�@�@�@��
�@���̔N�A�����◘�Ƃ������A�c�Ȃ��݂̖ʁX�Ƌ��|�̉Ă����������ΐ�щp���A���w�𑲋ƂƂƂ��ɃC�M���X�֗��w�����A�X�`���[���f�X�\�\�t���C�g�A�e���_���g�̐E�ɂ����B
�@�X�`���[���f�X�ɂȂ肽��(�t���C�g�A�e���_���g�Ȃ�Č��t�A���w�ܔN���̎щp�ɂ͉����Ȃ������B�X�`���[���f�X�����ʗp�ꂾ�����Ȃ�āB���̒��c�c�����B�Ƃ͂����A�t���C�g�A�e���_���g�ƂȂ������܂ł́A�щp���X�`���[���f�X�Ȃ�Ăі��̎g�p�ɂ͔�������)�A���̂��߂ɊO���ɗ��w����̂��Ƃ����l���́A���w���̂��납�瓪�����ė���Ȃ������B��e�Ƃ͌��_�������Ȃ��������A�n�I���������͉̂䖝�Ȃ�Ȃ������B
�@�щp�͂��Ƃ��邲�Ƃɕ�e�ɔ��R����悤�ɂȂ����B�ޏ��̔w��͂��̉Ă������Ă���}���ɐL�т͂��߁A�Z�N���̂͂��߂ɂ͕�e��ǂ������Ă����B�ޏ��̔��R�́A��e�����҂����悤�ȁu�܂��̗F�����v�̂����ł͂Ȃ��A�L�т��������i�̂����Ȃ̂��ƁA�ޏ��͐M���Ă���B
�@���ǁA�c�Ȃ��݂��}�}�S���ƌĂ�e�̎���̂���A�C�M���X�ɂ킽�邱�Ƃ��ł����̂��A���̉Ă̏o�������������Ǝv���悤�ɂȂ�̂����A�ޏ������̂悤�ȍl�������ɂ��������̂͂����Ƃ��Ƃ̂��ƁB
�@�ߌ�\�ꎞ�l�\�ܕ��B���ƈ�����݂����t���C�g�̂Ȃ��A�ΐ�щp�̏��u���e���b�V���G�A�E�F�Y41�ւ́A�i�H�𓌋��ɂނ��āA���̃X�����[�������肩�����Ă���B���̓��̃t���C�g�͑��Z������߂��B�R�[���{�^���͗����Ȃ���ɂЂ�߂����B�q���斱�������́A���̂��тɒʘH�𑖂�܂���Ă���B
�@�C���͍r�ꑱ���A41�ւ͋��Ԑ����ς炢���Ȃ��炾�B���q�@�����܂͔�Ԃ悤�ɂȂ��Ȃ����B��q�����͐������S�n�����Ă��Ȃ��c�c�B
�@�щp�͋@���H�����ǂ��Â���ӂƂ�����̐��b���Ă��Ȃ���A�@���Ɏ������͂��点��B����ƍ��Ȃ̂�����Ƃ���ɔG�ꂻ�ڂ������̏��������B���̘A�����A��ڂÂ����Ŏщp�Ɏ������������ł����B
�@���͌�������������Ă���B��Ⴂ�Ȓ����܂Œ�����ŁA���H���������点�Ă���B�M�������B�ŋ߂����������邠�̏��������B
�@�щp�͂��炦���ꂸ�ɔߖ������邪�A���̐��͋��R�N��������q�����̋����ɂ܂����B
�@��s�@���X���A��q�����̔ߖ��܂�������B�V�[�g�x���g�̃T�C���͂����ςȂ����B
�@�щp�̊�F�͐^���������B
�@���̊O�ł͍����_���@�̂��Ƃ�܂��Ă���B�Ƃ�����Ђ�߂��������A���̉_����Ƃ炵�����B
�@�щp�͂��̌��ƂƂ��ɑ������a�m�ɖڂ����ǂ��B�ޏ��͖����ł��̔w���Ȃł�B�a�m�̔w�����A�Ȃł���̏��������Ă���閂�@�̃����v���Ƃ������̂悤�ɁB
�@�������X�[�c�����ł������Ƃ�Ƃ������������邪�A�ޏ��͋C�ɂȂ�Ȃ��B�ق��̂��ƂɋC���Ƃ��Ă�������ł���B
�u���肪�Ƃ��N�A����������v
�@�a�m�͑܂����������������B�щp���Ȃ�Ƃ������Ƃ���낢���������ƁA���̊O�ł͓M�������������K���X�Ɏ��\������Ă����B�ڂ����J���A������J���Đ⋩���Ă���炵�����́A�S�삻�̂��̂������B
�@���낽���āA�ʘH�����Ƃ�����ƁA�r�����܂ꂽ�B
�u���v�Ȃ́A�C������邢�̂Ȃ�A�M�����[�ɂ��ǂ��āv
�@�i���V�[�������ł����₢���B�l�q���݂��˂ċ삯���Ă����炵���B
�u�����N�A���v�Ȃ̂��H�v
�@�������傪�q�˂�B�щp�͍l����B�`�[�t�A�e���_���g���A���̂ӂƂ�����A���f�̂��Ƃ��Y��邮�炢�A�킽���͊�F�������炵���c�c�B�щp�́A�M�����[�ɂ��ǂ�ƁA���������ƃ^�o�R���Ƃ肾���B�����ŕs�v�c�Ȃ��̂������B���l�̎q�ǂ��������ʘH�����������Ă����B�щp�͂���Ăė��������邪�A�V�[�g�x���g�̒��p�T�C���͏����Ă��Ȃ��B��q�͒N���Ȃ𗧂ĂȂ��͂����B
�u�݂Ȃ�����B���o�ƌ����̋�ʂ����Ȃ��Ȃ����v
�@�щp�͎��}�C���̏��������ׁA�����d���ɂ��ǂ낤���ƒʘH�ɖڂ����B�t�@�[�X�g�N���X�ƃM�����[���d��J�[�e���̗��ɁA�l�A���������B�щp�͓�����B
�@�܂��������c�c�B
�@�J�[�e���̐�����͗��̑����̂����Ă���B�������琅�H����������A�ʘH���O�~���܂������ԂɔG�炵�Ă����B
�@�щp�͑傫�������z���A�ڂ����ƁA�����������ƂȂ�ǂ��O�����B���̒[���炤�߂�������A�щp�͂����邨����ڂ��J���B
�@���͖ڂ̑O�ɗ����Ă���A�[�������Ⴊ�ޏ����̂�������ł����B���̔w��͌��邽�тɂ������̂����A�����͕S���\�܃Z���`����щp�ƕς��Ȃ��B��̏�ڂÂ����̖ڂŎщp���ɂ݂��A�r��L���Ă���B
�@�щp�͎v�킸����o���āA���̌������̂����B���蔲����Ǝv�����肪�A���ɂԂ���A���͂������Ȃ��コ�ő̂��ӂ������B�G�ꂽ�Ă̂Ђ�����߂Ĕߖ��グ��B
�@�M���������̖ڂ��ނ��Ă����B
�@�����Ɠ{��̂���܂�������ŁA�V�[�g�ɒu���ꂽ�G�����Ђ낢������B���o�ɂ�������̂͏��߂Ă������B����ĂĎG�����܂�߂�ƁA����ɂӂ肩�����A
�u�������Ȃ�A�������Ă��v
�@���̓���ł�������ƁA�G�ꂽ�����т����Ɩ����B���܂�̌������ɂނ��������ڂ���B�ޏ��͓{��钲���t�̂悤�ɁA����ǂ������Ă͓����Ԃ����B
�@�����B
�@�M�����͒ʘH������ƁA�g�C���ɋ삯���ݕ����������B
�@�щp�͍r������f���Ȃ���A����@���ɗ����������B
�u���o�ɂ�����Ƃ͂ˁc�c�v
�@���ꂽ�r����G����������B����ƁA��������z�������̂悤�ɔ��̌���������́A�Ђǂ���c�c�Ƃ����q�ǂ��̐��������B�щp�͂��̐��ɕ������ڂ�������A���������߂��B��}���Ŕ]����������ƁA��̂̐e�F�����������B
�u���H�v
�@���ɂނ����ČĂт�����B�щp�͒N���l�q�����ɂ��ǂ��Ă��Ȃ����Ƃɂق��Ƃ��Ȃ���A�����قǑł��������������Ԃ̃A�e���_���g�łȂ����Ƃ��F��(���̏��͌��o�̂����ɁA���������ăg�C���ɋ삯���̂�����A���̉\���͑傢�ɂ���)�A���ɂ����Ǝw�����킷�B�ޏ��͂��܂ɂ��������肻���ȏ݂������ׂ�B
�u���������A�������̓�����肾����������Ȃ��B���o�ɘb��������Ȃ�āc�c�v
�@���͂����Ƃ��Ă���B�щp�͖��ӎ��̂����Ɏ��L���A�m�u���܂킷�c�c����ƁA��������N�������������悤�ɁA�����Ȃ��Ȃ�B
�@�@���̏Ɩ����܂����������Ǝv���ƁA41�ւ͋}���ȋC���ɂ̂�A�������@�̂������B�щp�͎���Ђ炫�̂��x���悤�Ƃ��邪�A�����Ă���ꂸ�g�𓊂������B�ʘH���̂�@�������Ǝv���ƁA���������ł��A�ޏ��͈ӎ������|������B
�u�����c�c�v
�@����グ��ƁA���̂͂��������������肨�����B�щp�͏��Ɏ�����Đg���N�������Ƃ��邪�A���E�������ł��܂������Ȃ��B
�@�ޏ��̐E�ƈӎ��́A��q�̗l�q�����ɂ����Ƃ����ӔC�����������������A�_�o���ǂ����Őؒf���������A���Ƃ��Ƃ���ӎ��́A�葫���炷�ׂ藎���Ă����B
�@������x����グ��ƁA����ǂ͓M���������O�ɗ����Ă���B�щp�́A���̏����q�ǂ��̂���Ɍ����̂��Ƃ������Ƃ��A�������ŏ��Ɍ����̂��Ƃ������Ƃ��v�������B
�@�M�����͈�u�ŗ����������B�щp�́A�O���Ɍ�������i�Ɉ��R�ƂȂ����B
�u�Ȃɂ���́c�c�v
�@�����ł́A�O����͂������ĊJ�����Ƃ̂Ȃ��R�N�s�b�g���[���̃h�A���J��(�h�A�͓������炵���J�����Ȃ�)�A�@���̃����t�ƕ����c�m�̃G���O��������ł����B
�@41�ւ̑O���́A�I�[�����̂悤�Ȍ��������Ŗ�������Ă����A�����ł͂Ȃ��B���̌��͕��h�K���X��ʂ��ė��ꂱ�݁A�R�N�s�b�g���ł��˂�������Ă����̂ł���B
�@���̓M�����[�܂łƂǂ��Ă���B�Ɩ����ēx�܂��������B��q�̔ߖ��������邪�A����͉������N����������Ƃǂ��Ă������̂悤���B
�@�щp�͎l���̂܂܂͂������B�X�g�b�L���O���傫�������A�ނ������̔����O�~��������B�R�N�s�b�g�̒��O�܂ł͂������ނƁA�ǂɎ�����ė����オ��B���͐������̂悤�ɘR��Ă���B���F�̂悤�ł�����A���F�ł�����B����A���ׂĂ̐F���Ɣޏ��͎v���B
�@�R�N�s�b�g�ƃM�����[�ɂ͒i�����������Ă���B�]�Ȃ��悤�ɂ܂��߂Â��B�����j���Ȃł�B�t�̂̂悤�ɂȂ߂炩�ŁA�m���Ȋ��G���������B�h���@���Ŏ�����������щp�́A���ɂӂꂽ�w�������ނ̂�����B�g�������Ƃ߁A���̂Ȃ��ւƎ��������ł����B�r�͓����ɂȂ�A�傫���䂪��ŐL�т������B
�@���q�@�͓Q���Ƃ���Ԃ̂悤�ɐU�����Ă���B�щp�͌��ɂ݂��т����悤�ɂ��āA�R�N�s�b�g�ɂӂ݂��B
���@�@�@�@�O
�@�R�N�s�b�g�ɂӂ݂��ނƁA�щp�̑̂͌��Ŗ������ꂽ�B
�@���͐����Ă����B�g�F�͔M���A���F�͗₽�������B�Ӗڂ̂悤�ɂ������Ɛi�݁A�����t�̑��c�ȂɎ���������B�ނ͑��c�����Ђ��Č��������݂Ă�����(���̌��ۂ��͂��܂��Ă����Ɏ������c�͂����Ă���)�A�ׂɂ���щp�����Ă�����ƂȂ����B
�u�ǂ�����ē������c�c�v
�@�щp�͂����ƃ����t�ɖڂ����A���̊炪�w�������т��悤�ɑg�D���ނ������ɂ��A�`�[�Y�̂悤�ɂ��炩���䂪�ނ̂������B�ǂ���玩���̊�����Ȃ��̂悤���B�˂��܂���ꂽ�����t�̊炪�����ɕς��A�ӂ����ёO���Ɍ����Ȃ���B
�u���̌��͂Ȃ�Ȃ́H�v
�u�킩���A�ǂ�ǂ���肱��ł���B�����������Ȃ��B�W�F�b�g�G���W�����~�܂肩���Ă邼�I�v
�@�G���O�����ߖ̂悤�ȓ{�萺��������B�щp�͋����ā\�\��q�ɕ�����Ă͑�ς��\�\�h�A��������݂��B
�@�R�N�s�b�g����ʘH�ɖڂ��ނ����щp�́A�t�@�[�X�g�E�N���X�ɂ͐����͂��Ă��Ȃ����Ƃ�m�����B�@���T�[�r�X�������̒ʘH�́A�S���[�g������̉����H�������������I�����炵���B
�@�щp�͂��܌������̂�߂������̂悤�ɁA�͈�t�h�A�����߂��B
�@�����t���Ȃ����ɓ{��B
�u�Ȃ��A�͂��ꂽ�v
�u�h�A���J���������v
�u�����A���������̐��������Ƃ�ɂ����Ȃ��Ă邼�v�G���O���������ɔ�����������Ȃ��炢�����B�u�����t�A�i�H��ς��남�v
�@�G���O���Ɍ�����܂ł��Ȃ��A�����t�͑��c���ɂނ����đS�̏d�������Ă���B���̂Ȃ��ł͂��ׂĂ��䂪��Ō�����炵���A���ꂪ�g�������邽�тɎc�������܂��B�����t�̊�́A�Ȃ��т̂悤�ɃJ�[�u��`���B
�u���c�������Ȃ��v�����t���H�����������̂����܂��琺�������B41�ւ��܂��㉺�ɒ��˔�B
�@�G���O�����щp�Ɍ����B�u�Ȃɂ��āA�V�[�g�x���g����߂�v
�@�������A�ޏ��͂������Ƃ������Ȃ��B�㊯�̌��t�����āA����ɐg���̂肾�����B�����A���̐�ɂ�����̂��B
�u�Ȃ�Ȃ́A����́H�v
�u�킩��Ȃ��I�v�G���O�����v��p�l����@�����B��ǐ����A�������̂ށI�@�g���u�������I�@�������ɉ������̂ށI�@������u���e���b�V���G�A�E�F�Y41�ցI�@���c�������Ȃ��I�@��������G���Ă�I�@�������Ȃ��̂�!?�@�߂��̋�`�܂ŗU�����Ă���I�v
�@41�ւ̎��E�́A���ŕ����ĂȂɂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���q�@�͂��̌��������킯�i��ł����c�c�Ƃ������A��������ɂЂ��悹���Ă����B���̈Ӗ��ł́A�W�F�b�g�@�͂��܁A��������ޑD�Ɏ��Ă����B
�@���̉ЁX�������́A�͂邩�O������41�ւ��Ђ��悹�Ă���B��[�ł́A���͏������Ă���B���̋�Ԃɂ͐����_���Ȃ��B�щp�͂��̏ꏊ�̂��Ƃ��A�����[���Ɗ������B�������͐[�����邩��A�����Ȃɂ������Ȃ��̂��ƁB
�@�ޏ��͂��̋������A�ǂ����Ō����C������B
�@���E�͂˂��Ȃ����Ă���c�c�ޏ��͂Ԃ₭�B�������Ԃ₢�Ă��邱�Ƃɂ��C�Â��Ă��Ȃ��B���̂Ƃ��R�N�s�b�g�������̂Ȃ��́A�����鉹�ɖ�������Ă������炾�B
�@�G���O���͌v��𑀍삵�Ċǐ����Ƃ̌�M��������݂邪�A�����\�̃X�s�[�J�[����́A�z�C�ȃ��b�N����{�̗̉w�Ȃ�����Ă������ŁA�������ȗp���ʂ����Ȃ��B�⋩������B�N���̋��萺�A�������낵���Â��̂╷�������Ƃ��Ȃ��悤�ȉ́B�͂Ă͉���̂������̂悤�Ȑ��܂ŗ���Ă���B�����āA�ӂ��ɐÎ�ɂȂ�A�Ƃ���A�Ƃ���Ă͂܂������������B
�@�щp�͂��̌��̂����ɁA�q�ǂ�����̌��i���݂�B���������ς��ɂЂ܂�肪�炫����A���������͂Ђ܂��������킯�|�X�����Ă���B
�@�ޏ��͋��|�����A�����������͂��߂�B
�@�����t�͌��̐��E���悤�ƁA���c���ƂƂ����݂����������Ă���B�ނ̉E�r�͋��������ɂӂ��ꂠ����A�������݂����ɖ��ł��Ă��邪�A���̂�������ȑ㕨�́A���͂ŋ��܂�Ă��邩�̂悤�ɁA�҂���Ƃ����Ȃ������B�ނ炪���̊�ԂȃI�[�������݂��Ă���A�ܕ��Ƃ����Ă��Ȃ��B����ȑO�ɂ́A�I�[�g�p�C���b�g���A���c���Ɍy���ȃ����c��x�点�Ă����̂ł���B
�@�����t�͑��x�v�̐j���݂邽�߂ɓ���������(���E�͌��ɂӂ�����Ă�������A�ʏ�̈ʒu����ł͌v����ǂ߂Ȃ�����)�B���q���x���������Ă��邪�A���ꂽ����Ȃ��B�d���g�����Ȃ��m��Ȃ����A���X�������̂����ŁA�ŐV�̂͂��̓d�q�@�킪�������Ĕ������N�������̂��B
�@�����t�͊ɖ��ȓ����ő̂��������B���ɏd��������Ƃ͋��������A�����͊C���̂��Ƃ����B
�@�ނ͑��c����|�����Ƃ���w�͂�������āA�O�����݂߂�B
�@�ނ͂䂪��ɗ܂������щp�������B���b�Ԍ��߂��������ƁA�����t�͂����������B
�u�N�̂������Ƃ��肾�c�c���E�͂˂��Ȃ����Ă���c�c�v
�@�ނ�͑O���Ɋ���ނ���B���͎菵������悤�ɎO�l���Ȃł܂킷�B�щp�͓����ɂ��ǂ邱�Ƃ����������(�S�̕Ћ��ł́A�_�ے��ɂ��ǂ邱�Ƃ�����Ă����̂���)�B
�@41�ւ͌��̐[���ւƓ˂��i��ł������B���̏��������ԂցB�щp�͑��c�Ȃ̃V�[�g�ɂ����݂����B�r���܂����A�������ȋ��������Ԃ��A����ǃR�N�s�b�g����͏o�悤�Ƃ��Ȃ��B�ޏ��̋��͋��|���������ł킫�����Ă����B��ʂ̃G�l���M�[���\�\�F�����炩�ǂ�����Ȃ̂��킩��Ȃ����A�������܂�Ă��邩�̂悤���B�܊����Z�����܂�ׂ�Ȃ����܂肫���������B���̊����͎q�ǂ��̂���ɁA�Ȃ�ǂ���������C������B
�@���̏u�ԁA�ޏ��͂��̉ĂɋN���������Ƃ��������̂��v���������B�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ��N�������̂��A���̂킯����A���ڂ낰�Ȃ�������������B
�@�ޏ��͋@���̌���h�肤���������B
�u�����t�I�@�������肵�Ă�I�@�킽�������͓����ɂ����̂�I�@�������ē����̂��Ƃ��l���āI�v
�u�����A���C���E�L���r���̕��͂ǂ��Ȃ��Ă�I�v�����̃G���O�����щp�ɂނ����ē{��B�u�N�͂Ȃ�ł���ȂƂ���ɂ����݂��Ă�I�@�L���r���̊m�F�����Ă����I�v
�u���邳���A���̂��������ꂦ�I�v
�@�G���O���͖ڂ��܂邭�����B�ю}�͋S�̂悤�Ȍ`���œ{��B
�u�킽�������͓����ɂ����̂�I�@�����������Ă���ɂ���������A�����̂��Ƃł��O���Ȃ����I�v
�u�������c�c�v
�@�����߂Â��Ă���B
�@�����t���V�[�g�A�[���ɒu���ꂽ�G���O���̘r�Ɏ���̂��A�u�G���O���v�ƌĂт�����A�ނ����Â����Ƃ߂Ă���B�G���O���ɁA�щp�ɁA�������g�ɁB
�u�����邼�c�c�v
�@�u���e���b�V���G�A�E�F�Y41�ւ́A�����ɋz�����܂�Ă������B�щp�͓����̂��Ƃ��A�ނ����Ɏc�����F�����̂��Ƃ��l���Â����B���̗F�����Ƃ͈�N�ȏ���A�����Ƃ��Ă��Ȃ��̂ɁA�ނ炪�����ւ�Ȋ�@�ɂ��炳��Ă��邱�Ƃ�m��B41�ւ̋@��͂������Ă����ꂽ�Ƃ����̂ɁA�щp�̓��ɂ��郌�[�_�[�́A�Ɍ��܂Ő��\�����߂����̂悤���B
�@�R�N�s�b�g�̎��E����́A�����Ƃ�͂���Ă䂭�B�������g���̂肾���B
�u���̂ނ����ɂ���̂́A������c�c�v�Ɣޏ��͊m�M�����߂��͋������ł������B�u�M���āc�c�v
�@�����āA�^���ÂɂȂ����B
���@�@�@�@�l
�@���Ɉӎ����Ƃ���ǂ����Ƃ��A�щp�͏��ɂ�����A�����c�m�̃G���O���ɐg��h���Ԃ��Ă����B
�@�щp������グ��ƁA�G���O���͋����̕\��������ׂĔޏ��������낵�Ă����B���̊�ɂ͊����������藎���A�ܜ��̂��Ƃ��Z���B
�@�����t���L���r���ɂނ��Ď������������鐺����������B�u���e���b�V���G�A�E�F�Y41�ցA�����t�E�N���C���@���ł��B���@�͂͂��������C���ɂ݂܂��܂������A�����������ɒB���܂����B
�u�ǂ��Ȃ����́c�c�v
�@�ޏ��͐g���������B�@�������邭�Ȃ��Ă��邱�Ƃ�m�����B
�@�R�N�s�b�g�̊O�͈Èłǂ��납�A��ɂ�����Ă����B
�u�N�̂������Ƃ��肾�v�����t���������B�u������B�c�c���m�ɂ͔��䓇�̂������B�����͌ߑO���l�\�ꕪ�v
�u����ȁv�щp�͗����オ��B�u�������͌ߌ�̏\�ꎞ�������̂�B����ȂɋC�������Ă��́H�v
�u�����͈ӎ����Ƃ���ǂ��āA�����ɌN���N�������v�ƃG���O���͌������B
�@�@�͈̂��肵�Ă���B���̎c��͂�������Ȃ��B
�u���Ⴀ�A���Ȃ��������Z���Ԃ������A�ӎ����Ȃ����Ă����Ă킯�ˁv
�@�G���O���͎���ӂ�A���c�����w�������B
�u���肦�Ȃ��A�I�[�g�p�C���b�g�͐��Ă���v
�@�щp�ƃG���O���̓R�N�s�b�g�ɗ��������B�A�[�����X�g�̘e�ɂ����T�[�r�X�R���\�[���ɒu���ꂽ�R�[�q�[���A�܂����C���͂Ȃ��Ă���B
�u�܂�N�̂������ʂ肾�����킯���B�����͓�����O�����B�����āA�����ɂ����v
�u�����炵����ˁv
�u�����Əd�v�Ȃ̂́A��X�������h�������Ԃ�Ԉȏ���Z�k�����Ƃ������Ƃ��v�ƃ����t���������B
�u�N�͂Ȃ�œ����ɂ����Ƃ��킩�����v�G���O�����щp�̌������B�u���̂Ƃ��������낤�B�����ł��O����A���̂ނ����ɂ���͓̂������B�������������v
�u���̂悤�ˁv
�@�G���O���͂��Ԃ����ނ悤�ɔ����Ђ��߂�B�u�Ȃ��������Ă�����H�v
�u����������ł��̎d������J������邩���v
�u�Ȃɂ��H�@�Ȃɂ������Ă�H�v
�u�G���O���A�悹�A�Ȃɂ��N���������͂킩��Ȃ����A�ޏ��̂����ł͂Ȃ����낤�v
�@�ƃ����t�͌��������A�G���O���͂����͎v���Ȃ��ƌ��������Ɋ�������߂Ă���B�����t�͌������B
�u�W�F�b�g�G���W���͐���ɕ������B�������Ȃ����Ă���B��X�̖�ڂ͂������ӂ����ђn��ɂȂ��邱�Ƃ��v
�u��q�����킪�Ȃ����v
�u���킢���Ƃ��Ă��A�Ȃɂ����������������̂�������̂͂��₵�Ȃ��B�������ӂ��߂Ă��v
�@�R�N�s�b�g�̃h�A���m�b�N���ꂽ�B�O�l�͂��ǂ낢�Ċ�������킹���B�щp���Ђ炭�ƁA�i���V�[���O�ɗ����Ă����B�щp���R�N�s�b�g�ɂ���̂��݂Ă�����Ƃ����悤���B�щp�͂������o�����B�킽�������o���݂āA�������Ƃ������Ă��ˁB
�@�i���V�[�͂����قǂ̋@�̓��h�͂��ꂪ�������ƍl�����̂��B�������A����ł͐����̂��Ȃ����Ƃ����������邱�ƂɁA�����ɋC�Â������̂炵���B
�u�@���A�������Ă��炦�܂��B���C���ɂ̂܂ꂽ���Ǝv���ƁA��q�́\�\�킽�����ӂ��߂Ăł����\�\�S�����_���܂����B�C�����ƁA���̊O�̌i�F���������B���ɂȂ��Ă��邶�Ⴀ��܂��v
�u�҂āA��q���݂�ȋC�������Ă����̂��H�v�����t���u�����B
�u�����ł��v
�@�����t�̓V�[�g�ɐg�����������B���ق̒��ŃW�F�b�g�G���W���̉��������������B
�@��₠���Ĕނ͌������B�u�����������ƂȂ�@�������ŏ�������悤�B������R��̌�쓮�Łc�c�܂�q���^���ُ̈�ŁA��q�͈ӎ��������Ȃ����B���̊Ԃɓ����ɂ����c�c�v
�u�{���ɂ����Ȃ�ł����H�@�����̏��Ȃ�ł����H�v�i���V�[�͌������B�u�������S���Ԃœ����ɂ�����ł����H�v
�@�����t�͂ӂ�ނ��ď����B�u�Ȃɂ������Ă�A�������ɋL�^�I�ȑ��������c�c�v
�@�������A�i���V�[�͋B�R�ƌ������B�u�@���A���܂͉������Ɓv
�@�����t�͌v��ɖڂ�������B
�u���܂͌ߑO���l�\�O�����v�v��̃f�W�^�����v���݂Ȃ���G���O�����������B
�u�킽���̎��v�ł͂����ł͂���܂���v
�u�ȂƁH�v
�u���Ȃ������̂́A�p�l���̎��v�ł��傤�H�@�킽���̃A�i���O�͏\�ꎞ�\�ܕ��̂܂܂ł��v
�@�i���V�[�͘r���������Ȃ��炢�����B�щp���N�㕨�̃����b�N�X���݂��B�����t���B�G���O���͕@�ł����ē�l�̋q���斱���ɂ������B
�u�܂肱���������Ƃ��B�R���g���[���p�l���̂��͓̂d�g���v���B����Ɏ������C�����Ă�B���m�Ȏ����͂��ꂩ��ܕ��Ƃ����Ă��Ȃ��v
�u�Ȃ�Ƃł��������������v�����t�͔�ꂽ�悤�ɂ������B�u�����������Đ����̂��悤���Ȃ��B�����A�݂�ȃv���ɂ��ǂ��Ă���B�u���e���b�V���q�����ɍ����������͂���Ă���̂́A�p�j�N�邽�߂���Ȃ��v�Ƃ����āA�����ɁA�u�G���O�����H�v�Ɛu�����B
�u�킩���Ă�v�G���O���͓������ɂ����Ă��߂��݂����ށB�ڂ����B�����Ƃ�����ꂪ�A�]�ɐ��݂��ށB�u�I�[�P�[���v
�u�N�����̓L���r���ɂ��ǂ��ď�q�̖ʓ|���݂Ă���v�ƃ����t�͓�l�ɂ������B�u���ꂩ��Z�����Ȃ邼�c�c�v
�@�����t�̓}�C�N���Ƃ肠���A��q�ɐ������͂��߂��B�i���V�[�́A�щp�̎���Ƃ�A�R�N�s�b�g����ꂾ�����B
�u���Ȃ��͂Ȃ�ŃR�N�s�b�g�ɂ����́H�@�M�����[�ɂ��ǂ����Ƃ��́A���Ȃ��̎p�������Ȃ���ł�����Ƃ�����v�Ɣޏ��͌������B�u�Ȃɂ��������́H�v
�u�킩��Ȃ��B�����Ă��M���Ă���邩�ǂ����c�c�v
�u�����āv
�u�킩���Ă��B��s�@���n�ɑ������āA��q�����ƂȂ����@���~�肽��A�݂�Șb���v
�u�������Ă����Ƃ��肪������ˁv
�@�i���V�[�̓t�@�[�X�g�E�N���X�ɖ߂�͂��߂�B�@���ɂ̓����t�E�N���C���̐����Ђт��A��q����������߂��Ă���B
�@�i���V�[�̌��ǂ����Ƃ����щp�́A�w��ɋC�z�̂悤�Ȃ��̂������ӂ�ނ����B����ƁA�g�C���̃h�A���Ђ炢�Ă���A�т���ʂ�̗����A�q�ǂ��̗����܂��Ȃ����Ȃ�����Ɋ�肩�����Ă���̂��݂����B�щp�͌��t���Ȃ����āA�����Ђ��߂�B���������c�c�Ɣޏ��͍l����B�킽�������͂����������������Ă�B
�@�͂āA�����������ĂȂH�@�Ɣޏ��͎���ɖ₢�������B�킩��Ȃ��B�����ǁA���̒��ɖ߂�A�Ȃɂ����킩�邩������Ȃ��B
�@���̓m�u�ɂ����݂��Ă���B���̔ޏ��Ƀg�C���̒�����M�����̎肪�̂т�B
�u������Ȃ������āA�����ɂ��ǂ���c�c�v
�@�ӂ�ނ��ƃi���V�[�����b�Ȋ�ł܂��Ă����B�g�C���ɖڂ����ǂ��ƁA���͊J���Ă������A���̎p�͂Ȃ������B�щp�͂���ł��S�̂Ȃ��ŁA����������B
�@���S�Ȃ�����B�킽���͂������ڂ��̂��ق��Ƃ����肵�Ȃ��B
�@�����������ڂ��̂��A���܂��Ă݂Ă��肵�Ȃ��c�c�B
���@���́@�����Ƃɂ�
���@����ܔN�@�����\�����\�\�ؗj��
���@�@�@�@��
�@�������́A���_�R�ł̏o�������A���o���Ȃɂ����Ǝv���������Ƃ����B�����ǁA�ُ�ȏo�����͂��ĂÂ��ɋN�������B
�@�����̉ƂɐQ���肵�Ă����Ƃ����A�l�e�⌬���ɂ݂���ڋʂɔY�܂���Ă������A�������Ȃ�ǂ��������B�q�ǂ������͂����������ۂ�����邢���̇��ƌĂԂ悤�ɂȂ����B����́u��邢���̕��������v�Ƃ��A�u��邢���̌������v�ƌ������B�ӂ��ɂ���ꂽ�B
�@�щp�͎���œM�����ɏP��ꂽ�B�V���́A�t�}���قŁA�}�W�V�����ɉ�A�Z�̒B�Y�͂�邢���̂ɂ̂��Ƃ�ꂽ�R�[�`�ɉ����������ꂽ�B
�@�ǂ���爫���C������l������邢���̂����т��悹�Ă���̂��Ƃ������ƂɁA�������͂��ڂ낰�Ȃ���C�Â��͂��߂��B�ނ�́A�s���ǂɂ�����A�钆���o�����悤�ɂȂ����B�ނ�̐��_�́A���ꍏ�ƁA�ǂ��߂��Ă������B
�@�q�ǂ����������_�R�łȂߑ��Y�ɏo���킵�Ă���A�l����̘b�ł���B
���@�@�@�@�Z
�@�[���߂��}���V�����܂łÂ��������A��l�͒Z���e���̂��A�����̍������Ђ낤�悤�ɁA�ƂڂƂڂƕ����Ă���B���]�Ԃ������A��������ꂽ�l�q���B
�@���͐^�����Ȃs�V���c�ɍ��̃W�[���Y�A����q�̓s���N�̂s�V���c�ɁA�J�[�S�p���c���͂��Ă���B��l�̏��̎q�͂₹���ۂ��ŁA�������čׂ��͂Ȃ��W�[���Y���Ԃ��Ԃ��Ɍ�����B
�@���̃V���c�ɂ́A���Ђ̎�`�����Ă����B����q�̂ق��ɂ��B����D��������e�ɉ���ꂽ������(���ʼn���ꂽ�̂͂��Ԃ߂Ă��Ǝv��)���Ȃ�Z���������ł��Ă������A���̂����ɏd�Ȃ�悤�Ɍ��̋��̂тĂ����B
�@���͗ܖڂł��ނ��Ă���B���̂����ޏ��������~�܂����̂ŁA����q�������~�܂����B
�@����q�͏��݂Ȃ��ɑ̂���炵�Ȃ���A�������������̂�҂��Ă������A���͂����т��k�킷����ŁA���̂��������Ƃ��Ȃ��B
�u���ꂳ�Ȃ������ˁv
�@�Ɖ���q�͌����B���͖����ł��Ȃ������B���̏u�ԁA�ޏ��̊炩��@��������A�܂��ۂƂ�Ɨ����āA�����̔����^�C���ɐ��݂��B���͂��������[������ӂ�������A����q����͊炪�����Ȃ��Ȃ�B
�@�ޏ��͂Ȃ�Ƃ����Ă������킩�炸�A�����������Ď����������Ƃ����������Ȃ����B���̂����A�����A
�u����������A�ǂ��������������c�c�v
�@�A���Ђъ��ꂽ�݂����Ȃ��Ⴊ�ꐺ�ł���������A����q�͎q�ǂ��Ȃ���ɋ�������āA
�u������A���ǂ��Ă邩������Ȃ������v
�@�Ɨܐ��ł������B
�@����q�͗��̌��Ɏ�������悤�Ƙr�����������A���ǂӂ��ꂸ�ɋ��ւƈ������ǂ��B�����j������炷�ƁA�䖝�ł����ɓ�l�͕��������B
�@��l�̎q�ǂ�������Ȃӂ��ɐ[�������A�Ȃ����߂������̂��Ƃ��A�M�����i�����킷���ƂɂȂ������̂킯�́A�ڍ���ɂ����ˌ��Ă�K�˂����Ƃ������������B��l�͗��̕�e���������ɏo�������̂����A�̐t�̕�e�ɂ͉���A�낤����邢���̂ɕ߂܂肩�����̂��B
�@���͈ȑO�ɂ��\�\����͂����������n�܂��肸���ƑO�̂��Ƃ��������\�\���̉ƂɘA��Ă����ꂽ���Ƃ�����������A�������ǂ�ȂƂ���ŁA�ǂ�Ȑl������̂����킩���Ă����B�����łȂ���A����q���������͂����Ȃ��B�����ǁA��邢���̂�����q�̎v���Ƃ���A�݂�Ȃ̐S�ɔE�т���ł���̂��Ƃ�����A�������Ă����̎v���Ƃ���ɍs��������ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@���̕�e�́A���܂��肳�܂���߂������̓��ɂ��Ȃ��Ȃ����̂����A���e�ɐu���Ă������܂��ȓ��������ǂ�����(�ޏ��̕��͒Y�_�̂ʂ����R�[���݂����ɂȂ��Ă���)�A���݂�m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�ޏ��̕�e�A�O�Îq�́A�߉h��Ƃ��������n�̏@�h�ɓ�N�O���珊�����Ă����B�������������Ă������̂͂��̏@�h�ɓ��M�����邽�߂ŁA��������ꂾ�����͕̂��e�������Ă������炾�����B
�@���̉Ƃ́A�ǂ��ɂł�����ӂ��̖��Ƃ��B��搶�Ƃ����l���A�ӂ��̂�������ɂ��������Ȃ������B�����A�q�ǂ��Ȃ���ɂ��̐l�����̂����Ă��邱�Ƃ͂ւ�Ă��ɕ��������B
�@�ꂳ�����ɂ́A���͂������̏@���ɓ��M���Ă���(��������f��)�A���̂��Ƃ͕�����ɂ͂����Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ������B�ꂳ��͂��̂Ƃ��^���ȁ\�\���̓��Ɍ�����݂����Ȗڂ��ŁA�����ƌ��߂āA���̐l�ɂ����̂����Ȃɂ������������킩��͂�������A�ƌ����������B�ł��A���������ƂȂ̂ɕ�����ɉB�����Ă�����̂́A���ꂱ���ς���Ȃ����Ɣޏ��͊������B���͕��e�̂��Ƃ��M�����Ă�������A�ق��Ă��邱�Ǝ��̂��炩�����B
�@���͐ϋɓI�ɂ��̂��Ƃ�Y��āA�ꂳ�@����b��ɂ��悤�Ƃ��Ă����l�Ƃ��̂��Ƃ�b���Ă��Ă��A�Ȃ�ׂ��ւ�炸�ɕ����Ȃ��悤�ɁA�^��₢��ȋC�����ɂ͂ӂ�������悤�w�߂Ă����B�ꂳ����������Ȃ��āA�@�����ꂳ����������������Ǝv�����B�����āA�S�̂ǂ����ł͂��̉Ƃނ悤�ɂȂ����B�z���[�n�E�X�݂����Ɏ��Ȃ��̂�������悤�ɂȂ����̂��B
�@�ꂳ���Ȃ��Ȃ��āA�܂������ɓ��ɂ����̂����̉Ƃ������B���̉Ƃɓ��肱���(�߂܂���)�A����ŋA���Ă��Ȃ��ƁA�����l�����̂��B
�@���܂��肳�܂ɓ��肱��Ŏl���������Ă������A�ꂳ��͂܂��߂��Ă��Ȃ������B���e���d���ɂ����ƁA���͗F�����ƗV�тɂł������B�ꂳ���Ȃ��Ȃ������Ƃ́A�N�ɂ��b���Ă��Ȃ������B����ȂƂ��ɁA(���o�₨�����Ȑ��������Ė������Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ���)��e�����Ȃ��Ȃ�čň������A���e���炢�Ȃ��ĉƂɂ����e�ɂ͂Ԃ��Ƃ���Ă������q���͂܂����Ǝv����(����Ȃӂ��Ɏ������Ȃ����߂�̂́A����q�ɂ������Ĉ����Ǝv��������)�B
�@�����ǁA�V���Ƃ킩��A����q�Ɠ�l�A�邱�ƂɂȂ������̂Ƃ��A�}�ɂȂɂ��������䖝�ł��Ȃ��Ȃ����B�ƂɋA��̂��A����ɂȂ����̂��B
�@���͕�e�����Ȃ��Ȃ����̂́A���܂��肳�܂̂������ƍl�����B���o�▰��Ȃ����Ƃɂ����܂�Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�X�g���X�Ȃ�Č��t�́A���w�ܔN���ɂ͂҂�Ƃ��Ȃ��������ǁB�q�ǂ��͑�l���_�������Ȃ����A�Ȃ�ł����e�ł���킯����Ȃ��B���̃s�[�N������Ƃ���Ȃ�A���܂������B
�u����q�A�����������Ă��Ă��ė���A���Ă����v
�@�Ɣޏ��͌������B���̌��t�͂����Ȃ�Ō`���������܂�����������A�������ɉ���q�����t�ɂ܂����B
�@����̂��Ȃ��́A�Ɣޏ��͐����ɂ������B����q�͎v�킸������A�Ɠ������B�����Ă���A���܂����ƍl�����B
�u�ꂳ�A���Ă��Ȃ��Ȃ�����ˁv
�@���͋}�Ɍ������Ƃ��Ă����Ԃ₢���B����q�͂�����̏@���̂��Ƃ�(���̉ƂɎn�I�o���肵�Ă�Ύ��R�ɒm�邱�ƂɂȂ�̂���)�A���Ȃ�ڂ����m���Ă�������A�����ɂǂ��ɍs�������̂�����݂͂̂��߂��B
�u���Ⴀ�A������͂��̉Ƃɂ���v
�u�ق��ɍs���Ƃ��ȂȂ���v�Ɨ��͑��X�����ɂ������B�u����q���Ă��Ă����H�@�������A�ꂳ��ɂ��ǂ��Ă��Ăق����B������͂Ȃ�ɂ������Ă���Ȃ������A����Ƃ��������Ƃ����܂�����������A�������Ȃ����ꏊ�݂����ŁA��������������݂����ŁA��Ȃ�ˁc�c�v
�@�ق�Ƃ͕��e����������ς���Ă��܂����A��e�����Ȃ��Ȃ����̂͂ق��̍s���s��������(�E�l������)���Ȃ��Ȃ̂�������Ȃ��ƍl���Ă����B�����������Ƃ́A���ɂ����̂��|�������B
�u������Ƃ��A�閰��Ȃ����c�c�v
�@����q�͂��ǂ낢���B�u������������B������������Ȃ��c�c�v
�u�����炳�B�ꂳ���ǂ��Ă���������Ė����Ƃ͎v���Ȃ����ǁc�c���o���݂�낤���ǁA�ł��A���܂�肸���Ƃ܂�����B��������l�ł��������Ǝv��������v
�@����͂����������B
�u�ł��A����q�����Ă��Ă�����Ȃ���S����v
�@����Ȃӂ��ɂ�����āA�����C�͂��Ȃ��B����q�́A���̘b�����Ƃ��A�����������͂����܂��Ă����B
�@��e�̂��������������Ȃ��āA�\���w�Z���ɂЂ�܂����Ƃ��A����q�͂����Ԃ�Ȏv���������B���̎q�����͉A�ɂ܂���āA���킳�b���������炾�B����q�͂����Ԃ�䖝�����B�ʂƂނ����Č�����̂Ȃ炢�����������Ƃ��ł���B�ł��A�݂�ȕ������悪���ɂ�������Ȃ��B������A���������̂́A�K�c���q���B����q���ӂ�ނ��ƁA�f�m��ʊ�Ŗڂ����킹�Ȃ��Ȃ�B����q�������Ƃ��炦�Ă����ۂ��ނ��ƁA�܂��\�b���ĊJ����B
�@����Ȃ��Ƃ��ς݂����Ȃ��āA����q�͂�����A�������\�b�����Ă������q�̃O���[�v�ɁA�����ƕ��݂�����B�����āA�R�ق���ꓯ�ɁA���R�Ƃ������������B
�u������A�Ԃ�����܂����B������Ă������Ƃł���B�����H�v
�@�����āA���q���Ђ��ς������̂��B
�@�������܋������������ɂȂ����B�W�Ȃ��̂����������A�W����̂͂������ɍQ�Ăӂ��߂����B�������ܐ搶���Ƃ�ł����B
�@�搶�͂����Ȃ������R���l�ɐu�����Ƃ������A����q�͂���ƂȂ��Č���Ȃ������B
�@���̂����Ɏ���킩���āA�搶������q���������Ƃ𗝉����Ă��ꂽ�B����q�ɓ���I�������̂����A���āA���������Ɏӂ낤�Ƃ����i�ɂȂ����Ƃ��A�ǂ�Ȃɂ����߂��Ă�����q�͓��������Ȃ������B
�u�q�ǂ������܂���́A���炵�����Ƃ����Ă�������������B�����炠�����͈����Ȃ��v�ƌ������B�̂��B
�@�Ƃ�����A����q�̂�����͖̂\�͂��������A���q�̕�e�́A���w�Z�̖�����Ƃ����ƁA�����Ɋ�������l�ł�����B�搶�͈ꐶ�������������B����ł�����q����ł��͂���̂�����A�o���̕�e���Ă�邱�ƂɂȂ����B
�@�o���q�͐E�����ɂ͂���Ƃ������܃q�X�e���[���N�����A�搶�����q�̕���A����q�̂��Ƃ��������l�����B���̊ԁA����q�͐^���ԂȊ�����Ȃ�����A�K���ɋ����̂����͂��炦�Ă����B
�@���ǁA�o���q�̂������ʼn���q�͖��ߕ��ƂɂȂ����̂����A�ƂɋA��ƁA�D�P������e����\�s���������B
�@�[���ɂȂ�A���ɓd�b���������B���͎���ł����Ɖ���q�̐S�z�����Ă����B��l�̎���́A���Ȃ����c�}���V�����̂ƂȂ�̓�������A�����߂��ł���B
�@����q�����̉Ƃɂ������܂ł́A������Ƃ��莞�Ԃ����������B
�@���͉���q�̗l�q���݂Ă��ǂ낢���B�����������Ȃ̂��A����܂�Ђǂ��@���ꂷ���������Ȃ̂��A�ޏ��̊�͎��ڂ����������B�т������Ђ��Ă������A�厖�Ȋ�ɁA�菝���������������B
�@�����ɂ͂���������B���͈֎q�ɁA����q�͏��ɁB����q�͂���܂ŁA�w�Z�ł��Ƃł������Ȃ������̂����A���̂Ƃ��͂��߂Ď�ꂠ�������j�ɁA�ڂ�ڂ�Ɨ܂����ڂ����̂������B
�@�����������Ƃ�����������A�|������q�͗��ɂ������ĉ��`���������B�����̂�����S�߂ȕ������~�߂Ă����̂́A���e�ł͂Ȃ��A���������B
�@���炭����q�͏����݂Ɏ�����Ăɂӂ����B�₪�Ď����ł��[�����������̂��A�傫���ЂƂ��Ȃ������B
�u���Ⴀ�A�����������C�����čs���Ȃ��Ⴂ���Ȃ��B���������̂��Ƃ����邵�B�����ދ��Ƃ��A�������Ȃ��@�������Ă������ˁB�������B�Y�������������Ă��������ǁA��l�ł����H�v
�u�����v�Ɨ��͌������B�u�������A��������ǂ������̂�B���܂����ɁB�ꂳ��ɖ߂��Ă��Ăق����́v
�@����q�͂��Ȃ������B
���@�@�@�@��
�@���̉Ƃ͊ՐÂȏZ��X�̈�p�ɂ����āA�s�C���ȕ��͋C���͂Ȃ��Ă����B�Ǝ��̂͂������Ăӂ����B��͂���ӂꂽ�A���~�������A�ǂ��̃z�[���Z���^�[�ɂ������Ă���悤�ȁA�l�p���|�X�g�����Ă���B
�@�\�D�ɂ͒؈�Ƃ���B
�@����q�͏@���Ƃ����ƁA������z����������A����ȂƂ���ɋ��c�Ƃ��������̂́A������Ƒz�����ɂ��������B
�@��l�͂��������ꂽ�d���̉e����A�ْ������ʂ����ʼnƂ��Ȃ��߂����A�u���b�N���̌������͐Â܂肩�����Ă���B����q�́A�Â��A�Ƃ������t�����ł͑���Ȃ��悤�ȋC�������B���̂������тł́A��C���璾�ق��Ă��܂����݂�����(�ق�Ƃ��͂����鉹���Ђǂ����̂��������������̂����A�ޏ������͂��̂��ƂɋC�Â��Ȃ�����)�B
�@����q�͂�������C��ꂪ�������A���̎�O�Ђ��������킯�ɂ͂����Ȃ������B���̉Ƃ��ǂ�Ȃӂ����������́A�����畷���Ă���Ă��ǂ͒m���Ă����B
�u�s�����v
�@���͖�Ɏ��������A�������ɂ����݂Ȃ���A�����ɂЂ炢�Ă������B�킸���Ȃ����܂ɁA�g�����˂点��悤�ɂ��ē����Ă����B�u�U�[�Ɏ���̂��A����Ăā\�\�M�������ɐG�ꂽ�݂����ɁA�������߂��B
�u�Ód�C����v
�@�Ɣޏ��͋�������Ă������B
�@�u�U�[�͓��ނȂ����������B���͂�����x�������B������x�B�\�\�Ԏ����Ȃ��B
�u�N�����Ȃ���Ȃ��H�v
�u���Ȃ���������Ȃ����ǁc�c�v
�@���݂͂���ꂽ�悤�Ƀm�u���݂߁A�₪�Ă���Ɏ��L�����B
�@�ޏ��͂т����肵���݂����ɐU��ނ����B�u�J���Ă�v
�@�������ƌ˂��J���Ă����B�Ȃ��͈Â��A��C�͉����I���������ꂽ�Ƃ̂悤�ɂ�ǂ�ł���B�˂����߂����Ă����B���̂����ŁA�O�������������B
�@�����ӂ������Ă���B
�@���ւ�������Ă����ɊK�i������B���̂킫�ɁA�L�����܂������L�тĂ���B�L���ƊK�i�͉Ƃ̒����ɂ���A���E�̕������������Ă����B�ȑO�����Ƃ��ƁA�����ڂ͂܂������ς��Ȃ��̂ɁA���͂��̂�������a�����������B���������B
�u���߂������v
�@�k���������A�Â����ւɋz�����܂�Ă����B����ɂ�āA��l�͈������ƉƂ̂Ȃ��ɓ����Ă������B���̔w���ɂ͉���q���\����Ă���B���̔��̒g�������A�ޏ����ق��ƈ��S������B
�u�N�����Ȃ��̂��ȁH�v
�@����q�������B
�u�B��Ă�̂�������Ȃ��v
�u����ɓ���̂͂܂�����Ȃ��H�v
�u�������͂��̏@���̈��������v
�@������A�����Ă������͂����Ǝv�����B
�u���������|�����Ă�������A���ǂ��v���H�v����q�������B
�u���̋C�����킩����Ă�����v�O���������B�u�����������ĕ|������v
�@�L���ɂ��������B
�@�E���̔����J����ƃ��r���O�������B���C�h�e���r�Ƒ傫�Ȋ����ڂɂ����B���͉E��ɂ��邶��玮�̌˂��J�����B�䏊���B�쑤�̑����疾���肪�����Ă���B�O�����Ƃ��͑吨�̂������������������Ă������ǁA���܂͂��̎p���Ȃ��B
�@���ɂ͏���������邪�A���͌����܂��Ă���Ǝv�����B���������ł͂Ȃ��A�ƒ��̌����B
�@����Ȍ��ȗ\���ɂ������ĐU��ނ��ƁA���ւ̔����܂��Ă����B
�u�߂��́H�v
�@����q������ӂ�B��l�͓���������������킵���B�ǂ��炩��Ƃ��Ȃ�������肠���B
�@����q�̎�͗₽���B�����̉��x���A�ǂ��Ɖ��������������B�ƒ�����C����o���Ă��邩�̂悤�ɁB���ŔG�ꂽ�s�V���c���₽�����������B���߂����������̂Ȃ��ŁA�����ɂ������������B
�u���c�c�v
�@�Ɛ��������B��e�̐��������B
�u��K���炾�c�c�v
�@���͌������B����q�̎���Ђ��ă��r���O���ł��B�L���͂���ɈÂ��Ȃ��Ă���B�K�^�K�^�ƂȂɂ����܂鉹������B
�u�J�˂����߂鉹����v�Ɖ���q�������ς܂������Ō����B�u�����������͂��܂����B�����A���B�͂₭�o�Ȃ��Ɓc�c�v
�@�\�\�ł��A�ꂳ�c�c�Ɨ��͂��������A���̌��t�����݂���ł��܂��B�ォ���e�̐��������̂ɁA�Ђ����Ԃ�ɐ����������̂ɁA�ޏ��͂������|�������B
�@�ꂳ��̂��̐��B���O���ĂԐ��c�c�Ȃ����ȋC�z���܂��鐺�ł�����B�ޏ��͂��������A���o���݂āA���������ĕ����Ă�̂ɁA�Ȃ�ł���ȂƂ���ɂ���낤�Ǝv���͂��߂�B�����ɂ����̂͂܂������łƂ�ł��Ȃ��܂��������������Ă���悤�ȁc�c�����Ă�������̐��͂����������Ă����Ȃ���������Ȃ����A����q�̂����悤�ɂ��������Ȃ̂�����Ȃɂ͂܂����̂�������Ȃ��B�����Ă��������������Ă�̂͂킽��������������Ȃ���������Ȃ����A�䂭���ӂ߂��Ƃ������Ƃ����������Ƃ���������₽�炨�����c�c
�@�ł��A���͊K�i������̂ڂ�͂��߂��̂Ŕޏ��͂����������B�܂�����q�̎���Ђ��Ă���A�F�����Â�ɂ���݂����ɁB
�@�������A�K�i������A�܂�����Ƃ̂ڂ邽�тɁA�����قǂ܂œ��ɂ�����ł����^��͂��������A����q�ɂ�������S�z�̏�������Ă��܂��B���̂Ȃ��̎��ɁA�������ꂽ�݂����ɁB
�@�ޏ������́A�����ɓ������悤�ɁA�K�i���̂ڂ肾���B���܂͉ĂŁA�܂����������Ƃ����̂ɁA�Ƃ̒����ǂ�ǂ�Â��Ȃ��Ă������ƂɋC�����B�킸�������œ܂����낤���H�@�������O�Ō��������Ƃ��́A�_�Ȃ�ĂȂ������̂ɁB
�@�ł������ł͎��Ԃ��ǂ�ǂ�߂���̂�������Ȃ��B����Ȃ��Ƃ̕Ћ��ōl����B�O�����͉������������悤�Ȃ̂ɁA�]�݂��̒��S�̓t���X�s�[�h�ʼn�]���Ă��銴�����B�A�h���i�������z��������炪�A�o���u�S�J�ł��ӂꂾ���Ă�B
�@��l�͊K�i�̎肷��Ɏ��������B�Ō�̐��i���̂����A���͗����~�܂�B�������猩����L���̕ǂɁA�T�͂����Ă��邱�ƂɋC�Â������炾�B���̋T��́A�����łĂ���悤�ɂ��������B
�@���͂��ꂪ�����邩�ǂ����A����q�ɐu�������Ǝv�����B�o�͑S�J�̔]�݂����A����q�ɂ������Ă���Ƌ����Ă����B���͉���q�Ƃ́A�������т���������B
�@�ǂ�Ȏ��g�����Ђ낦�鍂���\�̎�M�@�݂����ɁA�ޏ��̔]�͂ӂ���͌����Ȃ����̂��A���Ă͂����Ȃ����̂܂Ō����Ă����B�T�炠�ӂ�ł���̂́A�������ǂ������A�������݂����Ɍ������B
�@����c�c
�@���͐S���̂�������E��ł��������B�ޏ��͐U��ނ��Ă��Ȃ����A����q�������悤�ɐS���Ɏ�ĂĂ���̂������B����ł͌��Ă��Ȃ����A�ޏ��̔]�݂��́A����̌��E�����炵���B
�@�����āA�T����ɑ傫���A�ǂ������������ӂꂾ���Ă������Ǝv���ƁA���̌��Ƃ��Ɏw�������{���˂��łāA�T��̕ǂ��A�����Ƃ��B
���@�@�@�@��
�@���͂�������A�щp�������Ƃ����M�������o�Ă���Ǝv�����B�������������������Ƃ��͔G�ꂽ�C���݂����ȏk�ꔯ�ŁA���̔��̌��Ԃ��猌�������Ⴊ�̂����Ă����̂����A����q���A�\�\�ꂳ��H�@�ƂԂ₢���u�ԂɁA���̏��͐��Y�o���q�ɂ�����Ă����B
�@����q�����т͂��߂��B
�u�ꂳ�I�@�ꂳ�I�@�ꂳ�I�v
�@����q�̕�e�̓X�J�[�g���܂��肠���A�T��̒�����傫�����݂����B�o���q�̗��Ă��郏���s�[�X�ɁA�T�炠�ӂ��ǂ����������܂Ƃ������B
�@�o���q�͘r�����E�ɂ����Ђ낰��A�T�߂��߂��Ƒ傫���Ȃ����B
�@������͕��ƌ����җ�ɐ��������A���Ɖ���q�͎v�킸�o�����X����������ɂȂ�B���₤���K�i�݂͂����Ƃ��낾�������A�����肷������̂�(�肷��̓T���_�����h��ꂽ�݂����ɋ}�ɂʂ�ʂ�Ɗ��肾���A���͎肷��̗��ߋ�Ɏw�����������邱�ƂŁA�ǂ��ɂ���l���̑̏d���x���邱�Ƃ��ł����A�����ĉ���q�Ƒ̂��ӂꂽ���̏u�ԁA����q������ȕ�e�����邮�炢�Ȃ�A�������痎���Ď��ɂ������Ă��邱�Ƃ�m�����A����Ȑe�F�̎v���ɁA���͐g���������݂����Ȕ߂��݂�������)�A�Ȃ�Ƃ����̓���͓��ꂽ�B
�@�ޏ��͉�ɂ������Ă������B
�u����q�A�������肵�Ă�I�@��������ȂƂ���ɂ���킯�Ȃ��I�v
�@�ӂ�ނ��ƁA�K�i�͎O�\�x������z���}�ɂ����݂������B���͉���q�̂��Ƃ�r��{�Ŏx���Ă���B��l�͊R���痎�����������b�N�N���C�}�[�݂����ɂȂ��Ă���B
�u����͂�邢���̂��A����͂����������A����Ȃ̂�����Ȃ��v
�@����q���������B�u�ꂳ���������E���I�v
�u�E�����肷����I�@�͂��|���悱�̖�Y�I�v
�u�����ĕꂳ�c�c�v
�@����q�͌��t�ɂ܂������A���͂��̌��t�̂Â��A�������͉���q�̋C�����݂����Ȃ��̂�S���������Ă��܂����B����q�̕�e���A�����ς���ē�l�Ŏ��̂����Ƃ����߂����Ƃ��A���܂����E���Ă�낤���A�Ƃ��A���Ȃ��܂Ȃ���悩�����ƌ������B���ƁA����̓h���}���炵���猎���݂Ȍ��t���肩������Ȃ�����ǁA����q���������V���b�N�͌����݂Ȃ���Ȃ��[�������B����q�͎v���o���Ȃ�����ǁA�c�����납��A�낭�ɂ���ׂ�����Ȃ����납�炻��Ȍ��t�𗁂тÂ��Ă������A����͔ޏ����v���o���Ȃ��Ă����݈ӎ��̂Ȃ��ŁA�����Ԃ��Ƃ������͂��Ă���B���͉���q�Ɛ��_���Ȃ���̂��������B����q�̂��������Ղ��A�ɂ݂��A���̐g�ōČ����Ȃ���̂����݂��B
�@���͔߂��݂��������Ƌ�������̂Ȃ��ł����������B
�u�������傤�A���̕ꂳ���ɂǂ����������āA�������͂��Ƃ������̂�I�@���ɂ����Ȃ�āA���ق��������Ȃ�āA�S�̂������݂ł����Ďv��Ȃ��ł�B����ȂƂ���o��B�������������A����ȕ��ɂȂ����Ȃ��v
�@�Ɨ��͂���������B
�u�����A�C�������悭�����Ă�B���������ɂ���ꂽ�݂����Ɂv
�u���������c�c�v
�@����q�����t�����݂��߂Ȃ��݂����ɕ�R�Ƃ���B
�u�����A���������B�K�i�͂���ȋ}����Ȃ��B�肷������ׂ����肵�Ȃ��I�v
�@�����肷����Ԃ����������B���̏u�ԁA���z�����Ƃɂ��ǂ��ē�l�͊K�i�ɒ@������ꂽ�B���͊K�i�̊p�ɘ]�ƍ��Ղ�ł����āA�ɂ݂ɂ��߂��Ȃ���K������グ��B
�@����q�̕�e�͊K�i�̏オ����ɘ��R�Ɨ����A�����A�������ɗ����A�ƌ������B�j�݂����ɖ쑾�����������B���̐����������u�ԗ��́A�����ɂ͂��Ȃ�Ȃ��A����ȓz�ɂ͂��Ȃ�Ȃ��A���b�ł���b�ł��Ȃ����ꏏ�ɂ�����A��������ĐS���ւ��܂��āA�����Ɛ�Ɉ������܂��A�Ǝv�����B��ł����ł��B����Ȏ苭����ɂ͂��Ȃ������Ȃ��A�ƁB
�@���͍Q�ĂĂ�邢���̓o���q����ڂ��͂Ȃ��ƁA����q���������Ă��B
�u�����A���ɍ~��āB���ւ����ē������v
�@��l�͉������ĂĊK�i���삯����͂��߂����A��납��͂�����͂邩�ɉz����傫�ȑ������Ђт��āA���͓��̐^���ɁA��邢���̂��҂�����͂���̂������A�������͂��o�����̑������̖т𐁂��͂炢�A�킠�����ւ���q�̂�������҂�������ɐH�����Ă�A�Ǝv�����B
�@�O�l���K�i���ǂ���g�ł����Ȃ���삯�������u�ԁA���r���O����o���q���o�Ă����B��u�ŊK���Ƀ��[�v���āA��l�̍s������҂���Ƃӂ������B
�u�ꂳ��c�c�v
�@����q�����߂��Ă���B�o���q�͘r���ӂ肠���A���̂ق�����ɂ��͂�Ƃ����B
�u��߂āI�v
�@���͔ߖ��グ���B�o���q�����������悤�Ȋ���Ō����낷�B����q�ɎE���ƌ������B�Ƃ��A������͂���Ȋ�����Ă����낤���H
�u�l�̐e�ɉ�����Ȃ�čŒႾ��c�c�v
�@�k�����łԂ₭�A�o���q���܂����U�肠�����Ƃ��ɂ͗��͂��̂�邢���̂����Ƃ��Ă����B���m�̃G�l���M�[���A�]�݂���������Ȃ��̒����삯�߂����Ă����B
�u����q���Ԃ��������Ƌ����Ȃ���I�v
�@���̂Ƃ��A���r���O�Ƃ͔��Α��́A���Ԃ̌˂��J�����B�߉h��̉�ɂ��āA���̉Ƃ̎�l�A�؈�P�O�����������Ȃ���A
�u���邳�����I�@�Ȃɂ𑛂��ł�I�v
�@���o�ł������Ă����炵���A���ɂ͕����̓������������������A��ɂ͐���������Ă���B�ނ͎O�l��(���m�ɂ͓|��Ă���O�l�ڂ̐l����)���āA����ƌ����J�����B���͎v�����B���̐l�ɂ͌����Ă�B
�@����ǗL�������킳���Ɏ�������ς����͉̂���q�������B�ޏ��͉Ƒ�N���������������ƂŁA�܂������x�̂��ʂ���ĕK���ɂȂ��Ă����B
�u�������I�v
�@����q�͌��ւ̃h�A���������B���̏u�ԁA�\�̐^�Ă̊O�C���Ƃ̂Ȃ��̗₦��������C�ƑΗ��������A��Ԃ������Ƃ��Ȃ�̂��l�͊������B������ǂ��납�A��Ԃ̂˂��Ȃ��鉹�܂ŕ������̂ł���B
�@����ł���l�͎�Ő����悤�ɂ��āA��Ԃ̋��������킯(���ڂ͓D�݂����ɓ�l�̎q�ǂ����Ƃ�܂���)�A�Ȃ�Ƃ��\�ɐg���̂肾�����B���̔x�ɔ����̐���ȋ�C�ƔM�C���Ȃ���͂���A���ƑS�����͂��̋}���ȉ��x�ω��ɂ�����Ək�݂�����B
�@�\�ɐ��������������Ƃ���ŁA��l�͐U��ނ����B�Ƃ̒��ł͓o���q����p��ς����Ȃɂ����A�؈�ɕ������Ԃ���Ƃ��낾�����B
�@��l���؈�������悤���Ȃɂ����������悤���Ɩ����Ă��邤���ɁA���ւ̌˂�����ƕ܂����B�A�j���̃R�}���A��~�����݂����ɐÂ��ɂȂ����B�ߖ��Ȃɂ��������Ȃ��B��l�͊�������킹��A���̏u�Ԃɂ͎��]�Ԃɋ삯�����A�T�h���ɔ�т̂�ƈ�ڎU�Ƀy�_���������͂��߂��B
�@�����̂��E�C�������Ƃ�ŁA����U�肩�����Ƃ肷��Ȃ��B
�@�؈�Ƃ��牓�����邻�̈ꎞ�A������͊m���ɐÂ܂肩�����Ă�������ǁA��l�̐S�������ߖ��Ă����B��Ԃ��˂��Ȃ����Ă��܂����Ƃ���́A���ׂẲ����R��Ȃ��Ȃ��Ă�������ǁA�t����]�̓��]���A����Ȕߖ����Ă��ꂽ�̂ł���B
���@�@�@�@��
�@��l���Ƃ܂łÂ��A�蓹�Ō��������������͉̂E�̂悤�Ȏ������������ŁA��l�������؈�Ƃ���o��ꂽ�̂́A�ޏ���������l�ł͂Ȃ���l�ł��������ɂЂ��������Ă��܂����Ƃ����A�������ꂾ���̗��R�ɂ����Ȃ��B����q�̖j�Ɨ��̔w���ɂ������̍��́A��邢���̂�������`�̂悤�Ȃ��̂�����(���̍����l�͂����ƋC�ɂ��Ă����̂����ǁA���s���l�ŋC�Â����l�͂��Ȃ�����)�B
�@��̎��]�Ԃ͑S���͂ł����ƂB�ߖ��������Ȃ��Ȃ�܂ŁB���̉����Ȃ��Ȃ�܂ŁB�]�݂������Ƃɖ߂�܂Ńy�_�����������B�������Ă���A�]�݂��ɂ܂�����I�C���𑫂��g���͂����Ă����݂����Ƀy�_�����������B
�@����̃}���V������������p�Ƃ͓����������Ă����̂�����ǁA���Z���Ԃ̑S�͎����́A���H�������l���������炰��Ƃ��́A�o���o���т���т��Ⴂ�������Ƃ������Ă��ꂽ�B
�@�ǂ��炩��Ƃ��Ȃ��X�s�[�h�����߁A���̂������̓u���[�L���o�[�����肵�߂��B����q���Ƃ܂����B
�@���]�Ԃ͂Ƃ܂������A�S���͑S�͎������Â��Ă����B���t�͑̒��������߂���A���ǂ͂ӂ���݂��ςȂ����B��l�̓n���h���ɂ��Ղ����p���̂܂܁A�ڂ��݂��킷�B
�@���͌����H�@�Ɗ�Őu�����B����q�͌����A�Ɗ�ł��Ȃ������B
�@��l�͎��]�Ԃō�����肽�B���Ƃ͕����ĉƂ܂ł̓������ǂ�͂��߂��B
�@����q�͗��ɐS�̂Ȃ����̂����ꂽ�悤�ȋC�����āA�Ƃ��ɕ�e�Ƃ̊W�ɂ��Ă͒N�ɂ��m��ꂽ���Ȃ����Ƃ�������������A�C�܂����v�������Ă����B�������ꂪ�킩���Ă�������A�o���q�ɂ��Ă͐G�ꂸ���܂��ł����܂ŗ����B�����A���������������͍��܂łɂȂ�����Ȃ��̂��������A���܂��肳�܂ւ̂��������Ƃ������́A���̐��ւ̂��������݂����������ȁA�Ɣޏ��͊����A����ł�������|���C�Â��ċ������̂������B��������͂����̂��ǂ��₷��������Ȃ��A�{���̖��̊댯���������B�Ȃ̂ɕ�e�͂��Ȃ��āA���e���l�q�����������A���k���ׂ���l�͂����N���܂��ɂ��Ȃ������B
�@��l�͍����̏o�����ŁA���������͓������������o�Ȃ���Ȃ��Ƃ������Ƃ�g�ɐ��݂�قǂɗ��������B�������āA������������������ǂ��߂��Ă��邱�Ƃ��A�q�ǂ��Ȃ���Ɋ������̂������B
�@���͂ق��̃����o�[���ǂ��v���Ă���̂��m�肽���������A�ƂɋA����ƁA�قǂȂ����ĒB�Y����d�b���������B���܂肤�ꂵ���d�b�ł͂Ȃ������B�ނ͎�����������������ƂƁA���c�p���Ȃ��Ȃ������Ƃ�`���Ă������炾�B
�@�B�Y�͖����A�Z��ɂ݂�ȂŏW�܂낤�ƁA����܂łɎ����͊����Ɖp��̂��Ƃׂɍs�����肾�ƌ������B�ނ݂͂�ȂŏW�܂��āA�b�������ق��������ƌ������B
�@�d�b�̉����Ȃ��Ȃ�ƁA�����͖ق肱��ł��܂����B���Ԃɂ͎����ƕ��e���ʂ��������Ƃ����炩���Ă���B
�@�䏊�ɂ����ƁA�J�b�v���[�����̊J�����̂�A�������܂܂̎M��R�b�v���A�e�[�u������ʑ�ɎU�����Ă���B���������̃S�~�Ŗڈ�t�ӂ���S�~���A���邾���߂��܂ꂽ�܂܌���Ă����Ȃ��S�~�܂������B
�@�������������ޑ䏊�́A�����ς������������B�S�~�܂ɂ����Â��ƁA�i�C�����ɂ̓��^�X�̕��������F���w�h���݂����̂����т���Ă����B���������B�ď�ɒN�����������邱�Ƃ��Ȃ��A�N�[���[�������邱�Ƃ��Ȃ����������́A����������C���������Ă���A���������ƃS�L�u���̑��鉹�������B
�u����Ȃ����̉Ƃ���Ȃ��c�c�v
�@���ɂ����Ƌ����Ă��āA���͕������S�~�̓����̂Ȃ��ŁA���Ⴍ��グ�Ȃ���@���𐂂炵���B���̉Ƃɂ����A�ꂳ��ɉ��Ǝv�����̂ɁA���ꂾ���炱���댯��Ƃ��Ă܂ʼn���q�ɂ��Ă��Ă�������̂ɁA���ʂ͂��������̂��B
�@�ЂƂ����苃���ƋC���������A���͂����������C�������O�����ɂȂ����B����Ȃӂ��ɋ����Ă��Ⴂ���Ȃ��B�����Ă��������ǁA���̌�͂����ς茳�C�������Ȃ��Ⴞ�߂��A�Ɗ����Y�ɂ���ꂽ�Ƃ���A�L�������ŋ���t�ɋ�C���z�����B
�@���͕���������܂���āA�����炱����̑����������B�N�[���[���S�J�ł����Ă�����B�ق�Ƃ͂���Ȃ��Ƃ�������A��������ɁA�d�C�オ������ł���A�Ɠ{���邯�ǁA��������͂��̐S�z���Ȃ��B
�u���Ȃ��ق���������v
�@�Ƃ����ƁA���������Ƃ����C���ɂȂ����B
�@��e�͙{���ʂȐl�ŁA�������U�炩���̂͌��֎�`�ŁA�|���@����������ǂ͂����A���K���X���T�ɂ����ǂ͐@���l�������B���̔����ŗ��͂܂������Ƃ̂��Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă�����(������ƌ��Ȑ��C���ɂ͂Ȃ��Ă�����)�A���܂�Ă͂��߂ĉƎ�����낤�Ƃ����C�ɂȂ����B
�@���͕��e�̃^���X����R����������B�ԕ��Ǘp�̃}�X�N�������B�S�~�܂̌����O�Ƃ����߂Ă܂��A���̃S�~�����܂ł����Ă��肽�B
�@���̌�A�ޏ��͂��܂����S�~���W�߂Ă܂��A���܂������ꕨ��A���܂����������@�ɂ������݁A���悤���܂˂ł܂킵�Ă݂��B��������Y�ꂽ���A��Œlj������B���C��ƁA���������߂����A���ꂩ�畔���Ƃ��������ɑ|���@���������B
�@�Z���ɂȂ�ƁA���e�����[�\���ٓ̕��������ċA���Ă����B�����Â����������݂āA���e�͂��炭�������������A��₠���ē��Ɏ���������B
�@�����܂Ƃ��Ȕ��������������̂͂��̂Ƃ������ŁA��͂����Ƃ���̋����B�܂�œ��̂Ȃ��̍l���ɔM�����āA�܂��̂��Ƃɂ͂Ȃɂ��C�����Ȃ��l�q�������B
�@���͓��D�ɂ���A�Ȃ�ׂ������b�N�X���悤�ƂƂ߂Ȃ���A������͂���Ђǂ��Ȃ��Ă��ȁA�ƍl�����B���C�Ɋ�����āA�܂������ɂ���Ȃ����B���e���H�������Ȃ�������炲�т��Ƃ肱�ڂ��l�q��A�s�����҂݂����ɁA�e���r�����Ă���̂ɂ܂�Ō��Ă��Ȃ��l�q���v���o�����B
�@���́A�܂�ŕ�����Ȃ��A���ꂩ���l�ƕ�炵�Ă���݂������ȁA�ƍl�����B��������ƕ|���Ȃ��āA�|��������s���������肷��Ƃ悭���o���݂邩��A�������W���o�W���o�Ɗ�ɂԂ������ċC���܂��炵���B
�@�������ď㌴���̐��_�́A������ƒǂ����܂�Ă������̂����A���܂��肳�܂ɂ��ǂ錈�S�������̂́A���C���炠���蔯���ӂ��Ȃ��畔���ɂ��ǂ�A���̏�ɒu���ꂽ�A���镨�����������炾�����B
�@�r�j�[���{�[�����������B
�@�ޏ��͂��炭�ˌ��ɗ��������A���ꂩ��������Ƃ��������Ŋ��ɋ߂Â��A�k����w�Ŏ�ɂƂ����B�Ђ����������������������B�F�̓s���N���B���F�����݂̂悤�ȕ������т���Ă����B�R�Ŏ̂Ă��{�[���������B�Ȃߑ��Y�������������Ă�������B
�@���̓r�j�[���{�[�����e�[�u���ɗ��Ƃ����B
�@���̂Ƃ��A���Ō˂��J���āA���͂Ȃߑ��Y���͂����Ă����Ǝv�����̂����A�˂����������悭�J�����͕̂��e�ŁA�ނ�ࣁX�Ƃ����ڂŁA�u�r�j�[���{�[���͌�������������I�v�ƈꐺ�����ԂƁA�{�I���h���قǁA�����˂�߂łĂ������B
�@���͑��𗐂��Ȃ���A���炭���̏�ŗ����������B�̂Ă��̂Ɂc�c�Ɣޏ��͂Ԃ₢���B�̂Ă��̂ɂǂ�����Ė߂��Ă����낤�H�@���������ɒu�����̂��ȁH
�@�r�j�[���{�[���Ɏ���̂��A�ޏ��͎w��łӂ�悤�Ƃ���B�{�[���͎��R�ɓ]�������B�{�[���ɂ������F�̐��݁B����͂��̂Ƃ��������̍��Ȃ̂����ǁA���̌����̓{�[���Ɋ�d�ɂ��������āA������̂悤�ɂ�������B
�@����͕�����Ȃ���Ȃ��A�ƍl����Ɛk�����N�����B�������o�āA�킫�ڂ��ӂ炸�ɋ��Ԃ�������A���ւ�������ƊO�ɂł��B�Ƃ��łĂ������B
���@�@�@�@�\
�@�����A�q�ǂ������͒B�Y�ɂ���ꂽ�Ƃ���_�ۓ쏬�w�Z�ɏW�������B
�@�Z��O�̑ʉَq���ɂ́A���łɎщp�����Ă����B���]���X�́A����ꂪ��݂̉���ɂȂ��Ă��āA�����ɍ������A���낰��悤�ɂȂ��Ă���B
�@�B�Y�Ɗ����́A�p��̂��Ƃ��������߂ɂ����āA�܂��������B
�@���͉���q�����ɂ��r�j�[���{�[�����������B�V���Ǝщp�͖����������B�݂�ȂЂǂ������ɂȂ����B
�@�\���قǂ���ƁA���������������B�ʉَq�����o��ƁA�w�Z�̖�͕�������A�^����ɂ͎q�ǂ������̎p���Ȃ��B���̂ق����D�s���������B
�@�݂�Ȃ͔��������َq�������āA����ɂ܂�����B��̂��Ɏ��]�Ԃ������߂Ă������B�B�Y��擪�ɂȂ��ɓ������B
�@���g���ł̉���̘b�����т�Ȃ���^����ɂ܂��ƁA�e���X�̊K�i�ɍ��𗎂��������B���̂Ƃ��ɂ͉J�͂�݁A�Ԃ��^�C���������Ă����B�Z�l�͂��������Ƃ��َq���Ђ낰�A�ق肱�����čZ���_���Ȃ��߂��B
�@�����������͉̂���q�������B�B�Y�ɁA
�u�~�n�ɂ͓��ꂽ�́H�v
�u����Ȃ������v
�@�x�@���������炾�Ɣނ��������̂ŁA�݂�Ȃ͂�����Ƌْ������B�B�Y�͊����Ƃꂾ���āA���d���̗l�q�����ɂ������̂��B�s�����ƌ����������̂͊����ŁA�ނ͂��܂���������Ă���B
�@���͐��c�p��Ƃ́A�l�N�̂Ƃ��̃N���X���C�g�������B�����́A���̎q�̂��Ƃ��p��N�Ƃ��ł����B�u�p��N�A���j�p���c�͂��ĂȂ�������ł���H�v
�@��Ȏ������W�������B�݂�Ȃ͉p��̗����v�������ׂ��̂��B
�u�o�b�N�̂Ȃ��ɓ������܂܂������Ă��ƁB������������ˁc�c�v
�@�B�Y���������B�u�x�@�͐��{���Ă��B���ڂꂽ�Ǝv���Ă��Ȃ����ȁH�v
�u���ڂꂽ��Ȃ���ł���H�v
�@����q�̌������͒f��I�������B�������������������Ƃ��ق��Ă����B
�u���ڂꂽ��Ȃ���B���j�p���c���͂����ɉj���Ȃ�Ă�����������B����ɔ��d���̉��ʼnj����킯�Ȃ��v
�@����q���������̂́A���̕ӂ�̐��[�����炾�B�q�ǂ������́A������������ɂ��鏼�̖̂�����ʼnj�����A���c�p�F�����ƏW�܂낤�Ƃ��Ă����̂����̏ꏊ���B
�@����q�͂������₵���B
�u�p��N�����Ȃ��Ȃ����́A���������ƊW����Ǝv���H�v
�u�킩��Ȃ���B���d���̋߂��ł��Ȃ��Ȃ����Ȃ�ċC�����������ǂ��A�ł��A�����͎R�ɂ͍s���ĂȂ�����H�v
�u�ʂ̂Ƃ��ɂ��܂��肳�܂ɍs�������Ă��Ƃ͂Ȃ��H�v
�@�݂�Ȃ͂��������Ɏщp�������B
�u�p��N�A�킽�������Ƃ͕ʂ̂Ƃ��ɂ��܂��肳�܂ɍs�����̂����B����ł����ɕ߂܂�����Ȃ����ȁv
�u�߂܂����Ȃ�Ă���Ȃ��ł�B�p��N���Ȃ��Ȃ���������������Ȃ������v
�@����q�̐��͐k���Ă����B�ł��A�݂�Ȃ̕\��́A���������ƊW����A�Ƃ����Ă����B����Ȗڂɂ����Ă���̂��A���������������Ƃ͎v���Ȃ��������A�v���������Ȃ������B�p��̐g�ɂȂɂ��������Ȃ�āA�����ƍl�������Ȃ��������A���d���ɒu���̂Ă�ꂽ���]�Ԃ́A�Ȃɂ����Î����Ă���C�������B�ꓯ�́\�\���Ȃ��Ȃ����q�ǂ��̂��Ƃ�b���������Ȃ�āA�s�C���Ȃ��Ƃ��������ǁ\�\���݂������Ȃ��悤�Ɋ����Ă��邩���m���߂��������B
�@�B�Y���f���������B�ނ̊�͑����ŁA�傫�ȃK�[�[���ɁX���������B
�@�B�Y�̓�����́A����l�������т���ė���Ȃ��B����ɂ݂�Ȃɂ��܂��`�����邩���M���Ȃ������B
�u���܂��肳�܂ɍs���Ă���A�ςȂ��Ƃ�����N�����ȁv
�@�Ɣނ͐肾�����B���ۂɂ͉ċx�݂ɂ͂���O����A���̗l�q�͂������������B�W�c���Z���͂��܂��āA�����̐��k�̂��߂ɑ��}�o�X�܂ŗp�ӂ���Ă���(�B�Y�����͂��Ԃꂽ����)�B�\�ŗV�Ԏq�ǂ������̎p���A�߂����Č���������ł�����B�Ȃ̂ɑ�l�͊̐t�ȂƂ���Œ��ӂ��͂��Ȃ������B�������Ȃ̂́A���������̐e������(�ς��Ȃ��͎̂щp�̐e�������������A����͔ޏ��̕ꂪ�q��Ăɂ��āA����ȐM�O�������Ă������炾�Ǝv����)�B���ꂾ���O���o�����āA�����̉Ƃɔ��܂肱��ł��A���炵�����������Ă��Ȃ��B
�@�B�Y�́A����Ȃ��Ƃ��v���o���Ȃ���b�������B
�u����͂��������̂����Ƃ���A���������̂��Ƃ́A���ȂƎv�����������B�ł��A�����͎v���Ȃ���ȁB�M�����Ƃ��Ȃߑ��Y�Ƃ��A����͔n���n���������āA����Ȃ̂���͂��Ȃ��A����Ȃ��ƋN����͂��Ȃ����Ďv���������Ƃ��Ă����ǁA���ꂽ������Ȃ��Ƃ����Ⴂ���Ȃ���v
�@�B�Y�͈�C�ɂ܂������āA�݂�Ȃ̂��Ƃ�����悤�Ȗڂ��Ō��n�����B
�@�щp���������B�u�ł��A���������͌��o�����Ă������B�B�Y������āA�Ȃߑ��Y�̂��Ƃ��ɂ��������v
�u����͂���܂��B���������ƁA����͂��܃��g���̎�����������厖��������ȁB�ł��A�R�[�`�̑ŋ��������āA�ق�ƂɊ댯�Ȃ�Ȃ������Ă������������B��邢���̂��āA���ꂽ���̓������������o�Ȃ���Ȃ����āA�ق�Ƃɂ����Ȃ������Ă���͎v���v
�@�B�Y�̊�͐^���ԂɂȂ��āA����ׂ鐺�͍b���������B�����Ȃ��̂ɑ��݂�����̂ɂ��Đ�������̂͂ނ������������B
�@�B�Y�����������ɂ��ĔF�߂�悤�Ȕ����������̂́A���ꂪ�͂��߂Ă������B�B�Y�̔M�S�Șb���Ԃ�ɂ݂�Ȃ͐g���̂肾�����B
�u����Ƃ��̗��K�͊ē����Ȃ��Ă��A�������đ�w���̃R�[�`���㗝�Ńm�b�N�����Ă��B�ŏ��͕��ʂ������B�����j���O���X�g���b�`�������Ƃ���Ȃ��ɂ�����B�L���b�`�{�[���̂Ƃ��͐l��������Ȃ��ăR�[�`���܂����Ă�����B���̂Ƃ��͕��ʂ������B�ł��A�m�b�N���͂��܂��āA�R�[�`�̗l�q���A���������Ȃ����v
�@�B�Y�̊�͐Ԃ��Ȃ�A���̍�����p���Ă���悤�Ȃ��Ԃ肾�����B
�@����q�͒B�Y�������ق��Ă��܂���Ȃ����Ǝv�������A�ނ͂�߂Ȃ������B
�u���̂��Ƃ̓��g���݂̂�Ȃ��F�߂Ă�B�R�[�`�̃m�b�N������ɏW�����͂��߂Ă��B������Ăقǂ����Ȃ��āA�Ȃ̂ɂ���ɂ����Ƌߊ����Ă�����B�����ƁA�����Ƃ��B�݂�Ȗڂ��ۂ����Ă��A�R�[�`�͂���ɋߊ����Ă�����������Ȃ��āA�̂̂����B����͂���������Ďv�������ǁA���̂Ƃ��ɂ͂����x�����āc�c�v
�u�{�[�������������c�c�v
�@����q���������B
�u���̃R�[�`�A����m���Ă邺�v
�@�����������ƁA�B�Y�͂��Ȃ������B
�u�₳���������l����B���т������ǂ��B�I���ƃW���[�X�������Ă��ꂽ�肷�邵�A�ʓ|�����悭���āA����͍D���Ȃ�ȁB�����ǁA���̂Ƃ��̓R�[�`�̊炪�䂪��Ō����Ă��A�R�[�`�̊炪���́c�c�v
�u��邢���݂̂����Ɍ������H�v�����������B
�@�B�Y�͂܂����Ȃ����A
�u�����Ȃ�B����A�������Ȃ��Ă��B�{�[�������������̂́A�g�������������B�{�[��������̂͌��������ǁA�r�������Ȃ��Ă��B���ꂪ�Ԃ��|�ꂽ��A�R�[�`�͂��Ƃɖ߂��āc�c�v
�@�������ށB
�u�ςȌ����������ǂق�ƂȂ�ȁB�S�݂����Ɍ������̂��A�����̊�ɂȂ��āA�Q�ĂĂƂ�ł�����B����̂��Ɩ{�C�ŐS�z���Ă��v
�u�B�Y�����ɉ��䂳�������瓖����O����v����q���������B
�u�R�[�`�̂��ƈ��������ȁB�R�[�`�̂�������Ȃ��B����͂���Ȃ��Ƃ݂�ȂɌ��������Ȃ����A�l���������Ȃ���B�ł��ȁA������������A�ق�ƂɊ�Ȃ���������Ȃ�����H�v
�u�܂�A�Ȃɂ����������̂�v
�@�щp���s�@���Ɍ����B
�u�܂�m���Ƃ����ق����������Ă��Ƃ���B�݂�Ȗ��f�����Ⴂ���Ȃ��B������������Ă邱�Ƃ͂܂��������B�ق�Ƃ����ǂ܂������Ȃv
�@���������Ƃ��点�A�u������Ă킯�킩��Ȃ���B�܂������Ȃ̂ɁA�ق�ƂȂ킯�H�v
�u�����͂ق�Ƃ��Ă��Ƃ���B�x��������A��邢���̂������ς炦��B����͂ق�Ƃ���������H�@�ł��A���������͂��ꂽ�������Ă�̂��A�����̌������Ďv���Ă�v�Ԃ������āA�u�ł��A����͂�������Ȃ����Ďv���Ă�v
�u�{�[�������ɓ��������肷�邩��A����Ȃ��ƍl����̂�v
�@�щp��������ǂ�ɂ������B
�@�݂�Ȃ̎������W�����āA�ޏ��͐Ԃ����ӂ��Ă��܂����B
�@�B�Y�͑�l�тĂ��Ȃ������B
�u���̃m�b�N�ł͂����肵���̂͂ق�ƂȂB���܂��肳�܂ɉ������邩�͂킩��Ȃ����ǁA�����͂��ꂽ���ɂȂߑ��Y����������A�R�[�`�𑀂����肵�Ă�Ǝv���B�����������Ȃ��m��Ȃ����ǁA�����������Ă̂��ق�Ƃɂ����āA�����͂����Ȃ��Ă�B�Ƃ���͎v���v
�@�B�Y�̌����͗͋��������B
�u���䂪�e���ɎE���ꂽ�̂��A��������܂���Ă�E�l�Ƃ��A�݂�Ȃ��܂��肳�܂������Ă�̂�������Ȃ��B�݂�Ȃ͂ǂ��v���H�v
�@�݂�Ȃ͊�������킹���B��������V�����ۂ�ۂ�Ƙb���͂��߂��B�}���قłȂɂ��������̂����B�V���̐S�́A���̂��Ƃ��v���o���̂����Ԃ������A�ɂ������ɂ͋t�炦�Ȃ��B�����ɘb�����ɂ������ɂ́B
�@�V���͍Ō�ɁA�Z�����̂����Ƃ��肾�Ǝv���A���Ȃ���Ȃ��Ăق�ƂɊ댯���Ǝv���A�ƌ������B
�@�V���̘b���I���ƁA�ꓯ�͂��܂肱�B����q�Ɨ��͊���݂��킹�A����N���������Ƃ�b���͂��߂��B�V���ƕʂꂽ���ƁA������e�������ɂ��������ƌ����͂��߂����ƁA�؈�Ƃ����@���Ƃ̉Ƃɂ��������Ƃ��A�݂����������m�ɘb�����B
�@���̉Ƃł͊K�i��肷�肪�ω��������A�ǂ̗ڂ���͉���q�̕�e�������ꂽ�B�����͂����������̐S���ǂ߂��A����q�͂����������B����ň�Ԃ���Ȃӂ��Ɏp��ς���B
�@����q������Ȃӂ��ɂ������̂ŁA�B�Y�͐g�k�����Ȃ��炱���v�����B������͂��ꂽ���̂��Ƃ�m������Ă�B
�@��l�̘b�ɁA�݂�Ȃ͐^���ȕ\��ŕ��������Ă������A�����r�j�[���{�[�����Ƃ肾���ƁA�H������悤�Ȗڂ��ɕς�����B�B�Y�Ɗ����͐M�����Ȃ��ƌ��������Ƀ{�[���Ɋ�������Â����B
�@�B�Y���A�u�Ȃ�A����B���܂������ċA���Ă����̂���v
�u�������A�C����������̏�ɂ������̂�B����̔ӂ����ǁc�c���o������Ƃ��͂Ȃ������̂Ɂv
�@�݂�Ȃ̓r�j�[���{�[���ɖڂ𗎂Ƃ����B����q���������B
�u�������A����̂Ă�Ƃ��ꏏ�ɂ�������A�m���ĂB�����ɂ���͂��Ȃ���ˁv
�u�B�Y�����̂����Ƃ��肾��B�e�����������̂͌��o����Ȃ�����v
�@���������ƁA�B�Y�͂��Ȃ������������Ȃ��炱���������B
�u��l�������݂����ɂ��A�E�l�Ƃ͂ق�Ƃɂ���낤�ȁB�����ǂ��ꂾ���Ă��܂��肳�܂Ɩ��W�Ƃ͂����Ȃ���������Ȃ��v
�u�ǂ��������Ƃ�H�v�Ǝщp�B
�@�B�Y�͗����オ�����B�ނ͓������������Ƃ������B
�u�R�[�`�𑀂����݂����ɁA���܂��肳�܂̗͂��Ɛl�����Ă邩������Ȃ��B���͂������̂��̂���Ȃ��āA���ꂽ���̐S�������Ă�̂�������Ȃ���ȁB�����ǁA���܂��肳�܂̗͂������āA�����Ƃ��ꂪ�����ł݂�Ȃ����������Ȃ��Ă��Ȃ����ȁv
�@����q�͕s�@�������Ɍ����Ƃ��点���B�ޏ��͒B�Y�����������Ƃ�F�߂����Ȃ������B
�u���Ⴀ�A���܂��肳�܂ɉ�������́H�@�_�[�X�x�C�_�[�݂����Ȉ�����������ẮH�v
�u����ȗd���Ȃ�Ă��Ȃ���Ȃ����ȁc�c�v
�@�B�Y�͂��������ނ��Ē��v�n�l���Ă���悤�������B
�u����͂Ƃ��Ă������͎v���Ȃ��B�ł��A�����̖�͐l�Ԃ����\�ɂȂ���Ă�������H�@���̎R�ɂ��鉽�����݂�Ȃ��������������Ă��Ȃ������āA����͂����v���v
�@�݂�Ȃ͖����̘b�́A�e���r�Ō��邩�A�G���œǂނ����Ă��ꂼ��ɒm���Ă͂����B�����̂�����g�����A�l�������ɂ�����̂��B����ȂƂ��A�ƍߌ����͂��Ȃ��o��ɂȂ�B
�@���_�R�ɂ́A���܂��肳�܂Ƃ����N�������Â��Ȃ��ꏊ�܂ł���B�݂�Ȃ͂��̎R�ɂ���Ȃɂ��ɂ��Đ^���ɍl���͂��߂��B
�u�������́H�v
�@����q���u�����B
�@���������A�����݂͂�Ȃ��������Ă���A�ꌾ�����𗘂��ĂȂ��B
�u��������A�����͂Ȃɂ��Ȃ������̂���H�v
�@�B�Y���u�����B
�@�݂�Ȃ̎����́A�|�������ɏW�������B�ނ��늰���̐g�ɂ��Ȃɂ��N�����Ă��邱�Ƃ��A���҂��Ă��邩�̂悤�Ȗڂ��������B
�@����ȏW���C�𗁂тĂ��A�����͐�������Ă��ނ��Ă���B�B�Y�́A�����͂�������ׂ�Ȃ��̂��ȁA�Ǝv���Ă����ۂ��ނ����B����Ⴕ��ׂ肽���Ȃ����Ƃ�����B
�@����ƁA�����������Ђ炢���B
�u���ꂢ����������Ȃ���ȁc�c�v
�@������ȁA�Ɣނ͌������B
�@�Ȃɂ��H�@�Ƃ�����ŁA�B�Y�͌����Ȃ���B�����͈�C�ɂ܂������Ă��B
�u����A�ق�Ƃ͏��̖ʼnj�������o�[�ɓ����Ă��B�ł��A�������͔��d���ɋ߂�����A�s���̂₾������B������A�f�����B��������A�p��̂���A����ɍs�����ƂɂȂ����v
�@�����͂�����������đ�������݁A���̑���ɂ���Ɗ���߂Â����B�����̂����炦�Ă���݂����������B
�@���������d���ɍs�����������̂́A�p��̂��Ƃ��m���߂邽�߂������B�p�����̐g����ɂȂ����݂����ȁA����ȍ߈����������Ă����̂��B
�u���܂��̂�������Ȃ���v
�@�B�Y�͂��܂炭�Ȃ��Ċ����̔w��@�����B�����͂��������݂����Ɏ��U�����B������������B�ނ̊炩��A�@���Ɨ܂�����āA���E�ɎU�����B�����Ɍ��C���Ȃ��̂���������ʂ��Ƃ������B
�@�݂�Ȃ̖ڂɂ��܂������B�B�Y�������l���[���Ȋ�����Ă���B
�u�B�Y�����A�����������ǂ���������H�v
�@����q���܂��ʂ����Đu�����B�ޏ��͎�̍b�ɂ����܂��A�����ƌ��߂��B
�u�}���قɂ����ĎR�ɂ��Ē��ׂĂ݂Ȃ����v
�@�ƒB�Y�͒�Ă����B�ނ͐V���ɖڂ�������B
�u�t�}���ق���Ȃ��Ă�����}���قɂ������B�����߂������B�������̕����Â��{�Ƃ��A�_�ے��̂��Ƃ������Ă���{����������͂����v
�@�B�Y�͊����̕I�Ɏ���܂킵�Ĕނ𗧂������B�݂�Ȃ��������B
�@�ނ�͍Z��̊O�ɂ��������]�Ԃ̂Ƃ���܂ŕ����Ă������B
�@�E�l�������N����͂��߂Ă��炱����A�Z��ł̗V�т͋ւ����Ă����B�w�Z�ɂ͓����̐搶�����āA�Z�l�̎p���ڂɂ��Ă����B�����ǁA�Ȃɂ�����Ȃ������B���ӂ��Ȃ������B���̂��Ƃɔނ�͋C�Â��Ă��Ȃ��B���܂��肳�܂̌�������ɂ������Ȃ������݂����ɁA���̐l�����͔ނ�ɊS���͂��Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@�Z����o��Ƃ��A�Ō�Ɏщp�������u�����B
�u�����������A�����ɂ����Ȃ��́H�v
�@�݂�Ȃ݂͌��̊���A������݂����ɖڂ������킵���B
�@�B�Y�͂����ƑO�������B����q���������ނ��āA�C����������͂��߂��B
�@����ɂ��ẮA�N���������悤�Ƃ͂��Ȃ������B
���@�@�@�@�\��
�@������}���ق͐_�ۓ�c�t���̂قNj߂��ɂ���B
�@�Z�l�͂����ŎR�ɂ���L�q��T���͂��߂����A�͂��߂Ă����ɁA����Ȃ����ł͈�������Ă��I���Ȃ����ƂɋC�������B�����ŕВ[���璲�ׂ�̂���߁A���_�R�ɂ��ď����Ă��肻���Ȗ{������I���甲���o���A���̏�ɎR�ς݂ɂ��Ă������B�{���ЂƂ�łɂ߂��ꂽ��A�O�̒�������ӂ�������A�L�����͂����Ă����N�����������߂���(���~��炵���Ǝщp�͎v����)�A�W�Q�͂��܂��܂��������A���ꂼ��Ɏd�������Ȃ����B�����ǁA���������Ɋւ���L�q�͂ǂ��ɂ��Ȃ������B�B�Y�́A���̎R�͂����Ɛ̂��炠�����ɂ������̂ɁA�N�����̂��ƂɋC�Â��Ȃ������낤���Ǝv�����B�ƍ߂��������錻�ۂ́A�ˑR�͂��܂����̂��H
�@���_�R�ɂ́A�̎R��������A�R�̂Ȃ��ɂ͐_�Ђ��������Ƃ������Ƃ����͂킩�����B�����A���ꂪ���������Ƃǂ��W������̂��܂ł͂킩��Ȃ������B�݂�Ȃ͋߂��̃R���r�j�ŐH�������݁A���������Ă��H�ׂȂ��璲�ׂ��B
�@���̂����B�Y���{���������B�ނ͂��܂��đ��̊O�ɖڂ�������B�O�ł̗͐���ƌĂꂽ�ꏊ�ŁA�q�ǂ��������h�b�W�{�[��������Ă���(���Ȃ݂ɕ\�̍Z��́A�����͒��ɔ����Ƃ��ē��H�ɂȂ�A���������͐}���ق̒��ԏ�ɂȂ��Ă���)�B�݂�Ȃ͂��܂��ĒB�Y�����߂��B�����O���ɂȂ��Ă����B
�u�����A�낤�v
�@�B�Y�͕s�@���Ȑ��ł������B
�u���ׂȂ��́v
�@����q���u�����B
�u���ׂĂ��킩��킯�Ȃ���v
�u���Ⴀ�A�ǂ�����̂�H�v
�@����q���u�����B�B�Y�͂ӂ�ނ����B�ܜ������\������B���������A�݂�Ȃ����Ɛ������Ƃ�Ȃ��āA�ڂ̉��ɃN�}�������Ă���B
�@���܂��肳�܂łȂߑ��Y�����Ă���A�l���������Ă����B���̊ԁA�܂Ƃ����������͈������Ƃ��Ȃ��B���ꂼ��ɋ��낵���̌������A���o�����Â��Ă����B
�u�݂�Ȃ��̂܂܉䖝�ł��邩�H�v�Ɛu���B�u���܂̂܂܂��ƁA���܂ł����Ă����������͏I���Ȃ���������Ȃ��v
�u������A�ǂ��������Ȃ̂�v
�@����q���s�@���Ɍ����Ƃ��点���B�B�Y�͕s�@�������ɍ��Ɏ�����Ă�B�킩���Ă邭���ɁA�ƌ��������ȕ\������B
�u���ꂽ��������x�R�ɂ��ǂ�ׂ�����B���܂��肳�܂ɉ������邩�킩��Ȃ��B���ǁA�����͂��ꂽ���ɂ��ǂ邱�Ƃ�]��ł�Ǝv������ȁv
�u����Ȃ́c�c�v�Ɖ���q�͐�債���B�u��Ȃ��ɂ��܂��Ă邶���B�����������̐l���܂ŏI������Ⴄ��������Ȃ���B�Ђł䂫���Ďq��A�p��N�݂����ɎE����邩������Ȃ��v
�u�p��͂܂�����łȂ��B����ɂ���͂��������ɂ��Ă��Ă��炦�����Ǝv���v
�@�B�Y�͌������B�����Y���ꏏ�Ƃ����āA�݂�Ȃ̊�����ς�����B�b�͋}�Ɍ�������тт͂��߂��B
�@�щp�̋�����������Ȗϑz��������Ԃ����B
�u�ł��A�Ȃ�ł��ǂ�Ȃ��Ⴂ���Ȃ��́H�@���������|����B�E�l�Ƃ�������ǂ�����H�@����Ƃ������Ă��A�����̌������ō�������ق�ƂɎ��ɂ����Ă��̂����v
�@�݂�Ȃ͂т����肵�Ĕޏ��������B�N������Ȃӂ��ɂ͍l���Ă��Ȃ������̂��B
�@����q���������B�^���Ȍ��ӂ߂����\������B
�u�ł��A�������͍s�������Ǝv����ˁc�c�ꂳ��̂��Ƃ����邵���B����ȏ゠��Ȗڂɂ͂��������Ȃ��B����ȕꂳ��A���Ƃ��{������Ȃ��Ă��������Ȃ���B�������̖ϑz���Ƃ����炳�A�ϑz�������ɂȂ������Ƃ�����A�Ȃ����爫����B�������A�ꂳ��̂��ƁA����Ȃӂ��Ɍ��Ă�́H�v
�@�N�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�u�Ȃ����爫����c�c�v
�@�Ɖ���q�͌����������B
�@���Ɍ����������̂͗��������B�}�����̊��͂��̏ꏊ���������āA�}���ɉ�c���̗l����悵�͂��߂��B
�u�������A�ꂳ���Ȃ��Ȃ��������B������Ă��܂��肳�܂̂�����������Ȃ��B������̗l�q������Ȃ������B���Ƃɖ߂��Ă�����Ȃ�A�Ȃ�ł��������v
�@�V�������Ȃ��C�����������B�������A(�߈�������)�߂�ׂ��Ȃ낤�Ȃƌ������B�p�߂��Ă����Ȃ�A�Ȃ�ł������������B���̈Ӗ��ł́A���c�p��͂��܂��肳�܂Ɏ��ꂽ�l���̂悤�Ȃ��̂������B
�u�����͊����̉Ƃɔ��܂낤�v�ƒB�Y�͌������B�u����ł��������ɂ��Ă��Ă�����Ă��̂ނB�����͗��_�R�ɂ����v
�@�����ė��Ɏ��������Ă������B�ޏ��͊��̂����Ńr�j�[���{�[�������ėV��ł���B�݂�Ȃ̎������ޏ��̎茳�ɏW������B���͂���ɋC�Â��ă{�[�������܂����B
�u�܂��͂��������ɗ��݂ɂ������v
�@�B�Y�͊��̏�ɂ�������{�������Â��͂��߂��B�݂�Ȃ�����ɂȂ�����B�ނ炪�O�ɂł邱��ɂ́A�����͎O�����܂��A�������_���߂����͂��߂Ă���B�V��͉������Ȃ��Ă����B
�@�ނ炪������}���ق���ɂ��邱��A���_�R�ł͂��łɉJ���~���Ă����B���̉J���́A���c�p��̈�̂��A����Ă����̂��B
���@�@�@�@�\��
�u����������Ȃ����H�v
�@�����̐����A�Ƃ̓y�ԂɂЂт��Ă������B�ꓯ�͊����̉Ƃɂ��ǂ��Ă����B�����͂������Ƙb���Ă����B���������ɗ��_�R�ɂ��Ă��Ă����悤�������ƁA�����̉ƂɏW�������̂ɁA�̐t�̊����Y���o�����Ă��Ȃ��ƌ����B
�u�Ȃ�ł��Ȃ���B�ǂ���������v
�u������ŁA�ƂȂ蒬�ɂ����Ƃ����Ƃ����v
�u������H�v
�@�݂�Ȃ͊�������킹���B�����Y�݂����Ȃ�������ł��A���������W�܂����肷��̂��낤���ƁA�^����������̂��B
�@�B�Y�́A���ʂ͂����Ƒ�������n�K�L���Ȃɂ��Œm�点��͂����ƍl�����B���͂��Ȃ��Ȃ�����e�̂��Ƃ��A�щp�͓M�����̂��Ƃ��v�������|���Ȃ����B����Ⴀ�A���������͒��ڂ���������ǂ��͂���Ă��ꂽ��͂��Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͂ł��Ȃ�(�����Ȃ�����)�B�ł��q�ǂ������ɂƂ��āA�����Y�͐S���I�Ȗh�g��̂悤�Ȃ��̂������B
�@�݂�Ȃ͂��������ɂ��낽�����B�D�_���ƂȂ�ɂ���̂��킩���āA�˒��܂�����悤�Ƃ���̂ɁA�̐t�̌����Ȃ��悤�Ȃ��̂������B�������A���̓D�_�́A�����Ȃ��̂�m���Ă���c�c�B����ȋC���������B
�@�����͂��̉Ƃɂ�邢���̂������Ȃ��ɓ��݂���ł���悤�ȋC�����āA�������ɂ������Ȃ��Ȃ����B
�u�����ǂ����H�v
�@�������ɂ߂��Ȃ��銰�����A�B�Y���Ƃ߂��B
�u��߂��B�ƂȂ蒬�ɂ�������Ȃ�A�����ɂ͂��ǂ��Ă��邾��v
�u�ł��c�c�v
�u�����������}���ōs�������킯����Ȃ����A�������͑҂��Ă������v
�@�Ɖ���q�͌������B�����������䖝����A���������͖߂��Ă���Ǝv�����̂��B�݂�Ȃ͂��Ȃ��C�����������B�������Ђ������邱�ƂɂȂ����B
�@�����A��ɂȂ��Ă������Y�����ǂ��Ă���C�z�͂Ȃ������B�A�����Ȃ���s������킩��Ȃ��B���C�ɂ͂���A���߂ɒ��ւ��邱��ɂȂ�ƁA�B�Y�����������Ǝv���͂��߂��B�����͂₫���������ςȂ����B
�@�|���Ƃɂ͒j�e�����Ȃ�����A�����Y�͏o������Ƃ��͍s����ƘA��������Ȃ炸�c���Ă������A�o��ŋA��Ȃ��Ƃ��͓d�b�������Ă���B�����͕������Ă���A�S�z������ŖZ���������B
�@�Z����������ƁA�����Ƃ̎��ӂł��J���~��͂��߂��B�������B�Y�����炾���Ă����B���_�R�ɍs���s���Ȃ������A�����Y�܂ł��Ȃ��Ȃ������Ƃɕs�������ڂ����B
�@�H�����I������B�e���r�͂܂�Ȃ������B�o���G�e�B���݂Ă��N����Ȃ��B���l���l�����āA�b�������Â��Ȃ��B
�@���Ɖ���q���g�����v���͂��߂����A�J�[�h�������Ĕz��Œ��ɁA�ǂ������߂悤�ƌ��������n���B�j�̎q�����͏R������@�����肵�Ăӂ����Ă������A������������Ɖ����ق��Ă��邱�Ƃ̂ق������������B
�@���������J�����A����ɍ��������Ă���B�J�����q�ǂ��������A�����ɕ����߂Ă���悤���B
�@���̑�J�́A��邢���̂̈��A�̂悤�ł��������B���܂��炻���֍s�����ƁB���_�ƂƂ��ɕ�������ł������������B���������͎��Əꏊ��I�Ȃ��B����͂ق�Ƃ��B
�@�ꓯ�͑��߂ɏA�Q���邱�Ƃɂ����B�����̂悤�ɉᒠ��݂�ƁA�z�c���Ђ��ĉ��Ȃ�тƂȂ����B
�@�J�͂�܂Ȃ������B
�@�����͂����ւ����Ȃ��B
�@�B�Y���z�c�̂Ȃ��łڂ���ƂԂ₢�����A���̍����Ƃ����̂́A�܂��I������킯�ł͂Ȃ������̂��B
���@�@�@�@�\�O
�@���������Ŗڂ����܂����Ƃ��A�Ƃ̂Ȃ��͐^���Â������B�ޏ��͕z�c�̂����ő̂��d�������Ă���B�O�̗��͂����܂��Ă��Ȃ��B�J�ƕ��̉����A�����̒��܂łƂǂ낢���B
�@�J�˂��K�^�K�^���Ă���B���͂����Ƒ����Ђ��܂��Ȃ���A�����������������͂܂��������ȁA�Ǝv�����B�������܂��B�݂�Ȃ̂��т������������A�����₩�ȓf���������B�����ǁA���肩��Ƃ������͂܂����������B�ЂƂ育�Ƃ��A�����ƂÂ����B�ӂ��̉��͖��܂łƂǂ��āA�ޏ��̖ڂ����܂������̂��B
�@�Ŗ�ɖڂ��Ȃ��ƁA�l�p���ᒠ�̓V�䂪�悤����ƌ������B���͗������������ǂ��ėF�������m�F�����B���̍��ɂ͎щp�Ɖ���q������B�E�ǂȂ�ɂ͐V���ƒB�Y�B����q���͂������͂��₾�Ƃ����̂ŁA�����͉���q�̂ƂȂ�ɂ���B
�@���͊|���z�c�̉��ł����Ƃ����܂܁A�N���̂ЂƂ育�Ƃ�(�����Ȃ��Ƃ��F�����̐Q���ł͂Ȃ������B���͏������畷����������)�����Ȃ���A���ꂪ�܂����Ȃ̂����l�����B
�@�J�˂��͂�������A�ޏ��͐g���ӂ�킹��B
�@�s�V���A�I
�@�ӂ��܂̕܂鉹�������B���͕z�c�̂Ȃ��ŁA���݂����ɐg���Ђ邪�������B���Ԃ��ɂȂ�A���鋰�����݂�ƁA�����̕����̌˂��������ɗh��ĕ܂��Ă����B
�@�܂����\�\�Ƃ������Ƃ́A
�@�J���������H
�@���Ă����C������B����Ƃ��͕��Ă����C������B������钆�ɋN���āA�J�����낤���H
�@���Ⴀ�A���܂͒N���߂��낤�H
�@���͖����Ă���l�����������͂��߂�(�����Ă�����ǂ����悤���Ǝv���g�k������)�B�������ӂ��߂ĘZ�l�B�����̐e�ׂ͂̕����ɐQ�Ă���B���̕����ɂ���͎̂q�ǂ��������肾�B
�@�������Ɛg���N�����A�ᒠ�̊O�܂Ŏ������Ƃ��B�����̂ƂȂ�̓e���r�̂��鋏�ԁA���̔��͘L���ŁA�J�˂ɂ܂łÂ��Ă���B�J�˂��J���͂��Ȃ����Ǝv���Ƌ��낵���B�z�c�̂Ȃ��Ŏ�����B�����݂͂�ȐQ���������A���̂Ȃ��ŋꂵ��ł�݂������B����������ɓ������낤���c�c�H�@�Ȃ�̂��߂ɁH
�@�����̉ᒠ���A�B�̂悤�Ɍ��������B���͂����Ƃ��Ă��邪�A�C�z������B�����̕����ɒN������c�c�Ɣޏ��͐M�����B
�u����q�c�c�v
�@���͎щp�̑̂������āA����q�̑̂��䂷�����B����q�͋����肾���ǁA������ɂȂ�͔̂ޏ��������B
�u����q�A�N����v
�@����q�͂т����Ɛg���ӂ�킹�ڂ����܂������A���炭�Ȃɂ��������g�������炵�Ȃ������B���̂Ƃ�����q�͂ƂȂ�ɐQ�Ă���̂��Ȃߑ��Y���ƐM���Ă����̂����A�₪�Ă����������̉ƂŁA���������䂷�����̂������Ƃ������ƂɋC�����ƁA�ґR�ƕ������Ă��B�g�C���ɂ��Ă��ĂƂ�������Ȃ�A�i�ߎE���Ă�낤�Ƃ����v�����B
�@����q�͐g���������A
�u�Ȃɂ��H�v
�@�Ɨ����ɂ�݂����B�J�˂����Ƃ��Ɩ��āA��l�͕z�c�������ƈ�������B�����ȁH�@�Ɨ��͂����������B�ق�Ƃɕ��Ȃ̂��ȁH
�@����q���ᒠ�̂ނ����ł����₢���B
�u�Ȃ�Ȃ̂�H�@�܂���ł���v
�u���̉����特������̂�B����ɂ������͂ӂ��܂��܂����v
�@����q�͏�������B���������B�����āA�u����������Ȃ��́H�v�Ɣޏ��͐u�����B�����ǁA�@�ŏ�����͂��Ȃ������B����q�͂��ْ������̂������B
�@���݂͂�Ȃ����Ă��B�u�ǂ����悤�H�v
�u�J���悤�v
�@����q�͉ᒠ�̒[���������Ɖ��������A�l����̂܂܊O�ɂł��B�����Â����B�ᒠ�̊O�ł́A�d�r���̉���������A�Ԃ������������Ă���B
�@����q�͏�Ɏ��������Â��āA�u�ق�Ƃ��A���肩�艹������v
�@���͉���q�̌������B�u�݂�Ȃ��N��������v
�u���߂���A�����������������N���Ă���v�Ɖ���q�͌������B
�@���͂��ꂪ�d�厖�ł��邩�̂悤�ɂ��Ȃ������B�����Y�̌��t���v�������\�\�|���Ƃ��ɕ|���邾���̂�͂��݂����ꂾ�B
�@���͂��������ɕ|�����Ă���Ǝv����̂͂��₾�����B�����Y�͂˂Ɍւ肽�����l�Ԃ��B���̂��Ƃ�������݂�Ȃɂ��v�����Ă���߂�����B���͎q�ǂ��Ȃ���ɂ��̊��҂ɂ��������������B����q�����Ȃ��C�����炵�������B
�@����q���A
�u���͂ЂƂ�łɕ܂����肵�Ȃ��B�����������͕|�������肵�Ȃ��v
�u���Ȃ��v
�@�Ɨ��͂��Ȃ������B
�@����q�����Ɏ�������A�f�����������B
�u���Α�����J���Ă�B��������ɊJ�����v
�@��l�͍��E���牦���ɂЂ����B�����V�ɐ����h���Ă�������A���͎v�����������������悭�J�����B
�@����q���K�݂������B���͂��߂��悤�ȓf�������炷�B�u�ЂႠ�������c�c�v
�@�����̂Ȃ��ɂ́A�����Ԃ牺�����Ă����B���_�R�ɒ��Ă��������A�_�Ђɖ��߂��͂��̕��������B�����Y�͎q�ǂ����������S����悤�ɂƁA��������ɐ_�Ђ̗��R�ɖ��߂Ă��ꂽ�̂ł���B������P�ɂԂ炳�����Ă��邾������Ȃ��A���͐V���Ȍ��ɂ܂݂�A�т���G��ɂȂ��Ă���B�Â����͂��ђ��F�ɂȂ�A�D�����Ă����B�@�肾���Ă�������݂����Ɂc�c�B
�@����q���A������̉����������ƕ߂��B�����߂��B
�u���肦�Ȃ��A���肦�Ȃ���v����q���Ԃ₭�悤�ɑ����ŁA�u�������炾�����炢���̂ɁA�������̂������炾���������̂Ɂv
�u���ꂱ�����肦�Ȃ���A���̕��A�_�Ђɖ��߂�����B�@�肾���Ȃ�Ăނ肶���B���������|�����Ă����v
�@���͉��܂ł������ɂȂ����Ƃ����悤�Ȋ���Ō˂����グ��B�u����ɏ�������Ă��B�����̕����Ȃ̂ɁA����Ȃ������炵�����Ȃ���v
�@����q�́A�h���悤�Ȗڂ��ŁA�������A
�u���̕��A�J�ŔG��Ă��̂��ȁH�v
�u�������Ǝv���v
�@���̏؋��ɏL��������B�R�����悤�ȁA���̏L�����B
�@�Ȃɂ����V�䗠���삯�ʂ��A��l�͔ߖ������Ĕ�яオ��B���̉��ŒB�Y���N�����B�ނ͕z�c������ۂɂȂ��Ă���̂ɋC�������B
�u���v�ƐV���̑̂������āA��l���Q�Ă����͂��̕z�c���Ȃł��B�u����q�v
�u��������v
�@�w���ɐ����������A�B�Y�͐g�肩���点��B
�u���ǂ����ȁA�������荘�ɂȂ邶���v
�@�B�Y���ꂪ�������̂ƁA�ق��ƈ��S�����̂Ƃł��ǂ��Ă��������A��l�͂܂������킸����ɂ��肠���Ă���B
�@�B�Y�̉��~���ɂȂ����V�����A
�u�Ȃ�ɂ������H�v
�@�����̊ዾ�����ށB�₽���Q���������������ŁA�Q�Ԓ������������ƔG��Ă���B
�u�������ɗ��Ă�v
�@����q���Â��Ȑ��Ō����B�����������N���Ă���̂����̂��A���킪���Ă���݂����Ȑ��F���B
�@�Z��͖����Ŋ�������킹��B�Ȃɂ��������̂��͍l���������Ȃ������B
�u�J����C�H�v��������q�ɐu�����B�u�܂��J����C�H�v
�u������v
�u��k�A����Ȃ̂������������Ȃ���B�C�����Ă�ł���A�L���������v
�u�L���H�v
�@�B�Y���ᒠ����͂��łĂ���B�����������̓������k�o���݂����B�ނ͕����ւƂÂ����������B�����̔������ɂ݂���B
�u�Ȃɂ������H�@�J�����̂��H�v
�@�B�Y����l�̂��ւ������B�ނ͂܂��q�ǂ������A���w�����炢�ɂ͑傫���B���͂킸���Ɉ��g����B����q���������B
�u�����������v
�@�Ђ��Ƒ����̂މ������A�O�l�͔�т�����B�ӂ�ނ��ƁA�V������Ō����������Ă���B
�@�V���͂��܂Ȃ����Ȋ�����A���������炵���B
�@�B�Y���A�u�_�Ђɖ��߂��̂ɂ��H�v
�u�Ȃߑ��Y����v
�@�V�����z�c���Ђ��悹�A�k���Ȃ��炭��܂�B
�@�B�Y�͂�����݂Ė�����������A�u�V���͂����ő҂��Ă�v�ƒ�ɂ������B�ނ͉��Ɋ�������Â����B���̂ނ����ɂȂߑ��Y�����āA�J����Ɖ��F���ڋʂ��ނ�������̂����āA���Ȃ��݂����ɑf�����r��������ނɂ������Ȃ��A�Ǝv���Ȃ�����Ɏ���������B
�@�����܃Z���`�Ђ炢���c�c�ނ�������قǂ̌��̏L�����A�ƂȂ�̕������炩�����Ă����B�B�Y�͂ӂ邦���B�����̕����͕��Ԃ����p���Ă��邩��A�����ɂ͕��d������ʔv���J���Ă���B���̊Ԃɂ͂ւ�Ă��ȊG�̕`���ꂽ���������ꂳ�����Ă���B���̂����ɂ͂���c���܂̎ʐ^�������Ă���B���̂����̎�X�����ʐ^�͊����Y�̌Z��̂��̂ŁA�����̐푈�Ŏ��l���ƌ����B�B�Y�͂����A�C���������ȁA�Ǝv���Ă������A���܂͂���Ȃ��̖ڂɂ͂���Ȃ������B
�@���Ɖ���q�̖ڂɂ����̕����������B�B�Y�̑̂�����܂����āA�V���ɂ͌����Ȃ������݂������B
�@�B�Y�͑����̂B����߂��B���܌������̂��l�����B�����͕����̓V��Ƀ��[�v���킽���āA�����Ƀv�����f����싅�̃y�i���g��݂��Ă���B���͂��̃��[�v�ɂ������Ă����B�B�Y�͕����Ƃ߂Ă��������݂������ƌ����B�������Ɍ��ЂŐ^���Ԃ������B
�u�ǂ����悤�H�v
�@����q���u�����B�������Ɗ����̕�e�͂ƂȂ�̕����ŐQ�Ă���B����q�͂�����N���������Ƃ����Ă���B
�@�B�Y�͕����ЂƂ�łɖ߂��Ă���Ȃ�āA���̖ڂŌ��Ă��M���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���������������������߂����Ă����������B�u�d�C�����悤�v
�@����q�����₭�����ăX�C�b�`�����ꂽ�B�����������B�u�����������̓����������c�c���̕��A������ʂ�ŁA�^�����݂����Ɍ���������v
�@����ƒB�Y�͓{���Ăӂ�ނ��A
�u���̂��肩�肢�����͂Ȃv
�@�݂�Ȃ͑傫�Ȑ�����������A��������ɕ������Ȃ��������S�z�������B���肩�肢�����͎l�l���Ђ��Ђ��b���Ԃ��A�����Ƃ�܂��ɂÂ��Ă����̂ł���B
�@�������щp���N���Ă����B��l�͐Q�Ă���Ԃɂ������莖����݂̂��悤��(��������������Ȃ����炢�Ɉ�������)�A���|�ɖڂ����Ђ炢�Ă���B
�u���������N�����Ȃ��́H�v
�@�����u�����B
�u���߂��B�����āA��l�ɂ͌����Ȃ����v
�@�ƒB�Y�͓������A���l�Ɂ\�\��l�Ɍ����Ȃ����Ǝ��̂����܂ł͕|�������B
�u�����A���܂��̕����ɕ����Ԃ炳�����Ă邼�v
�@�����̊炪�݂�݂���߂�B�݂�Ȃ̊���B
�u�_�Ђɖ��߂�����H�v
�u�������v
�u���߂��̂ɖ߂��Ă����̂��H�v
�u�������v
�u�Ȃɂ�A���̏L���H�v
�@�щp������Ō����������B�B�Y�������J�������ƂŁA���̏L���͂܂��܂������Ȃ��Ă���B�����Ǝщp���ᒠ����o�Ă����B
�@�V�����B�Y�̂��ɗ���B
�u���Ȃ��ق����������v
�@�ƒB�Y�͒�ɂ������B
�u����B���Ȃ���肢���v
�@�ƐV���͌Z�ɂ������B
�@���������悵�ĉ����J�����B�Q���̖����肪�����ւƂ̂т��B�������ŋ��|�S�͂ւ����̂����A���������ւ��Ă��Ȃ������B�т���ʂ�̕��͂����ɂ���A�����قǂ����悭�������B
�@���͉J�̂����Ɍ������т��炵���A������ۂۂƓH��A��Ɍ����܂�������Ă���B
�u�ň�����v�����͌������B�u�ň�����B�����A��܂ł�������肾�B�ǂ����H�@����A�ǂ�����H�v
�@����ɂ͒B�Y����������������B�����͂��ꂩ������̕����Ő��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B
�u�������̂��ꂶ��Ȃ����v
�@�������ܖڂŒB�Y�����グ���B
�u�킩���Ă�v
�@�����͊z����ł������A����t�C��Ȑ��ł������B�u��`���Ă����B���̕��O�ɂ����Ȃ��Ɓv
�@����q���������B
�u�����@���Ȃ��ƁB�����@���Ȃ��Ǝ��Ȃ��Ȃ��v
�u����ɂ����́v�щp�������B�u�f����B�܂������Ȃ��v�ޏ��͂����������Ă���B
�@�S�����������������ɂȂ��Ă����B���̎q�����͂��łɋ����Ă����B���炦�悤�Ƃ��Ă������A���炦����Ă��Ȃ������B�V���̓V���b�N�ł݂��났�����Ȃ��B�����͏ƁA���남�낵�Ă���B�p�j�b�N�̔g���݂�Ȃ���ŁA���E�����Ȃ��Ȃ�n�߂��B
�@�B�Y�͎v�����B���������Ɍ�����O�ɂȂ�Ƃ����Ȃ��ƁB�ׂɈ������Ƃ������킯����Ȃ��B��������∫���������킯����Ȃ��B�B�Y�̂����ł��N���̂����ł��Ȃ������B�����ǁA�ނ͕|�������B�B�Y�͂����킽���̂߂�ǂ����݂�悤�������Ă�������A�݂�Ȃ�����Ȗڂɂ����Ă���͎̂����̐ӔC���Ɗ������̂��B
�u���A�������Ă����v�ނ͊��������܂����B�u���܂��A�����������Ă����B�������邩��B�V�����ƃe�B�b�V���c�c����ɂ�����������v
�@�������ƂȂ�̕����ɋ삯���B
�@�щp���A
�u���������N��������v
�@�ƌ������B���A�N������݂����Ƃ��Ȃ��B���ꂾ�����������Ă��̂ɁA�N���o���Ȃ����Ǝ��̂��s�v�c���B
�@�N���������Ƃ��Ă���͂Ȃ��Ƃ킩��ƁA�щp�̓e�B�b�V����T���ɂ������B�B�Y�ƐV���́A���Ɍ������Ȃ��悤�A�����ɎU����Ă��镨��ЂÂ��͂��߂�B
�u�킽���A�Δ����Ƃ��Ă���v����q���������B�u���A���Ă��Ă�v
�@����q���������o�Ă������Ƃ���B���͍Q�Ăđ������B
���@�@�@�@�\�l
�@��l�͐Q������y�ԂɂÂ��˂��J�����B��q�˂̊O�ɂ́A�y�Ԃɍ~��邽�߂̒i������i�������B�����ɑ������낷�ƁA�����Ƃ̍L���y�Ԃ��݂킽����B���Ԃ���͊����������d���̖����肪�����Ă���B���̂����ł́A�^���Èł��A�������Ɖ��܂łÂ��Ă���B
�@��l�͂�������|���C�Â����B�����d���̃X�C�b�`�������A���������Ƃ��������Â�����ŁA�������Ȃ������B
�u����ς肾��B����Ȃ������낤�Ǝv�����c�c�v
�@����q�͏����ŁA�u�N������c�c�H�v�Ɛu�����B
�u����Ȃ��Ɛu���Ȃ��ł�v
�@���͏����ł������������B���������N�ɐu���Ă�̂��ƁA�^���������Ȃ�B
�@�y�Ԃ͈Â��Ȃɂ������Ȃ����A�N��������Ƃ͍l���������Ȃ��B�����d�����ق����Ǝv�������A�����ɈÂ�����Ƃ炵�����Ȃ������B���邭�Ȃ����Ƃ���ɁA�N����(�܂�Ȃߑ��Y��)�������܂��Ă�����A�ǂ����悤���Ǝv�����̂��B
�@����q�͗��̎���܂��ɂ����Ă���B���ɂ��Ƃ��c�邭�炢�����B�ޏ��͂��̎�������Ȃ��炱���������B
�u���A�������v
�u�����́H�v�Ɨ��B
�u���̕��A�f��ł��ދC�H�v����q�͐u�����B�u������|����c�c�v
�@�������̏�ɔ�т��葫���Ƃ������B��l�͗������̃C�{�C�{�ɂ����������ƂȂ����B
�u�Δ��́H�v
�@����q���u�����B��l�͕��C��̂ق��������B���C��͓y�Ԃ̉���ɂ���B�Δ��͂��̉��˂��������������^�̋���ɂЂ��������Ă���B���̕����́A���傤�Ǒ䏊�̏o������̉A�ɂȂ��Ă��āA�����Ƃ��Â������B
�@��l�͂�������Ђ�����悤�ɂ��ĉ��˂ɂ����Â��Ă����B���C��͑䏊�̔����قǂ̍L�������Ȃ��B���̂Ԃ܂��Ă���B���͉���q�̘r�ɂ����݂����B���Ԃ��疾����͗����Ă��邯�ǁA�ڂ̓͂��Ȃ��ꏊ�������ς��������B�S�����ǂ��ǂ��Ɩ��Ă���B���o���s�q�ɂȂ�A�킸���ȕ����ɂ��Ƃт�����B
�@����q�͂܂��䏊�ɋ߂Â����B���݂����܂ōs���A�w����ǂɉ������Ă��B�r���������˂̂ق��ɐL���Ă������B����q�̎�͉��˂��A��x�A�O�x�ƒ@�����B�����Y�́A�q�ǂ��������Ƃ�₷���ʒu�ɁA�Δ������Ă����B����q������ɂ����Ďw�����ׂ炷�ƁA�Δ��ɂӂꂽ�B
�@����q�͂��߂������炵�Ȃ���Δ������������B�����A�ǂɔw��\������̐��ł͂��܂����ނ��Ƃ��ł��Ȃ������B����q�͂��炭���ǂ������ƕ����������ƁA���ɂނ����āA
�u�Ƃ�ɂ����v�Ɠ{�����悤�ɂ������B�u�Ƃ�Ȃ���B�����Ă��߂Ȃ�����v
�@���́A���̑̐����ᖳ������ƌ��������������A���ˑ��ɂ܂���ĂƂ�Ȃ�Ă����Ȃ��B�������A�Ƃ�����̂��|�������B
�@����q�́A���̋C���������������̂��A�u��l�ł�������ˁv�Ɛ����悤�ɂ������B���͂��Ȃ������B
�@��l�͊����Y�ɋ�����������ċz��������B�O�x���肩�����ƁA�����������C�������������B�Ǎۂ��͂Ȃ��ƁA���C�ꑤ�ɂ܂�肱�B
�u�ȂA�Ȃɂ����Ȃ���v
�@����q�����g�̌����ł������B���˂̂�����ɂ͈Â��肪�L�������ŁA���̈ł͂����Ƃ��Ă���B�Ȃɂ��������߂����������Ȃ������B
�@���������₭�B�u�͂₭����Ă��ǂ낤�v
�u�킩���Ă��v
�@����q��擪�ɉ��˂ɂ����Â��B
�@���C��ɂ͓y�Ԃ��炵������Ȃ��B�F�K���X�̈����˂����Ă����B�ޏ����������˂ɂ����Â��ƁA���̌˂��L�C�B�c�c�A�ƊJ�����B��l�͔ߖ������������āA�k�ݏオ�����B
�@�܉E�q�啗�C�͂��܂ǂ̏�ɏ���Ă���B������A���C�̓�����͍����B��l�͂ۂ�����Ƃ������A�l�p����Ԃ����߂�B
�@���ɐ�������ꂽ����@�̔������c�c���̍������ݒi�̏�ɁA�^�����Ȏ肪�̂сA�Ђ�Ђ炵���B��ɂ͔G�ꂽ������������������B����q�͌����J���Čł܂����A�ߖ��グ�悤�Ƃ����̂����A��������o�Ă��Ȃ������B�ޏ��͑����������ƍ���܂�Ȃ������������B
�@�s�����N�������̂͗��������B�ޏ��͂��₭�Δ����Ђ����ނƁA����q�̘r���Ђ��ς����B��������R���Ăē������B�y�Ԃ��Ƃ���ʂ��悤�Ƃ���ƁA���Ԃ̏�q�˂��҂����ƊJ���B�����������A�G�ꂽ���������炵�ė����Ă���B��l�͖j�����Ԃ������Ȃ�����������Ĕ�т�����A�Q���ɂ��ǂ낤�ƕǍۂ܂ʼn����������������ɂ͂����i�ɂԂ���A���̂͂����͉������̕��u�ɂ̂ڂ邽�߂̂��̂����A���̉������ł����������ƂȂɂ����삯���鉹�������Ă���A�ޏ���͖����ŕ����ɂ��������B�����Ă�����������E���Ƃ��A�ᒠ�ɂ����肱�݁A������ʂ�ʂ��悤�Ƃ���ƁA�ׂ̕�������A�^�^�^�b�A�ƂȂɂ����삯�Ă��鉹�������B
�@��l�͖����ʼnᒠ�������蔲����ƁA�����̕����ɂ��ǂ����B
�@�݂�Ȃ͂��炭���C�ɂƂ��A�����œ�l�����߂Ă����B�l�l�͌R����͂߂āA����͎q�ǂ��̎�ɂ͂Ȃ�Ƃ��ӂ荇���ŁA���͌R��̔��ƌ��̐Ԃ̑Δ�̂������A�݂�Ȃ̂��Ƃ��|�������B�ޏ��͂�����Ƒ����̂ށB����q���������Ɣ���߂��B
�u�Ȃɂ��������̂��H�v
�@�B�Y�����킲��u�����B���͐������悤�Ƃ������A���t���o�Ă��Ȃ������B�A�������ē\���������������B
�@����q�͂Ȃ�ł��Ȃ��Ɠ������B�݂�Ȃɑł���������́A���̕��������Ƃ悩�����B
�@��݂̌����܂�ɂ́A���łɐV�����ƃe�B�b�V������܂���Ă����B�ǂ�������z���āA�d�Ԃ��Ȃ��Ă���B���͉Δ��Ńe�B�b�V�����܂B�щp���S�~�܂��Ђ낰��A�����ɕ��肱��ł������B
�@����q�̓`���`���Ɖ������Ă���B�������Ă������̏����C�ɂȂ�B�����𒅂ĔG�ꂻ�ڂ��Ă�Ȃ�āA�H�쏗�̒�Ԃ݂����Ȃ���B�ł��A�ޏ��͂Ƃ߂ċC�ɂ��Ȃ��悤�ɂ����B����Ȃ̌����A���B
�@���͌ċz��[�����āA�������낰�悤�Ƃ��Ă݂����A�A�̐���߂�ꂽ�݂����ɁA���܂������Ȃ��B���̊O�ɁA�������̏��������Ă����Ȃ����Ǝv���ƁA�C���C�ł͂Ȃ��������炾�B
�@�݂�Ȃ̓e�B�b�V������܂��A�V�������Ђ낰���Ƃ��Â����B�Ȃ�ǂ��J�肩�����ƁA���̌����܂�͂������Ȃ����B���̎q�����͂��Ⴊ�݂��ނƁA�G�Ђŏ�̌��Ԃɓ��肱�����ӂ��Ƃ肾�����B
�@�������֎q�ɂ̂ڂ����B�B�Y���Ă����������B�����͔w�L�т����āA������݂��O���Ă������B���������A�����B�Y���ĂŎƂ߂�B
�@���炭���āA���̓p�W���}���������f�����A�Ђ�Ђ�ƕ����Ȃł�̂ɋC�������B�ޏ��͂����邨����U��ނ��B�A�̃|���v������܂��č쓮�����݂����ɁA�C�ǂ��܂����\�\�����A�����Ă����B�ޏ��̎����͐Q���̉ᒠ���Ƃ��肱���āA��C�ɓy�Ԃ܂łƂB
�@���ւ̌˂��A�J���Ă�c�c�B
�@�y�ԂɂÂ���q�˂́A�J���͂Ȃ����܂܂��B����q���������߂Ă͂��Ȃ��B�����ǁA���̊O�ɂ��錺�ւ̔����A���܂ł͊J���Ă����B���̉��́A�����قǂ��������Ȃ��Ă���B�y�ԂɂȂ��ꂱ�މJ���������B
�@���́A�߂Ă��������悤����Ɠf�����B
�@���ւ̌˂������Ă��Ȃ�A���Ⴀ�N���͂����ė�����c�c
�@����Ƃ��A�o�čs�����̂��H
�@�ޏ��͏o�Ă����Ă��ꂽ���������Ǝv�����B�������̏����o�Ă����Ă��ꂽ��Ȃ炢���̂ɁB
�u�˂��J���Ă��c�c�v
�@����������ƁA���̎q�����͊���グ�A�j�̎q�����͂ӂ�ނ����B�݂�Ȃ�����Ƃ����\������Ă���B
�@�N���̌������̖��悤�Ȕߖ����ꂽ�B
�u���A���܂��猺�ւ��J�����̂���v
�@�B�Y���������B���Ɖ���q�͎���ӂ����B����ǂ��납�A�Q���ɂÂ������A���J���������킩��Ȃ������̂��B
�u�����A�������傤�v
�@�����͎肪���܂݂�ɂȂ�̂����܂킸�A�����O���Ă����B�݂�Ȃ͕\�������ƌ��߂�B�܂�ŁA�Ȃɂ������Ă�����̂����Ȃ����A�������Ă���݂����ɁB
�@�����W�ߏI���A�R��������ɕ��肱�B�݂�Ȃ͖����Ō݂������������B
�u�����O�ɏo���Ȃ��Ɓc�c�v�������������B
�u�����c�c�v
�@�ƒB�Y���������B�O���狿�����̉��́A�l�̔ߖ̂悤���B
�@�݂�Ȃ͋삯���œy�ԂɌ��������B�B�Y�����ݒi�ɑ������낷�A�₽����C������@�����B���ւ͑�J���ɂ����Ă���B
�@�B�Y�͑f���̂܂ܓy�Ԃɂ����ƁA����̉��ɂ������������B
�@�����Ƃ̒�ɂ́A�����ۂ��O�����ЂƂ���B���̖����肪���Ă���B�݂�Ȃ̖ڂɁA�J�ɔG�ꂽ�����������B���͉���q�Ǝ��������킵���B��l�Ƃ����ւ̔��͊J���Ă��Ȃ������B
�u���Ⴀ�N���J�����̂�v����q���u�����B
�u���_�R������Ă����Ǝv�����H�v
�@�B�Y���ӂ�ނ��������������B���͂�����ƐO�����B����q�͂��炦����Ȃ��Ȃ��Č����ނ����B�����̎�͌��܂݂�ŁA�V�����Ō����ʂ����Ă���B
�u�킩��˂���A����Ȃ��Ɓv
�@�����͐V�����𓊂����B���ō����Ȃ������̌ł܂肪�A���Ԃ��痎������̂Ȃ����A���낱��Ɠ]�������B
�u�m���߂邩�H�v�B�Y���u�����B
�u�Ȃɂ���v
�@����q����߂����������B�ł��A�B�Y���Ȃɂ��m���߂����̂��͂킩���Ă�B�_�Ђɂ��߂������A�����܂Ŏ����Ă����z�̐��̂��B�ň��Ȃ̂́A�݂�Ȃ����łɓ����������Ă��邱�Ƃ������B���_�R�ɒ��Ă��������������Ă����̂́A���_�R�ɂ��������Ɍ��܂��Ă�B
�u�����ɂ���Ɍ��܂��Ă��v�V�����������B�u�ɂ�����������������B���̂��肩�肢�����͂Ȃ��āv
�@�ނ͂��̏u�ԂȂߑ��Y�ɂ��܂ꂽ���̂��Ƃ��v���o�����̂��B�V���͉�������Ă�������A���̊��o�͂�肢�������Ȃ܂߂������h�����B
�u�����A�����͂������Ƃ��Ă�B����ŁA�ڂ������l���A�ꂳ��v
�u�҂Ă�B���͂������ǁA�L��������Ȃ�����H�v
�u�ł��A�킽���������v������v�����������B�u����Ȃӂ��ɍl����̂₾���ǂ��B�����v������B���タ���͂ǂ��v�����H�v
�u�v���������Ȃ�������B�����A���_�R������Ă����́H�@�Ȃ�̂��߂ɁH�v
�u�ڂ�������߂܂��邽�߂��v�ƐV������]�I�Ȑ��Ō����B
�u�������B����Ȃ͂��Ȃ��v�B�Y���������B�u�V���A���܂��̂����Ă�̂́A�搶�̘b���̂܂�܁c�c�v
�@���̂Ƃ��A��̈Èł�������E�ւƉA���������B
�@�V���͌������B�u�������₾��B����Ȃ̂ɑ�����܂ꂽ��A���䂵����A�|�����݂���A�������肾��v
�@�݂�Ȃ͕\�����Ă���B�J�����A���ւ̕����B
�@�B�Y���ӂ�ނ����B
�u���A��������c�c�v
�u���������āA�ǂ����̂�B�B�Y�����������́B�����ЂƂ�łɖ߂��Ă����肳�A���܂݂�ɂȂ��Ă��肳�A����Ȃ��Ƃ̐����������Ă̂��H�v����q�̐��̓q�X�e���[���N�������Ƃ��݂����ɑ傫���Ȃ����B�u����ł��̌������������ɂ͌����Ȃ���������Ȃ���I�v
�@�݂�Ȃ͉���q�̓{���ɂ������Ȃ����B���ɂ͂��̏u�Ԃ̉���q���A�{�����Ƃ��̓o���q�Ɍ������B����Ȃ��Ƃ����ɂ�������A����q�ɂ͂Ԃ���������邾�낤���ǁB����q�͑��l�ɖ\�͂��ӂ邤�̂��ɒ[�ɂ��킪���Ă�����B��������̂��ƁA����q�͂�������Ƃ��Ȃ���āA���̎���ɂ��肩�������B
�@���͒B�Y�Ɍ������Ă������B
�u�����������A���C���Ƃ��ŏ��̂��������݂��̂�B�G��ĂāA�������Ă��v
�@���������Ɖ���q���A
�u������Ďщp��������ł���B�M��������c�c�v
�@�ƌ������B���̂������̂��ƂȂ�݂�Ȓm���Ă����B�_�ۓ쏬�w�Z�ł́A�ʐ����𐅗͔��d�ł����Ȃ�����A���̉��k�͂Ȃ��Γ`���̂悤�ɂȂ��Ă���B
�u�����ł���c�c�v
�@�щp���u���ƁA���Ɖ���q�͎���ӂ��Ĕے肷��B
�@�B�Y�͂��₭���ɂ�����B�����悭�߂悤�Ƃ����̂����A���̂Ƃ����ւ̌���������肪�L�тāA���̉��������Ɖ��������B�B�Y�́A�������ł��Ƃ��������B�݂�Ȃɂ͌��܂݂�̎w�������������B
�@���炭�ꓯ�͖����������B
�@�����́A�����ւp�{���Ė߂��Ă����A�Ǝv�����B���ʂƂȂߑ��Y�̎q���ɂ����B
�@�w�́A�����Ђ��Ђ��ƒ@���A���Y�����Ƃ����B
�@�B�Y�������ƁA�w�͎~�܂����B
�u�����Ȃ�����������v
�@�����k�����ł������B
�@�w���܂������͂��߂��B���w���ꓯ�̓��ɂЂт��āA�C�����������ɂȂ�B
�@�B�Y�͊����Ɩڂ����킹���B��l�͊����Y�̂��������t���v���������B�������Ȃ��̂�������邮�炢�̋C����������Α��v�A�Ƃ������t���B�����Y�̂��������Ƃ͍������Ȃ��B�����ǁA�H�����������Ȃ����Ƃ����ƁA�����̓m�[�������B�̂͂ނ�ł��A���_�̗͂łȂ�A�����Ȃ����B
�@�����͂Ȃߑ��Y�ɐ��Ԃ�������A���̂��Ƃ�̂Ŋw��Œm���Ă����B����ɑ���͎q�ǂ����B�����Ȃ��Ƃ���l�̃����X�^�[����Ȃ��B
�@�B�Y���g���Ђ邪�����A�t�@�C���v���[�݂����Ȃ��Ȃ₩�ȓ����ŁA�ق������Ƃ����B�������y�ԂɂƂт���A�ǂ̉����d�����Ƃ����B
�u�������������v
�@�B�Y���k���鐺�ŋ��B
�@����q�������y�ԂɂƂт��肽�A�щp���B�V���͖��������A����ł��݂�Ȃ̌�ɂÂ����B
�@�B�Y��ⴂ�U�肩�Ԃ�ƁA�����Ŏ��ł��������B�j�̎q������������B�B�Y�͖ڂ��^�����A�v�킸���߂��ƌ�肻���ɂȂ����B�j�̎q�͌��܂݂�ǂ��낶��Ȃ��B�ق�Ƃɕ����Ă���B���܂��ɓ{���Ă����B�����ނ��o���āA�Y���т��グ���B�B�Y�͈�ԑO�ɂ�������A���̚��ɂ���������������B�ނ͂Ђ�B
�@�����������d���̃X�C�b�`������A�����X�^�[�̊�����ŏƂ炵���B�����͊���������āA�ߖ��グ��B�ނ����ɂ��ǂ�ƁA���ƕ����������Ƃт���B�y�ԂƃK���X�ɂׂ����Ɠ\����B�����͗x��Ȃ����ɂł��A�݂�Ȃ̎��ɁA�G�ꂽ�y�ރr�`���r�`���Ƃ������������B�j�̎q�̑̂́A�͂���邩�H���邩�����悤�ŁA���̍��͂ނ��������B
�@�݂�Ȃ̐S�ɂ������������B
�@�ނ�͒B�Y��擪�ɁA�O�ւƓ��݂������B
�@�O�ł͕��ƉJ�������Ă���B�����t������݂����Ă���B�{�����������A�q�ǂ������́A�J�ɔG���̂����܂킸�A�����������B
�@�����̌��͒j�̎q�̉e�����������`���Ȃ������B
�@�����͓d�����ӂ�܂킷�B����̂Ȃ����J�͔��������ė����Ă���B�g�C���������B���������������B�d���̌��̓T�[�`���C�g�̂悤�ɐ���A�Ō�ɔ��ƒ�̂������ɂ���A�ǂł������Ă��݂����Ȉ���Ƃ炵���B�����͂����Ɛ����グ���B
�@�Ȃߑ��Y�͈�̂Ă���ɂ����B���o���L���ɂ������p���ō��肱��ł���B���������т���т���ɔG��Ă���B�㔼�g�Ƀp�W���}�𒅂āB���̃p�W���}�̂����܂���́A�D�w�̂悤�ɂӂ��ꂠ�����������̂����B
�@���̎q�����́A�ߖ������Ċ����ɕ��������B�B�Y�����������Ƃ߂Ăӂ�ނ��ƁA
�u�ĂԂȂ�v
�@�Ȃߑ��Y���A�Ђъ��ꂽ�A�]�������܂��悤�Ȑ��𓊂��������B�ނ͉��̂悤�ɂ��Ⴊ��ł���A�����������߂��B
�u�������͌ĂȂ��ł����B�����͌������B���܂���͍D�����B����̂��̂�����v
�u���A���܂��̎q���͂�������v
�@�������d�����ނ����B�Ȃߑ��Y������������炵���B������ׂ������낤���B
�u���͂����Ȃ��v�ƌ������B�u���̂��ƁA�N�ɂ������ȁv
�@�ނ̐オ�n�ʂɂƂǂ��قǂɐL�т��B�B�Y��ⴂŒ@�����Ƃ������A���̑O�ɂȂߑ��Y�̃p���`����������B�r�������A�S���l�`�݂����ɐL�тĂ����̂��B�B�Y�͖_�݂����ɂԂ��|�ꂽ�B
�@�K�[�[���ׂ��Ƃ͂���A�����������ɂȂ�B
�@�����̎�͏k�܂�A���̂ɂ����܂����B
�@�������͒B�Y�������ɂ�����B�Ȃߑ��Y���E����ӂ����B�S���{�[���������Ă����B���̋����ɁB�ޏ��͂�����L���b�`�����B
�@���͊z�ɓ\��������������킯�Ȃ���A������グ��B�J�Ɨ܂̂����ŁA�Ȃߑ��Y�̎p�͂䂪��Ō������B
�u���l�ɂ����ȁB�e�ɂ��F�����ɂ��B���܂������͖߂��Ă�������v
�u�����v����q�͋������B�u����ȂƂ��A���ǂ�Ȃ�����v
�@�Ȃߑ��Y�͉_�����ނ悤�ɗ��r���グ���B
�u��������Ǝv���Ȃ�I�@���ꂳ�܂͂��ł����܂�������Ă邼�I�@���܂�������āA���܂�������Ȃ炸�A����ǂ��Ă��I�@�ÈłɂЂ����肱��ł��I�v
�@�Ȃߑ��Y�͗��r��Y�X�����V�ɐL���B�q�ǂ������͗͂��\�\���܂��肳�܂̗͂Ȃ̂��A�ǂ��������̂���C�����A�Q�������̂��������B�����ł͂Ȃ��A�ׂ̏ꏊ�ɖ����������������Ȃ����B
�u��C�ɂȂ�I�@���т��Ă��܂��I�@�������̂ŐS���݂����I�@���������܂����ƐM�����߁I�v
�@�Ȃߑ��Y�̎L�т��A�낭���݂����ɒn�ʂɍ~�肽�B�Ȃߑ��Y�͋��тȂ���A��l��l�̊�ɂ����Â��A�_��𔗂����B
�@���ƕ��������̏L���ő����ł��Ȃ��B
�u����Ȃ��v���ɐV���͌������B�u�����܂���B���܂��v
�@�Ȃߑ��Y�͎���ӂ�A�����̗Y���т��������B�u�K�[�K�[�K�[�K�K�[�v������D�ƍC���Ƃт������B���̐��͂������ɂ͕������Ȃ��A���͎v�����A���������Ȃ������݂����ɁB�����玩���̐��ŏ������Ăڂ��Ƃ����B�܂ƕ@���ɂ܂݂ꂽ����A�Ƃɂނ����B
�u�ĂȂ����낤�v�r�����܂ꂽ�B�u�ĂȂ����B�{�[���ɂ����Đ���v
�u����Ȗ��ĂȂ��c�c�v
�@���͓������B�Ȃߑ��Y�͑O�r�̍����������肢���Ԃ�B�O������Œɂ݂����炦��B
�u��߂��A�������Ƃ����v�B�Y�͌������B�u�N�ɂ�����Ȃ��v
�@�Ȃߑ��Y�͉��F���ڋʂłɂ���Ə����B���Y�����ނ��������B
�u���S���S�v�Ȃߑ��Y�͎�Ǝ�����ǂ��Ă����B�u�����Ƃ����ǁA������͂Ȃ������v�ނ͏����B�u�������Ȃ����B�Ђǂ��ڂɂ����͖̂����B�Ђǂ��ڂɂ��킹�邨�ꂪ���������v
�@�Ȃߑ��Y�͙�X������B���̐��͎��ł͂Ȃ��A���傭�����ɂЂт��A���W���̗ڂ��J���������B
�@�V���͓�����ʼn��������A�Ă���Ă��܂�Ȃ��悤����ł͂��B
�@���̂����ɑς�����Ȃ��Ȃ�A�V���͉Ƃɂ������B����q�Ǝщp���Â����B�����x�ꂽ�͔̂ޏ����r�j�[���{�[�����܂������Ă�������ŁA�Ȃߑ��Y�̓{�[���ɐ����Ăƌ���������A����Ȃ��̂������Ă���̂͌���I�ɂ܂����ȁA�Ǝv�����̂������B�ޏ��̓{�[�����̂Ă��B�B�Y�Ɗ������A���e���痘�̘r���Ђ��ς����B
�@�����ӂ�ނ��ƁA�Ȃߑ��Y�͈�̏�łƂ�ڂ�������������B�ڂ���Ƃ����������āA�ނ̑̂͋ɋz�����܂ꂽ�B�łɂ̂܂ꂽ�݂������ƁA���͎v�����B