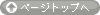「ねじまげ世界の冒険」へようこそ
ねじまげシリーズ第一弾です。
三十七歳の絵本作家、高村利菜は幻覚や不眠症といった症状になやまされていた。どうやら、小学五年生の夏に原因があるらしい。故郷の神保町では殺人事件が多発して……。
世界の崩壊がふたたびはじまるなか、六人仲間たちは再び結集し、勇気と信頼を寄せ集める。世界のねじまげに立ち向かうには、互いを信じる心を、力とすることだ! 本格冒険SF小説!
ねじまげ世界の冒険
▼第一部 おまもりさま
○ 章前 二〇二〇年 梅雨
□ 一
また、あの夢だ。
彼女は布団の重みを感じ、かっと目を見開いた。
暗闇のなかで、目をしばたく。汗をびっしょりかいている。悪夢のために体はこわばり、息をつめてさえいたが、そこが自宅の寝室だとわかると、やっと呼吸をつくことができた。
やせこけて、おもやつれがしている。暗闇で、目がランランと光っている。うすいピンクのパジャマを着ているが、その明るい色合いは、彼女の深刻な心境をかんがみるに、なんともふつりあいな感じがした。布団のなかで曲がったひざを伸ばすと、こわばった背筋がきしんで痛かった。眉をひそめながら、目がさめるたびに浮かぶあの言葉を、いまいましい思いでうけとめる。
世界はねじ曲げられている……という言葉。
「またあの夢か……」
泣きたい気分で一人ごちると、額に手をやり、大粒の汗をぬぐった。辺りは暗く、部屋はしんとしている。時計の音が、ほとほと鳴るばかりで、あとは夫の寝息がするだけだ。
彼女は37才の主婦で、名前は高村利菜と言った。高村秀男とは結婚して十二年がたち、小五の娘をもうけている。昨年絵本を出版したこといがいは、ごくふつうの主婦だと思っていた。
不眠症、不眠症という言葉がうかぶ。昨晩は何時にねむったのかと、焦燥にかられる。さいごに時計の針を確認したときは、夜中の二時だった。いまは三時半である。その間、熟睡の感覚はいちどもなかった。睡眠時間がへりはじめたのは、昨年の十二月――いまでは一時間もねむればいい方だ。
体を起こそうとすると、関節がきしんで痛かった。オーバーヒート寸前のエンジンみたいだ。不眠症と悪夢が始まって五ヶ月がたち、自分が限界に来ていることを知った。ベッドのうえで身をよじらし、夫をおこさないよう注意をして布団をどかす。鏡をみると頬のこけた女がいて、その女の光るひとみが見え、泣いていたんだな、と彼女はおもって、鼻をすすり、夫に背をむける。泣くほど怖がっていたのに、夢の内容はさっぱり思いだせない。
床に足をおろし、つめたい板間の感触に吐息をつく。動悸がおさまるのをまつ。ゆっくりと立ち上がるが、体がふらついた。彼女はすっくと身をたてると、胃袋の中身がさかのぼるのをこらえる。時計とにらめっこをするうちに、吐き気はとおざかった。部屋を歩くと、足下もしっかりした。
彼女は額と腰に手をあてるおなじみのポーズで、なじみの不眠症問題にとりくんだ。
はじめのうちは、体をつかっていないのが原因かと思った。ジョギングもしたし、水泳もやった。つまらない本を読んだり、コーヒーをことわったり、蜂蜜をたべたり、呼吸をふかくしてみたり、あらゆる努力をおこなったが、効果はなかった。自立訓練法をこころみたこともある。ヨガもやってみた。かかりつけの医者に相談もしたが、無駄だった。だいいち睡眠とは、努力をするようなことなのだろうか? 眠るのは、自然なことではないのか?
眠いときに眠るのは天国だと思う。要求と行為が合致する。眠れる健常人は、神経の問題だと彼女にいうが、それならば彼女はこのところずっとトゲトゲしていた。朝がきても疲れがぬけないのだから当然だし、じわじわとだが自分が鈍くなっていくのがわかる。精神をみたしているのは、不安と強迫観念だ。
頭が回らない、気が利かなくなる、注意力は散漫で、神経過敏になっている。娘に手をあげたこともある。それにたいし、反省もしている。
彼女は右のこめかみをもみながら――実のところ頭痛もしていたのである――部屋を歩き回った。
「こんなことをしたってどうせ名案なんか浮かばないわよ!」
壁を殴りつけたくなる。疲れをとるために眠るのに、眠るために疲れはてるとはどういうことだ?
とほうにくれた。不眠症がすべてを鈍らせている。判断力も、思考力も、記憶力も、生きる気力も削りとっている。いまでは感情をおさえることも難しかった。人にくらべれば寛大な方だったのに、神経過敏でヒステリーの兆候がつねにある。
口答えをしたからなに、とつぶやく。あの子の顔をはりとばしたのに、正当な理由はなかった。やつ当たりをしたのである。
いまでは鉢植えにさえ腹がたつ。体調はつねにくずれて貧血気味だし、それに幻覚をよく見るのである。声をきくし、誰もいないのに人の気配をかんじたりする。脳腫瘍でもあるんだろうか?
医者には、ストレスをためないこと、などと言われたが、そのことにもまたぞろ腹がたってきた。
「ストレスがたまってなにが悪いの? ストレスをためるな? 助言をどうも、役に立つわよ。ついでにストレスをためない方法も教えろってんだ。眠れないからストレスがたまるんだ! 人の百倍高給とるくせに、旦那とおなじことしか言えないのか。不眠症はたいしたことじゃない? 夜中に死にたいぐらいイラつくのがたいしたことじゃない? たいしたことじゃないんなら、いますぐ治せ!」
「利菜?」
声をかけられ、利菜は自分が一人ごとをつぶやいていたことに気がついた(つぶやくというより怒鳴っていたが)。彼女はばつの悪い気持ちでふりむいた。秀男がベッドのうえで、体を起こしていた。
秀男とは、講文社の職場で知りあった。利菜は大学の頃から原稿の持ちこみをしており、そのまま出版社に就職をしたのである。秀男は三つ年上で、彼女の上司だった。気のつよい彼女は、仕事のうえでは何度もぶつかりあったが、一年後には結婚し、その一年後には子どもが生まれたので仕事をやめた。
その後、秀男は編集長になり、雑誌をいくつも抱えている。利菜に絵本の仕事をもちかけたのも、この秀男である。
「眠れないのか?」
秀男はベッドの上から体をのばしナイトテーブルの明かりをつけた。部屋がすこし明るくなった。
彼女は鼻で笑いとばし、「おもしろい質問するじゃない。眠ってるように見えるんなら、そういって」
「また八つ当たりか」
秀男はグラスを手にとった。錠剤入りの瓶をもう片方の腕にもち、今年いくどめかになる質問をくりかえした。
「薬は飲んでるか?」
「飲んでない……」彼女は爪をかみはじめ、秀男はその手元をみている。
「飲んだほうがいい」
彼はペットボトルを手にとり、ミネラルウォーターをコップについだ。薬瓶のふたをまわすと、錠剤を手に落とした。ベッドを降り、近づいてきた。
「欲しくない……」涙声で言う。
「そんなに苦いのか?」秀男は鼻を錠剤にちかづける。「においは悪くないぞ。飲め」
利菜は強情に腕をくんだ。「いやよ」
「飲めよ」
秀男がなおも手をつきだしてくると、彼女は薬をうばいとった。
「いらないわよ!」
と壁に叩きつける。錠剤の一粒は、粉々になり床に落ちた。ほかの粒は周囲に散った。
彼女はあとじさった。
「欲しくない……欲しくないのよ……飲んでも効かないんだもん」
「はじめは効いたじゃないか」
秀男のおちつきぶりに、利菜はまた腹をたてた。
「それは最初だけよ!」怒りでふるえながら秀男をにらむ。「それはね、たしかに眠れたわよ。でもあのときだってすぐに目が覚めたのよ。あんたには言わなかったけど……」
「そうなのか?」
「そうよ。まぬけ面しないで。すぐに眠れたけど、すぐに目が覚めたのよ。もう薬なんて飲まないわ。眠れなくたってけっこうよ」
「そうやってやけをおこすのはやめろよ」秀男はがまんづよく腰に手をあてた。「眠らなくて平気なのか? まいってるのはわかるだろう?」
「当然よ。あたしがいつもどおりに見えるの? あんたこんな女に惚れたわけ?」彼女は両腕を広げて、首を左右に振りたてる。「まいってなにが悪いわけ? ろくに眠れなくてごめんなさいね」
「その早口と身振りは変わってないぞ」彼は彼女のまねをした。「オーバーアクション」
「あんたも、あたしを怒らすのはあいかわらずね」利菜は腕をくんだ。秀男が肩をすくめた。彼女の物真似をまだやめない。「あんたはいっしょに働いてるころからいっつもそうよ。あたしがいらついてるのが見えない?」
「感情は見えないし、おまえは怒ると頭がまわる」
「いまはあんたにキレてんのよ」と吐き捨てる。「八つ当たりだけどね」
「それも変わってない」秀男はふくみ笑いをもらす。
「そうね。絵本を書き出してまたぞろ上司と部下にもどったわけだし。礼でもいおうか?」
「ごほびに薬を飲めよ」
「いやよ」
「効くかもしれないだろう」
彼女は本気で腹をたて、きつくいった。「薬を飲むともっと自分がだめになるのよ。にぶくなんの。わかったっ?」
秀男は彼女の語気に口ごもった。ふざけるのをやめて本腰になったが、方途がなかった。利菜はもともと不眠症になるような性格をしていない。絵本の仕事が終わって、燃え尽き症候群でも出たのか、ライターズブロックかと思ったが、そんなありきたりなもののせいにするには、彼女の症状はおもかった。毎日小一時間と眠れていないし、日頃の挙動もおかしいのである。認めたくはなかったが、精神的な病に見えた。
不眠症がここまできた以上、薬を試してみるのは良策だと思えたが、当の妻兼部下が拒否している。秀男は腕をくんだまま弱りはてた。
「どうしてやったらいいんだ。眠れない理由がわからないし……ストレスが……」
「ストレスのせいじゃないっていってるでしょ!」
利菜の大声が、切り裂くように部屋をみたした。秀男は表情を硬くした。
「おい、大声をだすな。純子が起きるだろう」
二人はだまった。ややあって、彼女は言った。
「起きたからなんなの。あの子はいつでも眠れるじゃない」
秀男は傷ついた表情をみせたが、顔はふせなかった。
「そんなふうにいうなよ。そこはおまえらしくないね」
利菜はだまって唇をかむ。不眠症がすすむと、ばかな言葉が出るもんだ。
秀男はだまってポケットに手をつっこんだ。今度はちいさく肩をすくめた。「仕事はすすんでるか?」ときいた。秀男は、利菜の気晴らしになるかと思い、ライターの仕事をいくつか持ちかけていた。
「ぜんぜん。あんたが編集長じゃなきゃ、とっくにお払い箱かもね」
「心配ないよ」秀男は言った。「おまえは才能あるから」
利菜は鼻でわらったが、べつに嫌みな笑いではなかった。
「あたしをのせんのも、あいかわらず上手よね」
「ああ」秀男は一瞬とまどうように顔をふせたが、まっすぐにみつめ、「おまえが不眠症でも幻覚をみても。夜中におきておれにあたっても、関係はかわらないよ。いまでも惚れてるからな」
と秀男は言った。彼の目はつよく、おかげで彼女は彼の言葉を信じた。ときどき率直なことをいって喜ばすのもかわらないな、と彼女は思った。このところ、二人の関係はうまくいっていなかったが、彼女だっていまでも彼が好きだった。
秀男は、「おれもストレスが原因とは思ってない。おまえここんとこ、ほんとにおかしいもんな」
率直なご意見どうも、と利菜は思った。
二人は思い思いの行動をとった。利菜はポケットに手をつっこむと、ぷらぷらと歩きまわり、秀男はおなじ場所で、踵を浮かせてはおろすのをくりかえし、腕を組んで考えている。
秀男はやがてぽつりと、「実家に戻るか?」
利菜は立ち止まり、険のある表情をみせた。「なによそれ」
「純子も春休みだろう。寛ちゃんとこでも泊まって、のんびりしてきたらどうだ?」
「女二人追い出して、浮気相手でもつれこむ気?」と意地のわるい笑顔をみせた。
「浮気相手はいない」秀男はにやけた。「もてるけど」
二人は互いにうつむいて、にやりと笑った。
彼らはまた部屋をぶらつきはじめた。ときおり互いに目をやった。
「あんたなに考えてんの?」
「明日の仕事のこと」
「また雑誌をたちあげるんだって?」とあきれたように言う。
「そう」秀男は思いついたようにつけたす。「ああ、心配すんなよな。おまえの助けはいらないから」
「そんなこといって。仕事がつまったら原稿をまわすじゃない。いつもいつもいっつも」
「腕が落ちてなきゃ、こんども回してやる」
「もちろん落ちてるわよ……」
落ちこんだ声でいうと、秀男がそっと近づく。「できることがあったら、なんでもするよ」と彼女を抱きよせる。
「不眠症は治せないけど?」
秀男はすこし体を離して、彼女の額にキスをした。
「不眠症は治せないし、文も書けない。絵もだめだし。だから原稿はおまえに任す」
「頼りにしてるわよ、編集長」
「おれもおまえを頼りにしてる」と彼は言った。「わかるよなあ。お互いさまだってことぐらい」
「もちろん」と彼女は言う。「あたしだってあんたを頼りにしてる」
秀男は利菜の髪をなでおろす。利菜はほっと吐息をつく。秀ちゃんはまだ私が好きだな、とのんびり思った。いいかげん愛想をつかされるかと思っていた。このところ、八つ当たりばかりしていたからだ。でも、八つ当たりをするところは秀男にだってある。秀男のいうとおり、確かにお互いさまで、まだ互いが必要だった。
「こんな女と離婚したら?」と心にもないことをいった。
「よせよ」と彼が言う。「おれにほれてるくせに」
「ほれてるのはあんたの方でしょ」利菜は秀男の肩をそっと噛む。「一目ぼれだったくせに」
「さきに告白したのはそっちだ」
「最初のデートでせまってきたの誰?」
「それはおれじゃない」と秀男は笑った。「別の相手」
秀男は彼女の背をなではじめた。二人はいつもの言い合いをつづけた。そのうち、彼は体をぴたりとくっつけ、軽く体をゆすりだした。
彼女の右手をとった。
「なにしてんの?」
とさもゆかいげに声をたてた。
「おどってる」
二人はわりと長い間踊った。やがて二人でベッドについた。行為を終えたあと、利菜は秀男のとなりで天井をみつめた。
不安は消えてはいなかったが、いまは安心感も生まれている。彼は彼女と手をつないでる。互いを信じる気持ちは消えていない。二人が仕事上の上司と部下でしかなかったとき、秀男はよくこういった。「問題が見つかってよかった」そういって、肩をすくめてみせるのである。「なおせばもっとよくなる」
彼女は眠れなかったが、起きる前より前向きだった。ただ、彼女はこうも思った。悪夢や幻覚の遠因は、このなぜとは知らない不安感にあるのだと。彼女は不安だ。医者のいうストレスなど関係なかった。強い不安を感じていた。
強迫観念が、空気のように彼女をとりまいている。それでも利菜は、秀男のことを思い、一人娘を思い、あきらめないことを決めた。不眠症だって、いつかは解決するにちがいない。
ところが、彼女の心中には、あの言葉が浮かんでもいた……世界はねじ曲がっている――という言葉。
彼女は言った。
「世界はねじ曲がってなんかないよ。曲がってんのはあたしの性根の方」
結局彼女は彼女の夫を信じ、彼女自身を信じたのである。問題をかかえるのもお互いさまだが、いままで前向きに解決してきたのだ。だめだったことはあるが、だめにしたことは一度もない。
利菜はとなりで眠る秀男に、そっとつぶやいた。
「不眠症にはいちばん効果があるわよ」
□ 二
事態がうごきはじめたのは、数日後のことだった。その日は前日からの雨がつづいた。家には彼女だけがいた。夫は仕事にいき、娘は学校だった。午前十時すぎ、クロネコヤマトの宅配が、彼女に荷物をとどけてきた。
高村利菜の郷里は千葉県多賀郡の神保町だが、いまは東京の一戸建てに暮らしている。荷物をおくってきたのは、その郷里にすむ竹村佳代子で、利菜とは幼稚園のころからつづく幼なじみの親友である。佳代子は、これも小学校からの腐れ縁だった寛太と結婚し、十九年がたった今では、二人で自然農園をやっている。
利菜は中学の卒業とともに、県外の女子校にかよいはじめ、大学も就職も東京だった。神保町とはずっと疎遠だったのだが、佳代子と数人の仲間とだけは、ずっと交友がつづいている。
利菜は段ボールを居間まではこんだ。佳代子がホームセンターからもらってきた段ボールには、薄く土がついていた。いつものように野菜を送ってきたらしい。箱をひらくと、新聞紙でくるまれた野菜がある。
佳代子が野菜をとどけてくるのは毎月のことで宅配などめずらしくなかったが、今回は新聞の上に封筒がある。茶色の便箋がのっていた。
佳代子が手紙を? と彼女はいぶかしんだ。用があるのなら電話をかけてくればいいと思った。佳代子は筆まめな方ではなかったからだ。
そういえば……と彼女は気がつく。この数ヶ月は電話のやりとりすらしていない。以前は三日とあけずに連絡をとりあっていたのに? 彼女がかけなかったのではなく、向こうからもかかってはこなかった。
封筒をうらがえした。これといって署名はない。胸騒ぎがした。封筒を机に置きなおす。佳代子にもなにかあったのではないかという直観がした。不眠症では半年もなやんでいたのに、佳代子に相談する気にならなかったこと自体が不思議だ。友だちは大勢いるが、かくべつ思い入れのある親友といえば、佳代子をおいてほかにない。出版された絵本をまずみせたのは佳代子だし、結婚の報告をまっさきにしたのも佳代子だった。だれにも打ち明けられない悩みも、佳代子になら相談できた。ともに初潮を経験した友人とは、そういうものではないのか? 幼なじみといえば自然とはずかしいところも知ってしまうものだし、なんといっても佳代子は利菜に関するいろんな秘密をにぎっていたのである。
彼女は表にめんしたガラス戸に目をむけた。そのとき、六人の子どもたちが小雨のなかに立っているようにみえたが、気のせいだったようだ。彼女はおおきく息をついて、封筒に視線をもどした。
不眠症がはじまったのが昨年の十二月……三月のなかばからは、夢遊病がはじまった。ロフトに隠れていたこともあるし、庭に出ていたこともある。二日前は風呂場にかくれていた。目を覚ますと、バスタブにうずくまっていた。シャワーからは小雨のように水が落ち、彼女はずぶぬれになって、泣きながら膝をかかえていた。部屋は真っ暗闇だったが、突如として明かりがついた。自分がどこにいるかを悟った。バスタブのカーテンはしまっていたが、そこに人影がうつっていた。
「誰……」
と彼女はつぶやいた。夫のはずはない。輪郭でそれをさっした。立ち上がって、カーテンを開けた。
そこにはずぶ濡れの女が、着物とながい髪をたらして立っていた。彼女は溺死女だとおもい、悲鳴をあげ尻もちをついた。激痛に顔をしかめそれでも急いで顔をあげたが、そこではカーテンがかすかに揺れているだけでなにもいなかった。だれも。
彼女はシャワーを止めた。ずぶ濡れの体をみおろした。いつもの幻覚にしてはできすぎだな、と暗い笑みをもらし、服を着替え、台所の椅子にすわり、なにがおこったのかを考えた。包丁をもち、なにごとかを考えながら、ほうれんそうを切った。みそしるをつくり、目玉焼きをつくり、食卓にならべていると、家族が起きてきた。たまたま早く起きたのよ、と説明した。たまたま不眠症になったし、たまたま幻覚を見るようになったのよ、と考えた。二日前のことである。
彼女自身は、そうした幻覚などの症状には、すべてなにかしらの遠因があるのだと考えていた。無作為におこっているのではなく、ある一定のまとまりがあったからだ。無意識のうちに行動しているときは、なにかから逃げようとしていることが多かったし、例の悪夢も、おなじ内容をくりかえし見ているようだった。
佳代子の文面はつぎのようなものだった。
『まいど。ゲンキでやってるか? おひさしぶりです、竹村佳代子でございます。梅雨もちかごろ盛りがついて、こっちじゃあざんざんぶりがつづいてる。ここんとこあんたともご無沙汰だったんで、手紙を書こうかとおもう。こっちじゃあ近所の小学生を十人ばかりひきうけて、農園をてつだってもらった。収穫があったんであんたにおくる。そっちはどう? あんたは元気か?』
佳代子は簡単にご無沙汰だったと書いているが、彼女たちはメールのやりとりすらしていない。不眠症がはじまってからは、ふっつりと連絡がとだえていたのではないかと思って、彼女は眉をしかめた。半年もご無沙汰がつづけば、身のうえを心配しだしてもおかしくはない。
佳代子の手紙はこうつづいた。
『さいきん電話もしてなかったけど、あんたのことは気にはしてる。あんただってあたしのことを気にかけてくれているとは思うけど』
「ほんというと、あんたのことはかけらも思い出さなかったよ……」
利菜は茶をいれた。手が震えていたので、彼女はますます落ちこんだ。体の病気ならまだ対処のしようがあるよ、と彼女はおもって、熱い玄米茶をひとくち飲んだ。
『最近こっちは物騒でね、ちっぽけな町のくせに犯罪はよくあるし、子どもが連れ去られる事件が頻発して、うちの坊主も集団下校なんてやってる。東京より不安全なぐらいよ。こんな田舎で、割にあわないと思わない? うちの農園も、ちょっかいを出されてまいってる。警察にとどけたりはしてないけどね。いやがらせをされる覚えはないんだけどね……。できのいいスイカはぜんぶ踏みつぶされてるし、温室のビニールをひっぺがされたこともある。そんなわけで、あんたには聴いてほしい愚痴がいっぱいあるのよ。電話をしたかったけど、それだとうまくつたえられるか自信がない。根暗な話になりそうだしね……』
「だからなにがあったのよ」
手紙に話しかけながら、無意識のうちにポットをなでた。猫がいればいいのだが、二ヶ月前に家出をして、それきり戻ってきていない。
一枚目の紙をめくったとき、彼女が目にしたのは、不眠症という文字だった。
『こういう子どもじみたいたずらもたまらないけれど、一番まいってるのは眠れないことなのよ。去年の暮れあたりから寝つきが悪くなってるのに気づいたけど、それがよくならないまま今もつづいてる。いまじゃあ一時間とねむれない。悪い夢ばかりみるし。あんたにだけは打ち明けるけど、幻覚までみるようになった』
佳代子の文字は急速になぐり書きになり、読むのも難しいぐらいの字面がつづいた。利菜は、苦労しながらも必死によんだ。夢中になってペンをはしらす姿が、容易に想像できた。理不尽だが、おなじ悩みをもつ人間をみつけて、どっと安心したのである。
『寛太のやつもおなじだった。別に夜の営みに精を出してるわけじゃないんだけど。眠れないし、幻覚をみてるらしい。つまり夫婦そろって不眠症にかかったというわけ。あたしたちはそのうち好転するものと思いこみ、たがいにその話しをしなかったけど、症状はだんだん重くなってくるし、黙っているなんて不可能だった。二ヶ月前、あたしたちは悩みをうち明け合った』
「それはうらやましい限りね」
といらだちをにじませる。彼女はおなじ症状で苦しむ相手がそばにいない。
秀男も不眠症にかかればいいのに。
佳代子はほんとうに思いつくままに、ひとり思索にふけりながら筆をはしらせたらしい。手紙はだんだんと自己独白めいてくる。
『あたしたちは話すうちに、子どものころ似たような体験があったことをおもいだした。たしか小学四年か五年のころだ。あたしたちは不眠症にかかり、集団で幻覚をみるようになった。子どものころそんなことがあったなんて、思い出しても信じることができなかった。不眠症が伝染するなんてあたしはきいたことがないし、そんな強烈な体験を、うっかり忘れたりするものだろうか?
寛太とあたしは、新ちゃんと達郎ちゃんにもこのことを話した。すると、二人も不眠症で悩んでいることがわかった』
新治と達郎というのは、郷里にすむ尾上兄弟だ。いまも交友がつづく幼なじみたちである。
『症状が出はじめたのはみんなおなじ時期で、悪夢をみるという点でも、共通している。あたしたちはあの夏、おなじような経験をした仲間のことをおもいだした。あたしたち四人をのぞけば、後はあんたと紗英がいる。ふたりも不眠症にかかっているんじゃないだろうか? あたしたちはよくよく話しあったが、あの夏に関するあたしたちの記憶は、ほとんど抜け落ちていた。あたしにはあんたが覚えているかどうか確証がない。だけど、あんたは、あたしたちとちがう体験をしている。四人であつまって話をするうちに、新ちゃんが、とつぜん思いだしたように立ち上がってわめいた。稲光にあったみたいな顔だった。あの夏に、利菜が両神山で遭難した、と。あんたは二十五年前、あの山でひとり遭難した。ちょうどみんなで幻覚をみていた時期だった。二十年以上も忘れていたけれど、でもあたしは思い出すことができた、あたしたちは。あんたはどうなの?』
「おぼえてないわよ!」
利菜は手紙をなげ捨てた。しかしおぼえていたのである。佳代子の手紙は彼女の記憶も呼びもどした。朝礼台にのぼる、自分の姿がうかんでくる。
あれは無事かえったことを、みんなに知らせる集会だと彼女はさとり、佳代子たちと自転車を走らす姿や、あの子たちと笑いあう姿を思い出す。あのころ――佳代子、紗英、新治、達郎、寛太の五人はいちばんの親友だった。いまにいたっても交友がつづくほど、親密な友だちだった。だけど、二十五年前に自分たちが抱えたなやみのことは、すっかり忘れていたのである。
大人になって、昔のことを話しあうのは、幼なじみの特権だ。しかし、これまでに不眠症の話が出たことはいちどもなかった。遭難のことも。幻覚を見たことも。
彼女はふたたび外に目をやった。すると、二十五年前の子どもたちが、ずぶ濡れの庭に立っていた。六人の子どもたちが、雨に濡れながら。
彼女は手紙をとり落とした。
「あんたたち、あんたたちも苦しんでたんだ……」
と彼女は言った。彼女はこわごわしながら、ちらばった手紙をかきあつめる。外では雨が吹きしぶいている。しまい忘れたタオルが、風になびいている。子どもたちは一様に暗い表情をして彼女をみつめる。あの子たちが寄ってきはしないかと、彼女は不安になる。
二十五年前の佳代子が、子ども時代の自分のとなりに立っていた。おさげを編んで、そばかすを散らした顔の佳代子。二十五年もたつのに、ここにいる佳代子はあのころとおなじ格好をしている。デニムのつなぎを着て、両手をポケットに突っこんでいる。なんでも入れられるから、でかいポケットのついたのが好きで、寛太を殴るのが趣味だった。おなじ県営マンションに住んでいた佳代子。兄弟が多くていつもめんどうを押しつけられるんだと、腹立ちまぎれに愚痴をこぼした佳代子が、どんよりと濁った目をして立っている。
あのころ、県営マンションにはあと二人の親友がいて、それが達郎と新治の兄弟だった。達郎はひとつ年上で、リトルリーグのヒーローだった。高校のとき肩をこわして職人の道にすすんだが、当時はプロを嘱望された逸材でもあった。そこにいる一同のなかでは、いちばん背が高い。ほお骨がぐりぐりと突きでて、佳代子にはホームベースとあだ名された。
達郎のとなりに立つ、ちっちゃなネズミ男が新治である。二人の兄弟はおなじTシャツを着ている。本が好きで、利菜が絵本を書くことを、いちばんに喜んだのが新治だった。のび太がかけるみたいな、まん丸めがねに水滴がつき、彼の目玉はみえなくなっている(あの奥には目玉なんてないんだと思って利菜はぞっとする)。
列のはじっこで、すねたように口をとがらせている丸坊主の小僧が寛太だ。小学生当時の寛太は、じいさんにいつも丸刈りにされて、それで坊主頭だったのである。彼の顔をながれる雨の筋は、子どもたちのなかでもいちばん多く太い。喧嘩っぱやくて、神保小では問題児あつかい。いまではりっぱに仕事をこなして、トライヤルウィークの生徒のうけいれだってやっている。
反対端にいるのは、紗英だ。中学に入学すると同時に、急速に背をのばし、男の子たちにからかわれた背いたかのっぽの紗英も、このころは利菜たちと頭をならべている。肩までの髪からしずくが垂れている。黒いフリルのついたお上品なワンピースを着てる。彼女たちがママゴンとよんだ母親が、いつもそんな服をきせるのである。
「あんたもなの?」
と彼女は言った。このなかで町をはなれているのは、自分と紗英だけだった。紗英はいまではスチューワデスになり、世界中を飛びまわっている。結局ママゴンは、この子に足かせをつけるなんてできなかったのだ。線のほそかった紗英も、人一倍の粘りをみせ、文字どおりにあの町を巣立っていったのである。
新治と達郎は、いまでは二人で木工房ひら開いている。木にかんするものならなんでもつくってしまう、手作り工場をたちあげたのだ。利菜がデザインを手伝うこともある。二人とも絵の趣味を知っていたし、彼女の腕をかってもいた。
だけど、そこにいる子どもたちにとっては、まだとおい未来の話だった。あのころは大人になるなんて夢にも思わなかった。小学校生活のおしまいなんて、まだまだ考えられなかった。
一同のまんなかにいるのが、利菜だった。小学五年生の彼女は、ながく髪を伸ばしている。やせっぽちの脚にジーンズがぺったりとはりつく。まつげをとおして雨が目にはいるのか、まぶたをしばたたいている。
「あんたたちみんな……」と彼女は言葉をうしなう。「でも……なんでよ、なんでわたしたちはそんな目にあったの? どうやって解決したのよ」
気がつくと、彼女はいつにない行動に出ていた、幻覚に話しかけ、あまつさえ幻覚に近づこうとしたのである。あれは幻覚じゃないと、なぜとはしらない確信をもった。いままで見てきたものも、全部幻覚などではなかったのだ。
あの子たちの足は、ぬかるみにめりこんでいる、影まであった。溺死女は髪を落としていった。自分のものだとごまかしたが、ちがう。彼女の髪はストレートなのにあの髪はちぢれていた。旦那がほかの女でもいれたんでしょ、と、笑ってごまかそうとしたのだが、そんなはずはなかったのだ。
戸口のすぐそばまできて、きゅうに恐ろしくなり、利菜はサッシをあけるかわりに、カーテンをしめた。ガラスに背をくっつけた。心臓がはげしく鳴った。佳代子は記憶がないと言った。記憶がぬけおちている、と、書いていた。利菜もまた、遭難の日々と、その後の記憶がない。思いだせないのではなく、その部分の記憶が、すっぽりとぬけおちている感じだった。佳代子たちはなにかを思いだした様子だが、彼女にはもどってこないのだ……。
そのとき、背中で声がした。ガラスに子どもの利菜が口をつけ、そっとささやいてくる。「両神山にもどるのよ……」
「帰りなさいよ。あんたはあたしじゃない、あたしの友だちなんかじゃない。あんたたちみんな……」
みんな? みんな、何だというのだ? 幻覚なのか?
彼女にはとても幻覚だとは思えなかった。だから、「偽物じゃない……」とそれだけを言った。ひどく正確な表現におもえた。
鼻をすすりながら机にもどった。手紙をおいて、気がおちつくのを待った。秀男がもどってくれば、そんなばかなと一笑にふしてくれるにちがいない。幻覚に話しかけるなんて、ばかだなといってくれるにちがいないと彼女は思ったのだが、読みかけの手紙はまだ目の前にあり、記憶はたしかに戻ってきていた。利菜は紗英の心配もした。不眠症と幻覚があのころの仲間に起こっているのなら、あの子もおなじ体験をしていて不思議はない。
利菜は佳代子の手紙に目をやり、「まいった。頭がいかれたのがあたしだけじゃないなんて」と額をかかえた。「頼りのあんたまでいかれてるとはね」
佳代子の手紙を、読まずにたたんで物思いにふけった。そういえば、あのころはみんなが問題をかかえていた。佳代子には片親しかなくて、なのにその母親は娘も知らない男の子どもを産んだ。だから、当時は佳代子も白い目で見られていた。
佳代子の母親は、情緒不安定なところがあった。機嫌がよいときはいいが、かっとなると娘に暴力をふるうのである。佳代子はいつも妹や弟をかばっていた。だから、母親の暴力はもっとも佳代子にむけられた。頬を腫らしたり、体に傷をつくっていることがよくあった。そんなときは利菜も佳代子の母親に、憎しみをおぼえたものである。彼女は考える。あの子はどうなんだろうか? あの子も母親を憎んでいたんだろうか?
ガラス戸を、ドン! とはたかれた。子どもの声で佳代子が叫んだ。「もちろん憎んでたわよ! あいつが嫌いだったんだ! 殺えなさいよしてやろうと思ってたんだ!」
「消! 佳代子はそんなこと思いやしないわ! あんたは佳代子じゃない!」
利菜は、そちらを見もせずに言ったのだが、「ひどいよ……」と佳代子の傷ついた声がきこえたときは、さすがに表に目をむけた。カーテンには人影すら映っていなかった。
佳代子だけではない、新治と達郎の兄弟だって大問題だった。佳代子も利菜も、当時は自分たちよりあの兄弟に関心をもっていた。他人の問題に目をむけることで、自分たちの問題から、顔をそむけていたのかもしれないが。
尾上兄弟が、小学二年と三年だったころ、二人の両親が離婚した。母親が子どもたちをひきとったのだが、その二年後には再婚してしまった。あたらしい父親はとてもいい人だったのだが、達郎は大きくなっていたせいか、まるでなつこうとしなかった。ボロアパートに住む本物の父親を、しょっちゅう訪ねていた。泊まることもあるみたいよ、と、当時からゴシップ好きだった佳代子が話してくれたこともある。
一方で新治はあたらしい父親になつくようになった。家族がうまくいくよう、新治なりに心をくばっていたようで、そのせいか彼は他人の顔色をひどく気にする子どもになっていた。兄弟はいまでこそ同じ仕事についているが、あのころはうまくいっていなかったのだ。話もせず顔をあわせることもなく、互いにさけているようだった。別にどっちになつこうがかまわないと思うのだが、二人は子どもだったから、お互いにどう接していいかわからなかったようだ。その後、どうやったか知らないが、あの兄弟なりに折り合いをつけたわけだ。
紗英はカナダからの帰国子女だったが、やはり両親がうまくいっていなかった。カナダにいたころは仲良くやっていたそうだが、工場が倒産し、家族が日本に戻ってからは、父親は家に寄りつかなくなっていった。あの子の母親は、娘にすべての関心をそそぐようになった。そうしないと、娘も離れていくというかのように。紗英を規則と塾でしばりづけにし、友だちにすら口を出した。暴力こそふるわなかったが、ヒステリーで、言葉で紗英を傷つけた。
両親が離婚したのは、寛太のところも同じである。寛太は鷹揚で男っぽいところのあるやつだったが、なにかの拍子にひどくひねくれた面を見せることがあった。学校で喧嘩をしては、じいちゃんが呼び出されていた。利菜たちが彼の家に泊まりに行くようになってからは乱暴も少しはおさまったが、あいかわらずのじいちゃん子で、母親にあまりかまっていないようだった。子どもが母親にかまうとは、おかしな言い方だが。
「あんたはどうなのよ……」
子どもの利菜の声が、すぐ近くでした。
「そうね、わたしも問題はあった……」
彼女は悲しい気持ちでおもう。子どもの頃はひどい貧乏で、あの町ですむ最底辺のぼろアパートで暮らしていた。県営マンションにうつる前のことだ。中野区の克美荘というところにいた。父親はあまり働かず、職を転々とした。母親はいつも苦労していた。妊娠もしていた。
彼女はいまでもあのアパートを思いだす。割れたガラスをテープでとめた窓、きしむ床、暗い階段、そこに住む零細な、人、人、人。トイレは共同で風呂はなく、洗濯機は表にあり二階建てで、瓦屋根で、廊下は窓にせっしていて明るいがすきま風に底冷えがした。春よりも冬の木枯らしが似合い、日中の日差しよりも夜の暗がりが似合う。貧乏な学生が騒ぎ、おばさんたちは母親をいじめた。
「片桐さん……片桐さんにいじめられてた」
片桐さんには、髪をきってもらった思い出がある。彼女が三つの時である。ざんばらの髪にされたのか、虎刈りにされたのか(まさかそこまでひどくないだろう)、いまとなっては思い出せない。けれど、母親が頭を撫でながら、泣いていたのを覚えている。学生たちが怒ったが、片桐には文句すらいえなかった。あのアパートでは、主のような存在だった。片桐の亭主はいい人ではあったが、嫁には文句もいえずに小さくなっていた。母親はあそこで流産をした。
そのうち父親が県営マンションのくじを引き当て、暮らし向きは好転した。父親は仕事についた。二人はいまも問題を抱えながら、あの県営マンションに暮らしている。
だけど、あの年に佳代子の母親が子どもを産んだ。利菜の母親が信子という名前をつけた。生まれるはずだった、子どものために考えていた名前だった。そのせいか、夫婦の仲はふたたび冷めはじめた。利菜はまた克美荘にもどるのではないかと、恐々としたものである。
彼女はまた思いだした。あの頃、母親は新興宗教にはまっていたのだ。なんという名の宗教だったか?
当時、彼女たちはそれぞれの問題をかかえ、そのために結束をつよくした。だれか問題を抱えた仲間をそばにおくことで、安心していたのかもしれない。あの子たちだけは本当の仲間だったが、集団で不眠症や幻覚にかかるなど、いまの彼女には考えられなかった。手紙に目をおとし、佳代子が両神山と不眠症をむすびつけたように書いているのを不思議に思った。
手紙をひらく。ごくりと唾をのみながら、つづきを読みはじめる。
『当時の事件をおぼえていたのは寛太だった。あたしたちは、少しずつ記憶をとりもどしていった。あたしたちはまわりの状況も、二十五年前とにかよっていることに気がついた。あのころも、神保町とまわりの町では、犯罪が多発していた。行方不明や、傷害事件がかなりあったし、それに両神山では殺人事件があった。あんたが遭難したときは、殺人犯にさらわれたと噂がたったほどだ。あの山で死体が発見されたのは、遭難の直前だったんじゃないかと、慎ちゃんはいっていたけど。
ねえ、あたしたちこの話題を二十年以上も口にしなかった。子どものころのことは会えばかならず口にするのに、このことは話題にすらのぼらなかった。だって思い出すことすらなかったんだから!
寛太が遭難事件を思い出したのは、今回もあの山で殺人事件が起こったからだった。亡くなったのは六十代の男性で、林の中で絞殺されていた。テレビでもちらっとやったし、新聞にもちいさく載った。狭い町でのことだから自然に知ってはいたのに、あたしたちは四人であつまるまで、あのころのことを思い出すことができなかった。
それで、あの日、寛太のやつが言いだしたのだ。両神山に、いまから行こうと』
手紙をもつ手がふるえた。彼女は指のふるえにすら気づかなかった。佳代子たちは両神山に出かけたのだ。
子どもの頃は、あの山にたびたびピクニックに出かけた。中腹には草原があり、そこへ家族ぐるみで出かけた。草原にはアスレチックがあり、確か山道にはハイキングコースもあった。
吐息をみだし、額の汗をぬぐう。
さきほどカーテンをひいたので、部屋はうす暗くなっている。立ちあがって電気をつけると、部屋の戸口に誰かがいて彼女は悲鳴をあげたが、つぎの瞬間には人影はきえて、彼女はいま見えたのは、野球帽をかぶった子どもの水死体だったのかと、推測をめぐらすばかりだった。
すわりなおした彼女が目にしたものは、畳の上にできた水たまりだった。
佳代子はあの夏に殺人事件が頻発したと書いてる……この幻覚もあの夏と関係があるのではないか。水死体を見たことがあるんだろうか?
利菜は呼吸をととのえた。冷や汗がひくと、また手紙に目をおとし、佳代子の打ち明け話にもどっていった。
『両神山には二十年間出かけてない。あんたの事件があってからは、いちども。子どもを行かせたこともない。あの山のことはずっと忘れてたのよ……。
両神山につくと草原はすっかりさま変わりして、ロッジがいくつも建ちならんで、いつの間にかキャンプ場になっていた。信じられる? ロッジはかなりでかく、小中学の林間学校のチラシが貼られている。記憶にあった場所とずいぶんちがうんでめんくらった。小川だけが、昔とおなじとこを流れてた。流れに沿って石がそえられていたし、アスレチックも新しくなっていた。駐車場の脇には、でっかい管理施設も建っていた。子どものころはジュースも買えないって不満をもらしたものだけど、いまでは販売機もあるし、ジュースどころかビールもたばこも買える。食堂もできてたわ。
平日のせいか管理所はしまっていて、話を聞くことはできなかった。あたしたちは草原をみてまわった。子どものころはだだっぴろく感じたけど、大人になってきてみると、狭くなった感じだ(本当は杉を切り倒して、丘を広げてしまったらしい)。
新ちゃんはこういったわ。キャンプ場のパンフレットは前に見たことがあるって。だけど、両神山のことだとは気づかなかったし、行こうとも思わなかった。彼、アスレチックには興味あるじゃない? 達兄とくんで、神保小の校庭に寄付もしたよね。だから、見にいきもしなかったのは、不思議だっていっていた。あたしたちはロッジの間をぬけて斜面をのぼった。あたしはおまもりさまの蔓壁がなくなってるのに気がついた』
「おまもりさま……」
彼女は肘をついて両手で顔をおおった。草原の上にある杉林いったいを、地元の人はおまもりさまと呼んでいた。
林と草原の境界には網がはられていた。そこに低木と杉の木から垂れた蔓草が何重にもからみつき、ぶあついカーテンのように、林の縁をおおっていた。彼女たちは見たままの印象から、「蔓壁」と名づけたのである。
大人は子どもたちがおまもりさまに近づくのをいやがった。蔓壁は子どもたちを林から遠ざけるのに、格好の役目をはたしていた。あそこにちかづくと、大人たちが大あわてで飛んできた。休日に人があふれかえるようになっても、林の縁にござを広げる人はいなかったし、林を切り倒して草原をひろげようなどという、環境破壊団体もいなかった。奥には沼地があるという話だったし、まむしも出たからである。蔓草を刈りこもうとしないのは不思議だったが、子ども目にも、うす気味がわるかったのを覚えてる。
佳代子はおまもりさまのことをひとしきりつづっていた。
『子どものころは草原がかっこうの遊び場だったけど、大人になって来てみると、あたしたちは怖くてしかたなかった。山にいるのはあたしたちだけだった。草原は静かだった。鳥の声がいやによく聞こえた。蔓壁がなくなったせいか、あたしにはおまもりさまが口をあけて待ちかまえているクジラにみえた。あんたには馬鹿代子と笑いとばしてほしい。だれが蔓を切ったのか聞いてみたかったけど、てぢかには人がいなかった。管理所にも人をおいてない。閉鎖されたわけでもあるまいに……。
あたしたちは林にはいってみるか話あったけど、無人のロッジはなんとも不気味で、尻こみをするままに帰ってしまった。
不眠症とあの山が関係あるのか、あたしにはなんともいえない。だけど、二十五年前のあんたの遭難と集団幻覚は、ときをおなじくして起こってる。
寛太はあんたがあの事件のことは覚えてないんじゃないかといってる。手紙を書くのも反対してた。あんたまで不眠症にかかってるなんて、ばかげた話だと寛太は言った。あの人らしくはないけれど、そんなふうには考えたくもない様子だった。だけど、いままで音信不通だったこと自体、あたしにとっては不安だった。
あんたの身になにも起こっていないのならいい。だけど、もしあんたの身にあたしたちとおなじことが起こっているんなら気をつけてほしい。あんたの身におこってるのはたんなる不眠症ではないし、幻覚にもよくよく注意すること!
どうにもならなくなったら電話しておいで。あたしたちはあんたの味方だし、なにが起こっているか理解もできる。もしかしたら、あたしの方があんたを必要としているのかもしれないけど。
まわりがたとえ頼りにできなくとも、あたしだけは頼りにしてほしい。以上』
読みおわると、最初のページを上にした。彼女は手紙をにらみつけながら、これは容易ならないなと考えた。佳代子は長々と書いているが、なんのことはない、これは警告の文面なのである。
あんたはなにを思い出したの? と利菜は佳代子に問いかけた。事件のことを思いだすために山にいったはずなのに、手紙は核心にはふれないままに終わっている。なにも思いださなかったとは考えられない。佳代子は手紙の文面をこんなかたちで終えていたからである。
『最後にひとつだけ。ひまわりは咲いてなかったわ』
ひまわり? 草原にひまわりなんて咲いていただろうか?
手紙を読みかえしながら、彼女はこうつぶやいた。
「あの山でなにがあったのよ」
佳代子の心配のほどが理解できた。電話をかけてこなかったのは、慎重に慎重を重ねたかったからだろう。そうでなければ手紙をよこすはずはない。
利菜はこう考えた。佳代子のやつ、あたしも山に行くなんて言いだすのを怖がったんじゃないだろうか?
利菜は殺人事件のことをたしかめるために、置きためた新聞をとりにいきたかったが、なかなか。腰をあげるには勇気が言った。手紙を読むあいだも、見られている気配を、ずっと感じていたからだ。
表にはぜったいに顔をむけないと決めていたが、居間の畳には、子どもたちの人型が、長く影をおとしていた。
電話が必要になるのはまもなくらしい。
そうして、娘がもどってくるのを心待ちにしながら、彼女はたちあがろうともせず、佳代子の手紙を何度も何度も読みかえしていった。
そこに、隠されたメッセージがあるというかのように。
今夜は、ますます、眠れそうになかった。
◆ 第一章 両神山にて
○ 一九九五年 八月十三日〜
□ 三
すべてのはじまりは、一九九五年、八月十四日に帰着する。
この時点で、すでに二人の子どもが殺されていた。一人は斉藤秀幸という、神保北小学校の生徒で、もう一人はさくら幼稚園にかよう、小野田美由紀という五歳の女の子である。
殺人事件いがいにも行方不明が二件あり(家出人の届け出をくわえると、もうすこし多くなる)、自殺が四件あった。外にでれば葬式に行きあたったし、町中をはしるパトカーが、いつだって目をひいたころでもある。神保警察の人員はふだんの三倍にふくれあがったが、今年にはいって起こった殺人事件のうち、四件までは解決できていなかった。
六件の殺人は、ここ十年、神保町でおこった殺人事件の総計よりもおおく、また事件はこれで終わったわけではなかった。表面化されなかった事件もふくめて、神保町はだれにも気づかないうちに、東日本でもっとも事件の集中する犯罪スポットになりつつあった。
□ 四
その夏、彼女たちは、寛太の家で寝泊まりすることが多かった。そこでは寛太郎というふうがわりな老人が、趣味で農園をやっていた。寛太郎は周囲の畑をすべて買いとり、米や野菜をつくっている。
その日、利菜は縁下にすわって、スイカの種を庭にとばすのに忙しかった。寛太の家は庭がひろく、にわとりが放し飼いにされている。町中からは離れた場所にあり、殺人事件などうそみたいにほのぼのしている。そのとき集まっていたのは、佳代子、利菜、紗英、新治の四人だった。みんなは両神山について話し合っていた。寛太だけは、あの山に行ったことがない。
「あんた両神山にいったことがないなんて遅れてるね」
種とばしがへたな佳代子は、真下に種をはきだしながらいった。佳代子は三月生まれの遅いきで、新治のつぎに体がちいさかったが、クラスでは女子の先頭にたって、男子とやりあうたちだ。どのクラスでも、女の子というのはいくつものグループにわかれるものだが、佳代子は誰にでも好かれるほうだった。目下、幸田頼子がいちばんのライバルである。
「そんなもん、いかなくたっていいんだ」
寛太は種とばしもせず、ひまつぶしに鶏をつかまえては、物干し竿にのっけている。将来佳代子の旦那になり、このあたり一帯に自然農園をひらいてやりくりする寛太も、このときはただのいがくり坊主である。ガキ大将というより、一匹オオカミタイプの少年だったが、女子が佳代子をかつぎだしたときは、寛太がかつぎだされるのがつねだった。
利菜が縁下に寝転がりながら、
「あの山はなかなかおもしろいんだよ。でっかいスベり台もあるし。ソリスベりもできるしさ」
と言った。二十五年後には不眠症になやまされるこの娘もこのときは発症しておらず、目の下にはくまもなく、若さと長髪をもてあまし、佳代子のあとについてまわった。二人は幼稚園のころからのつきあいで、小学生ながら悩みをうちあけあい、息も合ってなかなかいいコンビである。
さいきん行ってないよね、紗英がものおしそうにいった。彼女は四年のときの転校生だ。将来スッチーになるだけあって、なかなかの美人顔で男子に人気がある。転校したてのときは、幸田頼子にねたまれいじめをうけた。そこに顔をだしたのが、なんにでも首をつっこむ杉浦佳代子で、この野次馬は二十五年後もかわらない。佳代子と利菜は、幸田頼子の向こうをはった。頼子とはもともと仲がよくなかったが、このときの大げんかで、決定的に仲たがいをしてしまった。
三人の女の子はそれ以来の親友で、紗英が塾でがんじがらめの時はやっぱり首をだし、おばさんに叱られて泣いているときは、やっぱり口をだしたりした。
紗英を寛太の家までひっぱってきたのもこの二人で、紗英が他人の家に泊まるといいだしたとき、ママゴンは火をふいて(とは佳代子の表現である)許さなかったのだが、そのときは寛太郎が、得意の弁舌で説得した。
紗英はカナダ時代は活発な娘だったが、環境の変化ですっかりおとなしい娘に変わっている。しかし、寛太郎の家にいるときだけはのびのびとしているようだ。
紗英のそばで黙りこくっているのが眼鏡ネズミの新治で、彼は両親が離婚しただけでもショックなのに、母親が今年再婚してしまい、二重にふさぎこんでいた。勉強もあまりできず、不器用で、そのうえ運動音痴でもあった。三拍子が、悪い方にそろっていたのである。先年までは達郎のあとをついて回っていたのに、その兄ともいまではうまくいかず悩める夏をすごしている。この夏は、寛太郎のひらく朗読会が、彼の楽しみである。
そして、一同のなかではなんでも言い出しっぺの佳代子が、やっぱりこのときも口火を切った。
「じゃあ、ひさびさにいこうよ。最近おもしろいことないしさ。ジャスコの屋上には入れなくなっちゃうし(屋上にはちょっとしたゲーム施設があるが、斉藤秀幸という少年の死体が見つかったのでは閉鎖もしかたがない)、行きたいなあ」
「いきたいよねえ」
「いこうよ、みんなでさあ」佳代子は流し目で、つめたい視線を寛太におくった。「寛太はばかだけど、じいちゃんには世話になってるし。つれてってやらなくもないよ」
「えらそうにいうない馬鹿代子」
「あんた、ほんとににくたらしいね」
とはいえ、寛太家のお泊まりはとてもすてきなことである。みんなは農作業に手をかすかわりに、寝泊まりをさせてもらっていたが、寛太郎がいるとなんでも遊びにはやがわりしたし、農作業自体もなかなかに味があることだった。
利菜が、暑そうにうつぶせになり、脚を縁下につきだしてぶらぶらさせた。一段下の踏み石にすわる紗英が、そのつま先をつまんで遊びだす。
「いくのは賛成だけど、日曜まで待たなきゃね。とうさんたちは夏休みないもん」と利菜。
「なんで待たなきゃいけないんだよ」と寛太。
「だって、車もないしさあ。親がついてないと遠くにいっちゃだめなんでしょ。終業式でいわれたじゃん」
と佳代子は言ったが、本当は両親がつれていってくれるか自信がなかった。今年はディズニーランドにも行けなくなった。というより、夏休みになってからというもの、みんなには出かけた記憶がとんとなかった。町にしばりつけられているような気がして、気味がわるかった。一同が両神山にいきたがったのは、そのうっぷんを晴らすためでもあったのだ。
しかし、寛太は、
「両神山ぐらい自転車でいけらあ」
みんなはしばらく話しあった。自転車でいくのなら大人はぬきだ。寛太の家に泊まるといってあるから、山にでかけてもばれる心配がない。
町でおこっている殺人事件のことを思うと、さすがにちょっと不安がったが、達郎についてきてもらうということで一決した。達郎は小学六年生で、大人ではぜんぜんないのだが、利菜たちの感覚では準大人のようなものだ。理屈ではだれも納得しない話だが、子どもは感覚でいきているから、これで親にだまっていくという罪悪感にはけりがついた。
佳代子は母親にいつもひどい目にあわされていたから、だまっていくのには賛成だった。母親をだますことに、ちょっとした快感すらおぼえた。
利菜のほうはこの夏、母親が宗教にはまりこんでいて、まだまだ家には帰りたくなかった。理解できないことを熱心に話されることぐらい苦痛なことはない。だいいち彼女はほかの子どもとおなじで、聞くより話すほうが好きだったのだ(佳代子が人気者なのは、みんなの話をよくきくからだ)。
両神山は自転車でいくにはすこし遠いが、サイクリングもたまになら悪くないな、とみんなが思った。紗英だけはこの秘密が母親にもれはしないか不安がったが(たしかにあのおばさんの目玉は、どこにでもとどきそうだとみんなは思った)、あのおばさんの心配をしていたら、指一本動かすのにも気をつかわなきゃいけなくなる。
新治はにいちゃんがいくと聞いて、暗い顔をみせた。そのころ新治と達郎の仲は最悪で、なんとなく互いをさけるようになっていた。利菜と佳代子は、二人を仲なおりさせるいい機会だと考えた。
達郎はその日野球場にいた。一同はリトルの練習場まで達郎をさそいにいった。球場にきて達郎をよびだすと彼は野球場のはじからすでに飛びぬけてでかくなった体を、ゆったりゆたりとはこんできた。
佳代子は、あたしたちだけじゃ不安だし、達さん達郎兄ちゃんよ、あんたあたしたちだけに行かせて心配じゃないわけ? でも、父さんたちにはだまっといてよね、行くの行かないのと得意の舌で説得した。達郎はしぶったが、けっきょく最後には同意した。達郎だって本心では弟と仲なおりがしたかったのである。
後年になり思いかえすと、一同が町に殺人がふきあれているこの時期に、自分たちだけで両神山に出かけることにしたこと自体が不思議なことだった。その意味では、おさそいは、山に着く前からはじまっていたのだった。
□ 五
ふざけながら自転車をおしおし、山をのぼるといがいに時間をくうもので、草原の駐車場に自転車をとめたときには、時刻は十時ちかかった。車は二台あった。親子づれがきているらしく、ちいさな子どもたちの歓声がきこえた。青葉はすでに陽にやけていたが、風がわたって涼やかだ。
草原のアスレチックは国村という老人が、ボランティアでつくりあげたものである。夏休みにしては、草原には人影がすくなかった。利菜たちは事件の影響だとかんがえた。隣町でも、同様の事件はおこっていたからである。
草原の小道をのぼった。山草が道をいろどり、ふきあげる風が、つかれた体に心地よい。吊り橋のしたにシートをひろげ、自分たちで用意したお菓子と、寛太の母親が用意した弁当をたべた。寛太はサンドイッチを口にはこんで、丘の林に目をむけた。
「ほんとにへんな蔦がはえてるな」
草原のさきは杉林が山頂までつづいている。林の縁には防獣ネットをわたして入れないようにしてあった。蔓と低木が網にからみつき、人の進入を阻止している。
蔓草のネットを利菜たちは蔓壁とよんでいる。その一帯は雑草もしげり放題だ。ネットにからみついた蔓草がじゃまをして、ここからでは林の奥はよくみえない。大人は、子どもたちが蔓壁の網をこえるのをいやがったようで、立ち入り禁止の看板をたて、草むらの周囲に杭をうちこんで、ロープを三重にわたしてあった。
「たっちゃん、あの林までいってみようぜ」と寛太。
「いくわけないじゃん。一人でいけば」
佳代子は枝を手にすると、地面にはえたオオバコを、乱暴にはらいとばした。
「今日は国村さんいないのかな」
新治が言った。国村以前に、今日の山は人出がなかった。下の溜池でブラックバスを狙う大人たちの姿もなければ、平らなところでベースボールをやっている子どもたちの姿もない。六人は親にもいわずに自分たちだけできたのは、本当はまずかったんじゃないかと思いはじめた。佳代子はそのことも気にして、
「国村さんがいたら、ぜったいとめるよ。あの林はほんとに危ないんだから。誰も手入れしてないっていってたし、まむしもいるもん」
そういえば、おまもりさまの幽霊話も、たいはんは国村から仕入れたものだった。彼は怪談の名人で、その話は細部まで真にせまっていた。
佳代子はその手の話が大嫌いだった。寛太の冒険心にふたがしたくて、大人たちからきかされた怪談のたぐいを話して聞かせた。それは子どもたちをおまもりさまから遠ざけるためのちょっとした作り話ではあったが、林の不気味さが話の裏づけに一役かっていた。子どもたちのたいはんが話を信じていなかったし、だから、おまもりさまに探検にいく男の子たちもときおりはいたのである。彼らはおっかない目にかなりあったし、怪我もした。林のなかは誰も手をつけず、荒れ地のようになっていたからだ。それに帰ってこなかった子もいた。達郎が切りだした、まよって死んだ子どもの話は、つまりほんとうに起こったことなのだ。
寛太はその手の話が大好きだった。子どもたちは国村のような雰囲気もだせず、声色もつかうことができなかった。
「そんなのいるわけねえな」と寛太は言った。「そんなお化けがいたら、こんなとこでピクニックなんかするもんか。あっほくさ、おまもりさまだって? ぜんぜん怖くないね、そんな名前」
「わたしがつけた名前じゃないよ」佳代子は枝をなげすてた。「怪談がどうこういうんじゃないよ。あの林ってほんとにあぶないもん。あたしたちだけで来てるのにさ、けがしたらどうすんの? 寛太、うちらのかあさんになんていうつもり?」(佳代子は紗英のおばさんになんていうつもりと思ったが、それは口にしなかった)
寛太は怒ったようにいった。「なにいってんだ。おまえはほんとに馬鹿だよな。おまもりさまが怖いんならそういえよ」
「怖いよ、悪い」佳代子はむきになって寛太をにらむ。「でも、お化けの話が怖いんじゃない。あの林じたいが嫌いなのよ」
利菜と紗英はうなずいた。佳代子のいうとおり、おまもりさまは不気味な林だった。みんなは、なんとなく黙りこんで、おまもりさまと呼ばれる林をみつめる。彼女たちがそんなふうにおまもりさまを特別視するのは、大人たちが本気で心配していたからだった。林にちかづくと親がとんできてつれもどしたし、なによりも大人たち自体があの林のことを気味悪がっていた。
利菜が切りだした。「はじめちゃんって知ってる? 三年生の子よ」
「知ってる。鼻水たれでしょ」佳代子は自分のおさげで鼻をこすっている。
利菜はうなずいた。「鼻水はたれてるね。でもあの子は馬鹿じゃない」と彼女は言った。「あの子たち、四月に林にはいったんだ。はじめちゃん、足首をつかまれてさ、転んだんだって。手につかまれたっていってた。ほかの子も怪我したんだ」
「モグラがほった穴にはまったんだ」寛太が言った。「どんくさいよな。おっかながるのがいけないんだ。足首をつかんだのだってさ、どうせ木の枝かなんかだよ。それがへんなもんにみえたんだ。そいつはハナタレじゃなくて、ヘタレだね――いいか、おれ、いい話し教えてやるよ。これじいちゃんに聞いた話だから、全部ほんとだ。いっとくけど、じいちゃんはヘタレじゃねえぞ」と寛太はことわった。「じいちゃん戦争でビルマにいっただろ。前線ってとこで(寛太は前線を地名だと思っている)逃げまわってたんだ。前線を下げてたんだって(この意味はいまだによくわからない)。じいちゃんは度胸があるけどさ、お化けもなんもこわがんねえもんな。おれ、子どもんとき(彼はいまでも子どもだが)幽霊屋敷でさ、こんにゃくになでられたときはさすがにびっくりしたけど、じいちゃん笑いながらこんにゃくつかんでるもんな。まいったよ。でも、そういうじいちゃんなのにさ、ビルマじゃただの木が敵にみえたっていうんだ。じいちゃんはそいつを撃とうとしたんだ」
「撃ったのかもしれないな」
達郎がおごそかにいった。
「撃ったかもな」達郎に向かって、寛太はうなずいた。「でも、ほんとに運のわるいやつらは、仲間同士で撃ちあったっていってた」
「そういうこともあるかもね」佳代子は気がなさそうだ。ちょっと泣きだしそうなぐらいにしょげている。
「うそじゃないぞ。じいちゃんの肩、鉄砲の穴があいてるだろ」
「知ってる。まだ弾が入ったままだっていってた」と利菜が言った。
「うそに決まってるよ。弾がはいってたらあんな器用に手はうごかせない」
佳代子がいうと、寛太は、
「ほんとなんだ。じいちゃんの手ときどきしびれるもんな。これ、おれがいったっていうなよ。ほんとここだけの話だ。じいちゃんはさ。ほんとは左利きだったのに、いまは右利きになってるもんな」寛太は秘密をもらすときの顔をして、「あれは味方に撃たれたんだよ」
「ひえ」新治が肩をすくめた。
「すげえな」と達郎が言った。
寛太はキラキラした目で、「じいちゃんはいろいろ体験してるんだ。味方の手榴弾がさ、ちかくで破裂してふっとばされたっていってた。これ、すごいだろ?」
佳代子は眉をしかめた。「すごいけどさ、それっておまもりさまと関係ないじゃん」
「だからさ、ビルマの山奥ってすごいジャングルなんだぞ。それにくらべたら、あんな林たいしたことないんだよな」と寛太は自分がジャングルに行ったみたいにいった。「じいちゃんはな、血まみれで三日も森んなかでうめいてたらしいんだ」
「ふっとばされたときにか?」
達郎が訊いた。
寛太はうなずいた。「手榴弾でやられたときだ」
達郎は感心した。彼はリトルでキャプテンをつとめるような少年だったから、みんなより大人びていたし、お化けの話などまったく信じていなかった(だけど、あそこに行くと漆にかぶれれるのはほんとだ)。寛太郎のことは素直にすごいと思ったのである。
「よく助かったなあ。オオカミや熊にやられたかもしれないぜ。ビルマなら虎もいたかもな」
と達郎は言った。
みんなは去年学校でみた、『ビルマの竪琴』という映画を思いだした。子どもにとってはむずかしい内容だったし、細かなことはわすれてしまったが、切々と心にひびく、いい映画であったことは覚えている。映画の登場人物と、若いころの寛太郎をかさねてみたりもした。
「そうだろ? だから、おれ、おまもりさまのお化けはほんとかって訊いたんだよな。そんな不気味なとこならさ、おまもりさまより不気味だとおれは思うんだよ。じゃあ、おまもりさまにお化けが出るぐらいなら、ビルマにはぜったいいるよなって思ったもんな」
「じいちゃん、なんていった?」利菜が訊いた。
「たぶん、うそだろうなっていったよ」
寛太は言ったが、じいちゃんの言葉にはつづきがあった。あそこには近づくんじゃないぞ、と寛太郎は言ったのだ、おかしなことが起こる場所はほんとにあるからな。でも、寛太はそのことを意図的にだまっておいた(寛太は自分でも気づかなかったが、心の中にしのびこんだ誰かが、その言葉を封じたみたいな感じがした。いままで味わったことのない奇妙な感じだったので、彼は顔をしかめてだまりこんだ)。
佳代子が、「たぶんじゃん。じいちゃん、たぶんっていったんじゃん。ぜったいなんていってない」
というと、利菜はふくれた。
「そんなのぜったいとおんなじだよ。でも寛太がいうことなんか信用できないね」
「おれはうそなんかいってない」
佳代子と寛太の間で、いった言わない戦争が勃発する。
「やめろって」達郎が口をはさんだ。「おまもりさまになんか誰もちかづかない。今日は大人がすくないからな。国村さんもいないみたいだし」
「それってほんとにあぶないことがあるみたいな言い方だよ」
利菜が言った。国村さんがいないのがいちばん不安だよ、と佳代子は思った。
国村はひょうひょうとした老人で、どこかしら寛太郎に似ていた。寛太郎にくらべると人間に重みがたりなかったが、行動的で、山を行楽地にかえることに、凡人ばなれした情熱をかたむけていた。ちいさなアスレチックは独力でつくったし、巨大なものになると、町役場までおしかけて人出をあつめてくる。怪談話を思いおこすだけでも、なかなかのアイディアマンだった。
達郎は二人を見た。「そうだよ。お化けなんかいなくたって危ないことはあるんだ。だから、おまもりさまの話はもうなしだ。いいな」
□ 六
子どもたちは、アスレチックのまわりで遊んでいた。ビニールボールをぶつけ合ったりしてふざけていたが、自分たちが、すこしずつ丘のうえを目指していることには、気づいていなかった。
当時、アスレチックからおまもりさまの林までは、二十メートルばかり空間があった。国村はその空間を草刈り機で手いれしたうえ、草場のふちに杭をうちこみ、念いりにロープをわたしていた。ロープのむこうは草むらになっている。その奥にあるのが、例の蔓壁だ(蔓壁があり、草むらがあり、杭とロープがあり、そして草刈りで手入れされた空間が、アスレチックまでつづいている)。草むらの中央には看板が立っている。書かれている文字は、このさき、立ち入るべからず――
利菜が林の杭がみんなひき抜かれていることに気がついたのは、自分たちがいつのまにか走りまわるのをやめて、蔓壁の前にならんでいたからだった。
彼女はおどろいて、となりに立つ佳代子の肩をゆすった。佳代子も驚いてまわりを見まわす、たったいま居眠りでもしていたようなそぶりだった。佳代子は紗英をゆりおこした、利菜は右どなりの達郎を、達郎は寛太を、寛太は新治をゆすりおこす。
みんなはおまもりさまの杉木立を呆然とみつめる。これほど蔓壁のちかくに来たことはなかった。蔓壁はもっとぶあついものだと思っていた。おまもりさまがのぞけるとは知らなかった。蔓と網のすきまからは、林の奥がほんのり見えた。
蔓壁との間には、うっそりとした草むらしかない。
「いつのまにのぼったんだ?」
達郎がだれにともなく訊いた。誰もこたえなかった。杭のあった場所には、ススキがながく伸びていた。草原から風が吹きあげ、そのススキをゆらしている。子どもたちは顔を見合わせた。国村がたてた看板は、ひんまがりススキのかげに隠れている。この間までは(そんなに昔じゃない)ニスをぬられて光っていたのに、いまでは朽ちはて虫食いだらけになっている。そこだけ時間がたって風化してしまったみたいだ。
見ろよ……達郎が地面をゆびさす。ススキの一角に日本手ぬぐいがひっかかっている。国村さんのだ、といって佳代子が手をのばし、利菜がとめた。
「なんでわかんのよ。だれのかなんてわかんないじゃん」
「あんなのもってんの、あの人ぐらいしかいないよ」
「そんなのわかるもんか」
佳代子にはあの手ぬぐいにふれてほしくないと思った。茶色のシミができていたからだ。血だろうか?
あんなのただの手ぬぐいだ、達郎は思った。彼はみんなを寛太郎の家まで送りとどける義務があった。この面子のリーダーだし、寛太郎には今朝、みんなをたのむぞと肩をたたかれたばかりだ。達郎はみんなに下まで降りようといおうとした。もう昼前だ。お菓子を食べに降りてもいいし、もう帰ってもいい……。
蔓のむこうから声がしたのは、そのときだった。「佳代ちゃんかい?」
「国村さんの声だ……」
佳代子は呆然と言った。
利菜は国村がおまもりさまにいるのはおかしいと思った。大人はおまもりさまに行かない。行くのは馬鹿でむこうみずな子どもだけだから。
利菜は佳代子に向かっていった。なんとなく網の向こうには声をかけられなかった。国村は姿を見せないし、声の調子もいつもとちがった。暗い、重苦しい声だった。
「うそだよ、なんでおまもりさまにいんの? 網のむこうにいんの?」
「きっとはいっていいんだよ」佳代子の目はかがやいて、頬は赤くそまっている。
「そんなのおかしいよ」
達郎が利菜の肘をとった、新治には左手を、紗英には腰を押された。みんな、いつのまにか彼女のまわりに回りこんでいた。利菜はやめてよと声をかけようとしたが、誰も自分と目をあわせないので声をつまらせる。利菜は恐ろしくなり、達郎の肩にかみついた。肉に歯が食いこむと、達郎が悲鳴をあげ、新治と紗英がぱっと離れた。
「なにしてんのよ」
佳代子がいった、利菜はいいかえした。
「そんなのこっちのせりふだよ。悪ふざけのつもりならこっぴどい目に遭わせてやる!」
紗英は泣き声をだした。「ねえ、わたしたちなにしてんの? いま、利菜のこと、おまもりさまにつれてこうとした?」
みんなはだまりこんで林を見かえした。林の奥を見ようとしたが、その光景はビデオの写りが悪いときみたいにちかちかしている。じっと見ていると、頭がおかしくなりそうだった。
みんなは殺人事件のことを思いだし、駐車場にパトカーがサイレンを鳴らしてあつまってくるのを想像した。神保町ではその年、そんな光景をよく目にしていたからみんなが連想したのも当然だが、それが未来の――それもちかい未来の光景だとはだれも気づいていなかった。
「もう帰ろう……」
新治がこわごわいって身をかえすと、急に突風が吹きつけてきた。新治は息が吸えなくなり、動きをとめる。草原には人がいなかった。アスレチックは無人だった。駐車場から大急ぎで車がでていくのが見えた。達郎が、震え声で、
「ここにいるのはおれたちだけだ」
「変な言い方やめてよ」
佳代子が小声でいいかえした。利菜も帰りたかったがそうもいかなくなる、国村がこう話かけてきたからだ。
「ちょっと助けてくれないか」
佳代子は、みんながびっくりするぐらいの速さで林に向きなおった。
「どうしたの?」もう半べそをかいている。「国村さん、おまもりさまに近づくなっていったじゃん。あたしたち下におりるよ」
「まってくれないか。助けてくれ」
利菜たちは顔を見合わせとまどった。助けてくれとは自分たちにいっているのか? 国村はいつも助ける側だ、それに助けるには林に入らなくてはならない。
「だから、なにがあったのよ」
佳代子が訊いた。
「国村さん、怪我したの?」
と利菜も訊いた。風はいよいよ子どもたちに向かって押しよせ、ススキを吹きながし、網にからまる蔓をはらいとばした。うずくまる人影が見えた。国村は座りこんでいるようだ。返事はなかったが、みんなは怪我をしたんだと思いこんだ。
「どうしたらいい?」
佳代子がいうと、みんなは年長者の達郎を見た。
「けがをしてるんなら、人を呼ばないと」達郎はひとり言のようにいうと、林にむかって怒鳴り声を上げた。「国村さん、大人が誰もいないんだよ! おれたち親と来てないから。寛太、下までおりて人を呼んできてくれないか」
「待ってよ。国村さんほんとに怪我したの? 大けがなの?」
利菜が訊くと、達郎は「わからないよ」と叫んで答えた。風がうなりを上げて、草や木立をゆさぶった。達郎が大声を出したのは、不安なのはもちろんだが、風がすごい勢いで渦を巻いていたからでもあった。
紗英が、「国村さん、歩けないのかな?」と訊くと、佳代子が手ぬぐいを指さした。「見てよ……」
手ぬぐいは、先ほどとおなじくススキにかかったままだった。ススキとともに、右に左に揺れていた。だけど、いまでは鮮血がしたたり落ちている。さっきは茶色の染みに見えたのに。利菜も佳代子も、さっきは乾いていたと思った。佳代子はさわろうとまでしたから、みまちがいとは思わなかった。だけど、二人は、血を見たショックで、深くは考えなかった。
ススキの壁をこして、国村が言った。「ここから出してくれないか」
「じゃあ、自分で出られないのね」
佳代子が訊いた。つかまっとるんだ、と国村は言った。みんながその意味を深く考えないうちに、草場からは血が流れおちてくる。
達郎は思った。うわあ、こいつはびっくりするぐらいの大けがだ。達郎は、そばの枝をすばやく拾って、ススキをばしばしと叩きはじめた。寛太も同じことをはじめた。寛太は今日はじめておまもりさまの蔓壁をみた。あのときはススキなんて生えていなかったのだが、だれかが大けがをしているときに、そんな疑問をはさむゆとりなんてあるだろうか? 二人は一心にススキを叩きつづける。達郎が首を伸ばして、ススキの中をのぞく。
「なにしてんのよ」佳代子がこわごわ訊いた。
「マムシを追っぱらってるんだ」達郎はこたえた。
利菜が、「国村さんとちがうんじゃない……」と言った。国村も年寄りだが、声の主はもっとずっと年寄りに聞こえた。声は……単に古びて聞こえた。
達郎は怖かった。だけど、どうしてもおまもりさまに近づかなくては気がすまなくなっていた。こんなの変だと心の片隅では思ったが。だけど、町で殺人犯が野放しになっているのはほんとだし、リトルのコーチたちが連続殺人の可能性について話しているのも知っていた。国村さんがそいつにやられたんじゃないかと思うと、気が気ではなかったのだ。
達郎は枝をのばしてススキをかきわけると、まむしがはいずっていないことを確かめた。振りむくと仲間の確認をまった。寛太がうなずき、新治がうなずいて眼鏡を上げた。女子たちは、手をつなぎ合っている。
寛太と達郎は、ススキ林にふみいった。血をふまないよう、おっかなびっくり。達郎が腕をのばして、枝のさきに手ぬぐいをひっかけた。手ぬぐいの先端からは血が幾筋もしたたり落ちる。傷口がそこにあるみたいに。寛太は、こいつは血の蛇口だあとおもい、達郎がふりむいた。
「やばいぞ、信じらんないぐらいの大けがだ」
辺りには生臭い血の臭いがただよっている。紗英が吐きそうな顔であえいでいる。利菜がその手をひいた。四人は達郎と寛太の後につづいた。
こんなに血がでたら、生きてるわけないよ、と利菜は思い、血をかわして足をふみおろす。国村の血液は地面に染みこまずに流れてくるが、子どもたちは誰もそのことに気づかない。
「包帯かなにかないのか」
と達郎は女の子たちに怒っていったが、そんなものをもってくるはずがない。達郎はパニックをかみ殺すみたいに唇をかんだ。なんでいまにかぎって大人がいないんだと困惑した。
「みんないなくなっちまったのか?」
国村の声がする。なんだか怒っているみたいな声だった。ここにいるわよ、と佳代子は答えた。達郎は枝ごと手ぬぐいを捨てた。
利菜は、手ぬぐいが真っ赤に染まっているのを見た。白い部分はほとんどなくなっている。まるで手ぬぐいが血を流したみたいだと思う。達郎がふりむいた。
「たんかがいる。新治、棒をみつけてこい。男はシャツをぬぐんだぞ」
「棒なんてないよ」
「はやくしてくれ」
国村の声が言った。子どもたちはさらに林に近づいた。蔓網まではまさに一歩の距離だった。利菜が、
「ねえ、なにか変じゃない」
とみんなにいった。彼女はさっきともだちに林につれこまれそうになった。そのせいだか知らないが、人一倍冷静で慎重だった。すこしいやな言い方だが、国村の身の安全より、自分の身の心配をしていたのだ。
みんなの目は、そんなのわかってるよ、といっていた。だけど、だまってツルアミを見かえしただけだ。網にも蔓にも血がついている。さっきはついてなかった、と、利菜は心中で悲鳴をあげた。
「ここはいいぞ」
国村が言う。六人は顔をみあわせる。
「なにがいいの」佳代子が訊いた。「けがをしてるんでしょ?」
国村は答えなかった。かわりに想像力が働きだす。子どもたちの頭は、おまもりさまの力が想像力をかきたてたみたいに、フル回転をしはじめる。利菜は蔓で首を吊って死んだ女の姿を頭にえがいた、彼女は女のたらす鼻水を感じ、首にくいこむ蔓の感触をまざまざと肌に感ずる。
おかしいよ、こんなのぜったいおかしい……
利菜はささやくようにつぶやき、呆然と足をみおろす――と、血が靴をとりまいていた。彼女を中心に血だまりがあった。
ちくしょう、なかに染みこんだりしたら、気をうしなうに決まってる。
佳代に手をのばし袖をひいた。佳代子は利菜がゆびさすほうを見た。
「やっぱり大人を呼んできたほうがいいよ……」
といって利菜は咳きこんだ。空気にまで血液が噴霧のようにまじってる。
利菜がつばを吐くと、血だまりに落ちた。佳代子はそれをじっと見た。
「でも、手遅れになったらどうするのよ」佳代子はふるえ声でいいかえす。「おっかないなんていってらんないよ」
国村さんじゃないかもしんないじゃんと利菜は思った。このとき考えたのは、四年のとき先生からキャンプ場できかされた怪談のことだった。こんなことを考えるなんて恥ずかしい。ともだちにばれたら、ヘタレ呼ばわりされるかもしれない。だけど、ここにいるのはみんな親友だったから、彼女はその考えを口にすることができた。
「なめ太郎っておぼえてる?」利菜は言った。「紗英ちゃんだって知ってるでしょ? 四年のときの話しだもん。いたっしょ? トイレについてきてもらったもん」
紗英もおなじ考えにたっしたようだ。
「知ってる、そいつ人の声をまねすんのよ」紗英はみんなにも聞こえないような小声でいった。国村には聞かれたくなかったのだ。「血をなめるお化けの話でしょ。男の子も聞いたっていってた」
達郎はふりむいた。「その話ならオレも知ってる。話したのは片山っちだろ」
片山っちという言い方は耳なれなかったから、年下の子たちは頭のなかで、片山先生のことだなと翻訳した。
「キャンプにつれてくときはかならずその話をするんだ。作り話だ。でたらめだよ。朝になるとかならずいうんだ。あれは作り話だって。夜中こわがらすんだ」
達郎は言ったが、みんなは不安げに顔をみあわせるばかりだ。
「いまは国村さんを助けないと、みんなばかな話しないで協力……」
達郎はだまった。達郎はみんなの方を向いていたから、林を見ていなかった。蔓のすきまから、痩せて(すごく痩せて)、薄汚れた手がでてきたことに気づかなかった。その手は指がうんと長く、爪もうんとのびている。十センチはある。その爪はまっすぐで、鋭利だ。
その手が、達郎の手首を、そっとつかんだ。
「助けならいらないよ」と、手の主は言った。
達郎が振りむくと、蔓をかきわけるようにして顔があった。髪がぼさぼさに伸びて、その髪がくっつきあっているのは、ヘアトニックのせいじゃなく垢と泥と血のせいだった。達郎は先生の話をあまり覚えていなかったが――なにせ二年前の話だ――その瞬間、記憶のなかにある映像と現実の像が一致した。
目玉は病的に黄色い。鼻からふーふー息を吸ってる。そのせいで鼻の穴がいっぱいにふくらむ。なめ太郎は目を見ひらいたまま笑う。歯は黄色く、尖ってギザギザで、血糊がいっぱい残っていた。
「うわあ……」と達郎は言った。
「よう!」
なめ太郎が手を引いたので、達郎はよろめき屈んだ。なめ太郎の顔が近くなり、そいつが舌をのばして耳をなめた。二メートルはありそうな長い舌だった。達郎はその悪臭と舌先の感触に身を凍らせる。
「うそだ、うそだ、ありえない!」
と利菜は叫んだ。脳が干上がって、神経が切れてしまいそうだ。彼女はなめ太郎をはっきり見た、あいつの顔を。なめ太郎の舌はヘビみたいに二つに割れてる。その声は、甲高いのとしわがれたのが重なったような、二重音声だ。ひゃあ、先生のいったとおりだ。佳代子はあいつが見えるのはあたしだけかな、と考えた。紗英は思考が停止して、なにも考えられなくなった(脳パンクだ、と彼女はその言葉をくりかえし考えた)。
「捕まえた」
となめ太郎は言った。新治が「兄ちゃんがつかまった」と金切り声で叫んだとき、蔓のなかからもう一本の手がのびて、彼の細い足首をつかむ。新治はススキのなかに倒れこみ、血の混じった土を跳ね上げる。彼は地面に頬をうちつけぼんやりする。眼鏡がずれ、顔にはねばねばした血が、べったりつく。
唾を垂らしながら、ぼんやりと顔をあげたとき、なめ太郎が蔓から身を乗りだした。
「捕まえたあ! 捕まえたあ! こっちに来い小僧ども!」
なめ太郎が思いきりよく腕をひくと、新治の靴がぬげ、手が足首をはなれた。なめ太郎はバランスを失い後ろに倒れかかる。達郎は手を捕まれたままだったから、なめ太郎に引かれるまま横様にころんだ。
二人は草むらに倒れこみ、血まみれになった。
「ちくしょう!」
となめ太郎が雄叫びを上げた。
寛太はあまりのことに呆然としていたが、その、ちくしょう、を聞いてしゃんとなった。彼はじいちゃんから、骨と皮だけになった人間のことはさんざん聞き出していた。その瞬間彼は、こいつはなめ太郎なんかじゃなくて、そのたぐいのこじきなんだと考えたのだ。なめ太郎が本物だったら、こんなに間抜けじゃない。
寛太はすばやく身をかがめると、石を拾おうとした。だけど、地面はススキまみれで、土も見えない。
彼は草をかきわけた。土と草の臭い以上に血の臭いは強烈で、地面は血の海と化している。彼は怖じ気づいたが、そのとき、じいちゃんに、しっかりしろ、と腰をたたかれた気がした。腹を据えろと自分に発破をかけると、えいえいとうなり声を上げながら、草をかきわけた、石があった。
そのとき、なめ太郎によくにたこじきは新治をあきらめ、達郎の腕をにぎっていた手を、両手にもちかえた。なめ太郎は細腕のくせに、すごい力だ。
「ちくしょう、こいつにひっぱられる」達郎はふんばろうとしたが、地面は血でできた汚泥にかわり、彼の足を滑らせる。
一方寛太は立ちあがって、石をぶつけようとしていた。だがなめ太郎はすごく近くにいて、あいつの顔を見ていると腕が萎えて、手元が狂いそうだった。彼はなめ太郎よりも、達郎や新治に当ててしまうことのほうが怖かった。
寛太は一歩踏み出した、また一歩、なめ太郎が彼の目玉で大きくなる。達郎を見ていたなめ太郎が、こちらを向く。寛太が拾ったのは、てのひらほどの割合大きな石で、ずっしりと重い。彼はこんな重さの石を投げたことはない。だから、近づいてよかったと思った。投げたりしたら、とてもこいつをひるませるほどの威力は出せなかったろう。
なめ太郎に睨まれたとき、彼は脳髄を一撃されるような感触をうけたが、体は無意識のうちに動きだしていた。寛太はわめき声をあげると、なめ太郎の顎に石を叩きつけた。骨と肉の砕けるぐしゃりとした鈍い感覚が、腕に伝わった。
「やった」達郎が言った。なめ太郎の手が腕から離れた。なめ太郎の顎から飛沫があがり、服にかかったが気づかなかった。
「やったぞ、寛太」
寛太は怖気をかんじたが、達郎の腕は自由になった。二人は後ろにはいずって逃げた。そして、転がっていた新治につまづきふらついた。
「わ、悪ふざけをした、おまえが悪いんだ!」
寛太が叫ぶのと、なめ太郎が腕をふるうのは同時だった。すごい勢いだったが、寛太はしゃがもうとしたし、達郎が彼の腰にくみついて転ばせたから、二人は鋭くとがった爪の餌食にならずにすんだ。二人は新治のうえに倒れこみ、達郎は弟とススキを踏みつぶす格好となった。
なめ太郎は、首のかわりに寛太の帽子をにぎりしめていた。ぐしゃぐしゃにつぶれるほどに強くつかんだ。女の子たちはそれまで息をつまらせていたが、それをきっかけに悲鳴をあげた。
「きゃああああああああああああ!」
「寛ちゃん、逃げてぇ!」
利菜がいち早く金切り声をあげた。三人は四つんばいのまま逃げようとしていて、後ろを見ていない。なめ太郎の手が寛太の首にむかってのびる。
達郎は恐怖の罵声を上げながら、立ち上がると、寛太を突き飛ばした。なめ太郎の手がまた空をかいた。
「あいつ、あいつ首をしめようとした」
佳代子が非難の叫びを上げる。
達郎がふりむくと、なめ太郎の血まみれの顔の奥で、目玉だけが憎しみの情念に燃えていた。うわあ、こいつはおれたちを憎んでる。達郎は思った。逆恨みだけど。恐怖の底になぜか喜びもあった。なめ太郎が苦しんでいるのを知ったからだ。
達郎は声をかぎりに号令する。
「みんな逃げろ!」
リトルで鍛えた彼のかけ声はすごかった。みんなは半分ばかり金縛りにかかっていたが、そのひと声でいっせいに動き出した。
なめ太郎は伸ばした腕を(なんと三メートルばかりにのびている)、新治に向けた。
利菜はおよび腰が幸いして、一同のいちばん後ろにいた。彼女は一部始終を目撃した。友だちの惨憺たるありさまに怒りがわいて、またたくまに恐怖を塗りつぶしていった。彼女は手にしたゴムボールを振りかぶると、渾身の力で投げつけた。いつもの手投げではなく、松坂みたいな腕の振りで。ピンクのボールは、風を切り裂くと一直線にすっとんでいき、滑稽にもなめ太郎は避けそこなって額に受けた。新治はなめ太郎の腕から逃れた。お腹がよじれるぐらい恐ろしかったが、彼女も夢中だった。
「ざまあみろ! おまえなんか死ねばいいんだ!」
利菜が怒鳴ると、なめ太郎は大口を開けてうなった。唾と血が重なりあい滝のように糸を引く。なめ太郎は蔓壁を引き裂きにかかった。
一同はパニックになった。達郎が寛太をひきずって蔓壁からはなれた。佳代子と紗英が新治を左右から抱えた。二人とも「誰か、誰か助けて」と助けを呼んでいる、新治は口をうごかすばかりで声もだせない。
達郎は寛太を、女の子たちは新治を抱えてススキの中から転げでた。みんなは血まみれになりながら、夢中で草原をかけおりた。
足に地がつかず誰もがころんだが、なめ太郎につかまるのではないかと思うと転びながらでも走って逃げた。利菜はなめ太郎の食事のじゃまをしたから(なめ太郎は死体の血を舐めるからだ)、きっと復讐されると思った。怒りなんて消しとんで、いまはひたすらおっかない。寛太郎がいったみたいに、おっかな虫が腹の底にはりついている。寛太はさきほどの英雄気分はどこへやら、あいつに捕まって殺されるんだとおもいこんでいたし、佳代子と紗英もなめ太郎をみたショックから、まるで立ちなおれていなかった。新治は片方の靴が脱げて靴下がむきだしだ。彼の靴下は血でずぶぬれだし、ほっぺたにも血がべっとりついてる。新治はいますぐ死にたいと思った。みんながまわりにいなけりゃ、きっとつかまっていたことだろう。達郎だけはみんなを追いたてるのに忙しく、おっかながっているひますらなかった。
ときおり、ざざざっざざざっと草をかきわけるような音がした。呼びとめられる声を聞いた気がしたし、国村の声をきいた気がした。
利菜が途中でふりむいたとき、おまもりさまからはゴムボールが帰ってきた。力まかせに投げつけられたんじゃない、友だちとキャッチボールをやるときみたいな、スローボールが帰ってきた。
だから、彼女は、無意識のうちに、そのボールをつかんでいたのだった。
□ 七
子どもたちは草原をかけおりた。自転車にとびのると、一目散に山をかけおりた(途中、ビニールボールをため池になげすてた)。
坂をくだって、ドライブインの駐車場にはいる。車は三台停まっていた。みんなは誰にも見られたくないという思いと、もっと大勢人がいればいいのにという思いで、みじめな気分をあじわった。達郎はちかくの男性に助けを求めたかったが、その感情をこらえにこらえた。自分や弟を襲ったものがなんだったのか、達郎にはわからない。あれが人間だとは、本心からは思えなかった。おまもりさまでなめ太郎に会ったなんて、そんなことをいうのはいくらなんでもまずいと思った。あれが人間で、本物の殺人犯だったのなら簡単だ。でも、そんな嘘はつけない。自分にはつけても、大人につくわけにはいかなかった。殺人犯に襲われたなんて切り出したら、とんでもない騒ぎになることはわかっていたからだ。
地図看板の前に自転車をとめると、ハンドルやサドルに血がついていた。達郎はみんなに物にさわらないよう気をつけさせた。トイレを行き来する人がいくらかあった。自販機からジュースをとっていた人が、ふと顔を上げた。
足早に店にむかうと、一行はさすがに人目をひいた。髪はざんばらで、服もみだれていたし、様子も尋常ではなかったからだ。
達郎が店にふみこむと、カウンターのおばさんが顔をあげた。ネームプレートには片桐とあった。新しくはいったパートのようで、子どもたちは誰もみおぼえがなかった。達郎はすぐさま質問攻めにあうと予想していたのだが、片桐はなにもいわない。仲間の目が自分に集中するのがわかる。頭に血がのぼったが、なんとか唾をのみこんだ。
「あの……」
達郎はみんなを見て、それから片桐に目をもどす。
「Tシャツとタオルを貸してもらえませんか?」
「タオルは売ってあるけど、Tシャツはないわよ」
「達郎ちゃん、お金がないよ」
佳代子が小声で袖をひく。片桐は彼女に目をむけた。
「タオルぐらい貸してあげるけどねえ、自転車で下りてきたの? ひどい髪になってるわよ。なんでそんな顔してんの?」片桐は一拍子おいて、「なにかあったの?」
片桐は二宮町の人間で、最近このあたりでちかんや変質者が多いことも知っている。殺人事件についても耳にしていた。その疑念は影みたいに彼女にひっそりしのびよる。彼女は身をのりだして、
「あんたたち山から下りてきたの? なにがあったの? 誰かになにかされたんじゃないでしょうね?」
達郎は面くらい、目線をさげて片桐からはずした。この人には、血がみえないんだろうか? 彼の頭はジャイロボールのように回転している。あいつのことをなんと言うかでいちばん迷った。殺人犯なのか……なめ太郎でいいんだろうか?
でも、片桐は答えをまっている。だから、
「うえで変なやつにあったんです」
と、とっさに答える。言ってから心のなかで胸をなでおろす。変なやつというのはほんとのことだし、これなら精神病院にぶちこまれることもない。
片桐はぎゃくに緊張したようだった。
「おかしな人って? 変質者かね。大人にいった? 国村さんはいなかったの?」
達郎は口をつぐんだ。国村はいたようでいなかったからだ。片桐は、最近あの人は見かけないからね、とひとりごちた。
片桐は表に目をはしらせながら、「タオルはなんにつかうの?」
「だって、みんな血まみれですよ」
達郎はリトルでしつけられてるだけあって、受け答えもしっかりしていた。片桐はおかしそうに笑っただけだった。
「おおげさなこと言って。どれ、手をみせてごらん」
片桐がレジに寄りかかり身をのりだした。新治が手をつきだした。彼の右手には、倒れこんだときにできた擦り傷がいくらかあった。草場の血も、手のひらにべったりついたままだった。拭きようがなかったし、さわりたくもなかったのだ。だけど、片桐は厚く塗ったどうらんのような血も気にならないようで、新治の手首をやさしくつかんだ。
「転んだんだね。おかしな人ってどんなやつ? 怒ってるんじゃないよ。あんたたちにおかしな真似をしたんなら、警察にもいわなきゃいけないからね。さいきん町で悪いやつがうろちょろしてるのは知ってるよね。まだ捕まってないんだから……神保町じゃ殺人事件もおこってるんだよ。どうなの? おばさん警察をよぼうと思うんだけど……というのはここにも警察がきて、怪しいやつがいたら通報してくれって言われてるからだけど。といっても、いままでそんな奴はいなかったけどね。警察をよぶほど大事だとおもう? いたずらだったら、あんたたちを叱らなきゃいけないけどね……そんなふうには見えないし」
と新治の手にくいこんだ小石を、爪で器用にはぎおとす。
利菜は達郎の真後ろにいたから、彼のひろい背中がよくみえた。血が乾きかけている。白いシャツの半分方が真っ赤になっているのに、片桐はそのことに触れなかった。落ち着きはらっていた。外にいた大人も。興味はしめしたが、駆け寄ってきたりはしなかったのだ。子どもが血まみれになってるのに……心配して当然なのに?
新治の傷はふかくはなかったが、泥がついていたし、消毒はしといたほうがいいな、と片桐はつぶやいた。
「ちょっとまってなさいよ」と片桐は言った。「ふみちゃん、ちょっとレジについてよ」奥に呼びかけ、「消毒ぐらいはした方がいいからね。おかしな人って男の人?」
片桐は新治よりも、おかしな人のほうに興味があるようだ(それは達郎もおなじだった)。若い女の人が、エプロンをしめながら奥から来、片桐が変わって姿をけした。利菜はその女のネームプレートを読んだ。
赤川文絵はエプロンをしめながら、片桐とおなじことを訊いた。
「みんなひどいかっこうね。大急ぎでおりてきたの?」
利菜の疑惑は、確信にかわる。彼女は達郎をドアのちかくまでつれていき、ささやいた。「見えてないよ」
「なんだって?」
「見えてないよ、血は見えてない」
「そんなばかなことあるわけない」と紗英が言った。「あの人、ひどいかっこうっていったじゃん。外の人もじろじろみてた」
「みんな自分の頭みてみろよ」
達郎が頬をひきつらせる、紗英と佳代子は長髪が乱れてぼさぼさだった。寛太は顔に草をつけたままだし、新治の眼鏡はずれたままだ。眼鏡にも血がついている、それに彼のスニーカーは片足だけだ。
利菜はアイスボックスのガラスにうつった自分の姿をのぞいた。まったく起きぬけの頭よりひどかったし、顔の肉もこわばっている。
利菜はクーラーボックスに手をついたままふりむいた。
「こんなかっこうしてたら、注目あびて当然だよ」
片桐という人は、奥でおばさん仲間と、おかしな人の話しをつづけているみたいだ。紗英が言った。
「出ようよ。あたし、ゆっくり話したい。外の人が、どんなふうにあたしを見るか見たい」
「だめだ」達郎はふるえながら首をふる。「そんなことしたら、よけい変に思われる」
「どうするつもりよ」
佳代子が訊くと、達郎は、
「おれが話すから、みんなはだまってろ」
ドアのそばでかたまっていると、赤川が、
「あんたたち、なにがあったの? おかしな人ってなによ?」とレジから身をのりだした。「その人、厚いコートでも着てなかった?」
彼女がにやにや笑うと、片桐が奥から顔を出した。
「ふみちゃん、子どもからかうんじゃないよ」
「だってさあ、みんなぶったまげの顔してんじゃん」
利菜が冷凍庫をはなれると、達郎は彼女が手をついたところをあわてて拭いた。ガラスに血がうつったのだ。
片桐は消毒液とタオルをもって姿をあらわした。追いたてるように、子どもたちの背に腕をまわした。
「みんな、外のベンチいく? おばさんが、アイスおごったげる」
達郎が冷凍庫から顔をあげ、
「ぼくら、大丈夫です。おっかなくて逃げただけだし……」
片桐はとりあわなかった。はいはいとうなずきながら、新治の手をひき外にいった。利菜たちは後を追いかけた。片桐は店のとなりにある休息所まで子どもたちをつれていった。片桐は新治に手をあらわせ、傷にはマキロンをふりかけた。新治の手についた血は、水をうけてうすまり、排水溝に落ちていった。
小谷というやせっぽちのおばさんが、アイスをもってきてくれた。みんなはアイスをわたされたものの、食べる気がしなかったので手に持ったままでいた。片桐が顔をしかめた。片桐は新治にちかづきすぎたらしく、エプロンのすそに血がついている。一同は我慢をして、アイスのカップをはずした。達郎はなるべくうそをつかないことにした。もともとうそは苦手だ。彼はなるべく事実にちかいことを話した。
「なにかされたわけじゃないんです」達郎はまごまごいった。「でも、浮浪者みたいな感じの人で……」
「服は着てた?」
「ふみちゃん、レジッ」
「――服もぼろぼろだったし、しつこく話しかけてきたから」
「そんだけ? ほんとに?」
「ええ」
「あたしたちがこわがって逃げたから、その人追いかけてきたんだと思う」
と佳代子がつけたしたから、達郎は顔をしかめた。
「そう?」片桐はちょっと身をおこして気をぬいた。「あんたたちも知ってると思うけど、最近へんな事件が多いからね。ねえ、行方不明の子みつかったっけ」
と片桐は小谷に話しかけた。
「まだだねえ。もう三日もたつんだけど……その子もこのへんでいなくなったのよ」
「そんな具合だからね。おばさんたちも心配なのよ。その人がふつうの人ならいいけど……汚くてもふつうの人はいるし、まあいろんな人がいるからね……」
「ふつうです」達郎はすこし口ごもり、「でも、ひげも髪ものばしっぱなしで、すごい汚い人だったし……新治が転んだから、みんな慌てたんです」
片桐は達郎の目をのぞきこむ。ちょっとうたがっているな、と達郎は思う。今の説明じゃまずかったかな?
「みんな、これからどっちに帰るの? 神保町のほう?」
「神保町です。自転車で来たんですけど」達郎はその自転車をさがすみたいに、駐車場に目を向けた。「これから親に迎えに来てもらおうと思います」
「ああ、親御さんがここにくるのね」片桐はほっとした顔をみせた。「そんな汚い身なりの人、このへんで見かけたことはないけどね。山でなにしてたのかしらね」
「おばさん」利菜は片桐の前に手をさしだした。血がついた方の手だ。「わたしも転んで手をついちゃったんだけど、なんともなってない?」
片桐はどれどれと利菜の手をもった。「なんともなってないけどね。心配なら、マキロンぬっとく?」
「うん。消毒しときたい」
「あたしも」
「わたしも」
佳代子と紗英もいった。おばさんがまた三人をじっと見た。佳代子は言った。
「その人の服にさわっちゃったから。紗英は手、にぎられたから。その人、殺人犯だと思う?」
期待するみたいに片桐を見た。まるで、殺人犯であってほしいみたいな言い方だ。
「まさかねえ」片桐はあわてたように打ち消した。「……まさかとは思うんだけど。いやね、みんながみんな、だれかれかまわず疑ったり、心配したりするのはよくないと思ってさ。警察にも通報がたくさんはいってるっていうのよねえ……いたずらもふくめて」
「ぼくらのはいたずらじゃありません」
「わかってるわかってる」
佳代子は噴水式の水道のところにいって、手を洗いだした。利菜と紗英が後ろについた。佳代子がちょっとうつむいて、肩を落としたから、こりゃ泣いてるな、と利菜は思った。自分も泣きたくなった。
佳代子は右手をつぶすほど力をいれて、掌をこすっている。血はなかなか落ちなかった。
利菜は佳代子をなぐさめ、泣くのをやめさせなきゃと思ったが、小谷という人は佳代子の涙を変な意味にとらなかった。
「泣かなくてもいいのよ。怖かったわねえ」
佳代子が泣いたのは同情をひくのによかったようで、二人のおばさんは急に警戒をといて、みんなをいたわりだした。
服をひっぱられたのでふりむくと、紗英がシャツをにぎって泣いていた。
泣いてる場合じゃないよ。利菜は妙に冷えた頭で考えた。血がみえないこと自体、おかしいんだから。
佳代子は片桐たちの見ている前で、家に電話をした。おばさんはひどく怒鳴っているようだった。
片桐は新治のためにサンダルを持ってきてくれた。新治が履こうとしないので、おばさんたちはふしぎそうに顔を見合わせた。新治はソックスに血がついたままだったし、そんな足のまま履きかえるのはいやだったのだ。達郎が肩をゆするが、新治はがんこだった。真っ赤なソックスをむきだしにして、つっ立ったままでいた。
「わたしはじいちゃんに来てほしい」
ふだんおとなしい紗英が意見をいった。みんなおなじ気持ちだったが、寛太郎は免許をもっていない。
「トラクターでくんのか?」
達郎が訊いた。みんなは暗い顔をしてだまりこんだ。利菜が、「そんなの陽がくれちゃうよ」とぼそりというと、佳代子はぱっと顔を上げ、目をまんまるにみひらいた。利菜はときどき佳代子の笑いのつぼをついた。彼女は寛太郎が耕耘機をごとごといわせながら、夕陽にむかって走るさまを想像したのだ。
佳代子のおかしみはみんなに伝染したようで、友だちは笑い声こそ上げなかったが、笑顔をかわすことはできた。
利菜はいってよかったな、と思った。なんでも、いってみるもんだ。
「なかにはいって待ってる? お茶でもいれるわよ」
と片桐がきいたが、達郎は断った。断るなんて変だけど、六人だけで話をしたかった。だから、「河原に降りたい」と言った。「あまり迷惑になるといけませんから」
へんな言い訳だけど、子どもたちは他にうまい言い訳を思いつかなかった。
□ 八
おばさんたちについたうそのなかで、これだけは本当だった。子どもたちは道をわたって河原に降りたからだ。鮎掛けのおじさんはまだ川にいたが、子どもたちからは遠く離れていた。この河原で遊んでいた明朝が、うそみたいだ。新治は草原を走っておりたとき、足の裏をけがしたようで、びっこを引いていた。寛太と達郎が手をかした。
手すりをつかみながら階段をおりると、ステンレスの棒には赤い筋がのこった。
河原には丸石がころがり、高い葦が生えていた。川岸には、菱形のコンクリートブロックがみっしりと積み上げられている。子どもたちは砂浜まで行った。達郎は血まみれのシャツを慎重にぬいだ。佳代子が「あっ」と声を上げた。達郎の背中が、絵の具を塗ったみたいに赤くなっていたからだ。達郎の顔はますます重く沈んだ。体についたなんて、ショックだった。
達郎たちが手をはなすと、新治は力つきたように尻をついた。達郎はTシャツを浜に落とし、新治の靴下を脱がせにかかった。寛太もシャツを脱いだ。達郎は新治のそばにかがみこんだまま、顔もあげずにシャツを指さし、
「みんなには見えてるか?」
と訊いた。五人は首を縦にふった。
「おばさんがきたら、見えるかどうか訊かないとね」
利菜はぶっきらぼうに答えた。彼女は自分の母親にきて欲しかったが、三津子は免許をもっていない。いっしょにきてと頼めばよかった。「おばさんなら見えるかもしんないよ」
佳代子が訊いた。「なんて訊くのよ。みんなには見えないみたいだけど、母さんには、わたしの服についた血が見えるって? そんなこと訊けないよ」
「こういえばいいのよ。新ちゃんの傷口にさわっちゃったんだけど、服に血がついてないかって。そんなのつけて帰ったら、母さんにしめ殺されるからね」
利菜がいうと、みんなはまた黙った。空気も黙った。子どもたちは、達郎が首をしめられかけたことを思い出していた。利菜が達郎をみると、首のあたりを恐ろしげに撫でていた。
寛太は帽子をとられたから、坊主頭をむき出しにしている。利菜は言わなきゃよかったと思ったが、きつい顔つきは変えなかった。
佳代子が、「そんなの変だよ。自分で見ればわかるもん」
「訊かないよりましだよ。佳代ちゃんは黙ってていいよ、あたしが訊くから。あとでおばさんに、あれこれうだうだ訊かれても困るしね」
嘘がばれてぶたれても困るしね、と利菜は思ったが、それは口にはしなかった。
「あんただったら、ふだんからおかしなこといってるしね」
佳代子はにやっと笑った。達郎もにやっと笑い、紗英もにんまりした。寛太と利菜もにやりと笑みをもらしたが、新治は笑わなかった。彼は急にのこった片方の靴をぬぐと、川に向かってほうり投げた。靴は川面にぷかりと浮いて、みんなが見ているなかを流れていった。
「いいの?」と佳代子がためらいがちに訊いた。
「いいんだ」と新治は答えた。「もういらない。片足しかないし、もう履きたくない」
「あとで怒られるんじゃない?」
「いいんだ」
「あたしもこの靴捨てたい」
利菜はすわりこんだ。靴のかたっぽを脱いだ。靴底には赤い染みができている。布製だったから、まわりから染みこむのはしかたないにしても、厚いゴム底をとおしてどうやって染みこんだのかがわからなかった。利菜は赤くなった靴下にも目をとめた。
彼女はうんざりして靴を落とした。
「もう履かないにしてもさ、下駄箱にあるってだけで気になるもん。でも、靴が減ったら、母さん怒るだろうな」
「わたしもそんなことしたら怒られると思う」
紗英がまた涙目になった。
「二人ともおこづかいは?」佳代子が訊いた。みんなは佳代を見た。「バザーで、やすい靴を買おうよ。そんで、みんなで交換したっていうの。どうかな?」
「サイズはどうすんの?」そういえばみんなちがっている。
「いっしょだったってことにすればいいじゃん」
「どのみち怒られるよ」
利菜は情けなさそうにいったが、このときはそれがいちばん現実的な方法に思えた。もう考えるのも億劫だった。
達郎が新治に顔をむけた。面とむかって話し合うのはひさしぶりだ。
「新治、足だせ。おまえ、靴下だけで走ったから、傷がいっぱいできてる」
「そういえばさ」佳代子が思いついたようにいった。「おばさんたち、新ちゃんの靴のことは、どうしたのかって訊かなかったね」
「見落としたんだよ。気づかないときだってある。靴の心配なんかすんな」
達郎は、新治の足首をもった。達郎はハンカチを濡らして、足の裏をそっと拭いた。
新治はぽろぽろと涙をこぼした。
達郎が訊いた。
「痛むか?」
「痛まないっ」
と新治は言った。
寛太は靴をぬぐと、ズボンの裾をたくしあげた。川に入り、いきおいよくシャツを洗いはじめた。
川の水が赤くなった。佳代子がおなじように川岸で達郎のシャツを洗った。利菜と紗英は、新治のシャツを脱がした。新治の傷は意外にふかく、足は赤く腫れている。
達郎がその足にハンカチをまきつけた。利菜と紗英は自分たちのハンカチもさしだした。
みんなは作業の間、口もきかずに黙りこみ、むっつりと考えこんでいた。寛太はシャツを洗ったが、血糊は落ちなかった。半ズボンにまでしみこんでいたから、寛太は風呂につかるみたいに川のなかであぐらをかいた。
佳代子はみんなのほうをみる、川面から光が照りかえる、髪は水で濡れていた、佳代子はいつもより美人に見えた。みんなが考えていることを、率先して口にした。
「みんなはどう思ってんのよ。あたしたちがおかしいんだと思う? あいつは確かにいたしさ、新ちゃんは靴をとられたし、寛ちゃんは帽子をやられたじゃん。でも、いまでも信じらんないよ。血は見えるけど……」
佳代子は腰に手をあてて、傲然と立ちながら、鼻をすすった。
「わたしも、あんなのうそみたいに思ってる」利菜が言った。
「でも、この血はうそじゃないよ」
紗英は新治の体を拭きながらいった。達郎はもらったタオルで体の血を落としはじめた。彼は、
「なめ太郎は先生の作り話だ」とぽつりと言った。
「わかんないよ、そんなの」利菜は靴を水につけ洗いだす。「わたしたちがあとで訊きに行ったら、あの話しうそでしょっていったら、先生否定してくんなかった」
「でも、朝になったら、ばかばかしいって思ってたよ」紗英が言った。「あんな話信じるなんて、どうかしてたと思ったもん」
「おれはあいつのことこじきだと思うよ」と寛太。
「だとしたら、とんでもないこじきだね」と佳代子は言った。
正直いって、こうしていつもの河原に降りてみると(しかも、こうもさんさんと陽の光のふりそぞく川面に立ってみると)、あんな体験が信じられなくなってきた。うそみたいに、ばかばかしく思えたのだ。体についた血さえなければ、子どもたちはうまい言い訳を思いついたにちがいない。
「この話も、明日になったら、うそみたいに思えるといいのに」
佳代子は水音をならして川から上がった。寛太も腰を上げた。
「思うにきまってるよ」利菜が言った。彼女は大きな丸い石の上に腰をおろした。「靴も服も捨ててさ。それでこのことはもうなし。両神山には、わたし行かないから。行きたくなってもさそわないでよね」
佳代子は利菜の正面にたって頬をふくらませた。「行きたいなんて思わないよ。わたしは帰って休みたい」
「みんな、家に帰るつもり?」紗英が不安げにいった。「わたし、ひとり部屋でしょ。家には母さんしかいないし。それにあの家……」
「空き部屋が多いよね」と佳代子があとをついだ。
「うん、こんなこというと、ばかにされるかもしんないけど……」
「するわけないよ」佳代子はぶっきらぼうにいった。「あんな目にあった後なんだよ」
「うん」紗英は素直にうなずいた。「昼間はがまんできるだろうけど、夜はだめだと思うんだよね。ぜったい眠れないし、音がするだけでも、怖いと思う」
紗英はだまった。利菜が口をきいた。
「寛ちゃん泊めてくんない」
利菜が挑発するみたいな目で見たから、寛太はどぎまぎした。
「うん? いいけど」
「みんなも泊めてもらおうよ」利菜は立ち上がると、みんなに訴えた。「わたしはじいちゃんがいるだけでも安心する」
「じいちゃんは妖怪にくわしいからな」
達郎が力なく答えた。いままで張りつめ通しだったから、急に気が抜けたみたいだった。
「でも、訊ける? あのこと話すの?」と利菜。
「じいちゃんなら、きいてくれるよ」
達郎は投げやりだ。寛太郎がなんとかしてくれると思うと、ようやく肩の荷が下りた。
「おれ、リトルがあるしさ。大会だってちかいから、いつまでも気にしたくないんだ」
「気にしたくないってなに?」佳代子はきっと言った。「気にしなきゃすむの? あれはなんていおうと、なめ太郎だった」
「そんなことあると思うか? そんなもんいると思うか?」
達郎は佳代子の目をのぞきこんだ。おまえ正気か? と訊きたがっているような視線だった。でも、達郎はリトルのキャプテンだったし、みんなの兄貴分だ。そんなことをいうほど意地悪ではなかった。
「でなかったら、あたしたちみんな頭がおかしいってことだよ」と佳代子は言った。「なめ太郎がいないんなら、子どもにだけ見える血もあるわけない」佳代子は達郎にシャツをむけた。「このシャツも捨てないとね。母さんが来たら、濡れてるいいわけもしないといけない。自転車だって洗わないと」
「大忙しだね」
利菜は川をみながら、ぼんやりいった。今度は誰も笑わなかった。寛太が川から上がってきた。
「山まで大人についてきてもらうか?」達郎が挙手を求めるように、わざとらしく手を挙げた。「たしかめにもどるか?」
「ぜったい嫌よっ。あんなとこ、もう行きたくないっ」
紗英がアゴを膝につけた。すねたみたいにふくれっつらになった。
寛太が、「でも、国村ってひとの声したろ? ほんとに怪我してたら、どうする?」
「それはなめ太郎がまねしたんだよ」利菜が答えた。
「なめ太郎なんていないっていってるだろ!」
達郎が大声をだした。寛太は誰かに訊かれなかったかと周囲を見まわした。紗英は顔をふせたまま泣き出した。佳代子は紗英の肩をだき、非難するように達郎をにらんだ。
「おまもりさまに近づいた子がいってたこと、あれうそじゃなかったんだよ」と利菜は言った。「気がつかないうちになかに入ってたっていってたもん。大人にはいいわけすんなって怒られたらしいけど……」
「もういいよ」
新治が言った。小声だったが、静かな落ちついた口調だった。みんなはだまった。
達郎はがまんをしてシャツをきた。「自転車を洗おう。新治、シャツを着ろ」
「いやだよ」
「いやでも着ろ。シャツは兄ちゃんが新しいの買ってやる」
達郎はシャツを丸めると、新治の頭にかぶせた。背中をさしだすと、新治はおとなしくかぶさった。寛太もだまってシャツを着た。
六人は達郎を先頭に階段をのぼった。階段の上に、なにかが待ち受けているような、それは慎重な足取りだったのである。