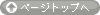「ねじまげ世界の冒険」へようこそ
このページは、ネットで小説を読まれる方用に用意しました。
長編、短編とそろえています。古い作品もあるので、できには目をつぶってやってください。
ねじまげ三部作も、よろしく!
ねじまげ世界の冒険
▼第八部 世界の終わりの最後の賭け
○ 章前 二〇二〇年 ――ねじまげ世界 八月十五日 午前十時五十分
□ 一
佳代子の意識が遠くなる。考えもない。痛みもない。怒りや悲しみ。郷愁?――といったごちゃごちゃした感情さえも消えてなくなるようだった。あいかわらず頭を揺さぶられている。首を絞めるのは実の母親だ。思えばこの母親からは、ぶったたかれたし蹴飛ばされたし首を絞められたことだって何度かある。そうしたいさかいも、これが最後となるらしい。佳代子は少しほっとした気持ちになる。母親とのある種ばかげた関係もこれで終わりになるのだろう。
彼女は真っ暗になりすべてが消えゆく寸前だったが、命の最後のひとかけらが抜け出るその瞬間、母親の指から力がぬけ、呼吸がどっと肺へと流れこんできた。止まっていた血液が頭に流れる。佳代子は咳きこみながら酸素をとりこんだ。背中を、誰かが撫でている。寛太だった。寛太は耳元でなにか怒鳴りつづけていたが、ろくすっぽ聞こえなかった。
脇を見ると母親が頭から血を流して倒れている。そのかたわらで脈を調べているのは、達郎と新治である。三人とも、火事場にいた消防士みたいにすすだらけ。頭はぺちゃんこ、おまけに体中にざぶとんを巻き付けている。気の狂った中年女をやっつけにきたにしては大仰な格好だった。
いや、このぐらいは必要だよね、と佳代子は思う。わるいものを相手にするときには、必要十分なんて言葉は決してないのだ。
佳代子はそんなことをぼんやりと考え続けていたのだが、伸子の「殺しちゃった! おじさんが、母さんを殺しちゃった!」という言葉で目がさめた。先ほどはあんなに生き生きと動いていたのに、こうしてぶっ倒れてみると登美子は調子の狂ったマネキンみたいだ。ああ母さんは痩せていたんだなあ、と妙な感想をもつ。静かに横たわる肉の塊が、灼熱の殺意をもっているとは信じがたい。
寛太の顔に確認をもとめたが、「殺してない」と彼は首を振った。一瞬、残念な気持ちがさす。そんな自分に罪悪感をおぼえる。
「ほんとにおばさんかよ」と達郎が尋ねる。自分と同年代の母親をみるのは変な気持ちだ。新治が台所からロープを持ってきて手足を縛る。
佳代子は寛太に立たされながら、「あんたたち、どうしてここに?」と訊いた。みんなひどいけがだ。佳代子はこめかみを押さえながら記憶をたどる。「そうだよ、母さんが電話をかけてきて、それであたし……」
「佳代子、神保町が空襲にあってるんだ。外はもう火の海だ」
まさか、と佳代子は顔を上げる。伸子も同じことをいった。警報を耳にしていたのに信じることができない。
「うそでしょう? また幻覚なんじゃ……」
寛太に肩をつかまれる。「今度はちがうんだ。これは現実だ。紗英と利菜が戻ってきた。二人とも町にいるんだよ。あいつらを助けないと」
二人を助ける? 利菜と紗英を?
とすると、あの二人はやはりのこのこと戻ってきていたわけだ。
佳代子はしばし呆然とした。状況の変化についていけない。三人から詳しい話を聞いたあとも信じることができなかった。自転車で走ったのは、ついさきほどのことである。その町が壊滅状態? 親子で殺し合っている間にか?
ともすると、これは壮大な親子喧嘩だったわけである。
「あの子たち、装置をとりに?」
「たぶんそうだ。でもこのままだとあいつたちは殺されてしまうんだよ。食い止めないと」
寛太が新聞を手渡す。佳代子はそれに目を落としつ寛太の袖をひっぱる。
「母さんはどうするの? こんなところに伸子を放っておけないよ」
「縛っていくしかないだろう。警察につきだしたりできるか?」
手首の縄痕をさする伸子をみつめる。親代わりに育てた妹だ。あの子が心配だった。だけど、彼女はわかっている。この子は伸子だけどほんとの伸子とも言えない、元の世界のことは覚えていない。第三帝国と戦争をし、人類の大半が死滅した世界の人間なのだ。
「佳代子、おれたちが元に戻してやらないと。これはおれたちにしかできないことだ」
佳代子は、どうやって、と訊きたかった。どうして? と。どうしてこんなことに? どうしてあたしたちが?
だけど、そこには理由なんてないのだろう。いつだって理由なんてなかった。あっても彼女にはわからなかった。佳代子は新聞を読むのをあきらめ(少しも頭に入ってこなかったし)くしゃくしゃにたたんだ。逃げ出したいのは山々だ。でも友だちがいる、今度もみんなそろっている。そろってくれた。佳代子の逡巡はほんの十数秒ばかり。それでも腹を固めるには十分だった。この世界にとどまって気を狂わすか、前に進んで死ぬかのいずれかしかない。
いずれは死ぬにしろ、まわりにいる誰かを助けてやりたいと彼女は思う。それだって世話好きの性分がもたらしている。起こったことをもたらすのが自分であるのなら、面と向かって立つしかない。寛太朗がよく言わなかったか? 逃げれば最悪、向かえば最高。やったろうじゃないか。
伸子の側に歩いていく。伸子が顔をあげる。その肩に手をおいた。「伸子。いいここから離れちゃだめよ。姉ちゃんが、全部なんとかしてやる」
背を向けた佳代子に伸子が言った。「姉さん、どこ行くのよ、そんな非国民なんかと付き合ったら、何されるかわかんないよ」
非国民、という言葉が、一同の胸につきささる。ある意味では言い得て妙だ。彼らはこの世界の部外者となっていた。
伸子はこんなこと言わない、こんなことをいう子じゃないと彼女は思った。けれど気丈にふりむいた。
「さあ、それは……あたしたちがずっと非国民みたいなもんだったからじゃないかな」
「行かないで、姉さん……」
「そうしたいけどね」
そして、伸子を抱いたのだった。
それで、この別れはおしまい。彼らはマンションを出ておまもりさまを目指すことになる。本当の意味で、最後の抵抗者となった四人を巡るおぞましい旅路の、それが最初の始まりだったのである。
○ 一九九五年 八月二十日 ――坪井宅 中段
□ 二
登美子の影が見えた瞬間、佳代子の恐怖は万倍になった。実際にはあれは登美子とは言えない。おまもりさま――あるいはその奥にあった物が生み出したモンスターだと言えた。彼女はそのことを知っていたのに、友だちをつれてきてしまった。佳代子は仲間を窮地に追いこんだことを考える。今も導きつつあることを考える。それになによりも利菜のことを。ここにはあのとき守ってくれた、利菜はいない。
自然に涙が出て、急いで拭った。目を離したらその隙に引っぱたかれるような気がして怖かった。あたし、間違ってた、利菜はこのさきにいるはずだけど、行けるはずがないよ……
だけど、佳代子は、力が高まっているのも感じている。脈拍が高まってる、血管をたたいて、心臓を叩いて、脳を叩いている。感覚が冴え冴えとして、視界も匂いも鮮明になった。登美子の悪意が明確に読みとれるのと同様、友だちの存在も高画質のテレビみたいにくっきりとかんじとれたのだ。
となりで紗英が、起き上がり、という言葉をくり返し考えているのがわかった。彼女はゴミ箱の死体を気にしているようだ。みんなは彼女につられていっせいに少年をみた。ポリバケツに押しこめられた坊ちゃん刈りの少年が、首をもたげて目を開く。彼がにやりと笑うと、新治はたまらず悲鳴を上げた。達郎が金切り声で叫んだ。
「みんな、変な想像するな!」
少年が体をゆすると、ゴミ箱がゴトゴト揺れた。佳代子は紗英と抱き合う。彼女の体温と、この家の冷たさを感じる。こいつ、出てこられないんだ、手足がはさかってるから。佳代子は震える声で、「ここもだ、ここもパワースポットなんだ!」
「だとしたら、まずいぞ」達郎が答える。「みんなこいつを信じるな! こいつに力を与えるな。ここは、おまもりさまとおんなじだ」
「だったら、最悪だよ……」紗英がつぶやく。その息に恐怖が混じる。
子どもたちの背後では、テーブルの足がどんどん伸びていた。台所の流し台が崖のようにせり上がり(こっけいなことにゴミ箱の少年も、そのさまを見て驚いた)、まるで成長期の子どものようだ。家はどんどん大きくなって、佳代子たちはまるで小人になる。床板の隙間からは、かいわれみたいな草が、木目をやぶってはい出してくる。どんどんどんどん成長して、佳代子たちにまとわりついてくる。
五人の視線は、ガラスの向こうの人影に釘付けになる。扉が開く音は、地響きのようだった。佳代子の心にたまりにたまった母親への恐怖が吹き出し、のどもとを突き上げ、吐きそうになる。
達郎が、「わるいほうに考えちゃだめだ。おまえの母さん、あたごまで迎えに来てくれただろ」
「でも……」と佳代子はつぶやく。
廊下につづく扉が、少し開いた。巨大な引き戸の向こうで、ちっちゃな(といっても、その大きさは佳代子たちと変わらないのだが)登美子が、邪悪な目をのぞかせる。
寛太は、おまえの母さんはあいつじゃない、と必死にいった。友だちの言葉に、佳代子は迷った。恐怖を振り払うのは、簡単ではない。これから最大のやいとが始まろうとしているからだ。
「あれはおまえの想像だ。本物のおばさんなんかじゃない」といってから、達郎はゴミ箱を揺らす少年に叫んだ。「うるさい、黙ってろ!」佳代子に向き直り、「あれはわるいものだ。おばさんじゃないじゃないか。この間だって、利菜が追っ払ってくれたろう!」
家の中はもう苔むしている。樹木が生えて、本物の森とかしていた。新治は顔にかかる枝を払って、
「みんな手をつなごうよ。もういっぺん、心を合わせよう」
と言った。その言葉に友だちは顔を見合わせた。
できるのか? あのときと同じことが?
みんなの結束を不安定にしているのは、利菜の欠落だ。恐怖心と後ろめたさが佳代子たちの心を打ちのめす。新治は癇癪を起こして、
「ぼくだっておっかないけど、もう逃げられないってわかってるんだ」と負けずに怒鳴った。「みんなのために行かなきゃだめだ!」
ゴミ箱の少年は、静かに目を閉じた。
「英二のためか?」寛太が訊いた。
新治はうなずき、「小野田って子や、死んだ子たちみんなのためだ」
彼が手を差し出すと、寛太と紗英がその手をとる。佳代子と達郎も急いで加わる。みんなは手をつなぎあい、そして一人足りない環となった。力が再び流れんでくる。佳代子は感じる。やいとでうけた数々の恐怖が、彼女の中で退いていく。胸が奇妙に暖かく、佳代子はちょっと涙ぐむ。冷徹な力が額におりて、なんだか本当なことが見えそう気がする。その平衡な感覚に、彼女は酔いしれた。
ああ、そうだ。母さんはあたしを育ててくれた。三人も兄弟がいるのに、ちゃんと見捨てずに、食べさせてくれた。佳代子の中に、怒りや恐怖ではない、別の感情が芽生えてきた。母さんの、お荷物だった? それも真実。母さんに、腹を立てた? それも真実。母さんに、憎しみを持った? それも真実だ。だけど、愛情も持った。母さんだから。つながりがあるから。感謝を忘れたらだめだって、じいちゃんが言った。それも真実なんだ。ひどいことをされたからって関係ない。してくれたことを忘れたらだめだ、と佳代子は考える。だって、わるいことばっかじゃない。やいとを据える母さんには、問題がある。だけど、それでも、あんな母さんは、フェアじゃない。だから佳代子は、母親のしてくれたこと、自分を思ってくれたことを思い出す。悪いとこばかりじゃない。まわりの母親に比べたら、ほんのちょっぴりかもしれないが、いいところだってちゃんとあるのだ。
母さん、ありがとう、と佳代子はつぶやいた。まわりには聞こえないほどの小声だったけど、母親の心には確かに届いたようだった。樹木の向こうにいる登美子が、「佳代子……」とつぶやいた、そして、消えた。
わるいものが引きこんでいく。五人が目を開けたとき、家の中はほとんど森に変わっていたが、大きさは、ぐっと縮まっている。国会議事堂の規模が体育館ぐらいにかわってしまった。
みんなは手をつないだままでいた。
わるいものは一時撤退していたが、虎視眈々と命を狙っている様子だ。その存在を、確かに感じた。そして、彼らは自分たちの最後のメンバー、おまもりさまに消えた唯一のメンバーが、どこか遠くの世界にいて、ひどく困っていることを知ったのだった。
□ 三
彼らは草むした台所を抜けた。その家は、彼らの呼吸にあわせて伸縮している。居間に入ると、畳が水気を吸い、厚く生えた苔に靴が沈んだ。
廊下につづく扉には蔓草が絡まり合い、まるで両神山の蔓壁のようだ。達郎と寛太が蔓を引きちぎると、傷口のように血がふきだす。
扉を開く。蔓の向こうには、死体があった。顔の半分方を食われ、脳を露出した坪井善三だった。
彼らは廊下に出る、階段を見上げる。そこも草むらと化していた。ずっと視線を上げるが、亀裂とやらは形も見えない。
五人は意を決すると、階段をのぼりはじめる。
階段に足を置いたとき、佳代子はこの家が生きていることを確信した。あちこちから、誰かの悲鳴や雄叫びがする。そのうちの一つは、なめ太郎のものだ。誰かの息づかいを感じて脇を向くと、壁が呼吸しているのだった。手摺りにまで、蔓が絡まり合っている。階段の二段目に足を置いたとき、佳代子はこの家が、生物に変わり始めていることを知った。木の感触はなく、誰かの腹を踏んづけたようだ。思い切って体重を乗せると、屁をこいたような音がした。ブハッ。それから、忍び笑う声がする。それが近くなり、遠くになり――めまいを感じて頭を振ると、前を行く達郎が急に遠くなっていた。
「みんな手をつながなきゃだめよ」
「でもよ……」
寛太は不安定な足場に、両手を伸ばしてバランスをとっている。標準サイズの階段だというのに、どこにもふれることができないでいた。佳代子たちが苦労して手を取り合うと、死者たちの怒り狂った雄叫びがした。
「い、行こう」
達郎が言った。
「で、でもよ」
「もう、引き返せない。行くしかないんだ」
佳代子は四つんばいになり、夢中で階段を上った。両手と膝の下には、グニャグニャとした感触がある。きっと死体だ。佳代子は下をなるたけ見ないようにした。
子どもたちが、二階の廊下、階段の上がり口にたどり着いたときには、五日前にみた壁が高くせり上がり、崖のようになっている。
佳代子は手を伸ばし、崖から垂れ落ちた蔓草の束を押しのけた。途中から、蔓は女の毛髪に変わったが、それでもめげずに髪をどかした。達郎たちも加わった。そうして、ようやく壁の地肌が見えたのだが、そこには茶色く古ぼけた(数十年がたったかのような)安っぽいクロスの紙があるだけで、数日前に見た亀裂はどこにもなかった。痕跡すらも。
「こんなはずない」と佳代子は言った。妙に確信に満ちた口調だ。「こんなはずないよ。あのときは確かにあったんだから。あのときは……」
冷気を足下に感じた。右手に顔を向ける。部屋に続く扉が開き、溺死女がなぜかタオルを握って立っていた。これほど間近でこれほどまじまじと見たのは初めてだった。
「消えてよ……」と佳代子は小声でいった。一瞬気を失っていた紗英が、その声で目を覚ます。「友だちを助けに行かなきゃなんないんだから!」
溺死女は、きえーっと、怪鳥のような雄叫びを上げ、手にした濡れタオルで佳代子の顔をしたたかに打った。扉が閉まった。
痛くはなかったが、佳代子の顔はびしょ濡れになった。彼女が泣き始めると、寛太が気遣うように肩を持つ。
佳代子は壁に手をついている。亀裂のあった場所。その壁をにらみ、
「ひらけ……」と震える声でいった。
達郎もいった。「そうだ、ひらけ」
子どもたちは、開け、開け、と口々にいった。彼らは手を取り合い肩を抱き合い、一つになって叫んでいる。その家に向かって。
「開け、開け、この野郎! 利菜を返せ!」
佳代子が壁を叩こうとしたとき、中央に丸い黒点が生じた。それは渦を巻きながら、広がりだす。風がわずかに起こって、佳代子の髪が黒点に向かって吹き寄せられた。子どもたちは、叫ぶのをやめた。その家にいた悪い連中も、一斉に押し黙った。
わるいものの巣と化した坪井宅に、その日初めて、静寂が訪れたのだった。
◆第十九章 ねじまげグループ、真実を知る
○ ジノビリ歴三年 貴族街
□ 四
朦朧としている。
通りでの戦闘に敗れ、仲間ともちりぢりになった。ノーマはもうまわりの仲間を確認することすら困難だった。先刻の敗戦で、精も根もつきてしまった。もう痛みに堪えきれず、混濁する意識を支えていられない……。
一行は、路地裏の一角に逃げ込んだ。トゥルーシャドウがノーマを路地におろす。ノーマは地面の冷たさにハッと目を覚ます。
砲声が轟いてくる。
ついてきたのは、ナバホの男たちだった。彼らはノーマの言葉を信じ、もう一度戦おうとしている。路地といってもまだ貴族街のことだから、下町の大通りほどには広かった。ノーマは塀に囲われた夜空を見上げ、口端から血を垂らした。ときおり意識が消えそうになる。夜明けはひどく遠くに感じられた。けれど、このまま何もせずに時を過ごせば、自分もイニシエの民も少年らも身の破滅だろう。ノーマは側にきたビスコに、丘を登るよう目だけで訴えかけた。
「おれたちどうなるんだ?」
とモタが言った。ヒッピはちらりと利菜をみた。利菜は毛布にくるまれて寝かされている。ヒッピのグループが彼女を心配して取り囲んでいる。逃亡の最中にこめかみに弾丸をうけて、気を失ったのである。弾丸は彼女の皮膚をかすめただけだったが、脳震盪を起こしたらしかった。利菜の手が仲間の血で汚れているのを見ると、ヒッピは自分の手を見るよりぞっとなる。今は意識をなくしたままでいるほうがいいだろうと、彼の仲間たちはそっとしておいた。
大人達はマーサを囲んでこれからどうするかを協議しあっている。残ったイニシエの民もここにはナバホ族が大半、二十名ほどしかいなかった。ヒッピはマーサの語るボソボソという声を聞きながら、
「利菜を城に連れて行こう」
「城になんかいけっこねえよ」パーシバルが腹を立てた。「みんな死んだんだぞ。みんな死んだじゃないか!」
パーシバルは血まみれの手で眼をおおった。彼の膝元にはこれも血にまみれた長銃がころがっている。銃身が焼けていたせいで、鉄の部分についた血が焦げて黒ずんでいる。みんなの脳裏を仲間の死体が埋め尽くした。ヒッピは無言で、手に付いた血を服で拭った。仲間たちも無言でこれに習った。
「この子は怪我をしてるじゃないか」とペックは言った。利菜を見ている。ヒッピはぎゅっと拳を固めた。ペックが非難するように彼を見た。「この子をこんなところに連れてくるべきじゃなかった。これ以上振り回すのか? 元の世界に戻れなくたって、死ぬよりはいいじゃないか」
「だめだ。ぼくらは下がれない」
「なんでだよ! なんでわからないんだ!」とペックは大声を出し、大人たちがぎょっとふりむいた。銃声は近くなっている。掃討戦が行われているのである。「君はいつもそうだ! 自分の意見を押しつける! 利菜がかわいそうとは思わないのか!」
「押しつけてなんかない! ここにきたのは全員の総意のはずだろう! それに利菜は……」
ヒッピはペックに胸をつかれてよろめいた。
「死にたいなんて思ってたやつはいないぞ! ぼくより小さな子まで死んだぞ!」
「二人ともよせよ!」
とパーシバルとモタがペックの前に割っては入り、パダルも片手でヒッピの腕をひいた。大人たちは(といっても、サイポッツはマーサ、ビスコ、ノーマの三人だけで、後は他種族ばかりである)彼らを怒らなかった。みな疲れ果てていた。ヒッピはマーサを睨んだ。マーサは今では立ち上がり、弟子たちのことを眺めていた。フードが陰を作り表情がわからない。けれど、ヒッピはその落ち着いた様子が気に入らなかった。
「ぼくは利菜をなんで連れてきたのかわからなかった。でも、あなたのすることはいつも理由があった」
ペックは今度は反論しなかった。ヒッピがマーサにむけて話していたからだ。
「利菜がこの世界に来たのは、きっと偶然じゃない。ぼくらは死者を呼び出そうとしたのに、利菜の世界とつながったんだ。それもぼくらと同じ目にあってるこの子の世界と。だからあなたは利菜を戦場まで引っ張ってきたんだ。この子が役に立つと思っていたから。必要だからだ。そうでしょう?」最後の疑問符はやや非難めいていた。「サイポッツの儀式なのに、イニシエの森に祭壇があること自体がおかしかったんだ。あの儀式には何か秘密があったのかも」
ペックが、「最初から利菜の世界とつながるように出来てたってことか?」と続けた。
それならハブラケットが危険な森に弟子を送ったのも納得できる。ヒッピは少し考え込んだ。ハブラケットは何か確信を持っていたのかもしれないのである。
「利菜の世界にも銅の鏡があったといってた」とヒッピ。「聖櫃はイニシエの民の宝ということになってる。でも誰も場所を知らない。マーサおばあさんにも記憶がない」
マーサは、そうだね、と小声でいったが、ヒッピには聞こえなかった。「聖櫃の在処を知らせないために消したんだ」
「誰が?」とパーシバル。
「きっとエビエラだ」ヒッピは利菜を見おろした。「この子たちの仲間がそろえば、答えがわかる気がする」
聖櫃を隠したのがエビエラなら、理由があったはずである。こちらにとっても危険な物だったんだろうか?
どのみち、とノーマが呻くようにつぶやいた。それは弱々しい声だったので、ヒッピも、ヒッピの言葉に注目していた人たちも、それぞれに彼を見た。「もう後には引けない。死んだ者たちのためにも丘をのぼろう」
でも今はおまえが死人みたいじゃないか、とはパーシバルも口にはしなかった。
「のぼってどうする?」とビスコがノーマの側にかがみこむ。「ハフスを救うのか?」
「あるいは、トレイスを殺そう」
「殺せなかったら?」
とヒッピ。ナバホ族たちは是が非でも殺すのだ、といきりたったが、ヒッピの言いたいことはそうではなかった。
彼らは話し合った。トレイスには謎が多すぎる。そもそも彼が何者でどこから来たのかもまだわかっていない。もし、三百年前もマーサと敵対したサウロンと同一人物であったのなら、なぜ戦勝のおりに殺さなかったのか? これまで出てこなかったことを考えると、自由の身であったとは考えにくい。殺せない理由があったのか?
「なにを悠長な」とスラブが言った。行動的な彼は、この場に留まっていることに我慢がならずにいる。「他の者たちは今もって戦っているのだぞ。彼らを救えるのは我々だけだ。王城には兵がいないはずだろう! 親衛隊は出払っている。この間隙をつくしかない」
逃げないのか、とパダルが震え声でいった。ビスコが、「逃げてどうなる。王都を出ても、みな難民になるだけだ。城門のダンカン人が、門を閉じていれば、我々は逃げられない。ハフスを救おう。ハフスを救えば、我々は暴動の首謀者ではなくなる。それしか、イニシエの民に報いる道はないのだ」
ビスコは初めて蛮族のことを、イニシエの民と口にした。ノーマはその言葉をかみしめる。
マーサが、「こっちも余力はないからね。出直すなんてことはありえないよ。トレイスは師団を呼び戻して防備をかためちまうだろう」
ヒッピは同意をするようにうなずく。「ぼくらは最後までやり抜かなきゃならない」
「なんでぼくまで……」なんでぼくが、とパダルが言った。それは彼の正直な気持ちであったし、多寡はあるにしろみんなが感じていた疑問でもある。なんでこんな嵌めに?
ヒッピは胸にのしかかるような恐怖を感じる。けれど、彼はこの面子のリーダーでもあったから、どうにか顔を上げることができた。「それができるのはぼくらだけじゃないか。他の誰にやらせるっていうんだ。みんな苦しんでる!」とヒッピは腕を広げて言う。ペックにはその腕の下に、今も戦う少年たちの姿が目に見えるようだった。「ぼくらはこれにどっぷり関わってきた。逃げたっていいのかもしれないけど、ぼくは逃げないぞ」
「あたしも逃げない」
足元からのぼってきた不気味な声に一同は飛び上がった。利菜だった。喉がしゃがれて、それで異邦人のような声に聞こえたのだ。彼女は路地に寝かされていた。彼女が起き上がると、後頭部からパラパラと砂が散った。彼女はこう考えていた。おまもりさまでは逃げ出したから、わるいものに支配されてしまった。あれは個人のわるいものとも結びつくのだ。あるいは、自分たちでわるいものを引き寄せたと言えるかも知れない。彼女たちに必要なのは、強い気持ちをもつこと、自分を信じること、平たく言えば、強い信念を持つことである。弱気になるのは仕方ない。けれど、気持ちいつだってをコントロールできることを彼女たちは証明してきた。そうしてきたことを彼女は手短に語った。だからみんないまだに生きているんだよ。
トゥルーシャドウはそれまで黙ってサイポッツたちの話を聞いていた。彼としては、全権をマーサに任せている心持ちである。信念をもつことに関してこの男以上に長けた者はいなかった。なぜなら、トゥルーシャドウにはもはや失うものがなかったからである。今の彼は選択肢のない、たった一つの目的意識のみで動いていた。
トゥルーシャドウは子どもたちから目を離し、路地の先に視線をやった。簡易ランプの火を消した。少年たちは驚き辺りを見回したが、もとよりナバホ族にとっては無用なものである。
「誰かいるぞ」とトゥルーシャドウは言った。その言葉で一同はいっせいに身を伏せて、通りから姿が見えぬように意念を払った。
ナバホ族らは目の光すら隠すように目蓋を細め、じわじわと正面に出て行く。スラブが側にきて、トゥルーシャドウにささやいた。「一人だぞ。仲間はいないらしい」
トゥルーシャドウはうなずいた。それにしても不審な男である。闇の中でぐらぐらと揺れているし、こちらには気づいたはずなのに声をかけようともしない。敵なのか?
トゥルーシャドウが仲間に合図すると、ナバホの若者たちが男に駆け寄ってたちまちのうちにからめとった。数人が通りに出て合図を寄越してきた。安全のようだ。
彼らは男の側に集まった。ヒッピたちが銃を構えた。男はマントを頭からかぶり、胸元でくくっている。塀にもたれて手足を投げ出し、胸のかすかな上下動がなければ死人だと思ったかも知れない。トゥルーシャドウがランプに灯を入れて、スラブがフードをはぎとった。利菜は目を見開き、ヒッピたちもごくりと息を飲んだ。男は眉や髭まで真っ白になり、ひどく老衰していた。
「何者だ?」とスラブが訊いた。理由はなんであれ、この男が恐ろしくおびえているのは本当だった。二〇代も前半であろうというのに(袖からのぞく手の甲はひどく若い)、髪は白く、深い皺が刻まれている。苦悩が容姿を変えるのならばこの男が実例だろう。
男は意外な返事をした。助けてくれ、と言ったのだ。スラブはマントをさらにめくり、
「この男、親衛隊士か」
「そんな馬鹿な親衛隊士に老人などいない」
ビスコがいうと、男は枯れた笑みを見せた。が、装束はまちがいなく親衛隊士のものである。
トゥルーシャドウが年老いてはいない、と厳かにいった。
男は少し顔を傾け、ランプの明かりすらまぶしげに、マーサを見上げた。
「私の名はフロイト。あなたに遇いに来たのです」
なんのためにだい、とマーサは言った。
「トレイス様を弑するために」
「おまえはトレイスの側にいたのか」ノーマがナバホ族に連れられて来た。フロイトは疲れたようにうなずいた。
「ならば、ハフス様やハブラケット司祭がどうなったか、知っておろう。あの方々はどこにいるのだ」
フロイトはかすかに首を左右に振った。
「二人ともすでに亡くなられております。あなた方は遅かった――」
「でたらめだ」
反論の声はすぐさまあがった。激しく罵るナバホ族に、
「だから私はあなたを頼って来たのです!」フロイトははじめて大声を出した。その声はしわがれてこそいたが、外見ほどには年老いていなかった。男はさっと顔を伏せた。その目に涙の残滓がひかりはじめたので、トゥルーシャドウたちはとまどうばかりだった。
「私はトレイス様が恐ろしい。自分のしでかしたことが恐ろしいのだ。私はトレイス様を救い出した……私のせいで、何百万という同胞を死に追いやってしまった」
「何をいってるんだ?」
ビスコも途方にくれる顔をする。というよりもこの男のいうことを全面的に認めたくなかった。ここまできてハフスが死んでいるなどと、信じたくはなかったのだ。
「どうするんだよ?」とパーシバルが言った。「ハフス大王が死んでるんじゃ、城を攻めても意味がないじゃないか」
大人達は何も言えなかった。フロイトの言葉を信じられずにいるようだった。マーサがフロイトの側に膝を付いた。フロイトは少し安心したようだった。
「おまえは、トレイスを救い出したと言ったね」と尋ねる。「いったい、あの男はどこにいたのだね」
フロイトは話した。自分が親衛隊士となり、そして、スミスという老人から、特別な仕事を与えられたこと。地下の回廊におりたこと、次元のねじまがりにでくわしたこと。
それは不可思議な話だったが、この場にマーサがいるだけに息をのむ話でもあった。マーサ以外にも死ななかった人間がいる?
「トレイス様は、エビエラに長年幽閉されていると言った。私にスミスさまを殺させた。そして、鍵をあけた私に、全ての記憶を見せたんだ」フロイトは額をおさえる。あのとき以来、いまだに激しい頭痛がするのだ。「私にはその大部分が理解できなかった。でもあいつがいろんな人間であることはまちがいない。あいつは最後にトレイス様を乗っ取った」
「乗っ取った?」とマーサが訊いた。「何をいってるんだ。あいつはトレイスではないのか?」
「そうなんだ。あいつはトレイスじゃない」フロイトは幼児のように体をゆがめる。マーサにしがみつこうとしたので、トゥルーシャドウが割って入った。「あなたは知っているはずだ! 三百年前に、あの男と戦ったんだから。エビエラはあの男の持っていた装置を奪った。あの男が元の世界から持ちこんだものだ。それを利用して、トレイスさまを封じたんだ!」
そこで、みんなはいっせいに利菜をみた。元の世界?
「すると、トレイスは……」マーサが言った。「その男は、この世界の人間ではないのか?」
「そう。そうなんだ。あいつは……」フロイトは顔をゆがませる。今では脂汗をかき震えている。「あいつにとんでもないものを見せられて、それ以来、私はおかしくなった。ああ、今も頭が痛む!」
フロイトはかんしゃくを起こして壁を叩いた。ヒッピは利菜にささやいた。装置とは聖櫃のことと見て間違いない。これで秘密がわかるかもしれない。
マーサはフロイトのそばに行き、額に手を添えた。トゥルーシャドウが、わきに立った。フロイトがおかしな真似をすれば、斬り倒すつもりだ。
「私の記憶をみるつもりですか?」とフロイトが言った。「やめた方がいい。あんなことは、誰も理解など……」
「気に病むのはよしなさい。おまえは辛い目にあった。ここまでよくやった」
「そんなことは、そんなことはない……」
と彼は言ったが、その声は鎮まっていた。マーサは目を閉じて、意識を集中した。利菜は思わず身を乗り出して注目した。その姿は、熱を出した息子をいたわる母親のようでもある。現にフロイトは頭に上った血の気が下りるようだった。
フロイトの記憶を探り出してから、長い時間がたった。最後にマーサは長い息をつくと、手をどけた。
「そうだったか……おかげで、なにがあったか、一部なりとも知ることができたよ。それも、トレイス側の視点でね」
「大丈夫ですか?」と、トゥルーシャドウがいたわった。
「あたしはむりやり記憶を流し込まれたわけじゃない」
「トレイス様は、あなたが装置を隠し持っていると思っていたんだ。あなたはずっとイニシエの森に隠れていたし、エビエラはわざわざ記憶を消している」
「どうかね。だが、あいつの秘密がいろいろとわかったよ。まず、あいつの本当の名はサウロンだ。たしかに、別の世界の人間だったらしい」
マーサがいうには、サウロンはその世界で、反乱軍のリーダーであったらしい。自分たちを支配する帝国と戦っていたのだ。ヒッピやビスコたちにはピンと来ない話のようだったが、利菜はすぐに理解した。話を聞いていると、サウロンというのは宇宙戦争のようなことをやっていたらしいのである。
帝国の科学力は圧倒的で、サウロンたち連合軍は追い詰められた。窮地にたったサウロンは、仲間とともに最後の作戦に出た。彼らは帝国の中枢にあった装置を暴走させた。
「次元の崩壊は、そのときはじまり、今も続いている。サウロンは、この宇宙自体がまちがった方向に進化した、と考えたのだね。
「じゃあ、そいつのせいなの?」利菜は大きな声を出した。世界のねじまげに原因があるとは(それもそいつが生きてすぐ近くにいるとは)、考えもしなかったのだ。
マーサはうなずいた。「元の世界では、絶大的なカリスマをもつ指導者にして英雄のような男だった。彼は、自分たちの国や歴史を守るために戦っていたんだよ。多くの仲間を率いてね――ともかく、この世界に流れ着いたサウロンは、半死半生の状態だった。体はミイラのようになり、動くこともできなかった。だが、サウロンは、死ななかった。彼を見つけた男に、乗り移ったんだよ」
「そんなことが可能なのですか?」とトゥルーシャドウ。
「サウロンにとっても意外なことのようだったよ。死の寸前で、奴も必死だったんだろう。彼らはあたしたちよりずっと――ことによると何万年もすすんだ文明をもっていたようだ。肉体的、精神的にも、ずっと優れていたようだね」
「あたしとヒッピが、大鏡でつながりあったのと同じなのかな?」
「少しちがう。まず第一に、サウロンは次元を介して、その男と通じ合ったわけではない。精神的なつながりをもったのではなく、完全に融合してしまったんだよ。新しい一個の人格になってしまった」
「そのとき乗っ取った男がトレイスなのですか?」
「ちがうね。男は農夫だったようだ。サウロンもしばらくは男になりかわって生活をしていたようだが――山賊に襲われて、家族を皆殺しにされた。男をのっとったサウロンも殺されかけた。男は死んだんだが……」
「殺した山賊にのりうつったのですか?」とノーマ。
マーサは疲れたように息を吐いた。「サウロンは、死の寸前に殺した相手に乗り移るコツのようなものをつかんだんだろう。誰にでも乗り移れるわけではないようだがね。それに問題もある。利菜とヒッピはつながりを持っても、全く別の人格だろう。だが、サウロンの場合は完全に融合してしまうんだよ。実際、融合を繰り返すたびに、サウロンの人格は変質している。彼がトレイスになりかわったきっかけはわからないが、ともあれ、トレイスは、当時の政府の要職にいた。ハフスも、その政府にいたようだね」
目の眩むような話だった。
「やつはトレイスとなり、当時の政権を乗っ取ろうとした――いや、事実は乗っ取ったのだが。ハフスたちは反対勢力になり、王都を追われた。そして、建国戦争のはじまりさ」
「それが三百年前だと?」
ビスコは信じがたげにマーサをみおろす。
「信じられないのはわかるがね。あたしだって、自分がなんで死ねないのか知りたいもんだよ。肝心の師匠は、ちゃっかり死んでるのに。あたしと、ハフスとスミス――知る限りでは、三人だけだね」
「スミス……その人物も、三百年生きてきたと?」とノーマ。
「そうだ。トレイス様はそうおっしゃっていた」とフロイト。
「奴を殺さずに幽閉したはずだよ。殺すこともできないんだからね。うっかり死なせて、また別の人間になったんじゃたまったもんじゃない」
「殺しようがないんですか? もう一度やつを幽閉できないのですか?」
ノーマがいうと、マーサは苦り切った顔をした。「師匠は、サウロンの持っていた装置を奪い取ったんだよ。それでどうにか封じ込めたようだ」
「元の世界の?」とノーマ。
「そうだ。帝国が生み出したものだったらしい」と言う。「厄介なことは他にもある。サウロンはね、もともとあたしたちよりもずっと進化した種族だったんだよ。だから、あたしやおまえたちの体をのっとっても、使いこなすのは造作もないんだ。扱いの簡単な道具を使ってるようなもんだからね。自分のあらゆる潜在脳力を使いこなせるとおもってごらん。修行をつむ必要すらない。あいつのおっとろしい力をみたかい? サイポッツを支配するなんざ、あいつにとっては簡単なことなのさ。元の世界でだって、覇王のような男だったんだからね」
「でも、サウロンだって、帝国に追いつめられたんでしょう」
「帝国の人間は、そのサウロンよりずっと優れていたのさ」
一同はだまりこむ。
「サウロンは、どの程度の数の人間と融合したのです」とトゥルーシャドウが訊いた。
「何人かはわからん。とても全部は見きれないよ。なんせ、一人の一生どころじゃあない、とんでもなく長い人生だ。要点をつかむだけでも、ふらふらになったね」
トゥルーシャドウはフロイトを見下ろした。「だが、奴の秘密を知り得たのは、この男のおかげだ」
トゥルーシャドウの敬服のまなざしにも、フロイトは気づいていないようだった。フロイトはとんでもなく長い一生を、無理矢理たたきこまれたのだから。考えてみると、恐ろしいことだった。
「なんということだ」ノーマは仰臥したまま嘆息した。「ここにきて、そんな事実を知らされるとはな」虚脱して、立つこともできない。「我々は最後の戦闘にもやぶれた。ハフス様ももういない。もう……もうおしまいだ」
子どもたちは何も言えずに互いの顔を見合った。重傷にもかかわらずここまで懸命に仲間を引っ張ってきたノーマが絶望して涙を流している。トゥルーシャドウはただ静かに左右に首を振った。
フロイトはぽつりぽつりとマーサに語りかけた。老人のような顔に、今は生気がさしている。目的がこの男をよみがえらせたかのようだった。
「あなたは三百年の昔からずっと対抗勢力だった。世界のねじまげと戦ってこられた。私はあなたに全てを託したい……」
「フロイト、おまえは思い違いをしている。あたしは……」
「いや、あなたには記憶がないだけだ。エビエラが記憶を消したのだ。トレイス様はそうおっしゃっていた」
フロイトがトレイス様、というたびに、利菜はびくりとした。これから殺そうとする相手に、尊称をつけるだろうか? フロイトは、心のどこかでトレイスを崇拝しているのだ。
「世界はねじまがり、滅びようとしている。それをやったのはトレイス様だ。しかし、世界の破滅が人の意志ならば、この世界の存続を願う人の意志があってもいいはずだ」
「まさしく、我々の先祖は、それを願うだろう」トゥルーシャドウが、はじめて同意した。
「あたしにつきがあるとでもいいたいのかい?」とマーサは吐息をついた。
「いかにも」とフロイトは言った。「もうわたしにできるのは信じることだけだ」
その言葉に利菜は深く納得した。彼らはここまで、なにかを信じる、ただそれだけでやってきたのだ。
彼女はこの場にいる面子を見回し、それから遠くの世界にいる佳代子たちを思った。彼女は世界の秘密を握ろうとしている。そのことをみんなに知らせてやりたかった。彼女はふいに自分の世界で見た死んだ子どもたちの霊を思い浮かべた。あれが幽霊だったのか幻覚だったのか、彼女にはわからない。けれど、このまま引き下がることが悔しかった。原因があるのなら、なんとかできるかもしれないじゃないか。
「あたし、佳代子たちに遇いたい。このことを教えに行きたいのよ」
利菜はヒッピの手を握る。ヒッピが真剣な顔で見つめかえす。利菜と同化しているヒッピも彼女と同じ気持ちだったのだ。彼がうなずくと、ペックらも同意した。
「フロイトがここに来たのも偶然じゃない気がする」
と利菜は言った。世界のねじまげが始まって以来、もっともわるいものに苦しみ打ち勝ってもきたはずの面子が戦場を潜り抜けて再びそろっている。儀式を行った三人の神官たちと、ヒッピのグループ、それに古代の戦争すら潜り抜けた骨董品の魔女。そうしたことが、偶然だとは彼女には思えない。利菜ははっきりとこう感じていたのだ。自分たちはこの夏続いた空恐ろしくも馬鹿馬鹿しい物事の最終決着を付けようとしているのだと。
同時に彼女はここにきて不気味な気配を感じてもいた。坪井の家やおまもりさまで感じた邪悪な気配と全く同質なものだった。パワースポットだ、と彼女はつぶやく。同時に顔を見上げた。ヒッピもそうした。二人が顔を向けたのは、城の方角だった。おさそいだ、おさそいがはじまってると彼女は思った。雷雲の中に沈む王城が、おいでおいでをしているように見えた。
利菜は大きく目を見開く、よろめくように足を踏み出す。何かを畏れるように胸元まで右手を挙げる。
「佳代子たちだ……」
と彼女は言った。
□ 五
「何をいってるんだ?」とマーサが訊き返した。
「佳代子たちだよ!」と彼女は叫んだ。目をかっと開き、形相も凄まじかったので、ヒッピはぎょっと身を引いた。「あの子たちこの世界に来てるんだ。助けにいかないと」
「そんな……」
とヒッピは顔を上げる。マーサたちも迷うようにヒッピを見た。
「本当だ。佳代子たちを感じる」と彼は言った。
利菜はもうヒッピの手を払いのけている。まるで目の前に佳代子たちがいるみたいに強烈に感じる。それにパワーだ。グループの到来とともに、利菜の力も戻りつつあった。今では仲間たちと強力にむすびついていた。あのパワーが戻ってくるのを感じる。血流を加速させ、脳の出力を全開にする。紗英も達郎たちもいる。利菜はその方角を向いて、みんなの居場所を探ろうとする。視界が輝いた。かと思うと額の裏に石造りの牢獄が映る。城の中だ、と彼女は言ったが、それは耳栓をしたときのような声に聞こえる。頭の中の光景に向かって駆け出そうとした。それを止めたのは彼女に組み付いたヒッピたちだったし、背筋を走る蛇のような怖気でもあった。その鱗が神経を削り彼女を凍り付かせる。
何者かの目線を感じる。
マーサが意識を遮断するんだと叫び、ヒッピが利菜やめろと彼女の肩を揺さぶった。けれど、そのときにはもう遅かった。
何者かに心をつかまれるのと、心臓が止まるのは同時だった。利菜の心はあの方だあいつだと叫んでいたが、体はピクリとも動かず声を発することもできなかった。精神に入りこんだ異物に抵抗するように、全身の筋肉が強張ったからだ。泡を吹いて硬直する。目玉が白目をむいて、頭の中で白色の閃光が炸裂した。利菜はみんなにそいつの正体を知らせようとするが、すでに意識は遠のき、自分の意思では舌も動かせない。
――聖櫃がなくては、おれには勝てんぞ
と自分の口が言う。利菜は信じられない怪力でまとわりつく友だちをはたきおとす、ペックたちは肩から地面に衝突した。ヒッピだけがとっさに手をはなして、利菜の背後に回りこんだ。彼女の後頭部に手をあてると、利菜の精神に入りこむ。ヒッピは利菜の中にいるどす黒い大海のような精神に怖気をなしたが、それでもそいつを追い払おうとした。今の利菜は全くの無防備だったし、トレイスにとっても完全な不意打ちだった。
バチン、バチンとゴムの弾けるような音がして、二人はその場に倒れこむ。利菜は体から一人分の体重が抜け出ていくのを感じた。
「利菜」
とマーサが抱え起こした。利菜は、あいつだ、あの方だよ、と彼女の腕をつかんだ。「トレイス……」
「やはりトレイスか」とうめく。
利菜は懐かしい気配を感じた。佳代子たちの到来は、いいものばかりを呼び寄せなかったらしい。利菜はこの世界に来て以来、わるいものを見ていない。なめ太郎も坪井の姿も見なかった。あの世界から切り離されて、ある種、孤島のように独立していたのだが、その離れ小島もとうとう奴らに見つかったらしい。
死の気配が毒の噴霧のように空気を満たし、とぐろのようにまといつく。佳代子たちが窮地に陥っている、と利菜は信じた。みんな生きているけど、死のコースターを滑り落ちるまで、後一歩のところにいる。
みんなを助けなきゃ……
利菜はそっと腕をついて身をおこす。ヒッピも体を回して立ち上がると、利菜と同じ方向を見た。ヒッピは、利菜とこの世界とをつなぐ、孤独でひ弱な桟橋である。けれど、今は利菜が逆の役目を果たすことになったようだ。
利菜は恐怖に負けて下を向いた。ヒッピが荒い息をついてうめいた。
「くそう、わるいものだ」
わるいものだ……
顔を上げると、路地の真ん中に、坪井善三が立っていた。そいつをみた瞬間、彼女の心臓は何分の一かにまで縮みこんだ。坪井はあいかわらず脳を露出させて、舌の先に虫をまといつかせながらニタニタと笑っている。彼はふざけて首を振ったから、脳漿が左右の壁に飛び散った。視線を感じて左を向く。と、溺死女が立っていた。右側には登美子がいる。彼女の口もとは血まみれで、佳代子を喰ったのはあたしだよ、と言った。
「うそだ」と利菜。「佳代子は生きてる。あの子を感じるもん!」
それを否定するかのように、大粒の雨が落ち始めた。ペックたちが悲鳴を上げた。あれは利菜の世界のモンスターなのに、彼らにも見えているらしい。戻ってきたぞお、という声がして頭上を見上げると、なめ太郎がひもにぶら下がりながら、振り子のように飛び交っている。戻ってきたんじゃなくて、やってきたんじゃないか、と彼女は言ったが、これは言葉にはならなかった。溺死女が彼女の大口に冷えて濡れた手をつきこんできたのだ。溺死女はおかまいなしに腕をつきこんで、彼女の喉の裏壁にまで触れかけた。ヒッピが夢中で溺死女の腹をついた。女は着物をびちゃつかせながら路地の塀に腰をぶつけた。女がひいひいと非難の声を上げる、ペックとモタは泣きながら抱き合う。
「くそう、なんだこいつは!」
パーシバルは、装填レバーをひいて薬室に弾丸を送りんだ。
「よせ、パーシバル! 同士討ちするぞ!」
とヒッピが怒鳴る。その刹那も、利菜はなめ太郎から目を離せない。目をいっぱいに開き、そのせいで大粒の雨がバチバチと目玉を叩いている。なめ太郎は、腰紐で天からぶら下がっている。傲然と腕を組んでいる。彼の背景に雷が、カッカッカッ、とコマ回しのように切れ切れに落ちる。
空間がゆがんで、路地は狭まったり、広がったりした。ナバホ族ですら平衡感覚をなくして倒れこんだ。彼らも自分たちの恐怖に基づく幻覚を見ていた。その中で、なめ太郎と利菜だけが対峙していた。
みんな死んだぞ、上原、なめ太郎は先生のような傲慢さで言った。そんなことない、と利菜はいいかえした。みんな生きてる、みんなあたしのこと迎えにきたもん!
「迎えだと!? 帰れるもんか! みんなここで死ぬんだ!」
となめ太郎が何かを投げた。利菜はそれをゴムボールだと思ったのだが、なめ太郎が投げたのは生首だった。空中で、それはいくつにも分裂して地面に転がる。利菜の足元に転がってきたのは佳代子の生首だった。ヒッピの足元に転がったのはタットンの生首だ。父上、とビスコの悲鳴がする。生首は雨池のできた路面をびちゃびちゃと転がりながら奇声を上げ始めたから、利菜たちは互いの怒鳴り声も聞こえなくなる。滑稽なことにそれはなめ太郎も同じのようで彼は顔をしかめては、耳に手を当てる仕草をした。
「ちくしょう! この大嘘つき!」利菜は天に向かって拳を突き上げる。首はどんどん増えて、紗英や達郎、彼女のメンバーが首だけでそろいはじめた。こんなのうそだ! みんな死んでない! 利菜は涙を浮かべて震えながらも、なめ太郎を睨み上げる。
「おまえなんかにやられるもんか――!」
真横から登美子に突き飛ばされた。利菜は壁に頭をぶつけて、倒れこんだ。雨をはね飛ばしながら、びしゃびしゃと転がる。頭から血が流れおち、水面にぽたぽたと波紋をつくる。貴族街の排水施設は馬鹿になったようで、路地は今ではちょっとした小川になっている。
泥水を吐き出しながら立ち上がろうとすると、溺死女が目の前に立っていた。その間も水位はどんどん増している。
「なんとかおし!」マーサの声がすぐ近くでする。「みんな殺されちまう!」
利菜にその声は聞こえなかった。溺死女が頭をおさえつけ溺れさせようとしていたからだ。ヒッピたちが肩を組んで体当たりをし、溺死女を突き倒した。
ヒッピは咳きこんでいる利菜を助け起こす。急な豪雨に息をつまらせながら、仲間たちに言った。
「みんな力を貸せ! ここに集まれ!」
利菜は胃袋の中身をげえっと吐いた。そこにいたわるような目をして(口元はちゃんとわらっている)佳代子の生首が転がってきた。里奈は涙に曇る目で、
「おまえは佳代子じゃない」と言った。怒りに燃えて立ち上がると仲間たちを集めた。
「円陣を組むのよ!」利菜は髪をかきあげ、水をふくんですっかり重くなったローブをたくし上げる。ヒッピたちと手を取り合った。ふりむくと、
「マーサおばあさん、力を貸して!」
マーサは這々の体でやってきた。ビスコもどうにか。ノーマはあやうく溺れるところだったが、トゥルーシャドウが負ぶいあげた。ナバホ族の肩の上から、人環を見つめている。
彼らは真っ暗闇のなかで互いを信じようとした。闇を助長するように光のない雷の音が、ほんの一メートル脇に落ちるような大音響で体を満たす。彼らは細胞の一つ一つにいたるまで身を震わせながら、互いの手をしっかりと組み合わせた。
利菜は目を閉じ、震える胸に大きく息を吸いこんだ。二つのグループの力が環を巡るようにして高まるのを感じる。なめ太郎たちは人環を崩そうと、生首を投げつけだす。ペックは鼻面に頭突きを喰らって、血を噴き出した。トゥルーシャドウたちは子どもたちを守ろうと、円陣の外にさらに陣を張った。
利菜は額をわずかに仰向けて、退け、と心に強く唱えた。雨粒が非難するように顔を叩いた。それは滝のように彼女の鼻筋や頬を流れ出す。けれど、鋭い力が全身を満たして、そんな妨害も気にならない。利菜はさらに強い気持ちで念じた。わるいものを追い払うのが強い意志であることに疑いはなかったからだ。マーサは呪文のような意味不明な言葉を唱えつづけている。パーシバルたちはひとりでに鼻血が出てくるのを感じていた。血流の高まりに、毛細血管が耐えられなくなったものらしい。三人ともこんな力になれていないのである。
利菜は友だちをはげまし、マーサの力も借りて、一同の心をつないでいった。みんなが抱いた意思はたった一つだった。彼らは互いを信じていた。
肯定感の高まりとともに、わるいものは潮のように引き下がっていく。なめ太郎以下わるいものたちは悲鳴を残して、空中にすぽんと吸い込まれた。どしん、という音がして、世界は縦に揺れた。周囲の庭園の樹木では、梢がいっせいに雫を落とし、そのザーザーという音がみんなの高ぶった鼓膜に聞こえた。足元の水が下水を目指していっせいに流れていく。
その一瞬、王国の全ての戦場では束の間戦闘がやんだ。みな心の奥底では何かが起こったことに気がついたようにも見えた。けれど、降り続く雨と共に戦闘は開始された。
わるいものは去ったが、豪雨は残った。みんなは篠突く雨の中、呆然と互いの顔を見合ったのだった。
□ 六
やっぱりだ、とヒッピは言った。
「やっぱりサウロンの探している装置は利菜の世界にあるんだよ。神官たちは二つの世界をつなぐために、ずっと儀式を繰り返してきたんだ。それなら、利菜がこの世界に来たのにも説明がつく」
「だが、師匠がなぜこの子の世界に?」
とマーサも疑問を持った。
「その子を……」とトゥルーシャドウもやってきた。「元の世界に戻せば、装置を取り戻せるのか?」
「だが、それだけでは、トレイスを殺せんぞ」とスラブたちも話に加わる。「少なくとも、エビエラと同じやり方で封じこめることは出来るかもしれないが。エビエラのことだ。向こうの世界に何か手がかりを残しているかも知れない」
利菜はさっと銅の鏡のあったお堂を思い浮かべた。ヒッピがすぐに考えを読みとって、
「いや、あのお堂は入り口のあった場所だ。あんなところに秘密を隠したとは思えない。君の世界には、何か装置に関わる伝承はないのか?」
「あるわけないよ。別の世界があること自体知らなかったのよ。こんな話、佳代子たちにしたって信じっこない。知ってるでしょ?」
けれど、ヒッピはうなずかない。
そのとき、路面にうずくまっていたフロイトが(彼のマントはぐっしょりと濡れそぼり、実に重そうだ)、
「トレイス様が来るぞ……なにをするつもりか知らないが、早くしなければ」
「トレイスがここに来るのか?」
スラブが城の方角を見やった。
「あの方には私の居場所がわかるのだ」
みな沈黙して、互いの意見を待った。殺せない相手とどう戦うんだ?
ヒッピが、「佳代子たちはたぶんこっちの世界には来ていない。向こうの世界でゲートを開いたんだ」
「ゲート? 次元の裂け目のことを言っているのか?」とフロイトは苦しげに身をおこした。「それなら、城の地下にある。トレイス様が幽閉されていた場所だ」
いいだろう、とスラブは武器を取り上げ、トゥルーシャドウに言った。「我々で時間を稼ぐ。おまえはこの子たちをゲートに連れて行け。元の世界に戻すんだ」
「装置は向こうの世界にないかもしれない」
「賭けるしかなかろう」
と言って、彼はサイポッツの子どもたちを見た。彼だって、こんなことを託したくはない。けれど、子どもたちの力は今見たばかりだ。彼らはマーサの目前にひと揃いして膝をついた。
「無茶を申しているのはわかっております。が、後のこと、おまかせ出来ますか?」
利菜はマーサがこの申し出を突っぱねると思った。普段の彼女ならそうしたはずだ。けれど、スラブたちは命を投げ出すと言っているのである。マーサはかすかな吐息すらつかず、スラブたちのたくましい肩に手を置いた。
「わかったよ。必ず聖櫃を持ちかえり、あの男を食い止めよう」
□ 七
佳代子たちの出現以来、利菜の力は急速な成長を遂げていた。彼女はその卓越した直感力で仲間たちを導いていった。
雨は幾分弱くなっていた。戦いの余熱を奪うほどでもない。風はなく、静かに泣く女のように、しっとりと貴族街を濡らしている。
「このまま、まっすぐのぼろう」と彼女は坂を指さしていった。「トレイスもまっすぐ降りてきてる」
「一人かい?」とマーサが訊いた。利菜は首を振った。
「兵隊を連れてる。でも十人もいない」
と利菜は言った。その言葉に、ビスコとノーマは希望を燃やした。彼らは別の人間にのりうつるなど信じていないのだ。それにサウロンの能力も知らない。彼の能力をいやというほど知っているマーサはトゥルーシャドウの隣で(ノーマを背負っている。この男は護衛だけあって、二人の魔女――と彼は思っている――の側を片時も離れようとしなかった。)物思いに沈んでいる。利菜はマーサの手の甲をそっと叩いた。
「行こう。装置がどこにあるかわかんないけど、なんとしても手に入れなけりゃ」
と彼女は言った。佳代子たちが生きていたことで、彼女の希望もぐんと燃えていた。
親衛隊の警備は上に行くほど手薄だ。丘の上から見下ろすと、貴族街の火の手が見えた。それに、赤々と燃える、東の空。ヤクハタ人たちはまだ戦いを続けているようだ。
銃撃の音は散漫になっている。ナバホ族の部隊は親衛隊とダンカン人を相手に肉弾戦を行っていたが、少年らのグループは統率者をなくして散開しつつあった。
利菜は仲間の先頭に立って、トゥルーシャドウたちを先導していった。ときおりマーサの意見も聞いたが、どのみちを通れば安全かが神様よりもよくわかる気がした。道はいくらでも分岐しているのに、彼女には一本道のように感じられた。ヒッピたちは銃を担いで走っている。利菜の足があんまり速いものだから、つい遅れがちとなっていた。アドレナリンが心臓をぐるぐる回している。かけっこも遅いぐらいなのに、今はいくらでも走れる気がした。
「トレイスはどうだ? かわせるのか?」とビスコが訊いた。
「あいつは無理だよ」と彼女はフロイトを見る。「あいつを目指してきてるもん」
「我々でどうにかする。心配するな」とスラブが言った。彼はいま気がついたようにふりむき、「フロイトが裏切る心配はないのだな」
「それはないよ。あいつもトレイスを怖がってるもん」
「よし」と彼は仲間をかえりみた。この場にいるのは、スラブをのぞいたらみな若者ばかりだった(利菜はナバホ族の年まで把握できるうようになっていた)。「トレイスとてサイポッツであることにはかわりがない。臆するな! ここまで世話になったな。かなうかどうかはわからんが、奴のことは任せろ」
ビスコは頬を紅潮させながら、スラブの腕を握った。「世話になったなど、こちらの方だ。おれはどう恩をかえすべきかわからない」
「ならば我が子孫に頼む」
とスラブは言った。若者たちが小声で笑った。スラブは利菜の痩せこけた肩に手をおいた。そうしてみると、この娘はますますもって小柄に見える。
「ナバホ族の勇者にもない勇敢な働きだった。今生の別れだろうと、おまえのことは忘れない」
「気をつけて」
スラブは微笑みを残すと、仲間を連れて立ち上がった。みな抜剣している。
利菜たちはそこからはゆるゆると登った。スラブたちは路地を回りこんで、側面から挟撃する作戦である。ナバホ族がいなくなると、利菜たちは急に心細くなった。トゥルーシャドウは残ったが、ノーマとフロイトは満足に動けない。後はマーサとビスコがいるだけで、子どもばかりが目立つようになった。
「ナバホ族はたぶん勝てないぞ」とヒッピは利菜にだけ聞こえる声でささやいた。ほとんど声を出していないが、指をふれているだけで互いの考えがわかるようだった。「あいつは乗っとった相手の能力も会得してるはずだ。ぼくらがそうだった」
利菜はうなずいた。あいつは狙撃の王でもあるし、剣術の達人ですらあるかもしれないのだ。
子どもたちは銃をかまえてにじり足のようにしてジワジワと丘を登った。突撃のラッパが鳴り響いたのは、利菜が丘の下を顧みたときだった。貴族街ではあちこちで火災が起こり始めていた。その火を知らせる警鐘のように親衛隊から奪ったラッパの音が高らかに赤い夜空を引き裂いた。
「隠れろ! 隠れろ!」
とビスコは子どもたちを路地の側面に押しやった。ナバホ族は考えていたよりずっと近くで戦い始めたようだった。視界の端に激突する両者が見えた。パーシバルは銃を抱えて、路地を飛び出そうとした。ビスコがその襟首をつかまえる。
「助けようぜ、トレイスを仕留めればいいじゃないか!」
「馬鹿を言うな、トレイスは殺せないかもしれん。おれたちは……」
一同は路地の奥にいき、物陰に隠れた。利菜は周囲に気を散らして安全な道を探った。ここで親衛隊に見つかったら、ひとたまりもない。
「周りに兵隊はいないみたいだね」
とマーサも気配をさぐって言った。サウロンにも、十分な手駒は残っていなかったらしい。
ビスコは長銃を抱えながら、樽の後ろから身を乗り出した。目の前ではナバホ族の巨大な背中がいくつもゆらめいている。ナバホ族の怒号が響き渡り、サイポッツの歓声もそれに唱和した。
「この声はトレイスなのか?」
ビスコは我慢できずに樽の外に出た。正面の大通りをナバホ族とサイポッツたちが転がるように駆けてくる。利菜は銀髪の男を見つけて、ビスコの腕を叩いた。
「オットーワイド!」
とビスコが叫び声を上げた。利菜はびっくりして彼をみた。
「何言ってるの? あいつがトレイスだよ」
「ちがうそうじゃない」とビスコは彼女を見おろし、もう一度通りに目を向ける。利菜は彼を下がらせようと、服の裾を引っ張った。通りではサイポッツらの銃火がいくつも火筋を描いている。ナバホ族は兵士を血祭りに上げながらオットーワイドに打ち掛かっていた。
「あいつだ、あいつが父上を殺したんだ」
「ビスコ、駄目だよ!」
利菜は駆け出そうとしたビスコの右足に組み付いた。彼ははっと我に返って、利菜を見おろす。その顔がだだっ子のように泣き崩れるのをみた。
「おまえたち、世話になったな。ここでお別れだ」
「馬鹿なことを言うな」とノーマが声を励ましいった。「戦争を止めても、新国家を建設しなければならないのだぞ! こんなところで死ぬ気か」
「そんなことまでおれが気にしなくちゃならないのか。もう十分やったよ。後はすきにさせてくれ」
「何言ってるの? あれを見なよ」
オットーワイド――トレイスは、ナバホ族を相手に大暴れに暴れている。信じられない体さばきで群がるナバホの剣筋を外し、悪鬼の形相を振り乱しながら剣を急所に突き刺していく。スラブたちは捕まえることもできない。
トレイスは老人だろうに(それもかなりの痩身だ)異様な怪力を示してナバホ族を撲殺せんばかりの勢いだった。利菜にはなんとなくその理屈がわかる気がした。彼女にも同様のことが起こっていたからだ。それにあいつに体を乗っ取られたとき、とんでもない力が出た。
パワーだ、あいつもパワーをうけてるんだ!
その思考が正しいのか正しくないのか彼女にはわからなかった。でもあいつがふつうじゃないのはわかる。
「あんなのと戦ったら、あんたもただじゃすまないよ。殺されるってわかんないの!」
「仇をとるんだ! 生死など問題ではない!」とビスコは言った。その形相のすさまじさにヒッピたちも黙り込んだ。彼は怒りと悲しみにくれている。そして、それはビスコの足にふれている利菜の身にも伝わってきた。あいつがビスコに何をしたのかそのときのビスコの情景まで伝わってきた。彼がお父さんをどんなに愛していたか、どんなに愛されたがっていたのか、愛したがっていたのかも。オットーワイドはその両方の可能性を奪ってしまった。ビスコの中では怒りと悲しみがせめぎ合うように高くなっている。そいつは彼の心を満たし、満タンになると、滂沱とした涙となった。
「政府をつくるんでしょ」利菜は彼の悲しみがわかったが、それでも自分は冷静でいようとした。「犬死になんかしちゃだめだよ」
ビスコは涙を拭いもしない。ただ、決然と顔を上げて、利菜のことを説得している。彼の顔から落ちかかる涙は万の言葉よりも雄弁だった。そして、それらは全て真実だと彼女にはわかった。彼は利菜の言葉に落胆している。彼が欲しがっていたのは理解だけである。
「おれが欲しかったのは、政府なんかじゃない。死に場所だ」
利菜は手を離してしまった。これまでの努力も変化もこのときのためだと彼の肌が語っていた。
「行かせてやれ」
トゥルーシャドウが利菜の肩を抱いた。ビスコは銃を抱えると、いちもくさんに駆け出した。利菜はもう遅いと知りながら、彼に向かって手を伸ばした。目の前に伸びた自分の白い指の向こうで、ビスコの躍動する背中が遠くなり、通りの角に消えてしまった。
利菜は呆然と膝立ちになりながら、ゆっくりと手が自然に降りるに任せた。
「そんな馬鹿な……」とノーマは言った。自分は死に瀕し、盟友も死地に赴いてしまった。
「死にたがる奴もいる。あいつを責めるな」
とトゥルーシャドウは言った。仲間の仇をうつということに関して一家言ある彼は、ビスコの気持ちが誰よりもわかるのだろう。
「行こう」とマーサは利菜の肩をやさしく抱いて揺さぶった。
利菜が首を左右に振ると、トゥルーシャドウはノーマを背負い上げた。子どもたちはこのサイポッツであらざる大男を見上げた。
「おれたちにはやるべきことが残っている。この世のことは全て生きている者にしかできないことだ。奴らはそのために命をかけてくれた。我々がやらなければ、今日天に召された者は全て犬死にだ。そのことを忘れるな」
ヒッピがうなずいた。ペックたちも後に続いた。彼らは、行こう、行こうと、無言でうなずきあい、互いの銃先をふれあわせる。自分たちが殺した相手に誓うみたいに。
□ 八
城に近づくほどに、利菜の、おさそいにはまった、という感覚は強くなった。なによりもそこは人の死でいっぱいだ。
「戦争の危険を感じ取った貴族たちが、城内に集まったのです」とフロイトは説明した。中で何が行われているか、知っているようだった。「あそこが安全だと思ったのでしょう」と首を左右に振る。その仕草は諦観にみちていた。
城の外壁をついに見上げる位置に付いたとき、彼らはぎょっと息をのむことになる。フロイトですら、城壁はおまもりさまで見たあのつる壁がみっしりとはびこっていたからだ。つる草からは雨の雫がぽたぽたと垂れ落ちていたが、よくみるとそれは真っ赤な血なのだった。堀は血液で満ちて、人の死体が浮いていた。そいつらはなぜかたこやきを職人が返すみたいに、一定のリズムで上を向いたり下を向いたりしていた。それで利菜は確信したのだった。どうやら自分はおまもりさまに戻ってきたらしい。
城門に近づくとわずかに開いていた。けれど、フロイトは入ることをためらった。門の隙間から真っ赤な目がいくつも覗いていたからだ。
「おまえはどこからやってきたのだ?」
とトゥルーシャドウが訊いた。トレイスがこの男を安易に出すはずがないと思ったからだ。
フロイトが出てきたのは水門からだった。数人の親衛隊士の死体があったが、それを殺したのはフロイト自身である。
城内は灯りがともっていたが、窓から見える人影は狂喜乱舞の真っ最中だった。逃げ惑い叫び声をあげ、ときおり窓ガラスに血痕が散った。
「あそこに入るのか!」
とパダルが言った。それはあまりに大声だったので、隣にいたヒッピとペックはすぐさま口をふさいだ。
けれど、それは城の中に控えるわるいものの面々にはしっかりと聞こえたようである。城内は急に静寂に包まれて、ザーザーという雨音が高く耳に響くようになった。
利菜たちは恐る恐る城を見上げた。そして、ひっと声を上げた。城内の全ての窓に人が立っていた。何百人というサイポッツたちが、一様にこちらを見おろしていたのである。
□ 九
利菜たちはいっせいに駆け出した。城の樹木も一緒に走った。根っこが無数の足になり、パーシバルたちに追いすがる。少年たちが発砲すると、常緑樹たちは、弾丸を受けるたびに悲鳴を上げる、傷口から噴血をあげて、少年たちを濡れそぼろかす。
トゥルーシャドウはフロイトに言われるままに、勝手口のドアを蹴り開けた。
「ここからが、回廊には一番近い。中に……」
トゥルーシャドウの後ろにいたフロイトは彼の脇から中を覗いて黙り込んだ。同時に、この巨漢が立ちどまったわけもわかった。そこは城の料理場である。
中では、真っ白な高帽子とコック服に身を包んだ太った男たちが(なぜかどの男も見覚えがなかった)、でかい包丁をふりかざして料理の真っ最中だった。まな板に乗るのは人体である。太ったコックたちはそいつを切り刻んで生肉のまま口に運んでいる。その場を見つかったのに恐慌したように悲鳴を上げ始めた。包丁を振りかざした。ヒッピたちもすくみあがって、絶叫した。
「発砲しろ!」
トゥルーシャドウがふりむき、号令すると、ヒッピたちは夢中で銃を上げた。狙いもつけずに轟音を轟かせた。
少年たちはしばらく引き金を引き続けた。弾丸がなくなって、かちかちという音がしてもしばらく引いていた。料理場の戸口は硝煙が真っ白に立ちこめて、料理台の足元でぴくぴくと震えているコックたちを隠していた。
「何事だい、こりゃあ」
マーサはみんなを励ますようにいったが、残念ながらその声すら震えていた。みんな無言だった。自分たちの犯した殺人と、コックたちの犯した凄惨な殺人の現場に気をのまれてしまったのだ。いち早く、現場に立ち戻ったのは利菜だった。彼女は階上から響く無数の足音に気がついたからだ。
「急いで!」と利菜は言った。「あいつらが来る!」
あいつら、というのが誰なのか、みんなは訊かなかった。訊かなくても一言で説明が出来たからだ。
殺人者たちだ。
一同は血で滑る料理場を抜け出した。小振りな食卓を抜けて(元は料理人たちのためのもので、今ではおまもりさまの珍味で満ちていた)、廊下に出た。ヒッピは夢中で仲間を叱咤して、走りながら弾ごめをさせた。トゥルーシャドウがいるとはいえ、あまりに多勢に無勢である。
廊下に出ると、ほとんど半死の男女が両手を掲げて襲いかかってきた。ヒッピたちは夢中で発砲した。トゥルーシャドウも斬った。背負われたノーマが激しく呻いている。傷口がどんどん開いて、トゥルーシャドウの動きに苦しんでいるのだ。
「ノーマ!」
と利菜は言った。彼の傷口の開きようが尋常ではなかったからである。
パーシバルが、全員殺す気か! とヒッピにいった。
「撃つんだ! 殺されてしまうぞ!」
フロイトは回廊の鍵を元の場所から盗み出していた。彼らは群がる(自殺)志願者たちを殺害しながら進んだ。みんなが、もうこんなことはいやだ、と心が折れかけていた。でもやるしかない。状況が逃げることを許してくれない。
利菜はふと我にかえって、貴族街の方角を向いた。サウロンに抵抗していた最後の一人が殺されたようだった。
◆第二十章 ねじまげグループ、世界の果てにいたること
□ 十
フロイトが一行を導いたのは、かつては、不慮の事故が頻発し、近づくすらを禁じられた区域である。七不思議のご当地として知られていたが、ペックは、ここに禁断の扉があったのなら、殺人や幽霊話にも納得が行く気がした。
その一角には、火が入らず、闇が深かった。サウロンが復活していらい、足を踏み入れたのは、彼らだけだろう。絨毯は、塵積もりとなり、元の色を隠している。管理者であるスミスが死んで、禁忌の場とかしたのだ。
トゥルーシャドウがランタンをかざした。蜘蛛が音をたて、幾何学模様の巣がきらきらと輝いた。足音はどんどん近づいてくる。なぜか太鼓や銅鑼音までした。
最後の抵抗者たちは、次元回廊につづく地下扉にたどりついた。ヒッピたちは折膝をしいて、廊下からやってくる貴族たちを銃撃した。
フロイトが花瓶の載った台をどかし、絨毯をめくると、扉があらわれた。フロイトはその扉をみて臆したようだ。トレイスを救い出してからこちら、開けたことがない。
内側からは、まがまがしい気配がただよいだし、人の進入を阻止している。地下扉に鍵をさしこもうとしたが、指が激しく震えてどうにもならない。利菜が鍵をうばって、鍵穴に差し込むと、地下扉は溶けるようにして下に落ち、体重を預けていた利菜も数段階段を転がり落ちた。
「利菜!」とトゥルーシャドウが覗きこんだ。「大丈夫か!」
利菜は頭のこぶをさすりながらうなずく。
階上では、ヒッピたちが、銃から生えだしたつる草に苦慮していた。そいつらは先端から血を吐きながら、呪いの言葉を唱えだした。ヒッピたちは銃を放りだした。
「もういい! 中に入れ!」
トゥルーシャドウはノーマを階段におしこむと、少年たちを地下へと追いやった。
トゥルーシャドウは階段に飛び込むと、下から扉を押し上げた。殺人者たちは(それは豪華なドレスやタキシードを着た高級貴族たちで、狂犬よりも悪辣な顔をしている)追いすがって、爪でひっかこうとした。トゥルーシャドウをわるいものに変えようとしたのだが、その前に扉がしまった。トゥルーシャドウが押したというよりも、一人でに押し上がって、ピタリと空間を閉ざしてしまった。
ガチリ、という音がした。
しばらくそよ風が利菜の髪を揺らしていた。みんなは扉のあった辺りを見上げていた。そこは本当に真っ暗で、扉の縁すら見えない。トゥルーシャドウは扉を撫でようとしたがあきらめた。ランタンの灯りが消えかかるように揺らめいた。マーサが確かめると、灯りはしっかりとともっている。
「急いだ方がよさそうだね」
とマーサはランタンを掲げた。そこからは曲がりくねった階段が、無限とも思える長さで暗闇の中に沈んでいる。
「この下にサウロンがいたのか?」ノーマが訊いた。
「三百年も? 冗談だろ?」とパーシバルが言った。
一同は、下りる前からおじけづいた。
おかしなことは他にもあった。フロイトが見たとき、階段はこんなに長くなかったし、曲がりくねってもいなかった。左右には壁があったし、松明もともっていた。今は松明も壁もなく、ただ暗黒が横たわるだけである。階段はその暗黒に陽炎にように浮かび上がっているのだった。
ヒッピは、階段を見下ろしながらマーサに囁いた。「本当にゲートは開くんですか?」
「魔法に必要なのは、集中力と教えたろう。儀式だっておんなじさ」とマーサ。
一同は階段を下りた。左右の闇からは、悲鳴や笑い声がかすかに聞こえた。城内の物音らしい。肉を斬る切断音、肉を叩く音、骨をひしゃぐ音、つねる音、殺人に関わる全ての音が聞こえるみたいだ。利菜はランタンを受け取ると、弱気になる一同を照らすように灯りを掲げた。すると、ランタンは彼女の心情をあらわすように光を強くした。
近づいている。佳代子たちはすぐそばまで来てる。
利菜が先頭に立つと、階段はさほどの長さもなく、廊下に行き着いた。フロイトが、
「ここは回廊だ。エビエラの築いた牢獄じゃない」
どのみち急いだ方がよさそうだ。とマーサは言った。ここはあまりにもわるいものの影響が強すぎる。みんな青白い顔をして今にも吐くか卒倒するかをしそうじゃないか。
「今から儀式を行う」とマーサは言った。「と言っても、歴とした神官は二人しかいないが……」
「一人だ」とトゥルーシャドウは言った。彼はノーマを廊下に横たえている。ノーマの顔はランタンの灯に照らされて、ぞっとするほど青い。「彼は死んでしまった……」
「ああ、そんな……」とペックが言った。みんなはそのあまりに深い悲嘆の声にすくみあがった。「彼が死ぬなんて。彼まで死んでしまうなんて。もうどうすれば……」
「落ち着くんだ」
マーサがペックの腕をとると、ヒッピは彼を抱き寄せた。ヒッピも青い顔で唇を噛んでいる。二人の少年はこの青年を兄とも慕うことが多かったのだ。
利菜は少しだけ涙をこぼしながら、ノーマの目を閉じてやった。わるいものはとうとうこの青年の命をも奪ってしまった。これまで一生懸命抵抗してきたけど、それも終わってしまったのだ。死んだノーマの顔はいやに孤独で、そのことも彼女の悲嘆を大きくした。ここまでよくやったね、と彼女は心の中でつぶやいた。語らないノーマの横顔が陰ろい、何かを映すようにも見えた。
□ 十一
「トレイスはすぐそこまで来てる」と利菜は言った。
「確かにここは力の集積地だ」とマーサが言った。「次元のねじれが強い。なんとかなるかもしれない」
利菜はうなずいて、ヒッピたちをみた。少年たちはなんとなくノーマを取り囲んでいる。死者を悼む参列者のようだったが、まさにそのとおりでもあった。
「みんなはあたしの世界に来られないの? 向こうで一緒に……」
「ぼくらは行かない」ヒッピは真っ先に否定した。パダルとモタが非難の目を向けた。「こちらに誰か残っていないと君たちを呼び戻せない。なにより、向こうに行って、戻ってこられる保証もない」ヒッピは顔を上げた。利菜と視線を合わせた。「ぼくらの世界はここなんだ。それにみんながまだ戦ってる。逃げるなんてできない」
「でも……」
「利菜、もういいんだ」とマーサは利菜の腕をとった。「ゲートを開こう。おまえにはやるべきことが向こうであるはずだ」
利菜はうつむいた。ヒッピが立ち上がった。利菜の前に立った。すぐ近くに。
「ぼくは君にこっちに戻って欲しいとは思わない。向こうが安全ならいいって、そう思ってる」とヒッピは言った。それは真実であると彼女には強く感じられたから、うなずいた。「君とぼくは精神がつながっている。でもその影響だとは思わない。君のことが自分のことのように大事だ。生きて欲しい」
利菜は目を閉じて頷いたから、冷たい石の回廊に涙が散った。ヒッピは利菜の腕を握ったまま、仲間たちを顧みた。
「決着をつけよう。ぼくらは協力してどんな問題も乗り越えてきた。今日が特別無理だとは思わない。利菜を元の世界に戻してやろう」
「その後は?」とパーシバルが言った。彼の鼻は赤い。その鼻筋の脇を涙が流れた。「おれはおまえみたいにご立派には語れねえよ。その後はどうすんだよ」
パーシバルはその場に膝をつき、二の腕で顔をおおうと泣き崩れてしまった。みんなはそんな彼をどうすることもできない。わるいものが彼らを弱気にし、結束をくずしかかっていた。
「おれ、おれ、人殺しなんかしたくなかったよお。でも、あいつらが向かってきたんだよお……」
パーシバルが言うと、みんなは無言で熱い涙をこぼしはじめた。今日、初めて人を殺したけど、そのことが子どもたちの心に本当は重くのしかかっていた。ヒッピはパーシバルの頭を抱いて、ずっと年長の少年がそうしてやるように、やさしく頭をなで始める。
「わかってる。わかってるとも。おまえは人殺しなんかするような奴じゃない。おまえはやさしい奴だってみんなわかってる。神様だってわからずやなもんか」
「おれたち地獄に堕ちるのか?」
「堕ちはしない。例え堕ちても、ぼくらは離れない。地獄だって切り抜ける。そうだろう?」
ヒッピの問いかけに、みんなは一人一人うなずいた。
「ぼくらは死ぬかもしれない。だけど死ぬときはみんな一緒だ。おまえが側にいてくれるんなら、ぼくは怖くなんかない」
パーシバルはようやく顔を上げた。「おまえも側にいてくれんのか?」
「ああ、絶対に側を離れない」
パーシバルはまた顔をうつむかせた。声を上げて泣きそうになったが、どうにか涙を引っこめた。そうすることで、心にわいた弱気の虫もひっこめた。パーシバルはつとめて笑顔をつくり、
「だったら、なんの心配もいらねえな」と強引に涙を拭った。「みんな集まろうぜ。おれたちはグループなんだ。いつだって一つにならなきゃいけない」
少年たちは手をとりあう。利菜も加わる。そのとき、回廊はすごく狭くなっていたけれど(子どもたちをおしつぶすみたいに)、そのときだけはまた元の広さに戻っていた。フロイトもトゥルーシャドウも、マーサもその光景を少しうらやましげに眺めた。
「グループは絶対に裏切らない。絶対に助け合うんだ。この規則は絶対だ」
パーシバルが今はすっかり古めかしくなった文言をいうと、みんなは少しだけ笑顔になった。
リーダーのヒッピが、一人一人の顔を眺め渡して言った。
「よし、もういい。もうみんな大丈夫だ。ゲートを開こう」
□ 十二
異変に気づいたのはマーサだった。
マーサはフロイトの姿を探した。彼は離れたところにいて、そこは、光が届くぎりぎりの距離だった。彼はおおかた闇に沈んでいる。不審に思ったトゥルーシャドウが、ランタンを掲げて近づくと、彼は短剣を抜いている。
「なんのまねだ」とトゥルーシャドウは訊いた。彼は短剣を奪い取ろうとしたが、フロイトも躙り下がる。
「ようやっと、ようやっと肩の荷が下りた気分だ」とフロイトはマーサを見る。「あなたのおかげだ。あなたは私をわかってくれた。私のしでかしたことを」
マーサはフロイトの考えを察し、諭すようにいった。「やめるんだ、フロイト」
「だめだ。トレイスさまには私の居場所がわかる。その少年と少女と同じだから。私はあの方につかまったままなんだ。じきにここにくる」
「何も死ぬことはない……」
「私はここまで必死にこらえてきた。だけど、もう」涙が落ちる。「自分で自分を保っていられないんだ……」
フロイトは短剣をのどにあてがい、真横にひいた。トゥルーシャドウがとめる間もない鮮やかさだった。フロイトは鮮血をまきちらし、最後の支えすらなくした枯れ木のように倒れる。彼の硬直した身体は、固い地面を揺らした。動脈は、完全に裂けていた。トゥルーシャドウが、布をあてがう。生き血が指を濡らした。ケタケタと笑い声が回廊の奥でした。
マーサがフロイトの傍らに膝をつき、その頭を抱き上げる。フロイトは、口から血をあふれさせながらも、冷静に自分の死を受けて入れているようだった。
「この回廊に下りてから、全てが狂い始めた。私は私の死でしか、何百万という同胞の死に報いることができない。私のしでかしたことが償えるとは思わないが、これで、私はもうなくなる」
「馬鹿なことを、何もおまえのせいばかりではない」
マーサがいうと、フロイトは痛む首を傾けた。「暴動が起こっているのも、私のせいだ」
「そんなことない!」と利菜が腹を立てた。「あたしの世界でだって、ひどいことばかりだったもん。誰かのせいだなんて思えない」
「紛争も飢饉も、ずっと前からあったものだ」とマーサ。「いずれはこうした事態が起こったろう」
「よしてくれ……このような戦争が、あの方もなく、起こったと言われるのか?」
「おまえが、開かなくとも、あいつは出てきていたさ」マーサの言葉はなぐさめにはならなかった。フロイトは静かに笑った。「おまえはよくやった。おかげでトレイスの秘密がわかった。おまえはやつに支配されなかったじゃないか。おまえは悪人などではない。よくやった」
マーサは彼の頭を膝にのせた。フロイトの意識は、薄れているようだった。
「全て滞りなくやるから、安心をし」
マーサはフロイトの汚れた髪をとかした。フロイトがうなずくことはなかったが、その表情はどこか満足げであった。
利菜が転びかけると、ヒッピが腕を出して支えた。回廊の鳴動はいよいよひどくなってきた。まるで命を吹きこまれて、活動をはじめたかのようだ。侵入者の追い出しにかかってるんだ、と利菜は思った。階上からは人々の罵り声が聞こえた。トゥルーシャドウが、こいつ、あいつらをここに入れる気か、と呟いた。
「もう時間がない! ゲートを開くなら、早くしてくれ!」
マーサはペックから、儀式の内容を詳しく聞き出した。儀式は神官たちのものだが、エビエラから習った魔術の類と大差のあるものではない。
「なんとかなりそうだ。みんな集まるんだ」
マーサが袖をたくしあげると、回廊の壁は胃袋のように脈動している。
「みんなしっかりしろ」ヒッピは利菜とペックの手をとりながら、自身の息に恐怖が混じるのを感じた。「幻覚にとらわれちゃだめだ。これまでだって乗り越えてきたはずだぞ」
ヒッピはとっさに友だちの手を離し、利菜を抱きしめる。
「向こうの世界に戻れ、佳代子や新治を助けてやってくれ」
利菜はうなずいた。ヒッピのいうとおりだった。彼と彼女はつながっている。ヒッピの気持ち、それにみんなの気持ちが、自分のことのように感じられる。自分を生かしたがっている。みんなのために生きたい残りたい、と、素直に思えたのだった。
「装置のことはおまえに任せる」とマーサは言った。「三百年前に世界の終わりを救ったのが事実なら、今度もできるはずだ。みんな自分を信じよう」
とマーサは言った。トゥルーシャドウは黙祷するように目を閉じた。子どもたちもそうした。利菜は手をつなぐ友だちの顔を眺め渡す。ここはわるいものでいっぱいだけど、彼女を元のグループに返そうとする力だって働いている。私はこの力を信じる、と思った。細胞の一つ一つがぱちりぱちりと目覚めていく。子どもたちはマーサに助けられ、意識の深い次元におりていく。心臓の脈動すら合わせるかのように。一つのグループとなり、一つの目的のために、心をあわせていった。彼らが大きな一つの意思になるほどに、雑念や邪念は消えていく、どんどん透明になり、深まっていった。
ひらけ……と誰かが、心につぶやいた。みな、その言葉を心に念じた。ひらけ……ひらけ……
利菜は目を閉じていたが、まわりで起こることが、その目にみえた。もう暗闇すら関係ない。地下だというのに風が起こり、みんなの髪や服を吹き払う。そして、環の中央に、ふたたび力が収束し、黒点が浮き上がったのだった。それは渦をまいて、大きくなった。
利菜はその向こうにわるいものを見た。わるい集団が彼女をまちかまえていたけれど、それだけじゃない。そのどす黒い集団の中にも光明が確かに存在していたのだ。
利菜は強い風に逆らって、どうにか目蓋を開こうとする。友だちの手をしっかりと握りながら。
「佳代子たちだ……」
と彼女は言った。
□ 十三
ナバホ族の死体が累々と横たわっていた。サウロンはその死体をときに踏みつけながら、狂ったように腕をふり歩いた。彼の白髪も雨に濡れて、皮膚にはりつく。
二〇人からいたナバホ族は、すべてトレイスが倒した。彼の衣服は返り血に染め上がっている。
サウロンはマーサの不在を知ると、鳥のように痩せた足で、死体の頭を蹴り飛ばした。
「蛮族がまた邪魔だてか! マーサはどこだ!」
肩で息をしている。叫ぶと、立ちくらみがして、さらなるいらだちが募る。
ナバホ族と戦ったのはまずかった。回復力の衰えは、自分でも目を覆うばかりだ。脳力をつかいすぎて疲労が噴き出すようだった。彼は、マーサたちの居場所をさぐろうとしたが、疲労物質がじゃまをして、力が使えない。借り物の体とはいえ、以前ならこんなことはなかった。若い肉体が欲しかった。だが、乗り移ること自体が危険なことだし、彼には自在に行えない。これまでも死の間際に夢中でやってきたことだった。
それに、他者との融合は、彼を変化させすぎる。
サウロンは疲労といらだちから、自制心をなくしかけていた。帝国時代の仲間たちや、皇帝の姿が時の向こうに見えた。彼は帝国時代の言葉でしゃべり、皇帝の悪辣さを罵った。わるいものに取り憑かれていたのは彼も同じだったのだ。
「三百年がたって、またあの女だ! 蛮族をひきいて、このおれを攻めおった」
胸が高鳴り、彼は喘息のような発作にみまわれた。落ち着け、と自分に言い聞かせる。みぞおちに手を起き、腹を撫で、呼吸を深くした。
フロイトだ。あの裏切り者め、ただではおかんぞ。
だが、妙だった。フロイトはマーサに手を貸して何を目論んでいるのか? それにマーサが連れてきた娘のこともある。
サウロンはふいに他者の存在の感じてふりむいた。それは城の方角だった。彼はようやく敵の企てを感得したのだった。
「ゲートを開こうとしているのか……」
□ 十四
渦は予想以上に大きくなった。イニシエの森で見たときの二倍ほどもあり、さらに大きくなる。その渦は高速回転する地球のようだ。その場にいる一同を、のみこむほどだった。
利菜は風におされて、目をつぶる。時空のねじまがりは、たしかにここまでおよんでいる。その渦の向こうに、利菜は確かに佳代子たちの存在を感じた。みんながいて、彼女の帰りを待っている。だけど……
「だめだ……!」
恐怖で目を開くと渦はさらに迫っている。想像はしていたが、これは予想以上のものだ。平衡感覚が失われ、利菜はよろめいた。こんなもの自分たちではコントロールできない。利菜は渦を押さえようと立ち上がる。その瞬間、となりの二人と手が離れた。
がさがさ、がさがさ
背後で音がする。かえりみると、深い闇の向こうで何かが蠢くのが見えた。みんなはもう手を離してバラバラになっている。
わるいものだ、あいつらが戻ってきた。あたしたちはゲートを開いただけじゃなかった。
「このゲートは、利菜の世界とつながってるのか!」
とヒッピがマーサに向かって怒鳴っている。もう互いの声も聞こえないのだ。
風はいよいよ強くなり、利菜を押し倒そうとする。利菜は片膝をついて耐えた。ランタンの光が狭まる。彼女らの生み出した闇が、光を飲み込んでいるのだ。トゥルーシャドウが予備のたいまつに火をつけた。
回廊が広くなっていた。地平線すら見えそうだ。彼らの少し先には、死体が山と積まれている。それはおまもりさまの用意した歓迎のオブジェである。森で死んだ兵隊たち、今日死んだ少年たち――彼らは、死んだのに生きていて、利菜の方に来ようとしている。完全に腐りきっているものも多かった。その群れに、なめ太郎の姿もみえた。あいつが、血をすすっていたような……。
パーシバルは、トゥルーシャドウのランタンを奪いとると、夢中で死体に向かって投げた。ランタンのガラスが砕け、中の油がまわりに飛び散る。死体に火がつき、風には肉の焦げるにおいと煙がまざる。利菜は体をおって咳き込んだ。隣で、ヒッピが叫んだ。
「幻覚じゃないぞ! 気をつけろ!」
死体たちは、火に燃えながら、まだ這い進んでくる。
「わるいものが、現実化してる。なんで……?」
マーサが利菜の手をひいて、渦に押しやる。「ゲートのせいだ! ここはいいから行くんだ!」
「でも……」
躊躇する利菜に、マーサは怒鳴る。
「こいつは次元のひずみなんだ。これのせいでねじまがりが強くなってる。おまえが行かないと、ゲートを閉じられない。さあ、行くんだ!」
「こんなところにみんなを置いてけないよ!」
友だちをおいて逃げ出すんだ、という声が、闇からあがった。それは数百人の大合唱でパダルたちはたまらずこけた。
「ぼくらは大丈夫だ!」とヒッピがすぐわきで言う。ペックもそばにきて彼女の腰にしがみつく。「わるいものに耳を貸すな。向こうの世界の、仲間を救え!」
利菜はパダルたちをみた。みんな彼女にすがりつくように集まってきている。トゥルーシャドウがそんな一同を守るようにして正面に立った。
「ここから先はあたしが何とかする」マーサは呪詛の言葉のように呻き上げる。「聖櫃がおまえの世界にあるのなら、トレイスよりも先に手に入れろ」
「あいつがあたしの世界に来るかもしれないってこと」彼女の胸は恐怖に波打つ。
「そうだ。あいつならなんでもやる。おまえは早く逃げるんだ」マーサは利菜の頬を挟み上げる。「おまえはここまであたしの弟子として立派にやった。十分にやった。これ以上、こっちの世界のことで気に病むことはない。逃げたっていい。おまえはまだ子どもなんだ」
でも、逃げどころなんてないよ
と利菜は叫びたかった。死体の山では、なめ太郎が頂上にのぼって飛び跳ねている。喜色満面で、来るのか来るのか、と訊いてくる。まるで向こうに戻るのを舌なめずりしているような声だった。
そのとき、佳代子と紗英の声が渦から聞こえた。ヒッピたちも聞こえた。みんなは渦の方角を顧みた。
「佳代子! 紗英!」
「利菜!」とヒッピは彼女の肩を力任せに叩いた。「向こうだって、危険なんだ! みんな危険を犯して君を迎えに来た。ぼくらもそうだ! 行ってくれ」
利菜はこわばる首を強引に動かす。
「ヒッピ、あんたのいったとおりだった。佳代子たち、あたしを待ってた」
ヒッピがうなずいた。「ぼくにも感じるよ」
「本物のグループは」とパーシバルが風にもめげずに言う。「仲間を見捨てない」
利菜はマーサを抱きしめる。
「ここまでありがとう。お別れなのが、残念だよ」
と老婆の耳に囁く。マーサが抱きしめ返してきた。彼女に似つかわしくない湿た声でいった。
「向こうに戻ったからって、おちおち死ぬんじゃない。これ以上の骨折り損はごめんだからね」
フードがぬげおち、長い白髪がたなびく。マーサの細くて骨張った指が髪をすき上げた。
利菜は立ち上がる、渦へと近づく。ここは神官たちが何百年と世界をつないだ大鏡じゃない。けれど、利菜の世界とつながっているのはわかる。そして、二つの世界をつなぐたびに世界のねじまげは強くなるようだった。あたしたちはこうしてゲートを開くたんびに世界をねじまげてもいたんだ。マーサのいうとおりだった。はやくこいつを閉じてしまった方がいい。佳代子たちとのつながりはますます強くなる。ヒッピのいった通りだ。彼らは危険をかえりみず、自分を助けに来たのである。
利菜は、渦に手をさしだし、ふりむいた。渦からは瘴気が竜巻のように立ち上り彼女にまといついた。手を髪をいつくしむように撫で(まるで利菜が生け贄みたいに見える)、そのせいで利菜の表情は半分がた見えない。
「みんなありがとう! ぜったいに装置を手に入れるから」
死なないで、と彼女は言った。いうつもりだった。けれど、その言葉は渦に手を差し入れた瞬間に凍り付いてしまった。何者かが彼女の足首をつかんだからだ。死体がきたんだ、と利菜は思った。
足を持ったのはフロイトだった。彼はまだ生きていた。
ゲートの力が、利菜とフロイトをつなぎあわせた。喉元に激痛が走り、失われた血液のために、立ちくらみがする。ヒッピと同化したように、今度はフロイトとの同化が始まったのだ。けれど、彼は死にかけだ。利菜の体も死の苦痛で満たされていく。一方で、渦に差し入れられた右腕は、とけたゴムのようにどこまでも伸びていった。人型のチーズがゲートの熱で溶けて伸びるみたいに(実際にはそのゲートはひどく冷たい。熱さを感じるほどに)。吸引力はさらにまして、彼女の肩までも吸い込んだ。フロイトはマーサの足下に転がり、今にも死に瀕しようとしている。死にかけの人間とは思えない力で、彼女を離すまいとする。ヒッピとペックが絶叫した。トゥルーシャドウがふりむいた。死体たちも。マーサは悪態をつきながら、フロイトの腕を引き離そうとする。その瞬間、利菜はマーサともつながる。フロイトの見ているものと、マーサの見ているものが彼女の視界で重なりあう。その瞬間、利菜はフロイトでもあり、マーサでもあった。記憶が流れこんでくる。
利菜は、そのあまりの量に悲鳴を上げた。脳細胞の一つ一つを破裂させる勢いで、二人の人生が飛び込んでくる。ヒッピのときとちがって、今度は二人分だ、マーサの人生は長い、おまけにサウロンのものもまじっていた。
それは小さくか弱い水路に流れ込む無限の濁流である。濁流はたちまちあふれて洪水となった。利菜の全身の許容量をおかして、さらに流れ込んでくる。一方で彼女の五体は本当にバラバラになりつつあった。渦がいまだ彼女を吸い込んでいたからだ。渦に肩が吸い込まれると、利菜は頭半分を突っ込んだ格好になる。渦とフロイトとに引っ張られる格好となる。右の側頭部がぐにゃりとのびて、まぶたははがれて眼球があらわになり、涙は渦にむかって流れていく。体が持ち上がり、足が浮いた。それでも、フロイトは手を離さない。
そのとき、ゲートの向こう側で、先行して伸びていった右腕が複数の指とからみあうのを感じた。佳代子だ、と思う内に、肺が飛んで、心臓も渦にきえた。利菜の身体は腰までゲートに飲まれていた。体中の血液が渦の向こうに吸い込まれる。利菜の足はどんどん細くなり、細胞が一滴も残さずにゲートの反対側に流れていく。フロイトが感じるのは、もはや骨と皮だけになった足首である。そこでようやくフロイトが手を離した。
利菜の体はすぽんという音を残して、渦に消えた。
後には、脱げ落ちた左の靴だけが残っていた。
□ 十五
「おまえ、なんのまねだい!」フロイトが指をはなした瞬間に、マーサは石畳に転がった。マーサは渦を見上げた。利菜が確かに向こうの世界に消えたことを知ったのだった。あの子の存在をもう感じない。安堵感につづいて、彼女を襲ったのは喪失感だった。自分がそんな感情に見舞われようとは思いもしなかった。考えてみると、あの子は古い仲間以外ではじめて彼女とまともに接した人間である。マーサはその感情を振り払い、ヒッピたちを集めようとする。「ゲートを閉じないと」
「だめだ……」
フロイトは、血だまりのなかで、起き上がろうと、腕を動かす。
「なに?」とマーサは言った。「なにがだめなんだい」
「トレイスのいた牢獄にうつるんです……そこからなら、逃げだせるはずだ」
トゥルーシャドウたちが退いてきた。死体の数はどんどんふくれあがっている。
こいつ、利菜に情報を与えるつもりであんな真似をしたのか? とマーサは察した。フロイトは死に瀕しながらも、まだ頭が冴えているようだ。考えるに、この男はこの一年、ずっと死に瀕していたようなものだから、こんな事態はお手の物なのかもしれない。
マーサはフロイトに訊いた。「それは、どこの牢獄だい」
フロイトは一瞬意識をなくし、また立ち直る。
「エビエラは、何もない空間に牢獄を作ったのですか? そんなことはないはずだ」
マーサは理解した。
トレイスを閉じこめた牢獄は、城の地下にあるわけではない。
どこかに通じているはずだ。
フロイトは半死の状態で体を起こす。マーサが近づくと、手でおしのけようとする。
「トレイスがくる。私に触るな。さわらないでくれ。ゲートが開いたことにきづいたんだ」
フロイトの血まみれの指があがり、マーサの喉をつかんだ。骨が砕けるほどのすごい力だ。マーサはフロイトの目をのぞきこんだ。瞳のむこうに、悪鬼の顔をしたトレイスがいた。マーサはフロイトの手をつかむ。
トゥルーシャドウは、手をもぎはなそうと剣をふりかぶったが、その前に、フロイトの瞳から生命が消えた。喉にかかった手も落ちた。
「マーサ!」
トゥルーシャドウが彼女を抱き起こす。マーサは咳きこみ、トゥルーシャドウの背後に目をやった。
死体たちが起き上がっている。腐臭が鼻をつき、その臭いを嫌うように、トゥルーシャドウのもつ松明が消えた。周囲が闇に飲まれると、少年たちの恐怖も増大した。
マーサはみんなを叱咤しながら、互いの身体を抱き合うようにした。もうゲートの出口を決める余裕もない。彼女の身体を死体たちのぎざついた爪が掠め始めたからだ。
「みなゲートにとびこむんだ! 急げ!」
死体がなだれをうって飛びかかる一方、マーサたちはゲートに雪崩を打った。彼らは数珠つなぎにどんどん縮小していく渦に吸い込まれていく。死体も渦にとびこんだ。ゲートは役目を終えたことを自認したようにかき消えて、ふたたび回廊がもどってきた。
トレイスたちが回廊にたどりついたとき、そこには何者の姿もなかったのであった。
○ 一九九五年 八月二十日 ――再会
□ 十六
何が起こるかを知っていたからだろうか? 二度目に時空を越えたとき、利菜にはハッキリとした意識があった。
体はバラバラになり、魂がぐうんと伸びていく。ひっぱっているのは五本の手だった。同時に、マーサの記憶、フロイトの記憶、サウロンの記憶が、彼女をもみくちゃにしていた。そして、意識の共有が、ふたたび起こっていた。利菜は佳代子たちに起こったことを知り、佳代子たちは利菜に起こったことを知っていったのである。
佳代子たちの開いたゲートは小さなものだった。達郎たちは壁に足をついて、利菜の右腕を引っ張った。指がまず亀裂を抜け出てきた。その指はびしょ濡れ、たこのようにぐにゃりと伸びる。子どもたちは夢中で指をひいた。利菜の右手は亀裂を離れるほどに存在感をまして、しっかりとさわれるようになった。骨と肉が形をなしてきたのだ。亀裂が最後の抵抗をして裂け目を閉じ始めると、達郎と寛太は夢中で蹴った。壁は怒りの唸りを上げて血を吐き、メリメリと異様な音をたててまた裂けた。利菜の頭が見えると、佳代子は亀裂に夢中で腕をつっこみ友だちの顎をつかんだ(なまこを掴んだような異様な感触だった)。
「利菜!」
と紗英も佳代子の腰にしがみついて引っ張った。新治も。寛太と達郎は利菜の記憶におぞけを振るいながらも(五人ともとんでもない量の記憶を頭からぶっかけられている気分だった)、頭から亀裂に身を乗り出し(そのとたん、ぐわん、という巨大な音が二人を叩いた。どでかいシンバルではさみうちをされた気分だ)、利菜の腰を足を捕まえて夢中で引っ張る。亀裂はゲロを吐き出すみたいに利菜の身体を吐き出した。利菜は生まれたての赤子みたいに血まみれだ。一同は大きな声を上げ、一塊になって倒れた。
目をさましたとき、利菜は佳代子の上にいた。身を起こそうとしたが、立てなかった。佳代子がしっかりと抱きとめていたからだ。紗英が近づいて、利菜の短くなった頭を抱いた。利菜は何か言おうとしたが、何も言えなかった。涙が心を満たしたからである。
達郎は頭を満たす記憶の渦に身をふらつかせていた。脳内のシナプスをものすごい電流がかけめぐっている。それでも男の子たちは利菜を取り戻したことを喜んだ。彼らはスクラムを組むみたいに肩を組んで、うずくまって泣いている女の子たちを見おろした。
「利菜、あんたひどい目にあってたんだね」と佳代子は言った。利菜は泣きながらうなずいた。
「みんなも見たのか?」
達郎が訊いた。呂律がちっとも回っていない。寛太はうなずいた。新治も。佳代子と紗英が立ち上がり、利菜を引き起こす。語ろうにも、言葉が見つからない。坪井が階段を上がってきたが(オリジナルの死体のようだった。幻覚よりも凄惨だ)、みんな一瞥しただけで何とも言わなかった。
六人のメンバーは、ふたたび一つになり、あちらの世界に残った仲間たちを思った。互いがうけとった記憶を整理するのは大変だった。
「スターウォーズみたいな映像が見えたぞ」
寛太が言った。目が回るのか、数度頭を振った。新治も、「そうだよ、宇宙船みたいだった」吐き気をこらえようと口元をおさえる。
「利菜」と佳代子が利菜の頬を撫でる。「あんた別の世界にいたの? ヒッピやマーサおばあさんを、あたしたちも見たのよ」
みんなは利菜を質問攻めにした。利菜はみんなを落ち着けようと必死になった。彼女だって三人の記憶におぼれかけているのだ(とくにサウロンの記憶だ!)。
最後に達郎がつぶやいた。
「あいつら、どうなったんだろう?」
みんなは、壁をみた。亀裂はきえて、早くも蔓が生い茂っている。
「ヒッピは無事だよ。まだ、あの子とつながってるから、死んでないってわかるんだ……」
利菜の言葉はいささか期待めいていた。佳代子たちはうなずいたが、受け取った記憶を受け入れるのは難しかった。
利菜は必死で考えを整理した。マーサやフロイトから聞いたことを思い出そうとする。でも、頭がくらくらする、まるで脳みそがずっと震動しているみたいだ。気を抜くと吐いてしまいそうになる。これだったんだ、フロイトが伝えたかったのはこれだったんだと利菜は思った。あの人はあたしとヒッピがつながったのを知ってた。あたしに、知ってほしかったんだ。
「フロイトって人が、サウロンの記憶を見せられたのよ。あの人は、理解できなかったみたいだけど……」
「そりゃ、そうだよな」と達郎。「あっちには、映画や漫画もないしさ、きっとSF小説だってないぜ」
利菜はまたうなずく。なんとかこのことを正確に理解しなければならなかった。フロイトやマーサのことを一番深く知っているのは彼女だからだ。佳代子たちは間接的に知ったに過ぎないし。自分にはそんな役割がある気がした。
利菜は額をぴしゃりと叩いて、「でも、あたしたちは理解できるよね? だって、そんな話にはなれっこだもん」とみんなに言う。「みんなが見た宇宙船みたいなのは、全部サウロンの記憶なんだよ。あいつの世界では帝国がものすごい力をもってた。あたしたちの世界より、ずっと科学が進んでる。宇宙の初まりからある、古い古い文明だったんだよ」
「あいつ宇宙人なのか?」と寛太が訊いた。「それに超能力をつかってたぞ。人間じゃないみたいだ」
利菜はうなずいた。マーサの言葉を思い出す。「サウロンはあたしたちよりずっと進化して、能力もあったんだって」
「すごい進んだ文明だったよね」紗英は記憶をさぐるそぶりをする。「タイムマシンもあったんだ」
彼女たちは自分たちが見た記憶について話し合った。
サウロンたちの文明はすごかった。タイムマシンが確かにあった。卓越した科学によって、時空間すら支配していた。法体系も進んでいて、歴史を改ざんすることは大罪であったのだ。
フロイトがそんな歴史を理解できなかったのはむりもない。けれど、彼女たちはドラえもんでも、映画でも、引用できるものはいくらでもあった。それが小学五年生の知識でも、理解するには十分だ。
彼らの文明は、銀河よりも広域な帝国を築いていた。といっても、議会制で、科学を悪用する事態は考えられなかったようだ。さらに進化した、新人類があらわれるまでは。
旧人類に少しずつあらわれた進化種たちは、議会制を否定して、帝国をのっとりだした。彼らのリーダーは、初代皇帝となり、科学を利用して、周辺銀河を支配していった。時空にかかわることのできる彼らにとって、他文明の支配など簡単なことだったのだ。
「それって歴史のねじまげだよ……」と佳代子。
「サウロンが帝国のリーダーだったのか?」
と達郎が訊いた。これは少しちがった。サウロンは、帝国に支配された側の国家にうまれた。彼らは帝国に反攻するレジスタンスとなった。自分たちの歴史を改竄する帝国に、決死の戦いを挑んだのだ。サウロンは、レジスタンスのリーダーとなり、大昔に(あるいは未来に)世界のねじまげをくいとめようとしたのだ。
彼らは苦労しながら必要な記憶をたどっていった。まるで巨大なデータバンクだが、それを扱うコンピュータは恐ろしく旧式だった。処理がまるで追っつかない。
彼らは自然と手を握りあった。
反乱軍側の抵抗は熾烈を極めたが、文明力の相違から、いちぢるしく劣勢に陥っていた。壊滅の危機にあった。時空をあやつる帝国には、どんな作戦も通じない。
追い詰められたサウロンは、最後の決断を強いられる。その当時、時空を支配していた装置を逆用して、時空間の崩壊を目論んだのである。宇宙の文明はまちがった方向に進んだ。その結果が、あの破滅的な進化種の出現だ――そう考えたサウロンたちは、宇宙をビックバン以前の、原始の姿に戻すことを計画した。否定的な意見もあったが、これ以上、ダイオン帝の傀儡に、堪えることはできなかった。彼らは、コスモリザーブ作戦を決行する。宇宙を、歴史を、進化を。今一度やりなおすために。
計画は完全には遂行できなかった。文明人の多くが死に絶え打撃をうけた。そのうえ、あらゆる時空がねじまがりはじめた。
宇宙は今、時間、空間、次元もふくめて、崩壊がはじまっている。その影響を利菜の世界も受けているのだ。
利菜の話は、ついに、サイポッツとなったサウロンの末路におよんだ。帝国は滅んだが、サウロン自身も異次元へと漂着する。
「サウロンは、ほんとの英雄だったのよ。ルーク・スカイウォーカーみたいな。そんでマーサおばあさんは、元々この世界の人間だったんだ」
利菜の思考は、マーサの記憶へとたどりついた。それは、数百年にわたる、長い歴史の物語だった。