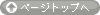「ねじまげ物語の冒険」へようこそ
この小説は、ねじまげ三部作の第二弾です。
伝説の書を胸に、本の世界の登場人物たちと奮闘する少年の姿を描いたファンタジック冒険小説!
侍の少年との友情を軸に、洋一がロビン・フッドの世界を冒険します。
◆ 第二部 果てしない物語と呪われたこどもたち
◆ 第一章 泣き虫ジョンとロビンの消息
□ その一 ちびのジョン、大いに弱ること
○ 1
ぐるり、ぐるり。ぐるり、ぐるり。
洋一には自分がアメーバかなにかに変わったかのように感じられた。体はチーズのようにとろけて伸び、上下左右もわからなくなる。ぐるりぐるり。ねじまがり、激しく回転、渦さえ巻いた。洋一は目を閉じて、歯を食いしばり悲鳴をこらえる。
真っ暗闇に放り出されたかと思うと、次の瞬間には、どこともしれない石の床に身を投げ出されていた。彼は激しい動悸に息を切らす、大の字に伸びたまま襲いくる吐き気とたたかった。大汗をかき湯気までたった。
視界はいまだに回っている……。
「ここはどこ」
洋一は倒れたまま、しゃがれ声でうめく。吐き気がして身を起こすことができない。
「洋一」
太助が右隣で体を起こす。体をさすり、腰に刀があるのを確かめ、ほっと胸をなでおろす。
目が次第に暗闇になれてきた。視界の回転もおさまる。洋一は城の調理場だと思った。男爵がそこに出るといっていたし、部屋の調度もまちがいなく調理場であることを告げていた。部屋の奥にはかまどがあり、まな板に包丁といった調理道具もみえる。
二人が倒れているのは、テーブルの真下あたり。ここでは食事をしないのか、椅子のたぐいがまったくない。部屋は広く、かまどが壁面に並んでいる。巨大な鍋が壁に吊されている。ここにいるのは彼らだけだった。
「男爵と父上がいないぞ」
太助が周囲を見回す。洋一もしゃがんだり、背伸びをしたりして二人の姿をさがしたが、人影がない。
「ここはほんとに本の世界なのかな?」
「わからない。でも、そうだと思う」
太助は気持ちを抑えようとしているようだったが、声には興奮が感じられた。洋一も脳天から舌まで染みるようなしびれを感じる。
そうした興奮が去ると、激しい不安がやってきた。
「男爵とおじさんはどこに行ったんだ?」
彼らは本の世界に来たのさえはじめてだ。どう振る舞っていいかもわからず、またなにをすべきなのかも知らなかった。洋一はミュンヒハウゼンの言葉を思いだした。狂った本の世界を元に戻す……
「たぶん、男爵たちはこの場所に来なかったんだ」太助が言った。「きっと別の場所に飛ばされたんだよ」
「でも、なんで?」
「わからないよ。入るときにページがめくれたのかもしれないし、ウィンディゴがじゃましたのかも」
洋一はたちまち怖ろしい巨顔を思い浮かべ、「そうだ、ウィンディゴは? あいつは追ってこないかな?」
「わからない。でも、ウィンディゴはいろんな物語の世界に影響を及ぼしてる。そのせいで……」
太助が急に黙った。緊張した表情になり、鼓膜に意識を集中している。
「な、なんだよ」
しぃ、太助が沈黙をうながした。洋一は黙り、自分も緊張しながら、辺りの気配に集中した。太助は剣術で鍛えこんでいるせいか洋一よりずいぶんと敏感なようだ。
「奥の部屋から音がする」
太助の視線の向こうには、アーチ型の闇がぽっかりとあいていた。よく見るとそこからかすかに明かりがもれていた。
「男爵たちかな?」
と洋一は尋ねたが、二人でないことはわかっていた。隣の部屋から響くのは、なにか物を食べるような音に聴こえたからだ。それに男爵たちなら二人を捜すに決まっている。
太助が用心深く腰の刀に手をかけた。洋一に向かってうなずいたが、表情はいかにも不安そうだ。
「向こうにいるのがウィンディゴだったらどうする?」
「ウィンディゴならぼくらはとっくに殺されてる」
「でも……」洋一の視線が揺らいだ。「刀を抜くのはよくないよ。相手はきっと大人だ」
洋一は、ボコボコにやられるに決まってると思ったが、口にはださなかった。
太助は首を左右に振った。「男爵はページを選んでた。危ないシーンにぼくらを連れてくるはずはないよ。きっとロビン・フッドか、ロビンの仲間がでてくるページを選んだはずだ」
でも、ロビンはすでに死んでいる。森の仲間たちにとって、今のロビン・フッドの世界はずっと住みにくくなっているはずだった。
二人は腰を落とし、ゆっくりとアーチに近づいた。そちらは食料の貯蔵庫になっていて、調理場との間には扉すらない。
洋一は言った。「主人公が死ぬなんて信じられないよ」
「いや、男爵たちが読んだのは頭の部分だけだ。後半では死んでないことになっているのかもしれない」
太助はわらじを履いているのでほとんど音を立てない。洋一は靴を脱いだ。
二人がかまどの脇から貯蔵庫の奥をのぞくと、そこでは見たこともないような巨体の持ち主が、精一杯に身をかがめて、食事にありついているところだった。こちらに背中を向けている。先ほどから漏れていた明かりは、布でおおったカンテラから漏れた明かりらしかった。男がどでかいソーセージにかぶりつき引きちぎるのが見えた。ずいぶんと腹を空かしているようだ。それをみて二人の男の子たちのお腹もぐううっと鳴った。
洋一はささやいた。「昨日の晩からろくに食べてないよ」
「ぼくもだ」
「あいつ緑の服を着てないぞ」
緑の服こそ森の盗賊ロビン・フッドの子分の証だ。少なくとも、洋一の読んだ本では。
「誰だ」
大男がふりむいた。二人は慌てて壁際に隠れた。大男はカンテラにかぶせた布をそっと外して、部屋の入り口をてらした。男はひげもじゃで髪もぼーぼーに伸びている。その髭はソーセージの油のせいでぬらぬらと光っていた。
「誰かいるのか?」大男が訊いた。「誰もいないのか? いないといってくれ」
「あいつおかしなことをいってるぞ」
と洋一。太助がまたしいいっと言って、洋一の口をふさいだ。
「だ、誰もいないんなら、それでいい。俺は食事をつづけるぞ」
男は震える声で言った。
太助と洋一は顔を見合わせた。男が急においおいと泣きはじめたからだ。
「まったくなあ、ひでぇことになったもんだ。ロビンはいなくなっちまうし、おかげで俺は朝から晩までこきつかわれる」
太助が思わず物陰から顔をだした。「あんたロビン・フッドを知ってるのか?」
「ひょっとして、ちびのジョン?」
太助と洋一が同時に問い尋ねると、男は大声を上げて飛び上がった。
○ 2
「だ、誰だか、知らねえが州長官さまには黙っててくれろ」男は転がったまま、両手を大きく振り立てた。「ろ、ろくに食ってねえもんだから、つい魔が差しちまって。だけど、誓う。これまで盗み食いなんて一度だってしたことがねえ。ノッティンガム長官さまには感謝いたしております。腹が減ったのだって、俺の図体がでかすぎるせいで、州長官さまのせいではまったくないですだ」
「おい、あんたこそ静かにしろよ」
太助が怒って部屋に入った。
「まずいよ、太助。男爵のやつ、州長官の調理場のシーンを選んだんだ。きっとちびのジョンが、州長官の家来になった場面だよ。ぼくらは代官の屋敷に閉じこめられた」
男は顔を上げた。二人の顔をみとめたようだ。「なんだ、こどもか」と気抜けしたように彼は言った。男の顔は涙とソーセージの油でぐちゃぐちゃになっている。
「お前たちどうやってここまではいった?」
「あんたちびのジョン? そうだろ」
と太助がにじりよった。洋一も後に続いた。
ちびのジョンらしき男は、巨大な手で顔をなで下ろし、
「ちびのジョンって呼ばれたのは昔の話だ。ここじゃあ、レイノルド・グリーンリーフって呼ばれてる。でもみんなはそんなふうには言わねえ。みんなは、泣き虫ジョンって、そう呼ぶんだ」
と言って、ジョンは大粒の涙をこぼしはじめた。太助と洋一は顔を見合わせた。
「しっかりしてよ。頭がいかれたのかな?」
「泣き虫ジョンって、州長官の家来がそう呼ぶの? あんな弱虫なやつらが?」
「しいい」と言ったのは、今度はジョンだった。「あいつらのこと、そんなふうに言っちゃいけねえ。すごくいじわるだし、なにされるかわかんねえぞお」と言って、巨大な体を伸ばし、誰もはいってこないか注意をしている。太助は、
「ほんとにちびのジョンだと思うか?」
「わかんないけど……物語が変わったから、登場人物の設定も変わってるんだよ。男爵がそういってた」
洋一が言うと、太助もうなずいた。
太助は剛胆にも、ジョンの肩に手を置いた。ジョンはそんな身振りにもおびえたようで体をすくめる。洋一はすっかりあきれてしまった。
太助が言った。「なあ、ジョン。しっかりしてくれよ」
「あんた、ロビン・フッドの片腕だったんじゃないの? 森の盗賊の副隊長だ」
「そりゃ昔の話だ。ここでロビンの話なんかぜったいにしちゃいけねえんだ」
とジョンは言った。この雲を突くような大男が(座っていても、二人よりずっと背が高かった)ジョン・リトルのなれの果てであることはまちがいないようだった。
洋一は勢いこんで言った。「ロビン・フッドはどうしたのさ、他の仲間は? みんなやられちゃったの?」
「しいい、ロビンは死んだ。その名は口にだすな」
「じゃあ、他の連中は? 赤服ウィルは? アラン・ア・デイルは?」
どれもロビン・フッドの物語にはおなじみの人物だ。
「あいつらはロビンについて十字軍に行っちまったよ」とジョンはまた小声でささやいた。
「じゃあ、ロビン・フッドは十字軍に参加して死んじゃったの?」洋一は絶望して訊く。
「ああ、仲間の半分をつれてな。俺はロビンに残りの仲間とシャーウッドの森を任されたんだ」
「じゃあ、なんでここにいるの?」
洋一はジョンがたんに偵察かなにかで潜りこんでいるんだと信じたかった。しかしジョンは、「わ、わからねえ」と頭を抱えた。「ともかく俺はいまじゃあ、ノッティンガム長官の家来で、一番の下っ端だ」
「なんでそんなことになったの?」
「わからねぇ。きっと州長官と戦って負けちまったんだ。そうに決まってる」
太助は顔を上げて洋一に言った。「すっかり混乱しているぞ」
「じゃあ、他の人は? 粉屋のマッチは?」
「あいつは一緒に州長官につかえてる。森の仲間でも長官の家来になったのが大勢いる。アラン・ア・バートルも元の料理長に戻っちまった」
アラン・ア・バートルといえば、ジョンが(まっとうだったころ)、州長官の屋敷から連れだし、仲間とした料理人である。
「じゃあ、もっと他の人はさ? タック坊主はどこ行ったんだ」
太助が問いつめると、ジョンは頭を抱えた。「わからねえ。最近頭がはっきりとしねえんだ。昔のことがうまく思い出せねえ」
「じゃあ、ロビンは? ロビン・フッドのことも忘れちゃったのか?」
「あいつを忘れるもんか!」とリトル・ジョンは辺りをはばからぬ声で叫んだ。「あいつはいまでも俺の隊長で、いちばんの親友なんだぞ。俺は、俺は――ロビンさえ生きてれば……」
といってジョンはさめざめと泣きはじめた。
「俺はもうリトル・ジョンじゃねえ、州長官の家来、泣き虫ジョンだよお。ロビンに、ロビンに申し訳がない、ロビン・フッドさえ生きてれば、こんなことにはならないのに」
ジョンはおいおいと泣きながら飯をかきこみはじめた。
「情けない」と太助は怒りに燃えて立ち上がった。「これがロビンの右腕、ちびのジョンとはとても思えん。おい、洋一もう行こう。こんな弱虫に用はないぞ。男爵と父上を捜すんだ」
「ああ、かってにしろ」とジョンは大きな食器に水をそそぎながらいった。「なんだ、おかしな格好をしやがって(たしかにジョンの目から見れば太助は珍妙な格好にちがいない)。俺だって、俺だってなあ、ロビンさえ生きてりゃ……」
「じゃあ、ロビン・フッドは確かに死んだんだね」
洋一が訊くと、ジョンは首をひねった。
「十字軍から命からがら戻った連中がロビンが死ぬところを見たといった。獅子心王ですらおっちんじまったんたぞ」
ロビンとリチャード獅子心王は死んだ。ロビンに従った者も、ある者は死に、ある者は帰ってきた。ジョンはそのものの口からロビンの死を聞かされたのである。
「じゃ、じゃあ、イングランドは今、ジョン王が(リチャード一世の弟)おさめてるの」
というと、ジョンはまた「そ、そうなんだ」とさめざめと泣きはじめた。「ロビンが生きていたころ、俺たちは自由な人間だった。だが、それももう昔の話だ。バラード(民謡)は、もう一つだって作られやしねえ。俺は、俺はロビンが死んだってのに、州長官の家来になってる。城のやつらには泣き虫ジョンだなんて呼ばれてる、俺は俺はほんとにだめなやつだ」
「それはちがう」太助がらんらんと光る目でふりむいた。「あんたは棒術の達人だ。勇敢な男だった。このまま終わるのがいやなら、一緒にこの城を抜けだそう」
「そ、そんなことしたら、州長官さまにこっぴどくぶたれちまう」
二人は二メートルを超す大男がこっぴどくぶたれる様を想像した。
太助はジョンの広い肩をつかんだ。「ロビン・フッドはあんたに必ず帰ると約束したんじゃないのか? そうでなかったら、副長のあんたを残していくはずがない」
太助が力強い声でいうと、ジョンはますますさめざめと泣き、くっくっと肩をゆらしはじめた。
「ロビンはな、いいか小僧よくきけ。異国の地で骨になっちまったんだ。あいつの示した義侠も勇気も、もう地上にあらわれることはない……」
「でも、ちびのジョンは生きてる」洋一は悲しげに言った。ちびのジョンはロビン・フッドの物語の中でも一番のお気に入りの人物だった。ひょっとしたら、ロビンより気に入っていたかもれない。大男で、勇気があって、ちょっぴりどじで、愛嬌がある。そしてロビンのことを死ぬほど愛しているのだ。だから、いつだって勇敢に彼に従った。
「ロビンはあなたに約束したんだ。そうでしょ?」
ジョンはびっくりした顔で、そのつぶらな瞳をぱちくりさせた。「そ、そのとおりだ。ロビンはうそなんかつかねえ。ロビンはかならず戻ると約束した。オレのロビン・フッドは、約束を守らなかったことは一度もない……」
「そのとおりだとも、ジョン」と太助は力強くうなずいた。
「なのに俺はリトル・ジョンの名を忘れ、州長官の家来になんぞなっちまった。俺は俺の身が嘆かわしい」
「それはあんたのせいじゃないよ。ウィンディゴってやつが悪いんだ」と洋一はいったが、
「うぃ? なんだそれは?」
「ウィンディゴだよ」
「ウィンディゴでなくともいい」と太助がわりこんだ。「ジョン、あんたは悪役で、強い力をもったやつを知らないか?」
「悪いやつか?」とジョンは言った。
太助はうなずく。「州長官や、ジョン王の他に」
ジョンの目が奇妙に光った。「モーティアナのことか……あいつは最近、ジョン王の側近になったやつだ。魔女だって言われてる」
洋一と太助は顔を見合わせた。
「そいつだ」洋一は勢いこんでいった。「そいつは映画に出てた」
「小説には出てこなかったやつだな」
「うん。最近でてきたキャラクターなのに、強い力を持ってる」
「きっとウィンディゴが力を貸してるんだ」太助が悔しそうにほぞをかむ。「ジョン、ロビンはきっと生きてる。あの人が死ぬはずないじゃないか(とも言い切れない。物語の最後でロビンは手首を切られて死んでしまうからだ)。ロビンはこれまで仲間のことは一度だって見捨てなかった。あんたが捕まったときだって彼は助けにいったんだぞ。こんどはあんたが助ける番だ」
ジョンは唖然とした顔を巨大な手でなでつけた。「お前たちはなにをいうとる。ロビンは死んだんだぞ」
「そんなもの自分で確かめたわけではないだろう」
「そうだよ、あとでひょっこりもどってくるなんてよくある話じゃないか。国王も死んだぐらいの激しい戦いだったら、どさくさで誰が死んだかなんてはっきりしなかったにちがいないよ」と洋一は言った。
「そいつらがロビンを殺したんなら別だけど」
と太助がいったから洋一はびっくりした。はたしてジョンは顔を真っ赤にして怒りはじめた。「あいつらがロビンを殺したりするはずがねえ」
「じゃあ、誰も見た見たっていってるだけだ。ロビンの死体を確認したやつは一人もいない」
ジョンは呆然とした。「そんな、だったらなんでロビンはもどってこねえ。あいつは今どこにいるんだ?」
「わからないけど、きっと事情があるんだよ」
「もしかしたら、大けがをしたのかもしれない」
ジョンが、「すると、死にはしなかったのか?」
「そうだよ」
洋一が力強く答えると、ジョンは彼に疑わしげな目を向けた。
「だけど、お前はなんでそんなに確信を持ってロビンが生きてるって言えるんだ?」とジョンは問いかけた。「まさか、ロビンに会ったのか?」
二人が答えに迷い顔を見合わすうちに、背後から明かりがさし、三人を照らしだした。
○ 3
「なつかしい名を耳にしたぞ。お前たち、ロビンの名を口にしていたな」
太助は腰をかがめ、刀に手をかけた。ジョンがその肩をおさえる。
「よせ、あれはアランだ」
「アランってアラン・ア・バートル? 料理番の?」
洋一がいうとジョンは驚いた。
「そうだ。よく知ってるな」
洋一はもごもご言った。「そりゃあ、みんな有名だから……」
ジョンはため息をついた。「昔は吟遊詩人にうたわれたもんさ」
アラン・ア・バートルがランプをかかげて貯蔵庫に入ってきた。でっぷりと太った赤ら顔ながら、ジョンに負けない棒術の達人である。
「こんな夜中に面をつきあわせて、まさか謀反のご相談かな、ちびのジョン。つまみぐいをしでかしたにしちゃお仲間が多いな。そのこどもたちはなんだ。使用人の子か?」
「ああ……」とジョンはもみ手をした。「まあ……そんなとこだ……」
太助は鞘ぐるみの脇差しでジョンの腹をどすりと突いた。
だが、アランはまるで信用していない様子。鼻で笑いながら、「ふざけるなよジョン。使用人の子はこんな時間に城をうろついたりしないし、ロビンが生きてると主張したりもしない」
ジョンはまた真っ赤になった。「こいつはでっけえ勘ちがいをしとるんだ、ロビンが生きてるから捜しに行けなんて俺にぬかしおる」
「でも、ほんとなんだ」
洋一がいうと、アランは驚いた顔で彼を見た。
「お前たちどういうことだ? 生きているロビンに会ったのか?」
「会えるはずがねえ。あいつらは死んだ。アラン・ア・デイルもウィル・スタートリーもみんなだ。ロビンが怪我をしたって、アランたちが連れ戻るに決まっとる」
「いや、ジョン二人の装束をみろ」とアラン・ア・バートルは洋一と太助にランプを近づけ、二人の服をとっくりと見た。アランの顔に次第に笑みが広がった。「この装束をみろ、見たこともないぞ。きっと異国の地の兄弟にちがいない。ロビンが自分の生存を知らしめるために遣わしたんだ」
「なんだと?」
ジョンは二人の前にまわりこんだ。「信じられん……お前たち、ロビンに会ったのなら、なんで早く言わねえ?」
太助と洋一は顔を見合わせた。太助はうそをつくのを恥じらうように視線をそらした。洋一が、腹に隠した本に手を置いた。
「あ、あれが、本物のロビンなのかわかんなくて……」とへどもど言った。「だって、怪我をしてたし、本人には始めて会ったんだ。ウィルやみんなも一緒にいた」
「なんてこった……」ジョンはわなわなと口に手をやる。「ロビンは、ロビンは動けねえほどの怪我をしてるのか、それで帰ってこれねえのか」
「待て」とアランがわりこんだ。「ロビンがただでお前たちをよこしただけとはおもえん。ロビンはなにか証拠になるものを渡さなかったか」
「そうだ、それになんでこどもを?」とジョンが疑りの目を向ける。
「ぼくたちだけで来たわけじゃない。男爵と父も一緒だ」と太助が言った。
「証拠は金の矢で、男爵たちが持ってる」と洋一も言った。
アランが、「その男爵とはどこにいる? お前たちだけで城にしのびこんだのか?」
太助はうなずいた。
「なんてことを、なんて危険なことを」アランはなかばなじるように手を振り回す。
「父上たちとはイギリスにきてはぐれてしまったんだ」
太助が弁解したので、洋一は驚いた。さっきから見ていると、太助は絶対にうそを言わない。いま弁解をしたが、それでも太助が口にしていることは全部ほんとのことだ(詳しく話していないだけだ)。洋一は、おじさんと太助は本物の侍なんだなあ、となんとなく信じるようになった。
「そうだったのか……」とジョンは嘆息をした。「いまのイギリスは安全じゃねえからな。とくに外人が旅をするには安全じゃねえ。ロビンの使者というならなおさらだ」
アランがジョンにこっそりささやいた。「一緒に来たという二人はもう……」
縁起でもない、と太助と洋一は憤慨した。
「とにかく、ロビンを捜しに行かないと」
「ロビンがどこにいるのか知っているのか?」
アランが辺りはばからない大声を上げた。
太助が洋一を見た。洋一はちょっと迷ってから、「パレスチナ」と答えた。これを聞くと、ジョンは大喜びをはじめた。洋一は罪悪感でいっぱいになった。彼がパレスチナと答えたのは、ケビン・コスナーが映画の中でとらえられたのがパレスチナだったからだし、そのパレスチナが世界地図のどの辺りにあるのかも知らなかった。
「いいのか?」
太助が横で聞いたが、洋一はそっちを見ずにうなずいた。
「こうしちゃあいられねえ」ジョンは水をがぶ飲みにし、残りは顔にぶっかけた。「お前たちのいうとおりだ。とっととこの城を逃げ出して、ロビンを捜しに行こう」
○ 4
一同はアランのランプを頼りに食料貯蔵庫を抜けだした。
ノッティンガムは交通の要所にあるだけに、巨大な城である。兵隊たちの数も多い。ジョンとアランは、以前二人がつかった地下水道をふたたび利用することにした。壁にかざりつけてあった剣とかぶとを拝借し、それを用心ぶかく腰に吊した。
洋一たちのいた調理場は一階にあり、地下水道への降り口はここからそう遠くないところにあった。
小説ではすんなりと城を抜け出せたのに、現実の本の世界(おかしな言い方だが)の逃避行はページをめくるようにはいかなかった。
「いまは夜中だが、宿直の兵が城内をうろついてるからな」
アランは通路が交わったところでは特に用心をした。ランプに厚い布をかぶせて廊下をのぞきみる。
「でも、森の仲間も大勢いるんでしょう?」と洋一が訊くと、
「ああ、だが、情勢が変わって誰が味方で敵なのか、わかりやしない」
と聞いて洋一たちはがっかりした。
「みんなまだロビンが死んだと思いこんどる。だが、あいつがもどってくればみんな変わってくるはずだ」
「だといいがな……」とアランがいったとき、
「これはいったいどういうことだ」
一同ははっと後ろをふりむいた。通路の影から、背の高い男と二人の兵士が躍り出てきた。
「森の仲間が二人もそろってお出かけとは、よくない考えとはおもわんか」
男がいうと、兵隊たちが声を蹴立てて笑った。兵の一人が持っていたたいまつに火をつけた。洋一のそばでアラン・ア・バートルがひゅっと息をのんだ。
「ガイ・ギズボーン」
○ 5
アランが鋭くいうと、ガイ・ギズボーンは冷笑を浮かべて近づいてきた。
「なんだ、なにを驚いてやがる。おっと、後ろにいるでっかいのは泣き虫ジョンか?」
ガイがおどけて後ずさると、ジョンはまた真っ赤になった。
「夜中にわんわん泣いてアランママになぐさめてもらってたのか?」ガイは突然首を突きだすと奇妙な赤ちゃん言葉で語りだした。「おお、よちよちちびのジョン、ロビン・ザ・フッドはのたうちまわって死にましたと……」
「黙れ!」
太助が辺りをはばからずに大声を上げた。ガイ・ギズボーンの顔色が変わった。おどけた表情が消え、さも残忍な人相がその面に現れた。
「なんだ、その餓鬼どもは?」
ジョンとアランは黙りこんだ。
「なんだと訊いてる。その餓鬼をどこから連れこんだ」
「二人ともイギリス人じゃない」
と兵隊がガイの耳元でささやく。「中国人か? ノッティンガム城にはクーリーはいないはずだ」
「ぼくは奴隷じゃない……」
洋一は震えながら吐き捨てるように言った。クーリーという言葉の意味を知っていたからだ。
ガイ・ギズボーンが残忍な目をさらに細めた。「ならなんだというんだ。お前たちは何者だ? なぜ森の盗賊たちといっしょにいる」
「ガイ、俺たちはもう州長官の家来なんだ」
アランがとりなすようにいうと、ガイ・ギズボーンは笑い声を上げた。
「家来だと? 俺たちが仲間同士とでもいうのか? ふざけるな!」ガイは長剣を抜きはなった。「貴様らが大きな顔で城にいることじたい虫酸がはしるんだよ! たわけのリチャードの息子も、謀反の動きをしている。お前たちが通じていないはずがない! 貴様らなど、これを機会に縛り首にしてくれる!」
大声を上げ唾を飛ばすガイの姿は、洋一に団野院長を思い起こさせた。どちらもおなじぐらい狂っているとしか思えなかった。
通路のあちこちから歓声と無数の足音がとどろく。ガイのよんだ応援が、声を頼りに駆けつけようとしている。
「もう、逃げられんぞ、泣き虫ジョン」ガイに怒鳴られるとジョンは縮み上がった。「貴様の昔の名声がどうあれ、ここでは一介の家来にすぎんことを忘れるな。お前は大人しく役に立つが」ガイは長剣でアランを指し示す。「狼藉がすぎたな。貴様は許すわけにはいかん、明朝しばりくびにしてくれる」
「ジョン、もう行こう!」
太助の叫び声がしたかと思うと、彼は黒い矢となって飛び出し、ガイに向かって剣を抜きはなっていた。彼はこどもだが、直新陰流の居合い技をずっと厳しく仕こまれていた。こどもの技とはいえ、ガイははじめて見る居合い術をかわしきることができなかった。
ガイ・ギズボーンは頬を切り裂かれると、悲鳴を上げて尻餅をついた。
「つかまえろ」ガイがわめいた。「その餓鬼を八つ裂きにしろ」
「そうもいかん」
アランはガイの言葉も終わらぬうちに、剣をガイの胸に突きこんでいた。ガイ・ギズボーンが悲鳴を上げ、血を噴いて、アランの剣をつかんだ。二人の兵隊たちはジョンの手によってたちまちのうちに叩きのめされた。
「驚いた」とジョンは自分の武勇に声を上げて喜んだ。「まだこんなことができるとは」
四人の喜色はつかの間で消え失せた。廊下の向こうから、たいまつをもった兵隊の群れが流れこんできたからである。
○ 6
アランはガイの腹部から剣を引きぬいた。悲鳴を上げたところからみて、まだ命があるようだったが、とどめをさしているひまはなかった。彼らは通路を駆けずりまわった。洋一は、一行に離れまいと必死だった。背後からはときおり弓が飛んできた。洋一は冷や冷やしたが、城の中なので容易には当たらない。やがて、ジョンが地下への扉を開けた。
地下には壁の仕切がない。大きな運動場ほどもある空間が広がっている。暗かった。巨大な柱が天にむけて突き立ち、広大な天井を支えている。洋一の目は石の空間に圧倒された。洋一たちはその壁際にもうけられた階段を駆け下りていた。真下には、四角い鉄の網が見えた。どうやらあそこから、地下にある下水道まで降りられるようだった。
後ろからは兵隊たちの足音が響いてくる。後ろでジョンが早く早くと急かしている。一方洋一はさきほどの光景が忘れられなかった。剣を突き刺したアラン、ガイ・ギズボーンの苦悶、彼の体のあちこちから噴きだした血、そして血の臭い……。
それらは強烈な記憶となって洋一の脳裏に貼りついた。洋一の頭でそうした光景がぐるぐるとまわった。彼は人があんなふうに争って血を流すところを始めて見た。しかも太助はあのギズボーンに切りつけた。洋一は大勢に囲まれているのに、一人場ちがいな場所にいるような気がした。覚悟といえば彼にはどんな覚悟もなかった。死ぬ覚悟もなければ誰かを殺す覚悟もない。両親の敵をとるという、その一心だけで、本の世界までやってきたのだ。
地下への道はさらに暗く、ジョンとアランのランプだけが頼りだった。兵隊の飛ばした槍が足下に突き刺さり、洋一はバランスを崩して階段の残った四段ばかりを転げ落ちた。ジョンが彼を抱き起こし、にじり下がる。
アランが下水口の網に手をかけ持ち上げようとしたその刹那、彼の分厚い背にイチイの矢がはっしと突き立ったのである。
□ その二 レイノルド・グリーンリーフ、ノッティンガム州長官と対決すること
○ 1
ジョンと洋一たちは、慌ててアランを助け起こした。アランは口角から血を噴いて意識をなくしている。この暗闇で正確に当てたことからも、長官の兵に似合わず剛の者が射抜いたらしく、アランの背に突き立った矢は深々と刺さっていた。
ジョンがアランの首筋に指を当てまだ脈があるのを確かめた。それから矢を抜くこともなく、アランの体を裏返すと、彼を抱きその胸を揺すぶった。「アラン、アラン、しっかりしろ」
「くそ」洋一は石だたみを蹴って立ち上がる。「これをやったのが、森の仲間だったら、絶対に許さないぞ!」
この言葉は功を奏したのか、さきほどのような弓矢は飛んでこなくなった。なによりもジョンとアランは今や彼らの仲間であり、詳しい情況は誰もわかっていなかった。
だが、情況はずっと最悪だった。地下道への鉄の扉は足下にあったが、兵隊たちに囲まれ引くことも退くこともかなわなくなった。そして、兵隊たちとともに、ノッティンガムの州長官が、何事だ、何事だと、階上に駆けこんできたのである。
○ 2
「レイノルド・グリーンリーフ!」州長官は驚きを隠せずに声を上げた。「騒ぎを起こしたのはお前か?」
ジョンはうろたえた。「州長官だ……州長官だぞ……」
「ジョン、しっかりしてくれ」太助は鉄の扉と取っ組み合っていたが、その鉄格子を持ち上げるのは誰が見ても無理があった。「あんなやつはほっとけ、早く逃げないとみんな殺されてしまうぞ」
洋一はその言葉を呆然と聞いた。さきほど転んだときに突いた肘の擦り傷を、腕を持ち上げてとくと眺めた。膝にも傷を負っていることに気がついた。本の世界なのに……本の世界なのに、転んだらちゃんと怪我をしている。洋一は本の世界に来るということを深く考えてこなかった(そんなひまはなかったからだ)。
洋一は訊いた。「本の世界で死んだら、どうなるの?」
太助はその目の光りに気がつき、慌てて立ち上がった。「洋一」と彼は州長官たちの方に目を向ける。「君のいる世界は現実でもあるが、でも、ぼくらのいた中間世界だって、男爵のいた本の世界だって、みんなともに現実なんだ。理解していなかったのか?」
「じゃあ、ここで怪我をしたら、ほんとに怪我をするってこと」
「当たり前だ」
「ちょっと待ってよ」
洋一は膝が震え、立っていられなくなった。彼はその場で尻餅をついた。
「こんな、こんな、相手は大人で、剣を持っているんだぞ。彼を見ろよ」
洋一はアランの体の下から血の池が広がってくるのを指さし言った。
「しっかりしろ、洋一。危険は承知のはずだろう」
太助は怒って脇差しを鞘ぐるみ腰から抜くと、洋一に押しつけた。
「やめろ! ぼくは刀なんて持ったこともないんだ」
「ならば、今日から持て!」
「おい、二人とも静かにしないか」ジョンはこどもたちを叱りつけると、アランを床に寝かして立ち上がり弁解をはじめた。「州長官さま、これは……」
「ああ、この不手際を説明しろ」と長官は階段を下りながら居丈高に言った。長官は就寝中だったのか、寝間着の上に豪奢なローブを羽織っている。「その小僧どもはなんだ。上で、ガイ・ギズボーンが何者かに刺されていたが、お前たちの仕業か」
ノッティンガム州長官は階段の半ばから大声を張り上げた。
「答えろ、レイノルド! さもなければ、また鞭で叩いてくれるぞ!」
太助が怒鳴った。「ジョンは、ジョンはもうお前の家来じゃない。ぼくらはロビン・フッドを助けに行くんだ!」
辺りは一瞬シーンとなった。それから、地下室には州長官を中心に、兵隊たちの笑い声が轟き渡った。声は石の部屋を反響して回り、洋一は耳に栓をして跪く。
「ロビンだと? ロビン・フッドだと? まだそんなことをいっておるのか!? やつは死んだ! 遠いパレスチナの地で、いまごろ野良犬のエサになっておるわ!」
と州長官は言った。州長官のこの言葉と、兵隊たちの笑い声はジョンを深く傷つけた。
「お前はまだあのごろつきの盗人を主人扱いしているのか。国王にとりいり、家来になったはいいが、結局自分も死におったわ! なにが自由な森の盗賊だ。貧しい農民に金を配ったというが、やつが死んだときアジトからはおびただしい金銀財宝がみつかったというぞ!」
「でたらめだ」
とジョンが小声でつぶやくのが、しゃがみこんだ洋一の耳に聞こえた。しかし、州長官はますます興に乗ったようだった。
長官の言葉とともに家来たちが雄叫びを上げるものだから、地下室の騒ぎは天を揺るがさんばかりになった。
「ロビンは森に隠れていただけの臆病者だ! 力の弱い商人や僧侶を襲っては、たんまりと財宝をためこんでいた! あいつは善人面をしたくずだ! 自分は能なしのくせに、国王にしたがって、結局はリチャード一世も死なせてしまった! そのあげくを見ろ! イングランドの混迷はなぜだ! ロビンのような残酷な無法者を放って置いたからだ! だが、あの悪党が死んだ今、全ブリテンには善政がしかれ、すべてはよい方に向かうだろう!」
男たちの歓声が轟いた。洋一が恐る恐る伏せた顔を上げると、ジョンがその肩に手を置いた。彼は血膨れしたような、真っ赤な顔をしている。やがて地の底からにじみあがるような、怒りに震えた声でささやいた。
「だまれ……」
○ 3
ジョンは一歩進みでた。兵隊たちの幾人かがジョンの行動に気がついた。ジョンが離れたので、洋一と太助は慌ててアランにとびつき、兵隊たちから守った。
「黙るんだ、州長官! お前の、お前のいうことは、全部でたらめだ!」
ジョンが怒鳴ると、州長官は驚いてだまりこんだ。兵隊たちのざわつきが地下を満たした。幾人かが剣を抜き、弓が構えられた。
「ロビンは、ロビンはおたずね者だが、正しい心を持った強い男だった。人を殺めたが、それは弱い者を守るため、お前のように私利私欲を肥やすために人を殺めたことは一度もない!」
「レイノルド・グリーンリーフ!」
「そんな名で呼ぶな!」
ジョンは雄叫び、木箱の上に駆け上がった。大男なのに飛んでもない身軽さで、代官の家来たちがたじろぐほどに素早かった。洋一と太助が歓声を上げる。
ちびのジョンは槍の林に囲まれながらも、まだ叫ぶのをやめない。
「たとえ、お前がロビンの名を辱めようとも、彼の魂は少しも傷つきやしない! そうとも、俺は自由を愛するヨーマンだ! お前なんぞの家来であったりするもんか! たとえこの身がイングランドに仕えようとも、俺はロビンと森の盗賊たちの副隊長であり、お前なんぞの家来であったりするもんか!」
ちびのジョンは周囲の男たちに呼ばわりはじめた。
「我々はバラードとして語られ、物語として語り継がれ、やがて人々の心にすむ姿なき者! この身がつきることはあっても、心が屈することはない! 俺は誇り高きヨーマンにして、その名も高きお尋ね者。棒をとれ、弓をもて!」
洋一と太助は周囲を見回す。棒も弓もそばになかった。ジョンは諸手をあげて雄叫ぶ。
「圧政を正すために、俺とロビンは戦った! そのためにおたずね者になろうとも、俺は少しも気にしやあしない! ロバート・ザ・フッドは俺の主人にして最高の友! そうとも、あいつがおめおめと十字軍の遠征なんかで死ぬもんか! ロビンは生きてる、ロバート・ザ・フッドは必ずや生きているぞ!!」
「黙れ!」
「誰がなんと言おうと、それがたとえリチャード一世だろうと、俺は叫ぶのをやめない! ロバート・ザ・フッドは生きているぞ!」
「そのとおりだ、ジョン……」
剣を手にした兵隊が、代官の側から進み出た。
「なんだ貴様は」
「お忘れか。我はロビンと行動をともにせんもの」と男はカブトを脱ぎ捨て、周囲に向かい声高らかに言い放つ。「ロバート・ザ・フッドは生きている! ロビン・フッドは生きているぞ!」
それを聞いてあちこちで、ジョンとおなじように代官の家来になった、かつての森の仲間たちが兜を脱いだ。彼らは口々に叫びはじめたのである。
ロビン・フッドは生きている! ロビン・フッドは生きているぞ!
地下室に大音響がオーケストラのように響き渡り、石組みからは塵がこぼれるほどだった。少年たちは天井が崩れるのではないかとうたろえた。この合唱に参加した森の盗賊たちは一人や二人ではなく、もはや代官の命令を聞こうともしない。ウィンディゴが物語をねじ曲げようとも、ロビン一味の結束は岩のように硬かった。そして、騒ぎをやめさせようとする兵隊と森の仲間たちの間で、続々と戦闘が行われはじめた。合唱につづいて剣戟の音が響き渡ると、太助はついに刀を抜きはなち、脇差しを洋一に手渡した。
最初に雄叫びを上げた男は肉屋のパイルだった。代官の家来たちを押し返しながら、
「戦え、ノッティンガム州長官と戦え! ロビンのために、聖母マリアのために、行けジョン! アラン・ア・バートルを連れて行け! これ以上仲間を死なせるな! お前が俺たちの副長で、仲間を死なせる気がないならば、頼むから行ってくれ!」
ちびのジョンは木箱の山から飛び降りながら、そばにいた兵隊を蹴倒し、その手から六尺棒を奪いとった。太助と洋一は刀をかまえてアランから兵隊を遠ざけようとした。洋一は周囲できらめく剣光に目眩がした。自分を貫く剣の切っ先が、今にも目に見えるようだった。
ジョンはとほうもない力を示し、アラン・ア・バートルをゆうゆうと担ぎ上げた。おまけに残りの腕で六尺棒を振り回し、ノッティンガム州長官の部下を、次々と木っ端のようにこづいてまわった。代官の家来たちは、たちまちジョンという大波から退いていった。ジョンを中心にして、家来たちの円ができあがる。階上からはジョンを仕留めようと石弓を持った兵士たちが駆け下りてくる。州長官が今は昔のレイノルド・グリーンリーフを指さし怒鳴り声を上げた。「あいつを射殺せっ!」
それを見ると、ジョンはたちまち大昔の武勇を発揮し、円陣につけいって兵隊たちをつぎつぎと吹き飛ばしてまわった。射手たちはジョンの素早さに狙いをつけることも出来ない。泣き虫ジョンのために、屈強の男たちが、鎧の音高く石の床に転がっていく。
「二人とも、下におりるんだ」
ジョンは手近にいた男たちに突きをくりだし、退けている。洋一たちは刀をしまうと、下水口に下りる縦ばしごに足をかけた。森の仲間たちがジョンの元に駆けつけ、兵隊たちをさらに追いやっている。下水口のまわりではすさまじいもみ合いとなった。
石弓の矢が飛来して、家来も盗賊も問わずに、男たちの体に突き立ちだすが、ジョンと仲間は一歩も引かない。
「よし、梯子はしっかりしているぞ」と先に縦穴に入った太助が言った。
「お前たち早くするんだ」とジョンが急かした。「もうちょっとだってもたないぞ」
洋一が梯子に足をかけていると、指の合間に矢がつきたった。破片が飛んで彼の顔を激しく打った。昔おもちゃで作ったゴムの弓とは比べものにならない威力だった。洋一は顔を上げた。石弓のすさまじさに、森の仲間たちは倒れるものが続出し、人垣が崩れはじめたのだ。梯子にしがみつく洋一のそばに、血まみれの顔が落ちてきた。男の白目と目が合い、彼は悲鳴を上げる。男はおそらくジョンの仲間だろうが、すでに事切れていた。森の盗賊たちは弓の名人が多かったのに、兵隊になった今は誰も弓を手にしていない。
「ジョン、早く!」
ちびのジョンは自分も梯子に足をかけながら、兵隊たちの向こうで見え隠れしている州長官に向かってこう叫んだ。
「待っていろ州長官! 俺はロビン・フッドとともに、かならずやこのブリテンの地を踏みしめることだろう! そのときはお前のその首はその体になく、その魂は地獄の業火で焼かれるにちがいない! 聖母マリアンは我らと共に! ロビン・フッドは大ブリテンと共にあり!」
ジョンとアラン・ア・バートルの姿が暗闇に消えると、森の盗賊たちは人垣を解いて、代官の家来たちに最後の突貫をはじめた。下水の先を急ぐ、洋一とジョンの耳には、ロビン・フッドは生きている、の呼び声がいつまでも聞こえつづけた。
○ 4
太助が手にしているカンテラは、魚の脂をつかっているらしかった。煙がひどく、しかもその明かりは懐中電灯に比べると、はなはだ心許なかった。それでも洋一たちの周囲一メートルばかりは明かりがあった。頭上からは、ノッティンガムの兵士と森の仲間たちが激しく戦う剣戟の音。下では澄んだ水がヘドロの膜の上をさらさらと流れ、突然の明かりに驚いたネズミたちがちゅーちゅーと逃げまどっている。洋一はネズミなんて平気だったが(洋館にはうんと大きなドブネズミだっていた)、石組みの巨大な建造物には圧倒された。崩れるんじゃないかと、壁を叩いてみたが、うんとしっかりできているようだ。
向かう先には、深い闇が黒々と横たわっている。
それにしても臭い。鼻が曲がりそうだ。しかし、数分とたたないうちに鼻の方が馬鹿になった。
下水の水が跳ね上がるために、太助は袴の股立ちを高くとった。洋一がジョンの六尺棒を受け取ると、ジョンはアラン・ア・バートルを背負いなおした。下水は巨大とはいえ、長身のジョンは身をかがめなければならなかった。へどろでぬるぬるして足下が危なっかしい。屈強の男を一人背負って、ジョンも苦しい逃避行だった。
「この下水」と洋一が尋ねた。「どこまでつづいてるの?」
後ろでどぼんという音がした。誰かが下水まで降りてきたのだろう。代官の兵でなければいいのに、と洋一は願った。
「たぶん、町の外までつづいてるはずだ」
当時のイギリスの町は城壁の中にある。だから、どこかで縦穴をみつけても簡単にはのぼれなかった。地上に出てもそこは城壁の中。門を閉じられてしまえば、外に出ることはかなわないからである。大男のジョンは目立つし、洋一と太助の服装も人目を引く。おまけに二人は日本人だ。この時代の人は、日本人はおろか中国人のことだってろくろく見たことがないにちがいない。しかし、アラン・ア・バートルは一人で歩けないし、それどころか命の瀬戸際で、一刻の猶予もありそうになかった。
ジョンはこどもたちの体力を気遣って時折歩いたりしたが、あまりぐずぐずもしていられなかった。州長官の急使はもう城壁まで届いているはずだし、そうなったら、下水の出口は兵隊が固めるに決まっている。ジョンは逃げるだけではなく、戦うための体力も残しておかなければならなかった。太助の抜き打ちにはジョンもびっくりしたが、それでも二人はこどもだ(それにジョンの見たところ、洋一は武術の心得がありそうになかった)。後ろからは城の軍勢が四人のあとを追いかけてきていた。森の仲間がいたとはいえ、屹度多勢に無勢だったのだろう。水を跳ね上げる足音と互いを罵る声がする。ジョンは幾度も脇道にとびこみ、行方をくらまさねばならなかった。もう自分たちが、どの方角に向かっているのかもわからなくなった。
二人がジョンにヨーマンの意味を訊くと、独立農民という意味のようだった。ロビンもヨーマンで、二人は自由を制する圧政を退けるために戦ったのである。
洋一は自分たちは臭い下水の中で迷ったまま外に出ることはできないんじゃないかと思った。ときおり縦穴があったが、そこから上にのぼったところで、そこはノッティンガムの城壁の中だ。カンテラの油は刻一刻となくなっていく。しかも、外に出ても、シャーウッドの森までは、ここからずいぶんあるという話だった。
彼らはさらに歩を進めた。兵隊たちの声は聞こえなくなったが、そのかわり外に出られるという見こみもなくなった。ジョンは玉のような汗をかき、吐く息も苦しそうだ。肝腎のアランが、どう声をかけても目を覚まさない。容態は刻々と悪くなっている……。
彼らが下水を跳ね上げながら、逃げること数刻、通路の奥から風が吹いた。あきらかに下水のよどんだ空気とはちがうものが、肺を満たしはじめた。
「外だ……外だぞ……」
ジョンは興奮した声で叫び、先を急ぎはじめた。
○ 5
もはや、前方に暗闇はなく、月明かりのもとで、草の生えた土手と泥の堀が輝いている。
「アラン、しっかり」
「もうちょっとで外だ」
こどもたちは後ろからアランの尻を押していたが、ジョンは急に立ち止まった。
「どうしたんだ?」
と洋一が抗議する。ジョンは緊張した声で言った。
「し、外に誰かいるぞ」
洋一は慌ててジョンの影に隠れた。太助は刀を抜いて一行の前に躍り出た。
「どくんだ、お前たち、俺がかたをつけてやる」
ジョンは太助の肩を押さえてどかそうとするが、
「だめだ、ジョン。やつら弓矢で君に狙いをつけているぞ」
洋一はびっくりした。太助は勇敢だ。ジョンに比べれば実にちっぽけなのに、体を張って傷ついたアランを守ろうとしている。洋一は隠れているのがすっかり恥ずかしくなり、意地になって太助の隣に並んだ。だけど、膝はがくがく震えた。脇差しを手渡されたところで、彼にはそれを抜く勇気もなかった。
外から野太い声が、下水の中に朗々と響いてきた。「俺たちは自由人、森の民にしてよきヨーマン、お前の同胞だ、リトル・ジョン。森の仲間はお主にそんなまねをしやしないぜ」
「ミドルか?」
ジョンは六尺棒を片手に水音を跳ね上げながら、出口に駆け寄った。三人が下水からでてみると、明るい月光がさっと世界に色をくれた。正門からは離れたしなびた場所のようで、排水が悪いのか、下水のまわりには泥水がたまり、高い葦が生えていた。
ずんぐりした人影は土手の上にいた。赤ら顔の屈強げな男だった。兵隊の格好をしてはいるものの、そばには仲間の兵隊が五人ばかり転がってもいた。
「おい、それはアランか?」と鋳掛け屋のミドルは言った。
「ああ、弓でやられて怪我をしてる」
ミドルは手をさしだし、土手の上からアランを受けとった。アランを下におろすと、ミドルは傷をたしかめはじめた。アランは蒼白な顔で大粒の汗をかいている。思った以上に容態は悪いようだった。
「ジョン、今度はなにをやったんだ? そのこどもたちは? 長官が君が兵隊を倒して逃げたと騒いでるんで驚いたぞ。俺はこの連中と(とミドルは倒れている兵隊を親指で指した)下水の出口の一つに配置されたんだが、とにかく君が手薄な場所に出てきたのはよかった。下水の出口が多いんで、兵隊たちは分散されるかっこうになったな」
「ミドル」ジョンがマッチの肩をつかんだ。「この子たちはな、ロビンからの使いなんだ。ロビンはパレスチナで生きてる」
ミドルはぽかんと口を開けた。洋一の見たところ、彼は今にもくずおれようとしていた。「ほんとか?」
ジョンはうなずいた。「ロビンは生きてる。ウィルもアランもだ。俺はきっとリチャード卿(イングランドの騎士)も生きてると思ってる。だが、ロビンは怪我をしてもどって来られないらしいんだ」
洋一がうつむくと、太助が彼の胸をどんと叩いた。洋一は慌てて上を向いた。
太助は自分がうそをついたみたいな真っ赤な顔だ。しかし、平静を装うみたいにしれっとしていた。
ミドルが、「もどってこられないなら、大けがじゃないか」とささやき声を荒げた。
「俺はこれからロビンを探しにパレスチナに向かおうと思う。だが、アランがこの怪我だ」
「アランのことは任しておけ、俺がシャーウッドの森まで連れて行く」とミドルが請け負った。それを聞いてジョンは、「まだ仲間が残っていたのか?」
「そうとも。まだ、タックたちがいるはずだ。さあ、三人ともあそこの木まで走れ。馬をつないである。いつまでもぐずぐずしていられないぞ。兵隊たちが城の外までうろうろしてるんだ」
○ 6
その木陰にはミドルの手によって三頭の馬が用意してあった。手綱を若木にくくりつけてある。その場で草を飯でいたが、一行の姿を見るとうれしそうに足踏みをした。
城の方で人声がたちはじめ、三人は耳を澄ました。だが、その人声は次第に遠のいていった。森の仲間たちが城の軍勢を攪乱してくれているのだろう。ミドルは、ジョンと協力してアランの体を馬の鞍に横たえると、自分も馬上の人となった。
「ジョン、俺はシャーウッドの森にもどって、ロビンの生存を伝えようと思う。俺も仲間をつれて、お前のあとを追うぞ」
「ああ、わかってる。だが、むりはしないでくれ」ジョンは馬上のミドルに怒鳴る。そしてやや芝居がかってこう告げた。「俺は命のつづく限りパレスチナに向かう。そしてロビンをつれて戻るだろう」
ミドルは馬に輪乗りをさせつつ、「三人とも武運を祈っているぞ。お主たちも、こどもながらによくイングランドまで来た。機会があればまた会おうではないか。そのときはロビンと共に」
鋳掛け屋のミドルは馬を竿立ちさせると拍車をかけシャーウッドの方角へ駆け去っていった。木立からミドルの姿が遠ざかり、やがて見えなくなる。洋一は頼もしい仲間が二人もいなくなって急速に心細くなってきた。確かにジョンは昔の勇敢さをとりもどしたけど、ことはそう簡単ではないような気がした。懐に隠した伝説の書が、そんなことを彼に告げているのである。
「さあ、俺たちも行こう。お主たちと一緒に来た大人とやらは、どこに行ったかわからんのか?」
二人はジョンの変わり様にとまどいながら首を振った。
「そうか、だが、この情勢ではその仲間を捜すことは叶うまい。俺はふたたびおたずね者となった。すまないが、このままハンバーの港まで出て、パレスチナまでの船をさがす」
「ぼくらも一緒に行くよ」
太助はさっそく鐙に足をかけている。ジョンが手を貸した。太助が危なげなく、鞍に収まると洋一は渋面になった。
「ぼくは馬に乗るの初めてなんだ」
洋一がいうと、ジョンはその頭をやさしく叩いた。「ああ、お前は俺と一緒に乗るといい。さあ向かうぞ」ジョンは馬の背に上ると、こう鞭打った。「なつかしいロビンの元へ」
こうして森の盗賊たちはふたたびなつかしいシャーウッドの森に集い、ちびのジョンはロビンの魂を求め、遠きパレスチナまでの旅路につくことになったのである。
◇章前 モーティアナ
イングランド王宮の地下深くに、水の流れる巨大な鍾乳洞がある。モーティアナはそこで一人足を急がせていた。血の滴と呼ばれる占術に導かれてここまできた。その力は、師マーリンより授かったものである。師の生き血をむりやり飲まされることによって……
水たまりをはねのけ、苔むした橋を渡る。消えることのないたいまつの火が洞穴内を照らしている。この洞穴じたいが、マーリンの拠点のひとつだった。大昔の呪具がそこかしこに散らばる場所についた。マーリンの死と共に大半の効力が失われたガラクタである。そのうち、台座のようになった鍾乳石の上で、光り輝くものがあった。モーティアナは慎重な指さばきで、紫の布に包まれた水晶球をとりだした。
「吉兆じゃ、吉兆じゃ」とモーティアナはつぶやいた。下僕である三匹の蛇が、足下にまとわりついてきた。蛇を邪険に蹴り払う。そして、水晶が――師匠の死後は、暗黒色となり二度と輝くことのなかった水晶球が、二百年ぶりに脈動をはじめていた。何重にも巻かれた布の最後の一枚をはぎとると、銀白色のかがやきが、モーティアナの老いた顔をなぎ、洞穴を揺るがすかのごとく照らしだした。モーティアナは洞穴の支流に転げ落ち、動物のような驚きの声を上げた。なんたること、なんたること。我が師がよもや復活を……
と恐れおののいた。その師を貶め死に追いやったのは、ほかならぬモーティアナなのである。蛇たちは(マーリンの蛇の息子たち)すぐさまモーティアナの懐にのぼる。モーティアナは冷えた水を垂らしながら支流を出、水晶を紫布の上にのせた。彼女は老いさらばえた手で水晶を包むように持ち、震える喉に唾をくだす。
「モーティアナ……!」
野太い声が、洞穴に轟いた。彼女は驚き、危うく水晶を取り落としそうになる。突然顔を打たれ、彼女はぎゃわと面妖な声を上げた。顔を打ったのは雨交じりの風だった。彼女は顔をしかめながら、天を満たす嵐を見上げる。洞穴の景色は消え去り、彼女は荒涼とした草原にいた。木々は黒々と枯れ果て、その骨格は死した悪魔のようだ。高く生えた葦草は、人を排斥するかのようにその身を揺らしている。雷鳴が轟き、彼女の足下は沼地に変わる。そして、水晶から、巨大な青白く輝く顔が出現し、中空に浮かび上がった。
「あ、あなたさまは……」
と彼女は震える声でいう。
ウィンディゴ
声が頭蓋を揺るがし、その声は蛇たちにも響いたようで、一人と三匹は沼地にひれ伏すように這いずった。
「久しいな、モーティ。ウェールズのサンタナ、オルーリアの娘よ」
「なぜその名を」
「わしは知っておる! おぬしの罪を、おぬしの喜びを、おぬしの恨みを……」
モーティアナは泥沼に伏した顔を上げた。「ああ、あなたさまなのですね、わたくしめをここまで導き……」
「無用、無用」
とウィンディゴは言った。モーティアナは、いつのまにか、尊師、とつぶやく自分に気がついた。なぜなら、自らの血にとけこんだマーリンの血液が囁いていたからである。純血、と。マーリンの血を飲み、得た力は微々たるものだ。だが、彼女は、古にうけた血が日に日に濃くなっていくことに気づいていた。今日現れた吉兆も、このウィンディゴと名乗る男の出現を予言していたのだろう。
「我が配下、マーリンを殺したであろう」
ウィンディゴがそうつぶやいた瞬間に、体を流れるマーリンの血が沸騰をはじめた。モーティアナは悲鳴を上げて沼地を転げまわった。
「誓え! この呪われた血に! おぬしの運命に誓いをたてろ!」
誓う、誓いますうううう
モーティアナは叫んだ。全身の血管を焼き尽くそうとしていた熱は消えた。モーティアナは手足を投げ出して、沼地に横たわる。雨がさーさーとふり、彼女の顔とほおを流れる涙を打った。
「我が望みをお前が叶えるのならば、みよ」
ウィンディゴの顔の隣で、地獄の劫火が燃え広がった。劫火の中には、美しく光る珠が逃げまどうように漂っている。モーティアナ、過去はサンタナと呼ばれた魔女は、それが人の魂であることに気がついた。
「お主がなくしたものはなんだ? 奪われたものはなんだ? 人の心か? そのようなものはいかほどのこともない! お前が奪われたもの、それは甘美なる復讐ではないか!」
とウィンディゴは言った。そして、モーティアナはその人魂こそが、母親オルーリアなのだと気がついた。わずかな金銭とひきかえに、自分をマーリンに売り渡した母。ために自分は犯され、冒涜され、古の血のために呪われたのだ。彼女の喉は母の魂を欲しがり鳴っている。
モーティアナは嬉々として叫んだ。
「ああ、そうでございます。うらんでおりました、憎んでおりました、なのに、私めが微細な力を身につけ、殺人に赴いたときには、あの女は土の中に……それどころか数百年が経過しておりました」
モーティアナは草地のなかに頽れた。しばらく雷鳴のみが彼女を包んだ。
「我が陣営につくか」誘惑の声が頭部に落ちる。「なればお主に復讐の果実を与えよう」
モーティアナは顔を上げる。「私めになにをお望みです……」
「モーティ、ミュンヒハウゼンを殺せ!
モーティ、奥村左右衛門之丞真行を殺せ!
モーティ、奥村太助を殺せ!
モーティ、牧村洋一を殺せ!
そして、やつらのもつ、伝説の書を奪うのだ!」
「そ、それは……」
「やつらはロビンの復活を目論んでおる」
「ロビン・ロクスリーにございますか」
モーティアナはいぶかしんだ。誇り高きヨーマンにして、伝説の男はすでに死んでいたからである。他ならぬモーティアナが国王を唆し、死に追いやったのだ。モーティアナはそのことをウィンディゴに伝えた。
「森の仲間たちはすでに散り散りになっております。なんの力もございませぬ」
「とどめをさせ。なぜならば、やつらは我とおなじ、古の力に導かれておるからだ」
「ミュンヒ、ハウゼン……でありますか」
このときモーティアナは、まだ見ぬ老人を、尊師のためにはっきりと憎んだ。
「見よ」
ウィンディゴが目を傾けると、大空にミュンヒハウゼンが、彫刻のように青白く浮かび上がる。
「我が宿敵である。大半を失効したが、いまだ創造の力を備えておる」
そして、奥村左右衛門之丞がミュンヒハウゼンに変わった。
「中間世界の侍である。古の修行をうけ、古の力を身につけておる。独自の武刀術をつかう。気をつけろ」
「はは」
「その息子である」太助だった。「やつらは幼少より、模擬の武器を持たせ、鉄のごとく鍛え上げる。元服の前に殺すのだ」
最後は洋一だった。
「憎き牧村の息子よ。伝説の書を守りし一族の、唯一の生き残りである。小僧ゆえ、なにもできまいが、父親から何事か授かっておるやもしれぬ。息の根をとめるのだ」
「はは」
「よかろう。ならば、やつらを殺しにむかうのだ」
ウィンディゴは、彼らがどこに出る手はずかを彼女に教えた。ウィンディゴが水晶に消えると、荒れ地は元の洞穴に戻った。けれど、モーティアナの全身は濡れそぼったままである。蛇たちは泥にまみれていたのだった。
「こうしてはおられん」
モーティアナは床におちた布を拾い集め、水晶を胸にかき抱いた。洞穴の松明はすべて消えてしまっていたが、そのことにも気づかなかった(今では水晶の明かりのみが、彼女の足下を照らしていた)。
ウィンディゴは知っていたろうか。彼はあの老婆に力を与えた他にも苦しみから救いだした。数百年に及ぶ彼女の苦しみ。
それは、孤独であった。
◆ 第二章 奴隷になったちびのジョン
□ その一 モーティアナと青いヘビ
○ 1
ノッティンガムをたった翌々日、三人が到着したのはイングランド南部にある、とある交易都市だった。人の出入りの多い大きな街は都合がいい。洋一は養護院で刑務所に入れられることを恐れていたけれど、すっかりお尋ね者になってしまった。ジョンは一軒の安宿に宿をとった。
洋一は久方ぶりのベッドに転がりこんだ。ここ何週間となかったゆったりとした時間があった。この数日は生きることに夢中だったから、両親のことはあまり考えずにすんだ。だけど、あの夜以来、はじめてベッドの毛布にくるまった。二人の不在が重くのしかかってきた。洋一は二人が死んだと認めたがる心に向かって、死んでないと言いつづけた。ときには口に出してつぶやいた。ほとんど眠れぬ時間がすぎて、浅い眠りから目を覚ました。窓は開け放たれて、路地裏の湿った空気が流れこんでいた。ジョンは出かけたまま、まだ帰っていない。太助は起きていた。椅子に座り、刀の手入れをしている。彼の刀に対する入れこみようは、ちょっと神経質なほどだ。とはいえ、この世界には刀がないし、どのぐらい居なければならないのかも分からなかった。
洋一は、万一出られない可能性もあるな、と思って溜息をついた。ベッドの上で、両親が死んで以来のことばかり繰り返し思い出している。体は疲れている。休まなければならないことはわかっていた。この先ゆっくりできる時間があるとは彼にだって思えない。毛布をどけて、ベッドを下りた。彼が起きたのを見ると、太助も手を止め顔を上げた。
洋一は窓際に行き、ぼんやりと外を眺める。宿は路地裏にあって、あまり陽も射さない。隙間の空がもう青かった。軒下には巣があり、鳥が鳴いている。緩やかな時間だというのに、ここ数日間の記憶がどっと押し寄せてきた。彼は息を詰めて身を震わせる。どれも幼い脳が吸収するには強烈な体験ばかりだ。両親の死、院長の虐待、ノッティンガムでの戦闘……いずれもまとわりついていたのは血と痛みだった。記憶の鼻には、鉄混じりの臭いがする。院長の日本酒の香りも。血まみれの死体や絶叫が、ずっと頭をちらついている。
太助が、そんな洋一を、無言で見ている。
遠い世界に来たんだな、と洋一は思った。本の世界は、ごっこ遊びなんかじゃない。戦いには本物の血と死体がある。あんなものが現実だったとは、今でも信じることができなかった。つまるところ、彼は本の世界が恐ろしかった。とてもやっていけないよ、と一人ごちた。本当は誰かに愚痴をこぼしたかったのに、側には太助少年しかいないのだ。
洋一が故郷を離れたのは、ほんの数日かもしれないが、両親からこんなに長く離れたことはない。洋一はこの世界に来て初めて二人が死んだことを信じる気になった。洋一は身が張り裂けそうで、体をおった。胸に穴が空いたみたいだ。その穴がなにかで埋まると、自然に涙があふれた。穴を埋めたのは悲嘆だった。洋一は瞼も閉じず表情も変えず、ただ涙だけを流している。感情の波に流されたら、きっとこれからやっていけなくなる、二人の仇は討てなくなると分かっていた。洋一は下唇を噛んで、叫びたくなるのをぐっと堪えた。窓枠についた手に、ぽたぽたと涙が落ちた。彼はその手を固く握りしめていた。後ろで太助が立ち上がったのが気配でわかった。
洋一は窓枠に向いたまま話そうとした。けれど、喉が詰まってなにもいえない。頭を振ると、涙も散った。洋一は涙を流すことで、両親に対する惜別と、決着をつけようとしていた。
「ぼ、ぼくは……」とようやく言った。「ぼくは弱虫だ。二人の仇なんてとれるわけがないって思ってる。父さんと、母さんが死んで……殺されて悔しいけど、ぼくは、怖いんだ」
もう立てなかった。
洋一は窓枠によりかかり膝をついた。下を向くと、涙が鼻筋を伝い、鼻水と混じって落ちた。洋一が本当に怖かったのは、なにもできないことだったのだ。ウィンディゴには両親の敵をとると啖呵を切ったが、その実彼は無力な小学生にすぎなかった。彼は自分にはもう価値がないと思った。自分の存在意義は両親にこそあったのに、少なくとも両親にとっては価値のある存在だったのに、その二人がいなくなった今、彼の価値は無になった。現に図書館とはほど遠い本の世界で、寄る辺のない帆船みたいにぽつりと窓辺に立っている。そうして泣いている自分がいよいよ情けなく、洋一は短い声を発して泣きだした。帰る場所はない。目的もわからなくなった。ロビンの世界にきて、ウィンディゴを倒す。それがいかに途方もないことか思い知らされた。かれときたら団野院長すらやっつけられなかったのに。
そんな洋一のうなじを早朝の穏やかな風がなでている。太助はその風を一身にうけながら、洋一の背後でともだちのことをながめていた。どういっていいものかわからなかった。彼は同年代の少年と接した経験があまりない。太助という少年は生まれたときから侍だったし、これまでどんな物事にもけじめというものをつけて生きてきた。彼はこどもかもしれないが、すでに他人をあわれむような人間ではなかったのだ。
太助は洋一を、かわいそう、とは思わなかった。ただ深くその悲しみを共感していた。悲しみが情を厚くするのなら、彼はその感情が人並み以上に分厚い少年だった。侍として育った彼は、涙をたしなみとはしなかったが、洋一の親の死もその悲しみも、まるで自分のことのように感じている。なによりも、この少年は死というものと、いやというほど直面してきた。太助は洋一に近づいて、そのうなじをそっとなでた。うなじは熱く、冷たく、震えていた。
「こわがるのは恥ずかしいことじゃない。もう泣くな」
「でも……」
「こわいのはしかたがないじゃないか。誰でもそうだよ。大切なのは逃げださずに、立ち向かうことだ。ぼくを育ててくれた人たちはそうして生きてた」
洋一は腹をたてて言った。「ぼくは侍じゃない! 普通の小学生だ! ぼくは太助とはちがうんだ!」
「違わない。なにがちがうんだ」
「ちがうじゃないか!」
洋一はきっとふりむいた。その視線に、太助も深く傷ついた。結局洋一の傷口はあまりにも深すぎたのだった。
「ちがうじゃないか! ぼくは刀も使えない、なにもできない、今だってジョンのお荷物だ! ぼくは……ぼくは……こんなことなら」
「こんなことなら?」と太助もきっとなった。洋一の泣き言に、自分でも意外なぐらい腹が立った。「養護院にいた方がいいというのか?」
「足手まといになるぐらいなら……」
「足手まといなんかじゃない、そんなふうに思うな」
太助は洋一の肩をぐっと掴む。その力強さに、今度は洋一がぐらつく番だ。
「ぼくだってお荷物だった。ぼくを守るために侍たちが何人も死んだ。ぼくはそれがいやだったんだ。生きてるのがぼくじゃなかったら、大人の剣客だったら、父上はもっと楽だったろう。ぼくがいなければ、みんな死なずにすんだんだ!」
話しているうちに、この腹立ちが実は自分に向けられたものだと気がついた。太助は気落ちして、視線をそらした。
「彼らはぼくの師匠だった。ぼくに人生を教えてくれた。その人たちがぼくなんかのために死んだんだ。自分がほとほといやだった。ぼくだって侍だ……なのに、人の助けで細々生きてる。そんなのみじめじゃないか?」と問いかける。
洋一は驚いた。考えてみると、太助は物心ついたころからお尋ね者だったのだ。太助が自分や自分の友人たちとはいっぷう変わっているのは、無理からぬことだった。洋一は今まできちんと考えてこなかった。目の前にいるのは本物の侍だったのだ。
「ぼくは父上にも言った。ぼくを側に置かなければいいじゃないかって訊いた」と涙がにじむ。「もう見捨ててほしかった。弱音なんて吐いたらだめだってことは知ってる。でも、侍らしく振舞いたくても、できなかった」
太助は洋一のことをもう見ていられない。真下を向いて震えている。彼はこんな話のできる同世代の友人をこれまで持たなかった。元の世界にいたとき、太助はずっと侍として振る舞ってきた。思えば、こうして大人の庇護を離れたのさえ、初めてのことだったのである。
「彼らはぼくを侍として育ててくれた。でも、父上を残してみんな死んだんだ」
「それは君のせいなんかじゃ……」
太助は睨むような顔を上げた。けれど、上げた目は弱々しかった。太助の瞳は揺れたが、ぐっと堪えてもいる。
洋一は泣けよ、と思った。悲しい気持ちでこう考えた。思い切り泣けばいいじゃないか、泣いちまえ!
けれど、太助は泣かなかった。ただ、そっと顔をそむけたのだった。
「父上はぼくを叱らなかった。できないことばかり考えずに、できることをしっかりやれ、って言った。みんなできることをしっかりやって死んだから、誰も恨んでないって言うんだ」と唇を噛んだ。「でもぼくは悔やんでる――あの人たちに生きていて欲しかったから。だからはやく大人に、一人前になりたい」
父親はあのときこう言ったのだ。誰だってなんでもできるわけではない。だから、侍は助け合うのだと。だから彼は助け合わねばだめだと思っている。洋一のことを助けなければと思っている。侍たちがそうしてくれたように。
洋一も目をそらした。悲しみに揺れる友人を、彼は見ていることができなかったのだ。「でも、ぼくにできることなんて……」
「君には伝説の書があるじゃないか」
「伝説の書なんて持っててもしょうがないよ。ぼくは本の使い方なんて知らない。あんな本使いこなせるわけがないよ! 男爵だってそう言ってたじゃないか」
「聞いてないのか?」
「なにをだよ」
太助は答えるのを迷うように目を伏せた。「おじさんが、父上に言ったんだ。君には文才がある。だから男爵は、君なら伝説の書が使えるかもしれないと思ったんだ」
「そんな――」と洋一は喉で声を詰まらせた。「父さんが? 父さんがそう言ったの?」
洋一は急いで涙を拭った。そうすれば太助の言葉がよく聞こえるとでもいうみたいに。太助は下を向いて言葉を選んでいた。
「ウィンディゴには大人の剣客もみんなやられた。生き残った侍は父上とぼくだけなんだ。だから、男爵は、君と伝説の書にかけた。君なら伝説の書が使えるからだ」
「そんな、ぼくは、そんなこと……」
「できるよ。おじさんは、君がすごい小説を仕上げたって喜んでた。そうなんだろ?」
そんな。洋一は自分でも気づかないほど呆然として呻いた。恭一がそんなふうに自分のことを人に話していたなんて、今まで知らなかった。一年も前のことだ。洋一は「ナーシェルと不思議な仲間たち」という一風変わった冒険小説を書きあげた。そういえば恭一に書き方をいろいろと教わりながら書いたのだ。父親は小説家でもなんでもないが、それでも洋一は教えを守って一生懸命書いた。それに小説を書くことはすごく面白かった。恭一が喜んだことはまちがいないし、自分を認めてくれていたことに洋一は深い喜びを感じた。その驚きは哀惜の念に変わった。後悔にも。人の口を通して聞くのではなく、面と向かってそのことを話して欲しかった。喜ぶ顔が見たかったのだ。
「ぼくは伝説の書のことじたい知らなかったんだ……」
洋一がつぶやくと、太助もうなずいた。
「本を使いこなせるのは強い文を書ける人間だけらしいんだ。つまり文才のある人間、物書きの人たちだよ。ウィンディゴはそうした人間を怖がってる。あいつは侍よりも、小説家を恐れてた。彼らが伝説の書を手にすることを怖がったんだ。だから、真っ先に殺してしまった」
その話に洋一は震え上がった。侍たちが殺されるのはまだ想像がつく。だって彼らは戦う人たちだ。でも、作家はちがうじゃないか
「おじさんはいずれは君もウィンディゴに狙われるとわかっていた。だから、君に文章修行をさせたんだよ」
「父さんが?」
洋一は信じられないとつぶやいた。あのお遊びにそんな意味があったなんて。そんなふうに思っていたなんて。洋一はともだちと比べて多少文章がうまいだけで、自分が特別だとはぜんぜん思っていなかった。
「だから、男爵は君に伝説の書を持たせたんだよ。男爵は本の世界の住人だから、伝説の書がそもそも使えない。父上は剣の達人だけど文が書けない。つまりロビンの世界の誰も伝説の書は使えないんだ」
と太助は言った。本の世界で作家を見つけてもその人には伝説の書が使えないのだ。ミュンヒハウゼンに至っては自分の創造の力すら無くしてしまっている。
「この世界にあるかぎり、伝説の書はある意味で安全だってことだよ。だって、使いこなせる人間は君だけだから。でも、父上と男爵が死んだら、ぼくらだけでやつらと戦わなきゃいけなくなる。わかるだろ? その本をつかう必要があるって事」
「そんなの無理だよ! 文が書けるからって、伝説の書が使えることになんかならないじゃないか!」
洋一は懐から本をとりだした。赤い表紙をじっとみつめた。二人はともに伝説の書を取り合った。
「この本は大事なんだな」と洋一は言った。
「ウィンディゴもこれを狙ってる」太助はうなずいた。
「じゃあ、モーティアナも?」
「きっと、ぼくらをさがしてる」
洋一は恐ろしくなった。本から目を反らした。
「ジョンにも話した方がいいんじゃないかな。三人で本を守った方が――」
「だめだ。ジョンには教えられない。信用できるが、精神がまだ不安定じゃないか。伝説の書は誰にも渡してはいけないし、本のことを教えてもいけない。ぼくらで本を守るんだ」
洋一は責任の重さを感じて身震いした。「できるかな」
「わからない。だけど、ウィンディゴに対抗できるのは、この本しかないよ」
「ウィンディゴがこの世界に来ていたら」
「あいつは本の世界に入る方法を知らない」と太助。「問題は伝説の書のことがよくわかっていないことだよ。誰が作ったのか、いつ作られたものなのかも誰も知らないんだ。それに、男爵はその本が危険だといっていた」
洋一は怖じ気づいたが、本から手を離せない。伝説の書は使われたがっているんじゃないかと思えた。それに本を使いたい、なにかを書きこんでみたいという衝動に彼は駆られている。頭の中で文章が飛び跳ねた。あの物語を書いて以来のことだった。
洋一は自分の変わりようが恐ろしかった。本はあいかわらずの熱気を帯びて、彼の指先に食い付いてくる。男爵のいうとおり、本に意志があるのなら、きっと狂気を帯びていると思った。胸に起こった熱狂が本のせいなのか単なる創作の衝動なのかわからなかったが、放っておいたら自分も狂わされるにちがいないと思えた。
洋一はどうにかして本から指を離す。それが太助の手に渡ったときは、心底ほっと胸をなで下ろした。
「元の世界で作家を探して渡した方がいいよ」
「だめだ。そいつが悪人で、伝説の書を奪われたらどうする? それに本を使いこなせる作家でなきゃだめだ。物書きの達人でなくちゃ、ウィンディゴとは戦えない」
「文豪を捜せっていうの?」
「ぼくらに味方してくれる文豪だ」
「そんなやついっこないよ」
「だから、君なんだよ」太助が言った。洋一は思わず息をのんだ。「現実世界の文豪だって、ウィンディゴ退治に協力してくれるわけじゃない。でも、君なら条件が合ってる。本の世界を守ってきた一族の一人じゃないか。だから、男爵は、君に修行を積ませて、伝説の書を使わせるつもりだったんだ」
洋一は途方に暮れてうろついた。顔を上げたときにはやっぱり途方にくれていた。自分が弱虫だとは思わない。でも、勇敢だったことだってない、普通の小学生だ。
「まさか、こんなことになるなんて……」
「やっぱりぼくらはパレスチナまで旅なんてできないよ。父上と男爵は、きっとぼくらのことをさがしてる。イングランドから出るべきじゃない。だって、フランスはロビンの世界には元々存在してないだろ? あそこにはなにもないんだ」
洋一はちょっと迷ってから答えた。「空白地帯ってこと?」
「そうだよ。なにもないんなら、なんとでもできるっていうことじゃないのか?」
洋一はなにかを避けるように目線をさまよわせた。
「ウィンディゴのことをいってるの? あいつがなにかしてくるって……?」
「あいつがなにもしないと思うか?」と太助は答えた。「あいつは創造の力を持ってるんだぞ。その力をどこから得ていると思う? 本の世界から吸い上げてるんだ。だから、ぼくらはやつと本のつながりを断ち切らなきゃならない」
「でも、ロビンを見つけなきゃ、物語を元に戻すなんて無理だよ」
太助は窓枠に手をついて地上を見おろした。路地裏では朝っぱらからこどもたちが走り回っている。
「ずっと考えてたんだ。ロビンを助ける方法を。伝説の書に、こう書くのはどうかな? ロビンがイングランドの港町にもどってきてるって」
洋一は本を抱えこんだ。まるで、恐ろしい魔物を見るみたいに太助を見た。「本気でそんなこと考えてるのか? この本に力があるって」
「なけりゃおじさんだって、その本を守りはしない」
太助は目線をそらさずに言った。洋一はつい引きこまれた。
「でも、ロビンは最初から死んでることになってたじゃないか。それがほんとだったら?」
「そこが問題なんだよ。男爵はその本が危険だといってたろ? つまり、伝説の書がつじつまあわせをしてしまうって言うんだ」
「つじつまあわせ?」
洋一は伝説の書に目を落とした。太助の話はこういうことだ。ロビンがイングランドを目指そうとしても、現実にはいくつも障害がある。本はその間をどう埋めるかわからない。下手をすると、街にたどりつくのは、ロビンの死体ということになりかねない。
「だって、そうだろ? この世界は作者の頭の中にあるんじゃない。ちゃんとした現実の世界でもあるんだ。その世界を本の力で作り替えるということは、すでにある世界に矛盾を起こすってことだ。下手なことは書けないんだよ。逆にいえば無理の起きないような自然な物語を考えろってことだ」
「そういうの、父さんに聞いたことがある」
洋一は興奮して言った。矛盾があるとストーリーは破綻する。そんなストーリーは自分でも書いて面白くないからすぐわかる。広げた話もまとまらないときている。もちろん洋一はこどもだから、恭一もこのとおりいった訳じゃない。話はもう少し簡単だった。けれど、彼は実際に書いて失敗もして、ストーリーをうまく書く骨はつかんでいた。彼はその一瞬いけるんじゃないだろうかと考えた。
「ジョンに話を聞いておいた。ロビンはシニックという港町から大陸に渡ったらしい。そこが十字軍の一大拠点だったっていうんだ」
「そこにもどってきたって書けっていうの?」
太助は力強く頷いた。「やるしかない。ロビンが生きていないのなら、パレスチナに行く意味なんてない。だいいち、パレスチナにロビンがいることじたい、君の思いつきだろう」と言った。「死体を探すために、パレスチナに行くなんてできないぞ。こうしている間も、ウィンディゴは暴れ回ってる。ひょっとしたら、本の世界に入る方法を見つけてくるかもしれない」
洋一は首を左右に振って否定した。「君はわかってないよ。ぼくは遊びで書いてただけだし、ぼくの父さんは図書館職員だよ。作家ですらないんだ」
太助は目鋭く光らせて言い切った。「もうやるしかないんだ」
洋一は迷った。が、心は八割方決まっていた。だって、彼はこの世界を頭から否定している。この本から出られるなら、なんでもしたろう。
「ぼく、こんな世界にいたくない。ロビンが生きてたら、きっとぼくらを助けてくれるよ」
太助は頭をかきあげて唸った。
「なんだよ!」
「ロビンはたしかに物語の主人公だけど、ジョンだって泣き虫になってたろ? そんなにうまく運ぶかな?」
「そんなことない。ロビンなら大丈夫だ。そんで、男爵とおじさんを見つけてもらう。そしたらこんな本の世界はおん出ておしまいさ」
「洋一」
太助はあきれたようにいう。
「ぼくは正直、外よりもこの世界の方が安全だと思うぞ」
洋一はそっぽを向いた。太助が言いたいのは、この世界にはウィンディゴが入って来られないからということだろう。洋一はそんな話聞きたくない、ウィンディゴは、入って来れなくてもちょっかいは出してきてるじゃないか、モーティアナがいい例だ、と腹を立てた。
洋一は伝説の書を振り立てた。太助に否定されて向きになってもいた。
「書こうよ。こいつは父さんが守ってきた本だ。ぼくらの本だ。ぼくら側の不利になんて働くもんか」
と洋一は言った。そう信じた。まだそのときは。
○ 2
二人は話し合った。ロビンを救うのはかれとともに戦った十字軍の騎士たち、ということにした。大陸にあるイングランド領土に流れ着いたということにすれば、生存の確率はグッと高くなる。太助がジョンに聞いた知識はずいぶん役に立った。
洋一は床に本を広げた。あぐらをかいて、万年筆のキャップをとった。ナーシェルの物語を書いたのはずっと前のような気がする。彼は自分が生みだした黒髪小麦色の肌の少年を思い描いた。背筋を伸ばし、肩をくつろげ、息が深くなるようつとめた。恭一が小説を書いていたのかは定かではない。が、彼の父親は文を書く上で必要なことを、かなり細かなことまで話していた。洋一は父親に教わったことを思い出していく。姿勢を整え、呼吸をさらに深くする。骨盤が次第に立ってくる。胸とおなかがゆったりとふくらんでいる。
彼は海峡に立つロビンの姿を思い描いた。父親の言葉を思いだす。それは少年には難しい言葉だったのだが、彼の体には深く刻みこまれていた。
情緒的に、淡々と描くんだ。
太助が固唾をのんで見守る中、洋一はついにペンを走らせる。万年筆のペン先からインクがこぼれて、紙に染みていった。彼は文章を考えていなかった。言葉は体の奥からあふれだしてきた。洋一は伝説の書に殴り書いた。
『ロビンフッドは死んではいなかった。彼は仲間とともにパレスチナを脱出し、フランスの海岸部に到着していたのだ。そこから海峡をこせば、懐かしいイングランドだ。ちびのジョンや、森の仲間たちが彼の帰りを待っているだろう。ロビンは、仲間とともに、海峡をわたるチャンスをまった。その旅の間も、フランスに着いてからも、彼を守ってきたのはロビンに付き従った十字軍の騎士たちだった。そして、ロビンの長い盟友となったヨーマンたちが側にいた。』
太助は目をみはって、文を追った。洋一の書く文章は後から後から消えていく。本が文章を飲みこむみたいに消えていった。洋一はまるでそのことにも気づいてないみたいだ。
これはすごい、こいつほんとに伝説の書をつかっているぞ!
太助は洋一に声をかけたかった。背中を思い切り叩いて褒めそやしてやりたかった。そこをぐっと我慢する。今は創作の邪魔をしたくない。
太助が扉の外に不穏な気配を感じてふりむいたのはそのときだった。彼はすっと身を立て、廊下に目を向ける。扉は閉まっているが、何者かが近づくのを感じた。痩せた床板を踏む、かすかな軋みを耳にした。太助は幼少のころから危険と抱き合うような生活をしてきた。その直観力には並外れたものがある。自分の感覚を信じ切っている。廊下を歩く人影すら目に見えるようだった。
太助は友人を見おろした。洋一はまだ書いている、まだ途中だ。けれど外にいる誰かはどんどん近づいてくる。太助は相手の用があるのはぼくらだと思った。全身の細胞が危険を告げて酸素を欲しがる、生き残るために。
その誰かが部屋をまっすぐにめざし、扉の前に立つにつけ、彼はもう限界だと思った。
『彼らはイングランド王妃アリエノールの持つフランス領土にたどりついた。そこはもうイングランドの勢力下だ。ロビンは常駐していたイングランド海軍の手を借りて、どうにか……』
「洋一、本を隠せ、ペンを止めろ」
と太助は小さな声で鋭く言った。同時に壁に立てかけた刀に向かって足を滑らせていた。
「なんだ、なんだよ。まだ途中じゃないか」
「声をたてるな。静かにするんだ」
太助は床板を鳴らさないよう慎重に足を滑らせ、腰を落としながら刀をとった。空中で身を入れ替えるようにして扉に向いた。その誰かは部屋の前で止まっている。
洋一が本を閉じ、万年筆をポケットにしまう。
扉を叩く、ほとほと、という音が聞こえた。二人は鍵のかかった扉を無言で凝視した。
太助は扉から目を離さずに囁いた。
「合い言葉を言わない。ジョンじゃないぞ」
太助は鮫皮の柄に指をかけ、そろそろと刀を抜いた。扉が、また、ほとほと、鳴った。か細い、中に来訪の意思を伝える気がないような強さで叩いている。二人は顔を見交わし、それぞれの頭に浮かんだ疑問をぶつけあった。
外にいるのは宿の主人か、それとも兵隊か?
太助がスルスルと戸口に向かうと、洋一はあっと声を上げそうになる。太助は左手に刀を持ち、ドアノブに指をかける。扉に鍵はない。体が震え、無意識のうちに息を呑む。太助は扉に口を近づけ、
「ウィンディゴか……?」
「尊師の名を口にしやるでない……」
嗄れた声が窘めるように言った。太助は不意打ちを食わぬよう左に逃れた。もうその言葉だけで十分だ。モーティアナだ。イングランドの魔女が外にいる。
「そんな」と洋一が言った。「なんでここがばれたんだ」
「入れておくれよ、憐れな老婆だよ」
太助が刀を抜こうとすると、扉が熱を放ちはじめた。太助はそのあまりの熱気に危険を感じて、部屋の中央に移動する。扉がジューっジューっと音をたて、真ん中から煙が上がる。モーティアナが扉に手を当てているのだ。彼女の手は熱くなり、手の形をしたハンダゴテのように扉を黒ずませていく。真ん中から煙が上がると、炭の円はどんどん広がり、中心からぼろぼろと崩れていった。
洋一が太助の背後に来て、「本物なのかな」と訊いた。
「どういう意味だ?」
「ロビンの物語には魔女なんていないじゃないか。映画でだって、魔法は使わなかったぞ」
太助が洋一と顔を見合わせたとき、ついに扉は大きく崩れた。穴の向こうに花柄のスカーフをまいた老婆がいる。炭になった扉をつかみ、さらに穴を突き崩した。花売りの格好をしているが、その目は黄色く瞳孔は細く尖っている――
人間の目じゃないぞ、と太助はつぶやく。モーティアナが口を開ける。血糊のついたどでかい牙が見えた。一同は扉を挟んで睨み合った。くそ、男爵がいてくれたら。
「お前が、モーティアナか」
「異国の小僧かい」
「なんで、ぼくを知ってる?」
「ちびのジョンはどうしたえ」
太助は思わずふりむいて洋一を見た。驚いた、こいつなんでも知っているらしい。
「せっかく骨抜きにしてやったのに馬鹿な男だよ! ロビン・フッド、イングランドの魂! やつは死んだあ!」
「だまれ!」と刀を下段に引きつける。
「お前のことは知ってる!」と洋一も言った。「イングランドの魔女だろ!」
「小僧二人であたしの相手をするのかい?」モーティアナは、ケケケッと大笑した。「分際をわきまえろ!」
魔女の髪がざわざわと逆立った。頭部に巻いたスカーフに火が放たれ、鳥のように部屋を羽ばたく。二人の周囲に、ぽとりぽとりと火が落ちた。少年たちは炎の円で囲まれる。スカーフはどんどん小さくなり最後の身が落ちると、炎は列車が走るようにつながりあって、魔法陣をかたちづくった。
洋一は炎をさけて足踏みをしている。「あいつは本物だ。本物の魔女だ!」
「落ちつけ、洋一」
と言う太助の身内でも恐怖が暴れていた。心臓が脈打って、それを押さえるために胸を叩いた。斬れるのか? と彼は久方ぶりに刀を疑う。太助という少年は大人に混じって堂々人も斬ってきた。だが、魔女だけは斬ったことがない。会うのもはじめてだ。大人たちは周りにいない。けれど、彼の背中には洋一少年がいる――逃げるな、奥村、あいつを斬るぞ! と太助は目を怒らせる。これまで侍たちが彼を守ってきたように、彼自身が誰かを守る番だった。怖がるな、と太助は胸の内で自らの怖心をどやしつける。もうやるしかないんだ、あいつをぶった切れ!! そう思いこむと、フツフツたる闘志が胸のうちに湧いてきた。太助はじわりと足を進めて言った。
「お前なんか怖くないぞ! 何十人でも、何百人でもかまうもんか! さあ、かかってこい!」
「ナイトかい? ナイトなのかい?」
モーティアナの声が、ガラリと変わる。喉がつぶれてダミ声となる。両手で扉をつかむと、扉は枠ごと炎を吹き上げ崩れ落ちた。炎は灼熱しているのにモーティアナは意に介してもいない。炎を背負い少年らを睨む。老婆の姿はまったくの悪女だった。
モーティアナが両腕を上げる。「ナイトは嫌いだよ、殺してやる!」
「だめだ、あいつは本物だ。逃げよう!」
洋一は、円を出ようとしたが、見えない壁にはじき返された。
やっぱりだめなんだ、と太助は思った。
「ウィンディゴも本物の魔法をつかった。あいつが本物なら、逃げるなんて不可能だ」と太助は刀を鞘におさめる。「洋一、ぼくの後ろに隠れろ……」
「どうするんだ?」
太助は答えなかった。答えることができなかった。そのぐらい集中していた。彼は少し足を開いて立ち、刀の鍔を親指で押し、そっ、と鯉口を切った。
ガイ・ギズボーンと斬り合ってわかったことがある。この世界の人間は、居合術を知らないのだ。侍が高め極めた刀術をイングランドの人たちは使わない。ウィンディゴがモーティアナに教えたとも思えない。そして、侍の中には抜刀流の達人たちがいて、彼は幼少のころから雑多な流派を叩きこまれてきた。その侍たちは、彼よりも早く命を落とした。そのことが深く彼の心を傷つけていた。あいつはウィンディゴの仲間だ! 今こそ敵を討つときだった。
太助はこの一撃にかけることにした。唇を舐め皮膚を湿らせる。円陣の外に出られないなら、モーティアナが近づくのを待つまでだ。だが、遠くから魔法をかけられては、ひとたまりもない……
思えばこれまでの幾度とない戦いも、大人たちが側にいてくれた。たった一人で敵と相対するのは、その長い戦いの経歴のなかでも(人生の短さを割り引いてもだ)初めてのことだった。彼は目線を下げてモーティアナを視界から遠ざけた。茫漠と視野を広げ、そうして落ち着こうとする。父親たちの教えを思いだす。
居着くな、居着いたらだめだ、と念仏のように唱える。居着くな、とは、留まるな、ということだ。
「父上……」
とつぶやいたのを最後に太助はほとんど目を閉じた。踵をべったりと地につけた。両手は鞘にひっかかっていた。左右に背骨を揺らし、腰骨を上げ、自在を得ようとした。
○ 3
後ろで、窓の雨戸がバッタリと閉まった。視覚を奪われ鼻先も見えなくなる。まるでこの世から光が消えたみたいだ。その闇の中でモーティアナの炎が黒や青に色を変えながら、ジワジワと漆喰に広がっていく。あれは魔法の炎だ。生き物のようにゆったりとした動きで炎の手を伸ばしている。額に汗がにじみ、目に入るのを嫌って眉をしかめる。
あいつぼくらを円から出られなくして焼き殺すつもりか。
緊張で視界が狭まる。炎の揺らめきの向こうで、モーティアナが小さく見えた。太助は、だめだしっかりしろ、と自らに言い聞かせる。目測を誤らないよう気を落ち着けようとした。
モーティアナは扉を砕きながら、部屋に入ってきた。
「伝説の書はどこだあ!」
「ぼくらが持ってる!」太助は恐怖を払いのけるように大声をだした。「本を取りに来たのか!? 欲しければ取りにこい!」
「殊勝だねえ。こどもは好きだよ。本当だよ」モーティアナが近づいてくる。「だって、おいしいから……」
モーティアナの口が火を噴いた。炎は魔方陣の障壁に当たって左右に割れた。が、猛烈な熱さで太助の全身からどっと水分が抜け出てくる。その熱だけで火膨れが出来そうだ。太助はモーティアナの炎にあぶられながら、下がろうとする心をぐっと堪えた。下がるな、踏みとどまれ! 胸中が恐怖に負けて悲鳴を上げる。本当に悲鳴を上げたのは洋一だった。それがモーティアナの残酷な心に火をつけた。
「骨までしゃぶってやる。頭から飲みこんでやるよ。骨を砕いて、生きたまま溶かしてやる。皮膚が溶けるのはいいよお。血がトロトロと出て、それがあたしの胃を満たすんだ。まずはお前からだ、異国の小僧!」
太助はモーティアナの首を刈り取るために、さらに腰を屈める。炎が邪魔で魔女が見えない。モーティアナが近づくのを熱にも負けずにぐっと堪えた。もっとだ、もっと近づけ、と自分に言い聞かせる。真剣の斬り合いでは、相手を遠くに感じるからだ。
太助は自分の恐怖を知っていたから、刀を振りたがる心をぐっと堪えた。太助の大刀は備前長船の古刀、貧乏御家人のひ孫たる彼は本来なら目にすることも叶わなかったはずの大名刀である。今は亡き吉村勘三郎という人物から譲り受けた。研ぎ減りがして刃区もわからないほどだが、反りの深い刀身が彼を励ますように腰間に揺れている。太助は吉村の死に報いるために、あいつを斬ろうと胸を奮わせる。炎が彼をあぶり、生臭い体臭が匂った。モーティアナがさらに近づいている。
あと少し、もう少しだ。
「本をお寄越し!」
炎が割れてモーティアナが現れた。魔女が巨大な口を開いた瞬間、奥村太助は足を踏みだし、老婆の足にほとんど脛をぶつけながら、抜刀術を解きはなった。モーティアナが、あ! と呻いて、小動物のように跳び下がったときには、太助は刀を抜き放っていた。それがモーティアナのこの世で見た最後の光となった。太助の腕と刀はまるで鞭のような軌道を描いた。彼はモーティアナを十分に引きつけてはいたが、モーティアナの動きは思ったより素早く、刃は喉に掛からなかった。それでも、老婆の醜い両眼を真一文字に切り裂いた。鮮血が炎に焼かれ、舞い上がる。
太助は留めを刺そうと動揺した。さらに前に進み出て、円陣の壁に跳ね返された。
「くそ、殺せなかった! 円を出られない!」
太助は見えない壁を拳で叩いた。洋一が、円陣の炎を伝説の書をつかって夢中で叩きだす。
モーティアナは宙を駆けるようにして、壁際に下がる。真一文字に裂かれた傷からは、涙のような血が垂れる。炎が左右に津波のように流れ、壁を燃やし尽くしていく。
モーティアナが絶叫すると、自らの顔面を飲みこむほどに開いた口から炎が吹き上がり、宿の天板を轟々と燃え上がらせる。
「こ、小僧、よくもやったね」
モーティアナは呪いの声を上げた。
「許さない、呪ってやるよ。苦しめてやる。血の一滴までも許すもんか!」
モーティアナの骨格がボコリボコリと音を立てて変わりはじめた。腕が丸太のように太くなりのたうちだした。太助と洋一は円陣の火を必死に足で踏み消そうとする。魔法の火はミミズのようにしぶとくのたうつ。そして、視力を無くしたモーティアナが無差別に攻撃をはじめた。その腕は壁をうち、安宿の漆喰が音をたてて崩れた。腕はさらに蛇のように鱗を生やして伸びた。
どこだ、小僧!
太助と洋一は、眩しい光に顔を顰めた。モーティアナの腕が外壁を突き崩したのだ。表から風が吹きこみ、焼けた肌の上をさらさらと流れる。戦いに夢中で気づかなかったが、外から罵声が轟いていた。突然の火事に人が集まっているのだ。
「薫るよ」とモーティアナが言った。「人間の小僧の匂いだ。甘ったるいよ。薫るよ」あらぬ方を向いていたモーティアナの顔が太助を向いた。「そこにいたね」
太助は夢中で刀を抜いた。モーティアナの腕が胸元めがけて伸びてきた。太助は青眼に構えた刀を右に左に傾けて、老婆の腕を叩き落とす。だが、モーティアナの腕は鉄のように固い、斬り裂くことができなかった。そのうえ攻撃を受けるたびに太く重たくなっていく。腕が波打ち、床を叩き、板がみしみしと砕かれる。円陣が歪み、見えない壁がなくなった。
太助は魔法陣の外に踏みだした。腕が斬れない以上は、モーティアナの体を切り裂くまでだ。モーティアナの腕が体を打ち、彼は大刀を取り落とした。太助は第二撃を右手に交わし、抜刀の要領で清麿の脇差しを抜きざま老婆の大腕に斬りつける。彼の刃はジャラジャラと腕の上を流れる。くそ、鱗だ。この鱗が鉄のように固いんだ。彼は老婆の大腕にはさまれて、肋がミシミシと音を立てた。気がつくと、夢中で叫んでいた。
「洋一、伝説の書をつかってくれ!」
「どうやったら……」
太助に答える術はなかった。二本の巨大な腕に押し戻され、その地位を失う寸前だった。腰を落とし、足を踏み換えると、思い切って体重を前方にかけた、粘りをかけて進んだ。モーティアナは轟然たる火炎を放っているが、太助が前に出たことで、巨大になった腕が皮肉にも炎から守ることになった。
「小僧!」モーティアナは火炎とともに叫ぶ。「燃えろ、小僧、灰になれ!」
太助はじりじりと前に進み、ようやく身動きのとれる立地を見つけた。モーティアナの腕は獲物を探して狂いのたくっている。殺せる、洋一、こいつを殺せるぞ! 一歩踏みこめば、胴体に刀が届く距離だった。だが、太助はふりむくことで、そのチャンスを自ら潰したのだった。彼は最後にできた友人の姿を確認しようとした。洋一が心配だった。モーティアナの腕がかほどに荒れ狂っては、叩き潰されてもおかしくないと思ったからだ。
――命の遣り取りでは、どんな些細なことにも気をとられてはいけない
居着くな。というのが父の教えだった。その瞬間、太助は洋一に気を止めて、紛うことなく居着いていた。モーティアナはその好機を逃さず、腕を元に戻すと少年の痩せた両肩を掴み上げたのだった。
「捕まえたよ……」
○ 4
「ちくしょう! ちくしょう!」
洋一は太助の姿を確認しながら、伝説の書を急いで開いた。太助の体は大蛇の胴に飲まれて服先も見えない。ペンが、ぶるぶると震える。キャップをとるのがやっとだった。周囲ではモーティアナの腕が荒れ狂っている。皮肉にも、円陣に残された効力が、少年を圧搾死から守っている。洋一は顎をつかみ、髪をかき上げた。なにかを書きこもうとしながら、真っ黒なパニックに飲みこまれていた。文を生み出せない。それどころかペン先すら定まらず、紙に醜いアフロを描いた。
小説を書いていると、猛烈に書ける瞬間がある。彼はそれをスイッチと呼んでいた。けれど、心と体が震えてそのスイッチが押せないのだ。スイッチを押すのには平常心が必要なのに、状況が彼の期待を裏切っている。
「無理だよ! 文章なんて思いつかない!」
洋一はぶるぶる震えて、息まで詰めていた。書くんだちくしょう、太助が死んじまうぞ! 洋一は父親を思いだした。その瞬間落ち着かないまでも、どうにかこうにかスイッチを押した。息を強く吸いこんで、それとともに文をうみ出そうとする。ジョン! 泣き虫ジョン! ぼくらを助けて!
彼はジョンの姿を、彼が街を駆ける姿を生み出そうとした。彼はそれを文に変えていく。自分の見たものを、感じたものを言葉にかえたのだ。スイッチだ、スイッチオンだ!
洋一は自分の生みだす小汚い文字に夢中になった。その瞬間は炎からもモーティアナの恐怖からも解放されていた。劇作の衝動に突き動かされていたのだ。本は文字を吸いこんでいく。
『ちびのジョンは、宿のすぐ近くまで舞いもどっていた。いやな予感に足を急かされてのことだった。二人のこども、新たに契りを結んだ幼い義兄弟たちの、命が危ないと感じ取ってのことだった。ジョンは狭い裏通りを駆けに駆けた。自分でも驚くような全速力で、人の波も屋台も踊り越し、今や炎に燃え落ちんとする宿に迫った』
「本を寄越せ!」
耳元で響く怒声に洋一は顔を上げた。目前にあったのは、モーティアナの手ではない。彼女の手先は、蛇の頭となり、その頭が彼に訴えている。本を寄越せ! 蛇の声はジュージューと鼓膜を焦がすかのようだ。洋一は本を胸にかいこんだ。蛇の牙から涎が落ち、涎と思ったものは実は毒で、床に弾けると塩酸のように木材を溶かした。硫黄にも似た奇妙な臭いが彼の鼻に届いてくる。
「太助……」と彼は呻いた。「助けてくれ」
だが、本当に助けが必要だったのは友人の方だ。太助の体はモーティアナの野太い腕に飲まれて見えなくなっていたからだ。蛇が洋一を一飲みせんと大口を開けた。洋一は頭を垂れ、きつく目を閉じた。蛇の生暖かい胴体に飲まれるのを覚悟してのことだった。そして、目を開けたとき、目の前に、大蛇の姿はなかった。かわりに太助が――異国の風変わりな侍の少年が、モーティアナに捕まっているのが見えた。彼女の手はもとにもどっていたが、顔は蛇の大頭と化している。その頭が、太助を飲みこもうとしていた。
「離せ!」
太助は牙から逃れようともがいている。老婆の痩せてしなびた指は、驚くほど力強く、太助を宙に吊り上げる。太助の左手にはまだ刀があったが、肩を押さえられてはとても扱えない。
蛇の大口が近づく、牙が伸びて、毒液が垂れ、舌まで伸びてきた。
シャーシャシャー
太助はいまや蛇に飲まれる寸前だった。洋一は太助の名を必死に呼んだ。懐かしいジョンの大声が階下より轟いたのはそのときだった。
「洋一! 太助! どこだ!」
モーティアナの野太い首が廊下に向かって走った。体はそのままだというのに、老婆の首はどんどん伸びた。音を立てて鱗が剥げ落ち、太助の顔を打った。モーティアナの雄叫びが少年たちに聞こえた。
「きええええーーーーーーー、ジョオオオオオンンンーーーーーーーンッ」
○ 5
洋一は本を放り投げると、円陣を飛び出し夢中で太助の落とした刀を拾った。モーティアナの頭が消えてる、あいつの胴はがら空きだ。彼は慣れない手つきで刀を構える。床がぐらぐらと揺れている。モーティアナの打撃は十分に宿の基礎を壊していた。部屋は炎に包まれ焼け落ちる寸前だ。魔術のせいで炎が外に出て行かないのだ。煙はまったく出ていないのに酸素が希薄になって、洋一はくらくらした。彼は刀の柄をでたらめに握った。震える喉をおして雄叫びを上げると、モーティアナに向かって突進した。刀が太助に当たるかもしれない、そんなことは毛ほども頭に浮かばなかった。彼は夢中で燃える床を走った。その後から床は下へ崩れていった。洋一はモーティアナに体当たりをし、猛烈な刺突をくれた。洋一の刀は老婆の醜い体に根元まで食いこんだ。鱗をかき分けるジャラジャラとした嫌な感触があった。モーティアナの体が震え、太助の体が床に落ちた。
太助は足が地面をつかむよりも早く、脇差しを横に打ち振るった。洋一の頭上を刀が走り、蛇の大首を捉える。太助は空中で刀を振ったにも関わらず、モーティアナの太首を真っ二つに斬り裂いた。洋一は支えをなくして、刀を抱いたまま転がった。モーティアナの体を押し倒す格好になったが、体の感触がない。モーティアナは服だけの抜け殻になった。溶けたんだ、と彼は思ったが、じっさいにはちがった。太助が急いで服をめくると、そこには首のない蛇の死体がぴくりとも動かず横たわっていたからだ。
太助は気色悪げに呻いた。「これが、モーティアナなのか? これが……」
「太助、本だ! 伝説の書が燃えちゃう!」
と洋一は言った。炎に包まれた部屋の中央で、伝説の書が無造作に転がっている。まるで魔方陣に守られているようにも見える。
太助は脇差を手に、燃える床を飛び越え、魔法陣に降り立った。そこだけは炎がない。太助が本を拾い上げた瞬間、炎に耐えかねた床が抜け落ち、少年は一階へと転げ落ちていった。洋一は太助の名を呼びながら尻餅をついた。
○ 6
洋一は階段を駆け下りる。宿の部屋はすべて扉が開いている。屋内の人たちは一人残らず死んでいた。洋一は悲鳴を上げながら階段を飛び降りた。死体なんて見たくないのに、宿中に血が飛び散っている。もうジョンも太助も死んだのではないかと思った。洋一は足を滑らせすっころんだ。廊下中がモーティアナの体液で濡れているのだ。あいつはジョンまで殺しに行った。洋一はその恐怖に震えている。あいつの体は死んだけど、頭はどうなんだろうか? それに太助はあんな高さから落ちて、死んだんじゃないだろうか?
「太助! ジョン!」
洋一は足を滑らせながら立ち上がる。階段の踊り場で手摺りから身を乗り出し二人の名を呼んだ。瓦礫の下敷きになっているのは太助のようだ。砕けた漆喰で真っ白になっているが生きているようで、洋一の声に呻き目を開くのがわかった。伝説の書をまだつかんでいる。
一階に落ちた床の木材は、まだ炎を放っていて、洋一はおかしいなと思った。それは七色に変わる魔法の炎だったからだ。彼の認識では術者が死ねば魔法の類は消えるはずである。モーティアナは死んでない。階段を駆け下りながら思った。あいつは蛇だった。きっとモーティアナの使い魔だ。洋一は本物のモーティアナがどこかにいるんじゃないかと思って、なんども階段の上を振り仰いだ。瓦礫の山のすぐ側にはマントにくるまれたちびのジョンが倒れている。
洋一は残りの段を飛ぶように降りて、太助の上に乗った瓦礫をどけた。炎が彼の手を焼き、太助は無理をするなと言った。
「黙れ! 本物のモーティアナが来るぞ! 急いで逃げないと!」
と洋一が言ったので、太助も目を見開いた。そのとき、二人は宿の中に男たちが入ってくるのを見た。野次馬たちが、騒ぎがすんだのを見て、確認にきたものらしい。洋一は男たちが少年らの他になにかに見入っているのに気がついた。一階にいた宿の主人だ。他にも惨殺されているものたちがいる。洋一は恐怖に震えて唾を飲んだ。ここにいたら、この火事も人殺しも、みんなぼくらのせいにされる。
ぼくらじゃない、と洋一はつぶやきながら、ともだちを助け起こす。そのときには、ジョンが意識を吹きかえして立ち上がり、二人を助けていた。
「おめえたち」とジョンは大声で言った。「いってえ、なにがあった! こりゃあ、なんの騒ぎだ」
「こっち」
洋一は大人たちの視線を恐れ、まだボンヤリしている太助とジョンの腕をひっぱった。
洋一はジョンの倒れていたすぐ側に蛇の頭が落ちているのを見た。間一髪だった。あの大頭に噛まれていたら、ジョンだってひとたまりもなかったろう。
「モーティアナが出たんだ。すぐにここを出ないと」
ジョンもすぐさま事態を飲みこんだ。そうでなくとも、彼らはお尋ね者なのだ。背後では野次馬たちが、逃げるぞ、武器を持ってこい、と喚いている。ジョンは太助を抱えると、洋一の手を引いて宿の奥へと進んでいった。事務所らしき部屋を通り抜け(そこでも宿の奥さんが死んでいる)、裏木戸から外へ出た。薄暗い路地が塀に沿ってのびていた。洋一の体を冷たい風が包んだ。こどもたちや近所の奥さんたちが、三人の面妖な様子に悲鳴を上げて飛び下がった。
「このままじゃあ、街の門を閉じられちまう。捕まったら縛り首だ。急いで、ここから出よう」
ジョンは洋一を背負い走りだした。太助はどこも骨を折らなかったようだ。すぐにジョンの腕から降りて脇を走った。
◆第三章 シャーウッドの隊長と副隊長、イングランドに再会すること
◇章前 モーティアナ
モーティアナは嘆き悲しんだ。所は王宮。彼女はジョン王に与えられた一室にいて天蓋のついたベッドの中央に水晶球をおいている。その玉にぶつぶつと話しかけている。彼女自身は跪いて、怒りに身を震わせていた。
「お許し下さい尊師。きゃつらめを取り逃がし申した」
ウィンディゴは水晶球の内から鼻を鳴らしたようだった。「さすがは牧村の一族よ。幼年といえど訓練は受けていたと見える。伝説の書を使いこなしおったわ」
モーティアナは舌打ちをしたい気分だった。憎むべきは刃物を持った異相の少年。あろうことか彼女の大切な蛇をおぞましい刀剣術で斬り裂きおった!
が、この失態もウィンディゴはおもしろがっているようである。モーティアナはウィンディゴと少年らの関係を疑った。いったいどういうおつもりか。
「やつらめロビン復活をあきらめておらんと見える。小僧共の考えそうな事よ」
「好きにさせますので」
「そうではない……」
とウィンディゴはここで声を潜めた。モーティアナは彼の言葉を聞き逃すまいと膝立ちのままにじり寄った。彼女は承諾の声を上げ、小刻みに頷く。それは一興、一興! 水晶球のウィンディゴが揺れ残忍な笑みを浮かべた。
「手はすでにうっておる。やつらがその窮地を切り抜けるか見物よ」
「――つきましてはやつらの守護者のことにございます」
モーティアナは奥村とミュンヒハウゼン男爵の行動について語った。二人がシャーウッドの森に出たこと、モーティアナ自らがおもむき、その手で森を焼き払ったこと。
「軍勢を率いて攻め立てましたが、きゃつら森の残党どもに手を貸し、窮地を切り抜けました。今はリチャードの子息のいる居城に立て籠もっております。ノッティンガムの州長官をそそのかして、城を攻めさせる手筈にございますが……」
「しぶといやつらよ。どうあがいた所で、すべては我が手の内にある。伝説の書もあの小僧もわしのものだ!」
はっ、とモーティアナは平服したが、ウィンディゴの声が外に漏れはしないか冷や冷やした。そして、モーティアナは奇妙に思った。ウィンディゴはあの洋一という小僧をすぐに殺す気がないと見える。それどころか小僧共が力をつけるのを喜んでいる節がある。ウィンディゴは水晶球より立ち消えたが、モーティアナはいぶかるように玉を見つづけた。が、そこからは自らの年老いた顔が見返すのみだったのである。
□ その一 死刑囚になったロビン・フッド
○ 1
三人はふたたび馬を奪い、ひたすら南を目指して走った。シニックに向かうためである。洋一と太助は伝説の書に書きこんだ内容について話し合った。伝説の書は文章を吸いこんだ。文字は確かに書く後から消えていった。それに洋一には本が自分の願いを受け入れたという奇妙な手応えをつかんでいる――けれど、それは確信などではないし、事実がどうなったかはわからない。ただそう感じるだけなのだった。一方で、太助は洋一の言葉を全面的に信用しているようだった。洋一は伝説の書の唯一の持ち主だ。本は持ち主を選ぶ。ということは、この本は牧村洋一がつかったときに一番にその能力を発揮するはずである。問題はジョンにシニック港に行くことを納得させることだった。港に到着したはずのロビンを探さねばならないからだ。なにせジョンはパレスチナまで飛んでいく気になっているから、説得は骨のいることだった。
「ジョンにほんとのことを言おう」と太助は言った。「ロビンに会ったことなどないと話すんだ」
「でも」
「どうせ、ロビン本人に会えば、ぼくらが会っていないのはわかることだ。伝説の書のことも話すしかない。信用するかはわからないが」
「会えるかどうかはわからないじゃないか」
太助は洋一を見もせずに言った。「会えることを祈ろう」
洋一はほとほと泣きたくなった。非難が怖くなったのである。
洋一と太助はある晩にちびのジョンと本格的な話をした。ジョンはモーティアナの襲撃に不思議がっていたから、この話にはすぐに乗ってきた。
三人はジョンの起こした火を囲んでいる。あぶっている肉はジョンが得意の弓で射止めた鹿である。前回の街で塩など旅に必要な道具をそろえていたから(軍資金はノッティンガムで奪った馬を売ることで仕入れたようだ)、食事は割りに豪勢だった。
彼らの背後では二頭の馬が木にくくられ、火から顔を背けながら、ときおり鼻音を鳴らしている。洋一は話した。自分たちがウィンディゴという、モーティアナよりもずっと恐ろしい男に狙われていること。その男が狙っているのは彼らの持つ本だということ。モーティアナがウィンディゴの手先になっていることはもはや疑いようがなかったのだ。
彼は伝説の書をジョンに渡した。このごろ、本が誰かの手に渡るとチクリと心が痛むのだった。まるで、伝説の書をつかうたびに、本とかれとのつながりが深まるみたいだ。
ジョンは唖然としているようだった。
「この本が……この本を狙う連中がいるってのか?」
「ただの本じゃない」と太助が口を挟んだ。「信じられない話だが、その本は書いた内容を現実にする力を持っているんだ」
ジョンは驚き、そんな馬鹿なという顔をして本を見おろした。
「こいつをモーティアナが奪いに来たって? こんな、こんな、なにも書いてないじゃないか」
とジョンはページを繰った。
「でも、ぼくらは宿で書いたんだ。ロビンが生きてパレスチナからもどってくるって。彼がシニック港についたことを書いた。十字軍とヨーマンの仲間に守られてると書いたんだ」
ジョンは心なしか首を左右に振っている。少年らのことは信用している。けれど、こんな話を信用できるだろうか? ジョンは魔法とは縁遠い世界の人物なのだ。
「モーティアナにはウィンディゴが力を与えてるんだ」太助は熱心に言った。「あの宿の様を見たろう。ぼくらは――父上とミュンヒハウゼン男爵とずっと旅をしてきたが、あいつには敵わなかったんだ。あいつに対抗できるのはロビンだけだ。だから、ロビンを助けたかったんだよ」
「だけど、お前たちはあいつの使いで――」
「うそなんだ」と太助は言った。ジョンがひゅっと息を飲み、洋一は申し訳なさそうに目を伏せた。
「ぼくら、ロビン・フッドにはまだ会ったことがない。ロビンに会いに来ただけで、生きているロビンの確認はしていないんだ」
ジョンはなにかを言おうとした。罵声を浴びせようとしたのかも知れないが、またも息を飲んで首を振った。
「うそだ。いまさらなにを言いだすんだ。俺はどれも信じねえぞ――」
「うそじゃない」と太助は声を励ました。「ぼくらがイングランドに行ったのは、ロビンを助けるためだった。けれど、ロビンはいなかった」
「だったら」とジョンは遮る。「なんでおめえたちはあんなことを言った。俺をここまで連れてきた? お前たちは」とつばをのむ。「モーティアナやジョン王の味方なのか? いったい……」
「モーティアナはぼくらの敵だ。ぼくらの敵とつながってるから」
と洋一は言った。ジョンにそんなふうに思って欲しくなかった。洋一の心は悲しみで満たされた。ちびのジョンの敵だなんて。
彼はこの小さな大男が前以上に好きになっていた。誠実で臆病で勇敢な人だ。なによりもやさしい人だった。今だって、自分の心配なんて少しもしていない。洋一はこんな人にあったことがない。ちびのジョンが数百年の長きに渡って人々に支持されてきたわけが、今こそ分かった気がしたのだ。
「それがウィンディゴなんだな?」
ジョンの問いに二人はうなずいた。
「俺はどうすりゃあいい。この本がおめえの書いた言葉を現実にしたなんて、そんな突飛もねえ話信じるのは無理だ」
「信じてくれというつもりはない。ただ確かめてくれ。ロビンがシニックの港についたかどうかを」
太助の真剣な言葉にジョンの心は動いたようだった。
洋一もいやに低い声でぼそりと言った。
「本当はぼくらも伝説の書をつかったのは初めてなんだ。この本は危険だって男爵に言われていたから。だから、この本が本当にそんな力を持っているのか、ぼくたちどうしても確かめたい。ぼくの父さんがなにを守ってきたのか知りたいんだ」
いぶかるジョンに、太助が言った。
「洋一は伝説の書を守ってきた一族の最後の生き残りなんだ。彼の両親は、ウィンディゴに殺されてしまった」
ジョンはそのことをまるで悼むように目を閉じた。そして、顔を開けると、
「わかった。おめえたちの言うとおりにしよう。俺はおめえたちだから正直にうちあけてえんだ。そんな本の話は信用できねえ。だけどな。俺はおめえたちのことは、腹の底から信用してる。そのことだけはわかってくれ」
二人はジョンの率直な言葉にいたく感動を覚えた。もともとちびのジョンはこういう人物だったのだ。ジョンは旅が進むにつれて本来の自分をとりもどしているみたいだった。ロビン・フッドに近づくことで。
「すまない、ジョン」と太助は言った。「だけど、騙すつもりだったんじゃない。ぼくらはロビンを救いたかった。君が死んだって、ぼくらでロビンを守るつもりだった。そうだな、洋一」
「ぼくらモーティアナとウィンディゴを倒すのは、ロビン以外にはいないと思うんだ」
太助はきちんとお辞儀をしてすまないと言った。洋一も真似た。二人は大人の侍がそうするようにきちんと謝罪をしたから、ジョンも大いに照れてしまった。同時にその赤本のことが、ほんのちょっぴり怖くなった。二人の本気がよく分かったからである。
「よせ、いまさら聞きたくねえ」口調に反して、その顔は泣き出しそうに優しい。「だってお前らは俺を命がけで助けてくれたもんな。俺にロビンを信じる気持ちを呼び起こさせてくれた。俺はそのことに感謝してる。詫びがなぜ必要なんだ?」と彼は言った。「お前たちに助けが必要ならいつだって力を貸すとも。だって、俺はお前たちを信じたから。一度信じたら、二度と疑わねえのがヨーマンの流儀だ。馬鹿かもしれねえけど、俺はそう育てられたから、お前らのことは絶対に疑わねえ」
ジョンとこどもたちは手をとりあった。もう辺りはとっぷりと闇である。モーティアナがどこからか三人を狙っているのかもしれないが、その瞬間だけは互いの存在を心強く感じた。
「ああ、ロビンはいるとも。俺にはわかるんだ。ロビン・フッドの、ヨーマンの魂は地上にある」
○ 2
シニック港についたとき、陽は暮れかかっていた。巨大なお椀で抉りとったような入り海、湾岸には町並みが広がっている。北側には山がある。格好の漁場のようで、まだ漁船が出ていた。
ちびのジョンは深更になり、人が集まる時間を待って酒場に向かった。洋一と太助は山中でジョンの帰りを待った。ジョンが向かったのは、街でもさびれた小さな酒場である。旅の僧に変装もしてずいぶんと念入りなことだった。
さて、ちびのジョンが街の小さな酒場に潜りこみ仕入れてきた情報は次のようなものだった。このところ、名無しのこじきが絞首刑になることに決まっており、街の人間の噂の的になっていること。街にフランス貴族が到着し、その処刑を観覧する予定であること。
こじき風情が絞首刑でさらされるのも異例のことである。街の人間はこじきが相当な悪事を働いたと噂しているが、そのこじき、誰がどう見てもふぬけの阿呆なのだ。それをフランスからきた貴族がわざわざと見物するのも妙な話だった。無法者でなければよもやこじきを絞首刑にするはずもない。あのこじき、振りをしているだけなのではないか、という者もあった。
時は夜更け、三人はいつものように焚き火を囲んで話し合っている。そのこじき、ロビンなのかな、と太助が訊いた。
「まさか、ロビンはおめおめつかまりゃしねぇ。それに十字軍じゃ大将だったんだぞ。名無しのはずがねえ」
ジョンは元の姿にもどっている。変装の達人の名にたがわぬ早業振りだ。
洋一も太助もそんな話は信じなかった。物語は変転を遂げている。フランスが物語に関わったのは、ウィンディゴが何事か仕掛けているからにちがいない。街にはその貴族の連れてきた銃士と呼ばれる連中が威張っているとジョンが言ったから、もう決定のようなものだった。
「銃士? 銃士が街にいるの? 鉄砲を持ってるやつらのこと?」
洋一が聞くと、ジョンは鉄砲のことは知らない。この時代には存在しない代物なのだから当然だ。だが、銃士と呼ばれる連中は、新式の武器を持っていて、それをみなおっかながっているそうだ。
「それが、鉄砲なんだ」と洋一。「弓矢よりずっと強力な武器だよ」
「俺も見かけたが、そうは見えなかったぞ」とジョンは首をひねった。「あんなものが本当に使えるのか? 細っこい棒じゃねえか。玉っころが出るらしいが、そんなに威力があるとは思えねえな」
「侍もそう言っていてやられたんだ」
と太助が洋一に囁いた。どうも戊辰戦争の聞き語りを言っているらしいが、これは洋一にすらピンと来なかった。それよりも、銃士だ。物語の狂いは加速している。そんなやつらが登場したとあっては、決定的にまずかった。
その夜、ジョンが寝静まってから、洋一と太助は三度話し合いの場を持った。当初、この世界には銃士なんていなかった。もちろん有名な三銃士の物語はあるが、ロビンの物語とはまったくの無関係だ。時代がちがうし、書き手もちがう。銃が出てくるの自体ずっと後の話である。
「ウィンディゴだよ。あいつがまた物語をねじ曲げたんだ」
と洋一は言った。そうやって、邪魔をしてくるからには、その縛り首になるというこじきはロビンと見てまちがいない。
「だけど、なぜふぬけの阿呆なんだ? なんで縛り首になるんだ」と太助はも首をひねる。「これも伝説の書のつじつまあわせなのかな?」
「ウィンディゴのちょっかいのせいに決まってるよ」と洋一は否定した。伝説の書を信じる心が強くなっていた。「それで物語がいっそうおかしくなったんだ」
「ともかく、処刑は数日後だというぞ。もう日がない」
「でも、ぼくらロビンの仲間も一緒に帰ってくると書いたろ?」
太助はうなずいた。
「それなら、アラン・ア・デイルや、赤服ウィルだって、この街にいてもおかしくないよ」
「そいつらを探すのか?」
と太助は腕を組んだ。その腕を下ろすと、
「明日、ぼくらだけで街に出てみないか。昼間の街に。変装してもジョンは有名すぎるから置いていこう。服をかっぱらって、変装すればばれやしないさ。ぼくらは元の物語を知ってるから、ジョンよりもちがいがよくわかる。洋一、聞いてるか?」
洋一は、はっと焚き火から目を上げた。「聞いてるよ」
「そうかな。最近、ぼうっとしてるぞ」
「そんなことあるもんか」
と洋一は腹を立てた。太助は鼻から吐息をついて、
「しかし、その銃士というのはやっかいだな。そのフランス人はモルドレッドというんだろ?」
「うん」
「デュマの物語には出てこないな。銃士と関係のある人物で、モルドレッドか……」
「ウィンディゴのでっち上げかもしれない。きっとあいつの創作した人物だ」
ともあれ、ウィンディゴの手先、あるいは息の掛かった者と見てまちがいなさそうだった。
「とにかく、時間がない。夜だけじゃなく、昼間も動くべきだ。ジョンだって、休息は必要なんだし」
洋一は太助の言葉がどんどん小さくなるのを感じた。そうして森の奥から、ふふふ、とこどもたちの笑う声を聞いた。洋一は森の奥をかえりみた。太助がどうしたんだ、と訊いた。なんでもないよ、と洋一は答えた。焚き火に目を戻し考えこむ振りをした。太助は不審がったが、それ以上なにも訊かなかったのでほっとした。けれど、自分の中の異変が少しずつ、それも悪い方に変わっていくのに気づいてもいたのだった。
洋一と太助はこの国に紛れられるような格好をして街に出た。帽子を深くかぶり注意深く見てまわった。なるほど、黒服で軽装の連中がサーベルを下げて歩き回っている。銃こそ持っていないが、街の連中の恐れる様子からみて、黒服の男たちこそ銃士のようだ。洋一と太助は街にこじきが多いのにも気がついた。そして、そのこじきたちは、古傷や生傷を抱えている。きっと激しい戦闘をくぐり抜けてきたのだ。十字軍の残党らしかった。
「やっぱりこの街には十字軍が流れ着いてる。伝説の書は君の願いを叶えたんだ」
「でも、ぼくらじゃロビンの仲間の顔までわからないよ。どうやって、あいつらを味方につけるんだ?」
と洋一が言ったから、太助は妙な顔をした。
「だって、ぼくらだけじゃ、捕まったロビンを助けられないよ。アランや十字軍の力を借りないと」
太助は感心したようにうなずいた。
「名案だが、ロビンが捕まったぐらいだぞ。アランたちだって昼間うろつきはしないだろう」と言った。「今日は最も大きな酒場にもぐりこもう。ジョンについていくんだ。うまく行けば、銃士たちの武器が見られるかもしれない」
○ 3
二人は宣言どおり、いやがるジョンにむりやりついていった。ジョンはこどもなど連れて酒場にいれば、怪しまれるし、目立つと自由に行動できないといってしぶった。が、太助はどうしても銃士の持つ武器を確かめておきたかったのである。彼の世界にも旧式の銃は多くあった。それも先込めならまだましだ。だが、後込めの連発銃なら勝負にならない。ロビンたちの武器は弓と剣槍がせいぜいである。そうなってはおしまいだ。
一階の酒場は二階まで吹き抜けとなっていて、天井が高い。たばこの煙でくすんでみえた。ランプの淡い光の下で、男たちがざわめきあっている。船乗りの姿が多かった。宵の口だというのに、もう酔っぱらっている。客をひく女もたくさんいるようだ。ジョンがテーブルにつくと、洋一と太助は彼を挟むように座った。
「見ろよ、銃士がいる」
太助はコップに口をつける振りをしながら、帽子のツバの隙間から銃士たちの様子を観察した。いいぞ、と彼は思った。うまい具合に先込め式だった。たぶん、三銃士の持っていたのとおなじマスケット銃だろう。火縄式らしく、かなり初期の代物だ。それでも二十秒に一発は撃てるはずである。刀のとどく距離にちかづかないと危ない、不意をついて斬りたおしてしまうか、と太助は油断なく目をはしらせた。
その黒ずくめの男たちは壁にもたれてしゃべらず酒も飲まずにいる。そのうち太助は銃士のことをこっそり見る必要はないことに気がついた。店のものはみな興味深げにあるいは恐ろしげにこの寡黙な連中のことを見やっていたからだ。
太助はすぐにこの連中がある男を無遠慮に見つめていることに気がついた。その相手はちいさなテーブルで、一人でビールを飲んでいる。フードを目深にかぶり、太助は顔を確かめられなかった。どうも、飲む振りをしているだけのようだ。ひんぱんに傾けているのに、のど仏が動いていない。というよりも、銃士たちの重圧に押されているようだった。
「ジョン、あいつら、あのテーブルの男を狙ってる」
「なに?」
ジョンは驚いて、ぐっと顔を伏せると、脇の下の隙間から太助の指さす方を見るようにした。
「フードの男か?」
「あいつら、あからさまだよ。きっと店から追いだして、撃ち殺す気なんだ」
「あの人が仲間なの?」と洋一が訊いた。
「ここからじゃなんともいえねえ」
だが、ジョンの胸は興奮に震えていた。そのとき、男が立ち上がるのが目の端に見えた。フードの端にのぞく端正な横顔……。
「アランだ。あれはアラン・ア・デイルにちがいねえ」とジョンは目を仰天で丸くしながらけれど気づかれないよう首をすくめながらささやく。「痩せとるが、まちがいねえ。あのやろう、生きとったぞ」
「銃士たちが動いたぞ」
「あいつら、アランをつかまえるつもりだ」と洋一。
「くそ、アランは十字軍で立派に戦ったんだぞ。それがなんでお尋ね者にならなきゃならねえ」
ジョンはすぐさま後を追おうとしたが、太助が止めた。
「まだすわってるんだ。後からついていって挟み撃ちにしよう」
ジョンはほかにも仲間はいないかと素早く酒場をみまわした。
そうしている間にも、アランは戸口を出て行った。三人の銃士は酒場の男たちを押しのけながら後につづく。船乗りたちが歓声を上げた。みなこの捕り物に気づいているのだ。
太助はマントの下に隠した刀をとりだすと、柄にビールをさっとかけた。
ジョンが立ち上がった。「行くぞ。アランを救うんだ」
洋一がその腰に抱きついた。「ジョンは銃のことがよくわかってないよ。あれはほんとに威力があるんだ。胴体にくらったりしたらまちがいなく死んでしまう。鉄の玉がめりこむんだよ。わかる?」
ジョンは動揺した。鉄の玉が腹を引き裂くのを想像したのだ。むろんそんなものを治す医療はこのイングランドのどこにもない。
「火薬をつかう武器だ。古い銃だから、どの程度きくかわからないが――」
太助もだまった。ジョンが聞いていないことに気がついたからだ。ちびのジョンは目を閉じ、ややうつむいた。彼は長い付き合いとなった泣き虫ジョンと激しく罵り合っていた。彼の心は泣き虫ジョンに押し戻されそうになった。だけど、パレスチナへと旅立ちようやくもどってきた仲間だ。ここまでどんなにか苦労してきたろう。そのことを思うと、自分がノッティンガムでのうのうと生きてきたことも相まって、ジョンは涙しそうになったのだ。だめだ、こんなこっちゃいけねえ。ようやく会えたアラン見捨てるのか? そんなの駄目だと彼は思った。死んでいたと思っていた仲間が生きていたことだけでも彼にはありがたい。泣き虫ジョンは彼の中からどんどん退いていった。感謝の念が、恐怖を駆逐していったのだ。
ジョンは青ざめているけれど、血色もさしてきた中途半端な顔を上げ、ズカズカとカウンターに近づいた。途中男たちに幾度もぶつかってその度にビールが零れたがまるで頓着しなかった。なかで調理をしている男の腕をつかみ、
「そいつをよこせ!」
と炒め物が乗ったフライパンを奪いとった。
「ジョン!」
と洋一は言った。ジョンはフライパンの中身を振るい落としている。待ってろよ、アラン。今俺が助けてやるぞ! 宿中の男たちの注目が集まる中、ジョンは左手にフライパン、右手に剣を手にして、体に巣くう臆病者を打ち払うべくこう吠えた。
「さあ、行くぞ! アラン・ア・デイルを救うんだ!」
ちびのジョンは二人の少年を従えると、悪魔を吹き飛ばすような大股で店の外へと駆け出て行った。
○ 4
太助が早口にまくしたてる。「あいつらの銃は装填に時間がかかる。一発目を躱すんだ。そのすきに近づいて斬りたおしてしまおう」
この時代の銃は、弾丸と火薬を先端から流しこみ、さらに棒でつついて押しこまなければならないはずである。ひどく面倒な代物だ。
むろんジョンは銃の構造などてんで知らない。ともかく、初弾をかわすことだけを心にとめた。
ジョンが剣を背中に隠す。月光を跳ね返さないようにするためだ。太助が刀の鯉口を切った。洋一が遅れているのを気にしている。
「洋一、無理をするな!」
アランの姿はもう見えないが、銃士たちの翻すマントは見える。裏地の赤は夜目にも鮮やかだ。
ジョンの視界から銃士たちは姿を消した。アランが路地に逃げこんで、彼らもそれを追って左に折れたのだ。ジョンは大股を飛ばしてアランの後を追った。
「いたぞ、アランだ」
視線の先には深い闇に包まれたか細い路地が伸びていた。L字型の角ではアランが追い詰められている。
ジョンが立ち止まると、こどもたちもようやっと追いついた。ジョンは仁王立ちしている。こどもたちは、ジョンが昔の臆病風に吹かれたのかと思ったが、そうではなかった。ジョンはようやく出会えた古くからの仲間が殺され掛かるに及んで、とうとう激高したのだった。
「おめえたち! アランから離れろ!」
ジョンが大音声で呼ばわるのと、銃士たちがふりむくのは同時だった。三つの火縄の明かりがぽつりと見えた。ジョンは立ち止まった。太助風にいえば居着いてしまった。あれが、銃か? どんな武器だ?
「ジョン!」
ジョンが迷ううちに、洋一が夢中で腰に組み付いてきた。太助がしゃがみながら足がらみをくわせたから、さすがのジョンも尻からすとんと地面に落ちた。マスケット銃の轟発が路地に轟き、ジョンの鼓膜を激しく揺らした。弾丸が頭上に突き刺さり、彼の頭髪を浮き立たせる。ジョンのうなじに悪寒が走った。ブロック塀がガラガラと落ちてくる。
ジョンと洋一は粉塗れになっていたが、太助が
「三発鳴ったぞ、走れ!」
と我先に走りだした。ジョンはすまねえとばかり、洋一の体をおしのけると、脇に落ちていた剣をひっつかみ、太助を追って駆けだした。「アラン! 待ってろ!」
銃士たちは新手の三人に気をとられすぎていたのだ。アランが細身の剣を抜き放ち、一人を背後から串刺しにするのが見えた。今は浮浪に身をやつしてはいるが、元はシャーウッドからロビンに従う勇姿である。隣にいた男が銃を捨て、アランにまっこう斬りつけた。危ういところでアランが受けた。
残りの一人が紙の早合を噛み破り、火薬と玉を銃口から流しこんでいる。太助は装填の時間を与えまいと、飛ぶようにして距離をつめた。男はさく杖と呼ばれる棒を引き抜いて、薬室に弾丸を突きこんだ。彼は銃を立て火皿に火薬を入れたが、もう銃を構えて狙いをつける時間がない。太助が手元に躍りこんできたからだ。男は銃を投げ捨て、サーベルを抜き合わせようとしたのだが、太助はそれよりも早く間合いを踏み越え、男の胴を真っ二つに薙ぎ払った。彼は体をくの字に折り、バッタリと座りこんでしまった。
「でかしたぞ!」
ジョンは太助の脇をすり抜けると、剣戟の音高く打ち合うアランの元へ駆け寄った。死体を飛び越えて突きを繰りだす。二人の打ちだす火花が轟々と顔にかかった。ところが、銃士はこの攻撃を読んで左へ身を躱した。まるで後ろに目玉があるようだ。ジョンの視界から男が消え、アランの驚愕の顔が迫る。危うくアランを突き刺すところだ。ジョンは刃先を下げるのが精一杯。肩からアランに打ち当たると、二人はもつれ合って転んでしまった。ジョンは、背中がヒヤリと硬直するのを感じた。背中がガラ空きだったからだ。
ところが、その銃士も仲間がやられたのをみて動揺していた。ジョンがふりむくと、太助が男に斬りかかるのが見えた。太助は敵の側面へと体を沈ませる。男には少年が視界から消えたように見えた。視界の左端でなにかが走ったと思ったときには、その首には鋭い刃筋が食いこんでいた。ズルリ―― 刃滑りと共に肉が裂け、噴血が舞い上がった。銃士はゴボゴボと喉音を立てながら、ジョンの脇を数歩後ずさる。壁にどっと背中を打ち当てると、血の筋を引きながら滑り落ちていった。ジョンも初めて目にする早業だった。
「居着いた貴様の負けだ」
と太助がいうのが聞きながら、アランが自分の下でまだ剣を振ってもがいているのに気がついた。巨体のジョンがのしかかるものだから、起き上がりようがないのだ。
アランは貴族と見まごう色男だが、その顔も無精髭におおわれ、さんざんに薄汚れている。
「貴様ら、何者だ。なぜ俺を助ける」
ジョンも暴れるアランをもてあました。
「よせ、アラン。俺だ。リトル・ジョンだ」とフードを脱ぎ捨てる。「長い軍隊生活で俺を忘れたか」
しばらくの間、アランは口をきかなかった。闇のなかで、大男の顔を見上げ、
「まさか、ジョン、君か?」
「ああ、俺だとも」とジョンは言った。「アラン、おめえはなんでこんなところにいる。ロビンはどうした?」
太助とジョンはその答えに気をとられていた。だからそのとき、異変に気づいたのは路地の先でまだ倒れている牧村洋一だった。洋一は自分の見ている物が信じられずに目を瞬いた。
「なんだ、あれ?」
洋一は体に乗ったブロックを押しのけながら、暗闇の先を空かし見た。倒れた銃士の上でなにかがヒラヒラと踊っている。洋一は目をしぶりまた開いたが見まちがいではなかった。なにかが死体にまとわりついている。
おかしいおかしいぞ。
洋一は伝説の書に文を書きこんで以来、妙に五感が冴え渡るのを感じていた。頭に浮かんだのは、ウィンディゴの憎たらしい笑顔だった。銃士があいつの創造物だというんなら、どどうして普通の人間だと考えたんだろう?
「気をつけろ……」
と洋一はささやく、粉を吸って咳きこんだ。腰にのった煉瓦をのけて立ち上がると、友人に向けて叫んでいた。
「気をつけろ! そいつらまだ生きてる! 人間じゃないぞ!」
○ 5
路上には真新しい血臭が、力強く立ちこめていた。太助はややボンヤリとした顔つきで、先ほど斬りたおした男を眺めていたのだが、友人の声にいち早く顔を上げた。
彼は洋一を見て、それからもっとも最初に死んだ男に視線を移した。アランが突き殺した男だった。男の体をなにかが覆っている。男にまとわりついているのは男自身が流した血液だった。血液が戻るたびに、男の筋肉がぼこりぼこりと沸騰するかのごとくふくれ上がった。そのとき、男が血塗られた指を伸ばして、彼の足首をつかんだ。彼は足首ではなく心臓を直接掴まれたような気になった。男の手はすでに冷たくなっていたからだ。太助は悲鳴を上げると刀を打ち振るい、その手首を切り落とした。夢中で飛び下がると、死体につまずいた。その死体にも血が結集しはじめている。
「気をつけろ、そいつら生きてる!」また洋一の声がしたが、太助にはひどく現実感がない。「死んでるけど動いてるぞ!」
なにを言ってるんだ?
太助は徹頭徹尾、現実的な人間だ。そうした面でも洋一とはずいぶん違っていた。銃士たちが死ななかったのだと思ったのだ。斬りごたえは十分だったが。体重の乗せ方が甘かったのかもしれない。
背後で風切り音と肉を断つ音がした。アランが死体の首を斬り落としたのだ。
「首を落とせ、復活するぞ小僧!」
太助は考えるよりも早く動き、自分のつまずいた死体の首を切り落とした。太助は最後の一人を斬ろうとした。彼が動きを止めたのは、自分の切り落とした手首がすごい勢いで持ち主の元にもどっていったからだ。男は流れ出た血液の大半をとりもどしている。太助は飛ぶようにして身を寄せると、刀を振りかぶった。転がったままでは落としにくいため襟首を掴もうとした。男は突然四肢を立てると、太助が捕まえるよりも早く宙に飛び上がった。斬りかかる暇もない。男は五メートルばかりも跳躍して、壁に張りついたからだ。太助は瞠目する。なんだ、あの跳躍力は?
「まずいぞ、死兵に変わった! 二人とも気をつけろ!」
アランが言った。その銃士は闇の中を飛び回っている。驚いたことに、建物の合間を飛び交っているのだ。その間も、銃士の体はどんどん膨れ上がっていく。と同時に路地に黒い気体が噴出し(地面からガスのように湧き出てくる)、男に向かって集まっていくのが見えた。
「大きくなってるんじゃねえのか……」
とジョンが震える声で言った。上からなにかが落ちてくる。ジョンと太助は頭をかばって腰を屈めた。化け物が建物の間を飛び交う内に、煉瓦がどんどん突き崩れているのだ。
「くそ、気体がじゃまでよく見えない! ジョン……!」
黒雲をはねのけるようにして、毛むくじゃらの妖怪が牙を剥いて降ってきた。太助はとっさに身を投げだし、男は地面に拳を突き立てる。路面は衝撃でクレーター型にへこみ、石畳は粉々になり周囲に散った。太助はそのクレーターの脇を二転三転して起き上がる。
喧噪はひどくなる一方だ。アパートの住人たちが騒動に耐えかねて騒いでいるのだ。明かりこそつかないが(そんな設備がないのだろう)逃げ出しているのがここからでも分かる。早く決着を付けないと、と太助は焦った。ぼくらまで捕まったらおしまいだ!
ジョンとアランが二手に分かれて斬りかかる。
太助は男の腕はきっとつぶれたにちがいない、あんな勢いで石に当たったら骨がグシャグシャになったはずだと思った。
男が腕を引き抜いたとき、その拳はどす黒い血に覆われていたが、同時に泡が立ってもいた。男はジョンの剣を二の腕で受ける。獣の咆哮を上げたかと思うと、ジョンを殴った。腕が壊れていてはできない打撃だ。巨体のジョンが文字通りきりきり舞いをして、壁に頭をぶつけている。その間もアランは攻撃しているのに、男は痛がる様子も見せない。アランの斬撃はたしかに化け物を傷つけている。けれど、も泡が噴き出し、どんどん回復しているのだ。
太助は、こうなっても首を刈れば死ぬのかといぶかったが、そもそも刀の届く位置に首はない。元は一七〇そこそこの体格だったのに、今では二メートルを超えている。そもそもあんな太い首を切り落とすには、自分より下まで押し下げてやるしかないだろう。こうなったら、足を切り飛ばしてでも、首の位置を下げるしかなかった。
太助は上段から真っ向唐竹割りに斬りつけた。尻の下部から腿裏をスパリと斬ったが、瞬く間に治ってしまう。「くそ、両断するしかないぞ!」
アランが体当たりを喰って昏倒した。太助は袈裟斬りに足を狙ったが後一歩の所で躱される。男がこちらに向かって体をひねりつつ拳を飛ばしてきた。正拳突きともいえない出鱈目な攻撃だったが、太助は刀を引き戻すのがやっとだった。迫る拳に峰を絡ませるが、刀ごと押し戻されて彼は吹き飛んだ。太助は腰を丸めて丁寧に転がったが、それでも突きの威力で頭が揺れた。太助は起き上がろうとしたが、筋肉がうまく働かない。アランとジョンは気絶したのか動く気配もない。太助は脳震盪を起こしながらもどうにか刀を握った。
こいつはかなわない! みんな殺されるぞ!
「洋一、よせ!」
と太助は言った。火縄のついたマスケット銃を拾い上げるのが、化け物の股越しに見えたからだった。
○ 6
鼓膜がどうにかなったらしい。平衡感覚が狂っている。真っ直ぐ歩けない。ぶれて三つに見える火縄を目指してそれでも歩いた。あの銃士は装填の途中で放りだした。あのとき弾丸と火薬はこめたはずだ。彼は太助から火縄銃の装填手順を一通り聞いていた。
「使える、あれは使えるはずだ」
足首の力が抜けて変な方に曲がった。ジョンがやられると洋一は小走りになった。マスケット銃は近くで見ると思っていたより大きかった。洋一は膝をついて、ズッシリと重みのある銃を拾い上げた。路地の先ではアランが化け物を相手に狂ったようにサーベルを振り回している。
「くそ! 下がれ!」
とアランがいうのが聞こえた。彼のサーベルは怪物の重い胴に跳ね返されて根本から曲がっている。
「火皿、火皿だ!」
洋一は銃身の横にある皿のような装置に目をこらした。いじってみると、水平に動く部品がある。どうやらこれが火蓋らしい。ちゃんと開いているが、火皿に着火薬(口薬)が詰まっているのかはよく見えない。暗すぎるのだ。引き金を引けば、火縄のついたバネが下りて、火皿に火点を押しつける仕組みのはずだ。口薬がなければ火縄を押しこんでも玉は出ないはずである。
そうする内にアランがやられて転倒するのが見えた。太助は今やたった一人で化け物と相対している。
「太助!」
洋一はもうやるしかないと覚悟を決めた。祈るような気持ちで、マスケット銃を持ち上げる。すごく重くて気を抜くと銃口が下がってしまうほどだ。それにどの程度命中力があるのか分かったものではない。太助に当たるのが恐ろしくて、洋一は思い切り近づくことにした。ジョンはあんな弾っころでは死なないと言った。ジョンは死ぬだろうが、あの化け物につかうにはまったく心許なかった。気づくな、こっちに気づくなよ、と祈るような気持ちで歩を進めた。太助が拳を喰らって(と彼には見えた)ついに昏倒している。自分に向かってなにかいうのが聞こえたが、洋一には銃口についた目当てと火点しか見えない。洋一は銃を突きだせば男の後頭部をつつけるほどの位置まで近づいた。彼にはその銃士が狼男の現実版にしか見えない。それにしてもひどい悪臭だ。腐りきった死体の臭いがする。
彼は短く息を吸いこむと、目をつぶって引き金を引いた。火縄が下りると火薬が爆発して、巨大な炎が銃の側面に噴き上がった。炎は火穴を通って銃内の火薬を炸裂させる。弾丸が勢いよく飛び出して、怪物のこめかみを突き刺した。
洋一は反動で火縄銃を抱えて転がる。後頭部を打って、朦朧となる。とどめだ、とどめをささないと。洋一は銃を持ち上げようとした。が、もう玉がない。そして、怪物となったその兵隊は脳に弾を喰らっても死なないらしかった。ゆったりと首を巡らし、彼を睨み、唸り声を上げたのだった。
太助が刀を杖に立ち上がった。銃士はすでに洋一に向かって足を踏み出している。
「こいつ待て!」
太助は夢中で斬りつけたが、膝が揺れている。それでもむちゃくちゃに刀を振り回して怪物の体という体、ところかまわず刃筋を走らせた。脳に食いこんだ玉のせいか動きが鈍くなっている。ゆっくりとこちらを向く太助と目があう。まるでこうるさい蚊を見るようだ。太助は無我夢中で体を回し、男を斬りつづけた。息のつづくかぎりに。真っ黒な血が周囲に散って男の傷口からはどす黒い気体が立ち上りだした。
「だめだ!」と彼はとうとう動きを止めて怒鳴りつけた。「こいつ死なないぞ!」
銃士の眉間から大剣の切っ先が突き出てきたのはそのときだった。昏倒から立ち直ったちびのジョンが背後から男の後頭部を串刺しにしたのだ。男の背丈はジョンよりも高い。だから斜め下の延髄から眉間までを貫く形となった。男の頭蓋がグボリと砕け、左の目玉が飛びだした。銃士は犬のような唸り声を発した。
「下がれ、こいつ!」
とジョンは柄を力任せに押し下げて、男の腰を折ろうとする。さすがに脳を貫通されて銃士の動きは目に見えて鈍くなった。が、体中の黒気がもっとも重い傷口に集まり細胞の復活を始めている。
「ジョン、動かすな!」
と太助は刀を振るったが、かれも疲労と恐れで目測を誤った。首の半ばまでは断ち割ったものの、ジョンの剣に打ち当たって両断できない。
太助が刀を引き抜いたとき、アランが口の端からダラダラと血を流して立ち上がった。そのままフラフラと近づくと、銃士の膝裏を力任せに蹴り飛ばした。さしもの怪物も膝を折った。ジョンが大剣を捻り回すと、まるで首を差しだすような格好になる。太助は脇差しをすっぱ抜くと気合いの罵声を放った。脇差しを水平に薙ぐ。首は真っ二つに斬り裂かれた。
化け物の首がようやく胴を離れると、ジョンはその重みでつんのめる。剣が下がって、首級は大剣から滑り落ちた。まるで水の詰まった風船が弾けるようにして中の液体をまき散らした。どす黒い血の海には砕けた骨が散らばったのだった。そして、胴体は気体が抜け出ると共にしぼんでいった。あっという間に腐敗が進んでいったのだった。
「洋一、そんなもの捨てろ」
と太助は友人に駆け寄ってマスケット銃を取り上げた。洋一は放心したように亡骸を見ている。
ジョンがアランを助け起こしていった。
「すぐにここを離れよう。警備隊が来ちまうぞ」
□ その二 ロビン・フッドと伝説の
王○ 1
ジョンはアランを抱えて路地を先へと進んでいった。体に感じるアランは昔日の面影がない。
「おめえこんなにやせ細って……」
とジョンは涙ぐんだ。なるほどアランの体重は全盛期の半分ほどしかない。
「一体、なんであんな連中に襲われてる。あいつら一体何者なんだ」
「あの連中はモルドレッドの部下だ……ロビンを追ってここまで来たんだ」
「モルドレッドって、フランス貴族の?」と洋一は訊いた。「ロビンはあいつと戦ったの?」
アランは首を振って否定する。「元は十字軍の仲間だった。だが、銃士たちを見たろう。やつらは昼間は並の兵隊だが、夜間では無敵なんだ。死んでも蘇って敵味方の区別なく襲うそうだ」
「そんなやつらがなぜ十字軍に?」
「俺たちもそんな話は信じなかったからさ。負けたサラディンの言い訳ぐらいにしか思わなかった。だが、噂は本当だった。やつら本物の化け物だ」
アランは苦しそうに腹を押さえた。
「おめえは一人なのか? 噂じゃあこじきが縛り首になるって話だが」
ジョンたちはアランの顔を盗み見た。アランはひどく苦しそうな顔つきをした。
「いやみんな生きてる」とアランがいったから、ジョンはほっとした。それから洋一の顔を盗み見た。あの本の力なんだろうか? そこまではわからなかった。「ガムウェルもスタートリーも一緒だ。俺たちはパレスチナからロビンを守って逃げてきた。だけど、ロビンはもう元のロビンじゃないんだ。ロビンは自分から守備隊に出頭しちまった。このままじゃ明後日に縛り首になる。この街の長官はロビンにかねてから恨みを持っていたんだ」
じゃあ、あのこじきというのはやっぱりロビンか?
「だが、なぜロビンが? イングランドにもどってこれたってえのに、なんで自分から捕まるような真似をしたんだ」
「仕方あるまい。ロビンはモルドレッドに魂を抜かれたんだ」
ジョンが手を離したので、アランは壁にもたれかかった。太助と洋一も呆然としたが、ジョンの自失した様は胸が悪くなるほどにひどかった。洋一はジョンの腕を引いて励ました。ジョンはアランの胸ぐらを掴み上げた。
「いってえなにがあったというんだ! 魂を抜かれただと? そんなことが……」
「本当なんだ!」とアランもジョンを突っぱねた。「ロビンはな、パレスチナで、魂を抜かれちまったんだ! あいつの魂はパレスチナに残ったままだ! ロビンは抜け殻になっちまった。ウィルと俺たちはここまでロビンを守ってきたが、もう駄目だったんだ。ロビンは生きる気力すらなくしてる。俺たちのことだって、忘れちまってるんだ」
「なんてこった……!」とジョンは頭をかかえた。自らに起こった忘却も、そのことが遠因だったような気がした。「先に十字軍から戻った連中は、ロビンが死んだといっていたんだぞ!」
アランの体から、力が抜けていった。満足に食べていないのに、激しく動いたせいだ。血の気がすっかり抜けている。ジョンはアランの体を逆に支えることになった。
「ロビンが魂を抜かれた現場をみてそう思ったんだろう。誰でもそう思うさ。現に十字軍は、あの戦いでサラディンにさんざん追い散らされたんだ。イギリス軍は散り散りになってしまった。獅子心王もその戦いで死んだ。ロビンさえ健在なら、あんなことにはならなかったのに」
「そんなこと、そんなことが……」
ジョンはよろめいた。
「事実だ。俺とウィル・スタートリーは、あのときロビンのすぐ近くにいたんだ。ロビンの胸の辺りから、輝く玉のようなものが出てくるのがみえた。そのとたん、ロビンはバッタリと倒れて動かなくなってしまったんだ。ロビンの体は冷たく、意識が目覚めることはなかった。時間がたつと、ロビンは少しずつ手足が動かせるようになった。もっと日がたつと、言葉をとりもどしはじめた。だけど、以前の記憶もなければ、性根も変わってしまったんだよ」
ともあれ、ロビンは、魂を抜かれてこのかた、飯も一人で食えない痴呆者に成り果ててしまった。わずかな物音にも怯え、すべてに絶望しているようだった。アランたちは海峡を渡り、シニック港にたどりついた。だが、イングランドはすっかりジョン王の勢力下となっていた。シャーウッドを戻るすべを探しているうちに、ロビンが姿を消した。すべてに絶望したロビン・フッドは、自らの命を絶つため、ボルドーの守備兵に、我が身を投げだしたのである。この港町にも国王の息の掛かった者がいて、処刑の邪魔が入る前に、ロビンを殺そうとしている。
ともあれ、アランはモルドレッド・デスチェインという男を呪い上げた。
「リチャード獅子心王の討ち死にも、やつの裏切りのせいだ。俺たちが助かる道はロビンにしかないのに、あの状態では、救い出してもジョン王と戦うことは不可能だ。ロビン自身が死をのぞんでいるんだぞ」
むろんアランたちはロビンを救出するつもりでいた。だからこそ危険な街に出て情報集めに努めていたのである。
一同は言葉をなくして、むっつりと歩きつづけた。たとえ、救い出しても、ロビンはもう以前のかれではない。よしんば助け出せたとしても、今のロビンに行くべきところはどこにもないのである。
アランは、海岸の近くで、巨大な排水溝へと降りた。下には歩道があり、水の流れる溝は、船が通れるほど広かった。海が近いせいか、潮風が冷え冷えと吹き、服の隙間に入りこむ。歩道には、アランたちの仕掛けた罠がところどころにほどこしてあった。人が通ると音が鳴る仕掛けである。アランは、鉄のパイプを叩くと、巧妙に隠された蓋を外した。遠くでパイプを叩いたらしい音が、かすかに響いた。アランはパイプに向かって呼びかけた。
「ガムウェル、アランだ。俺たちの副長がやってきたぞ。五人ばかり連れて行く。攻撃しないようにいってくれ」
アランは晴れ晴れとした顔を上げた。「さあ、行こう。粗末なアジトだが、雨風はしのげる」
○ 2
ロビン一味のアジトは、排水溝の出口付近にあった。目をそばめると、格子の外はすぐに海のようだ。洋一は波の音を聞いた。もう何十時間も経った気がするのに、その実夜は明けていないのだった。歩道には土嚢が高く積み上げられ、簡便な要塞のように見えた。土嚢の前に立っていた男が、後ろにいる仲間に告げるのが聞こえた。
「ジョン・リトルだ、本当にちびのジョンがやってきたぞ!」
ジョンはアジトから顔をだした男たちを見て、喜色に満ちた声を上げた。
「あれは赤服ウィルだ。顔をだしたのは、粉屋のマッチだぞ。ああ、見ろ。みんながあそこにいる。いったいいつ以来だ!」
ジョンの脳裏に、シャーウッドでの栄光の日々が音を立ててやってきた。あの連中が自分の元を去ってもう三年が経っていた。その間なにもしてやれなかった自分がもどかしく、ジョンは我知らず駆けだしていた。
背の低いマッチは、傷だらけの顔にぽろぽろと涙をこぼし、ジョンの腰にしがみつく。か細くなった我が身の置き所が三界のどこにもなく、それだけで心細かったのだろう。元は粉屋で、平穏無事に暮らしていた男である。ロビンのためなら命もいらぬと十字軍に参加したのに、肝心のロビン・フッドがあんなざまになってしまった。
自分に負けないぐらいの大食らいで、太りじしのマッチが、人並みの体に細っている。それだけでジョンは涙した。
「おめえたち」
ジョンの目はアーサー・ア・ブランドにうつった。瞳の上で、燃え立つような巻き毛がほつれあう。潮風の湿気で爆撃を食らったような頭だが、その下のひどい童顔は昔のままだ。
「ひでえ面だアーサー。ガムウェル、おしゃれのおめえがなんてざまだ」
赤服ウィルの肩を叩く。ウィル・ガムウェルは、ロビンの甥だ。不器用だが、その怪力無双で、幾度となく一味の危機を救ってきた。赤毛のアーサーとおなじく不屈の魂をもった男で、この二人の赤は不思議とうまがあう。
ともあれ洋一は心底ほっとした。伝説の書はちゃんと自分の願いを叶えてくれたのだ。ウィンディゴの横やりもあって、結果はひどい様だが、それでもロビンが死んでいるよりましだった。
物珍しげにアジトを覗くと焚き火があった。壁には弓矢が立てかけられ、いつでも迎撃の姿勢がとれる体勢になっている。海側の歩道は、火明かりを隠すために板塀が張り巡らされていた。排水溝には逃走のためのボートがあった。そして、焚き火の側には、一目でイングランドの騎士とわかる男が寝そべり、二人の男の看病を受けていた。
「ウィル・スタートリー、おめえも無事だったか」
ジョンは土嚢の上に涙をこぼす。どの顔も頬こけ、目が落ちくぼんでいた。ここまでの道程の困難さを物語っている。陽気のウィルが、ふてくされたようにそっぽをむいた。ジョンが来てくれて、うれしいやら我が身を嘆くやらで、心中忙しかったのだ。
「ジョン、なにしにきた」とひねくれ者のウィルは、泣き声で訊いた。「お前まで死にに来たのか」
「ああ、ちびのジョン」傷を得ている男はリチャード卿だった。ゆっくりと首を傾け、火明かり揺れ、涙に濡れたジョンの顔を見上げた。その傷はパレスチナを出たころより、軽くなっていたが、十分に立ち上がることはできないようだった。「君はやってきたのだな。ロビンの最後を見届けに……」
「サー・リチャード、あなたが生きていたことを心から神に感謝する。だが、俺はロビンを救うためにきたのだ。あいつをシャーウッドに連れ戻すために」
「ロビンを連れ戻すだと」スタートリーが荒声を上げる。「守備隊がロビンを捕まえてるんだぞ! ロビンの魂はパレスチナに残ったままだ! 救ってどうなる。あいつは死にたがってるんだ! 俺はな、俺は、腑抜けになったロビンをずっとみてきたんだ。あんなロビンをみるぐらいなら、十字軍の戦いで死んでおけばよかった」
ジョンは面くらった。「どうしたんだあいつは?」とアランに囁いた。アランは肩をすくめた。
「ロビンが居なくなって、いじけちまってるのさ」
「そんな風にいうな、ウィル」とウィルの隣にいた騎士が言った。「せっかくの仲間との再会ではないか。もう嘆くのよせ」
「彼は、ギルバートだ」とアランがジョンに説明した。十字軍では大将だった男で、ボルドーでも敗残兵のまとめ役を買って出ている。端正な顔も今では髭に覆われている。獅子心王の側近として、弱年のころより、戦場を渡り歩いてきた。
思うに、ウィルはふだんから陽気な男なだけに、こうした鬱屈とした事態に耐えられないのだろう。
そのとき、アジトの隅に座りこんでいた男が、のそりと身を起こした。一目で異国人とわかる、異相の男である。頭にはターバンをまき、人相を隠している。ちびのジョンが、「ムーア人か?」と訊いた。
「心配するな。あいつも、ずっとロビンに従ってきた男だ」
アランが言った。洋一が土嚢に身を乗りだし、
「アジームだ」
と叫んだ。アジームと呼ばれた男は、顔にかけた布を落とした。真っ黒な肌と、それよりも黒い髭とちぢれた髪が、火明かりに照らされる。映画でみたアジームの顔そのものだ。来ている鎧まで洋一の記憶と一致している。
「なんで俺の名を知ってる」
「そ、それは」
洋一はまごまごと言った。まさか、映画で見たことがあるとはいえない。
また新しい登場人物だった。ロビンの世界は物語の筋が狂っているだけじゃない。新しい人物がどんどん出てくる。まるで本が新たに創作しているようだった。洋一は考えこんだ。これは本当にウィンディゴ一人の力なんだろうか? 男爵はウィンディゴが本の世界の登場人物だと言った。つまりあいつはミュンヒハウゼンとおなじ人種に当たるのだ。なんの本だろう? と洋一は自問する。ウィンディゴという名前には心当たりがない。彼は男爵に会いたかった。会ってこのことを話し合わなきゃ。男爵は本の力が弱まって創造の力を無くしたのに、なんであいつだけが特別なのか。
洋一は太助がなにか知っているかと彼の方を見たが、太助は刀に腕をかけて油断なくロビン一味を見回している。この中にウィンディゴの仲間がいるのではないかと疑っているのだ。
太助が洋一に代わって言った。「あなた方のことは、父上から聞いている。ぼくたちは、モーティアナを倒すために、イングランドに向かったのだ」
「モーティアナだと? 誰のことだ?」
アーサーが訊いた。そこでジョンはアーサーらに、イングランドの近況をはじめた。五人のイギリス人にとっては、久々にきく故郷の情報だった。
「モーティアナは本物の魔女なんだ」とジョンは言った。「ジョン王の側近で、裏から操ってるのかもしれねえ」
ジョンはモーティアナに襲われたときのことを語って聞かせた。普通なら信じられないような話ばかりだが、ロビンが魂を奪われるのを目撃した後だし、それもアランは死兵に出くわした後だから、妙に信憑性があった。
洋一がジョンを見上げる。「ロビンが魂をとられたのだって、ウィンディゴの仕業なのかもしれない」
「そうかもしれねえな」
そこで洋一がウィンディゴの話を慎重に語りだした。もちろん本の世界についてはうまく省いてだった。太助はウィンディゴの話を聞いて妙な反応をする者がいないかじっくりと見ていたが、怪しい顔つきをしたやつはいなかった。
銃士が町にいると聞いて、剛強のロビンの部下たちも震え上がった。ウィルが怒りに燃えて言った。
「あの野郎、ロビンに止めを刺すためにここまで追ってきやがった!」
「ロビンが死なない限り、あいつの魂はモルドレッドが握っていると考えるべきだ」とアジームが言った。「モルドレッドが側にいない以上、俺はロビンの魂をとりもどす見こみはない物と考えていた。だが、モルドレッドはこの街にいる……」
赤服のガムウェルが、サー・リチャードの耳元に口を寄せる。「まだなんとかなるかもしれません。ロビンの魂さえ取り戻せれば……」
「だが、ロクスリー(ロビン・フッドのこと)は二日後には縛り首なのだぞ。魂をとりもどしてもロクスリーが死んではどうにもならん」
「それに、モルドレッドの軍隊とどう戦うんだ」マッチが言った。「この港には俺たちの仲間は残っていないぞ」
ギルバートが、「いや、ここには十字軍の生き残りが大勢流れこんでいる」
どれも十字軍の敗北で行き場をなくした連中ばかりだった。
「そいつらを集めるのか」とアラン。
「まさか十字軍の」リチャード卿は言葉をなくした。「彼らは敗軍の兵ではないか。もはや軍隊ではない。弱体化した十字軍で、どう戦うというのだ」
「だが、ロビンの部下だったやつらも大勢いる」とウィルが言った。
「しかし、彼らは」リチャード卿が声を荒げた。「彼らを頼って、最後の賭に出るというのか。それは進められない。巻き添えを増やすだけだ」
「彼らは、行き場をなくして浮浪者になっているだけです。元は歴とした騎士たちだ。戦い方を知っている」とギルバートが言った。「このままでは、その連中とて、銃士とジョン王に追い散らされることになる。生き残るためには結束するしかありますまい」
「モルドレッドの恐ろしさは連中が身に染みてわかっているさ」ガムウェルが言った。「地中海では、異教徒を赤子にいたるまで殺しまわっていたやつだからな。浮浪者となっているとはいえ、十字軍の残党を見逃すとは思えない」
洋一は一同の話を注意深く聞いている。太助も熱心に話し手の顔を見た。二人はウィンディゴがどこまでこの状況に干渉しているのか分からなかった。けれど、ここにいる二人の少年だけは、対抗勢力であることにまちがいはない。つまるところ洋一たちがロビンの世界に乗りこむことで、ウィンディゴの意図通りには事が運ばなくなってきている。その証拠に泣き虫だったちびのジョンも今ではすっかり立ち直り元の本分を果たそうとしている。
ジョンは急に黙りこんで仲間たちの会話をむっつりと聞いている。実のところ彼はすっかり腹を立てていた。戦力がどうだとか、誰が味方かなどとそんな話は聞きたくもない。ジョンの脳裏には、天地に向かって立ち上がるロビンの姿がいつもある。ジョンはあいつのそんな姿が見たかった。自分が死んだって見たかった。あいつを救ってやりたかった。他の誰もやらないなら、自分が成り代わってあいつに恩を返すべきだと思った。俺こそがあいつを救わなきゃならねえ。あいつの義侠に答えてやらなきゃならねえ。俺とロビンだけは正しいヨーマンであらなきゃならねえ
「ロビンはいつだって人を救ってきた。自分がどんなに劣勢でも泣き言も愚痴も言わない。あいつは訊くために、人の願いを叶えるために、いつだっていてくれたじゃないか」ジョンは立ち上がり、仲間たちに訴えた。「このままじゃ、ロビンは名無しの無法者として縛り首だ。そんな屈辱をロビンにあたえられん。あいつを救おう!」
「弱体化したとはいえ、十字軍は戦争のプロだ」アジームは我が意を得たりとうなずいた。「そいつらがこの街に集まっている。偶然とは思えん」
「シニックは景気にわいてるが、俺たちゃしみったれだぜアジーム」
行儀の悪いウィルが、また寝転がる。
「ならば、ロビン・フッドを助けることだな」
と、アジームが言い、ウィルは鼻を鳴らした。
「だが、ロビンの魂をどうとりもどすというのだ」リチャード卿が訊いた。勇敢な男だが、長い闘病生活でいくぶん弱気になっている。「我々は死刑台のロクスリーをも救わねばならん。街にいる十字軍はいかほどなのだ」
「四百ばかりでしょう。武具をもっていない連中もいます」
「その後はどうする。どうやってシニックを出る?」
脱出の案はすぐにまとまった。というよりも安全で確実な方法はひとつしかなかった。私掠船である。フランスからイングランドに戻るのにアランたちは彼らを頼ったのだ。普段は海賊行為をしているが、歴としたイングランド海軍だった。
問題はやはりロビンの魂だった。ちびのジョンが洋一に目顔で合図してきた。ジョンは洋一と一緒に伝説の書のことを話しはじめた。仲間たちの反応は太助の想像したとおりだった。彼らは伝説の書のことを頭から信じなかったのだ。
「じゃあなにか、俺たちが生きてここにいるってのもその本のおかげだってのか!」とウィル・スタートリーは怒って言った。「そんな馬鹿な話はねえ。おめえが本に書きこんだのはついこの間の話だろう。俺たちが何ヶ月苦労して旅をつづけてきたと思う!」
アランは意見を求められたが首をひねり、
「戦いは勇敢だったが、その本というのはどうかな」
「おめえたち」とジョンは言った。「俺を信用しろって。この子たちに会えなけりゃ、俺だってここにはいなかった」
「その子たちを疑っているのではない。その本のことを聞いているのだ」
とギルバートも態度を硬くした。洋一もしつこく食い下がった。
「それを言うなら、ロビンが魂を抜かれたって話もどうなのさ。それこそ嘘みたいな話じゃないか――」
その話の間中、太助は違和感を拭いきれなかった。最初のうちは、肉体の疲労と痛みで洋一の変化に気づかなかったのだ。妖怪と化した銃士との戦いは、彼の幼い体にはあまりに負担が大きかった。節々が痛み、体がバラバラになってしまいそうだ。本当は迫り来る敵のことは忘れてゆっくりと体を休めたかった。けれど、今は気を抜くわけにはいかない。
太助は洋一を注意深く見守った。洋一が一味を相手に熱弁を振るいだすと、太助の違和感はいよいよ深くなった。洋一とはこんな人物だったか? こんなに能弁だったろうか。洋一はロビンの部下たちの反駁にひとつひとつ懇切丁寧といっていい調子で、反論し説諭している。洋一は、伝説の書の力を力説し、自分はうまくつかえたと言いはった。そのことも妙だ。以前は本をつかうことにあんなにためらい不安がっていたのに。一回の成功で自信をつけたというには彼の変化は極端すぎた。むしろ、伝説の書を礼賛しているともとれる態度だ。
ロビン・フッドの魂をうばった不可思議な魔術に対抗するには、伝説の書をつかうしかない、とは彼も思う。だけど、その危険性は洋一とてよく熟知しているはずだ。とにかく伝説の書には不確定要素がありすぎる。なるほど、ロビンはイングランドに戻りはしたがあのざまだ。
男爵がいれば洋一を止めてくれるのに、と太助は思った。
伝説の書を使いこなすのは難しい。そのことはわかる。だからこそ、洋一を戸惑わせるようなことを言うべきではないかも知れない。彼が彼らしくない、まるで別人のようだなどとは言うべきではないかもしれない。
太助が思い惑ううちにも、一味の意見は伝説の書とやらに頼ってみてはどうかという意見にまとまってきた。それはそうだろう。ロビン側にはそのような不可思議な魔術に対抗する術がまるきりないのである。
洋一は伝説の書に力を発揮させるためには、事実を詳しく書きこむ必要がある、と言った。だから、現場でモルドレッドの様子をみたいのだと。モルドレッドの人となりを少しでも描写しようという案には太助も賛成だった。
話がこちら側にまとまりだすと、洋一はニヤニヤと人の悪い笑みをもらした。そのたびに太助はこの少年が恐ろしくなった。洋一、というよりも、この少年に棲み着いたなにかが。太助は大人たちの誰もこのことに気がつかないのだろうかと疑った。そのときアジームと目があった。彼は彼で太助の迷うさまを見抜いていたと見える。アジームは太助から目を反らして、
「俺とスタートリーで洋一についていこう」
「ロビンを救うつもりが、ガキのお守りとはね」
とウィルは土嚢にもたれかかったが、ことの重要性には気づいている。太助は冷や冷やした。アジームという男、洋一が失敗したら、あいつの首をはねるつもりじゃないのか。
最後にジョンが、それでいいか、という同意を太助に求めてきた。太助はすぐに返事をしたかったが、できなかった。そのとき、洋一がじっと自分を見つめていることに気づいたから、自分がどちらの意見を口にしようとしたのかはついにわからず仕舞いになった。
○ 3
ジョンたちの行動は早かった。
ギルバートを中心にした陽動隊は十字軍に作戦の決行をつたえに言った。十字軍は、勇敢に戦ったにもかかわらず、思うような結果を得られず野盗とかすものも多くいた。シニックに流れついた十字軍は、リチャード獅子心王と行動をともにしたイングランド正規軍が多かったにもかかわらず、恩賞もなく正規軍からも放置されていた。彼らは肉体的にも精神的にも疲弊しきっている。戦うほかに生きるすべを持たない騎士たちにとって、局面を打開するには武装蜂起の他はなかったのだ。
もっとも、弱体化したとはいえ、十字軍には歴戦の軍人がそろっている。銃士に対して、武器の面では見劣りするが(銃を撃てるものも少なかった)地の利を得、組織だって戦えば、ぶざまな戦いをするはずがないと思われた。
そして、大人たちが戦いの準備に時間を費やす間、奥村太助は牧村洋一につきまとっていた。洋一の様子はやはりおかしかった。これから大変な戦いが起こる、その戦いの主役はおそらく彼になる、少なくとも正否を握るのは洋一だというのに、まったく集中していない。それどころか行動がおかしかった。なにかを熱心に見ているのにその先にはなにもなかったりした。夜も寝ていないみたいだ。誰もいないのに一人で話していたりする。独り言かと思ったが、ちゃんと受け答えをしているようだ。太助は彼に声をかけたり、体に触れることでその状態から呼び戻したが、洋一自身は自分のしていることに気づいていないのだった。
伝説の書だ。やっぱりあの本だ。あの本に文を書きこんでから洋一はおかしくなっている。太助は安易に伝説の書を使わせたことを後悔した。洋一のために、はっきりとウィンディゴとモーティアナを憎んだ。けれど、太助が看破したとおりの変化を洋一自身は気づいていないのだ。
この話を下手に切りだして、洋一が文を書くのに失敗したら? その結果がどうなるのか、彼は知らない。けれど、伝説の書をつかってきた人は、何千何万といるし、その人たちの顛末が概して不幸なのだった。
太助がついに話を切りだしたのは、洋一が伝説の書を開いて熱心にページに見入るようになってからだった。そこにはむろんなにも書いていない。
「洋一、しばらくその本を手元から放してはどうだ?」
と彼は言った。洋一は勢いよく顔を上げた。彼を見た目は明確な敵意を宿していたので、太助は驚いた。
「なにを言うんだよ! ぼくはこの本をつかって、ロビンを救わなきゃいけないんだぞ!」
「わかってるよ。ただ、最近様子がおかしいから……」
「おかしい!? おかしくもなるよ! 死体に狙われて魔女に狙われて、こんな重役を任されて、普通でいる方がおかしいじゃないか! おかしなことを言ってるのはお前の方だ!」
「そんな言い方はないだろう! ぼくは君のことを心配していってるんだ!」
「大きなお世話だ」
洋一は本を持って立ち上がった。
「なんだと?」
「大きなお世話だと言ったんだ! なんだっていうんだ! 創作のことなんか君にはまるでわからないだろう! ぼくは集中して、どんな文を書くか練っていたところなんだ! これからこの本をつかうのに、手元から放せって!?」
洋一は太助を押しのけた。
「じゃあ、君は刀を放せって言われたらそうするのか? ぼくに言ってるのはそういうことだぞ!」
「刀には魔法がかかってない、そいつはただの本じゃないだろ! 危険だから言ってるんだ!」
「いまさらなんだよ!」洋一は本気で腹を立てた。癇癪を起こして側の机をひっぱたいた。「この本に文を書きこめと言ったのはお前だぞ! そんないい加減なことがよく言えるな! もういいよ! ぼくは一人でやる! お前はロビンを助ける方に加われよ! お前がそばにいちゃ集中なんてできな……!」
「おい、二人ともいい加減にしねえか!」
ジョンが見かねて口をだした。二人の声を聞きつけてやってきたのだ。太助と洋一はばつが悪そうにそっぽを向き合った。ジョンは大いに弱って二人をかき口説いた。
「その本の効果を疑ってるやつらは大勢おるんだぞ。そんなこどもみてえな喧嘩をしてちゃ信用されねえぞ」
「ぼくらはこどもだ」と洋一。
ジョンはとりなすように言った。「ともかく話は俺が聞くから。こんなこたあ言いたくねえがな。でも、みんないつ死ぬかはわからねえんだぞ。それは俺やお前たちだっておんなじだ。なのに、喧嘩をしたまま別れるのか?」
この言葉はさすがにこたえた。太助があやまると、洋一もごめんと言った。けれど、すぐに部屋を出て行ってしまった。
ジョンは胸をはって威嚇するように太助をみおろした。
「さあ、太助、どうしたっていうんだ。洋一はともかく、おめえがあんな大声だすなんてよ。おめえの方が年も上だろう?」
「そうじゃない。洋一の様子がおかしいんだ。さっきだって……」
「太助」とジョンは遮った。「そりゃあ、仕方のねえこった。あんだけの戦いがつづいた後だぞ。俺だってあの銃士の様子は夢にまで見る。おめえだってそうだろう?」
確かにそうだった。
「あの子はおめえとちがって剣も使えねえしな。そりゃ、素手で大人につっかかっていくようなもんさ。それでもよくやってきたじゃねえか」
「そんなことは言われなくてもわかっている」
と太助は怒って言った。がその声はちいさく、ジョンは太助が納得したと勘ちがいしたようだ。
そうだ、彼はよくわかっている。実際に洋一はよくやった。それどころか、あの一発の弾丸がなければ二人ともいまごろ命はなかったろう。
「洋一が伝説の書をつかうのに反対なのか?」
「そうじゃない。洋一の力がどうしても必要なことは分かってる。だからこそだよ」
太助はこのもやもやをうまく言葉にまとめられない自分を呪った。
「ジョン、あれは書きこむ内容が大事なんだよ。伝説の書は彼の文を受け入れたけど、もし今度がそうでなかったら? なにが起こるかぼくらは知らないんだ。洋一が本の持ち主だって事はわかってるし、ぼくはそう信じてる。あいつはきっと本をつかいこなすって」
「だったらいいじゃねえか。あいつを信じて任してやれよ」ジョンはかがみこんだ。「一番近くにいる人間が信じてやらなくてどうする」
「わかってるよ。だから、ぼく、黙ってようと思ってた。でも、万全の状態じゃなきゃ、うまく使えるはずがないよ。洋一は様子がおかしいじゃないか。伝説の書は持ち主を拒否することだってあるんだ」
ジョンはうーむと考えこんだ。
「だけどよう、もうどうしようもねえんじゃねえのか? あの本を使えるのはあの子だけだって、おめえ言ったろ?」
「そうだ。それが問題なんだ」
「ともかく、もう洋一を動揺させるようなことは言っちゃだめだ。あの子をベストな状態で送りだしてやるつもりなら、喧嘩はやめるべきだと思うぞ」
ジョンは言葉通りに肉料理を無理算段で仕入れてはこどもたちを喜ばせようとした。けれど、こどもたちの関係は改善しなかった。太助はもちろん洋一の心を引き戻そう、なんとか彼を説得しようとしたけれど、彼は訊く耳をもたなかった。取りつく島すらなかったのだ。
処刑当日。
ちびのジョンと十字軍は、ロビン救出のために、変装をして港街に散乱した。この連中は、作戦がはじまれば、処刑場に集まるてはずである。
○ 4
ジョンの言ったとおりになってしまった。太助と洋一は本当に喧嘩別れをしてしまったのだ。もちろん太助は洋一の後についていきたかった。でもあいつはお前が来たら成功するもんもしなくなるといって彼を断固拒絶したのだ。そのせいで、彼は広場の人混みの中にいる。洋一はいまごろ、この会場(と言っていいだろう。この国の人々は処刑をお祭りのように考えている節がある)のどこか高い場所にいるはずだ。太助は心配で仕方なかった。やっぱりあの洋一はふつうじゃない。本だ。あの本が洋一の心を喰らっているとしか思えない。というよりも、洋一に文を書きこませたがっているんじゃないだろうか?
太助はこう考えた。恭一おじさんがあの本を封印したのは、ウィンディゴから守るためではなく、洋一を本から守るためだったんじゃないだろうかと。だけど、もう遅い。彼には洋一がどの建物にいるのかわからない。
こうとなっては、友人の無事を祈るばかりだ。
ロビン・フッドの処刑は街の中心部にある時計台の下で行われることになった。巨大な首つり台が引き据えられた。普段は市の開かれる大きな広場だが、今は兵士と市民に埋め尽くされている。まるで、街中の住民が集まって、すし詰めになっているかのようだ。けれど、三分の一は、変装した味方のはずだ。
首吊り台の後ろには、大がかりな物見台が設けられている。まるで国王の玉座のように絹の衣で着飾っている。太助は吐き気がした。壇上には、街の長官が座っている。隣の若い女は長官の娘だろう。あんなところで処刑を見おろす女の気が知れなかった。物見台には護衛の兵士が詰めかけているが、銃士たちの姿も幾人か見えた。裏の階段をつかって壇上にモルドレッドが登場すると、広場の盛り上がりは最高潮に達した。
○ 5
ジョンは人波に押されている。少年を見失わないよう帯をそっとつかまえていた。ジョンは大柄だが、今では並の人間と変わらぬ背丈まで縮んでいる。乞食になりすましているのだ。おかげで目をとめる者はいなかった。
一方、太助は足首まであるローブをかぶり、そこに刀を隠している。二人ともロビンの到着を今か今かと待ちわびていた。
洋一が側にいないのが不思議な心地だ。斬り合いの助けにはならないが、心のどこかであの少年の存在をずいぶんと頼もしく感じていたのだった。太助は最後に洋一と喧嘩をしたときのことを思い出し、哀しみに胸を締め付けられた。こども同士の喧嘩を彼は生まれて初めてやった。でも、こどもの喧嘩は、仲直りをして初めて終了となるんじゃないだろうか? 太助はしっかりしろと心細くなる胸を叩き、ローブの下の刀を握った。ロビンが死んだらどうにもならないぞ。洋一とこの世界を抜けだすんだろ
やがて群衆の後方で騒ぎが起こった。ロビンを乗せた馬車が広場に到着したのだ。粗末な荷台に乗り、首には縄が掛けられ、まったく囚人以外の何者でもない。若者たちがこぞってこじきをはやし立てるのを兵士たちが追っ払っている。ロビンは誰かに殴られたのか、顔には痣がいくつもあった。
ちびのジョンは、かつての首領の無惨な姿に呻き声を上げた。心中では自分の心臓をかきむしっていた。彼を傷つけたのは、第一にロビンの目つきだった。ジョンは涙でにじむ目玉を瞬いた。垢じみた皮膚、ろくでなしのように伸びた髪、汚れた髭もジョンは許したろう。だがあの目つきだけは我慢できなかった。眼光鋭く周囲を圧したロビンの威光はどこにもない。生きているのに死んでいるかのようだった。ロビン、おめえはどうしちまったんだ――あそこにロビンの魂がないのなら、確かにあのロビンは生ける屍なのだろう。ジョンは、こう呻いた。
なぜなんだロビン。
まるで、群衆も兵士も消えて、広場には自分とロビンだけになったかのようだった。ジョンは周囲に気づかれるのも構わず背を伸ばした。まわりの男たちがぎょっとなった。ジョンはその男たちを突き飛ばしてロビンの元に向かいはじめた。太助が夢中で後を追った。
「なぜなんだロビン! なぜこんなことになった! なぜお前が死ななきゃならねえ、答えろ、ロビン!」
壇上の長官らがすでに騒ぎ出している。太助は無念さにはがみした。この騒ぎに兵士たちはいち早く乗りだしてくるだろう。作戦はきっと失敗してしまう。
広場の外れでは、ギルバートが仲間たちに攻撃の準備を命じていた。十字軍の騎士たちはロビンを救おうと結集し、中央へと向かいはじめた。
ジョンからそう離れていない場所では、粉屋のマッチがジョンを哀れむかのように顔を伏せている。マッチも作戦の崩壊を予感していた。けれど、仕方のない、仕方のないことだ。あのようなロビンと顔をあわすのは、ちびのジョンは始めてなのだから。
こうとなっては、ジョンと死のうと、マッチは懐に忍ばせた短剣に手を伸ばすのだった。
○ 6
太助はジョンに追いつき、その手をとった。ロビンを乗せた馬車はあっという間に広場を横切り、処刑台に到着している。長官がジョンに気づいて急がせたのだ。
太助はジョンの腕をひっぱったが、彼の力では大男は止まらない。
「ジョン、どういうつもりだ! 身を隠さないと駄目じゃないか!」
しかし、ちびのジョンには、太助の姿すら目に入っていないようだ。
「俺の前であいつは二度も死ぬのか。そんなことはあっちゃならねえ。世界があいつを見限っても、俺だけはロビンを信じなくちゃならねえ」と彼は言った。「俺はロビンが大好きだった。俺の目の前に見えるあいつは、今じゃ魂をなくしたかもしれねえ。それでも俺は、あいつのために命を張りてえんだ。もう止めるな」
「ジョン!」
ちびのジョンは太助の手をふりはらい、ロビンの元に向かいはじめた。太助の視野の中で大きな背中が群衆に飲まれていく。
「ジョン、待て!」
太助は慌てた手つきで水筒の蓋を外し、柄に水を振った。柄巻きをギュッと絞ると目釘を湿らせた。こうしておけば竹の目釘が膨張して、柄の強度が増すからだ。
顔を上げると、意を決して処刑台を睨む。そして、この場にいない友人に声をかけるのだった。
「洋一、すまないが、ぼくもこの場で命を捨てるぞ。ジョンを放っておけないんだ」
太助はジョンの後を追い、群衆の合間をすり抜けはじめた。救出作戦は思わぬ形で始まりはじめた。
□ その三 パレスチナのロビン・フッド
○ 1
洋一は時計台の鐘の下にいた。そこからだとすし詰めとなっている群衆がよく見えた。
「どうだ、小僧。モルドレッドは見えるか?」
とスタートリーが訊いた。ロビンの古参の部下は、このスタートリーとアジームだけだった。後は十字軍の騎士たちが五人。この人たちはちゃんと武装している。街にいたときは浮浪者然としていたが、さすがに甲冑を着こむとちがうものだった。五人は敵の侵入を防ぐために、階下へと下りていった。
アジームとスタートリーは、洋一に不審を抱くようになっていた。このところずっと様子がおかしかったし、どうみても情緒不安定である。今も不安げな顔をして、二人の顔を見ようともしない。アジトで一同を説得した洋一の姿はどこにもなかった。やはりこんなこどもに大役を任すのは無理があったのだ。
「小僧、訊いてるのか?」
スタートリーは苛々として洋一の肩を叩いた。自分を見上げた少年の不安げな表情をみて、背後にたつアジームに顔を向けたのだった。その顔にははっきりとした困惑が刻みこまれていた。さっきまであんなに自信に満ちていたのに、どうしたんだこいつ?
洋一は大人たちの不信をはっきりと感じていた。彼は自分の中から、何者かが急速に引き上げたのを感じていたのだ。今まで、本をつかうぞ、文を書きこむんだとそのことばかり考えてきたのに、伝説の書を広げ処刑場を見おろしたときには、創作の衝動はすっかり枯れ果ててしまっていた。彼は自分が一体なにに熱中していたのか、それすらわからなくなったほどだ。太助にはあんなふうに答えておきながら、自分が書きこむべき文章もその内容もまったく考えてこなかったことに気がついた。あんなにうんと考えてきたはずなのに、一人の時間もうんとあった(なにしろ太助とはうんと離れて行動していたのだから)。これまでどう時間を過ごしてきたのかもはっきりしない。
そういえば、太助がなにか話していなかったか?(実際は怒鳴ってこなかったか?)伝説の書に関することを。
洋一は全身の血管が裏返るほどの焦りと気味の悪さを覚えた。首根っこをつかまれるとはこのことだろう。彼はもうどうしようもないと思っている。書く内容がない。なのに、今さら書かないなんてとてもいえない。どころか、アジームは疑惑の目を向けてくる。あの奇妙な刀で彼の首を切断するつもりかもしれなかった。でも、彼は自分が書けないのを知っていた。だってゴーサインが出ていない。だから、洋一はこう思った。こいつは成功しない、失敗だ。
そのとき、けたたましい笑い声を聞いた気がして、洋一は天井に吊られた巨大な鐘を見上げる。伝説の書を拾い上げて、お前がやったのか、ぼくをはめたんだな、と胸裏に問いかけた。
ともかく、もうロビン・フッドは処刑場についたようだ。歓声はいやまして、アジームたちは時計台から身を乗り出している。
「太助は、太助はどこ!」
と洋一は訊いた。スタートリーはめんどくさげにこう応えた。
「あいつならこの下だ。お前がそうしろって言ったろ」
洋一には記憶がない。ともあれ、自分はこの窮地を一人で乗り切らねばならないらしい。
「おい小僧、どうなんだよ。書くならさっさとしねえか! もうギルバートたちが仕掛けちまうぞ」
「わかってるよ! ただ、このまま書いたってうまくいかないんだ。だってぼくはモルドレッドがどんなやつかも知らない」
「言い訳はいい」とアジームは三日月刀をつきつけた。洋一は喉首の下に冷たい刃を押し当てられ息も出来なくなった。「御託を述べる前に書きこめ。出来ないならそう言え。俺は下りてロビンを救う」
「おい、なにをしてるんだよ」スタートリーが割って入った。「小僧を脅してもどうにもなるもんか。おい、小僧、おめえに力がねえのなら、怒らねえから正直にそう言え」
「なにも嘘なもんか!」
洋一は怒って腕を振り回した。二の腕が剣に触れたから、アジームもようやく三日月刀をひっこめた。
「情報だよ! 情報がもっといるんだ! モルドレッドが魂をどう扱ったのか、どこにしまったのか、あんたたちそれすら知らないじゃないか! 下手なことを書いたら、この本はどんなつじつまあわせをするかわからない! 本当はもっとこと細かに書くべきなんだ!」
「どういうことだ?」
と二人の大人は同時に訊いた。洋一は焦りでおかしくなりそうだった。下の喧噪はますますひどくなる。暴動が起こる寸前だ。
「だから、書くんなら、事実に忠実に書かないとぼくらの思い通りにはならないってことだよ! あんたたちにはロビンの魂をどうとりもどして、その後どうするのか、そのプランがなにもないじゃないか!」
「今更なんだ!」とスタートリーも腹を立てた。「そんな必要があるんなら、なんで先に言わねえ!」
「洋一」とアジームは洋一の肩をつかまえた。洋一はやむなく入れ墨の男を見た。「そういうことなら、魂はモルドレッドが持っている。ロビンから抜けだした輝く玉が、あの男の胸に入っていくのを見た」
「輝く玉?」
洋一は光明を見る気がした。彼にはその場面がたやすく想像できた。
「それはどうやったら出てくるの?」
二人は今度こそ顔を見合わせた。
「なにを言ってる。それをさせるのがお前の役目だろう」
「ちがうよ、それを実現させるアイディアが必要なんだ。それをこの本に書きこめば……!」
「このくそ餓鬼、そんなものたった今思いつくもんか!」
スタートリーは釣り鐘を叩いたから、ゴオンという鈍い鐘の音が頭上に響いた。護衛の騎士が何事かと様子を見に来たが、アジームは手を振って追い払った。
「それはどうしても必要なのか?」
「わかんないよ。どうなるかなんて検討もつかない。だって、この本のことぼくはなにも知らないんだ」
スタートリーはナイフを引き抜いて詰め寄った。頭に血が上って、ジョンの忠告すら忘れている。
「だったら、なんで俺たちをここまで連れてきた。ガキの戯言を聞かせるためか!」
「待て、スタートリー」今度止めたのはアジームだった。大人たちもこの千載一遇のチャンスを活かそうと必死なのだ。「洋一、俺たちはロビンを救うために最善を尽くしたいだけなんだ。お前も協力してくれ。俺たちを説得したときはあんなに自信に満ちていたろう」
それはぼくじゃないんだ! 洋一は心中で悲鳴を上げていた。でも、口に出してはとてもいえない。本に嵌められただなんて。自分が本の持ち主というより、本に呪われた被害者かもしれないなんて今更いえない。
洋一は涙目になった。アジームに気づかれないよう時計台の端により、手すりから物見台にいるモルドレッドを見おろした。本物のモルドレッドがそこにいる。その外見を描写することだってできる。問題はその先だ。これが小説の一場面だとしたら、と考える。仲間たちの呼び声にロビンが答えるというのはどうだろうか? モルドレッドの体から魂が抜け出る。処刑場を飛び交うさまを描いたとしたらどうなるだろう。
ふと気がつくと、処刑場の人混みは激しく動くようになっていた。守備兵らが処刑場の中央を目指して突き進んでいる。誰かを捉えようとしているようだが、そうすることでさらに混乱を大きくしているのだ。処刑の観覧にはモルドレッドの私兵も参加していたが、まだ傍観を保ち、整然とした隊列を崩していない。洋一は太助の姿を探そうとしたが、もちろんこんなところから豆粒のような少年を捜すのは無理だった。
今のアイディアに矛盾があるとは思えない。書こう、と洋一は心に決めた。動機としては弱い。だけど、ゴーサインが出たのかどうか、こんなに焦った状態ではわからない。頼むぞ……と彼は万年筆をみつめてつぶやいた。
洋一の決意を感じとり、アジームとスタートリーは息を飲んだのだった。
洋一は石の欄干に本を広げた。高層の風にページが揺れた。
『モルドレッドはまだ三十代の壮年だった。人並みのひげを蓄え、茶色の髪で、どちらかというと平凡な顔立ちに見えた。背丈もウィル・スタートリーと変わらない。やせぎすで、ジョンやアーサー・ア・ブランドのような筋骨はかけらもなかった。けれど、その魔術とカリスマ性は彼を実際より大きく見せていた』
アジームとスタートリーは感心して呻いた。伝説の書はまだその力を欠片も見せていなかったが、見たこともない複雑な文字(漢字のことだ)をこんな少年が操っている。
『モルドレッドはその体内に魂を抱えていた。彼がロビン・フッドから奪い封じこめた人魂だった。モルドレッドは異変を感じた。それは彼の耳がちびのジョンの呼び声を聞き、ロビンの魂が――』
洋一はあることに気づいてペンを止めた。
「文が消えない……」
喉が少し震えた。紙の上には文字が残ったままだった。スタートリーが後ろから肩をつかんだ。
「おい、なんだ、なんでやめる! もう全部書いたのか?」
「ちがうそうじゃない。本が文を吸いこまないんだ! いつもはすぐに消えてくのに……」
そのときページが独りでにバラバラとめくれだした。
「だめだ!」
と洋一は言った。
伝説の書から風が吹き上がっている。重い釣り鐘を揺らすほどで、アジームたちもたじろいだ。そして、紙の上で文字が揺れている。まるで、伝説の書が文を追い出しているみたいに見えた。インクで出来た文章が、本から浮き上がり、左右に身をくねらせる。
洋一は風にも負けずに前に出た。両手で文を押さえにかかった。スタートリーも後ろからのしかかる。三人の手の下で、洋一の書いたへたくそな文字が、紙から離れようと鳥みたいに暴れている。バタバタバタ。洋一は肩が外れるほどの衝撃に耐えかねて悲鳴を上げた。だめだ、こいつぼくを疑ってた、ぼくを見抜いてた! このアイディアじゃ駄目だって知ってるんだ!
洋一は懸命に訴えた。「やめろ、文をすいこんでくれ!」
そのとたん、洋一の体は大きく後方にはじかれた。彼は釣り鐘の真下に落ちて、鉄の巨大な空洞を覗くかっこうになった。そこへ紙を離れた文字たちが群がる。洋一は転がったままメチャクチャに腕を振り回した。二次元の文字が周囲をぐるぐると周りながら、爆撃機のように降ってくる。洋一は体をふって逃げ回ろうとしたが、額や頬にペタペタと貼りついた。
「うわ、うわあ!」
アジームが空を躍る文字に向かって三日月刀を振り回した。スタートリーもナイフで突いた。ところがなんの手応えもない。
洋一の顔はどんどんインクに覆われていった。今では伝説の書からは洋一の書いた以上の文が吐き出されていた。洋一が悲鳴を上げると、その喉にも文は飛びこんだ。頬がみるみるうちに痩けていき、目が眼下に落ちくぼむ。その下には大きなクマができた。血液が抜けていく恐ろしい感覚を味わう。彼は生命力を吸い取られている。手足があっというまに痩せていった。筋肉がなくなり、皮膚が骨に張りつく感触が自分でもわかる。肌はまるで皺だらけで老人だ。体の水分がごっそり減って、喉が渇き血液は濁り息苦しさに喉をかきむしる。アジームとスタートリーではどうにも出来なかった。騎士たちが二人上がってきたが、やはりこの光景に唖然となった。
呪われた文字は洋一の生命力がすり減るごとに数を減らしていった。
バタンと大きな音がした。アジームがふりむくと、伝説の書がページを閉じていたのだった。まるでこの小僧からはもう搾り取るものはないといっているかのようだった。伝説の書は、つまらぬ文章に、それを書いた張本人に、厳しい断罪を下したみたいに傲然としている。洋一は体が空っぽになった感触に苦しみ(なぜか猛烈に腹が減った。背中とお腹がくっつくようだ)、おちくぼんだ頬に手をあてた。指の先でかさついた肌――まるで干物みたいだ。ぼくは干物になっちゃった――アジームが抱き起こすと、彼は本に殺される、と乾いた唇で言う。すると、皮膚が裂けて、下唇から滴が落ちた。
「なんてこった」とスタートリーが言った。「あの本は本物だった。でもって小僧は文を書くのに失敗した! なんてこった!」
だが、彼らの苦しみはそこでは終わらなかったのだ。下から悲鳴が聞こえて何者かが上がってくる、ブーツが石を叩く高い靴音がした。上にいた二人の若者が剣を抜いて階段口に向かったが、下から躍り出た男に一人はたちまち頭蓋を割られ、もう一人は胸を串刺しにされた。男はそのまま騎士を抱くようにして階段の残りを上ってくる。アジームは迎え撃とうと、洋一たちの前に出た。
男の姿が階上に出、陽の光のうちに入ったとき、ロビン一味の剛強、ウィル・スタートリーは、うめき声を上げたのだった。
「モルドレッド……」
○ 2
洋一はアジームの腕の中で震えている。恐ろしいやつならなんどもあった。恐ろしい目にも遭ってきたのだが、存在そのものに圧倒されたのは、これが二度目のことだった。モルドレッドは彼が書いた以上の存在だったのだ。その恐ろしさときたら、ウィンディゴに引けをとらない。人の魂に大きさがあるというのなら、モルドレッドの魂は、その場にいた三人を飲みこむほどに大きかった。
「小僧」とモルドレッドは言った。「貴様なにかをしようとしていたな。このモルドレッドを害する気があったのだ! ちがうか!」
「ぼく――ぼく知らないよ。なにもしてない……」
洋一はいったが、舌が干からびてほとんど言葉にならない。わずかに残った水分も涙となって抜けていった。
モルドレッドは黒剣で伝説の書を指した。「あの本はなんだ。そんなものでなにをするつもりだった」
「ぼく、ぼくちがう。ぼくはなにも――」
「黙れ、小僧!」
アジームは洋一をそっと床に寝かせた。頭蓋骨と皮膚の間の肉が無くなって、石の硬い感触が生々しく骨に伝わるのを感じた。アジームがちょうどいい、とつぶやくのが聞こえた。
「こちらから出向く手間が省けた。ロビンの魂は返してもらうぞ!」
「笑わせるなわっぱども」
とモルドレッドは巨大な黒剣を死んだ騎士から引き抜いた。ウィル・スタートリーが言った。
「なにをしにイングランドに来た! なぜロビンを狙う!」
「狙う? ロビンをだと? それこそ笑止よ! この俺がなぜあんな小物を相手にする! 俺はこの俺のための玉座をとりにきたのだ。数百年の間簒奪された王位をだ」
「なにを言ってる?」
スタートリーはじりじりと移動して、弓をとり矢をつがえた。その間の牽制はアジームが引き受けた。
スタートリーは不敵に笑ったが、その片面は引き攣っている。「貴様は不死身を名乗っているそうだが、おつむは相当に弱いな。リチャード王を殺せば王権が自分に転がりこむとでも考えたか」
「お前はなにもわかっていない。王権はもともとが俺のものだ。リチャードこそが簒奪者だ!」
「ばかをいえ、戯れ言はもうたくさんだ!」
スタートリーは弓弦を離そうとしたが、モルドレッドはそれよりも早くウィルの懐に飛びこんだ。アジームが身動きする暇もない。モルドレッドはスタートリーの利き腕をつかむと、逆巻きにねじって骨をへし折った。
「国王に弓引く気か、それでもイングランドの民草か!」とモルドレッドは言った。「俺こそは大ブリテンの王、アーサー・ペンドラゴンの息子、モルドレッド・デスチェインである! 控えろ!」
「アーサー? アーサー王だって?」
洋一は頭をもたげた。その脳は答えを得て火花を散らした。その名前なら聞いたことがある。彼らは勘ちがいをしていたのだ。モルドレッドがフランスの貴族だときいていたから。ここはイングランドが舞台なのだから、ウィンディゴが登場させた人物とてイングランドの関係者のはずだ。そして、モルドレッドという名前の出てくる物語、それは――
「アーサー王だ……」
と彼はつぶやいた。そのときスタートリーが、モルドレッドに答えて怒声をあげた。
「ばかを言うな。イングランドの王は、貴様が罠にはめ、殺した獅子心王をおいて他にない!」
モルドレッドは哄笑をあげた。
「ジョンもリチャードも真の王不在の折をついた簒奪者にすぎん。イングランドの王たりえるのはこの世に俺をおいてないのだ!」
モルドレッドはスタートリーを突き放した。スタートリーは悲鳴を上げながら、アジーム、アジーム、こいつを殺せ、と言った。アジームはすでに斬りかかっていたが、モルドレッドはまるでいくつも目玉があるみたいに、死角からのこの攻撃をやすやすと外した。黒剣の攻撃は、巌のように重く硬かった。アジームは三日月刀ごと吹き飛ばされ、釣り鐘に頭をぶつけて混濁する。洋一の上に鐘音が超音波のように振ってきた。アジームは洋一のすぐ足下に腰から落ちてきた。
洋一は骨だけになったような体を(力がまるで入らない)どうにか動かしてうつぶせになり、
「ウィンディゴだ、こいつウィンディゴの手下なんだ」
モルドレッドはかっと目を剥いた。彼の目玉は赤く光り、そして、目玉の奥に無数の目があった。
「控えろ、小僧! このモルドレッドがいかな男の下につく! 王は偉大なり、あのアーサーよりも! 我は不死であり、三つの呪いを背負いし王だ! 五百の赤子の魂をまとい、マーリンの血を受けし王! 我より偉大なものがどこにいる!」
洋一とアジームはモルドレッドの怒声を受けて文字通り平伏した。どれも聞いたことのある話ばかりだ。それはそうだろう。彼はこの男の物語を読んだのだから。だけど、二つの物語が混ざり合ったりするものだろうか? ウィンディゴのやつ、そんな真似までできるのか?
アジームは後頭部から血を流し、クラクラと頭を回している。傷口から脳がはみ出ていないのは幸いだ。ただ出血がひどかった。
洋一は気丈にも立ち上がろうと、手を突っ張った。でも、足がいうことを聞かない。洋一は手足を地面についたまま、モルドレッドを見上げた。
「ロビンの魂をかえせ! ウィンディゴの手先め!」
「この俺が誰の手下だというのだ。この俺こそが世界の王だ!」
「あいつはなにを言ってるんだ」
朦朧とするアジームがつぶやいた。洋一が言った。
「だから、アーサー王だよ。あいつはアーサー王の息子なんだ」
「ばかな、アーサーなど、何百年も昔の人物だろう」
とアジームは震える声で言いかえした。彼は血液まじりの唾を垂らしている。とても戦えそうにない。
洋一は動かない体が悔しかった。本に力をとられなかったら、こんなやつ!
「卑怯者! この卑劣漢! 円卓の騎士なら、正々堂々ロビンと勝負しろ! 侍ならそうする。お前なんかに負けない。お前なんか、ぼくの知ってる侍なら……」
「小僧! 俺を円卓の騎士と呼ぶな! 俺は王だ!」
「うそだ! お前は王なんかじゃない! 一度も王になんてなれなかった。お前はアーサー王に勝てなかった! お前は敗北者だ。王なんかじゃ……」
「黙れ!」
洋一が顔を上げたときには、モルドレッドは目の前にいた。アジームは力なく両腕を伸ばしたが、それはどうみてもモルドレッドに救いを求めているようにしか見えなかった。モルドレッドは無慈悲にも少年を蹴転がした。洋一の心が恐怖に燃え立った。その炎で内蔵が焦げたかのようだ。スタートリーが、逃げろ、呪われ小僧、といったときはもう遅かった。モルドレッドは右腕を高く上げ、洋一の額に指をめりこませた。まるで骨などなく、豆腐でできているかのようだった。
「ちくしょう、やめろ!」
ウィル・スタートリーの折れた腕が揺れている。モルドレッドが叫んだ。
「俺を円卓の騎士と呼ぶな! 俺はあの者どもと同列などでは断じてない。俺は王だ! 中世より生きつづける不死の王だ!」
洋一は、ぼくは死んだ! と悲痛な叫びを心に上げたが、不思議なことに痛みはなく、血も脳漿も流れなかった。ただ、脳をまさぐる指の感触を生々しく感じた。モルドレッドの指が電気を発したかのように、頭の奥で、ぱちぱちという音がする。
「貴様に呪いを植えつけてやる! 我が魂の爪痕を、貴様も味わうがいい!」
洋一は、やめろ、と叫んだ。釣り鐘が揺れるほどの大声で叫んだはずだった。けれどその舌は言葉を求めて震えるばかり。口端からは涎が一滴垂れただけだった。まるで死体になって、魂だけが心に残ったかのようだ。痩せこけた体が冷えだす。声もでず息もできない。活動のすべてが隅に追いやられている。血流が脳に集まって、二倍三倍にふくれ上がる。
呪いを植えつけられるその刹那、彼はモルドレッドの心に触れた。いまや洋一とモルドレッドは、呪いを通じてたがいに深く結びつきあっていた。洋一はモルドレッドに起こった数々の出来事を知り、その苦悩の人生に怖気をなした。こんな目にあって正気を保っているこの男はどうかしている。こいつに封じられているのはロビンだけじゃない。五百の赤子もおなじじゃないか! 彼の魂は救助をもとめて叫びまわった。恐慌をきたした狂おしい叫びに、モルドレッドもたじろいだ。それは何者かが洋一の声に応えて、雄叫びを上げたからでもある。
モルドレッドは洋一の頭から指を抜き去り飛び下がった。彼の胸が光を放っている、モルドレッドはその光を両手で押さえようとする。洋一はその眩しさに目を閉じた。モルドレッドの苦悶とともに、金色に輝く魂が、モルドレッドの指を突き抜け宙に躍り出た。
モルドレッドはその光り輝く玉を追った。
「ロクスリー!」
ロビンの魂は宙を旋回して、モルドレッドに襲いかかる。モルドレッドは攻撃を防ごうと黒剣で身を守る。アジームは床に転がった洋一を抱きかかえると、スタートリーの側に避難した。スタートリーは、ロビン、ロビンと懐かしい名を呼んだ。もう何世紀もロビンの姿を見なかったようだというのに、その魂の輝きを目にした途端、二人の心に熱い親愛の情があふれてきた。ロビンは魂だけだというのに、仲間を救うたびにふたたび立ち上がったのである。
ロビンは二度三度とモルドレッドを襲う。モルドレッドが黒剣をふるい、なんと釣り鐘をたやすく斬り裂いた。
「ロビン、ロビン逃げろ! 俺の仲間を助けてくれ!」
とスタートリーが言った。アジームが彼のナイフを奪い、モルドレッドの胴を突き刺した。モルドレッドは不意をくらってよろめく、貴様、と眼光鋭くアジームをにらんだ。洋一は恐怖に震え上がる。アジームに刺された傷口が、死兵とおなじあぶくをたてていたからだ。
ロビンの魂はモルドレッドの顔をうち、つぎに傷口にとびこんで、そのまま彼を引きずりだした。モルドレッドはたたらをふんで、欄干に腰を打ち当てる。アジームが後を追う暇もなかった。ロビンの魂はモルドレッドともつれあって彼を時計台から突き落としたのだ。
アジームとスタートリーはすぐさま欄干に駆けよって下をのぞいた。下界の樹木の隙間にモルドレッドのものとおぼしき足が投げだされているのが見えた。すでに人が集まりだしている。
「あいつは死んだのか?」
とスタートリーが訊いた。
アジームはわからんと答えたが、モルドレッドがやすやすと死ぬはずのないことは、この二人がよくよく分かっていたのである。
○ 3
洋一は悲鳴をあげて転げまわる。右手の中に、灼熱の痛みがあった。
アジームが伝説の書をもってもどってくる。
「みせてみろ」
ウィル・スタートリーが洋一の指をひらくと、手のひらには、どす黒い亀裂がひらけている。肉はなく、血もなかった。まるで、大地の亀裂のようだ。亀裂の後には暗黒が漂っている。アジームはうめいた。「あいつの毒だ」
洋一は痛みのあまり涙をながす。アジームは彼の胸に気休めみたいに本を置いた。
「どうなるの?」と洋一は訊いた。
「十字軍で、おなじ傷をもつ死体をなんどもみた」アジームはつぶやくように言った。「その傷跡は、やがて全身に広がりお前を喰いつくす。パレスチナで広がった奇病だが、あいつのせいだとは知らなかった」
「いったい、どうなってる」とスタートリーがアジームに訊いた。「あいつはフランスの貴族じゃないのか?」
「ちがう。あいつは本物なんだ」洋一が言った。額には脂汗が浮いている。「あいつに呪われたときに、いろんなものを見せられたんだ。あいつはほんとに中世から生きてる。本物のモルドレッドなんだよ」
「そんなばかな」とスタートリー。「いくら王家の人間でもそんなに生きられるはずがねえぜ」
「聖杯だよ。円卓の騎士は聖杯をさがしだしたじゃないか。あいつは永遠の命をえるために、ゴブレットの生き血を飲んだんだ」
「三つの呪いとはそのことか?」とアジーム。
洋一は震えながらうなずいた。「マーリンだよ。全部、マーリンが仕組んだんだ。マーリンはモルドレッドが生まれたとき、五月一日に生まれたこどもが災いをもたらすって予言した。五百の赤子っていうのは、そのとき小舟で海に捨てられたこどものことなんだ。その中にモルドレッドもいた。船の中は、赤ちゃんの死体でいっぱいだったのに、あいつだけは死ななかった」
「もともと不死身だったってえのか?」
ウィルの言葉に洋一は首を振った。
「そうじゃない。死ななかったのは、マーリンが自分の生き血を飲ませたからだ。あいつはモルドレッドを自分の手下にしたかったんだ」
「待てよ、伝説じゃあマーリンはアーサー王を助けたんだろう」
とスタートリーが言った。
「もとのマーリンはそうだった。でも、マーリンは夢魔と人間の間に生まれたんだ。マーリンのお母さんは、マーリンをまっとうな人間にするために、教会で洗礼を受けさせた。マーリンから悪の心がぬけて、不思議な力だけが残ったんだ。でも、悪のマーリンも生きつづけた。そして、善のマーリンを殺して、なりかわった」
マーリンのもくろみどおりになった。モルドレッドは古の血とイングランド王家の血筋をもつ混血となったのだ。
海峡をわたったモルドレッドはフランス貴族に拾われ育てられる。やがて、育ての親を殺したモルドレッドは、イングランドにもどり、円卓の騎士の一員となる。彼はマーリンと結託して、父王アーサーを追い落とそうとする。モルドレッドはアーサーと戦い、その槍に胸を貫かれる。だが、アーサーもまた深傷のために亡くなってしまう。マーリンは円卓の騎士を壊滅させ、モルドレッドもまた父王殺しの呪いをうけてしまった。
「モルドレッドは死ななかった。そのときには、聖杯の生き血を飲んでいたから。だけど、マーリンは動けないモルドレッドを、迷宮に封じるんだ」
「そこから、出てきたってえのか。復讐のためにリチャード王を殺し、イングランドの王位につこうってのか」ウィル・スタートリーは釣り鐘の下を歩きまわった。「こうしちゃいられねえ。ロビンを救わねえと」
「まだあるんだ」と洋一はひきとめた。「ジョン王の側近のモーティアナは、自分はマーリンの弟子なんだって言ってた」
「なんてこった……」
スタートリーがうめく。洋一もおなじ気持ちだった。イングランド王家の血を引きながら、マーリンの生き血を啜り、五百の赤子の呪いをうけ、聖杯の呪いを受けし男。さらに父王殺しの呪いまで背負っている。ウィンディゴに勝るとも劣らないやつだ。
洋一は右手をかかげて傷口をとっくりとながめた。傷口の闇は、まるで暗黒の霧であるかのようにうごめいていた。洋一の心は絶望に冷えた。ただの傷口なんかじゃない。本物の呪いがそこにあった。 あんなすごいやつがいたんじゃ、ロビンが復活しても、きっと……
「洋一」アジームがやさしく少年の肩をゆさぶった。「すまないが、いまは一刻を争う。立てるか?」
洋一はアジームに抱え上げられる。左手で傷ついた腕と伝説の書を抱え、痛覚を楊枝でほじくられるような痛みに苛まれながら。脳裏では友人に語りかけている。
アジームが走り、洋一は体が揺れ、頬を流れる一滴の涙を風が揺らすのを感じる。幼い友人がどこかでおなじように走っているのを感じる。
あいつに謝らなくちゃ、ぼくのために忠告してくれたのに、ひどい口をきいてしまった。それに伝えないと! モルドレッドのことを、あいつがどんなに危険かって……
洋一はアジームの腕のなかで本を開こうとしたが、体が奥底から震えて指がうまくつかえない。本になにかを書きこむには、彼は傷つき、かつ疲れすぎていた。
彼は表紙に掌をおいた。伝説の書がしっとりと息づくのを感じる。本は味方でないと知りながらも願わずにはいられない。
彼は、太助太助死ぬなと心中に言葉を発しながら、意識を薄れさせていった。太助に伝えるんだあいつを助けるんだと念じながら、彼は意識をなくしたのだった。
○ 4
ジョンは必死に走りつづけた。ロビンの元をめざし、群衆を掻きわけていく。フードは脱げ、武器も丸出しになっていたがそれにも構わなかった。ちびのジョンは無意識のうちにつぶやいていた。
「ロビン、ロビン待ってくれ、死刑囚などにならねえでくれ」
群衆にもまれるジョンの大向こうで、ロビンは死刑台に引き上げられる。あのロビンが犬のように両手をついていた。それだけでジョンの胸は張り裂けそうだ。あれはロビンじゃねえ、あんなものロビンであるもんか!
彼は怒りの唸りを上げた。
「おめえら、おめえらにロビンを殺す権利があるのか! あの男は真っ正直に生きたんだぞ。名無しの浮浪なんかじゃねえ、やめろ!」
ジョンは周りの人間を残らず蹴散らし、ついに兵隊たちが目をとめた。処刑台の兵士たちは、ジョンを捕らえようとする者と、処刑を執行しようとする者、二手に分かれる。ジョンは剣を抜き放ち、逃げまどう人々の中を突き進んだ。ロビンは首に縄をかけられ、ぐったりと頭を垂れている。もう死んでいるようにも見える。
「ロビン、ロビン・フッド! 目をあけて俺を見ろ! おめえの副隊長がきたんだぞ!」
兵士たちは壇上に並んで槍を突きだしてきた。鰯の群れのような穂先が彼の行く手を阻んだ。ジョンは仰け反りながらそのけらくびを斬り上げ、たった一人で槍ぶすまを突き進んだ。
「くそう、邪魔をするな!」
兵士たちはジョンを叩き落とそうとするが、大勢でいっせいに槍を繰りだすものだから、いっかなジョンには当たらない。ジョンは棒で叩かれ、穂先に肉を削がれながらもロビンを救おうと猛り狂った。そのうちにジョンのもとに仲間の騎士たちが駆けつけ、弓の援護がはじまった。
広場へつづく二つの道路から十字軍が津波のように押し寄せてきた。守備隊の陣形が崩れたち、死刑台にも動揺が走った。ちびのジョンはそのすきをついて、剣を風車のように振りまわし、死刑台の上の足を払ってまわった。血が飛散し、台を濡らし、ジョンの顔を撫でまわす。兵士たちが敵わずとみて飛び下がると、ジョンは巨体を踊らし、死刑台に飛び上がった。
「俺はジョン・リトル、イングランドのヨーマンだ! ロビンを返してもらうぞ!」
太助も日本刀を手に駆けつけた。彼は死刑台から落ちた槍に足をかけて跳ね上がる。ジョンに近づく敵兵を斬り倒した。ロビン側の騎士たちは威勢を駆って台に上がり、敵兵を追い落とした。
ちびのジョンは夢中で叫んだ。
「太助、ロビンだ、ロビンがいたぞ!」
「ならばロビンの縄を解け!」
銃声が轟いた。太助の周りで騎士たちがバタバタと撃ち倒された。銃士隊だ。モルドレッドの連れてきた私兵隊が、死刑台の右手から攻撃を加えている。太助は身を投げだすと同時に兵士の落とした盾を拾った。太助は盾の陰に身を隠しながら、死刑台の周りを見回した。もう、敵も味方も入り乱れての混戦となっている。一方で銃士隊は区別をつけずに発砲してくるのだから始末に終えない。銃弾が盾に当たって貫通した。太助は盾の銃痕を裏から見ながら、火縄銃とはこんなに威力があるのかと瞠目した。これでは新式銃にも劣らない。
仲間たちは幾人も壇上に上ってくるが、後から後から撃ち殺されている。太助は堪らず叫んだ。
「ジョン、早くしろ!」
ロビンの脇では、司祭が手を合わせて命乞いをしている。ジョンはこの老人の手を取り追っ払うと、ロビンの体をしがみつくようにして抱き上げた。
「ロビン・フッド!」
ロビンが顔をもたげる。その虚ろな目が、ジョンの脳髄を突き刺した。
「俺がわからねえのか?」
「なんだ、貴様……」
とロビンが言った。ジョンの瞳に涙が浮いた。昔日のロビンが脳裏にいくつも蘇る。彼はまぶたをしぶると、震える胸をのみこみ言った。
「俺が来たからにはもう大丈夫だぞ。シャーウッドに帰ろう」
帰ろう
その声はひび割れ、言葉の終わりはかすれて消えた。だが、その暖かな呼びかけも、ロビンを呼び戻すには至らなかった。ジョンが縄をほどこうとすると、ロビンはいやがるように身をよじらせる。やめろ、と拒絶したのだった。
「俺だ、ちびのジョンだ!」
「貴様など知らん」とロビンが言う。「俺は今死にたいのだ」
ジョンは本気で腹を立てた。地響きのするような唸り声を上げた。ロビン・フッドはこんなことを言わない、生きるために、仲間を生かすためにどんな力も発揮した男がいまさらなんだ! ジョンはロビンの肩を揺さぶりだした。
「パレスチナがなんだ! 魂がなんだ! 貴様の体は今ここにあるだろうが! さあ、目を開けて俺を見ろ! 俺の名を呼べ! 俺は誰だ!」
「やめろ、貴様!」
もみあう二人の周囲にも銃弾が飛び交いだした。銃士たちが周囲の建物にあがって、下界をめがけて銃撃をはじめたのだ。
太助はもう盾を捨てて戦っていたが、たまらずジョンの元に下がってくる。「ジョン、なにをしてる! 銃隊だ! 皆殺しにされるぞ! ロビンを下ろせ!」
「こいつはロビンじゃねえ! 俺はロビンのために命をはるんだ! おめえがロビンじゃねえのなら、俺はお前を助けねえ!」
「ジョン、意地を張るな!」
首吊り台の木片が散り、三人は首をひっこめた。
奥村太助は首吊り台の根本にうずくまりながら、怒りのうなりを上げた。無差別な銃撃で市民たちが折り重なるように倒れていくのが見えたのだ。
彼は生まれてこの方、私心を捨て公のために生きる侍の教えをたたきこまれてきた。公とは民草のことだ。供に旅した大人たちがこの小柄な少年に叩きこんだのは、侍の理想像にほかならなかった。すべての人民のために、侍は命をかけるのではないのか。銃士は侍ではないが、騎士はその近くにあると聞いている。
太助は怒りに震えて立ち上がると、銃士めがけて呼ばわった。
「貴様らの所行しかとみとどけたぞ。天が許そうとも侍たる自分がお主らを許さん! そこをおりて剣をまじえろ! 無抵抗の者を狙うな!」
太助、やめろ、とジョンは言った。そう言いながら彼は、ロビンの前に仁王立ちとなった。弾丸が幾度となくかすめて頬を焼いた。彼の眼上では銃弾が煙を噴いて飛び交っている。銃士たちが進撃して、処刑台の正面に回りこんできた。
「そんなにロビンを殺してえなら、俺の命をとってみろ! そんな鉄の玉っころで死ぬもんか!」
彼らは群衆より高い位置にいて格好の的になっている。銃士が折膝の姿勢をとって銃を構えだす。ジョンは顔を背けなかった。これまで長年月そうしてきたようにロビンのために体を張っている。ロビンはそこをどいてくれと懇願し、ジョンはどくもんかと言い張った。太助もついに呆れかえった。二人ともだだっ子みたいに強情だ。
「なぜそんな真似をする。俺などを救ってどうなる。俺は食い、寝、排便するだけの下らん存在だ……もう誇りもなにもない」
ロビンは十字架に縛られたまま、鼻水を垂らして泣いている。ジョンは涙に頬を濡らしてつぶやいた。
「俺にはお前が必要なんだ。必要なくたって必要なんだ。絶望するなら、精一杯やってからにしろ!」
ロビンはジョンの背中に語りかけた。君は、自分などのために死ぬべきではない。自分は君など知らない。自分は生きていてもしかたのない人間だとかき口説いた。
ジョンは涙した。かつてのロビンは生命力に満ちあふれた人間だった。絶望にあっても活路を思い、どんな窮地も切り抜けてきた。くそったれ、とジョンはロビンに腹を立てた。何年ぶりかに帰ってきておめえの無様なざまはなんだ。俺に弱音を吐きにもどってきたのか
「何百万の敵にだって角笛をならして立ち向かったおめえはどこに行った! どんな相手にも体を張ったおめえはどこだ! 立派な生き様をする気がねえのなら、立派な死に様をする資格だってねえ! 俺たちがそんな人間に成り下がったんなら、天は俺たちを殺すべきだ。ともに死んでやるから、ともに行こう、ロビン・フッド」
ジョンはついにどかなかった。銃弾がその体を揺らした。腕に食いこみ、胸に当たった。けれど、ジョンは歯を食いしばり耐えた。呻き声すら上げなかった。ジョンの足下を濡らす血溜まりが、ロビンの目にも見えた。
「やめろ、なぜこんなことをする!」
「だまれ、名無しの無法者!」
とジョンは吠えた。ロビン・フッドがこの天地にいないのなら、彼はこの男と一緒に死ぬつもりだったのである。
ロビンはパレスチナからこちら、自分がなにを見、どんな目にあってきたのかを言いつのった。ロビンが世に絶望したのも無理はない、と太助は思った。仲間とはぐれては、虐待にあい、戦乱に巻きこまれ、虐殺の現場に立ち会ってきた。魂をなくし、赤子のようになった人間が、そんな目にあってきたのだ。だが――
太助は目を細め、硝煙にけぶる広場を見渡した。処刑台に集まる銃撃はますます数をましている。刀の腹に弾が当たって、彼は柄を取り落とす。愛刀がガラリと台場に落ち、太助は血に塗れた台を這って刀を拾った。
「洋一!」
と彼は言った。ぼくらを助けてくれ!
その声が聞こえたわけではあるまい。まして、彼は洋一が文を書くのは失敗したろうと信じこんでいた。
もうおしまいだ。自分たちは父上と男爵に会えぬまま、この街で死ぬんだ。
太助は血で滑る掌をぬぐうと、刀を握りなおして壇上を降りようとした。鉄の玉に殺されるぐらいなら、敵兵と戦い斬り死にしたかったのだ。
そうして、処刑台から駆け下りようとしたとき、時計台のあたりから光がたち去るのが見えた。彼は雲の下で光を見失ったが、光はすぐに現れて、広場を旋回し、銃士たちの頭上を飛びこえて、敵兵の生き肝を抜いた。
ロビンの魂だ!
「ジョン、見ろ!」と太助は言った。「洋一のやつ、やったぞ!」
光が処刑台を目指して飛んできた。ジョンの体を突き抜けて、ロビンの胸に突き刺さる。
その間も、ジョンは朦朧としつつ、まだ巨体をたてていた。こめかみを弾丸がかすめると、ジョンは大きく身を蹌踉めかせる。ロビンは、ついにその名を呼んだ。
「やめろ! やめろ、リトル・ジョン!」
ジョンは驚いて意識をとりもどした。よろめいたおかげで、半身の姿勢となって、それでロビンと顔を合わせる結果となった。フルラウンドを打ち合ったボクサーのように茫漠としたジョンの意識が、このときだけは明瞭となった。
ロビンの顔は涙に濡れていたが、その瞳は燃え上がる義憤に輝いている。さきほどまでの弱々しさは微塵もない。ジョンは、おおと口元を両手で隠した。涙があふれると、その手で目玉を覆ったのだった。リトル・ジョン。なんて懐かしい呼び名だろうと思った。それはロビンが、本気で怒ったときに口にする言葉だ。聴きたかった声だ。いまこそ、こいつはロビン・フッドだ!
「リトル・ジョン! 俺のいうことが聞けんのか! 下がれ!」
ジョンが言われた通りに身をしゃがめると、ロビンの右肩を弾丸が掠めた。ジョンが悲鳴を上げ、太助が刀を回し、ロビンのいましめを切り裂いていく。
その間も弾幕が乱れ飛ぶが、ロビンはびくともしなかった。太助が足の縄を切ると、首にかかった縄をほどきつ、死刑台から身を乗りだしたのだ。
「アラン・ア・デイル、弓をもて! ヨーマンよ、我が元に集え! 我が敵を討ち果たせ!」
ロビンの呼び声に十字軍は奮い立った。銃士隊が旧装備の騎士たちに押されはじめた。
ジョンはロビンの側で膝をついていた。かつてのままのロビンが、突然出現したかのようだった。彼は他のどんなものより人間らしかった。まさしく正しい人間がそこにいた。自分がどんなに飢えても、困っている人間には手をさしのべる男――不信に苦しみ、猜疑にとらわれた人間も、ロビンならば信用するだろう。なぜなら、ロビン・ロクスリーはどんなことにだってその身を投げ出して立ち向かう男だし、どんな困難にも決して後ろを向いたり道を逸れたりしなかった。人のいるべきど真ん中にいつだって立っている男だ。ジョンは、この男のこの姿が見たかった。ヒーローに憧れる少年のように、彼はこのロビンにこそ会いたかったのだ。
手近にいた騎士たちが、ロビンのもとへと駆けつけてくる。
「ロビン……」とジョンは友人を見上げる。
「ちびのジョン。お前に会うのもずいぶん久方ぶりだなあ」
「ああ、ああ」
「ジョン、おかしいのだ。ここは戦場だというのに、この穏やかな気持ちはどうしたことだろう」
ロビンは自分を付け狙う矢弾が別世界のことであるかのように、ゆったりと目を閉じた。まわりに居並ぶものは、身を隠すことも忘れて彼に見惚れた。
ロビンは自分をとりまく日の光や風を、心ゆくまで味わった。細胞の一つ一つが目覚めていき、そのたびに喜びがわきおこる。力がふつふつと踊るように湧いてくる。
天が地上にいる人間に味方をすることがあるのだとしたら、まさにこのときだったろう。奥村太助は、この男こそ、この物語の主人公、ロビン・フッドにまちがいないと強く感じた。自分に心服する男たちを従え、悠然と目を閉じている姿は、まさしく侍そのものだった。
ロクスリーのロビンは、古い友人をかたわらにつぶやく。
「長い暗闇の中にいたようだ。ジョン、見ろ、この日の光を。潮風をかげるか。曇り空すら美しいではないか。俺はたった今生まれたようだぞ」
「ロビン、あぶねえ」
ちびのジョンは弾丸から守ろうとしたが、ロビンは彼を追いはらった。
「かまうな、ジョン。今下で死に玉を恐れず戦うヨーマンたちを見ろ! なぜ俺だけがひっそりと隠れることができようか! さあ、みな陽の下に顔をさらせ、俺たちは誇りたかきヨーマンだ!」
そのとおりだ!
ジョンはロビンに唱和したかったが、のどは涙につまり、なにも言葉にすることはできなかった。
ロビンは壇の上からふりむいた。
「ジョン、長いあいだ苦労をかけたが、それも最後だ。これからはともに苦しみ、ともに喜びをわかちあおう。ともに行こう、兄弟よ!」
ジョンはむせび泣いた。
「俺にはその言葉だけで十分だ。そして、許してくれ。お前の苦しみを、俺はたった今までとりのぞくことができなかった」
「なにを言うジョン。その苦しみすら、今日の喜びを得るためにあったのだ! さあ、今こそ戦いの時だ! 俺たちは、ヨーマンだ!」
二人のまるで似ていない兄弟たちは互いの背を叩き合った。太助が、兵隊より奪いとった長弓と一束の弓矢をさしだした。ロビンは少年の肩をたたき、武具を受け取る。
「これこそ最上の贈り物だ」とロビンは言った。「さあ、太助、ともにつづけ!」
ロビンは次々と矢をつがえながら絞首台を飛び降り、ちびのジョンが後に続いた。
奥村太助は二人の勇姿を見送った。ロビンの口にした言葉にとらわれている。
ロビン、ロビンはぼくのことを知ってる。
「洋一……」
太助は、牧村洋一がいるだろう方角に目を向けた。そこには曇り空が広がるばかりで、友人の安否はようとしてしれなかった。
○ 5
ロビンはまるで軍神のように、フランス銃士隊の前に立ちふさがった。伝説のロビン・フッドが弓をとるに当たって、獅子十字軍はついにその息を吹き返した。
銃士が処刑台を囲みだすと、ロビンたちは得意の弓で応戦した。ジョンの棒術が男たちを遠ざけたし、運良くとりついた者も太助によって斬られてしまった。
「ちくしょう、ロビン、あの銃ってのがやっかいだぜ」
「俺の弓ほどあたらん。心配するな」
ロビンが肩を叩いても、ジョンはちっとも安心できない。ロビンの弓ときたら、外れたためしがないし、それより劣るのは当たり前ではないか。
「大通りにはギルバートと十字軍がいるぞ」
「ギルバート、あいつもか」
「そうだ。あいつらがフランス軍をひきつける。俺たちはその間に、港に走るんだ。仲間の船が待ってる」
ロビンは軽快な笑いをあげた。「まったく君みたいなまめで義理堅い男は見たことがない」
「俺はお前の副隊長だぞ」
「ああ、そのことを天地に感謝するとも」
群衆に交じっていたロビンの仲間たちが、その正体を現して、処刑台に集まりはじめた。彼らは市民とおなじ格好をしていたので、銃士たちも手こずった。ために、本物の市民を誤発するという事件も起きた。ロビンの古い仲間たちは、隊長の下を目指して一散に駆ける。ロビンは彼らを救うために弓を引き絞りつづけた。長い眠りの中にいたというのに、ロビンの弓は衰えるということを知らなかった。
アラン・ア・デイルが、ロビンに向かって叫んだ。
「ロビン、ロビン、隠れろ。銃士が君を狙っているぞ」
「なんの、その身をさらして戦う部下がいるというのに、俺一人が身を隠せるか。さあ、存分に戦え。矢弾は俺が引き受けたぞ!」
矢弾を一手に引き受け奮戦するロビンの周りに、懐かしいシャーウッドの仲間が集まってきた。彼らは得意の弓で銃士隊を押し返しはじめた。
マスケット銃は、どれも先ごめ式だ。装填に時間がかかっているのをみて、ロビンは仲間の周囲を飛び回り、右に左に指揮してまわった。このため、満足に弾ごめもできなくなった。
不利を覚った銃士たちは、黒い玉に火をつけて回り、つぎつぎと遠投をはじめた。ソフトボールよりも大きな玉が、ドテドテとジョンの方に転がってくる。
「ロビン、ありゃなんだ!」
「伏せろ!」
ロビンがジョンに組みついた、爆炎とともに、炎と鉄片が二人の体を叩いた。
「炸裂弾か」
とロビンは言った。粉屋のマッチが、
「あいつら、十字軍に参加してたやつらだ。サラディンの武器をまねやがったんだ」
ジョンはあわてて太助の姿を探した。少年は騎士たちの一団に守られて無事だった。
体勢をたてなおした銃士たちが、弾ごめを終え、いっせいに射撃を開始する。
「処刑台だ、処刑台の裏へ回れ!」
ロビンが叫ぶと、アランたちはすぐさまその意図を察して、処刑台を土台から担ぎ上げ、横倒しにした。銃弾と、炸裂弾が轟々と倒れた台座を突き崩す。
「弓の達者なものは集まれ!」
マッチは呵々大笑した。「それじゃあ、おおかたきちまうぜ」
「なら、手頃に集まれ」とロビンはやりこめた。「いいか、火薬をつかうやつを残らずしとめて回れ、それ!」
ロビンたちは弓の射角を上げ、銃士たちの真上から矢を振り落とした。炸裂弾の炎が敵陣に上がる。マッチが、大穴の隙間から向こうを覗いて言った。
「どうだ、まっすぐしか飛ばねえ銃弾にはできねえ芸当だろう!」
ロビンは処刑台をよじ登ると、真上に身を乗り出して、自慢の弓をきりきりと引き絞る、隊長と見られる男めがけて射はなった。ロビンの矢は、男の胸当てを貫き通し、深々とうまる。男は倒れることもままならず、真下に膝から崩れ落ちた。イングランドでも滅多とお目にかかれない、見事な威力と正確さだ。
「弓だ、もっと矢を持ってこい!」
それからロビンはジョンに耳を近づけ、
「ジョン、君は斬りこみ隊を連れて行け。俺たちは銃士どもをやっつけるんだ。弓隊集まれ!」
ロビンが懐かしいヨーマンとともに銃士隊の囲みを突破しようとするころ、ギルバートひきいる十字軍は大通りと広場をはさんで、守備隊と激しくぶつかりあっていた。
ギルバートは、処刑台のロビン・フッドに銃士たちが群がるのを見た。彼は仲間の背中を押しながら言った。
「処刑台のロビンを生かせ! あの男を死なせるな!」
ギルバートはロビン救出にあたって、部隊を三つに分けていた。広場にのりこむ部隊、ロビンを逃がす隊、そして、守備隊をおびきよせるため、退路を固める部隊である。彼は、それぞれの隊を区別するために、色分けした布を騎士たちの腕に巻かせていた。いま、ギルバートのまわりにいるのは、赤布を巻いた決死の男ばかりである。彼らは大将のギルバートを下がらせようとしたが、ギルバートは引かなかった。
「俺たちはリチャード王を死なせた。サラディンに敗れ、このままではジョン王に討たれるだろう。だが、ロビンがいれば、俺たちはもう一度戦うことができるのだ!」
彼はロビンにこそ大儀があると言いたかったのだ。仲間の背をおし、死体を乗り越えながら、騎士たちを鼓舞してまわった。騎士たちは喚声をあげて守備隊を切り崩しはじめた。
甲冑の音が、ギルバートの耳をつんざいた。銃弾が鎧にうち当たっているのである。すでに、かれ自身も身に数発の弾丸を受けていた。
敵と切り結ぶギルバートの脳裏に遠き故郷の姿がありありと浮かんでくる。両親や、妻、娘たちの姿がなんども浮かんではそれをふりはらうために剣を振るった。
生きて帰る、俺は生きて帰るぞ!
十字軍は守備隊を二つに断ち割った。ギルバートの目に、ジョンや仲間にかこまれたロビンの姿が見えた。ギルバートには、あれこそイングランドの雄々しき魂だと思えた。ギルバートたちはロビンを中心に逃すまいとする守備陣を打ち破った。銃士隊が追ってこなかったのは幸いだった。モルドレッドがいないために組織だって戦えなかったのだ。
ロビンが海上で待つ私掠船団を目指すころ、洋一もアジームにおぶわれて仲間の後を追っていた。モルドレッドの呪いを受けて以来、まったく目を覚まさない。その右手には大きな亀裂が口をあけ、銃士が放っていたのとおなじ黒気を漂わせている。
牧村洋一は、そうして異国人の背に揺られながら、伝説の書と戦っていた。彼の本は主人の心を食らいつきに掛かっていた。
以下はその顛末である。
○ 6
洋一は闇の中を漂っていた。そうして闇を漂いながら、多くの人々の声を聞いていた。それは大半がくだらない願いで、大半が醜かった。それは本に閉じこめられた人々、本に魂を喰われた人々の声だった。昔本は中立だったのに、本に願いを書きこんだ物書きたちが、伝説の書を汚してしまった。洋一は人々の呪詛の声や、妬みや恨みを聞きつづけて悲しくなった。もうやめて欲しい。もう聞きたくないよ。もうたくさんたくさんだ……
そうして彼は泣いていたから、自分がいつのまにか闇を漂うのをやめ、硬い闇に(おかしな表現だが)横たわっているのを感じた。洋一は首を巡らした。自分の姿が見えるようになっている。他にはなにもなく声もしなくなっていた。
動悸が激しかった。フルマラソンの後みたいに、汗をぐっしょりとかき、あえぎながら目を瞬いている。洋一が起き上がると、ぱさぱさになった筋肉の腱が、今にも斬れそうに軋みを上げた。
くそっ、と彼は小声で言った。側におぼろな影が立っていた。ウィンディゴ……。恐怖のなかでつぶやいたとき、そのうっすら光る影は幾重にも分裂し、十二の人体となって彼を囲んで回りだす。やめろ! 大声で叫んだ。右に左に走ったが、影たちは彼につられて環を動かし、逃げられない。
「小僧!」
その声は、十二の塊となって洋一をうちのめした。彼は環のなかで倒れ伏した。
「ウィンディゴだな」
懐に手を入れる。だが、そこにあるはずの本がない。
「お前は幻だ! だまされないぞ!」
「そんな様で親の敵などとれるものか。呪われた体でなにができる」
「そんなことない。ロビンだってちゃんと復活したぞ」
「お前は失敗した。その証拠に伝説の書に生命を奪われたではないか」
洋一は反論できなかった。本に殺されるかと思ったあの瞬間を思いだすと、今でも心が震えてくる。
「お前はなんの力もない小僧だ、父親からなにも教わらなかった」
「そんなことない」
「お前に本を持つ資格はない、伝説の書をわたせ、小僧! お前にはすぎたるものだ!」
「ぼくのだ、あの本はぼくのだ」
「本に取り殺されてもかね」
ウィンディゴの回転はどんどん速くなっていった。洋一は自分が回っているようにすら感じる。胃袋の中身が逆流し、地面に伏せる。片手で口を押さえながら、洋一はしっかりしろ、と自分に言い聞かせた。
洋一はぼくをおかしくしていたのはこいつらなんだと考えた。こいつらがぼくにおかしなことを吹きこんだ。ぼくと太助の仲を割った。ぼくが聞いてたのはこいつらの声だった。
こどものころもおなじようなことはよくあった。聞こえない声に耳を傾け、見えない誰かに物ごたえをしていたらしい。恭一は見つけるたびにきつく叱って、注意を促した物だった。本に呪われた者の哀れな末路を、たどらせないために。今思うと、彼は伝説の書の声をあのころも聞いていたのだ。恭一が声に対処する方法を教えてからはそうした声は遠ざかった。物心がつくころには本からのささやき声はほとんど聞こえなくなった。それは、きっと恭一が伝説の書に結界を施してくれてからだろう。
「お前、お前なんか、お前なんかに渡さない。お前は本の世界に来られないんだ」と吐き気を飲む。「お前のやっつけ方なら知ってるぞ。追っ払い方なら知ってるぞ」
彼は本当に吐いた。影はゲタゲタと笑う。悪意に満ちた歓喜が、洋一をねじ伏せる。彼は本の世界に取りこまれかけていた。
負けない、負けちゃだめだ。死んじゃ駄目だ。あんなやつらの仲間になんかなるな!
洋一は曲げていた体をぐっと伸ばし、顔を上げた。ウィンディゴの笑いが止まった。
「色は匂へど、散りぬるを!」
洋一の声は、まるで魔法のようだった。光を帯びて、十二の影をぶっ叩く。回転が弱まり、ウィンディゴたちは苦痛に耐えかねたように体をゆがませよろめいた。
「我が世誰ぞ、常ならむ! どうだ! おっぱらい方なら知ってるって言っただろ! ぼくを笑いやがって! 本を持つ資格がないなんて嘘だ! 有為の奥山、今日越えて! さあ、どうだ、言葉ならたくさん知ってるぞ! 古い言葉の力だぞ! 浅き夢見じ、酔ひもせず! お前の負けだ! さあ、ぼくを自由にしろ! お前が伝説の書の影なら、ちゃんとぼくに従え!」
影たちの手が一つ一つ離れていった。バラバラとなり、倒れ、そして、闇へと解けていく。形をなしていた闇が、ほどけていくようでもある。闇だ、あいつらは本物の闇だったんだ、と洋一が思ったとき、かれ自身も脳の血が抜けるようにして意識をなくし、地面すらない闇の中へとけこんでいった。
洋一は、
「父さんになにも習わなかったって。バカをいえ」
とウィンディゴに向かって叫び、そして、闇の世界から現実へと立ちもどっていく。
「洋一、洋一」
誰かが手を握っている。洋一が目やにでくっついた瞼をどうにか開けると、顔の上に太助がいた。洋一は少年の隣に両親が立っている気がしたけど、その部屋にいるのはこどもたちだけだった。
木で出来た狭い部屋で、彼はベッドの上に寝かされている。頭の上には丸いガラスの窓があって、ときおり体が揺れている。
「ここは?」
「船の上だよ。みんな助かったんだ。君がやったんだぞ」
と太助は言った。洋一はこれまでのことをみんな思い出して、体を起こした。
「ぼくは君の忠告を聞かなかった。伝説の書が……」
「全部聞いたよ。大変だったな」
と太助はいたわるような顔をした。洋一は言いたいことが全部抜けて、ただ唇と瞳を震わせる。太助が全部受け止めてくれたからだった。洋一は枕に頭を戻した。天井に目線を戻す。頭の下で海が揺れている。はらはらと涙が落ちて、耳際を伝い枕に落ちた。太助は困ったように頭をかいたが、ずっとそこに座っていた。
二人はメインマストの見張り台にのぼった。マストの天辺にいると海は果てがなく、波間はキラキラと輝いていた。二人はこの期間に起こった色々なことを話し合った。
中世の王モルドレッドの話。伝説の書に命を吸い取られたこと。処刑台での戦い。
「とにかく父上と男爵をさがさなきゃ」
と太助は言った。二人は望楼の欄干に寄りかかり潮風に吹かれている。話は伝説の書の危険にうつっていった。創作に失敗したときの結果は恐れていたが、ここまでひどい真似をするとは思わなかった。洋一と来たら、飢餓に苦しむ戦災孤児だ。水を散々飲ませて肌の艶はいくらかもどっていたが、一時は不整脈を起こして危なかった。こうなってみると、洋一は自分が本の持ち主というよりは単に呪われているだけのような気がしてくる。やっぱり恭一はウィンディゴから守るためではなく、かれ自身を伝説の書から守るために、この本を封印したのだろう。それならば、これまで彼に伝説の書のことを語ってこなかったことにも納得がいく。
洋一は、この本は持ってるだけじゃ駄目なんだ。この本は――本の中にいる連中はぼくの命を狙ってる。ぼくを仲間に引き入れたがってるんだ、と考えた。
洋一は帆船に乗るのもこんな高い所から海を見おろすのもはじめてだった。彼には経験していないことがまだまだあった。
気持ちのいい風だった。気分のいい景色だった。それらのすべてが少年たちの心を癒し落ち着かせる。洋一は広い海で過ごす内に少しずつ自分をとりもどしていった。伝説の書が自分に働きかけていると自覚して、それに対処するよう努めた。太助とジョンは喜んだ。
洋一はいつのまにかこの世界をなんとしても抜け出そうとは思わなくなっていることに気がついた。彼は本を使い、失敗もすることで、この世界でやっていく自信のようなものをつけたのかもしれない。
洋一と太助は欄干によりかかって、くだらない打ち明け話をしたり、カモメの数を数えたりした。洋一はそうして話をしてくれる太助がひどく好きだった。そしてそうした時間がひどく大切なものに思えたのだった。